さて、毎度おなじみの、安価なミラーレス中古機に様々な
マニアックなレンズを装着して楽しむというシリーズ。
今回第38回目は、このシステムから。

カメラは、アダプター母艦のNEX-7である。
レンズは、MINOLTA AF Macro 50mm/f2.8
1980年代後半の銀塩AF一眼、αシリーズ(7000,9000等)
と同時期の発売と思われる、いくつかのバージョンが存在
するが、このレンズは最初期型だ。が、レンズ構成は
後期型(SONY Aマウントに至るまで)も変更は無いと思う。
AFレンズなので、本来はAマウント機(銀塩α、デジタルα、
ソニーα Aマウント)に装着するのが望ましい。
その方がAF等、機能が限定されないからだ。
「アダプター遊びでは、ボディとレンズのお互いの欠点を
相殺する組み合わせが望ましい」と、再三このシリーズ記事
でも書いているのだが、シリーズも回が進むに連れて
リファレンス(参考)的意味合いも本シリーズ記事に
加わってきて、私自身のレンズデータベース的な目的も
持たせようと思っている為、最近は「AFレンズ無し」という
自主制限も緩和している。
それに、マクロレンズではそもそもAFは殆ど使用しないし、
ミラーレス機と組み合わせる事で、被写界深度、露出や
色の補正状況、ボケ質、などがリアルタイムでEVF上で
確認できる事もアダプター使用上の大きなメリットな訳だ。
AFが効かない、というデメリットと比較すると、長所の
方が大きいような気もしてきている。

さて、本レンズは、私は銀塩時代より「最強の標準マクロ」
と評価しているレンズである。
まずボケ質は、場合により破綻するケースもあるが、
多くの状況で非常に優れている。
銀塩時代、ボケ質世界最強の、ミノルタSTF135/2.8と、
本AF Macro 50/2.8を同時に持ち出し、レンズ交換
しながら撮っていた事があったが、後で現像が上がってきて
一瞬、STFで撮ったのか、本レンズで撮ったのか見分けが
つきにくいカットもあった位である。
最短撮影距離は20cm、いわゆる等倍マクロであるが、
等倍というのは、35mmフィルムに、被写体と同じ大きさで
写るという意味であるから、APS-C機であるNEX-7では
センサーサイズが小さい為、1.5倍マクロ相当となる。
これはちょっと実用的には、大きく写りすぎる場合もあるので、
μ4/3や、APS-Cミラーレスで使う上では、あまり等倍という
スペックに拘る必然性も少なく、銀塩MF時代の1/2倍マクロでも、
まあ十分だ。
例えば・・

こうした小さい昆虫を接写して、あまり大きく写して
しまうと、ちょっと気持ち悪い(汗)
人間が思う感覚というのもあって「実物とのサイズ感
の差異が大きいと違和感が出る」という話もある。
一例として、銀塩時代の写真展などで、まず最初に
2L版程度でプリントしたマクロ写真などを、展示会用に
4つ切りなどに大きく伸ばしてしまうと、印象が大きく
変わってしまうような事もあった。

勿論、マクロレンズと言っても、中距離での撮影も可能だ。
で、一般的な写真用レンズは、無限遠の撮影で最適な
画質が得られるように設計されており、近接撮影にする程
画質が劣化するのが普通だ。
だが、マクロレンズはその逆、近接撮影で最高の画質が
得られるようになっており、中遠距離撮影ではむしろ
画質が劣化してしまう。
しかし、MF銀塩時代は、そのあたりの設計思想もレンズに
より、まちまちであって、例えば、ニコンのAi55/3.5や、
オリンパス OM50/3.5のマクロは、近接撮影での解像度を
重視した設計で、その代わり中距離撮影でのボケ質が極めて固い。
あるいは、人気のあるタムロン90mmマクロは、MF時代の
90/2.5は1/2倍であるが中距離でのボケ質に優れ、AF時代からの
90/2.8は、近距離のボケ質に優れるが中距離ではイマイチだ。
ミノルタ AF Macro 50/2.8は、その両者のバランスが良い、
第7回記事で紹介した ミノルタ銀塩時代のMD Macro50/3.5 は
1/2倍で、どちらかと言えば、オールドのマクロ、すなわち
解像度重視でボケが固い要素が強い。
ミノルタAF時代では、50/3.5というマクロがずっと併売
されていた、残念ながらそのレンズは所有していないのだが、
もしかすると、そちらはオールドマクロに近いような
解像度重視型なのかも知れない(?)、安価なレンズなので、
いずれ機会があれば、そちらも購入してみるとするか。

本レンズの最大の特徴は、その描写力もさることながら
コストパフォーマンスである、初期型の中古価格は銀塩時代
より、ずっと1万円前後で推移している。
私が購入した1990年代では若干高価で15000円であったが、
2000年代以降は、若干相場が下がってきたのだ。
市場には、NewやD型と呼ばれる後期型の2型や3型も存在
していて少し操作性が良くなっている(ピントリングが広い)
ただ、その差異はあまり大きくない、初期型のピントリング
は狭いのだが、使えないという程では無い。で、中身のレンズ
構成は一緒であるから、若干相場が高い後期型や、SONY型を
選ばず、MINOLTAの初期型でも十分という判断だ。
あまりに良いレンズであったので、友人知人にも勧めて
以前のMINOLTA MC50/1.7と同様に、7~8本、このレンズ
の中古を購入しただろうか・・ α(Aマウント)ユーザー
必携のレンズであると思う。
---
さて、次のシステム

本格派のAF Macro 50mm/f2.8 とはうって変わって
HOLGA 25mm/f8 のトイレンズである。
カメラは、Eマウントの「トイレンズ母艦」のNEX-3だ。
本レンズは、既にシリーズ第3回記事でも紹介しているが、
再度の登場だ。
HOLGAは、中国製の安価なトイカメラで、1980年代より
発売されている、当初は、中判用フィルムを使うなどで
ちょっと敷居が高かったが、後に35mmフィルム版なども
発売されている。
2000年代前半において、HOLGAはアート的な意味合いで
支持され、特に若い女性のユーザー層に爆発的な人気が
あった。
というのも、HOLGAで撮った写真は非常に個性的な描写を
もたらした為だ、そのため、個性や感覚を重視する女性
カメラマンに特にウケたのだろう。当時流行した女性向け
カメラ雑誌なども、こぞってHOLGAやLOMOといった
トイカメラを紹介し、現代で言うところの(悪い意味での)
一極集中化現象が起こってしまったのだ。

私は、トイカメラやトイレンズは、アンコントーラブルな部分、
がある、すなわち撮影者自身では制御できない「偶発的な写真」
である事を良く理解した上で使うのであれば肯定派だ。
ただ、逆に、自身の撮影技術や知識、経験などが不足している
状態で、面白い写真が撮れるから、という理由でトイカメラや
トイレンズを使うのには反対であり、それはあくまで偶然写真
でしかないという事だと思っている。
写真を長くやっていればその人の個性や作風というものが出て
くるであろう、トイレンズでは、もし、たまたま面白い作品が
出来たところで、その理由がわかっていなければ、その作風
での再現性が無くなってしまう。
また、面白い写真が撮れるのは、あくまでトイカメラや
トイレンズのおかげであり、撮影者自身が色々と工夫をして
撮った結果で無い、というところも問題だと思っている。
銀塩トイカメラのブームは、2000年代なかばに収束、
2000年代後半には、あれだけ流行った(つまり高価だった)
トイカメラも、珍しいグッズを売る店とかで1000円台で
販売されるようになってしまった(まあそれが妥当だが)
しかし、2010年代、HOLGAやLOMOは主にミラーレス機
ユーザー層に向け、こうしたトイカメラのレンズを単体で
発売するようになった、価格はいずれも3000円程度、
私も何本かその手のトイレンズを買って、たまに使用して
遊んでいる。

まあでも、こうしたトイカメラやトイレンズの背景を理解した
うえで、トイレンズを使うのは面白い。
ヴィネッティング(周辺光量落ち)も出るし、フレア、
ゴーストも盛大に発生する、カラーバランスは悪く、どんな
色で撮れるかも良くわからない、ピントは勿論ボケボケだ。
ピントはMFであるが、ゾーンフォーカス型であり、
山の絵や、人数の絵が書いてあり、その目盛りに合わせる、
最短撮影距離は記載が無く不明である。
ピントリングは重くて固い。
当初、このレンズがデジタル一眼向けに単体発売された時、
6x6判(中判)用のレンズをそのまま使用したので、
焦点距離は60mmと長く、かつイメージサークルが大きいので
周辺光量落ちの効果が出なく、不評であったと聞く。
やはりトイカメラでは周辺光量が落ちないと、らしく無い。
その後、BC(ブラックコーナー)エフェクトという特殊な
機構を内蔵したバージョンに改められ、同時にミラーレス機
に向けて焦点距離も25mmに短くなった。
それが本レンズである。
BCエフェクトの実現は、いくつかの小さい穴があいている
プラスチック板を、絞りに相当する位置に配置し、
その結果、周辺光量落ちを発生させるというユニークな
機構であるが、この機構がついているため、実際のf値は
スペック通りのf8ではなく、もう少し暗いと思われる。
また、BCエフェクト機構には弱点があり、遠距離の撮影では
正しく周辺が丸く暗くなるのだが、中近距離の撮影では、
周辺光量の落ち方が、円形ではなく不規則な形に歪む。
(2つ上の銅像の写真がそれだ)
ただまあ、そういうのはトイレンズなのでどうでも良い、
面白い写真が撮れれば、それで良い訳だ。

本レンズの購入価格は、新品で3000円ほどであった、
こちらはSONY Eマウント版であるが、μ4/3や一眼用も
販売されている、センサーサイズが変わると、描写の
効果も変化するかもしれないが、それも気にする必要は
あまり無いであろう。
最近では、Qマウント版や、NIKON 1,EOS M版とかも
発売されていると聞いているので、いずれどこかで
見かけたら、他マウント版も買っておく事にしようか・・
必携のレンズという訳では無いが、たまに使うと面白い。
---
さて、次のシステム

再びトイレンズだ、しかも恐ろしく長い(汗)
カメラは、FUJI X-E1 AF精度やMF操作系に弱点を持つ。
FUJI 最初期のミラーレス機であるため、私の中では
未完成機という位置づけだ。ただ、これよりさらに
AFやMF性能の劣る PENTAX K-01であっても、
様々なレンズをとっかえひっかえして試しているうちに、
超広角AFレンズやSDMレンズでは、まあまあ使える事が
わかってきた、X-E1も、限界性能を試すとともに、
相性の良いレンズを探している状態だ。
レンズは、ニコンおもしろレンズ工房 400mm/f8である。
一眼レフユーザーにレンズ交換の楽しさを広める目的で、
魚眼、ソフト兼マクロ、超望遠の3本セットで安価な価格
(2万円弱)で発売された一種のトイレンズセットである。
1990年代の限定発売であるが、一度再生産された。
すでに、第13回記事で、ソフトとマクロを、
第18回記事で、魚眼を紹介しているので、そのセットの
詳細については重複するので割愛しよう。
本レンズは、「どどっと400」という愛称で呼ばれて
いる超望遠である。
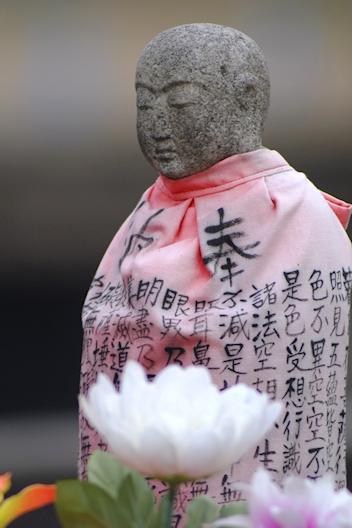
X-E1装着時の換算画角は、600mm相当と、かなりの
望遠になる、X-E1にはデジタルズーム機能は無いが、
ここまで望遠だと、そもそも被写体探しに苦労するので、
これ以上望遠になってもしかたが無いであろう。
望遠画角よりも問題なのは、そのサイズである。
紹介写真でもわかると思うが、ともかく鏡筒が長い。
実はこのレンズ、同じセットのソフト兼マクロと同様に、
分解が可能となっている。
レンズの真ん中で分割し、前群を逆さまにして後群の
中に収容できる、つまり、途中にはレンズが入っていない
スカスカの望遠なのだ(前群2枚、後群2枚の2群4枚構成だ)
でも、折りたたみ収納式とは言え、収納時でも約15cmあり、
最終的に伸ばすと、およそ26cm以上にもなる、それプラス
アダプターだ、ショルダー型のカメラバッグにはまず
収納できないサイズである。組み立ては、簡単とは言え
ねじ込み式なので、撮影時にその都度組立てるわけには
いかず、全長約30cmのままで持ち歩く必要がある。
これは周囲にも目立ちすぎるし、格好悪い(汗)
まあ、400mm超級の超望遠レンズであると、いずれに
してもカメラバッグには入らない。リュックタイプのバッグの
真ん中に収納するか、あるいは近年人気の150~500,
150~600,200~500,200~600mm等の一眼用
超望遠ズームの場合は、付属の専用のケースや汎用ケース
が販売されていて、それに収納するのが良いのだが、やはり
撮影時に、いちいちケースから出してカメラに装着するのも
面倒だ。
で、超望遠レンズをカメラにつけたまま歩くと、今度は、
周囲の人達から厳しい目線が集中する(汗)
「いったいあんなレンズで何を撮っているんだ、盗撮か?」とか、
「高そうなレンズを見せびらかして歩いている、成金趣味か?」
などである(汗)
そういう目線で見られてしまったら、いくら、このレンズは、
6000円~7000円相当の安物だよ、と値段をバラした所で、
もはや手遅れだ(笑)
超望遠レンズを使うのはスポーツ・イベントの撮影とか、野鳥や、
動物園などに限るとは思うが、そういう分野のカメラマンは
皆、いったい周囲の目線にどう対処しているのであろうか・・?

600mm相当の手持ち撮影、かつ手ブレ補正無しは、ビギナー
には相当の壁かと思うが、慣れればさほど難しくは無い。
本当に難しいのは、被写体が捉えられなくなってくる1000mm
以上の撮影だ、1000mm超ともなると、カメラを向けたところに
被写体はピタリとは入らないし、そもそもブレが大きく、
被写体が動き廻ってファインダーをはみ出す程になる。
そのあたりを我慢しつつ、ぎりぎりで1500mm程度までは
いけるのだが、それ以上はもうお手上げだ、まあそれも
技術によるかと思うので、2000mmクラスで訓練を積めば
なんとかなるかもしれないが・・

で、X-E1のピーキング性能があまり良くないので、ピント
合わせは困難だ、また、X-E1の拡大操作系は劣悪であり、
使い物にはならない。おまけに、このレンズは、MF操作でも
トルクという言葉のカケラも無いほど、ギリギリと金属の
きしみ音を立てながらヘリコイドが廻る。
まあ、元々、トイレンズなのでそのあたりはしかた無い,
でも思ったよりも結構写るでは無いか。
聞くところによると、この「おもしろレンズ工房」は
コストダウンを狙うために、様々なところで安価にレンズ
を作る工夫がされているとのことで、この「どどっと400」
も、元々はレンズ構成をもっと単純化する予定であったのが
試作品ではレンズ全長が長くなりすぎ、レンズ長を短く
しようとした結果、天体望遠鏡と同等の2群4枚構成に
なったとの事だ。これで画質は向上したとの事だ。
・・でも、その割には、依然レンズが長すぎるが(汗)
ちなみに、最短撮影距離は、4.5mと、恐ろしく長い(汗)
まあでも、天体望遠鏡風のレンズ構成なので、それもまた
しかたないか・・

本レンズは、「おもしろレンズ工房」セットとして3本組
で発売されていたので、単品ではまず入手が出来ない。
セットも発売数が少なく、ほとんど中古が出てこない
あったとしても、コレクターズ・アイテム扱いとして
「時価」になってしまう事であろう。そこまで無理して入手
するべきレンズでも無いと思うので、まあ、運良くこれを
所有している人がいれば、たまには使ってみるのも面白い、
という感じであろうか。
勿論実用的には現代の超望遠ズーム(テレ端500~600mm
級等)がはるかに使いやすいと思うので、それらを5~7万円
程度で中古購入し、デジタル一眼に装着して750~960mm
相当の画角にして使うか、あるいは、マイクロフォーサーズ+
オールド望遠単焦点+デジタルズームで手軽に1000mm
程度の画角を得るのか、いずれかが良いと思う。
(ロングズームコンパクトでも良いが、近年良い機種が無い)
---
さて、次は今回のラスト。

カメラは、LUMIX DMC-GX7である。
高感度、ピーキング、ボディ内手ブレ補正、エフェクトなど、
最新の機能を持つ比較的新しいカメラだが、旧機種に比べ、
操作系に若干の問題も抱えている。
レンズは、ミノルタα用 AF Soft 100mm/f2.8 である。
ソフトレンズは、本シリーズでは、第5回記事でのVK70R,
第14回記事での「ふわっとソフト」、第19回記事での
KENKO 85mmソフト、をそれぞれ紹介しているのだが、
いずれの記事でも「ピントをどうやって合わせるのか?」
という問題点が発覚していた。
第19回記事では、NEX-3の優秀なピーキング機能との
組み合わせでトライしたが、ピーキングが検出されず、
お手上げに近い状態であった。
本レンズは、希少なオートフォーカスを実現したソフト
レンズである、この AF Soft Focus 100mm/f2.8の他は
キヤノンEF135/2.8 Soft、PENTAX FA Soft85/2.8 が
存在していたのを記憶している。他にもAFソフトは存在する
かも知れないが、私が知っているのは、その3本だけである。
(注:ニコンDC105/2 第35回記事は、私はソフトレンズとは
見なしていない)

MFのソフトレンズの殆どは、絞りとソフト量の調整が
共通化されている、つまり、絞り込むと収差が減って
同時にソフト効果も無くなるのだ。
本レンズは、その点異なり、絞りとソフト効果を別々に
調整する事が可能だ、そして、ピーキングでは手も足も
出なかったのに、何故かAF一眼ではAFが動作していたのだ。
(やはり位相差AFだからか?)
今回、GX7の優秀なピーキング機能を使いながら、
そのあたりの謎を探ってみる事にしよう。
まず、ピーキングであるが、GX7では、多少は検知する
模様だ、ただ、それはソフト量と密接な関係があり、
あまりソフト量を増やしてしまうと、やはり検知できない。
絞りとソフト調整が別々のリングになっている件であるが、
本レンズを使用する上で、マウントアダプターは、
レンズの絞りレバーを機械的に操作して絞り込むタイプの
アダプターを用いている、絞り羽根内蔵型とは異なり、
このタイプでは実際に絞りを動作させているので、
一眼レフに装着した場合と同等であろう。
で、絞り開放ではやはりソフト量が大きくなる。
ソフト量調整は、4段階で、0,1,2,3の各々の目盛りが
ある、0から3に向けて、前玉の繰り出し量が減る、
このことで何か、レンズの収差を増やしていると思う。
ただ、これは撮影直前にそうなるのではなく、ソフト量
を調整すると、その時点でレンズ構成が変化するのだ。
だから、一眼でのピント合わせは、それができやすい
レンズ構成のままで行うのでは?という予想は外れである。
あくまで、ソフト効果のままでピントを合わせている訳だ。
そして、ソフト量調整を大きくしたとしても、絞りを
絞り込むとソフト効果は出にくくなる。
思っていたような「絞りとソフト量は完全に独立」という
訳ではなさそうである。

結局のところ、ピーキング機能は、ソフト量調整と
絞り値の相乗によるソフト効果の程度次第で、検出できる
場合もあり、そうで無い場合もある、という感じであった。
つまり、ソフト効果を減らせば、ピーキングで拾えるが
増やしたらお手上げ、という事である。まあ、それは
当たり前の話だ、NEX-3の時よりも、GX7の方が若干は
マシなような気もしているが、レンズにもよるであろう、つまり
KENKO のソフトは、ソフト効果大で使う事が大半であったが
本レンズ AF Soft 100mm/f2.8は、ソフト量調整リングを
頻繁に操作しているので、ピーキングでピントを合わせた
後で、ソフト量を増やすという操作も出来るからである。
きっと、一眼レフ用の位相差AFセンサーは、ミラーレス機
用のコントラスト検出AFよりも、ピント精度が高いので
あろう、だからソフトレンズにおいても、一眼の位相差
であればなんとかピント合わせが出来るのかも知れない。
実際のところは良くわからないが(汗)まあ、無難な結論
なので、そういう事にしておこうか・・

で、ソフト効果ばかり続けて撮っていると疲れてくる、まあ、
最大の問題はそのピント合わせなのだ。
なので、ソフトレンズではあるが、ソフト効果を使わず、
GX7の多彩な機能と合わせて楽しむとするか。

GX7のエフェクトである「インプレッシブアート」つまり
擬似絵画調HDR効果である、GX7の場合は、他メーカーの
同機能のように、露出をバラした連写をする訳ではなく
単写なので気軽で良い。連写タイプの本格的なHDR機能では
撮影後の画像合成に、数秒から10秒近くかかってしまう
事が多く、あまり実用的では無いのだ。
ちなみに、GX7には「ソフトフォーカス」効果のエフェクト
も内蔵されているので、ソフトレンズを使わなくとも
ソフト効果を得る事ができる。
まあでも、それで十分、と言ったら、ソフトレンズの存在
価値が無くなってしまう、エフェクトと本物は若干違うのだ。
そして、ソフトフィルターという物も昔から存在しているが、
それもやはり本物のソフトレンズとは若干効果の出方が変わる。
やはり、ソフトレンズには、それなりの存在価値があると言って
良いであろう。
なお、本レンズの最短撮影距離は、80cmと短いので、
マクロ的な近接撮影にも向いているであろう。

こちらは、GX7のデジタル・テレコンを使って4倍相当に
した写真だ、100mmレンズxμ4/3(2倍)xテレコン4倍で
都合800mm相当、しかし、ここまでくると画質の劣化が
はなはだしく、パキパキの画像になってしまう。
パナソニックのミラーレス機では実用的な範囲としては
デジタルズームでの2倍程度か、もう少しはいけるか?
という感じであろう。
ちなみに、SONY NEX-7でも、オールドレンズでデジタル
ズームが可能であるが、そちらは10倍まで可能なものの、
実用的には、3~4倍程度だと思う、まあ、Gシリーズより
若干ましなのであるが、Gシリーズはμ4/3なので、
NEX-7の約1.5倍の画角となる、なので、総合的には両者は
ほぼ同等という事になり、マスターレンズの画角の、都合
5~6倍程度までは、ミラーレス機+デジタルズームでは
実用範囲という感じだ。
本レンズ、MINOLTA AF Soft Focus 100mm/f2.8 の
入手性だが、極めてレアである、中古はまず見ないし、
あったとしても「時価」になってしまうであろう。
私が購入したのは1990年代後半で、35000円であった、
これは当然高価すぎたと思う、でも、レアであったので
思わず・・(汗)その後、キヤノン版のEF135/2.8SOFTで
あれば2万円台で入手できた、そちらも一度購入したので
あるが、どうしても欲しいという人に譲渡してしまった。
ただ、キヤノン版の方が豊富に中古市場にはあったと思う。
あるいは、AFに拘らなければ、KENKO の85mm SOFTは、
1万円前後の安価な価格で入手できるので、それでも十分だと
思う、各MFマウント版があるが、実はそれは交換可能であり
(=Tマウントシステム)、どうせミラーレス機でアダプター
で使用する上では、マウントは何であっても良いであろう。
さて、今回はこのあたりまでで、次回シリーズ記事に続く。