「オールドレンズ」ならぬ、古いデジタルカメラを、
時代とカテゴリーで分類して、順次紹介していく
シリーズ記事。
今回の記事はコンパクト(デジタル)カメラ編の
その2(後編)とし、2007年~2010年代前半の
コンパクト機を、6機種(+α)紹介する。
言うまでも無いが、本シリーズ記事に登場する
カメラは、勿論、全て自身で購入した現有機であり、
過去および現役で長期に使用してきたカメラである。
単に機種名や仕様を調べて纏めただけの記事では無い。
----
では、今回最初のオールド(デジタル)コンパクト機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
カメラは、FUJIFILM X-S1 (2/3型機)
(2011年発売、発売時実勢価格約8万円)
(中古購入価格 27,000円)
レンズ仕様、24~624mm(相当)/f2.8~5.6
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第4回
まず最初に。
本記事(及び第3回記事)で紹介しているコンパクト
(デジタル)機は、2016年の本ブログのシリーズ記事
「コンパクト・デジタル・クラッシックス」(計4記事)
と紹介機種の大半が重複している。
その為、本記事では各紹介機の仕様等は割愛し、長所
や短所等も、できるかぎり簡略化して述べる事とする。
なお、何故、6年も前の記事と重複する内容になるかは
その時代以降、欲しいと思えるコンパクト機の発売が
皆無であったからだ。何故そうなってしまうのか?は、
勿論、コンパクト(デジタル)機の市場が大きく縮退し、
高付加価値化戦略等もあった為、コスパに優れていて
魅力的な機種が1つも無くなってしまったからである。
本記事においては、そのあたりの市場分析等も、適宜
おりまぜて説明していく事とする。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
さて、FUJIFILM(社)だが、1998年の「FinePix700」
から、デジタル(コンパクト)カメラの販売を
開始している。発売当初は、自社のフィルムビジネス
を否定するデジタル機の発売に驚きの声も上がったが、
まあ、その当時からフィルムからデジタルへの変遷は
当然の流れとして見なされていた為、無理にフィルム
事業にしがみ付かなかった事は英断であっただろう。
(参考:同じくフィルム大手の米KODAK社は、1970年代
頃から、デジタルの撮像センサーの開発を行っていた)
初期のFinePixシリーズは、高描写力・高品位な事が
評判であり、2000年代前半頃まで、人気のブランド
であった。だが、2000年代後半では、デジタル一眼
レフも一般層に普及した為、高画質を求める消費者層
は、そちらに興味の対象を向けていく。
さらに、2000年代末では、ミラーレス機の登場、
そして携帯電話搭載カメラや初期スマホの普及により
(デジタル)コンパクト機のビジネスは、だんだんと
苦しくなっていく。
なので、FUJIFILM社は、2000年代後半からは、
女性向けのスタイリッシュなFinePix Zシリーズや、
望遠機能を増強したロングズーム機(注:FUJIでは
「ネオ一眼」と呼んでいた)FinePix Sシリーズ等
の多面的な商品展開を始め、新規購入層の市場開拓
を意図する。
しかし、2010年頃からは、ミラーレス機とスマホの
普及がさらに加速した為、コンパクト機のビジネスが
いよいよ厳しくなってくる。
そこでFUJIFILMは、それまでのFinePixの各シリーズを
縮小し、防水機能を主体としたFinePix XPシリーズと
高付加価値型(=価格が高く、販売数が少なくとも
利益率が高い)Xシリーズ(注:FinePix銘は無し)
に戦略転換をする。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
本機X-S1は、初期(2011年~)のXシリーズの
製品であり、同時代の製品には、他には
*高級(単焦点)コンパクト機の「X100」
(注:最初期の販売品のみFinePix銘)や、
*高級ズームコンパクト機「X10」
(いずれも2011年発売)がある。
これらは、高性能・高機能を謳ったカメラであるから
市場からは好意的な印象で受け止められたのだが、
当然ながら「高価に売りたい」商品群である為に、
価格帯は旧来のFinePixシリーズよりも大幅に上昇した。
(X100=約13万円、X10=約7万円、X-S1=約8万円。
従前のFinePix Fフタケタ機等は、約5万円の定価)
FUJIFILMは、このXシリーズの市場での好評価を受け、
翌年2012年には、同Xシリーズでミラーレス機市場に
参入する。(X-E1等、ミラーレス・クラッシックス
第6回記事参照)
さて、という事で、本機X-S1は、私があまり好まない
「高付加価値型商品」(=たいてい、コスパに劣るから。
そして、そういう高価な商品は、レビュー記事等では
”売りたいが為の高評価”しか行わず、面白く無い)
なのではあるが、大型センサーを搭載したロングズーム機
は珍しく、手動ズーム機である事は、他社の同等製品には
存在しない「唯一無二」の仕様であった為、そういう風に
パフォーマンス(実力値、実用性能)が高い機種であれば、
「多少コストが高くても、コスパが悪いとは見なさない」
という持論を適用して、本機を購入する事とした。
主要利用目的はボート競技の撮影であり、実際に2010年
代に本ブログに掲載しているボート競技の写真の多くは、
本機X-S1で撮影している。
ちなみに、本機X-S1以降、ロングズーム機で手動ズーム
搭載機は絶滅してしまった。本機での特性が歴史上最後と
なっているので、本機は予備機も一応所有している。
(注:予備機については、FUJIFILM製カメラの耐久性は
低いという認識があるからだ、詳しくは後述しよう)
まあ、本機はスペック上の優位性は高い機体ではあるが、
ただ、実用的に撮影に用いるのは、本機X-S1には色々と
弱点があり、最大の課題はAF/MF性能に劣る事である。
まあ、コンパクト機のコントラストAFでは、限界がある
事は確かではあるが、AFが合い難く、ボート競技等での
重要なシーンを撮り逃がす事も多々あった。
よって、2010年代末頃からは本機X-S1をボート競技
に持ち出す事も減り、デジタル一眼レフや、(AF精度
が向上した)ミラーレス機を、本機の代替としている。
しかしながら、望遠域を利用可能なサブ機というのも
殆ど存在しない為、X-S1を使わない、という措置は
必ずしも適正では無い。そこが困った問題なのだが、
代替できる機種が(本機以降の時代においては)1つも
無いだけに、まあ、やむを得ない状況か・・
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17291970.jpg]()
なお、電動ズーム搭載機は私の用法では使用不可だ。
所望する画角に速やかに調整が出来ないロングズーム機
などは、私の感覚では、実用上では有り得ないカメラだ。
一眼レフ等用の本格ズームレンズは全て「手動」である、
その事実は、市場の誰もが知っているだろう。
何故、コンパクト機では、手動ズーム機を作れない
のであろうか? むしろ製造コストが増加するから
だろうか? だとしたら、価格が高くなったとしても
手動ズーム機を販売/併売すれば良いだけの話だ。
それとも、初級ユーザー層が「電動ズームでなくちゃ
嫌だ、今時手動操作など格好悪い」などと誤まった
感覚を持っていいるからだろうか・・?
まあ、なかなか困った状況である。
それと、前述した、デジタルコンパクト機の衰退の歴史
はFUJIFILM社だけに限った話では無い、これについては
もう少し詳細を後述しよう。
----
では、2台目のオールドコンパクト。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17292671.jpg]()
カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-LX3 (1/1.63型機)
(2008年発売、発売時実勢価格約6万5000円)
(中古購入価格 9,000円)
レンズ仕様、24~60mm(相当)/f2~2.8
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第3回
私が「準」高級コンパクトと定義している、隠れた
高性能機である。広角中心でズーム比が小さい搭載
レンズは、スナップ撮影用途を想定されるとは思うが
シームレスに動作するデジタルズーム機能を搭載
していて(若干の画質劣化を伴うが)最大約400mm
相当の望遠画角までの利用が可能だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17292630.jpg]()
操作系は独特だが悪く無い。本機あたりの時代から、
Panasonic(LUMIX)のコンパクト機や初期ミラーレス機
の操作系が、撮影時での効率について意識され始めて、
使い易いカメラとなった。
その理由としては、本機の時代の数年前に、関西系の
老舗カメラメーカーのいくつかがカメラ事業から撤退して
いて、それらに属していたカメラ技術者がPanasonic
(やSONY)に流れ、家電メーカーの状態から参入した
新規カメラメーカーでの新製品開発における、写真撮影
に係わるノウハウの投入がなされたのだと推測している。
まあ、簡単に言ってしまえば、写真を撮っていない人が
カメラを作る(設計する)のは、無理な話であり、
ちゃんと実用的に使えるカメラの開発には、写真撮影
経験が深い人達が居ないと困難、という事である。
そういう差異は「操作系」に、モロに現れてくる。
現代のカメラでも、写真を撮るという行為において、
非常に使い難いカメラも多々存在している事は確かで
あり、そういうカメラは設計時点で、「写真を撮る」
時の手法を、あまり/全く意識していない事が明白だ。
「写真を撮った事が無いのに、カメラを開発している」
というのは残念な話だが、これは明らかな事実だ。
何故ならば、そのカメラを持ち出し、1時間でも写真を
撮ってみれば、ビギナー層でも簡単に認識できるような
欠点が色々と発見できるだろうからだ、これはどう考えても、
カメラを作っている側に写真撮影ノウハウが無いという
事であろう。下手をすれば技術者は開発中のカメラを屋外
に持ち出して試写するような事もしていないかも知れない。
非常に専門的な業務であるデジタル設計をする人達が、
全て、カメラ/写真のファン層である保証は全く無い。
なお、これは歴史のある大メーカーでも同様であり、
メーカーの問題というより、機種(開発チーム)毎の
カメラ設計スキルや設計思想の差異の課題が大きいのと、
また、そうした不完全な仕様の製品が、そのまま市場に
出てしまう、チェック・決議体制にも問題があると思う。
ただ、現代においては消費者やユーザー側でも、そうした
写真撮影のノウハウが少ないビギナー層の比率が増えて
きていて、新鋭の高級カメラをフルオートの撮影モードで
撮っている(フルオートでしか撮れない)ユーザーが
大多数、という情けない状況だ。
そういうユーザー層では「カメラの使いやすさ」などは
理解できる筈も無く、”ダイヤルやスイッチが廻し易い、
押し易い”、”タッチパネルで操作が出来る”等の、
単なる「操作性」についてしか、評価をする事が
できない、という残念な世情である。
これでは、メーカー側としても「操作系を改善する」
という事は、たとえその課題に気づいていたとしても、
優先度の低い開発項目となってしまうのだろう。
具体例としては、操作系の優れたSONY NEX-7(2012年)
は、続くα7系シリーズ(2013年~)で、初級中級者層
向けの安易な操作系にダウングレードされているし、
旧来機よりも操作系が格段に向上したPENTAX KP(2017年)
は「高感度が搭載されただけで値段が2倍に値上げされた」
という悪評が初級ユーザー層の間で流れ、不人気だ。
まあつまり、操作系の良し悪しは、フルオートのモード
でしか撮らないビギナー層には無縁の話であり、むしろ
そこにメーカー側が手を掛けたとしても、ユーザー側では
「使い難い」「さっぱりわからない」「複雑すぎる」等の
ネガティブな評価しか出来ない状態になり易い訳だ。
(注:現代の中級クラスでも似たりよったりであり、絞り
優先AEでの絞り値変更、測距点変更、露出補正、だいたい
そのあたりの操作しかしない事であろう)
困った世情ではあるが、これもまたカメラ市場の縮退から
来るものであり、高付加価値化して高価になりすぎた
カメラには、中上級層は興味を持てず(今までのカメラ
でも十分に撮れるからだ)、そうした高価な新鋭機を、
カタログスペックだけに注目するビギナー層が買う、
という現代市場での図式が課題なのであろう。
つまり高付加価値機には、当然、新しい高機能が搭載されて
いるのだが、ビギナー層では、その新鋭機能を活用する手段
や技法が全くわかっていない、という矛盾を生んでいる訳だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17292637.jpg]()
ここで本機DMC-LX3の操作系の長所を説明しようと思ったが
今回はやめておく、もう古いカメラだから今更入手不能だし
そもそもコンパクト機のユーザー層で、あれこれとカメラの
設定を変えて撮ろうとする人達は、そう多くは無い。
で、本機DMC-LX3の後の時代の後継機では、これもまた
高付加価値化してしまい、そこそこ高価になってしまった
(例:DMC-LX9=約9万円弱、DMC-LX100=約11万円)
まあ、本機DMC-LX3と、続くLX5/LX7あたりまでがコスパ
に優れる準高級コンパクトだとは思うが、既に発売年代が
古く、中古市場でも殆ど流通していないのが課題である。
本機の優れた操作系設計仕様は、後継機に引き継がれて
いるかどうか?は、後継機は未所有なのでわからない。
ただまあ、この後の時代には、どのカメラも高付加価値化
と高機能化されて、そこに操作系の改善が追いついて無い
状況が普通だ・・
----
さて、3台目のオールドコンパクト機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17292672.jpg]()
カメラは、 NIKON COOLPIX S50 (1/2.5型機)
(2007年発売、発売時実勢価格約3万5000円)
(中古購入価格 12,000円)
レンズ仕様、38~114mm(相当)/f3.3~4.2
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第3回
ごく平凡なスペックのオーソドックスなコンパクト機
である。特に記載するべき特徴も無いが、NIKONの
コンパクト機としては、無難にまとめた印象だ。
(注:何故「NIKONとしては・・」という話になるか?は、
NIKONは低価格帯商品に力を入れない企業戦略だからだ。
コンパクト機における、その実例は、銀塩コンパクト・
クラッシック第2回「NIKON MINI(AF600)」編に詳しい)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293103.jpg]()
特徴に欠けるコンパクト機なので、マニア的視点からは
あまり書くべき内容は無い。
まあ、ここで前述の、コンパクト(デジタル)機の歴史の
話の続きをしておこう。
最初に一般ユーザーに注目された(民生用)デジタル
コンパクト機としては、CASIO QV-10(1994年発表、
1995年発売)が、初と言って良いであろう。
価格は65,000円であり、初のデジカメとしては安価だ。
ただし、若干の性能上の未成熟もあって、実用機と
しての初は、QV-10A(1996年)が上げられると思う。
オフィス用途(画像情報伝達・共有)としても良く
使われ、多くの企業等にも、QV-10Aは普及した。
その後1990年代後半には、OLYMPUSやFUJIFILM等
からも民生用コンパクト(デジタル)機が発売され、
2000年代前半頃までに、一気にこれらコンパクト
機は、一般層に迄、普及する。
以下、最初期のコンパクト・デジタル機の代表機だ。
1996年
CASIO QV-10A
OLYMPUS C-400L/C-800L
CANON PowerShot 600
SONY CyberShot DSC-F1
1997年
CASIO QV-11
OLYMPUS C-1400XL
MINOLTA Dimage V
1998年
FUJIFILM FinePix700
以降は記載省略。膨大な機種数がある。
また、これらの機種群の現有数はゼロである、
何台かは使っていたが、古過ぎて、故障廃棄やら
譲渡処分となってしまっている。
2000年代前半には、デジタル一眼レフも色々と
発売されるが、廉価版コンパクト機の10倍近くも高価
であった為、本シリーズ第3回記事で説明したように、
「ガンデジ」「コンテジ」と言った一種の差別用語が
生まれる事となった。(注:デジタル一眼レフが
欲しくても買えないから、そういう俗語で卑下する。
G/D/Z濁点系発音の呼称は、普通は「敵役」の名前だ。
ただし、「機動戦士ガンダム」だけは例外。これは
もしかすると、「連邦とジオンのどちらが正義か?」
を、あえて曖昧にする意図があったのかも知れない。
他のアニメや映画等は、殆どがシンプルな勧善懲悪
形式なので、濁点系呼称は敵役として、ごく普通だ)
2000年代後半ともなると、デジタル一眼レフの
価格帯も下がり、一般層でも入手できるようになると
「ガンデジ」「イチデジ」「デジイチ」と言った
蔑称からなる差別用語は瞬時に死語となる。
この時代、コンパクト機の記録画素数は1000万画素
を超えるものも出て来て、既に成熟期である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293190.jpg]()
ちなみに、銀塩35mm判フィルムは、当然アナログで
あるから、画素数という概念は無いのだが、一般的に
「35mm判フィルムの画素数は、デジタルの1000~2000
万画素に相当する」と言われている。つまり、この時代
にデジタルカメラ(一眼レフもコンパクト機も)の
画素数はフィルムと同等か、それ以上となった訳だ。
(注1:単純に「画素数が大きければ高画質だ」という
訳でも無い。特に一眼レフでは、装着するレンズの性能に
依存する要因の方が、センサーの画素数より遥かに大きい)
(注2:フィルムをデジタルの画素数に換算する方法論は
不明である。真面目にやれば「ウィーナースペクトル」や
「RMS粒状性」から換算できるのかも知れないが、専門的
すぎて計算方法は不明だ。しかも原理的にも、そう簡単
に、アナログとデジタルを対応できるとも思えず、単に
「だいたいこれくらいか?」という感覚値で、誰かが
言い出した事が、広まったに過ぎないかも知れない?)
だが、この時代には、既に、携帯電話のほぼ全てに
カメラ機能が搭載されていた。まあデジタルカメラの
技術が進歩(および低価格化)した為、携帯電話等への
搭載が可能となった、とも言えるであろう。
しかし、それがむしろ仇となり、簡易撮影機材としての
コンパクト(デジタル)機の用途は、どんどんと減っていく。
2010年前後には、ミラーレス機および初期スマホの
台頭により、コンパクト機の売り上げはさらに鈍化し、
(本記事で紹介している時代)その後のコンパクト機は、
販売台数が少なくても利益が上がる「高付加価値化」商品
となってしまっている。(つまり、大幅に値上げされた)
2010年代後半頃からのコンパクト機には、コスパの良い
魅力的な機種は残念ながら皆無となってしまい、私も、
その時代以降のコンパクト機は殆ど所有していない。
(注:2015年以降では2台のみ購入、順次紹介予定)
まあ、こんな歴史であり、結局のところ1990年代後半
から2010年代後半迄の高々20年程度が、コンパクト・
デジタル機の時代/黄金期であった訳だ。
(匠の写真用語辞典第19回「カメラ形態20年寿命説」
の項目を参照。これはつまり、様々な銀塩/デジタルの
カメラの形態は20年程で進化のピークに達してしまい、
新機種での改良の余地が無くなり、別のカメラの形態
に変化せざるを得なくなる、という持論である)
さて、ここで、本機S50の時代の少し後に発売された
ユニークなNIKON機についても「補足」として紹介して
おこう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293100.jpg]()
カメラは、 NIKON COOLPIX S1100pj (1/2.3型機)
(2010年発売、発売時実勢価格約4万3000円)
(新品購入価格 15,000円)
レンズ仕様、28~140mm(相当)/f3.9~5.8
プロジェクター(投影)機能搭載
希少な「プロジェクター機能」搭載カメラであり、
本機と前機種S1000pjのみ2機種が市販されただけ、
だと記憶している。
その後、このジャンルの製品が伸びなかったのは、
デジカメの内蔵電源では、プロジェクション(投影)
に必要な光量が確保できなかったからであろう。
私も本機を、カメラ仲間の集まりに作品の投影用に
使ったり、プレゼンやレクチャーでの資料投影用にも
用いてみたが、いずれも光量および投影解像度の
課題があって、あまり実用的だとは言えなかった。
プロジェクターの機能を封印し、カメラとして使おう
とも思ったのだが・・ 本機の操作系は壊滅的な程の
低レベルであり、何故そんな事になっているのか?と
目を疑うばかりだ。まあ、カメラとしての利用も難しく、
ほとんど活用機会が無いまま、ビジネスメモ用途機
としてカバンの中に入っている次第だ。
---
では、4台目のコンパクト機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293117.jpg]()
カメラは、YASHICA EZ Digital F537 IR (1/3.2型機)
(2010年発売、発売時実勢価格約8,000円)
(新品購入価格 7,000円)
レンズ仕様、40mm(相当)/f3.2
近赤外線(NIR)投射・近赤外線撮影機能搭載機
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第4回
本機には、YASHICAのブランド銘がついているが、
元祖ヤシカや、京セラ傘下のヤシカ製では無い。
京セラが2005年にカメラ事業から撤退した後は、
ヤシカ/YASHICAのブランドは、様々な企業を転々と
している(名前だけが譲渡されている)状態だ。
本機の時代では、EXEMODE(エクゼモード)
(株式会社ドリーム・トレイン・インターネット)
が、YASHICAブランドの商品を取り扱っていた、
製造は、恐らく海外(中国)製であろう。
この後、EXEMODEもYASHICA銘を手放した模様であり、
2010年代末頃では、全国的雑貨チェーン店である
ヴィレッジバンガード(Village Vanguard Webbed)
が、フィルムカメラ風デザインのYASHICA銘の
トイカメラを扱っていた。(未所有)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293927.jpg]()
本機は、希少な近赤外線投影機能を持つコンパクト
機ではあるが、性能は「トイカメラ」相当であり、
実用性が殆ど無い事が課題である。
近赤外線については、専門的技術分野である為に、
巷での大多数の人達は、その具体的内容を理解できて
いない。その為、様々な誤解が存在するが、他記事でも
何度も書いてきた内容な為、そのあたりは割愛する。
まあ簡単に言えば、近赤外線は一種の「光」であるから
それを「写真」として映像化する事は可能だ。
しかし近赤外線は人間の目に見えない「光」である為、
特殊な用途に用いられる。その代表的な応用は、暗所
での監視カメラ(セキュリティ用途の物)であろう。
そして、本機の構造もまたその通りであり、監視カメラで、
「デイナイトモード」(昼間も夜間も監視が出来る機能)
を搭載している機体と、ほぼ同様である。
面白いコンセプトのカメラではあるが、このジャンルの
カメラは残念ながら本機で終了であり、その後、類似した
商品は出てきていない。
以下余談だが、本機より以前の時代で、SONY製の近赤外線
ビデオカメラの商品が存在していたが、「暗所での盗撮」
等の不正な目的に利用された為か?すぐに発売中止となり、
後継機は存在していない。
ちなみに、この製造中止となった希少なカメラを後年に
高額に転売する目的か?「赤外線では水着が透けて写る」
等の根拠の無いデマが大々的に流れた。そういうデマを
流せば、「お金を出しても欲しい」と言う好事家が出て
くるからであろう。他に「健康に良い」などと言う話も
巷では良くあるが、残念ながら、「近赤外線」は単なる
光の一種であるから、そうした「嬉しい効能」は無い。
(注:一般層では、近赤外線と、中(熱)赤外線の
原理を混同しているケースが大半である)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293912.jpg]()
本機F537 IRでは、そうした投機的要素は幸いにして
無い模様だ。まあ、元々販売数も少ないカメラだとは
思うし、基本的にはトイカメラ相当だ。いくら近赤外線
投射機能があるとは言え、その到達範囲は数mと短く、
かつ基本的な感度はISO100相当でしか無い。これで
暗所でブレずに撮影が出来るようならば、もう達人の
領域であろう。全くブレずに上手く暗所で撮れている
写真を見かけたら、それは赤外線撮影風に見せた偽物
(フェイク)写真である可能性も高い事は述べておく。
(→愉快犯、または投機的な相場高騰が目的)
----
では、5台目のコンパクト機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293970.jpg]()
カメラは、FUJIFILM XQ1 (2/3型機)
(2013年発売、発売時実勢価格約4万5000円)
(中古購入価格 24,000円)
レンズ仕様、25mm~100mm(相当)/f1.8~4.9
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第4回
本機は従前記事で紹介した「FinePix F10(2005年)」
の再来とも言えるカメラであり、高性能・高機能が
特徴である。それでいて価格が比較的安価であり、
「コスパ」評価が非常に高く、名機と言えるだろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17293977.jpg]()
FinePix F10では「壊滅的」と言える程の酷い操作系
設計が最大の弱点であったが、本機XQ1では、さすがに
F10から8年の時を経て、多少は改善されている。
(注:Xシリーズの始まった2011年頃から、FUJI機の
操作系は、若干だが改善された。
両者の差異等の詳細は、本ブログの旧記事
「名機対決 FinePix F10 vs XQ1」編を参照の事)
まあ、本機XQ1であれば、コンパクト機の域に留まらず
実用レベルのカメラとしても及第点であろう。
・・というか、恐らくは、普及コンパクト機最後の
実用機が、本機XQ1であると思う。
あまり褒めて、中古相場が上がってしまうのも良く無い。
本機は、もし壊れたら同一機種を中古で再購入する
予定なので、適正な相場のままで推移してもらいたい訳だ。
(参考:銀塩時代から現代に至るまで、FUJIFILM製の
カメラで耐久性に劣るものが稀にある。私は計数十台の
FUJI機を所有していたが、故障廃棄となってしまった
ものが5~6台もある。私は物持ちが良く、所有カメラの
平均故障率は3%以下の比率であるのだが、FUJI機では
20%程度を超える故障率だ。本機XQ1と同時代のXF1も
XQ1のサブ機を想定して購入したものの、そちらも
やはり故障廃棄となってしまい本ブログでは未紹介だ。
また本機XQ1も2021年頃、背面のコマンドダイヤル
(ロータリーエンコーダー)が接触不良となって
しまっている。(絞り値等を廻しても変化しない)
また、従前にも、カメラ前面のコントロールリングが
同等症状の接触不良となった事がある。
これらは接点復活剤の注入で復旧したが、どうにも
耐久性が怪しい状態である)
で、特に近年では、投機層がFUJIFILM製の様々な希少な
カメラに目をつけ、常識では考えられない程の高額相場
で売却しようとしている模様だ。勿論そんな風に不条理
なまでに相場高騰したカメラを買おうとする実用派
マニアは皆無であるが、また別の投機層が、さらなる
転売利益を出す為に高額相場を受容するケースもある。
けど、そういった「実用上とは無関係の理由」で、
適切な市場バランスを乱してもらいたくないと思う。
また、その為に、FUJIFILM製の各種オールド機を「名機」
として紹介するレビュー記事等も増えている。それらは
多分に「投機的」観点も強い(=高額に売りさばきたい)
ケースも多いだろうから、要注意だ。
(簡単な回避策としては、「名機」のキーワードで
FUJIFILM機を検索しない事が賢明だろう)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17294692.jpg]()
さて、本機以降の時代のコンパクト機では魅力的な
機種が殆ど発売されず、結果的に私も、僅かに2台
しか、コンパクト機を購入していない。
「カメラマニアですら、殆ど欲しいカメラが無い」
というのが、残念ながら現在のコンパクト・デジタル機
の市場の様相である。
----
1機種だけ、簡単に紹介しておこう。
今回ラストの(デジタル)コンパクト機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17294686.jpg]()
カメラは、SIGMA dp0 Quattro (APS-C型機)
(2015年発売、発売時実勢価格約11万円)
(新古購入価格 66,000円)
レンズ仕様、14mm(21mm相当)/f4
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第5回
(注:掲載予定記事)
他記事で詳細紹介前の機体だが、ここで取り上げる。
コンパクト機と言うには、あまりに大きいカメラだ。
いや、大きいというよりも、この異形のフォルムは
縦横がそれぞれ長く、カメラバック等への収納も、
ほぼ一眼レフ等と同等の容積を必要としてしまう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17294602.jpg]()
大きな特徴は2つある。
まず、Foveon X3(Quattro)という特殊な撮像センサー
を搭載している。このセンサーは3層構造であり、
B(青)、G(緑)、R(赤)の光を3層で受けて
それを画像化する為、カラーフィルターやローパス
フィルターが不要であり、補間をせずに額面どおり
の画素数(解像度)が得られる。(注:他の一般的な
ベイヤー配列センサーは、RGGBのカラーフィルター
がある為、フル画素の1/4しか実効画素数が無い。
これを、4倍等に拡大(演繹)補間して用いる為、
場合により、フル画素よりも、小画素で撮った方が
解像感が高くなったりする)
なお、Quattro型(APS-C)センサーでの画素数は、
トップ層約2000万、第2/第3層が各500万画素
である。複雑な仕組みにより、これでも一応
2000万画素相当の記録解像度(=記録画素数)
は得られるのだが、前述の演繹補間演算の手法が
不明(特許を閲覧しても、依然不明)な事から、
個人的な嗜好性(=内容が良くわからない技術
に対しては、安全策を取る)により、本機では
常に第2層相当の500万画素で撮るようにしている。
第二の特徴として、デジタルの単焦点コンパクト
機では(アクションカメラや全天球カメラを除き)
最広角である14mm(換算21mm)の超広角レンズ
を搭載している事である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17294603.jpg]()
この2つの特徴により、本機dp0 Quattroは非常に
マニアックなカメラである。よって、あまり多数
が売れている様子も無いし、ユーザーレビュー
(流通等での販売側が書く「宣伝記事」を除く)
も、殆ど存在しない。
本機について詳しく語ると、非常に長い文章量を
必要とする。詳細はやむなく割愛するが、興味が
あれば「コンパクト・デジタル・クラッシックス
第5回」記事(掲載予定)を参照されたし。
(ただし、約2万文字の、超長文記事である)
ごく簡単に長所、短所のみ述べておこう。
<長所>
*高い解像感による、極めてシャープな絵作り
*周辺減光や歪曲収差が殆ど無い優秀なレンズ
*マニアックな製品企画コンセプト
<短所>
*搭載レンズの逆光耐性が非常に低い
*カメラとしての性能・機能不足
*操作性・操作系が悪い
*中途半端に大きく、場所を取る
*ノイズ耐性、高感度性能が低い
まあ、だいたいこんなところか。
前述したとおり、2010年代はコンパクト機の
受難の時代である。まあスマホが台頭(普及)
すれば、そうなるのもやむを得ないであろう。
だから、製品企画的にも、まずは販売数減少を
補填する為の、高価格(高付加価値)型のコンパクト
機ばかりとなってしまった。ただ、いくらコンパクト
機の性能を上げても、ミラーレス機等で同等の性能
のカメラが成り立つならば、わざわざ、高価すぎる
コンパクト機を買う事も無いであろう。
そうした悪循環により、2010年代では、コンパクト
機の市場は大きく縮退を続けた・・
もう、そうなると、マニア的には極めてマニアック
なカメラしか購入する候補には成り得ない。
本機dp0 Quattroは、その典型例のようなカメラだ。
本機は、その特異性から、一般層には推奨できない
カメラであり、あくまで上級マニア層御用達である。
----
では、今回の「オールド・コンパクト(2)」編は、
このあたり迄で。他にも本記事執筆後に購入した
コンパクト機が1台あるが、キリが無いので別途の
紹介としておく。では、次回本シリーズ記事に続く。
時代とカテゴリーで分類して、順次紹介していく
シリーズ記事。
今回の記事はコンパクト(デジタル)カメラ編の
その2(後編)とし、2007年~2010年代前半の
コンパクト機を、6機種(+α)紹介する。
言うまでも無いが、本シリーズ記事に登場する
カメラは、勿論、全て自身で購入した現有機であり、
過去および現役で長期に使用してきたカメラである。
単に機種名や仕様を調べて纏めただけの記事では無い。
----
では、今回最初のオールド(デジタル)コンパクト機。
Clik here to view.

(2011年発売、発売時実勢価格約8万円)
(中古購入価格 27,000円)
レンズ仕様、24~624mm(相当)/f2.8~5.6
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第4回
まず最初に。
本記事(及び第3回記事)で紹介しているコンパクト
(デジタル)機は、2016年の本ブログのシリーズ記事
「コンパクト・デジタル・クラッシックス」(計4記事)
と紹介機種の大半が重複している。
その為、本記事では各紹介機の仕様等は割愛し、長所
や短所等も、できるかぎり簡略化して述べる事とする。
なお、何故、6年も前の記事と重複する内容になるかは
その時代以降、欲しいと思えるコンパクト機の発売が
皆無であったからだ。何故そうなってしまうのか?は、
勿論、コンパクト(デジタル)機の市場が大きく縮退し、
高付加価値化戦略等もあった為、コスパに優れていて
魅力的な機種が1つも無くなってしまったからである。
本記事においては、そのあたりの市場分析等も、適宜
おりまぜて説明していく事とする。
Clik here to view.

から、デジタル(コンパクト)カメラの販売を
開始している。発売当初は、自社のフィルムビジネス
を否定するデジタル機の発売に驚きの声も上がったが、
まあ、その当時からフィルムからデジタルへの変遷は
当然の流れとして見なされていた為、無理にフィルム
事業にしがみ付かなかった事は英断であっただろう。
(参考:同じくフィルム大手の米KODAK社は、1970年代
頃から、デジタルの撮像センサーの開発を行っていた)
初期のFinePixシリーズは、高描写力・高品位な事が
評判であり、2000年代前半頃まで、人気のブランド
であった。だが、2000年代後半では、デジタル一眼
レフも一般層に普及した為、高画質を求める消費者層
は、そちらに興味の対象を向けていく。
さらに、2000年代末では、ミラーレス機の登場、
そして携帯電話搭載カメラや初期スマホの普及により
(デジタル)コンパクト機のビジネスは、だんだんと
苦しくなっていく。
なので、FUJIFILM社は、2000年代後半からは、
女性向けのスタイリッシュなFinePix Zシリーズや、
望遠機能を増強したロングズーム機(注:FUJIでは
「ネオ一眼」と呼んでいた)FinePix Sシリーズ等
の多面的な商品展開を始め、新規購入層の市場開拓
を意図する。
しかし、2010年頃からは、ミラーレス機とスマホの
普及がさらに加速した為、コンパクト機のビジネスが
いよいよ厳しくなってくる。
そこでFUJIFILMは、それまでのFinePixの各シリーズを
縮小し、防水機能を主体としたFinePix XPシリーズと
高付加価値型(=価格が高く、販売数が少なくとも
利益率が高い)Xシリーズ(注:FinePix銘は無し)
に戦略転換をする。
Clik here to view.

製品であり、同時代の製品には、他には
*高級(単焦点)コンパクト機の「X100」
(注:最初期の販売品のみFinePix銘)や、
*高級ズームコンパクト機「X10」
(いずれも2011年発売)がある。
これらは、高性能・高機能を謳ったカメラであるから
市場からは好意的な印象で受け止められたのだが、
当然ながら「高価に売りたい」商品群である為に、
価格帯は旧来のFinePixシリーズよりも大幅に上昇した。
(X100=約13万円、X10=約7万円、X-S1=約8万円。
従前のFinePix Fフタケタ機等は、約5万円の定価)
FUJIFILMは、このXシリーズの市場での好評価を受け、
翌年2012年には、同Xシリーズでミラーレス機市場に
参入する。(X-E1等、ミラーレス・クラッシックス
第6回記事参照)
さて、という事で、本機X-S1は、私があまり好まない
「高付加価値型商品」(=たいてい、コスパに劣るから。
そして、そういう高価な商品は、レビュー記事等では
”売りたいが為の高評価”しか行わず、面白く無い)
なのではあるが、大型センサーを搭載したロングズーム機
は珍しく、手動ズーム機である事は、他社の同等製品には
存在しない「唯一無二」の仕様であった為、そういう風に
パフォーマンス(実力値、実用性能)が高い機種であれば、
「多少コストが高くても、コスパが悪いとは見なさない」
という持論を適用して、本機を購入する事とした。
主要利用目的はボート競技の撮影であり、実際に2010年
代に本ブログに掲載しているボート競技の写真の多くは、
本機X-S1で撮影している。
ちなみに、本機X-S1以降、ロングズーム機で手動ズーム
搭載機は絶滅してしまった。本機での特性が歴史上最後と
なっているので、本機は予備機も一応所有している。
(注:予備機については、FUJIFILM製カメラの耐久性は
低いという認識があるからだ、詳しくは後述しよう)
まあ、本機はスペック上の優位性は高い機体ではあるが、
ただ、実用的に撮影に用いるのは、本機X-S1には色々と
弱点があり、最大の課題はAF/MF性能に劣る事である。
まあ、コンパクト機のコントラストAFでは、限界がある
事は確かではあるが、AFが合い難く、ボート競技等での
重要なシーンを撮り逃がす事も多々あった。
よって、2010年代末頃からは本機X-S1をボート競技
に持ち出す事も減り、デジタル一眼レフや、(AF精度
が向上した)ミラーレス機を、本機の代替としている。
しかしながら、望遠域を利用可能なサブ機というのも
殆ど存在しない為、X-S1を使わない、という措置は
必ずしも適正では無い。そこが困った問題なのだが、
代替できる機種が(本機以降の時代においては)1つも
無いだけに、まあ、やむを得ない状況か・・
Clik here to view.

所望する画角に速やかに調整が出来ないロングズーム機
などは、私の感覚では、実用上では有り得ないカメラだ。
一眼レフ等用の本格ズームレンズは全て「手動」である、
その事実は、市場の誰もが知っているだろう。
何故、コンパクト機では、手動ズーム機を作れない
のであろうか? むしろ製造コストが増加するから
だろうか? だとしたら、価格が高くなったとしても
手動ズーム機を販売/併売すれば良いだけの話だ。
それとも、初級ユーザー層が「電動ズームでなくちゃ
嫌だ、今時手動操作など格好悪い」などと誤まった
感覚を持っていいるからだろうか・・?
まあ、なかなか困った状況である。
それと、前述した、デジタルコンパクト機の衰退の歴史
はFUJIFILM社だけに限った話では無い、これについては
もう少し詳細を後述しよう。
----
では、2台目のオールドコンパクト。
Clik here to view.

(2008年発売、発売時実勢価格約6万5000円)
(中古購入価格 9,000円)
レンズ仕様、24~60mm(相当)/f2~2.8
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第3回
私が「準」高級コンパクトと定義している、隠れた
高性能機である。広角中心でズーム比が小さい搭載
レンズは、スナップ撮影用途を想定されるとは思うが
シームレスに動作するデジタルズーム機能を搭載
していて(若干の画質劣化を伴うが)最大約400mm
相当の望遠画角までの利用が可能だ。
Clik here to view.

Panasonic(LUMIX)のコンパクト機や初期ミラーレス機
の操作系が、撮影時での効率について意識され始めて、
使い易いカメラとなった。
その理由としては、本機の時代の数年前に、関西系の
老舗カメラメーカーのいくつかがカメラ事業から撤退して
いて、それらに属していたカメラ技術者がPanasonic
(やSONY)に流れ、家電メーカーの状態から参入した
新規カメラメーカーでの新製品開発における、写真撮影
に係わるノウハウの投入がなされたのだと推測している。
まあ、簡単に言ってしまえば、写真を撮っていない人が
カメラを作る(設計する)のは、無理な話であり、
ちゃんと実用的に使えるカメラの開発には、写真撮影
経験が深い人達が居ないと困難、という事である。
そういう差異は「操作系」に、モロに現れてくる。
現代のカメラでも、写真を撮るという行為において、
非常に使い難いカメラも多々存在している事は確かで
あり、そういうカメラは設計時点で、「写真を撮る」
時の手法を、あまり/全く意識していない事が明白だ。
「写真を撮った事が無いのに、カメラを開発している」
というのは残念な話だが、これは明らかな事実だ。
何故ならば、そのカメラを持ち出し、1時間でも写真を
撮ってみれば、ビギナー層でも簡単に認識できるような
欠点が色々と発見できるだろうからだ、これはどう考えても、
カメラを作っている側に写真撮影ノウハウが無いという
事であろう。下手をすれば技術者は開発中のカメラを屋外
に持ち出して試写するような事もしていないかも知れない。
非常に専門的な業務であるデジタル設計をする人達が、
全て、カメラ/写真のファン層である保証は全く無い。
なお、これは歴史のある大メーカーでも同様であり、
メーカーの問題というより、機種(開発チーム)毎の
カメラ設計スキルや設計思想の差異の課題が大きいのと、
また、そうした不完全な仕様の製品が、そのまま市場に
出てしまう、チェック・決議体制にも問題があると思う。
ただ、現代においては消費者やユーザー側でも、そうした
写真撮影のノウハウが少ないビギナー層の比率が増えて
きていて、新鋭の高級カメラをフルオートの撮影モードで
撮っている(フルオートでしか撮れない)ユーザーが
大多数、という情けない状況だ。
そういうユーザー層では「カメラの使いやすさ」などは
理解できる筈も無く、”ダイヤルやスイッチが廻し易い、
押し易い”、”タッチパネルで操作が出来る”等の、
単なる「操作性」についてしか、評価をする事が
できない、という残念な世情である。
これでは、メーカー側としても「操作系を改善する」
という事は、たとえその課題に気づいていたとしても、
優先度の低い開発項目となってしまうのだろう。
具体例としては、操作系の優れたSONY NEX-7(2012年)
は、続くα7系シリーズ(2013年~)で、初級中級者層
向けの安易な操作系にダウングレードされているし、
旧来機よりも操作系が格段に向上したPENTAX KP(2017年)
は「高感度が搭載されただけで値段が2倍に値上げされた」
という悪評が初級ユーザー層の間で流れ、不人気だ。
まあつまり、操作系の良し悪しは、フルオートのモード
でしか撮らないビギナー層には無縁の話であり、むしろ
そこにメーカー側が手を掛けたとしても、ユーザー側では
「使い難い」「さっぱりわからない」「複雑すぎる」等の
ネガティブな評価しか出来ない状態になり易い訳だ。
(注:現代の中級クラスでも似たりよったりであり、絞り
優先AEでの絞り値変更、測距点変更、露出補正、だいたい
そのあたりの操作しかしない事であろう)
困った世情ではあるが、これもまたカメラ市場の縮退から
来るものであり、高付加価値化して高価になりすぎた
カメラには、中上級層は興味を持てず(今までのカメラ
でも十分に撮れるからだ)、そうした高価な新鋭機を、
カタログスペックだけに注目するビギナー層が買う、
という現代市場での図式が課題なのであろう。
つまり高付加価値機には、当然、新しい高機能が搭載されて
いるのだが、ビギナー層では、その新鋭機能を活用する手段
や技法が全くわかっていない、という矛盾を生んでいる訳だ。
Clik here to view.

今回はやめておく、もう古いカメラだから今更入手不能だし
そもそもコンパクト機のユーザー層で、あれこれとカメラの
設定を変えて撮ろうとする人達は、そう多くは無い。
で、本機DMC-LX3の後の時代の後継機では、これもまた
高付加価値化してしまい、そこそこ高価になってしまった
(例:DMC-LX9=約9万円弱、DMC-LX100=約11万円)
まあ、本機DMC-LX3と、続くLX5/LX7あたりまでがコスパ
に優れる準高級コンパクトだとは思うが、既に発売年代が
古く、中古市場でも殆ど流通していないのが課題である。
本機の優れた操作系設計仕様は、後継機に引き継がれて
いるかどうか?は、後継機は未所有なのでわからない。
ただまあ、この後の時代には、どのカメラも高付加価値化
と高機能化されて、そこに操作系の改善が追いついて無い
状況が普通だ・・
----
さて、3台目のオールドコンパクト機。
Clik here to view.

(2007年発売、発売時実勢価格約3万5000円)
(中古購入価格 12,000円)
レンズ仕様、38~114mm(相当)/f3.3~4.2
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第3回
ごく平凡なスペックのオーソドックスなコンパクト機
である。特に記載するべき特徴も無いが、NIKONの
コンパクト機としては、無難にまとめた印象だ。
(注:何故「NIKONとしては・・」という話になるか?は、
NIKONは低価格帯商品に力を入れない企業戦略だからだ。
コンパクト機における、その実例は、銀塩コンパクト・
クラッシック第2回「NIKON MINI(AF600)」編に詳しい)
Clik here to view.

あまり書くべき内容は無い。
まあ、ここで前述の、コンパクト(デジタル)機の歴史の
話の続きをしておこう。
最初に一般ユーザーに注目された(民生用)デジタル
コンパクト機としては、CASIO QV-10(1994年発表、
1995年発売)が、初と言って良いであろう。
価格は65,000円であり、初のデジカメとしては安価だ。
ただし、若干の性能上の未成熟もあって、実用機と
しての初は、QV-10A(1996年)が上げられると思う。
オフィス用途(画像情報伝達・共有)としても良く
使われ、多くの企業等にも、QV-10Aは普及した。
その後1990年代後半には、OLYMPUSやFUJIFILM等
からも民生用コンパクト(デジタル)機が発売され、
2000年代前半頃までに、一気にこれらコンパクト
機は、一般層に迄、普及する。
以下、最初期のコンパクト・デジタル機の代表機だ。
1996年
CASIO QV-10A
OLYMPUS C-400L/C-800L
CANON PowerShot 600
SONY CyberShot DSC-F1
1997年
CASIO QV-11
OLYMPUS C-1400XL
MINOLTA Dimage V
1998年
FUJIFILM FinePix700
以降は記載省略。膨大な機種数がある。
また、これらの機種群の現有数はゼロである、
何台かは使っていたが、古過ぎて、故障廃棄やら
譲渡処分となってしまっている。
2000年代前半には、デジタル一眼レフも色々と
発売されるが、廉価版コンパクト機の10倍近くも高価
であった為、本シリーズ第3回記事で説明したように、
「ガンデジ」「コンテジ」と言った一種の差別用語が
生まれる事となった。(注:デジタル一眼レフが
欲しくても買えないから、そういう俗語で卑下する。
G/D/Z濁点系発音の呼称は、普通は「敵役」の名前だ。
ただし、「機動戦士ガンダム」だけは例外。これは
もしかすると、「連邦とジオンのどちらが正義か?」
を、あえて曖昧にする意図があったのかも知れない。
他のアニメや映画等は、殆どがシンプルな勧善懲悪
形式なので、濁点系呼称は敵役として、ごく普通だ)
2000年代後半ともなると、デジタル一眼レフの
価格帯も下がり、一般層でも入手できるようになると
「ガンデジ」「イチデジ」「デジイチ」と言った
蔑称からなる差別用語は瞬時に死語となる。
この時代、コンパクト機の記録画素数は1000万画素
を超えるものも出て来て、既に成熟期である。
Clik here to view.

あるから、画素数という概念は無いのだが、一般的に
「35mm判フィルムの画素数は、デジタルの1000~2000
万画素に相当する」と言われている。つまり、この時代
にデジタルカメラ(一眼レフもコンパクト機も)の
画素数はフィルムと同等か、それ以上となった訳だ。
(注1:単純に「画素数が大きければ高画質だ」という
訳でも無い。特に一眼レフでは、装着するレンズの性能に
依存する要因の方が、センサーの画素数より遥かに大きい)
(注2:フィルムをデジタルの画素数に換算する方法論は
不明である。真面目にやれば「ウィーナースペクトル」や
「RMS粒状性」から換算できるのかも知れないが、専門的
すぎて計算方法は不明だ。しかも原理的にも、そう簡単
に、アナログとデジタルを対応できるとも思えず、単に
「だいたいこれくらいか?」という感覚値で、誰かが
言い出した事が、広まったに過ぎないかも知れない?)
だが、この時代には、既に、携帯電話のほぼ全てに
カメラ機能が搭載されていた。まあデジタルカメラの
技術が進歩(および低価格化)した為、携帯電話等への
搭載が可能となった、とも言えるであろう。
しかし、それがむしろ仇となり、簡易撮影機材としての
コンパクト(デジタル)機の用途は、どんどんと減っていく。
2010年前後には、ミラーレス機および初期スマホの
台頭により、コンパクト機の売り上げはさらに鈍化し、
(本記事で紹介している時代)その後のコンパクト機は、
販売台数が少なくても利益が上がる「高付加価値化」商品
となってしまっている。(つまり、大幅に値上げされた)
2010年代後半頃からのコンパクト機には、コスパの良い
魅力的な機種は残念ながら皆無となってしまい、私も、
その時代以降のコンパクト機は殆ど所有していない。
(注:2015年以降では2台のみ購入、順次紹介予定)
まあ、こんな歴史であり、結局のところ1990年代後半
から2010年代後半迄の高々20年程度が、コンパクト・
デジタル機の時代/黄金期であった訳だ。
(匠の写真用語辞典第19回「カメラ形態20年寿命説」
の項目を参照。これはつまり、様々な銀塩/デジタルの
カメラの形態は20年程で進化のピークに達してしまい、
新機種での改良の余地が無くなり、別のカメラの形態
に変化せざるを得なくなる、という持論である)
さて、ここで、本機S50の時代の少し後に発売された
ユニークなNIKON機についても「補足」として紹介して
おこう。
Clik here to view.

(2010年発売、発売時実勢価格約4万3000円)
(新品購入価格 15,000円)
レンズ仕様、28~140mm(相当)/f3.9~5.8
プロジェクター(投影)機能搭載
希少な「プロジェクター機能」搭載カメラであり、
本機と前機種S1000pjのみ2機種が市販されただけ、
だと記憶している。
その後、このジャンルの製品が伸びなかったのは、
デジカメの内蔵電源では、プロジェクション(投影)
に必要な光量が確保できなかったからであろう。
私も本機を、カメラ仲間の集まりに作品の投影用に
使ったり、プレゼンやレクチャーでの資料投影用にも
用いてみたが、いずれも光量および投影解像度の
課題があって、あまり実用的だとは言えなかった。
プロジェクターの機能を封印し、カメラとして使おう
とも思ったのだが・・ 本機の操作系は壊滅的な程の
低レベルであり、何故そんな事になっているのか?と
目を疑うばかりだ。まあ、カメラとしての利用も難しく、
ほとんど活用機会が無いまま、ビジネスメモ用途機
としてカバンの中に入っている次第だ。
---
では、4台目のコンパクト機。
Clik here to view.

(2010年発売、発売時実勢価格約8,000円)
(新品購入価格 7,000円)
レンズ仕様、40mm(相当)/f3.2
近赤外線(NIR)投射・近赤外線撮影機能搭載機
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第4回
本機には、YASHICAのブランド銘がついているが、
元祖ヤシカや、京セラ傘下のヤシカ製では無い。
京セラが2005年にカメラ事業から撤退した後は、
ヤシカ/YASHICAのブランドは、様々な企業を転々と
している(名前だけが譲渡されている)状態だ。
本機の時代では、EXEMODE(エクゼモード)
(株式会社ドリーム・トレイン・インターネット)
が、YASHICAブランドの商品を取り扱っていた、
製造は、恐らく海外(中国)製であろう。
この後、EXEMODEもYASHICA銘を手放した模様であり、
2010年代末頃では、全国的雑貨チェーン店である
ヴィレッジバンガード(Village Vanguard Webbed)
が、フィルムカメラ風デザインのYASHICA銘の
トイカメラを扱っていた。(未所有)
Clik here to view.

機ではあるが、性能は「トイカメラ」相当であり、
実用性が殆ど無い事が課題である。
近赤外線については、専門的技術分野である為に、
巷での大多数の人達は、その具体的内容を理解できて
いない。その為、様々な誤解が存在するが、他記事でも
何度も書いてきた内容な為、そのあたりは割愛する。
まあ簡単に言えば、近赤外線は一種の「光」であるから
それを「写真」として映像化する事は可能だ。
しかし近赤外線は人間の目に見えない「光」である為、
特殊な用途に用いられる。その代表的な応用は、暗所
での監視カメラ(セキュリティ用途の物)であろう。
そして、本機の構造もまたその通りであり、監視カメラで、
「デイナイトモード」(昼間も夜間も監視が出来る機能)
を搭載している機体と、ほぼ同様である。
面白いコンセプトのカメラではあるが、このジャンルの
カメラは残念ながら本機で終了であり、その後、類似した
商品は出てきていない。
以下余談だが、本機より以前の時代で、SONY製の近赤外線
ビデオカメラの商品が存在していたが、「暗所での盗撮」
等の不正な目的に利用された為か?すぐに発売中止となり、
後継機は存在していない。
ちなみに、この製造中止となった希少なカメラを後年に
高額に転売する目的か?「赤外線では水着が透けて写る」
等の根拠の無いデマが大々的に流れた。そういうデマを
流せば、「お金を出しても欲しい」と言う好事家が出て
くるからであろう。他に「健康に良い」などと言う話も
巷では良くあるが、残念ながら、「近赤外線」は単なる
光の一種であるから、そうした「嬉しい効能」は無い。
(注:一般層では、近赤外線と、中(熱)赤外線の
原理を混同しているケースが大半である)
Clik here to view.

無い模様だ。まあ、元々販売数も少ないカメラだとは
思うし、基本的にはトイカメラ相当だ。いくら近赤外線
投射機能があるとは言え、その到達範囲は数mと短く、
かつ基本的な感度はISO100相当でしか無い。これで
暗所でブレずに撮影が出来るようならば、もう達人の
領域であろう。全くブレずに上手く暗所で撮れている
写真を見かけたら、それは赤外線撮影風に見せた偽物
(フェイク)写真である可能性も高い事は述べておく。
(→愉快犯、または投機的な相場高騰が目的)
----
では、5台目のコンパクト機。
Clik here to view.

(2013年発売、発売時実勢価格約4万5000円)
(中古購入価格 24,000円)
レンズ仕様、25mm~100mm(相当)/f1.8~4.9
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第4回
本機は従前記事で紹介した「FinePix F10(2005年)」
の再来とも言えるカメラであり、高性能・高機能が
特徴である。それでいて価格が比較的安価であり、
「コスパ」評価が非常に高く、名機と言えるだろう。
Clik here to view.

設計が最大の弱点であったが、本機XQ1では、さすがに
F10から8年の時を経て、多少は改善されている。
(注:Xシリーズの始まった2011年頃から、FUJI機の
操作系は、若干だが改善された。
両者の差異等の詳細は、本ブログの旧記事
「名機対決 FinePix F10 vs XQ1」編を参照の事)
まあ、本機XQ1であれば、コンパクト機の域に留まらず
実用レベルのカメラとしても及第点であろう。
・・というか、恐らくは、普及コンパクト機最後の
実用機が、本機XQ1であると思う。
あまり褒めて、中古相場が上がってしまうのも良く無い。
本機は、もし壊れたら同一機種を中古で再購入する
予定なので、適正な相場のままで推移してもらいたい訳だ。
(参考:銀塩時代から現代に至るまで、FUJIFILM製の
カメラで耐久性に劣るものが稀にある。私は計数十台の
FUJI機を所有していたが、故障廃棄となってしまった
ものが5~6台もある。私は物持ちが良く、所有カメラの
平均故障率は3%以下の比率であるのだが、FUJI機では
20%程度を超える故障率だ。本機XQ1と同時代のXF1も
XQ1のサブ機を想定して購入したものの、そちらも
やはり故障廃棄となってしまい本ブログでは未紹介だ。
また本機XQ1も2021年頃、背面のコマンドダイヤル
(ロータリーエンコーダー)が接触不良となって
しまっている。(絞り値等を廻しても変化しない)
また、従前にも、カメラ前面のコントロールリングが
同等症状の接触不良となった事がある。
これらは接点復活剤の注入で復旧したが、どうにも
耐久性が怪しい状態である)
で、特に近年では、投機層がFUJIFILM製の様々な希少な
カメラに目をつけ、常識では考えられない程の高額相場
で売却しようとしている模様だ。勿論そんな風に不条理
なまでに相場高騰したカメラを買おうとする実用派
マニアは皆無であるが、また別の投機層が、さらなる
転売利益を出す為に高額相場を受容するケースもある。
けど、そういった「実用上とは無関係の理由」で、
適切な市場バランスを乱してもらいたくないと思う。
また、その為に、FUJIFILM製の各種オールド機を「名機」
として紹介するレビュー記事等も増えている。それらは
多分に「投機的」観点も強い(=高額に売りさばきたい)
ケースも多いだろうから、要注意だ。
(簡単な回避策としては、「名機」のキーワードで
FUJIFILM機を検索しない事が賢明だろう)
Clik here to view.
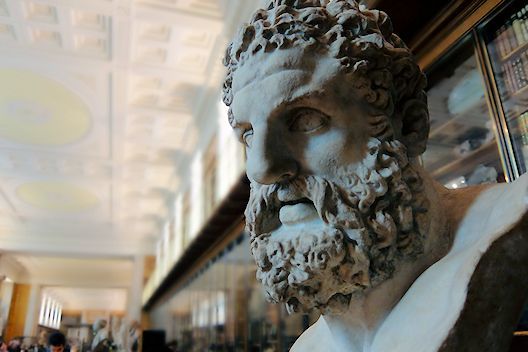
機種が殆ど発売されず、結果的に私も、僅かに2台
しか、コンパクト機を購入していない。
「カメラマニアですら、殆ど欲しいカメラが無い」
というのが、残念ながら現在のコンパクト・デジタル機
の市場の様相である。
----
1機種だけ、簡単に紹介しておこう。
今回ラストの(デジタル)コンパクト機。
Clik here to view.

(2015年発売、発売時実勢価格約11万円)
(新古購入価格 66,000円)
レンズ仕様、14mm(21mm相当)/f4
紹介記事:コンパクト・デジタル・クラッシックス第5回
(注:掲載予定記事)
他記事で詳細紹介前の機体だが、ここで取り上げる。
コンパクト機と言うには、あまりに大きいカメラだ。
いや、大きいというよりも、この異形のフォルムは
縦横がそれぞれ長く、カメラバック等への収納も、
ほぼ一眼レフ等と同等の容積を必要としてしまう。
Clik here to view.

まず、Foveon X3(Quattro)という特殊な撮像センサー
を搭載している。このセンサーは3層構造であり、
B(青)、G(緑)、R(赤)の光を3層で受けて
それを画像化する為、カラーフィルターやローパス
フィルターが不要であり、補間をせずに額面どおり
の画素数(解像度)が得られる。(注:他の一般的な
ベイヤー配列センサーは、RGGBのカラーフィルター
がある為、フル画素の1/4しか実効画素数が無い。
これを、4倍等に拡大(演繹)補間して用いる為、
場合により、フル画素よりも、小画素で撮った方が
解像感が高くなったりする)
なお、Quattro型(APS-C)センサーでの画素数は、
トップ層約2000万、第2/第3層が各500万画素
である。複雑な仕組みにより、これでも一応
2000万画素相当の記録解像度(=記録画素数)
は得られるのだが、前述の演繹補間演算の手法が
不明(特許を閲覧しても、依然不明)な事から、
個人的な嗜好性(=内容が良くわからない技術
に対しては、安全策を取る)により、本機では
常に第2層相当の500万画素で撮るようにしている。
第二の特徴として、デジタルの単焦点コンパクト
機では(アクションカメラや全天球カメラを除き)
最広角である14mm(換算21mm)の超広角レンズ
を搭載している事である。
Clik here to view.

マニアックなカメラである。よって、あまり多数
が売れている様子も無いし、ユーザーレビュー
(流通等での販売側が書く「宣伝記事」を除く)
も、殆ど存在しない。
本機について詳しく語ると、非常に長い文章量を
必要とする。詳細はやむなく割愛するが、興味が
あれば「コンパクト・デジタル・クラッシックス
第5回」記事(掲載予定)を参照されたし。
(ただし、約2万文字の、超長文記事である)
ごく簡単に長所、短所のみ述べておこう。
<長所>
*高い解像感による、極めてシャープな絵作り
*周辺減光や歪曲収差が殆ど無い優秀なレンズ
*マニアックな製品企画コンセプト
<短所>
*搭載レンズの逆光耐性が非常に低い
*カメラとしての性能・機能不足
*操作性・操作系が悪い
*中途半端に大きく、場所を取る
*ノイズ耐性、高感度性能が低い
まあ、だいたいこんなところか。
前述したとおり、2010年代はコンパクト機の
受難の時代である。まあスマホが台頭(普及)
すれば、そうなるのもやむを得ないであろう。
だから、製品企画的にも、まずは販売数減少を
補填する為の、高価格(高付加価値)型のコンパクト
機ばかりとなってしまった。ただ、いくらコンパクト
機の性能を上げても、ミラーレス機等で同等の性能
のカメラが成り立つならば、わざわざ、高価すぎる
コンパクト機を買う事も無いであろう。
そうした悪循環により、2010年代では、コンパクト
機の市場は大きく縮退を続けた・・
もう、そうなると、マニア的には極めてマニアック
なカメラしか購入する候補には成り得ない。
本機dp0 Quattroは、その典型例のようなカメラだ。
本機は、その特異性から、一般層には推奨できない
カメラであり、あくまで上級マニア層御用達である。
----
では、今回の「オールド・コンパクト(2)」編は、
このあたり迄で。他にも本記事執筆後に購入した
コンパクト機が1台あるが、キリが無いので別途の
紹介としておく。では、次回本シリーズ記事に続く。