さて、「最強選手権」シリーズ記事では、これまで
各カテゴリー内での最強レンズを決める為に対戦して
来たのだが、今回は、さらにその中から最強のレンズ
をノンカテゴリー(無差別級)で対戦する事とする。
すなわち、これが「真のレンズ王者決定戦」となる。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17531190.jpg]()
ただし、本ブログでは過去にも、「ミラーレス・
マニアックス名玉編」(全カテゴリーの共通)や、
「ハイコスパレンズBEST40編」(高コスパレンズでの
限定)、「価格別レンズ選手権」、および本シリーズ
での「焦点距離別選手権」等の、レンズのランキング
系の記事を多数実施している。
それらのランキング系記事で上位となったレンズは、
本ランキングでも、上位となる可能性が極めて高い。
いつも同じような戦績ばかりになっても、面白味が無い
為、有力な強豪レンズは、本シリーズでは「殿堂入り」
として対戦(ノミネート)を控える事としよう。
検討の結果「殿堂入りレンズ」は以下の10本となった。
01:smc PENTAX-FA 77mm/F1.8 Limited (2001年)
02:smc PENTAX-DA ★ 55mm/F1.4 (2009年)
03:MINOLTA STF 135mm/F2.8[T4.5] (1998年)
04:MINOLTA AF Macro 50mm/F2.8 (1985年)
05:MINOLTA MC ROKKOR-PF 50mm/F1.7 (1970年前後)
06:SONY DT 35mm/F1.8 SAM (SAL35F18) (2010年)
07:TAMRON SP 45mm/F1.8 Di VC USD(F013) (2015年)
08:Voigtlander APO-LANTHAR 90mm/F3.5 SL
Close Focus(注:変母音省略) (2002年)
09:Voigtlander NOKTON 42.5mm/F0.95 (2013年)
10:NIKON AiAF DC-NIKKOR 105mm/F2D (1993年)
上記のレンズ群は、いずれも過去のランキング系
記事で上位となった実績を持つ「レジェンド」の
強豪レンズであるので、「殿堂入り」としよう。
また、以下の4本のレンズは、ランキング上位となれる
可能性があるが、現代における入手性が極めて低い為、
(=レア物、あるいは投機対象で不条理な高額相場に
なっている為)ノミネート対象から外す。
11:CONTAX N Planar T* 85mm/F1.4 (2002年)
12:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 125mm/F2.5 SL
(注:変母音省略) (2001年)
13:YASHICA LENS ML 35mm/F2.8 (1970年代後半)
14:OLYMPUS OM-SYSTEM Zuiko 90mm/F2 Macro
(1980年代後半)
これら14本(機種)を除く、他の所有レンズ群で(注:
未購入、または現在未所有のレンズは評価・対戦をしない。
借りてきたレンズ等では正当な評価が出来ない事は当然だ)
本短期シリーズでの対戦を行う。
場合により、今回の最強レンズ選手権での上位レンズでは、
上記「殿堂入り」レンズ群には、描写性能的、または
総合性能(コスパ等も含む)では敵わないかも知れない。
逆に言えば、真の最強レンズが欲しければ、上記14本の
いずれかを探して入手すれば良い、との事になってしまう。
ただまあ、今回の対戦にノミネートされているレンズ
群も、それなりに個性的・マニアックで、魅力的なもの
ばかりではある。
なお、ロシアンレンズ、中国製格安レンズ、オールドレンズ、
トイレンズ、エントリー(お試し版)レンズ等は、参戦を
制限するものでは無いのだが、本決勝シリーズにおいて
ノミネートされているそれらの機種数は、非常に少ない。
(何かの特徴があっても、総合評価は高まらないからだ)
今回は、その殆どが「高描写力」レンズと「特殊効果」
(≒高表現力)レンズばかりの参戦となるだろう。
本シリーズ(や、本ブログ全般)で紹介(対戦)をする
レンズ群は、その全てが実践的・実用的な側面で有益な
ものばかりである。勿論、コレクション(収集)向けや
投機(転売)対象のレンズ群は、一切登場する事は無い。
それと、同一の(決勝)リーグ戦に進出するレンズは、
できるだけメーカー/シリーズ被りを避ける事とする。
(同じメーカー又は同じシリーズのレンズ群ばかりを
対戦させない。ただし、稀に被る事もある)
また、レンズ紹介の際の使用母艦(カメラ)は自由に
選択するが、多少はレンズの使用を効率的・効果的と
する事(=「弱点相殺型システム」)を意識する。
いつものように、実写は三脚を使用せず、その際の、
カメラ側に備わる機能(例:エフェクトやデジタル
拡大機能等)は自由に使えるルールとする。
ただし撮影後のアフターレタッチ(編集)については、
画像縮小、輝度調整、構図調整の為の僅かなトリミング
等、最小限のレベルに限定する。
また、全てJPEGでの小画素・低画質設定による撮影で
あり、RAW現像(撮影)は一切行わない。
(これらは他のシリーズ記事とも同じルールである)
----
では、始めよう。
本B決勝戦(1)には、8本のレンズがノミネート
されている。
まず、最初のノミネート(参戦)レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17531166.jpg]()
レンズは、NIKON AF-S NIKKOR 58mm/f1.4 G
(中古購入価格 110,000円)(以下、AF-S58/1.4)
カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)
2013年発売の大口径AF標準レンズ。
「三次元的ハイファイ」(注:3D Hi-Fi等、他の表記が
使われる場合もある)を謳った、最初のレンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17531108.jpg]()
しかし「三次元的ハイファイ」とは、そういう名称
の「部品や技術」が入っているという訳では無く、
これは、いわば「味付けのコンセプト」である。
これについては、誰も上手く説明できないからか?
「三次元的ハイファイ」の効能や特性を理解している
ユーザー層も極めて少ない。
・・この為、「よくわからない」「うまく撮れない」
「描写力が低い」という、ネガティブな初級評価が
蔓延したり、あるいは上手く撮れない事を自身の課題
だ、とは認識したくない中級層やマニア層においては、
「クセ玉だ」と、これをレンズの問題点や責任として
押し付けてしまう傾向(評価等)が、とても多い。
だが、これ(三次元的ハイファイ)について述べていく
と、軽く1記事分の文章量となってしまうだろうし、
そうやって説明をつくしたところで、設計思想が理解
できる保証も無く(→ユーザー側の理解力と言うよりは
そもそも「作った側」にしかわからない話でもあるかも
知れないからだ)結局、どれも無意味になりかねない。
まあ、興味があれば、レンズ・マニアックス第63回
「三次元的ハイファイ」編記事を参照していただくと
して、本記事においては、本レンズの詳細は割愛する。
描写表現力的には悪いレンズでは無いが、異常な迄に
高額であり、コスパ評価は最低点に近い状況だ。
---
では、次はマクロレンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17531137.jpg]()
レンズは、Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm/f2
(注:独語綴りの変母音は省略。本ブログで全て同様)
(新品購入価格 122,000円)(以下、MAP65/2)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
2017年に発売された、フルサイズ対応大口径MF
準中望遠1/2倍(ハーフ)マクロレンズ。
今回、APS-C機で利用しているのは、本レンズはハーフ
マクロであり、最大撮影倍率に若干の不満があるからだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532090.jpg]()
APS-C機で使うと、約100mm換算の画角、約0.75倍の
最大撮影倍率(注:カメラ側のデジタル拡大機能を併用
すれば、撮影倍率を仮想的に高める事は可能だ)となり
銀塩時代からの経験値の高い「中望遠マクロ」と、ほぼ
同等の換算スペックとなる為、経験則が適用でき、さらに
周辺収差の低減、重量バランスの向上(→特に、今回の
システムでは、ピントリングおよび前部の絞り環の操作
が全体重心のホールド状態からのレンズの持ち替え無し、
となり、操作性と撮影エンジョイ度が向上する)
・・といった理由でのAPS-C機の母艦利用である。
初級中級層では、「必ずフルサイズ機が高性能なのだ」
と信じて疑わないかも知れないが、フルサイズ機が高価
なのは、2010年代に大きく縮退したカメラ市場において
(=つまり、全くカメラが売れない)メーカーや流通
市場が事業を継続するために、高付加価値化を謳って
(=つまり、「フルサイズ機は高級で高性能なのだ」
という論理を、消費者層に強く植え付けようとした)
高価格化(値上げ)をした市場戦略であった訳だから、
フルサイズ機のコスパは、一般的にAPS-C以下機よりも
大きく劣る。
加えて、少し前述したが、レンズの特性を活かし、様々な
被写体状況に対応する為には、母艦はフルサイズ機に拘らず、
各種のセンサーサイズを選ぶ事が基本である。
(例:遠距離スポーツ撮影では、APS-C機の高速連写型
一眼レフを母艦とする事は常識的な措置であろう)
だが、勿論フルサイズ機が絶対に必要なケースも存在する。
(例:魚眼、シフト、ぐるぐるボケ、等の特殊効果レンズ
では、フルサイズ機でないと、それらの効能が得られない)
まあつまり、レンズとカメラは、それぞれの特徴・特性を
理解し、お互いの長所を助長し、弱点を相殺するような
組み合わせにする必要がある(=「弱点相殺型システム」)
余談が長くなったが、余談とは言い切れず、「適正な
システム(カメラ+レンズの組み合わせ)を構築する」
という事は、機材運用上の最も基本であり、極めて
重要な事でもある。
「フルサイズ機の高級機を買ったから、他のカメラは
もう、いらんよ」という訳では勿論ないし、はたまた
「オレのカメラの方が高価だから」と、周囲の他者を
見下すようなスタンスは、最もやってはならない事だ。
イベントの撮影にフラリとやってきたアマチュアカメラマン
達が、雨が降ると「大事な機材が壊れるから」と言って、
蜘蛛の子を散らすように、あっと言う間に全員撤収して
しまうことが良くある。だが業務撮影や、重用な依頼
撮影(例:そのイベントに家族知人が出演する等)では
「雨が降ったので撮れませんでした」という言い訳は
通用しない。そんな場合、雨中や悪条件においても撮影を
継続できるシステム(防水であったり、あるいは壊しても
惜しくないレベルの安価な「消耗用撮影機材」)の必要性は
誰にでも理解できるであろう。
まあつまり、撮影機材というものはケースバイケースであり
そのケース(条件)を、いかに多く想定できるか? または
そういう経験値を持っているか否か? が重要な事であり、
その、ケースバイケースやTPO(時、場所、条件)に応じて
最適な機材を選択できるか否か?が、機材運用上、あるいは
事前に機材の購入検討をする上での最大のポイントとなる訳だ。
MAP65/2レンズの話がちっとも出てこなかったが、
基本的に、本決勝リーグにノミネートされたレンズ群は
大きな弱点を持たないか、あるいは些細な弱点があったと
しても、技能で回避できるようなレベルのレンズばかりだ。
(注:本MAP65/2がMFレンズだから、という理由で、
使いこなせない、というようなビギナー層は、本記事の
対象読者とは見なしていない。
そもそも近接撮影時では、AFの方が全く使い物にならない
事も、中級層以上には良く知られた常識であろう)
まあだから、レンズ自体の仕様や長所短所等を細かく
記載しても意味が無い状態である。本最強・決勝リーグ
にノミネートされたレンズ群は、どれも一級品であり、
致命的な弱点(=重欠点)を持たないレンズばかりだ。
---
さて、3本目はミラー(レンズ)である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532091.jpg]()
ミラーは、TOKINA Reflex 300mm/f6.3 MF MACRO
(中古購入価格 18,000円)(以下、MF300/6.3)
カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)
2012年発売のミラー(反射型)(レンズ)である。
μ4/3機専用であり、換算600mmの超望遠画角だ。
電子接点にも対応していて、μ4/3機の内蔵手ブレ
補正機能は、手動焦点距離入力不要で使用できる。
ただし、換算600mm、あるいはデジタルテレコン等
の利用で換算1200mm以上ともなると、たとえ優秀
な内蔵手ブレ補正機能があったとしても精度不足で
まともには動作せず、加えて、多くのμ4/3機では
AUTO ISOの切り替わり(低速限界)シャッター速度
が手動設定不可であるので、本レンズのような超望遠
で暗い開放F値のレンズの場合は、AUTO ISOのままでは
シャッター速度が低くなりすぎて、手ブレを頻発する。
撮影者毎のスキルに応じた手ブレ限界シャッター速度を
維持する上では、頻繁なISO手動設定が必須であり、
操作性に課題が出る上に、やや高難易度だ。
(注:2016年発売以降のμ4/3高級機には、低速限界
設定機能が搭載されているケースもある。
例:OLYMPUS OM-D E-M1 MarkⅡ(2016年)以降の
旗艦機や、PANASONIC DC-G9(2018年)等)
さらには、換算600mmを超える超々望遠領域では、
システムを構えた場所に被写体を捉える事すら難しい。
加えて、ミラー(レンズ)のピント合わせは、遠距離
でも回転角が大きくて、感覚的にも技能的にもMF操作
がやや難しい。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532191.jpg]()
また、解像力も、通常ガラスレンズに比べてあまり
高いとは言えない、被写体を選ぶ必要があるだろう。
(注:上の「月」の写真は、「限界性能テスト」だ。
あまり解像感が高くない事がわかるので、こういう
細密な被写体を撮るには向かない、という事となる)
そして、本レンズは、最短撮影距離80cm、1/2倍の
「超望遠マクロ」としての利用が最大の特徴だが、
近接撮影でも、被写体フレーミングと、MF合焦が
課題となる。
まあでも、弱点をあらかじめ多数挙げてはいるが、
総合的には、比較的バランスの取れた優秀なミラー
である為、過去の本ブログのランキング記事では、
比較的上位を複数回マークしている。
(ミラーレス名玉編第13位。ハイコスパ名玉編第12位。
超望遠レンズ選手権第1位)
仕様的には優秀なレンズながら、本ミラー(レンズ)を
周囲の人達に推奨して買って貰っても、どうにも上手く
使いこなせない模様だ。よって、近年においては、
本ミラーは「実践派上級マニア層向け」という観点で
あまり周囲には推奨しないようにしている。
(注:2022年現在では生産終了となっている)
---
では、次は準オールドレンズだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532146.jpg]()
レンズは、CONTAX Planar T* 100mm/f2 MMJ
(新品購入価格 106,000円)(以下、P100/2)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
1980年代後半頃に発売されたMF中望遠レンズ。
本ブログでは過去に何度も紹介している「名レンズ」で
ある。近年は、これをEFマウント一眼レフで用いる事が
多いのだが、これは所有機材でのマウントアダプター等
の保有種や、使いまわしの関係が理由であり、あまり
適切なシステムとは言えないように思えてきている。
その理由は、一眼レフの光学ファインダーでは、ボケ質
破綻の回避技法が使いにくい(使えない)事が、やや
不満となってきており、稀に、ボケ質破綻が発生する際、
「せっかくの高描写力レンズなのに勿体無い」と思う
ようになってきたからだ。
今後は、ミラーレス機で使用できるように、システムを
整えていこうと思っている。(注:ミラーレス機に装着
するだけであれば容易に可能だが、本レンズの特性に
見合う母艦の機種を選ぶ事が、やや難しい)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532862.jpg]()
セミ(準)オールドレンズ故に、収差補正等が完全では
無く、「完璧な描写力」とは言えないが、このレンズの
発売当時においては、他レンズよりも頭一つ飛びぬけた
高描写表現力レンズであった事だろう。
当時の人気商品の「CONTAX Planar T* 85mm/f1.4」
と比較すると、「ピント歩留まり」、「ボケ質破綻」、
「焦点移動」の3つの課題が良く改善されていて、
「安定した描写力を得られるレンズ」として、実用性
に多大な差があった。
大きな弱点は、高価な事であり、1990年代位の定価
では、P85/1.4の、およそ2倍の178,000円+税で
あり、富裕層が多いCONTAX党においても、購入を
躊躇うような贅沢品であったように思える。
人気レンズの、P85/1.4とMakro-Planar 100/2.8
の2本に挟まれたスペックでもあるから、本レンズの
購入者は極めて少なく、当時の中古カメラブーム時の
マニア層での口コミネットワーク(注:これは馬鹿に
できないレベルでの情報の質と量があった。その後の
インターネット時代では、情報の量は増えたが、質が
大きく低下してしまい、ビギナー層や、情報操作を
目論む層に発信機会が増えた為、膨大な「ゴミ情報」や
「欺瞞(フェイク)情報」とか「単なる宣伝情報」や
「アクセス稼ぎ情報」といった中から、正確で、かつ
有益な情報を見分ける事が大変困難になってしまった)
・・その口コミ情報にも、本レンズはまず登場せず、
マニア層等の誰にも注目されていないまま、銀塩時代が
終わり、役目を終えてしまった、やや悲運のレンズだ。
だが、そうなったのは、高額な定価をつけたメーカー
側にも問題があったと言えよう。コスパを考えると
20万円近くもするレンズとは思えず、現代で考える
ならば、単焦点100mm級での超高描写表現力を持つ
レンズは、他にいくらでも存在するし、その殆ど
全ては、本レンズより後の時代の製品なのに割安だ。
何故、こんなに高額なレンズとなってしまったのか?
企画やマーケティングの問題であろうか。
「CONTAX(Carl Zeiss)ならば高くても売れる」と
思ったのならば、それはちょっと企画側の勘違いで
あろう、当時の消費者層は、もっと賢くレンズの商品
価値を吟味して購入行動を起こしている。
それら消費者層が「高価すぎると思うから買わない」
となったのであれば、それが市場(マーケット)からの
「暗黙の回答」となった訳だ。
まあでも、本レンズが発売されてから35年以上が
経過し、京セラCONTAXがカメラ事業から撤退してから
も15年以上が経過した現在においては、本レンズの
中古品は、そこそこ安価に流通している場合もある。
売れていなかった為、あまり中古の玉数は豊富では無いが
4~5万円程度の相場で購入できるのであれば、
現代の感覚でコスパを評価しても、悪く無いレンズだと
思われる。(追記:コロナ禍以降、殆ど中古品を見なく
なってしまった。他のCONTAX RTS系レンズの相場が
高騰している状況を鑑みると、「希少価値演出」という
投機的措置も類推され、あまり好ましい状況では無い)
---
さて、5本目は超大口径レンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532846.jpg]()
レンズは、Voigtlander NOKTON 60mm/f0.95
(注:独語綴りの変母音は省略)
(新品購入価格 113,000円)(以下、NOKTON60)
カメラは、PANASONIC DMC-G5 (μ4/3機)
2020年発売のμ4/3機専用超大口径MF望遠画角レンズ。
F0.95級レンズとしては、発売時点で最も実焦点
距離が長いレンズである。
(参考:実焦点距離の長い次点は、2019年発売の
「NIKON NIKKOR Z 58mm/F0.95 S Noct」だ。
ただしそのレンズは、定価約126万円の「異常」
とも言える超高額レンズである。いったい誰が、
何の目的で買うのであろうか? そして、何故
そんな高額な商品を企画し発売するのだろうか?
まあ「こんな凄いレンズを作れるのですよ」という
「広告塔」であろうが、カメラ市場が大きく縮退して
しまっている昨今の状況で作る商品であろうか?
何だか、裏側にある、良くわからない「からくり」を
危惧してしまう。・・当然だが一切購入する気は無い)
COSINAでは2013年にNOKTON 42.5mm/F0.95
を発売していて(特殊レンズ第25回記事等、
多数の記事で紹介。使いこなしがとても困難な、
最難関レンズである)それが、発売時点では恐らく
最長焦点距離のF0.95レンズだったかも知れず、
その後、2010年代後半においては、各社から、
わらわらと様々なF0.95レンズが発売されている
ので、COSINAとしても「ここらで、最長の焦点
距離のF0.95を出しておくか?」という企画意図
だったのかも知れない。
(注:勿論、そうでも無いかも知れないが、
上記のZ58/0.95が、ちょっと異常な企画なので、
「こういう普通の企画方針の商品であるならば
好ましい」という消費者視点での話だ・・
ただ、COSINAは、やはりZ58/0.95を相当に意識
している模様であり、2020年にSUPER NOKTON
29mm/F0.8(換算58mm/F0.8)を発売している)
まあこの結果、COSINAとしては、久しぶりの
F0.95シリーズの新製品発売となった訳だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532833.jpg]()
で、特殊レンズ第25回記事「超大口径レンズ編」
で紹介した3本のF0.95レンズは、いずれも正直
言えば、F0.95~F2あたりまでの、絞り開放近く
では、球面収差を始めとする、諸収差の発生を
抑えられておらず、「ボケボケの写りだ」とも
言えただろう。しかし、超大口径レンズとしての
多大な「表現力」を持っている為、個人評価DBでの
旧型NOKTONの「描写表現力」は5点満点評価であった。
だが、本NOKTON60/0.95は、いったい、どこから
どうなってしまったのだろうか・・? これまでの
NOKTON F0.95レンズとは、全く別物のように
収差の発生が少なく、解像感もかなり高い。
匠「あれ? 間違って、マクロアポランター65mm
(本記事2本目で紹介、解像感が極めて高い)
を、付けてきてしまったのかな?」
と、不審に思って、レンズやカメラをチェックするが、
まあ、元々マウントも違うし、そんな変な間違いを
する事は無い。(・・まあでも、数年に1度くらい、
装着する予定だったレンズと違うものを、間違って
付けてしまい、何枚か撮ってから、「あれ? これ、
違うレンズじゃあないの?!」と気付くケースも、
ある事はあった(汗) 外観等が、とても似ている
レンズが、結構色々と存在しているからだ)
で、思うに2010年代後半からのCOSINAの設計力は
なんだか格段に向上している気がしてならない。
私は、以下の、近年の各年度のCOSINA製レンズを
所有しているのだが・・
2016年:COSINA Carl Zeiss Milvus 50mm/f1.4
2017年:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm/F2
2018年:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/F2.5
2019年:Voigtlander APO-LANTHAR 50mm/F2 Aspherical
2020年:Voigtlander NOKTON 60mm/F0.95
このあたり(2016年以降)の、COSINA製レンズの
描写力は、どれも、非常に(驚くほど)高い。
(全て「描写表現力」を満点評価にしている)
2000年代の初期Voigtlanderレンズに比べると、
「1枚も2枚も上手」という感じがするのだが・・
ただ惜しむらくは、上記に挙げたレンズ群は、どれも
価格が軽く10万円以上もする高額レンズである(汗)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17532856.jpg]()
で、値段が高くても、描写表現力がたいした事はない
レンズも世の中には多々存在する。変にブランドが
著名で一般層に知られていたり、希少価値あるいは
意図的な情報操作(誰かが、これは良い、と褒める等)
により「投機対象」となっていたりするレンズの事だ。
そういうレンズは「コスパが壊滅的に悪い」と見なし、
絶対に購入する事は無いのだが、上記のCOSINA製の
レンズ群は、値段が高くても描写表現力も高いのだ、
だからコスパはさほど悪く無い。
けど、これらを、まともに新品で買っていたら・・
(注:どれも中古品が潤沢に出てくるような、一般的な
レンズでは無い。欲しければ、発売期間内に新品で買う
しか無いのだ。
---
まあ、近年のCOSINA製品では、長期に渡って継続生産
されるケースも多いが、2000年代のCOSINA製レンズ
は、いつの間にか生産完了になってしまい、後年には
「投機層」等により、意図的に定価の何倍もに値上げ
された超高額な中古品しか無くなってしまうのだ。
だから、万が一、COSINA製の「有益なレンズ」を
買いそびれると酷い目にあってしまう、という訳だ。
---
ただし勿論、全てのCOSINA製レンズを買う必要は無い。
どのレンズが自分にとって「有益」であり、どれが
そうで無いかを必ず消費者自身で判断する必要がある)
・・で、新品で買う場合、いちいち、その都度、軽く
10万円オーバーの出費を強いられる事になってしまう。
う~ん、困った状態だが、まあ、マニアであるならば
こういう高性能レンズを「見逃す」という選択肢は無い
のかも知れない。毎年1本くらいの、超高性能レンズの
購入費用は、まあ「必要経費だ」という感じか・・(?)
(追記:2020年以降、COSINA製新鋭レンズの中古品
も良く流通するようになった。現状、その理由(何故、
マニアックなレンズの中古品が市場に流れるのか?)
は不明である。多くのマニア層が、いよいよカメラの
趣味を辞めていっているからだろうか? はたまた
コロナ禍等の影響もあってか、新品が売れず新古品
流通が増えているのかも知れない?
ちなみに、コロナ禍以降、中古品の相場は新品と
そう変わらないケースも多々あり、「少し待って
中古相場が下がってから買う」という方法論が
近年においては通用しない場合もある)
---
さて、6本目はAF望遠マクロレンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17533811.jpg]()
レンズは、TAMRON SP AF 180mm/f3.5 Di LD [IF]
MACRO 1:1 (Model B01)
(中古購入価格 30,000円)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2003年に発売されたAF望遠等倍マクロレンズ。
非常に「描写表現力」が高いレンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17533824.jpg]()
しかし、やや古い仕様であり、望遠マクロの特性上
(無限遠から最短撮影距離迄、極めて広範囲のピント
駆動が必要となる)からも、AFは実用レベル以下
であり、ほぼ100%、MFでの使用を余儀なくされる。
で、たとえMFで使っても、狭い画角と浅い被写界深度
により、目の前の、すぐそこに居る、小さい被写体
(例:昆虫等)であっても、ファインダーには何も
写っておらず(=場所が違うか、完全にピンボケ)
まず写真を撮る事自体が、大変に難しいレンズである。
MF操作に習熟すれば、ピントリングを概算距離まで
廻した後に、レンズを正確に被写体の方へ向けれる、
そうできるならば、ファインダーに被写体の概要が
見えているから、そこからの構図・ピントの微調整は
さほど困難では無い。
だが、そう上手くはできないレベル(スキル)だと、
本レンズは、全く使う事が出来ない、最難関のレンズ
となるだろう。
ちなみに、AFを使う等の安易な解決策は全く無効だ、
まず、狭い画角での近接する小さい被写体に正確に
レンズを向ける事は、その時点で「ゴルゴ13」ばりの
高い技能が必要とされる。おまけに駆動範囲が大きく
大質量の大型レンズをAF駆動するのは、待っていられない
程の、かったるい長時間がかかり(AF速度が遅すぎる)
おまけに、浅い被写界深度ではAFの精度も足りない。
まあつまり、AFは使用不可と言っても過言では無い。
ここで少し余談だが、近年の「ゴルゴ13」には、
デューク東郷の娘か?と想像される「万能少女」が
2度程出てきて(2016年「Gの遺伝子」、2019年
「ゴルゴダの少女」)準レギュラーキャラ化される
かも知れず興味深い。超長寿劇画である「ゴルゴ13」
だが、娘(?)の登場により、いつ最終回を迎えても、
納得の行くエンディングや続編は成り立つであろう。
ただ、劇中でデューク東郷は歳を取らない設定だが
娘(?ファネット)の方は現状、成長しているので、
その整合性が難しいかも知れないが・・
そして、2021年に原作者の「さいとうたかお」氏
が逝去してしまっている。勿論、継続はされるが、
故に、終わりが無い劇画となるかも知れない。
さて、余談はともかく、AFの速度、精度の話だ。
「超音波モーター搭載ならばいけるのでは?」と
思うようならば、ちょっとそれも勘違いが含まれる。
超音波モーター搭載型レンズの多くは、シームレスMF
機能を謳い文句として、高付加価値化(=値上げ)を
目論んでいる。その事によるコスパ評価の大幅悪化は
さておき、シームレスMF実現の為の無限回転式の
ピントリングでは、近接(または遠距離)精密ピント
合わせの為のMF時の性能要件を満たしていない。
つまり高度なMF技法がまったく使えず、結果的に、
多くのケースで「撮影機会を逃すか、多大な悪影響が
出る」という次第である。
いったい何故、上記のような仕様のレンズばかりに
なってしまったのか?と言えば、レンズ市場が大きく
縮退している(=全く売れていない)状況においては、
超音波モーター搭載等の、初級ユーザー層の不安要素
に訴えかける(つまり、ビギナーはピンボケが怖いから、
高性能のAF機能を欲しがる)戦略である事が1つある。
こうしておけば(超音波モーターを入れれば)レンズを
高価な値付けにできるから、販売数が縮退した市場でも
利益率の向上で、事業(ビジネス)が維持しやすくなる。
そして、そういう高付加価値市場(=市場が縮退し
高価な商品ばかりとなってしまった)においては、
その分野に造詣が深い消費者・ユーザー層であれば
ある程に、高価になりすぎた新製品には興味をなくして
しまう。何故ならば、まず「高すぎる」という第一印象
(価値感覚)があるし、次いで、多少古い旧世代の機材
でも性能的に不満を感じ難い(例:別に超音波モーター
が入っていなくても、MFで十分撮れるから問題は無い)
からである。
別の側面からの課題としては、そうして主力ユーザー層
がビギナー層ばかりになってしまうと、「高度なMF技法」
等を扱えるユーザーは皆無になってしまう。
そういう訳で「超音波モーターが入り、無限回転式の
ピントリングになると、MF操作性が壊滅的に悪化する」
という重欠点は、メーカー側でも見て見ぬふりをするしか
無くなってしまう。また、ユーザー側でも、誰もそんな
撮り方はしないのだから、「AFが速くなった!」とかと
単純な、単純すぎる、ビギナー的評価しか誰もしない。
又、場合により、設計開発側でも高度で実用的なMF技法
など、誰もわかっていないかも知れない。AF一眼レフ
が実用化されて既に40年近くが経過し、今時の設計者
では、MFで多数の(少なくとも数十万枚の)撮影経験を
持つ人など、皆無であろうからだ。
「超音波モーターのAFで、もしピントが合わなかったら、
その時はシームレスMFで合わせてください」等の
超初級MF技法しか、仕様設計上では認識していない
可能性が極めて高い訳だ。
勿論、そんな撮り方(技法)が上手く行く筈も無い事は、
例えば、本SP180/3.5、又は超音波モーターが搭載
された、より後年の望遠/中望遠マクロをフィールド
(屋外)に持ち出して撮ってみれば、ものの30分で
誰にでも理解できるであろう。
まあ、そういう検証すらも誰もやっていないか・・
又は、その事自体が「大問題だ」という認識すらない、
という残念な状況である。
総括だが、本SP180/3.5は、非常に高い描写表現力を
持つ望遠マクロである事は間違いの無い事実である。
だが、現代の初級中級層のスキルでは、残念ながら
使いこなせない高難易度のレンズである事もまた事実だ。
まあでも、近年では中古相場が安価な本レンズを買って
徹底的にMF近接撮影の練習をする、といった前向きな
スタンスがあるならば、購入は悪く無いレンズであると
思う。
---
では、7本目は、超高解像力AF準標準レンズだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17533837.jpg]()
レンズは、SIGMA 40mm/f1.4 DG HSM | Art
(新古品購入価格 100,000円)(以下、A40/1.4)
カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)
2018年発売の高描写力AF単焦点大口径準標準レンズ。
40mm/F1.4と言えば、「準標準レンズ」という感覚と
なるとは思うが、これは、そうした印象からは想像の
範疇を超える、超本格派レンズである。
しかし、「三重苦」が非常に顕著であり、
1:大きく(フィルター径φ82mm)
2:重く(EFマウント版で重量1200g)
3:高価な(定価16万円+税)
「超三重苦」の「超弩(ド)級レンズ」である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17533888.jpg]()
もう、あれこれと細かい話をしても無意味だろう、
こうしたレンズを必要とするならば買えば良いし、
買った際での性能(描写表現力)上での不満も
一切無い事であろう。
(注:逆光耐性は、やや低いので、そこだけが
注意点である)
これを、あくまで「違う世界」の商品だと見なして、
買わないならば、それもまた1つの選択肢だ。
余談だが、「弩(ド)級」の弩とは、元々の語源は、
1906年(20世紀初頭)に竣工した、英国海軍の
戦艦「ドレッドノート」(HMS Dreadnought)の事
を指す。
30.5cm 45口径連装主砲5基10門を装備した火力は、
当時の他国の戦艦よりも圧倒的に優位であり、命名の
由来となった造語Dreadnought(=恐れを知らない)と
ともに、列強他国の軍事政策に大きな衝撃を与え
「ドレッドノート革命」とも言われていた。
まあ、カメラ界で言えば、MINOLTAの「αショック」
(1985年)のような出来事であろう。
他社を圧倒する、実用的なAF一眼レフシステムが
発売された事で、当時の他社は、一眼レフのAF化に
一斉に追従、その結果、それが出来たメーカーも
あれば、失敗して撤退したメーカーも出て来た。
で、他国や日本では、「弩(ド)級戦艦」を超える、
「超ド級戦艦」の開発方針に、一斉に転換した訳だ。
この故事に基づき、現代においても、他を圧倒する
凄いもの(商品等)が出てきた際に、「ド級」や
「超ド級」という表現が、至るところで使われている。
本レンズA40/1.4は、「超弩(ド)級」と言うよりは
「ド級」であろうか?これで他レンズを圧倒する事は
できるだろう。もし、これを見て他社等がA40/1.4
を超えるものを目指して開発を行えば、それは
「ド級」を超えるから、「超弩級」となる訳だ。
まあだから、いきなり最初から「超弩級」の製品が
出てくる筈は、その語源の意味からは、あり得ない話
なのであるが、現代では「超弩級」という言葉自体が
「凄いもの」を表す慣用表現となっているから、まあ
細かい事は言わない方が良いのかも知れない。
余談ばかりとなったが、ともかく本A40/1.4は
「凄いレンズ」である事は間違いは無い。
---
では、今回のラストは高解像力MF標準レンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17534537.jpg]()
レンズは、COSINA Carl Zeiss Milvus 50mm/f1.4
(中古購入価格 85,000円)(以下、Milvus50/1.4)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1 MarkⅡ (μ4/3機)
2016年に発売されたMF単焦点大口径標準レンズ。
50mm/F1.4という、ありふれたスペックながら、
これも一種の「ド級レンズ」と言えるであろう。
光学系は、8群10枚の多群(ディスタゴン)構成
という、標準レンズとしては過去に類を見ない構成だ。
フィルター径φ67m、重量780g(Fマウント版実測値)
定価148,500円+税は、上記のA40/1.4程では
無いが、十分に「三重苦」のレンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17534516.jpg]()
描写力は、かなり高め。ただしMFにおいては、ピント
の山が掴み難い(個人的には、多くのディスタゴン型
多群構成レンズで、同様の課題を感じる)ので、
NIKON Fマウント版で購入したとしても、NIKON一眼
レフには、あえて装着せず、MFアシスト機能を備える
ミラーレス機を母艦とする方が賢明であろう。
本レンズの発売の、ほんの10年前、2000年代迄は
各社の50mm/F1.4級(AF)標準レンズは、およそ
1980年代頃からの、古い(が、ほぼ完成された)
光学系設計を、ずっと踏襲したものが殆どであった。
そうしたレガシー(≒伝統的な遺産)な標準レンズは
3~5万円程度の定価で、重量も200g~300g、
フィルター径も、φ49mm~φ55mm程度と、
安価で、小型軽量で、そこそこの高画質であり、
魅力と、高いコストパフォーマンスが存在していた。
しかしながら、2010年代からの一眼レフ・交換レンズ
市場の大幅な縮退により、そうした「良心的」な標準
レンズを、いつまでも安価に売っていても、メーカー
も流通も、儲けが少なくてビジネスが継続できない。
それに、銀塩MF時代であれば、一眼レフのキット
(付属販売)レンズは、50mm標準レンズである事
が普通だったが、現代ではキットレンズは「標準
ズーム」である、だから、誰も、焦点距離が被る
50mm(/F1.4)級レンズなど、買おうとはしない。
特にビギナー層では、レンズの焦点距離を「平面的な
画角の変化」としか捉える事ができない。よって
ビ「何? 50mm? そんなの、オレが持っている
(標準)ズームに入っているから、いらないよ!」
という感覚しか持っていない事であろう。
だから、従って、50mmレンズを新たに買う消費者
層は、レンズの事を良くわかっている人達であろう。
そうであれば、高性能(=収差補正が行き届き、
高解像力で、高描写表現力のHi-Fiレンズ)な
新鋭標準レンズを開発し、それを売れば良い、と
メーカーは考えるであろう。
そうして、2010年代には、各カメラ・レンズ
メーカーから、これまでの50mm/F1.4級標準レンズ
の、4~5倍も重く、定価も4~8倍も高価な、
高付加価値型の新鋭標準レンズが出揃った訳だ。
新型の高性能標準レンズは、マニア的な観点に
おいても興味は出るだろう。私も本レンズを含め、
5本程度の新鋭標準レンズを購入してみた。
それらは、確かに良く写る、描写表現力的な不満は
一般的な評価基準においては、一切無い事であろう。
ただ、それが、価格や重量の増加に見合う性能か
否か?は微妙なところだ。
例えば、銀塩MFの50mm/F1.4標準レンズであれば
大放出時代(2010年前後)に、1,000円程度で
買えたものもある。それが、本記事で対戦している
新鋭標準レンズでは、中古でも10万円を超える物
が2本もある、100倍以上の価格差に見合う性能が
あるか否か? まあ、普通は、あり得ない話だ。
例えば、喫茶店で500円のコーヒーを飲む際に、
百倍ならば1杯5万円!のコーヒーを飲む事になる。
その高額コーヒーが、たとえ美味しかったとしても、
それを注文する客は、アラブの石油王あたりしか、
あり得ない話であろう。百倍の価格差というのは、
そういう感覚となる。
だから、ぶっちゃけ言えば、新鋭の標準レンズは
どれもコスパが恐ろしく悪い。まあ、そりゃそうだ、
市場縮退により、メーカーや流通が「利益を出さないと
事業が継続できない」という状況で発売された新製品
な訳だからだ、「消費者(ユーザー)側が、損をする」
事は、始めから決まっているシナリオな訳だ。
そういう仕掛けがわかった所で、もうよしとしよう。
まだ何本か、入手していない新鋭標準レンズもあるが
もう「どれも同じ、いずれもコスパが悪い!」という
事前評価により、まず購入する事は無いであろう。
・・さて、とは言うものの、本シリーズ記事は、
最強のレンズを決定する記事である。
例えば、高画質ではあるが高額すぎるレンズの場合、
コスパ評価点が1点や1.5点(いずれも5点満点)の、
レベルの低い戦いとなる事は避けられそうも無い。
まあ、恐らくだが決勝戦でも、そんな感じとなる
であろう、場合により、コスパ評価点を削除した上で
総合順位を決定するかも知れない。さもないと、
今回「殿堂入り」した(欠場している)レジェンドの
レンズ群には、どう転んでも勝てそうに無いからだ。
----
では最後に、今回の「最強・最強レンズ」編での、
「B優勝(1)」を選出しておこう。
選出基準は、個人レンズ評価データベース得点+
特別加点(実用性や、特別な効能の価値等、独断)
である。
*B決勝(1回戦)優勝レンズ
「SIGMA 40mm/f1.4 DG HSM | Art」
*評価点:4.00点(内、特別加点0.5点)
*寸評および追加作例
超絶的な描写力を持つ超高性能レンズである。
このレンズの高い解像力性能は、要求画素数を満たす
ならば、3倍や4倍程度のトリミングにも十分に耐える
事が出来る。まあつまり、画面の何処かに被写体が
写ってさえいれば、その被写体を「普通の写真として
利用できる」という事であり、ズームレンズでは無く
とも、仮想ズーム(トリミング)レンズとして使え、
実用撮影には無類の適合性を誇る事であろう。
ただし、「三重苦」の重欠点を持つ為、そう簡単に
誰にも推奨できるレンズでは無い。
業務用途専用レンズか、あるいはマニア的な知的好奇心
であれば「最高の解像力性能を持つレンズは、いったい
どういうものか?」という点で、研究対象には十分に
なり得るレンズだと思う。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17534590.jpg]()
では、次回の本シリーズ記事は、
「最強・最強レンズ選手権/B決勝2回戦」
となる予定。
各カテゴリー内での最強レンズを決める為に対戦して
来たのだが、今回は、さらにその中から最強のレンズ
をノンカテゴリー(無差別級)で対戦する事とする。
すなわち、これが「真のレンズ王者決定戦」となる。
Clik here to view.
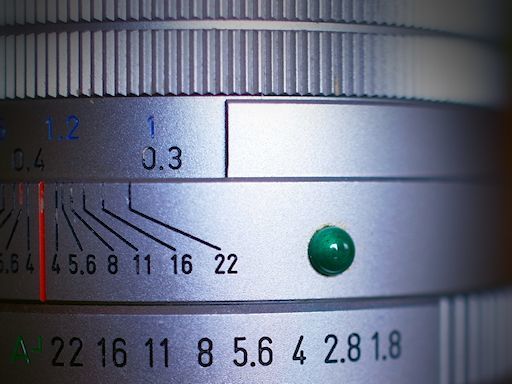
マニアックス名玉編」(全カテゴリーの共通)や、
「ハイコスパレンズBEST40編」(高コスパレンズでの
限定)、「価格別レンズ選手権」、および本シリーズ
での「焦点距離別選手権」等の、レンズのランキング
系の記事を多数実施している。
それらのランキング系記事で上位となったレンズは、
本ランキングでも、上位となる可能性が極めて高い。
いつも同じような戦績ばかりになっても、面白味が無い
為、有力な強豪レンズは、本シリーズでは「殿堂入り」
として対戦(ノミネート)を控える事としよう。
検討の結果「殿堂入りレンズ」は以下の10本となった。
01:smc PENTAX-FA 77mm/F1.8 Limited (2001年)
02:smc PENTAX-DA ★ 55mm/F1.4 (2009年)
03:MINOLTA STF 135mm/F2.8[T4.5] (1998年)
04:MINOLTA AF Macro 50mm/F2.8 (1985年)
05:MINOLTA MC ROKKOR-PF 50mm/F1.7 (1970年前後)
06:SONY DT 35mm/F1.8 SAM (SAL35F18) (2010年)
07:TAMRON SP 45mm/F1.8 Di VC USD(F013) (2015年)
08:Voigtlander APO-LANTHAR 90mm/F3.5 SL
Close Focus(注:変母音省略) (2002年)
09:Voigtlander NOKTON 42.5mm/F0.95 (2013年)
10:NIKON AiAF DC-NIKKOR 105mm/F2D (1993年)
上記のレンズ群は、いずれも過去のランキング系
記事で上位となった実績を持つ「レジェンド」の
強豪レンズであるので、「殿堂入り」としよう。
また、以下の4本のレンズは、ランキング上位となれる
可能性があるが、現代における入手性が極めて低い為、
(=レア物、あるいは投機対象で不条理な高額相場に
なっている為)ノミネート対象から外す。
11:CONTAX N Planar T* 85mm/F1.4 (2002年)
12:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 125mm/F2.5 SL
(注:変母音省略) (2001年)
13:YASHICA LENS ML 35mm/F2.8 (1970年代後半)
14:OLYMPUS OM-SYSTEM Zuiko 90mm/F2 Macro
(1980年代後半)
これら14本(機種)を除く、他の所有レンズ群で(注:
未購入、または現在未所有のレンズは評価・対戦をしない。
借りてきたレンズ等では正当な評価が出来ない事は当然だ)
本短期シリーズでの対戦を行う。
場合により、今回の最強レンズ選手権での上位レンズでは、
上記「殿堂入り」レンズ群には、描写性能的、または
総合性能(コスパ等も含む)では敵わないかも知れない。
逆に言えば、真の最強レンズが欲しければ、上記14本の
いずれかを探して入手すれば良い、との事になってしまう。
ただまあ、今回の対戦にノミネートされているレンズ
群も、それなりに個性的・マニアックで、魅力的なもの
ばかりではある。
なお、ロシアンレンズ、中国製格安レンズ、オールドレンズ、
トイレンズ、エントリー(お試し版)レンズ等は、参戦を
制限するものでは無いのだが、本決勝シリーズにおいて
ノミネートされているそれらの機種数は、非常に少ない。
(何かの特徴があっても、総合評価は高まらないからだ)
今回は、その殆どが「高描写力」レンズと「特殊効果」
(≒高表現力)レンズばかりの参戦となるだろう。
本シリーズ(や、本ブログ全般)で紹介(対戦)をする
レンズ群は、その全てが実践的・実用的な側面で有益な
ものばかりである。勿論、コレクション(収集)向けや
投機(転売)対象のレンズ群は、一切登場する事は無い。
それと、同一の(決勝)リーグ戦に進出するレンズは、
できるだけメーカー/シリーズ被りを避ける事とする。
(同じメーカー又は同じシリーズのレンズ群ばかりを
対戦させない。ただし、稀に被る事もある)
また、レンズ紹介の際の使用母艦(カメラ)は自由に
選択するが、多少はレンズの使用を効率的・効果的と
する事(=「弱点相殺型システム」)を意識する。
いつものように、実写は三脚を使用せず、その際の、
カメラ側に備わる機能(例:エフェクトやデジタル
拡大機能等)は自由に使えるルールとする。
ただし撮影後のアフターレタッチ(編集)については、
画像縮小、輝度調整、構図調整の為の僅かなトリミング
等、最小限のレベルに限定する。
また、全てJPEGでの小画素・低画質設定による撮影で
あり、RAW現像(撮影)は一切行わない。
(これらは他のシリーズ記事とも同じルールである)
----
では、始めよう。
本B決勝戦(1)には、8本のレンズがノミネート
されている。
まず、最初のノミネート(参戦)レンズ。
Clik here to view.

(中古購入価格 110,000円)(以下、AF-S58/1.4)
カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)
2013年発売の大口径AF標準レンズ。
「三次元的ハイファイ」(注:3D Hi-Fi等、他の表記が
使われる場合もある)を謳った、最初のレンズである。
Clik here to view.

の「部品や技術」が入っているという訳では無く、
これは、いわば「味付けのコンセプト」である。
これについては、誰も上手く説明できないからか?
「三次元的ハイファイ」の効能や特性を理解している
ユーザー層も極めて少ない。
・・この為、「よくわからない」「うまく撮れない」
「描写力が低い」という、ネガティブな初級評価が
蔓延したり、あるいは上手く撮れない事を自身の課題
だ、とは認識したくない中級層やマニア層においては、
「クセ玉だ」と、これをレンズの問題点や責任として
押し付けてしまう傾向(評価等)が、とても多い。
だが、これ(三次元的ハイファイ)について述べていく
と、軽く1記事分の文章量となってしまうだろうし、
そうやって説明をつくしたところで、設計思想が理解
できる保証も無く(→ユーザー側の理解力と言うよりは
そもそも「作った側」にしかわからない話でもあるかも
知れないからだ)結局、どれも無意味になりかねない。
まあ、興味があれば、レンズ・マニアックス第63回
「三次元的ハイファイ」編記事を参照していただくと
して、本記事においては、本レンズの詳細は割愛する。
描写表現力的には悪いレンズでは無いが、異常な迄に
高額であり、コスパ評価は最低点に近い状況だ。
---
では、次はマクロレンズである。
Clik here to view.

(注:独語綴りの変母音は省略。本ブログで全て同様)
(新品購入価格 122,000円)(以下、MAP65/2)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
2017年に発売された、フルサイズ対応大口径MF
準中望遠1/2倍(ハーフ)マクロレンズ。
今回、APS-C機で利用しているのは、本レンズはハーフ
マクロであり、最大撮影倍率に若干の不満があるからだ。
Clik here to view.

最大撮影倍率(注:カメラ側のデジタル拡大機能を併用
すれば、撮影倍率を仮想的に高める事は可能だ)となり
銀塩時代からの経験値の高い「中望遠マクロ」と、ほぼ
同等の換算スペックとなる為、経験則が適用でき、さらに
周辺収差の低減、重量バランスの向上(→特に、今回の
システムでは、ピントリングおよび前部の絞り環の操作
が全体重心のホールド状態からのレンズの持ち替え無し、
となり、操作性と撮影エンジョイ度が向上する)
・・といった理由でのAPS-C機の母艦利用である。
初級中級層では、「必ずフルサイズ機が高性能なのだ」
と信じて疑わないかも知れないが、フルサイズ機が高価
なのは、2010年代に大きく縮退したカメラ市場において
(=つまり、全くカメラが売れない)メーカーや流通
市場が事業を継続するために、高付加価値化を謳って
(=つまり、「フルサイズ機は高級で高性能なのだ」
という論理を、消費者層に強く植え付けようとした)
高価格化(値上げ)をした市場戦略であった訳だから、
フルサイズ機のコスパは、一般的にAPS-C以下機よりも
大きく劣る。
加えて、少し前述したが、レンズの特性を活かし、様々な
被写体状況に対応する為には、母艦はフルサイズ機に拘らず、
各種のセンサーサイズを選ぶ事が基本である。
(例:遠距離スポーツ撮影では、APS-C機の高速連写型
一眼レフを母艦とする事は常識的な措置であろう)
だが、勿論フルサイズ機が絶対に必要なケースも存在する。
(例:魚眼、シフト、ぐるぐるボケ、等の特殊効果レンズ
では、フルサイズ機でないと、それらの効能が得られない)
まあつまり、レンズとカメラは、それぞれの特徴・特性を
理解し、お互いの長所を助長し、弱点を相殺するような
組み合わせにする必要がある(=「弱点相殺型システム」)
余談が長くなったが、余談とは言い切れず、「適正な
システム(カメラ+レンズの組み合わせ)を構築する」
という事は、機材運用上の最も基本であり、極めて
重要な事でもある。
「フルサイズ機の高級機を買ったから、他のカメラは
もう、いらんよ」という訳では勿論ないし、はたまた
「オレのカメラの方が高価だから」と、周囲の他者を
見下すようなスタンスは、最もやってはならない事だ。
イベントの撮影にフラリとやってきたアマチュアカメラマン
達が、雨が降ると「大事な機材が壊れるから」と言って、
蜘蛛の子を散らすように、あっと言う間に全員撤収して
しまうことが良くある。だが業務撮影や、重用な依頼
撮影(例:そのイベントに家族知人が出演する等)では
「雨が降ったので撮れませんでした」という言い訳は
通用しない。そんな場合、雨中や悪条件においても撮影を
継続できるシステム(防水であったり、あるいは壊しても
惜しくないレベルの安価な「消耗用撮影機材」)の必要性は
誰にでも理解できるであろう。
まあつまり、撮影機材というものはケースバイケースであり
そのケース(条件)を、いかに多く想定できるか? または
そういう経験値を持っているか否か? が重要な事であり、
その、ケースバイケースやTPO(時、場所、条件)に応じて
最適な機材を選択できるか否か?が、機材運用上、あるいは
事前に機材の購入検討をする上での最大のポイントとなる訳だ。
MAP65/2レンズの話がちっとも出てこなかったが、
基本的に、本決勝リーグにノミネートされたレンズ群は
大きな弱点を持たないか、あるいは些細な弱点があったと
しても、技能で回避できるようなレベルのレンズばかりだ。
(注:本MAP65/2がMFレンズだから、という理由で、
使いこなせない、というようなビギナー層は、本記事の
対象読者とは見なしていない。
そもそも近接撮影時では、AFの方が全く使い物にならない
事も、中級層以上には良く知られた常識であろう)
まあだから、レンズ自体の仕様や長所短所等を細かく
記載しても意味が無い状態である。本最強・決勝リーグ
にノミネートされたレンズ群は、どれも一級品であり、
致命的な弱点(=重欠点)を持たないレンズばかりだ。
---
さて、3本目はミラー(レンズ)である。
Clik here to view.

(中古購入価格 18,000円)(以下、MF300/6.3)
カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)
2012年発売のミラー(反射型)(レンズ)である。
μ4/3機専用であり、換算600mmの超望遠画角だ。
電子接点にも対応していて、μ4/3機の内蔵手ブレ
補正機能は、手動焦点距離入力不要で使用できる。
ただし、換算600mm、あるいはデジタルテレコン等
の利用で換算1200mm以上ともなると、たとえ優秀
な内蔵手ブレ補正機能があったとしても精度不足で
まともには動作せず、加えて、多くのμ4/3機では
AUTO ISOの切り替わり(低速限界)シャッター速度
が手動設定不可であるので、本レンズのような超望遠
で暗い開放F値のレンズの場合は、AUTO ISOのままでは
シャッター速度が低くなりすぎて、手ブレを頻発する。
撮影者毎のスキルに応じた手ブレ限界シャッター速度を
維持する上では、頻繁なISO手動設定が必須であり、
操作性に課題が出る上に、やや高難易度だ。
(注:2016年発売以降のμ4/3高級機には、低速限界
設定機能が搭載されているケースもある。
例:OLYMPUS OM-D E-M1 MarkⅡ(2016年)以降の
旗艦機や、PANASONIC DC-G9(2018年)等)
さらには、換算600mmを超える超々望遠領域では、
システムを構えた場所に被写体を捉える事すら難しい。
加えて、ミラー(レンズ)のピント合わせは、遠距離
でも回転角が大きくて、感覚的にも技能的にもMF操作
がやや難しい。
Clik here to view.

高いとは言えない、被写体を選ぶ必要があるだろう。
(注:上の「月」の写真は、「限界性能テスト」だ。
あまり解像感が高くない事がわかるので、こういう
細密な被写体を撮るには向かない、という事となる)
そして、本レンズは、最短撮影距離80cm、1/2倍の
「超望遠マクロ」としての利用が最大の特徴だが、
近接撮影でも、被写体フレーミングと、MF合焦が
課題となる。
まあでも、弱点をあらかじめ多数挙げてはいるが、
総合的には、比較的バランスの取れた優秀なミラー
である為、過去の本ブログのランキング記事では、
比較的上位を複数回マークしている。
(ミラーレス名玉編第13位。ハイコスパ名玉編第12位。
超望遠レンズ選手権第1位)
仕様的には優秀なレンズながら、本ミラー(レンズ)を
周囲の人達に推奨して買って貰っても、どうにも上手く
使いこなせない模様だ。よって、近年においては、
本ミラーは「実践派上級マニア層向け」という観点で
あまり周囲には推奨しないようにしている。
(注:2022年現在では生産終了となっている)
---
では、次は準オールドレンズだ。
Clik here to view.

(新品購入価格 106,000円)(以下、P100/2)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
1980年代後半頃に発売されたMF中望遠レンズ。
本ブログでは過去に何度も紹介している「名レンズ」で
ある。近年は、これをEFマウント一眼レフで用いる事が
多いのだが、これは所有機材でのマウントアダプター等
の保有種や、使いまわしの関係が理由であり、あまり
適切なシステムとは言えないように思えてきている。
その理由は、一眼レフの光学ファインダーでは、ボケ質
破綻の回避技法が使いにくい(使えない)事が、やや
不満となってきており、稀に、ボケ質破綻が発生する際、
「せっかくの高描写力レンズなのに勿体無い」と思う
ようになってきたからだ。
今後は、ミラーレス機で使用できるように、システムを
整えていこうと思っている。(注:ミラーレス機に装着
するだけであれば容易に可能だが、本レンズの特性に
見合う母艦の機種を選ぶ事が、やや難しい)
Clik here to view.

無く、「完璧な描写力」とは言えないが、このレンズの
発売当時においては、他レンズよりも頭一つ飛びぬけた
高描写表現力レンズであった事だろう。
当時の人気商品の「CONTAX Planar T* 85mm/f1.4」
と比較すると、「ピント歩留まり」、「ボケ質破綻」、
「焦点移動」の3つの課題が良く改善されていて、
「安定した描写力を得られるレンズ」として、実用性
に多大な差があった。
大きな弱点は、高価な事であり、1990年代位の定価
では、P85/1.4の、およそ2倍の178,000円+税で
あり、富裕層が多いCONTAX党においても、購入を
躊躇うような贅沢品であったように思える。
人気レンズの、P85/1.4とMakro-Planar 100/2.8
の2本に挟まれたスペックでもあるから、本レンズの
購入者は極めて少なく、当時の中古カメラブーム時の
マニア層での口コミネットワーク(注:これは馬鹿に
できないレベルでの情報の質と量があった。その後の
インターネット時代では、情報の量は増えたが、質が
大きく低下してしまい、ビギナー層や、情報操作を
目論む層に発信機会が増えた為、膨大な「ゴミ情報」や
「欺瞞(フェイク)情報」とか「単なる宣伝情報」や
「アクセス稼ぎ情報」といった中から、正確で、かつ
有益な情報を見分ける事が大変困難になってしまった)
・・その口コミ情報にも、本レンズはまず登場せず、
マニア層等の誰にも注目されていないまま、銀塩時代が
終わり、役目を終えてしまった、やや悲運のレンズだ。
だが、そうなったのは、高額な定価をつけたメーカー
側にも問題があったと言えよう。コスパを考えると
20万円近くもするレンズとは思えず、現代で考える
ならば、単焦点100mm級での超高描写表現力を持つ
レンズは、他にいくらでも存在するし、その殆ど
全ては、本レンズより後の時代の製品なのに割安だ。
何故、こんなに高額なレンズとなってしまったのか?
企画やマーケティングの問題であろうか。
「CONTAX(Carl Zeiss)ならば高くても売れる」と
思ったのならば、それはちょっと企画側の勘違いで
あろう、当時の消費者層は、もっと賢くレンズの商品
価値を吟味して購入行動を起こしている。
それら消費者層が「高価すぎると思うから買わない」
となったのであれば、それが市場(マーケット)からの
「暗黙の回答」となった訳だ。
まあでも、本レンズが発売されてから35年以上が
経過し、京セラCONTAXがカメラ事業から撤退してから
も15年以上が経過した現在においては、本レンズの
中古品は、そこそこ安価に流通している場合もある。
売れていなかった為、あまり中古の玉数は豊富では無いが
4~5万円程度の相場で購入できるのであれば、
現代の感覚でコスパを評価しても、悪く無いレンズだと
思われる。(追記:コロナ禍以降、殆ど中古品を見なく
なってしまった。他のCONTAX RTS系レンズの相場が
高騰している状況を鑑みると、「希少価値演出」という
投機的措置も類推され、あまり好ましい状況では無い)
---
さて、5本目は超大口径レンズである。
Clik here to view.

(注:独語綴りの変母音は省略)
(新品購入価格 113,000円)(以下、NOKTON60)
カメラは、PANASONIC DMC-G5 (μ4/3機)
2020年発売のμ4/3機専用超大口径MF望遠画角レンズ。
F0.95級レンズとしては、発売時点で最も実焦点
距離が長いレンズである。
(参考:実焦点距離の長い次点は、2019年発売の
「NIKON NIKKOR Z 58mm/F0.95 S Noct」だ。
ただしそのレンズは、定価約126万円の「異常」
とも言える超高額レンズである。いったい誰が、
何の目的で買うのであろうか? そして、何故
そんな高額な商品を企画し発売するのだろうか?
まあ「こんな凄いレンズを作れるのですよ」という
「広告塔」であろうが、カメラ市場が大きく縮退して
しまっている昨今の状況で作る商品であろうか?
何だか、裏側にある、良くわからない「からくり」を
危惧してしまう。・・当然だが一切購入する気は無い)
COSINAでは2013年にNOKTON 42.5mm/F0.95
を発売していて(特殊レンズ第25回記事等、
多数の記事で紹介。使いこなしがとても困難な、
最難関レンズである)それが、発売時点では恐らく
最長焦点距離のF0.95レンズだったかも知れず、
その後、2010年代後半においては、各社から、
わらわらと様々なF0.95レンズが発売されている
ので、COSINAとしても「ここらで、最長の焦点
距離のF0.95を出しておくか?」という企画意図
だったのかも知れない。
(注:勿論、そうでも無いかも知れないが、
上記のZ58/0.95が、ちょっと異常な企画なので、
「こういう普通の企画方針の商品であるならば
好ましい」という消費者視点での話だ・・
ただ、COSINAは、やはりZ58/0.95を相当に意識
している模様であり、2020年にSUPER NOKTON
29mm/F0.8(換算58mm/F0.8)を発売している)
まあこの結果、COSINAとしては、久しぶりの
F0.95シリーズの新製品発売となった訳だ。
Clik here to view.

で紹介した3本のF0.95レンズは、いずれも正直
言えば、F0.95~F2あたりまでの、絞り開放近く
では、球面収差を始めとする、諸収差の発生を
抑えられておらず、「ボケボケの写りだ」とも
言えただろう。しかし、超大口径レンズとしての
多大な「表現力」を持っている為、個人評価DBでの
旧型NOKTONの「描写表現力」は5点満点評価であった。
だが、本NOKTON60/0.95は、いったい、どこから
どうなってしまったのだろうか・・? これまでの
NOKTON F0.95レンズとは、全く別物のように
収差の発生が少なく、解像感もかなり高い。
匠「あれ? 間違って、マクロアポランター65mm
(本記事2本目で紹介、解像感が極めて高い)
を、付けてきてしまったのかな?」
と、不審に思って、レンズやカメラをチェックするが、
まあ、元々マウントも違うし、そんな変な間違いを
する事は無い。(・・まあでも、数年に1度くらい、
装着する予定だったレンズと違うものを、間違って
付けてしまい、何枚か撮ってから、「あれ? これ、
違うレンズじゃあないの?!」と気付くケースも、
ある事はあった(汗) 外観等が、とても似ている
レンズが、結構色々と存在しているからだ)
で、思うに2010年代後半からのCOSINAの設計力は
なんだか格段に向上している気がしてならない。
私は、以下の、近年の各年度のCOSINA製レンズを
所有しているのだが・・
2016年:COSINA Carl Zeiss Milvus 50mm/f1.4
2017年:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm/F2
2018年:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/F2.5
2019年:Voigtlander APO-LANTHAR 50mm/F2 Aspherical
2020年:Voigtlander NOKTON 60mm/F0.95
このあたり(2016年以降)の、COSINA製レンズの
描写力は、どれも、非常に(驚くほど)高い。
(全て「描写表現力」を満点評価にしている)
2000年代の初期Voigtlanderレンズに比べると、
「1枚も2枚も上手」という感じがするのだが・・
ただ惜しむらくは、上記に挙げたレンズ群は、どれも
価格が軽く10万円以上もする高額レンズである(汗)
Clik here to view.

レンズも世の中には多々存在する。変にブランドが
著名で一般層に知られていたり、希少価値あるいは
意図的な情報操作(誰かが、これは良い、と褒める等)
により「投機対象」となっていたりするレンズの事だ。
そういうレンズは「コスパが壊滅的に悪い」と見なし、
絶対に購入する事は無いのだが、上記のCOSINA製の
レンズ群は、値段が高くても描写表現力も高いのだ、
だからコスパはさほど悪く無い。
けど、これらを、まともに新品で買っていたら・・
(注:どれも中古品が潤沢に出てくるような、一般的な
レンズでは無い。欲しければ、発売期間内に新品で買う
しか無いのだ。
---
まあ、近年のCOSINA製品では、長期に渡って継続生産
されるケースも多いが、2000年代のCOSINA製レンズ
は、いつの間にか生産完了になってしまい、後年には
「投機層」等により、意図的に定価の何倍もに値上げ
された超高額な中古品しか無くなってしまうのだ。
だから、万が一、COSINA製の「有益なレンズ」を
買いそびれると酷い目にあってしまう、という訳だ。
---
ただし勿論、全てのCOSINA製レンズを買う必要は無い。
どのレンズが自分にとって「有益」であり、どれが
そうで無いかを必ず消費者自身で判断する必要がある)
・・で、新品で買う場合、いちいち、その都度、軽く
10万円オーバーの出費を強いられる事になってしまう。
う~ん、困った状態だが、まあ、マニアであるならば
こういう高性能レンズを「見逃す」という選択肢は無い
のかも知れない。毎年1本くらいの、超高性能レンズの
購入費用は、まあ「必要経費だ」という感じか・・(?)
(追記:2020年以降、COSINA製新鋭レンズの中古品
も良く流通するようになった。現状、その理由(何故、
マニアックなレンズの中古品が市場に流れるのか?)
は不明である。多くのマニア層が、いよいよカメラの
趣味を辞めていっているからだろうか? はたまた
コロナ禍等の影響もあってか、新品が売れず新古品
流通が増えているのかも知れない?
ちなみに、コロナ禍以降、中古品の相場は新品と
そう変わらないケースも多々あり、「少し待って
中古相場が下がってから買う」という方法論が
近年においては通用しない場合もある)
---
さて、6本目はAF望遠マクロレンズである。
Clik here to view.

MACRO 1:1 (Model B01)
(中古購入価格 30,000円)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2003年に発売されたAF望遠等倍マクロレンズ。
非常に「描写表現力」が高いレンズである。
Clik here to view.

(無限遠から最短撮影距離迄、極めて広範囲のピント
駆動が必要となる)からも、AFは実用レベル以下
であり、ほぼ100%、MFでの使用を余儀なくされる。
で、たとえMFで使っても、狭い画角と浅い被写界深度
により、目の前の、すぐそこに居る、小さい被写体
(例:昆虫等)であっても、ファインダーには何も
写っておらず(=場所が違うか、完全にピンボケ)
まず写真を撮る事自体が、大変に難しいレンズである。
MF操作に習熟すれば、ピントリングを概算距離まで
廻した後に、レンズを正確に被写体の方へ向けれる、
そうできるならば、ファインダーに被写体の概要が
見えているから、そこからの構図・ピントの微調整は
さほど困難では無い。
だが、そう上手くはできないレベル(スキル)だと、
本レンズは、全く使う事が出来ない、最難関のレンズ
となるだろう。
ちなみに、AFを使う等の安易な解決策は全く無効だ、
まず、狭い画角での近接する小さい被写体に正確に
レンズを向ける事は、その時点で「ゴルゴ13」ばりの
高い技能が必要とされる。おまけに駆動範囲が大きく
大質量の大型レンズをAF駆動するのは、待っていられない
程の、かったるい長時間がかかり(AF速度が遅すぎる)
おまけに、浅い被写界深度ではAFの精度も足りない。
まあつまり、AFは使用不可と言っても過言では無い。
ここで少し余談だが、近年の「ゴルゴ13」には、
デューク東郷の娘か?と想像される「万能少女」が
2度程出てきて(2016年「Gの遺伝子」、2019年
「ゴルゴダの少女」)準レギュラーキャラ化される
かも知れず興味深い。超長寿劇画である「ゴルゴ13」
だが、娘(?)の登場により、いつ最終回を迎えても、
納得の行くエンディングや続編は成り立つであろう。
ただ、劇中でデューク東郷は歳を取らない設定だが
娘(?ファネット)の方は現状、成長しているので、
その整合性が難しいかも知れないが・・
そして、2021年に原作者の「さいとうたかお」氏
が逝去してしまっている。勿論、継続はされるが、
故に、終わりが無い劇画となるかも知れない。
さて、余談はともかく、AFの速度、精度の話だ。
「超音波モーター搭載ならばいけるのでは?」と
思うようならば、ちょっとそれも勘違いが含まれる。
超音波モーター搭載型レンズの多くは、シームレスMF
機能を謳い文句として、高付加価値化(=値上げ)を
目論んでいる。その事によるコスパ評価の大幅悪化は
さておき、シームレスMF実現の為の無限回転式の
ピントリングでは、近接(または遠距離)精密ピント
合わせの為のMF時の性能要件を満たしていない。
つまり高度なMF技法がまったく使えず、結果的に、
多くのケースで「撮影機会を逃すか、多大な悪影響が
出る」という次第である。
いったい何故、上記のような仕様のレンズばかりに
なってしまったのか?と言えば、レンズ市場が大きく
縮退している(=全く売れていない)状況においては、
超音波モーター搭載等の、初級ユーザー層の不安要素
に訴えかける(つまり、ビギナーはピンボケが怖いから、
高性能のAF機能を欲しがる)戦略である事が1つある。
こうしておけば(超音波モーターを入れれば)レンズを
高価な値付けにできるから、販売数が縮退した市場でも
利益率の向上で、事業(ビジネス)が維持しやすくなる。
そして、そういう高付加価値市場(=市場が縮退し
高価な商品ばかりとなってしまった)においては、
その分野に造詣が深い消費者・ユーザー層であれば
ある程に、高価になりすぎた新製品には興味をなくして
しまう。何故ならば、まず「高すぎる」という第一印象
(価値感覚)があるし、次いで、多少古い旧世代の機材
でも性能的に不満を感じ難い(例:別に超音波モーター
が入っていなくても、MFで十分撮れるから問題は無い)
からである。
別の側面からの課題としては、そうして主力ユーザー層
がビギナー層ばかりになってしまうと、「高度なMF技法」
等を扱えるユーザーは皆無になってしまう。
そういう訳で「超音波モーターが入り、無限回転式の
ピントリングになると、MF操作性が壊滅的に悪化する」
という重欠点は、メーカー側でも見て見ぬふりをするしか
無くなってしまう。また、ユーザー側でも、誰もそんな
撮り方はしないのだから、「AFが速くなった!」とかと
単純な、単純すぎる、ビギナー的評価しか誰もしない。
又、場合により、設計開発側でも高度で実用的なMF技法
など、誰もわかっていないかも知れない。AF一眼レフ
が実用化されて既に40年近くが経過し、今時の設計者
では、MFで多数の(少なくとも数十万枚の)撮影経験を
持つ人など、皆無であろうからだ。
「超音波モーターのAFで、もしピントが合わなかったら、
その時はシームレスMFで合わせてください」等の
超初級MF技法しか、仕様設計上では認識していない
可能性が極めて高い訳だ。
勿論、そんな撮り方(技法)が上手く行く筈も無い事は、
例えば、本SP180/3.5、又は超音波モーターが搭載
された、より後年の望遠/中望遠マクロをフィールド
(屋外)に持ち出して撮ってみれば、ものの30分で
誰にでも理解できるであろう。
まあ、そういう検証すらも誰もやっていないか・・
又は、その事自体が「大問題だ」という認識すらない、
という残念な状況である。
総括だが、本SP180/3.5は、非常に高い描写表現力を
持つ望遠マクロである事は間違いの無い事実である。
だが、現代の初級中級層のスキルでは、残念ながら
使いこなせない高難易度のレンズである事もまた事実だ。
まあでも、近年では中古相場が安価な本レンズを買って
徹底的にMF近接撮影の練習をする、といった前向きな
スタンスがあるならば、購入は悪く無いレンズであると
思う。
---
では、7本目は、超高解像力AF準標準レンズだ。
Clik here to view.

(新古品購入価格 100,000円)(以下、A40/1.4)
カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)
2018年発売の高描写力AF単焦点大口径準標準レンズ。
40mm/F1.4と言えば、「準標準レンズ」という感覚と
なるとは思うが、これは、そうした印象からは想像の
範疇を超える、超本格派レンズである。
しかし、「三重苦」が非常に顕著であり、
1:大きく(フィルター径φ82mm)
2:重く(EFマウント版で重量1200g)
3:高価な(定価16万円+税)
「超三重苦」の「超弩(ド)級レンズ」である。
Clik here to view.

こうしたレンズを必要とするならば買えば良いし、
買った際での性能(描写表現力)上での不満も
一切無い事であろう。
(注:逆光耐性は、やや低いので、そこだけが
注意点である)
これを、あくまで「違う世界」の商品だと見なして、
買わないならば、それもまた1つの選択肢だ。
余談だが、「弩(ド)級」の弩とは、元々の語源は、
1906年(20世紀初頭)に竣工した、英国海軍の
戦艦「ドレッドノート」(HMS Dreadnought)の事
を指す。
30.5cm 45口径連装主砲5基10門を装備した火力は、
当時の他国の戦艦よりも圧倒的に優位であり、命名の
由来となった造語Dreadnought(=恐れを知らない)と
ともに、列強他国の軍事政策に大きな衝撃を与え
「ドレッドノート革命」とも言われていた。
まあ、カメラ界で言えば、MINOLTAの「αショック」
(1985年)のような出来事であろう。
他社を圧倒する、実用的なAF一眼レフシステムが
発売された事で、当時の他社は、一眼レフのAF化に
一斉に追従、その結果、それが出来たメーカーも
あれば、失敗して撤退したメーカーも出て来た。
で、他国や日本では、「弩(ド)級戦艦」を超える、
「超ド級戦艦」の開発方針に、一斉に転換した訳だ。
この故事に基づき、現代においても、他を圧倒する
凄いもの(商品等)が出てきた際に、「ド級」や
「超ド級」という表現が、至るところで使われている。
本レンズA40/1.4は、「超弩(ド)級」と言うよりは
「ド級」であろうか?これで他レンズを圧倒する事は
できるだろう。もし、これを見て他社等がA40/1.4
を超えるものを目指して開発を行えば、それは
「ド級」を超えるから、「超弩級」となる訳だ。
まあだから、いきなり最初から「超弩級」の製品が
出てくる筈は、その語源の意味からは、あり得ない話
なのであるが、現代では「超弩級」という言葉自体が
「凄いもの」を表す慣用表現となっているから、まあ
細かい事は言わない方が良いのかも知れない。
余談ばかりとなったが、ともかく本A40/1.4は
「凄いレンズ」である事は間違いは無い。
---
では、今回のラストは高解像力MF標準レンズである。
Clik here to view.

(中古購入価格 85,000円)(以下、Milvus50/1.4)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1 MarkⅡ (μ4/3機)
2016年に発売されたMF単焦点大口径標準レンズ。
50mm/F1.4という、ありふれたスペックながら、
これも一種の「ド級レンズ」と言えるであろう。
光学系は、8群10枚の多群(ディスタゴン)構成
という、標準レンズとしては過去に類を見ない構成だ。
フィルター径φ67m、重量780g(Fマウント版実測値)
定価148,500円+税は、上記のA40/1.4程では
無いが、十分に「三重苦」のレンズである。
Clik here to view.

の山が掴み難い(個人的には、多くのディスタゴン型
多群構成レンズで、同様の課題を感じる)ので、
NIKON Fマウント版で購入したとしても、NIKON一眼
レフには、あえて装着せず、MFアシスト機能を備える
ミラーレス機を母艦とする方が賢明であろう。
本レンズの発売の、ほんの10年前、2000年代迄は
各社の50mm/F1.4級(AF)標準レンズは、およそ
1980年代頃からの、古い(が、ほぼ完成された)
光学系設計を、ずっと踏襲したものが殆どであった。
そうしたレガシー(≒伝統的な遺産)な標準レンズは
3~5万円程度の定価で、重量も200g~300g、
フィルター径も、φ49mm~φ55mm程度と、
安価で、小型軽量で、そこそこの高画質であり、
魅力と、高いコストパフォーマンスが存在していた。
しかしながら、2010年代からの一眼レフ・交換レンズ
市場の大幅な縮退により、そうした「良心的」な標準
レンズを、いつまでも安価に売っていても、メーカー
も流通も、儲けが少なくてビジネスが継続できない。
それに、銀塩MF時代であれば、一眼レフのキット
(付属販売)レンズは、50mm標準レンズである事
が普通だったが、現代ではキットレンズは「標準
ズーム」である、だから、誰も、焦点距離が被る
50mm(/F1.4)級レンズなど、買おうとはしない。
特にビギナー層では、レンズの焦点距離を「平面的な
画角の変化」としか捉える事ができない。よって
ビ「何? 50mm? そんなの、オレが持っている
(標準)ズームに入っているから、いらないよ!」
という感覚しか持っていない事であろう。
だから、従って、50mmレンズを新たに買う消費者
層は、レンズの事を良くわかっている人達であろう。
そうであれば、高性能(=収差補正が行き届き、
高解像力で、高描写表現力のHi-Fiレンズ)な
新鋭標準レンズを開発し、それを売れば良い、と
メーカーは考えるであろう。
そうして、2010年代には、各カメラ・レンズ
メーカーから、これまでの50mm/F1.4級標準レンズ
の、4~5倍も重く、定価も4~8倍も高価な、
高付加価値型の新鋭標準レンズが出揃った訳だ。
新型の高性能標準レンズは、マニア的な観点に
おいても興味は出るだろう。私も本レンズを含め、
5本程度の新鋭標準レンズを購入してみた。
それらは、確かに良く写る、描写表現力的な不満は
一般的な評価基準においては、一切無い事であろう。
ただ、それが、価格や重量の増加に見合う性能か
否か?は微妙なところだ。
例えば、銀塩MFの50mm/F1.4標準レンズであれば
大放出時代(2010年前後)に、1,000円程度で
買えたものもある。それが、本記事で対戦している
新鋭標準レンズでは、中古でも10万円を超える物
が2本もある、100倍以上の価格差に見合う性能が
あるか否か? まあ、普通は、あり得ない話だ。
例えば、喫茶店で500円のコーヒーを飲む際に、
百倍ならば1杯5万円!のコーヒーを飲む事になる。
その高額コーヒーが、たとえ美味しかったとしても、
それを注文する客は、アラブの石油王あたりしか、
あり得ない話であろう。百倍の価格差というのは、
そういう感覚となる。
だから、ぶっちゃけ言えば、新鋭の標準レンズは
どれもコスパが恐ろしく悪い。まあ、そりゃそうだ、
市場縮退により、メーカーや流通が「利益を出さないと
事業が継続できない」という状況で発売された新製品
な訳だからだ、「消費者(ユーザー)側が、損をする」
事は、始めから決まっているシナリオな訳だ。
そういう仕掛けがわかった所で、もうよしとしよう。
まだ何本か、入手していない新鋭標準レンズもあるが
もう「どれも同じ、いずれもコスパが悪い!」という
事前評価により、まず購入する事は無いであろう。
・・さて、とは言うものの、本シリーズ記事は、
最強のレンズを決定する記事である。
例えば、高画質ではあるが高額すぎるレンズの場合、
コスパ評価点が1点や1.5点(いずれも5点満点)の、
レベルの低い戦いとなる事は避けられそうも無い。
まあ、恐らくだが決勝戦でも、そんな感じとなる
であろう、場合により、コスパ評価点を削除した上で
総合順位を決定するかも知れない。さもないと、
今回「殿堂入り」した(欠場している)レジェンドの
レンズ群には、どう転んでも勝てそうに無いからだ。
----
では最後に、今回の「最強・最強レンズ」編での、
「B優勝(1)」を選出しておこう。
選出基準は、個人レンズ評価データベース得点+
特別加点(実用性や、特別な効能の価値等、独断)
である。
*B決勝(1回戦)優勝レンズ
「SIGMA 40mm/f1.4 DG HSM | Art」
*評価点:4.00点(内、特別加点0.5点)
*寸評および追加作例
超絶的な描写力を持つ超高性能レンズである。
このレンズの高い解像力性能は、要求画素数を満たす
ならば、3倍や4倍程度のトリミングにも十分に耐える
事が出来る。まあつまり、画面の何処かに被写体が
写ってさえいれば、その被写体を「普通の写真として
利用できる」という事であり、ズームレンズでは無く
とも、仮想ズーム(トリミング)レンズとして使え、
実用撮影には無類の適合性を誇る事であろう。
ただし、「三重苦」の重欠点を持つ為、そう簡単に
誰にも推奨できるレンズでは無い。
業務用途専用レンズか、あるいはマニア的な知的好奇心
であれば「最高の解像力性能を持つレンズは、いったい
どういうものか?」という点で、研究対象には十分に
なり得るレンズだと思う。
Clik here to view.

「最強・最強レンズ選手権/B決勝2回戦」
となる予定。