本シリーズ記事は所有している古いデジタルカメラ
(オールドデジタル機)を、時代とカテゴリーで
分類し、順次紹介していく記事群である。
今回は、「ミラーレス編(2)」とし、本記事での
紹介機は、2011年~2013年の期間に発売された
ミラーレス機を5台とする。
装着レンズは、同時代(2010年代前半頃)に
発売された、トイレンズ/個性的レンズを選択する。
殆どが「Hi-Fi」(高描写力)では無く、「Lo-Fi」
(低描写力)のミラーレス機専用レンズ群である。
これまでの銀塩時代~デジタル初期の時代であれば、
「写真とは、高画質であるべき」という強い思想が
アマチュアユーザー層全般に根強かったのだが、
勿論それは、単なる「思い込み」に過ぎない。
デジタル化しておよそ10年のこの時代から、やっと
「高画質であるばかりが写真の表現では無い」という
当たり前の発想が広まりつつある時代となった。
なお、音楽の世界では、そんな事(Lo-Fi音楽)は、
20年以上前の1990年代頃から、すでに常識だ。
カメラ(映像)の世界は、音楽(音響)の世界より
技術のデジタル化が、およそ15年も遅かったから、
音楽(音響)の歴史を後追いする形となっている。
(例:近年のデジタル・シンセサイザー(楽器)では
「部品の経年劣化をシミュレートし、わざわざ音質
を悪くする機能(可変式)」が付いていたりする。
デジタルカメラで、そんな機能が付くのは、まだまだ
遥かに先の時代であろう。技術的な実現性ではなく、
ユーザー(利用者)側に、そんな要望が無いからだ)
---
では、今回最初のオールド・ミラーレス。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)
(2012年発売、発売時実勢価格約9万円)
(中古購入価格 26,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第6回
レンズは、FUJIFILM FILTER LENS XM-FL S 24mm/f8
(2015年発売)を使用する。
さて、今回の記事では、やや古い時代のミラーレス機
群に、トイレンズや個性的なレンズを装着している。
1つの理由としては、この時代までのミラーレス機は
AF性能に優れないものが多く(=コントラストAF機構
のみの搭載で、像面位相差AF等の新世代の技術は、まだ
搭載されていない) また、MF性能にも優れない機体も
多かった。(EVFが無かったり、EVFがあっても解像度が
低かったり、ピーキング機能が未搭載か、それが
あったとしても精度が低かった。あるいは画面拡大
等の操作系に課題があり、MF操作が行い難い)
結局、この時代のミラーレス機では、AF/MFの性能
つまり「ピント合わせ」に問題があった事となる。
その最たる機種は、今回紹介のFUJIFILM X-E1や
PENTAX Qであるが、他のこの時代(2010年代初頭迄)
のミラーレス機の多くも似たようなものだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
こうしたピント合わせが苦手な機体を用いる場合は、
高いピント精度を要求されないレンズ、すなわち
ピンホール、パンフォーカスレンズ(今回使用の
FUJIFILM XM-FL等)、ボディキャップレンズ、
トイレンズ(LOMO、HOLGA、PENTAXユニークレンズ
等)を用いる事により、機体側のピント性能の弱点が
消えて快適に使える事となる(=弱点相殺型システム)
もう1つのトイレンズを使う理由であるが、基本的に
トイレンズはLo-Fi(ローファイ)描写である。
Lo-Fiは、Hi-Fi(ハイファイ)に対峙する、映像や音楽
の世界で使われる用語なのだが。映像で使う場合には、
「低画質」「低精細」という意味だ。
「映像記録」であれば、勿論Hi-Fi(高精細、高画質)
である事は望ましいが、「写真」の場合は、常に
Hi-Fi写真が要求される訳ではない。
写真は映像記録とは異なり、「映像表現」なのだから、
そこでは、必ずしも高画質である事は必須では無い。
まあ、例えば絵画の世界を思い起こしてもらえれば
良いが、印象派や現代アート等では、物凄くリアル
でHi-Fiな絵画ばかりでは無い訳だ。
そこには画家やアーティストが望む、あるいは表現
したい様々な方向性・志向性などが存在し、それは
まさしく「千差万別」である。
また、日本等の写真界においても、1950年代頃迄は、
その殆どが「映像記録」としての写真であったのだが、
その後の時代(日本では1960年代頃)からでは、
「映像表現としての写真」が、急速に発展していく。
(例として、写真家「奈良原一高」1931~2020年
等の作品が挙げられる)
ただ、大半のアマチュア初級中級層は、Hi-Fi写真
(だけ)を撮る事を目指してしまう。これの何が
問題なのか?は、膨大な説明文章が必要となるが、
本ブログでは、折に触れ、何度も説明してきた事で
あるし、上記、「絵画」の例を理解できるのであれば
それが写真の世界(注:映像記録では無い世界)にも
十分に同じ概念が適用できる事は理解が容易であろう。
で、トイレンズを使ってLo-Fi写真を撮る場合は、
カメラ本体側は最新の性能・機能の最高の画質の機体
でなくても何ら問題は無い。いや、むしろ出切るだけ
古い(デジタル)カメラ等を用いて、それが発売
された当時の、未成熟な技術(撮像センサーや、
画像処理エンジン等)でも、個性的な出力画像(例:
オリンパスブルー等の極端に青味が強調された映像)
を用いて、それらを「表現」に変えてしまう事が
出来るかも知れない訳だ。
さて、本記事においては Lo-Fiレンズを使う意義
等を主に紹介していくが、この内容は長くなる為、
話の途中で適宜カメラとレンズを交替する。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06435572.jpg]()
その前に、本機FUJIFILM X-E1の総括であるが、
FUJIFILM社は、ミラーレス機市場への参入は最後発
(2012年)であり、かつ、それ以前の時代では
約30年間の長期に渡り、レンズ交換式カメラを殆ど
開発していなかった(中判機やTX等を除き、国内最終
機種は、FUJICA AXシリーズ(1980年頃)であろう)
この空白期間では、FUJIは銀塩コンパクト機やデジタル
コンパクト機が好調ではあったが、カメラの機種毎に
大きく仕様やコンセプト、使用部品等が異なる状況を
見ると、その殆どがOEM製品であっただろうと推察できる。
この状況で、いきなりレンズ交換型のXシリーズの発売だ。
しかも、本機X-E1は、最初期のミラーレスXシリーズ機
であるから、そのAF/MF性能、および操作系全般、
さらには機能不足等もあって、正直言えば、同時代の
他社機に比べ、大きくビハインド(遅れた)の状態だ。
そこから数年間で、Xシリーズでは多数の改善が行われた。
さすがに、このX-E1の設計水準では、ユーザー層からも
不満が大きかったのであろう。
本機の低性能は購入前から予想が出来ていた為、当初は
Xシリーズ機を買う気は、さらさら無かったのであるが
2014年に、史上2本目のアポダイゼーションレンズが
FUJIから発売されてしまったので、そのレンズを絶対に
入手する必要があると見なし、その母艦として中古相場
が下がっていた本X-E1を、やむなく購入した次第である。
現在において、本機X-E1を指名買いする事は、推奨
出来ない。もう少し後年の、せめて像面位相差AFが
搭載されたX-Tシリーズ機を選択する事が無難であろう。
ただし、ダメダメのカメラであっても、今回の用法の
ように、ピント合わせの負担が少ない(または、パン
フォーカス)トイレンズや特殊レンズを用いれば、
X-E1の短所は概ね解消でき、「絵作り(発色)に優れる」
というFUJIFILM X機共通の長所を活用できる。
(=弱点相殺型システムとなる)
----
では、2台目のオールド・ミラーレス機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06435533.jpg]()
カメラは、PENTAX Q (1/2.3型機)
(2011年発売、発売時実勢価格約7万円
ただし、単焦点レンズキットの価格)
(中古購入価格 9,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第11回
レンズは、HOLGA LENS 10mm/f8 HL-PQ
(2014年頃発売)を使用する。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06442772.jpg]()
PENTAX(旧:旭光学工業株式会社)は、1960年頃
から銀塩MF一眼レフの製造販売を始め、これを
ロングセラーのヒット商品(例:ASAHI PENTAX
SPシリーズは累計350万台の販売数)とし、さらに
AF一眼レフ、中判(645/67等)、110(ワンテン)
等のカメラ群や、双眼鏡等の光学製品で、好調な
ビジネスを続けていたが・・・
2000年代、デジタル化の変革期において、
これまでの事業構造を再編する為、他社との協業を
模索する。そこからは、すったもんだ、があって、
HOYAとの合併が成立したのが2008年頃であった。
HOYAは徹底的なリストラと、エントリー層向けに
特化した大胆な市場戦略を実施し、この時代の
PENTAXのカメラ事業を黒字化させるのだが、まあ
内部的に色々と、やりにくい点はあった事だろう。
HOYAは2011年頃にPENTAX(カメラ、双眼鏡)を
RICOHに売却譲渡する事を決定。その後の時代では
PENTAXという企業名は消滅し「リコーイメージング
株式会社」として現在に至る。
さて、本機PENTAX Qは、世界最小のレンズ交換型
(ミラーレス)カメラであり、PENTAXがRICOHの
傘下となった直後に発売されたカメラではあるが、
その企画は完全にHOYA時代のものであり、話題性の
ある、エントリー層向けの戦略機である。
エントリー層向けであるから、その市場評価は
「小型である」「アダプターを使うと、どんな
レンズでも望遠となる」「ユニーク(トイ)
レンズがラインナップされている」あたりが好意的
な評価であり、さらに翌年のQ10からは、オーダー
カラー制導入や、人気アニメとのコラボ商品等で、
エントリー層への話題性も加わった。
その逆に、ネガティブな意見としては・・
「センサーサイズが小さすぎる」「交換レンズの
選択肢が少ない」あたりがあっただろう。
私の場合のQシリーズ機の用途は、それが持つ優れた
「エフェクト操作系」を活かした、トイレンズ母艦
および、センサーサイズが小さい事からの
「マシンビジョン用(FA用)レンズ母艦」としての
役割が、ほぼ100%となっている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06442756.jpg]()
ここから、トイレンズでのLo-Fiや、それと密接な
関係性がある「エフェクト」の話に戻る。
カメラ自体の設計年度が古く、使用部品等の技術的
な未成熟により、カメラの性能が劣っていたとする。
普通、現代のユーザー層においては、そういう
オールド(デジタル)カメラ等は、使う気にも
なれない事であろう。
だが、例えばLo-Fiレンズを用いて、写真に、ある種の
映像表現を求めるのであれば、高画質である必要性は
無いどころか、むしろ低画質である事を望む場合すら
出てくる。
そんな場合に「エフェクト」(デジタルフィルター
等、各社で呼び方は異なる)機能により、多彩な
表現機能を求める事は、もう、今の時代では常識と
なっている。
例えば、本格派ユーザー層向けのカメラ、具体的には
RICOH GRシリーズとか、OLYMPUS OM-D E-M1
系列の機体であっても、「銀残し」(ブリーチ・
バイパス)等の特殊効果(エフェクト)が入っている。
これは、写真での特殊な現像技法ではあるが、多数の
映画(例:マトリックス、1999年)等でも映像表現
として使われた事もある、普遍的なものだ。
ブリーチバイパスの話に限らず、様々な映像表現の
必要性は、古くは絵画の世界で、そして近代では
デジタル化された時代以降での、多くの映画や
TV CM、NET配信、その他、の映像作品の中では、
もう、切っても切れないものとなっている。
写真の世界でも、2010年代頃からは、ミラーレス機
を始め、(デジタル)一眼レフの多くにもエフェクト
機能が搭載されている。
だが、一部のデジタル一眼レフ高級機にはエフェクト
が搭載されていない、これは何故か?
その理由は単純であり、そういう機体を買う消費者
層(ユーザー層)では、エフェクトを必要としない
という意識が大半であるからだ。
現代において、高級機の主力ユーザー層は、決して
職業写真家層等ではなく、「実はビギナー層である」
事は、様々な記事で説明してきた通りである。
その事は様々な場所でカメラを構えている人達を見て、
そのカメラやレンズの機種名(や、発売年、価格等)
と、腕前(カメラやレンズの持ち方、構え方、狙って
いる被写体、画角(構図)等)が外から見分けれる人で
あれば、気づく事である。つまり「腕前と機材価格が
反比例している」事実があるのだが、今回は、そこは
論点では無い。
で、そうした、ビギナー層から中級層あたりまでの
アマチュアカメラマンでの、写真を撮る意識の上で、
「エフェクトの使用は、王道では無い」がある。
それは何故か? これも単純な話であり、1970年代
位での高度成長期+銀塩写真の一般層への発展期に
おいて、高画質(Hi-Fi)な写真を撮る事は、その
技能的にも経済的(高級カメラや高級レンズを用いる)
にも、ステータス(=自慢できる)の象徴であった
からであり、その時代からの意識が、写真界全般
(=その99%以上が、趣味で撮るアマチュア層だ)
に定着してしまっていて、その考えが、当時からの
同一の人物(=現代のシニア層)、または、そこから
周囲にも影響を与えて引き継がれてしまっているから
である。
そうした層では、綺麗(高画質)な写真を撮る為に、
より高価で高性能なカメラやレンズを買う。
手ブレ補正や超音波モーターが入っていないと、
「手ブレやピンボケは下手な証拠」という概念で
周囲からも馬鹿にされるから、それが怖い為に、
さらに高性能な機材を欲しがる一方だ。
結果的に近年では高額な新鋭機材を買うのは、見事な
までに、ビギナー層ばかりになってしまっている。
高い技能(スキル)を持つ上級層等は、もはやそんな
高額機材には目を向けない、そんなコスパの悪い新鋭
機材を使わずとも、どうとでも撮れるからだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06442788.jpg]()
また、アマチュア層は、綺麗な被写体や珍しい被写体
ばかりを追い求め、そうした場所やイベント等に
ビギナー層が群がる。
世間一般では、「そういう人達がカメラマンの典型だ」
という、誤まった「報道」等も行うから、ますます、
その他の層も、「撮影スポット」にまで、時間や金を
かけて出かけ、醜い「場所取り争い」をしてまで、
他人よりも、少しでも綺麗な写真を撮りたがる。
あるいは、そういう撮影スポットにおいて、様々な
マナー・モラル知らず、そして近年では、コロナ禍に
おける密を発生させる等により、いくつもの社会的な
問題を引き起こしている。
まあ、こういう方向性だけが「写真」では無い事は
少し考えれば、誰にでもわかるだろう。
でも、実際の行動は何も変わる事は無い。そもそも
その大半が日曜カメラマンなのだから、何かを変える
必要性も無く、休日に、そういう行動をする事自体が、
平日の日常ストレスからの回避手段であり、そこでは
非日常が得られさえすれば、写真における概念とか、
ポリシーや社会的なマナーやモラル等は、残念ながら、
どうでも良い話となってしまう訳だ。
結局、非日常(ハレの日、またはそれに類するもの)
や、「映え」(ばえ)ばかりを追い求め、そのまま、
何も疑問に思わず、いつまでも同じカメラライフを
続けてしまう・・
これは、別にシニア層だけの問題点では無い。
撮影者の手柄などは何もない「SNS映え」写真だけを
追い求める若年層であっても、まったく同様の課題を
持つのではあるまいか? まあつまり、それらは全て
何もわかっていない「超ビギナー層」でしか無い訳だ。
----
さて、3台目のオールド・ミラーレス機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06442744.jpg]()
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
(2012年発売、発売時実勢価格約13万円)
(中古購入価格 35,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第8回
レンズは、RISING PINHOLE WIDE V
(2012年頃発売)を使用する。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06443604.jpg]()
本機NEX-7は、当時のSONYにおける、ミラーレス機
市場でのテストマーケティングの機体だ、と個人的
には分析している。
SONYは2010年~2012年にかけ、各種のミラーレス
機毎に様々な異なるコンセプトを与え、ユーザー層
の反応を探っていた節がある。旧来の記事では、
「市場戦略に迷いが見られた」と分析した事も
あったが、その後の時代のSONYの市場戦略と照らし
合わせると、その真意が明らかになってきた次第だ。
その中でも、本機NEX-7は最右翼の本格派カメラだ、
上級機を欲しがるユーザー層のニーズやスキルを
探っていたに違い無い。
本機発売の後、SONYは中級層にターゲットを定め、
NEXシリーズを辞めて、2013年からはブランドを
「α」に統合し、さらには段階的ロードマップ戦略
(Ⅱ型機やⅢ型機で、所定の付加価値(→手ブレ
補正や高速連写等)を追加して大幅値上げする戦略)
を実施し、Ⅲ型機やα9の登場あたりで、「α」が
プロユースにも使える、という宣伝戦略を行った。
非常に良く練られた、お手本のような市場戦略では
あるが、どうもユーザー(消費者)側が乗せられて
(振り回されて)しまっているようにも感じられる。
(いいように新鋭高額機種を買わさてしまう様相が
見られた為、私のαフルサイズ所有機は、最初期の
α7とα7Sのみで、その後の機体は購入していない)
2010年代に、カメラ市場が縮退していく中で、
「αの1人勝ち」という傾向が年々強くなる度に、
天邪鬼な私は、α新型機への興味が、どんどんと
薄れていくのを感じていた。
本機NEX-7を好むのも、そんな心理が裏腹にある
からかも知れない。市場でNEX-7を高く評価する
事例は殆ど無いが、本ブログでは、この機体に
SONY機として唯一搭載された「動的操作系」を
高く評価しているし、ミラーレス・クラッシックス
シリーズ記事では、本機NEX-7は、所有機の中でも
1、2を争う高得点の評価となっていた。
でも、それは少々過剰評価気味であるかも知れない。
市場全般から考えれば、「操作系」について
意識または配慮、評価する事は、まず有り得ない。
ビギナー層が主力となった、現代の高級機ユーザー
では、カメラをフルオートのままで使い、少しでも
AF性能、手ブレ補正性能、連写性能が高い方が
”良い写真を撮る事ができる”という大きな誤解を
持っているので・・
「カメラの持つ、全機能・パフォーマンスを
最大限に引き出して撮る事が望ましい」
といった機材使用概念を持っているユーザーなど、
恐らくは非常に低い割合か、または皆無に等しいと
思われるからだ。
その証拠として、本機NEX-7に関するレビュー記事を
かたっぱしからネットで検索して読んでみれば
すぐにわかると思うが、動的操作系を使いこなして
いる実例が、全くと言っていい程に見当たらない。
だから、せっかくの革新的な操作系・・ それ故に、
ミノルタ時代から続く、エポックメイキングな機体
に与えられる「7番機」の称号を与えられながらも、
本機NEX-7は、客観的に判断すれば営業的に失敗作で
あろう。いや、逆に「成功例だ」とも見なす事も可能で
あり、つまり「ここまで高度なUI設計をしても、現代の
ユーザー層では誰もついて来れない事が明確にわかった」
という事(マーケット分析)である。
だからまあ、次機種α7系では、高度な動的操作系を
潔く廃し、安易な静的操作系にダウングレードした
訳であり、結果的にそれは、α7シリーズのヒットに
繋がった訳である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06443603.jpg]()
ある意味、NEX-7は「非運のカメラ」なのかも知れない。
実験台(テストマーケティング)にされた事は、まあ
市場戦略上では良いとして、結局、誰ひとりとして、
本機の動的操作系を使いこなすユーザーは現れなかった
という残念な事実である。
「像面位相差AFが無い」(AF性能が低い)とかいうのは、
この時代では、まだその技術が生まれていないので、
やむを得ない話だ。私は、そんな事は承知の上で、
本機は、ずっとオールドレンズ母艦(勿論、MFで使う)
として、長期に渡り、活躍しつづけている。
要は、どんなカメラであったとしても、それにぴったり
とハマる用途がある訳で、それを見つけ、その用法を
実践する事が、マニア道として最も重要な事である。
「α7Ⅲを買ったから、古いNEX-7なんてもういらないよ」
などという話では決して無いのだが、そこに気づく
ユーザー層は、残念ながら、まず居ない。
----
さて、4台目のオールド・ミラーレス機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06443680.jpg]()
カメラは、PANASONIC DMC-G5 (μ4/3機)
(2012年発売、発売時実勢価格約7万円)
(中古購入価格 16,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第7回
レンズは、Voigtlander NOKTON 42.5mm/f0.95
(変母音省略) (2013年発売)を使用する。
地味な機体である、カタログスペック上だけでは
特筆すべき特徴は何も持たない。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06443614.jpg]()
初期のPANASONICのミラーレス機ラインナップは
SONYと同様のテストマーケティング的な状況も
あったとは思うが、SONYよりも、もう少し明確
かつ体系的に行われていた。
それには、以下のラインナップが存在する(した)
G :オーソドックスな静止画撮影向け
GF:エントリー層向け、ファッショナブルな機体
GM:超小型機
GX:シニア層やマニア層向け上級機
GH:動画撮影主体の高級機
各々のシリーズが全て生き残っている訳でも無く
事実上終焉、あるいは機種展開の戦略を大きく
変更したものもある。
最もオーソドックスな、静止画向けGシリーズの展開に
関しては、G5、G6あたりで少しトーンダウンした
様相も見られ、「G6までで終わりか?」と個人的には
思っていたが、少し時間が空いてG7、G8と発売が継続。
しかし、高付加価値化戦略により、次々に値上げされ、
DC-G9(2018年)では、発売時実勢価格が約21万円と、
初代DMC-G1(2008年)や本機DMC-G5(2012年)の
約3倍の価格にまで高騰してしまった。
上記、「トーンダウンした」と書いた理由であるが、
本機DMC-G5においては、旧機種G3(2011年、未所有)
から、スペック的には大きく変更された部分は無く、
消費者層から見て、購買欲をそそる要素が少ないの
ではなかろうか? という点が理由だ。
ただし、G5/G6(のみ)に共通して存在する重要
な機能として「ファンクションレバー」がある。
これにデジタルズーム機能を割り振る事が出来、
任意のレンズ(マウントアダプター使用時でも)
において、これは有効だ。(ただし記録画素数を
低めて用いる、いわゆるスマートズーム処理だ)
この機能を、例えばMFの望遠(光学)ズームと
組み合わせる事で、無類の画角汎用性と操作系が
実現できる。さらにデジタルテレコン機能を併用
する事で、驚異的な画角汎用性が得られる。
(注:この用法に気づくユーザー層は稀であろう。
本機のレビュー等でも、そのような記述は見られない)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06464056.jpg]()
実例だが、例えば、オールドのMF望遠ズームで、
70-210mm/F4という平凡なスペックのレンズを使った
場合、140-3360mm/F4という超絶的な画角範囲が、
ごく簡単なボタン操作を併用するだけで得られ
ボタン操作無しで、ファンクションレバーと
光学ズームだけの使用でも、140-840mm/F4という
実用上十分すぎる(超)望遠画角範囲が得られる。
(注:記録画素数は400万画素迄に制限される)
光学ズームとデジタルズームの両者を組み合わせる
事で、被写界深度やボケ質破綻を回避した状態を
固定しながら画角を変化させたり、パースペクティブ
(遠近感)を変えないズーム操作等が自由自在だ。
この超快適でテクニカルな要素は他機では類を見ず
G5に、さらにピーキング機能が搭載されたDMC-G6
(2013年、後日紹介)は、私が言う所の「望遠母艦」
として、長期に渡り趣味的撮影に使用している。
特に、上記のような、オールドMF望遠ズームで
開放F値固定型ワンハンドズームをG5やG6で使う
際には、物凄く快適であり、おまけにそうした
古いMF望遠ズームは中古市場で500円~3000円と、
二束三文で売られている。そして、それら全てが
性能が低い訳では無く、CANON New FD70-210/4
等では、現代にも通用する描写力を持ち、一度
その組み合わせ(特にDMC-G6が良いであろう)を
体験すれば、そのテクニカル的なエンジョイ度は
特筆すべき高レベルである事を実感できると思う。
ただし、本機G5の場合は、ピーキング機能が無く、
汎用の「望遠母艦」の用途にはしていない。
むしろ、今回使用レンズ「Voigtlander NOKTON
42.5mm/f0.95」の、ほぼ専用母艦としての利用だ。
その理由は、NOKTON42.5/0.95は、超大口径で
あり、ピント合わせが困難な事と作画が難しい事
での難関レンズであり(レンズマニアックス第12回
「使いこなしが困難なレンズ特集」でワースト第2位)
そのレンズを使う場合の母艦との相性を色々と考察した
結果での「弱点相殺型システム」な訳だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06464079.jpg]()
具体的なポイントとしては、本機DMC-G5までの時代
のEVFは、144万ドットのカラー液晶を使用していて
これは輪郭線が強い映像を出すので、ピントの山が
見易い。次機種DMC-G6ではEVFは144万ドット有機
ELとなり、これは明瞭な映像なのだが、精密なピント
合わせには、やや向いていない。しかし、G6には
優秀なピーキング機能が搭載されていて、一般レンズ
ではG6の方が優位なのだが、NOKTONのような特殊な
レンズでは、さすがのG6のピーキングでも、常に
精度が高い状態が得られるとは言えない訳だ。
(→超大口径化と、大きい収差の為に、ピーキングの
画像処理で必要な十分な輝度差分値が得られない)
それと、Gシリーズにおいては、本機DMC-G5から、
1/4000秒までに限定ながら電子シャッター機能が
搭載された。これは完全無音撮影が出来る長所が
あるのだが、動体歪み(ローリングシャッター歪み)
が出るのと、ディスプレイやプロジェクター映像での
走査線の縞が写る、等の被写体の制限事項がある。
まあでも、長所短所をよく意識して使うならば
本機DMC-G5は、まだまだ十分に現役機である。
特に「ノクトン母艦」として、当面の間は使用を
続ける事であろう。
ちなみにNOKTON42.5/0.95を本機に装着した場合、
前述のデジタル拡大機能群をフルに活用すれば、
単純なスペック上では、85-680mm/F0.95 という
「夢の超大口径望遠ズーム」として使用できる。
おまけに最短撮影距離は、この焦点距離全域で
23cmで使えるから、フィールド(屋外)撮影に
おいて、等倍以上のマクロ撮影から遠方の野鳥まで
なんでもかんでも、欲張りに被写体を捉える事が
出来、主に、その目的で本システムを活用している。
まあ結局、カメラ側の仕様(性能)だけで、それを
評価するのでは無く、レンズを含めたシステム
としての特徴や、それを、どのような被写体や用途
に用いるか?で、総合的な評価が決まる次第だ。
そして、古いカメラや性能の劣ったカメラであっても
それに適した使い方がある訳であり、最新の機種に
次々と買い換えて行く事が、必ずしも適切な措置だ
とは言い切れない。
----
では、今回ラストのオールド・ミラーレス機。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06465015.jpg]()
カメラは、PENTAX Q7 (1/1.7型機)
(2013年発売、発売時実勢価格約4万円)
(中古購入価格 10,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第11回
レンズは、PENTAX 07 MOUNT SHIELD LENS
11.5mm/f9 (2013年発売)を使用する。
本機の出自に関しては、まず上記のPENTAX Qの
項目を参照していただきたいが、QおよびQ10の
撮像センサーサイズは、1/2.3型と、2000年代の
普及コンパクト(デジタル)機並みに小さかった
事が、本機Q7からは、1/1.7型と、心持ち大型化。
これは2000年代の高級コンパクト(デジタル)機
と同等のサイズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06465075.jpg]()
本機も、「トイレンズ母艦」としての利用に適し、
今回の使用レンズは、「国産レンズの中で史上最も
Lo-Fiである」と思われる、PENTAX O7レンズを
装着している。
PENTAXのQシステム用ユニークレンズ(トイレンズ)
に関しては、特殊レンズ第16回記事等、多数の記事
に詳しいので、その詳細については割愛する。
ポイントとしては、「PENTAX Q7(やQシステム)を、
Lo-Fi母艦として使う事は有益である」という点だ。
PENTAX Qシリーズが展開されていた期間(2011年~
2014年頃)での、ユーザー層のQシステムの評価
等を見ていると、どうも、「用途開発」が進んで
いなかったように思える。
つまり、Qシリーズの一般的なユーザー用途として、
「超小型である(だから、格好良い/目立つ)」
「マウントアダプターで何でも望遠レンズになる」
程度の長所しか、皆、想定できていなかったのでは
なかろうか。
対して、一般層評価でのQシリーズの短所としては
「バッテリーの持ちが悪い」
「まともな交換レンズが無い」
「画質が悪い」
(注:この評価に関しては、このシステムの技術的仕様
を理解できて、「そのスペックから見れば優れている」、
と判断するユーザーと、低いスペックをそのまま捉えて
「スペックが低いので画質が悪い」と思い込み評価を
するユーザー層に、見事に二分されてしまっていた)
などがあった。
だが、私から見たQシリーズの長所は
「国内メーカー唯一のトイレンズのラインナップがある」
「エフェクトの仕様、操作系に非常に優れる」
「対応センサーサイズが小さい特殊レンズが使用できる」
があり、これらの長所からは、Qシリーズの適正用途は、
「トイレンズ母艦」「特殊(マシンビジョン、シネ等)
レンズ母艦」で決まりである。
こういう特徴を持つシステムは唯一であるから、
他の弱点は欠点にはなりにくい。
いやむしろ逆に、例えば、小さいセンサーによるDレンジ
性能の狭さはエフェクト利用時に適正であるし、
小型センサーからの記録画素数の低さは、装着する
レンズの想定解像力数値(LP/mm)を計算すると、
適正か、むしろ過剰となるケースすらも多々ある。
まあ、Qシステムが展開されていた時代のPENTAXは、
HOYA時代の「エントリー層向けに特化した市場戦略」が
(RICOH時代になっていたとは言え)顕著であったから、
その購入者層も、エントリー(入門)または初級者層
であった事だろう。
(中上級層では、スペック的に「Qシステムは玩具だ」
と思って、これらを買う事は少なかったと思われる)
よって、Qシリーズでの「用途開発」が出来ない
ユーザー層が中心だったと思われるので、上記のような
「一般的なカメラ評価」しか出来なかったと思われる。
ただし、Qシリーズの展開が終わる頃(2010年代中頃)
になると、PENTAX党等のマニア層でも、この歴史的
価値が高いシステムを入手するようになり、正しく
これらを評価するような様相は見れたように思える。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06444783.jpg]()
まあ、結局、ここでも同じ結論であり、
「古いカメラや性能の劣ったカメラであっても
それに適した使い方がある」という話に帰着する。
その為には、そのカメラ(やレンズを含めたシステム)
の長所短所を徹底的に分析し、かつ、その長所を活かし
短所を目立たなく(または解消する)用法をユーザー
自ら、その用途に応じて考えなければならない。
さもないと、「Qシステムはセンサーサイズが小さいし
画素数も低いから、良く写る筈が無い」などの、狭い
視点での思い込み評価しか出来なくなってしまう訳だ。
そんな評価内容で、「トイレンズ/特殊レンズ母艦」
として、唯一無二の適合性を誇るQシステムの最大の
特徴を見落としてしまう事は、実に勿体無い話だ。
----
では、今回の「オールド・デジカメ(6)」編は、
このあたり迄で、次回記事に続く。
(オールドデジタル機)を、時代とカテゴリーで
分類し、順次紹介していく記事群である。
今回は、「ミラーレス編(2)」とし、本記事での
紹介機は、2011年~2013年の期間に発売された
ミラーレス機を5台とする。
装着レンズは、同時代(2010年代前半頃)に
発売された、トイレンズ/個性的レンズを選択する。
殆どが「Hi-Fi」(高描写力)では無く、「Lo-Fi」
(低描写力)のミラーレス機専用レンズ群である。
これまでの銀塩時代~デジタル初期の時代であれば、
「写真とは、高画質であるべき」という強い思想が
アマチュアユーザー層全般に根強かったのだが、
勿論それは、単なる「思い込み」に過ぎない。
デジタル化しておよそ10年のこの時代から、やっと
「高画質であるばかりが写真の表現では無い」という
当たり前の発想が広まりつつある時代となった。
なお、音楽の世界では、そんな事(Lo-Fi音楽)は、
20年以上前の1990年代頃から、すでに常識だ。
カメラ(映像)の世界は、音楽(音響)の世界より
技術のデジタル化が、およそ15年も遅かったから、
音楽(音響)の歴史を後追いする形となっている。
(例:近年のデジタル・シンセサイザー(楽器)では
「部品の経年劣化をシミュレートし、わざわざ音質
を悪くする機能(可変式)」が付いていたりする。
デジタルカメラで、そんな機能が付くのは、まだまだ
遥かに先の時代であろう。技術的な実現性ではなく、
ユーザー(利用者)側に、そんな要望が無いからだ)
---
では、今回最初のオールド・ミラーレス。
Clik here to view.

(2012年発売、発売時実勢価格約9万円)
(中古購入価格 26,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第6回
レンズは、FUJIFILM FILTER LENS XM-FL S 24mm/f8
(2015年発売)を使用する。
さて、今回の記事では、やや古い時代のミラーレス機
群に、トイレンズや個性的なレンズを装着している。
1つの理由としては、この時代までのミラーレス機は
AF性能に優れないものが多く(=コントラストAF機構
のみの搭載で、像面位相差AF等の新世代の技術は、まだ
搭載されていない) また、MF性能にも優れない機体も
多かった。(EVFが無かったり、EVFがあっても解像度が
低かったり、ピーキング機能が未搭載か、それが
あったとしても精度が低かった。あるいは画面拡大
等の操作系に課題があり、MF操作が行い難い)
結局、この時代のミラーレス機では、AF/MFの性能
つまり「ピント合わせ」に問題があった事となる。
その最たる機種は、今回紹介のFUJIFILM X-E1や
PENTAX Qであるが、他のこの時代(2010年代初頭迄)
のミラーレス機の多くも似たようなものだ。
Clik here to view.

高いピント精度を要求されないレンズ、すなわち
ピンホール、パンフォーカスレンズ(今回使用の
FUJIFILM XM-FL等)、ボディキャップレンズ、
トイレンズ(LOMO、HOLGA、PENTAXユニークレンズ
等)を用いる事により、機体側のピント性能の弱点が
消えて快適に使える事となる(=弱点相殺型システム)
もう1つのトイレンズを使う理由であるが、基本的に
トイレンズはLo-Fi(ローファイ)描写である。
Lo-Fiは、Hi-Fi(ハイファイ)に対峙する、映像や音楽
の世界で使われる用語なのだが。映像で使う場合には、
「低画質」「低精細」という意味だ。
「映像記録」であれば、勿論Hi-Fi(高精細、高画質)
である事は望ましいが、「写真」の場合は、常に
Hi-Fi写真が要求される訳ではない。
写真は映像記録とは異なり、「映像表現」なのだから、
そこでは、必ずしも高画質である事は必須では無い。
まあ、例えば絵画の世界を思い起こしてもらえれば
良いが、印象派や現代アート等では、物凄くリアル
でHi-Fiな絵画ばかりでは無い訳だ。
そこには画家やアーティストが望む、あるいは表現
したい様々な方向性・志向性などが存在し、それは
まさしく「千差万別」である。
また、日本等の写真界においても、1950年代頃迄は、
その殆どが「映像記録」としての写真であったのだが、
その後の時代(日本では1960年代頃)からでは、
「映像表現としての写真」が、急速に発展していく。
(例として、写真家「奈良原一高」1931~2020年
等の作品が挙げられる)
ただ、大半のアマチュア初級中級層は、Hi-Fi写真
(だけ)を撮る事を目指してしまう。これの何が
問題なのか?は、膨大な説明文章が必要となるが、
本ブログでは、折に触れ、何度も説明してきた事で
あるし、上記、「絵画」の例を理解できるのであれば
それが写真の世界(注:映像記録では無い世界)にも
十分に同じ概念が適用できる事は理解が容易であろう。
で、トイレンズを使ってLo-Fi写真を撮る場合は、
カメラ本体側は最新の性能・機能の最高の画質の機体
でなくても何ら問題は無い。いや、むしろ出切るだけ
古い(デジタル)カメラ等を用いて、それが発売
された当時の、未成熟な技術(撮像センサーや、
画像処理エンジン等)でも、個性的な出力画像(例:
オリンパスブルー等の極端に青味が強調された映像)
を用いて、それらを「表現」に変えてしまう事が
出来るかも知れない訳だ。
さて、本記事においては Lo-Fiレンズを使う意義
等を主に紹介していくが、この内容は長くなる為、
話の途中で適宜カメラとレンズを交替する。
Clik here to view.

FUJIFILM社は、ミラーレス機市場への参入は最後発
(2012年)であり、かつ、それ以前の時代では
約30年間の長期に渡り、レンズ交換式カメラを殆ど
開発していなかった(中判機やTX等を除き、国内最終
機種は、FUJICA AXシリーズ(1980年頃)であろう)
この空白期間では、FUJIは銀塩コンパクト機やデジタル
コンパクト機が好調ではあったが、カメラの機種毎に
大きく仕様やコンセプト、使用部品等が異なる状況を
見ると、その殆どがOEM製品であっただろうと推察できる。
この状況で、いきなりレンズ交換型のXシリーズの発売だ。
しかも、本機X-E1は、最初期のミラーレスXシリーズ機
であるから、そのAF/MF性能、および操作系全般、
さらには機能不足等もあって、正直言えば、同時代の
他社機に比べ、大きくビハインド(遅れた)の状態だ。
そこから数年間で、Xシリーズでは多数の改善が行われた。
さすがに、このX-E1の設計水準では、ユーザー層からも
不満が大きかったのであろう。
本機の低性能は購入前から予想が出来ていた為、当初は
Xシリーズ機を買う気は、さらさら無かったのであるが
2014年に、史上2本目のアポダイゼーションレンズが
FUJIから発売されてしまったので、そのレンズを絶対に
入手する必要があると見なし、その母艦として中古相場
が下がっていた本X-E1を、やむなく購入した次第である。
現在において、本機X-E1を指名買いする事は、推奨
出来ない。もう少し後年の、せめて像面位相差AFが
搭載されたX-Tシリーズ機を選択する事が無難であろう。
ただし、ダメダメのカメラであっても、今回の用法の
ように、ピント合わせの負担が少ない(または、パン
フォーカス)トイレンズや特殊レンズを用いれば、
X-E1の短所は概ね解消でき、「絵作り(発色)に優れる」
というFUJIFILM X機共通の長所を活用できる。
(=弱点相殺型システムとなる)
----
では、2台目のオールド・ミラーレス機。
Clik here to view.

(2011年発売、発売時実勢価格約7万円
ただし、単焦点レンズキットの価格)
(中古購入価格 9,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第11回
レンズは、HOLGA LENS 10mm/f8 HL-PQ
(2014年頃発売)を使用する。
Clik here to view.

から銀塩MF一眼レフの製造販売を始め、これを
ロングセラーのヒット商品(例:ASAHI PENTAX
SPシリーズは累計350万台の販売数)とし、さらに
AF一眼レフ、中判(645/67等)、110(ワンテン)
等のカメラ群や、双眼鏡等の光学製品で、好調な
ビジネスを続けていたが・・・
2000年代、デジタル化の変革期において、
これまでの事業構造を再編する為、他社との協業を
模索する。そこからは、すったもんだ、があって、
HOYAとの合併が成立したのが2008年頃であった。
HOYAは徹底的なリストラと、エントリー層向けに
特化した大胆な市場戦略を実施し、この時代の
PENTAXのカメラ事業を黒字化させるのだが、まあ
内部的に色々と、やりにくい点はあった事だろう。
HOYAは2011年頃にPENTAX(カメラ、双眼鏡)を
RICOHに売却譲渡する事を決定。その後の時代では
PENTAXという企業名は消滅し「リコーイメージング
株式会社」として現在に至る。
さて、本機PENTAX Qは、世界最小のレンズ交換型
(ミラーレス)カメラであり、PENTAXがRICOHの
傘下となった直後に発売されたカメラではあるが、
その企画は完全にHOYA時代のものであり、話題性の
ある、エントリー層向けの戦略機である。
エントリー層向けであるから、その市場評価は
「小型である」「アダプターを使うと、どんな
レンズでも望遠となる」「ユニーク(トイ)
レンズがラインナップされている」あたりが好意的
な評価であり、さらに翌年のQ10からは、オーダー
カラー制導入や、人気アニメとのコラボ商品等で、
エントリー層への話題性も加わった。
その逆に、ネガティブな意見としては・・
「センサーサイズが小さすぎる」「交換レンズの
選択肢が少ない」あたりがあっただろう。
私の場合のQシリーズ機の用途は、それが持つ優れた
「エフェクト操作系」を活かした、トイレンズ母艦
および、センサーサイズが小さい事からの
「マシンビジョン用(FA用)レンズ母艦」としての
役割が、ほぼ100%となっている。
Clik here to view.

関係性がある「エフェクト」の話に戻る。
カメラ自体の設計年度が古く、使用部品等の技術的
な未成熟により、カメラの性能が劣っていたとする。
普通、現代のユーザー層においては、そういう
オールド(デジタル)カメラ等は、使う気にも
なれない事であろう。
だが、例えばLo-Fiレンズを用いて、写真に、ある種の
映像表現を求めるのであれば、高画質である必要性は
無いどころか、むしろ低画質である事を望む場合すら
出てくる。
そんな場合に「エフェクト」(デジタルフィルター
等、各社で呼び方は異なる)機能により、多彩な
表現機能を求める事は、もう、今の時代では常識と
なっている。
例えば、本格派ユーザー層向けのカメラ、具体的には
RICOH GRシリーズとか、OLYMPUS OM-D E-M1
系列の機体であっても、「銀残し」(ブリーチ・
バイパス)等の特殊効果(エフェクト)が入っている。
これは、写真での特殊な現像技法ではあるが、多数の
映画(例:マトリックス、1999年)等でも映像表現
として使われた事もある、普遍的なものだ。
ブリーチバイパスの話に限らず、様々な映像表現の
必要性は、古くは絵画の世界で、そして近代では
デジタル化された時代以降での、多くの映画や
TV CM、NET配信、その他、の映像作品の中では、
もう、切っても切れないものとなっている。
写真の世界でも、2010年代頃からは、ミラーレス機
を始め、(デジタル)一眼レフの多くにもエフェクト
機能が搭載されている。
だが、一部のデジタル一眼レフ高級機にはエフェクト
が搭載されていない、これは何故か?
その理由は単純であり、そういう機体を買う消費者
層(ユーザー層)では、エフェクトを必要としない
という意識が大半であるからだ。
現代において、高級機の主力ユーザー層は、決して
職業写真家層等ではなく、「実はビギナー層である」
事は、様々な記事で説明してきた通りである。
その事は様々な場所でカメラを構えている人達を見て、
そのカメラやレンズの機種名(や、発売年、価格等)
と、腕前(カメラやレンズの持ち方、構え方、狙って
いる被写体、画角(構図)等)が外から見分けれる人で
あれば、気づく事である。つまり「腕前と機材価格が
反比例している」事実があるのだが、今回は、そこは
論点では無い。
で、そうした、ビギナー層から中級層あたりまでの
アマチュアカメラマンでの、写真を撮る意識の上で、
「エフェクトの使用は、王道では無い」がある。
それは何故か? これも単純な話であり、1970年代
位での高度成長期+銀塩写真の一般層への発展期に
おいて、高画質(Hi-Fi)な写真を撮る事は、その
技能的にも経済的(高級カメラや高級レンズを用いる)
にも、ステータス(=自慢できる)の象徴であった
からであり、その時代からの意識が、写真界全般
(=その99%以上が、趣味で撮るアマチュア層だ)
に定着してしまっていて、その考えが、当時からの
同一の人物(=現代のシニア層)、または、そこから
周囲にも影響を与えて引き継がれてしまっているから
である。
そうした層では、綺麗(高画質)な写真を撮る為に、
より高価で高性能なカメラやレンズを買う。
手ブレ補正や超音波モーターが入っていないと、
「手ブレやピンボケは下手な証拠」という概念で
周囲からも馬鹿にされるから、それが怖い為に、
さらに高性能な機材を欲しがる一方だ。
結果的に近年では高額な新鋭機材を買うのは、見事な
までに、ビギナー層ばかりになってしまっている。
高い技能(スキル)を持つ上級層等は、もはやそんな
高額機材には目を向けない、そんなコスパの悪い新鋭
機材を使わずとも、どうとでも撮れるからだ。
Clik here to view.

ばかりを追い求め、そうした場所やイベント等に
ビギナー層が群がる。
世間一般では、「そういう人達がカメラマンの典型だ」
という、誤まった「報道」等も行うから、ますます、
その他の層も、「撮影スポット」にまで、時間や金を
かけて出かけ、醜い「場所取り争い」をしてまで、
他人よりも、少しでも綺麗な写真を撮りたがる。
あるいは、そういう撮影スポットにおいて、様々な
マナー・モラル知らず、そして近年では、コロナ禍に
おける密を発生させる等により、いくつもの社会的な
問題を引き起こしている。
まあ、こういう方向性だけが「写真」では無い事は
少し考えれば、誰にでもわかるだろう。
でも、実際の行動は何も変わる事は無い。そもそも
その大半が日曜カメラマンなのだから、何かを変える
必要性も無く、休日に、そういう行動をする事自体が、
平日の日常ストレスからの回避手段であり、そこでは
非日常が得られさえすれば、写真における概念とか、
ポリシーや社会的なマナーやモラル等は、残念ながら、
どうでも良い話となってしまう訳だ。
結局、非日常(ハレの日、またはそれに類するもの)
や、「映え」(ばえ)ばかりを追い求め、そのまま、
何も疑問に思わず、いつまでも同じカメラライフを
続けてしまう・・
これは、別にシニア層だけの問題点では無い。
撮影者の手柄などは何もない「SNS映え」写真だけを
追い求める若年層であっても、まったく同様の課題を
持つのではあるまいか? まあつまり、それらは全て
何もわかっていない「超ビギナー層」でしか無い訳だ。
----
さて、3台目のオールド・ミラーレス機。
Clik here to view.

(2012年発売、発売時実勢価格約13万円)
(中古購入価格 35,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第8回
レンズは、RISING PINHOLE WIDE V
(2012年頃発売)を使用する。
Clik here to view.
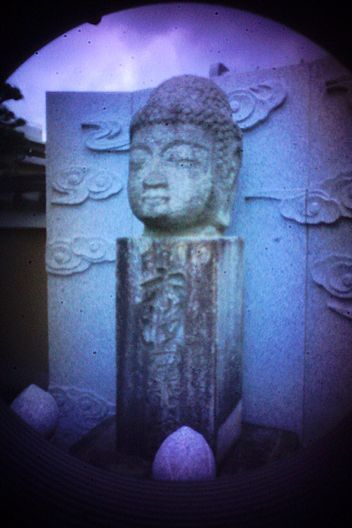
市場でのテストマーケティングの機体だ、と個人的
には分析している。
SONYは2010年~2012年にかけ、各種のミラーレス
機毎に様々な異なるコンセプトを与え、ユーザー層
の反応を探っていた節がある。旧来の記事では、
「市場戦略に迷いが見られた」と分析した事も
あったが、その後の時代のSONYの市場戦略と照らし
合わせると、その真意が明らかになってきた次第だ。
その中でも、本機NEX-7は最右翼の本格派カメラだ、
上級機を欲しがるユーザー層のニーズやスキルを
探っていたに違い無い。
本機発売の後、SONYは中級層にターゲットを定め、
NEXシリーズを辞めて、2013年からはブランドを
「α」に統合し、さらには段階的ロードマップ戦略
(Ⅱ型機やⅢ型機で、所定の付加価値(→手ブレ
補正や高速連写等)を追加して大幅値上げする戦略)
を実施し、Ⅲ型機やα9の登場あたりで、「α」が
プロユースにも使える、という宣伝戦略を行った。
非常に良く練られた、お手本のような市場戦略では
あるが、どうもユーザー(消費者)側が乗せられて
(振り回されて)しまっているようにも感じられる。
(いいように新鋭高額機種を買わさてしまう様相が
見られた為、私のαフルサイズ所有機は、最初期の
α7とα7Sのみで、その後の機体は購入していない)
2010年代に、カメラ市場が縮退していく中で、
「αの1人勝ち」という傾向が年々強くなる度に、
天邪鬼な私は、α新型機への興味が、どんどんと
薄れていくのを感じていた。
本機NEX-7を好むのも、そんな心理が裏腹にある
からかも知れない。市場でNEX-7を高く評価する
事例は殆ど無いが、本ブログでは、この機体に
SONY機として唯一搭載された「動的操作系」を
高く評価しているし、ミラーレス・クラッシックス
シリーズ記事では、本機NEX-7は、所有機の中でも
1、2を争う高得点の評価となっていた。
でも、それは少々過剰評価気味であるかも知れない。
市場全般から考えれば、「操作系」について
意識または配慮、評価する事は、まず有り得ない。
ビギナー層が主力となった、現代の高級機ユーザー
では、カメラをフルオートのままで使い、少しでも
AF性能、手ブレ補正性能、連写性能が高い方が
”良い写真を撮る事ができる”という大きな誤解を
持っているので・・
「カメラの持つ、全機能・パフォーマンスを
最大限に引き出して撮る事が望ましい」
といった機材使用概念を持っているユーザーなど、
恐らくは非常に低い割合か、または皆無に等しいと
思われるからだ。
その証拠として、本機NEX-7に関するレビュー記事を
かたっぱしからネットで検索して読んでみれば
すぐにわかると思うが、動的操作系を使いこなして
いる実例が、全くと言っていい程に見当たらない。
だから、せっかくの革新的な操作系・・ それ故に、
ミノルタ時代から続く、エポックメイキングな機体
に与えられる「7番機」の称号を与えられながらも、
本機NEX-7は、客観的に判断すれば営業的に失敗作で
あろう。いや、逆に「成功例だ」とも見なす事も可能で
あり、つまり「ここまで高度なUI設計をしても、現代の
ユーザー層では誰もついて来れない事が明確にわかった」
という事(マーケット分析)である。
だからまあ、次機種α7系では、高度な動的操作系を
潔く廃し、安易な静的操作系にダウングレードした
訳であり、結果的にそれは、α7シリーズのヒットに
繋がった訳である。
Clik here to view.

実験台(テストマーケティング)にされた事は、まあ
市場戦略上では良いとして、結局、誰ひとりとして、
本機の動的操作系を使いこなすユーザーは現れなかった
という残念な事実である。
「像面位相差AFが無い」(AF性能が低い)とかいうのは、
この時代では、まだその技術が生まれていないので、
やむを得ない話だ。私は、そんな事は承知の上で、
本機は、ずっとオールドレンズ母艦(勿論、MFで使う)
として、長期に渡り、活躍しつづけている。
要は、どんなカメラであったとしても、それにぴったり
とハマる用途がある訳で、それを見つけ、その用法を
実践する事が、マニア道として最も重要な事である。
「α7Ⅲを買ったから、古いNEX-7なんてもういらないよ」
などという話では決して無いのだが、そこに気づく
ユーザー層は、残念ながら、まず居ない。
----
さて、4台目のオールド・ミラーレス機。
Clik here to view.

(2012年発売、発売時実勢価格約7万円)
(中古購入価格 16,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第7回
レンズは、Voigtlander NOKTON 42.5mm/f0.95
(変母音省略) (2013年発売)を使用する。
地味な機体である、カタログスペック上だけでは
特筆すべき特徴は何も持たない。
Clik here to view.

SONYと同様のテストマーケティング的な状況も
あったとは思うが、SONYよりも、もう少し明確
かつ体系的に行われていた。
それには、以下のラインナップが存在する(した)
G :オーソドックスな静止画撮影向け
GF:エントリー層向け、ファッショナブルな機体
GM:超小型機
GX:シニア層やマニア層向け上級機
GH:動画撮影主体の高級機
各々のシリーズが全て生き残っている訳でも無く
事実上終焉、あるいは機種展開の戦略を大きく
変更したものもある。
最もオーソドックスな、静止画向けGシリーズの展開に
関しては、G5、G6あたりで少しトーンダウンした
様相も見られ、「G6までで終わりか?」と個人的には
思っていたが、少し時間が空いてG7、G8と発売が継続。
しかし、高付加価値化戦略により、次々に値上げされ、
DC-G9(2018年)では、発売時実勢価格が約21万円と、
初代DMC-G1(2008年)や本機DMC-G5(2012年)の
約3倍の価格にまで高騰してしまった。
上記、「トーンダウンした」と書いた理由であるが、
本機DMC-G5においては、旧機種G3(2011年、未所有)
から、スペック的には大きく変更された部分は無く、
消費者層から見て、購買欲をそそる要素が少ないの
ではなかろうか? という点が理由だ。
ただし、G5/G6(のみ)に共通して存在する重要
な機能として「ファンクションレバー」がある。
これにデジタルズーム機能を割り振る事が出来、
任意のレンズ(マウントアダプター使用時でも)
において、これは有効だ。(ただし記録画素数を
低めて用いる、いわゆるスマートズーム処理だ)
この機能を、例えばMFの望遠(光学)ズームと
組み合わせる事で、無類の画角汎用性と操作系が
実現できる。さらにデジタルテレコン機能を併用
する事で、驚異的な画角汎用性が得られる。
(注:この用法に気づくユーザー層は稀であろう。
本機のレビュー等でも、そのような記述は見られない)
Clik here to view.

70-210mm/F4という平凡なスペックのレンズを使った
場合、140-3360mm/F4という超絶的な画角範囲が、
ごく簡単なボタン操作を併用するだけで得られ
ボタン操作無しで、ファンクションレバーと
光学ズームだけの使用でも、140-840mm/F4という
実用上十分すぎる(超)望遠画角範囲が得られる。
(注:記録画素数は400万画素迄に制限される)
光学ズームとデジタルズームの両者を組み合わせる
事で、被写界深度やボケ質破綻を回避した状態を
固定しながら画角を変化させたり、パースペクティブ
(遠近感)を変えないズーム操作等が自由自在だ。
この超快適でテクニカルな要素は他機では類を見ず
G5に、さらにピーキング機能が搭載されたDMC-G6
(2013年、後日紹介)は、私が言う所の「望遠母艦」
として、長期に渡り趣味的撮影に使用している。
特に、上記のような、オールドMF望遠ズームで
開放F値固定型ワンハンドズームをG5やG6で使う
際には、物凄く快適であり、おまけにそうした
古いMF望遠ズームは中古市場で500円~3000円と、
二束三文で売られている。そして、それら全てが
性能が低い訳では無く、CANON New FD70-210/4
等では、現代にも通用する描写力を持ち、一度
その組み合わせ(特にDMC-G6が良いであろう)を
体験すれば、そのテクニカル的なエンジョイ度は
特筆すべき高レベルである事を実感できると思う。
ただし、本機G5の場合は、ピーキング機能が無く、
汎用の「望遠母艦」の用途にはしていない。
むしろ、今回使用レンズ「Voigtlander NOKTON
42.5mm/f0.95」の、ほぼ専用母艦としての利用だ。
その理由は、NOKTON42.5/0.95は、超大口径で
あり、ピント合わせが困難な事と作画が難しい事
での難関レンズであり(レンズマニアックス第12回
「使いこなしが困難なレンズ特集」でワースト第2位)
そのレンズを使う場合の母艦との相性を色々と考察した
結果での「弱点相殺型システム」な訳だ。
Clik here to view.

のEVFは、144万ドットのカラー液晶を使用していて
これは輪郭線が強い映像を出すので、ピントの山が
見易い。次機種DMC-G6ではEVFは144万ドット有機
ELとなり、これは明瞭な映像なのだが、精密なピント
合わせには、やや向いていない。しかし、G6には
優秀なピーキング機能が搭載されていて、一般レンズ
ではG6の方が優位なのだが、NOKTONのような特殊な
レンズでは、さすがのG6のピーキングでも、常に
精度が高い状態が得られるとは言えない訳だ。
(→超大口径化と、大きい収差の為に、ピーキングの
画像処理で必要な十分な輝度差分値が得られない)
それと、Gシリーズにおいては、本機DMC-G5から、
1/4000秒までに限定ながら電子シャッター機能が
搭載された。これは完全無音撮影が出来る長所が
あるのだが、動体歪み(ローリングシャッター歪み)
が出るのと、ディスプレイやプロジェクター映像での
走査線の縞が写る、等の被写体の制限事項がある。
まあでも、長所短所をよく意識して使うならば
本機DMC-G5は、まだまだ十分に現役機である。
特に「ノクトン母艦」として、当面の間は使用を
続ける事であろう。
ちなみにNOKTON42.5/0.95を本機に装着した場合、
前述のデジタル拡大機能群をフルに活用すれば、
単純なスペック上では、85-680mm/F0.95 という
「夢の超大口径望遠ズーム」として使用できる。
おまけに最短撮影距離は、この焦点距離全域で
23cmで使えるから、フィールド(屋外)撮影に
おいて、等倍以上のマクロ撮影から遠方の野鳥まで
なんでもかんでも、欲張りに被写体を捉える事が
出来、主に、その目的で本システムを活用している。
まあ結局、カメラ側の仕様(性能)だけで、それを
評価するのでは無く、レンズを含めたシステム
としての特徴や、それを、どのような被写体や用途
に用いるか?で、総合的な評価が決まる次第だ。
そして、古いカメラや性能の劣ったカメラであっても
それに適した使い方がある訳であり、最新の機種に
次々と買い換えて行く事が、必ずしも適切な措置だ
とは言い切れない。
----
では、今回ラストのオールド・ミラーレス機。
Clik here to view.

(2013年発売、発売時実勢価格約4万円)
(中古購入価格 10,000円)
紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第11回
レンズは、PENTAX 07 MOUNT SHIELD LENS
11.5mm/f9 (2013年発売)を使用する。
本機の出自に関しては、まず上記のPENTAX Qの
項目を参照していただきたいが、QおよびQ10の
撮像センサーサイズは、1/2.3型と、2000年代の
普及コンパクト(デジタル)機並みに小さかった
事が、本機Q7からは、1/1.7型と、心持ち大型化。
これは2000年代の高級コンパクト(デジタル)機
と同等のサイズである。
Clik here to view.

今回の使用レンズは、「国産レンズの中で史上最も
Lo-Fiである」と思われる、PENTAX O7レンズを
装着している。
PENTAXのQシステム用ユニークレンズ(トイレンズ)
に関しては、特殊レンズ第16回記事等、多数の記事
に詳しいので、その詳細については割愛する。
ポイントとしては、「PENTAX Q7(やQシステム)を、
Lo-Fi母艦として使う事は有益である」という点だ。
PENTAX Qシリーズが展開されていた期間(2011年~
2014年頃)での、ユーザー層のQシステムの評価
等を見ていると、どうも、「用途開発」が進んで
いなかったように思える。
つまり、Qシリーズの一般的なユーザー用途として、
「超小型である(だから、格好良い/目立つ)」
「マウントアダプターで何でも望遠レンズになる」
程度の長所しか、皆、想定できていなかったのでは
なかろうか。
対して、一般層評価でのQシリーズの短所としては
「バッテリーの持ちが悪い」
「まともな交換レンズが無い」
「画質が悪い」
(注:この評価に関しては、このシステムの技術的仕様
を理解できて、「そのスペックから見れば優れている」、
と判断するユーザーと、低いスペックをそのまま捉えて
「スペックが低いので画質が悪い」と思い込み評価を
するユーザー層に、見事に二分されてしまっていた)
などがあった。
だが、私から見たQシリーズの長所は
「国内メーカー唯一のトイレンズのラインナップがある」
「エフェクトの仕様、操作系に非常に優れる」
「対応センサーサイズが小さい特殊レンズが使用できる」
があり、これらの長所からは、Qシリーズの適正用途は、
「トイレンズ母艦」「特殊(マシンビジョン、シネ等)
レンズ母艦」で決まりである。
こういう特徴を持つシステムは唯一であるから、
他の弱点は欠点にはなりにくい。
いやむしろ逆に、例えば、小さいセンサーによるDレンジ
性能の狭さはエフェクト利用時に適正であるし、
小型センサーからの記録画素数の低さは、装着する
レンズの想定解像力数値(LP/mm)を計算すると、
適正か、むしろ過剰となるケースすらも多々ある。
まあ、Qシステムが展開されていた時代のPENTAXは、
HOYA時代の「エントリー層向けに特化した市場戦略」が
(RICOH時代になっていたとは言え)顕著であったから、
その購入者層も、エントリー(入門)または初級者層
であった事だろう。
(中上級層では、スペック的に「Qシステムは玩具だ」
と思って、これらを買う事は少なかったと思われる)
よって、Qシリーズでの「用途開発」が出来ない
ユーザー層が中心だったと思われるので、上記のような
「一般的なカメラ評価」しか出来なかったと思われる。
ただし、Qシリーズの展開が終わる頃(2010年代中頃)
になると、PENTAX党等のマニア層でも、この歴史的
価値が高いシステムを入手するようになり、正しく
これらを評価するような様相は見れたように思える。
Clik here to view.

「古いカメラや性能の劣ったカメラであっても
それに適した使い方がある」という話に帰着する。
その為には、そのカメラ(やレンズを含めたシステム)
の長所短所を徹底的に分析し、かつ、その長所を活かし
短所を目立たなく(または解消する)用法をユーザー
自ら、その用途に応じて考えなければならない。
さもないと、「Qシステムはセンサーサイズが小さいし
画素数も低いから、良く写る筈が無い」などの、狭い
視点での思い込み評価しか出来なくなってしまう訳だ。
そんな評価内容で、「トイレンズ/特殊レンズ母艦」
として、唯一無二の適合性を誇るQシステムの最大の
特徴を見落としてしまう事は、実に勿体無い話だ。
----
では、今回の「オールド・デジカメ(6)」編は、
このあたり迄で、次回記事に続く。