海外製のマニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。
今回は海外製その他(2)編として、雑多な海外メーカー
製の所有レンズ7本を紹介する。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
これらのレンズ群は、本シリーズでのメーカー別
の本編記事には分類できなかった物、あるいは、
当該記事執筆後に追加購入したレンズである。
なお、本シリーズでの紹介を割愛した海外製の
マイナーなレンズまたはトイレンズ等もあるが、
それらは過去記事の、いずれかで紹介済みだ。
本記事が本シリーズの暫定最終回となる。
----
ではまず、今回最初の海外製レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズは、VILTROX PFU RBMH 85mm/f1.8 (VM8518E)
(中古購入価格 15,000円)(以下、VM8518E)
カメラは、SONY α7S (フルサイズ機)
2019年に発売された中国製のフルサイズ対応MF中望遠
レンズ。マウントはミラーレス機用に数機種が
発売されている。姉妹レンズとして同スペックでの
AF版があるが、MF版は、ずっと安価である。
(注:この中古価格の安さは、販売店側の値付け
間違いだったかもしれない)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
近年の中国製レンズのメーカーは、深セン(しんせん)
地区を中心に多数が集結しているようだ。香港と隣接
するこの地区は「経済特区」となっている模様であり、
すなわち産・官・学のコラボレーションが実現されて
いて、技術的な進歩が著しい状態と思われる。
この深センには、恐らくだが、有益なレンズ製造
メーカー(工場)があるのだろう、と推測している。
例えば日本で言えば、往年のコシナとか、小堀製作所や
日東光学等は他社レンズを製造して供給するOEMメーカー
であったし、現代のSIGMAやTAMRONも、一部では著名
メーカー製品のOEM製造は続けているであろう。
そうした有力なOEM製造メーカー(工場)が、中国にも
当然存在すると思われる。
そうであれば、現代は「コンピューター光学設計」が
当たり前となった時代であるから、誰かが新たに
「レンズメーカー」になりたかったら、自宅又は
小さいオフィスを借りて、パソコンを1台置き、
それで自分が作りたい仕様のレンズを自動設計すれば、
後はパソコンから出力される図面をOEMメーカー(工場)
にメールで送れば、新しいレンズが出来上がってしまう。
つまり、光学的知識と、ある程度の初期製造資金が
あれば、「誰でもレンズメーカーになれる」という
凄い時代となっている訳だ。
沢山の中国メーカーが出てくる理由も、わからない
訳でも無い世情である。
そしてそのOEM工場(1つだけなのか?複数あるかは
良くわからない)の製造品質は、2010年代後半から
恐ろしく向上している。
近年の国産レンズは、レンズ市場縮退によるコスト
ダウン措置により、プラスチック成型の鏡筒ばかりと
なっていて、あまり高級感が無いのだが、これら
中国製レンズは、昔の国産レンズのような金属鏡筒で
相当に高級感が高い。
これであれば、国内メーカーからも図面を中国に
送って、そちらで製造した方が品質が向上しそうだ。
まあ、かつての「海外生産」では、中国等での安い
人件費を利点とした「コストダウン」の様相が
大きかったのだが、現代となると、中国の人件費も
相当に高騰してしまっているので、コストダウンでは
無く、「品質の向上の為に中国生産とする」という
ケースすらあり得る、という話だ。
事実、大メーカーでは無いが、日本で設計して、中国
で製造しているケースの製品を知っている。
「レンズの作り」を見れば、それがわかる訳だ。
ただまあ、中国(海外)生産も、現状では日本製
レンズに比べての課題(不足点)がいくつかある。
1)AFレンズの製造が難しい。
これはAFモーターの調達と、各マウントにおける
AFプロトコル(レンズとカメラとの情報のやりとり)
の解析の2つの課題がある。AFプロトコル解析は
SIGMAやTAMRON等でもやっていた訳だから、専門家
がプロトコルアナライザー等の計測器を使えば可能
なのであろう。追々AFレンズは増えて来ると思う。
AFモーターだが・・
DC(直流)モーターは中国等でも調達は可能で、
STM(ステッピングモーター)も、だんだんと
調達が可能となっている模様。
USM(超音波モーター)は、まだそれを搭載して
いる海外製レンズは無い。おそらくこの点だけが
日本メーカーの海外製レンズに対する優位点だ。
なお、いずれもAFモーター自体の調達は困難では
無いだろうが、機構の複雑化や原価上昇による
コストアップと、(少ない)ブランド力における
市場価格の妥協点の問題だけであろう。
2)非球面レンズが作れない
レンズ設計ソフトにおいては、通常のタイプの
レンズに加え、特殊(異常)低分散ガラスや
非球面レンズを使った設計を自動で行う事も出来る。
ただし、通常ガラス→特殊ガラス→非球面 の順に
高価になるので、レンズの想定販売価格によっては
贅沢な素材は使いにくい。
また、非球面レンズは、それを製造するには、
非球面切削機(研磨機)または、非球面用モールド
(金型)が必要となり、これは高価な機器または
製造コストアップを招くので、あまり安価なレンズ
には使いにくい。
ただ、技術的に難しい、という訳では無いので、
資金力やレンズ販売価格の問題だけだ。
既に非球面製造機を調達した中国メーカーもある、
と聞いているので、近いうちに非球面レンズ搭載
の中国製レンズも一般的になるであろう。
(追記:2021年、LAOWAや銘匠光学より非球面レンズ
搭載型レンズ各種の発売が開始されている)
3)手ブレ補正搭載のレンズが作れない
まあ、これはそうなのだろうが・・ とは言え、
様々な撮影条件において、レンズに常に手ブレ
補正が入っていないとならない、という訳では
無いし、ボディ側に手ブレ補正を内蔵している
カメラも多いので、あまり重要な課題では無いとは
思う。この点、むしろ国産レンズがなんでもかんでも
手ブレ補正機能を入れて、それを「付加価値」として
値上げしてしまっている様相には、個人的には賛同
できない。
近年では、むしろ「SIGMA ART LINE」等の手ブレ補正
無しのレンズの方が、硬派なコンセプトで個人的には
好みであり、それらを何本か買った次第だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13473383.jpg]()
さて、余談が長くなったが、本レンズVILTROX85/1.8
は、基本性能や品質的には十分だ。
若干の周辺減光・周辺収差等の課題は、それを嫌う
ならばフルサイズ機では無くAPS-C機で使えば解決だ。
AF版は未所有なので、その速度や精度等は不明だ。
ただ、上記のように、中国製レンズでのその辺の
技術は発展途上である為、オーソドックスなMF版
の方が手堅いであろう。
中級層やマニア層には推奨できるレンズである。
(追記:2020年には、早くも後継のⅡ型レンズ
が発売されている。そちらは未所有であり比較は
出来ないが、当然ながら価格は上昇している)
----
では、次の海外製レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475140.jpg]()
レンズは、(FED/KMZ) INDUSTAR-61 L/D 53mm/f2.8
(中古購入価格 9,000円)
カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)
ロシアンレンズなので、詳しい情報は不明だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475100.jpg]()
恐らくは、旧ソ連時代の国営工場のFEDやKMZで
(1980年代頃まで?)製造されていたレンズで
あろう。
近年において、熊本の商社「GIZMON」が、本レンズ
のデッドストックをロシアから選別輸入し、マニア層
向けに、少数だけ販売したものだ。
私は、それを買いそびれてしまい(すぐ売り切れた)
数年後に出てきた中古を買ったのだが、残念ながら
若干のプレミアム相場で、販売時の新品価格より
少しだけ高額な価格で購入せざるを得なかった。
本レンズには「星型ボケ」が得られる、独特の
絞り形状を持つ他バージョンがあり、マニア層には
著名だが、本レンズはそのバージョンでは無く、
通常の絞り形状である。(改良された、と言うべき
であろう。常に星型ボケでは困る場合もある)
まあ、そういう用途に用いるのであれば、例えば
近代のLomography製(New) Petzvalレンズの数機種に
「ウォーターハウス型」絞り機構が搭載されていて、
付属またはオプション部品として、星型やハート型の
形状の絞りが存在している。
また、国内GIZMON社からも、非常に多数の交換型の
特殊形状の絞り部品を付属した安価なトイレンズ
「GIZMON Bokeh Lens Illumina」が発売されている。
そうしたレンズ群と付属部品を使った方が特殊形状
ボケを出す上で簡便だし、作画の自由度も高い。
(それを出したくないケースでは、絞り部品を
入れ替えてしまえば良い)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475166.jpg]()
で、本レンズであるが、テッサー型構成であるから
そこそこの描写力を持つ理屈なのだが、細かい弱点
(周辺収差、最短撮影距離の長さ、逆光耐性の低さ)
などが色々とある為、使いこなすのは少々難しい。
まあ、比較的近年に販売されていたレンズなので、
中古等の入手性はゼロでは無い。従前の時代に
流通していたロシアン(Jupiter系やMIR系等)は
現代ではセミレア化してしまって、高価な相場に
なっているケースも良くあるので、そういう点では
本レンズは「ロシアンの入門編」として、中級
マニア層等に向けては良いかも知れない。
・・と言うのも、ロシアンレンズの多くは、ちゃんと
使いこなすのが非常に難しい為、ベテランのマニア層
等が良く言う「ロシアンは良く写る」という状態を
初級層等が再現するのは困難だ。だから、あまり最初
から高価な(高価すぎる)ロシアンを買ってしまうと、
使いこなせず、出資が無駄になる危険性が高いので
まずは安価なロシアンで、感触を試して見るのも良い
と思う。
---
では、3本目の海外製レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475233.jpg]()
レンズは、FUJIAN GDS-35 35mm/f1.7
(中古購入価格 2,000円相当)(以下、FUJIAN35/1.7)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1 (μ4/3機)
2010年代後半頃に発売と思われる、CCTV(監視カメラ)
用のMF単焦点レンズ。(注:メーカー(ブランド)名は
他の表記の場合もある)
レンズ上に「TV LENS」の記載があるが、これは
CCTV(Closed-Circuit TeleVison)用、という意味で
あろう。Cマウント品であり、2/3型イメージサークル
に対応との事。
数年前に新品で2000円台で通販で販売されていた
模様だが、すでに販売終了。後に出てきた中古品で、
Cマウントのアダプター付属で3000円で入手した。
レンズ自体の価格は、2000円という事にしておこう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475669.jpg]()
本レンズだが、実用的には使い物にはならない。
構造上、無限遠までピントが来ず、中距離までの
撮影に制限されるし、絞って被写界深度を深めて
使ったとしても、描写力は、お世辞にも褒められた
ものでは無い。あくまでアナログ時代(ハイビジョン
以前の時代)の監視カメラ用の仕様・性能だ。
一応、今回はμ4/3機を母艦とし、2倍テレコン
モードを常時ONとしている、この用法だと、
イメージサークルが2/3型相当となる為、本レンズ
の仕様にマッチするのではあるが・・
これでも、周辺がギリギリとなり、Hi-Fi写真は
撮れない。ならば、1/2.3型のPENTAX Q/Q10で
使えば良いか?と言えば、まあ、そうしたとしても、
やはり画面全域での描写力は大いに不満だ。
いずれの用法でも、換算画角は、140mm~
192mm相当となり、かなりの望遠画角である。
画質的な面から「これはトイレンズだ」と、使用
目的をLo-Fi用途に変えてしまうのが、最も簡便な
考え方なのだが、「望遠画角のトイレンズ」
というのも、あまり無いので、経験則や作画表現
的には、ちょっと厳しいかも知れない。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475617.jpg]()
本レンズは、安価ではあるが、元々が監視カメラ
用なので、実用的な写真用途としては使えず、使う
ならば、あくまで「トイレンズ」として捉えるのが
賢明だ。エフェクト等を適宜追加するのが良いであろう。
----
さて、4本目のシステム。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475668.jpg]()
レンズは、KAMLAN FS 50mm/f1.1 (初期型)
(新品購入価格 23,000円)(以下、FS50/1.1)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
2019年に販売開始された新鋭メーカーの海外製
超大口径MFレンズ。
台湾のメーカー(瑪暢光電有限公司/Sainsonic社)が
設計し、同社工場のある中国の「深セン」地区で
製造されたレンズである。
(なので、純粋な中国製レンズとは言い難い)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13475693.jpg]()
だが、これは、典型的な「失敗レンズ」であろう。
5群5枚構成であるが、いくら異常低分散ガラスを
採用しているからと言って、非球面レンズ不使用では
このシンプルな設計での「球面収差」は全く防げない。
絞りを開けていくと、ボケボケの酷い写りとなる。
その為、せっかくの超大口径(F1.1)が全く活かせず
絞り値を少なくともF8以上に絞り込まない限りは、
まともな解像感を得る事が出来ない。
KAMLANとしては、これが最初の発売レンズであり、
なんだか、「コンピューター光学設計が出来るように
なったので、大口径レンズを作ってみましたが・・」
という風に、とりあえず作ったものの、実際に市場に
出てしまったら写真業界での描写力の水準(レベル)
には全く届いていなかった・・(汗) という状況を
想像してしまう。
まさに、それが理由か? 本レンズは発売後僅かに
3ヶ月で、新型(Ⅱ型)にリニューアルされた。
そちらのレンズは未所有だが、レンズ構成がかなり
複雑化している模様で、それは諸収差低減、つまり
「まともな描写力」を目指した改良である事は、
どうやら間違い無さそうだ。
つまりⅡ型は「ごめんなさい製品」である。
Ⅱ型に買い換えるのが良さそうな状況なのだが、
天邪鬼な私は、そうなると、この写りが酷い初期型を
なんとか使いこなそうとしたくなる(笑)
まあ、良く写るレンズは他にも色々と持っているので、
むしろこうした酷い描写力のレンズは希少に思える。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13481368.jpg]()
だが、他の課題として、本レンズはピントリングの
動きが不安定で、稀に、ひっかかりが出たりする。
これが出ると鬱陶しいので、あまり好んで屋外に
持ち出したいとも思わなくなってしまった。
なんとか使えているうちは良いが、ちょっとした
弾みで完全に動かなくなってしまったら、途中で
写真が撮れなくなってしまうからだ。
まあつまり、メーカーとしても最初期の製品だから、
まだまだ設計も製造も品質的に未成熟という事だ。
この課題を鑑み、当面の間はKAMLAN製品を買い控え
する事とした。数年して新製品の品質が向上した頃に
必要であれば、それらを入手すれば良いかと思っている。
----
さて、5本目のシステム。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13481371.jpg]()
レンズは、Meike 50mm/f2 (MK50F20EFM)
(新品購入価格 10,000円)
カメラは、CANON EOS M5(APS-C機)
2019年に発売された中国製MFレンズ。
APS-C機以下のイメージサークル対応なので、
中望遠画角相当となる。
発売はミラーレス機用マウントのみである。
本シリーズ第4回「Meike編」には、評価が
間に合っていなかったレンズなので、こちらの
記事で追加紹介しておこう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13481336.jpg]()
「Meike編」でも記載したが、Meikeは、なんだか
製品毎の品質のバラツキがあるメーカーだと思う。
最短撮影距離と、その距離指標とのズレの課題が、
一部のMeike製品にあり、最短撮影距離が伸びたり
オーバーインフ(無限遠を超えてピントが合う)と
なったりしていて、あまり好ましく無い。
ただ、稀に、とても良いレンズも存在するので、
完全に無視する訳にもいかないメーカーだ。
(注:詳細は全く不明だが、Meikeというのは、
もしかして、一種の「製造連合体」なのだろうか?
たとえば、「揖保乃糸」(いぼのいと、そうめん)
は、「兵庫県手延素麺協同組合」の商品名であるが、
それは、非常に多数の製麺所で作られている)
本レンズだが、ピントリングの動作に若干の
ひっかかりが出る事がある、前述のKAMLAN FS50/1.1
と類似の症状だが、こちらはまだ軽微だ。
今のところ問題は無さそうなので使用は継続している。
描写力は、さほど悪いものでは無い。5群6枚の
恐らくは変形ダブルガウス型構成であり、古くから
小口径標準レンズ等では完成度の高い設計である。
ただまあ、スペック的には恐ろしく地味だ。
開放F2は、まあ、収差低減を狙っていて好ましい
のではあるが、最短撮影距離が65cmと、かなり長く
「寄れない」不満が顕著である。
APS-C機で75~80mm相当の画角となるから、
最短が65cmでも、一応は「焦点距離10倍則」を
満たすのではあるが、デジタル拡大(テレコン/ズーム)
が無いミラーレス機(例えば今回使用のEOS M5や、
FUJIFILM社ミラーレス機等)では、不満が大きい
かも知れない。
まあ、デジタル拡大機能を使っても、最短撮影距離
までは短縮できないから、アングルの自由度の制限
(例:360°どこからでもは撮れない)は一緒だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13481454.jpg]()
ちょっと「用途開発」が難しいレンズである。つまり
何に使うか? 何を撮るものなのか? そのあたり
について、本レンズの特徴を活かした用法を見つける
事が困難であるという意味だ。
あまり誰にでも薦められるレンズとは言い難い状態
である、まあいずれ「用途開発」を進めてからの
追加検証になるという感じか・・
----
さて、6本目のシステム。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13483168.jpg]()
レンズは、CONTAX Planar T* 50mm/f1.4(Y/Cマウント)
(中古購入価格 19,000円)(以下、P50/1.4)
カメラは、SONY α6000 (APS-C機)
1975年に(ヤシカ)CONTAX RTS(銀塩一眼第5回記事)
の登場に合わせて発売された大口径MF標準レンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13483107.jpg]()
西独カールツァイス社が1970年代前半に、カメラ・
レンズ事業から撤退してしまった(=その原因は、
日本製カメラの台頭)為、ツァイス西は、その知名度
から、「ブランド銘」を日本のメーカーに提供(販売)
する方針をとった。当初、旭光学(PENTAX)に打診が
あった模様だが成立せず、最終的にYASHICA(ヤシカ)
が「CONTAX」のブランド銘(使用権)を取得した。
YASHICAは速やかにCONTAX RTSを発売するのだが、
なんと、その年(1975年)に経営破綻してしまう。
「そんなにCONTAXを買うのは高額だったのか?」と
思うかも知れないが、そこは詮索するまい。
すぐさま京セラが資本投資し、数年後にはYASHICAは
京セラの子会社となる。よって一般的には、これら
の製品群は「京セラCONTAX」と呼ばれる事が多い。
YASHICAブランドはそのまま継続され、CONTAXを
上級機、YASHICA銘を廉価版および輸出向けとして
展開した。
これはツァイス社がYASHICAにブランド提供をした為、
YASHICAのネームバリューが世界的に高まった事
(=ZeissがYASHICAを認めた、両者は同等だ、の論理)
が海外展開を可能とした理由だ。しかし国内では
その事情が理解できず、「YASHICAはCONTAXの安物だ」
という認識が一般層に広まってしまう。
(マニア層では、そのあたりの事情がわかっていた為、
むしろYASHICA製や、その子会社だった富岡光学製の
レンズは人気商品となっていた)
まあ、そこら辺の話は、今回の本筋とは関係ない。
YASHICA/京セラは、せっかく(高価に)CONTAXの
ブランド銘を買った訳だから、そのネームバリューは
最大限に利用しないとならない。
仮に「ツァイスのレンズをYASHICAで作っています」と
公言したら、事の本質が良くわかっていない当時の
一般ユーザー層では、「なんだ、国産の安物か!」と、
ここでも、同様な誤解による認識が始まってしまう。
そもそも、独国のビッグブランド(カメラ、レンズ)は、
第二次大戦前のヒトラー政権により、「優秀な光学兵器」
を作る為に発展した産業である。しかし独国の敗戦と
東西分断、等の理由で、戦後には、日本製のカメラや
レンズに後塵を拝するようになって来てしまい、その
結果としての、西独カールツァイス社のカメラ・レンズ
事業からの撤退なのだ。
だけど、その歴史を知らない国内ビギナーユーザー層が
CONTAXやツァイス銘を有りがたがるのは、不勉強では
あるとは言えるが、ある意味、しかたが無い状態だ。
だから結局、国産ツァイスを展開するにあたっては
「これらのレンズは、本来、西独で生産されたもので
あり、日本の場合はライセンス生産に過ぎない」
という広報戦略を取った。
だけど、実際のところは、カメラやレンズに限らず
全ての工業製品は、「その製品が形になった国が
生産国である」という国際的なルールが存在する。
例えば、全て日本製の部品(レンズや鏡筒等)を
西独に送って組み立てれば、Made in West Germany
であり、中国で組み立てればMade in Chinaである。
前者の例は、1970年代後半の京セラCONTAXレンズ、
後者の例は、近代でのNIKON製一眼レフ等用高価格
レンズの一部に、その例がある。
つまり「生産国なんて、深い意味は何も無い」
という事を如実に示している事実だ。
で、恐らくだが、1972年前後に、西独ツァイス社
が、「カメラ事業からの撤退」を表明した後でも、
ツァイス関連工場(=外部協力工場。一般的な
言葉を使えば「下請け工場」)は、相当に残って
いただろうと思われる。それらの全てを操業停止
としてしまうのは酷なので、一部では操業確保の
為に、日本から送られてきたレンズ部品や、西独で
製造された部品を用いて、そこで組み立てを行い、
それらを「Made in West Germany」の京セラCONTAX
レンズとして、日本や他国で販売したのであろう。
特に本レンズ、P50/1.4に関しては、西独製造の
可能性か非常に高いレンズである。それはつまり
ヤシカ/京セラCONTAX機(RTS等)の付属レンズで
あり、生産数が多いから、特定工場での大量生産に
向く事、それと「標準レンズはメーカーの顔」
という時代でもあるから、京セラCONAXにおいて
「我が社のカメラの付属標準レンズは西独のカール・
ツァイス製なのです!」と言えれば、日本の
金満家のビギナー層等では、ブランドの魅力に
負けて、高価なそれを納得して買うからである。
この話は完全なる私の想像ではあるが、大きくは
外れていないシナリオだろう、と思っている。
まあ、当時として極めて妥当な措置だからだ。
で、こうした情報は現代では何も残っていない。
何故ならば「ツァイスレンズは西独製が基本である」
という論理で、当時のツァイスレンズの付加価値を
高めようとしていた市場戦略があったからであり、
それ故に、当時のツァイス(CONTAX)レンズは、
他社製品を遥かに上回る高価な値付けを可能として
いたからである。そのブランドイメージを壊さない
為には「実は日本製なのです」とは、口が裂けても
誰も言うことは出来ない。
ただ、それはもう今から50年近くも前の話だ、
現代では、そうした環境や世情も変わっていて、
その後、50年間で「Made in Japanのカメラや
レンズが世界最高品質である」という常識が、
世界各国全般に十分に定着している。
だから、京セラCONTAXの当時のように、頑なに
西独製に拘る必要性も、現代の感覚からすれば、
ずいぶんと不思議な世情に思える訳だ。
なお、日本製が最高品質、という状況もいつまでも
続くとは限らない。特に、2010年代後半頃からの
進化が著しい中国製レンズは、現時点でさえも
「仕上げの品質」については、既に日本製品を
上回っているし、いずれ描写性能(例:非球面や
特殊素材ガラスの搭載)や、機構の性能(例:手ブレ
補正や超音波モーター等)も、もう何年かすれば
日本製品を上回るようになっていくかも知れない。
何故ならば、2010年代以降の国内カメラ市場の
縮退により、日本製レンズは「元気が無い」状況が
明らかに見て取れるからだ。「ビギナー受けし、
かつ高価なレンズ」(例:大三元レンズ等)しか
企画されない、売れない、という状態では、もはや、
多くのマニア層等では、そうした優等生的なレンズに
興味を持つ事も無くなっている。
それ故に、私もマニアであるから、今回のシリーズ
記事の根幹である「海外製レンズ」に興味が行って
しまっている訳だ。まだまだ未成熟なところもある
海外(特に中国製)レンズではあるが、逆にそこが
現代の日本製レンズには無い魅力が満載なのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13483120.jpg]()
(上写真は、京都嵐山の「福田美術館」にて。
2年程前にオープンした、この新しい美術館は、
珍しく、殆どの作品の撮影が自由であり、SNS等
での情報拡散を意図している模様だ)
さて、余談が長くなったが、余談とも言い切れず、
CONTAXレンズに関して言えば「ブランド」という
要素が何を意味するのか? そしてそのブランドが
消費者やユーザーにおいて、どんな魅力や得失が
存在するのか? それらについては、消費者個々に
良く考え、自分なりの価値観を持つ必要があるだろう。
ちなみに、本P50/1.4に関しては、写りが悪い
レンズでは無く、1975年当時であれば、まあ
間違いなくトップクラスの標準レンズであろう。
だが、1980年代には、各社においても「Planarに
追いつき、追いこせ!」という開発方針があった
のだろうか? 急激に各社50mm/F1.4級レンズの
性能は改善され、その時代に各社の標準レンズの
描写力は、ほぼ同等なまでに進化している。
(別シリーズ「最強50mmレンズ選手権」等を参照)
1980年代後半には、一眼レフのAF化の時代を
向かえ、各社は、その完成度の高い標準レンズの
光学系を、そのままAF化し、それを非常に長期
(~2010年代頃までの約20~30年間に渡って、
あるいは一部の標準レンズは今なお販売継続中)
に渡って販売を続けていた。
つまり、本P50/1.4をトリガーとして始まった
標準レンズの性能改善は、それが収束した後も
近代に至るまで、ずっと歴史が継続されていた訳だ。
ただ、さすがに30年~40年以上も前の光学系では、
いくら完成度が高かったと言われても、もう設計が
古すぎるし、そうしたオーソドックスな(ありふれた)
レンズでは値上げをする事も出来ず、3~5万円という
安価な価格で売り続ける事をせざるを得なかったが
それでは現代の縮退したレンズ市場では儲けが出ず、
販売数の減少をカバーする事が出来ない。
だから、2010年代からの各社新鋭標準レンズでは、
1975年~1980年代での完成度の高い6群7枚構成を
潔く(やむなく?)捨てて、十数枚等の構成の
複雑な新設計の標準レンズに戦略転換した訳だ。
新しい標準レンズならば値上げが可能だ。よって
そうした各社新鋭レンズは10万円~40万円という
(平均定価で十数万円)価格範囲の高額レンズと
なっている。(=値上げする事が出来た)
まあ私も、そうした新鋭高額標準レンズを何本か
入手して使っているが、確かにそれらの描写力は
高いが、大きく重く高価な「三重苦レンズ」では
あるし、そもそも旧来の標準レンズの最低5倍から
最大100倍も差がある高額な入手価格を、妥当だと
思えるかどうか?は微妙である。
結局、いつの時代でも、メーカーや流通市場側は、
あの手、この手で、商品を高価に売りたい訳だ。
だから、消費者側では常に、その商品の価格と
性能や価値が妥当か否か?の「コスパ感覚」を強く
意識して、商品の購入を行わなければならない。
ここが商品購入における大原則であろう。
無駄に高価すぎるものを買ってしまう行動は、
けっして「マニア」だとは言い難い訳だ。
----
では、次は今回ラストのシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13483191.jpg]()
レンズは、安原製作所 MOMO 100 28mm/f6.4 Soft
(新品購入価格 21,800円)
カメラは、PANASONIC LUMIX DMC-G1(μ4/3機)
2016年に発売された、とても希少な広角ソフトレンズ
である。一眼レフ用のソフトレンズでは、焦点距離が
28mmというレベルまで広角なものは殆ど存在しない。
(注1:ただまあ、μ4/3機で使う際には標準画角だ)
(注2:LENSBABY TRIO28というトイ・ソフトレンズ
が存在する。また、近年、同じくLENSBABY社より
Velvet 28mm/F2.5 ソフトマクロが新発売された)
で、こちらのレンズは、一応日本製であるが・・
ご存知のように「安原製作所」は、あるカメラメーカー
から独立した安原氏個人が経営する
「世界最小のカメラ・レンズメーカー」である。
(注:安原氏は2020年に逝去。現在では安原製作所
の運営は停止している。無闇に問い合わせ等は
行わない事が望ましい)
その形態は本記事冒頭でも書いたように、安原氏が
設計した図面を国内外の工場に送って、そこで製造を
行う、という「ファブレス」(工場無し)形態だ。
最終組み立ては恐らく中国で行っているだろうから、
これはMade in・・ で言えば、海外製レンズとなる。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13483514.jpg]()
ここで言いたい事は、本レンズの性能とかの話では
無く、本レンズでの実例のように、現代における
商品の設計・製造システムにおいては、もはや
「何々国製である」(Made in ・・国)という概念
は無い、という事実だ。
本シリーズ記事の中での、別の例を挙げても、
*Lomography製(オーストリア)、製造はロシア。
*KAMLAN製レンズ 設計は台湾、製造は中国。
*京セラCONTAXレンズ 日本と西独の両国で製造。
*現代のZeiss銘レンズ 製造は日本のみ。
*安原製作所 設計は日本、製造は日本と中国。
・・等、いくらでも「製造国」という概念が曖昧な
製品が存在している。
これと同様に、現代の国産デジタルカメラ等でも
様々な部品メーカーによる構成部品を各社が共通に
使っているケースも多々あり、レンズであっても
完全にカメラメーカー自身で製造しているケースは
むしろ稀であり、多くがOEMメーカーへの製造委託だ。
また、NIKONの20万円以上もする高級レンズにも
「Made in China」と書いてあるので、シニア層など
では、「騙された!」と怒るかも知れないが、まあ
もう、そういった時代では無い訳だ。
製造分業は、もはや国際的であり、製造国、ブランド、
メーカー名、そういう差での、「昔ながらの感覚」で、
優劣を判断する事など、もはや不可能な時代である。
だから、いつも言うように、現代のビギナー層が
必ずと言っていい程に質問してくる内容で
「レンズは(カメラは)どこのメーカーのものが
良いのだ?」
という話(質問)は完全に無意味(的外れ)だ。
そういう質問には「どれも同じです、劣っていたら
そのメーカーはとっくに潰れていますよ」と答える
ようにしているのだが、まあ、そういう質問を
してくる事自体が、今時の世情を全く理解していない
ビギナー質問であろう。カメラがビギナーかどうか
では無く、世の中についての「ビギナー」なのだ。
くれぐれも、製造国、ブランド(メーカー)銘で
製品の優劣を判断してはならない、ここは大原則だ。
まあ、この事を言いたいが為に、本「海外レンズ・
マニアックス」のシリーズ記事を始めたようなもの
である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_13483578.jpg]()
では、今回の「海外製その他(2)編」は、このあたり迄で、
本記事をもって、本シリーズは暫定終了とする。
(また追加購入した海外レンズがれば、補足編を
書くかも知れないが、本シリーズ記事の主旨は、
個々のレンズの紹介では無く、「今時の海外レンズ
の状況」を伝えたいものであるので、補足編は無く
別途記事での個別紹介になると思う)
今回は海外製その他(2)編として、雑多な海外メーカー
製の所有レンズ7本を紹介する。
Clik here to view.

の本編記事には分類できなかった物、あるいは、
当該記事執筆後に追加購入したレンズである。
なお、本シリーズでの紹介を割愛した海外製の
マイナーなレンズまたはトイレンズ等もあるが、
それらは過去記事の、いずれかで紹介済みだ。
本記事が本シリーズの暫定最終回となる。
----
ではまず、今回最初の海外製レンズ。
Clik here to view.

(中古購入価格 15,000円)(以下、VM8518E)
カメラは、SONY α7S (フルサイズ機)
2019年に発売された中国製のフルサイズ対応MF中望遠
レンズ。マウントはミラーレス機用に数機種が
発売されている。姉妹レンズとして同スペックでの
AF版があるが、MF版は、ずっと安価である。
(注:この中古価格の安さは、販売店側の値付け
間違いだったかもしれない)
Clik here to view.
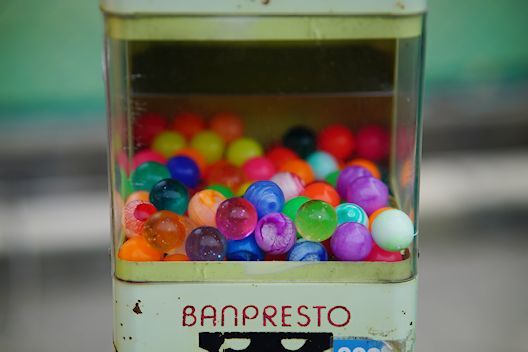
地区を中心に多数が集結しているようだ。香港と隣接
するこの地区は「経済特区」となっている模様であり、
すなわち産・官・学のコラボレーションが実現されて
いて、技術的な進歩が著しい状態と思われる。
この深センには、恐らくだが、有益なレンズ製造
メーカー(工場)があるのだろう、と推測している。
例えば日本で言えば、往年のコシナとか、小堀製作所や
日東光学等は他社レンズを製造して供給するOEMメーカー
であったし、現代のSIGMAやTAMRONも、一部では著名
メーカー製品のOEM製造は続けているであろう。
そうした有力なOEM製造メーカー(工場)が、中国にも
当然存在すると思われる。
そうであれば、現代は「コンピューター光学設計」が
当たり前となった時代であるから、誰かが新たに
「レンズメーカー」になりたかったら、自宅又は
小さいオフィスを借りて、パソコンを1台置き、
それで自分が作りたい仕様のレンズを自動設計すれば、
後はパソコンから出力される図面をOEMメーカー(工場)
にメールで送れば、新しいレンズが出来上がってしまう。
つまり、光学的知識と、ある程度の初期製造資金が
あれば、「誰でもレンズメーカーになれる」という
凄い時代となっている訳だ。
沢山の中国メーカーが出てくる理由も、わからない
訳でも無い世情である。
そしてそのOEM工場(1つだけなのか?複数あるかは
良くわからない)の製造品質は、2010年代後半から
恐ろしく向上している。
近年の国産レンズは、レンズ市場縮退によるコスト
ダウン措置により、プラスチック成型の鏡筒ばかりと
なっていて、あまり高級感が無いのだが、これら
中国製レンズは、昔の国産レンズのような金属鏡筒で
相当に高級感が高い。
これであれば、国内メーカーからも図面を中国に
送って、そちらで製造した方が品質が向上しそうだ。
まあ、かつての「海外生産」では、中国等での安い
人件費を利点とした「コストダウン」の様相が
大きかったのだが、現代となると、中国の人件費も
相当に高騰してしまっているので、コストダウンでは
無く、「品質の向上の為に中国生産とする」という
ケースすらあり得る、という話だ。
事実、大メーカーでは無いが、日本で設計して、中国
で製造しているケースの製品を知っている。
「レンズの作り」を見れば、それがわかる訳だ。
ただまあ、中国(海外)生産も、現状では日本製
レンズに比べての課題(不足点)がいくつかある。
1)AFレンズの製造が難しい。
これはAFモーターの調達と、各マウントにおける
AFプロトコル(レンズとカメラとの情報のやりとり)
の解析の2つの課題がある。AFプロトコル解析は
SIGMAやTAMRON等でもやっていた訳だから、専門家
がプロトコルアナライザー等の計測器を使えば可能
なのであろう。追々AFレンズは増えて来ると思う。
AFモーターだが・・
DC(直流)モーターは中国等でも調達は可能で、
STM(ステッピングモーター)も、だんだんと
調達が可能となっている模様。
USM(超音波モーター)は、まだそれを搭載して
いる海外製レンズは無い。おそらくこの点だけが
日本メーカーの海外製レンズに対する優位点だ。
なお、いずれもAFモーター自体の調達は困難では
無いだろうが、機構の複雑化や原価上昇による
コストアップと、(少ない)ブランド力における
市場価格の妥協点の問題だけであろう。
2)非球面レンズが作れない
レンズ設計ソフトにおいては、通常のタイプの
レンズに加え、特殊(異常)低分散ガラスや
非球面レンズを使った設計を自動で行う事も出来る。
ただし、通常ガラス→特殊ガラス→非球面 の順に
高価になるので、レンズの想定販売価格によっては
贅沢な素材は使いにくい。
また、非球面レンズは、それを製造するには、
非球面切削機(研磨機)または、非球面用モールド
(金型)が必要となり、これは高価な機器または
製造コストアップを招くので、あまり安価なレンズ
には使いにくい。
ただ、技術的に難しい、という訳では無いので、
資金力やレンズ販売価格の問題だけだ。
既に非球面製造機を調達した中国メーカーもある、
と聞いているので、近いうちに非球面レンズ搭載
の中国製レンズも一般的になるであろう。
(追記:2021年、LAOWAや銘匠光学より非球面レンズ
搭載型レンズ各種の発売が開始されている)
3)手ブレ補正搭載のレンズが作れない
まあ、これはそうなのだろうが・・ とは言え、
様々な撮影条件において、レンズに常に手ブレ
補正が入っていないとならない、という訳では
無いし、ボディ側に手ブレ補正を内蔵している
カメラも多いので、あまり重要な課題では無いとは
思う。この点、むしろ国産レンズがなんでもかんでも
手ブレ補正機能を入れて、それを「付加価値」として
値上げしてしまっている様相には、個人的には賛同
できない。
近年では、むしろ「SIGMA ART LINE」等の手ブレ補正
無しのレンズの方が、硬派なコンセプトで個人的には
好みであり、それらを何本か買った次第だ。
Clik here to view.

は、基本性能や品質的には十分だ。
若干の周辺減光・周辺収差等の課題は、それを嫌う
ならばフルサイズ機では無くAPS-C機で使えば解決だ。
AF版は未所有なので、その速度や精度等は不明だ。
ただ、上記のように、中国製レンズでのその辺の
技術は発展途上である為、オーソドックスなMF版
の方が手堅いであろう。
中級層やマニア層には推奨できるレンズである。
(追記:2020年には、早くも後継のⅡ型レンズ
が発売されている。そちらは未所有であり比較は
出来ないが、当然ながら価格は上昇している)
----
では、次の海外製レンズ。
Clik here to view.

(中古購入価格 9,000円)
カメラは、PANASONIC DMC-GX7 (μ4/3機)
ロシアンレンズなので、詳しい情報は不明だ。
Clik here to view.

(1980年代頃まで?)製造されていたレンズで
あろう。
近年において、熊本の商社「GIZMON」が、本レンズ
のデッドストックをロシアから選別輸入し、マニア層
向けに、少数だけ販売したものだ。
私は、それを買いそびれてしまい(すぐ売り切れた)
数年後に出てきた中古を買ったのだが、残念ながら
若干のプレミアム相場で、販売時の新品価格より
少しだけ高額な価格で購入せざるを得なかった。
本レンズには「星型ボケ」が得られる、独特の
絞り形状を持つ他バージョンがあり、マニア層には
著名だが、本レンズはそのバージョンでは無く、
通常の絞り形状である。(改良された、と言うべき
であろう。常に星型ボケでは困る場合もある)
まあ、そういう用途に用いるのであれば、例えば
近代のLomography製(New) Petzvalレンズの数機種に
「ウォーターハウス型」絞り機構が搭載されていて、
付属またはオプション部品として、星型やハート型の
形状の絞りが存在している。
また、国内GIZMON社からも、非常に多数の交換型の
特殊形状の絞り部品を付属した安価なトイレンズ
「GIZMON Bokeh Lens Illumina」が発売されている。
そうしたレンズ群と付属部品を使った方が特殊形状
ボケを出す上で簡便だし、作画の自由度も高い。
(それを出したくないケースでは、絞り部品を
入れ替えてしまえば良い)
Clik here to view.

そこそこの描写力を持つ理屈なのだが、細かい弱点
(周辺収差、最短撮影距離の長さ、逆光耐性の低さ)
などが色々とある為、使いこなすのは少々難しい。
まあ、比較的近年に販売されていたレンズなので、
中古等の入手性はゼロでは無い。従前の時代に
流通していたロシアン(Jupiter系やMIR系等)は
現代ではセミレア化してしまって、高価な相場に
なっているケースも良くあるので、そういう点では
本レンズは「ロシアンの入門編」として、中級
マニア層等に向けては良いかも知れない。
・・と言うのも、ロシアンレンズの多くは、ちゃんと
使いこなすのが非常に難しい為、ベテランのマニア層
等が良く言う「ロシアンは良く写る」という状態を
初級層等が再現するのは困難だ。だから、あまり最初
から高価な(高価すぎる)ロシアンを買ってしまうと、
使いこなせず、出資が無駄になる危険性が高いので
まずは安価なロシアンで、感触を試して見るのも良い
と思う。
---
では、3本目の海外製レンズ。
Clik here to view.

(中古購入価格 2,000円相当)(以下、FUJIAN35/1.7)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1 (μ4/3機)
2010年代後半頃に発売と思われる、CCTV(監視カメラ)
用のMF単焦点レンズ。(注:メーカー(ブランド)名は
他の表記の場合もある)
レンズ上に「TV LENS」の記載があるが、これは
CCTV(Closed-Circuit TeleVison)用、という意味で
あろう。Cマウント品であり、2/3型イメージサークル
に対応との事。
数年前に新品で2000円台で通販で販売されていた
模様だが、すでに販売終了。後に出てきた中古品で、
Cマウントのアダプター付属で3000円で入手した。
レンズ自体の価格は、2000円という事にしておこう。
Clik here to view.

構造上、無限遠までピントが来ず、中距離までの
撮影に制限されるし、絞って被写界深度を深めて
使ったとしても、描写力は、お世辞にも褒められた
ものでは無い。あくまでアナログ時代(ハイビジョン
以前の時代)の監視カメラ用の仕様・性能だ。
一応、今回はμ4/3機を母艦とし、2倍テレコン
モードを常時ONとしている、この用法だと、
イメージサークルが2/3型相当となる為、本レンズ
の仕様にマッチするのではあるが・・
これでも、周辺がギリギリとなり、Hi-Fi写真は
撮れない。ならば、1/2.3型のPENTAX Q/Q10で
使えば良いか?と言えば、まあ、そうしたとしても、
やはり画面全域での描写力は大いに不満だ。
いずれの用法でも、換算画角は、140mm~
192mm相当となり、かなりの望遠画角である。
画質的な面から「これはトイレンズだ」と、使用
目的をLo-Fi用途に変えてしまうのが、最も簡便な
考え方なのだが、「望遠画角のトイレンズ」
というのも、あまり無いので、経験則や作画表現
的には、ちょっと厳しいかも知れない。
Clik here to view.

用なので、実用的な写真用途としては使えず、使う
ならば、あくまで「トイレンズ」として捉えるのが
賢明だ。エフェクト等を適宜追加するのが良いであろう。
----
さて、4本目のシステム。
Clik here to view.

(新品購入価格 23,000円)(以下、FS50/1.1)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
2019年に販売開始された新鋭メーカーの海外製
超大口径MFレンズ。
台湾のメーカー(瑪暢光電有限公司/Sainsonic社)が
設計し、同社工場のある中国の「深セン」地区で
製造されたレンズである。
(なので、純粋な中国製レンズとは言い難い)
Clik here to view.

5群5枚構成であるが、いくら異常低分散ガラスを
採用しているからと言って、非球面レンズ不使用では
このシンプルな設計での「球面収差」は全く防げない。
絞りを開けていくと、ボケボケの酷い写りとなる。
その為、せっかくの超大口径(F1.1)が全く活かせず
絞り値を少なくともF8以上に絞り込まない限りは、
まともな解像感を得る事が出来ない。
KAMLANとしては、これが最初の発売レンズであり、
なんだか、「コンピューター光学設計が出来るように
なったので、大口径レンズを作ってみましたが・・」
という風に、とりあえず作ったものの、実際に市場に
出てしまったら写真業界での描写力の水準(レベル)
には全く届いていなかった・・(汗) という状況を
想像してしまう。
まさに、それが理由か? 本レンズは発売後僅かに
3ヶ月で、新型(Ⅱ型)にリニューアルされた。
そちらのレンズは未所有だが、レンズ構成がかなり
複雑化している模様で、それは諸収差低減、つまり
「まともな描写力」を目指した改良である事は、
どうやら間違い無さそうだ。
つまりⅡ型は「ごめんなさい製品」である。
Ⅱ型に買い換えるのが良さそうな状況なのだが、
天邪鬼な私は、そうなると、この写りが酷い初期型を
なんとか使いこなそうとしたくなる(笑)
まあ、良く写るレンズは他にも色々と持っているので、
むしろこうした酷い描写力のレンズは希少に思える。
Clik here to view.

動きが不安定で、稀に、ひっかかりが出たりする。
これが出ると鬱陶しいので、あまり好んで屋外に
持ち出したいとも思わなくなってしまった。
なんとか使えているうちは良いが、ちょっとした
弾みで完全に動かなくなってしまったら、途中で
写真が撮れなくなってしまうからだ。
まあつまり、メーカーとしても最初期の製品だから、
まだまだ設計も製造も品質的に未成熟という事だ。
この課題を鑑み、当面の間はKAMLAN製品を買い控え
する事とした。数年して新製品の品質が向上した頃に
必要であれば、それらを入手すれば良いかと思っている。
----
さて、5本目のシステム。
Clik here to view.

レンズは、Meike 50mm/f2 (MK50F20EFM)
(新品購入価格 10,000円)
カメラは、CANON EOS M5(APS-C機)
2019年に発売された中国製MFレンズ。
APS-C機以下のイメージサークル対応なので、
中望遠画角相当となる。
発売はミラーレス機用マウントのみである。
本シリーズ第4回「Meike編」には、評価が
間に合っていなかったレンズなので、こちらの
記事で追加紹介しておこう。
Clik here to view.

製品毎の品質のバラツキがあるメーカーだと思う。
最短撮影距離と、その距離指標とのズレの課題が、
一部のMeike製品にあり、最短撮影距離が伸びたり
オーバーインフ(無限遠を超えてピントが合う)と
なったりしていて、あまり好ましく無い。
ただ、稀に、とても良いレンズも存在するので、
完全に無視する訳にもいかないメーカーだ。
(注:詳細は全く不明だが、Meikeというのは、
もしかして、一種の「製造連合体」なのだろうか?
たとえば、「揖保乃糸」(いぼのいと、そうめん)
は、「兵庫県手延素麺協同組合」の商品名であるが、
それは、非常に多数の製麺所で作られている)
本レンズだが、ピントリングの動作に若干の
ひっかかりが出る事がある、前述のKAMLAN FS50/1.1
と類似の症状だが、こちらはまだ軽微だ。
今のところ問題は無さそうなので使用は継続している。
描写力は、さほど悪いものでは無い。5群6枚の
恐らくは変形ダブルガウス型構成であり、古くから
小口径標準レンズ等では完成度の高い設計である。
ただまあ、スペック的には恐ろしく地味だ。
開放F2は、まあ、収差低減を狙っていて好ましい
のではあるが、最短撮影距離が65cmと、かなり長く
「寄れない」不満が顕著である。
APS-C機で75~80mm相当の画角となるから、
最短が65cmでも、一応は「焦点距離10倍則」を
満たすのではあるが、デジタル拡大(テレコン/ズーム)
が無いミラーレス機(例えば今回使用のEOS M5や、
FUJIFILM社ミラーレス機等)では、不満が大きい
かも知れない。
まあ、デジタル拡大機能を使っても、最短撮影距離
までは短縮できないから、アングルの自由度の制限
(例:360°どこからでもは撮れない)は一緒だ。
Clik here to view.

何に使うか? 何を撮るものなのか? そのあたり
について、本レンズの特徴を活かした用法を見つける
事が困難であるという意味だ。
あまり誰にでも薦められるレンズとは言い難い状態
である、まあいずれ「用途開発」を進めてからの
追加検証になるという感じか・・
----
さて、6本目のシステム。
Clik here to view.

(中古購入価格 19,000円)(以下、P50/1.4)
カメラは、SONY α6000 (APS-C機)
1975年に(ヤシカ)CONTAX RTS(銀塩一眼第5回記事)
の登場に合わせて発売された大口径MF標準レンズである。
Clik here to view.

レンズ事業から撤退してしまった(=その原因は、
日本製カメラの台頭)為、ツァイス西は、その知名度
から、「ブランド銘」を日本のメーカーに提供(販売)
する方針をとった。当初、旭光学(PENTAX)に打診が
あった模様だが成立せず、最終的にYASHICA(ヤシカ)
が「CONTAX」のブランド銘(使用権)を取得した。
YASHICAは速やかにCONTAX RTSを発売するのだが、
なんと、その年(1975年)に経営破綻してしまう。
「そんなにCONTAXを買うのは高額だったのか?」と
思うかも知れないが、そこは詮索するまい。
すぐさま京セラが資本投資し、数年後にはYASHICAは
京セラの子会社となる。よって一般的には、これら
の製品群は「京セラCONTAX」と呼ばれる事が多い。
YASHICAブランドはそのまま継続され、CONTAXを
上級機、YASHICA銘を廉価版および輸出向けとして
展開した。
これはツァイス社がYASHICAにブランド提供をした為、
YASHICAのネームバリューが世界的に高まった事
(=ZeissがYASHICAを認めた、両者は同等だ、の論理)
が海外展開を可能とした理由だ。しかし国内では
その事情が理解できず、「YASHICAはCONTAXの安物だ」
という認識が一般層に広まってしまう。
(マニア層では、そのあたりの事情がわかっていた為、
むしろYASHICA製や、その子会社だった富岡光学製の
レンズは人気商品となっていた)
まあ、そこら辺の話は、今回の本筋とは関係ない。
YASHICA/京セラは、せっかく(高価に)CONTAXの
ブランド銘を買った訳だから、そのネームバリューは
最大限に利用しないとならない。
仮に「ツァイスのレンズをYASHICAで作っています」と
公言したら、事の本質が良くわかっていない当時の
一般ユーザー層では、「なんだ、国産の安物か!」と、
ここでも、同様な誤解による認識が始まってしまう。
そもそも、独国のビッグブランド(カメラ、レンズ)は、
第二次大戦前のヒトラー政権により、「優秀な光学兵器」
を作る為に発展した産業である。しかし独国の敗戦と
東西分断、等の理由で、戦後には、日本製のカメラや
レンズに後塵を拝するようになって来てしまい、その
結果としての、西独カールツァイス社のカメラ・レンズ
事業からの撤退なのだ。
だけど、その歴史を知らない国内ビギナーユーザー層が
CONTAXやツァイス銘を有りがたがるのは、不勉強では
あるとは言えるが、ある意味、しかたが無い状態だ。
だから結局、国産ツァイスを展開するにあたっては
「これらのレンズは、本来、西独で生産されたもので
あり、日本の場合はライセンス生産に過ぎない」
という広報戦略を取った。
だけど、実際のところは、カメラやレンズに限らず
全ての工業製品は、「その製品が形になった国が
生産国である」という国際的なルールが存在する。
例えば、全て日本製の部品(レンズや鏡筒等)を
西独に送って組み立てれば、Made in West Germany
であり、中国で組み立てればMade in Chinaである。
前者の例は、1970年代後半の京セラCONTAXレンズ、
後者の例は、近代でのNIKON製一眼レフ等用高価格
レンズの一部に、その例がある。
つまり「生産国なんて、深い意味は何も無い」
という事を如実に示している事実だ。
で、恐らくだが、1972年前後に、西独ツァイス社
が、「カメラ事業からの撤退」を表明した後でも、
ツァイス関連工場(=外部協力工場。一般的な
言葉を使えば「下請け工場」)は、相当に残って
いただろうと思われる。それらの全てを操業停止
としてしまうのは酷なので、一部では操業確保の
為に、日本から送られてきたレンズ部品や、西独で
製造された部品を用いて、そこで組み立てを行い、
それらを「Made in West Germany」の京セラCONTAX
レンズとして、日本や他国で販売したのであろう。
特に本レンズ、P50/1.4に関しては、西独製造の
可能性か非常に高いレンズである。それはつまり
ヤシカ/京セラCONTAX機(RTS等)の付属レンズで
あり、生産数が多いから、特定工場での大量生産に
向く事、それと「標準レンズはメーカーの顔」
という時代でもあるから、京セラCONAXにおいて
「我が社のカメラの付属標準レンズは西独のカール・
ツァイス製なのです!」と言えれば、日本の
金満家のビギナー層等では、ブランドの魅力に
負けて、高価なそれを納得して買うからである。
この話は完全なる私の想像ではあるが、大きくは
外れていないシナリオだろう、と思っている。
まあ、当時として極めて妥当な措置だからだ。
で、こうした情報は現代では何も残っていない。
何故ならば「ツァイスレンズは西独製が基本である」
という論理で、当時のツァイスレンズの付加価値を
高めようとしていた市場戦略があったからであり、
それ故に、当時のツァイス(CONTAX)レンズは、
他社製品を遥かに上回る高価な値付けを可能として
いたからである。そのブランドイメージを壊さない
為には「実は日本製なのです」とは、口が裂けても
誰も言うことは出来ない。
ただ、それはもう今から50年近くも前の話だ、
現代では、そうした環境や世情も変わっていて、
その後、50年間で「Made in Japanのカメラや
レンズが世界最高品質である」という常識が、
世界各国全般に十分に定着している。
だから、京セラCONTAXの当時のように、頑なに
西独製に拘る必要性も、現代の感覚からすれば、
ずいぶんと不思議な世情に思える訳だ。
なお、日本製が最高品質、という状況もいつまでも
続くとは限らない。特に、2010年代後半頃からの
進化が著しい中国製レンズは、現時点でさえも
「仕上げの品質」については、既に日本製品を
上回っているし、いずれ描写性能(例:非球面や
特殊素材ガラスの搭載)や、機構の性能(例:手ブレ
補正や超音波モーター等)も、もう何年かすれば
日本製品を上回るようになっていくかも知れない。
何故ならば、2010年代以降の国内カメラ市場の
縮退により、日本製レンズは「元気が無い」状況が
明らかに見て取れるからだ。「ビギナー受けし、
かつ高価なレンズ」(例:大三元レンズ等)しか
企画されない、売れない、という状態では、もはや、
多くのマニア層等では、そうした優等生的なレンズに
興味を持つ事も無くなっている。
それ故に、私もマニアであるから、今回のシリーズ
記事の根幹である「海外製レンズ」に興味が行って
しまっている訳だ。まだまだ未成熟なところもある
海外(特に中国製)レンズではあるが、逆にそこが
現代の日本製レンズには無い魅力が満載なのだ。
Clik here to view.

2年程前にオープンした、この新しい美術館は、
珍しく、殆どの作品の撮影が自由であり、SNS等
での情報拡散を意図している模様だ)
さて、余談が長くなったが、余談とも言い切れず、
CONTAXレンズに関して言えば「ブランド」という
要素が何を意味するのか? そしてそのブランドが
消費者やユーザーにおいて、どんな魅力や得失が
存在するのか? それらについては、消費者個々に
良く考え、自分なりの価値観を持つ必要があるだろう。
ちなみに、本P50/1.4に関しては、写りが悪い
レンズでは無く、1975年当時であれば、まあ
間違いなくトップクラスの標準レンズであろう。
だが、1980年代には、各社においても「Planarに
追いつき、追いこせ!」という開発方針があった
のだろうか? 急激に各社50mm/F1.4級レンズの
性能は改善され、その時代に各社の標準レンズの
描写力は、ほぼ同等なまでに進化している。
(別シリーズ「最強50mmレンズ選手権」等を参照)
1980年代後半には、一眼レフのAF化の時代を
向かえ、各社は、その完成度の高い標準レンズの
光学系を、そのままAF化し、それを非常に長期
(~2010年代頃までの約20~30年間に渡って、
あるいは一部の標準レンズは今なお販売継続中)
に渡って販売を続けていた。
つまり、本P50/1.4をトリガーとして始まった
標準レンズの性能改善は、それが収束した後も
近代に至るまで、ずっと歴史が継続されていた訳だ。
ただ、さすがに30年~40年以上も前の光学系では、
いくら完成度が高かったと言われても、もう設計が
古すぎるし、そうしたオーソドックスな(ありふれた)
レンズでは値上げをする事も出来ず、3~5万円という
安価な価格で売り続ける事をせざるを得なかったが
それでは現代の縮退したレンズ市場では儲けが出ず、
販売数の減少をカバーする事が出来ない。
だから、2010年代からの各社新鋭標準レンズでは、
1975年~1980年代での完成度の高い6群7枚構成を
潔く(やむなく?)捨てて、十数枚等の構成の
複雑な新設計の標準レンズに戦略転換した訳だ。
新しい標準レンズならば値上げが可能だ。よって
そうした各社新鋭レンズは10万円~40万円という
(平均定価で十数万円)価格範囲の高額レンズと
なっている。(=値上げする事が出来た)
まあ私も、そうした新鋭高額標準レンズを何本か
入手して使っているが、確かにそれらの描写力は
高いが、大きく重く高価な「三重苦レンズ」では
あるし、そもそも旧来の標準レンズの最低5倍から
最大100倍も差がある高額な入手価格を、妥当だと
思えるかどうか?は微妙である。
結局、いつの時代でも、メーカーや流通市場側は、
あの手、この手で、商品を高価に売りたい訳だ。
だから、消費者側では常に、その商品の価格と
性能や価値が妥当か否か?の「コスパ感覚」を強く
意識して、商品の購入を行わなければならない。
ここが商品購入における大原則であろう。
無駄に高価すぎるものを買ってしまう行動は、
けっして「マニア」だとは言い難い訳だ。
----
では、次は今回ラストのシステム
Clik here to view.

(新品購入価格 21,800円)
カメラは、PANASONIC LUMIX DMC-G1(μ4/3機)
2016年に発売された、とても希少な広角ソフトレンズ
である。一眼レフ用のソフトレンズでは、焦点距離が
28mmというレベルまで広角なものは殆ど存在しない。
(注1:ただまあ、μ4/3機で使う際には標準画角だ)
(注2:LENSBABY TRIO28というトイ・ソフトレンズ
が存在する。また、近年、同じくLENSBABY社より
Velvet 28mm/F2.5 ソフトマクロが新発売された)
で、こちらのレンズは、一応日本製であるが・・
ご存知のように「安原製作所」は、あるカメラメーカー
から独立した安原氏個人が経営する
「世界最小のカメラ・レンズメーカー」である。
(注:安原氏は2020年に逝去。現在では安原製作所
の運営は停止している。無闇に問い合わせ等は
行わない事が望ましい)
その形態は本記事冒頭でも書いたように、安原氏が
設計した図面を国内外の工場に送って、そこで製造を
行う、という「ファブレス」(工場無し)形態だ。
最終組み立ては恐らく中国で行っているだろうから、
これはMade in・・ で言えば、海外製レンズとなる。
Clik here to view.

無く、本レンズでの実例のように、現代における
商品の設計・製造システムにおいては、もはや
「何々国製である」(Made in ・・国)という概念
は無い、という事実だ。
本シリーズ記事の中での、別の例を挙げても、
*Lomography製(オーストリア)、製造はロシア。
*KAMLAN製レンズ 設計は台湾、製造は中国。
*京セラCONTAXレンズ 日本と西独の両国で製造。
*現代のZeiss銘レンズ 製造は日本のみ。
*安原製作所 設計は日本、製造は日本と中国。
・・等、いくらでも「製造国」という概念が曖昧な
製品が存在している。
これと同様に、現代の国産デジタルカメラ等でも
様々な部品メーカーによる構成部品を各社が共通に
使っているケースも多々あり、レンズであっても
完全にカメラメーカー自身で製造しているケースは
むしろ稀であり、多くがOEMメーカーへの製造委託だ。
また、NIKONの20万円以上もする高級レンズにも
「Made in China」と書いてあるので、シニア層など
では、「騙された!」と怒るかも知れないが、まあ
もう、そういった時代では無い訳だ。
製造分業は、もはや国際的であり、製造国、ブランド、
メーカー名、そういう差での、「昔ながらの感覚」で、
優劣を判断する事など、もはや不可能な時代である。
だから、いつも言うように、現代のビギナー層が
必ずと言っていい程に質問してくる内容で
「レンズは(カメラは)どこのメーカーのものが
良いのだ?」
という話(質問)は完全に無意味(的外れ)だ。
そういう質問には「どれも同じです、劣っていたら
そのメーカーはとっくに潰れていますよ」と答える
ようにしているのだが、まあ、そういう質問を
してくる事自体が、今時の世情を全く理解していない
ビギナー質問であろう。カメラがビギナーかどうか
では無く、世の中についての「ビギナー」なのだ。
くれぐれも、製造国、ブランド(メーカー)銘で
製品の優劣を判断してはならない、ここは大原則だ。
まあ、この事を言いたいが為に、本「海外レンズ・
マニアックス」のシリーズ記事を始めたようなもの
である。
Clik here to view.

本記事をもって、本シリーズは暫定終了とする。
(また追加購入した海外レンズがれば、補足編を
書くかも知れないが、本シリーズ記事の主旨は、
個々のレンズの紹介では無く、「今時の海外レンズ
の状況」を伝えたいものであるので、補足編は無く
別途記事での個別紹介になると思う)