マニアックなレンズを紹介するシリーズ記事だが、
今回の記事も補足編として「85mm(級)マニアックス
(2)」という主旨とする。
実焦点距離が85mm前後(概ね70mm~90mm)または、
APS-C機以下専用で、フルサイズ換算画角が85mm前後
のレンズの内、比較的マニアック(あまり有名では無い)
なものを20本集め、前後編で各10本づつを紹介して
いるが、今回は残りの10本だ。
----
ではまず、今回最初の85mmレンズ。
![_c0032138_17174461.jpg]()
(中古購入価格 60,000円)
カメラは、NIKON D500 (APS-C機)
1981年頃に発売されたMF大口径中望遠レンズ。
銀塩時代から愛用しているレンズであるが・・
銀塩時代の1970年代~1980年代頃のNIKON NIKKOR
銘レンズの多くは解像力を優先した設計で、ボケ質等は
あまり配慮していないものが殆どであった。
その理由は、恐らくだが、当時のNIKON製品は、報道や
学術分野での利用が多く、そうであれば、その分野では
ともかく「被写体が、くっきり、はっきり写っている」
必要性があったからであろう。
解像感を優先すれば、他の様々な性能要素が犠牲に
なるのはやむを得ない。現代の超高性能レンズのように、
収差を限りなく補正する為に、同じ85mm/F1.4級レンズ
であっても、異常低分散ガラスや非球面レンズを多用した
十数群十数枚の複雑な光学(光路)設計をコンピューター
で行えるような時代では無いのだ。
当時は、非球面や新ガラスも無く(注:無い事は無いが、
非常に高価→Noct-NIKKOR 58mm/F1.2 1977年で使用)
また、光学設計も手計算で行わざるを得ない。であれば、
要求仕様における「何か」を優先すれば、他の要素は
犠牲になってしまう。
結局、こういう状況であったから、私は銀塩MF時代の
NIKKORレンズが、あまり好みでは無かった。つまり
「描写が固すぎる」という印象がとても強かったからだ。
だが、そういうNIKKORの中でも、稀にそうでは無い特性、
具体的には、解像感を若干犠牲にしても、ボケ質とかを
含めたトータルのバランスを重視する特性を持たせた
レンズが何本か存在している。
私の知っている範囲では、それは、さほど多くは無く、
本Ai85/1.4や、Ai105/1.8、Ai135/2、ED180/2.8
あたりだ。
(注:近年の「3次元的ハイファイ」設計のNIKKOR、
例:AF-S NIKKOR 58mm/F1.4G 2013年、等も同様
なコンセプトによる設計だ)
![_c0032138_17174410.jpg]()
おける最大口径のレンズだ」という事だ。
それらが「バランス重視」の特性の設計になる理由は
2つ想像できる、
1、これらは、報道・学術用のレンズとは見なしておらず
アート、ファッション・ポートレート、自然撮影
が主目的であろう。(だから、カリカリな固い描写
傾向は、あまり望ましく無い)
2、口径比を明るくすると、諸収差のオンパレードとなり、
解像力を高める光学設計とする事が、そもそも難しい。
それから、本レンズの光学設計は、前記事で紹介した
CONTAX (RTS) Planar 85mm/F1.4のレンズ構成に似ている。
そちらのレンズは1975年発売、センセーショナルな特性で
「神格化」される程のレンズであったが、いくつかの
弱点を持ち、使いこなしが非常に難しいレンズであった。
それから6年の時が経過して発売の本Ai85/1.4である。
RTS P85/1.4程の使いこなしの難しさは本レンズには無い。
まあ、だから銀塩時代からずっと愛用している次第だが、
でも、別な言い方をすれば、RTS P85/1.4には
「条件が上手く揃った際での、爆発的な高描写力」という
切り札があったのだが、本Ai85/1.4には、それが無い。
いつでも無難に撮れるが、面白みは少ないかもしれない。
ただまあ、そこは写真を撮る環境や目的によりけりだ、
結局、「85mm/F1.4級は、1本だけ持っておけば済む」
という話にはならず、色々な特性のものを条件に合わせて
選択する必要性を感じている。(それと、現代の超高性能
レンズは、こういうレンズ毎の個性が無く、つまらない)
なお、RTS P85/1.4や本Ai85/1.4、それから他は未所有
ではあるが、この時代(1980年代前後)のMF85mm/F1.4
級レンズには、似たようなレンズ構成のものがあると思う。
よって近年、私は、これらを総称し「プラナー系85mm」
と呼んでいる。
「何故、そういう呼び名が必要なのか?」については、
近年、2019年頃に発売された、中国製レンズの
「七工匠55mm/F1.4」が、このようなプラナー系85mm
のレンズ構成を、2/3程度にダウンサイジングして設計
された「ジェネリック・レンズ」である事がわかった
からだ。だが、具体的に、どのレンズをベースとして
再設計したかはわからない、ジェネリック設計の場合、
バックフォーカスの調整等で、レンズ後群の構成を
変更する場合があるからだ。
だから、特に具体的なレンズ名は特定せずに、
「七工匠55mm/F1.4はプラナー系85mmレンズの
ジェネリック」と称している訳だ。
----
では、次の85mmレンズ。
![_c0032138_17174429.jpg]()
(中古購入価格 16,000円)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
2010年に発売された、AF単焦点中望遠レンズ。
一応、SONYにおけるエントリーレンズではあるが、
他のDT型番のエントリーレンズとは異なり、本レンズ
はフルサイズ対応である。
(特殊レンズ第51回SONYエントリーレンズ編参照)
なお、85mm単焦点で、フルサイズ対応では無い
(つまり、APS-C機以下専用の)ものは、非常に
数が限られていて、記憶している限り3機種程度しか
無いと思う。この理由は「85mmは、フルサイズ機で
ポートレートに使うもの」という常識(思い込み)が
市場全般に根強いからであろう。
よって、85mmレンズを企画するならば、必然的に
フルサイズ対応のものしか作られない。
![_c0032138_17174501.jpg]()
暗い為、浅い被写界深度を得にくいが、その点は
最短撮影距離が60cmと「焦点距離10倍則」を
下回って寄れる為、少しその不満は解消できる。
あまり明確な用途が無い点が課題のレンズだ。
SONY α(A)マウント機で純正の85mmは、他は高価な
ものばかりなので、これを低価格品として代用する事は
出来なくは無いが、どうしても大口径85mmを安価に
入手したいのであれば、SIGMAやTAMRONといった
サードパーティ製85mmもあるし(注:近年の機種では、
SONY Aマウント版は用意されていないケースが多い)
あるいは近接撮影を中望遠画角で行いたいならば、
同じくSIGMAやTAMRONの旧型中望遠マクロも、安価に
中古で入手は容易だ。
結局、本レンズには「用途不明」なところがあり、
それが本レンズにおける唯一にして最大の課題であろう。
----
では、3本目は換算85mm(級)トイレンズだ。
![_c0032138_17175330.jpg]()
(中古購入価格 3,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
2011年発売の、PENTAX Qシステム専用トイレンズ、
(注:PENTAXではユニークレンズと称している)
換算画角は、装着するQ系機体により異なり、
約99mm相当:1/2.3型機:PENTAX Q,Q10
約83mm相当:1/1.7型機:PENTAX Q7,Q-S1
となる。
![_c0032138_17175344.jpg]()
機種からセンサーサイズが変化している。
ちなみに、だいたい同じ時代での、SONY E(APS-C型)
から、SONY FE(フルサイズ)への変更であれば、
これは最初からNEX→αへの変更を意図して、マウント
廻りはフルサイズ用で設計していたし、レンズも明確に、
APS-C機用(E型番)と、フルサイズ用(FE型番)で区分
されていたのだが・・
このPENTAX Q系の場合は、そういう当初からの意図が
あまり無い状態で、センサーサイズを途中で大型化
したのかも知れない。
・・と言うのも、本レンズや初代PENTAX Qの発売年は、
東日本大震災のあった2011年だ。この年、他社の多く
は、製造や流通の課題と、世情や消費者心理を鑑みて、
あまりカメラ等の新発売を行っていない。
で、その間、研究開発は何をやっていたか?と言えば
多分、カメラのフルサイズ化に係わる開発であろう。
よって、翌年2012年には、私が「フルサイズ元年」
と呼んでいるくらい、一般層に向けてのフルサイズ
一眼レフが多数出揃った次第だ。
具体的には、CANON EOS-1DX,EOS 5D MarkⅢ,
EOS 6D,NIKON D4,D800/E,D600,SONY α99等が、
いずれも2012年の発売である。
又、翌々年2013年にはミラーレス機SONY α7/7R
も(NEXから変わり)フルサイズ化。
このように一気に市場がフルサイズ化したのは、
フルサイズの撮像センサー部品の製造が低価格化したか、
あるいは、もしかすると、それまで供給を渋っていた
センサー製造メーカーが、他社への供給を開始(解禁)
したから、かも知れない。
・・はたまた、この2012年~2013年の主に一眼レフの
フルサイズ化戦略と、後年2018年~2019年の
主にミラーレス機のフルサイズ化戦略は、どちらも、
「市場を盛り上げようとする」意図が私には感じられる。
つまり、1社だけで「フルサイズになりました」と
言っても、市場に与える影響は無いが、「全社一斉に」
となると、これまでのカメラユーザーに対しても
「もう、カメラはフルサイズの時代です!」と強く
訴求できるし、カメラの事に詳しく無い一般消費者に
対してすらも大きな話題性がある。
事実、2018年のカメラショーには、TV局が取材に来て、
長蛇の列となっている新鋭フルサイズカメラのブースで、
そこで、カメラの事を、まるっきり何も知らないといった
様子の見学者を捕まえてインタビューをしていた模様が
TVニュースで流れていた、その内容だが・・・
TV「どのカメラを見に来たのですか?」
客「フルサイズですよ、やっぱ、フルサイズは
良いですね・・」
あまりの馬鹿馬鹿しさに、私は、思わずニュースの
チャンネルを変えてしまった。
だって、これでは、何もわかっていない人達が、単なる
「お祭り騒ぎ」に乗せられているだけでは無いか!
例えば、マイナーなスポーツ競技でも、滅多に進めない
世界大会へ決勝進出するとなったら、各TV局がこぞって
それを放映し、競技のルールもわかっていない「にわか
ファン」が急増し、会場に足を運んだり、グッズを購入
したりする。まあ、それも作られた「流行」であろうし
その裏には、それを「ビジネス」として成り立たせようと
する意図がある。まあ、それが真の目的であり、むしろ
現代の世情では、「いかにして流行を作り出すか?」が
ビジネスモデルや市場戦略の根幹となっている。
まあ、それはその通りだろうが・・ 個人的には、その
戦略に乗せられる事は好まない。
で、それで50万円もする新鋭フルサイズ機を買うのだ、
繰り返すが、何もカメラの事を知らないユーザーが、だ。
まあ、逆に、何も知らないから、50万円の価格が
異常なまでに高価すぎる事に気づかないのであろう。
でも、こういう売り方って、公正なのだろうか・・?
さて、PENTAXは、2012年のフルサイズ・フィーバー
を見て困ってしまった。
それまでのPENTAX QやQ10が、1/2.3型機であった
事への、ユーザー層の不満が出てきているのだ。
「フルサイズ機の方が良い」等の、詳しい理由すら
良くわからない常識が、市場での情報戦略により、
2012年頃にビギナー層の間で蔓延してしまったのだ。
すると、ちょっとめざといビギナーは、こう言う
「QやQ10は、コンパクト機と同じ1/2.3型の小型
センサーだ、そんなカメラ、良く写る訳が無い」
PENTAXは、この市場状況の変化を感じて、2013年に
PENTAX Q7(今回使用機)を発売、そこでは
1/1.7型と、心持ちセンサーが大型化された。
なお、色々と言っているのは全てビギナー層であるから、
フルサイズ、1/1.7型、1/2.3型に、どれくらいの差
があるのかは知らない。センサー面積の差、画素数の差
ピクセルピッチの差、必要イメージサークル、設計上での
収差補正の困難度合い、使用するレンズの必要解像力・・
ビギナーはもとより、殆どのユーザー層は、このあたり
全般を理解していない。
いや、逆に言えば、細かい事がわからないから、単純に
「フルサイズ機が良い」と思い込んでしまうのだろう。
さて、レンズ交換型のカメラのセンサーサイズを途中
で変える、というのは大英断だ。後年のSONYの例では、
レンズの型番で、対応カメラが明確に区別できるが、
PENTAX Qの場合は、そうでは無い。同じ既存レンズで、
1/2.3型と1/1.7型とを両方対応させなければならない。
すると、イメージサークルだとか、換算画角とか
手ブレ補正の駆動角度とか、面倒な問題が沢山出てくる。
PENTAXはこの課題に対応する為に非常に複雑な内部処理
を行っている模様だ。その詳細については冗長になる為、
(まあ、Web等で参照可能だ)割愛するが・・
私の個人的な感覚では、その複雑な内部処理/画像処理が、
どうも正しく動作していない雰囲気を感じる。
まあ、その検証の為には、かなり専門的かつメーカー内部の
人でしかわかりようの無い手法を行わなければならないが、
勿論、ユーザー側では、そこまでは無理だ。
だから、あくまで「なんとなく、おかしい」としておこう。
でもまあ、あくまで今回使用のレンズは「トイレンズ」
である、仮に内部画像処理に不具合があって描写が不自然に
なったとしても、何も問題にはならない。
いや、むしろそれは望むところであり「アンコントローラブル」
な特性(匠の用語辞典第21回)は、Lo-Fi写真(同、5回記事)
においては、大歓迎だ。
----
さて、4本目の85mm級レンズ。
![_c0032138_17175338.jpg]()
(中古購入価格 22,000円)
カメラは、PENTAX K-01(APS-C機)
2006年発売のAF単焦点中望遠レンズ。
実焦点距離は70mmであるが、APS-C機専用の為、
換算焦点距離(画角)は105mm相当となる。
![_c0032138_17175302.jpg]()
高描写力の物がとても多いので、それらと比べると
わざわざ本レンズを選択する必然性があまり無い。
それから、初級中級層では、「開放F値の明るい
レンズの方が常に高描写力だ」という誤解を持って
いるので、そういう視点では本レンズは買い難い。
まあ、「とてつもなく小型だ」というのが本レンズ
の最大の特徴であろう。見た目ではこれが中望遠
レンズだ、とは思えず、あえて呼ぶならば「望遠
パンケーキ」という感じだ。
なお、本レンズは、数年前2000年代初頭発売の
「Voigtlander COLOR-HELIAR 75mm/f2.5 SL」
と「内部光学系が同じ」という噂がマニア層の間で
流れていて、私はCOLOR-HELIARを愛用していた為、
その噂に惑わされて「同じならば2本は不用か・・」
と、ずいぶんと本レンズの購入が遅れてしまった。
だが、実際に購入してみると両レンズは「用途開発」
視点での特徴が、まるで異なる事が判明、噂を気にして
本レンズの購入が遅れた事を、ちょっと後悔している。
その詳細については、本シリーズ第49回記事において
両レンズの用途上の差異を詳しく解説している。
なお、光学系コピーの件については、その後の
私の研究により、真相としては、両レンズとも、
完成度の極めて高い銀塩時代の50mm/F1.7レンズの
光学系を、それぞれ1.4倍、1.5倍に、拡大コピーして
設計された「ジェネリック・レンズ」であったから、
だと思われる。つまり、普遍的な設計手法により、
両者は偶々同じような光学系になっただけであろう。
(それを言うならば、銀塩用AF/MFの50mm/F1.7
級レンズは、各社とも、殆ど同じ光学系設計だ)
それから、「レンズ構成図」は、サイズ感がまるで
わからないし、硝材の特性(屈折率や色分散)も
全く記載されていないので、それだけを見ても、
同じ光学系かどうかは判断できないし、他社の
レンズ構成を図面からコピーして作る事も困難だ。
(→よって、各社とも堂々とレンズ構成図を公開
している)
----
さて、5本目の85mm(級)レンズ。
![_c0032138_17180947.jpg]()
(中古購入価格 28,000円)
カメラは、EOS 6D (フルサイズ機)
2006年発売のフルサイズ対応中望遠AF等倍マクロレンズ。
前記事で紹介した「SIGMA 70mm/f2.8 DG MACRO | Art」
が2代目「カミソリマクロ」であるならば、本レンズが
元祖「カミソリマクロ」である。
![_c0032138_17180911.jpg]()
マクロレンズは、優秀な描写特性を持つものが殆ど
であるから、特にこの70mmのシリーズだけを指して
カミソリとかと言うのは、どうなのだろうか?
いつも思うのだが、上級マニアとか評論家等では、
「たった1本のレンズだけを見て、その特性が完璧に
把握できるのだろうか?」という疑問がある。
それではまるで、ワインとかウィスキーを1杯だけ
試飲して、産地がどこで、どんな風味があって、
どんな特徴があるから、だから評価は何点だ、と、
そんな風な、超人的とも言える専門性と「絶対的評価
感覚/能力」を持つ事と同じようなものだと思う。
そういう専門家(上級ソムリエ等)は、実在はするで
あろうが、まあ、一般的には、そんな事はまず無理だ。
で、私が良く言う「マニアの条件」である「トリプル
スリーの法則」では、
1、30本(台)以上のレンズ・カメラ機材を所有し
2、30年以上前に発売された古い機材から、現代の
新鋭機材に至るまでの使用経験があり
3、年間3万枚以上の写真を撮影する事
であるが、
恐らくだが「絶対的評価感覚」を、少しでも持てる
ようにするには、上記「トリプルスリーの法則」を
さらにヒトケタからフタケタ嵩上げした難しい条件を
クリアする必要があるのではなかろうか?
具体的には、以下のレベルだ、
1、300本(台)以上の機材所有
2、30年間以上の実際の撮影経験
3、合計300万枚以上の実際の撮影経験
でも、これ位やっても、まだまだ「絶対的評価感覚」
は身に付かないかも知れない・・
で、私の個人的な目標値は、もっと上にあり、
「500本、50年、500万枚」が今のところの目標だ。
ただまあ、「相対的評価感覚」だったら、そこまで
精進しなくても、一般人でも身につける事が出来る
かも知れない。具体的には、ウイスキーの飲み比べを
すれば、「どっちが美味しい」とか、そこまでいかず
とも「どっちが好みだ」とか、それはわかるであろう。
レンズも同様、「カミソリマクロ」と言うならば、
他社の、あるいは他のマクロと徹底的に撮り比べて
見たら良い。そうやって「相対的」に評価して、
その上で、本レンズEX型や後継のART型において、
カミソリ的な「キレ」を感じるのであれば、もう
それはそれで個人の評価内容としては十分だと思う。
繰り返すが、本レンズ1本だけを見て「カミソリだ」
とかは言えない筈だ。そしてこれは本レンズに限らず
あらゆるレンズやカメラでも同様な話であり、
1本や2本のレンズを所有しただけで、「これは凄い」
とか「神レンズだ」とかは、そう評価する事は絶対に
無理な話だと思う。
ましてや、機材を借りて来て短期間だけ使っただけでは
その評価など、出来る筈も無いし、やってはならない
事だとも思う。
カメラの話では無いが、先年、文房具の市場分野で、
専門家と称する人達が集まり、年間の新製品の大賞を
決めるイベントが雑誌に載っていたのだが、その審査員、
つまり専門家(?)は、そこにノミネートされている商品を
誰も自分では買っていなかった。
で、評価コメントに「この商品だったら買っても良いと
思った」という文章を読んだ時、私は「ふざけるな!」
と憤慨してしまった。
文房具のプロ、つまり、そのジャンルを生業として
いるのであれば、全ての気になる(目についた)商品を
自分で購入し、徹底的に長期に渡って評価するべきで
あろう、それは、そういう仕事をする上での「必須要件」
だろうし、「必要経費」であり「設備投資」でもある。
それをやっていないで、比較する商品も何も持って
いなければ、新製品の良し悪しなど、分かるはずも無い。
また、自分の財布から一切お金を出さずして、商品の
購入者の気持ちなど、絶対に分かるはずも無い。
そもそも、殆ど何も商品を買わずして、専門家と言える
のだろうか?
ちなみに、その文房具の雑誌は、不快になったので
すぐに捨てて、私は私なりの評価基準で、自分の好きな
高品質のボールペンを何種類か買う事にした・・
----
では、6本目の(換算)85mm(級)レンズ。
![_c0032138_17181030.jpg]()
(注:言語の変母音は省略)(新品購入価格 90,000円)
カメラは、PANASONIC DMC-G5 (μ4/3機)
2013年発売のμ4/3機専用超大口径MF中望遠画角レンズ。
中途半端な焦点距離ではあるが、μ4/3で2倍するので
換算85mm相当になる。
![_c0032138_17181025.jpg]()
なレンズだ、しかも使いこなしが相当に難しく、
本シリーズ第12回「使いこなしが困難なレンズ」編で、
堂々の(?)ワースト2位をマークしている(汗)
超大口径による、肉眼とは全く異なる雰囲気を「創造」
する事ができる極めて特異なレンズではあるが・・
このマニアック度の高さと、使いこなしの難しさから
言えば、一般層に対しては、全く推奨できない。
典型的な「上級マニア御用達」レンズと言えよう。
ちなみに「御用達」は、「ごようたし」と読むのが
ごくごく一般的だが、最近の広辞苑等では「ごようたつ」
も「可」とされているようだ。
だがまあ、殆どの人達は「ごようたし」と読むように、と
学んできていると思うので、これを「ごようたつ」と読んで
しまうタレントやコメンテーターは「間違って読んでいる」
と思われてしまい、「もしかして無学なのでは?」と、
評判を落としてしまう事も実際にあった模様で、要注意だ。
----
さて、7本目の85mm(級)レンズ。
![_c0032138_17182690.jpg]()
(中古購入価格 59,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1(μ4/3機)
2012年に発売されたμ4/3機専用中望遠AF単焦点レンズ。
![_c0032138_17182629.jpg]()
まず、母艦のμ4/3機のAF性能が芳しく無い。
最新のμ4/3機を所有していないので何とも言えない
部分があるが、ハイエンド機であるOM-D E-M1の
像面位相差AFでも、ちょっと不足する感覚がある。
本来ならば、MFで使ってしまえば、AFの課題などは
どうでも良いのだが、本レンズの場合、無限回転式
ピントリング仕様により、MF性能が壊滅的にNGだ。
優秀な描写力を誇るレンズなのに、カメラやレンズの
仕様により、そのパフォーマンスが発揮できないのは
とても惜しい、まあ、もうしばらくの間、母艦となる
μ4/3機のAF性能が向上するのを待つとしよう。
(追記:記事執筆後に、2台ほど新鋭μ4/3機を
購入しているが、目に見えるほどのAF性能の改善は
少なくとも、本レンズとの組み合わせでは無かった)
----
さて、8本目の85mmレンズ。
![_c0032138_17182622.jpg]()
(中古購入価格 16,000円)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
詳細不明、恐らくは1980年代~1990年代位の
MF中望遠ソフトフォーカス(軟焦点)レンズ。
![_c0032138_17182648.jpg]()
(フォーカス)レンズは、1本も無い状況なので、
必要とするならば、過去に発売されていた製品を
中古で購入するか、あるいは、現代でもレンズ専業
メーカー(LENSBABY、LOMO、安原製作所等)から、
僅かに数機種のみ発売されているソフトフォーカス
レンズを購入するしか無い。
まあ、現代において新製品が殆ど無いのは、
画像編集(レタッチ)、(物理)ソフトフィルター、
カメラ内エフェクト、等のいずれでもソフト効果が
実現できるからであろう。ただ、いつもソフトレンズ
の記事で述べているように、ホンモノのソフトレンズ
と、その他の手法による後付効果は、まるで異なる。
機会があれば、実際にソフトフォーカスレンズを
購入してみるのも悪く無いであろう。
ソフト・エフェクト等とはまるで異なる描写表現に
ある意味、驚きがあるかも知れない。
(参考記事:特殊レンズ第7回ソフトレンズ編)
----
では、9本目の85mmレンズ。
![_c0032138_17183922.jpg]()
(新品購入価格 5,000円)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
1960(?)~1980年代(?)頃のロシア(旧ソビエト連邦)
製MF中望遠レンズ。
![_c0032138_17183972.jpg]()
仕様は様々であるが、本レンズはM42マウント版
(東独の「プラクティカ」がM42の元祖だ)であり、
恐らくは1960年代(1970年代?)頃に、光学系を
従来品から、やや変更して設計され(注:一眼レフで
伸びた、バックフォーカスへの対応の為か?)
これも恐らくだが、1990年頃のソビエト崩壊の
時代迄、ロシアの国営工場等で生産が続いたレンズ
であろう。
まあ、当時の東側(共産圏)の情報は殆ど無いので
いずれも様々な状況の分析からの推測である。
ソビエト崩壊後に、しばらくして日本では第一次中古
カメラブームが起こった。その当時は、東京等にも
ロシアンレンズ専門店の実店舗(KING-2等)があり、
ロシアの旧国営工場等からの在庫品を輸入販売して
いたりもした。(参考:2010年代後半では、熊本の
GIZMO社も、同様にロシアの工場在庫レンズを輸入
販売した事がある)
本Jupiter-9も東京での購入だ。当時の新品価格は
僅かに5000円、その後すぐに6500円に値上げされた
のだが、さらに後年では、もう新品在庫が無く、
その割には、マニア層に非常に著名なレンズの為、
相場は際限なく高騰、2010年頃には1万円台後半に、
2020年頃には3万円台前半までに高価になっている。
まあ、ベテランマニアからすれば、新品5000円の
時代を知っているならば、いくらなんでも、その
7倍以上もの価格で買うという事態は考え難い。
つまり、「ロシアンは、安価に往年の銘レンズの
特性(雰囲気)を体感できる」という事が全てであり、
それ以上でも、それ以下でも無いと思う。
新規マニア等が、先輩マニア層から伝え聞くような
「ロシアンレンズは良く写る」という話は、そのまま
額面どおりに解釈してはならない。
(参考記事:本シリーズ第33/34回、特殊レンズ第4回
ハイコスパ第19回の各記事での「ロシアン編」、
その他、本シリーズ第39回、第43回、第44回等)
----
では、今回ラストの85mmレンズ。
![_c0032138_17183935.jpg]()
(新品購入価格 22,000円)
カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)
2014年発売の中国製MF中望遠レンズ。
CREATORシリーズには、35mm/F2、85mm/F2、
135mm/F2.8(Ⅱ)の3機種が存在している。
(全て所有しており、過去記事で紹介済み)
各種一眼レフ用マウントや一部のミラーレス機用(FE)
マウント版が存在し、いずれもフルサイズ対応のMF
レンズだ。
コツとしては、NIKON Fマウント版で購入すれば、
およそあらゆるミラーレス機や、一部の他社一眼レフ
にも(アダプター経由で)装着可能である、私も全て
NIKON Fマウント版の購入だ。
ただし、Fマウント版であっても、NIKON製デジタル一眼
レフで使用するのは困難だ、何故ならば「非Ai」仕様で
ある為、一般的なNIKON機では露出が不安定となって
しまう。一応デジタル機ではNIKON Dfのみ、非Aiの
レンズが使用可能だが、使い難いという点は大差無い。
今回使用のように、アダプターを介して他社ミラーレス
機で使うのが賢明だ。
![_c0032138_17184086.jpg]()
一見して、銀塩MF時代のレンズのようだ。
しかし、どれも、比較的近年の光学設計であり、銀塩
MF時代の同等スペックのレンズとは一味違う。
それでいて安価なのも魅力ではあるが、場合により
銀塩MF時代の国産の同スペックのレンズの中古品よりも
高価になってしまう。
その点がネックとなっているのだろうか? CREATOR
シリーズは、マニア層等には、あまり人気が無い模様
である。
まあ「35mm、85mm,135mmとかは色々と持って
いるから、特に新しいのはいらんよ」となるのだろう。
だから、マニア層にも強く推奨できるレンズには
成り得ないのだが、もしたまたま中古等を見かけて、
安価に入手できるようであれば、購入の選択肢も
悪く無い。意外にまで良く写り、銀塩MF時代のレンズ
とは、ずいぶんと異なる事がわかるであろう。
---
では、本記事はこのあたりまでで、次回記事に続く。
今回の記事も補足編として「85mm(級)マニアックス
(2)」という主旨とする。
実焦点距離が85mm前後(概ね70mm~90mm)または、
APS-C機以下専用で、フルサイズ換算画角が85mm前後
のレンズの内、比較的マニアック(あまり有名では無い)
なものを20本集め、前後編で各10本づつを紹介して
いるが、今回は残りの10本だ。
----
ではまず、今回最初の85mmレンズ。

(中古購入価格 60,000円)
カメラは、NIKON D500 (APS-C機)
1981年頃に発売されたMF大口径中望遠レンズ。
銀塩時代から愛用しているレンズであるが・・
銀塩時代の1970年代~1980年代頃のNIKON NIKKOR
銘レンズの多くは解像力を優先した設計で、ボケ質等は
あまり配慮していないものが殆どであった。
その理由は、恐らくだが、当時のNIKON製品は、報道や
学術分野での利用が多く、そうであれば、その分野では
ともかく「被写体が、くっきり、はっきり写っている」
必要性があったからであろう。
解像感を優先すれば、他の様々な性能要素が犠牲に
なるのはやむを得ない。現代の超高性能レンズのように、
収差を限りなく補正する為に、同じ85mm/F1.4級レンズ
であっても、異常低分散ガラスや非球面レンズを多用した
十数群十数枚の複雑な光学(光路)設計をコンピューター
で行えるような時代では無いのだ。
当時は、非球面や新ガラスも無く(注:無い事は無いが、
非常に高価→Noct-NIKKOR 58mm/F1.2 1977年で使用)
また、光学設計も手計算で行わざるを得ない。であれば、
要求仕様における「何か」を優先すれば、他の要素は
犠牲になってしまう。
結局、こういう状況であったから、私は銀塩MF時代の
NIKKORレンズが、あまり好みでは無かった。つまり
「描写が固すぎる」という印象がとても強かったからだ。
だが、そういうNIKKORの中でも、稀にそうでは無い特性、
具体的には、解像感を若干犠牲にしても、ボケ質とかを
含めたトータルのバランスを重視する特性を持たせた
レンズが何本か存在している。
私の知っている範囲では、それは、さほど多くは無く、
本Ai85/1.4や、Ai105/1.8、Ai135/2、ED180/2.8
あたりだ。
(注:近年の「3次元的ハイファイ」設計のNIKKOR、
例:AF-S NIKKOR 58mm/F1.4G 2013年、等も同様
なコンセプトによる設計だ)

おける最大口径のレンズだ」という事だ。
それらが「バランス重視」の特性の設計になる理由は
2つ想像できる、
1、これらは、報道・学術用のレンズとは見なしておらず
アート、ファッション・ポートレート、自然撮影
が主目的であろう。(だから、カリカリな固い描写
傾向は、あまり望ましく無い)
2、口径比を明るくすると、諸収差のオンパレードとなり、
解像力を高める光学設計とする事が、そもそも難しい。
それから、本レンズの光学設計は、前記事で紹介した
CONTAX (RTS) Planar 85mm/F1.4のレンズ構成に似ている。
そちらのレンズは1975年発売、センセーショナルな特性で
「神格化」される程のレンズであったが、いくつかの
弱点を持ち、使いこなしが非常に難しいレンズであった。
それから6年の時が経過して発売の本Ai85/1.4である。
RTS P85/1.4程の使いこなしの難しさは本レンズには無い。
まあ、だから銀塩時代からずっと愛用している次第だが、
でも、別な言い方をすれば、RTS P85/1.4には
「条件が上手く揃った際での、爆発的な高描写力」という
切り札があったのだが、本Ai85/1.4には、それが無い。
いつでも無難に撮れるが、面白みは少ないかもしれない。
ただまあ、そこは写真を撮る環境や目的によりけりだ、
結局、「85mm/F1.4級は、1本だけ持っておけば済む」
という話にはならず、色々な特性のものを条件に合わせて
選択する必要性を感じている。(それと、現代の超高性能
レンズは、こういうレンズ毎の個性が無く、つまらない)
なお、RTS P85/1.4や本Ai85/1.4、それから他は未所有
ではあるが、この時代(1980年代前後)のMF85mm/F1.4
級レンズには、似たようなレンズ構成のものがあると思う。
よって近年、私は、これらを総称し「プラナー系85mm」
と呼んでいる。
「何故、そういう呼び名が必要なのか?」については、
近年、2019年頃に発売された、中国製レンズの
「七工匠55mm/F1.4」が、このようなプラナー系85mm
のレンズ構成を、2/3程度にダウンサイジングして設計
された「ジェネリック・レンズ」である事がわかった
からだ。だが、具体的に、どのレンズをベースとして
再設計したかはわからない、ジェネリック設計の場合、
バックフォーカスの調整等で、レンズ後群の構成を
変更する場合があるからだ。
だから、特に具体的なレンズ名は特定せずに、
「七工匠55mm/F1.4はプラナー系85mmレンズの
ジェネリック」と称している訳だ。
----
では、次の85mmレンズ。

(中古購入価格 16,000円)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
2010年に発売された、AF単焦点中望遠レンズ。
一応、SONYにおけるエントリーレンズではあるが、
他のDT型番のエントリーレンズとは異なり、本レンズ
はフルサイズ対応である。
(特殊レンズ第51回SONYエントリーレンズ編参照)
なお、85mm単焦点で、フルサイズ対応では無い
(つまり、APS-C機以下専用の)ものは、非常に
数が限られていて、記憶している限り3機種程度しか
無いと思う。この理由は「85mmは、フルサイズ機で
ポートレートに使うもの」という常識(思い込み)が
市場全般に根強いからであろう。
よって、85mmレンズを企画するならば、必然的に
フルサイズ対応のものしか作られない。

暗い為、浅い被写界深度を得にくいが、その点は
最短撮影距離が60cmと「焦点距離10倍則」を
下回って寄れる為、少しその不満は解消できる。
あまり明確な用途が無い点が課題のレンズだ。
SONY α(A)マウント機で純正の85mmは、他は高価な
ものばかりなので、これを低価格品として代用する事は
出来なくは無いが、どうしても大口径85mmを安価に
入手したいのであれば、SIGMAやTAMRONといった
サードパーティ製85mmもあるし(注:近年の機種では、
SONY Aマウント版は用意されていないケースが多い)
あるいは近接撮影を中望遠画角で行いたいならば、
同じくSIGMAやTAMRONの旧型中望遠マクロも、安価に
中古で入手は容易だ。
結局、本レンズには「用途不明」なところがあり、
それが本レンズにおける唯一にして最大の課題であろう。
----
では、3本目は換算85mm(級)トイレンズだ。

(中古購入価格 3,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
2011年発売の、PENTAX Qシステム専用トイレンズ、
(注:PENTAXではユニークレンズと称している)
換算画角は、装着するQ系機体により異なり、
約99mm相当:1/2.3型機:PENTAX Q,Q10
約83mm相当:1/1.7型機:PENTAX Q7,Q-S1
となる。

機種からセンサーサイズが変化している。
ちなみに、だいたい同じ時代での、SONY E(APS-C型)
から、SONY FE(フルサイズ)への変更であれば、
これは最初からNEX→αへの変更を意図して、マウント
廻りはフルサイズ用で設計していたし、レンズも明確に、
APS-C機用(E型番)と、フルサイズ用(FE型番)で区分
されていたのだが・・
このPENTAX Q系の場合は、そういう当初からの意図が
あまり無い状態で、センサーサイズを途中で大型化
したのかも知れない。
・・と言うのも、本レンズや初代PENTAX Qの発売年は、
東日本大震災のあった2011年だ。この年、他社の多く
は、製造や流通の課題と、世情や消費者心理を鑑みて、
あまりカメラ等の新発売を行っていない。
で、その間、研究開発は何をやっていたか?と言えば
多分、カメラのフルサイズ化に係わる開発であろう。
よって、翌年2012年には、私が「フルサイズ元年」
と呼んでいるくらい、一般層に向けてのフルサイズ
一眼レフが多数出揃った次第だ。
具体的には、CANON EOS-1DX,EOS 5D MarkⅢ,
EOS 6D,NIKON D4,D800/E,D600,SONY α99等が、
いずれも2012年の発売である。
又、翌々年2013年にはミラーレス機SONY α7/7R
も(NEXから変わり)フルサイズ化。
このように一気に市場がフルサイズ化したのは、
フルサイズの撮像センサー部品の製造が低価格化したか、
あるいは、もしかすると、それまで供給を渋っていた
センサー製造メーカーが、他社への供給を開始(解禁)
したから、かも知れない。
・・はたまた、この2012年~2013年の主に一眼レフの
フルサイズ化戦略と、後年2018年~2019年の
主にミラーレス機のフルサイズ化戦略は、どちらも、
「市場を盛り上げようとする」意図が私には感じられる。
つまり、1社だけで「フルサイズになりました」と
言っても、市場に与える影響は無いが、「全社一斉に」
となると、これまでのカメラユーザーに対しても
「もう、カメラはフルサイズの時代です!」と強く
訴求できるし、カメラの事に詳しく無い一般消費者に
対してすらも大きな話題性がある。
事実、2018年のカメラショーには、TV局が取材に来て、
長蛇の列となっている新鋭フルサイズカメラのブースで、
そこで、カメラの事を、まるっきり何も知らないといった
様子の見学者を捕まえてインタビューをしていた模様が
TVニュースで流れていた、その内容だが・・・
TV「どのカメラを見に来たのですか?」
客「フルサイズですよ、やっぱ、フルサイズは
良いですね・・」
あまりの馬鹿馬鹿しさに、私は、思わずニュースの
チャンネルを変えてしまった。
だって、これでは、何もわかっていない人達が、単なる
「お祭り騒ぎ」に乗せられているだけでは無いか!
例えば、マイナーなスポーツ競技でも、滅多に進めない
世界大会へ決勝進出するとなったら、各TV局がこぞって
それを放映し、競技のルールもわかっていない「にわか
ファン」が急増し、会場に足を運んだり、グッズを購入
したりする。まあ、それも作られた「流行」であろうし
その裏には、それを「ビジネス」として成り立たせようと
する意図がある。まあ、それが真の目的であり、むしろ
現代の世情では、「いかにして流行を作り出すか?」が
ビジネスモデルや市場戦略の根幹となっている。
まあ、それはその通りだろうが・・ 個人的には、その
戦略に乗せられる事は好まない。
で、それで50万円もする新鋭フルサイズ機を買うのだ、
繰り返すが、何もカメラの事を知らないユーザーが、だ。
まあ、逆に、何も知らないから、50万円の価格が
異常なまでに高価すぎる事に気づかないのであろう。
でも、こういう売り方って、公正なのだろうか・・?
さて、PENTAXは、2012年のフルサイズ・フィーバー
を見て困ってしまった。
それまでのPENTAX QやQ10が、1/2.3型機であった
事への、ユーザー層の不満が出てきているのだ。
「フルサイズ機の方が良い」等の、詳しい理由すら
良くわからない常識が、市場での情報戦略により、
2012年頃にビギナー層の間で蔓延してしまったのだ。
すると、ちょっとめざといビギナーは、こう言う
「QやQ10は、コンパクト機と同じ1/2.3型の小型
センサーだ、そんなカメラ、良く写る訳が無い」
PENTAXは、この市場状況の変化を感じて、2013年に
PENTAX Q7(今回使用機)を発売、そこでは
1/1.7型と、心持ちセンサーが大型化された。
なお、色々と言っているのは全てビギナー層であるから、
フルサイズ、1/1.7型、1/2.3型に、どれくらいの差
があるのかは知らない。センサー面積の差、画素数の差
ピクセルピッチの差、必要イメージサークル、設計上での
収差補正の困難度合い、使用するレンズの必要解像力・・
ビギナーはもとより、殆どのユーザー層は、このあたり
全般を理解していない。
いや、逆に言えば、細かい事がわからないから、単純に
「フルサイズ機が良い」と思い込んでしまうのだろう。
さて、レンズ交換型のカメラのセンサーサイズを途中
で変える、というのは大英断だ。後年のSONYの例では、
レンズの型番で、対応カメラが明確に区別できるが、
PENTAX Qの場合は、そうでは無い。同じ既存レンズで、
1/2.3型と1/1.7型とを両方対応させなければならない。
すると、イメージサークルだとか、換算画角とか
手ブレ補正の駆動角度とか、面倒な問題が沢山出てくる。
PENTAXはこの課題に対応する為に非常に複雑な内部処理
を行っている模様だ。その詳細については冗長になる為、
(まあ、Web等で参照可能だ)割愛するが・・
私の個人的な感覚では、その複雑な内部処理/画像処理が、
どうも正しく動作していない雰囲気を感じる。
まあ、その検証の為には、かなり専門的かつメーカー内部の
人でしかわかりようの無い手法を行わなければならないが、
勿論、ユーザー側では、そこまでは無理だ。
だから、あくまで「なんとなく、おかしい」としておこう。
でもまあ、あくまで今回使用のレンズは「トイレンズ」
である、仮に内部画像処理に不具合があって描写が不自然に
なったとしても、何も問題にはならない。
いや、むしろそれは望むところであり「アンコントローラブル」
な特性(匠の用語辞典第21回)は、Lo-Fi写真(同、5回記事)
においては、大歓迎だ。
----
さて、4本目の85mm級レンズ。

(中古購入価格 22,000円)
カメラは、PENTAX K-01(APS-C機)
2006年発売のAF単焦点中望遠レンズ。
実焦点距離は70mmであるが、APS-C機専用の為、
換算焦点距離(画角)は105mm相当となる。
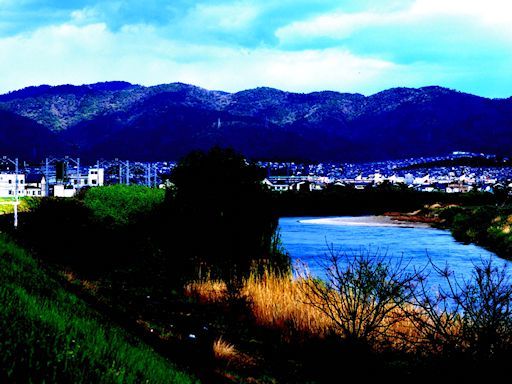
高描写力の物がとても多いので、それらと比べると
わざわざ本レンズを選択する必然性があまり無い。
それから、初級中級層では、「開放F値の明るい
レンズの方が常に高描写力だ」という誤解を持って
いるので、そういう視点では本レンズは買い難い。
まあ、「とてつもなく小型だ」というのが本レンズ
の最大の特徴であろう。見た目ではこれが中望遠
レンズだ、とは思えず、あえて呼ぶならば「望遠
パンケーキ」という感じだ。
なお、本レンズは、数年前2000年代初頭発売の
「Voigtlander COLOR-HELIAR 75mm/f2.5 SL」
と「内部光学系が同じ」という噂がマニア層の間で
流れていて、私はCOLOR-HELIARを愛用していた為、
その噂に惑わされて「同じならば2本は不用か・・」
と、ずいぶんと本レンズの購入が遅れてしまった。
だが、実際に購入してみると両レンズは「用途開発」
視点での特徴が、まるで異なる事が判明、噂を気にして
本レンズの購入が遅れた事を、ちょっと後悔している。
その詳細については、本シリーズ第49回記事において
両レンズの用途上の差異を詳しく解説している。
なお、光学系コピーの件については、その後の
私の研究により、真相としては、両レンズとも、
完成度の極めて高い銀塩時代の50mm/F1.7レンズの
光学系を、それぞれ1.4倍、1.5倍に、拡大コピーして
設計された「ジェネリック・レンズ」であったから、
だと思われる。つまり、普遍的な設計手法により、
両者は偶々同じような光学系になっただけであろう。
(それを言うならば、銀塩用AF/MFの50mm/F1.7
級レンズは、各社とも、殆ど同じ光学系設計だ)
それから、「レンズ構成図」は、サイズ感がまるで
わからないし、硝材の特性(屈折率や色分散)も
全く記載されていないので、それだけを見ても、
同じ光学系かどうかは判断できないし、他社の
レンズ構成を図面からコピーして作る事も困難だ。
(→よって、各社とも堂々とレンズ構成図を公開
している)
----
さて、5本目の85mm(級)レンズ。

(中古購入価格 28,000円)
カメラは、EOS 6D (フルサイズ機)
2006年発売のフルサイズ対応中望遠AF等倍マクロレンズ。
前記事で紹介した「SIGMA 70mm/f2.8 DG MACRO | Art」
が2代目「カミソリマクロ」であるならば、本レンズが
元祖「カミソリマクロ」である。

マクロレンズは、優秀な描写特性を持つものが殆ど
であるから、特にこの70mmのシリーズだけを指して
カミソリとかと言うのは、どうなのだろうか?
いつも思うのだが、上級マニアとか評論家等では、
「たった1本のレンズだけを見て、その特性が完璧に
把握できるのだろうか?」という疑問がある。
それではまるで、ワインとかウィスキーを1杯だけ
試飲して、産地がどこで、どんな風味があって、
どんな特徴があるから、だから評価は何点だ、と、
そんな風な、超人的とも言える専門性と「絶対的評価
感覚/能力」を持つ事と同じようなものだと思う。
そういう専門家(上級ソムリエ等)は、実在はするで
あろうが、まあ、一般的には、そんな事はまず無理だ。
で、私が良く言う「マニアの条件」である「トリプル
スリーの法則」では、
1、30本(台)以上のレンズ・カメラ機材を所有し
2、30年以上前に発売された古い機材から、現代の
新鋭機材に至るまでの使用経験があり
3、年間3万枚以上の写真を撮影する事
であるが、
恐らくだが「絶対的評価感覚」を、少しでも持てる
ようにするには、上記「トリプルスリーの法則」を
さらにヒトケタからフタケタ嵩上げした難しい条件を
クリアする必要があるのではなかろうか?
具体的には、以下のレベルだ、
1、300本(台)以上の機材所有
2、30年間以上の実際の撮影経験
3、合計300万枚以上の実際の撮影経験
でも、これ位やっても、まだまだ「絶対的評価感覚」
は身に付かないかも知れない・・
で、私の個人的な目標値は、もっと上にあり、
「500本、50年、500万枚」が今のところの目標だ。
ただまあ、「相対的評価感覚」だったら、そこまで
精進しなくても、一般人でも身につける事が出来る
かも知れない。具体的には、ウイスキーの飲み比べを
すれば、「どっちが美味しい」とか、そこまでいかず
とも「どっちが好みだ」とか、それはわかるであろう。
レンズも同様、「カミソリマクロ」と言うならば、
他社の、あるいは他のマクロと徹底的に撮り比べて
見たら良い。そうやって「相対的」に評価して、
その上で、本レンズEX型や後継のART型において、
カミソリ的な「キレ」を感じるのであれば、もう
それはそれで個人の評価内容としては十分だと思う。
繰り返すが、本レンズ1本だけを見て「カミソリだ」
とかは言えない筈だ。そしてこれは本レンズに限らず
あらゆるレンズやカメラでも同様な話であり、
1本や2本のレンズを所有しただけで、「これは凄い」
とか「神レンズだ」とかは、そう評価する事は絶対に
無理な話だと思う。
ましてや、機材を借りて来て短期間だけ使っただけでは
その評価など、出来る筈も無いし、やってはならない
事だとも思う。
カメラの話では無いが、先年、文房具の市場分野で、
専門家と称する人達が集まり、年間の新製品の大賞を
決めるイベントが雑誌に載っていたのだが、その審査員、
つまり専門家(?)は、そこにノミネートされている商品を
誰も自分では買っていなかった。
で、評価コメントに「この商品だったら買っても良いと
思った」という文章を読んだ時、私は「ふざけるな!」
と憤慨してしまった。
文房具のプロ、つまり、そのジャンルを生業として
いるのであれば、全ての気になる(目についた)商品を
自分で購入し、徹底的に長期に渡って評価するべきで
あろう、それは、そういう仕事をする上での「必須要件」
だろうし、「必要経費」であり「設備投資」でもある。
それをやっていないで、比較する商品も何も持って
いなければ、新製品の良し悪しなど、分かるはずも無い。
また、自分の財布から一切お金を出さずして、商品の
購入者の気持ちなど、絶対に分かるはずも無い。
そもそも、殆ど何も商品を買わずして、専門家と言える
のだろうか?
ちなみに、その文房具の雑誌は、不快になったので
すぐに捨てて、私は私なりの評価基準で、自分の好きな
高品質のボールペンを何種類か買う事にした・・
----
では、6本目の(換算)85mm(級)レンズ。

(注:言語の変母音は省略)(新品購入価格 90,000円)
カメラは、PANASONIC DMC-G5 (μ4/3機)
2013年発売のμ4/3機専用超大口径MF中望遠画角レンズ。
中途半端な焦点距離ではあるが、μ4/3で2倍するので
換算85mm相当になる。

なレンズだ、しかも使いこなしが相当に難しく、
本シリーズ第12回「使いこなしが困難なレンズ」編で、
堂々の(?)ワースト2位をマークしている(汗)
超大口径による、肉眼とは全く異なる雰囲気を「創造」
する事ができる極めて特異なレンズではあるが・・
このマニアック度の高さと、使いこなしの難しさから
言えば、一般層に対しては、全く推奨できない。
典型的な「上級マニア御用達」レンズと言えよう。
ちなみに「御用達」は、「ごようたし」と読むのが
ごくごく一般的だが、最近の広辞苑等では「ごようたつ」
も「可」とされているようだ。
だがまあ、殆どの人達は「ごようたし」と読むように、と
学んできていると思うので、これを「ごようたつ」と読んで
しまうタレントやコメンテーターは「間違って読んでいる」
と思われてしまい、「もしかして無学なのでは?」と、
評判を落としてしまう事も実際にあった模様で、要注意だ。
----
さて、7本目の85mm(級)レンズ。

(中古購入価格 59,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1(μ4/3機)
2012年に発売されたμ4/3機専用中望遠AF単焦点レンズ。

まず、母艦のμ4/3機のAF性能が芳しく無い。
最新のμ4/3機を所有していないので何とも言えない
部分があるが、ハイエンド機であるOM-D E-M1の
像面位相差AFでも、ちょっと不足する感覚がある。
本来ならば、MFで使ってしまえば、AFの課題などは
どうでも良いのだが、本レンズの場合、無限回転式
ピントリング仕様により、MF性能が壊滅的にNGだ。
優秀な描写力を誇るレンズなのに、カメラやレンズの
仕様により、そのパフォーマンスが発揮できないのは
とても惜しい、まあ、もうしばらくの間、母艦となる
μ4/3機のAF性能が向上するのを待つとしよう。
(追記:記事執筆後に、2台ほど新鋭μ4/3機を
購入しているが、目に見えるほどのAF性能の改善は
少なくとも、本レンズとの組み合わせでは無かった)
----
さて、8本目の85mmレンズ。

(中古購入価格 16,000円)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
詳細不明、恐らくは1980年代~1990年代位の
MF中望遠ソフトフォーカス(軟焦点)レンズ。

(フォーカス)レンズは、1本も無い状況なので、
必要とするならば、過去に発売されていた製品を
中古で購入するか、あるいは、現代でもレンズ専業
メーカー(LENSBABY、LOMO、安原製作所等)から、
僅かに数機種のみ発売されているソフトフォーカス
レンズを購入するしか無い。
まあ、現代において新製品が殆ど無いのは、
画像編集(レタッチ)、(物理)ソフトフィルター、
カメラ内エフェクト、等のいずれでもソフト効果が
実現できるからであろう。ただ、いつもソフトレンズ
の記事で述べているように、ホンモノのソフトレンズ
と、その他の手法による後付効果は、まるで異なる。
機会があれば、実際にソフトフォーカスレンズを
購入してみるのも悪く無いであろう。
ソフト・エフェクト等とはまるで異なる描写表現に
ある意味、驚きがあるかも知れない。
(参考記事:特殊レンズ第7回ソフトレンズ編)
----
では、9本目の85mmレンズ。

(新品購入価格 5,000円)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
1960(?)~1980年代(?)頃のロシア(旧ソビエト連邦)
製MF中望遠レンズ。

仕様は様々であるが、本レンズはM42マウント版
(東独の「プラクティカ」がM42の元祖だ)であり、
恐らくは1960年代(1970年代?)頃に、光学系を
従来品から、やや変更して設計され(注:一眼レフで
伸びた、バックフォーカスへの対応の為か?)
これも恐らくだが、1990年頃のソビエト崩壊の
時代迄、ロシアの国営工場等で生産が続いたレンズ
であろう。
まあ、当時の東側(共産圏)の情報は殆ど無いので
いずれも様々な状況の分析からの推測である。
ソビエト崩壊後に、しばらくして日本では第一次中古
カメラブームが起こった。その当時は、東京等にも
ロシアンレンズ専門店の実店舗(KING-2等)があり、
ロシアの旧国営工場等からの在庫品を輸入販売して
いたりもした。(参考:2010年代後半では、熊本の
GIZMO社も、同様にロシアの工場在庫レンズを輸入
販売した事がある)
本Jupiter-9も東京での購入だ。当時の新品価格は
僅かに5000円、その後すぐに6500円に値上げされた
のだが、さらに後年では、もう新品在庫が無く、
その割には、マニア層に非常に著名なレンズの為、
相場は際限なく高騰、2010年頃には1万円台後半に、
2020年頃には3万円台前半までに高価になっている。
まあ、ベテランマニアからすれば、新品5000円の
時代を知っているならば、いくらなんでも、その
7倍以上もの価格で買うという事態は考え難い。
つまり、「ロシアンは、安価に往年の銘レンズの
特性(雰囲気)を体感できる」という事が全てであり、
それ以上でも、それ以下でも無いと思う。
新規マニア等が、先輩マニア層から伝え聞くような
「ロシアンレンズは良く写る」という話は、そのまま
額面どおりに解釈してはならない。
(参考記事:本シリーズ第33/34回、特殊レンズ第4回
ハイコスパ第19回の各記事での「ロシアン編」、
その他、本シリーズ第39回、第43回、第44回等)
----
では、今回ラストの85mmレンズ。

(新品購入価格 22,000円)
カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)
2014年発売の中国製MF中望遠レンズ。
CREATORシリーズには、35mm/F2、85mm/F2、
135mm/F2.8(Ⅱ)の3機種が存在している。
(全て所有しており、過去記事で紹介済み)
各種一眼レフ用マウントや一部のミラーレス機用(FE)
マウント版が存在し、いずれもフルサイズ対応のMF
レンズだ。
コツとしては、NIKON Fマウント版で購入すれば、
およそあらゆるミラーレス機や、一部の他社一眼レフ
にも(アダプター経由で)装着可能である、私も全て
NIKON Fマウント版の購入だ。
ただし、Fマウント版であっても、NIKON製デジタル一眼
レフで使用するのは困難だ、何故ならば「非Ai」仕様で
ある為、一般的なNIKON機では露出が不安定となって
しまう。一応デジタル機ではNIKON Dfのみ、非Aiの
レンズが使用可能だが、使い難いという点は大差無い。
今回使用のように、アダプターを介して他社ミラーレス
機で使うのが賢明だ。
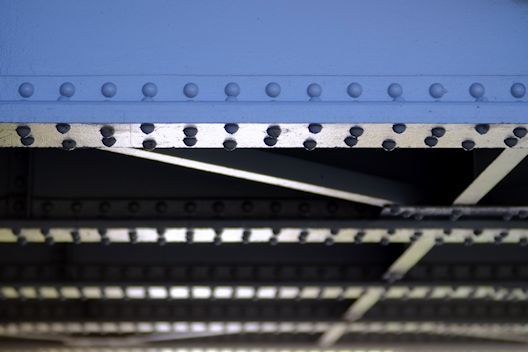
一見して、銀塩MF時代のレンズのようだ。
しかし、どれも、比較的近年の光学設計であり、銀塩
MF時代の同等スペックのレンズとは一味違う。
それでいて安価なのも魅力ではあるが、場合により
銀塩MF時代の国産の同スペックのレンズの中古品よりも
高価になってしまう。
その点がネックとなっているのだろうか? CREATOR
シリーズは、マニア層等には、あまり人気が無い模様
である。
まあ「35mm、85mm,135mmとかは色々と持って
いるから、特に新しいのはいらんよ」となるのだろう。
だから、マニア層にも強く推奨できるレンズには
成り得ないのだが、もしたまたま中古等を見かけて、
安価に入手できるようであれば、購入の選択肢も
悪く無い。意外にまで良く写り、銀塩MF時代のレンズ
とは、ずいぶんと異なる事がわかるであろう。
---
では、本記事はこのあたりまでで、次回記事に続く。