さて、新シリーズの開始である。
本シリーズは、所有している古いデジタルカメラを、
時代およびカテゴリー(一眼レフ、コンパクト機、
ミラーレス機)で分類して、順次紹介していく記事群
である。
![_c0032138_06475000.jpg]()
とする。古い時代のデジタルカメラの性能は、現代の
ものに比べて見劣りするのは当然であり、その為に
旧機種は、急速に実用範囲以下のレベルとなり、
不人気にもなってしまうので、今更、古いカメラの
性能/仕様等の詳細を述べても無意味であろう。
よって、このシリーズは、時代背景、市場の状況、
メーカー間のライバル関係等の事情により、何故
そのカメラが生まれてきたのか? 等の歴史的な
説明を主体としたり、古いカメラを、今なお使い
続けるのは何故か?というあたりにも着目する
記事群とする。
また、隠れたテーマとして
「オールドレンズは人気があるのに、何故オールド
デジカメは不人気なのか?」という点も、とても
重要な分析内容である。これは簡単には答えが出て
くるものでは無いから、シリーズ途中や終盤において
少しづつ纏めていく事にする。
では、今回第1回目だが、「デジタル一眼レフ編」
として、2000年~2004年の期間に発売された
(オールド)デジタル一眼レフを4機種紹介する。
なお、この時代ではデジタル一眼レフ専用のレンズ
は、殆ど発売されていない為、ユーザー層は、皆、
銀塩一眼レフ用のAF(稀にMF)レンズを、そのまま
デジタル機に装着して使っていたので、本記事でも
時代背景を鑑みて、その用法に従う事とする。
(つまり、今回使用のシステムは、オールドデジタル
一眼レフ+銀塩用AFレンズ、という組み合わせとする)
以降、そのオールド一眼レフと銀塩時代のAFレンズでの
実写をはさんで記事を進めていくが、掲載写真はカメラ
本体の写真を除き、そのシステムで撮影したものとする。
ただし、当該カメラ内に備わっている機能(エフェクト
やHDR合成、テレコン等)は、自由に使用可とする。
(しかし、この時代のカメラには、まだその手の機能は
搭載されていなかったので、これは後年の機種の話だ)
それと、PCによる写真の後編集は、僅かな「輝度調整、
構図調整のトリミング、縮小」という限定範囲に留め、
過度な編集を禁ずるルールとする。(注:JPEGのみで
あり、RAW現像は一切使用しない)あまり、こねくり
廻してしまうと、本来のカメラやレンズの性能が
わからなくなり、紹介記事の意味が無いからである。
まあでも、こうした紹介記事以外では、レタッチ編集
をする事は、現代においては、必然の処置ではある。
(注:今回の記事の時代では「カメラマン」と言っても
パソコンを触れない人達が大半であった為、この頃は
「レタッチ編集をするのは邪道だ!」とかいった、自身の
問題を正当化しようとする発言がとても多い世情であった)
そして、今回は古い時代のカメラやレンズを使うので、
それなりに写りは悪くなるが、それも当然であり、
その「程度」を検証する目的もある。
でも、オールドカメラ+古いレンズだから、と言って
「ダメダメの酷い写り」にはならない事実を提示する
事も、本シリーズ記事の目的もなっている。
---
では始めよう、最初は、最も古い時代の(初の?)
実用的デジタル一眼レフである。
![_c0032138_06475003.jpg]()
(2000年発売、定価358,000円+税)
(中古購入価格 70,000円、税込み。以下全て税込)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第23回
レンズは、CANON EF50mm/f1.8(Ⅰ/初期型)
(1987年)を使用する。
本機の型番は「D30」であり、他のEOS機の後年の
機種(例:EOS-1D、EOS 30D)とは、型番のルール
が異なっている。
この型番の流れは「D60」(2002年)まで続いた後、
「10D」(2003年)からは、全てのCANON EOS
デジタル一眼レフ(注:Kiss系とミラーレス機を除く)
では、型番の数字の後に「D」をつける事に統一
された模様だ。
なお、銀塩時代より、デジタル一眼やミラーレス機に、
至るまで、EOS-1、EOS-3系機体のみが型番にハイフン
が入り、他は入らない(例:EOS Kiss、EOS 7、
EOS 5D、EOS 8000D、EOS M5、EOS RP等)
そしてハイフンが入らない場合は、空白(スペース)
を替わりに入れるので、EOS90D等の記載は誤りだ。
また、3番機ではあるが、(新鋭の)EOS R3には、
ハイフンは入らない。
![_c0032138_06475092.jpg]()
1990年代から、CANONは米国KODAK社と提携して、
デジタル一眼レフの試作開発を続けていた。
1995年~1998年の間で、EOS DCS3、EOS DCS1、
EOS D2000、EOS D6000の4機種が発売されたが
いずれも試作機的、かつ非常に高価であったので、
報道や学術等の専門的分野向けであり、これらは
まだ一般層が買えるものでは無かった。
(この当時は、「1万画素あたり1万円」とも
言われていた。つまり200万画素機は200万円だ!)
その後、CANONはCMOS撮像センサーを自社開発する
方針に転換し(恐らくはKODAKとの提携も解消され、
KODAKは、OLYMPUSへ4/3型CCDセンサーを供給して、
2003年のOLYMPUS E-1発売に繋がる歴史だろう。
ちなみに、何故フィルムメーカーの世界的大手で
あるKODAK社が撮像センサーを先行して開発していた
のかは?フィルムは、いずれデジタルに変遷する事が
明白であった為、早く(1970年代)からKODAKは
撮像センサーの研究開発に着手していた歴史がある)
・・それによる、CANON完全自社開発による、初の
機体が本機EOS D30(2000年)である。
かつ、価格も35万円台と、これまでは数百万円も
していた黎明期の試作デジタルEOSから比べて安価
となり、初めて一般層でも入手可能となった機体だ。
よって、本機の歴史的価値は非常に高い。
ただまあ、本機の前年の1999年には、NIKONより
NIKON D1(65万円)が発売されているので、
初のコンシュマー(一般消費者)向けの機体は、
そのNIKON D1だ、と定義できるかも知れない。
しかし、65万円は、依然高価すぎる状況だから、
個人的には、本機EOS D30を初の「一般機」
(民生機、コンシュマー機)と定義している次第だ。
だが、本機は不人気機種であった。記録画素数は
300万画素と低いし、連写性能等も非常に弱い。
旧来のEFマウント版(銀塩用)AFレンズが使える
とは言え、センサーサイズがAPS-C型だから画角も
ずいぶんと変わってしまう。(1.6倍相当)
描写力は、一部のユーザー層には「黄色く写る」と
酷く嫌われていた。(→誤解。詳細後述)
また、バッテリーの持ちも悪く、数百枚しか撮れず、
これは1日の撮影には持たないので、満充電をした
予備バッテリーの携行が必須だ。
おまけに、価格も銀塩EOS中高級機の3倍も高価だ。
まあ、これでは、銀塩一眼レフの方が、まだずっと
実用的なので、なかなか本機を欲しいと思う人は
現れない状態であったかも知れない。
![_c0032138_06475027.jpg]()
を見ても、現代において、あまりそういう印象は
持たない事であろう。
むしろ、この時代の多くのデジタル機の色味は、
「オリンパス・ブルー」というマニア用語に代表
されるように、青色が強い発色となる。
この理由は、当時の(KODAK製等の多くの)撮像センサー
においては、「短波長(青色等)の感度が低い」事への
対策で、青色域をエンハンス(増強)する特性(補正)
を加えているからだ、と思われる。
この措置により、2000年~2006年頃のデジタル機
(一眼レフ、コンパクト機)の多くに、こういう
「強い青味」を発する傾向が見られる。
(すなわち、オリンパス機だけの特徴では無い)
これにより、写真に写る青空等については、比較的
気持ちの良い青色描写が得られるのだが・・
しかし、青色エンハンス処理を施した機体では、
青色よりさらに短波長の、菫(すみれ)色や藍色
等の被写体を撮ると、実物とは似ても似つかぬ
不思議な色味となる。(注:それはそれで面白い)
まあつまり、「黄色く写る」とは、この当時の
デジタル機の背面(液晶)モニターが、技術的に
未成熟であり、解像度が低く、カラーバランスも
正しくないから、それを見ての「印象」に過ぎない
訳だ。
これは、笑ってしまう程の「酷い誤解」であり、
デジタルの原理も何もわかっていない状態なのだが、
銀塩カメラからデジタル機に持ち替えたばかりの
人達では、いくらマニアや上級層、職業写真家層で
あっても、「デジタルの事は、まるでわからない」
という時代背景からは、まあ、やむを得ない。
(注:パソコンにデジタル写真を取り込んで鑑賞や
編集をする事すら、この時代では殆ど行われていない。
つまり、カメラの背面モニター上でしか、撮影をした
写真を見ていなかった状況が大半だ)
ちなみに、カメラ背面モニター液晶の発色が良好に
なるのは、概ね2006年以降の話であり、さらに
後年の2014年前後からは、より鮮やかな発色となる。
前述のように、背面モニター上に映った再生画像
だけを見て「このカメラは色味が悪い」とかと言う
超ビギナー層が、現代においてもかなり多いから、
メーカー(または部品メーカー)としては、背面
モニター液晶やEVFの、発色や解像度等の改善は、
ずっと優先開発事項として捉えているのであろう。
(消費者層が、それだけを見て「良く写るカメラだ」
と誤解するから、そう思わせたい訳だ)
さらにちなみにだが、一般ユーザー層におけるカメラ
関連知識の不足は、デジタル化された近代だけが
顕著だった訳でもない。銀塩時代での類似の事例を
挙げれば、中古カメラブーム時に高い人気があった
「銀塩レンジファインダー機」の、光学的に素通しの
ファインダー/ビューファインダーの綺麗な映像を覗いて、
「このカメラは、良く写るのぅ」とかの感想を言い、
それらを購入した人達は大変多かった。
勿論、それはただ単にファインダー像が綺麗に見える
というだけの話であり、実際の写真における写りとは、
まるで無関係だ。
![_c0032138_06480198.jpg]()
実用性は極めて低い。この理由から本機を趣味撮影
等に持ち出す頻度も非常に低いし、総撮影枚数も
約20年間で1万数千枚と、かなり少ない状態だ。
ただ、近年においては、個人的な持論により、
「一旦購入した以上、たとえ実用性能に満たない
カメラやレンズでも、それを使いこなそうと
努力する事は、オーナー側の責務である」
と考えていて、本機も、ごく稀に持ち出すように
している。
その際、まあ、確かにカメラとしての実用性は
低いが、現代機ではまず見られない本機の独特な
青色発色傾向等は、「なかなか興味深い」という
印象に繋がり、「これをなんとか使えないか?」と、
ポジティブな考えに変わって来る次第だ。
---
では、次のオールド・デジタル一眼レフ。
![_c0032138_06480199.jpg]()
(2003年発売、定価490,000円+税)
(新品購入価格 128,000円)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第1回
レンズは、NIKON AiAF Micro-NIKKOR 60mm/f2.8D
(1993年)を使用する。
NIKONのデジタル初期の旗艦(フラッグシップ)機
でありながら、不当な悪評判が流れた事で、極めて
不人気となってしまった悲運の機体である。
![_c0032138_06480176.jpg]()
としてはトップクラス。かつ「ミラー像消失時間が
短い」という特徴を持つ為、連写中でのレンズのMF
操作も出来てしまう(→連写MFブラケット技法が可)
レリーズ・タイムラグ(シャッターボタンを押して
から、実際にシャッターが切れるまでの時間)は、
それ以前のAF一眼レフ、およびそれ以降のデジタル
一眼レフ全般を通じ、本機D2Hが、AF機史上最速の
37ms(0.037秒)である。
(注:ミラーレス機では、もっと速い)
まあつまり、「より素早く撮影する」為に特化した
実践派ユーザー好みの製品コンセプトであり、その
分野(速写性、即時性)の撮影を志向しない場合は
本機の特性は発揮できない。さらに言えば、銀塩
時代の同様のコンセプトの機体は、NIKON F5
(銀塩一眼第19回記事)等、ごく少数しか存在
しない特性であるから、一般層にこうした企画意図の
機体が受け入れられるかどうか?は微妙なところだ。
つまり、銀塩時代での一般的撮影では、三脚を立てて
じっくりと構図や光線状況を見ながら、ほんの数枚
だけ撮影する、というスタイルが大半であった所に・・
手持ちで、「あちらこちらの被写体にカメラを向けて
大量の写真を素早く撮る」という新たな撮影技法へは、
銀塩機から持ち替えたばかりの当時のユーザー層では、
そう簡単には転換できない、という事であっただろう。
見かけは同じ「カメラ」であっても、まるっきり
使い方が違う機械だ、考え方を180度変えない限り
本機D2Hの効果的な使用法にはならない。
(この、「全く考え方を変えなければ本機を使えない」
という点は、一般ユーザー層には理解不能であるから、
それが、本機に関する不当な悪評を広めた原因の1つ
になったのかもしれない・・)
そして、最大のポイントは、本機の撮像センサーが、
NIKON独自開発のLBCAST(JFET型CMOS)であった事だ。
これを新規開発した事で、「高速連写」と、当時の
カメラとしては最大感度であった「ISO6400」が
実現されている。ただし、記録画素数は上げられず、
僅かに約400万画素に留まっているし、本機の本体
だけでは、センサーの色味等の調整は殆ど出来ない。
これが、本機が市場で不人気となった原因であろう。
いわく「ノイズが酷い」「色味が悪い」等の、市場
での悪評判があった。
しかし、これについては、誤解または明確な理由が
ある、と私は分析している。
1)フィルム機から持ち替えたばかりのユーザー層
では高感度ノイズの発生原因や、その許容範囲を
理解していない。ISO6400の設定があれば、それを
目一杯使うのもやむを得ないであろうし、その状態で
「ノイズが多い」と評価するのも、当たり前の話だ。
2)NIKONのセンサー独自(自力)開発を、「脅威」と
見た対抗勢力、あるいは反対派等が、そうした
流言を流した可能性が高いと見ている。
(現代で言う、ネガティブ・キャンペーン)
3)センサーの色味や発色の調整は、後年であれば
ユーザー側で行うのが常識だ。しかしこの時代は
まだ銀塩時代の感覚であったから、「DPEは
カメラマンでは無く、写真屋さん(DPE担当者)
の仕事である」という意識が非常に強い。
まあ、「自分で調整したい」と思ったとしても、
本機D2Hに、その機能が無かった事も原因だろう。
この時代では、たとえ上級カメラマンであっても、
「画像編集ソフト」等は、誰も触ったことが無く、
持ってもいないし、使いこなせる人も居なかった。
・・という状況であり、本機D2Hは、不当な悪評に
より、市場での売れ行きが止まってしまった。
「NIKON D2」という機種が存在しない事も問題点で
あった事だろう。本機D2Hがいきなり新発売されれば、
一般消費者は、皆、「これが次世代の旗艦機か!?」
と思うだろうから、この機体が、これまでの銀塩時代
の常識の範疇では、全く使いこなす事が出来ない類の
”速写特化型の実用高速連写機”である事に気づかず、
「これは、きっと最高級の、ラグジュアリーなカメラ
だろう」と、消費者層は、皆、勘違いしていた訳だ。
また、高価すぎた(税込み50万円以上)のも、
売れない原因となった。
本機発売翌年の2004年頃には、各社から20万円を
切る実用的なデジタル一眼レフが入門機(普及機)
として、次々に発売された時代なのだ。
![_c0032138_06480237.jpg]()
本機の新品在庫を持て余したカメラ店から、大幅な
値引き販売提案があり、その提示金額をさらに
値切って(汗)128,000円(税込み)という、
とても安価な(実質、定価の1/4程度の価格)で
本機を新品購入できたので、まあ良かった。
ただまあ、実用的に本機の性能を発揮できる
撮影シーンが極めて少なかったのは課題であった。
スポーツ競技の業務撮影に持ち出した事も何度か
あったが、記録画素数が最大400万画素しか
無いのでは、写真納品時の要求画素数に満たない
場合も多々ある。(例:ポスター等には使えない)
後年には趣味撮影専用機としたが、そういう分野で
高速連写は、あまりにアンバランスな性能であろう。
本機の減価償却(撮影1枚あたりが3円となる事で
元を取ったと見なす、個人的なルール)の完了は
遅れに遅れ、購入後約15年を経過した2020年頃
までかかった。
これにより「デジタル機では仕様老朽化寿命が短い」
という点を痛感した。
つまり、カメラ自体は何も故障も無く動作している
のに、周囲の新鋭機に比べて、どんどんと仕様・性能的
に古く感じて、そのカメラを使いたく(持ち出したく)
無くなったり、実用的に使えなくなってしまうのだ。
この課題を鑑みて、「デジタル機ではフィルム時代の
常識は通用しない」という風にも思い、銀塩時代には
むしろ、「仕様老朽化寿命」が長い(=そう簡単には
新鋭機に見劣りせず、長く使える)と思って、好んで
多数購入した銀塩旗艦機(最高級機、ハイエンド機)は、
デジタルにおいては「旗艦機は、できるだけ購入しない」
という方針に転換。本機D2H以降、そのルールを遵守
するようにしている。(旗艦機は1台も買っていない。
まあつまり、趣味および業務上での実用機としては、
「上級機」と区分される機体が最も効率的である、
という持論を作り、それを実践している)
![_c0032138_06481132.jpg]()
と発色の面から、実用的には厳しい、という結論に
なるだろう。だが、本機での極めて快適な高速連写
性能は、その当時としては衝撃的なインパクトが
あった。そして、その快適性を、現代においても
得られる機体はそう多くは無い。例えばNIKON D500
や、CANON EOS 7D MarkⅡ(デジタル一眼レフ
第20回、第19回記事参照)あたりであろうか。
(注:近年では、電子(撮像素子)シャッターの
利用で、秒何十コマというカタログスペックを謳う
ミラーレス機が多いが、それらは、個人的には、
「実用的高速連写機」とは見なしていない。
一応、”秒60コマ連写”の機体は所有しているが、
「実用的に、その性能が使える」と思った事は一切
ない。所詮は、単なるカタログ性能だけの話だ)
真の「高速連写機」という物が、どういう類の機体
であるか?を体感したいのであれば、現代、稀に
見かける本機D2Hの中古品は、恐ろしく安価であり、
二束三文となっているので、研究用に購入してみる
のも悪く無いかも知れない。SNS用であれば400万
画素は十分であり、色味は、任意のレタッチソフト
で調整すれば良い。また、日中で低感度設定で使う
ならば、本機のノイズ性能は全く問題にはならない。
なお、D2Hの弱点として以下の2点を挙げておく。
1)高速連写音がとてもうるさく、使える状況が
限られてしまう(静かなイベントの記録撮影は不可)
2)背面液晶が製造後10年程から劣化していき、ほとんど
見えなくなる(注:他の2000年代NIKON機も同様)
---
では、3台目のオールド・デジタル一眼レフ。
![_c0032138_06481145.jpg]()
(2004年発売、発売時実勢価格約20万円)
(中古購入価格 90,000円)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第3回
レンズは、MINOLTA AF 100mm/f2
(推定1980年代末頃発売)を使用する。
MINOLTAがKONICAと合併(2003年)し、初めて
発売されたデジタル一眼レフが、本機α-7 DIGITAL
である。「世界初の内蔵手ブレ補正機能」を搭載した
センセーショナルな機体であり、MINOLTA時代から
の伝統的慣習に従い、革新的な機体の型番である
「7番機」を命名された(と思われる)
![_c0032138_06481173.jpg]()
次いでα-Sweet DIGITAL(2005年、故障廃棄)の
たった2機種のデジタル一眼レフが発売されただけで、
2006年には、α(カメラ、レンズ)の事業一式を
SONYに移管譲渡し、KONICA/MINOLTAは、その百年
以上にも及んだ写真(機)事業から撤退してしまう。
これはまあ、急激にデジタル化が進んだ事により、
これまでの銀塩時代のビジネスモデルや、あるいは
企画・研究・設計・開発・製造・販促・販売等の
全ての業務プロセスが、まるで変わってしまった事が
最大の原因であった事であろう。
当時のユーザー(コンシュマー)層は、呑気にも
「フィルムが不要になったカメラ」くらいにしか、
デジタル機の事を意識していなかったのかも知れないが
それを作る側は、今までとはまるで違う事をやらなく
てはならないので、物凄く大変なのだ。
例えば、昨日まで半田付けをしていた技術者や職人に
「お前は今日から、LSIのロジック回路設計をやれ」
と命じても、それは断じて不可能な話である。
だからこの時代に、銀塩時代からの老舗カメラメーカー
のいくつもが、事業(企業)再編やら事業撤退やらと
厳しい対応を迫られていた訳だ。
メーカーのみならず、ユーザー側の混迷も激しかった
時代である。「デジタルのDiの字」も理解していない
消費者層が、「フィルムが不要になった便利なカメラ」
という認識でデジタル機を買うものだから、この時代
ありとあらゆる、誤解やら流言やら、間違っている
(フェイクの)情報が世の中に蔓延した。
一々、その実例を挙げるのも馬鹿馬鹿しく、無意味な
話ではあるが、実際に私は、その多数の誤情報を聞き
続けていたし、そうした間違った事を主張する人達は
頑なまでに、自分達が言っている事が真実だと信じて
疑わない。まあ、酷い「思い込み」思想であった訳だ。
まあ、そこから約20年が経過した現代においては、
だいぶユーザー層にもデジタルの知識がついて来た
のではあるが、それでも、その間のユーザー層は
完全に代替わりした訳では無く、銀塩時代の古い
時代の常識を抱えたままの同じユーザーが、そのまま
デジタル機で写真を撮っている事も多いから、依然
デジタルに関する誤まった認識が蔓延している事も、
残念ながら事実である。
情けない話だが、それが現代でのユーザー層の
実態であり、その事が2010年代からのカメラ市場
の縮退を、さらに加速する結果になった(=つまり、
何もわかっていないビギナーのユーザー層に対し、
単に、カタログスペックだけを「盛った」カメラを
売りつけようとして、逆に中上級層の反感を買って
しまい、オピニオンリーダー等からの好評価の口コミ
等が大幅に減少し、余計にカメラが売れなくなった)
・・のであれば、極めて残念な話だ。
![_c0032138_06481244.jpg]()
となってしまったレア機である。まあ、発売時点でも
他社機と比べて、若干高価であったから、販売数も
少なかったと思われ、その事もまたKONICA MINOLTAの
カメラ事業撤退を早めた原因となったのかも知れない。
また、耐久性はあまり高く無く、一応本機はボロボロ
になるまで実用的に使って、今なお動作はするのだが
あちこちにガタが来てしまっている。現代なお残る
機体でも完動品は少ないであろう。(それ故に、殆ど
中古品が流通していないのだろう、と推測できる)
だから、現代において本機を「指名買い」する事は
まず困難であるし、そこまでして購入する必然性も
まるで無い。同じα Aマウントを採用する後年の
SONY機を使った方が、あらゆる面で高性能だからだ。
よって、本機α-7 DIGITALの性能詳細は割愛する。
(興味があれば、デジタル一眼第3回記事に詳しい)
さて、カメラマニア層を中心に「オールドレンズ」の
ファン層は、とても多いが、「オールド(デジタル)
カメラ」のファン層は、非常に少ない事であろう。
ここで「何年前の製品ならばオールドなのか?」という
定義は難しいが、銀塩時代の中古ブーム(1990年代)
では、概ね1930年代~大戦を挟み~1960年代の
レンズが「オールド」という感じであったと思う。
第一次中古ブームから20年以上が経過した現代に
おいては、オールドレンズの時代も、もう少し新しく
なっていて、1950年代~1970年代の製品もオールド
と言えるのではなかろうか? まあつまり、いつの
時代であっても、オールドと呼ぶからには、少なくとも
40~50年程度は昔の時代のレンズを指すとは思う。
さて、ではカメラの場合はどうか? オールドデジカメ
というものは人気があるのか? いや、それはあるまい。
カメラだが、2000年前後にフィルムからデジタルへと
大きな変革があり、そこで時代が分断されてしまって
いる。勿論フィルムカメラは現代でも使用はできるが
撮影コストや利便性から、非常に少ない数のマニア層
しか、現代では使っている人を見なくなってしまった。
それに、フィルムカメラの人気機種、あるいは実用的な
機種は、ある程度は決まっていて、実用的にフィルム
カメラを使いたいのであれば、中古品が安価となった
それらを買えば良い。一部の希少カメラは、投機目的に
より、中古相場も高価ではあるが、それらはコレクター
向けの機体であるから、実用的視点からは無視できる。
(参考:別シリーズ、銀塩一眼レフ・クラッシックス、
銀塩コンパクト・クラッシックスの記事群を参照。
それらの記事で紹介している機体、つまり私が処分せず
残している機体程度しか、実用的な銀塩カメラは無いと
思われる。→勿論、嗜好性の強い投機的機種は対象外だ)
では、デジタルカメラはどうなのだろうか?
前述のようにオールドと言っても、デジタル機では
高々20年程度前に発売されたものである。
レンズの場合では、40~50年も前のものであれば
現代のレンズとは、製造技術も設計思想も外観も
メーカー名も、それを使うユーザー層も、全てが
変化してしまっているから、目新しさはあると思う。
しかし、デジタルカメラの10数年前程度の製品は、
それを使っていたユーザー層もまだ残っているし、
ただ単に「性能が未成熟であった旧機種」という
印象しか持たないと思う。
持論では、デジタルカメラには「仕様的老朽化寿命」
というものがあり、これは、たとえそのカメラが
故障せずに動作していたとしても、「新鋭機に比べて
性能や仕様が、とてつもなく古く感じて、使いたい
気持ちが無くなってしまう」という寿命である。
で、その寿命は、「およそ10年間」という持論だ。
その10年、いや正確に言えば、購入してから10年間
では無く、その製品が発売された時点から10年間だ。
それを過ぎると、「古い」という感覚から、自身でも
使いたくなくなるし、市場に流通している中古品も、
古すぎて不人気で売れず、二束三文のレベルにまで
中古相場が下落してしまう。(又は、ごく近年に
おいては中古市場も苦しい為、格安相場となる機材は、
専門店では中古品としては販売しない傾向が出ている)
だから、デジタルカメラは「消耗品」と見なせる訳で、
それを使うならば、その発売後10年間の使用可能期間
で元を取るように、十分に使い込まないとならない。
さもないと、使わないカメラは、どんどんと価値が
下がっていき、仮に売却しようとしても査定も付かない。
ユーザーにとって何も良い事は無いので、なんとしても
期限内に使い潰す必要がある訳だ。
この状況はデジタル時代に入ってすぐに気づいたので
個人的には「1枚3円の法則」を考察した。
このルールでは、購入価格を撮影枚数で割って3円
となったら「元を取った」と見なし、その時点で
新型機を追加(または代替)購入する訳だ。
このルールをこれまでずっと踏襲していたのだが、
近代、2010年代後半以降では、カメラがあまり売れて
いない為、新機種の価格が、旧来からは考えられない
程に高騰してしまっている。例えば、40万円も
50万円もする新型機を購入してしまったら、
「1枚3円の法則」を遵守する事は、まず不可能だ。
そのカメラで15万枚以上もの撮影を行う事はまず無い。
多数のカメラを所有し、実際にそれらをガンガンに
使っている私の場合でも、最も多く撮影している
カメラで5万枚程度である。で、そこまで使うと
本当にボロボロになってしまうので、代替機を
買わざるを得ない。ただし、私は常に複数台の
カメラを並行して使っているので、もし1台だけを
ずっと使うのであれば、数十万枚~百万枚という
レベルの撮影枚数とはなるだろう。
しかし、そこまで使うと、恐らくは、もうメカが
持たない。部品等の耐久性がそこまでは無いからだ。
そんな状態で、しょっちゅう病院(修理)送りに
なるようであれば、お金もかかるし、そこまで
するならば、もう新型機に代替しているであろう。
・・というか、個人的にはカメラを耐久性の理由で
完全に壊してしまう前に、他機を追加購入するように
している。だから、現在、多数所有している銀塩機や
デジタル機は、ほぼ全てが完全に動作するのだ。
(注:不運が重なった、または、経年劣化による
電気的故障の場合は例外だ)
![_c0032138_06482543.jpg]()
「動態保存」という概念があるが、それと同様の
状況を目指している。
よって、例えば本機α-7 DIGITALが、古くて老朽化
寿命を過ぎてしまっていて、中古ももう見当たらない
ような状況であっても、依然、本機はまだ現役で
使用可能な訳だし、こうした古い機体を、定期的に
使ってあげて”状態をチェックする”という目的も
あるので、本ブログでは、こうしたオールドの
カメラやレンズを使うシリーズ記事の執筆が多く
なる訳である。
まあ、いずれも自分自身の研究目的や価値観維持等の
理由の為であり、あまり他者への情報提供や商品の
推奨、つまり「レビュー」やら「広告」や「投機性」
としての本ブログ記事の必然性(目的)は、全く無い。
よって、希少な機材などでは、「これは入手不能
につき非推奨、詳細情報も割愛」等と、ばっさり
切り捨ててしまうケースも多々ある訳だ。
本ブログの記事を原因や理由として、当該機種を
必死に探す人が増えてプレミアム相場等になるのは
好ましい状態では無いからだ。
で、本機α-7 DIGITALも、希少機であるが故に、
「どうしてもそれが欲しい」等と言う「好事家」が
出て来ないとも限らない。
念のために再度「現代における実用価値は皆無
であり、かつ、”動態保存”はかなり難しい機体」
と、締めくくっておく事にしよう。
---
では、今回ラストのオールド・デジタル一眼レフ。
![_c0032138_06483204.jpg]()
(2004年発売、発売時実勢価格約10万円)
(中古購入価格 30,000円)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第2回
レンズは、smc PENTAX-FA Macro 50mm/f2.8
(推定1991年頃発売)を使用する。
さて、本機発売の時代の2004年は「デジタル一眼
レフ元年」と私が呼んでいる位に、各社から、一般層
でも買える、安価な価格帯のデジタル一眼レフが
出揃った年(時代)であった。
その中でも本機PENTAX *istDsは、10万円を僅かに
切る新品実勢価格で、各社のデジタル一眼レフの
中でも、最も安価であった事が最大の特徴だ。
(注:この時代から「オープン価格」制度が増えて
きていて、なかなか正確な「定価」がわからない)
![_c0032138_06483228.jpg]()
抜いておらず、他社製品と同等の600万画素CCD
撮像センサー(恐らくは各社で共通の部品を調達
したのであろう)であり、最高ISO感度はISO3200
と、前述のNIKON D2Hを除き、当時最高レベルで、
しかも、高感度域は他社機よりも実用的性能だ。
連写性能は低い(遅いし最大コマ数も少ない)が、
本機は連写性能を犠牲にして小型軽量化していて
発売時は世界最小、および重さも恐らくは最軽量
クラスであった事であろう。(本体のみ505g、
これは、CANON EOS Kiss Digital(初代)の
560gよりも軽い)
しかし、本機は、単三電池4本または、同等形状
のリチウム電池(例:CR-V3 x2本)を使用する
ので、その電源の重さは結構重い。
単三型電池の利用は、デジタル機では珍しく、
他社あるいは他機での専用バッテリー使用型に比べ
電源消耗時にも、コンビニや一般店舗等で乾電池
の購入は容易であるから、使用利便性はある。
ただし、マンガン電池での駆動は厳しく、最低限
アルカリ電池、できればリチウム/ニッケル水素系の
高性能乾電池/二次電池(充電式電池)を使わないと、
あっと言う間に電池が消耗してしまうので、これの
利点と弱点は隣り合わせだ。
(参考:現在、本機*istDsは経年劣化からか・・?
ハイパワー電池を用いないと起動しない状態である)
初期デジタル一眼レフ(それまでの時代における
デジタル・コンパクト機も同様)での、消費電力の
多さ、すなわち「バッテリーの持ち」は大きな課題
であって、2000年代初頭迄は、デジタル機のみで
丸1日の撮影をこなすことは、まず不可能であり、
「必ず銀塩機を併用する」などの必要性があった。
デジタル一眼レフでのバッテリーの持ちが改善
されるのは、ほぼこの時代、2004年発売のNIKON
D70(後日紹介、デジタル一眼第4回記事参照)
およびCANON EOS 20D(故障廃棄)からであり、
それらの機体であれば、1000枚程度の撮影を
なんとかこなす事が出来るようになった。
これはバッテリーが改良された事からではなく、
カメラの電子部品が低消費電力化された理由の
方が大きい。なお、さらに後年2000年代後半の
機種では、背面モニターの大型化や、内蔵手ブレ
補正機能の搭載により、従前の機種よりも
バッテリーの持ちが悪化した事もあったが、
2010年代前半くらいの機種からは、機種により
3000枚~6000枚程度の撮影枚数をこなせる程
に進歩していて、これであれば、丸一日の業務等
での撮影で、ほぼ撮影しっぱなし、という状況にも、
かろうじて耐えられる。
(注1:カメラを2台持ちで、交互に撮影するとか、
念の為に予備バッテリーを持てば、まず大丈夫)
(注2:各カメラのCIPA規格による撮影可能枚数仕様
表記の、5~6倍の枚数を撮る事を常に心がけている。
これは技能が必要だが、出来ない話では無い)
さて、本機*istDsであるが、連写性能と、AFの
精度・速度不足の課題を除き、他の重欠点は
見当たらず、なかなか優れた機体であると思う。
高感度性能は当時の他機よりもノイズが少なく、
AWB(オートホワイトバランス)機能は、割と
優秀で、複雑な光線状況にも良く対応している。
よって、本機は、暗所でのライブ等のステージ
撮影で長期間に渡って活躍したカメラとなっていた。
(その目的は後年にはPENTAX K-5で代替している。
K-5は、高感度ISO51200を搭載していて、かつ
シャッター音が静粛であるから、暗所イベント撮影
には極めて適切であった。後日紹介予定、又は
デジタル一眼第12回記事参照)
![_c0032138_06483275.jpg]()
本機にも前述の「青色波長のエンハンス(増強補正)」
が少し見られ、気持ちの良い青空発色が得られる。
短所だが、AFの精度は、現代的な視点からすると
かなり厳しい。通常のAFモーター非搭載レンズでは、
ガタピシと細かい合焦動作を繰り返したり、あるいは
全くAFが合わなかったりもする。
この課題への対策としては、本機*istDsは、
ファインダーが優秀(ガラスペンタプリズム、
視野率95%、倍率0.95倍相当、ナチュラルブライト
マットスクリーン)である為、適宜MFを併用するか
又は、もう最初からMFでしか使わない事が賢明だ。
なお、本機の最初期のファームウェアでは、確か
AF-Cモードが無く、AF-Sでは、ピントが合わないと
シャッターが切れない(フォーカス優先)で
あったと記憶している。この状態では低いAF精度と
あいまって、殆ど撮影が不能(シャッターが
切れない)となるので、当時のビギナー層の間では
本機は、この課題がある為に不人気であった。
しかしながら、ファームウェアをアップデート
するか、あるいはMF撮影に特化してしまう事で、
AF精度の問題点は消える。この為、中級層や
マニア層の間では、本機*istDsは、価格の安さと
あいまって、コスパの良い機体として人気であった。
まあつまり、本機の話には限らないが、撮影機材の
評価は、利用者のスキルに依存してしまうという
訳である。本機のAFの弱点を、課題としか捉えられ
ないのであれば、本機はダメカメラとなってしまい、
「そんな問題は、いくらでも回避の手段はある」と
思い、それが実践できるのであれば、本機*istDsは
ハイコスパの名機となる。
ちなみに、デジタル一眼第2回記事における
本機の総合評価は、約3点と、ほぼ平均的だ。
ある意味平凡な評価点ではあるが、機材の長所短所
を良く理解して、適正な撮影目的において適正な
用法を行うのであれば、十分に実用的なカメラに
なりうる。
なお、AF問題を回避する為に、MFレンズを使う、
という選択肢は無きにしもあらずだ。何故ならば
PENTAX Kマウントは、銀塩MF/AF時代から、そして
デジタル時代となっても形状互換性が高いからだ。
ただし、本機*istDsでMFのレンズを使う際には、
PENTAX K(MF)マウントにおける、A型より前の
タイプ(K/P、M)は、使えない事は無いが、露出値
を得る為に、極めて煩雑な操作が必要とされるので、
実用範囲外だ。
またM42系列の場合、A/M切換スイッチを持つか
又はプリセット型であれば「マウントアダプターK」
の併用で絞り優先AE等で、かろうじて実用範囲だが、
それ以外のM42レンズは使用困難だ。
いずれにしても、このMFレンズでの用法は、マニア
級の知識と高い技能が必要とされ、一般初級中級層
には非推奨である。
(これは本機に限らず、その後のPENTAX デジタル
一眼レフ全般でも同様)
ただまあ、さすがに本機もまた仕様的老朽化寿命
に達してしまっている。現代においても、稀に
数千円という格安相場で本機が流通している状況
も見かけるが、これも「指名買い」をする類の
カメラでは無いであろう。
![_c0032138_06483771.jpg]()
本機の後ダイヤル(の中のロータリーエンコーダー)
が接触不良を起こし易く、それが発生した場合には
CRC5-56等の潤滑/接点復活剤を注入して対応する。
(この問題は、各社のカメラでも稀に起こる)
まあ、オールドカメラでは物理的な老朽化の対策も
必要だ、という事である。
もう古い時代のカメラゆえに、もう少しだけ予算を
出せるのであれば、後年のPENTAX K-5(2010年)
あたりが、はるかに実用的で、かつ現代では低廉な
中古相場で、コスパが極めて良い状態となっている。
それと、今回の記事での紹介機は、本機*istDsを
除き、全てCF(コンパクトフラッシュ)カード使用機
である。CFカードの入手性は年々悪くなっていくので
これらの機体を現代でも実用としたい場合、その点は
要注意である。
----
では、今回の「オールド・デジカメ(1)」編は、
このあたり迄で、次回記事は、引き続き古い時代の
デジタル一眼レフ4機種を紹介する予定だ。
本シリーズは、所有している古いデジタルカメラを、
時代およびカテゴリー(一眼レフ、コンパクト機、
ミラーレス機)で分類して、順次紹介していく記事群
である。

とする。古い時代のデジタルカメラの性能は、現代の
ものに比べて見劣りするのは当然であり、その為に
旧機種は、急速に実用範囲以下のレベルとなり、
不人気にもなってしまうので、今更、古いカメラの
性能/仕様等の詳細を述べても無意味であろう。
よって、このシリーズは、時代背景、市場の状況、
メーカー間のライバル関係等の事情により、何故
そのカメラが生まれてきたのか? 等の歴史的な
説明を主体としたり、古いカメラを、今なお使い
続けるのは何故か?というあたりにも着目する
記事群とする。
また、隠れたテーマとして
「オールドレンズは人気があるのに、何故オールド
デジカメは不人気なのか?」という点も、とても
重要な分析内容である。これは簡単には答えが出て
くるものでは無いから、シリーズ途中や終盤において
少しづつ纏めていく事にする。
では、今回第1回目だが、「デジタル一眼レフ編」
として、2000年~2004年の期間に発売された
(オールド)デジタル一眼レフを4機種紹介する。
なお、この時代ではデジタル一眼レフ専用のレンズ
は、殆ど発売されていない為、ユーザー層は、皆、
銀塩一眼レフ用のAF(稀にMF)レンズを、そのまま
デジタル機に装着して使っていたので、本記事でも
時代背景を鑑みて、その用法に従う事とする。
(つまり、今回使用のシステムは、オールドデジタル
一眼レフ+銀塩用AFレンズ、という組み合わせとする)
以降、そのオールド一眼レフと銀塩時代のAFレンズでの
実写をはさんで記事を進めていくが、掲載写真はカメラ
本体の写真を除き、そのシステムで撮影したものとする。
ただし、当該カメラ内に備わっている機能(エフェクト
やHDR合成、テレコン等)は、自由に使用可とする。
(しかし、この時代のカメラには、まだその手の機能は
搭載されていなかったので、これは後年の機種の話だ)
それと、PCによる写真の後編集は、僅かな「輝度調整、
構図調整のトリミング、縮小」という限定範囲に留め、
過度な編集を禁ずるルールとする。(注:JPEGのみで
あり、RAW現像は一切使用しない)あまり、こねくり
廻してしまうと、本来のカメラやレンズの性能が
わからなくなり、紹介記事の意味が無いからである。
まあでも、こうした紹介記事以外では、レタッチ編集
をする事は、現代においては、必然の処置ではある。
(注:今回の記事の時代では「カメラマン」と言っても
パソコンを触れない人達が大半であった為、この頃は
「レタッチ編集をするのは邪道だ!」とかいった、自身の
問題を正当化しようとする発言がとても多い世情であった)
そして、今回は古い時代のカメラやレンズを使うので、
それなりに写りは悪くなるが、それも当然であり、
その「程度」を検証する目的もある。
でも、オールドカメラ+古いレンズだから、と言って
「ダメダメの酷い写り」にはならない事実を提示する
事も、本シリーズ記事の目的もなっている。
---
では始めよう、最初は、最も古い時代の(初の?)
実用的デジタル一眼レフである。

(2000年発売、定価358,000円+税)
(中古購入価格 70,000円、税込み。以下全て税込)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第23回
レンズは、CANON EF50mm/f1.8(Ⅰ/初期型)
(1987年)を使用する。
本機の型番は「D30」であり、他のEOS機の後年の
機種(例:EOS-1D、EOS 30D)とは、型番のルール
が異なっている。
この型番の流れは「D60」(2002年)まで続いた後、
「10D」(2003年)からは、全てのCANON EOS
デジタル一眼レフ(注:Kiss系とミラーレス機を除く)
では、型番の数字の後に「D」をつける事に統一
された模様だ。
なお、銀塩時代より、デジタル一眼やミラーレス機に、
至るまで、EOS-1、EOS-3系機体のみが型番にハイフン
が入り、他は入らない(例:EOS Kiss、EOS 7、
EOS 5D、EOS 8000D、EOS M5、EOS RP等)
そしてハイフンが入らない場合は、空白(スペース)
を替わりに入れるので、EOS90D等の記載は誤りだ。
また、3番機ではあるが、(新鋭の)EOS R3には、
ハイフンは入らない。

1990年代から、CANONは米国KODAK社と提携して、
デジタル一眼レフの試作開発を続けていた。
1995年~1998年の間で、EOS DCS3、EOS DCS1、
EOS D2000、EOS D6000の4機種が発売されたが
いずれも試作機的、かつ非常に高価であったので、
報道や学術等の専門的分野向けであり、これらは
まだ一般層が買えるものでは無かった。
(この当時は、「1万画素あたり1万円」とも
言われていた。つまり200万画素機は200万円だ!)
その後、CANONはCMOS撮像センサーを自社開発する
方針に転換し(恐らくはKODAKとの提携も解消され、
KODAKは、OLYMPUSへ4/3型CCDセンサーを供給して、
2003年のOLYMPUS E-1発売に繋がる歴史だろう。
ちなみに、何故フィルムメーカーの世界的大手で
あるKODAK社が撮像センサーを先行して開発していた
のかは?フィルムは、いずれデジタルに変遷する事が
明白であった為、早く(1970年代)からKODAKは
撮像センサーの研究開発に着手していた歴史がある)
・・それによる、CANON完全自社開発による、初の
機体が本機EOS D30(2000年)である。
かつ、価格も35万円台と、これまでは数百万円も
していた黎明期の試作デジタルEOSから比べて安価
となり、初めて一般層でも入手可能となった機体だ。
よって、本機の歴史的価値は非常に高い。
ただまあ、本機の前年の1999年には、NIKONより
NIKON D1(65万円)が発売されているので、
初のコンシュマー(一般消費者)向けの機体は、
そのNIKON D1だ、と定義できるかも知れない。
しかし、65万円は、依然高価すぎる状況だから、
個人的には、本機EOS D30を初の「一般機」
(民生機、コンシュマー機)と定義している次第だ。
だが、本機は不人気機種であった。記録画素数は
300万画素と低いし、連写性能等も非常に弱い。
旧来のEFマウント版(銀塩用)AFレンズが使える
とは言え、センサーサイズがAPS-C型だから画角も
ずいぶんと変わってしまう。(1.6倍相当)
描写力は、一部のユーザー層には「黄色く写る」と
酷く嫌われていた。(→誤解。詳細後述)
また、バッテリーの持ちも悪く、数百枚しか撮れず、
これは1日の撮影には持たないので、満充電をした
予備バッテリーの携行が必須だ。
おまけに、価格も銀塩EOS中高級機の3倍も高価だ。
まあ、これでは、銀塩一眼レフの方が、まだずっと
実用的なので、なかなか本機を欲しいと思う人は
現れない状態であったかも知れない。

を見ても、現代において、あまりそういう印象は
持たない事であろう。
むしろ、この時代の多くのデジタル機の色味は、
「オリンパス・ブルー」というマニア用語に代表
されるように、青色が強い発色となる。
この理由は、当時の(KODAK製等の多くの)撮像センサー
においては、「短波長(青色等)の感度が低い」事への
対策で、青色域をエンハンス(増強)する特性(補正)
を加えているからだ、と思われる。
この措置により、2000年~2006年頃のデジタル機
(一眼レフ、コンパクト機)の多くに、こういう
「強い青味」を発する傾向が見られる。
(すなわち、オリンパス機だけの特徴では無い)
これにより、写真に写る青空等については、比較的
気持ちの良い青色描写が得られるのだが・・
しかし、青色エンハンス処理を施した機体では、
青色よりさらに短波長の、菫(すみれ)色や藍色
等の被写体を撮ると、実物とは似ても似つかぬ
不思議な色味となる。(注:それはそれで面白い)
まあつまり、「黄色く写る」とは、この当時の
デジタル機の背面(液晶)モニターが、技術的に
未成熟であり、解像度が低く、カラーバランスも
正しくないから、それを見ての「印象」に過ぎない
訳だ。
これは、笑ってしまう程の「酷い誤解」であり、
デジタルの原理も何もわかっていない状態なのだが、
銀塩カメラからデジタル機に持ち替えたばかりの
人達では、いくらマニアや上級層、職業写真家層で
あっても、「デジタルの事は、まるでわからない」
という時代背景からは、まあ、やむを得ない。
(注:パソコンにデジタル写真を取り込んで鑑賞や
編集をする事すら、この時代では殆ど行われていない。
つまり、カメラの背面モニター上でしか、撮影をした
写真を見ていなかった状況が大半だ)
ちなみに、カメラ背面モニター液晶の発色が良好に
なるのは、概ね2006年以降の話であり、さらに
後年の2014年前後からは、より鮮やかな発色となる。
前述のように、背面モニター上に映った再生画像
だけを見て「このカメラは色味が悪い」とかと言う
超ビギナー層が、現代においてもかなり多いから、
メーカー(または部品メーカー)としては、背面
モニター液晶やEVFの、発色や解像度等の改善は、
ずっと優先開発事項として捉えているのであろう。
(消費者層が、それだけを見て「良く写るカメラだ」
と誤解するから、そう思わせたい訳だ)
さらにちなみにだが、一般ユーザー層におけるカメラ
関連知識の不足は、デジタル化された近代だけが
顕著だった訳でもない。銀塩時代での類似の事例を
挙げれば、中古カメラブーム時に高い人気があった
「銀塩レンジファインダー機」の、光学的に素通しの
ファインダー/ビューファインダーの綺麗な映像を覗いて、
「このカメラは、良く写るのぅ」とかの感想を言い、
それらを購入した人達は大変多かった。
勿論、それはただ単にファインダー像が綺麗に見える
というだけの話であり、実際の写真における写りとは、
まるで無関係だ。

実用性は極めて低い。この理由から本機を趣味撮影
等に持ち出す頻度も非常に低いし、総撮影枚数も
約20年間で1万数千枚と、かなり少ない状態だ。
ただ、近年においては、個人的な持論により、
「一旦購入した以上、たとえ実用性能に満たない
カメラやレンズでも、それを使いこなそうと
努力する事は、オーナー側の責務である」
と考えていて、本機も、ごく稀に持ち出すように
している。
その際、まあ、確かにカメラとしての実用性は
低いが、現代機ではまず見られない本機の独特な
青色発色傾向等は、「なかなか興味深い」という
印象に繋がり、「これをなんとか使えないか?」と、
ポジティブな考えに変わって来る次第だ。
---
では、次のオールド・デジタル一眼レフ。

(2003年発売、定価490,000円+税)
(新品購入価格 128,000円)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第1回
レンズは、NIKON AiAF Micro-NIKKOR 60mm/f2.8D
(1993年)を使用する。
NIKONのデジタル初期の旗艦(フラッグシップ)機
でありながら、不当な悪評判が流れた事で、極めて
不人気となってしまった悲運の機体である。

としてはトップクラス。かつ「ミラー像消失時間が
短い」という特徴を持つ為、連写中でのレンズのMF
操作も出来てしまう(→連写MFブラケット技法が可)
レリーズ・タイムラグ(シャッターボタンを押して
から、実際にシャッターが切れるまでの時間)は、
それ以前のAF一眼レフ、およびそれ以降のデジタル
一眼レフ全般を通じ、本機D2Hが、AF機史上最速の
37ms(0.037秒)である。
(注:ミラーレス機では、もっと速い)
まあつまり、「より素早く撮影する」為に特化した
実践派ユーザー好みの製品コンセプトであり、その
分野(速写性、即時性)の撮影を志向しない場合は
本機の特性は発揮できない。さらに言えば、銀塩
時代の同様のコンセプトの機体は、NIKON F5
(銀塩一眼第19回記事)等、ごく少数しか存在
しない特性であるから、一般層にこうした企画意図の
機体が受け入れられるかどうか?は微妙なところだ。
つまり、銀塩時代での一般的撮影では、三脚を立てて
じっくりと構図や光線状況を見ながら、ほんの数枚
だけ撮影する、というスタイルが大半であった所に・・
手持ちで、「あちらこちらの被写体にカメラを向けて
大量の写真を素早く撮る」という新たな撮影技法へは、
銀塩機から持ち替えたばかりの当時のユーザー層では、
そう簡単には転換できない、という事であっただろう。
見かけは同じ「カメラ」であっても、まるっきり
使い方が違う機械だ、考え方を180度変えない限り
本機D2Hの効果的な使用法にはならない。
(この、「全く考え方を変えなければ本機を使えない」
という点は、一般ユーザー層には理解不能であるから、
それが、本機に関する不当な悪評を広めた原因の1つ
になったのかもしれない・・)
そして、最大のポイントは、本機の撮像センサーが、
NIKON独自開発のLBCAST(JFET型CMOS)であった事だ。
これを新規開発した事で、「高速連写」と、当時の
カメラとしては最大感度であった「ISO6400」が
実現されている。ただし、記録画素数は上げられず、
僅かに約400万画素に留まっているし、本機の本体
だけでは、センサーの色味等の調整は殆ど出来ない。
これが、本機が市場で不人気となった原因であろう。
いわく「ノイズが酷い」「色味が悪い」等の、市場
での悪評判があった。
しかし、これについては、誤解または明確な理由が
ある、と私は分析している。
1)フィルム機から持ち替えたばかりのユーザー層
では高感度ノイズの発生原因や、その許容範囲を
理解していない。ISO6400の設定があれば、それを
目一杯使うのもやむを得ないであろうし、その状態で
「ノイズが多い」と評価するのも、当たり前の話だ。
2)NIKONのセンサー独自(自力)開発を、「脅威」と
見た対抗勢力、あるいは反対派等が、そうした
流言を流した可能性が高いと見ている。
(現代で言う、ネガティブ・キャンペーン)
3)センサーの色味や発色の調整は、後年であれば
ユーザー側で行うのが常識だ。しかしこの時代は
まだ銀塩時代の感覚であったから、「DPEは
カメラマンでは無く、写真屋さん(DPE担当者)
の仕事である」という意識が非常に強い。
まあ、「自分で調整したい」と思ったとしても、
本機D2Hに、その機能が無かった事も原因だろう。
この時代では、たとえ上級カメラマンであっても、
「画像編集ソフト」等は、誰も触ったことが無く、
持ってもいないし、使いこなせる人も居なかった。
・・という状況であり、本機D2Hは、不当な悪評に
より、市場での売れ行きが止まってしまった。
「NIKON D2」という機種が存在しない事も問題点で
あった事だろう。本機D2Hがいきなり新発売されれば、
一般消費者は、皆、「これが次世代の旗艦機か!?」
と思うだろうから、この機体が、これまでの銀塩時代
の常識の範疇では、全く使いこなす事が出来ない類の
”速写特化型の実用高速連写機”である事に気づかず、
「これは、きっと最高級の、ラグジュアリーなカメラ
だろう」と、消費者層は、皆、勘違いしていた訳だ。
また、高価すぎた(税込み50万円以上)のも、
売れない原因となった。
本機発売翌年の2004年頃には、各社から20万円を
切る実用的なデジタル一眼レフが入門機(普及機)
として、次々に発売された時代なのだ。

本機の新品在庫を持て余したカメラ店から、大幅な
値引き販売提案があり、その提示金額をさらに
値切って(汗)128,000円(税込み)という、
とても安価な(実質、定価の1/4程度の価格)で
本機を新品購入できたので、まあ良かった。
ただまあ、実用的に本機の性能を発揮できる
撮影シーンが極めて少なかったのは課題であった。
スポーツ競技の業務撮影に持ち出した事も何度か
あったが、記録画素数が最大400万画素しか
無いのでは、写真納品時の要求画素数に満たない
場合も多々ある。(例:ポスター等には使えない)
後年には趣味撮影専用機としたが、そういう分野で
高速連写は、あまりにアンバランスな性能であろう。
本機の減価償却(撮影1枚あたりが3円となる事で
元を取ったと見なす、個人的なルール)の完了は
遅れに遅れ、購入後約15年を経過した2020年頃
までかかった。
これにより「デジタル機では仕様老朽化寿命が短い」
という点を痛感した。
つまり、カメラ自体は何も故障も無く動作している
のに、周囲の新鋭機に比べて、どんどんと仕様・性能的
に古く感じて、そのカメラを使いたく(持ち出したく)
無くなったり、実用的に使えなくなってしまうのだ。
この課題を鑑みて、「デジタル機ではフィルム時代の
常識は通用しない」という風にも思い、銀塩時代には
むしろ、「仕様老朽化寿命」が長い(=そう簡単には
新鋭機に見劣りせず、長く使える)と思って、好んで
多数購入した銀塩旗艦機(最高級機、ハイエンド機)は、
デジタルにおいては「旗艦機は、できるだけ購入しない」
という方針に転換。本機D2H以降、そのルールを遵守
するようにしている。(旗艦機は1台も買っていない。
まあつまり、趣味および業務上での実用機としては、
「上級機」と区分される機体が最も効率的である、
という持論を作り、それを実践している)

と発色の面から、実用的には厳しい、という結論に
なるだろう。だが、本機での極めて快適な高速連写
性能は、その当時としては衝撃的なインパクトが
あった。そして、その快適性を、現代においても
得られる機体はそう多くは無い。例えばNIKON D500
や、CANON EOS 7D MarkⅡ(デジタル一眼レフ
第20回、第19回記事参照)あたりであろうか。
(注:近年では、電子(撮像素子)シャッターの
利用で、秒何十コマというカタログスペックを謳う
ミラーレス機が多いが、それらは、個人的には、
「実用的高速連写機」とは見なしていない。
一応、”秒60コマ連写”の機体は所有しているが、
「実用的に、その性能が使える」と思った事は一切
ない。所詮は、単なるカタログ性能だけの話だ)
真の「高速連写機」という物が、どういう類の機体
であるか?を体感したいのであれば、現代、稀に
見かける本機D2Hの中古品は、恐ろしく安価であり、
二束三文となっているので、研究用に購入してみる
のも悪く無いかも知れない。SNS用であれば400万
画素は十分であり、色味は、任意のレタッチソフト
で調整すれば良い。また、日中で低感度設定で使う
ならば、本機のノイズ性能は全く問題にはならない。
なお、D2Hの弱点として以下の2点を挙げておく。
1)高速連写音がとてもうるさく、使える状況が
限られてしまう(静かなイベントの記録撮影は不可)
2)背面液晶が製造後10年程から劣化していき、ほとんど
見えなくなる(注:他の2000年代NIKON機も同様)
---
では、3台目のオールド・デジタル一眼レフ。

(2004年発売、発売時実勢価格約20万円)
(中古購入価格 90,000円)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第3回
レンズは、MINOLTA AF 100mm/f2
(推定1980年代末頃発売)を使用する。
MINOLTAがKONICAと合併(2003年)し、初めて
発売されたデジタル一眼レフが、本機α-7 DIGITAL
である。「世界初の内蔵手ブレ補正機能」を搭載した
センセーショナルな機体であり、MINOLTA時代から
の伝統的慣習に従い、革新的な機体の型番である
「7番機」を命名された(と思われる)
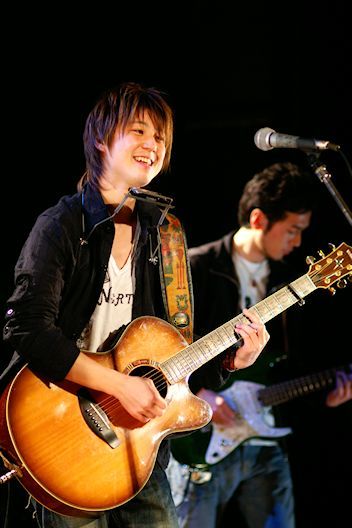
次いでα-Sweet DIGITAL(2005年、故障廃棄)の
たった2機種のデジタル一眼レフが発売されただけで、
2006年には、α(カメラ、レンズ)の事業一式を
SONYに移管譲渡し、KONICA/MINOLTAは、その百年
以上にも及んだ写真(機)事業から撤退してしまう。
これはまあ、急激にデジタル化が進んだ事により、
これまでの銀塩時代のビジネスモデルや、あるいは
企画・研究・設計・開発・製造・販促・販売等の
全ての業務プロセスが、まるで変わってしまった事が
最大の原因であった事であろう。
当時のユーザー(コンシュマー)層は、呑気にも
「フィルムが不要になったカメラ」くらいにしか、
デジタル機の事を意識していなかったのかも知れないが
それを作る側は、今までとはまるで違う事をやらなく
てはならないので、物凄く大変なのだ。
例えば、昨日まで半田付けをしていた技術者や職人に
「お前は今日から、LSIのロジック回路設計をやれ」
と命じても、それは断じて不可能な話である。
だからこの時代に、銀塩時代からの老舗カメラメーカー
のいくつもが、事業(企業)再編やら事業撤退やらと
厳しい対応を迫られていた訳だ。
メーカーのみならず、ユーザー側の混迷も激しかった
時代である。「デジタルのDiの字」も理解していない
消費者層が、「フィルムが不要になった便利なカメラ」
という認識でデジタル機を買うものだから、この時代
ありとあらゆる、誤解やら流言やら、間違っている
(フェイクの)情報が世の中に蔓延した。
一々、その実例を挙げるのも馬鹿馬鹿しく、無意味な
話ではあるが、実際に私は、その多数の誤情報を聞き
続けていたし、そうした間違った事を主張する人達は
頑なまでに、自分達が言っている事が真実だと信じて
疑わない。まあ、酷い「思い込み」思想であった訳だ。
まあ、そこから約20年が経過した現代においては、
だいぶユーザー層にもデジタルの知識がついて来た
のではあるが、それでも、その間のユーザー層は
完全に代替わりした訳では無く、銀塩時代の古い
時代の常識を抱えたままの同じユーザーが、そのまま
デジタル機で写真を撮っている事も多いから、依然
デジタルに関する誤まった認識が蔓延している事も、
残念ながら事実である。
情けない話だが、それが現代でのユーザー層の
実態であり、その事が2010年代からのカメラ市場
の縮退を、さらに加速する結果になった(=つまり、
何もわかっていないビギナーのユーザー層に対し、
単に、カタログスペックだけを「盛った」カメラを
売りつけようとして、逆に中上級層の反感を買って
しまい、オピニオンリーダー等からの好評価の口コミ
等が大幅に減少し、余計にカメラが売れなくなった)
・・のであれば、極めて残念な話だ。

となってしまったレア機である。まあ、発売時点でも
他社機と比べて、若干高価であったから、販売数も
少なかったと思われ、その事もまたKONICA MINOLTAの
カメラ事業撤退を早めた原因となったのかも知れない。
また、耐久性はあまり高く無く、一応本機はボロボロ
になるまで実用的に使って、今なお動作はするのだが
あちこちにガタが来てしまっている。現代なお残る
機体でも完動品は少ないであろう。(それ故に、殆ど
中古品が流通していないのだろう、と推測できる)
だから、現代において本機を「指名買い」する事は
まず困難であるし、そこまでして購入する必然性も
まるで無い。同じα Aマウントを採用する後年の
SONY機を使った方が、あらゆる面で高性能だからだ。
よって、本機α-7 DIGITALの性能詳細は割愛する。
(興味があれば、デジタル一眼第3回記事に詳しい)
さて、カメラマニア層を中心に「オールドレンズ」の
ファン層は、とても多いが、「オールド(デジタル)
カメラ」のファン層は、非常に少ない事であろう。
ここで「何年前の製品ならばオールドなのか?」という
定義は難しいが、銀塩時代の中古ブーム(1990年代)
では、概ね1930年代~大戦を挟み~1960年代の
レンズが「オールド」という感じであったと思う。
第一次中古ブームから20年以上が経過した現代に
おいては、オールドレンズの時代も、もう少し新しく
なっていて、1950年代~1970年代の製品もオールド
と言えるのではなかろうか? まあつまり、いつの
時代であっても、オールドと呼ぶからには、少なくとも
40~50年程度は昔の時代のレンズを指すとは思う。
さて、ではカメラの場合はどうか? オールドデジカメ
というものは人気があるのか? いや、それはあるまい。
カメラだが、2000年前後にフィルムからデジタルへと
大きな変革があり、そこで時代が分断されてしまって
いる。勿論フィルムカメラは現代でも使用はできるが
撮影コストや利便性から、非常に少ない数のマニア層
しか、現代では使っている人を見なくなってしまった。
それに、フィルムカメラの人気機種、あるいは実用的な
機種は、ある程度は決まっていて、実用的にフィルム
カメラを使いたいのであれば、中古品が安価となった
それらを買えば良い。一部の希少カメラは、投機目的に
より、中古相場も高価ではあるが、それらはコレクター
向けの機体であるから、実用的視点からは無視できる。
(参考:別シリーズ、銀塩一眼レフ・クラッシックス、
銀塩コンパクト・クラッシックスの記事群を参照。
それらの記事で紹介している機体、つまり私が処分せず
残している機体程度しか、実用的な銀塩カメラは無いと
思われる。→勿論、嗜好性の強い投機的機種は対象外だ)
では、デジタルカメラはどうなのだろうか?
前述のようにオールドと言っても、デジタル機では
高々20年程度前に発売されたものである。
レンズの場合では、40~50年も前のものであれば
現代のレンズとは、製造技術も設計思想も外観も
メーカー名も、それを使うユーザー層も、全てが
変化してしまっているから、目新しさはあると思う。
しかし、デジタルカメラの10数年前程度の製品は、
それを使っていたユーザー層もまだ残っているし、
ただ単に「性能が未成熟であった旧機種」という
印象しか持たないと思う。
持論では、デジタルカメラには「仕様的老朽化寿命」
というものがあり、これは、たとえそのカメラが
故障せずに動作していたとしても、「新鋭機に比べて
性能や仕様が、とてつもなく古く感じて、使いたい
気持ちが無くなってしまう」という寿命である。
で、その寿命は、「およそ10年間」という持論だ。
その10年、いや正確に言えば、購入してから10年間
では無く、その製品が発売された時点から10年間だ。
それを過ぎると、「古い」という感覚から、自身でも
使いたくなくなるし、市場に流通している中古品も、
古すぎて不人気で売れず、二束三文のレベルにまで
中古相場が下落してしまう。(又は、ごく近年に
おいては中古市場も苦しい為、格安相場となる機材は、
専門店では中古品としては販売しない傾向が出ている)
だから、デジタルカメラは「消耗品」と見なせる訳で、
それを使うならば、その発売後10年間の使用可能期間
で元を取るように、十分に使い込まないとならない。
さもないと、使わないカメラは、どんどんと価値が
下がっていき、仮に売却しようとしても査定も付かない。
ユーザーにとって何も良い事は無いので、なんとしても
期限内に使い潰す必要がある訳だ。
この状況はデジタル時代に入ってすぐに気づいたので
個人的には「1枚3円の法則」を考察した。
このルールでは、購入価格を撮影枚数で割って3円
となったら「元を取った」と見なし、その時点で
新型機を追加(または代替)購入する訳だ。
このルールをこれまでずっと踏襲していたのだが、
近代、2010年代後半以降では、カメラがあまり売れて
いない為、新機種の価格が、旧来からは考えられない
程に高騰してしまっている。例えば、40万円も
50万円もする新型機を購入してしまったら、
「1枚3円の法則」を遵守する事は、まず不可能だ。
そのカメラで15万枚以上もの撮影を行う事はまず無い。
多数のカメラを所有し、実際にそれらをガンガンに
使っている私の場合でも、最も多く撮影している
カメラで5万枚程度である。で、そこまで使うと
本当にボロボロになってしまうので、代替機を
買わざるを得ない。ただし、私は常に複数台の
カメラを並行して使っているので、もし1台だけを
ずっと使うのであれば、数十万枚~百万枚という
レベルの撮影枚数とはなるだろう。
しかし、そこまで使うと、恐らくは、もうメカが
持たない。部品等の耐久性がそこまでは無いからだ。
そんな状態で、しょっちゅう病院(修理)送りに
なるようであれば、お金もかかるし、そこまで
するならば、もう新型機に代替しているであろう。
・・というか、個人的にはカメラを耐久性の理由で
完全に壊してしまう前に、他機を追加購入するように
している。だから、現在、多数所有している銀塩機や
デジタル機は、ほぼ全てが完全に動作するのだ。
(注:不運が重なった、または、経年劣化による
電気的故障の場合は例外だ)

「動態保存」という概念があるが、それと同様の
状況を目指している。
よって、例えば本機α-7 DIGITALが、古くて老朽化
寿命を過ぎてしまっていて、中古ももう見当たらない
ような状況であっても、依然、本機はまだ現役で
使用可能な訳だし、こうした古い機体を、定期的に
使ってあげて”状態をチェックする”という目的も
あるので、本ブログでは、こうしたオールドの
カメラやレンズを使うシリーズ記事の執筆が多く
なる訳である。
まあ、いずれも自分自身の研究目的や価値観維持等の
理由の為であり、あまり他者への情報提供や商品の
推奨、つまり「レビュー」やら「広告」や「投機性」
としての本ブログ記事の必然性(目的)は、全く無い。
よって、希少な機材などでは、「これは入手不能
につき非推奨、詳細情報も割愛」等と、ばっさり
切り捨ててしまうケースも多々ある訳だ。
本ブログの記事を原因や理由として、当該機種を
必死に探す人が増えてプレミアム相場等になるのは
好ましい状態では無いからだ。
で、本機α-7 DIGITALも、希少機であるが故に、
「どうしてもそれが欲しい」等と言う「好事家」が
出て来ないとも限らない。
念のために再度「現代における実用価値は皆無
であり、かつ、”動態保存”はかなり難しい機体」
と、締めくくっておく事にしよう。
---
では、今回ラストのオールド・デジタル一眼レフ。

(2004年発売、発売時実勢価格約10万円)
(中古購入価格 30,000円)
紹介記事:デジタル一眼レフ・クラッシックス第2回
レンズは、smc PENTAX-FA Macro 50mm/f2.8
(推定1991年頃発売)を使用する。
さて、本機発売の時代の2004年は「デジタル一眼
レフ元年」と私が呼んでいる位に、各社から、一般層
でも買える、安価な価格帯のデジタル一眼レフが
出揃った年(時代)であった。
その中でも本機PENTAX *istDsは、10万円を僅かに
切る新品実勢価格で、各社のデジタル一眼レフの
中でも、最も安価であった事が最大の特徴だ。
(注:この時代から「オープン価格」制度が増えて
きていて、なかなか正確な「定価」がわからない)

抜いておらず、他社製品と同等の600万画素CCD
撮像センサー(恐らくは各社で共通の部品を調達
したのであろう)であり、最高ISO感度はISO3200
と、前述のNIKON D2Hを除き、当時最高レベルで、
しかも、高感度域は他社機よりも実用的性能だ。
連写性能は低い(遅いし最大コマ数も少ない)が、
本機は連写性能を犠牲にして小型軽量化していて
発売時は世界最小、および重さも恐らくは最軽量
クラスであった事であろう。(本体のみ505g、
これは、CANON EOS Kiss Digital(初代)の
560gよりも軽い)
しかし、本機は、単三電池4本または、同等形状
のリチウム電池(例:CR-V3 x2本)を使用する
ので、その電源の重さは結構重い。
単三型電池の利用は、デジタル機では珍しく、
他社あるいは他機での専用バッテリー使用型に比べ
電源消耗時にも、コンビニや一般店舗等で乾電池
の購入は容易であるから、使用利便性はある。
ただし、マンガン電池での駆動は厳しく、最低限
アルカリ電池、できればリチウム/ニッケル水素系の
高性能乾電池/二次電池(充電式電池)を使わないと、
あっと言う間に電池が消耗してしまうので、これの
利点と弱点は隣り合わせだ。
(参考:現在、本機*istDsは経年劣化からか・・?
ハイパワー電池を用いないと起動しない状態である)
初期デジタル一眼レフ(それまでの時代における
デジタル・コンパクト機も同様)での、消費電力の
多さ、すなわち「バッテリーの持ち」は大きな課題
であって、2000年代初頭迄は、デジタル機のみで
丸1日の撮影をこなすことは、まず不可能であり、
「必ず銀塩機を併用する」などの必要性があった。
デジタル一眼レフでのバッテリーの持ちが改善
されるのは、ほぼこの時代、2004年発売のNIKON
D70(後日紹介、デジタル一眼第4回記事参照)
およびCANON EOS 20D(故障廃棄)からであり、
それらの機体であれば、1000枚程度の撮影を
なんとかこなす事が出来るようになった。
これはバッテリーが改良された事からではなく、
カメラの電子部品が低消費電力化された理由の
方が大きい。なお、さらに後年2000年代後半の
機種では、背面モニターの大型化や、内蔵手ブレ
補正機能の搭載により、従前の機種よりも
バッテリーの持ちが悪化した事もあったが、
2010年代前半くらいの機種からは、機種により
3000枚~6000枚程度の撮影枚数をこなせる程
に進歩していて、これであれば、丸一日の業務等
での撮影で、ほぼ撮影しっぱなし、という状況にも、
かろうじて耐えられる。
(注1:カメラを2台持ちで、交互に撮影するとか、
念の為に予備バッテリーを持てば、まず大丈夫)
(注2:各カメラのCIPA規格による撮影可能枚数仕様
表記の、5~6倍の枚数を撮る事を常に心がけている。
これは技能が必要だが、出来ない話では無い)
さて、本機*istDsであるが、連写性能と、AFの
精度・速度不足の課題を除き、他の重欠点は
見当たらず、なかなか優れた機体であると思う。
高感度性能は当時の他機よりもノイズが少なく、
AWB(オートホワイトバランス)機能は、割と
優秀で、複雑な光線状況にも良く対応している。
よって、本機は、暗所でのライブ等のステージ
撮影で長期間に渡って活躍したカメラとなっていた。
(その目的は後年にはPENTAX K-5で代替している。
K-5は、高感度ISO51200を搭載していて、かつ
シャッター音が静粛であるから、暗所イベント撮影
には極めて適切であった。後日紹介予定、又は
デジタル一眼第12回記事参照)

本機にも前述の「青色波長のエンハンス(増強補正)」
が少し見られ、気持ちの良い青空発色が得られる。
短所だが、AFの精度は、現代的な視点からすると
かなり厳しい。通常のAFモーター非搭載レンズでは、
ガタピシと細かい合焦動作を繰り返したり、あるいは
全くAFが合わなかったりもする。
この課題への対策としては、本機*istDsは、
ファインダーが優秀(ガラスペンタプリズム、
視野率95%、倍率0.95倍相当、ナチュラルブライト
マットスクリーン)である為、適宜MFを併用するか
又は、もう最初からMFでしか使わない事が賢明だ。
なお、本機の最初期のファームウェアでは、確か
AF-Cモードが無く、AF-Sでは、ピントが合わないと
シャッターが切れない(フォーカス優先)で
あったと記憶している。この状態では低いAF精度と
あいまって、殆ど撮影が不能(シャッターが
切れない)となるので、当時のビギナー層の間では
本機は、この課題がある為に不人気であった。
しかしながら、ファームウェアをアップデート
するか、あるいはMF撮影に特化してしまう事で、
AF精度の問題点は消える。この為、中級層や
マニア層の間では、本機*istDsは、価格の安さと
あいまって、コスパの良い機体として人気であった。
まあつまり、本機の話には限らないが、撮影機材の
評価は、利用者のスキルに依存してしまうという
訳である。本機のAFの弱点を、課題としか捉えられ
ないのであれば、本機はダメカメラとなってしまい、
「そんな問題は、いくらでも回避の手段はある」と
思い、それが実践できるのであれば、本機*istDsは
ハイコスパの名機となる。
ちなみに、デジタル一眼第2回記事における
本機の総合評価は、約3点と、ほぼ平均的だ。
ある意味平凡な評価点ではあるが、機材の長所短所
を良く理解して、適正な撮影目的において適正な
用法を行うのであれば、十分に実用的なカメラに
なりうる。
なお、AF問題を回避する為に、MFレンズを使う、
という選択肢は無きにしもあらずだ。何故ならば
PENTAX Kマウントは、銀塩MF/AF時代から、そして
デジタル時代となっても形状互換性が高いからだ。
ただし、本機*istDsでMFのレンズを使う際には、
PENTAX K(MF)マウントにおける、A型より前の
タイプ(K/P、M)は、使えない事は無いが、露出値
を得る為に、極めて煩雑な操作が必要とされるので、
実用範囲外だ。
またM42系列の場合、A/M切換スイッチを持つか
又はプリセット型であれば「マウントアダプターK」
の併用で絞り優先AE等で、かろうじて実用範囲だが、
それ以外のM42レンズは使用困難だ。
いずれにしても、このMFレンズでの用法は、マニア
級の知識と高い技能が必要とされ、一般初級中級層
には非推奨である。
(これは本機に限らず、その後のPENTAX デジタル
一眼レフ全般でも同様)
ただまあ、さすがに本機もまた仕様的老朽化寿命
に達してしまっている。現代においても、稀に
数千円という格安相場で本機が流通している状況
も見かけるが、これも「指名買い」をする類の
カメラでは無いであろう。

本機の後ダイヤル(の中のロータリーエンコーダー)
が接触不良を起こし易く、それが発生した場合には
CRC5-56等の潤滑/接点復活剤を注入して対応する。
(この問題は、各社のカメラでも稀に起こる)
まあ、オールドカメラでは物理的な老朽化の対策も
必要だ、という事である。
もう古い時代のカメラゆえに、もう少しだけ予算を
出せるのであれば、後年のPENTAX K-5(2010年)
あたりが、はるかに実用的で、かつ現代では低廉な
中古相場で、コスパが極めて良い状態となっている。
それと、今回の記事での紹介機は、本機*istDsを
除き、全てCF(コンパクトフラッシュ)カード使用機
である。CFカードの入手性は年々悪くなっていくので
これらの機体を現代でも実用としたい場合、その点は
要注意である。
----
では、今回の「オールド・デジカメ(1)」編は、
このあたり迄で、次回記事は、引き続き古い時代の
デジタル一眼レフ4機種を紹介する予定だ。