最強のマクロレンズを決定するシリーズ記事。
現在、「中望遠マクロ」のカテゴリー対戦中だが
本記事は、中望遠の最終の予選第4組とする。
次回記事からは、また別のカテゴリーとなる。
では早速、中望遠マクロの予選(4)を始めよう。
----
まずは最初の中望遠マクロレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズ名:YASHICA LENS ML MACRO 100mm/f3.5
レンズ購入価格:20,000円(中古)(以下、ML100/3.5)
使用カメラ:OLYMPUS PEN-F (μ4/3機)
詳細不明、恐らくは1980年前後に発売された、
フルサイズ対応MF中望遠ハーフ(1/2倍)マクロ。
マウントは、Y/C(RTS)である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
同一メーカー(京セラ)、同一マウント(RTS)で、極めて
高価な「CONTAX Makro-Planar T* 100mm/f2.8」
が別途存在する。(注:そちらが若干後での発売だ)
その価格差が物凄いので、販売期間では、そちらの
マクロプラナーばかりが注目され、それが高級・高性能
レンズとして「神格化」されていた様相があったと思う。
結果、本レンズ(ML100/3.5)は霞んでしまい、その
存在すらも、あまり知られていなかったかも知れない。
近年に、これを入手した際にも、若干の「レアもの」
扱いからか? 少し高価な値付けであるように思えた。
本レンズは、言ってみれば京セラの製品ラインナップ
上での「廉価版」であり、レンズ構成(4群6枚)等も、
コストダウンの措置で簡略化されている様相だ。
(MP100/2.8は、7群7枚、等倍マクロだ)
銀塩時代(1980年代頃)での、他社同等品としては、
*COSINA 100/3.5 MACRO(中望遠マクロ予選1)
*TOKINA 100/3.5 MACRO(中望遠マクロ予選2)
が、存在し、これらの企画意図、設計仕様、描写力、
価格感、等も、ほぼ本ML100/3.5と同等である。
これらは皆、「弱い平面マクロ」傾向を持ち、
解像感はやや強め、ボケが固く、ボケ質破綻が出る。
レンズ構成等が少し変化した(3群5枚等)同等品は、
*NIKON Ai105/4(中望遠マクロ予選1)
*KONICA AR105/4(中望遠マクロ予選2)
等が、別途存在し、これらの描写傾向は「やや強い
平面マクロ」であり、解像感がさらに強くなるが
依然、ボケが固く、ボケ質破綻も発生する。
(これらは、やや古い1970年代位の製品だ)
ここにあげた他社同等品は、いずれも1万円以下
程度の中古価格で入手している為、本ML100/3.5の
2万円という価格は、「コスパが悪い」と感じてしまう
要因となる。
要点としては、この時代(1970年代~1980年代頃)
における、こうしたシンプルなMFマクロレンズの
特性(弱い~やや強い~完全な、「平面マクロ」)を
どう捉えるか?であろう。
個人的には、銀塩時代では、これらの描写特性は、
「ボケが固い、撮れる被写体が限られる」という
観点で、あまり好きでは無かった。同様な特性を持つ
銀塩MFマクロは、他にも何本か所有していたが、
ことごとく処分(譲渡や売却)してしまっていた。
まあ「描写が好みでは無い」という理由の他に、この
時代の「一眼レフ+光学ファインダー開放測光」では
これらの癖のあるレンズの描写特性を撮影者が自在に
コントロールする事は、ほぼ不可能であり、「偶然に
左右される」点も、今から思い起こせば、機材環境面
での大きな課題であったのだろうと思われる。
だが、近年では撮影環境も変わり(例:ミラーレス機
による高精細EVFでの実絞り測光)、またデジタル化
で撮影コストが低減(=いくらでも試行錯誤が出来る)
された事で、この時代のMF「平面マクロ」であっても、
撮影者側での描写の制御(コントロール)が、若干だが
可能になった事がある。
さらには、近代マクロレンズの高性能化がある。
これは、近代(2000年代以降)のAF/等倍マクロは、
どれも非常に良く写り、描写力上の不満は殆ど無い。
その事自体は良いのだが、逆に「差別化が出来ない」
(=誰が撮っても同じように普通に良く写ってしまう)
また、「使いこなしの楽しみが無い」(難しいレンズを
使うテクニカルな要素が無く、面白くない)といった、
贅沢な不満が出てきてしまう訳だ。
なので、個人的にはこうした、銀塩MF時代のマクロ
(平面マクロ描写のあるもの)は、逆に好みのレンズと
なってきていて、近年では重点的に収集している。
中には、昔手放したものを再購入したケースもあり、
まあつまり「時代が変わった、機材環境も変わった、
よって、好みも変わった」という事になる。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08245805.jpg]()
本ML100/3.5は、若干だがクセが少なく、大人しい
描写だ。まあ他のエキセントリック(特異な)平面的
マクロより、やや実用的とは言えるのだが、現代の
私の好みからすると「もっと、ハジけていて欲しい」
という感じになる。
準レアものにつき、購入時には相場高騰に注意だ。
---
では、次のマクロレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08245843.jpg]()
レンズ名:LAOWA 100mm/f2.8 (CA-Dreamer)
(Ultra) Macro 2X (APO) (LAO0042)
レンズ購入価格:58,000円(新品)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)
2019年に発売された、MF中望遠2倍マクロレンズ。
正式名称は不明で、上記の()は、出典によっては
書かれている場合と、そうでないケースもある。
いずれにしても、最大撮影倍率が等倍(1:1、1倍)
を超える(2倍)マクロレンズは、まあ、スペック的
には珍しいとは言えるであろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08250513.jpg]()
ただまあ、例えば、50mm等倍マクロをμ4/3機に
装着するだけで、100mmの2倍と、本レンズと同等の
スペックとなる訳だから、現代においては、マクロ
レンズそのものの最大撮影倍率の仕様は、あまり重要視
する必要性は無いと思う。
肝心なのは良く写るかどうか? いや、そういう点では
多くのマクロレンズは描写力に優れるので、一般レンズ
に比べ(特に近接域では)良く写るのは当たり前の話だ。
さらに1歩踏み込んだ話をするならば、レンズ個々には
その企画・設計上で、どんな部分の性能を高めようと
したのかの「コンセプト」があるのだから、それをまず
見抜き、さらにそのコンセプトがユーザー自身の目的に
合致するか否か?あるいは、合致しなくとも、そのレンズ
の特徴を活かせる被写体環境等を「用途開発」出来るか
否か?が重要であろう。
で、本レンズでの「超」近接撮影は、非常に難しい。
だから、あまりこの「2倍マクロ」というスペックを
必要以上に期待したりする事は禁物だ。
実際に撮っていても、超近接では、極薄の被写界深度や
大きな被写体ブレ・手ブレ、高い露光倍数等により、
「上手く撮れない」と、ストレスを募らせる事となって
しまうので、むしろ・・
「ああ、もう適当に撮影倍率を下げて撮った方が
ずっと楽だよ。家に帰ったらトリミングしよう」
で、安直に済ませようと思ってしまう事の繰り返しだ。
なので「用途開発」は、正直、諦め気味である(汗)
まあ、三脚や台座にこれを固定し、学術的な用途、
例えば、小さい検体被写体の複写記録等には向くかも
知れないが、そうした用途では、さらなる超マクロ
(例:5倍程度の撮影倍率を持つ特殊マクロレンズ、
中一光学FreeWalker20mm/F2、等)が存在する
ので、本レンズは、やはり一般屋外撮影向けであろう。
LAOWAの創業者は、日本のカメラ(レンズ)メーカー
の技術者の出身と聞く。現代の日本のメーカーでは
レンズ市場の縮退により、売れるレンズ(ビギナー層
が欲しがる仕様で、かつ高価)しか、作る事ができない
事を知っていて(あるいは、憂いていて)LAOWAでは、
そうした日本メーカーが、手を出せない領域である、
特殊なスペックを持つレンズ群(アポダイゼーション、
超マクロ、超低歪曲、ドローン搭載用等)を付加価値
とした、比較的高価なレンズを開発販売する戦略を
取っている。
まあ、簡単に言えば「マニア向け戦略」または
「特定用途向け戦略」である。
私としては、LAOWA製品の特殊スペックは、特に
それが唯一無二の仕様である場合等では、気に入って
いて「コスト高は容認できるレベル」と見なしている。
つまり「付加価値が、正しく付加価値となっている」
という意味であり、この「付加価値」がメーカー側から
見た単なる「値上げの理由」になっている場合・・
例えば、レンズでは「超音波モーターと手ブレ補正を
搭載したので、高価になりました」という理屈や、
あるいは、カメラでは「フルサイズ化し、高速連写、
超高感度、4K動画等がついたから高価になりました」
・・では、それらの機能が、自身にとって有益とか
必要とか見なされない場合では、そうした要素を
「付加価値」とは、個人的には認めていない。
(=必要性が無いかぎり、好んでは買わない。
まあ、単純に「コスパが悪すぎる」からだ。)
LAOWA製品は、そういう類の「不要な付加価値」では
無いので、近年では重点的に購入しており、今後も
きっと購入数は増えていくだろう。
LAOWA製品全般、そして本レンズにも言える弱点だが、
まず、若干だが高価すぎる。この点は、現状、どれも
新品で購入せざるを得ない(=中古流通が少ない)
事が課題であり、これらがもっと売れてくれるならば
製造コストダウンも、中古入手性も増すので望ましい。
(ただ、マニア向けなので、あまり売れないだろう。
ビギナー層が欲しがるスペックでは決して無い)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08250538.jpg]()
もう1つの課題は描写力だ。
現状所有する範囲のLAOWAレンズは、どれも悪い描写力
では無いが、「あと一歩」という感覚が強い。
(個人評価点は、3.5~4点(5点満点)くらい)
これは、日本メーカーの技術者であった経歴は良いが
少しだけ設計思想が古い。まあつまり、非球面レンズや
異常低分散ガラス等を多用せず、比較的オーソドックス
な、銀塩時代レベルの設計・製造手法で、無難に纏め
られたレンズである事が原因だと思われる。
ただ、非球面や特殊硝材を用いるには、現在の中国
での製造技術水準では、少し厳しい(まだ使えない)
点もある。
そうした新技術は、日本のメーカー側も競争力の原点
であるから、あまり海外に(特に中国には)流出させ
たく無いのだろうと思われる。近年発売の他の(格安)
中国製レンズも同様であり、非球面レンズを採用
しているものは(2020年時点頃までは)1本も無い。
でも、噂によると、LAOWAも非球面研磨機を導入した
とも聞いている(2019年頃)、だとすると、近い将来
には、そうした新技術を用いて、国産レンズ並みの
レベルに上がった描写力を持つ、特殊レンズ群が
開発販売されるとしたら、かなり嬉しい状況だ。
(追記:本記事の執筆は2020年頃であったが、
本年2021年から、いくつかのLAOWA製品で、
ついに非球面レンズが搭載されるようになった)
LAOWAは、まだ発展途上である。「今後に大きく期待」
としておこう。
---
では、3本目のレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08250557.jpg]()
レンズ名:Voigtlander NOKTON 42.5mm/f0.95
(注:独語綴の変母音は省略)
レンズ購入価格:90,000円(新品)(以下、NOKTON42.5)
使用カメラ:PANASONIC DMC-G5(μ4/3機)
2013年発売のμ4/3機専用超大口径MF中望遠画角レンズ。
本レンズはマクロでは無いが、最短撮影距離が23cmと、
焦点距離10倍則を遥かに下回る優秀な近接性能を持ち、
その際の撮影倍率は1/4倍にも達する。
μ4/3機専用なので、フルサイズ換算倍率だとか、
デジタル拡大機能とかを言い出せば、さらに撮影
倍率はスペック的には高まるが、その数字の実用的な
意味は無く、ただ単に「寄れる超大口径レンズだ」と
認識しておけば良いであろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08250567.jpg]()
超大口径(F0.95)と、近接撮影能力により、多大
な背景(前景)ボケ量を得る事が出来るが、そうした
領域では、紙のように薄い被写界深度と、諸収差の
発生(増加)により、実用範囲以下の描写性能と
なってしまうケースも多発する。
ただ、そうなる事は承知の上で、その課題を回避
しながら使ったり、あるいは、あえてその欠点を強調
しつつ独特の描写表現を得る事は可能だ。
また、近接撮影にとどまらず、中距離の被写体を撮る
場合でも、この超大口径による、独特の世界観を得る
事が出来る。
人間の目では、被写界深度という概念を持たないので
目視している物は、はっきりと見えるのであるが、
本NOKTON42.5を通すと、目の前の多くの被写体に
おいて「注目点(合焦面)と、それ以外(ボケ部)」
を明確に区分する事が可能となる。
まあつまり、目で見えている世界と別物の世界観が
本レンズを通す事で得られる訳だ。
これにより、本レンズの【描写表現力】の個人評価点
は5点満点である。ただし、「描写力」だけを見れば
標準の3点か、あるいはそこにも届かない低評価にしか
ならないだろうが、ともかく「表現力」が凄まじい。
で、本レンズのその特徴を活かした使いこなしは、簡単な
話では無い。別シリーズ「レンズマニアックス第11/12回
使いこなしが難しいレンズ特集」記事においては、
本NOKTON42.5はワースト2位にランクインしてしまった。
まあ、つまり、とてもクセがあるレンズであり、かつ
使いこなしも難しい、ビギナー層ではお手上げになる
だろうから、上級マニア層の御用達レンズとも言える。
(追記:この時代(2010年代前半)のNOKTON F0.95
レンズの紹介記事では、いつも「描写力に劣る」と書き
続けて来たのだが、2020年発売のNOKTON 60/0.95
レンズでは描写力が大幅に改善された→後日紹介予定)
---
では、4本目のマクロレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08251260.jpg]()
レンズ名:TAMRON SP AF 90mm/f2.8 Di MACRO
1:1 USD(Model F004)
レンズ購入価格:25,000円(中古)(以下、SP90/2.8USD)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2012年に発売されたAF中望遠等倍マクロレンズ。
TAMRON 90 Macroシリーズでは、最も新しい光学系
を搭載しているのだが・・(注:後継F017型も同一)
USD(超音波モーター)仕様により、近接撮影時に
主力となるMF撮影時の操作性を、残念ながら悪化させて
しまったレンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08251240.jpg]()
まあ、TAMRONでは、旧来の72系列(72型=1996年、
172E型=1999年、272E型=2004年)の光学系の完成度
が極めて高く、かつ2000年代では、一眼レフはAPS-C
機が主流であった為(90mmは、換算135mmとなり
長すぎる為)8~9年間もバージョンアップが出来なかった
経緯がある。
2010年代では、フルサイズ一眼レフも多数発売され
(特に、この2012年は「フルサイズ元年」である)
新製品をリリースするタイミングであった要素がある。
ただ、光学系に72系列以上の改善を施す事は難しく、
光学系は小改良(=ほとんどわからない。中遠距離
撮影時の描写力改善程度か?)に留まってしまい、
それでもレンズ市場縮退から、(悪い意味での)
高付加価値化をせざるを得ず、結果的に、安直な策、
つまり「手ブレ補正搭載、超音波モーター搭載」に
手をつけ、結果、272E型の定価68,000円から、
F004型では、定価90,000円への約32%の値上げを
実施している(=レンズの販売数が減っているので
利益率を高めないとメーカーは事業が維持できない)
ただ、TAMRONは良心的な社風も持ち合わせているので、
272E型は生産中止にはせず、これは併売されていた。
(注:2019年頃に生産終了)
まあ、つまり「超音波モーターを入れたら、近接
撮影では使い難くなる」事は、設計側でも承知して
いるのであろう。でも、この時代では、他社が全て
同様な戦略を取っているから、「なんだ、TAMRONの
マクロだけ超音波なしかよ? 技術力が低いのか?」
等と、ビギナー主体の消費者層から、余計な邪知を
されない意味での対策なのであろう。
この事実は、もう、消費者またはユーザー側が、
あまりに未熟である事を起因としているのだが、
それはもう、この時代(2010年代)では、ビギナー
しか新鋭機材を買ってくれないので、やむを得ない。
まあ良い、問題点は全て分析できているし、課題
への対策も色々とわかって来ている、具体的には
「デジタル一眼レフ・クラッシックス第26回α99編」
で、本レンズSP90/2.8USDの、MF問題をどう回避
していくか?の実例を色々と紹介している。
MFの問題点が解決できるのであれば、本F004型は
ほぼ完成の域にあった272E型(本シリーズ中望遠
マクロ編予選第1回戦)を、さらに改良したもので
あるから、描写力的な不満は、殆ど存在しない。
(描写表現力個人評価点4.5点(5点満点)、ただし
これはやや厳しい評価であり、実質4.7点位か?)
本レンズ(又は他のSP90/2.8Macro)は、本シリーズ
記事での決勝戦あるいはB決勝戦にノミネートされる
べきレンズであろう。
---
では、5本目のマクロレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08251292.jpg]()
レンズ名:TOKINA AT-X M100 PRO D (100mm/f2.8)
レンズ購入価格:20,000円(中古)(以下、AT-X M100)
使用カメラ:NIKON D70(APS-C機)
2005年に発売された、フルサイズ対応AF中望遠等倍
マクロレンズ。
TOKINAのマクロは、著名なTAMRON製中望遠(90mm)
マクロの影に隠れて、全く目立たない。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08251222.jpg]()
まあ”SIGMAも同様だ”とも言えるが、SIGMAの場合は
「カミソリマクロ」等のマニアックな異名や好評価も
存在しているから、若干はマニア層へのウケは良い。
また、マニア層の特性として「誰でも知っている
有名な商品を所有する事を嫌う」という性質もある。
それは「そういう物を欲しがるビギナー層とは違うのだ」
という差別化要因・個性の主張など、色々な心理が
存在しているからだ。これはカメラやレンズの例に
限らず、あらゆる商品分野で共通の性質だと思うが、
その考え方が度を越すと「誰も持っていない商品を
集める事がマニアなのだ!」と、ちょっと変な方向性
に走ってしまいかねない、そうなるともう、マニアと
言うよりも、「好事家」の領域に入ってしまい、
「際限なく、希少なモノを求めるようになってしまう」
ので要注意だ。
さて、TOKINAのマクロだが、「商品」としてこれが
存在する以上、TAMRONやSIGMAのマクロに対して
劣った性能の物を販売する訳にはいかない。
知名度が低い状況かつ、仕様もほとんど同じ状態で、
誰が見ても性能が劣っているならば、商品が売れず、
もう極端に値下げをする、とかしか対抗策が無い。
だけど、そうせずに普通に市場において対抗する
のであれば、もうそれは「ちゃんとした性能を持つ
製品」であろう。さもなければ、”全く勝ち目の無い
土俵に上がる事は無い”からだ。
その事実を確かめたいと思って、私も、近年では
TOKINA製の(中望遠)マクロを、重点的に購入して
いる。総合的な纏めは「レンズマニアックス第70回
知られざるTOKINAマクロ編」(掲載予定)に詳しい。
その評価は、案の定、「どれも悪く無いマクロだ」
という結論になっている。やはり”性能の低い製品で
他社に対抗しよう”等の愚行を犯す筈が無いからだ。
ただ、気になる点は、「飛びぬけた長所・特徴は
持っていない」という事実がある。
まあ、非常にざっくりと言えば・・
*TAMRONの90mm系(マクロ)は、(近代のものは)
「近接撮影時の高い描写力」を主眼としている。
*SIGMAの50/70/105/150系マクロは、
「高い解像感」(シャープネス)を優先だ。
対して、TOKINAは、その製品数は多くは無いが、
本レンズの場合は、「万能タイプ」であるように
思える。近接もよし、中距離もよし、という感じでは
あるが、反面、個性や特徴が無い「優等生」タイプだ。
これらTOKINA製マクロ、あるいは本レンズを、どう
使っていくか?の「用途開発」は、なかなか難しい。
あくまで感覚的、あるいはユーザー個々の好みや
志向性やスタイルに依存するとは思うのだが、
「本レンズAT-X M100でなくてはならない」という
用途が、あまり思いつかないのだ。
まあ、「たった1本の中望遠マクロしか持たない」
というビギナー層向けには、”被写体汎用性が高い”
ので、実用価値も高いとは言えるであろう。
(注:TAMRON90MACRO系は中遠距離撮影に弱い、
SIGMA系MACROはボケを生かした表現に弱い)
でも、マニア層等では「TAMRONやSIGMAのMACRO
を持っていない」という人は、まず居ないので、
それらの、特徴のある(強い武器を持つ)マクロと
並行して、万能タイプのマクロを別途持つ必要性が
あるのか否か? そのあたりが、どうも疑問となる。
また、販売数が少ないからか?中古相場もこなれて
おらず、2万円の入手価格は、この時代(2000年代)
のTAMRONやSIGMAのマクロと比べて、若干高価だ。
つまり「コスパが悪い」という切実な問題に繋がり
ここが本レンズの最大の課題であろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08252866.jpg]()
決して悪いレンズでは無いが、用途とコスパ、そこを
どう判断するか?が、本レンズの購入検討項目だ。
---
では、6本目のレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08252823.jpg]()
レンズ名:OLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO 100mm/f2
レンズ購入価格: 35,000円(中古)(以下、OM100/2)
使用カメラ:PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
発売年不明、恐らくは1980年代頃と思われる大口径
単焦点MF中望遠レンズ。
本レンズはマクロでは無いのだが、最短撮影距離70cm
を誇り、銀塩MF時代の100mm単焦点レンズとしては
トップ(?)クラスの近接撮影能力であろう。
ただ、これでも撮影倍率は計算上約0.14倍(1/7倍)
にしかならない。しかしμ4/3機への装着や、今回の
母艦DMC-G6に備わる、各種デジタル拡大機能を併用
すれば、簡単に等倍以上の撮影倍率を得る事は可能だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08252885.jpg]()
ちなみに、マクロでは無い100mm単焦点レンズで
マクロ切換を持つレンズとしては、前記事で紹介の
「SONY FE100mm/F2.8 STF GM」があり、これは
57cmの最短撮影距離で撮影倍率0.25倍(1/4倍)。
一応、こちらが100mmレンズ中、トップだと思われる。
さらに、ロシアンレンズ系の記事で良く紹介する
「アルセナール MC KALEINAR-5N 100mm/f2.8」
は、80cmの最短撮影距離で約1/8倍程度。
他には「MINOLTA AF SOFT FOCUS 100mm/f2.8」
(特殊レンズ第7回記事等)も、同じく80cmの最短。
まあ、これらも寄れる100mmレンズだ。
上記は記憶に頼って書いているので、抜けがあるかも
知れないが、他にあまり寄れる100mmレンズを
見た事が無い、普通は1m程度の最短撮影距離だ。
なのでまあ、恐らくはこのあたりの100mmレンズが
トップクラスであろう。(勿論、マクロは例外だ)
で、寄れる事はわかったが、描写力はどうか?
これについては、本OM100/2は、全般的に悪く無い。
銀塩時代でのオーソドックスな設計(6群7枚)
であり、これは場合により、50mm/F1.4級大口径
標準レンズを2倍にスケールアップした、「自社内
ジェネリック設計」なのかも知れないが、あまり
情報が無く、詳しい出自は不明だ。
ただ、このシリーズのOM F2級中望遠は、「レンズ
設計の教科書」にも引用されている事もあるくらい
で、まあ、当時としては、ちゃんとした設計だ。
「描写表現力」は4.5点(5点満点)と、優秀である。
ただし、この評価点は、どちらかと言えば「表現力」
に重きを置いた評価であり、描写力は3.5~4点、
表現力が4~4.5点あたりと思っておくのが妥当だ。
課題は、小型軽量な事を特徴とするOM-SYSTEMの
レンズとしては、やや大型であり、高価でもあった
事から、販売数が極めて少ないと思われ、後年の
中古市場でも、殆ど流通していない。
つまり、「入手困難なレアものレンズ」となって
いる事が大きな問題点だ。
購入時価格の35,000円は、コスパ評価2.5点。
つまり「これではやや高い」という評価であるから
2万円台後半が妥当だ。仮に、銀塩標準50mm/1.4の
2倍拡大レンズであれば、そのあたりの相場が適正
という感覚であろう。
しかし、現代の中古市場においては、本OM100/2は
まず見つからず、仮にあったとしても希少性からの
プレミアム相場(8~10万円程度、あるいは時価)
となるだろう。
勿論、そこまで値段を出して買うべきレンズでは無い。
「どんな感じに写るのか?」を体感したいのであれば
任意の50m/F1.4標準レンズを持ち出し、μ4/3機
に装着してみれば良い。それがOM100/2のフルサイズ
での使用感と、ほぼ共通の雰囲気、かつ、ほぼ同等の
描写力になると思う。おまけに、その場合では
標準レンズの最短撮影距離は一般に45cmであるので、
本OM100/2(最短70cm)をフルサイズ機で使った
場合よりも、撮影倍率を高める事が出来る。
で、本OM100/2を、μ4/3機で使う意味(意義)は、
「望遠マクロの代用とする事、撮影倍率を高める事、
その際にも、開放F値がF2と明るい事(撮影倍率
を高めた場合での「露光倍数」の影響が少ない)」
と、かなり特殊な用途・目的を狙っての事である。
一般撮影時でのμ4/3機の使用は、200mm単焦点
となり、あまり汎用的な被写体に向くレンズだとは
言えなくなるので、あくまで用途に依存した母艦選択
が必要だ。
総括だが、レアものにつき、非推奨だ。
----
さて、次は本記事ラストのマクロレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08252854.jpg]()
レンズ名:TAMRON SP AF60mm/f2 Di Ⅱ LD [IF]
MACRO 1:1 (Model G005)
レンズ購入価格:20,000円(中古)(以下、SP60/2)
使用カメラ:SONY α65 (APS-C機)
2009年に発売された、APS-C機専用、中望遠画角
大口径AF等倍マクロレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08253444.jpg]()
開放F2級マクロレンズは、OLYMPUS(OM、4/3)、
ZEISS等から、そして本レンズと、数える程しか機種数
が無いと思われる。が、その中でも、等倍マクロ仕様の
物は本SP60/2しか存在していなかったと記憶している。
前述の90マクロの改良停止期間(2004年~2012年)
の間において、APS-C機(一眼レフ)ユーザーを
ターゲットとして発売された、90マクロ代替レンズ
であろう。
ただ、優秀な90マクロ(72E系)の代替とするので
あれば、それ相応の高描写力が要求される。
さもないと、これまで52B(1979年)から数十年間
もの間で築いてきた、「高性能マクロのTAMRON」の
ブランドイメージに泥を塗ってしまうからだ。
よって、本レンズは、まずスペック的には世界初
である「大口径F2マクロで等倍」を与えられた。
また、焦点距離が比較的短い(標準域)でありながら、
比較的長いWD(ワーキング・ディスタンス)を確保
している。(=レンズ前から被写体までの撮影距離。
これが長くできるのは、レンズ長を短くしたからだ。
でも、単に”長ければ良い”というものでも無い)
描写傾向だが、カリカリに解像感が強い特性だ。
これは90マクロシリーズと、あえて差別化した
特性から、かも知れず、主にビギナー層に向けての
携帯カメラや初期スマホ、初期ミーラレス機との
差別化要因もあったかも知れない。
すなわち「一眼レフ用のマクロは、こんなにも
はっきり、くっきり、シャープに写るのですよ」
というアピールである。
ただ、中上級層にとってみれば、この特性は
マクロレンズとしてはやや過剰であり、「被写体を
選ぶ」という、微妙な不満に繋がるかも知れない。
課題は、その特徴的な描写特性の他にもある。
シームレスMF(フルタイムマニュアル)機構を
採用しているが、これは、マクロレンズとしては
やや使い難い。MFならMFに特化した方が、中上級層
にとっては使い易い事は確実ではあるが、まあでも
前述のように、本レンズのターゲットユーザーが
ビギナー層であるならば、そうした高度なMF技法を
使う人は、まず誰もおらず、「AFで合わせてみた、
ピントが合い難いので、MFに変えてみた」程度の
初級MF技法しか使わないと思われるので、まあこの
仕様でも、やむを得ないのであろう。
総合的には、初級中級層向けのレンズだ。
ただまあ、描写特性は個性的ではあるので、
実践派マニア層等で、このシームレスMFの課題を
回避して使える腕前があるならば、推奨できる。
おまけに、2010年代後半からは、フルサイズ機
の普及により、こうしたAPS-C機専用レンズは
不人気で、相場がかなり下落している。
現代では、1万円台後半等の、かなり安価な価格で
これを購入出来るため、総合的なコスパはかなり良い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_08253414.jpg]()
本レンズは、コスパ評価点が良い為、過去記事の
「ハイコスパレンズBEST40」では、総合15位の
上位にランクインした強豪レンズとなっている。
ただまあ、本シリーズ「最強マクロ選手権」では
純粋な実力勝負が主眼なので、本レンズが決勝戦
やB決勝戦にノミネートされるか?は微妙だ。
(まあ、ちょっと無理かも知れない)
----
次回の本シリーズ記事は、
「最強マクロ選手権・望遠マクロ・予選(1)」を予定。
現在、「中望遠マクロ」のカテゴリー対戦中だが
本記事は、中望遠の最終の予選第4組とする。
次回記事からは、また別のカテゴリーとなる。
では早速、中望遠マクロの予選(4)を始めよう。
----
まずは最初の中望遠マクロレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:20,000円(中古)(以下、ML100/3.5)
使用カメラ:OLYMPUS PEN-F (μ4/3機)
詳細不明、恐らくは1980年前後に発売された、
フルサイズ対応MF中望遠ハーフ(1/2倍)マクロ。
マウントは、Y/C(RTS)である。
Clik here to view.

高価な「CONTAX Makro-Planar T* 100mm/f2.8」
が別途存在する。(注:そちらが若干後での発売だ)
その価格差が物凄いので、販売期間では、そちらの
マクロプラナーばかりが注目され、それが高級・高性能
レンズとして「神格化」されていた様相があったと思う。
結果、本レンズ(ML100/3.5)は霞んでしまい、その
存在すらも、あまり知られていなかったかも知れない。
近年に、これを入手した際にも、若干の「レアもの」
扱いからか? 少し高価な値付けであるように思えた。
本レンズは、言ってみれば京セラの製品ラインナップ
上での「廉価版」であり、レンズ構成(4群6枚)等も、
コストダウンの措置で簡略化されている様相だ。
(MP100/2.8は、7群7枚、等倍マクロだ)
銀塩時代(1980年代頃)での、他社同等品としては、
*COSINA 100/3.5 MACRO(中望遠マクロ予選1)
*TOKINA 100/3.5 MACRO(中望遠マクロ予選2)
が、存在し、これらの企画意図、設計仕様、描写力、
価格感、等も、ほぼ本ML100/3.5と同等である。
これらは皆、「弱い平面マクロ」傾向を持ち、
解像感はやや強め、ボケが固く、ボケ質破綻が出る。
レンズ構成等が少し変化した(3群5枚等)同等品は、
*NIKON Ai105/4(中望遠マクロ予選1)
*KONICA AR105/4(中望遠マクロ予選2)
等が、別途存在し、これらの描写傾向は「やや強い
平面マクロ」であり、解像感がさらに強くなるが
依然、ボケが固く、ボケ質破綻も発生する。
(これらは、やや古い1970年代位の製品だ)
ここにあげた他社同等品は、いずれも1万円以下
程度の中古価格で入手している為、本ML100/3.5の
2万円という価格は、「コスパが悪い」と感じてしまう
要因となる。
要点としては、この時代(1970年代~1980年代頃)
における、こうしたシンプルなMFマクロレンズの
特性(弱い~やや強い~完全な、「平面マクロ」)を
どう捉えるか?であろう。
個人的には、銀塩時代では、これらの描写特性は、
「ボケが固い、撮れる被写体が限られる」という
観点で、あまり好きでは無かった。同様な特性を持つ
銀塩MFマクロは、他にも何本か所有していたが、
ことごとく処分(譲渡や売却)してしまっていた。
まあ「描写が好みでは無い」という理由の他に、この
時代の「一眼レフ+光学ファインダー開放測光」では
これらの癖のあるレンズの描写特性を撮影者が自在に
コントロールする事は、ほぼ不可能であり、「偶然に
左右される」点も、今から思い起こせば、機材環境面
での大きな課題であったのだろうと思われる。
だが、近年では撮影環境も変わり(例:ミラーレス機
による高精細EVFでの実絞り測光)、またデジタル化
で撮影コストが低減(=いくらでも試行錯誤が出来る)
された事で、この時代のMF「平面マクロ」であっても、
撮影者側での描写の制御(コントロール)が、若干だが
可能になった事がある。
さらには、近代マクロレンズの高性能化がある。
これは、近代(2000年代以降)のAF/等倍マクロは、
どれも非常に良く写り、描写力上の不満は殆ど無い。
その事自体は良いのだが、逆に「差別化が出来ない」
(=誰が撮っても同じように普通に良く写ってしまう)
また、「使いこなしの楽しみが無い」(難しいレンズを
使うテクニカルな要素が無く、面白くない)といった、
贅沢な不満が出てきてしまう訳だ。
なので、個人的にはこうした、銀塩MF時代のマクロ
(平面マクロ描写のあるもの)は、逆に好みのレンズと
なってきていて、近年では重点的に収集している。
中には、昔手放したものを再購入したケースもあり、
まあつまり「時代が変わった、機材環境も変わった、
よって、好みも変わった」という事になる。
Clik here to view.

描写だ。まあ他のエキセントリック(特異な)平面的
マクロより、やや実用的とは言えるのだが、現代の
私の好みからすると「もっと、ハジけていて欲しい」
という感じになる。
準レアものにつき、購入時には相場高騰に注意だ。
---
では、次のマクロレンズ。
Clik here to view.

(Ultra) Macro 2X (APO) (LAO0042)
レンズ購入価格:58,000円(新品)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)
2019年に発売された、MF中望遠2倍マクロレンズ。
正式名称は不明で、上記の()は、出典によっては
書かれている場合と、そうでないケースもある。
いずれにしても、最大撮影倍率が等倍(1:1、1倍)
を超える(2倍)マクロレンズは、まあ、スペック的
には珍しいとは言えるであろう。
Clik here to view.

装着するだけで、100mmの2倍と、本レンズと同等の
スペックとなる訳だから、現代においては、マクロ
レンズそのものの最大撮影倍率の仕様は、あまり重要視
する必要性は無いと思う。
肝心なのは良く写るかどうか? いや、そういう点では
多くのマクロレンズは描写力に優れるので、一般レンズ
に比べ(特に近接域では)良く写るのは当たり前の話だ。
さらに1歩踏み込んだ話をするならば、レンズ個々には
その企画・設計上で、どんな部分の性能を高めようと
したのかの「コンセプト」があるのだから、それをまず
見抜き、さらにそのコンセプトがユーザー自身の目的に
合致するか否か?あるいは、合致しなくとも、そのレンズ
の特徴を活かせる被写体環境等を「用途開発」出来るか
否か?が重要であろう。
で、本レンズでの「超」近接撮影は、非常に難しい。
だから、あまりこの「2倍マクロ」というスペックを
必要以上に期待したりする事は禁物だ。
実際に撮っていても、超近接では、極薄の被写界深度や
大きな被写体ブレ・手ブレ、高い露光倍数等により、
「上手く撮れない」と、ストレスを募らせる事となって
しまうので、むしろ・・
「ああ、もう適当に撮影倍率を下げて撮った方が
ずっと楽だよ。家に帰ったらトリミングしよう」
で、安直に済ませようと思ってしまう事の繰り返しだ。
なので「用途開発」は、正直、諦め気味である(汗)
まあ、三脚や台座にこれを固定し、学術的な用途、
例えば、小さい検体被写体の複写記録等には向くかも
知れないが、そうした用途では、さらなる超マクロ
(例:5倍程度の撮影倍率を持つ特殊マクロレンズ、
中一光学FreeWalker20mm/F2、等)が存在する
ので、本レンズは、やはり一般屋外撮影向けであろう。
LAOWAの創業者は、日本のカメラ(レンズ)メーカー
の技術者の出身と聞く。現代の日本のメーカーでは
レンズ市場の縮退により、売れるレンズ(ビギナー層
が欲しがる仕様で、かつ高価)しか、作る事ができない
事を知っていて(あるいは、憂いていて)LAOWAでは、
そうした日本メーカーが、手を出せない領域である、
特殊なスペックを持つレンズ群(アポダイゼーション、
超マクロ、超低歪曲、ドローン搭載用等)を付加価値
とした、比較的高価なレンズを開発販売する戦略を
取っている。
まあ、簡単に言えば「マニア向け戦略」または
「特定用途向け戦略」である。
私としては、LAOWA製品の特殊スペックは、特に
それが唯一無二の仕様である場合等では、気に入って
いて「コスト高は容認できるレベル」と見なしている。
つまり「付加価値が、正しく付加価値となっている」
という意味であり、この「付加価値」がメーカー側から
見た単なる「値上げの理由」になっている場合・・
例えば、レンズでは「超音波モーターと手ブレ補正を
搭載したので、高価になりました」という理屈や、
あるいは、カメラでは「フルサイズ化し、高速連写、
超高感度、4K動画等がついたから高価になりました」
・・では、それらの機能が、自身にとって有益とか
必要とか見なされない場合では、そうした要素を
「付加価値」とは、個人的には認めていない。
(=必要性が無いかぎり、好んでは買わない。
まあ、単純に「コスパが悪すぎる」からだ。)
LAOWA製品は、そういう類の「不要な付加価値」では
無いので、近年では重点的に購入しており、今後も
きっと購入数は増えていくだろう。
LAOWA製品全般、そして本レンズにも言える弱点だが、
まず、若干だが高価すぎる。この点は、現状、どれも
新品で購入せざるを得ない(=中古流通が少ない)
事が課題であり、これらがもっと売れてくれるならば
製造コストダウンも、中古入手性も増すので望ましい。
(ただ、マニア向けなので、あまり売れないだろう。
ビギナー層が欲しがるスペックでは決して無い)
Clik here to view.

現状所有する範囲のLAOWAレンズは、どれも悪い描写力
では無いが、「あと一歩」という感覚が強い。
(個人評価点は、3.5~4点(5点満点)くらい)
これは、日本メーカーの技術者であった経歴は良いが
少しだけ設計思想が古い。まあつまり、非球面レンズや
異常低分散ガラス等を多用せず、比較的オーソドックス
な、銀塩時代レベルの設計・製造手法で、無難に纏め
られたレンズである事が原因だと思われる。
ただ、非球面や特殊硝材を用いるには、現在の中国
での製造技術水準では、少し厳しい(まだ使えない)
点もある。
そうした新技術は、日本のメーカー側も競争力の原点
であるから、あまり海外に(特に中国には)流出させ
たく無いのだろうと思われる。近年発売の他の(格安)
中国製レンズも同様であり、非球面レンズを採用
しているものは(2020年時点頃までは)1本も無い。
でも、噂によると、LAOWAも非球面研磨機を導入した
とも聞いている(2019年頃)、だとすると、近い将来
には、そうした新技術を用いて、国産レンズ並みの
レベルに上がった描写力を持つ、特殊レンズ群が
開発販売されるとしたら、かなり嬉しい状況だ。
(追記:本記事の執筆は2020年頃であったが、
本年2021年から、いくつかのLAOWA製品で、
ついに非球面レンズが搭載されるようになった)
LAOWAは、まだ発展途上である。「今後に大きく期待」
としておこう。
---
では、3本目のレンズ。
Clik here to view.

(注:独語綴の変母音は省略)
レンズ購入価格:90,000円(新品)(以下、NOKTON42.5)
使用カメラ:PANASONIC DMC-G5(μ4/3機)
2013年発売のμ4/3機専用超大口径MF中望遠画角レンズ。
本レンズはマクロでは無いが、最短撮影距離が23cmと、
焦点距離10倍則を遥かに下回る優秀な近接性能を持ち、
その際の撮影倍率は1/4倍にも達する。
μ4/3機専用なので、フルサイズ換算倍率だとか、
デジタル拡大機能とかを言い出せば、さらに撮影
倍率はスペック的には高まるが、その数字の実用的な
意味は無く、ただ単に「寄れる超大口径レンズだ」と
認識しておけば良いであろう。
Clik here to view.

な背景(前景)ボケ量を得る事が出来るが、そうした
領域では、紙のように薄い被写界深度と、諸収差の
発生(増加)により、実用範囲以下の描写性能と
なってしまうケースも多発する。
ただ、そうなる事は承知の上で、その課題を回避
しながら使ったり、あるいは、あえてその欠点を強調
しつつ独特の描写表現を得る事は可能だ。
また、近接撮影にとどまらず、中距離の被写体を撮る
場合でも、この超大口径による、独特の世界観を得る
事が出来る。
人間の目では、被写界深度という概念を持たないので
目視している物は、はっきりと見えるのであるが、
本NOKTON42.5を通すと、目の前の多くの被写体に
おいて「注目点(合焦面)と、それ以外(ボケ部)」
を明確に区分する事が可能となる。
まあつまり、目で見えている世界と別物の世界観が
本レンズを通す事で得られる訳だ。
これにより、本レンズの【描写表現力】の個人評価点
は5点満点である。ただし、「描写力」だけを見れば
標準の3点か、あるいはそこにも届かない低評価にしか
ならないだろうが、ともかく「表現力」が凄まじい。
で、本レンズのその特徴を活かした使いこなしは、簡単な
話では無い。別シリーズ「レンズマニアックス第11/12回
使いこなしが難しいレンズ特集」記事においては、
本NOKTON42.5はワースト2位にランクインしてしまった。
まあ、つまり、とてもクセがあるレンズであり、かつ
使いこなしも難しい、ビギナー層ではお手上げになる
だろうから、上級マニア層の御用達レンズとも言える。
(追記:この時代(2010年代前半)のNOKTON F0.95
レンズの紹介記事では、いつも「描写力に劣る」と書き
続けて来たのだが、2020年発売のNOKTON 60/0.95
レンズでは描写力が大幅に改善された→後日紹介予定)
---
では、4本目のマクロレンズ。
Clik here to view.

1:1 USD(Model F004)
レンズ購入価格:25,000円(中古)(以下、SP90/2.8USD)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2012年に発売されたAF中望遠等倍マクロレンズ。
TAMRON 90 Macroシリーズでは、最も新しい光学系
を搭載しているのだが・・(注:後継F017型も同一)
USD(超音波モーター)仕様により、近接撮影時に
主力となるMF撮影時の操作性を、残念ながら悪化させて
しまったレンズである。
Clik here to view.

172E型=1999年、272E型=2004年)の光学系の完成度
が極めて高く、かつ2000年代では、一眼レフはAPS-C
機が主流であった為(90mmは、換算135mmとなり
長すぎる為)8~9年間もバージョンアップが出来なかった
経緯がある。
2010年代では、フルサイズ一眼レフも多数発売され
(特に、この2012年は「フルサイズ元年」である)
新製品をリリースするタイミングであった要素がある。
ただ、光学系に72系列以上の改善を施す事は難しく、
光学系は小改良(=ほとんどわからない。中遠距離
撮影時の描写力改善程度か?)に留まってしまい、
それでもレンズ市場縮退から、(悪い意味での)
高付加価値化をせざるを得ず、結果的に、安直な策、
つまり「手ブレ補正搭載、超音波モーター搭載」に
手をつけ、結果、272E型の定価68,000円から、
F004型では、定価90,000円への約32%の値上げを
実施している(=レンズの販売数が減っているので
利益率を高めないとメーカーは事業が維持できない)
ただ、TAMRONは良心的な社風も持ち合わせているので、
272E型は生産中止にはせず、これは併売されていた。
(注:2019年頃に生産終了)
まあ、つまり「超音波モーターを入れたら、近接
撮影では使い難くなる」事は、設計側でも承知して
いるのであろう。でも、この時代では、他社が全て
同様な戦略を取っているから、「なんだ、TAMRONの
マクロだけ超音波なしかよ? 技術力が低いのか?」
等と、ビギナー主体の消費者層から、余計な邪知を
されない意味での対策なのであろう。
この事実は、もう、消費者またはユーザー側が、
あまりに未熟である事を起因としているのだが、
それはもう、この時代(2010年代)では、ビギナー
しか新鋭機材を買ってくれないので、やむを得ない。
まあ良い、問題点は全て分析できているし、課題
への対策も色々とわかって来ている、具体的には
「デジタル一眼レフ・クラッシックス第26回α99編」
で、本レンズSP90/2.8USDの、MF問題をどう回避
していくか?の実例を色々と紹介している。
MFの問題点が解決できるのであれば、本F004型は
ほぼ完成の域にあった272E型(本シリーズ中望遠
マクロ編予選第1回戦)を、さらに改良したもので
あるから、描写力的な不満は、殆ど存在しない。
(描写表現力個人評価点4.5点(5点満点)、ただし
これはやや厳しい評価であり、実質4.7点位か?)
本レンズ(又は他のSP90/2.8Macro)は、本シリーズ
記事での決勝戦あるいはB決勝戦にノミネートされる
べきレンズであろう。
---
では、5本目のマクロレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:20,000円(中古)(以下、AT-X M100)
使用カメラ:NIKON D70(APS-C機)
2005年に発売された、フルサイズ対応AF中望遠等倍
マクロレンズ。
TOKINAのマクロは、著名なTAMRON製中望遠(90mm)
マクロの影に隠れて、全く目立たない。
Clik here to view.
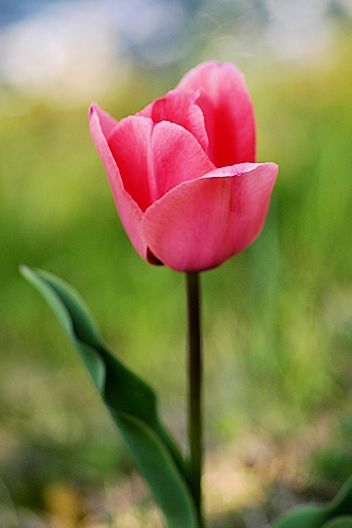
「カミソリマクロ」等のマニアックな異名や好評価も
存在しているから、若干はマニア層へのウケは良い。
また、マニア層の特性として「誰でも知っている
有名な商品を所有する事を嫌う」という性質もある。
それは「そういう物を欲しがるビギナー層とは違うのだ」
という差別化要因・個性の主張など、色々な心理が
存在しているからだ。これはカメラやレンズの例に
限らず、あらゆる商品分野で共通の性質だと思うが、
その考え方が度を越すと「誰も持っていない商品を
集める事がマニアなのだ!」と、ちょっと変な方向性
に走ってしまいかねない、そうなるともう、マニアと
言うよりも、「好事家」の領域に入ってしまい、
「際限なく、希少なモノを求めるようになってしまう」
ので要注意だ。
さて、TOKINAのマクロだが、「商品」としてこれが
存在する以上、TAMRONやSIGMAのマクロに対して
劣った性能の物を販売する訳にはいかない。
知名度が低い状況かつ、仕様もほとんど同じ状態で、
誰が見ても性能が劣っているならば、商品が売れず、
もう極端に値下げをする、とかしか対抗策が無い。
だけど、そうせずに普通に市場において対抗する
のであれば、もうそれは「ちゃんとした性能を持つ
製品」であろう。さもなければ、”全く勝ち目の無い
土俵に上がる事は無い”からだ。
その事実を確かめたいと思って、私も、近年では
TOKINA製の(中望遠)マクロを、重点的に購入して
いる。総合的な纏めは「レンズマニアックス第70回
知られざるTOKINAマクロ編」(掲載予定)に詳しい。
その評価は、案の定、「どれも悪く無いマクロだ」
という結論になっている。やはり”性能の低い製品で
他社に対抗しよう”等の愚行を犯す筈が無いからだ。
ただ、気になる点は、「飛びぬけた長所・特徴は
持っていない」という事実がある。
まあ、非常にざっくりと言えば・・
*TAMRONの90mm系(マクロ)は、(近代のものは)
「近接撮影時の高い描写力」を主眼としている。
*SIGMAの50/70/105/150系マクロは、
「高い解像感」(シャープネス)を優先だ。
対して、TOKINAは、その製品数は多くは無いが、
本レンズの場合は、「万能タイプ」であるように
思える。近接もよし、中距離もよし、という感じでは
あるが、反面、個性や特徴が無い「優等生」タイプだ。
これらTOKINA製マクロ、あるいは本レンズを、どう
使っていくか?の「用途開発」は、なかなか難しい。
あくまで感覚的、あるいはユーザー個々の好みや
志向性やスタイルに依存するとは思うのだが、
「本レンズAT-X M100でなくてはならない」という
用途が、あまり思いつかないのだ。
まあ、「たった1本の中望遠マクロしか持たない」
というビギナー層向けには、”被写体汎用性が高い”
ので、実用価値も高いとは言えるであろう。
(注:TAMRON90MACRO系は中遠距離撮影に弱い、
SIGMA系MACROはボケを生かした表現に弱い)
でも、マニア層等では「TAMRONやSIGMAのMACRO
を持っていない」という人は、まず居ないので、
それらの、特徴のある(強い武器を持つ)マクロと
並行して、万能タイプのマクロを別途持つ必要性が
あるのか否か? そのあたりが、どうも疑問となる。
また、販売数が少ないからか?中古相場もこなれて
おらず、2万円の入手価格は、この時代(2000年代)
のTAMRONやSIGMAのマクロと比べて、若干高価だ。
つまり「コスパが悪い」という切実な問題に繋がり
ここが本レンズの最大の課題であろう。
Clik here to view.

どう判断するか?が、本レンズの購入検討項目だ。
---
では、6本目のレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格: 35,000円(中古)(以下、OM100/2)
使用カメラ:PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
発売年不明、恐らくは1980年代頃と思われる大口径
単焦点MF中望遠レンズ。
本レンズはマクロでは無いのだが、最短撮影距離70cm
を誇り、銀塩MF時代の100mm単焦点レンズとしては
トップ(?)クラスの近接撮影能力であろう。
ただ、これでも撮影倍率は計算上約0.14倍(1/7倍)
にしかならない。しかしμ4/3機への装着や、今回の
母艦DMC-G6に備わる、各種デジタル拡大機能を併用
すれば、簡単に等倍以上の撮影倍率を得る事は可能だ。
Clik here to view.

マクロ切換を持つレンズとしては、前記事で紹介の
「SONY FE100mm/F2.8 STF GM」があり、これは
57cmの最短撮影距離で撮影倍率0.25倍(1/4倍)。
一応、こちらが100mmレンズ中、トップだと思われる。
さらに、ロシアンレンズ系の記事で良く紹介する
「アルセナール MC KALEINAR-5N 100mm/f2.8」
は、80cmの最短撮影距離で約1/8倍程度。
他には「MINOLTA AF SOFT FOCUS 100mm/f2.8」
(特殊レンズ第7回記事等)も、同じく80cmの最短。
まあ、これらも寄れる100mmレンズだ。
上記は記憶に頼って書いているので、抜けがあるかも
知れないが、他にあまり寄れる100mmレンズを
見た事が無い、普通は1m程度の最短撮影距離だ。
なのでまあ、恐らくはこのあたりの100mmレンズが
トップクラスであろう。(勿論、マクロは例外だ)
で、寄れる事はわかったが、描写力はどうか?
これについては、本OM100/2は、全般的に悪く無い。
銀塩時代でのオーソドックスな設計(6群7枚)
であり、これは場合により、50mm/F1.4級大口径
標準レンズを2倍にスケールアップした、「自社内
ジェネリック設計」なのかも知れないが、あまり
情報が無く、詳しい出自は不明だ。
ただ、このシリーズのOM F2級中望遠は、「レンズ
設計の教科書」にも引用されている事もあるくらい
で、まあ、当時としては、ちゃんとした設計だ。
「描写表現力」は4.5点(5点満点)と、優秀である。
ただし、この評価点は、どちらかと言えば「表現力」
に重きを置いた評価であり、描写力は3.5~4点、
表現力が4~4.5点あたりと思っておくのが妥当だ。
課題は、小型軽量な事を特徴とするOM-SYSTEMの
レンズとしては、やや大型であり、高価でもあった
事から、販売数が極めて少ないと思われ、後年の
中古市場でも、殆ど流通していない。
つまり、「入手困難なレアものレンズ」となって
いる事が大きな問題点だ。
購入時価格の35,000円は、コスパ評価2.5点。
つまり「これではやや高い」という評価であるから
2万円台後半が妥当だ。仮に、銀塩標準50mm/1.4の
2倍拡大レンズであれば、そのあたりの相場が適正
という感覚であろう。
しかし、現代の中古市場においては、本OM100/2は
まず見つからず、仮にあったとしても希少性からの
プレミアム相場(8~10万円程度、あるいは時価)
となるだろう。
勿論、そこまで値段を出して買うべきレンズでは無い。
「どんな感じに写るのか?」を体感したいのであれば
任意の50m/F1.4標準レンズを持ち出し、μ4/3機
に装着してみれば良い。それがOM100/2のフルサイズ
での使用感と、ほぼ共通の雰囲気、かつ、ほぼ同等の
描写力になると思う。おまけに、その場合では
標準レンズの最短撮影距離は一般に45cmであるので、
本OM100/2(最短70cm)をフルサイズ機で使った
場合よりも、撮影倍率を高める事が出来る。
で、本OM100/2を、μ4/3機で使う意味(意義)は、
「望遠マクロの代用とする事、撮影倍率を高める事、
その際にも、開放F値がF2と明るい事(撮影倍率
を高めた場合での「露光倍数」の影響が少ない)」
と、かなり特殊な用途・目的を狙っての事である。
一般撮影時でのμ4/3機の使用は、200mm単焦点
となり、あまり汎用的な被写体に向くレンズだとは
言えなくなるので、あくまで用途に依存した母艦選択
が必要だ。
総括だが、レアものにつき、非推奨だ。
----
さて、次は本記事ラストのマクロレンズ。
Clik here to view.

MACRO 1:1 (Model G005)
レンズ購入価格:20,000円(中古)(以下、SP60/2)
使用カメラ:SONY α65 (APS-C機)
2009年に発売された、APS-C機専用、中望遠画角
大口径AF等倍マクロレンズ。
Clik here to view.

ZEISS等から、そして本レンズと、数える程しか機種数
が無いと思われる。が、その中でも、等倍マクロ仕様の
物は本SP60/2しか存在していなかったと記憶している。
前述の90マクロの改良停止期間(2004年~2012年)
の間において、APS-C機(一眼レフ)ユーザーを
ターゲットとして発売された、90マクロ代替レンズ
であろう。
ただ、優秀な90マクロ(72E系)の代替とするので
あれば、それ相応の高描写力が要求される。
さもないと、これまで52B(1979年)から数十年間
もの間で築いてきた、「高性能マクロのTAMRON」の
ブランドイメージに泥を塗ってしまうからだ。
よって、本レンズは、まずスペック的には世界初
である「大口径F2マクロで等倍」を与えられた。
また、焦点距離が比較的短い(標準域)でありながら、
比較的長いWD(ワーキング・ディスタンス)を確保
している。(=レンズ前から被写体までの撮影距離。
これが長くできるのは、レンズ長を短くしたからだ。
でも、単に”長ければ良い”というものでも無い)
描写傾向だが、カリカリに解像感が強い特性だ。
これは90マクロシリーズと、あえて差別化した
特性から、かも知れず、主にビギナー層に向けての
携帯カメラや初期スマホ、初期ミーラレス機との
差別化要因もあったかも知れない。
すなわち「一眼レフ用のマクロは、こんなにも
はっきり、くっきり、シャープに写るのですよ」
というアピールである。
ただ、中上級層にとってみれば、この特性は
マクロレンズとしてはやや過剰であり、「被写体を
選ぶ」という、微妙な不満に繋がるかも知れない。
課題は、その特徴的な描写特性の他にもある。
シームレスMF(フルタイムマニュアル)機構を
採用しているが、これは、マクロレンズとしては
やや使い難い。MFならMFに特化した方が、中上級層
にとっては使い易い事は確実ではあるが、まあでも
前述のように、本レンズのターゲットユーザーが
ビギナー層であるならば、そうした高度なMF技法を
使う人は、まず誰もおらず、「AFで合わせてみた、
ピントが合い難いので、MFに変えてみた」程度の
初級MF技法しか使わないと思われるので、まあこの
仕様でも、やむを得ないのであろう。
総合的には、初級中級層向けのレンズだ。
ただまあ、描写特性は個性的ではあるので、
実践派マニア層等で、このシームレスMFの課題を
回避して使える腕前があるならば、推奨できる。
おまけに、2010年代後半からは、フルサイズ機
の普及により、こうしたAPS-C機専用レンズは
不人気で、相場がかなり下落している。
現代では、1万円台後半等の、かなり安価な価格で
これを購入出来るため、総合的なコスパはかなり良い。
Clik here to view.

「ハイコスパレンズBEST40」では、総合15位の
上位にランクインした強豪レンズとなっている。
ただまあ、本シリーズ「最強マクロ選手権」では
純粋な実力勝負が主眼なので、本レンズが決勝戦
やB決勝戦にノミネートされるか?は微妙だ。
(まあ、ちょっと無理かも知れない)
----
次回の本シリーズ記事は、
「最強マクロ選手権・望遠マクロ・予選(1)」を予定。