本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー
別に紹介している。
今回は「24~28mmマニアックス」という主旨で、
一眼レフ用(稀にミラーレス機用)の、実焦点距離が
24~28mmの範囲で、マニアックなレンズを20本準備し、
前編、後編記事で各10本づつ取り上げよう。
----
ではまず、最初のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズは、NIKON Ai NIKKOR 28mm/f2.8
(中古購入価格 20,000円)(以下、Ai28/2.8)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
1977年発売のMF広角レンズ。
後年(1981年)発売のAi NIKKOR 28mm/f2.8Sでは、
最短撮影距離が、20cmまで短縮されており、これは
恐らく MFの単焦点28mmでは最も短いスペックだと
思われるが、本レンズは旧型で最短撮影距離が30cmと
平凡なスペックである(両者は光学系も異なる)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
新型(S型)も一時期使用していたが、理由があって譲渡。
後年に、こちらの旧型を安価で見かけ、買い直した
次第なのだが、やはり広角レンズでの最短撮影距離の
スペック差は、想像以上に撮影における影響(制限)が
大きい。
・・と言うか、「広角レンズで、最短撮影距離が長いものは、
用途が極めて限定される」という事実に気づかせてくれた
のが、このAi28/2.8の新旧2タイプの差であったとも言える。
まあ、もう20年以上も前の話なので、今となっては新旧の
両レンズの厳密な描写傾向(描写力)の差は、わからないの
だが、表現力の面からは、新型(S型)に軍配が上がるのは
間違いない。
なお、NIKKONのMF広角には、さらに「シリーズE」版の
28mm/f2.8が存在するが、こちらは輸出専用レンズで
国内市場での入手性が悪く、未所有につき、その詳細は
良く知らない。(注:国内版NIKKOR 28/2.8の売り上げに
影響が出る(と考えた)為、廉価版SERIES Eの国内販売を
控えたのかも知れない)
ちなみに、新型(S型)は、当初、1980年代前半に
短期間だけ発売され、後年1986年には、AF化により
AiAF NIKKOR 28mm/f2.8S となったのだが、こちらは
また光学系が変わっていて、最短撮影距離が30cmと
伸びてしまった(本シリーズ第29回記事で紹介)
これの理由は、小型軽量化(AF速度にも関連)と、初期
AF機構の精度不足を補う意味もあったと思う。
(すなわち近接撮影では、被写界深度が浅くなり、AF精度
が低下する為。また、ヘリコイド駆動量も多くなる)
で、このAiAF型での製品ラインナップ上での弱点を補う為か、
あるいは、AF化以降もMF旗艦F3を残す決断をした為か?
最短20cmのMFのAi(S)型の再生産が、この時期より開始
されている(こちらは、比較的近年まで生産が継続されて
いたと思う)
まあつまり、現代において、ミラーレス機等で使用する際
実用的なNIKKOR 28mmMF単焦点が必要とされる場合では、
本レンズでは無く、新型のAi NIKKOR 28mm/f2.8Sを
強く推奨する、外観での見分け方は、最短撮影距離が
20cmになっているものを買えば良い。
----
さて、次のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズは、MINOLTA AF 24mm/f2.8
(中古購入価格 12,000円)
カメラは、SONY α65(APS-C機)
1980年代後半に発売と思われる、α用AF広角レンズ。
α(Aマウント)機における、ボディ・レンズ間の情報伝達
プロトコルの基本部分は変わっていない為、このように
四半世紀を超えて、現代のSONY製デジタル一眼レフに装着
でき、AFや絞り動作はもとより、銀塩時代には実現不能で
あったボディ内手ブレ補正、デジタル(スマート)テレコン、
エフェクト等の機能も有効に働く。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18222184.jpg]()
ただ、特徴的な機能や性能を何も持たないレンズである。
まあ、今から30年以上も前のオールドレンズであるので、
現代においては、人気のあるレンズでは無い。
でも1つだけ、本レンズは最初期αシステム、すなわち
1985年のα-7000の発売時(=「αショック」)に、
「広角から望遠まで、ずらりとAFレンズが揃っている」
という他社を圧倒する為の市場戦略に基づいてラインナップ
されたレンズであろう。
α-7000以前にも、各社から、試作機的なAF一眼レフが
発売された事があったが、それらAFの交換レンズは専用の
(つまり互換性の少ない)試作機的なレンズが数本程度
あった程度であり、他社の場合は、どう見ても実用的な
システムとは言えなかった訳だ。
ミノルタのα(AF)レンズは、旧来のMFのMDマウントとは
完全に互換性を失ったが、新鋭AFレンズ群が豊富で魅力的
であった為、「MDのとの互換性無し」の件は不問とされた。
ミノルタのこの戦略を見て、その後の他社(例:CANON等)
は、AF化に際して、ズームレンズの開発を促進した歴史が
ある。すなわち、「単焦点レンズのラインナップでは、
もはや、αに勝つ事は出来ない」という判断であろう。
まあ、そうした話は当時のメーカー間の戦いの話なのだが、
ユーザー層から見た変化もある。特に本レンズにおいては、
銀塩MF時代にMDマウントや他社MFレンズにおいて、24mm
という単焦点を入手するのは、価格や中古流通の面で少々
厳しかった(つまり、市場には、広角は28mmまでしか
ポピュラーでは無い。24mmは高価で希少であった)
それが、AFのαシステムでは、本レンズのような24mmでも
比較的安価に入手可能となった(これはその後のAF時代の
各社24mm単焦点も同様であった)
つまり、AF一眼レフの時代になって、ようやく24mm広角が
一般に普及した、という事となる。
まあ、そういう意味では、本レンズの歴史的価値は高い。
でも、本レンズの特徴はそれくらいなので、あまり
本AF24/2.8を指名買いする必然性は少ないであろう。
----
さて、3本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223004.jpg]()
レンズは、KONICA HEXANON (AR) 28mm/f3.5
(中古購入価格 5,000円)(以下、AR28/3.5)
カメラは、Panasonic DMC-G1 (μ4/3機)
本シリーズ第34回「KONICA HEXANON AR」編で
取り上げる予定だったのが、すっかり忘れていた(汗)
まあ、所有レンズ数が多くなってくると、そういう事も
稀にあるだろう。本記事で改めて紹介する。
本レンズは準ジャンク品での購入であり、レンズ内部に
ゴミが多数あった。2010年代初頭での中古専門店での
購入であったが、「ゴミが多い」という点で、値引きの
交渉を行うも、それは成立せず。
2000年代までは、関西圏での中古機材購入は、値切り
交渉する事が常識であった。店側は、常連客はもとより
初見の客でさえ、愛想よく値切りを受け入れる事が
ごく普通の時代でもあった。
これはつまり、一種の「リピーター戦略」である。
客側が「あの店に行けば得をする」という印象を持てば
何度もその店に通うからだ、まあ例えばポイントカード
とか、ランチ定食のスタンプカードと同様の話である。
しかし、2010年前後にフィルムの終焉/カメラ市場の
縮退が始まり、そういうおおらかな戦略をやっていても
リピーター客は増えず、店側は、よりシビアな経営を
行わなければ、やっていられなくなり、そうしたとしても
この時代、多くの中古カメラ専門店が廃業に追い込まれた。
よって、値引き(値切り)も、この時代には終焉。長らく
続く「関西の値切り文化」が失われるのは寂しいし、かつ
値切りが効か無ければ、面白さやコストメリットも減った。
まあ仮に、値切り文化が続いていたとしても、今時の
初級マニア層などでは、値切りを言い出すことも出来ない
事であろう、そういう話を切り出すタイミングとか会話の
テンポ等もあり、「関西人的」な素養が必要だからだ。
そして、そういう関西型コミュニケーションを受け止める
事ができるベテラン中古店店員も、今や殆ど皆無となって
しまった。アルバイト風の店員等では、そうした値切りの
話を持ち出しても、キョトンとするか、慌てふためいて
店長を呼び出すだけ、という残念な風潮となっている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223039.jpg]()
さて、本AR28/3.5であるが、あまり長所を持たない
平凡なレンズである。一応「ヘキサノン」であるが、
中級マニア層等が良く言うように「ヘキサノンは良く写る」
などの、「十把一絡げ」(=いろいろな物を同列に扱う事)
の概念は通用しない。勿論、個々のレンズには、設計上の
コンセプトや技術的な制約があり、長所と短所があるし
総合的な良し悪しも存在する。
そこを見抜き、ちゃんと使いこなす事が上級層における
責務であるが、それにしても、あまりに特徴(長所)が
無ければ、結局、使い道も少なくなってしまうのだ。
で、勿論、そういう「面白味」が無いレンズも世の中には
多数存在する。それでも安価であれば、救いようがあるが
もし、そういうレンズがブランドイメージ等により、
本来持つ性能よりも高価な相場や値づけになっている場合
「コスパが悪いレンズ」という事となり、私が最も嫌う
状態になる。
本レンズは一応「ヘキサノン」であるから、市場(店舗)
側としては「若干ブランド力がある」と見なしている、
それ故に、ジャンクレンズながら、やや高価な値付けと
なっている訳だ。
私は、「ごく普通の”量産ヘキサノン”に、そこまでの
付加価値は感じられない」と思って、だからこそ値引きの
交渉をした次第なのだ。他社28mmと同等またはそれ以下の
性能・仕様・程度で、この価格約5000円は高すぎる。
許せても3000円迄であり、実質的な価値は2000円以下だ。
これは1000円や2000円の価格差をうんぬん言っている
のではなく、「比率」の問題である。例えば、本レンズが
2万円に相当する性能価値があったとして、それがもし
5万円で売っているならば、誰でも「高い!」と思うで
あろう。そして、その価格帯より10分の1の話であっても、
同様なコスパ(比率)感覚を持たなければならない。
例えば、スーパーで毎日買い物をする主婦層であれば、
「10円でも高ければ買わない」という価値感覚を持っている、
それと同様だ、10円をケチるのではなく、あくまで、その
商品の本来あるべき価値を判断する「コスパ感覚」を持つか
持たないか、なのである。
ただ、モノが溢れた現代においては「買い物に慣れていない
ユーザー層」が極めて増えている、これは男性層に特に
多い状態だが、モノを買う際に、「コスパ」という感覚を
持っておらず、単に「コスト」や「ブランド」のみに注目
してしまう。
その考え方による弊害は、ここでは語りつくせない程に多い、
まあつまり、あまり好ましくない考え方や購買倫理である。
詳細は割愛するが、様々な記事で頻繁に登場する、本ブログ
での購買行動の主張や理由を多数読んでもらえれば、その
あたりの感覚は、いずれわかってくるであろう・・・
自力でそこに到達したいならば、「マニアの条件」である
「トリプルスリーの法則」、すなわち①30台以上の機材保有
②30年以上前の機材の現用 ③年間3万枚以上の撮影枚数
を実践していけば、コスパ感覚は、おのずとついてくると
思われる。
----
では、4本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223062.jpg]()
レンズは、OLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO W 28mm/f3.5
(中古購入価格 9,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
1970年代の、小型軽量MF小口径広角レンズ。
大きな特徴は持たないが、写りもそこそこ、弱点も殆ど無く、
マニア好みの広角レンズと言えよう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223136.jpg]()
現代のμ4/3機に装着した場合は、56mm相当の標準画角
となってしまい、広角撮影的用途には全く適さないが、
銀塩OM一眼レフに装着時は、小型軽量システムとなり、
ハンドリング性能に優れる。銀塩時代であれば旅行用や
記念撮影的用途に適した1本であろう。
まあ、各社フルサイズ・ミラーレス機に装着すれば、
銀塩時代と同様の用途には適するかも知れないが、
現代においては、このレンズでなくてはならない理由も
無い。また、ボディとのデザインマッチング等も含めて
考えると、やはりオリンパスのμ4/3機との組み合わせが、
気分的には好ましい。
ただまあ、マウントアダプターの厚みで、小型にあまり
見えない点は、ご愛嬌としておこう。
本レンズは「OM党」マニアであれば必携のレンズと言えよう。
----
さて、5本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223716.jpg]()
レンズは、MINOLTA MC W ROKKOR 28mm/f2
(中古購入価格 24,000円)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
1970年代中頃と思われるMF大口径広角レンズ。
様々な記事で述べているが、銀塩時代の各種28mm/F2級
レンズは、私の好みでは無いものが大半だ。
これはまあ、当時の技術においては、広角レンズで
F2級のものを設計しようとすると、まるで望遠レンズの
ような長い鏡筒となり、大型化する他、描写力的にも、
諸収差の補正がいき届いておらず、イマイチだからだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223776.jpg]()
しかし、これらの課題の技術的な解決は、ずいぶんと時間が
かかったと思われる。銀塩時代後期(AF時代)には、これらの
F2級広角を上回る28mm/F1.4級大口径広角もいくつか存在
したが、あまりに高価なものばかりで、購入に至っていない。
その後の、1つの転機は、銀塩末期の2001年発売の
SIGMA 28mm/F1.8(EX DG ASPHERICAL MACRO)で
あろうか(本シリーズ第52回、SIGMA広角三兄弟編参照)
大口径化と近接撮影能力を合わせ持った実用的なレンズで
あり、旧来の銀塩時代でのF2級広角の弱点をよく解消しては
くれたが、大型・重量級という課題は解消できていない。
SIGMAは、さらに2019年には、Art Line で28mm/F1.4
を発売するが、こちらは高描写力は保証されているだろう
が、大きく重く高価なレンズ故に、現状未購入である。
余談はともかく、本MC28/2であるが、時代(技術)の
未成熟故に実用価値が少ないレンズである。
この後、本シリーズ「広角」の前後編では、同スペックの
各社レンズが数本登場するが、いずれも同様の実用価値の
低いレンズだと思っておいて良いであろう。
現代において、本レンズを指名買いする必然性は殆ど無い。
----
さて、6本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223773.jpg]()
レンズは、SICOR 24mm/f3.5
(中古購入価格 4,000円相当)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
「SICOR」は、「サイコール」と読む模様だ。
出自の良くわからないレンズであり、恐らくは国産
レンズである。私は、このレンズを銀塩時代に、韓国の
ソウルへの旅行中に、東大門の中古店で購入している。
マウントは購入時は不明、帰国後調べるとKONICA AR
マウントであった。ARマウントは、デジタル時代に
入ってしばらくは使用不能のマウントであったが、
2010年前後のミラーレス時代になって、ARマウントの
短いフランジバックに対応するマウントアダプターが
発売され始め、およそ10年ぶりの復活を見た次第である。
最大の特徴は、最短撮影距離が16cmと極めて短い事、
これは、過去から現代までの、フルサイズ対応24mm
レンズで最も短い値だと思われる。
次点は恐らく、SIGMA 24mm/F1.8(EX DG・・)の
18cmであろう(本記事でも後で紹介)
(注:2019年に発売されたTAMRON 24mm/f2.8
(Model F051)が最短12cmで、初めて、それらの
性能を更新。ただしミラーレス機専用レンズだ)
で、それ故に「サイコー(ル)」なのか? と駄洒落の
ネーミングセンスを疑ってしまう位であるのだが、その
近接性能以外は、壊滅的とも言える酷い描写力である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18223764.jpg]()
「弱点回避」とか「用途開発」を色々と模索はして見たが
どうにも成功例が無い、つまり、使い道が殆ど見つからない
レンズとなってしまっている。
まあでも、とてもマニアックなレンズである事は確かだ。
ある意味、本シリーズ記事のテーマ、「超」マニアックに
ふさわしいレンズなのかも知れない。
----
さて、7本目のシステムは、トイレンズだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224270.jpg]()
レンズは、HOLGA LENS 25mm/f8 HL(W)-SN
(新品購入価格 3,000円)
カメラは、SONY NEX-3(APS-C機)
2010年代前半頃に発売の広角トイレンズ。
それまでの時代でもHOLGAのトイレンズは(デジタル)一眼
レフ用マウントで発売されてはいたが、焦点距離が60mm
と長いものばかりであり(本シリーズ第3回HOLGA LENS編
記事参照)、銀塩時代のHOLGA(カメラ)使用法のような、
広角気味(概算32mm相当)の撮影用途に適さない事が
課題になっていたが、ミラーレス機専用の本HOLGA 25/8
の登場で、やっと銀塩時代の雰囲気でHOLGAレンズが使用
できるようになった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224200.jpg]()
期待の周辺減光は結構でるが、銀塩HOLGAカメラのような
スクエア(1対1、正方形)のフォーマットでは無いし、
NEX等の3:2フォーマットを1対1にトリミングしたら、
周辺減光の出方が減ってしまう。だからまあ、銀塩時代の
雰囲気を模倣するのではなく、デジタル時代に合わせた
撮影技法に置き換えていけば良い。
その点では、(ピクチャー)エフェクトの利用も、
デジタル撮影で「Lo-Fi技法」を用いる上でのセオリー
ではあるが、今回使用のNEX-3には時代的に残念ながら
エフェクトが搭載されていない。
まあ、今回はこのままとするが、後年のNEX/αの
APS-C機(エフェクト有り)を母艦とする方が望ましい。
誰にでも必要なレンズとは言い難いが、トイレンズとか
Lo-Fiの世界を知りたいと思うのであれば、まずは買って
おくべき入門用トイレンズである。
----
さて、8本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224380.jpg]()
レンズは、SIGMA 24mm/f1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO
(新品購入価格 38,000円)(以下、EX24/1.8)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
2001年に発売された、銀塩フルサイズ・デジタル兼用の
AF大口径広角単焦点、準マクロレンズ。
最短18cm、最大撮影倍率1/2.7倍である。
前述のSICORに最短性能で僅かに負けるが、実用的な
描写性能を持つレンズとしては、本EX24/1.8が、24mm
広角レンズ中、最良の近接性能を誇るレンズである。
(注:ミラーレス機用で前述のTAMRON F051型がある)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224312.jpg]()
2001年に新品購入したレンズであり、およそ20年も
利用している為、本ブログでは過去何度も紹介している
レンズだ、本シリーズでも第52回「SIGMA広角3兄弟編」
で紹介しているため、説明は最小限としよう。
長所はその近接性能と大口径、短所は逆光耐性の低さ
である。ただまあ、弱点を回避しながら、その用途は
いくらでもある事だろう。
銀塩末期の開発コンセプト通り、現代において普及した
フルサイズ機と旧来からのAPS-C機で共用して、両者の
フォーマットで各々実用価値が高く、汎用性が高い事も、
本EX24/1.8の大きな特徴かも知れない。
後継レンズはART LINEとなり、三重苦レンズとなった、
そちらも悪くは無さそうだが、コスト高は否めない。
本レンズEX24/1.8であれば、中古相場は安価だし、まだ
ぎりぎり入手(および実用)できるタイミングであろう、
初級中級マニア層向けには、十分に推奨できるレンズである。
----
さて、9本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224804.jpg]()
レンズは、CANON (New) FD 24mm/f2
(中古購入価格 30,000円)(以下、NFD24/2)
カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)
1979年発売のMF単焦点(大口径)広角レンズ。
本シリーズ第46回「CANON New FD F2レンズ編」でも
紹介済みであるので、本記事では簡単に・・
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224991.jpg]()
長所は、銀塩時代のレンズとしては、実用レベルに耐えうる
F2級広角である事だ。前述のMC28/2のところでも述べたが、
この1970年代~1990年代頃の、F2級広角は、実用性能に
満たないものが殆どである中、本NFD24/2の高描写力は、
他にあまり類を見ない。
ただまあ、その「描写力」というものが、何を指している
のか?によっても評価は変わってくるであろう。
具体的には、本レンズでは、絞り込んで使う事により、
解像感等の描写性能に優れる。ただし、絞りを開けると、
ボケ質破綻が頻発し、使い難い。これは、ちょっと困った
特性であり、つまり、大口径(広角)だから、絞りを開けて
使いたいのだが、それは(銀塩低感度フィルムでの)暗所での
撮影であれば、メリットではあるが、ボケ質が悪いのでは、
被写界深度を浅くする撮影技法(目的)には合わなくなる。
低感度フィルム使用時のメリットは、現代、デジタル時代で
どのようなカメラにも超高感度性能が搭載されている以上、
これはメリットには成り得ない。
だからまあ、本レンズの評価は銀塩時代であれば良好だが
デジタル時代においては、やや評価点は下がってしまう。
最初期の本ブログでは、まだ銀塩とデジタルの併用期で
あった為、本(New)FD24/2を高く評価する事も多々あったと
思うが、そこから15年以上も経過すれば、時代も撮影環境も
変化し、結果、レンズの評価も時代に合わせて変わってくる、
という事になるのだろう・・
----
では、今回ラストのシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224975.jpg]()
レンズは、smc PENTAX 28mm/f2
(中古購入価格 29,000円)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)
1970年代中頃に発売と思われる、MF(大口径)広角レンズ。
この時代のPENTAXレンズは、旧来のM42マウントから、
(現代にも続く)Kマウントに置き換わったばかり、
そしてこの後、時代は小型化競争に突入してしまった為、
PENTAXレンズも、PENTAX-Mという小型化されたタイプに
順次置き換わっていく。この、過渡期のレンズ群には、
-M(や、後の-FA,-DA)等の区分が無く、中古流通等では
便宜上、「P」「K」「無印」と呼ばれて区別さてれいる。
P(K)レンズの多くは、M42時代のSMC-T(TAKUMAR)の設計を
踏襲してはいるが、本P28/2は、Kマウント登場に合わせて
の新設計と思われる。M42とKマウントは、マウント互換性を
最大限に確保しているとは言え、新マウントに切り替わる際
には常にユーザー離れや不満が起こる為、新マウント変更時
には魅力的なスペックの新レンズを発売する事が、昔から
各メーカーにおける基本的(常識的)な戦略となっている。
(注:ほぼ全てのケースで、この措置が行われたが、唯一の
例外と言える状況は、京セラCONTAXでの、2000年の
Y/Cマウント→Nマウントへの移行時であろうか・・
この時、新規Nマウントには魅力的なレンズがラインナップ
されておらず、ユーザー離れを引き起こし、2005年の
CONTAXのカメラ事業撤退への遠因になったと思われる。
この時期、京セラCONTAXは、多くの開発テーマを同時期に
抱えて、とても多数の新型レンズ開発には手が廻らなかった
のだろう、と擁護できるが、結果、それが致命傷となった。
→銀塩一眼レフクラッシックス第24回CONTAX N1参照)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_18224969.jpg]()
さて、本P28/2であるが、MC28/2のところで前述した
ように、この手の長鏡筒(注:稀に「長焦点」と呼ばれる
場合もあるが、例によって、昔から光学の世界では用語統一
が行われておらず、様々な用語により混乱を招いている)
・・長鏡筒のタイプの28mm/F2級のレンズの描写力は
イマイチである。ただし、MC28/2と全くの同じ設計では
無い模様で、僅かにレンズ構成等は異なっている。
まだこの時代の他社にも同様な設計の28mm/F2級が存在
すると思う、全てをチェックした訳では無いが、いずれも
同様の描写力の課題があると推察され、これは前述のように
時代(技術)の未成熟だ。
なのでまあ、本レンズにも過度な期待を持つ事は禁物だ。
なお、何故、そういう弱点があるのに似たような28mm/F2級
レンズを何本も買ってしまっているのか? という点だが、
銀塩時代、これらの28mm/F2級広角は一般的な28mm/F2.8級
よりも開放F値が明るく、値段も高価であるから、私もまた
「どれだけ良いレンズなのだろうか?」と、ビギナーのような
「数値スペックや値段だけを見て、過剰な期待をする」という
錯覚状態に陥ってしまっていたのだ(汗)
最初に買った28mm/F2級が、どのレンズだったかは忘れたが
描写力が気に入らず、他社製品だったらどうだろうか?と
高価なそれらを、3本、4本、5本と購入を重ね、そうした中で、
やっと「長鏡筒タイプの28mm/F2は、どれもNGだ」という
事に、遅ればせながら気づいた次第なのだ。
もっと早く気づけば被害(?)も最小限となっただろうが、
まあやむを得ない、それだけお金を掛けないとわからない
事も世の中にはある。
でもまあ、現代においても、せっかく何本か残してある
こうした28mm/F2級で、「弱点回避」や「用途開発」を
行う事で、新たな使い道が発見できるかも知れない。
けど・・ どうにも、元々、嫌いなレンズであるだけに、
持ち出して、そこまで手間隙をかけよう、という気には
全くなれないのである。
これは、すなわち「エンジョイ度」の評価点が極めて
低い状況だ、残念な状況だが、やむを得ないであろう。
----
では、今回の「24~28mmマニアックス(前編)」は、
このあたり迄で。次回後編記事に続く。
別に紹介している。
今回は「24~28mmマニアックス」という主旨で、
一眼レフ用(稀にミラーレス機用)の、実焦点距離が
24~28mmの範囲で、マニアックなレンズを20本準備し、
前編、後編記事で各10本づつ取り上げよう。
----
ではまず、最初のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 20,000円)(以下、Ai28/2.8)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
1977年発売のMF広角レンズ。
後年(1981年)発売のAi NIKKOR 28mm/f2.8Sでは、
最短撮影距離が、20cmまで短縮されており、これは
恐らく MFの単焦点28mmでは最も短いスペックだと
思われるが、本レンズは旧型で最短撮影距離が30cmと
平凡なスペックである(両者は光学系も異なる)
Clik here to view.

後年に、こちらの旧型を安価で見かけ、買い直した
次第なのだが、やはり広角レンズでの最短撮影距離の
スペック差は、想像以上に撮影における影響(制限)が
大きい。
・・と言うか、「広角レンズで、最短撮影距離が長いものは、
用途が極めて限定される」という事実に気づかせてくれた
のが、このAi28/2.8の新旧2タイプの差であったとも言える。
まあ、もう20年以上も前の話なので、今となっては新旧の
両レンズの厳密な描写傾向(描写力)の差は、わからないの
だが、表現力の面からは、新型(S型)に軍配が上がるのは
間違いない。
なお、NIKKONのMF広角には、さらに「シリーズE」版の
28mm/f2.8が存在するが、こちらは輸出専用レンズで
国内市場での入手性が悪く、未所有につき、その詳細は
良く知らない。(注:国内版NIKKOR 28/2.8の売り上げに
影響が出る(と考えた)為、廉価版SERIES Eの国内販売を
控えたのかも知れない)
ちなみに、新型(S型)は、当初、1980年代前半に
短期間だけ発売され、後年1986年には、AF化により
AiAF NIKKOR 28mm/f2.8S となったのだが、こちらは
また光学系が変わっていて、最短撮影距離が30cmと
伸びてしまった(本シリーズ第29回記事で紹介)
これの理由は、小型軽量化(AF速度にも関連)と、初期
AF機構の精度不足を補う意味もあったと思う。
(すなわち近接撮影では、被写界深度が浅くなり、AF精度
が低下する為。また、ヘリコイド駆動量も多くなる)
で、このAiAF型での製品ラインナップ上での弱点を補う為か、
あるいは、AF化以降もMF旗艦F3を残す決断をした為か?
最短20cmのMFのAi(S)型の再生産が、この時期より開始
されている(こちらは、比較的近年まで生産が継続されて
いたと思う)
まあつまり、現代において、ミラーレス機等で使用する際
実用的なNIKKOR 28mmMF単焦点が必要とされる場合では、
本レンズでは無く、新型のAi NIKKOR 28mm/f2.8Sを
強く推奨する、外観での見分け方は、最短撮影距離が
20cmになっているものを買えば良い。
----
さて、次のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 12,000円)
カメラは、SONY α65(APS-C機)
1980年代後半に発売と思われる、α用AF広角レンズ。
α(Aマウント)機における、ボディ・レンズ間の情報伝達
プロトコルの基本部分は変わっていない為、このように
四半世紀を超えて、現代のSONY製デジタル一眼レフに装着
でき、AFや絞り動作はもとより、銀塩時代には実現不能で
あったボディ内手ブレ補正、デジタル(スマート)テレコン、
エフェクト等の機能も有効に働く。
Clik here to view.
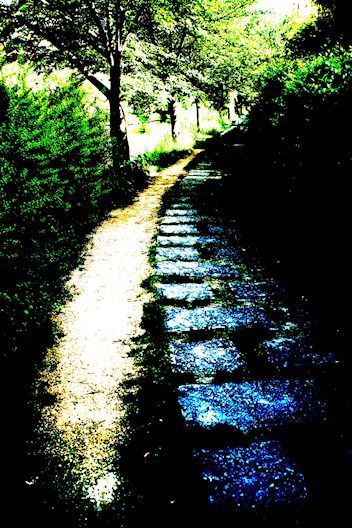
まあ、今から30年以上も前のオールドレンズであるので、
現代においては、人気のあるレンズでは無い。
でも1つだけ、本レンズは最初期αシステム、すなわち
1985年のα-7000の発売時(=「αショック」)に、
「広角から望遠まで、ずらりとAFレンズが揃っている」
という他社を圧倒する為の市場戦略に基づいてラインナップ
されたレンズであろう。
α-7000以前にも、各社から、試作機的なAF一眼レフが
発売された事があったが、それらAFの交換レンズは専用の
(つまり互換性の少ない)試作機的なレンズが数本程度
あった程度であり、他社の場合は、どう見ても実用的な
システムとは言えなかった訳だ。
ミノルタのα(AF)レンズは、旧来のMFのMDマウントとは
完全に互換性を失ったが、新鋭AFレンズ群が豊富で魅力的
であった為、「MDのとの互換性無し」の件は不問とされた。
ミノルタのこの戦略を見て、その後の他社(例:CANON等)
は、AF化に際して、ズームレンズの開発を促進した歴史が
ある。すなわち、「単焦点レンズのラインナップでは、
もはや、αに勝つ事は出来ない」という判断であろう。
まあ、そうした話は当時のメーカー間の戦いの話なのだが、
ユーザー層から見た変化もある。特に本レンズにおいては、
銀塩MF時代にMDマウントや他社MFレンズにおいて、24mm
という単焦点を入手するのは、価格や中古流通の面で少々
厳しかった(つまり、市場には、広角は28mmまでしか
ポピュラーでは無い。24mmは高価で希少であった)
それが、AFのαシステムでは、本レンズのような24mmでも
比較的安価に入手可能となった(これはその後のAF時代の
各社24mm単焦点も同様であった)
つまり、AF一眼レフの時代になって、ようやく24mm広角が
一般に普及した、という事となる。
まあ、そういう意味では、本レンズの歴史的価値は高い。
でも、本レンズの特徴はそれくらいなので、あまり
本AF24/2.8を指名買いする必然性は少ないであろう。
----
さて、3本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 5,000円)(以下、AR28/3.5)
カメラは、Panasonic DMC-G1 (μ4/3機)
本シリーズ第34回「KONICA HEXANON AR」編で
取り上げる予定だったのが、すっかり忘れていた(汗)
まあ、所有レンズ数が多くなってくると、そういう事も
稀にあるだろう。本記事で改めて紹介する。
本レンズは準ジャンク品での購入であり、レンズ内部に
ゴミが多数あった。2010年代初頭での中古専門店での
購入であったが、「ゴミが多い」という点で、値引きの
交渉を行うも、それは成立せず。
2000年代までは、関西圏での中古機材購入は、値切り
交渉する事が常識であった。店側は、常連客はもとより
初見の客でさえ、愛想よく値切りを受け入れる事が
ごく普通の時代でもあった。
これはつまり、一種の「リピーター戦略」である。
客側が「あの店に行けば得をする」という印象を持てば
何度もその店に通うからだ、まあ例えばポイントカード
とか、ランチ定食のスタンプカードと同様の話である。
しかし、2010年前後にフィルムの終焉/カメラ市場の
縮退が始まり、そういうおおらかな戦略をやっていても
リピーター客は増えず、店側は、よりシビアな経営を
行わなければ、やっていられなくなり、そうしたとしても
この時代、多くの中古カメラ専門店が廃業に追い込まれた。
よって、値引き(値切り)も、この時代には終焉。長らく
続く「関西の値切り文化」が失われるのは寂しいし、かつ
値切りが効か無ければ、面白さやコストメリットも減った。
まあ仮に、値切り文化が続いていたとしても、今時の
初級マニア層などでは、値切りを言い出すことも出来ない
事であろう、そういう話を切り出すタイミングとか会話の
テンポ等もあり、「関西人的」な素養が必要だからだ。
そして、そういう関西型コミュニケーションを受け止める
事ができるベテラン中古店店員も、今や殆ど皆無となって
しまった。アルバイト風の店員等では、そうした値切りの
話を持ち出しても、キョトンとするか、慌てふためいて
店長を呼び出すだけ、という残念な風潮となっている。
Clik here to view.

平凡なレンズである。一応「ヘキサノン」であるが、
中級マニア層等が良く言うように「ヘキサノンは良く写る」
などの、「十把一絡げ」(=いろいろな物を同列に扱う事)
の概念は通用しない。勿論、個々のレンズには、設計上の
コンセプトや技術的な制約があり、長所と短所があるし
総合的な良し悪しも存在する。
そこを見抜き、ちゃんと使いこなす事が上級層における
責務であるが、それにしても、あまりに特徴(長所)が
無ければ、結局、使い道も少なくなってしまうのだ。
で、勿論、そういう「面白味」が無いレンズも世の中には
多数存在する。それでも安価であれば、救いようがあるが
もし、そういうレンズがブランドイメージ等により、
本来持つ性能よりも高価な相場や値づけになっている場合
「コスパが悪いレンズ」という事となり、私が最も嫌う
状態になる。
本レンズは一応「ヘキサノン」であるから、市場(店舗)
側としては「若干ブランド力がある」と見なしている、
それ故に、ジャンクレンズながら、やや高価な値付けと
なっている訳だ。
私は、「ごく普通の”量産ヘキサノン”に、そこまでの
付加価値は感じられない」と思って、だからこそ値引きの
交渉をした次第なのだ。他社28mmと同等またはそれ以下の
性能・仕様・程度で、この価格約5000円は高すぎる。
許せても3000円迄であり、実質的な価値は2000円以下だ。
これは1000円や2000円の価格差をうんぬん言っている
のではなく、「比率」の問題である。例えば、本レンズが
2万円に相当する性能価値があったとして、それがもし
5万円で売っているならば、誰でも「高い!」と思うで
あろう。そして、その価格帯より10分の1の話であっても、
同様なコスパ(比率)感覚を持たなければならない。
例えば、スーパーで毎日買い物をする主婦層であれば、
「10円でも高ければ買わない」という価値感覚を持っている、
それと同様だ、10円をケチるのではなく、あくまで、その
商品の本来あるべき価値を判断する「コスパ感覚」を持つか
持たないか、なのである。
ただ、モノが溢れた現代においては「買い物に慣れていない
ユーザー層」が極めて増えている、これは男性層に特に
多い状態だが、モノを買う際に、「コスパ」という感覚を
持っておらず、単に「コスト」や「ブランド」のみに注目
してしまう。
その考え方による弊害は、ここでは語りつくせない程に多い、
まあつまり、あまり好ましくない考え方や購買倫理である。
詳細は割愛するが、様々な記事で頻繁に登場する、本ブログ
での購買行動の主張や理由を多数読んでもらえれば、その
あたりの感覚は、いずれわかってくるであろう・・・
自力でそこに到達したいならば、「マニアの条件」である
「トリプルスリーの法則」、すなわち①30台以上の機材保有
②30年以上前の機材の現用 ③年間3万枚以上の撮影枚数
を実践していけば、コスパ感覚は、おのずとついてくると
思われる。
----
では、4本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 9,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
1970年代の、小型軽量MF小口径広角レンズ。
大きな特徴は持たないが、写りもそこそこ、弱点も殆ど無く、
マニア好みの広角レンズと言えよう。
Clik here to view.

となってしまい、広角撮影的用途には全く適さないが、
銀塩OM一眼レフに装着時は、小型軽量システムとなり、
ハンドリング性能に優れる。銀塩時代であれば旅行用や
記念撮影的用途に適した1本であろう。
まあ、各社フルサイズ・ミラーレス機に装着すれば、
銀塩時代と同様の用途には適するかも知れないが、
現代においては、このレンズでなくてはならない理由も
無い。また、ボディとのデザインマッチング等も含めて
考えると、やはりオリンパスのμ4/3機との組み合わせが、
気分的には好ましい。
ただまあ、マウントアダプターの厚みで、小型にあまり
見えない点は、ご愛嬌としておこう。
本レンズは「OM党」マニアであれば必携のレンズと言えよう。
----
さて、5本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 24,000円)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
1970年代中頃と思われるMF大口径広角レンズ。
様々な記事で述べているが、銀塩時代の各種28mm/F2級
レンズは、私の好みでは無いものが大半だ。
これはまあ、当時の技術においては、広角レンズで
F2級のものを設計しようとすると、まるで望遠レンズの
ような長い鏡筒となり、大型化する他、描写力的にも、
諸収差の補正がいき届いておらず、イマイチだからだ。
Clik here to view.

かかったと思われる。銀塩時代後期(AF時代)には、これらの
F2級広角を上回る28mm/F1.4級大口径広角もいくつか存在
したが、あまりに高価なものばかりで、購入に至っていない。
その後の、1つの転機は、銀塩末期の2001年発売の
SIGMA 28mm/F1.8(EX DG ASPHERICAL MACRO)で
あろうか(本シリーズ第52回、SIGMA広角三兄弟編参照)
大口径化と近接撮影能力を合わせ持った実用的なレンズで
あり、旧来の銀塩時代でのF2級広角の弱点をよく解消しては
くれたが、大型・重量級という課題は解消できていない。
SIGMAは、さらに2019年には、Art Line で28mm/F1.4
を発売するが、こちらは高描写力は保証されているだろう
が、大きく重く高価なレンズ故に、現状未購入である。
余談はともかく、本MC28/2であるが、時代(技術)の
未成熟故に実用価値が少ないレンズである。
この後、本シリーズ「広角」の前後編では、同スペックの
各社レンズが数本登場するが、いずれも同様の実用価値の
低いレンズだと思っておいて良いであろう。
現代において、本レンズを指名買いする必然性は殆ど無い。
----
さて、6本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 4,000円相当)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
「SICOR」は、「サイコール」と読む模様だ。
出自の良くわからないレンズであり、恐らくは国産
レンズである。私は、このレンズを銀塩時代に、韓国の
ソウルへの旅行中に、東大門の中古店で購入している。
マウントは購入時は不明、帰国後調べるとKONICA AR
マウントであった。ARマウントは、デジタル時代に
入ってしばらくは使用不能のマウントであったが、
2010年前後のミラーレス時代になって、ARマウントの
短いフランジバックに対応するマウントアダプターが
発売され始め、およそ10年ぶりの復活を見た次第である。
最大の特徴は、最短撮影距離が16cmと極めて短い事、
これは、過去から現代までの、フルサイズ対応24mm
レンズで最も短い値だと思われる。
次点は恐らく、SIGMA 24mm/F1.8(EX DG・・)の
18cmであろう(本記事でも後で紹介)
(注:2019年に発売されたTAMRON 24mm/f2.8
(Model F051)が最短12cmで、初めて、それらの
性能を更新。ただしミラーレス機専用レンズだ)
で、それ故に「サイコー(ル)」なのか? と駄洒落の
ネーミングセンスを疑ってしまう位であるのだが、その
近接性能以外は、壊滅的とも言える酷い描写力である。
Clik here to view.

どうにも成功例が無い、つまり、使い道が殆ど見つからない
レンズとなってしまっている。
まあでも、とてもマニアックなレンズである事は確かだ。
ある意味、本シリーズ記事のテーマ、「超」マニアックに
ふさわしいレンズなのかも知れない。
----
さて、7本目のシステムは、トイレンズだ。
Clik here to view.

(新品購入価格 3,000円)
カメラは、SONY NEX-3(APS-C機)
2010年代前半頃に発売の広角トイレンズ。
それまでの時代でもHOLGAのトイレンズは(デジタル)一眼
レフ用マウントで発売されてはいたが、焦点距離が60mm
と長いものばかりであり(本シリーズ第3回HOLGA LENS編
記事参照)、銀塩時代のHOLGA(カメラ)使用法のような、
広角気味(概算32mm相当)の撮影用途に適さない事が
課題になっていたが、ミラーレス機専用の本HOLGA 25/8
の登場で、やっと銀塩時代の雰囲気でHOLGAレンズが使用
できるようになった。
Clik here to view.

スクエア(1対1、正方形)のフォーマットでは無いし、
NEX等の3:2フォーマットを1対1にトリミングしたら、
周辺減光の出方が減ってしまう。だからまあ、銀塩時代の
雰囲気を模倣するのではなく、デジタル時代に合わせた
撮影技法に置き換えていけば良い。
その点では、(ピクチャー)エフェクトの利用も、
デジタル撮影で「Lo-Fi技法」を用いる上でのセオリー
ではあるが、今回使用のNEX-3には時代的に残念ながら
エフェクトが搭載されていない。
まあ、今回はこのままとするが、後年のNEX/αの
APS-C機(エフェクト有り)を母艦とする方が望ましい。
誰にでも必要なレンズとは言い難いが、トイレンズとか
Lo-Fiの世界を知りたいと思うのであれば、まずは買って
おくべき入門用トイレンズである。
----
さて、8本目のシステム
Clik here to view.

(新品購入価格 38,000円)(以下、EX24/1.8)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
2001年に発売された、銀塩フルサイズ・デジタル兼用の
AF大口径広角単焦点、準マクロレンズ。
最短18cm、最大撮影倍率1/2.7倍である。
前述のSICORに最短性能で僅かに負けるが、実用的な
描写性能を持つレンズとしては、本EX24/1.8が、24mm
広角レンズ中、最良の近接性能を誇るレンズである。
(注:ミラーレス機用で前述のTAMRON F051型がある)
Clik here to view.

利用している為、本ブログでは過去何度も紹介している
レンズだ、本シリーズでも第52回「SIGMA広角3兄弟編」
で紹介しているため、説明は最小限としよう。
長所はその近接性能と大口径、短所は逆光耐性の低さ
である。ただまあ、弱点を回避しながら、その用途は
いくらでもある事だろう。
銀塩末期の開発コンセプト通り、現代において普及した
フルサイズ機と旧来からのAPS-C機で共用して、両者の
フォーマットで各々実用価値が高く、汎用性が高い事も、
本EX24/1.8の大きな特徴かも知れない。
後継レンズはART LINEとなり、三重苦レンズとなった、
そちらも悪くは無さそうだが、コスト高は否めない。
本レンズEX24/1.8であれば、中古相場は安価だし、まだ
ぎりぎり入手(および実用)できるタイミングであろう、
初級中級マニア層向けには、十分に推奨できるレンズである。
----
さて、9本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 30,000円)(以下、NFD24/2)
カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)
1979年発売のMF単焦点(大口径)広角レンズ。
本シリーズ第46回「CANON New FD F2レンズ編」でも
紹介済みであるので、本記事では簡単に・・
Clik here to view.

F2級広角である事だ。前述のMC28/2のところでも述べたが、
この1970年代~1990年代頃の、F2級広角は、実用性能に
満たないものが殆どである中、本NFD24/2の高描写力は、
他にあまり類を見ない。
ただまあ、その「描写力」というものが、何を指している
のか?によっても評価は変わってくるであろう。
具体的には、本レンズでは、絞り込んで使う事により、
解像感等の描写性能に優れる。ただし、絞りを開けると、
ボケ質破綻が頻発し、使い難い。これは、ちょっと困った
特性であり、つまり、大口径(広角)だから、絞りを開けて
使いたいのだが、それは(銀塩低感度フィルムでの)暗所での
撮影であれば、メリットではあるが、ボケ質が悪いのでは、
被写界深度を浅くする撮影技法(目的)には合わなくなる。
低感度フィルム使用時のメリットは、現代、デジタル時代で
どのようなカメラにも超高感度性能が搭載されている以上、
これはメリットには成り得ない。
だからまあ、本レンズの評価は銀塩時代であれば良好だが
デジタル時代においては、やや評価点は下がってしまう。
最初期の本ブログでは、まだ銀塩とデジタルの併用期で
あった為、本(New)FD24/2を高く評価する事も多々あったと
思うが、そこから15年以上も経過すれば、時代も撮影環境も
変化し、結果、レンズの評価も時代に合わせて変わってくる、
という事になるのだろう・・
----
では、今回ラストのシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 29,000円)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)
1970年代中頃に発売と思われる、MF(大口径)広角レンズ。
この時代のPENTAXレンズは、旧来のM42マウントから、
(現代にも続く)Kマウントに置き換わったばかり、
そしてこの後、時代は小型化競争に突入してしまった為、
PENTAXレンズも、PENTAX-Mという小型化されたタイプに
順次置き換わっていく。この、過渡期のレンズ群には、
-M(や、後の-FA,-DA)等の区分が無く、中古流通等では
便宜上、「P」「K」「無印」と呼ばれて区別さてれいる。
P(K)レンズの多くは、M42時代のSMC-T(TAKUMAR)の設計を
踏襲してはいるが、本P28/2は、Kマウント登場に合わせて
の新設計と思われる。M42とKマウントは、マウント互換性を
最大限に確保しているとは言え、新マウントに切り替わる際
には常にユーザー離れや不満が起こる為、新マウント変更時
には魅力的なスペックの新レンズを発売する事が、昔から
各メーカーにおける基本的(常識的)な戦略となっている。
(注:ほぼ全てのケースで、この措置が行われたが、唯一の
例外と言える状況は、京セラCONTAXでの、2000年の
Y/Cマウント→Nマウントへの移行時であろうか・・
この時、新規Nマウントには魅力的なレンズがラインナップ
されておらず、ユーザー離れを引き起こし、2005年の
CONTAXのカメラ事業撤退への遠因になったと思われる。
この時期、京セラCONTAXは、多くの開発テーマを同時期に
抱えて、とても多数の新型レンズ開発には手が廻らなかった
のだろう、と擁護できるが、結果、それが致命傷となった。
→銀塩一眼レフクラッシックス第24回CONTAX N1参照)
Clik here to view.

ように、この手の長鏡筒(注:稀に「長焦点」と呼ばれる
場合もあるが、例によって、昔から光学の世界では用語統一
が行われておらず、様々な用語により混乱を招いている)
・・長鏡筒のタイプの28mm/F2級のレンズの描写力は
イマイチである。ただし、MC28/2と全くの同じ設計では
無い模様で、僅かにレンズ構成等は異なっている。
まだこの時代の他社にも同様な設計の28mm/F2級が存在
すると思う、全てをチェックした訳では無いが、いずれも
同様の描写力の課題があると推察され、これは前述のように
時代(技術)の未成熟だ。
なのでまあ、本レンズにも過度な期待を持つ事は禁物だ。
なお、何故、そういう弱点があるのに似たような28mm/F2級
レンズを何本も買ってしまっているのか? という点だが、
銀塩時代、これらの28mm/F2級広角は一般的な28mm/F2.8級
よりも開放F値が明るく、値段も高価であるから、私もまた
「どれだけ良いレンズなのだろうか?」と、ビギナーのような
「数値スペックや値段だけを見て、過剰な期待をする」という
錯覚状態に陥ってしまっていたのだ(汗)
最初に買った28mm/F2級が、どのレンズだったかは忘れたが
描写力が気に入らず、他社製品だったらどうだろうか?と
高価なそれらを、3本、4本、5本と購入を重ね、そうした中で、
やっと「長鏡筒タイプの28mm/F2は、どれもNGだ」という
事に、遅ればせながら気づいた次第なのだ。
もっと早く気づけば被害(?)も最小限となっただろうが、
まあやむを得ない、それだけお金を掛けないとわからない
事も世の中にはある。
でもまあ、現代においても、せっかく何本か残してある
こうした28mm/F2級で、「弱点回避」や「用途開発」を
行う事で、新たな使い道が発見できるかも知れない。
けど・・ どうにも、元々、嫌いなレンズであるだけに、
持ち出して、そこまで手間隙をかけよう、という気には
全くなれないのである。
これは、すなわち「エンジョイ度」の評価点が極めて
低い状況だ、残念な状況だが、やむを得ないであろう。
----
では、今回の「24~28mmマニアックス(前編)」は、
このあたり迄で。次回後編記事に続く。