新規購入等の理由で、過去の本ブログのレンズ紹介
記事では未紹介のマニアックなレンズを主に紹介する
シリーズ記事。
今回は、未紹介レンズ4本を取り上げよう。
(一部は別カテゴリー記事で紹介済みだ)
----
まず、今回最初のレンズ。
![_c0032138_16331282.jpg]()
(中古購入価格 14,000円)(以下、CREATOR135)
カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)
2016年に発売された、中国製フルサイズ対応MF
単焦点望遠レンズ。
型番はⅡ型となっているが、旧製品が流通していた
記憶は無い。場合により、本Ⅱ型からの国内(日本)
流通なのかも知れない。
![_c0032138_16331383.jpg]()
追加した6群6枚構成との事。
旧製品との比較はわからないが、こうした構成だと
旧来の銀塩MF時代の135mm/F2.8級望遠での
一般的な4~5枚構成よりも、(色)収差補正等で
若干のアドバンテージはあるのだろう。
まあ、簡単に言えば、一見古い時代のスペックの
単焦点望遠だが、その実は、近代高性能レンズである、
という意味である。
これはなかなか(使う上でも)渋い製品コンセプトだ。
それに、これを入手する事で中一光学のCREATORシリーズ
(35mm/F2、ハイコスパ名玉編第4回記事等、
85mm/F2、ハイコスパレンズ第23回記事等)
が3機種(しかない)が揃う事も、マニアの習性である
「コンプリート願望」が出てしまっていた(汗)
幸いにして中古品が出てきたので、これを安価に購入。
まあ、こういった平凡なスペックのレンズはマニア層
でも興味が沸かないと思うし、さらにその中でも
恐らくは最も人気が無いのが、MFの135mm単焦点で
あろう。
人気の無さの理由の大半は心理的なものであり、
まず、マニア層が興味を持つ銀塩レンジファインダー機
用等では、この焦点距離は長すぎて使用困難であるし、
一眼レフ用としても、銀塩MF時代の初級中級層が必ずと
言っていいほど購入した135mm望遠であるから、珍しい
モノとは言い難いし、さらに言えば、銀塩AF時代では、
135mm単焦点は、望遠ズームに内包される焦点距離と
なってしまった為、AF135mm単焦点という仕様のレンズ
自体が、数える程しか存在していない状況だった。
すなわち、銀塩AF時代(1990年代前後)には、
MF135mm単焦点は、既に過去の時代のスペックの
レンズとなっていた訳だから、そこから30年位が
経過した現代においては、もう、とてつもなく古い
時代の、忘れられた仕様のレンズとなってしまっている。
こうした心理的な理由から135mm単焦点は不人気であり、
中古市場においても、MF135mm単焦点は、程度の良い
ものでも、ジャンクコーナーに置かれていたりして、
数千円という二束三文の相場だ。
心情的な理由等を持たない新規マニア層等は、
それらを見つけても「安かろう、悪かろう」と価値を
解釈するから、そうしたレンズが売れる筈も無い。
また、今回のように、ごく(非常に)稀に、135mmの
MF単焦点レンズが新発売されたとして、例えその新品
価格が2万円台と安価であっても、誰も見向きもしない。
むしろ、良く中古市場に流れてきたな、と、それの方が
不思議な状況だ。奇特なユーザーが居たのであろう。
ただまあ、私個人の感覚としては、1960年代頃から
1980年代頃まで、MF135mm単焦点レンズは、長期に
渡り、良く改良が続けられてきた商品だと思っている。
良く書く事だが、その時代のMF一眼レフユーザーが、
50mm標準レンズの次に買う単焦点レンズは、殆どが、
135mm望遠と28mm広角であったという状況がある。
その状況で、135mm望遠の性能(画質等)が、がっかり
とするものであると、初級ユーザー等は二度とその
メーカーのレンズを買ってはくれなくなるだろう。
だから、メーカーへの信頼を維持する為にも、135mm
望遠レンズは低い性能のものを作る事は許されない。
そして当時の価格も重要だ、安価でなければならず、
もし交換レンズがどれも高価すぎたならば、ビギナー
層は、キットレンズ(50mm標準)以外の交換レンズ
を買ってくれない。そして事実、当時の大半のユーザー
は50mm標準だけを使い、交換レンズなど買わないのだ、
その理由は、いつも言うように2つあり、
「交換レンズが高価だから」「種類が多すぎて、
どれを買ったら良いかわからないから」である。
この対策の為には、レンズ毎に利用目的を特定して
しまう事だ。これにより、1970~1980年代頃には、
28mm=風景、35mm=スナップ、50mm=汎用、
85mm=人物、といった住み分けを、この時代メーカーや
市場は、多くのユーザー層に「植え付ける」事に成功した。
(その「思い込み」は、50年もたった現代においても
多くの初級中級層の間で定着している、これはあまり
好ましい状態では無いが、まあ「薬が効きすぎた」
のであろう・・)
ただ、その上記の「常識」において、135mm望遠の
用途は不明である。しかし、ビギナー層はその当時も
今も、必ずと言って良いほど「望遠レンズ」に憧れる
ものである。だから、135mmや200mmなどは、黙って
いても売れていくのだ、特にこれらを「花や鳥を
撮るレンズだ」などと言わなくても十分だ。
まあでも、もしかすると、その「用途が曖昧で不明」
という点が、ユーザー層において、後年に135mmレンズ
の不人気を招いてしまったのかも知れない。
だとすると、不幸な話であろう。結局、現代においても
マニア層に至るまで、誰も135mm単焦点レンズの真の
実力値であるとか、その歴史的な変遷について知らない
という事になってしまうからだ。
なお、近代135mm級単焦点レンズについては、非常に
高性能なものが多く、それは「最強レンズ選手権
135mm編」で対戦済みである。
また、旧世代(銀塩時代)の135mm単焦点群は、
「特殊レンズ・スーパーマニアックス第62/63回」
記事で、紹介済みだ。
![_c0032138_16331324.jpg]()
本CREATOR135であるが、NIKON Fマウント版での
購入である。しかしながら、Ai露出連動爪を持たない
タイプのレンズなので、これがNIKON機(一眼レフ)
では非常に使い難い。殆ど全てのNIKON一眼レフでは
露出が狂って使えないが、唯一、NIKON Dfであれば
まあ使えない事は無い。だが、それでもあえて
NIKON Fマウント版で購入しているのは、こうして
おけば、殆ど全てのミラーレス機や、一部の一眼レフ
で使用可能だからだ。(Fマウントは汎用性が高い)
今回も、その利点を活かし、CANON 一眼レフで
本レンズを使用している。
描写力であるが、銀塩時代のMF135mm単焦点よりも
収差補正に配慮している設計で、なかなか悪く無い。
ただ、稀にボケ質破綻が出るので、それに留意する
必要があるが、今回使用の(デジタル)一眼レフでは、
なかなかボケ質破綻回避の技法は使えないので、もう
そのあたりは、手動絞りブラケットとか、背景の図柄
の連続的変更(アングルを変えながら撮影)等の
「数撃って探す」という手法しかできないと思う。
![_c0032138_16331325.jpg]()
この事は、135mm単焦点レンズの紹介記事の時に、
良く述べているのだが、「何を撮るレンズなのか?」
という課題だ。まあ、APS-C機で使えば、換算200mm
相当になるので、自然観察分野には、ある程度使える
と思うし、本レンズで少し発生する周辺減光の度合い
も抑える事が出来る。
ただし、その際に、本レンズの最短撮影距離は、
1.5mと、焦点距離の10倍則よりも長めであるので、
「思ったほど寄れない」という不満は出て来ると思う。
何かと制限があって、使い難い部分もあるレンズだ。
価格が安価だからと言って、初級中級層にはあまり推奨
し難いレンズであり、上級マニア向けとしておこう。
----
では、次のシステム
![_c0032138_16332298.jpg]()
(Model 278D)
(ジャンク購入価格 1500円)(以下、278D)
カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)
1999年発売のAF望遠ズーム。
銀塩用レンズなので、勿論フルサイズ対応である。
今回は、周辺性能等を判断する為、オフサイドルールを
緩和し、フルサイズ機のNIKON Dfを母艦とする。
前機種178D(1995年発売)が存在するが、本レンズ
においては外観デザインが少し変更されただけであり、
これらは同一のモデルと考えて良いであろう。
![_c0032138_16332217.jpg]()
8群9枚だとか、最短撮影距離1.5mも平凡だ。
まあ、廉価版望遠ズームと思われ、発売時の定価は
4万2000円との記録があるのだが、これは安売りの
対象商品、あるいは当時はよくあった、量販店等での
カメラボディとのセット販売(ダブルズームキット)
用だったかも知れない。何故ならば、この時代
1990年代後半は、AF一眼レフの売れ行きが芳しく無く、
当時から始まった新規格APS(IX240)カメラ、
高級(35mm判)コンパクト機、そしてチラホラとデジタル
カメラの発売も開始され(CASIO QV-10が1995年発売)
さらには中古カメラブームが起きている頃でもあった。
(=新鋭一眼レフに魅力が少ない為、マニア層を初め
とするユーザー層は、古い銀塩機に注目を始めた)
ローコスト型商品ではあるが、小型軽量である利点
はある。フィルター径はφ52mm、重量は僅かに281g
しか無く、エントリー層やビギナー層でも手軽に
望遠撮影が楽しめ、一眼レフの魅力を高める。という
コンセプトの商品であろう(注:当時の銀塩コンパクト機
等では、望遠域のレンズを搭載していた機種は少ない)
![_c0032138_16332380.jpg]()
当時のビギナー層でも、不満を感じ難いであろう。
ただし、ボケ質は、破綻とか言う以前に全般的にあまり
好ましく無い。これは設計上での諸収差の補正において
ビギナー層でもすぐわかる、解像感(例:球面収差等を
補正すれば良くなる)等に重点を置き、ボケ質等に
係わる収差(例:像面湾曲や非点収差)を重視しない
設計であると思われる。
つまり、ビギナーが気づく点だけ重点的に性能を高め
ビギナーが指摘しない部分の性能を妥協する事により
低価格化を実現している、という製品コンセプトだと
思われる。
だが、別に、それはそれで悪く無い。
(レンズ)製品を設計する上では、様々な設計基準
(注:これは「広い意味」での用語だ。巷でよく
言われるように、近接時での描写力とか、そういう
狭くて誤解しやすい意味では無い)を満たす為に、
何かの性能を高めれば、何かが犠牲になるという
「トレードオフ関係」が存在している。
限られた製造コスト(これは製品企画コンセプトの
影響が強い。「定価4万円、実売2万円で売るレンズ」
と言われれば、それに見合う原価で設計せざるを
得ないのだ)・・そのコストの中で、最善を尽くそう
とした結果であろう。
全ての収差を補正しようとすれば、大きく重く高価な
「三重苦」レンズとなってしまうし、例えば同様な
スペックで定価10万円越え、ともなれば、ビギナーは
もう誰も買ってくれなくなってしまう。
しかし、TAMRONとしても、さすがにこういう安価な
望遠ズームを作っていても、らちがあかない、と
考えたのだろうか? あるいは、こうしたサード
パーティー製廉価版望遠ズームを販売店舗主導で
「ダブルズームキット」とする風潮が、2000年代頃に
失われたからか?(注:メーカーから横槍が入った?
あるいは、レンズ・サードパーティーがカメラメーカー
のOEM生産を行うようになった? いずれも推測)
・・なので、この時代から後、2000年代でのTAMRONは
200mmや300mmの望遠端焦点距離をズームに内包する
「高倍率ズーム」の開発に主軸を移して行く事になる。
その為、TAMRONが次に「望遠ズーム」を開発するのは、
(フルサイズ対応としては)実に10数年が経過した
2010年に、TAMRON60周年記念モデルの高級レンズ
SP70-300mm/f4-5.6 Di VC USD(Model A005)
(ハイコスパレンズ名玉編第8回記事等参照)と
なった次第だ。
すなわち、TAMRONのローコスト望遠ズームという
ものとして、本278Dは、希少な製品となっている。
(注:x72D系300mmズームもローコスト版と言える
かもしれない)
![_c0032138_16332301.jpg]()
本レンズでは、あまり良質なスペックを与える事が
出来なかった(制限事項があった)と思われる。
しかし、そこまでわかったならば、そうした弱点に
留意して使用すれば良いだけである。
ちゃんと課題を意識して回避して用いれば、
そこそこ良く写るレンズとなり、おまけに安価である。
比較的近年とも言える銀塩AF時代末期のレンズとしては、
購入価格1500円は、なかなかお買い得でコスパが良い。
----
では、次のシステム。
![_c0032138_16332998.jpg]()
(ジャンク購入価格 500円)(以下、AF28-105)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
1997年発売のAF標準ズーム。
MINOLTA α-807si(未所有)と同時発売の記録が
あるが、同カメラのキット(付属)レンズで
あったかどうかは不明。
![_c0032138_16332944.jpg]()
(ミラーレス・マニアックス第56回記事等で紹介)
となり、広角端を拡張したと思われる。その後継
レンズは、後に、名機MINOLTA α-7(2000年発売、
Limited版を銀塩一眼第29回記事で紹介)のキット
標準ズームとなった。後継版の描写力は、個人的にも
なかなか気に入っていたので、今回、その前機種を
ジャンクからサルベージし、MINOLTAにおける標準
ズーム改良の歴史を研究してみよう、という目的も
あるが、本記事においては後継版との比較は行わない。
本レンズの描写力全般は、バランスが取れた設計で
悪く無い。まあ、本レンズは、発売当時のミノルタ
最上位機(α-807si、注:siシリーズに9番機は
存在しない)との併用を想定して開発された標準
ズームだと思われるので、あまり手を抜いた設計は
許されなかったのであろう。まあ、その傾向は
名機α-7のキット標準ズームであった、後継モデル
AF(ZOOM)24-105/3.5-4.5の際にも同様であって、
このような、高級機のキットズーム、又はそれに
準ずる併売ズームレンズの場合は、もしその描写力が
低ければ、カメラ本体の評判も落としてしまうからだ。
高級機の販売戦略上、それはまずい事になる。
だが、銀塩時代なので、実際の所は、極端に言えば
カメラはフィルムを入れる単なる「暗箱」なので、
同じレンズで同じフィルム、同じ絞り・シャッター
速度、同じピントであれば、カメラが何であっても
全て同じ写りとなる。まあ、だからレンズの性能が
描写力の7割程度を決める要素となっていた訳であり、
(残りの2割は撮影技法、さらに残り1割がフィルム、
という感じの比率であろうか・・・)カメラ自身は、
もうこの時代から既に、高級機であろうが無かろうが、
同じ写りであったのだ(これは現代のデジタル時代に
おいても、基本的には似たようなものだ。
現代の高級機には、通常の撮影では必要としないような
機能や性能を入れ、それを謳って付加価値としている、
=つまり、高額な定価としている、という仕組みだ)
![_c0032138_16332902.jpg]()
良い設計のレンズである。MINOLTA α-9(1998年)の
紹介記事(銀塩一眼第23回)でも書いたが、この時代の
MINOLTA製レンズは、相対的に他社の同時代の製品の
描写力を上回るケースが多い。
ただ、これもα-9の記事で書いたが、MINOLTAは
1992年~1998年頃、様々な事情で銀塩AF一眼レフの
販売が低迷していた時代でもある。
場合により、カメラ本体が売れないのであれば、レンズの
設計開発に注力し、この時代に他社を上回るレベルを
目指していたのかも知れない、もし「見る人が見れば」
その点は明白であるから、「ミノルタのレンズは良い」
という評判が世間に広まれば、低迷していたカメラ側の
売り上げの回復にも貢献できる可能性があったからだ。
でも、残念ながら、世間はそんな細かい所は見ては
いなかった。そもそも、この時代の1990年代後半は、
ユーザーの誰もが、AF一眼レフには興味を持っておらず
中古カメラの収集や、新しいコンセプトのカメラ
(APS機、高級コンパクト、デジタルコンパクト)に
興味の対象が移っていたからである。
・・だとしたら、不幸な話なのかも知れない。
技術者が人知れず改良を重ねたミノルタ製高性能銀塩用
レンズ群の事を、世間の誰もが知らないままで、時代は
急激にデジタル化に突入してしまったからだ。
![_c0032138_16332976.jpg]()
や、SONYへのカメラ事業の譲渡(2006年)の荒波に
飲み込まれ、銀塩末期のミノルタのカメラやレンズの
事など、もう誰も覚えていない(注目もしない)状況に
なってしまったからだ。
だが、例えば、その銀塩末期のミノルタ製一眼レフは、
α-9、α-7、α-SweetⅡといった、傑作機が勢ぞろい
しているし(各々、銀塩一眼レフクラッシックスで紹介済)
レンズも例えば、STF135/2.8(1998年)
(特殊レンズ第0回アポダイゼーション・グランドスラム
記事等の多数で紹介)といった、傑作レンズを世に
送り出しているのだ。
まあつまり、様々な不運により、ミノルタが世間に注目
されていなかった時代であっても、技術者はちゃんと
良い仕事をやっていた、という事が如実にわかる歴史
となっている。でもまあ、技術者心理というものは
そういうものである事も理解できる。営業とか市場戦略
とか、そんなものはどうでも良いのだ、限られた条件
の中で、最良の製品を創り出す事、それ以外に興味は
無いと思うし、市場が厳しければ厳しいほど、逆に、
「それならば、誰もが驚く良いものを作ってやろう」
という反骨精神が芽生え、それが技術開発業務上での
重要なモチベーションとなっていく訳だ。
それが無ければ、開発の仕事などやっていられない、
もし「売れるモノを作れ」等と上司から言われたとしても、
「スペックなんて、ただの飾りです!
偉い人には、それはわからんのです」と
ガンダムの技術者のように反論するしか無いであろう。
(注:MINOLTAは1991年頃のバブル期、超高機能化を
推進したα-xiシリーズを展開し、商業的に失敗している)
このあたりの技術開発の話は、たとえマニア層であっても
理解困難な話かも知れないが、実際に多くの時代の沢山の
製品を触っていれば、その背景に潜む「作った人の考えや
気持ち」は、おのずと見えてくる筈だ。
すなわち、ただ単に多数の機材をコレクションしている
だけでは勿体無い、マニアであれば、できれば、それらの
製品が訴えてくる「声」にも注目してもらいたい訳だ。
いや、むしろ、それが理解できる事が、上級マニアとして
必須なのかも知れない、さもなければ、「スペックや市場
での人気だけを気にする」という、前述の「偉い人」と
同じになってしまう・・
![_c0032138_16333607.jpg]()
大変良い。ただし焦点域から考えて、フルサイズ機か
銀塩機で使うのが無難であろう、APS-C機で常用ズームと
するには、広角域が足りなくなってしまう。
その際、SONYデジタル一眼で適正なフルサイズの機体が
無いのが課題となるかも知れない。、つまりα900は古く、
α99は持病持ち、α99Ⅱは高価すぎて、私もいずれも
購入できていない(追記:α99は後日購入済み)
そうならばむしろ、AF性能・精度の低下を甘んじても
α7系のミラーレス機で使う方が賢明かも知れない。
----
次は、今回ラストのレンズ
![_c0032138_16333619.jpg]()
(中古購入価格 30,000円)(以下、EF-S35/2.8)
カメラは、CANON EOS 8000D(APS-C機)
2017年頃発売の、APS-C機専用AF準広角(標準画角)
等倍マクロレンズ。
![_c0032138_16333691.jpg]()
躊躇していたCANON EF-S型レンズを初購入した旨を
説明した。何故EF-Sレンズをそれまで買わなかったの
かは、利用汎用性が低く、そのシステムのコンセプトが
個人的な好みに合わなかったからである。
(=EFレンズならば、CANONフルサイズ機でもAPS-C機
でも利用できるが、EF-SレンズはAPS-C機でしか使えない。
何故、クロップ等の対応が出来なかったのか?という意味)
ただ、もう事実上EF-Sレンズの購入は「解禁」である。
そうなれば、欲しいEF-Sレンズは何本か存在している、
その筆頭格が、今回紹介のEF-S35/2.8であった。
本レンズの最大の特徴は、白色LED照明を内蔵した
交換レンズ(マクロ)である事だ。
この仕様のレンズは、本レンズとCANONミラーレス機用
EF-Mマウントの「EF-M 28mm/F3.5 Macro IS STM」
の2本しか存在しない。
EF-M版が1年早く2016年に登場していたので、その
レンズを使う為に(未所有の)EF-M機(EOS Mシリーズ)
を買おうかと画策していたのだが・・
(注:「使いたいレンズがあるならば、使用マウントを
増やしても良い」という個人的ルールがある)
幸い、翌年、EF-S版でもLED付きマクロが出てくれたので、
そちらを買えば、新規マウントを増やさずに済む。
EF-Mは、正直言えばそのLED付きマクロ以外には魅力的な
レンズが無く、レンズラインナップ自体も数本しか存在して
いなかったのだ。
・・とは言え、後日には、中古相場が下がったEOS M5を
入手しているが、一応それは事前に想定していて、EF-S版
のレンズを買っておけば、EOS APS-C機でも、EOS M機でも
両者で使えるという汎用性を利点と見ていた。
![_c0032138_16333664.jpg]()
本レンズの特徴は、勿論LED付きマクロであり、その1点に
尽きるのだが、具体的にその詳細を説明して行こう。
まず、LEDを点灯させるには、フード(兼フィルター枠)
部品を取り外さなくてはならない。
この場合、LEDおよびレンズ面がむき出しとなり、
かつ保護フィルターの装着も不可となるので、
ハンドリング(持ち運び時)や、近接撮影時に、何処かに
ぶつける等の危険性が出てくるので、十分に留意して
使用する必要がある。
レンズ横のスイッチ(ボタン)を1度押すと、LEDが
全点灯、もう1度押すと、およそ半分の光量で半点灯、
さらに押すと消灯となる。だが、カメラの電源を入れて
使用する度に、この操作となるので、少々操作性は悪い。
これをスライド型スイッチにして貰えたのならば、カメラ
の電源ON/OFF時に、この面倒さは解消できたので残念だ。
LEDの効果だが、暗所では勿論補助照明として有効だ。
ちなみに、完全暗所の場合でも、LED光のみでの撮影が
可能であり、高感度(例:ISO3200程度)で、開放で
手持ち撮影が可能な程度(例:シャッター速度1/50秒
~1/60秒)の光量となる。
屋外等の明所であっても、フラッシュ(日中シンクロ)を
使った時のように、近接撮影でレンズ等の影を消したり
被写体上の明暗差を消す、などの高度な利用法が実現
できるか?と思ったのだが、直射日光等の当たっている
環境においては、直接光とLED光は、光量の差が大き
すぎる為(LEDが暗すぎる為)、上記のような「明暗差を
消す」等の用途には殆ど効果が無い。
まあ、僅かに被写体上の反射トーンが均一化される程度
であり、効果は微々たるものである。おまけに、その
テクスチャー(=被写体表面の質感等)感については、
アンコトローラブル(=利用者側で自在に制御できない)
ので、大変難しい撮影技法となる。
まあ、現状では、日中明所の近接撮影において、LEDの
ON/OFFを繰り返して効果を見ている段階であるが、きっと
もっと中途半端な光線状況(例:まだ暗い早朝、夕暮れ、
やや暗い室内等)では、LEDの効果が上手く現れる可能性
はある(ただし、依然、アンコントローラブルだ)
基本的に内蔵LEDを有効に用いる使いこなしは、かなり
ハイレベルなスキルを要求されるであろう。
レンズ自身の描写力であるが、解像感は悪く無いが、
ボケ質破綻が頻発する。というか設計上で像面湾曲収差
や非点収差が残っている模様で、全般的にボケが汚く、
ほんの僅かに「グルグルボケ傾向」も見られる。
これはまあ、ビギナー層に向けた設計思想であり、
すなわちビギナーが気づく点のみを重点的に改善している
状態だ。前述のTAMRON 278D廉価版スームと同様の設計
コンセプトであり、こういうのは、「通」好みでは無い。
ただ、「平面マクロ」としての特性を持つ、とも言える
ので、その特性がユーザー側の利用目的に合致するので
あれば、この弱点は見逃す事はできる。(ここはかなり
高度な話なので上級者向けの概念だ)
また、ピント精度が良く無い。これは母艦とする一眼レフ
の性能にも依存すると思うが、今回使用のEOS 8000Dでは
やや厳しく、おまけにEOS普及/初級機の貧弱なファインダー
性能では、MFではピントの山がわからず、MFに切り替えて
AF精度の問題点を回避する技法が使えない。
これ以上のピント精度をCANONのAPS-C機(一眼レフ)で
求めるならば、例えば、EOS 7D MarkⅡを使用する事に
なるのだが、オフサイド状態(=ボディとレンズの価格比が
アンバランス)となり、個人的な持論(ルール)に抵触する。
まあつまり、母艦の選択肢が少なくなる事が、私がこれまで
EF-S型レンズの購入を躊躇していた最大の理由なのだ。
![_c0032138_16333975.jpg]()
「LEDが付いているから便利そうだ」と考えての購入理由は
ちょっと早計であった(汗) 過去、LEDが付いている
交換レンズが、前述のようにほとんど存在していなかった
事も、勝手にそう(=便利そう)と思い込んでしまった
原因なのだろう。
LEDが付いていたとしても、それが有効に使える状況が
極めて限られていて、しかも制御が難しいのであれば、
あまりLEDの価値は大きく無い。
そして、マクロレンズとしての描写性能は、並み以下で
あるから、あまり魅力的では無い。
それでもまあ、CANON APS-C機(一眼レフ)を持って
いるならば、他にあまり有益な標準(相当)画角マクロ
は無いので、本レンズが有力な選択肢となるだろう。
だが、その場合は、価格(中古相場)には注意する
必要がある、私の場合は、発売間もない段階で買って
しまったので、やや高価すぎ、コスパが悪く感じる。
SONY E 30/3.5Macro(SEL30M35)と類似の描写傾向
と考えれば、そのレンズの中古相場である15000円
前後、というのが本EF-S35/2.8でも妥当であろう。
----
さて、今回の記事は、このあたり迄で。次回記事に続く。
記事では未紹介のマニアックなレンズを主に紹介する
シリーズ記事。
今回は、未紹介レンズ4本を取り上げよう。
(一部は別カテゴリー記事で紹介済みだ)
----
まず、今回最初のレンズ。

(中古購入価格 14,000円)(以下、CREATOR135)
カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)
2016年に発売された、中国製フルサイズ対応MF
単焦点望遠レンズ。
型番はⅡ型となっているが、旧製品が流通していた
記憶は無い。場合により、本Ⅱ型からの国内(日本)
流通なのかも知れない。

追加した6群6枚構成との事。
旧製品との比較はわからないが、こうした構成だと
旧来の銀塩MF時代の135mm/F2.8級望遠での
一般的な4~5枚構成よりも、(色)収差補正等で
若干のアドバンテージはあるのだろう。
まあ、簡単に言えば、一見古い時代のスペックの
単焦点望遠だが、その実は、近代高性能レンズである、
という意味である。
これはなかなか(使う上でも)渋い製品コンセプトだ。
それに、これを入手する事で中一光学のCREATORシリーズ
(35mm/F2、ハイコスパ名玉編第4回記事等、
85mm/F2、ハイコスパレンズ第23回記事等)
が3機種(しかない)が揃う事も、マニアの習性である
「コンプリート願望」が出てしまっていた(汗)
幸いにして中古品が出てきたので、これを安価に購入。
まあ、こういった平凡なスペックのレンズはマニア層
でも興味が沸かないと思うし、さらにその中でも
恐らくは最も人気が無いのが、MFの135mm単焦点で
あろう。
人気の無さの理由の大半は心理的なものであり、
まず、マニア層が興味を持つ銀塩レンジファインダー機
用等では、この焦点距離は長すぎて使用困難であるし、
一眼レフ用としても、銀塩MF時代の初級中級層が必ずと
言っていいほど購入した135mm望遠であるから、珍しい
モノとは言い難いし、さらに言えば、銀塩AF時代では、
135mm単焦点は、望遠ズームに内包される焦点距離と
なってしまった為、AF135mm単焦点という仕様のレンズ
自体が、数える程しか存在していない状況だった。
すなわち、銀塩AF時代(1990年代前後)には、
MF135mm単焦点は、既に過去の時代のスペックの
レンズとなっていた訳だから、そこから30年位が
経過した現代においては、もう、とてつもなく古い
時代の、忘れられた仕様のレンズとなってしまっている。
こうした心理的な理由から135mm単焦点は不人気であり、
中古市場においても、MF135mm単焦点は、程度の良い
ものでも、ジャンクコーナーに置かれていたりして、
数千円という二束三文の相場だ。
心情的な理由等を持たない新規マニア層等は、
それらを見つけても「安かろう、悪かろう」と価値を
解釈するから、そうしたレンズが売れる筈も無い。
また、今回のように、ごく(非常に)稀に、135mmの
MF単焦点レンズが新発売されたとして、例えその新品
価格が2万円台と安価であっても、誰も見向きもしない。
むしろ、良く中古市場に流れてきたな、と、それの方が
不思議な状況だ。奇特なユーザーが居たのであろう。
ただまあ、私個人の感覚としては、1960年代頃から
1980年代頃まで、MF135mm単焦点レンズは、長期に
渡り、良く改良が続けられてきた商品だと思っている。
良く書く事だが、その時代のMF一眼レフユーザーが、
50mm標準レンズの次に買う単焦点レンズは、殆どが、
135mm望遠と28mm広角であったという状況がある。
その状況で、135mm望遠の性能(画質等)が、がっかり
とするものであると、初級ユーザー等は二度とその
メーカーのレンズを買ってはくれなくなるだろう。
だから、メーカーへの信頼を維持する為にも、135mm
望遠レンズは低い性能のものを作る事は許されない。
そして当時の価格も重要だ、安価でなければならず、
もし交換レンズがどれも高価すぎたならば、ビギナー
層は、キットレンズ(50mm標準)以外の交換レンズ
を買ってくれない。そして事実、当時の大半のユーザー
は50mm標準だけを使い、交換レンズなど買わないのだ、
その理由は、いつも言うように2つあり、
「交換レンズが高価だから」「種類が多すぎて、
どれを買ったら良いかわからないから」である。
この対策の為には、レンズ毎に利用目的を特定して
しまう事だ。これにより、1970~1980年代頃には、
28mm=風景、35mm=スナップ、50mm=汎用、
85mm=人物、といった住み分けを、この時代メーカーや
市場は、多くのユーザー層に「植え付ける」事に成功した。
(その「思い込み」は、50年もたった現代においても
多くの初級中級層の間で定着している、これはあまり
好ましい状態では無いが、まあ「薬が効きすぎた」
のであろう・・)
ただ、その上記の「常識」において、135mm望遠の
用途は不明である。しかし、ビギナー層はその当時も
今も、必ずと言って良いほど「望遠レンズ」に憧れる
ものである。だから、135mmや200mmなどは、黙って
いても売れていくのだ、特にこれらを「花や鳥を
撮るレンズだ」などと言わなくても十分だ。
まあでも、もしかすると、その「用途が曖昧で不明」
という点が、ユーザー層において、後年に135mmレンズ
の不人気を招いてしまったのかも知れない。
だとすると、不幸な話であろう。結局、現代においても
マニア層に至るまで、誰も135mm単焦点レンズの真の
実力値であるとか、その歴史的な変遷について知らない
という事になってしまうからだ。
なお、近代135mm級単焦点レンズについては、非常に
高性能なものが多く、それは「最強レンズ選手権
135mm編」で対戦済みである。
また、旧世代(銀塩時代)の135mm単焦点群は、
「特殊レンズ・スーパーマニアックス第62/63回」
記事で、紹介済みだ。

本CREATOR135であるが、NIKON Fマウント版での
購入である。しかしながら、Ai露出連動爪を持たない
タイプのレンズなので、これがNIKON機(一眼レフ)
では非常に使い難い。殆ど全てのNIKON一眼レフでは
露出が狂って使えないが、唯一、NIKON Dfであれば
まあ使えない事は無い。だが、それでもあえて
NIKON Fマウント版で購入しているのは、こうして
おけば、殆ど全てのミラーレス機や、一部の一眼レフ
で使用可能だからだ。(Fマウントは汎用性が高い)
今回も、その利点を活かし、CANON 一眼レフで
本レンズを使用している。
描写力であるが、銀塩時代のMF135mm単焦点よりも
収差補正に配慮している設計で、なかなか悪く無い。
ただ、稀にボケ質破綻が出るので、それに留意する
必要があるが、今回使用の(デジタル)一眼レフでは、
なかなかボケ質破綻回避の技法は使えないので、もう
そのあたりは、手動絞りブラケットとか、背景の図柄
の連続的変更(アングルを変えながら撮影)等の
「数撃って探す」という手法しかできないと思う。

この事は、135mm単焦点レンズの紹介記事の時に、
良く述べているのだが、「何を撮るレンズなのか?」
という課題だ。まあ、APS-C機で使えば、換算200mm
相当になるので、自然観察分野には、ある程度使える
と思うし、本レンズで少し発生する周辺減光の度合い
も抑える事が出来る。
ただし、その際に、本レンズの最短撮影距離は、
1.5mと、焦点距離の10倍則よりも長めであるので、
「思ったほど寄れない」という不満は出て来ると思う。
何かと制限があって、使い難い部分もあるレンズだ。
価格が安価だからと言って、初級中級層にはあまり推奨
し難いレンズであり、上級マニア向けとしておこう。
----
では、次のシステム

(Model 278D)
(ジャンク購入価格 1500円)(以下、278D)
カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)
1999年発売のAF望遠ズーム。
銀塩用レンズなので、勿論フルサイズ対応である。
今回は、周辺性能等を判断する為、オフサイドルールを
緩和し、フルサイズ機のNIKON Dfを母艦とする。
前機種178D(1995年発売)が存在するが、本レンズ
においては外観デザインが少し変更されただけであり、
これらは同一のモデルと考えて良いであろう。

8群9枚だとか、最短撮影距離1.5mも平凡だ。
まあ、廉価版望遠ズームと思われ、発売時の定価は
4万2000円との記録があるのだが、これは安売りの
対象商品、あるいは当時はよくあった、量販店等での
カメラボディとのセット販売(ダブルズームキット)
用だったかも知れない。何故ならば、この時代
1990年代後半は、AF一眼レフの売れ行きが芳しく無く、
当時から始まった新規格APS(IX240)カメラ、
高級(35mm判)コンパクト機、そしてチラホラとデジタル
カメラの発売も開始され(CASIO QV-10が1995年発売)
さらには中古カメラブームが起きている頃でもあった。
(=新鋭一眼レフに魅力が少ない為、マニア層を初め
とするユーザー層は、古い銀塩機に注目を始めた)
ローコスト型商品ではあるが、小型軽量である利点
はある。フィルター径はφ52mm、重量は僅かに281g
しか無く、エントリー層やビギナー層でも手軽に
望遠撮影が楽しめ、一眼レフの魅力を高める。という
コンセプトの商品であろう(注:当時の銀塩コンパクト機
等では、望遠域のレンズを搭載していた機種は少ない)

当時のビギナー層でも、不満を感じ難いであろう。
ただし、ボケ質は、破綻とか言う以前に全般的にあまり
好ましく無い。これは設計上での諸収差の補正において
ビギナー層でもすぐわかる、解像感(例:球面収差等を
補正すれば良くなる)等に重点を置き、ボケ質等に
係わる収差(例:像面湾曲や非点収差)を重視しない
設計であると思われる。
つまり、ビギナーが気づく点だけ重点的に性能を高め
ビギナーが指摘しない部分の性能を妥協する事により
低価格化を実現している、という製品コンセプトだと
思われる。
だが、別に、それはそれで悪く無い。
(レンズ)製品を設計する上では、様々な設計基準
(注:これは「広い意味」での用語だ。巷でよく
言われるように、近接時での描写力とか、そういう
狭くて誤解しやすい意味では無い)を満たす為に、
何かの性能を高めれば、何かが犠牲になるという
「トレードオフ関係」が存在している。
限られた製造コスト(これは製品企画コンセプトの
影響が強い。「定価4万円、実売2万円で売るレンズ」
と言われれば、それに見合う原価で設計せざるを
得ないのだ)・・そのコストの中で、最善を尽くそう
とした結果であろう。
全ての収差を補正しようとすれば、大きく重く高価な
「三重苦」レンズとなってしまうし、例えば同様な
スペックで定価10万円越え、ともなれば、ビギナーは
もう誰も買ってくれなくなってしまう。
しかし、TAMRONとしても、さすがにこういう安価な
望遠ズームを作っていても、らちがあかない、と
考えたのだろうか? あるいは、こうしたサード
パーティー製廉価版望遠ズームを販売店舗主導で
「ダブルズームキット」とする風潮が、2000年代頃に
失われたからか?(注:メーカーから横槍が入った?
あるいは、レンズ・サードパーティーがカメラメーカー
のOEM生産を行うようになった? いずれも推測)
・・なので、この時代から後、2000年代でのTAMRONは
200mmや300mmの望遠端焦点距離をズームに内包する
「高倍率ズーム」の開発に主軸を移して行く事になる。
その為、TAMRONが次に「望遠ズーム」を開発するのは、
(フルサイズ対応としては)実に10数年が経過した
2010年に、TAMRON60周年記念モデルの高級レンズ
SP70-300mm/f4-5.6 Di VC USD(Model A005)
(ハイコスパレンズ名玉編第8回記事等参照)と
なった次第だ。
すなわち、TAMRONのローコスト望遠ズームという
ものとして、本278Dは、希少な製品となっている。
(注:x72D系300mmズームもローコスト版と言える
かもしれない)

本レンズでは、あまり良質なスペックを与える事が
出来なかった(制限事項があった)と思われる。
しかし、そこまでわかったならば、そうした弱点に
留意して使用すれば良いだけである。
ちゃんと課題を意識して回避して用いれば、
そこそこ良く写るレンズとなり、おまけに安価である。
比較的近年とも言える銀塩AF時代末期のレンズとしては、
購入価格1500円は、なかなかお買い得でコスパが良い。
----
では、次のシステム。

(ジャンク購入価格 500円)(以下、AF28-105)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
1997年発売のAF標準ズーム。
MINOLTA α-807si(未所有)と同時発売の記録が
あるが、同カメラのキット(付属)レンズで
あったかどうかは不明。

(ミラーレス・マニアックス第56回記事等で紹介)
となり、広角端を拡張したと思われる。その後継
レンズは、後に、名機MINOLTA α-7(2000年発売、
Limited版を銀塩一眼第29回記事で紹介)のキット
標準ズームとなった。後継版の描写力は、個人的にも
なかなか気に入っていたので、今回、その前機種を
ジャンクからサルベージし、MINOLTAにおける標準
ズーム改良の歴史を研究してみよう、という目的も
あるが、本記事においては後継版との比較は行わない。
本レンズの描写力全般は、バランスが取れた設計で
悪く無い。まあ、本レンズは、発売当時のミノルタ
最上位機(α-807si、注:siシリーズに9番機は
存在しない)との併用を想定して開発された標準
ズームだと思われるので、あまり手を抜いた設計は
許されなかったのであろう。まあ、その傾向は
名機α-7のキット標準ズームであった、後継モデル
AF(ZOOM)24-105/3.5-4.5の際にも同様であって、
このような、高級機のキットズーム、又はそれに
準ずる併売ズームレンズの場合は、もしその描写力が
低ければ、カメラ本体の評判も落としてしまうからだ。
高級機の販売戦略上、それはまずい事になる。
だが、銀塩時代なので、実際の所は、極端に言えば
カメラはフィルムを入れる単なる「暗箱」なので、
同じレンズで同じフィルム、同じ絞り・シャッター
速度、同じピントであれば、カメラが何であっても
全て同じ写りとなる。まあ、だからレンズの性能が
描写力の7割程度を決める要素となっていた訳であり、
(残りの2割は撮影技法、さらに残り1割がフィルム、
という感じの比率であろうか・・・)カメラ自身は、
もうこの時代から既に、高級機であろうが無かろうが、
同じ写りであったのだ(これは現代のデジタル時代に
おいても、基本的には似たようなものだ。
現代の高級機には、通常の撮影では必要としないような
機能や性能を入れ、それを謳って付加価値としている、
=つまり、高額な定価としている、という仕組みだ)
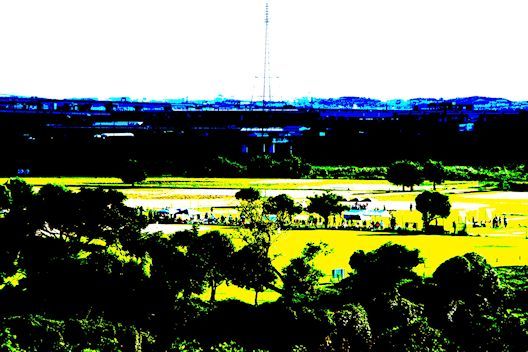
良い設計のレンズである。MINOLTA α-9(1998年)の
紹介記事(銀塩一眼第23回)でも書いたが、この時代の
MINOLTA製レンズは、相対的に他社の同時代の製品の
描写力を上回るケースが多い。
ただ、これもα-9の記事で書いたが、MINOLTAは
1992年~1998年頃、様々な事情で銀塩AF一眼レフの
販売が低迷していた時代でもある。
場合により、カメラ本体が売れないのであれば、レンズの
設計開発に注力し、この時代に他社を上回るレベルを
目指していたのかも知れない、もし「見る人が見れば」
その点は明白であるから、「ミノルタのレンズは良い」
という評判が世間に広まれば、低迷していたカメラ側の
売り上げの回復にも貢献できる可能性があったからだ。
でも、残念ながら、世間はそんな細かい所は見ては
いなかった。そもそも、この時代の1990年代後半は、
ユーザーの誰もが、AF一眼レフには興味を持っておらず
中古カメラの収集や、新しいコンセプトのカメラ
(APS機、高級コンパクト、デジタルコンパクト)に
興味の対象が移っていたからである。
・・だとしたら、不幸な話なのかも知れない。
技術者が人知れず改良を重ねたミノルタ製高性能銀塩用
レンズ群の事を、世間の誰もが知らないままで、時代は
急激にデジタル化に突入してしまったからだ。

や、SONYへのカメラ事業の譲渡(2006年)の荒波に
飲み込まれ、銀塩末期のミノルタのカメラやレンズの
事など、もう誰も覚えていない(注目もしない)状況に
なってしまったからだ。
だが、例えば、その銀塩末期のミノルタ製一眼レフは、
α-9、α-7、α-SweetⅡといった、傑作機が勢ぞろい
しているし(各々、銀塩一眼レフクラッシックスで紹介済)
レンズも例えば、STF135/2.8(1998年)
(特殊レンズ第0回アポダイゼーション・グランドスラム
記事等の多数で紹介)といった、傑作レンズを世に
送り出しているのだ。
まあつまり、様々な不運により、ミノルタが世間に注目
されていなかった時代であっても、技術者はちゃんと
良い仕事をやっていた、という事が如実にわかる歴史
となっている。でもまあ、技術者心理というものは
そういうものである事も理解できる。営業とか市場戦略
とか、そんなものはどうでも良いのだ、限られた条件
の中で、最良の製品を創り出す事、それ以外に興味は
無いと思うし、市場が厳しければ厳しいほど、逆に、
「それならば、誰もが驚く良いものを作ってやろう」
という反骨精神が芽生え、それが技術開発業務上での
重要なモチベーションとなっていく訳だ。
それが無ければ、開発の仕事などやっていられない、
もし「売れるモノを作れ」等と上司から言われたとしても、
「スペックなんて、ただの飾りです!
偉い人には、それはわからんのです」と
ガンダムの技術者のように反論するしか無いであろう。
(注:MINOLTAは1991年頃のバブル期、超高機能化を
推進したα-xiシリーズを展開し、商業的に失敗している)
このあたりの技術開発の話は、たとえマニア層であっても
理解困難な話かも知れないが、実際に多くの時代の沢山の
製品を触っていれば、その背景に潜む「作った人の考えや
気持ち」は、おのずと見えてくる筈だ。
すなわち、ただ単に多数の機材をコレクションしている
だけでは勿体無い、マニアであれば、できれば、それらの
製品が訴えてくる「声」にも注目してもらいたい訳だ。
いや、むしろ、それが理解できる事が、上級マニアとして
必須なのかも知れない、さもなければ、「スペックや市場
での人気だけを気にする」という、前述の「偉い人」と
同じになってしまう・・

大変良い。ただし焦点域から考えて、フルサイズ機か
銀塩機で使うのが無難であろう、APS-C機で常用ズームと
するには、広角域が足りなくなってしまう。
その際、SONYデジタル一眼で適正なフルサイズの機体が
無いのが課題となるかも知れない。、つまりα900は古く、
α99は持病持ち、α99Ⅱは高価すぎて、私もいずれも
購入できていない(追記:α99は後日購入済み)
そうならばむしろ、AF性能・精度の低下を甘んじても
α7系のミラーレス機で使う方が賢明かも知れない。
----
次は、今回ラストのレンズ

(中古購入価格 30,000円)(以下、EF-S35/2.8)
カメラは、CANON EOS 8000D(APS-C機)
2017年頃発売の、APS-C機専用AF準広角(標準画角)
等倍マクロレンズ。

躊躇していたCANON EF-S型レンズを初購入した旨を
説明した。何故EF-Sレンズをそれまで買わなかったの
かは、利用汎用性が低く、そのシステムのコンセプトが
個人的な好みに合わなかったからである。
(=EFレンズならば、CANONフルサイズ機でもAPS-C機
でも利用できるが、EF-SレンズはAPS-C機でしか使えない。
何故、クロップ等の対応が出来なかったのか?という意味)
ただ、もう事実上EF-Sレンズの購入は「解禁」である。
そうなれば、欲しいEF-Sレンズは何本か存在している、
その筆頭格が、今回紹介のEF-S35/2.8であった。
本レンズの最大の特徴は、白色LED照明を内蔵した
交換レンズ(マクロ)である事だ。
この仕様のレンズは、本レンズとCANONミラーレス機用
EF-Mマウントの「EF-M 28mm/F3.5 Macro IS STM」
の2本しか存在しない。
EF-M版が1年早く2016年に登場していたので、その
レンズを使う為に(未所有の)EF-M機(EOS Mシリーズ)
を買おうかと画策していたのだが・・
(注:「使いたいレンズがあるならば、使用マウントを
増やしても良い」という個人的ルールがある)
幸い、翌年、EF-S版でもLED付きマクロが出てくれたので、
そちらを買えば、新規マウントを増やさずに済む。
EF-Mは、正直言えばそのLED付きマクロ以外には魅力的な
レンズが無く、レンズラインナップ自体も数本しか存在して
いなかったのだ。
・・とは言え、後日には、中古相場が下がったEOS M5を
入手しているが、一応それは事前に想定していて、EF-S版
のレンズを買っておけば、EOS APS-C機でも、EOS M機でも
両者で使えるという汎用性を利点と見ていた。

本レンズの特徴は、勿論LED付きマクロであり、その1点に
尽きるのだが、具体的にその詳細を説明して行こう。
まず、LEDを点灯させるには、フード(兼フィルター枠)
部品を取り外さなくてはならない。
この場合、LEDおよびレンズ面がむき出しとなり、
かつ保護フィルターの装着も不可となるので、
ハンドリング(持ち運び時)や、近接撮影時に、何処かに
ぶつける等の危険性が出てくるので、十分に留意して
使用する必要がある。
レンズ横のスイッチ(ボタン)を1度押すと、LEDが
全点灯、もう1度押すと、およそ半分の光量で半点灯、
さらに押すと消灯となる。だが、カメラの電源を入れて
使用する度に、この操作となるので、少々操作性は悪い。
これをスライド型スイッチにして貰えたのならば、カメラ
の電源ON/OFF時に、この面倒さは解消できたので残念だ。
LEDの効果だが、暗所では勿論補助照明として有効だ。
ちなみに、完全暗所の場合でも、LED光のみでの撮影が
可能であり、高感度(例:ISO3200程度)で、開放で
手持ち撮影が可能な程度(例:シャッター速度1/50秒
~1/60秒)の光量となる。
屋外等の明所であっても、フラッシュ(日中シンクロ)を
使った時のように、近接撮影でレンズ等の影を消したり
被写体上の明暗差を消す、などの高度な利用法が実現
できるか?と思ったのだが、直射日光等の当たっている
環境においては、直接光とLED光は、光量の差が大き
すぎる為(LEDが暗すぎる為)、上記のような「明暗差を
消す」等の用途には殆ど効果が無い。
まあ、僅かに被写体上の反射トーンが均一化される程度
であり、効果は微々たるものである。おまけに、その
テクスチャー(=被写体表面の質感等)感については、
アンコトローラブル(=利用者側で自在に制御できない)
ので、大変難しい撮影技法となる。
まあ、現状では、日中明所の近接撮影において、LEDの
ON/OFFを繰り返して効果を見ている段階であるが、きっと
もっと中途半端な光線状況(例:まだ暗い早朝、夕暮れ、
やや暗い室内等)では、LEDの効果が上手く現れる可能性
はある(ただし、依然、アンコントローラブルだ)
基本的に内蔵LEDを有効に用いる使いこなしは、かなり
ハイレベルなスキルを要求されるであろう。
レンズ自身の描写力であるが、解像感は悪く無いが、
ボケ質破綻が頻発する。というか設計上で像面湾曲収差
や非点収差が残っている模様で、全般的にボケが汚く、
ほんの僅かに「グルグルボケ傾向」も見られる。
これはまあ、ビギナー層に向けた設計思想であり、
すなわちビギナーが気づく点のみを重点的に改善している
状態だ。前述のTAMRON 278D廉価版スームと同様の設計
コンセプトであり、こういうのは、「通」好みでは無い。
ただ、「平面マクロ」としての特性を持つ、とも言える
ので、その特性がユーザー側の利用目的に合致するので
あれば、この弱点は見逃す事はできる。(ここはかなり
高度な話なので上級者向けの概念だ)
また、ピント精度が良く無い。これは母艦とする一眼レフ
の性能にも依存すると思うが、今回使用のEOS 8000Dでは
やや厳しく、おまけにEOS普及/初級機の貧弱なファインダー
性能では、MFではピントの山がわからず、MFに切り替えて
AF精度の問題点を回避する技法が使えない。
これ以上のピント精度をCANONのAPS-C機(一眼レフ)で
求めるならば、例えば、EOS 7D MarkⅡを使用する事に
なるのだが、オフサイド状態(=ボディとレンズの価格比が
アンバランス)となり、個人的な持論(ルール)に抵触する。
まあつまり、母艦の選択肢が少なくなる事が、私がこれまで
EF-S型レンズの購入を躊躇していた最大の理由なのだ。

「LEDが付いているから便利そうだ」と考えての購入理由は
ちょっと早計であった(汗) 過去、LEDが付いている
交換レンズが、前述のようにほとんど存在していなかった
事も、勝手にそう(=便利そう)と思い込んでしまった
原因なのだろう。
LEDが付いていたとしても、それが有効に使える状況が
極めて限られていて、しかも制御が難しいのであれば、
あまりLEDの価値は大きく無い。
そして、マクロレンズとしての描写性能は、並み以下で
あるから、あまり魅力的では無い。
それでもまあ、CANON APS-C機(一眼レフ)を持って
いるならば、他にあまり有益な標準(相当)画角マクロ
は無いので、本レンズが有力な選択肢となるだろう。
だが、その場合は、価格(中古相場)には注意する
必要がある、私の場合は、発売間もない段階で買って
しまったので、やや高価すぎ、コスパが悪く感じる。
SONY E 30/3.5Macro(SEL30M35)と類似の描写傾向
と考えれば、そのレンズの中古相場である15000円
前後、というのが本EF-S35/2.8でも妥当であろう。
----
さて、今回の記事は、このあたり迄で。次回記事に続く。