海外製のレンズを紹介するシリーズ記事。
今回は「HOLGA LENSマニアックス」という主旨とし、
同社製の4本のレンズを紹介する。
なお、過去記事「特殊レンズ第3回HOLGA LENS編」と
完全に紹介レンズが被ってしまう為、本記事では
使用する母艦を変更、撮影技法も従前の記事とは
変えて、説明も異なる内容として、重複を避ける。
![_c0032138_14583748.jpg]()
製の安価なカメラのブランド(シリーズ)銘である。
(注:正確には「Holga」と、先頭のみ大文字表記で
あると思われるが、本記事では便宜上「HOLGA」と
全て大文字で記載する。つまり特定のメーカーだけ、
独自の記載法をしていたらキリが無いし、そもそも
光学界全般では、用語統一等が全く行われていない。
そこで、「メーカー名は全て大文字表記とする。
レンズ名は実機上の記載を基準とする。ただし開放F値
の表記は/fとする」、という風に本ブログでは独自の
標準記載ルールを作り、できるだけそれを守っている)
で、HOLGA(カメラ)だが・・
主に、中国国内のプロレタリアート(労働者階級)
に向けて、「多数のカメラを安価に販売する」事が
企画開発意図であったとは思うが、その後の時代で
世情は大きく変わり(中国での賃金向上、香港返還、
デジタルカメラの登場、その他もろもろ)により、
このHOLGA(120系)カメラは、1990年代後半~
2000年代前半頃では、主に海外に輸出される
ようになった。また、現在においては、ほぼ
生産完了(ディスコン)となっていると思われる。
このHOLGA 120系カメラは、設計における徹底的な
コストダウンの影響での性能不足、及び低い製造品質
により、いわゆる「Lo-Fi描写」(匠の写真用語辞典
第5回記事)が得られる事で著名であり、広義での
「トイカメラ」に属するフィルムカメラであった。
現代でもHOLGA(120系)カメラは、中古品または
新品在庫等で入手できるのだが、銀塩ビジネスの
縮退により、ブローニー(120)判フィルムの入手や
現像、そして、それらのコスト高が非常に厳しい。
(例:フィルムを1本買って撮って現像するだけで、
HOLGAカメラ本体よりも高価になってしまう)
まあ、このあたりの銀塩環境のコスト高が、HOLGA
カメラの生産販売が継続し難くなった理由であろう。
・・で、本記事で紹介する製品は、HOLGA銀塩カメラ
では無く「HOLGA LENS」である。
それが何か?は、記事中で追々説明していくが、
個々のレンズの特徴よりも、「Lo-Fi」という思想を
中心に、歴史的背景等の内容の記事を構成していく。
----
ではまず、今回最初のHOLGAレンズ。
![_c0032138_14583735.jpg]()
(新古品購入価格 1,000円)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
2010年代前半に発売と思われる単焦点MFトイレンズ。
こちらは一眼レフ用であり、60mmのオリジナルHOLGA
と同じ焦点距離、つまりHOLGA 120系に搭載されていた
プラスチック・レンズを単体発売したものである。
以降、いずれのHOLGA LENSも同様に、2010年代前半
頃の発売で、勿論MF単焦点であるが、焦点距離のみ
対応マウントによりけりで異なっている。
以下、ほとんどの記事内容は、レンズそのものの
話では無く、全般的かつ、歴史的・心理的な内容となる。
紹介システムで撮った写真を挟みながら進めていくが、
途中で、適宜カメラとレンズのシステムを交替していく。
![_c0032138_14583739.jpg]()
だけ続ける。HOLGAが日本国内市場に、どのように
浸透して来たか、という話だ。
銀塩末期の1990年代後半には、大規模な「第一次中古
(銀塩)カメラブーム」が起こった事は、ご存知の通り
だろう。
そのブームは、末期には投機的な要素が加わっていき
(つまり、希少なカメラを高価に取引している状態)
純粋なマニア層が興味を失ってしまった事、そして
続く2000年代前半からのデジタル時代の到来において
「今更フィルムで撮るなど・・」という風潮が出て
きた為、まもなく中古カメラブームは終焉を迎えた。
![_c0032138_14583755.jpg]()
「女子カメラブーム」である。
これは「Lo-Fi」という思想や文化に密接に関連する。
ただし、このブームは女性だけのものではなく、
正確に言えば、「アート層」「写真学生」といった
ユーザー層も連動して、このブームに乗っていた。
まず「アート層」とは何か?と言えば・・
彼らは、”写真を単なる「映像記録」とは見なさず、
「映像表現」あるいは「映像コミュニケーションツール」
と見なす層”と定義しておく。
つまり、それまでの銀塩時代(1990年代頃まで)の
マニア層や写真中級層では、いずれも写真を撮る上で
「高性能な撮影機材を用いて、高画質な写真を撮る」
(≒「Hi-Fi」思想、あるいは「映像記録」)という
考え方が、ほぼ100%であった訳だ。
・・だが、それも度を越すと、数十万円もする高額な
カメラやレンズを買い、そして、誰も行った事が無い
秘境や絶景を求めて、日本中、いや、世界中に被写体
探しの旅に出る事になってしまう。
つまり、「Hi-Fi思想」は、それが行き過ぎると、
「お金と時間が無いと出来ない趣味」となってしまう。
勿論、世の中の大半の人達は、そんな恵まれた環境
には身を置いていない。したがって、そうした志向に
対して「ブルジョワ的だ」「老人の趣味だ」「道楽だ」
「成金趣味だ」等と反発する層が必ず現れる。
まあでも、そう言う人達も、もし、お金と時間を手に
する機会があれば、いつかは、まだ見ぬ世界各国の
奥地や情景を、のんびり撮影して廻りたいのだ・・
とも思っているケースは多いだろう。
まあつまり、反発心は、殆どの場合、妬み等の感情から
来るものだ。
![_c0032138_14584135.jpg]()
やレンズの技術的進歩(AE/AF化、高性能レンズの出現)
と、それにも増してフィルムの進化により、誰でも
Hi-Fi写真を撮る事は、さほど難しくなくなっていた。
加えて、当時は「第一次中古カメラブーム」でもあった、
後期のそれは、投機的観点から希少品が高価に取引される
陳腐な市場となってしまったが、まあでも全般的に見れば
普通の中古機材(カメラ、レンズ)が安価に販売されて
いる状況であり、マニアでは無い一般層でも、専門中古店に
入り易い環境であったので、安価に撮影機材を入手できた。
(参考:おまけに、APSフィルム登場からの全自動現像機
(QSS等)の普及により、巷では「0円プリント」店が林立し、
現像コストも下げる事が出来た時代でもあった)
すなわち、この時点で、誰にでも「Hi-Fi」撮影環境が
構築出来るようになり、前述の、「Hi-Fiに反発する」
思想は急速に減っていく。
しかし、詳細は後述するが、この時代に誰もが「Hi-Fi
写真」を撮れるようになると、それまで良くあった珍しい
風景等の綺麗な写真は、見慣れた、ありふれた写真として
一般層の興味も、また減っていくようになって行く。
----
では、話の途中だが、ここでHOLGAレンズを交替する。
![_c0032138_14584108.jpg]()
(新品購入価格3,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
こちらも2010年代前半発売。PENTAX Qシステム用
のレンズであり、小さいセンサーサイズに合わせて、
10mmという短い焦点距離で発売されている。
Qシステムでの換算画角は機種によって異なり、
PENTAX Q/Q10(1/2.3型)の場合は55mm相当
PENTAX Q7/Q-S1(1/1.7型)の場合は46mm相当となる。
Qシステムは、トイレンズ系と相性の良い母艦である。
が、こうした電子接点の無いレンズでQ機においては
電子(撮像素子)シャッター動作となり、動体被写体
や手ブレにより、写る被写体形状が歪んでしまうが、
それすらも「Lo-Fi思想」における、「偶然性」とか
「アンコントローラブル(制御不能)」においては
歓迎すべき傾向だ。
Qシステムの内蔵手ブレ補正機能をOFFして、手ブレ
限界シャッター速度ぎりぎりで、ブレるかブレ無いか?
といった偶然性要素を追加する撮影技法は、高難易度
ではあるが、中級層以上には推奨したい技法だ。
![_c0032138_14584103.jpg]()
現代のビギナー層は、現代において画質の悪い(Lo-Fiな)
(デジタル)写真を見ると、「フィルムっぽい写真だ」と
良く言うのだが、実際には、さにあらず・・
この、銀塩末期(2000年前後)の銀塩写真は、非常に
高画質であり、2000年代前半からの初期デジタルカメラ
システムでの画質を軽く上回る程であった。
デジタルカメラは、フィルムを用いないと言う簡便さから、
その後の時代で急速に普及したのだが、2000年代後半頃
までは、頑なにフィルムカメラを使い続ける中上級層も
かなり多かった。それには「デジタルなど安直だ」等の
心理的要因もあるかもしれないが、全てが反発心だとも
言いきれず、良く良く見れば「2000年代前半の初期の
デジタルシステムよりも、銀塩システムの方が高画質で
あった」という”真の理由”も大きかったと思う。
(まあ、メーカーや流通市場は皆、新規デジタルカメラ
を売りたかったし、ユーザー層もまたデジタル機を
入手して喜んでいたから、「本当は銀塩写真の方が綺麗」
という話は、まるで腫れ物に触るように誰もしなかった)
そういう画質の差に敏感に反応する「物凄く目が肥えた」
層も、2000年代後半頃にはデジタルに転換して行く。
何故ならば、その頃にやっと、末期銀塩システムを上回る
高画質化が、デジタルシステムでも実現されたからだ。
目の肥えた中上級層までがデジタル化してしまうと、
もう残念ながら銀塩のビジネスモデルは崩壊だ。
2010年頃には、殆どの地方DPE店等が廃業に追い込まれ、
銀塩カメラや銀塩時代のレンズの中古流通も崩壊し
それらが数千円という二束三文の相場で販売された。
同時に、フィルム自体の価格も大幅に高騰、そして
その現像も、現像所やDPE店を探すのも苦労するし
見つけたとしても、現像代はとても高価だ。
![_c0032138_14584285.jpg]()
まあ、誰もが銀塩Hi-Fi写真を撮れる環境にはなった。
デジタルシステムは、もう、少しづつ発売されている。
デジタル・コンパクト機は既に普及しているが、
ただし、それらは画質面等でまだ銀塩写真には及ばない。
デジタル一眼レフは、この時代では業務専用機であり
数十万円から数百万円と高額だ。2000年には、やっと
一般層向けのCANON EOS D30(デジタル一眼第23回
補足編記事を参照)が発売されたが、依然、35万円
以上と高額であり、性能もたいした事が無かった。
では、この時代において「贅沢にお金と時間をかけて
写真を撮る」という志向性に反発する「アンチHi-Fi」
層は、いったいどうしていたのか?
まあ、自分達も、既にHi-Fi銀塩機材は持っている、
2000年前後の銀塩末期では、銀塩用機材は、高性能
なものであっても、中古市場等で相当に安価になって
いたからだ。(又、デジタル転換準備の為、高性能銀塩
機材を安価に販売する「囲い込み」市場戦略もあった)
そして、この頃からカメラ店等で顧客にサービスする
景品としてのカレンダー(等)の様相が変わって来た。
フィルムやカメラメーカーが制作し供給するカレンダー
等は、高額なHi-Fi機材を数多く売る為の販売促進の
意味もある為、1990年代迄は、綺麗で珍しい風景等の
写真が載っている事が大半であった訳だが・・
2000年前後から「そんな写真は、その場所に行き
さえすれば、オレのカメラでも撮れるよ」と、むしろ
「時間と費用をかけてロケに行ける」という、そちら
の恵まれた(=恵まれすぎて、あり得ない)状況への、
ユーザーからの反発心が出てきてしまった訳だ。
そんな世情を敏感に感じたカレンダー等の制作側でも
この時代から、載せる写真は、可愛い動物や子供とか、
懐かしくのんびりした情景とか、そういった、一般層
でも機会さえあれば撮れるような写真に大幅に転換した。
この時代、DPE店からカレンダーを貰う際にも店主等から
店「カレンダーの写真も最近はずいぶんと変わったね、
今時、もう綺麗な風景等は面白くないしな・・・」
といった話を聞くようになった。
まあ、店主等は、毎日毎日、何十年もDPE業務を続けて
いれば、銀塩末期で写真品質がずいぶんと向上した事は、
誰よりも良くわかっているのだろう。DPEをしにくる
お客さん達の作品が、カレンダー写真と同等の品質や
志向性であれば、そういう写真の載ったカレンダーを
お客さんに進呈しても、まず喜ばれない訳だ。
カレンダーに限らず、写真コンテストや写真雑誌の
写真も同様だ。もう「お金と時間をかけて力ずくで
撮りました」といった、それまでのブルジョワ的な
Hi-Fi写真は、ずいぶんと減っていった。
そして、代わりに台頭した新しいタイプの写真を良く
見れば、それらには何らかの「意味」「意図」「シナリオ」
等が隠れている事に、敏感なユーザー層は気づいた事で
あろう。それらは、簡単に言えば「表現」であり、
「撮影者の意図が介在している写真」なのだ。
それまでの時代の、絶景や秘境の写真は、その被写体や
自然そのものが凄いのであり、撮影者はただ単にそれを
「映像記録」しているだけだ。綺麗な写真を見ても、
いったいその撮影者が、どんな状況で、どんな気持ちで
シャッターを押したかなど、決してわからない。
想像できることは、なんだかロケ隊みたいなチームが
登山でもするようにキャラバンを組んで秘境を目指し、
交替で見張りをして、珍しい風景や光景が現れたら
そら出たぞ、と、カメラを構えてシャッターを押す。
つまりもう完全な「業務写真」であって、そこでは
希少な光景を映像の記録として捉える義務がある訳だ。
そんな状態が多くのユーザー層に想像できてしまうと、
もう、「お金と時間をかけて、放浪の旅に出て、
その場で出くわした情景の写真を好きに撮る」といった、
ある意味、現実逃避的な憧れ、いわば「男のロマン」も、
それが、ちっともロマンになっておらず、むしろ
「厳しい仕事」に思えてしまえば、憧れも何も無い。
![_c0032138_14584794.jpg]()
この時代、それに気づいたユーザー層は多かったと思う。
「オレが、ワタシが、その場所で被写体に対峙して撮った
写真が、表現なのだ、アートなのだ。その気持ちを写真
に込めて、多くの人達に提供し、共感や評価を得たい」
そう、長々と説明してきたが、これが「アート層」と
定義する思想の根幹だ。
---
では、話の途中だが、3本目のHOLGAレンズシステム。
![_c0032138_14584730.jpg]()
(新品購入価格 3,000円)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
他のHOLGA LENSと同様に2010年代前半の発売。
それまで先行して発売されていた(デジタル)一眼レフ
用のHOLGA LENSが、60mmの焦点距離であり、フルサイズ
機を使わなければ90mm相当の望遠画角で、HOLGAらしく
無く(注:銀塩HOLGAカメラは1対1縦横比で、その
換算対角線焦点距離は、およそ32mm相当の準広角だ)
かつ、最初期のHOLGAレンズが、APS-Cデジタル機では
特徴的な周辺減光が得られなかった課題を、特殊な
BC(ブラックコーナー)機構を追加して解決すると、
ますますフルサイズ機でもAPS-C機でも、画面中央部
の望遠域相当の画角しか得られなかった為、そういう
ユーザー側の不満を解消する為、本ミラーレス機用
HOLGA LENSでは、25mmの焦点距離となった。
これでNEX等のミラーレス機では、約37mm相当の
準広角画角となって、銀塩HOLGAカメラを使う感覚に
やや近くなる。(注:スクエアフォーマットでは
無いので、やはりHOLGAカメラとは感覚が異なる。
で、ミラーレス機では1対1アスペクトへ変更できた
としても、画面周辺のヴィネッティング(周辺減光)
の雰囲気が変わってしまうので、1対1アスペクトで
使う意味が殆ど無い)
なお、本レンズの型番(W)は、白塗装の意味であり、
この頃から「デジタル機でも気軽なトイレンズと
して使える」というコンセプトとなってきたのだろう。
なお、そういう意味もあり、全てのHOLGA LENSの
新品定価は、3,000円(+税)と安価である。
ただ、前述の4/3機用等のLENSは、後年(2010年代後半)
には母艦が無い(フォーサーズシステムが終焉している)
事から、新品在庫処分で、1,000円前後と安価に
入手できている。
![_c0032138_14584724.jpg]()
「アート層」の定義は前述の通りである。
なお、アート層が2000年前後に発生した訳では無く、
もちろん、さらにそれ以前、100年やそれ以上も
前から主に海外などで写真を表現と見なし、アートと
見なす人達はいくらでも居た。
ただ、日本ではそれは少ない、何故ならば、日本で
カメラ産業が大きく発展した1960年代~1970年代は、
丁度、日本の高度成長期と被る事から、カメラは
日常生活における「ハレの日」(特別な事=冠婚葬祭、
旅行、祭礼、イベント等)における、「映像記録」の
為の道具として発展し、ユーザー層にも、そう捉え
られていた。つまり、戦後において庶民にも文化的、
経済的な余裕が出来てきたので、家族等における映像
をプライベートな範疇で記録していく事が当然、という
時代となった訳だ。
そうした文化の中で発生したカメラファン層(又は
カメラマニア層)は、映像記録をいかに「Hi-Fi」
(つまり、高忠実度)に残すか? という考えしか
持っていなかった訳だ。だから、どんどんと、より
高画質な機材を買い、技能を磨いて、綺麗な写真を
残す事を目標にしてしまう。それが家族や周囲からも
喜ばれたり、尊敬されたり、自己満足度を高める事に
繋がるからだ。
この時代に良く、当時の中級層で言われていた言葉に
「写真とは、”真を写す”と書く」がある。
まあつまり、”見たままを写す事が写真だ”と思って
いて、それを「正統」と見なし、そうで無い写真は
すべて「邪道」と見なした。まあつまり、自分達が
お金をかけ機材に投資し、「カン露出技法」等や
「パンフォーカス」等の初歩的な撮影技法を苦労して
身につけて来た事を否定しない為にも、Hi-Fi写真こそ
が王道である、と思い込まざるを得ない状況だった。
だから、日本国内における「アート層」、つまり
写真を「映像表現」として見なす層は、ここまでの
文化的背景から、あまり比率が多く無く、むしろ
かなりの少数派であった。(というか、1960年代頃
では、アート層は周囲からの圧力で、消されようと
していた。ここも原因は、Hi-Fi写真を進めてきた層は、
「異端」が生じる事を嫌ったからだ。
例えば、アート派の職業写真家層等も、それが出始める
と、同業周囲から酷評され、「宗派替え」を要望される、
という残念な「右へ倣え」思想だったと思われる)
で、その(アート層)の比率が上がってきたのが、
銀塩末期、すなわちデジタルへの転換期であった訳だ。
![_c0032138_14584889.jpg]()
類似している。
ここで「写真学生」とは、「写真を芸術の一環として
学びたいと思っている人達」の総称と定義していて、
写真関連の専門学校、芸術系大学の写真学科等の
本格的な学生層に加え、例えば、市井の写真教室の
生徒であるとか、はたまた、そういう教育的な組織に
所属していなかったとしても、真面目に写真表現を
学ぼうとする人達も、全て「写真学生」と呼んで
差し支え無いであろう。
ただし、一般的な写真サークルのような同好会は
「写真学生」とは見なせない場合も多い。
何故ならば、そうした同好会の一部では、前述の
高度成長期での「Hi-Fi」志向が極めて強い人達が
仕切っているケースがとても多い(大半だ)からだ。
その状況では、皆で三脚を並べ、高額機材の品評会
のような雰囲気で、同じ被写体を狙うような状態に
なってしまい、「映像表現」とかとは縁遠い世界だ。
で、2000年代前半、デジタルへの転換期を迎えると
同時に「アート層」(含む「写真学生」)や、前述の
「女子カメラ層」は、2つの意味でデジタル化に反発
していた。
それはまず、これまで述べて来たように、銀塩末期で
一般的であった、ただ綺麗なだけの「Hi-Fi」写真では、
「映像表現」「自己表現」「個性の提示」等が全く
出来ない事への不満と反発心である。
もう1つは、ともかく初期のデジタルカメラシステムは
高価であった事だ。この時代で、デジタル一眼レフと
その交換レンズ群を新たに揃えようとしたら、軽く
数十万円の予算が必要となる。
純粋な「写真学生」(収入が無い)という人達では、
その出費はかなり厳しい。
これらの考え方を纏めれば、アート層や女子カメラ層に
おいては、
「お金(や時間)をかけて、ただ綺麗なだけの写真を
撮るのはブルジョア的なやり方だ。しかもそうした
Hi-Fi(綺麗)な写真は表現でもアートでも何でも無い。
だから、我々は、お金をかけずとも、感性や才能で
個性的なアートとしての写真を撮るのだ!」
という志向性が、物凄く強く現れた時代である。
この考え方であれば、写真の画質はどうでも良い、
いや、むしろ、ブルジョアなHi-Fi写真に反発して
いるのであるから、できるだけ低画質「Lo-Fi」な
写真の方が、映像的に主張や個性を込め易い訳だ。
![_c0032138_14585745.jpg]()
層は、チープ(安価)だが個性的な写真を撮れる機材を
探し始めた。
そこに存在していたLo-Fi機材は、概ね2種類である。
それが「HOLGA(カメラ)」と「LOMO」(旧ソ連製)
である。
まあ、これらに限らず、この時代は、ありとあらゆる
トイカメラや個性的かつ安価な機材に、アート層は
興味を持ったのだが、入手性や価格の問題とか、
「どれほどにLo-Fi度が得られるか?」といった観点
からすると、数年で、ほぼHOLGAとLOMOが、アート層
や女子カメラ層に対して定着・定番化した訳だ。
そして、このブームはユーザー側だけの範疇に留まらず
これを市場(マーケット)として捉える動きが出て来た。
当初、それらの海外機材は直販(通販)とか、稀に
一部の雑貨店などで入手できる状況であったが、
多数の女性向け写真雑誌等が刊行され、それらに掲載
されている写真の殆どがHOLGAやLOMO等で撮った
Lo-Fi写真であった事から、ニーズが爆発。
これらを「ビジネス」と考える流通や代理店等により
入手しずらいトイカメラが本来の価格(数千円)の
数倍の数万円という価格で販売されるようになると
「これでは、トイカメラを買う方がブルジョアだ!」
と、私は思うようになってしまった。
後年には一部のカメラ店や量販店でも、こうしたLo-Fi
機材を置くようになったので、価格高騰は止まったが
今度はフィルムや現像代が高価になって、やはり
トイカメラ・システムのブルジョア感は否めなかった。
デジタルカメラ(一眼レフ等)が一般層に普及していく
2000年代後半となると、これらのトイカメラブームも
沈静化していく。他にもSNSの普及も理由としてあると
思われるが、他記事でも書いている内容につき割愛する。
----
では、次は今回ラストのHOLGA LENSシステム
![_c0032138_14585732.jpg]()
(新古購入価格 1,000円)
カメラは、CANON EOS 8000D(APS-C機)
こちらは2010年代初頭(頃)に発売された、初期
(正確には二代目)のHOLGA LENSである。
なお、初代HOLGA LENSはBC機構が搭載されておらず、
周辺減光(ヴィネッティング)の効果が殆ど出ない。
![_c0032138_14585722.jpg]()
始めとするトイカメラや「Lo-Fi」のブームは終息して
しまっていた。
原因は、「デジタルへの移行」「フィルムの入手性の
低下と高騰」「SNS掲載に適さない(銀塩である事と、
作風が安定しない事)」の3つが代表的であろう。
HOLGAも、もう銀塩(HOLGA)カメラの生産を辞めて、
デジタル時代への転換時期を迎えていた。よって
ここで企画開発されたのが「HOLGA LENS」である。
当初は銀塩HOLGAのままのレンズ(在庫部品か?)を
プラスチック製の簡素な鏡筒に入れて、マウントを
デジタル一眼レフ用としたのだが、すぐに前述のBC機構
を追加したバージョンが発売され、さらには、同時期に
普及が始まっていた、ミラーレス機各マウント向けの
製品群も発売する等、なかなかアクティブな市場戦略
を展開していたのが印象的だ。
だが、HOLGAの製品コンセプトは、「安価な製品を
大量に販売する」である。 これは果たして成功して
いたのだろうか? 少なくとも日本国内では、あまり
話題になった(売れていた)とは思えない。
前述の「アート層」が入手していたのかも知れないが
日本国内の多くのユーザー層は、旧来から続く
「Hi-Fi」志向である、なかなか「Lo-Fi」なるものの
付加価値(ここではユーザーから見た魅力という意味)
は感じ難いかも知れない。
![_c0032138_14585784.jpg]()
良くわからない、詳しい情報が無いからである。
しかし、1990年代前半に設立された「Lomograhy社」
(オーストリア)が「Lomography 10 Golden Rule」
(著名な「ロモグラフィー宣言」と、ほぼ同じ内容)
を世界中に発信し、こうした「Lo-Fi思想」は、日本
よりも、むしろ海外の方が一般的であったと思うので、
海外ではHOLGA LENSも売れていたのかも知れない。
まあ、日本国内のユーザー層では、新型カメラや中古
カメラも身近な存在であるが、海外市場においては、
日本製カメラ(やレンズ)は、ブランド品であり、
「憧れの高級品」な訳だ。これは昔(1960年代頃)の
日本のカメラファン層が、(西)ドイツ製の高価な
カメラに憧れていた事と同様な心理であろう。
だとすると、必ずそこには「アンチ」の心理が働く、
ここまでの話の前半部でも書いたように、デジタル
移行期において、新規デジタルカメラが高価すぎた
為に、それを「ブルジョアだ」と反発した事が
トイカメラブームの発端であった理由と同様である。
海外での「アンチ日本製カメラ層」においては、
”トイカメラ”とか、”新鋭中国製格安レンズ”
とかは、意外に人気商品なのかも知れない訳だ。
それに、そもそも、「アート」に関する外国人の
感性や感覚は、日本人とはケタ違いに高い。
日本人では、そういう分野の思想や感覚は持ち難い
かも知れない訳だ。
![_c0032138_14590022.jpg]()
「Lo-Fi思想」とは、一過性のブームのようなもの
では無い。
写真が「芸術」であり「表現」であるとすれば、
そこには無数の「様式」や「個性」が存在する。
絵画での例を見れば、写実派も印象派も現代絵画も
何でも存在するし、それらは、どれが正統だとか、
どれが優れているというものでは無い、いずれもが
表現の為の「様式」である訳だ。
他の芸術分野でも全て同様、音楽でも書道でも
俳句でも工芸でも、すべて様々な様式や個性が
表現者毎にある事は、極めて当たり前の道理だ。
そして、例えばスポーツの分野の「野球」もまた、
直球もあれば変化球もある。別に直球だけで勝負
する事が「潔い」という訳でもあるまい。
・・なのに、何故、日本市場における大半のカメラ
ユーザーは「写実派」や「直球一本勝負」の事しか
考えていないのであろうか?そこが大きく疑問だ。
「Lo-Fi」は、写真の単なる一様式であり、表現形式
でもある、決して「Hi-Fi」に劣るものでも無いし、
「邪道」でも無い。
それを理解していく事が、現代のビギナー層に必要
とされる最重要課題ではなかろうか?
さもないと、写真という分野において、何十年間も
何ら文化的な進歩が得られて無い、という事にも
なってしまう・・
----
では、今回の「HOLGA LENSマニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。
今回は「HOLGA LENSマニアックス」という主旨とし、
同社製の4本のレンズを紹介する。
なお、過去記事「特殊レンズ第3回HOLGA LENS編」と
完全に紹介レンズが被ってしまう為、本記事では
使用する母艦を変更、撮影技法も従前の記事とは
変えて、説明も異なる内容として、重複を避ける。

製の安価なカメラのブランド(シリーズ)銘である。
(注:正確には「Holga」と、先頭のみ大文字表記で
あると思われるが、本記事では便宜上「HOLGA」と
全て大文字で記載する。つまり特定のメーカーだけ、
独自の記載法をしていたらキリが無いし、そもそも
光学界全般では、用語統一等が全く行われていない。
そこで、「メーカー名は全て大文字表記とする。
レンズ名は実機上の記載を基準とする。ただし開放F値
の表記は/fとする」、という風に本ブログでは独自の
標準記載ルールを作り、できるだけそれを守っている)
で、HOLGA(カメラ)だが・・
主に、中国国内のプロレタリアート(労働者階級)
に向けて、「多数のカメラを安価に販売する」事が
企画開発意図であったとは思うが、その後の時代で
世情は大きく変わり(中国での賃金向上、香港返還、
デジタルカメラの登場、その他もろもろ)により、
このHOLGA(120系)カメラは、1990年代後半~
2000年代前半頃では、主に海外に輸出される
ようになった。また、現在においては、ほぼ
生産完了(ディスコン)となっていると思われる。
このHOLGA 120系カメラは、設計における徹底的な
コストダウンの影響での性能不足、及び低い製造品質
により、いわゆる「Lo-Fi描写」(匠の写真用語辞典
第5回記事)が得られる事で著名であり、広義での
「トイカメラ」に属するフィルムカメラであった。
現代でもHOLGA(120系)カメラは、中古品または
新品在庫等で入手できるのだが、銀塩ビジネスの
縮退により、ブローニー(120)判フィルムの入手や
現像、そして、それらのコスト高が非常に厳しい。
(例:フィルムを1本買って撮って現像するだけで、
HOLGAカメラ本体よりも高価になってしまう)
まあ、このあたりの銀塩環境のコスト高が、HOLGA
カメラの生産販売が継続し難くなった理由であろう。
・・で、本記事で紹介する製品は、HOLGA銀塩カメラ
では無く「HOLGA LENS」である。
それが何か?は、記事中で追々説明していくが、
個々のレンズの特徴よりも、「Lo-Fi」という思想を
中心に、歴史的背景等の内容の記事を構成していく。
----
ではまず、今回最初のHOLGAレンズ。

(新古品購入価格 1,000円)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
2010年代前半に発売と思われる単焦点MFトイレンズ。
こちらは一眼レフ用であり、60mmのオリジナルHOLGA
と同じ焦点距離、つまりHOLGA 120系に搭載されていた
プラスチック・レンズを単体発売したものである。
以降、いずれのHOLGA LENSも同様に、2010年代前半
頃の発売で、勿論MF単焦点であるが、焦点距離のみ
対応マウントによりけりで異なっている。
以下、ほとんどの記事内容は、レンズそのものの
話では無く、全般的かつ、歴史的・心理的な内容となる。
紹介システムで撮った写真を挟みながら進めていくが、
途中で、適宜カメラとレンズのシステムを交替していく。

だけ続ける。HOLGAが日本国内市場に、どのように
浸透して来たか、という話だ。
銀塩末期の1990年代後半には、大規模な「第一次中古
(銀塩)カメラブーム」が起こった事は、ご存知の通り
だろう。
そのブームは、末期には投機的な要素が加わっていき
(つまり、希少なカメラを高価に取引している状態)
純粋なマニア層が興味を失ってしまった事、そして
続く2000年代前半からのデジタル時代の到来において
「今更フィルムで撮るなど・・」という風潮が出て
きた為、まもなく中古カメラブームは終焉を迎えた。
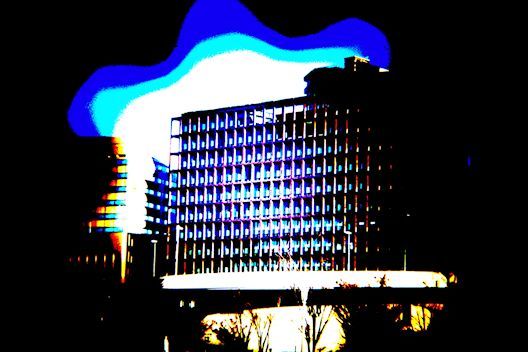
「女子カメラブーム」である。
これは「Lo-Fi」という思想や文化に密接に関連する。
ただし、このブームは女性だけのものではなく、
正確に言えば、「アート層」「写真学生」といった
ユーザー層も連動して、このブームに乗っていた。
まず「アート層」とは何か?と言えば・・
彼らは、”写真を単なる「映像記録」とは見なさず、
「映像表現」あるいは「映像コミュニケーションツール」
と見なす層”と定義しておく。
つまり、それまでの銀塩時代(1990年代頃まで)の
マニア層や写真中級層では、いずれも写真を撮る上で
「高性能な撮影機材を用いて、高画質な写真を撮る」
(≒「Hi-Fi」思想、あるいは「映像記録」)という
考え方が、ほぼ100%であった訳だ。
・・だが、それも度を越すと、数十万円もする高額な
カメラやレンズを買い、そして、誰も行った事が無い
秘境や絶景を求めて、日本中、いや、世界中に被写体
探しの旅に出る事になってしまう。
つまり、「Hi-Fi思想」は、それが行き過ぎると、
「お金と時間が無いと出来ない趣味」となってしまう。
勿論、世の中の大半の人達は、そんな恵まれた環境
には身を置いていない。したがって、そうした志向に
対して「ブルジョワ的だ」「老人の趣味だ」「道楽だ」
「成金趣味だ」等と反発する層が必ず現れる。
まあでも、そう言う人達も、もし、お金と時間を手に
する機会があれば、いつかは、まだ見ぬ世界各国の
奥地や情景を、のんびり撮影して廻りたいのだ・・
とも思っているケースは多いだろう。
まあつまり、反発心は、殆どの場合、妬み等の感情から
来るものだ。

やレンズの技術的進歩(AE/AF化、高性能レンズの出現)
と、それにも増してフィルムの進化により、誰でも
Hi-Fi写真を撮る事は、さほど難しくなくなっていた。
加えて、当時は「第一次中古カメラブーム」でもあった、
後期のそれは、投機的観点から希少品が高価に取引される
陳腐な市場となってしまったが、まあでも全般的に見れば
普通の中古機材(カメラ、レンズ)が安価に販売されて
いる状況であり、マニアでは無い一般層でも、専門中古店に
入り易い環境であったので、安価に撮影機材を入手できた。
(参考:おまけに、APSフィルム登場からの全自動現像機
(QSS等)の普及により、巷では「0円プリント」店が林立し、
現像コストも下げる事が出来た時代でもあった)
すなわち、この時点で、誰にでも「Hi-Fi」撮影環境が
構築出来るようになり、前述の、「Hi-Fiに反発する」
思想は急速に減っていく。
しかし、詳細は後述するが、この時代に誰もが「Hi-Fi
写真」を撮れるようになると、それまで良くあった珍しい
風景等の綺麗な写真は、見慣れた、ありふれた写真として
一般層の興味も、また減っていくようになって行く。
----
では、話の途中だが、ここでHOLGAレンズを交替する。

(新品購入価格3,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
こちらも2010年代前半発売。PENTAX Qシステム用
のレンズであり、小さいセンサーサイズに合わせて、
10mmという短い焦点距離で発売されている。
Qシステムでの換算画角は機種によって異なり、
PENTAX Q/Q10(1/2.3型)の場合は55mm相当
PENTAX Q7/Q-S1(1/1.7型)の場合は46mm相当となる。
Qシステムは、トイレンズ系と相性の良い母艦である。
が、こうした電子接点の無いレンズでQ機においては
電子(撮像素子)シャッター動作となり、動体被写体
や手ブレにより、写る被写体形状が歪んでしまうが、
それすらも「Lo-Fi思想」における、「偶然性」とか
「アンコントローラブル(制御不能)」においては
歓迎すべき傾向だ。
Qシステムの内蔵手ブレ補正機能をOFFして、手ブレ
限界シャッター速度ぎりぎりで、ブレるかブレ無いか?
といった偶然性要素を追加する撮影技法は、高難易度
ではあるが、中級層以上には推奨したい技法だ。

現代のビギナー層は、現代において画質の悪い(Lo-Fiな)
(デジタル)写真を見ると、「フィルムっぽい写真だ」と
良く言うのだが、実際には、さにあらず・・
この、銀塩末期(2000年前後)の銀塩写真は、非常に
高画質であり、2000年代前半からの初期デジタルカメラ
システムでの画質を軽く上回る程であった。
デジタルカメラは、フィルムを用いないと言う簡便さから、
その後の時代で急速に普及したのだが、2000年代後半頃
までは、頑なにフィルムカメラを使い続ける中上級層も
かなり多かった。それには「デジタルなど安直だ」等の
心理的要因もあるかもしれないが、全てが反発心だとも
言いきれず、良く良く見れば「2000年代前半の初期の
デジタルシステムよりも、銀塩システムの方が高画質で
あった」という”真の理由”も大きかったと思う。
(まあ、メーカーや流通市場は皆、新規デジタルカメラ
を売りたかったし、ユーザー層もまたデジタル機を
入手して喜んでいたから、「本当は銀塩写真の方が綺麗」
という話は、まるで腫れ物に触るように誰もしなかった)
そういう画質の差に敏感に反応する「物凄く目が肥えた」
層も、2000年代後半頃にはデジタルに転換して行く。
何故ならば、その頃にやっと、末期銀塩システムを上回る
高画質化が、デジタルシステムでも実現されたからだ。
目の肥えた中上級層までがデジタル化してしまうと、
もう残念ながら銀塩のビジネスモデルは崩壊だ。
2010年頃には、殆どの地方DPE店等が廃業に追い込まれ、
銀塩カメラや銀塩時代のレンズの中古流通も崩壊し
それらが数千円という二束三文の相場で販売された。
同時に、フィルム自体の価格も大幅に高騰、そして
その現像も、現像所やDPE店を探すのも苦労するし
見つけたとしても、現像代はとても高価だ。

まあ、誰もが銀塩Hi-Fi写真を撮れる環境にはなった。
デジタルシステムは、もう、少しづつ発売されている。
デジタル・コンパクト機は既に普及しているが、
ただし、それらは画質面等でまだ銀塩写真には及ばない。
デジタル一眼レフは、この時代では業務専用機であり
数十万円から数百万円と高額だ。2000年には、やっと
一般層向けのCANON EOS D30(デジタル一眼第23回
補足編記事を参照)が発売されたが、依然、35万円
以上と高額であり、性能もたいした事が無かった。
では、この時代において「贅沢にお金と時間をかけて
写真を撮る」という志向性に反発する「アンチHi-Fi」
層は、いったいどうしていたのか?
まあ、自分達も、既にHi-Fi銀塩機材は持っている、
2000年前後の銀塩末期では、銀塩用機材は、高性能
なものであっても、中古市場等で相当に安価になって
いたからだ。(又、デジタル転換準備の為、高性能銀塩
機材を安価に販売する「囲い込み」市場戦略もあった)
そして、この頃からカメラ店等で顧客にサービスする
景品としてのカレンダー(等)の様相が変わって来た。
フィルムやカメラメーカーが制作し供給するカレンダー
等は、高額なHi-Fi機材を数多く売る為の販売促進の
意味もある為、1990年代迄は、綺麗で珍しい風景等の
写真が載っている事が大半であった訳だが・・
2000年前後から「そんな写真は、その場所に行き
さえすれば、オレのカメラでも撮れるよ」と、むしろ
「時間と費用をかけてロケに行ける」という、そちら
の恵まれた(=恵まれすぎて、あり得ない)状況への、
ユーザーからの反発心が出てきてしまった訳だ。
そんな世情を敏感に感じたカレンダー等の制作側でも
この時代から、載せる写真は、可愛い動物や子供とか、
懐かしくのんびりした情景とか、そういった、一般層
でも機会さえあれば撮れるような写真に大幅に転換した。
この時代、DPE店からカレンダーを貰う際にも店主等から
店「カレンダーの写真も最近はずいぶんと変わったね、
今時、もう綺麗な風景等は面白くないしな・・・」
といった話を聞くようになった。
まあ、店主等は、毎日毎日、何十年もDPE業務を続けて
いれば、銀塩末期で写真品質がずいぶんと向上した事は、
誰よりも良くわかっているのだろう。DPEをしにくる
お客さん達の作品が、カレンダー写真と同等の品質や
志向性であれば、そういう写真の載ったカレンダーを
お客さんに進呈しても、まず喜ばれない訳だ。
カレンダーに限らず、写真コンテストや写真雑誌の
写真も同様だ。もう「お金と時間をかけて力ずくで
撮りました」といった、それまでのブルジョワ的な
Hi-Fi写真は、ずいぶんと減っていった。
そして、代わりに台頭した新しいタイプの写真を良く
見れば、それらには何らかの「意味」「意図」「シナリオ」
等が隠れている事に、敏感なユーザー層は気づいた事で
あろう。それらは、簡単に言えば「表現」であり、
「撮影者の意図が介在している写真」なのだ。
それまでの時代の、絶景や秘境の写真は、その被写体や
自然そのものが凄いのであり、撮影者はただ単にそれを
「映像記録」しているだけだ。綺麗な写真を見ても、
いったいその撮影者が、どんな状況で、どんな気持ちで
シャッターを押したかなど、決してわからない。
想像できることは、なんだかロケ隊みたいなチームが
登山でもするようにキャラバンを組んで秘境を目指し、
交替で見張りをして、珍しい風景や光景が現れたら
そら出たぞ、と、カメラを構えてシャッターを押す。
つまりもう完全な「業務写真」であって、そこでは
希少な光景を映像の記録として捉える義務がある訳だ。
そんな状態が多くのユーザー層に想像できてしまうと、
もう、「お金と時間をかけて、放浪の旅に出て、
その場で出くわした情景の写真を好きに撮る」といった、
ある意味、現実逃避的な憧れ、いわば「男のロマン」も、
それが、ちっともロマンになっておらず、むしろ
「厳しい仕事」に思えてしまえば、憧れも何も無い。

この時代、それに気づいたユーザー層は多かったと思う。
「オレが、ワタシが、その場所で被写体に対峙して撮った
写真が、表現なのだ、アートなのだ。その気持ちを写真
に込めて、多くの人達に提供し、共感や評価を得たい」
そう、長々と説明してきたが、これが「アート層」と
定義する思想の根幹だ。
---
では、話の途中だが、3本目のHOLGAレンズシステム。

(新品購入価格 3,000円)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
他のHOLGA LENSと同様に2010年代前半の発売。
それまで先行して発売されていた(デジタル)一眼レフ
用のHOLGA LENSが、60mmの焦点距離であり、フルサイズ
機を使わなければ90mm相当の望遠画角で、HOLGAらしく
無く(注:銀塩HOLGAカメラは1対1縦横比で、その
換算対角線焦点距離は、およそ32mm相当の準広角だ)
かつ、最初期のHOLGAレンズが、APS-Cデジタル機では
特徴的な周辺減光が得られなかった課題を、特殊な
BC(ブラックコーナー)機構を追加して解決すると、
ますますフルサイズ機でもAPS-C機でも、画面中央部
の望遠域相当の画角しか得られなかった為、そういう
ユーザー側の不満を解消する為、本ミラーレス機用
HOLGA LENSでは、25mmの焦点距離となった。
これでNEX等のミラーレス機では、約37mm相当の
準広角画角となって、銀塩HOLGAカメラを使う感覚に
やや近くなる。(注:スクエアフォーマットでは
無いので、やはりHOLGAカメラとは感覚が異なる。
で、ミラーレス機では1対1アスペクトへ変更できた
としても、画面周辺のヴィネッティング(周辺減光)
の雰囲気が変わってしまうので、1対1アスペクトで
使う意味が殆ど無い)
なお、本レンズの型番(W)は、白塗装の意味であり、
この頃から「デジタル機でも気軽なトイレンズと
して使える」というコンセプトとなってきたのだろう。
なお、そういう意味もあり、全てのHOLGA LENSの
新品定価は、3,000円(+税)と安価である。
ただ、前述の4/3機用等のLENSは、後年(2010年代後半)
には母艦が無い(フォーサーズシステムが終焉している)
事から、新品在庫処分で、1,000円前後と安価に
入手できている。
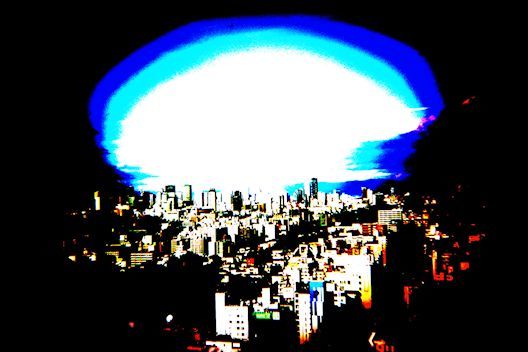
「アート層」の定義は前述の通りである。
なお、アート層が2000年前後に発生した訳では無く、
もちろん、さらにそれ以前、100年やそれ以上も
前から主に海外などで写真を表現と見なし、アートと
見なす人達はいくらでも居た。
ただ、日本ではそれは少ない、何故ならば、日本で
カメラ産業が大きく発展した1960年代~1970年代は、
丁度、日本の高度成長期と被る事から、カメラは
日常生活における「ハレの日」(特別な事=冠婚葬祭、
旅行、祭礼、イベント等)における、「映像記録」の
為の道具として発展し、ユーザー層にも、そう捉え
られていた。つまり、戦後において庶民にも文化的、
経済的な余裕が出来てきたので、家族等における映像
をプライベートな範疇で記録していく事が当然、という
時代となった訳だ。
そうした文化の中で発生したカメラファン層(又は
カメラマニア層)は、映像記録をいかに「Hi-Fi」
(つまり、高忠実度)に残すか? という考えしか
持っていなかった訳だ。だから、どんどんと、より
高画質な機材を買い、技能を磨いて、綺麗な写真を
残す事を目標にしてしまう。それが家族や周囲からも
喜ばれたり、尊敬されたり、自己満足度を高める事に
繋がるからだ。
この時代に良く、当時の中級層で言われていた言葉に
「写真とは、”真を写す”と書く」がある。
まあつまり、”見たままを写す事が写真だ”と思って
いて、それを「正統」と見なし、そうで無い写真は
すべて「邪道」と見なした。まあつまり、自分達が
お金をかけ機材に投資し、「カン露出技法」等や
「パンフォーカス」等の初歩的な撮影技法を苦労して
身につけて来た事を否定しない為にも、Hi-Fi写真こそ
が王道である、と思い込まざるを得ない状況だった。
だから、日本国内における「アート層」、つまり
写真を「映像表現」として見なす層は、ここまでの
文化的背景から、あまり比率が多く無く、むしろ
かなりの少数派であった。(というか、1960年代頃
では、アート層は周囲からの圧力で、消されようと
していた。ここも原因は、Hi-Fi写真を進めてきた層は、
「異端」が生じる事を嫌ったからだ。
例えば、アート派の職業写真家層等も、それが出始める
と、同業周囲から酷評され、「宗派替え」を要望される、
という残念な「右へ倣え」思想だったと思われる)
で、その(アート層)の比率が上がってきたのが、
銀塩末期、すなわちデジタルへの転換期であった訳だ。

類似している。
ここで「写真学生」とは、「写真を芸術の一環として
学びたいと思っている人達」の総称と定義していて、
写真関連の専門学校、芸術系大学の写真学科等の
本格的な学生層に加え、例えば、市井の写真教室の
生徒であるとか、はたまた、そういう教育的な組織に
所属していなかったとしても、真面目に写真表現を
学ぼうとする人達も、全て「写真学生」と呼んで
差し支え無いであろう。
ただし、一般的な写真サークルのような同好会は
「写真学生」とは見なせない場合も多い。
何故ならば、そうした同好会の一部では、前述の
高度成長期での「Hi-Fi」志向が極めて強い人達が
仕切っているケースがとても多い(大半だ)からだ。
その状況では、皆で三脚を並べ、高額機材の品評会
のような雰囲気で、同じ被写体を狙うような状態に
なってしまい、「映像表現」とかとは縁遠い世界だ。
で、2000年代前半、デジタルへの転換期を迎えると
同時に「アート層」(含む「写真学生」)や、前述の
「女子カメラ層」は、2つの意味でデジタル化に反発
していた。
それはまず、これまで述べて来たように、銀塩末期で
一般的であった、ただ綺麗なだけの「Hi-Fi」写真では、
「映像表現」「自己表現」「個性の提示」等が全く
出来ない事への不満と反発心である。
もう1つは、ともかく初期のデジタルカメラシステムは
高価であった事だ。この時代で、デジタル一眼レフと
その交換レンズ群を新たに揃えようとしたら、軽く
数十万円の予算が必要となる。
純粋な「写真学生」(収入が無い)という人達では、
その出費はかなり厳しい。
これらの考え方を纏めれば、アート層や女子カメラ層に
おいては、
「お金(や時間)をかけて、ただ綺麗なだけの写真を
撮るのはブルジョア的なやり方だ。しかもそうした
Hi-Fi(綺麗)な写真は表現でもアートでも何でも無い。
だから、我々は、お金をかけずとも、感性や才能で
個性的なアートとしての写真を撮るのだ!」
という志向性が、物凄く強く現れた時代である。
この考え方であれば、写真の画質はどうでも良い、
いや、むしろ、ブルジョアなHi-Fi写真に反発して
いるのであるから、できるだけ低画質「Lo-Fi」な
写真の方が、映像的に主張や個性を込め易い訳だ。

層は、チープ(安価)だが個性的な写真を撮れる機材を
探し始めた。
そこに存在していたLo-Fi機材は、概ね2種類である。
それが「HOLGA(カメラ)」と「LOMO」(旧ソ連製)
である。
まあ、これらに限らず、この時代は、ありとあらゆる
トイカメラや個性的かつ安価な機材に、アート層は
興味を持ったのだが、入手性や価格の問題とか、
「どれほどにLo-Fi度が得られるか?」といった観点
からすると、数年で、ほぼHOLGAとLOMOが、アート層
や女子カメラ層に対して定着・定番化した訳だ。
そして、このブームはユーザー側だけの範疇に留まらず
これを市場(マーケット)として捉える動きが出て来た。
当初、それらの海外機材は直販(通販)とか、稀に
一部の雑貨店などで入手できる状況であったが、
多数の女性向け写真雑誌等が刊行され、それらに掲載
されている写真の殆どがHOLGAやLOMO等で撮った
Lo-Fi写真であった事から、ニーズが爆発。
これらを「ビジネス」と考える流通や代理店等により
入手しずらいトイカメラが本来の価格(数千円)の
数倍の数万円という価格で販売されるようになると
「これでは、トイカメラを買う方がブルジョアだ!」
と、私は思うようになってしまった。
後年には一部のカメラ店や量販店でも、こうしたLo-Fi
機材を置くようになったので、価格高騰は止まったが
今度はフィルムや現像代が高価になって、やはり
トイカメラ・システムのブルジョア感は否めなかった。
デジタルカメラ(一眼レフ等)が一般層に普及していく
2000年代後半となると、これらのトイカメラブームも
沈静化していく。他にもSNSの普及も理由としてあると
思われるが、他記事でも書いている内容につき割愛する。
----
では、次は今回ラストのHOLGA LENSシステム

(新古購入価格 1,000円)
カメラは、CANON EOS 8000D(APS-C機)
こちらは2010年代初頭(頃)に発売された、初期
(正確には二代目)のHOLGA LENSである。
なお、初代HOLGA LENSはBC機構が搭載されておらず、
周辺減光(ヴィネッティング)の効果が殆ど出ない。

始めとするトイカメラや「Lo-Fi」のブームは終息して
しまっていた。
原因は、「デジタルへの移行」「フィルムの入手性の
低下と高騰」「SNS掲載に適さない(銀塩である事と、
作風が安定しない事)」の3つが代表的であろう。
HOLGAも、もう銀塩(HOLGA)カメラの生産を辞めて、
デジタル時代への転換時期を迎えていた。よって
ここで企画開発されたのが「HOLGA LENS」である。
当初は銀塩HOLGAのままのレンズ(在庫部品か?)を
プラスチック製の簡素な鏡筒に入れて、マウントを
デジタル一眼レフ用としたのだが、すぐに前述のBC機構
を追加したバージョンが発売され、さらには、同時期に
普及が始まっていた、ミラーレス機各マウント向けの
製品群も発売する等、なかなかアクティブな市場戦略
を展開していたのが印象的だ。
だが、HOLGAの製品コンセプトは、「安価な製品を
大量に販売する」である。 これは果たして成功して
いたのだろうか? 少なくとも日本国内では、あまり
話題になった(売れていた)とは思えない。
前述の「アート層」が入手していたのかも知れないが
日本国内の多くのユーザー層は、旧来から続く
「Hi-Fi」志向である、なかなか「Lo-Fi」なるものの
付加価値(ここではユーザーから見た魅力という意味)
は感じ難いかも知れない。

良くわからない、詳しい情報が無いからである。
しかし、1990年代前半に設立された「Lomograhy社」
(オーストリア)が「Lomography 10 Golden Rule」
(著名な「ロモグラフィー宣言」と、ほぼ同じ内容)
を世界中に発信し、こうした「Lo-Fi思想」は、日本
よりも、むしろ海外の方が一般的であったと思うので、
海外ではHOLGA LENSも売れていたのかも知れない。
まあ、日本国内のユーザー層では、新型カメラや中古
カメラも身近な存在であるが、海外市場においては、
日本製カメラ(やレンズ)は、ブランド品であり、
「憧れの高級品」な訳だ。これは昔(1960年代頃)の
日本のカメラファン層が、(西)ドイツ製の高価な
カメラに憧れていた事と同様な心理であろう。
だとすると、必ずそこには「アンチ」の心理が働く、
ここまでの話の前半部でも書いたように、デジタル
移行期において、新規デジタルカメラが高価すぎた
為に、それを「ブルジョアだ」と反発した事が
トイカメラブームの発端であった理由と同様である。
海外での「アンチ日本製カメラ層」においては、
”トイカメラ”とか、”新鋭中国製格安レンズ”
とかは、意外に人気商品なのかも知れない訳だ。
それに、そもそも、「アート」に関する外国人の
感性や感覚は、日本人とはケタ違いに高い。
日本人では、そういう分野の思想や感覚は持ち難い
かも知れない訳だ。

「Lo-Fi思想」とは、一過性のブームのようなもの
では無い。
写真が「芸術」であり「表現」であるとすれば、
そこには無数の「様式」や「個性」が存在する。
絵画での例を見れば、写実派も印象派も現代絵画も
何でも存在するし、それらは、どれが正統だとか、
どれが優れているというものでは無い、いずれもが
表現の為の「様式」である訳だ。
他の芸術分野でも全て同様、音楽でも書道でも
俳句でも工芸でも、すべて様々な様式や個性が
表現者毎にある事は、極めて当たり前の道理だ。
そして、例えばスポーツの分野の「野球」もまた、
直球もあれば変化球もある。別に直球だけで勝負
する事が「潔い」という訳でもあるまい。
・・なのに、何故、日本市場における大半のカメラ
ユーザーは「写実派」や「直球一本勝負」の事しか
考えていないのであろうか?そこが大きく疑問だ。
「Lo-Fi」は、写真の単なる一様式であり、表現形式
でもある、決して「Hi-Fi」に劣るものでも無いし、
「邪道」でも無い。
それを理解していく事が、現代のビギナー層に必要
とされる最重要課題ではなかろうか?
さもないと、写真という分野において、何十年間も
何ら文化的な進歩が得られて無い、という事にも
なってしまう・・
----
では、今回の「HOLGA LENSマニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。