海外製のレンズを紹介するシリーズ記事。
今回は「中一光学マニアックス」という主旨とし、
同社製の5本のレンズを紹介する。
![_c0032138_06481258.jpg]()
共和国)遼寧(りょうねい)省の瀋陽(しんよう)市
にある光学機器メーカーであり、30数年の歴史を
持つと聞く。
ヨーロッパ向け、OEM (委託生産)一眼レフ用の
交換レンズ「MITAKON」(三竹光学のブランド)が
かつて主軸だったと思われるが、MITAKON銘の
レンズは、あまり(日本)国内流通は、盛んでは
無く、同社が2010年代前半頃から日本市場に参入
した際には「中一光学」のオリジナルブランド銘
となっている。
国内代理店は「焦点工房」が務めるが、通販の他、
現在では、カメラ量販店等でも新品購入が可能だ。
本記事においては、レンズ個々の話は、過去の
紹介記事と重複する為、最小限として、中一光学
に係わる全般的な話を主として行こう。
----
ではまず、今回最初の中一光学レンズ。
![_c0032138_06481269.jpg]()
(新品購入価格 20,000円)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
2014年発売のMF準広角レンズ、フルサイズ対応
製品である。
なお「CREATOR」表記は、レンズ上あるいは同社の
WEB等では全て大文字であり、本記事でもそれに従う。
(他機種、SPEEDMASTAR等でも同様に全て大文字)
![_c0032138_06481250.jpg]()
が一般的だ。稀に、一部では「なかいちこうがく」と
呼ばれるケースもある)は、他の中国メーカーよりも
やや早くの2010年代前半から日本市場に参入していて、
「安価でよく写る、高品質の正統派レンズ」
としての評価が高い。
ただ、2010年代後半からは、他の中国(または
他の海外)レンズメーカーが多数、日本市場に参入
していて、それらの中には、中一光学製のレンズ
よりも安価な製品もあるので、むしろ中一光学は
現代の感覚では「やや高級なレンズ」という印象すら
あるし、中一光学の現代の製品ラインナップも、
(他社の格安レンズとの差別化の為か?)
超大口径F0.95シリーズ等の高付加価値型レンズ
の販売も始めた為、さらに「高級品メーカー」の
イメージが強まっている。
![_c0032138_06481217.jpg]()
国内流通が始まったレンズである。
「CREATOR」というシリーズ名は、正統派のレンズ
群からラインナップされているが、その仕様は、
35mm/F2、85mm/F2、135mm/F2.8と、
銀塩時代からのMF単焦点と同様であり、国内マニア層
等では、これらの仕様のレンズを持っていない事は
まず有りえず、よって、購入し難いレンズ群だ。
だから、CREATORシリーズの購入/ユーザー層の
大半は、価格が安価(新品2万円前後)に魅かれて
購入した初級中級層または初級マニア層であり、
そうしたユーザー層からは、評価スキルの面からも
適切な評価情報は得られ難い為、これらのCREATOR
レンズ群の正当な評価は、無いにも等しい状況だ。
本記事においては、個々のレンズの詳細な評価は
過去記事と重複する為に割愛するが、詳細は抜きに
して、本ブログの過去ランキング系シリーズでの
本CREATOR 35/2の評価順位のみ紹介しておこう。
・ハイコスパレンズBEST40=第34位
・最強35mm選手権B決勝1回戦=第4位
ここでの母集団のレンズ数は320本以上である。
まあつまり、本レンズは、そこそこの上位に
ランクインする優秀なレンズであり、決して
「安かろう、悪かろう」という格安レンズでは無い。
(少ないながらも)5本の中一光学製レンズを
所有している私の感覚では、中一光学のレンズ
設計力は高く、かつ独自性も高い(他社のレンズ
構成などを参考にしたり、コピーする事は殆ど無い)
OEM(製造委託)メーカーとしての長い実績もあり、
まあ、言うならば「中国のコシナ」という感じだ。
![_c0032138_06482851.jpg]()
若干の課題も感じる。具体的には「絞り」の仕様
であり、絞り羽根が粘って動作不良となったケース
が1件(1本)ある事と、レンズの絞り値表記で、
抜けている値があり、論理性に欠ける事である。
描写力だが、どのレンズも、可も無く不可も無し、
悪くは無いのだが、もう一声、パンチが欲しい。
まあ特にCREATORシリーズは、中一光学の中では
廉価版とも言えるし、オーソドックスな味付けだ。
---
では、次のシステム。
![_c0032138_06482829.jpg]()
(新品購入価格 22,000円)
カメラは、FUJIFILM X-T10 (APS-C機)
2014年発売のMF中望遠レンズ、こちらも勿論
フルサイズ対応製品である。
![_c0032138_06482816.jpg]()
独CONTAX(ツァイス)のSonnar 85mm/F2
レンズが伝説的で著名であろう。
その、当時としては極めて高性能なレンズは、
後年に様々なコピー品を生み、著名なところでは、
まず、日本光学 NIKKOR-P 8.5cm(85mm)/F2
(1948年頃~)があるだろう。
そのレンズは1950年頃に、米LIFE誌のフォト・
ジャーナリスト「D.D.ダンカン」氏により
高く評価され、世界的にNIKKORの名前を知らしめる
事となったのは伝説的だ。
ただ、個人的には「誰かが良いと言ったから・・」
と付和雷同するスタンスは好きでは無い。
それに、この話は多分にNIKONにおけるブランド
イメージの構築の為に使われた節も見受けられ、
そういった(販売側からの)一方的な話も、私は
あまり好きでは無い。
で、同時期、第二次大戦の敗戦国ドイツにおいては、
カール・ツァイス(Carl Zeiss)も又、東西に分断
されてしまい、東独側の光学技術は共産圏に流通し
これまた著名な(Sonnar 85/2のコピー品である)
Jupiter-9(ユピテル/ジュピター)をソビエト連邦
において生み出す事となる。
ただし、Jupiter-9は、Sonnar85/2のレンズ構成の
3群5枚から、後年では若干変更された3群7枚程度の
構成が主流だったとは思うが、当時のソビエト連邦
においては、様々な国営工場(注:メーカーという
概念は共産圏には無い)で分散されて製造されて
いた様相もあり、レンズマウントも色々と変化した
為、様々なバージョンが並行して存在していたので、
詳しい内容の確認は困難だ。
で、本レンズCREATOR 85mm/F2も、同様にSonnar
コピーか?と思いきや、レンズ構成は6群6枚と、
Sonnar系とは全く異なる模様だ。
でもまあ、「Sonnarか否か?」という話よりも、
「良く写るのか否か?」という点の方が、遥かに
重要であろう。
と言うのも、本家Sonnarの設計は、現代から
遡る事、90年近くも前の古い時代の話なのだ。
それだけ時代が異なれば、例えば、車が空を
飛んでもおかしく無いくらいの技術的な変遷と
進歩があると思う。
![_c0032138_06482830.jpg]()
あるし、銀塩時代の各社85mm/F2級レンズは、
いずれもゾナー型や、その他の構成での比較的
シンプルな光学系(5枚構成程度)であったから、
本レンズは近代的な設計であり、かつ、それらの
セミ・オールドレンズとの差異を、当然意識して
設計されているだろうから、描写力が高いのも
必然であろう。
ただし、現代的レンズのように、非球面レンズや
異常(特殊)低分散ガラスを使っている訳では無い
為(注:コストダウンの目的だろう)、あくまで
「一般的な設計手法による、僅かな画質優位点」
程度でしか無い。
弱点は絞り機構全般だ、本レンズの絞り環は
クリック・ストップ付きの無段階絞りであるが、
倍数(段数)系列上でのF16の指標が存在しない。
他の中一光学製レンズでも、同様に絞り値の抜け
があったりして、これらは、いずれも電子接点の
無いレンズ故に、絞り値情報がカメラ側に伝達
される事は無く、手指の感触だけでの制御が
主体となるので、レンズによっては抜けている
絞り値があるのは、実用上はともかく、心理的
には「どの絞り値で撮っているかわからず」に
やや不安となる。
また、本レンズは、私の個体では絞り羽根の粘り
が発生してしまい、絞り形状が乱れる場合がある、
絞り開閉を繰り返せば、上手く正常に戻る場合も
あるのだが、それを確認するにはレンズを取り外す
必要があり、実際の撮影中には、その確認は煩雑
すぎて無理だ。
あくまで私の個体での課題かも知れないが、全般に
絞り機構の完成度が低いようにも思えてならない。
![_c0032138_06483362.jpg]()
中級層には推奨できるレンズである。
ただし、本レンズ発売後の2010年代後半位から
他の海外(中国が主)新鋭メーカーが、本レンズ
を下回る価格帯での、低価格レンズを主軸に
多数日本市場に参入してきているので、それらと
の比較を考えると、本レンズCREATOR 85/2も
もはや、安価な類のレンズとは言い難くなって
きている。まあ、他社低価格レンズとの差異と
しては、本レンズや他のCREATOR系レンズは、
一眼レフ用が主体だ。他の新鋭中国製レンズは
ミラーレス機用が主体なので、そこでの住み分け
がユーザーから見た大きな差異となる。
特に、本CREATORシリーズをNIKON Fマウント版で
買っておけば、他の、およそ全てのミラーレス機
でも利用できるため、汎用性が極めて高い。
----
さて、3本目のシステム。
![_c0032138_06483469.jpg]()
(中古購入価格 14,000円)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
2016年に発売された、フルサイズ対応MF単焦点
望遠レンズ。
型番はⅡ型だが、旧製品が流通していた記憶は無く
場合により、本Ⅱ型からの国内流通かも知れない。
![_c0032138_06483411.jpg]()
6群6枚構成なのだが、1枚のED(特殊低分散
ガラス)レンズを含んでいる。
すなわち、その手のレンズを使うという事は、
色収差を始め、望遠レンズにおいて発生しやすい
諸収差の低減を設計コンセプトとしているレンズ
であろう。
だから、135mm/F2.8と言っても、銀塩MF時代の
1970年代頃の同等スペックの単焦点レンズとは、
ずいぶんと特性も異なっている。
ちなみに、銀塩MF135/2.8級レンズは、その後
1980年代後半頃から以降のAF時代において、
ズームレンズの普及から、自然消滅してしまった。
なので、2000年代からのデジタル時代においては
MF135/2.8hは、もう数十年も前の時代の古い
レンズでしか無く、不人気であり、中古品等を
見かけた場合において、たとえ程度が、ある程度
良くてもジャンク品相当の二束三文の低価格相場で
しか無い。
だから、現代の初級マニア層等においては、
初「何? 135mm/F2.8の単焦点MFレンズ??
そんなのは安物であろう?良く写る筈が無い」
と、一笑に付してしまうだけであろう。
だが、本CREATOR 135/2.8Ⅱは、銀塩時代の同等
スペックレンズとは別物である。
まあ確かに1970年代のMF135/2.8では、EDレンズ
などを搭載しているレンズは無かった。
EDレンズの1枚追加くらいでは、劇的な性能改善は
無いとも言えるのだが・・ それでも40年の
時代の差は大きい。
![_c0032138_06483496.jpg]()
2017年~2019年あたりに、他の中国製メーカー
の新鋭格安レンズが多数、日本市場に参入している。
よって、本レンズや他のCREATORシリーズレンズで
あっても「最も安価に買える高性能レンズ」では
無くなってしまった。
「価格メリット」が低減した事に対する、私の
対応であるが、前記CREATOR 35/2とCREATOR 85/2
は新品購入したのだが、本CREATOR 135/2.8Ⅱは
慌てて新品を購入する事は避けて、中古流出を
待つ事とした。中古玉数は、あまり多くは無かった
が、ようやく発売後3年程した2019年頃に、
中古品を発見し、購入に至った次第である。
だがこれでも、他の中国製格安レンズの新品価格
と同等である、コストメリットが感じ難いが、
まあそこは、前述のように、本レンズが一眼レフ用
マウント品である為、ほぼ全てのミラーレス機で
使用できる、という汎用性メリットを重視しよう。
例えば、他の中国製レンズをFUJIFILM Xマウント
のミラーレス機で使いたい場合、Xマウント版を
買うしか方法が無く、かつ、それを買ってしまったら
他のマウント機では、まず使用する事が出来ない。
まあ、FUJI Xマウントシステムは、MFピント精度
の問題点により、MFレンズ母艦とするには多大な
課題があるのだが、その話は本レンズとは無関係で
ある為に割愛する。
![_c0032138_06484059.jpg]()
の追加などの設計努力により悪くは無いが、感動的に
優れているという訳でも無い。
例えば、135mm単焦点として、極めて優秀な、
SIGMA ART135mm/F1.8やSONY ZA135mm/F1.8、
MINOLTA/SONY STF135mm/F2.8[T4.5]等とは
比較にもならず、それらは「格が違う」という
感じである。
別シリーズ「最強135mm選手権」では、その執筆
時点では本レンズの評価が間に合っていなかった
のでノミネートされていないのだが、仮に評価済み
であったとしても、同135mm決勝戦にエントリー
させる事は無かったであろう。
それら決勝戦進出レンズの「描写表現力」個人評価は、
いずれも4.5点~5点(満点)と、超絶的であるが
本CREATOR135/2.8Ⅱの同評価点は3.5点にすぎない。
そして、この状態だと、銀塩時代の135mm/F2.8
級(概ね描写表現力評価が2.5点~3点)と大差が
ある訳でもなく、それら銀塩MF135/2.8が、
だいたい1000円~3000円の二束三文の中古相場
である事もあいまって、なかなかコスパ的には
厳しい状態だ。
まあ実は、その点は本レンズ購入前から事前検討
していた訳であり、「新品購入だとコスパが悪い」
から、中古を待っていた訳である。
ただ、中古14000円でも、まだ微妙に高価に感じる。
性能あるいはコスパ面から考えると、中古1万円
程度が、本レンズでの妥当な相場であろうか?
まあ、その価格帯で入手できるのであれば、
悪く無いレンズであると思われる。
それと、絞り環とか、ピントリングの回転角が
本レンズでも、感覚的にやや違和感を感じる、
ここは他の中一光学製レンズでも同様であり、
MFで使う(MFでしか使えない)上で、ちょっとだけ
操作性上の課題を感じてしまう点が、やや問題だが、
ここは重欠点とは言えないであろう。
----
さて、4本目のシステム。
![_c0032138_06484066.jpg]()
(新品購入価格 23,000円)(以下、FW20/2)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
2017年に発売されたMF超マクロレンズ。
FREEWALKERシリーズは、同社のレンズ群の中で、
やや特殊なスペックの商品群の名称だと思われる。
「超」マクロとは、本レンズの撮影倍率が
4~4.5倍(注:フルサイズ時)に達する事から、
個人的には、そう呼んでいる。
(匠の写真用語辞典第3回記事での定義参照)
ただし、本レンズは中遠距離撮影をする事は出来ず、
近接撮影専用である他、ピントリング(ヘリコイド)
すら持たない。
![_c0032138_06484025.jpg]()
本レンズは、1970年代頃に日本のOLYMPUS社が
開発した、銀塩OM-SYSTEMの医療用特殊マクロ
(OM20mm/F2)の完全コピー品(ただし、マウント
はNIKON Fを始め、いくつかの現代機用のマウント
となっている)であるからだ。
そのOM20/2は、ベローズ(延長用鏡筒)を併用
する事でピント調節を可能とする他、最大撮影倍率
が、およそ13倍(フルサイズ時)にも達するという、
まあ、いわゆる「簡易顕微鏡」であった訳だ。
(当時は、デジタル顕微鏡がある訳でも無く、医療
における検体等では、写真による撮影が主流だ)
しかし、本FW20/2用には、ベローズは発売されて
おらず、この為、本レンズではピント合わせの
目的には、レンズを装着したカメラを前後させて
被写体距離にピントを合わせるしかない。
そのピント距離(≒WD)は、数mm程度しか無い為
一般的な屋外手持ち撮影は大変困難であり、私の
場合で、成功率は1%以下、つまり100枚撮っても
1枚以下程度しかピントが合ったカットは得られ
ないし、ピントが合ったとしても、コンマ数mmと
思われる極薄の被写界深度の為、立体被写体では
画面上の、ごく一部のピンポイントにしかピントが
合わず、なんだか良くわからない写真になってしまう。
![_c0032138_06484007.jpg]()
訳であり、本レンズは、一般的には、カメラごと
何かの台座や三脚等に固定し、室内での静止&平面的
被写体を、一定距離で撮る事しか出来ないであろう。
よって、勿論、ユーザーレビューでも、そんな作例しか
有りえない。
さらに屋外撮影を困難にする原因として「露光倍数」
(又は露出倍数)と呼ばれる光学的原理により、
(撮影倍率+1)x(撮影倍率+1)の計算式
の分だけ露出が暗くなる事であり、例えF2の明るい
開放F値があっても、一般撮影よりも約32倍以上も
シャッター速度が低下し、ISO感度を非常に高める
等の対策を行わない限り、手持ちではブレブレで、
まともに撮る事が出来ない。
すなわち、屋外での手持ち撮影での成功作例は、
相当な「無駄撃ち」が必ず伴っている訳だ。
屋外での「偶然狙い撮影」をしないのであれば、
本レンズの用途は、それこそ、学術とか医療とか
そんな分野での近接「超マクロ」撮影に限られる。
ただし、本レンズの絞り開放での「解像力」は、
簡易的な実測値では、120LP/mm程度しか無い。
これはまあ、銀塩時代の設計を転用した為であり、
フィルムならこの性能で良いが、デジタルでは不足
気味だし、研究や業務用途では、少々厳しい。
絞り込んだ場合の解像力は実測していないが、仮に
解像力が向上したとしても、前述の「露光倍数」の
問題により、相当に強力な照明装置を併用する必要
があるだろう。
まあ、一般的なレンズとは、とても言えないので、
説明は早々に切り上げよう。
ちなみに本FW20/2は、過去記事でも、ちょくちょく
紹介している。他記事では、μ4/3機等に装着し、
最大9倍程度の撮影倍率でも使っているが・・
その状態での、屋外での手持ち撮影は、まさしく
「曲芸」であり、もう完全に非推奨だ。
----
では、次は今回ラストのシステム
![_c0032138_06484651.jpg]()
(新品購入価格 63,000円)(以下、SM35/0.95)
カメラは、SONY α6000 (APS-C機)
2016年発売の超大口径MF標準画角レンズ。
SPEEDMASTARシリーズは、同社のレンズ群の中で、
「大口径レンズ」の商品群の名称だと思われる。
本記事では、本レンズのみAPS-C機以下専用レンズ
となっている。(注:SONY αフルサイズ機で
使用する場合は、APS-C撮影モードに切り替えるが
記録画素数が大幅に減る為、α6000のような
APS-C機で使った方が、フル画素で撮れて簡便だ)
従前の初期型(Ⅰ型/MITAKON銘)に対して、
本Ⅱ型は小型軽量化を実現している。
ただし、前述の「CREATOR 135/2.8Ⅱ」と同様に、
初期型発売の時点では中一光学は、まだ日本市場に
未参入だったと思われ、初期型の国内流通は稀だ。
![_c0032138_06484685.jpg]()
超大口径レンズのスペックを聞くと
「さぞかし背景が大きくボケるに違い無い」
と思う事であろう。
しかし、実際にはさほどでは無く、35mmという
やや短い実焦点距離と、(ややボケ難い)APS-C型
センサーのシステムにおいては、一般的な大口径
中望遠レンズ並みか、それ以下のボケ量(被写界深度)
しか得られない。
具体的な被写界深度の計算例を以下に示す
(注;デジタル光学における許容錯乱円の定義は
依然、曖昧なままなので、銀塩時代の35mm判
フィルムの数値 0.03mmを適用する)
*85mm/F1.4レンズ 絞りF1.4開放 撮影距離1m
被写界深度=約1.2cm
*100mm/F2レンズ 絞りF2開放 撮影距離1m
被写界深度=約1.2cm
*本SM35/0.95 絞りF0.95開放 撮影距離1m
被写界深度=約4.7cm
・・となり、撮影距離1mでは、むしろ大口径
中望遠よりも被写界深度はずっと深い(ボケ無い)
F0.95超大口径レンズが真価を発揮するのは、
近接撮影においてであって、例えば本レンズの最短
撮影距離35cmにおいては・・
*本SM35/0.95 絞りF0.95開放 撮影距離35cm
被写界深度=約5.7mm
と、相当に被写界深度が浅くなる。
ただし、近接撮影状態でも、例えば中望遠等倍マクロ
レンズの最短撮影距離での等倍撮影の方が被写界深度
が遥かに浅くなる。
*90mm/F2.8等倍マクロ 絞りF2.8 撮影距離29cm
被写界深度=約1.7mm
はたまた、同じF0.95レンズでも、国産コシナ製
25mm/F0.95等では、最短撮影距離が短く、
必然的に被写界深度も浅い。
(注:μ4/3型センサー機における許容錯乱円定義も
銀塩35mm判フィルムと同等と見なす。
OLYMPUS社ではμ4/3機用に別の数値を提案しているが、
実際の撮影での感覚と、その計算結果は一致しない。
また、OLYMPUS以外の他社では、デジタルカメラでの
許容錯乱円の定義を行っておらず、曖昧なままだ。
ただし、産業用CCTVレンズや同小型センサー等では
センサーサイズに見合った許容錯乱円定義を行って
いる企業もあるが、写真では無いので、ボケが生じる
ケースは少なく、実測も困難なので、その数値が
合っているかどうかの保証は無い)
*μ4/3用25mm/F0.95レンズ 絞りF0.95 撮影距離17cm
被写界深度=約2.6mm
結局、本レンズの場合は、一般的な「大口径中望遠」、
「中望遠等倍マクロ」や「他社F0.95近接レンズ」の
いずれよりも被写界深度を浅く取る事が出来ない。
まあつまり、最短撮影距離が、やや長すぎる点が
ネックとなっている訳だ。
「では、背景がボカせないF0.95レンズなど、
どういう利用価値があるのだ?」
という疑問が沸いてくるだろう。
それについては、やはり、F0.95という圧倒的に
明るい開放F値により、同一照明環境、同一システム
においても「速いシャッター速度が得られる」事が
大きい。つまり英語で言う「Hi-Speed Lens」であり、
例えば暗所でも手ブレし難い、明所では高速シャッター
で被写体の動きを止めて写せる、などである。
また、「被写界深度があまり浅くならない」と前述
したが、それは各タイプのレンズを、いずれも絞り
開放や最短撮影距離での撮影と、極端に撮影条件を
限定した場合の話である。
一般的な「中庸」な撮影条件においては、被写界深度は
他のレンズよりも浅くなり、背景(前景)ボケを得易い
事は確かだ。
具体的には「標準ズームレンズ」と比較した場合、
*標準ズーム 焦点距離35mm 絞りF4 撮影距離80cm
被写界深度=約12.6cm
*本SM35/0.95 絞りF0.95開放 撮影距離80cm
被写界深度=約3cm
という差となる。
![_c0032138_06484688.jpg]()
あまり顕著では無く、ここは重欠点では無い。
ボケ質や被写界深度の微細な調整の為には、頻繁に
絞り環を廻す必要があるが、電子接点の無い本レンズ
では、カメラ本体内に絞り値が表示されない。
よって、絞り環を廻す手指の感触で現在の絞り値を
類推するしか無いのだが、本レンズの絞り環には
クリックストップが無い為、その値がわかりにくい。
また、いくつかのレンズで前述したが、中一光学製
レンズでの「絞り機構」は弱点であり、中間数値の
絞り値が存在しなかったり、絞り込むと絞り羽根の
形状が乱れたり、最悪は絞りが粘って動作不良となる。
本レンズの場合、例えば、絞り環を手指の感覚で
中間位置くらいにまで絞って、「うん、これで
だいたいF5.6くらか?」と、念の為にカメラの
構えを解いてレンズの絞り値を見ると、まだ
F2.8くらいだったりする。
「あれ~? じゃあ、もう少し絞らないと収差低減の
効果や、表現に合った被写界深度が得られないか?」
等となって、なんだか操作性がモタモタと非効率的に
なってしまう。
これの主原因は、絞り環にクリックストップが無い事
では無い。F0.95開放からF2.8あたりまでの絞り環
の回転角が大きすぎて、そこから先は逆に細かすぎる
訳だ。まあつまり、手指の感触での絞り環の回転角の
変化と、実際の絞り値の変動が、あまり感覚的な
連動ができていない。この点は、本レンズに限らず
他の中一光学製レンズの多くで感じる問題点である。
まあつまり「絞り機構」が、まだ全般的に仕様的、
構造的、操作性的に練れていない状況を感じてしまう。
それから、F0.95等の超大口径レンズは、設計上での
大口径化による諸収差の補正がとても困難であり、
一般的には「球面収差」などの発生が抑えきれず、
絞り開放近くではボケボケの甘い描写となってしまう
ケースが多い。(前述のコシナ・フォクトレンダー
ブランドでのF0.95レンズ群等)
ただ、本SM35/0.95の場合は、絞り開放近くでも
そこまで酷くボケボケな写りにはなりにくい。
まあ、その(収差補正の)為に、最短撮影距離を
長めとしているならば、良心的な設計と言えるで
あろうし、あるいは「仕様上の実利よりも画質を
優先した設計思想である」とも言える。
![_c0032138_06484792.jpg]()
なってしまったが、まあ本レンズのような超大口径に
興味があるユーザーであれば、実用上の興味においても
そこ(被写界深度やボケ)に集中するだろうから、
他の仕様や特徴は、ある意味どうでも良いかも知れない。
価格が、やや高価なのが難点だが、中古流通が皆無と
いう訳では無いし、これでも例えばNIKON製の新鋭
F0.95レンズに比べれば、20分の1程度の価格で買える
状況である、欲しければ買うしか無いであろう。
ただまあ、個人的にはフォクトレンダー製F0.95
レンズ群の方が「寄れる」強みがあるので、画質の
課題(収差が大きい)を鑑みても、そちらの方が
好みである。(追記:NOKTON 60mm/F0.95、
2020年、未紹介、は、旧来のF0.95 NOKTON
よりも描写力が大幅に改善されている)
----
では、今回の「中一光学マニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。
今回は「中一光学マニアックス」という主旨とし、
同社製の5本のレンズを紹介する。

共和国)遼寧(りょうねい)省の瀋陽(しんよう)市
にある光学機器メーカーであり、30数年の歴史を
持つと聞く。
ヨーロッパ向け、OEM (委託生産)一眼レフ用の
交換レンズ「MITAKON」(三竹光学のブランド)が
かつて主軸だったと思われるが、MITAKON銘の
レンズは、あまり(日本)国内流通は、盛んでは
無く、同社が2010年代前半頃から日本市場に参入
した際には「中一光学」のオリジナルブランド銘
となっている。
国内代理店は「焦点工房」が務めるが、通販の他、
現在では、カメラ量販店等でも新品購入が可能だ。
本記事においては、レンズ個々の話は、過去の
紹介記事と重複する為、最小限として、中一光学
に係わる全般的な話を主として行こう。
----
ではまず、今回最初の中一光学レンズ。

(新品購入価格 20,000円)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
2014年発売のMF準広角レンズ、フルサイズ対応
製品である。
なお「CREATOR」表記は、レンズ上あるいは同社の
WEB等では全て大文字であり、本記事でもそれに従う。
(他機種、SPEEDMASTAR等でも同様に全て大文字)

が一般的だ。稀に、一部では「なかいちこうがく」と
呼ばれるケースもある)は、他の中国メーカーよりも
やや早くの2010年代前半から日本市場に参入していて、
「安価でよく写る、高品質の正統派レンズ」
としての評価が高い。
ただ、2010年代後半からは、他の中国(または
他の海外)レンズメーカーが多数、日本市場に参入
していて、それらの中には、中一光学製のレンズ
よりも安価な製品もあるので、むしろ中一光学は
現代の感覚では「やや高級なレンズ」という印象すら
あるし、中一光学の現代の製品ラインナップも、
(他社の格安レンズとの差別化の為か?)
超大口径F0.95シリーズ等の高付加価値型レンズ
の販売も始めた為、さらに「高級品メーカー」の
イメージが強まっている。
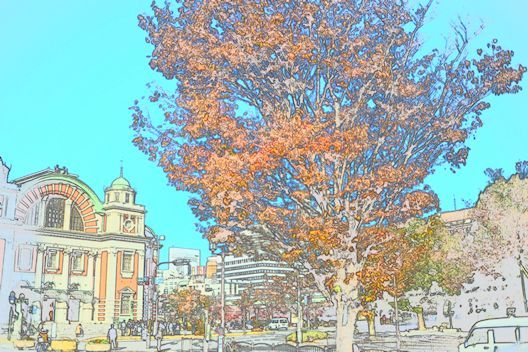
国内流通が始まったレンズである。
「CREATOR」というシリーズ名は、正統派のレンズ
群からラインナップされているが、その仕様は、
35mm/F2、85mm/F2、135mm/F2.8と、
銀塩時代からのMF単焦点と同様であり、国内マニア層
等では、これらの仕様のレンズを持っていない事は
まず有りえず、よって、購入し難いレンズ群だ。
だから、CREATORシリーズの購入/ユーザー層の
大半は、価格が安価(新品2万円前後)に魅かれて
購入した初級中級層または初級マニア層であり、
そうしたユーザー層からは、評価スキルの面からも
適切な評価情報は得られ難い為、これらのCREATOR
レンズ群の正当な評価は、無いにも等しい状況だ。
本記事においては、個々のレンズの詳細な評価は
過去記事と重複する為に割愛するが、詳細は抜きに
して、本ブログの過去ランキング系シリーズでの
本CREATOR 35/2の評価順位のみ紹介しておこう。
・ハイコスパレンズBEST40=第34位
・最強35mm選手権B決勝1回戦=第4位
ここでの母集団のレンズ数は320本以上である。
まあつまり、本レンズは、そこそこの上位に
ランクインする優秀なレンズであり、決して
「安かろう、悪かろう」という格安レンズでは無い。
(少ないながらも)5本の中一光学製レンズを
所有している私の感覚では、中一光学のレンズ
設計力は高く、かつ独自性も高い(他社のレンズ
構成などを参考にしたり、コピーする事は殆ど無い)
OEM(製造委託)メーカーとしての長い実績もあり、
まあ、言うならば「中国のコシナ」という感じだ。

若干の課題も感じる。具体的には「絞り」の仕様
であり、絞り羽根が粘って動作不良となったケース
が1件(1本)ある事と、レンズの絞り値表記で、
抜けている値があり、論理性に欠ける事である。
描写力だが、どのレンズも、可も無く不可も無し、
悪くは無いのだが、もう一声、パンチが欲しい。
まあ特にCREATORシリーズは、中一光学の中では
廉価版とも言えるし、オーソドックスな味付けだ。
---
では、次のシステム。

(新品購入価格 22,000円)
カメラは、FUJIFILM X-T10 (APS-C機)
2014年発売のMF中望遠レンズ、こちらも勿論
フルサイズ対応製品である。

独CONTAX(ツァイス)のSonnar 85mm/F2
レンズが伝説的で著名であろう。
その、当時としては極めて高性能なレンズは、
後年に様々なコピー品を生み、著名なところでは、
まず、日本光学 NIKKOR-P 8.5cm(85mm)/F2
(1948年頃~)があるだろう。
そのレンズは1950年頃に、米LIFE誌のフォト・
ジャーナリスト「D.D.ダンカン」氏により
高く評価され、世界的にNIKKORの名前を知らしめる
事となったのは伝説的だ。
ただ、個人的には「誰かが良いと言ったから・・」
と付和雷同するスタンスは好きでは無い。
それに、この話は多分にNIKONにおけるブランド
イメージの構築の為に使われた節も見受けられ、
そういった(販売側からの)一方的な話も、私は
あまり好きでは無い。
で、同時期、第二次大戦の敗戦国ドイツにおいては、
カール・ツァイス(Carl Zeiss)も又、東西に分断
されてしまい、東独側の光学技術は共産圏に流通し
これまた著名な(Sonnar 85/2のコピー品である)
Jupiter-9(ユピテル/ジュピター)をソビエト連邦
において生み出す事となる。
ただし、Jupiter-9は、Sonnar85/2のレンズ構成の
3群5枚から、後年では若干変更された3群7枚程度の
構成が主流だったとは思うが、当時のソビエト連邦
においては、様々な国営工場(注:メーカーという
概念は共産圏には無い)で分散されて製造されて
いた様相もあり、レンズマウントも色々と変化した
為、様々なバージョンが並行して存在していたので、
詳しい内容の確認は困難だ。
で、本レンズCREATOR 85mm/F2も、同様にSonnar
コピーか?と思いきや、レンズ構成は6群6枚と、
Sonnar系とは全く異なる模様だ。
でもまあ、「Sonnarか否か?」という話よりも、
「良く写るのか否か?」という点の方が、遥かに
重要であろう。
と言うのも、本家Sonnarの設計は、現代から
遡る事、90年近くも前の古い時代の話なのだ。
それだけ時代が異なれば、例えば、車が空を
飛んでもおかしく無いくらいの技術的な変遷と
進歩があると思う。

あるし、銀塩時代の各社85mm/F2級レンズは、
いずれもゾナー型や、その他の構成での比較的
シンプルな光学系(5枚構成程度)であったから、
本レンズは近代的な設計であり、かつ、それらの
セミ・オールドレンズとの差異を、当然意識して
設計されているだろうから、描写力が高いのも
必然であろう。
ただし、現代的レンズのように、非球面レンズや
異常(特殊)低分散ガラスを使っている訳では無い
為(注:コストダウンの目的だろう)、あくまで
「一般的な設計手法による、僅かな画質優位点」
程度でしか無い。
弱点は絞り機構全般だ、本レンズの絞り環は
クリック・ストップ付きの無段階絞りであるが、
倍数(段数)系列上でのF16の指標が存在しない。
他の中一光学製レンズでも、同様に絞り値の抜け
があったりして、これらは、いずれも電子接点の
無いレンズ故に、絞り値情報がカメラ側に伝達
される事は無く、手指の感触だけでの制御が
主体となるので、レンズによっては抜けている
絞り値があるのは、実用上はともかく、心理的
には「どの絞り値で撮っているかわからず」に
やや不安となる。
また、本レンズは、私の個体では絞り羽根の粘り
が発生してしまい、絞り形状が乱れる場合がある、
絞り開閉を繰り返せば、上手く正常に戻る場合も
あるのだが、それを確認するにはレンズを取り外す
必要があり、実際の撮影中には、その確認は煩雑
すぎて無理だ。
あくまで私の個体での課題かも知れないが、全般に
絞り機構の完成度が低いようにも思えてならない。

中級層には推奨できるレンズである。
ただし、本レンズ発売後の2010年代後半位から
他の海外(中国が主)新鋭メーカーが、本レンズ
を下回る価格帯での、低価格レンズを主軸に
多数日本市場に参入してきているので、それらと
の比較を考えると、本レンズCREATOR 85/2も
もはや、安価な類のレンズとは言い難くなって
きている。まあ、他社低価格レンズとの差異と
しては、本レンズや他のCREATOR系レンズは、
一眼レフ用が主体だ。他の新鋭中国製レンズは
ミラーレス機用が主体なので、そこでの住み分け
がユーザーから見た大きな差異となる。
特に、本CREATORシリーズをNIKON Fマウント版で
買っておけば、他の、およそ全てのミラーレス機
でも利用できるため、汎用性が極めて高い。
----
さて、3本目のシステム。

(中古購入価格 14,000円)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
2016年に発売された、フルサイズ対応MF単焦点
望遠レンズ。
型番はⅡ型だが、旧製品が流通していた記憶は無く
場合により、本Ⅱ型からの国内流通かも知れない。

6群6枚構成なのだが、1枚のED(特殊低分散
ガラス)レンズを含んでいる。
すなわち、その手のレンズを使うという事は、
色収差を始め、望遠レンズにおいて発生しやすい
諸収差の低減を設計コンセプトとしているレンズ
であろう。
だから、135mm/F2.8と言っても、銀塩MF時代の
1970年代頃の同等スペックの単焦点レンズとは、
ずいぶんと特性も異なっている。
ちなみに、銀塩MF135/2.8級レンズは、その後
1980年代後半頃から以降のAF時代において、
ズームレンズの普及から、自然消滅してしまった。
なので、2000年代からのデジタル時代においては
MF135/2.8hは、もう数十年も前の時代の古い
レンズでしか無く、不人気であり、中古品等を
見かけた場合において、たとえ程度が、ある程度
良くてもジャンク品相当の二束三文の低価格相場で
しか無い。
だから、現代の初級マニア層等においては、
初「何? 135mm/F2.8の単焦点MFレンズ??
そんなのは安物であろう?良く写る筈が無い」
と、一笑に付してしまうだけであろう。
だが、本CREATOR 135/2.8Ⅱは、銀塩時代の同等
スペックレンズとは別物である。
まあ確かに1970年代のMF135/2.8では、EDレンズ
などを搭載しているレンズは無かった。
EDレンズの1枚追加くらいでは、劇的な性能改善は
無いとも言えるのだが・・ それでも40年の
時代の差は大きい。

2017年~2019年あたりに、他の中国製メーカー
の新鋭格安レンズが多数、日本市場に参入している。
よって、本レンズや他のCREATORシリーズレンズで
あっても「最も安価に買える高性能レンズ」では
無くなってしまった。
「価格メリット」が低減した事に対する、私の
対応であるが、前記CREATOR 35/2とCREATOR 85/2
は新品購入したのだが、本CREATOR 135/2.8Ⅱは
慌てて新品を購入する事は避けて、中古流出を
待つ事とした。中古玉数は、あまり多くは無かった
が、ようやく発売後3年程した2019年頃に、
中古品を発見し、購入に至った次第である。
だがこれでも、他の中国製格安レンズの新品価格
と同等である、コストメリットが感じ難いが、
まあそこは、前述のように、本レンズが一眼レフ用
マウント品である為、ほぼ全てのミラーレス機で
使用できる、という汎用性メリットを重視しよう。
例えば、他の中国製レンズをFUJIFILM Xマウント
のミラーレス機で使いたい場合、Xマウント版を
買うしか方法が無く、かつ、それを買ってしまったら
他のマウント機では、まず使用する事が出来ない。
まあ、FUJI Xマウントシステムは、MFピント精度
の問題点により、MFレンズ母艦とするには多大な
課題があるのだが、その話は本レンズとは無関係で
ある為に割愛する。

の追加などの設計努力により悪くは無いが、感動的に
優れているという訳でも無い。
例えば、135mm単焦点として、極めて優秀な、
SIGMA ART135mm/F1.8やSONY ZA135mm/F1.8、
MINOLTA/SONY STF135mm/F2.8[T4.5]等とは
比較にもならず、それらは「格が違う」という
感じである。
別シリーズ「最強135mm選手権」では、その執筆
時点では本レンズの評価が間に合っていなかった
のでノミネートされていないのだが、仮に評価済み
であったとしても、同135mm決勝戦にエントリー
させる事は無かったであろう。
それら決勝戦進出レンズの「描写表現力」個人評価は、
いずれも4.5点~5点(満点)と、超絶的であるが
本CREATOR135/2.8Ⅱの同評価点は3.5点にすぎない。
そして、この状態だと、銀塩時代の135mm/F2.8
級(概ね描写表現力評価が2.5点~3点)と大差が
ある訳でもなく、それら銀塩MF135/2.8が、
だいたい1000円~3000円の二束三文の中古相場
である事もあいまって、なかなかコスパ的には
厳しい状態だ。
まあ実は、その点は本レンズ購入前から事前検討
していた訳であり、「新品購入だとコスパが悪い」
から、中古を待っていた訳である。
ただ、中古14000円でも、まだ微妙に高価に感じる。
性能あるいはコスパ面から考えると、中古1万円
程度が、本レンズでの妥当な相場であろうか?
まあ、その価格帯で入手できるのであれば、
悪く無いレンズであると思われる。
それと、絞り環とか、ピントリングの回転角が
本レンズでも、感覚的にやや違和感を感じる、
ここは他の中一光学製レンズでも同様であり、
MFで使う(MFでしか使えない)上で、ちょっとだけ
操作性上の課題を感じてしまう点が、やや問題だが、
ここは重欠点とは言えないであろう。
----
さて、4本目のシステム。

(新品購入価格 23,000円)(以下、FW20/2)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
2017年に発売されたMF超マクロレンズ。
FREEWALKERシリーズは、同社のレンズ群の中で、
やや特殊なスペックの商品群の名称だと思われる。
「超」マクロとは、本レンズの撮影倍率が
4~4.5倍(注:フルサイズ時)に達する事から、
個人的には、そう呼んでいる。
(匠の写真用語辞典第3回記事での定義参照)
ただし、本レンズは中遠距離撮影をする事は出来ず、
近接撮影専用である他、ピントリング(ヘリコイド)
すら持たない。

本レンズは、1970年代頃に日本のOLYMPUS社が
開発した、銀塩OM-SYSTEMの医療用特殊マクロ
(OM20mm/F2)の完全コピー品(ただし、マウント
はNIKON Fを始め、いくつかの現代機用のマウント
となっている)であるからだ。
そのOM20/2は、ベローズ(延長用鏡筒)を併用
する事でピント調節を可能とする他、最大撮影倍率
が、およそ13倍(フルサイズ時)にも達するという、
まあ、いわゆる「簡易顕微鏡」であった訳だ。
(当時は、デジタル顕微鏡がある訳でも無く、医療
における検体等では、写真による撮影が主流だ)
しかし、本FW20/2用には、ベローズは発売されて
おらず、この為、本レンズではピント合わせの
目的には、レンズを装着したカメラを前後させて
被写体距離にピントを合わせるしかない。
そのピント距離(≒WD)は、数mm程度しか無い為
一般的な屋外手持ち撮影は大変困難であり、私の
場合で、成功率は1%以下、つまり100枚撮っても
1枚以下程度しかピントが合ったカットは得られ
ないし、ピントが合ったとしても、コンマ数mmと
思われる極薄の被写界深度の為、立体被写体では
画面上の、ごく一部のピンポイントにしかピントが
合わず、なんだか良くわからない写真になってしまう。

訳であり、本レンズは、一般的には、カメラごと
何かの台座や三脚等に固定し、室内での静止&平面的
被写体を、一定距離で撮る事しか出来ないであろう。
よって、勿論、ユーザーレビューでも、そんな作例しか
有りえない。
さらに屋外撮影を困難にする原因として「露光倍数」
(又は露出倍数)と呼ばれる光学的原理により、
(撮影倍率+1)x(撮影倍率+1)の計算式
の分だけ露出が暗くなる事であり、例えF2の明るい
開放F値があっても、一般撮影よりも約32倍以上も
シャッター速度が低下し、ISO感度を非常に高める
等の対策を行わない限り、手持ちではブレブレで、
まともに撮る事が出来ない。
すなわち、屋外での手持ち撮影での成功作例は、
相当な「無駄撃ち」が必ず伴っている訳だ。
屋外での「偶然狙い撮影」をしないのであれば、
本レンズの用途は、それこそ、学術とか医療とか
そんな分野での近接「超マクロ」撮影に限られる。
ただし、本レンズの絞り開放での「解像力」は、
簡易的な実測値では、120LP/mm程度しか無い。
これはまあ、銀塩時代の設計を転用した為であり、
フィルムならこの性能で良いが、デジタルでは不足
気味だし、研究や業務用途では、少々厳しい。
絞り込んだ場合の解像力は実測していないが、仮に
解像力が向上したとしても、前述の「露光倍数」の
問題により、相当に強力な照明装置を併用する必要
があるだろう。
まあ、一般的なレンズとは、とても言えないので、
説明は早々に切り上げよう。
ちなみに本FW20/2は、過去記事でも、ちょくちょく
紹介している。他記事では、μ4/3機等に装着し、
最大9倍程度の撮影倍率でも使っているが・・
その状態での、屋外での手持ち撮影は、まさしく
「曲芸」であり、もう完全に非推奨だ。
----
では、次は今回ラストのシステム

(新品購入価格 63,000円)(以下、SM35/0.95)
カメラは、SONY α6000 (APS-C機)
2016年発売の超大口径MF標準画角レンズ。
SPEEDMASTARシリーズは、同社のレンズ群の中で、
「大口径レンズ」の商品群の名称だと思われる。
本記事では、本レンズのみAPS-C機以下専用レンズ
となっている。(注:SONY αフルサイズ機で
使用する場合は、APS-C撮影モードに切り替えるが
記録画素数が大幅に減る為、α6000のような
APS-C機で使った方が、フル画素で撮れて簡便だ)
従前の初期型(Ⅰ型/MITAKON銘)に対して、
本Ⅱ型は小型軽量化を実現している。
ただし、前述の「CREATOR 135/2.8Ⅱ」と同様に、
初期型発売の時点では中一光学は、まだ日本市場に
未参入だったと思われ、初期型の国内流通は稀だ。

超大口径レンズのスペックを聞くと
「さぞかし背景が大きくボケるに違い無い」
と思う事であろう。
しかし、実際にはさほどでは無く、35mmという
やや短い実焦点距離と、(ややボケ難い)APS-C型
センサーのシステムにおいては、一般的な大口径
中望遠レンズ並みか、それ以下のボケ量(被写界深度)
しか得られない。
具体的な被写界深度の計算例を以下に示す
(注;デジタル光学における許容錯乱円の定義は
依然、曖昧なままなので、銀塩時代の35mm判
フィルムの数値 0.03mmを適用する)
*85mm/F1.4レンズ 絞りF1.4開放 撮影距離1m
被写界深度=約1.2cm
*100mm/F2レンズ 絞りF2開放 撮影距離1m
被写界深度=約1.2cm
*本SM35/0.95 絞りF0.95開放 撮影距離1m
被写界深度=約4.7cm
・・となり、撮影距離1mでは、むしろ大口径
中望遠よりも被写界深度はずっと深い(ボケ無い)
F0.95超大口径レンズが真価を発揮するのは、
近接撮影においてであって、例えば本レンズの最短
撮影距離35cmにおいては・・
*本SM35/0.95 絞りF0.95開放 撮影距離35cm
被写界深度=約5.7mm
と、相当に被写界深度が浅くなる。
ただし、近接撮影状態でも、例えば中望遠等倍マクロ
レンズの最短撮影距離での等倍撮影の方が被写界深度
が遥かに浅くなる。
*90mm/F2.8等倍マクロ 絞りF2.8 撮影距離29cm
被写界深度=約1.7mm
はたまた、同じF0.95レンズでも、国産コシナ製
25mm/F0.95等では、最短撮影距離が短く、
必然的に被写界深度も浅い。
(注:μ4/3型センサー機における許容錯乱円定義も
銀塩35mm判フィルムと同等と見なす。
OLYMPUS社ではμ4/3機用に別の数値を提案しているが、
実際の撮影での感覚と、その計算結果は一致しない。
また、OLYMPUS以外の他社では、デジタルカメラでの
許容錯乱円の定義を行っておらず、曖昧なままだ。
ただし、産業用CCTVレンズや同小型センサー等では
センサーサイズに見合った許容錯乱円定義を行って
いる企業もあるが、写真では無いので、ボケが生じる
ケースは少なく、実測も困難なので、その数値が
合っているかどうかの保証は無い)
*μ4/3用25mm/F0.95レンズ 絞りF0.95 撮影距離17cm
被写界深度=約2.6mm
結局、本レンズの場合は、一般的な「大口径中望遠」、
「中望遠等倍マクロ」や「他社F0.95近接レンズ」の
いずれよりも被写界深度を浅く取る事が出来ない。
まあつまり、最短撮影距離が、やや長すぎる点が
ネックとなっている訳だ。
「では、背景がボカせないF0.95レンズなど、
どういう利用価値があるのだ?」
という疑問が沸いてくるだろう。
それについては、やはり、F0.95という圧倒的に
明るい開放F値により、同一照明環境、同一システム
においても「速いシャッター速度が得られる」事が
大きい。つまり英語で言う「Hi-Speed Lens」であり、
例えば暗所でも手ブレし難い、明所では高速シャッター
で被写体の動きを止めて写せる、などである。
また、「被写界深度があまり浅くならない」と前述
したが、それは各タイプのレンズを、いずれも絞り
開放や最短撮影距離での撮影と、極端に撮影条件を
限定した場合の話である。
一般的な「中庸」な撮影条件においては、被写界深度は
他のレンズよりも浅くなり、背景(前景)ボケを得易い
事は確かだ。
具体的には「標準ズームレンズ」と比較した場合、
*標準ズーム 焦点距離35mm 絞りF4 撮影距離80cm
被写界深度=約12.6cm
*本SM35/0.95 絞りF0.95開放 撮影距離80cm
被写界深度=約3cm
という差となる。

あまり顕著では無く、ここは重欠点では無い。
ボケ質や被写界深度の微細な調整の為には、頻繁に
絞り環を廻す必要があるが、電子接点の無い本レンズ
では、カメラ本体内に絞り値が表示されない。
よって、絞り環を廻す手指の感触で現在の絞り値を
類推するしか無いのだが、本レンズの絞り環には
クリックストップが無い為、その値がわかりにくい。
また、いくつかのレンズで前述したが、中一光学製
レンズでの「絞り機構」は弱点であり、中間数値の
絞り値が存在しなかったり、絞り込むと絞り羽根の
形状が乱れたり、最悪は絞りが粘って動作不良となる。
本レンズの場合、例えば、絞り環を手指の感覚で
中間位置くらいにまで絞って、「うん、これで
だいたいF5.6くらか?」と、念の為にカメラの
構えを解いてレンズの絞り値を見ると、まだ
F2.8くらいだったりする。
「あれ~? じゃあ、もう少し絞らないと収差低減の
効果や、表現に合った被写界深度が得られないか?」
等となって、なんだか操作性がモタモタと非効率的に
なってしまう。
これの主原因は、絞り環にクリックストップが無い事
では無い。F0.95開放からF2.8あたりまでの絞り環
の回転角が大きすぎて、そこから先は逆に細かすぎる
訳だ。まあつまり、手指の感触での絞り環の回転角の
変化と、実際の絞り値の変動が、あまり感覚的な
連動ができていない。この点は、本レンズに限らず
他の中一光学製レンズの多くで感じる問題点である。
まあつまり「絞り機構」が、まだ全般的に仕様的、
構造的、操作性的に練れていない状況を感じてしまう。
それから、F0.95等の超大口径レンズは、設計上での
大口径化による諸収差の補正がとても困難であり、
一般的には「球面収差」などの発生が抑えきれず、
絞り開放近くではボケボケの甘い描写となってしまう
ケースが多い。(前述のコシナ・フォクトレンダー
ブランドでのF0.95レンズ群等)
ただ、本SM35/0.95の場合は、絞り開放近くでも
そこまで酷くボケボケな写りにはなりにくい。
まあ、その(収差補正の)為に、最短撮影距離を
長めとしているならば、良心的な設計と言えるで
あろうし、あるいは「仕様上の実利よりも画質を
優先した設計思想である」とも言える。

なってしまったが、まあ本レンズのような超大口径に
興味があるユーザーであれば、実用上の興味においても
そこ(被写界深度やボケ)に集中するだろうから、
他の仕様や特徴は、ある意味どうでも良いかも知れない。
価格が、やや高価なのが難点だが、中古流通が皆無と
いう訳では無いし、これでも例えばNIKON製の新鋭
F0.95レンズに比べれば、20分の1程度の価格で買える
状況である、欲しければ買うしか無いであろう。
ただまあ、個人的にはフォクトレンダー製F0.95
レンズ群の方が「寄れる」強みがあるので、画質の
課題(収差が大きい)を鑑みても、そちらの方が
好みである。(追記:NOKTON 60mm/F0.95、
2020年、未紹介、は、旧来のF0.95 NOKTON
よりも描写力が大幅に改善されている)
----
では、今回の「中一光学マニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。