本シリーズでは写真用交換レンズ(稀に例外あり)を
価格帯別に数本づつ紹介し、記事の最後にBest Buy
(=最も購入に値するレンズ)を決めている。
今回は、7000円級(価格は全て税込み)編とする。
----
では、早速7000円級レンズ7本の対戦を開始する。
まず、最初のエントリー(参戦)。
![_c0032138_12250676.jpg]()
(中古購入価格 15,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
1980年代後半のAF標準等倍マクロレンズ。
後継レンズとの識別の必要がある場合、中古市場では、
初期型またはⅠ型と称されるか、あるいは無印となる。
![_c0032138_12250619.jpg]()
光学系には、大きな変更は無いか、同一と思われ、
初期型から完成度が極めて高かった名レンズだ。
この結果、過去のランキング系記事においても
ミラーレス名玉編:第4位
ハイコスパ名玉編:優勝
最強50mm選手権:B決勝優勝(総合第6位相当)
と、全てで高順位獲得を実現した名玉である。
本レンズが高描写力を持つものだ、とは、購入時点
(1990年代頃)では、あまり認識していなかった。
しかし、1999年頃、私は、買ったばかりの高価な
MINOLTA α-9とSTF135/2.8を、機嫌良く撮影に
持ち出そうとしていた、ただ、135mmの単焦点
だけで丸1日撮る事には不安があった。
現在でこそ、私は単焦点1本で、その画角に見合う
被写体は探せるし、デジタル時代なので、画角の
自由度も(トリミングやデジタルズーム機能で)
高い状態だが、当時ではスキル的にも機材環境的
にも厳しいので、たいていの場合には、2本以上の
焦点距離の異なるレンズ群を同時に持ち出していた。
そこで、その日も、予備として本AF50/2.8を
持ち出し、標準画角で広く撮りたい時や近接撮影を
したい場合には、適宜レンズを交換して撮っていた。
撮影後、そのまま行きつけのDPE店に寄り、写真を
現像した。すると何枚かの写真が、STF135/2.8
で撮ったのか、本AF50/2.8で撮ったのか、区別が
できない状態になってしまったのだ。
匠「あれ? この写真ってどっちだろう、STF?
50マクロ? 全然わからないや(汗)」
画角の違いは、両者、近接撮影が得意なレンズで
あるから、近距離撮影では、殆ど区別が出来ない。
「その被写体に対して、どっちのレンズを使って
いたか?」は、現在であれば、多分覚えておけたとは
思うが、当時は、そこまで撮影に余裕が無かったので、
そういう点にまで、気を配れる状況でも無かった。
STFが高性能で、ボケ質にも配慮した良く写るレンズ
である事は勿論知っていた。なにせ、本レンズの
約10倍もの高額価格で購入したのだ。
だが・・ レンズ間に値段差ほどの描写力の差が無い
事も、その時点で強く認識した。
私は、それまで、本レンズは1万円台で買ったので、
「安かろう、悪かろう」という認識しか持って
いなかったのであった。
「安価なレンズでも、たまたま撮影条件がハマれば
10倍も高価な高性能レンズ(しかも相手は超名玉STFだ)
に、さしてひけをとらない高描写力を発揮できる!」
という事実は目から鱗が落ちる程であった。
でも、そこから何度も試写を重ねて、ようやく気づいた
点がある。
「これは、AF50/2.8も、それなりに優れるレンズなのだ」
という事実であった。
![_c0032138_12250663.jpg]()
おいても、依然、本レンズは「頼れるレンズ」であり、
実際に、近年の様々なランキング系記事の全てで
高順位をマークしている。
別に初期型である必要は無いが、後年のバージョンも
含め、いずれかのMINOLTA/SONY 50mm/f2.8 MACRO
は、マニア層必携のレンズと言えよう。
----
では、次のシステム。
![_c0032138_12250641.jpg]()
(BCL-0980) (9mm/f8.0 Fisheye)
(新品購入価格 9,000円)(実用価値 約7,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
2014年発売の魚眼型ボディキャップレンズ。
オリンパスではこれをレンズではなく、アクセサリーと
称している。
対角線画角は、およそ140°なので、180°には満たず、
あくまで「魚眼風」レンズだ。
![_c0032138_12252011.jpg]()
事ではなく、「構図の練習をする事」だと思う。
魚眼(風)レンズの場合、画面中心から放射状に
伸びる直線上の被写体は歪まない。また、当然
その線に乗らない被写体直線部は大きく歪む。
だから、例えば海や川等の水平線を歪まないように
写すには正確に画面中心の水平線にそこを合わせる。
これは簡単なようで、非常に難しい。
カメラを構える構えが、各回転軸に対して水平に
なっていなければ、水平線等にうまく合わない。
各回転軸というのは、ロー、ヨー、ピッチの事である。
水準器等を使って三脚撮影時の水平を取ろうとする
シニア層等はとても多いが、上記の各回転軸の事を
理解しているだろうか? いや、それは無理だるう。
こういう回転軸が存在する事は、当たり前の物理
原理ではあるが、工業的な計測や製造分野、あるいは
船舶や航空機、二輪車等の三次元的な動きをする
乗り物の動きを解析する等の、やや専門的な分野に
係わっている状況でないと、日常生活では、これらの
用語や概念は、まず使われない。
たとえば、フライパンで野菜を炒める際に
「ピッチング方向にも十分にフライパンを振って」
などとレシピに書いてある訳でも無い。
ただし、ごく最近では、カメラにおける「5軸手ブレ
補正機能」等の技術説明において、手ブレには様々な
回転軸がある事が、やっと一般層に広まりつつがある。
最初にこれを見たユーザーは、「5軸って何だ?
タテ、ヨコ、ナナメ(?)、あと、どの方角だ?
東西南北? まさかね・・(汗)」といったような、
印象や疑問を持った事であろう。
でも、カタログ等で技術の説明を見ると、ローリングや
ヨーイング、ピッチングなどの図解があって、
「なるほど、こういう方向にも手ブレが起こるのか!」
という事がやっと理解できる。
(注:ただし、実際にそういう軸で手ブレが起こって
いるかどうか?は不明。撮影者にもよりけりであろう。
なんだか、他分野での「菌が居るから除菌しなさい!」
というTV CMと同様で、「回転軸方向にも手ブレを
するから、5軸手ブレ補正機を買いなさい!」と、脅迫
心理を植えつけられてしまっているようにも思える)
さて、三次元的な回転軸を理解できたところで、
魚眼レンズにおいては、これらの三次元的な回転軸を
正確に捉えて(手持ち撮影で)構えないと、自身が
求める構図や描写を得る事ができない。
(注:例え、三脚を立てて、水準器で水平を取っても
無意味である。真上から見た捻り(ヨーイング軸)等
には、水準器は反応しないからだ。あるいは三脚を
立てる高さ(レベル)によっても、描写は変化する。
こういう僅かな、回転軸やレベル、アングルのズレが、
魚眼レンズでは「直線が歪む」という描写の差として、
写真に顕著に現れる訳だ。)
この練習の為には魚眼レンズは最適と言えるのだが、
非常に高度な内容であり、手持ちで回転軸を整える
には高度な技量が要求される。(勿論、前述のように
三脚を使っても、課題が解消される訳では無い)
だけどまあ、安価な魚眼レンズで、この構図練習を
する事は悪く無い。
三次元的な回転軸を理解せずに、平面的な「三分割構図」
やら「S字構図」などの練習をしても、ほとんど意味が
無い、そもそも「どのようにカメラを構えたら良いか?」
という部分の技能習得が、ぽっかりと欠けてしまうからだ。
![_c0032138_12252040.jpg]()
このレンズ、または他の安価な魚眼レンズを購入して
練習する事は悪く無い選択肢だ。
----
では、3本目のシステム。
![_c0032138_12252124.jpg]()
(中古購入価格 16,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
詳細不明、恐らくは1980年代~1990年代位の
MFソフトフォーカス(軟焦点)中望遠レンズ。
(以下、ソフトレンズ)
![_c0032138_12252154.jpg]()
では存在しておらず、LENSBABY、安原製作所、LOMO
等のレンズサードパーティで数機種が発売されているに
過ぎない。
そして銀塩時代でも、さほど数は多く無く、メーカー
純正であれば、MINOLTA,PENTAX,CANON,NIKON
(注:おもしろレンズ工房)で各々1~2機種が存在し、
さらにレンズメーカーでは、KENKO、清原光学、海外
メーカー等から、各々数機種が発売されていたのみで
あった、と記憶している。
いつもソフトレンズの記事で書く事と重複するが、
簡単に書いておこう。
1)これらの光学(的)ソフトレンズの描写傾向は、
ソフトフィルター、ソフトエフェクト(画像処理)、
ソフトレタッチ(画像編集)、そして、その他の手法
(例:保護フィルターに油分を塗る等の特殊技法)の、
いずれの場合とも異なる。
ソフトレンズの真の描写はソフトレンズでしか味わえない。
2)ソフトレンズのピント合わせは大変難しい、
一眼レフの光学ファインダーはもとより、ミラーレス機
の「ピーキング機能」でも反応しない場合が大半だ。
絞り込めば、球面収差が減少し、ピントが合わせやすく
なるのだが、撮影の為に再度絞りを開けると、またピント
が合っている保証が無くなり、堂々巡りになり難しい。
(注:一眼レフで「フォーカスエイド」が効く場合がある)
3)ソフトレンズは希少ではあるが、さほど価値のあるもの
では無く、1万円台を超えてまで高額に入手する必然性は
殆ど無い。
以上である。
いずれの特徴も、本KENKO SOFT 85/2.5 に当てはまる。
無理をしてまで入手するものでは無いが、たまたま安価に
見かけたら、購入してみるのも悪く無い。
参考記事:「特殊レンズ第7回SOFT LENS編」
----
では、4本目のシステム。
![_c0032138_12252610.jpg]()
f3.8-5.6 Aspherical XR [IF] MACRO (A03)
(中古購入価格 17,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)
2001年に発売された、AF高倍率(高ズーム比)レンズ。
本ブログでは、あまり「高倍率ズーム」という
呼び方を推奨していない。
その理由を説明すると長くなるので割愛するが・・
要は、あまり正しい呼び方では無く、かつ、ビギナー
層等に対して効能を誤解させやすい「確信犯的」な
呼称なので、あまり好ましく無いと思っているからだ。
(詳細は、匠の写真用語辞典第3回記事を参照)
まあ、レンズの呼び方の詳細の話は良い。
本記事では、「高倍率ズーム」と呼ぶ事にしよう。
![_c0032138_12252693.jpg]()
については、本レンズが「実用的な高倍率ズーム
としては、初めての製品である」という認識からだ。
勿論、それ以前から高倍率ズームは存在している、
恐らく、最初の製品は、1980年代頃(?)の、
「キノ精密工業 KIRON 28-210mm/F4-5.6」
(レンズマニアックス第13回記事参照)
だったであろうか? だが、当該記事を参照して
もらえればわかるが、そのレンズは様々な意味で
実用性能にまるで達していない。
その後、TAMRONも1990年代初頭から28-200mm
高倍率ズームを開発販売しているが、やはり初期の
ものは実用範囲外であり、購入には値しないもので
あった。だが、TAMRONは、そこで諦める事は無く、
地道に10年間ほど改良を続け、やっと実用レベルに
達した高倍率ズームが、本XR28-200である。
という事で、本XR28-200は、発売年頃には各種の
賞を総なめとした。当然、人気&ヒット商品となる。
「高倍率ズームなんて、まだまだ(の性能)だよ」と
思っていた私でも「どれどれ? そんなに良くなったか?」
と興味が出て、本レンズを中古購入した次第であった。
この商品、および同時期に発売された兄弟レンズの
XR28-300(こちらも所有しているが、望遠域を拡張
した事で、収差補正等の面で描写力的には厳しい)
が市場での「高倍率ズーム」の代表格(筆頭)となり、
TAMRON社への市場からのイメージも、それまでの
「マクロのTAMRON」から、「高倍率ズームのTAMRON」
という認識が広まり、TAMRONはブランドイメージを
拡張および高める事に成功した。
この事実、あるいは功績を持って、本XR28-200は、
「歴史的価値が高いレンズである」という認識を
私は持っている。
本XR28-200の長所は3点、
*これまでに無い小型軽量の高倍率ズームである事
*描写力をさほど低めていない事(実用範囲)
*ズーム全域で49cmの最短撮影距離を確保している事、
これは広角域ではやや不満な性能だが、望遠端に
おいては準マクロレンズ並みの最大撮影倍率1/4倍
の近接性能が得られる。
そして短所はあまり無い、まああえて言えば、解像感や
ボケ質(の破綻頻度)、ズーム焦点距離毎に変動する
諸収差、逆光耐性などがあり、あまり厳密な撮影には
向かない点が弱点であろう。
ただ、そういう風に「ちゃんと撮りたい」ならば、
本格的高性能単焦点やら中望遠マクロレンズを持ち出せば
良いので、本レンズを持ち出すシチュエショーンは、別に
存在する。たとえば散歩撮影とか、小旅行などであり、
レンズ交換も不要で、ほとんどの被写体は本XR28-200
の1本で撮れてしまうのだ。
そういった「用途開発」が容易なレンズである事と、
気軽に使える「エンジョイ度」の高さが、本レンズの
真骨頂であろう。
![_c0032138_12252712.jpg]()
約20年経った現代においても中古流通は豊富である。
見つけたら数千円という安価な相場であろうから、
「初の実用的高倍率ズーム」という歴史的価値の実感を
得たり、性能を研究する為にも、購入は悪く無い選択だ。
----
では、次のシステム。
![_c0032138_12252733.jpg]()
(中古購入価格 8,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
詳細不明、ウクライナ(旧ソ連)のキエフの国営工場
にて製造されたと思われるレンズ。同工場は、現代に
おいては「アルセナール社」(アーセナル社)となり
「光学および電子総合メーカー」(企業)である。
![_c0032138_12253512.jpg]()
現代の視点からは実用性能に満たないものが大半である。
ただ、本レンズの描写力、および近接性能(最短撮影距離
が24cmであり、これはマクロを除く、フルサイズ対応
35mm級レンズ中でトップクラスの性能である)により、
本レンズの個人評価点は、ロシアンの中では抜群に高い。
この結果、過去のランキング系記事においても
ミラーレス名玉編:第17位
最強35mm選手権:決勝進出準優勝
と、いずれも、ロシアンレンズ中では唯一となる
ランクインの快挙を成し遂げている。
弱点は、現代において入手性が極めて低い事である。
1990年代頃には国内でも新品販売されていた模様であり
その頃であれば入手性が低い事は無かっただろうが、
ソビエト崩壊により、ウクライナのアルセナール社も
工場から独立して企業となってしまった訳だから、
もう「国策」で、このような古い時代のレンズを
1990年代においては、作り続ける必要もなくなったので
あろう。
工場在庫品の国内(日本)販売がはけた頃(2000年頃?)
には、もう、すっかり見かけなくなってしまった。
現代においては、こうした希少な「ロシアン」レンズは、
所有者や市場関係者により「過剰な好評価」が成される
場合が多い。
現物を誰も目にした事が無いのだから、誰かが「良い」と
言えば、その他大勢の一般層は、その情報を簡単に信じて
しまう。その結果「あのMIR-24が、どうしても欲しい」
とか言い出してしまう訳だ。
そうなったら、販売側はもう「言い値」であろう。
4万円、あるいは5万円といった、不条理なプレミアム価格
を提示されたとしても、購入側はそれを呑むしかない。
これでは完全に「消費者(ユーザー)の負け」の取引条件
であり、買い物のやり方としては、もっともやっては
いけないケースである事は、様々な記事で説明した通りだ。
![_c0032138_12253517.jpg]()
ので、近年では、本ブログでは、あまりロシアンレンズを
褒めたりはしたく無いとも思っているのだが、これが意外と
難しい。
例えば、良い写りの写真を載せれば
「やっぱ、ロシアンって良く写るんだなあ」となり、
ボケ質破綻とか、フレアやゴーストが出ている写真では
「個性的な写りだ、国産レンズではこうはいかない!」
と、それぞれ都合の良い視点で、勝手に解釈されてしまう
訳なのだ。
ならばもう、ロシアンレンズに限らないが、全ての機材
評価(や購入検討)においては、ユーザー側が各々、
確固たる「価値感覚」をもっていないとならない。
やはり最も重要なのは「コスパ感覚」であろう。
本レンズは、私の購入価格は8,000円だ。実用価値も
それと全く同じ金額で約8,000円と評価している。
それ以上でも、それ以下でも無い、という話だ。
(追記:ごく近年、1本だけ本レンズの中古品を
見かけたが、売価は18,000円程であった。
この価格だと、1990年代のソビエト崩壊後の、ロシア
国営工場からの直輸入の新品と、ほぼ同一価格となる。
だから高いと思うか、安いと思うかは、人それぞれ
だと思うが、私は高価すぎると思うし、他者もそう
思うからか? 当該中古品は、なかなかすぐに売れる
事はなかった模様だ)
----
では、6本目のシステム。
![_c0032138_12253522.jpg]()
(中古購入価格 10,000円)(実用価値 約6,000円)
カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)
2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。
「3G」とは、第三世代、という意味だと思われるが、
第一世代や第二世代の製品は、国内では殆ど流通
していない。まあ「3G」が一般的に入手できる最も
古い時代のTILT(ティルト)型製品であろう。
LENSBABY社は、米国にあり、設立は2004年と新しい。
当初は製品は直販(通販)のみであったと思われるが、
2000年代末位には、国内KENKO TOKINA社が輸入代理店
を務めるようになり、その頃から国内流通が活性化した。
「3G」以降のTILT型の製品数は非常に多いので、詳細は
本記事では割愛するし、個人的にも「後継機でも効能は
殆ど同じ」と見なしていて、光学系が交換方式になった
「LENSBABY MUSE」より新しいTILT型製品は購入していない。
(ただし、後継機になる程、操作性は向上している)
![_c0032138_12253567.jpg]()
光軸を被写体面に対して傾ける事で得られる、独特の
描写効果だ。
TILT機構を用いた「アオリ」技法では、例えば、傾いた
被写体面に同時にピントを当てられる。
昔の修学旅行等の大人数集合写真で、斜めに奥行きが
ある人物群に同時にピントを当てるには、僅かにレンズ
を傾ける、すなわち「アオる」必要がある。
この為、修学旅行等で集合写真を撮る「写真館」等の人が、
蛇腹のついた大判カメラで、蛇腹を微調整してレンズを
傾けていた光景は、目にした事のある人も多いであろう。
また、ナナメに置かれた小物商品(時計や万年筆等)
の全体にピントを当てるにも、同様の「アオリ」が必須だ。
で、ここまでの話は、業務撮影用途等において、
TILT機構レンズを「正しく」使った場合である。
「正しく」とは、TILT機構により傾く光軸を被写体面に
垂直にした場合だ。この場合、傾いた被写体面の全般に
ピントが合う事になる。
しかしながら、TILT機構には「逆アオり」と呼ばれる
技法が存在する、これはあえて被写体面の傾きと光軸
の傾きをずらしてしまう技法だ、これにより、撮影者
に平面的に対峙する被写体であっても、そのごく一部
だけの領域(傾く光軸と直交する領域)のみにピント
を合わせる事が可能となる。
こうした写真は、ミニチュア(模型)を撮ったような
写真に見える事から「ミニチュア効果」という名前で、
近年の多くの(デジタル)一眼レフやミラーレス機の
エフェクト(画像効果)として搭載されている。
で、このピントの合う一部の領域の事を、アート系
(学生)カメラマンの間では「スイートスポット」と
呼ぶ。
アート系写真用語は、「トンネル効果」(注:本来は
重要な物理・電子工学用語)等、他分野からちゃっかり
拝借してくる事が良くあり、個人的には、あまり好ましく
無いと思っている。(アート系ならば、適切な全く新しい
用語を「創造・創出」してもらいたいとも思う)
そして「スイートスポット」も、本来はスポーツ用語
であり、ゴルフのクラブやテニスのラケットで、そこに
ボールが当たると「飛びやすい」という領域(最適な
打球点)の事だ。(これも、ちゃっかり拝借用語だ)
ただまあ、エフェクトでの「ミニチュア効果」は、
横とか縦とかの領域を指定して効果を掛けるのだが、
TILT(機構)レンズの場合は、被写体の三次元性と、
傾く光軸の直交エリアとの合焦の効果は、エフェクトの
場合のような直線的にはならず、本当に、ごく一点
だけに合う場合もあるので、「スイートスポット」の
「スポット」は悪く無い表現だ。(でも、「スイート」
の方がいけない、ピントが合う場所なのだから、そこは
シャープで固いイメージだ、「ハードスポット」とかと
呼んでくれていた方が、ましだったと思う)
で、TILT(レンズ)の技術的原理は、少々ややこしい
ので、ビギナー層とか、アート系初級層では、上手く
コントロールする事は、まず出来ないであろう。
「色々試していたら、たまたまミニチュア風に撮れた」
というケースが、ほぼ100%だと思う。
![_c0032138_18135846.jpg]()
上で、あえて無茶な使用法をしている、具体的には
「スイートスポット」を、わざと作らない、とかだ。
これにより、「アンコントローラブル」(制御不能、
予測不能)な要素を作り出し、「Lo-Fi」写真に必要
な偶然性の要素を意図的に得ようとしている。
(匠の写真用語辞典第5回、項目「Lo-Fi」および
同、用語辞典第21回、項目「アンコントローラブル」)
LENSBABY 3G(または後継型)は、必須のレンズと
いう訳では無いが、使っていて色々と面白いので、
中級層(中級実用派層、中級アート層、中級マニア層)
あたりであれば、入手してみるのは悪く無い。
----
では、今回ラストのシステム。
![_c0032138_18135896.jpg]()
(中古購入価格 11,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
2010年に発売された、APS-C機(α Aマウント)専用
準広角(標準画角)AFエントリーレンズ。
![_c0032138_18135802.jpg]()
価格が安く、コスパが極めて良い。
この為、過去のランキング系記事において
ミラーレス名玉編:第14位
ハイコスパ名玉編:準優勝
最強35mm選手権:優勝
と、全てで高順位を獲得した名玉である。
ただし、課題としては現在、SONY α一眼レフ機
(Aマウント)は、事実上終焉していて、本レンズ
を気軽に使える母艦が無い事である。
今回使用機のSONY α65 (2012年)あたりが適正と
思われるが、そろそろこの機体も仕様老朽化寿命
(持論では発売後10年まで)を迎える時期である。
勿論、α(A)マウントレンズは、多くのミラーレス
機でアダプターで使用できるが、現在、SONYの
ミラーレス機ユーザーの大半はフルサイズ機志向だ、
APS-C型専用の本レンズも勿論フルサイズ機で利用
可能であるが、APS-Cにクロップすると記録画素数が
大幅に減少する事は、初級中級層は嫌がるであろう。
また、電子アダプターで無い場合は、MF操作と
なるが、本レンズのピントリングはトルク感が無く
スカスカなので、撮っていて楽しく無い(というか
MF操作性が落ちてしまう、という実用面での弱点と
なる)
結局、あまりミラーレス機で使用する事は推奨できず、
やはり、旧世代機でも良いからSONY Aマウント機を
使うのが良いであろう。
なお、α77Ⅱ(2014年)あたりであれば、高機能・
高性能なので、なかなか仕様老朽化寿命が来ない
とは思えるのだが、今度は、カメラ側が高価すぎたり
無駄に性能が良すぎる、という「オフサイド状態」は
良く意識して使う必要があるだろう。
(=カメラとレンズからなる「システム」において、
トータルバランスが悪く、「用途開発」や実用性に
悪影響が出る、という意味だ。→上級者向けの概念)
![_c0032138_18135934.jpg]()
特徴であるが、実のところ本レンズも「ジェネリック」
であると思われる。
銀塩時代の1970~1980年代での、MF小口径標準
(50mm/F1.7~F2)レンズ(一部はAF時代やデジタル
時代にまで継続された)は、「完成の域に達していた」
とは、本ブログでの様々な記事で書いた通りである。
例えば、PENTAX SMCT55/1.8、通称「銀のタクマー」
RICOH XR50/2、通称「和製ズミクロン」
CANON EF50/1.8Ⅱ(史上初のエントリーレンズ、
EOSの救世主?)等、全てが初級中級層に「神格化」
された程である。
(詳細は、「最強50mm選手権」シリーズで、数十本
の標準レンズを紹介(対戦)している)
で、その優秀で完成の域に到達している「レジェンド」
5群6枚構成の「変形ダブルガウス型」のレンズを、
2/3程度にスケールダウン設計すると、F値は変わらず、
焦点距離とイメージサークルが約2/3に減少する。
つまり、50mmx0.7=35mm、F1.8、APS-C型専用
という数値となり、すなわち本レンズの仕様である。
まあ、本レンズの場合、上記の「ジェネリック」設計
技法に加えて、最短撮影距離を銀塩標準レンズよりも
大幅に短縮しているのが特徴であり、これは銀塩標準
の45cmの2/3の値を遥かに下回る23cmである。
これは、35mmマクロレンズと、一部の海外製オールド
レンズを除き、35mmレンズとしては、この時代最強の
近接性能であったし、1/4倍マクロに相当する値だ。
(参考:2015年に発売されたTAMRON SP35/1.8
(Model F012)は、最短20cmと本レンズを上回った。
また、2019年発売のTAMRON 35/2.8 DiⅢ M1:2
(Model F053)(未所有)では、最短15cmと、
さらに記録を更新している。だが、後者は「殆ど
マクロレンズだ」とも言える)
![_c0032138_12253904.jpg]()
必携のレンズである、とは言えるが、課題として、
α Aマウント市場縮退の為、だんだんと使用環境が
厳しくなっている点がある。
----
では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。
1)AF50/2.8 =4.5点
2)BCL-0980 =3.7点
3)KENKO 85 =3.5点
4)XR28-200 =2.8点
5)MIR24 =4.0点
6)LENSBABY3G=3.6点
7)DT35/1.8 =4.1点
今回の7000円級対戦においては、「Best Buy」は
「MINOLTA AF50mm/F2.8 Macro」となった。
まあ、数々のランキング系記事でラインクインして
いるので当然だとは思う。
ただし、本記事では7000円級というカテゴリーだが
この価格で買えるのはAF50/2.8の初期型のみで
あろう、色々ある後継型(注:光学系は同一だが
MF操作性が、どんどんと改善されている)については
この値段では買えないと思うので念のため。
また、今回の記事では、他に好評価レンズが2本ある。
*MIR-24については、買うに値するが、数少ない
ロシアンレンズであり、安価に見かけたら絶対に
買いだ。
*SONY DT35/1.8は、α(A)ユーザーならば必携。
APS-C機専用だとか、そういう事は気にする必要
も無い。
本ブログでは、個人DB(データベース)のレンズ評価
得点が4点以上のものを「名玉」と判断している。
ここに挙げた3本は、勿論、全て「名玉」である。
----
さて、今回の「7000円級レンズ編」記事は、
このあたり迄で、次回記事に続く。
価格帯別に数本づつ紹介し、記事の最後にBest Buy
(=最も購入に値するレンズ)を決めている。
今回は、7000円級(価格は全て税込み)編とする。
----
では、早速7000円級レンズ7本の対戦を開始する。
まず、最初のエントリー(参戦)。

(中古購入価格 15,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
1980年代後半のAF標準等倍マクロレンズ。
後継レンズとの識別の必要がある場合、中古市場では、
初期型またはⅠ型と称されるか、あるいは無印となる。

光学系には、大きな変更は無いか、同一と思われ、
初期型から完成度が極めて高かった名レンズだ。
この結果、過去のランキング系記事においても
ミラーレス名玉編:第4位
ハイコスパ名玉編:優勝
最強50mm選手権:B決勝優勝(総合第6位相当)
と、全てで高順位獲得を実現した名玉である。
本レンズが高描写力を持つものだ、とは、購入時点
(1990年代頃)では、あまり認識していなかった。
しかし、1999年頃、私は、買ったばかりの高価な
MINOLTA α-9とSTF135/2.8を、機嫌良く撮影に
持ち出そうとしていた、ただ、135mmの単焦点
だけで丸1日撮る事には不安があった。
現在でこそ、私は単焦点1本で、その画角に見合う
被写体は探せるし、デジタル時代なので、画角の
自由度も(トリミングやデジタルズーム機能で)
高い状態だが、当時ではスキル的にも機材環境的
にも厳しいので、たいていの場合には、2本以上の
焦点距離の異なるレンズ群を同時に持ち出していた。
そこで、その日も、予備として本AF50/2.8を
持ち出し、標準画角で広く撮りたい時や近接撮影を
したい場合には、適宜レンズを交換して撮っていた。
撮影後、そのまま行きつけのDPE店に寄り、写真を
現像した。すると何枚かの写真が、STF135/2.8
で撮ったのか、本AF50/2.8で撮ったのか、区別が
できない状態になってしまったのだ。
匠「あれ? この写真ってどっちだろう、STF?
50マクロ? 全然わからないや(汗)」
画角の違いは、両者、近接撮影が得意なレンズで
あるから、近距離撮影では、殆ど区別が出来ない。
「その被写体に対して、どっちのレンズを使って
いたか?」は、現在であれば、多分覚えておけたとは
思うが、当時は、そこまで撮影に余裕が無かったので、
そういう点にまで、気を配れる状況でも無かった。
STFが高性能で、ボケ質にも配慮した良く写るレンズ
である事は勿論知っていた。なにせ、本レンズの
約10倍もの高額価格で購入したのだ。
だが・・ レンズ間に値段差ほどの描写力の差が無い
事も、その時点で強く認識した。
私は、それまで、本レンズは1万円台で買ったので、
「安かろう、悪かろう」という認識しか持って
いなかったのであった。
「安価なレンズでも、たまたま撮影条件がハマれば
10倍も高価な高性能レンズ(しかも相手は超名玉STFだ)
に、さしてひけをとらない高描写力を発揮できる!」
という事実は目から鱗が落ちる程であった。
でも、そこから何度も試写を重ねて、ようやく気づいた
点がある。
「これは、AF50/2.8も、それなりに優れるレンズなのだ」
という事実であった。

おいても、依然、本レンズは「頼れるレンズ」であり、
実際に、近年の様々なランキング系記事の全てで
高順位をマークしている。
別に初期型である必要は無いが、後年のバージョンも
含め、いずれかのMINOLTA/SONY 50mm/f2.8 MACRO
は、マニア層必携のレンズと言えよう。
----
では、次のシステム。

(BCL-0980) (9mm/f8.0 Fisheye)
(新品購入価格 9,000円)(実用価値 約7,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
2014年発売の魚眼型ボディキャップレンズ。
オリンパスではこれをレンズではなく、アクセサリーと
称している。
対角線画角は、およそ140°なので、180°には満たず、
あくまで「魚眼風」レンズだ。

事ではなく、「構図の練習をする事」だと思う。
魚眼(風)レンズの場合、画面中心から放射状に
伸びる直線上の被写体は歪まない。また、当然
その線に乗らない被写体直線部は大きく歪む。
だから、例えば海や川等の水平線を歪まないように
写すには正確に画面中心の水平線にそこを合わせる。
これは簡単なようで、非常に難しい。
カメラを構える構えが、各回転軸に対して水平に
なっていなければ、水平線等にうまく合わない。
各回転軸というのは、ロー、ヨー、ピッチの事である。
水準器等を使って三脚撮影時の水平を取ろうとする
シニア層等はとても多いが、上記の各回転軸の事を
理解しているだろうか? いや、それは無理だるう。
こういう回転軸が存在する事は、当たり前の物理
原理ではあるが、工業的な計測や製造分野、あるいは
船舶や航空機、二輪車等の三次元的な動きをする
乗り物の動きを解析する等の、やや専門的な分野に
係わっている状況でないと、日常生活では、これらの
用語や概念は、まず使われない。
たとえば、フライパンで野菜を炒める際に
「ピッチング方向にも十分にフライパンを振って」
などとレシピに書いてある訳でも無い。
ただし、ごく最近では、カメラにおける「5軸手ブレ
補正機能」等の技術説明において、手ブレには様々な
回転軸がある事が、やっと一般層に広まりつつがある。
最初にこれを見たユーザーは、「5軸って何だ?
タテ、ヨコ、ナナメ(?)、あと、どの方角だ?
東西南北? まさかね・・(汗)」といったような、
印象や疑問を持った事であろう。
でも、カタログ等で技術の説明を見ると、ローリングや
ヨーイング、ピッチングなどの図解があって、
「なるほど、こういう方向にも手ブレが起こるのか!」
という事がやっと理解できる。
(注:ただし、実際にそういう軸で手ブレが起こって
いるかどうか?は不明。撮影者にもよりけりであろう。
なんだか、他分野での「菌が居るから除菌しなさい!」
というTV CMと同様で、「回転軸方向にも手ブレを
するから、5軸手ブレ補正機を買いなさい!」と、脅迫
心理を植えつけられてしまっているようにも思える)
さて、三次元的な回転軸を理解できたところで、
魚眼レンズにおいては、これらの三次元的な回転軸を
正確に捉えて(手持ち撮影で)構えないと、自身が
求める構図や描写を得る事ができない。
(注:例え、三脚を立てて、水準器で水平を取っても
無意味である。真上から見た捻り(ヨーイング軸)等
には、水準器は反応しないからだ。あるいは三脚を
立てる高さ(レベル)によっても、描写は変化する。
こういう僅かな、回転軸やレベル、アングルのズレが、
魚眼レンズでは「直線が歪む」という描写の差として、
写真に顕著に現れる訳だ。)
この練習の為には魚眼レンズは最適と言えるのだが、
非常に高度な内容であり、手持ちで回転軸を整える
には高度な技量が要求される。(勿論、前述のように
三脚を使っても、課題が解消される訳では無い)
だけどまあ、安価な魚眼レンズで、この構図練習を
する事は悪く無い。
三次元的な回転軸を理解せずに、平面的な「三分割構図」
やら「S字構図」などの練習をしても、ほとんど意味が
無い、そもそも「どのようにカメラを構えたら良いか?」
という部分の技能習得が、ぽっかりと欠けてしまうからだ。

このレンズ、または他の安価な魚眼レンズを購入して
練習する事は悪く無い選択肢だ。
----
では、3本目のシステム。

(中古購入価格 16,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
詳細不明、恐らくは1980年代~1990年代位の
MFソフトフォーカス(軟焦点)中望遠レンズ。
(以下、ソフトレンズ)
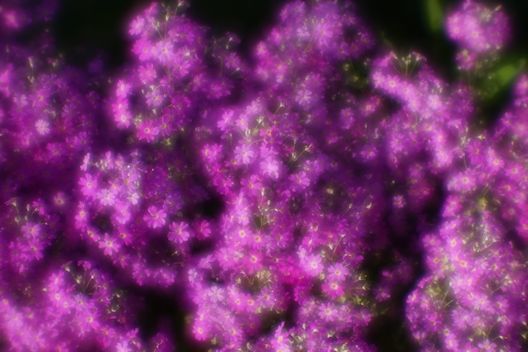
では存在しておらず、LENSBABY、安原製作所、LOMO
等のレンズサードパーティで数機種が発売されているに
過ぎない。
そして銀塩時代でも、さほど数は多く無く、メーカー
純正であれば、MINOLTA,PENTAX,CANON,NIKON
(注:おもしろレンズ工房)で各々1~2機種が存在し、
さらにレンズメーカーでは、KENKO、清原光学、海外
メーカー等から、各々数機種が発売されていたのみで
あった、と記憶している。
いつもソフトレンズの記事で書く事と重複するが、
簡単に書いておこう。
1)これらの光学(的)ソフトレンズの描写傾向は、
ソフトフィルター、ソフトエフェクト(画像処理)、
ソフトレタッチ(画像編集)、そして、その他の手法
(例:保護フィルターに油分を塗る等の特殊技法)の、
いずれの場合とも異なる。
ソフトレンズの真の描写はソフトレンズでしか味わえない。
2)ソフトレンズのピント合わせは大変難しい、
一眼レフの光学ファインダーはもとより、ミラーレス機
の「ピーキング機能」でも反応しない場合が大半だ。
絞り込めば、球面収差が減少し、ピントが合わせやすく
なるのだが、撮影の為に再度絞りを開けると、またピント
が合っている保証が無くなり、堂々巡りになり難しい。
(注:一眼レフで「フォーカスエイド」が効く場合がある)
3)ソフトレンズは希少ではあるが、さほど価値のあるもの
では無く、1万円台を超えてまで高額に入手する必然性は
殆ど無い。
以上である。
いずれの特徴も、本KENKO SOFT 85/2.5 に当てはまる。
無理をしてまで入手するものでは無いが、たまたま安価に
見かけたら、購入してみるのも悪く無い。
参考記事:「特殊レンズ第7回SOFT LENS編」
----
では、4本目のシステム。

f3.8-5.6 Aspherical XR [IF] MACRO (A03)
(中古購入価格 17,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)
2001年に発売された、AF高倍率(高ズーム比)レンズ。
本ブログでは、あまり「高倍率ズーム」という
呼び方を推奨していない。
その理由を説明すると長くなるので割愛するが・・
要は、あまり正しい呼び方では無く、かつ、ビギナー
層等に対して効能を誤解させやすい「確信犯的」な
呼称なので、あまり好ましく無いと思っているからだ。
(詳細は、匠の写真用語辞典第3回記事を参照)
まあ、レンズの呼び方の詳細の話は良い。
本記事では、「高倍率ズーム」と呼ぶ事にしよう。

については、本レンズが「実用的な高倍率ズーム
としては、初めての製品である」という認識からだ。
勿論、それ以前から高倍率ズームは存在している、
恐らく、最初の製品は、1980年代頃(?)の、
「キノ精密工業 KIRON 28-210mm/F4-5.6」
(レンズマニアックス第13回記事参照)
だったであろうか? だが、当該記事を参照して
もらえればわかるが、そのレンズは様々な意味で
実用性能にまるで達していない。
その後、TAMRONも1990年代初頭から28-200mm
高倍率ズームを開発販売しているが、やはり初期の
ものは実用範囲外であり、購入には値しないもので
あった。だが、TAMRONは、そこで諦める事は無く、
地道に10年間ほど改良を続け、やっと実用レベルに
達した高倍率ズームが、本XR28-200である。
という事で、本XR28-200は、発売年頃には各種の
賞を総なめとした。当然、人気&ヒット商品となる。
「高倍率ズームなんて、まだまだ(の性能)だよ」と
思っていた私でも「どれどれ? そんなに良くなったか?」
と興味が出て、本レンズを中古購入した次第であった。
この商品、および同時期に発売された兄弟レンズの
XR28-300(こちらも所有しているが、望遠域を拡張
した事で、収差補正等の面で描写力的には厳しい)
が市場での「高倍率ズーム」の代表格(筆頭)となり、
TAMRON社への市場からのイメージも、それまでの
「マクロのTAMRON」から、「高倍率ズームのTAMRON」
という認識が広まり、TAMRONはブランドイメージを
拡張および高める事に成功した。
この事実、あるいは功績を持って、本XR28-200は、
「歴史的価値が高いレンズである」という認識を
私は持っている。
本XR28-200の長所は3点、
*これまでに無い小型軽量の高倍率ズームである事
*描写力をさほど低めていない事(実用範囲)
*ズーム全域で49cmの最短撮影距離を確保している事、
これは広角域ではやや不満な性能だが、望遠端に
おいては準マクロレンズ並みの最大撮影倍率1/4倍
の近接性能が得られる。
そして短所はあまり無い、まああえて言えば、解像感や
ボケ質(の破綻頻度)、ズーム焦点距離毎に変動する
諸収差、逆光耐性などがあり、あまり厳密な撮影には
向かない点が弱点であろう。
ただ、そういう風に「ちゃんと撮りたい」ならば、
本格的高性能単焦点やら中望遠マクロレンズを持ち出せば
良いので、本レンズを持ち出すシチュエショーンは、別に
存在する。たとえば散歩撮影とか、小旅行などであり、
レンズ交換も不要で、ほとんどの被写体は本XR28-200
の1本で撮れてしまうのだ。
そういった「用途開発」が容易なレンズである事と、
気軽に使える「エンジョイ度」の高さが、本レンズの
真骨頂であろう。

約20年経った現代においても中古流通は豊富である。
見つけたら数千円という安価な相場であろうから、
「初の実用的高倍率ズーム」という歴史的価値の実感を
得たり、性能を研究する為にも、購入は悪く無い選択だ。
----
では、次のシステム。

(中古購入価格 8,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
詳細不明、ウクライナ(旧ソ連)のキエフの国営工場
にて製造されたと思われるレンズ。同工場は、現代に
おいては「アルセナール社」(アーセナル社)となり
「光学および電子総合メーカー」(企業)である。

現代の視点からは実用性能に満たないものが大半である。
ただ、本レンズの描写力、および近接性能(最短撮影距離
が24cmであり、これはマクロを除く、フルサイズ対応
35mm級レンズ中でトップクラスの性能である)により、
本レンズの個人評価点は、ロシアンの中では抜群に高い。
この結果、過去のランキング系記事においても
ミラーレス名玉編:第17位
最強35mm選手権:決勝進出準優勝
と、いずれも、ロシアンレンズ中では唯一となる
ランクインの快挙を成し遂げている。
弱点は、現代において入手性が極めて低い事である。
1990年代頃には国内でも新品販売されていた模様であり
その頃であれば入手性が低い事は無かっただろうが、
ソビエト崩壊により、ウクライナのアルセナール社も
工場から独立して企業となってしまった訳だから、
もう「国策」で、このような古い時代のレンズを
1990年代においては、作り続ける必要もなくなったので
あろう。
工場在庫品の国内(日本)販売がはけた頃(2000年頃?)
には、もう、すっかり見かけなくなってしまった。
現代においては、こうした希少な「ロシアン」レンズは、
所有者や市場関係者により「過剰な好評価」が成される
場合が多い。
現物を誰も目にした事が無いのだから、誰かが「良い」と
言えば、その他大勢の一般層は、その情報を簡単に信じて
しまう。その結果「あのMIR-24が、どうしても欲しい」
とか言い出してしまう訳だ。
そうなったら、販売側はもう「言い値」であろう。
4万円、あるいは5万円といった、不条理なプレミアム価格
を提示されたとしても、購入側はそれを呑むしかない。
これでは完全に「消費者(ユーザー)の負け」の取引条件
であり、買い物のやり方としては、もっともやっては
いけないケースである事は、様々な記事で説明した通りだ。

ので、近年では、本ブログでは、あまりロシアンレンズを
褒めたりはしたく無いとも思っているのだが、これが意外と
難しい。
例えば、良い写りの写真を載せれば
「やっぱ、ロシアンって良く写るんだなあ」となり、
ボケ質破綻とか、フレアやゴーストが出ている写真では
「個性的な写りだ、国産レンズではこうはいかない!」
と、それぞれ都合の良い視点で、勝手に解釈されてしまう
訳なのだ。
ならばもう、ロシアンレンズに限らないが、全ての機材
評価(や購入検討)においては、ユーザー側が各々、
確固たる「価値感覚」をもっていないとならない。
やはり最も重要なのは「コスパ感覚」であろう。
本レンズは、私の購入価格は8,000円だ。実用価値も
それと全く同じ金額で約8,000円と評価している。
それ以上でも、それ以下でも無い、という話だ。
(追記:ごく近年、1本だけ本レンズの中古品を
見かけたが、売価は18,000円程であった。
この価格だと、1990年代のソビエト崩壊後の、ロシア
国営工場からの直輸入の新品と、ほぼ同一価格となる。
だから高いと思うか、安いと思うかは、人それぞれ
だと思うが、私は高価すぎると思うし、他者もそう
思うからか? 当該中古品は、なかなかすぐに売れる
事はなかった模様だ)
----
では、6本目のシステム。

(中古購入価格 10,000円)(実用価値 約6,000円)
カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)
2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。
「3G」とは、第三世代、という意味だと思われるが、
第一世代や第二世代の製品は、国内では殆ど流通
していない。まあ「3G」が一般的に入手できる最も
古い時代のTILT(ティルト)型製品であろう。
LENSBABY社は、米国にあり、設立は2004年と新しい。
当初は製品は直販(通販)のみであったと思われるが、
2000年代末位には、国内KENKO TOKINA社が輸入代理店
を務めるようになり、その頃から国内流通が活性化した。
「3G」以降のTILT型の製品数は非常に多いので、詳細は
本記事では割愛するし、個人的にも「後継機でも効能は
殆ど同じ」と見なしていて、光学系が交換方式になった
「LENSBABY MUSE」より新しいTILT型製品は購入していない。
(ただし、後継機になる程、操作性は向上している)

光軸を被写体面に対して傾ける事で得られる、独特の
描写効果だ。
TILT機構を用いた「アオリ」技法では、例えば、傾いた
被写体面に同時にピントを当てられる。
昔の修学旅行等の大人数集合写真で、斜めに奥行きが
ある人物群に同時にピントを当てるには、僅かにレンズ
を傾ける、すなわち「アオる」必要がある。
この為、修学旅行等で集合写真を撮る「写真館」等の人が、
蛇腹のついた大判カメラで、蛇腹を微調整してレンズを
傾けていた光景は、目にした事のある人も多いであろう。
また、ナナメに置かれた小物商品(時計や万年筆等)
の全体にピントを当てるにも、同様の「アオリ」が必須だ。
で、ここまでの話は、業務撮影用途等において、
TILT機構レンズを「正しく」使った場合である。
「正しく」とは、TILT機構により傾く光軸を被写体面に
垂直にした場合だ。この場合、傾いた被写体面の全般に
ピントが合う事になる。
しかしながら、TILT機構には「逆アオり」と呼ばれる
技法が存在する、これはあえて被写体面の傾きと光軸
の傾きをずらしてしまう技法だ、これにより、撮影者
に平面的に対峙する被写体であっても、そのごく一部
だけの領域(傾く光軸と直交する領域)のみにピント
を合わせる事が可能となる。
こうした写真は、ミニチュア(模型)を撮ったような
写真に見える事から「ミニチュア効果」という名前で、
近年の多くの(デジタル)一眼レフやミラーレス機の
エフェクト(画像効果)として搭載されている。
で、このピントの合う一部の領域の事を、アート系
(学生)カメラマンの間では「スイートスポット」と
呼ぶ。
アート系写真用語は、「トンネル効果」(注:本来は
重要な物理・電子工学用語)等、他分野からちゃっかり
拝借してくる事が良くあり、個人的には、あまり好ましく
無いと思っている。(アート系ならば、適切な全く新しい
用語を「創造・創出」してもらいたいとも思う)
そして「スイートスポット」も、本来はスポーツ用語
であり、ゴルフのクラブやテニスのラケットで、そこに
ボールが当たると「飛びやすい」という領域(最適な
打球点)の事だ。(これも、ちゃっかり拝借用語だ)
ただまあ、エフェクトでの「ミニチュア効果」は、
横とか縦とかの領域を指定して効果を掛けるのだが、
TILT(機構)レンズの場合は、被写体の三次元性と、
傾く光軸の直交エリアとの合焦の効果は、エフェクトの
場合のような直線的にはならず、本当に、ごく一点
だけに合う場合もあるので、「スイートスポット」の
「スポット」は悪く無い表現だ。(でも、「スイート」
の方がいけない、ピントが合う場所なのだから、そこは
シャープで固いイメージだ、「ハードスポット」とかと
呼んでくれていた方が、ましだったと思う)
で、TILT(レンズ)の技術的原理は、少々ややこしい
ので、ビギナー層とか、アート系初級層では、上手く
コントロールする事は、まず出来ないであろう。
「色々試していたら、たまたまミニチュア風に撮れた」
というケースが、ほぼ100%だと思う。

上で、あえて無茶な使用法をしている、具体的には
「スイートスポット」を、わざと作らない、とかだ。
これにより、「アンコントローラブル」(制御不能、
予測不能)な要素を作り出し、「Lo-Fi」写真に必要
な偶然性の要素を意図的に得ようとしている。
(匠の写真用語辞典第5回、項目「Lo-Fi」および
同、用語辞典第21回、項目「アンコントローラブル」)
LENSBABY 3G(または後継型)は、必須のレンズと
いう訳では無いが、使っていて色々と面白いので、
中級層(中級実用派層、中級アート層、中級マニア層)
あたりであれば、入手してみるのは悪く無い。
----
では、今回ラストのシステム。

(中古購入価格 11,000円)(実用価値 約8,000円)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
2010年に発売された、APS-C機(α Aマウント)専用
準広角(標準画角)AFエントリーレンズ。

価格が安く、コスパが極めて良い。
この為、過去のランキング系記事において
ミラーレス名玉編:第14位
ハイコスパ名玉編:準優勝
最強35mm選手権:優勝
と、全てで高順位を獲得した名玉である。
ただし、課題としては現在、SONY α一眼レフ機
(Aマウント)は、事実上終焉していて、本レンズ
を気軽に使える母艦が無い事である。
今回使用機のSONY α65 (2012年)あたりが適正と
思われるが、そろそろこの機体も仕様老朽化寿命
(持論では発売後10年まで)を迎える時期である。
勿論、α(A)マウントレンズは、多くのミラーレス
機でアダプターで使用できるが、現在、SONYの
ミラーレス機ユーザーの大半はフルサイズ機志向だ、
APS-C型専用の本レンズも勿論フルサイズ機で利用
可能であるが、APS-Cにクロップすると記録画素数が
大幅に減少する事は、初級中級層は嫌がるであろう。
また、電子アダプターで無い場合は、MF操作と
なるが、本レンズのピントリングはトルク感が無く
スカスカなので、撮っていて楽しく無い(というか
MF操作性が落ちてしまう、という実用面での弱点と
なる)
結局、あまりミラーレス機で使用する事は推奨できず、
やはり、旧世代機でも良いからSONY Aマウント機を
使うのが良いであろう。
なお、α77Ⅱ(2014年)あたりであれば、高機能・
高性能なので、なかなか仕様老朽化寿命が来ない
とは思えるのだが、今度は、カメラ側が高価すぎたり
無駄に性能が良すぎる、という「オフサイド状態」は
良く意識して使う必要があるだろう。
(=カメラとレンズからなる「システム」において、
トータルバランスが悪く、「用途開発」や実用性に
悪影響が出る、という意味だ。→上級者向けの概念)

特徴であるが、実のところ本レンズも「ジェネリック」
であると思われる。
銀塩時代の1970~1980年代での、MF小口径標準
(50mm/F1.7~F2)レンズ(一部はAF時代やデジタル
時代にまで継続された)は、「完成の域に達していた」
とは、本ブログでの様々な記事で書いた通りである。
例えば、PENTAX SMCT55/1.8、通称「銀のタクマー」
RICOH XR50/2、通称「和製ズミクロン」
CANON EF50/1.8Ⅱ(史上初のエントリーレンズ、
EOSの救世主?)等、全てが初級中級層に「神格化」
された程である。
(詳細は、「最強50mm選手権」シリーズで、数十本
の標準レンズを紹介(対戦)している)
で、その優秀で完成の域に到達している「レジェンド」
5群6枚構成の「変形ダブルガウス型」のレンズを、
2/3程度にスケールダウン設計すると、F値は変わらず、
焦点距離とイメージサークルが約2/3に減少する。
つまり、50mmx0.7=35mm、F1.8、APS-C型専用
という数値となり、すなわち本レンズの仕様である。
まあ、本レンズの場合、上記の「ジェネリック」設計
技法に加えて、最短撮影距離を銀塩標準レンズよりも
大幅に短縮しているのが特徴であり、これは銀塩標準
の45cmの2/3の値を遥かに下回る23cmである。
これは、35mmマクロレンズと、一部の海外製オールド
レンズを除き、35mmレンズとしては、この時代最強の
近接性能であったし、1/4倍マクロに相当する値だ。
(参考:2015年に発売されたTAMRON SP35/1.8
(Model F012)は、最短20cmと本レンズを上回った。
また、2019年発売のTAMRON 35/2.8 DiⅢ M1:2
(Model F053)(未所有)では、最短15cmと、
さらに記録を更新している。だが、後者は「殆ど
マクロレンズだ」とも言える)

必携のレンズである、とは言えるが、課題として、
α Aマウント市場縮退の為、だんだんと使用環境が
厳しくなっている点がある。
----
では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。
1)AF50/2.8 =4.5点
2)BCL-0980 =3.7点
3)KENKO 85 =3.5点
4)XR28-200 =2.8点
5)MIR24 =4.0点
6)LENSBABY3G=3.6点
7)DT35/1.8 =4.1点
今回の7000円級対戦においては、「Best Buy」は
「MINOLTA AF50mm/F2.8 Macro」となった。
まあ、数々のランキング系記事でラインクインして
いるので当然だとは思う。
ただし、本記事では7000円級というカテゴリーだが
この価格で買えるのはAF50/2.8の初期型のみで
あろう、色々ある後継型(注:光学系は同一だが
MF操作性が、どんどんと改善されている)については
この値段では買えないと思うので念のため。
また、今回の記事では、他に好評価レンズが2本ある。
*MIR-24については、買うに値するが、数少ない
ロシアンレンズであり、安価に見かけたら絶対に
買いだ。
*SONY DT35/1.8は、α(A)ユーザーならば必携。
APS-C機専用だとか、そういう事は気にする必要
も無い。
本ブログでは、個人DB(データベース)のレンズ評価
得点が4点以上のものを「名玉」と判断している。
ここに挙げた3本は、勿論、全て「名玉」である。
----
さて、今回の「7000円級レンズ編」記事は、
このあたり迄で、次回記事に続く。