「最強レンズ選手権」のマクロ編記事群である。
現在の予選リーグは、「標準マクロ」編であり、
この(標準マクロ)カテゴリーでは、計26本の
マクロレンズにより、全4戦を予定している。
本記事は、その予選第3戦だ。
----
まずは今回最初の標準マクロレンズ。
![_c0032138_18423909.jpg]()
レンズ購入価格: 9,000円(中古)(以下EX50/2.8)
使用カメラ:CANON EOS 7D(APS-C機)
2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ
レンズ。
正式型番は不明。レンズ上の記載を参考にしようにも、
部分的な型番が順不同で書かれている状態だ。
まあ、あまり正式名には拘らずに、妥当と思われる
機種名を記載している。
![_c0032138_18423989.jpg]()
CANON側の処置で新型EOS機で使えなくなった事を、
個人的には「ユーザーの事を考え無い」と、ずっと
「根に持って」いて、本ブログでは、何度も何度も
その件を記載し、それらSIGMA製レンズがEOS機で
使えなくなった後でも、マウントアダプター等を
非正規に用いた珍妙な用法で、それらを「意地でも」
使い続けて来た訳だ。
・・ただ、もう「さすがにクドい」とか「時効か?」
とも思っていて、ようやく事件勃発から20年近くも
経った時点で、当該レンズ(SIGMA 50mm/F2.8 Macro)
の、CANON EF新プロトコル対応版(EX DG版)の
中古品を購入した次第であり、それが本レンズだ。
旧型が「まともに使えない」状態であっても、それを
処分せずに使いつづけたのは、前述の「意地」や
「事件を風化させたくない」(→二度と同じような
措置をやって欲しくない)為の紹介理由もあったのが、
まあ、それよりも、旧型の描写力が、捨て難いものが
あったからである。したがって、本レンズは、その
後継機種であり、購入前から高描写力が保証されて
いるような状況であった。
本レンズは2000年代発売だが、その時代においても、
他社の純正の標準マクロの価格よりも安価な、新品・
中古相場であったので・・
初級中級層より「どの(一眼レフ用の標準)マクロを
買ったら良いのですか?」という相談を受けた際には、
「MINOLTA/SONY機で使うならば、MINOLTA AF50/2.8
系列が最善。他社マウントではSIGMA EX50/2.8が
良いと思いますよ」と、必ずこれを推奨した。
ただまあ、このアドバイスは、厳密には「所有しても
いないレンズ(本EX50/2.8型)を他者に推奨した」
という事で、マニア道的には「ご法度」(やっては
ならない行為)であるだろう。旧型は所有していても
新型では描写性能以外での、何らかの改悪が発生して
いるかも知れない訳だ。(例:AF精度が低い等・・)
まあ、そういう「曖昧なアドバイスをしてしまった」
という事への、贖罪(罪滅ぼし)も、本レンズを購入
した理由の1つだ。
ただまあ、幸いにして、描写力上での旧型に対する
改悪は無い。しかし、「やはり」というか、懸念して
いたAF問題(速度、特に精度)は、かなり厳しい
ものがあった。
まあつまり、旧型では「正規に使えない」という
課題を解消する上でも、全てMFで撮っていた訳であり
旧型のAF性能が貧弱でも、それは度外視できた。
が、本EX DG型は、一応デジタル時代でのAFレンズと
して発売されているから、AFで使おうとするのが
妥当である。ただ、とは言え、厳密なAF精度を要求
される近接撮影では、結局「AF性能がNGだ」という
結論になってしまった。
で、本EX50/2.8の購入後、しばらくは、オフサイド
ルール(カメラの方が、レンズよりも高性能または
高価格すぎる状態を戒める持論)の緩和の意味もあり、
初級機EOS 8000Dを母艦としていたが、その機体の
AF/MF性能では、正直、実用範囲以下である。
よって今回は少しでも母艦のAF性能を高めながらも、
オフサイドルールに抵触しにくい(中古が安価な)
EOS 7Dを母艦としてチョイスしている。
AFの弱点は、わずかだか緩和できるが、EOS 7Dの
光学ファインダーおよびスクリーン(交換不可)では、
MFでの使用は、やはり実用範囲外の低性能でしか無い。
(注:一応、測距点連動型のフォーカスエイド機能
はEOS機に存在しているが、MFで構図上のどこででも
ピントを合わせたいのに、フォーカスエイドを使う為に
測距点の選択操作をしていたら、本末転倒であろう)
![_c0032138_18423920.jpg]()
課題はAF/MFのピント合わせだけである。
まあ、今後はEOS 6D+Eg-S(MF用スクリーン)で
MF重視で使うか、又はEOS M5と電子アダプターで、
ピーキングにより、MFの課題を緩和しつつ使って
行こうと考えている。
なお、α Aマウント機用のものを入手するならば、
近代2010年代の、αフタケタ一眼レフならば、
ピーキング機能の搭載により、本レンズであっても
MF精度を高める事は可能だ。ただ、チラリと前述
したように、MINOLTA/SONYでは、とても優秀な
銀塩時代からのAF50/2.8系標準マクロが存在する
ので、それと比較すると、本EX50/2.8は、ほんの
僅かだが被写体汎用性が劣る気がする為、そちら
を推奨する事となる。それに、現代においては、
SONY α Aマウント機は絶滅危惧種となっているので
やはりまあ、NIKON/CANON用あたりを入手するのが
ますます無難であろう。それらのメーカーの純正
マクロと比較すれば、本EX50/2.8のコスパの良さ
とは「雲泥の差」がある。
また、この時代(EX DG)のSIGMA製レンズのNIKON
F(Ai)マウント版は、絞り環を持つ仕様であるから、
それを購入しておくならば(特にMFが主体のマクロ
では)他社機や他社ミラーレス機での使用汎用性が
高まる事は特筆すべき点だ。
(注:以降の時代のSIGMA NIKON F用レンズは
絞り環の無いG型仕様となってしまっている)
---
では、次の標準マクロレンズ。
![_c0032138_18424045.jpg]()
レンズ購入価格:20,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS PEN-F(μ4/3機)
1980年代のMF標準(ハーフ)マクロレンズ。
「A」仕様のレンズであるから、現代のPENTAXの
デジタル一眼レフでもMFで問題なく使用できるが、
まあ今回は、少し捻って、μ4/3機での試用だ。
これで100mm、等倍マクロの換算仕様となる。
![_c0032138_18424582.jpg]()
あるが、実用上での差異は、本レンズは1/2倍マクロ
とは言っても、標準マクロなので、最短撮影距離が
24cmと短く、一般的な100mm級等倍マクロでの
最短30~35cm程度よりも、ずっとWD(ワーキング
ディスタンス)を短く取れる点がある。
マクロレンズにおいての「WD」は、実用上では、長い
ものと短いもの両方が、撮影条件に準じて要求される。
まあ、様々な焦点距離のマクロレンズが世の中には
存在し、それらが全て「等倍」ならば、初級層等では
初「皆、同じ大きさに被写体が写るのでしょう?
じゃあ、マクロレンズで焦点距離が違う物は、
何故それが必要なのか?」
と疑問を持つ事であろう。
でも、実際には焦点距離毎でマクロの用途は異なる。
例え、被写体が同じ大きさ(等倍)で写ったとしても、
被写界深度、背景の取り込み範囲、遠近感等、
それらの描写傾向が、まるで異なるし、加えて、
WD(撮影距離)が、全然違うのだ。
WDが異なると、撮れる被写体や、撮影技法までも、
まるで変わってきてしまう。でも、それが長い・短い
事が良い訳なのではなく、被写体状況によりけりだ。
まあ、なので、今回のような、こういう特殊用法
(中望遠等倍マクロ相当だが、WDが短い)という
システムを組む必要性も、”無きにしもあらず”
という事となる。
![_c0032138_18424571.jpg]()
レンズだ。銀塩MF時代の(1/2倍)各社マクロは、
描写力に優れないものが殆どであったのだが、
本A50/2.8は、やや例外的なレンズである。
本レンズは銀塩時代より、常にPENTAX一眼レフ
で使っては来たが、たまにこのように、μ4/3機で
使うと、また、ずいぶんと異なる用途のマクロに
変貌する事が、なかなか興味深い発見であった。
現代において本レンズを「指名買い」する必然性は
殆ど無いが、たまたま安価な相場(1万円台前半
程度)のものを発見できたならば、購入は悪くは
無い選択だ。だがまあ、その相場であれば、前述の
EX50/2.8やTAMRON90マクロの初期型等が買えて
しまう訳だから、選択肢としてはやや難しいのだが、
マニア等であれば、安価なそれらをかたっぱしから
入手し、詳細に比較してみる事も、知的好奇心を
満たす意味では悪く無い。
---
では、3本目のレンズ。
![_c0032138_18424579.jpg]()
レンズ購入価格:36,000円(中古)(以下、SP45/1.8)
使用カメラ:NIKON D5300(APS-C機)
2015年発売のフルサイズ対応単焦点(小口径)AF標準
レンズ。
ただし、これはマクロレンズでは無く、最短撮影距離
29cmで最大0.29倍の「寄れる標準レンズ」である。
だが今回はAPS-C機に装着している為、最大約0.44倍
となり、およそ1/2倍マクロに相当する、近接撮影に
強いレンズだ。(注:μ4/3機に装着すれば、さらに
撮影倍率を高める事が出来る。またデジタルテレコン
(クロップ)やデジタルズーム機能の併用で、さらに
仮想的に撮影倍率を高める事ができるが、それらの
いずれでも、最短撮影距離は29cmのままである)
![_c0032138_18424518.jpg]()
(手ブレ補正内蔵、超音波モーター内蔵)にしては
さほど高価では無いので(注:開放F1.8という
仕様がビギナー層から見て不人気で、販売価格が
暴落したからだ)その為、コスパに優れる。
弱点が殆ど無いレンズの為、「最強50mm選手権」
シリーズ記事では、見事「優勝」の栄冠を得ている。
本レンズが、たった1つの「開放F1.8である」という
理由だけで(→F1.4の方が優れると消費者層は思う)
市場で正当に評価されていない状況は、TAMRONと
しても「たった数年間で、そこまで急速に消費者層
での評価レベルが下がっていたのか!?」と大誤算で
あった事だろう。でも、そういう現代のレンズ市場
(主力の消費者層はビギナーばかりだ。まあ、レンズ
が高付加価値化して、高価すぎる状況は、中上級層
から見て、魅力的だとは思えないからだ。加えて
本レンズは「標準レンズ」であり、同等品を所有して
いない中上級層は皆無だ。新たに買い増す必要は無い)
においては、やむを得ないのかも知れない。
でもまあ、わかっている人達は、優れたパフォーマンス
を持つレンズが、不人気で安価な相場となっているので
あれば、それを入手すれば、極めて「コスパが高い」
買い物となる訳だ。
以下、余談であるが、本レンズの時代(2015年頃)
から、TAMRON製の単焦点レンズ群の多くにおいて
フィルター径をφ67mmで統一する動きが始まった。
これは地味な改善であるが、ユーザーメリットが
大きい(様々な径の各種フィルターを買わなくて済む。
例えば、NDフィルターも、様々なTAMRON製レンズで
併用できるので、今回のようにNIKON D5300という
初級機に装着した場合でも、日中に最高シャッター
速度に到達する事なく、絞りをフルレンジで使用可)
・・ので好ましい。
特に、2019年頃からの市場では、安価なフィルター
類が、すべてディスコン(生産中止)となっていて、
現状で販売されているものが、旧来の製品と比べて
非常に高価な、「高付加価値型フィルター」
(例:コーティング、薄枠、撥水、高透過性、等)
のみになってしまった(値段は、数倍~十数倍まで
跳ね上がった。定価1万円を超えることもザラだ・汗)
状況なので、これらを沢山揃える事は、価格的にも
心情的にも困難な話だ。(→”売れていないから”と
言って、”単純に値上げをすれば良い”話でも無いで
あろう、ちょっと、この市場戦略には賛同しにくい)
よって、レンズ間でのフィルター径の統一は、かなり
歓迎すべき方向性である。
なお、銀塩MF時代(1970年代~1980年代)では、
オリンパス、ニコン、キヤノン等においては、
自社発売の、多くの交換レンズ群のフィルター径を
見事なまでに統一していた。
製造面でも利用者利便性でも優れている、その慣習が
無くなってしまったのは、”高度成長期”も終わって
しまい、日本の製造業での「ノウハウ」が失われて
しまったからなのだろうか? あるいはバブル期を
(1990年頃)迎えるにあたり、メーカー側の論理でも、
「フィルターの値段など、たかが知れている。
そんな物はユーザーが個々に買えば良い話であり、
設計側としては自由に、高性能のレンズを、好きな
フィルター径で作れば良いのだ!」
という考え方にシフトしてしまったのだろうか・・?
まあでも、メーカー側が好き放題に設計する事は、
「モノ作り」の観点からも、「消費者目線」からも、
あまり褒められた考え方では無い。
TAMRONが、そういう風に”原点に立ち返る姿勢”を
見せてくれつつあるのは、高く評価したいポイントだ。
![_c0032138_18430211.jpg]()
であろう。ただ、マニア層等であれば、
「他にも、単焦点の標準レンズは持っているから、
被るので不要だよ」と思う人も多いかも知れないが、
過去シリーズ「最強50mmレンズ選手権」記事において、
およそ80本程度の所有標準レンズ群の中から、堂々の
優勝となった実力値は半端無い。一度、本SP45/1.8の
パフォーマンスとコスパを実感してみる事を推奨する。
なお、NIKON F(Ai)マウント版の場合、本SP45/1.8
であればG型仕様なので、他社機等での使用時には、
NIKON G型対応アダプターを使用すれば可能である。
ただし、姉妹レンズSP85/1.8等では、NIKON用でも
E型(電磁絞り)対応となってしまい、NIKON機以外
での利用は極めて厳しい事は注意点として挙げておく。
(注:E型の場合、NIKON一眼レフであったとしても
2007年製(例:NIKON D3、D300等)より前の古い
機体では「電磁絞り」は動作しないので使用不可だ。
また、TAMRON製E型仕様レンズでは、さらに厳しく、
2009年以降のNIKON機でないと使えない可能性が高い。
どうも、E型は汎用性が低く、個人的には好まない。
E型で期待される露出精度の向上の件であるが・・
高速連写時に機械絞り動作がバラつく事は、昔の
NIKON F5(1996年)あたりから、ずっと気になっては
いたが、NIKON機以外のミラーレス機等の高速連写機
で実絞り(絞り込み)測光で使えば、それは問題では
無くなる。つまりE型レンズである必然性は少ない。
なお、ここで”AFが効かない”等は、どうとでもなる
問題なので、露出値がバラバラになるよりはマシだ)
---
では、4本目のレンズ。
![_c0032138_18430244.jpg]()
レンズ購入価格:10,000円(中古)(以下、DT50/1.8)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2010年に発売された、APS-C機(α Aマウント)専用
AF標準(中望遠画角)レンズ。
こちらもマクロレンズでは無い。最短撮影距離は
34cmで、最大0.2倍だ。これをAPS-C機α77Ⅱに
装着し、さらに同機に備わるデジタルテレコン機能を
2倍で用いると、最大約0.6倍となり、これも
1/2倍マクロに相当する、近接撮影に強いレンズだ。
![_c0032138_18430377.jpg]()
ハイコスパ名玉編では、総合6位にランクインした。
だが、「エントリーレンズ」としての、本レンズの
SONY α Aマウント戦略での役割は短期間で終了し、
その後、2013年からは、SONYはα E(FE)マウント
のミラーレス機販売に主軸を移し、以降のα A機の
新製品はα77Ⅱ(2014年)、α99Ⅱ(2016年)の
たった2機種しか(国内では)展開が無い。
結局、α Aマウント・システムは自然消滅という
形になるだろうから、今更、本レンズを推奨し難い
点が痛いところだ。
まあでも、裏を返して考えてみれば、2010年前後
において、SONY α Aマウント機の市場展開が
厳しくなっていたからこそ、「エントリーレンズ」
を発売して、市場を活性化したいと思ったのが
本レンズ(や、DT35/1.8等の同時代のレンズ群)
が発売された理由であったのだろう。
で、あれば、その後のα FEマウントのフルサイズ
ミラーレス機での高付加価値化(→製品の値上げ)
により、本レンズDT50/1.8は、もう役目を完全に
終えてしまった、という話となる。
ある意味、勿体無い話であるが・・ 個人的には、
α A機はバリバリの現役機であり、完全終焉後に
おいても、できるだけ継続利用する為の準備等も、
ボチボチ進んでいる状況であるから、まあ、特に
問題だとは思っていない。
(他の市場分野での類似例を挙げれば、PCに詳しい
ユーザーであれば、サポート終了となったWindows 7
を使い続ける事は十分に可能であるが、PCのビギナー
層等では、何が何でもWindows 10以降にしないと、
”不安で使っていられない”という状態と似ている。
ポイントは、中身や全容を理解しているか否か?だ。
また、現代の様々な市場では「製品に詳しく無い人程、
高価な最新鋭機材を買う羽目になり、無駄な出費となる」
という状況とも言える。勿論カメラやレンズも同様だ。
→だから新鋭機材を使う人はビギナー層ばかりとなった)
---
さて次は、マシンビジョンレンズだ。
![_c0032138_18430383.jpg]()
レンズ購入価格:18,000円(新品)
使用カメラ:PENTAX Q7(1/1.7型機)
2010年代後半に発売されたと思われる、2/3型対応
Cマウント、マシンビジョン(FA)用単焦点汎用
MFレンズ。
![_c0032138_18434615.jpg]()
範疇では、これのスペックを考察するのは難しい。
SV-1214Hを一種のマクロレンズとして考えた場合、
最短撮影距離は10cm、その際の撮影範囲は、
PENTAX Q7装着時の実測(注:こういうシステム
においては、こんな簡単な実測すら高難易度となる)
では、おおよそだが長辺画角が約4cm程度となる。
Q7の1/1.7型センサーは長辺7.6mmなので、センサー
換算倍率は、およそ0.2倍程度だ。
まあ、仕様計算としては、ここまでで十分だが・・
これを写真(カメラ)界の常識を適用して、
「では、フルサイズ換算なら、何倍なのか?」
とか言い出すと、話がややこしくなる。
「原理」が異なるから、あまりやるべき計算では
無いのだが、まあ、無理やりやってみるとすれば
撮影範囲の長辺が、およそ4cmならば、36mm長辺の
フルサイズ機換算で0.9倍程度、ほぼ等倍マクロだ。
だが、Q7やCCTV用2/3型センサーとは縦横比
(アスペクト)が異なるし、それらですら現代では
16:9のワイドアスペクトで使う場合もある。
(注:地デジ対応のTVを、CCTVにおけるモニターに
する事も多々あるからだ)
また、本レンズSV-1214Hの最大解像力は
推定180LP/mm程度となるのだが(注:そういう
スペックも何処にも書かれていない)、その性能と
小サイズセンサーを高画素状態で使った場合での
ピクセルピッチは、適合しているのかどうか?
・・で、そもそも、フルサイズセンサー(35mm判
フィルム)と、Q7の1/1.7型センサーは、
およそ20倍も面積が異なる、果たしてそれらを
同列に扱っても良いのかどうか?
また、ベイヤー型配列のセンサーにおける、カラー
フィルターを用いて画素補完している状態において
レンズ解像力と画素ピッチは上手く対応するか否か?
あれこれと、考えるべき点が多すぎるので、前述の
ように「カメラの常識は通用しない」と言う訳だ。
このジャンル(マシンビジョン)の専門家向けの
レンズである。「カメラ界との接点は何も無い」
と考えるのが無難だろう。これを一般写真撮影用途
として使おうとする事自体が、異端中の異端だ。
マニア層も含め、全ての写真家層には完全非推奨の
レンズである。
---
では、6本目のマクロ。
![_c0032138_18430839.jpg]()
レンズ購入価格:8,000円(中古)(以下、ZD35/3.5)
使用カメラ:OLYMPUS E-410(4/3機)
2005年発売のフォーサーズ(4/3)用のAF軽量等倍
マクロ。
![_c0032138_18435086.jpg]()
2010年頃から、その展開を、ほぼ停止していた。
2013年のμ4/3機「OM-D E-M1」の発売時には、
オリンパスから「フォーサーズとμ4/3を統合した・・」
という主旨の発表があり、そこで事実上フォーサーズ
(4/3)は終焉してしまっていた。
その後、4/3機や4/3用レンズは中古市場でも大きく
相場が下落、逆に言えばコスパに優れ、買い易い
システムとなっている。
だが、4/3機本体に関しては、殆どが2000年代の
発売であり、2000年代の性能水準であるから、
(例:最高感度がISO3200止まり、1000万画素等)
発売後10年以上が経過して「仕様老朽化寿命」が来て
しまっている現代の状況では、新たには買い難い。
今回のように、そうした時代の4/3機を既に所有して
いるのであれば、それを使ってもまあ良いのだが、
より実用的にはOLYMPUS製MMF-2等の電子アダプター
を用いて、4/3用レンズをμ4/3機で使用するのが
簡便な解決策である。
母艦とするμ4/3機の種類によっては、像面位相差
AF機能がこの状態でも動作する為、4/3一眼レフでの
使用時に比べて極端にAF性能が劣る訳でもない。
そして、本レンズのようにマクロであれば、なおさら
であり、AFよりもMFで使う頻度が多い近接撮影では、
μ4/3機に備わるMFアシスト機能(ピーキングや
画面拡大機能)を用いる事で、オリジナルの4/3機
よりも、むしろ使い易い。
ただまあ、4/3のオリンパス純正マクロは、2機種
(ZD35/3.5およびZD50/2)しか存在しない
ので、その2本を入手してしまえば、もう4/3の
マクロは終わり(収集完了)となる。
まあ、その手の方向性(4/3システムの再興)を
考えるというマニア的な思考のみならず、シンプルに
μ4/3機用の「補助マクロレンズ」として考える
ならば、4/3用レンズは現代ではコスパが良いので、
μ4/3純正マクロを揃えるユーザーラインナップ
よりも効率的かも知れない。なお、4/3用マクロは、
各社μ4/3純正マクロとのスペック(仕様)被りは
無い為、その点でも収集の障害は少ない。
![_c0032138_18430984.jpg]()
平面マクロ傾向も見られるが、現代において
わざわざ4/3用レンズに目をつける実践派マニア層
であれば、そのあたりの弱点は、どうとでも回避
できるスキルを持っている事であろう。
----
次は本記事ラストのマクロレンズとなる。
![_c0032138_18431439.jpg]()
レンズ購入価格:9,000円(中古)(以下、NMD50/3.5)
使用カメラ:PANSONIC DMC-G6 (μ4/3機)
1980年代のMF標準ハーフ(1/2倍)マクロ。
個人的にはどうも、この銀塩MF時代の1/2倍標準
マクロは性能的に未成熟であるように思えてならない。
まあ、その分析は、様々なこの時代の標準マクロの
紹介記事で何度も行っているので、重複するので割愛
するが、大きくは2点あって
1)当時の設計技術的な限界点
2)当時のマクロレンズに求められる用途環境
が、現代とは大きく異なる点となっている。
![_c0032138_18431475.jpg]()
あるいは変化が求められたのは、概ね1990年代であり、
その時代からの、AF/等倍の標準又は中望遠マクロは、
現代的視点からは、どれも高性能なものに変貌して
いて「現代でも十分に実用範囲だ」と認識している。
それら1990年代の完成度が高い標準・中望遠マクロ
は、2000年代では、主にデジタル対応、すなわち
新規プロトコル対応、後玉コーティングの改善、
APS-C機用に焦点距離を縮める、等の変更に留まり
大きな光学系の進化は、どれにも施されていない。
2010年代では、ミラーレス機用のマクロの発売が
ポイント(それらの一部は近代設計である)だが、
一眼レフ用の既存マクロは、もう完成度が高くて、
あまり改良の余地が無くなっていた。
よって、2010年代では、内蔵手ブレ補正機構の搭載、
超音波モーターの搭載、および非球面や特殊硝材
の使用が一般的になった為、それらを新規採用して
光学系の若干の改良が行われていたのだが・・
手ブレ補正、超音波モーター等は、ビギナー層の
比率が非常に増えた2010年代の消費者層に向けて
は、「付加価値」(製品を欲しいと思える理由)と
なり、それは同時に、メーカーや流通市場からも
「付加価値」(製品を高く売る為の理由、弁明)とも
なる。まあつまりコスパが酷く悪化している訳だ。
まあ、こんな状況なので、私は、個人的には
2000年代のマクロ製品を「性能的に必要十分に
達し、不要と思われる機能も入っておらず、かつ
中古相場が十分に安価である」という状態から、
「最もコスパが高い」と判断しており、近年では、
重点的にそれらを収集・使用している。
メーカー純正品は、まだそれらについてはコスパが
良く無い状態なので、あまり入手していないが、
レンズメーカー(サードパーティ)製の2000年代
マクロは、もう概ね収集が完了し、どれも良く写り、
コスパが良い事も確認済みなので、それらを実用上
において、とても機嫌良く使用している。
で、実用的には2000年代マクロで十分なのだが、
ちょっと「普通に良く写りすぎる」という僅かな
不満も存在している。・・なんと言うか、個性が無く
差別化要因も無い(誰が撮っても同じように普通に
良く撮れてしまう)訳だ。
そんな、テクニカルあるいは表現的な不満がある際に
おいては、銀塩MF時代の、ややエキセントリックな
特性(風変わりな、という意味。例:平面マクロ)を
持つマクロは、近年においては、ちょっと興味深い
対象となってきている。
勿論、前述のように時代的背景が異なるから、当時
の技術的、用途的な制限から、これらは現代的な
描写のマクロとは言えない。
![_c0032138_18431426.jpg]()
マニア層も居る事であろう。
1970年代~1980年代のオールドマクロであっても
上手く条件を整えて撮影すれば、現代の高性能マクロ
に勝るとも劣らない描写力を発揮する事も出来る。
ただ、それは毎回それが可能なのでは決して無くて、
あくまで、上手く条件がハマった場合のみの話だ。
だが、職業的(実用的)用途の写真撮影ではなく、
あくまで趣味的な要素が大半の撮影であれば、その
措置(試行錯誤)に掛ける時間は、ほぼ無限に
許されている、という恵まれた状況である。
・・であれば、現代の新鋭マクロレンズのおよそ
ヒトケタも安価な(十数万円→1万数千円、数万円→
数千円)という、オールドマクロを上手く使いこなし、
現代の高性能マクロに匹敵するような写真が、
「偶然」でも「必然」でも、それが撮れたのであれば、
なんだか「とても痛快な気分」にならないだろうか?
相当に捻くれた考え方だ、とも言えるかもしれないが、
こういうのも、一種の「マニア道」である。
誰にでもそういう志向性がある訳では無いとは思うが、
「知的好奇心」は十分に満たしてくれると思う、
一部の中上級マニア層に向けては、オールドマクロは
割りと推奨できるレンズとなってくる。
----
さて、次回の本シリーズ記事は、
「最強マクロ選手権・標準マクロ・予選(4)」の予定。
現在の予選リーグは、「標準マクロ」編であり、
この(標準マクロ)カテゴリーでは、計26本の
マクロレンズにより、全4戦を予定している。
本記事は、その予選第3戦だ。
----
まずは今回最初の標準マクロレンズ。

レンズ購入価格: 9,000円(中古)(以下EX50/2.8)
使用カメラ:CANON EOS 7D(APS-C機)
2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ
レンズ。
正式型番は不明。レンズ上の記載を参考にしようにも、
部分的な型番が順不同で書かれている状態だ。
まあ、あまり正式名には拘らずに、妥当と思われる
機種名を記載している。

CANON側の処置で新型EOS機で使えなくなった事を、
個人的には「ユーザーの事を考え無い」と、ずっと
「根に持って」いて、本ブログでは、何度も何度も
その件を記載し、それらSIGMA製レンズがEOS機で
使えなくなった後でも、マウントアダプター等を
非正規に用いた珍妙な用法で、それらを「意地でも」
使い続けて来た訳だ。
・・ただ、もう「さすがにクドい」とか「時効か?」
とも思っていて、ようやく事件勃発から20年近くも
経った時点で、当該レンズ(SIGMA 50mm/F2.8 Macro)
の、CANON EF新プロトコル対応版(EX DG版)の
中古品を購入した次第であり、それが本レンズだ。
旧型が「まともに使えない」状態であっても、それを
処分せずに使いつづけたのは、前述の「意地」や
「事件を風化させたくない」(→二度と同じような
措置をやって欲しくない)為の紹介理由もあったのが、
まあ、それよりも、旧型の描写力が、捨て難いものが
あったからである。したがって、本レンズは、その
後継機種であり、購入前から高描写力が保証されて
いるような状況であった。
本レンズは2000年代発売だが、その時代においても、
他社の純正の標準マクロの価格よりも安価な、新品・
中古相場であったので・・
初級中級層より「どの(一眼レフ用の標準)マクロを
買ったら良いのですか?」という相談を受けた際には、
「MINOLTA/SONY機で使うならば、MINOLTA AF50/2.8
系列が最善。他社マウントではSIGMA EX50/2.8が
良いと思いますよ」と、必ずこれを推奨した。
ただまあ、このアドバイスは、厳密には「所有しても
いないレンズ(本EX50/2.8型)を他者に推奨した」
という事で、マニア道的には「ご法度」(やっては
ならない行為)であるだろう。旧型は所有していても
新型では描写性能以外での、何らかの改悪が発生して
いるかも知れない訳だ。(例:AF精度が低い等・・)
まあ、そういう「曖昧なアドバイスをしてしまった」
という事への、贖罪(罪滅ぼし)も、本レンズを購入
した理由の1つだ。
ただまあ、幸いにして、描写力上での旧型に対する
改悪は無い。しかし、「やはり」というか、懸念して
いたAF問題(速度、特に精度)は、かなり厳しい
ものがあった。
まあつまり、旧型では「正規に使えない」という
課題を解消する上でも、全てMFで撮っていた訳であり
旧型のAF性能が貧弱でも、それは度外視できた。
が、本EX DG型は、一応デジタル時代でのAFレンズと
して発売されているから、AFで使おうとするのが
妥当である。ただ、とは言え、厳密なAF精度を要求
される近接撮影では、結局「AF性能がNGだ」という
結論になってしまった。
で、本EX50/2.8の購入後、しばらくは、オフサイド
ルール(カメラの方が、レンズよりも高性能または
高価格すぎる状態を戒める持論)の緩和の意味もあり、
初級機EOS 8000Dを母艦としていたが、その機体の
AF/MF性能では、正直、実用範囲以下である。
よって今回は少しでも母艦のAF性能を高めながらも、
オフサイドルールに抵触しにくい(中古が安価な)
EOS 7Dを母艦としてチョイスしている。
AFの弱点は、わずかだか緩和できるが、EOS 7Dの
光学ファインダーおよびスクリーン(交換不可)では、
MFでの使用は、やはり実用範囲外の低性能でしか無い。
(注:一応、測距点連動型のフォーカスエイド機能
はEOS機に存在しているが、MFで構図上のどこででも
ピントを合わせたいのに、フォーカスエイドを使う為に
測距点の選択操作をしていたら、本末転倒であろう)

課題はAF/MFのピント合わせだけである。
まあ、今後はEOS 6D+Eg-S(MF用スクリーン)で
MF重視で使うか、又はEOS M5と電子アダプターで、
ピーキングにより、MFの課題を緩和しつつ使って
行こうと考えている。
なお、α Aマウント機用のものを入手するならば、
近代2010年代の、αフタケタ一眼レフならば、
ピーキング機能の搭載により、本レンズであっても
MF精度を高める事は可能だ。ただ、チラリと前述
したように、MINOLTA/SONYでは、とても優秀な
銀塩時代からのAF50/2.8系標準マクロが存在する
ので、それと比較すると、本EX50/2.8は、ほんの
僅かだが被写体汎用性が劣る気がする為、そちら
を推奨する事となる。それに、現代においては、
SONY α Aマウント機は絶滅危惧種となっているので
やはりまあ、NIKON/CANON用あたりを入手するのが
ますます無難であろう。それらのメーカーの純正
マクロと比較すれば、本EX50/2.8のコスパの良さ
とは「雲泥の差」がある。
また、この時代(EX DG)のSIGMA製レンズのNIKON
F(Ai)マウント版は、絞り環を持つ仕様であるから、
それを購入しておくならば(特にMFが主体のマクロ
では)他社機や他社ミラーレス機での使用汎用性が
高まる事は特筆すべき点だ。
(注:以降の時代のSIGMA NIKON F用レンズは
絞り環の無いG型仕様となってしまっている)
---
では、次の標準マクロレンズ。

レンズ購入価格:20,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS PEN-F(μ4/3機)
1980年代のMF標準(ハーフ)マクロレンズ。
「A」仕様のレンズであるから、現代のPENTAXの
デジタル一眼レフでもMFで問題なく使用できるが、
まあ今回は、少し捻って、μ4/3機での試用だ。
これで100mm、等倍マクロの換算仕様となる。

あるが、実用上での差異は、本レンズは1/2倍マクロ
とは言っても、標準マクロなので、最短撮影距離が
24cmと短く、一般的な100mm級等倍マクロでの
最短30~35cm程度よりも、ずっとWD(ワーキング
ディスタンス)を短く取れる点がある。
マクロレンズにおいての「WD」は、実用上では、長い
ものと短いもの両方が、撮影条件に準じて要求される。
まあ、様々な焦点距離のマクロレンズが世の中には
存在し、それらが全て「等倍」ならば、初級層等では
初「皆、同じ大きさに被写体が写るのでしょう?
じゃあ、マクロレンズで焦点距離が違う物は、
何故それが必要なのか?」
と疑問を持つ事であろう。
でも、実際には焦点距離毎でマクロの用途は異なる。
例え、被写体が同じ大きさ(等倍)で写ったとしても、
被写界深度、背景の取り込み範囲、遠近感等、
それらの描写傾向が、まるで異なるし、加えて、
WD(撮影距離)が、全然違うのだ。
WDが異なると、撮れる被写体や、撮影技法までも、
まるで変わってきてしまう。でも、それが長い・短い
事が良い訳なのではなく、被写体状況によりけりだ。
まあ、なので、今回のような、こういう特殊用法
(中望遠等倍マクロ相当だが、WDが短い)という
システムを組む必要性も、”無きにしもあらず”
という事となる。
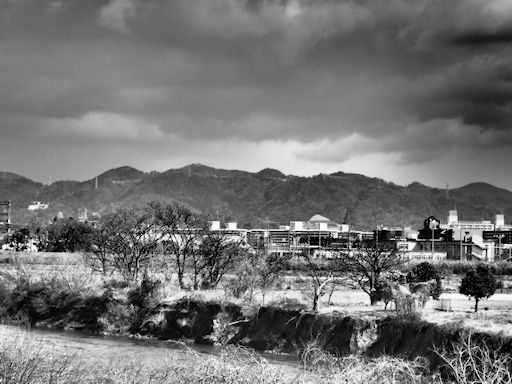
レンズだ。銀塩MF時代の(1/2倍)各社マクロは、
描写力に優れないものが殆どであったのだが、
本A50/2.8は、やや例外的なレンズである。
本レンズは銀塩時代より、常にPENTAX一眼レフ
で使っては来たが、たまにこのように、μ4/3機で
使うと、また、ずいぶんと異なる用途のマクロに
変貌する事が、なかなか興味深い発見であった。
現代において本レンズを「指名買い」する必然性は
殆ど無いが、たまたま安価な相場(1万円台前半
程度)のものを発見できたならば、購入は悪くは
無い選択だ。だがまあ、その相場であれば、前述の
EX50/2.8やTAMRON90マクロの初期型等が買えて
しまう訳だから、選択肢としてはやや難しいのだが、
マニア等であれば、安価なそれらをかたっぱしから
入手し、詳細に比較してみる事も、知的好奇心を
満たす意味では悪く無い。
---
では、3本目のレンズ。

レンズ購入価格:36,000円(中古)(以下、SP45/1.8)
使用カメラ:NIKON D5300(APS-C機)
2015年発売のフルサイズ対応単焦点(小口径)AF標準
レンズ。
ただし、これはマクロレンズでは無く、最短撮影距離
29cmで最大0.29倍の「寄れる標準レンズ」である。
だが今回はAPS-C機に装着している為、最大約0.44倍
となり、およそ1/2倍マクロに相当する、近接撮影に
強いレンズだ。(注:μ4/3機に装着すれば、さらに
撮影倍率を高める事が出来る。またデジタルテレコン
(クロップ)やデジタルズーム機能の併用で、さらに
仮想的に撮影倍率を高める事ができるが、それらの
いずれでも、最短撮影距離は29cmのままである)

(手ブレ補正内蔵、超音波モーター内蔵)にしては
さほど高価では無いので(注:開放F1.8という
仕様がビギナー層から見て不人気で、販売価格が
暴落したからだ)その為、コスパに優れる。
弱点が殆ど無いレンズの為、「最強50mm選手権」
シリーズ記事では、見事「優勝」の栄冠を得ている。
本レンズが、たった1つの「開放F1.8である」という
理由だけで(→F1.4の方が優れると消費者層は思う)
市場で正当に評価されていない状況は、TAMRONと
しても「たった数年間で、そこまで急速に消費者層
での評価レベルが下がっていたのか!?」と大誤算で
あった事だろう。でも、そういう現代のレンズ市場
(主力の消費者層はビギナーばかりだ。まあ、レンズ
が高付加価値化して、高価すぎる状況は、中上級層
から見て、魅力的だとは思えないからだ。加えて
本レンズは「標準レンズ」であり、同等品を所有して
いない中上級層は皆無だ。新たに買い増す必要は無い)
においては、やむを得ないのかも知れない。
でもまあ、わかっている人達は、優れたパフォーマンス
を持つレンズが、不人気で安価な相場となっているので
あれば、それを入手すれば、極めて「コスパが高い」
買い物となる訳だ。
以下、余談であるが、本レンズの時代(2015年頃)
から、TAMRON製の単焦点レンズ群の多くにおいて
フィルター径をφ67mmで統一する動きが始まった。
これは地味な改善であるが、ユーザーメリットが
大きい(様々な径の各種フィルターを買わなくて済む。
例えば、NDフィルターも、様々なTAMRON製レンズで
併用できるので、今回のようにNIKON D5300という
初級機に装着した場合でも、日中に最高シャッター
速度に到達する事なく、絞りをフルレンジで使用可)
・・ので好ましい。
特に、2019年頃からの市場では、安価なフィルター
類が、すべてディスコン(生産中止)となっていて、
現状で販売されているものが、旧来の製品と比べて
非常に高価な、「高付加価値型フィルター」
(例:コーティング、薄枠、撥水、高透過性、等)
のみになってしまった(値段は、数倍~十数倍まで
跳ね上がった。定価1万円を超えることもザラだ・汗)
状況なので、これらを沢山揃える事は、価格的にも
心情的にも困難な話だ。(→”売れていないから”と
言って、”単純に値上げをすれば良い”話でも無いで
あろう、ちょっと、この市場戦略には賛同しにくい)
よって、レンズ間でのフィルター径の統一は、かなり
歓迎すべき方向性である。
なお、銀塩MF時代(1970年代~1980年代)では、
オリンパス、ニコン、キヤノン等においては、
自社発売の、多くの交換レンズ群のフィルター径を
見事なまでに統一していた。
製造面でも利用者利便性でも優れている、その慣習が
無くなってしまったのは、”高度成長期”も終わって
しまい、日本の製造業での「ノウハウ」が失われて
しまったからなのだろうか? あるいはバブル期を
(1990年頃)迎えるにあたり、メーカー側の論理でも、
「フィルターの値段など、たかが知れている。
そんな物はユーザーが個々に買えば良い話であり、
設計側としては自由に、高性能のレンズを、好きな
フィルター径で作れば良いのだ!」
という考え方にシフトしてしまったのだろうか・・?
まあでも、メーカー側が好き放題に設計する事は、
「モノ作り」の観点からも、「消費者目線」からも、
あまり褒められた考え方では無い。
TAMRONが、そういう風に”原点に立ち返る姿勢”を
見せてくれつつあるのは、高く評価したいポイントだ。

であろう。ただ、マニア層等であれば、
「他にも、単焦点の標準レンズは持っているから、
被るので不要だよ」と思う人も多いかも知れないが、
過去シリーズ「最強50mmレンズ選手権」記事において、
およそ80本程度の所有標準レンズ群の中から、堂々の
優勝となった実力値は半端無い。一度、本SP45/1.8の
パフォーマンスとコスパを実感してみる事を推奨する。
なお、NIKON F(Ai)マウント版の場合、本SP45/1.8
であればG型仕様なので、他社機等での使用時には、
NIKON G型対応アダプターを使用すれば可能である。
ただし、姉妹レンズSP85/1.8等では、NIKON用でも
E型(電磁絞り)対応となってしまい、NIKON機以外
での利用は極めて厳しい事は注意点として挙げておく。
(注:E型の場合、NIKON一眼レフであったとしても
2007年製(例:NIKON D3、D300等)より前の古い
機体では「電磁絞り」は動作しないので使用不可だ。
また、TAMRON製E型仕様レンズでは、さらに厳しく、
2009年以降のNIKON機でないと使えない可能性が高い。
どうも、E型は汎用性が低く、個人的には好まない。
E型で期待される露出精度の向上の件であるが・・
高速連写時に機械絞り動作がバラつく事は、昔の
NIKON F5(1996年)あたりから、ずっと気になっては
いたが、NIKON機以外のミラーレス機等の高速連写機
で実絞り(絞り込み)測光で使えば、それは問題では
無くなる。つまりE型レンズである必然性は少ない。
なお、ここで”AFが効かない”等は、どうとでもなる
問題なので、露出値がバラバラになるよりはマシだ)
---
では、4本目のレンズ。

レンズ購入価格:10,000円(中古)(以下、DT50/1.8)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2010年に発売された、APS-C機(α Aマウント)専用
AF標準(中望遠画角)レンズ。
こちらもマクロレンズでは無い。最短撮影距離は
34cmで、最大0.2倍だ。これをAPS-C機α77Ⅱに
装着し、さらに同機に備わるデジタルテレコン機能を
2倍で用いると、最大約0.6倍となり、これも
1/2倍マクロに相当する、近接撮影に強いレンズだ。

ハイコスパ名玉編では、総合6位にランクインした。
だが、「エントリーレンズ」としての、本レンズの
SONY α Aマウント戦略での役割は短期間で終了し、
その後、2013年からは、SONYはα E(FE)マウント
のミラーレス機販売に主軸を移し、以降のα A機の
新製品はα77Ⅱ(2014年)、α99Ⅱ(2016年)の
たった2機種しか(国内では)展開が無い。
結局、α Aマウント・システムは自然消滅という
形になるだろうから、今更、本レンズを推奨し難い
点が痛いところだ。
まあでも、裏を返して考えてみれば、2010年前後
において、SONY α Aマウント機の市場展開が
厳しくなっていたからこそ、「エントリーレンズ」
を発売して、市場を活性化したいと思ったのが
本レンズ(や、DT35/1.8等の同時代のレンズ群)
が発売された理由であったのだろう。
で、あれば、その後のα FEマウントのフルサイズ
ミラーレス機での高付加価値化(→製品の値上げ)
により、本レンズDT50/1.8は、もう役目を完全に
終えてしまった、という話となる。
ある意味、勿体無い話であるが・・ 個人的には、
α A機はバリバリの現役機であり、完全終焉後に
おいても、できるだけ継続利用する為の準備等も、
ボチボチ進んでいる状況であるから、まあ、特に
問題だとは思っていない。
(他の市場分野での類似例を挙げれば、PCに詳しい
ユーザーであれば、サポート終了となったWindows 7
を使い続ける事は十分に可能であるが、PCのビギナー
層等では、何が何でもWindows 10以降にしないと、
”不安で使っていられない”という状態と似ている。
ポイントは、中身や全容を理解しているか否か?だ。
また、現代の様々な市場では「製品に詳しく無い人程、
高価な最新鋭機材を買う羽目になり、無駄な出費となる」
という状況とも言える。勿論カメラやレンズも同様だ。
→だから新鋭機材を使う人はビギナー層ばかりとなった)
---
さて次は、マシンビジョンレンズだ。

レンズ購入価格:18,000円(新品)
使用カメラ:PENTAX Q7(1/1.7型機)
2010年代後半に発売されたと思われる、2/3型対応
Cマウント、マシンビジョン(FA)用単焦点汎用
MFレンズ。

範疇では、これのスペックを考察するのは難しい。
SV-1214Hを一種のマクロレンズとして考えた場合、
最短撮影距離は10cm、その際の撮影範囲は、
PENTAX Q7装着時の実測(注:こういうシステム
においては、こんな簡単な実測すら高難易度となる)
では、おおよそだが長辺画角が約4cm程度となる。
Q7の1/1.7型センサーは長辺7.6mmなので、センサー
換算倍率は、およそ0.2倍程度だ。
まあ、仕様計算としては、ここまでで十分だが・・
これを写真(カメラ)界の常識を適用して、
「では、フルサイズ換算なら、何倍なのか?」
とか言い出すと、話がややこしくなる。
「原理」が異なるから、あまりやるべき計算では
無いのだが、まあ、無理やりやってみるとすれば
撮影範囲の長辺が、およそ4cmならば、36mm長辺の
フルサイズ機換算で0.9倍程度、ほぼ等倍マクロだ。
だが、Q7やCCTV用2/3型センサーとは縦横比
(アスペクト)が異なるし、それらですら現代では
16:9のワイドアスペクトで使う場合もある。
(注:地デジ対応のTVを、CCTVにおけるモニターに
する事も多々あるからだ)
また、本レンズSV-1214Hの最大解像力は
推定180LP/mm程度となるのだが(注:そういう
スペックも何処にも書かれていない)、その性能と
小サイズセンサーを高画素状態で使った場合での
ピクセルピッチは、適合しているのかどうか?
・・で、そもそも、フルサイズセンサー(35mm判
フィルム)と、Q7の1/1.7型センサーは、
およそ20倍も面積が異なる、果たしてそれらを
同列に扱っても良いのかどうか?
また、ベイヤー型配列のセンサーにおける、カラー
フィルターを用いて画素補完している状態において
レンズ解像力と画素ピッチは上手く対応するか否か?
あれこれと、考えるべき点が多すぎるので、前述の
ように「カメラの常識は通用しない」と言う訳だ。
このジャンル(マシンビジョン)の専門家向けの
レンズである。「カメラ界との接点は何も無い」
と考えるのが無難だろう。これを一般写真撮影用途
として使おうとする事自体が、異端中の異端だ。
マニア層も含め、全ての写真家層には完全非推奨の
レンズである。
---
では、6本目のマクロ。

レンズ購入価格:8,000円(中古)(以下、ZD35/3.5)
使用カメラ:OLYMPUS E-410(4/3機)
2005年発売のフォーサーズ(4/3)用のAF軽量等倍
マクロ。

2010年頃から、その展開を、ほぼ停止していた。
2013年のμ4/3機「OM-D E-M1」の発売時には、
オリンパスから「フォーサーズとμ4/3を統合した・・」
という主旨の発表があり、そこで事実上フォーサーズ
(4/3)は終焉してしまっていた。
その後、4/3機や4/3用レンズは中古市場でも大きく
相場が下落、逆に言えばコスパに優れ、買い易い
システムとなっている。
だが、4/3機本体に関しては、殆どが2000年代の
発売であり、2000年代の性能水準であるから、
(例:最高感度がISO3200止まり、1000万画素等)
発売後10年以上が経過して「仕様老朽化寿命」が来て
しまっている現代の状況では、新たには買い難い。
今回のように、そうした時代の4/3機を既に所有して
いるのであれば、それを使ってもまあ良いのだが、
より実用的にはOLYMPUS製MMF-2等の電子アダプター
を用いて、4/3用レンズをμ4/3機で使用するのが
簡便な解決策である。
母艦とするμ4/3機の種類によっては、像面位相差
AF機能がこの状態でも動作する為、4/3一眼レフでの
使用時に比べて極端にAF性能が劣る訳でもない。
そして、本レンズのようにマクロであれば、なおさら
であり、AFよりもMFで使う頻度が多い近接撮影では、
μ4/3機に備わるMFアシスト機能(ピーキングや
画面拡大機能)を用いる事で、オリジナルの4/3機
よりも、むしろ使い易い。
ただまあ、4/3のオリンパス純正マクロは、2機種
(ZD35/3.5およびZD50/2)しか存在しない
ので、その2本を入手してしまえば、もう4/3の
マクロは終わり(収集完了)となる。
まあ、その手の方向性(4/3システムの再興)を
考えるというマニア的な思考のみならず、シンプルに
μ4/3機用の「補助マクロレンズ」として考える
ならば、4/3用レンズは現代ではコスパが良いので、
μ4/3純正マクロを揃えるユーザーラインナップ
よりも効率的かも知れない。なお、4/3用マクロは、
各社μ4/3純正マクロとのスペック(仕様)被りは
無い為、その点でも収集の障害は少ない。

平面マクロ傾向も見られるが、現代において
わざわざ4/3用レンズに目をつける実践派マニア層
であれば、そのあたりの弱点は、どうとでも回避
できるスキルを持っている事であろう。
----
次は本記事ラストのマクロレンズとなる。

レンズ購入価格:9,000円(中古)(以下、NMD50/3.5)
使用カメラ:PANSONIC DMC-G6 (μ4/3機)
1980年代のMF標準ハーフ(1/2倍)マクロ。
個人的にはどうも、この銀塩MF時代の1/2倍標準
マクロは性能的に未成熟であるように思えてならない。
まあ、その分析は、様々なこの時代の標準マクロの
紹介記事で何度も行っているので、重複するので割愛
するが、大きくは2点あって
1)当時の設計技術的な限界点
2)当時のマクロレンズに求められる用途環境
が、現代とは大きく異なる点となっている。

あるいは変化が求められたのは、概ね1990年代であり、
その時代からの、AF/等倍の標準又は中望遠マクロは、
現代的視点からは、どれも高性能なものに変貌して
いて「現代でも十分に実用範囲だ」と認識している。
それら1990年代の完成度が高い標準・中望遠マクロ
は、2000年代では、主にデジタル対応、すなわち
新規プロトコル対応、後玉コーティングの改善、
APS-C機用に焦点距離を縮める、等の変更に留まり
大きな光学系の進化は、どれにも施されていない。
2010年代では、ミラーレス機用のマクロの発売が
ポイント(それらの一部は近代設計である)だが、
一眼レフ用の既存マクロは、もう完成度が高くて、
あまり改良の余地が無くなっていた。
よって、2010年代では、内蔵手ブレ補正機構の搭載、
超音波モーターの搭載、および非球面や特殊硝材
の使用が一般的になった為、それらを新規採用して
光学系の若干の改良が行われていたのだが・・
手ブレ補正、超音波モーター等は、ビギナー層の
比率が非常に増えた2010年代の消費者層に向けて
は、「付加価値」(製品を欲しいと思える理由)と
なり、それは同時に、メーカーや流通市場からも
「付加価値」(製品を高く売る為の理由、弁明)とも
なる。まあつまりコスパが酷く悪化している訳だ。
まあ、こんな状況なので、私は、個人的には
2000年代のマクロ製品を「性能的に必要十分に
達し、不要と思われる機能も入っておらず、かつ
中古相場が十分に安価である」という状態から、
「最もコスパが高い」と判断しており、近年では、
重点的にそれらを収集・使用している。
メーカー純正品は、まだそれらについてはコスパが
良く無い状態なので、あまり入手していないが、
レンズメーカー(サードパーティ)製の2000年代
マクロは、もう概ね収集が完了し、どれも良く写り、
コスパが良い事も確認済みなので、それらを実用上
において、とても機嫌良く使用している。
で、実用的には2000年代マクロで十分なのだが、
ちょっと「普通に良く写りすぎる」という僅かな
不満も存在している。・・なんと言うか、個性が無く
差別化要因も無い(誰が撮っても同じように普通に
良く撮れてしまう)訳だ。
そんな、テクニカルあるいは表現的な不満がある際に
おいては、銀塩MF時代の、ややエキセントリックな
特性(風変わりな、という意味。例:平面マクロ)を
持つマクロは、近年においては、ちょっと興味深い
対象となってきている。
勿論、前述のように時代的背景が異なるから、当時
の技術的、用途的な制限から、これらは現代的な
描写のマクロとは言えない。

マニア層も居る事であろう。
1970年代~1980年代のオールドマクロであっても
上手く条件を整えて撮影すれば、現代の高性能マクロ
に勝るとも劣らない描写力を発揮する事も出来る。
ただ、それは毎回それが可能なのでは決して無くて、
あくまで、上手く条件がハマった場合のみの話だ。
だが、職業的(実用的)用途の写真撮影ではなく、
あくまで趣味的な要素が大半の撮影であれば、その
措置(試行錯誤)に掛ける時間は、ほぼ無限に
許されている、という恵まれた状況である。
・・であれば、現代の新鋭マクロレンズのおよそ
ヒトケタも安価な(十数万円→1万数千円、数万円→
数千円)という、オールドマクロを上手く使いこなし、
現代の高性能マクロに匹敵するような写真が、
「偶然」でも「必然」でも、それが撮れたのであれば、
なんだか「とても痛快な気分」にならないだろうか?
相当に捻くれた考え方だ、とも言えるかもしれないが、
こういうのも、一種の「マニア道」である。
誰にでもそういう志向性がある訳では無いとは思うが、
「知的好奇心」は十分に満たしてくれると思う、
一部の中上級マニア層に向けては、オールドマクロは
割りと推奨できるレンズとなってくる。
----
さて、次回の本シリーズ記事は、
「最強マクロ選手権・標準マクロ・予選(4)」の予定。