今回記事も補足編の「高マニアック度B級編(後編)」
である。
「B級」とは「一級品では無いが、それなりの良さが
あるもの」という意味であって、今回後編記事でも
「それなりにマニアックな」レンズを8本取り上げる。
なお、前後編のいずれの「B級マニアック」レンズも、
誰にでも勧められるレンズとは、あまり思えない状況
であり、基本的には完全非推奨だが、あえて言うならば
「上級マニア御用達」という感じだ。
----
まず、今回最初のB級マニアックレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズは、SONY DT 30mm/f2.8 Macro SAM
(中古購入価格 10,000円)をマスターレンズとし
加えて、「ZENJIX soratama 72」(宙玉レンズ)
(新品購入価格 6,000円)を用いる。
カメラは、SONY α65(APS-C機)
2009年発売のAPS-C機専用AF単焦点準広角(標準画角)
マクロレンズDT30/2.8をマスター(主)レンズとして、
2014年発売の特殊アタッチメント型レンズ「Soratama」
を主レンズの前部に装着して撮影をする。
「Soratama」(宙玉)は、「ガラス玉に写った風景を
カメラで撮る」という仕組みであり、魚眼レンズとも
また違う、不思議な映像となる事が魅力のシステムだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
工作派のマニアの方が、2010年頃に発明。様々な
メディア等で紹介され、私も興味を持ったのだが、
当時は、システムを自作するしか無く、「ガラス玉を、
どうやって空中で固定するのだ?」という難しい
工作があり、「とりあえずは、ガラス玉を手で持って
撮るしか無いかな・・?」と思っていた。
まあ、巷で評判が良かった割に自作が困難であったので、
この発明者はその後、これを「事業化」した、つまり
「ZENJIX」というブランドを立ち上げ(起業して)、
そこで「soratama 72」を始めとする、いくつかの宙玉
レンズの製造と市販を始めた訳だ。
当初は直販しか無かったと思われるが、2015~2016年頃
には、代理店や量販店からの購入が可能となり、私も
ようやく、これを入手。価格はさほど高くは無かったが、
基本、材料原価も、そう高くは無いだろう。
この価格をどう見るかは、要は、この面倒なガラス玉の
加工が済んでいるのならば、「材料代+加工費」という
観点で「納得ができる」という判断である。
さて、実際に「soratama 72」を使ってみると、なかなか
使用システム(環境)を整えるのが難しい。
最大の課題は、レンズ前数cmに存在するガラス玉(宙玉)
にピントが合うような、WD(ワーキング・ディスタンス)
がとても短いレンズがなかなか存在しない事である。
(注:宙玉に写る映像は「虚像」であろうから、近接
焦点に拘る必要は無いかも知れない。だが、一応は
宙玉の写る大きさのバランスもあるから、近距離で
ピントを合わせる事を可能とする要素が必要だ)
また、「soratama 72」の型番が示すように、φ72mm
という大きい径の宙玉に装着できる大型レンズは、逆に
WDの長いものばかりだ。
これは、一般的な初級中級層の所有機材(レンズ)では
適合するものが見当たらず、「皆どうしているのだろう?」
という疑問が沸いた。中にはWDを伸ばす為の延長鏡筒を、
ボール紙等で自作した用例も聞いたが、その工作も面倒で
あるし、仕上がりの外観もスマートとは言えないし、
WDが長すぎて、宙玉が小さく写り過ぎているものも
多かったように思えた。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
私が色々と試行錯誤した結果、「soratama 72」に最適な
WDの短いレンズは、オーソドックスなものであれば、
本DT30/2.8(SAL30M28)で、又は、少々変則的なものは
LAOWA 15/4 が最適である事がわかり、以降は、
それらをマスター(主)レンズとして「soratama 72」
を楽しんでいる。
これは特に必須、というレンズ(宙玉)では無いが、
このユニークな写りは、なかなか興味深い。
これを使う為のシステム環境が面倒とは言えるが、
DT30/2.8をマスターとするのであれば、現代では中古
で1万円以下と安価なエントリー・マクロであるし、
縮退したSONY α(A)マウントでの課題も、α(A)機の
中古は安価であるし、あるいはAマウント絞りレバー調整
機構を持つマウントアダプターも色々発売されているので、
任意のAPS-C型以下ミラーレス機で使えば良い。
なお、宙玉の描写の性格上、フルサイズ機で使う意味は
殆ど無い。
----
では、次のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06504001.jpg]()
レンズは、Voigtlander SC SKOPAR 35mm/f2.5
(新品購入価格 30,000円)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
(注:フォクトレンダー綴りの変母音は省略)
2000年代初頭に発売されたNIKON S/旧CONTAX C
(レンジファインダー機)マウント兼用の準広角
MFレンズ。
同時期に発売されていた、同社VM(M)マウント品と
同等のレンズである。ただし、S/Cという特殊マウント
で生産数も少ないから、定価もだいぶ割高となっていた。
元々は、2000年代初頭に、NIKON およびCOSINAから
発売された数機種の特殊マウントのレンジ機、すなわち
NIKON S3/SP、Voigtlander BESSA-R2S/BESSA-R2C
の4機種用、あるいは過去のSおよびCマウントレンジ機
のみで使用可能な、特殊用途レンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06504525.jpg]()
本レンズについては、色々書きたい(言いたい)事は
あるが、限定生産だし、現代における入手性もゼロに
等しい。一切推奨も出来ない為、早々に終了しよう。
興味があれば、特殊レンズ第22回「フォクトレンダー・
レンジ機用レンズ」記事を参照の事。
----
では、3本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06504576.jpg]()
レンズは、RICOH XR RIKENON 200mm/f4
(中古購入価格 7,000円)(以下、XR200/4)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
出自不明、恐らくは1970年代末頃発売と思われる
単焦点MF望遠レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06504510.jpg]()
ごくオーソドックスな望遠レンズであるのだが、
XR RIKENONについては、初級中級マニア層に良く
知られている物として、「和製ズミクロン」つまり、
ライカの名玉と同等の描写力を持つ事で「神格化」
された「XR50mm/F2」のみが知られている程度で、
その他のXRリケノンが注目される事はまず無い。
まあ、そんな状況を持って、「XR50/2」以外の
リケノンを「B級マニアック」と見なしている訳だ。
XR(RIKENON)マウントは、ほぼ「PENTAX Kマウント」
と互換性がある。発売当時はAE機構等の差異から、
RICOH機(XRシリーズ)での利用が推奨されていたが・・
(注:この仕様がやや複雑なので、XR(RIKENON)レンズ
を志向するユーザーが少なかったのは確かだと思う)
現代においては、ミラーレス機用のKマウントアダプター
を用いる上では、PENTAXの(MF)Kマウントレンズと
同等に、差異なく用いる事ができる。
ただし、近年のPENTAX機(デジタル一眼レフ)では、
XRマウントレンズや、PENTAX純正でも1970年代後半頃
のレンズ(無印=P/K、またはM)は使用困難か、または
使用不能だ。よって、この1980年前後のKマウントレンズ
は、PENTAX機ではなく、マウントアダプターを介して、
ミラーレス機に装着して使うのが基本である。
なお、1970年代前半迄は、PENTAXはM42マウントの
旗手(市場をリードする)の立場であったが、M42の
ままではAE化への対応が困難であった為、1975年に
PENTAXは独自のKマウントに移行、RICOHも同様に
M42を諦め、PENTAX Kとほぼ互換のXRマウントで
追従した歴史であるが・・
そこから35年が過ぎた2010年頃では、PENTAXは、
RICOHの子会社となっていた次第だ。
前述のように、XR RIKENONはXR50mm/F2以外は
マニア層に全く注目されない状況が、もう何十年も
続いているのだが・・
XR50/2に限らず、どのXR RIKENONも、重欠点という
ようなものは殆ど無く、そこそこ良く写ると思う。
当時のXR RIKENONを、どのレンズメーカーが作って
いたかは不明であるが、たとえ、どのOEMメーカーで
あったとしても、MF時代末期においては単焦点レンズの
設計製造完成度は上がっている、いや、むしろメーカー
間での品質(や性能)の差異が無くなってきた時代が、
この1980年前後だったかも知れない訳だ。
ビギナー層が良くする質問で
「どこのメーカーのレンズが良く写るのか?」という
ものがあるが、それはもうこの40年も昔の時点で、その
差異は無くなっている。
それにもし、特定のメーカーのレンズの性能が悪かったら
それは売れず、この40年間の間に、とっくにレンズ市場
から撤退している事であろう。現代において生き残って
いるレンズ(カメラ)メーカーの全般的な品質や性能は、
どれをとっても同じようなものであり、差異が出ると
すれば、それは市場戦略上での、レンズ機種毎の企画や
コンセプトから来るものだ(例:高額に販売する為に
超高性能化を目指す等)
他のXR RIKENONについては
「特殊レンズ第36回 RICHO XR RIKENON編」記事を
参照の事。
----
さて、4本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06504529.jpg]()
レンズは、PENTAX Fish-eye-Takumar 17mm/f4
(中古購入価格 30,000円)(以下 Takumar17/4)
カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)
1960年代頃に発売されたM42マウントMF魚眼レンズで
あるが、NIKON(F)マウントに改造されたものが多数
あって、その改造品が中古市場に流れて来たものである。
(注:前編でも記載したが、TAKUMAR/Takumar 等の
レンズ上での表記は、時代により異なっている)
本レンズについては「特殊レンズ第28回魚眼レンズ」編
記事でも紹介していて、重複する為、詳細は割愛するが・・
要は、NIKON F/F2の時代(概ね1960年代前後)において
NIKON純正では、適切な魚眼レンズがラインナップされて
いなかった為、報道用途を中心にPENTAX M42マウントの
Takumar魚眼が多数、NIKON Fマウントへの改造が行われ
たのだが、その後、NIKONも魚眼レンズを発売し、不用に
なったTakumar改造品が、後年に中古市場に流れていた
ものである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06505091.jpg]()
ただし、NIKON F/F2(初期)の時代は、Fマウントと
言っても、露出(計)連動機構、すなわちAi機構は無い
ので、現代のNIKON機(デジタル一眼レフ)においては、
NIKON Df以外の機体では、ほぼ使用不能、または著しく
使用困難である。(=露出が全く合わない)
よって、ここも、前述のXR RIKENONと同じなのだが、
古くから普及していて、現代でもなお形状互換がある、
NIKON FおよびPENTAX Kマウントであっても、時代に
より使える組み合わせと使えないケースが発生するので
FやKマウントのレンズだからと言って、現代のNIKON/
PENTAXデジタル一眼レフに直接装着する事は得策では無く
FやKのマウントアダプターを介して、任意のミラーレス機
で使用する事が基本だ。
ただまあ、そこまで色々と無理をしてまで、本レンズを
使う意味は殆ど無い。基本設計は1960年代と、今から
60年も昔のレンズであり、あくまでオールドレンズだ。
それにレア品であり、本レンズは銀塩時代に購入したが
レアもの改造品が故に、高値な中古相場で買ってしまった
事も後年に後悔していた。
まあ、ぶっちゃけ言えばコスパが極めて悪い状態である。
----
では、5本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06505051.jpg]()
レンズは、TAMRON SP AF200-500mm/f5-6.3 Di LD [IF]
(Model A08) (中古購入価格 33,000円)
カメラは、NIKON D300(APS-C機)
2004年発売のAF超望遠ズームレンズ。
本レンズは、異マウントで2本所有しているが、
ほぼ100%、ボート競技の撮影用途で使っていた。
ボート競技撮影用超望遠ズームは、
2000年代においては、主に、本レンズの前モデル、
AF200-400mm/f5.6 LD [IF] (Model 75D)を2本使用し、
2010年代後半迄は、本レンズを2本使用、
2010年代末頃からは、本レンズの後継とも言えるTAMRON
100-400mm/f4.5-6.3 Di VC USD(Model A035)および、
SIGMA 100-400mm/f5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
の2本が主力レンズとなっている。
ただ、本レンズを使用していた2010年代においても、
本レンズは大型でハンドリング性能が悪い為、必要に応じ
旧モデル (Model 75D)や、ロングズーム・コンパクト機
FUJIFILM X-S1(2011年)を併用する事も多かった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06505066.jpg]()
長所は、望遠端500mmの超望遠ズームとしては、最軽量
(1200g台、三脚座が外せるので、さらに軽くなる)
であり、手持ちで振り回す事が出来る、最も焦点距離の
長い(ズーム)レンズである事だ。
まあでも、ここもユーザーのスキル次第であり、自身の
手ブレ限界(シャッター)速度を把握していなかったり
カメラをフルオートのままの設定で用いて、AUTO ISO
の低速限界(ISOが上に切り替わるシャッター速度)に
無頓着な初級中級層であれば、手持ち撮影は大変困難だ。
今回使用のシステムでは、軟弱な手ブレ補正機構等は
入っていないので、使うならば様々な原理理解は必須だ。
そういう点を理解しているのであれば、本レンズ以外
でも、500mm~600mm級のミラーレンズで、本レンズ
よりも軽量なものは存在する。ただまあ、焦点距離も
(開放)F値も固定なミラー(レンズ)では、撮影条件は
著しく制限されるだろうし、画質面でも、SP(高画質)
仕様の本レンズと、ミラー(レンズ)では雲泥の差がある。
結局、一眼レフ用の実用的な500mm以上の手持ち可能な
超望遠ズームレンズは、本レンズ(A08型)が史上唯一
という事となる。
なお、他社あるいは他の500mm以上の超望遠ズームは
本レンズより遥かに重量が重く、長時間の手持ち使用は
疲労を回復する術(すべ)が大変困難だ。ビギナー層等で
あれば、1時間も経たないうちに使用不能になるだろう。
ちなみに疲労対策の具体例としては「長時間構えない事」
がある。レンズを構えたら数秒以内に撮影し、それ以上は
システムを維持(ホールド)しない。ただし、数秒以内に
撮る為には、AFの高速性とかよりも、自分がどんな構図で
どのように撮りたいかを事前に想定し、ズーミングや
各種カメラ設定を事前に行ってから構えないと無理であり、
ファインダーを覗きながら、あれこれと設定や構図を迷って
いる状況では、絶対に短時間での撮影は無理だ。
だからまあ、初級中級層では、余計に疲労を蓄積してしまう
訳であり、かつ、外から見ていて、カメラを構えてから
いつまでもモタモタと迷ってシャッターが切れない状況を
見れば、たいてい、そのカメラマンのスキル(技能)は推察
できる。数秒以内で、テキパキと撮影ができる人は上級者
であり、何十秒あるいは1分以上もかかっていれば、完全な
初級者である。
観光地等で、誰がが記念撮影を行っているのを見て、周囲の
通行人等が気を使って、待ってあげている事が良くある。
しかし撮影者が初級者であると、何十秒もシャッターが切れず、
通行人がずっと待ち続けていて、下手をすれば信号待ちの
ように行列すら出来てしまう。
でも、撮影者のビギナーは、そもそも写真をとる事に必死で、
周囲の状況等も全く見えていないので、周囲に迷惑をかけて
いる事すら、まるっきり気がついていない。
そこで、撮影される方の団体や人物等が、気を使い、周囲に
気が散って、良い表情どころか、視線が(通行人等の)左右に
泳いでしまっている。これでは良い記念撮影は出来ない。
これは撮影者の責任であり、情けない状態だ。
どんな状況でも、構えてから数秒以内に撮影が出来るように
修練する事が、ビギナー層を脱出する1つの条件となる。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06505068.jpg]()
さて、本レンズの弱点は、大型で、ハンドリング性能に劣る
事である。具体的には、カメラバッグには入らず、専用又は
汎用の「超望遠ケース」を使わないと移動(運搬)ができない。
当然、撮影前にも、組み立ての準備作業が必要となる為、
たとえば、不意に現れた遠距離の野鳥等への即時対応が
困難である。
他にも細かい弱点はいくつかあるが、微細なものなので
割愛する。本レンズのような、手ブレ補正も超音波モーター
も無い、ある意味「硬派」なレンズを使いこなすのは
正直言えば、初級中級層では無理だ。だから、本レンズを
使うユーザー層は、それ以上のレベルである事が前提
(必須条件)であるならば、細かい弱点等は回避できる
スキルを身につけている事であろう。
なお、400mm級超望遠ズーム(一眼レフ用)であれば、
2017年以降において、初級中級層でも手持ち撮影が可能な
レンズは、SIGMAとTAMRONから各1機種発売されている。
(注:μ4/3機用でも、Panasonicから同等仕様品が発売
されているが、これは定価25万円超えの高額製品だ、
また、2020年にはOLYMPUSからも同等仕様の超望遠
ズームが発売、しかしこれも高額レンズである)
所有範囲での超望遠レンズ群の得失については、
*特殊レンズ第6回「超望遠ズーム」編
*最強超望遠レンズ選手権~決勝戦
記事等を参照の事。
----
さて、6本目は、トイレンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06511164.jpg]()
レンズは、HOLGA LENS 25mm/f8 HL(W)-SN
(新品購入価格3,000円)
カメラは、SONY NEX-3(APS-C機)
2010年代に発売の準広角画角相当MFトイレンズ。
「Lo-Fi」とは何か? あるいは、その存在意義を
理解していないと、こうした(トイ)レンズを使う
意味がわからない事であろう。
そうした内容の詳細については、
*匠の写真用語辞典第5回記事 項目「ローファイ」
*特殊レンズ第3回「HOLGA」編記事
を参照して貰えれば良いのだが、ただ記事を読んだ
だけではやはり理解は困難だと思われ、実際にこうした
トイレンズ等を入手し、Lo-Fi技法や、Lo-Fi表現を
常日頃から試してみた上で無いと、永久に良くわからない
ままだと思う。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06511161.jpg]()
だけどまあ、世の中の写真界、あるいはカメラマンの
99%は「Hi-Fi」志向だ、つまり、被写体がはっきり
くっきり写っている事が、王道であり、正当な写真で
あると思い込んでいる。
まあ、これは「写真」を「映像記録」の側面でしか
見ていない、という事であろう。
・・まあ、あれこれと説明しても理解が困難な世界だ。
今回は、別の芸術分野でのわかりやすい例をあげれば、
美術(絵画)の世界での「印象派」が、その1例であろう。
印象派は1800年代後半~末くらいに、旧来の絵画とは
全く別のものとして誕生したスタイルである。
近年、私は美術史を良く勉強していて、その分野にも
だいぶ詳しくなってきているが、ここで印象派の誕生の
経緯等について説明しだすと、とても長くなるので
残念ながら割愛しよう。
要は、それまでの絵画では、対象が、はっきりくっきり
描けている「Hi-Fi絵画」であった事とは、対極の立場
で生まれた「Lo-Fi」絵画の一種が印象派だ。
当然、当初は美術評論家等からはボロクソに言われた。
世間でも同様であり、まあ、いずれも新分野の芸術の
意味や表現が、全く理解できなかった訳だ。
(注:ごく近年での美術史の研究成果によると、印象派
の登場時の批評家からの意見は、さほど酷いものでは
なく、むしろ殆どが好意的だったという解釈もある模様)
しかし、数十年でその様式は難なく定着、百数十年が
経過した現代においては、絵画オークション等で高額に
落札される絵の多くは、「印象派」であり、絶大な人気
と、高度な芸術性が認められている次第である。
絵画は誰も描ける訳では無いので、まあ敷居が高い
芸術分野であろう、しかし現代における写真は違う。
本格的なカメラを持っていなくても、スマホや携帯の
内蔵カメラでも写真は撮れるので、世の中のほぼ全員が
カメラマンである。すなわち「一般大衆」に過ぎないし、
それらが志向するのは芸術では無く、映像記録であり、
その目的(用途、志向性)は「Hi-Fi映像」である。
(注:近代のスマホ撮影では、SNS用途等において
「加工・編集」や「盛る」事は常識化しつつある)
だから逆に言えば、その状況において、Lo-Fiやらの
高度な作画意図や芸術性を持たせるのは一般大衆では
心理的に理解が無理であり、綺麗に写っているHi-Fi写真
だけが正しいものだ、と強く思い込んでいる。
印象派、あるいはそれ以降の近代芸術において、絵画の
表現や芸術性は、極めて多数の新しい様式を生み出した。
今時においては、もはや「何でもあり」の状況である。
現代の写真の世界での一般大衆における価値感は、まるで
中世の絵画界のようであり、300年や500年も前の感覚
となっている。写真が、印象派や近代絵画の様な芸術性を
得る為には、いったいあと何十年、いや何百年かかる
のであろうか? なんだか、ずいぶんとつまらない世情だ。
----
さて、7本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06511191.jpg]()
レンズは、CANON (New) FD 35mm/f2
(中古購入価格 10,000円)(以下、NFD35/2)
カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)
1979年発売の単焦点準広角MFレンズ。
1980年代のCANON製 New FD レンズにおいては、
開放F値がF2のレンズは6本存在するが、内、5本を
特殊レンズ第46回「CANON New FD F2レンズ編」
で紹介している。
特に特筆すべきマニアック性は無いレンズではあるが、
注目すべきは、この時代にCANONが、F2という明るい
口径比のレンズを多数の焦点距離でラインナップして
いた事である。
当時、同様の戦略を取ったのは、OLYMPUSであり、
マニア層では「ZUIKOは、20(21)mmから250mm迄、
全てF2で揃える事ができる」と、良く言われていた。
ちなみに、OM20mm/F2は医療用特殊マクロ(近年に
中一光学から復刻された)ので、OM ZUIKOの実用写真
レンズであれば、21mmからのF2ラインナップである。
まあ、実際にはOM ZUIKOのF2級はいずれも高価な
レンズであったので、それをコンプリートできる
(OM)マニアは皆無に近い状況であったとは思われるが
それが(OM)マニアの憧れや機材購入モチベーションと
なっていたのは確かであろう。
参考:特殊レンズ第33回「OLYMPUS OM F2レンズ」
CANONにおいて、もし、この(NEW)FD F2級レンズの
ラインナップ戦略が、OLYMPUS OM党の、その心理状態
を理解した上で行われていたならば(つまり、New FD
でも同様にF2レンズを揃えたいと、CANON党に思わせる)
これはなかなか高度な、マニアックな心理を突いてきた
市場戦略だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06511166.jpg]()
ちなみに、New FDについては、開放F2レンズは、
24mm,28mm,35mm,50mm,100mm,135mmの
6本が存在し、50mmを除く5本を、前述の特殊レンズ
第46回記事で紹介している。
なおNew FDレンズで、OMのようにズラリと焦点距離を
並べていないのは、OM-SYSTEMでは「小型軽量化」と
「高い汎用性」という、強い設計コンセプトが存在
していて、無理やりF2より明るい開放値の焦点距離の
レンズを作ろうとはしなかったが、CANON NEW FDに
おいては、F2よりも明るいF1.2~F1.8級のレンズも
焦点距離によっては存在していたからである。
だからまあ、CANONにおいては、あまり強く「F2で
揃える」というラインナップ戦略は無かったのかも
知れない。
しかし、実例があって、実は、上記の私が所有して
いるNew FD F2レンズ群のうち、3本のレンズ、
24mm/F2,28mm/F2,35mm/F2は、銀塩時代に
同じタイミングで中古入手した、という経緯がある。
つまり、前オーナー(誰だかは不明)は24~35mm
を「全てF2で揃えたかった」訳であり、同様に、私も
全く同じ理由で、この3本の中古レンズを揃えたかった
のだ。つまり、ここが「マニア心理」となっていて
一種の「コンプリート願望」が、この根源であろう。
----
では、今回ラストのB級マニアックシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06512559.jpg]()
レンズは、MINOLTA RF ROKKOR 250mm/f5.6
(中古購入価格 35,000円)(以下、RF250/5.6)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)
恐らくは1980年頃の発売と思われる小型軽量ミラーレンズ。
MD型の時代の製品であるが、絞りが無いので、カメラ側の
露出モードの差異、すなわちこの時代はMCからMD/New MD
への転換期や転換後であり、一眼レフ本体も、初の両優先
AE機MINOLTA XD(1977年、銀塩一眼第6回記事)や、
初のプログラムAE機MINOLTA X-700(1981年、銀塩一眼
第10回記事)といった風に、AE機能の差異があったのだが、
本レンズの場合は、それらの差異に影響される訳では無い。
また、現代においては、ミラーレス機でアダプターで使う
上では、MD型か否か等のAE機能の差異はどうでも良い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06512517.jpg]()
さて、本レンズはミラー(レンズ)としては、史上最も
小型軽量であったと思われる。
一般的にミラーレンズと言えば、500mm級が中心であり
稀に旧ソ連製等で、800mmや1000mmの物が存在した。
(注:軍事用途の民生転用品であろうか?)
国産でも、SIGMAやPENTAXでは600mm級もあった。
(注:PENTAXは、ズームミラーレンズという特殊仕様)
小さい(短い)方では、350mm級が、やはり旧ソ連製
であったが、もはや、ソビエト崩壊から数十年経った
現代では入手困難であろう。
近年においては、KENKO社から400mm級(および
一部では500mm)ミラーが発売されており、これらは
かなり小型軽量だ。
また、TOKINAより300mmのμ4/3機専用ミラーが
発売されていて、これも相当に小型軽量ながら、
600mmの換算画角と、80cmの最短撮影距離が特徴で
ミラーマクロ、という新しく現代的な撮影技法が使える。
ただまあ、KENKOやTOKINAの製品は、2010年代と
新しいので、銀塩時代においては、本RF250/5.6が、
最も小型軽量であるとともに、焦点距離的にも、
やはり250mmは、最も短い仕様であろう。
これらのミラーレンズのうち、4機種に関しては、
特殊レンズ第18回「ミラーレンズ」編記事で紹介済みだ。
長所はその史上最短焦点距離ミラー(レンズ)としての
歴史的価値である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_06512537.jpg]()
ただし、弱点が多数あって、まず描写力はお世辞にも
褒められたものでは無い、おまけに最短撮影距離も
2.5mと長く、被写体に対峙した際、近くのものが
全く撮れずに、かなりイライラとする。
さらには、超レアものであり、入手が大変困難だ。
私が銀塩時代に入手後、1、2度だけしか中古市場では
見かけた事がなく、しかも「投機対象」となっていて、
性能や実用性から見たら不条理なほどの高額相場で
あった。高値で買う意味が全く見出せないレンズである。
もう少し言えば、このRF250/5.6は、ミラー加工の
耐久性が弱く、「経年劣化が激しい」という情報があり、
後年において、ミラーが高品質を保てている個体は
極めて少ない。いくつか中古市場に出てきた個体でも
ミラー劣化(蒸着の剥げ)が発生していたものもあった。
幸いにして、私の所有個体はミラー劣化は無いのだが、
他の個体については、殆ど所有者が居ない状況なので、
現代において、いったいどうなっているか?は不明だ。
(追記:ごく最近、知人のマニア氏が、本レンズの
ジャンク品を入手したが、修理不能なまでに劣化した
状態だった模様だ)
まあ、現代において、本レンズを指名買いする必然性は
皆無に等しい。小型軽量のミラー(レンズ)が欲しい
ならば前述のTOKINA 300mm/F6.3が、本RF250/5.6
よりも何倍も何十倍も、使用利便性が高い。
TOKINA版は、数年前まで現行製品だったので、入手は
さほど困難では無いだろう。そちらの中古であれば
1万円台後半と安価だ。
本レンズを所有する意味は「歴史的価値」における
マニアック度や研究対象としての資料にしかなり得ず
現代において実用的なレンズであるとは全く思えない。
----
さて、今回の補足編「高マニアック度B級編」後編記事は、
このあたり迄で。次回は通常記事となる予定だ。
である。
「B級」とは「一級品では無いが、それなりの良さが
あるもの」という意味であって、今回後編記事でも
「それなりにマニアックな」レンズを8本取り上げる。
なお、前後編のいずれの「B級マニアック」レンズも、
誰にでも勧められるレンズとは、あまり思えない状況
であり、基本的には完全非推奨だが、あえて言うならば
「上級マニア御用達」という感じだ。
----
まず、今回最初のB級マニアックレンズ。
Clik here to view.

(中古購入価格 10,000円)をマスターレンズとし
加えて、「ZENJIX soratama 72」(宙玉レンズ)
(新品購入価格 6,000円)を用いる。
カメラは、SONY α65(APS-C機)
2009年発売のAPS-C機専用AF単焦点準広角(標準画角)
マクロレンズDT30/2.8をマスター(主)レンズとして、
2014年発売の特殊アタッチメント型レンズ「Soratama」
を主レンズの前部に装着して撮影をする。
「Soratama」(宙玉)は、「ガラス玉に写った風景を
カメラで撮る」という仕組みであり、魚眼レンズとも
また違う、不思議な映像となる事が魅力のシステムだ。
Clik here to view.

メディア等で紹介され、私も興味を持ったのだが、
当時は、システムを自作するしか無く、「ガラス玉を、
どうやって空中で固定するのだ?」という難しい
工作があり、「とりあえずは、ガラス玉を手で持って
撮るしか無いかな・・?」と思っていた。
まあ、巷で評判が良かった割に自作が困難であったので、
この発明者はその後、これを「事業化」した、つまり
「ZENJIX」というブランドを立ち上げ(起業して)、
そこで「soratama 72」を始めとする、いくつかの宙玉
レンズの製造と市販を始めた訳だ。
当初は直販しか無かったと思われるが、2015~2016年頃
には、代理店や量販店からの購入が可能となり、私も
ようやく、これを入手。価格はさほど高くは無かったが、
基本、材料原価も、そう高くは無いだろう。
この価格をどう見るかは、要は、この面倒なガラス玉の
加工が済んでいるのならば、「材料代+加工費」という
観点で「納得ができる」という判断である。
さて、実際に「soratama 72」を使ってみると、なかなか
使用システム(環境)を整えるのが難しい。
最大の課題は、レンズ前数cmに存在するガラス玉(宙玉)
にピントが合うような、WD(ワーキング・ディスタンス)
がとても短いレンズがなかなか存在しない事である。
(注:宙玉に写る映像は「虚像」であろうから、近接
焦点に拘る必要は無いかも知れない。だが、一応は
宙玉の写る大きさのバランスもあるから、近距離で
ピントを合わせる事を可能とする要素が必要だ)
また、「soratama 72」の型番が示すように、φ72mm
という大きい径の宙玉に装着できる大型レンズは、逆に
WDの長いものばかりだ。
これは、一般的な初級中級層の所有機材(レンズ)では
適合するものが見当たらず、「皆どうしているのだろう?」
という疑問が沸いた。中にはWDを伸ばす為の延長鏡筒を、
ボール紙等で自作した用例も聞いたが、その工作も面倒で
あるし、仕上がりの外観もスマートとは言えないし、
WDが長すぎて、宙玉が小さく写り過ぎているものも
多かったように思えた。
Clik here to view.

WDの短いレンズは、オーソドックスなものであれば、
本DT30/2.8(SAL30M28)で、又は、少々変則的なものは
LAOWA 15/4 が最適である事がわかり、以降は、
それらをマスター(主)レンズとして「soratama 72」
を楽しんでいる。
これは特に必須、というレンズ(宙玉)では無いが、
このユニークな写りは、なかなか興味深い。
これを使う為のシステム環境が面倒とは言えるが、
DT30/2.8をマスターとするのであれば、現代では中古
で1万円以下と安価なエントリー・マクロであるし、
縮退したSONY α(A)マウントでの課題も、α(A)機の
中古は安価であるし、あるいはAマウント絞りレバー調整
機構を持つマウントアダプターも色々発売されているので、
任意のAPS-C型以下ミラーレス機で使えば良い。
なお、宙玉の描写の性格上、フルサイズ機で使う意味は
殆ど無い。
----
では、次のシステム
Clik here to view.

(新品購入価格 30,000円)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
(注:フォクトレンダー綴りの変母音は省略)
2000年代初頭に発売されたNIKON S/旧CONTAX C
(レンジファインダー機)マウント兼用の準広角
MFレンズ。
同時期に発売されていた、同社VM(M)マウント品と
同等のレンズである。ただし、S/Cという特殊マウント
で生産数も少ないから、定価もだいぶ割高となっていた。
元々は、2000年代初頭に、NIKON およびCOSINAから
発売された数機種の特殊マウントのレンジ機、すなわち
NIKON S3/SP、Voigtlander BESSA-R2S/BESSA-R2C
の4機種用、あるいは過去のSおよびCマウントレンジ機
のみで使用可能な、特殊用途レンズである。
Clik here to view.
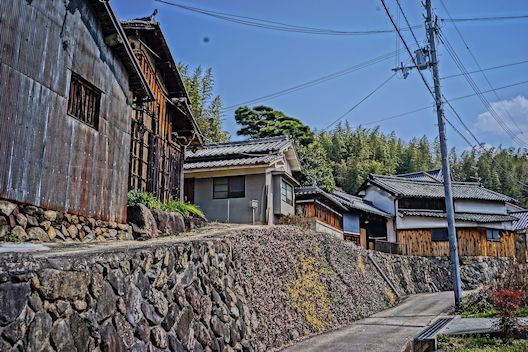
あるが、限定生産だし、現代における入手性もゼロに
等しい。一切推奨も出来ない為、早々に終了しよう。
興味があれば、特殊レンズ第22回「フォクトレンダー・
レンジ機用レンズ」記事を参照の事。
----
では、3本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 7,000円)(以下、XR200/4)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
出自不明、恐らくは1970年代末頃発売と思われる
単焦点MF望遠レンズ。
Clik here to view.

XR RIKENONについては、初級中級マニア層に良く
知られている物として、「和製ズミクロン」つまり、
ライカの名玉と同等の描写力を持つ事で「神格化」
された「XR50mm/F2」のみが知られている程度で、
その他のXRリケノンが注目される事はまず無い。
まあ、そんな状況を持って、「XR50/2」以外の
リケノンを「B級マニアック」と見なしている訳だ。
XR(RIKENON)マウントは、ほぼ「PENTAX Kマウント」
と互換性がある。発売当時はAE機構等の差異から、
RICOH機(XRシリーズ)での利用が推奨されていたが・・
(注:この仕様がやや複雑なので、XR(RIKENON)レンズ
を志向するユーザーが少なかったのは確かだと思う)
現代においては、ミラーレス機用のKマウントアダプター
を用いる上では、PENTAXの(MF)Kマウントレンズと
同等に、差異なく用いる事ができる。
ただし、近年のPENTAX機(デジタル一眼レフ)では、
XRマウントレンズや、PENTAX純正でも1970年代後半頃
のレンズ(無印=P/K、またはM)は使用困難か、または
使用不能だ。よって、この1980年前後のKマウントレンズ
は、PENTAX機ではなく、マウントアダプターを介して、
ミラーレス機に装着して使うのが基本である。
なお、1970年代前半迄は、PENTAXはM42マウントの
旗手(市場をリードする)の立場であったが、M42の
ままではAE化への対応が困難であった為、1975年に
PENTAXは独自のKマウントに移行、RICOHも同様に
M42を諦め、PENTAX Kとほぼ互換のXRマウントで
追従した歴史であるが・・
そこから35年が過ぎた2010年頃では、PENTAXは、
RICOHの子会社となっていた次第だ。
前述のように、XR RIKENONはXR50mm/F2以外は
マニア層に全く注目されない状況が、もう何十年も
続いているのだが・・
XR50/2に限らず、どのXR RIKENONも、重欠点という
ようなものは殆ど無く、そこそこ良く写ると思う。
当時のXR RIKENONを、どのレンズメーカーが作って
いたかは不明であるが、たとえ、どのOEMメーカーで
あったとしても、MF時代末期においては単焦点レンズの
設計製造完成度は上がっている、いや、むしろメーカー
間での品質(や性能)の差異が無くなってきた時代が、
この1980年前後だったかも知れない訳だ。
ビギナー層が良くする質問で
「どこのメーカーのレンズが良く写るのか?」という
ものがあるが、それはもうこの40年も昔の時点で、その
差異は無くなっている。
それにもし、特定のメーカーのレンズの性能が悪かったら
それは売れず、この40年間の間に、とっくにレンズ市場
から撤退している事であろう。現代において生き残って
いるレンズ(カメラ)メーカーの全般的な品質や性能は、
どれをとっても同じようなものであり、差異が出ると
すれば、それは市場戦略上での、レンズ機種毎の企画や
コンセプトから来るものだ(例:高額に販売する為に
超高性能化を目指す等)
他のXR RIKENONについては
「特殊レンズ第36回 RICHO XR RIKENON編」記事を
参照の事。
----
さて、4本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 30,000円)(以下 Takumar17/4)
カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)
1960年代頃に発売されたM42マウントMF魚眼レンズで
あるが、NIKON(F)マウントに改造されたものが多数
あって、その改造品が中古市場に流れて来たものである。
(注:前編でも記載したが、TAKUMAR/Takumar 等の
レンズ上での表記は、時代により異なっている)
本レンズについては「特殊レンズ第28回魚眼レンズ」編
記事でも紹介していて、重複する為、詳細は割愛するが・・
要は、NIKON F/F2の時代(概ね1960年代前後)において
NIKON純正では、適切な魚眼レンズがラインナップされて
いなかった為、報道用途を中心にPENTAX M42マウントの
Takumar魚眼が多数、NIKON Fマウントへの改造が行われ
たのだが、その後、NIKONも魚眼レンズを発売し、不用に
なったTakumar改造品が、後年に中古市場に流れていた
ものである。
Clik here to view.

言っても、露出(計)連動機構、すなわちAi機構は無い
ので、現代のNIKON機(デジタル一眼レフ)においては、
NIKON Df以外の機体では、ほぼ使用不能、または著しく
使用困難である。(=露出が全く合わない)
よって、ここも、前述のXR RIKENONと同じなのだが、
古くから普及していて、現代でもなお形状互換がある、
NIKON FおよびPENTAX Kマウントであっても、時代に
より使える組み合わせと使えないケースが発生するので
FやKマウントのレンズだからと言って、現代のNIKON/
PENTAXデジタル一眼レフに直接装着する事は得策では無く
FやKのマウントアダプターを介して、任意のミラーレス機
で使用する事が基本だ。
ただまあ、そこまで色々と無理をしてまで、本レンズを
使う意味は殆ど無い。基本設計は1960年代と、今から
60年も昔のレンズであり、あくまでオールドレンズだ。
それにレア品であり、本レンズは銀塩時代に購入したが
レアもの改造品が故に、高値な中古相場で買ってしまった
事も後年に後悔していた。
まあ、ぶっちゃけ言えばコスパが極めて悪い状態である。
----
では、5本目のシステム
Clik here to view.

(Model A08) (中古購入価格 33,000円)
カメラは、NIKON D300(APS-C機)
2004年発売のAF超望遠ズームレンズ。
本レンズは、異マウントで2本所有しているが、
ほぼ100%、ボート競技の撮影用途で使っていた。
ボート競技撮影用超望遠ズームは、
2000年代においては、主に、本レンズの前モデル、
AF200-400mm/f5.6 LD [IF] (Model 75D)を2本使用し、
2010年代後半迄は、本レンズを2本使用、
2010年代末頃からは、本レンズの後継とも言えるTAMRON
100-400mm/f4.5-6.3 Di VC USD(Model A035)および、
SIGMA 100-400mm/f5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
の2本が主力レンズとなっている。
ただ、本レンズを使用していた2010年代においても、
本レンズは大型でハンドリング性能が悪い為、必要に応じ
旧モデル (Model 75D)や、ロングズーム・コンパクト機
FUJIFILM X-S1(2011年)を併用する事も多かった。
Clik here to view.

(1200g台、三脚座が外せるので、さらに軽くなる)
であり、手持ちで振り回す事が出来る、最も焦点距離の
長い(ズーム)レンズである事だ。
まあでも、ここもユーザーのスキル次第であり、自身の
手ブレ限界(シャッター)速度を把握していなかったり
カメラをフルオートのままの設定で用いて、AUTO ISO
の低速限界(ISOが上に切り替わるシャッター速度)に
無頓着な初級中級層であれば、手持ち撮影は大変困難だ。
今回使用のシステムでは、軟弱な手ブレ補正機構等は
入っていないので、使うならば様々な原理理解は必須だ。
そういう点を理解しているのであれば、本レンズ以外
でも、500mm~600mm級のミラーレンズで、本レンズ
よりも軽量なものは存在する。ただまあ、焦点距離も
(開放)F値も固定なミラー(レンズ)では、撮影条件は
著しく制限されるだろうし、画質面でも、SP(高画質)
仕様の本レンズと、ミラー(レンズ)では雲泥の差がある。
結局、一眼レフ用の実用的な500mm以上の手持ち可能な
超望遠ズームレンズは、本レンズ(A08型)が史上唯一
という事となる。
なお、他社あるいは他の500mm以上の超望遠ズームは
本レンズより遥かに重量が重く、長時間の手持ち使用は
疲労を回復する術(すべ)が大変困難だ。ビギナー層等で
あれば、1時間も経たないうちに使用不能になるだろう。
ちなみに疲労対策の具体例としては「長時間構えない事」
がある。レンズを構えたら数秒以内に撮影し、それ以上は
システムを維持(ホールド)しない。ただし、数秒以内に
撮る為には、AFの高速性とかよりも、自分がどんな構図で
どのように撮りたいかを事前に想定し、ズーミングや
各種カメラ設定を事前に行ってから構えないと無理であり、
ファインダーを覗きながら、あれこれと設定や構図を迷って
いる状況では、絶対に短時間での撮影は無理だ。
だからまあ、初級中級層では、余計に疲労を蓄積してしまう
訳であり、かつ、外から見ていて、カメラを構えてから
いつまでもモタモタと迷ってシャッターが切れない状況を
見れば、たいてい、そのカメラマンのスキル(技能)は推察
できる。数秒以内で、テキパキと撮影ができる人は上級者
であり、何十秒あるいは1分以上もかかっていれば、完全な
初級者である。
観光地等で、誰がが記念撮影を行っているのを見て、周囲の
通行人等が気を使って、待ってあげている事が良くある。
しかし撮影者が初級者であると、何十秒もシャッターが切れず、
通行人がずっと待ち続けていて、下手をすれば信号待ちの
ように行列すら出来てしまう。
でも、撮影者のビギナーは、そもそも写真をとる事に必死で、
周囲の状況等も全く見えていないので、周囲に迷惑をかけて
いる事すら、まるっきり気がついていない。
そこで、撮影される方の団体や人物等が、気を使い、周囲に
気が散って、良い表情どころか、視線が(通行人等の)左右に
泳いでしまっている。これでは良い記念撮影は出来ない。
これは撮影者の責任であり、情けない状態だ。
どんな状況でも、構えてから数秒以内に撮影が出来るように
修練する事が、ビギナー層を脱出する1つの条件となる。
Clik here to view.

事である。具体的には、カメラバッグには入らず、専用又は
汎用の「超望遠ケース」を使わないと移動(運搬)ができない。
当然、撮影前にも、組み立ての準備作業が必要となる為、
たとえば、不意に現れた遠距離の野鳥等への即時対応が
困難である。
他にも細かい弱点はいくつかあるが、微細なものなので
割愛する。本レンズのような、手ブレ補正も超音波モーター
も無い、ある意味「硬派」なレンズを使いこなすのは
正直言えば、初級中級層では無理だ。だから、本レンズを
使うユーザー層は、それ以上のレベルである事が前提
(必須条件)であるならば、細かい弱点等は回避できる
スキルを身につけている事であろう。
なお、400mm級超望遠ズーム(一眼レフ用)であれば、
2017年以降において、初級中級層でも手持ち撮影が可能な
レンズは、SIGMAとTAMRONから各1機種発売されている。
(注:μ4/3機用でも、Panasonicから同等仕様品が発売
されているが、これは定価25万円超えの高額製品だ、
また、2020年にはOLYMPUSからも同等仕様の超望遠
ズームが発売、しかしこれも高額レンズである)
所有範囲での超望遠レンズ群の得失については、
*特殊レンズ第6回「超望遠ズーム」編
*最強超望遠レンズ選手権~決勝戦
記事等を参照の事。
----
さて、6本目は、トイレンズである。
Clik here to view.

(新品購入価格3,000円)
カメラは、SONY NEX-3(APS-C機)
2010年代に発売の準広角画角相当MFトイレンズ。
「Lo-Fi」とは何か? あるいは、その存在意義を
理解していないと、こうした(トイ)レンズを使う
意味がわからない事であろう。
そうした内容の詳細については、
*匠の写真用語辞典第5回記事 項目「ローファイ」
*特殊レンズ第3回「HOLGA」編記事
を参照して貰えれば良いのだが、ただ記事を読んだ
だけではやはり理解は困難だと思われ、実際にこうした
トイレンズ等を入手し、Lo-Fi技法や、Lo-Fi表現を
常日頃から試してみた上で無いと、永久に良くわからない
ままだと思う。
Clik here to view.

99%は「Hi-Fi」志向だ、つまり、被写体がはっきり
くっきり写っている事が、王道であり、正当な写真で
あると思い込んでいる。
まあ、これは「写真」を「映像記録」の側面でしか
見ていない、という事であろう。
・・まあ、あれこれと説明しても理解が困難な世界だ。
今回は、別の芸術分野でのわかりやすい例をあげれば、
美術(絵画)の世界での「印象派」が、その1例であろう。
印象派は1800年代後半~末くらいに、旧来の絵画とは
全く別のものとして誕生したスタイルである。
近年、私は美術史を良く勉強していて、その分野にも
だいぶ詳しくなってきているが、ここで印象派の誕生の
経緯等について説明しだすと、とても長くなるので
残念ながら割愛しよう。
要は、それまでの絵画では、対象が、はっきりくっきり
描けている「Hi-Fi絵画」であった事とは、対極の立場
で生まれた「Lo-Fi」絵画の一種が印象派だ。
当然、当初は美術評論家等からはボロクソに言われた。
世間でも同様であり、まあ、いずれも新分野の芸術の
意味や表現が、全く理解できなかった訳だ。
(注:ごく近年での美術史の研究成果によると、印象派
の登場時の批評家からの意見は、さほど酷いものでは
なく、むしろ殆どが好意的だったという解釈もある模様)
しかし、数十年でその様式は難なく定着、百数十年が
経過した現代においては、絵画オークション等で高額に
落札される絵の多くは、「印象派」であり、絶大な人気
と、高度な芸術性が認められている次第である。
絵画は誰も描ける訳では無いので、まあ敷居が高い
芸術分野であろう、しかし現代における写真は違う。
本格的なカメラを持っていなくても、スマホや携帯の
内蔵カメラでも写真は撮れるので、世の中のほぼ全員が
カメラマンである。すなわち「一般大衆」に過ぎないし、
それらが志向するのは芸術では無く、映像記録であり、
その目的(用途、志向性)は「Hi-Fi映像」である。
(注:近代のスマホ撮影では、SNS用途等において
「加工・編集」や「盛る」事は常識化しつつある)
だから逆に言えば、その状況において、Lo-Fiやらの
高度な作画意図や芸術性を持たせるのは一般大衆では
心理的に理解が無理であり、綺麗に写っているHi-Fi写真
だけが正しいものだ、と強く思い込んでいる。
印象派、あるいはそれ以降の近代芸術において、絵画の
表現や芸術性は、極めて多数の新しい様式を生み出した。
今時においては、もはや「何でもあり」の状況である。
現代の写真の世界での一般大衆における価値感は、まるで
中世の絵画界のようであり、300年や500年も前の感覚
となっている。写真が、印象派や近代絵画の様な芸術性を
得る為には、いったいあと何十年、いや何百年かかる
のであろうか? なんだか、ずいぶんとつまらない世情だ。
----
さて、7本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 10,000円)(以下、NFD35/2)
カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)
1979年発売の単焦点準広角MFレンズ。
1980年代のCANON製 New FD レンズにおいては、
開放F値がF2のレンズは6本存在するが、内、5本を
特殊レンズ第46回「CANON New FD F2レンズ編」
で紹介している。
特に特筆すべきマニアック性は無いレンズではあるが、
注目すべきは、この時代にCANONが、F2という明るい
口径比のレンズを多数の焦点距離でラインナップして
いた事である。
当時、同様の戦略を取ったのは、OLYMPUSであり、
マニア層では「ZUIKOは、20(21)mmから250mm迄、
全てF2で揃える事ができる」と、良く言われていた。
ちなみに、OM20mm/F2は医療用特殊マクロ(近年に
中一光学から復刻された)ので、OM ZUIKOの実用写真
レンズであれば、21mmからのF2ラインナップである。
まあ、実際にはOM ZUIKOのF2級はいずれも高価な
レンズであったので、それをコンプリートできる
(OM)マニアは皆無に近い状況であったとは思われるが
それが(OM)マニアの憧れや機材購入モチベーションと
なっていたのは確かであろう。
参考:特殊レンズ第33回「OLYMPUS OM F2レンズ」
CANONにおいて、もし、この(NEW)FD F2級レンズの
ラインナップ戦略が、OLYMPUS OM党の、その心理状態
を理解した上で行われていたならば(つまり、New FD
でも同様にF2レンズを揃えたいと、CANON党に思わせる)
これはなかなか高度な、マニアックな心理を突いてきた
市場戦略だ。
Clik here to view.

24mm,28mm,35mm,50mm,100mm,135mmの
6本が存在し、50mmを除く5本を、前述の特殊レンズ
第46回記事で紹介している。
なおNew FDレンズで、OMのようにズラリと焦点距離を
並べていないのは、OM-SYSTEMでは「小型軽量化」と
「高い汎用性」という、強い設計コンセプトが存在
していて、無理やりF2より明るい開放値の焦点距離の
レンズを作ろうとはしなかったが、CANON NEW FDに
おいては、F2よりも明るいF1.2~F1.8級のレンズも
焦点距離によっては存在していたからである。
だからまあ、CANONにおいては、あまり強く「F2で
揃える」というラインナップ戦略は無かったのかも
知れない。
しかし、実例があって、実は、上記の私が所有して
いるNew FD F2レンズ群のうち、3本のレンズ、
24mm/F2,28mm/F2,35mm/F2は、銀塩時代に
同じタイミングで中古入手した、という経緯がある。
つまり、前オーナー(誰だかは不明)は24~35mm
を「全てF2で揃えたかった」訳であり、同様に、私も
全く同じ理由で、この3本の中古レンズを揃えたかった
のだ。つまり、ここが「マニア心理」となっていて
一種の「コンプリート願望」が、この根源であろう。
----
では、今回ラストのB級マニアックシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 35,000円)(以下、RF250/5.6)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)
恐らくは1980年頃の発売と思われる小型軽量ミラーレンズ。
MD型の時代の製品であるが、絞りが無いので、カメラ側の
露出モードの差異、すなわちこの時代はMCからMD/New MD
への転換期や転換後であり、一眼レフ本体も、初の両優先
AE機MINOLTA XD(1977年、銀塩一眼第6回記事)や、
初のプログラムAE機MINOLTA X-700(1981年、銀塩一眼
第10回記事)といった風に、AE機能の差異があったのだが、
本レンズの場合は、それらの差異に影響される訳では無い。
また、現代においては、ミラーレス機でアダプターで使う
上では、MD型か否か等のAE機能の差異はどうでも良い。
Clik here to view.

小型軽量であったと思われる。
一般的にミラーレンズと言えば、500mm級が中心であり
稀に旧ソ連製等で、800mmや1000mmの物が存在した。
(注:軍事用途の民生転用品であろうか?)
国産でも、SIGMAやPENTAXでは600mm級もあった。
(注:PENTAXは、ズームミラーレンズという特殊仕様)
小さい(短い)方では、350mm級が、やはり旧ソ連製
であったが、もはや、ソビエト崩壊から数十年経った
現代では入手困難であろう。
近年においては、KENKO社から400mm級(および
一部では500mm)ミラーが発売されており、これらは
かなり小型軽量だ。
また、TOKINAより300mmのμ4/3機専用ミラーが
発売されていて、これも相当に小型軽量ながら、
600mmの換算画角と、80cmの最短撮影距離が特徴で
ミラーマクロ、という新しく現代的な撮影技法が使える。
ただまあ、KENKOやTOKINAの製品は、2010年代と
新しいので、銀塩時代においては、本RF250/5.6が、
最も小型軽量であるとともに、焦点距離的にも、
やはり250mmは、最も短い仕様であろう。
これらのミラーレンズのうち、4機種に関しては、
特殊レンズ第18回「ミラーレンズ」編記事で紹介済みだ。
長所はその史上最短焦点距離ミラー(レンズ)としての
歴史的価値である。
Clik here to view.

褒められたものでは無い、おまけに最短撮影距離も
2.5mと長く、被写体に対峙した際、近くのものが
全く撮れずに、かなりイライラとする。
さらには、超レアものであり、入手が大変困難だ。
私が銀塩時代に入手後、1、2度だけしか中古市場では
見かけた事がなく、しかも「投機対象」となっていて、
性能や実用性から見たら不条理なほどの高額相場で
あった。高値で買う意味が全く見出せないレンズである。
もう少し言えば、このRF250/5.6は、ミラー加工の
耐久性が弱く、「経年劣化が激しい」という情報があり、
後年において、ミラーが高品質を保てている個体は
極めて少ない。いくつか中古市場に出てきた個体でも
ミラー劣化(蒸着の剥げ)が発生していたものもあった。
幸いにして、私の所有個体はミラー劣化は無いのだが、
他の個体については、殆ど所有者が居ない状況なので、
現代において、いったいどうなっているか?は不明だ。
(追記:ごく最近、知人のマニア氏が、本レンズの
ジャンク品を入手したが、修理不能なまでに劣化した
状態だった模様だ)
まあ、現代において、本レンズを指名買いする必然性は
皆無に等しい。小型軽量のミラー(レンズ)が欲しい
ならば前述のTOKINA 300mm/F6.3が、本RF250/5.6
よりも何倍も何十倍も、使用利便性が高い。
TOKINA版は、数年前まで現行製品だったので、入手は
さほど困難では無いだろう。そちらの中古であれば
1万円台後半と安価だ。
本レンズを所有する意味は「歴史的価値」における
マニアック度や研究対象としての資料にしかなり得ず
現代において実用的なレンズであるとは全く思えない。
----
さて、今回の補足編「高マニアック度B級編」後編記事は、
このあたり迄で。次回は通常記事となる予定だ。