本シリーズは、各カメラメーカーが発売した銀塩・
デジタルのカメラをおよそ1970年代~現代2020年代
に至る迄の約50年間の変遷の歴史を辿る記事群である。
今回はPANASONIC編として、2000年代から2010年代
後半迄のPANASONICデジタル機(コンパクト、μ4/3機)
を中心に紹介する。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
本シリーズでの紹介機は、現在所有しているカメラで、かつ実際に使っているものに限るルールであるが、PANASONIC
がデジタルカメラ市場に参入してからは、まだ時代が浅いのと、
後述する理由とで、所有カメラ数は、さほど多くない。
また、挿入している写真は、PANASONIC製カメラの紹介写真
および、それらのカメラで撮影した写真を適宜用いる。
なお、PANASONICは、Panasonicと先頭だけ大文字にする
のが正しい社名だと思われるが、他記事との関連/慣例もあり、
便宜上、全て大文字で書く事を基本とするが、適宜混在させる。
また、Panasonic製デジタルカメラはLUMIX(ルミックス)
というブランド銘で売られていて、カメラ本体には、
Panasonic等の社名は大きくは書かれてはいない。
(参考:底部の「銘板」以外には、何も書かれていない
ケースが大半だ。つまり、他社機ではカメラの前部や
上部に、型番等が記載されている事が多いが、LUMIXの
場合では、ミラーレス初期の機種を除き、メーカー名や
機種名が、カメラ上に全く何も書かれていない。
「ブランド・バリュー」が無い事が所以だとは思うが、
それにしても、なかなか興味深い「文化」だと思う)
LUMIXは造語だと思う。Luminous(光る、明るい、明解)
という英語から来るもの、あるいは、もっと語源的には、
「lumi」という「ラテン語」が「光」を意味している。
それらを接頭語とした Lumi-は、「光る、光の」という
意味であり、様々な各言語での派生語がある。
有名な言葉(行事)としては、「神戸ルミナリエ」があるし、
液晶テレビ等での有機EL(エレクトロ・ルミネ(ッ)センス)
とかもある。
化学や鑑識での「ルミノール反応」も、光る事が由来だ。
同じく学術で言えばlumen(ルーメン、光束の単位)も、
やはりlumiが変形したものであろう。
また、夜景「イルミネーション」という言葉にも、lumiの
綴りが含まれている。一般的に(人名以外で)「ルミ」と
聞けば、光が関係していると思って、まず間違いは無い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
では、例によってPANASONICのカメラの歴史から始める。
*デジタル初期 1990年代末
さて、PANASONIC(以下、適宜、PANAと省略する)は、
銀塩カメラは作っていなかったが、1990年代末頃から、
松下の系列会社より、COOLSHOTのブランドで、コンパクト・
デジタル機を発売。しかし、世にあまり知られず、商業的に
成功したとは言い難いであろう。私もこの時代や、少し後の
時代まで、PANA製のデジタル機には興味が持て無かったし、
他の家電メーカーでも、デジタルカメラを販売するケースも
稀にあったが、それらも同様に興味が持てなかった。
すなわち「写真を撮る道具」としての「最低限の要件を
満たしていない」と感じていたからである。
*LUMIXブランドの立ち上げ 2000年代~
2001年には、LUMIXのブランドで、本格的にデジカメ市場に
参入する。
ライカ社との提携で、レンズにはライカの名前を冠するが・・
例によってブランド銘だけの話であり、単純にその名前で
これらのレンズの画質が良いと判断するのは早計だ。
ただまあ、CCD撮像センサーや画像処理エンジン(PANA
では、Venus Engineと呼ばれている)は自社製と思われ、
その点ではビジネス的には競争優位性があっただろう。
2000年代前半のLUMIXカメラは、小型コンパクト機と
大口径望遠ズームを搭載したロングズーム機が主力であり
手ブレ補正機構もいち早く内蔵されていた為、後発カメラ
メーカーながらも技術的優位点は結構あったと思う。
新機種の発売数も多く、新古品や中古品の相場も比較的
早く下がった為、ブランド銘に拘らない一部のマニア層
にも人気であった。
2006年~2008年にかけ、オリンパス等が採用していた
4/3(フォーサーズ)規格に賛同し、DMC-L1、DMC-L10
の2機種が発売された(注:オリンパスとの共同開発
であったという話もある)
加えて、数本の4/3用交換レンズが発売されている。
なお、詳細は不明だが「PANA製レンズは内製されている」
との話を聞いた事がある。(前述のライカ社とのブランド
提携の関連もあってか、このあたりの詳しいところは一切
公開されていないので、あくまで噂のレベルでしか無い)
レンズの性能は全般的に可も無く不可も無しという感じで
あろうか? 特別な優位性は感じられず、同社製のレンズ
の所有数も数本のみの範囲に留まっている。
また、DMC-L10は、同年の初のμ4/3機、DMC-G1の
試作のベース機となったと思われる。
・・で、私は正直言って、2000年代前半のPANA機には、
全く興味が持てなかった。「新規参入の家電メーカーで
あるし、写真撮影を意識したカメラの企画・設計・開発の
ノウハウなんて、何も持っていないに違い無い」と
勝手に思い込んでいたのだ(汗)
事実、店頭や知人の所有物として手にする同社のコンパクト
機の印象も、それを裏付けるものであり「まだまだだな・・」
という実感を強くしていた。(注:この時代の各社の
コンパクト・デジタル機は、巨大な1つのOEMメーカーで
共通して作られていた事も理由かも知れない)
しかしながら、2007年~2008年頃にかけ、急激に、
PANA機のカメラとしての性能(写真を撮る道具としての
基本性能、企画コンセプト、操作系等)が向上したのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16570833.jpg]()
*LUMIXコンパクトの名機 DMC-LX3
それ(品質の向上)を実感したのは、準高級コンパクト機
とも言える、LXシリーズの3代目、DMC-LX3(2008年)
である。(下写真)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16570822.jpg]()
詳細は、コンパクト・デジタル・クラッシックス第3回
記事に詳しいので、本記事では、ごく簡単に述べるが、
まあすなわち、本機は、設計思想(コンセプト)に
とても優れた名機であると言える。
絶妙なバランスで企画設計されたこの機体や、同年の
初のμ4/3機DMC-G1は、設計思想が非常に秀逸であり、
相当にカメラの事を知っている設計者である事が推測
できた。
その話は、続く機種の所でも述べる。
*史上初のミラーレス機 LUMIX DMC-G1
2008年の夏頃、マイクロフォーサーズ規格の発表があった。
その公開資料を一通り読んだ私は、正直いって、ピンとは
来なかった(汗)
公開資料は技術的なポイントのみの範囲で留まっており、
その技術内容は理解はできたものの、以下のような否定的
な印象を感じてしまったのだ。
1:また新規マウントか・・・ レンズ代が大変だな。
2:技術仕様の話ばかりで、写真撮影上のメリット等は、
何も書いていないではないか、いったい何が便利になるのだ?
3:ミラーを無くしたら、AFはライブビュー(コントラストAF)
になるな、その構造では、とてもAF性能が低そうだ。
4:完全無音撮影(注:電子シャッター)は、出来るのかな?
それが出来たら嬉しいのだが・・
5:解像度の低いEVFや背面モニターでは、MFは絶望的だな。
6:レンズが小型化できそうだが、はたしてどれだけ小型化の
メリットがあるのか? 性能を落としたら意味が無いぞ。
7:そもそも、4/3型センサーだと小さいんだよね・・・
フルサイズとは言わないが、せめてAPS-C型が欲しい。
以降、メーカー談とか、カメラ専門誌、マニア層等で、
「μ4/3が優れる理由」のような話も色々と出て来たが、
規格・仕様上からのメリットのような話が主体であり、
そんな事は、ユーザーから見れば、撮影状況に応じて
適切な機材を選択するだけだから、十把ひとからげ的に
「μ4/3(や、旧来の4/3)が優れている」等といった
話には興味が無かった。特にマニア層、ハイアマチュア層、
職業写真家層から見れば「そういうのは、単なる宣伝だ」
と思う事も多いであろう。
まあ、これらは、ありきたりの「傍観者的」な感想だ。
どちらかと言えば、私は、ミラーレス機を買う筈も無い
だろうし、自分とは関係の無い世界の製品だと思っていた。
でも、初のミラーレス機、PANASONIC DMC-G1は、
規格の発表から僅か数ヶ月後の2008年末に発売された。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572140.jpg]()
製品化の対応が早すぎるので、恐らくは、先にG1の試作機
が存在し、それを見て「イケる!」と思って、μ4/3規格が
後から生まれたのであろう。なお、以前の記事でも書いたが
そうした技術者のアイデアによる「プロダクト・アウト」型
の製品戦略は、松下の時代から寛容な社風がある、と推測
している。(注:現代的な、「マーケット・イン」型の
製品企画開発では、技術者が好き勝手な製品を試作する
等は、まず許されない状況だろう)
DMC-G1の発売直後、2008年末か2009年初頭か?量販店の
店頭で、気になっていた上記4番の「無音撮影が出来るか?」
についてだけチェックした。
するとG1はメカシャッターであり、結構シャター音がする。
もし完全な無音であれば、静かなイベント等での業務撮影に
有益な機材になるか?と思ったが、これではダメだ。
(注:DMC-G2以降では電子シャッター機構が搭載された)
私は、初のμ4/3機を無視する事としたのだが、その後、
各社から、マウントアダプターが沢山発売されてきた。
私は、「しまった! そういう事だったのか、そこは
完全に見落としていた」と、すぐさま反省する事となる。
つまり、「ミラーBOXが無いミラーレス機であれば、
フランジバック長を、とても短くする事が出来る。
μ4/3純正レンズを使う上では、そこはどうでも良いが
マウントアダプターを使うならば、これまでのデジタル
一眼レフでは、現行マウントよりもフランジバック長が
短いFD、MD、ARなどの古いマウントのMFレンズは
使いようがなかったが、ミラーレス機ならば、どれも
使えるようになるではないか! これは凄いメリットだ!」
・・と、ミラーレス機の真意を、やっと理解できた訳だ。
おまけに、オールドレンズ母艦とするならば、AFの未成熟
など、どうでも良い、全てMFレンズしか使わないからだ。
何故、その事がマイクロフォーサーズ規格の発表時に
アピールされなかったのか?は明白だ、もしそんな事を
公言してしまったら、せっかくの新規格のカメラのビジネス
をメーカー自ら否定するような発言となってしまう。
恐らくは開発側は、その事は十分承知した上でμ4/3機を
試作したのであろう。でもこれも推察だが、その裏の事実は
決して上司へや検討会議の場では言わなかったに違い無い。
それがバレたら「他社製のレンズを使う為のカメラを
作ると言うのか?!怒」と、大問題になる(汗)
だけど、開発者は恐らく相当のカメラマニアだ、PANA社は
いくらライカのブランド銘を買ってつけているとは言え、
上級マニア層等がパナソニック銘のレンズに何も期待して
いない事は良くわかっている。だから、そもそも自社製の
レンズなんて、市場競争力が無いではないか・・と。
で、うがった見方をすれば、マウントアダプターの発売が
やたらと速かった事を鑑みれば、積極的にサードパーティ
に、それらを作って売るように、と裏から事前に手配して
いたのかも知れない、とまで妄想が膨らんでしまったのだ。
(つまり、μ4/3の規格・仕様書をアダプターメーカーに
送りさえすれば、製造は容易だ)
そして、マニア層を中心にμ4/3機等で、アダプターを
用いてオールドレンズを使う事が流行し、2010年代前半
は「第二次中古レンズブーム」と言える様相となったが、
この流行はマニア層を超えて一般層に波及する事は無かった。
だが、この事が、ミラーレス機の普及に功績があった事は
間違いの無い事実だ。やはり「確信犯」であった事だろう。
それらの憶測の真偽を確かめる格好の機会が私に訪れた。
写真関連の業務とは違う、デジタル画像処理の技術的な件で、
パナソニック社を訪問して、商談(技術討議)を行う機会
が、2009年初頭にあったのだ。
この話は、他のDMC-G1関連の記事でも書いた事があるので
簡単に書くが、要は、DMC-G1の開発陣は、皆、とてつもなく
カメラ技術および撮影全般に詳しい人達であったのだ。
後日、よくよく考えてみると、その数年前に、関西では
大きな2つのカメラメーカーが、カメラ事業から撤退して
いる。それらのメーカーのベテラン技術者であったのでは
なかろうか? と推察していた。
恐らくは、ミラーレス(μ4/3)機の規格そのものも、きっと
彼らによるアイデアが発祥であったに違い無い、とも想像した。
私は商談よりも、DMC-G1そのものに強い興味を持ってしまい、
後日すぐにDMC-G1を入手し、使ってみると、さらに驚いた。
事前の予想よりも、まだそれを上回るほどに「操作系」の
完成度が高かった。つまり、あらゆる点でムダが無いのだ、
それは、マウントアダプターを使った際にも同様であった。
DMC-G1の無駄の無い操作系は、銀塩傑作機「MINOLTA α-7」
(2000年)にも通じるものがあるし、またDMC-G1より後年の
製品だが、SONY NEX-7(2012年)の「動的操作系」とも
通じる優れた設計思想であった。
この「設計思想」の源流は、1990年代末のMINOLTAにあり、
そのノウハウが、2000年代末のPanasonic機、そして、
SONY機などに人的資源と共に受け継がれていたのだろう、
と、私はそう結論づける事とした。
これは勿論、悪い話では無い。たとえカメラメーカーが
無くなってしまっても、その設計思想の血脈が、なんらかの
形で他社のカメラに引き継がれて行く事は、とても良い事だ。
ただ、そうした所までユーザーや評論家は、わかっている
のであろうか? DMC-G1が発売された後、画素数が少ない
とか、色つきボティは軟弱だとか、AFが遅い、とか、
ユーザーも評論家も、好き勝手に、表面的な部分だけを見て
評価をしているだけの状態であったのだ。
でもまあ、それもやむを得ないであろう、例えば数百台の
カメラを実際に長期に渡って使ってみるなどの、「研究」
とも言えるレベルの時間と予算と手間をかけないと、なかなか、
カメラの設計思想の本質迄は、わかって来ないだろうからだ。
一般ユーザーはもとより、評論家層でもそれは無理な話だ。
それに、ミラーレス機は全くの新分野だ、旧来の一眼レフの
感覚や価値観でそれを評価しても、全く意味が無い事だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572103.jpg]()
DMC-G1は、お気に入りのカメラとなり、後日、色違いの
予備機まで購入している。こんな場合、個体識別の為に
ボティ・カラーバリエーションがある事は非常に助かる。
私は他にも同じ機体を複数所有しているケースがいくつか
あるが、まったく同じ機体色だと機材ローテーション上で
混乱を招く。ごく簡単な例をあげれば、外出前にバッテリー
を充電しておく必要があるか無いか?等、見た目が同じ機体
の場合は、一々それを管理または覚えておく事が困難だ。
旧来の感覚のまま「色つきボディは軟弱だ」と言うのでは
無く、その変化による長所と短所をよく分析する事が重要だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572145.jpg]()
後年、新型機が色々と出て安価になったDMC-G1を
「コスパが最も良いレンズ交換式カメラ」として、MFレンズ
とのセットで、何人もの知人友人に勧めている。
DMC-G1で撮影をした上写真の女性も、DMC-G1とMF50mmの
レンズのオーナーだ。
*その後のLUMIX Gシリーズ 2010年代~
PANAのGシリーズは、その後、特異なマーケティングスタイル
を展開した。それ以前の時代の各社の一眼レフは、銀塩時代
からデジタル時代に至るまで、いずれもが、例えば、初級機、
中級機、高級機・・と、明確に価格帯と性能とを差別化した
ラインナップを組んでいた。
ところが、PANAのGシリーズでは、性能や価格での段階的な
ラインナップを行わず、以下のような感じであった。
G :本格的写真撮影を中心とした正統派の中級機
GF:小型軽量でファッショナブルな機体(入門機)
GH:本格的動画撮影を意識した中高級機
GX:ベテラン層やシニア層向けのややマニアックな機体
GM:超小型化をコンセプトとした機体
こういうラインナップとなる理由は2つ推測できる。
1)ミラーレス機は新規市場であり、どのような消費者層が
どのようなニーズでカメラを買ってくれるかが不明である。
であれば、消費者層をターゲット毎に分けて、それらの
個別に対応し、個々に販売状況とか市場ニーズ等を反映
させていく(又は、ユーザーの反応を見て今後のシリーズ
をどう展開させていくかを決める)戦略が得策であろう。
さらに加えて、Panasonicは後発参入メーカーである。
ユーザー層の動向調査は、他の老舗カメラメーカーよりも
慎重に行う必要がある。
2)μ4/3では、撮像センサーや画像処理エンジン等の使用可能
な部品の種類が少なく、また規格上でもセンサーサイズは
予め決められている為、センサーや画像処理エンジンで
性能差を作り出すようなラインナップを組む事が、そもそも
困難である。
まあ、これの傾向はPANASONIC社に限らず、他社ミラーレス
機でも同様であった。オリンパスもμ4/3初期には、PEN、
PEN Lite、PEN Miniの3シリーズを続けざまにリリースし
市場の反応を探っている。
後年さらに、OM-Dシリーズを追加、その中でも、OM-D E-M1
E-M5、E-M10系列は、それぞれターゲットユーザー層が異なる
し、加えてPEN-Fまで追加している。
すなわち、数年かけて、だんだんとターゲットユーザーの
具体像が見えて来た、という状況であろうし、もっと年月が
経てば、市場環境の変化などもあって、さらにユーザー層は
微妙に変遷を続けていく事であろう。まあ、そういう変化に
も耐えられるだけの製品ラインナップを作るという事であり、
一眼レフのような価格別ラインナップでは、市場状況への
柔軟な対応が難しくなってしまう訳だ。
また、SONYでも同様だ、2010年発売のNEX-3とNEX-5は、
当初は、ほぼ同じ仕様の機体で何故2機種あるのかの理解に
苦しむ要素もあったが、その後数年間で、NEX-3を女性等
向け、NEX-5を男性向けに細かい仕様チューニングを行って
いる。それらの「テストマーケティング」が一段落した
段階での2013年には、いさぎよくNEXシリーズを廃止し、
本格的なユーザー層向けのフルサイズ・α機をリリース。
旧来のNEXもαにブランド統合し、「上位機種を上級層が
使っているから、ビギナーもSONY αを買え!」といった、
「トップダウン戦略」に全面的に切り替えている。
ただ、このような「広角打法」的に、同時に複数の
ユーザーニーズを探り出すという市場戦略は、当然ながら
失敗する、あるいは発展性の無い、はたまた市場の変化に
対応しきれない、といった製品カテゴリーも出てくる。
Panasonicについては後述するが、他社では、NIKON 1
シリーズや、FUJIFILM X-Mシリーズ、PENTAX Qシリーズ、
同K-01等は、市場では既に廃止または凍結されている
ラインナップだ。
後発のCANON EOS Mシリーズでも、後年においてEOS M5、
M6、M10、Kiss Mそして高級機EOS Rの複合ラインナップ
を「広角打法」的に並行展開し、その中から生き残れる
シリーズを模索していたが、2018年頃からは、
フルサイズ機EOS Rシリーズを主力に切り替えている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572264.jpg]()
PANASONICにおいては、上記の複合ラインナップとして、
Gだが、一度休眠しかけたが、G7で復活、G8あるいは
G9からは高付加価値型機として高額商品となった。
(加えて海外生産とし、さらなる利益率向上を狙った)
GHは、GH4より、高付加価値型のハイエンド機に設定。
GXは、GX7シリーズだけ生き残って,それのバージョン
アップが繰り替えされている(いた)。
GMは、GM5をもって凍結(終了)と思われる。
GFは、引き続きエントリー層向けの展開を続けているが、
ボディ単体発売は無くなり、新製品も減っている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572901.jpg]()
上写真は、DMC-GX7(2013年)である、これ以降は、
DMC-GX7 MK2(2016年)、DC-GX7 MK3(2018年)と
この型番機体のみ、順次バージョンアップされていた。
他のシリーズでは、1から始まり順次番号が増えて
いくケースが大半だ(例:GF1~GF10)
下写真は、DMC-GF1(2009年)である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572934.jpg]()
なお、型番DMCだが、デジタル・ミラーレス・カメラの
略と思いきや、そうでもなく、LUMIX最初期の2001年
頃のコンパクト機でも、DMC型番となっていた為、
LUMIXの真ん中のMの字か、あるいは「松下」のMなのか?
または「デジタル・メディア・カメラ」説も有力だが、
その詳細は不明である。
ただ、3文字型番は、商標上の識別力が発生する可能性
がある。例えば、他社が「DMC」という企業名や
ブランド名で、その商標をその商品分野(カメラ等)で、
取得していたとすると、それの権利を主張された場合、
PANASONICは「DMC」銘の使用料を払わなくてはならなく
なるのだ。これは国内の話のみならず、全世界に輸出する
には、各国での商標取得状況を調査しなくてはならない。
これは大変な手間がかかるし、おまけに、ある時期は
OKであっても、ある国で、ある企業が、DMCの商標を
取得し、強引にPANASONICに使用料を請求する訴訟が
いつ起こってもおかしく無い。
まあ、そういう事例が実際にあったのか無かったかは
不明であるが、ともかく、それへの安全対策であろう。
商標としての識別力が発生しにくいと思われる2文字
型番に改められる事となり、2017年以降のPANA機では
旧来のDMC型番ではなく、DC型番に変更されている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572944.jpg]()
補足だが、2文字であれば常に安全か?という訳でもなく、
その国などにおいて、十分に知名度が高い英字2文字の
企業名やブランド銘では、意匠(デザイン)との
組み合わせで、商標を取得する事が出来る模様だ。
日本国内での具体例としては、「JR」(鉄道)や「JT」
(タバコ)、「au」(携帯電話)等があると聞く。
*所有LUMIX Gシリーズと、その全般的な特徴
私のLUMIX Gシリーズの所有機はさほど多くは無く
以下の通りである。
DMC-G1 (2008年)x2台 (ミラーレス第1回記事)
DMC-GF1(2009年)(ミラーレス第3回記事)
DMC-G5 (2012年)(ミラーレス第7回記事)
DMC-G6 (2013年)(ミラーレス第10回記事)
DMC-GX7(2013年)(ミラーレス第12回記事)
DC-G9 (2018年)(ミラーレス第?回記事、予定)
いずれも、ミラーレス・クラッシックスの各記事で
詳細(用途、長所、短所等)を紹介済み/予定である。
ミラーレス時代初期(2008年~2013年、私の
定義するところの、第一世代~第三世代)の機体が
殆どなのは、この時期のLUMIX Gシリーズは
前述の「操作系の充実」による完成度が高い事がまず
重要な長所であった事、そして性能もまずまずであり、
決して他社ミラーレス機にひけを取る事もなかった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16572911.jpg]()
加えて、新機種が次々と出てくる事と、おまけにブランド
力の低いPANA製品であった事で、中古相場の下落が激しく、
2年前位の機種でも2万円くらいで安価に買う事が出来て
とてもコスパが良かった訳だ。
これはもう、当時であれば買うべき機体であっただろう。
*以降のLUMIX Gシリーズについて
しかし2015年以降、私が定義するミラーレス第四世代
(成熟期)に突入すると、LUMIX Gシリーズの主力機と
なりうる本格派機体の多くは、「超絶性能」を搭載した
「高付加価値型」商品となってしまった、つまり大きく
値上げされた訳であり、コスパの低下が甚だしい。
まあそれでも、前機種よりも様々な改善点が見られる
ならば、コスパの悪さに目をつぶり、パフォーマンス
だけを重視して購入する事もありうるだろう。
しかし、DMC-GX7以降の機体では、それまでのDMC-G
シリーズの特徴であった「無駄の無い操作系」という
職人芸的かつ優れた設計要素が無くなってしまっている。
前述の「設計思想」の話に強く関連するが、この時代
以降のLUMIX Gシリーズには、DMC-G1の時代の当初に
あった優れた設計思想が感じられない。これも推測だが、
当初の優れた設計陣は、異動とか退職とか昇進で、
もう残っていないのであろうか?だから設計思想が
変わってしまったのだと思われる事が1つ、
あるいは、もう市場での消費者層のニーズが、大幅に
変化してしまい、「写真を撮る」という行為が特別な
事ではなく、誰にでも行えるようにする為、あえて
「操作系」のダウングレードを続けているのかも知れない。
そういう事は、カメラを手にして十分に使ってみれば、
だいたい推測できる、どれだけカメラを「写真を撮る
道具」として作っているか否か、の差異は明白だ。
例えば、DMC-GX7は、カタログスペック上では
優秀な機体である。276万ドットEVFや、最速1/8000秒
シャッターは当時のミラーレス機としては最高クラスだ。
おまけにPANA機初の内蔵手ブレ補正まで搭載されている。
だが、写真を撮るカメラとしての性能がヘロヘロに低い。
AFはダメ、MFも使い難い、純正レンズを付けても
マウント・アダプターを使っても、どちらもダメ、
操作系は全然練れておらず、無駄なダイヤルが出たり
煩雑な操作が色々と発生する。旧来のバリアングル式
モニターも失われ、EVFとモニターが同じ縦方向に
ティルトしても、いったい何の意味があるのか・・?
すなわち全体的にカメラとしての完成度が低すぎるのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16574101.jpg]()
GX7シリーズ後継機や、G7以降のGシリーズも同様に
カメラの本質の部分が未成熟で、改良もされていない。
「これは、やはり設計チームが居なくなったな」と
私は推察し、これらの後継機を買い控えする事とした。
おまけに2018年のDC-G9は、PROのサブネームをつけた
典型的な高付加価値型商品となった。発売時実勢価格は
最初期のG1(2008年)からは何と約4倍(実質5万円台
→21万円)と、考えられない程の値上げ幅だ。
僅か10年で同様な商品の価格が4倍にもなった例は、
1970年代の10年間が「狂乱物価」と言われて、物価が
およそ3倍になった時の、それ以上の値上げ幅である。
その1970年代当時は、トイレットペーパーを買い溜め
するなど、市場は大騒ぎとなっていた。すなわち暴動が
起こってもかしく無いという事であり、DC-G9に限らず
他社のカメラでも起こっている近年の新機種の大幅な
値上げに対し、ユーザーや市場は何故冷静なのだろうか?
写真を撮る為の実質的な性能がほとんど向上していない
にも係わらず、カタログスペックだけ上げて、値上げを
繰り返していたら、「ふざけるな!」とユーザー層が
怒っても決して不思議では無い筈だ。
まあDC-G9に関しては、カタログスペックは高性能なので、
当初の市場での評価はなかなか良かったが、そうした
評価に関しても、非常に注意して聞く必要がある。
すなわち、高額商品となれば、それが売れれば、メーカー
や市場(流通、小売店)などは、どこも儲かって助かる。
そして、性能が高い商品を褒める事は、どこからも
文句が出ることは無い。だから、市場や評論家などは
高性能な高額商品を、いつの時代でも褒め称えるのだ。
でも、市場が儲かるという事は、ユーザー(消費者)は
損をしている訳だ。この状態を本ブログでは「ユーザー
の負け」と称している。上級の消費者(例:主婦層)で
あれば、「消費者の負け」となる買い物は絶対にしない。
「モノを高く買うのは負けである」という強い意識を
日常的に養っているからだ、当然ながら、それに伴う
「絶対的価値感覚」も持っている。
私も同様だ、コスパの悪い商品を買う事は絶対に無い。
まあでも、パフォーマンス(実用性能)が十分に高かったり
唯一無二の機能や性能を持っている場合では、その限り
では無い、パフォーマンスはコストよりも重要な要素だ。
で、市場での評価、評論家の評価、あるいは人気投票、
それらの評価は、本当にその機材を実際に所有して使って
いる人の評価であるか?は、とても重要なポイントとして
十分に注意を払う必要がある。持ってもいない機材に
ついて、色々と語っているだけではなかろうか・・?と、
疑念を持つ事は決して悪い事では無い。
DC-G9だが、後日、「本当にこれが高価格に見合う
パフォーマンスを持っているのか?」という観点から、
そして、PanasonicのフルサイズLマウント機の展開開始と
OLYMPUSの分社化により、μ4/3機の絶滅を危惧して
一応入手している。ただ、本記事執筆時点では評価が
間に合っていなかった為、詳細は別記事に譲ろう。
*LUMIX ミラーレス機 Gシリーズの総括
という事で、2008年~2013年頃のLUMIX Gシリーズ機に
ついては個人的な認識としても好評価であり、優れた
機体が多く、当然ながら所有機種数も多かった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16574157.jpg]()
しかしながら、2014年以降でのLUMIX Gシリーズ機に
ついては、残念ながら興味を持てなくなってしまった。
(ちなみに、2019年からのフルサイズ LUMIX Sシリーズ
も、同様に全く興味が持てない)
でも、それは、PANASONICだけの話ではなく、あらゆる
メーカーの様々な世代(時代)のカメラで、同様に
繰り返し起こる歴史である。
なお、Gシリーズに関しては、以下の技術的革新がある。
2008年 DMC-G1 世界初のミラーレス機
2010年 DMC-G2 タッチパネル操作系搭載
2013年 DMC-G6 ピーキング機能の搭載
2013年 DMC-GX7 手ブレ補正機能の搭載
2014年 DMC-GH4 4K動画対応 空間認識AF搭載
2015年 DMC-GX8 Dual I.S. 機能搭載
様々な新機能は、ユーザーによっては有益なものも
あるだろう。ただ、勿論、それらの新機能を必要と
しないケース(例:4K動画は撮らない、等)も
あるだろうから、それによる「高付加価値化」
(すなわち、値上げ)は歓迎できない場合もある。
その新機能等が、「ユーザー側から見た付加価値」
(つまり製品を欲しいと思う魅力)に、なるか否か
は、結局のところ、ユーザーによりけりなのだろう。
そして、上記の年表では、2015年以降における、
Panasonicの特徴的な技術革新は記載されていない・・
本シリーズ記事「カメラの変遷」では、1970年頃~
2020年頃の、約50年間の各カメラメーカーのカメラ
の歴史を紹介しているのだが、中には、ある時代の
あるメーカーの、ある種類のカメラに魅力を感じずに、
その時代の機種を1台も所有していない事も良くある。
しかし、また後年に新機能の搭載等で、魅力のある
機種が出てくるのであれば、その時点で、そのメーカー
のカメラを、また買い始めれば良いだけの話である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16574168.jpg]()
この事は、「メーカー党」と言う感じで、同一のメーカー
のカメラばかり買って使っていると、殆ど理解できない
感覚であろう。まあ、そのあたりは趣味の世界であれば、
個人の好き好きと言えるであろうが、趣味の範疇を超えて
実用的に、または業務上で、あるいはマニアックな観点で
カメラを使い続けようとする場合、その特定の時期の
特定のメーカーの「ビハインド状態」(=他社に比べて
遅れている。すなわち、性能や機能が劣っていたりして、
魅力が無い状態)があっては困る訳だ。それでは、
その期間、そのメーカーのカメラ(と交換レンズ)が
使えなくなる。あるいは我慢してストレスを持ちながら
使わざるを得なくなる。
その問題を避ける為にも、複数のメーカーのカメラを
併用して使わざるを得ない。
でも勿論、そのビハインド状態が永久に続く訳ではない。
もしそういう状態となったら、そのメーカーのカメラは
だんだんと評判を落として、事業が継続できなくなるから、
必然的に「盛り返し」の措置を図ってくる訳だ。
ただ、それもままならず、カメラ事業から全面撤退した
メーカーは、本シリーズ記事での50年間の歴史の中でも
残念ながらいくつもある。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16574156.jpg]()
まあ、消費者側は、むしろ気楽なもので、魅力が無いと
思えば、買い控えをする「選択権」を持っているのだが、
メーカー側はそうはいかないであろう。カメラが売れなく
なって事業撤退ともなれば、その社員や関係者は路頭に
迷ってしまうかも知れない訳だ。
だから、メーカー側はカメラを作る事には真剣である。
それに応えるには、ユーザー側も真剣でなければならない、
ただ単に「値段の高いカメラは良いカメラだ」などと
思い込んでいるようだったら、ちょっと違うと思う。
ユーザーとして欲しいカメラのイメージや価値感覚を
ちゃんと養わなければならないし、あらゆる形でそうした
ユーザーニーズをアピールしていかないとならないだろう。
それは別に積極的に意見を言うとかのみならず、消極的な
スタンスとしても「気に入らないカメラは買わない」等
で、個人の価値感覚をしっかり持つ事だ。
「誰かが良いと言ったから買う」などの行為は勿論NGだ。
・・さもないと、どんどんと欲しくも無い類のカメラが
市場に蔓延してしまう事になる、そうなったら、カメラ
ファン層や市場関係者は、皆、誰もが困ってしまう訳だ。
(事実、そういう状況において中古カメラブームが起こり、
市場が混迷してしまった歴史もあるが、そのあたりは
本ブログや本シリーズでは何度も書いてきた事である)
さて、「さすがに最新の所有機種が2013年製迄では、
仕様的老朽化が酷い!」と感じ、本記事執筆後に
代替の後継機として、DC-G9(2018年)を購入した。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_16574892.jpg]()
こちらの機体は、まだちゃんと評価が済んでいないので、
いずれ、「ミラーレス・クラッシックス」の記事で、
別途紹介する事とする。
ただし、高価すぎて、コスパがとても悪い機種なので、
あまり好評価にはならない事は、予め述べておく。
最後に、ここまで、主にGシリーズのカメラの説明を
して来たが・・ 2019年のSシリーズ(フルサイズ
Lマウント機)の発売以降は、Gシリーズ(μ4/3機)の
新発売は、動画向けのGHシリーズを除き、ほとんど無い。
----
さて、今回の記事は、このあたりまでで・・
次回記事に続く。
デジタルのカメラをおよそ1970年代~現代2020年代
に至る迄の約50年間の変遷の歴史を辿る記事群である。
今回はPANASONIC編として、2000年代から2010年代
後半迄のPANASONICデジタル機(コンパクト、μ4/3機)
を中心に紹介する。
Clik here to view.
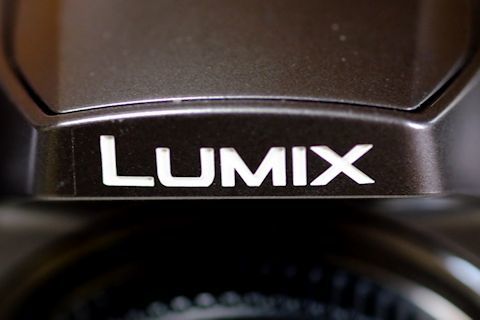
がデジタルカメラ市場に参入してからは、まだ時代が浅いのと、
後述する理由とで、所有カメラ数は、さほど多くない。
また、挿入している写真は、PANASONIC製カメラの紹介写真
および、それらのカメラで撮影した写真を適宜用いる。
なお、PANASONICは、Panasonicと先頭だけ大文字にする
のが正しい社名だと思われるが、他記事との関連/慣例もあり、
便宜上、全て大文字で書く事を基本とするが、適宜混在させる。
また、Panasonic製デジタルカメラはLUMIX(ルミックス)
というブランド銘で売られていて、カメラ本体には、
Panasonic等の社名は大きくは書かれてはいない。
(参考:底部の「銘板」以外には、何も書かれていない
ケースが大半だ。つまり、他社機ではカメラの前部や
上部に、型番等が記載されている事が多いが、LUMIXの
場合では、ミラーレス初期の機種を除き、メーカー名や
機種名が、カメラ上に全く何も書かれていない。
「ブランド・バリュー」が無い事が所以だとは思うが、
それにしても、なかなか興味深い「文化」だと思う)
LUMIXは造語だと思う。Luminous(光る、明るい、明解)
という英語から来るもの、あるいは、もっと語源的には、
「lumi」という「ラテン語」が「光」を意味している。
それらを接頭語とした Lumi-は、「光る、光の」という
意味であり、様々な各言語での派生語がある。
有名な言葉(行事)としては、「神戸ルミナリエ」があるし、
液晶テレビ等での有機EL(エレクトロ・ルミネ(ッ)センス)
とかもある。
化学や鑑識での「ルミノール反応」も、光る事が由来だ。
同じく学術で言えばlumen(ルーメン、光束の単位)も、
やはりlumiが変形したものであろう。
また、夜景「イルミネーション」という言葉にも、lumiの
綴りが含まれている。一般的に(人名以外で)「ルミ」と
聞けば、光が関係していると思って、まず間違いは無い。
Clik here to view.

*デジタル初期 1990年代末
さて、PANASONIC(以下、適宜、PANAと省略する)は、
銀塩カメラは作っていなかったが、1990年代末頃から、
松下の系列会社より、COOLSHOTのブランドで、コンパクト・
デジタル機を発売。しかし、世にあまり知られず、商業的に
成功したとは言い難いであろう。私もこの時代や、少し後の
時代まで、PANA製のデジタル機には興味が持て無かったし、
他の家電メーカーでも、デジタルカメラを販売するケースも
稀にあったが、それらも同様に興味が持てなかった。
すなわち「写真を撮る道具」としての「最低限の要件を
満たしていない」と感じていたからである。
*LUMIXブランドの立ち上げ 2000年代~
2001年には、LUMIXのブランドで、本格的にデジカメ市場に
参入する。
ライカ社との提携で、レンズにはライカの名前を冠するが・・
例によってブランド銘だけの話であり、単純にその名前で
これらのレンズの画質が良いと判断するのは早計だ。
ただまあ、CCD撮像センサーや画像処理エンジン(PANA
では、Venus Engineと呼ばれている)は自社製と思われ、
その点ではビジネス的には競争優位性があっただろう。
2000年代前半のLUMIXカメラは、小型コンパクト機と
大口径望遠ズームを搭載したロングズーム機が主力であり
手ブレ補正機構もいち早く内蔵されていた為、後発カメラ
メーカーながらも技術的優位点は結構あったと思う。
新機種の発売数も多く、新古品や中古品の相場も比較的
早く下がった為、ブランド銘に拘らない一部のマニア層
にも人気であった。
2006年~2008年にかけ、オリンパス等が採用していた
4/3(フォーサーズ)規格に賛同し、DMC-L1、DMC-L10
の2機種が発売された(注:オリンパスとの共同開発
であったという話もある)
加えて、数本の4/3用交換レンズが発売されている。
なお、詳細は不明だが「PANA製レンズは内製されている」
との話を聞いた事がある。(前述のライカ社とのブランド
提携の関連もあってか、このあたりの詳しいところは一切
公開されていないので、あくまで噂のレベルでしか無い)
レンズの性能は全般的に可も無く不可も無しという感じで
あろうか? 特別な優位性は感じられず、同社製のレンズ
の所有数も数本のみの範囲に留まっている。
また、DMC-L10は、同年の初のμ4/3機、DMC-G1の
試作のベース機となったと思われる。
・・で、私は正直言って、2000年代前半のPANA機には、
全く興味が持てなかった。「新規参入の家電メーカーで
あるし、写真撮影を意識したカメラの企画・設計・開発の
ノウハウなんて、何も持っていないに違い無い」と
勝手に思い込んでいたのだ(汗)
事実、店頭や知人の所有物として手にする同社のコンパクト
機の印象も、それを裏付けるものであり「まだまだだな・・」
という実感を強くしていた。(注:この時代の各社の
コンパクト・デジタル機は、巨大な1つのOEMメーカーで
共通して作られていた事も理由かも知れない)
しかしながら、2007年~2008年頃にかけ、急激に、
PANA機のカメラとしての性能(写真を撮る道具としての
基本性能、企画コンセプト、操作系等)が向上したのだ。
Clik here to view.

それ(品質の向上)を実感したのは、準高級コンパクト機
とも言える、LXシリーズの3代目、DMC-LX3(2008年)
である。(下写真)
Clik here to view.

記事に詳しいので、本記事では、ごく簡単に述べるが、
まあすなわち、本機は、設計思想(コンセプト)に
とても優れた名機であると言える。
絶妙なバランスで企画設計されたこの機体や、同年の
初のμ4/3機DMC-G1は、設計思想が非常に秀逸であり、
相当にカメラの事を知っている設計者である事が推測
できた。
その話は、続く機種の所でも述べる。
*史上初のミラーレス機 LUMIX DMC-G1
2008年の夏頃、マイクロフォーサーズ規格の発表があった。
その公開資料を一通り読んだ私は、正直いって、ピンとは
来なかった(汗)
公開資料は技術的なポイントのみの範囲で留まっており、
その技術内容は理解はできたものの、以下のような否定的
な印象を感じてしまったのだ。
1:また新規マウントか・・・ レンズ代が大変だな。
2:技術仕様の話ばかりで、写真撮影上のメリット等は、
何も書いていないではないか、いったい何が便利になるのだ?
3:ミラーを無くしたら、AFはライブビュー(コントラストAF)
になるな、その構造では、とてもAF性能が低そうだ。
4:完全無音撮影(注:電子シャッター)は、出来るのかな?
それが出来たら嬉しいのだが・・
5:解像度の低いEVFや背面モニターでは、MFは絶望的だな。
6:レンズが小型化できそうだが、はたしてどれだけ小型化の
メリットがあるのか? 性能を落としたら意味が無いぞ。
7:そもそも、4/3型センサーだと小さいんだよね・・・
フルサイズとは言わないが、せめてAPS-C型が欲しい。
以降、メーカー談とか、カメラ専門誌、マニア層等で、
「μ4/3が優れる理由」のような話も色々と出て来たが、
規格・仕様上からのメリットのような話が主体であり、
そんな事は、ユーザーから見れば、撮影状況に応じて
適切な機材を選択するだけだから、十把ひとからげ的に
「μ4/3(や、旧来の4/3)が優れている」等といった
話には興味が無かった。特にマニア層、ハイアマチュア層、
職業写真家層から見れば「そういうのは、単なる宣伝だ」
と思う事も多いであろう。
まあ、これらは、ありきたりの「傍観者的」な感想だ。
どちらかと言えば、私は、ミラーレス機を買う筈も無い
だろうし、自分とは関係の無い世界の製品だと思っていた。
でも、初のミラーレス機、PANASONIC DMC-G1は、
規格の発表から僅か数ヶ月後の2008年末に発売された。
Clik here to view.

が存在し、それを見て「イケる!」と思って、μ4/3規格が
後から生まれたのであろう。なお、以前の記事でも書いたが
そうした技術者のアイデアによる「プロダクト・アウト」型
の製品戦略は、松下の時代から寛容な社風がある、と推測
している。(注:現代的な、「マーケット・イン」型の
製品企画開発では、技術者が好き勝手な製品を試作する
等は、まず許されない状況だろう)
DMC-G1の発売直後、2008年末か2009年初頭か?量販店の
店頭で、気になっていた上記4番の「無音撮影が出来るか?」
についてだけチェックした。
するとG1はメカシャッターであり、結構シャター音がする。
もし完全な無音であれば、静かなイベント等での業務撮影に
有益な機材になるか?と思ったが、これではダメだ。
(注:DMC-G2以降では電子シャッター機構が搭載された)
私は、初のμ4/3機を無視する事としたのだが、その後、
各社から、マウントアダプターが沢山発売されてきた。
私は、「しまった! そういう事だったのか、そこは
完全に見落としていた」と、すぐさま反省する事となる。
つまり、「ミラーBOXが無いミラーレス機であれば、
フランジバック長を、とても短くする事が出来る。
μ4/3純正レンズを使う上では、そこはどうでも良いが
マウントアダプターを使うならば、これまでのデジタル
一眼レフでは、現行マウントよりもフランジバック長が
短いFD、MD、ARなどの古いマウントのMFレンズは
使いようがなかったが、ミラーレス機ならば、どれも
使えるようになるではないか! これは凄いメリットだ!」
・・と、ミラーレス機の真意を、やっと理解できた訳だ。
おまけに、オールドレンズ母艦とするならば、AFの未成熟
など、どうでも良い、全てMFレンズしか使わないからだ。
何故、その事がマイクロフォーサーズ規格の発表時に
アピールされなかったのか?は明白だ、もしそんな事を
公言してしまったら、せっかくの新規格のカメラのビジネス
をメーカー自ら否定するような発言となってしまう。
恐らくは開発側は、その事は十分承知した上でμ4/3機を
試作したのであろう。でもこれも推察だが、その裏の事実は
決して上司へや検討会議の場では言わなかったに違い無い。
それがバレたら「他社製のレンズを使う為のカメラを
作ると言うのか?!怒」と、大問題になる(汗)
だけど、開発者は恐らく相当のカメラマニアだ、PANA社は
いくらライカのブランド銘を買ってつけているとは言え、
上級マニア層等がパナソニック銘のレンズに何も期待して
いない事は良くわかっている。だから、そもそも自社製の
レンズなんて、市場競争力が無いではないか・・と。
で、うがった見方をすれば、マウントアダプターの発売が
やたらと速かった事を鑑みれば、積極的にサードパーティ
に、それらを作って売るように、と裏から事前に手配して
いたのかも知れない、とまで妄想が膨らんでしまったのだ。
(つまり、μ4/3の規格・仕様書をアダプターメーカーに
送りさえすれば、製造は容易だ)
そして、マニア層を中心にμ4/3機等で、アダプターを
用いてオールドレンズを使う事が流行し、2010年代前半
は「第二次中古レンズブーム」と言える様相となったが、
この流行はマニア層を超えて一般層に波及する事は無かった。
だが、この事が、ミラーレス機の普及に功績があった事は
間違いの無い事実だ。やはり「確信犯」であった事だろう。
それらの憶測の真偽を確かめる格好の機会が私に訪れた。
写真関連の業務とは違う、デジタル画像処理の技術的な件で、
パナソニック社を訪問して、商談(技術討議)を行う機会
が、2009年初頭にあったのだ。
この話は、他のDMC-G1関連の記事でも書いた事があるので
簡単に書くが、要は、DMC-G1の開発陣は、皆、とてつもなく
カメラ技術および撮影全般に詳しい人達であったのだ。
後日、よくよく考えてみると、その数年前に、関西では
大きな2つのカメラメーカーが、カメラ事業から撤退して
いる。それらのメーカーのベテラン技術者であったのでは
なかろうか? と推察していた。
恐らくは、ミラーレス(μ4/3)機の規格そのものも、きっと
彼らによるアイデアが発祥であったに違い無い、とも想像した。
私は商談よりも、DMC-G1そのものに強い興味を持ってしまい、
後日すぐにDMC-G1を入手し、使ってみると、さらに驚いた。
事前の予想よりも、まだそれを上回るほどに「操作系」の
完成度が高かった。つまり、あらゆる点でムダが無いのだ、
それは、マウントアダプターを使った際にも同様であった。
DMC-G1の無駄の無い操作系は、銀塩傑作機「MINOLTA α-7」
(2000年)にも通じるものがあるし、またDMC-G1より後年の
製品だが、SONY NEX-7(2012年)の「動的操作系」とも
通じる優れた設計思想であった。
この「設計思想」の源流は、1990年代末のMINOLTAにあり、
そのノウハウが、2000年代末のPanasonic機、そして、
SONY機などに人的資源と共に受け継がれていたのだろう、
と、私はそう結論づける事とした。
これは勿論、悪い話では無い。たとえカメラメーカーが
無くなってしまっても、その設計思想の血脈が、なんらかの
形で他社のカメラに引き継がれて行く事は、とても良い事だ。
ただ、そうした所までユーザーや評論家は、わかっている
のであろうか? DMC-G1が発売された後、画素数が少ない
とか、色つきボティは軟弱だとか、AFが遅い、とか、
ユーザーも評論家も、好き勝手に、表面的な部分だけを見て
評価をしているだけの状態であったのだ。
でもまあ、それもやむを得ないであろう、例えば数百台の
カメラを実際に長期に渡って使ってみるなどの、「研究」
とも言えるレベルの時間と予算と手間をかけないと、なかなか、
カメラの設計思想の本質迄は、わかって来ないだろうからだ。
一般ユーザーはもとより、評論家層でもそれは無理な話だ。
それに、ミラーレス機は全くの新分野だ、旧来の一眼レフの
感覚や価値観でそれを評価しても、全く意味が無い事だ。
Clik here to view.

予備機まで購入している。こんな場合、個体識別の為に
ボティ・カラーバリエーションがある事は非常に助かる。
私は他にも同じ機体を複数所有しているケースがいくつか
あるが、まったく同じ機体色だと機材ローテーション上で
混乱を招く。ごく簡単な例をあげれば、外出前にバッテリー
を充電しておく必要があるか無いか?等、見た目が同じ機体
の場合は、一々それを管理または覚えておく事が困難だ。
旧来の感覚のまま「色つきボディは軟弱だ」と言うのでは
無く、その変化による長所と短所をよく分析する事が重要だ。
Clik here to view.

「コスパが最も良いレンズ交換式カメラ」として、MFレンズ
とのセットで、何人もの知人友人に勧めている。
DMC-G1で撮影をした上写真の女性も、DMC-G1とMF50mmの
レンズのオーナーだ。
*その後のLUMIX Gシリーズ 2010年代~
PANAのGシリーズは、その後、特異なマーケティングスタイル
を展開した。それ以前の時代の各社の一眼レフは、銀塩時代
からデジタル時代に至るまで、いずれもが、例えば、初級機、
中級機、高級機・・と、明確に価格帯と性能とを差別化した
ラインナップを組んでいた。
ところが、PANAのGシリーズでは、性能や価格での段階的な
ラインナップを行わず、以下のような感じであった。
G :本格的写真撮影を中心とした正統派の中級機
GF:小型軽量でファッショナブルな機体(入門機)
GH:本格的動画撮影を意識した中高級機
GX:ベテラン層やシニア層向けのややマニアックな機体
GM:超小型化をコンセプトとした機体
こういうラインナップとなる理由は2つ推測できる。
1)ミラーレス機は新規市場であり、どのような消費者層が
どのようなニーズでカメラを買ってくれるかが不明である。
であれば、消費者層をターゲット毎に分けて、それらの
個別に対応し、個々に販売状況とか市場ニーズ等を反映
させていく(又は、ユーザーの反応を見て今後のシリーズ
をどう展開させていくかを決める)戦略が得策であろう。
さらに加えて、Panasonicは後発参入メーカーである。
ユーザー層の動向調査は、他の老舗カメラメーカーよりも
慎重に行う必要がある。
2)μ4/3では、撮像センサーや画像処理エンジン等の使用可能
な部品の種類が少なく、また規格上でもセンサーサイズは
予め決められている為、センサーや画像処理エンジンで
性能差を作り出すようなラインナップを組む事が、そもそも
困難である。
まあ、これの傾向はPANASONIC社に限らず、他社ミラーレス
機でも同様であった。オリンパスもμ4/3初期には、PEN、
PEN Lite、PEN Miniの3シリーズを続けざまにリリースし
市場の反応を探っている。
後年さらに、OM-Dシリーズを追加、その中でも、OM-D E-M1
E-M5、E-M10系列は、それぞれターゲットユーザー層が異なる
し、加えてPEN-Fまで追加している。
すなわち、数年かけて、だんだんとターゲットユーザーの
具体像が見えて来た、という状況であろうし、もっと年月が
経てば、市場環境の変化などもあって、さらにユーザー層は
微妙に変遷を続けていく事であろう。まあ、そういう変化に
も耐えられるだけの製品ラインナップを作るという事であり、
一眼レフのような価格別ラインナップでは、市場状況への
柔軟な対応が難しくなってしまう訳だ。
また、SONYでも同様だ、2010年発売のNEX-3とNEX-5は、
当初は、ほぼ同じ仕様の機体で何故2機種あるのかの理解に
苦しむ要素もあったが、その後数年間で、NEX-3を女性等
向け、NEX-5を男性向けに細かい仕様チューニングを行って
いる。それらの「テストマーケティング」が一段落した
段階での2013年には、いさぎよくNEXシリーズを廃止し、
本格的なユーザー層向けのフルサイズ・α機をリリース。
旧来のNEXもαにブランド統合し、「上位機種を上級層が
使っているから、ビギナーもSONY αを買え!」といった、
「トップダウン戦略」に全面的に切り替えている。
ただ、このような「広角打法」的に、同時に複数の
ユーザーニーズを探り出すという市場戦略は、当然ながら
失敗する、あるいは発展性の無い、はたまた市場の変化に
対応しきれない、といった製品カテゴリーも出てくる。
Panasonicについては後述するが、他社では、NIKON 1
シリーズや、FUJIFILM X-Mシリーズ、PENTAX Qシリーズ、
同K-01等は、市場では既に廃止または凍結されている
ラインナップだ。
後発のCANON EOS Mシリーズでも、後年においてEOS M5、
M6、M10、Kiss Mそして高級機EOS Rの複合ラインナップ
を「広角打法」的に並行展開し、その中から生き残れる
シリーズを模索していたが、2018年頃からは、
フルサイズ機EOS Rシリーズを主力に切り替えている。
Clik here to view.

Gだが、一度休眠しかけたが、G7で復活、G8あるいは
G9からは高付加価値型機として高額商品となった。
(加えて海外生産とし、さらなる利益率向上を狙った)
GHは、GH4より、高付加価値型のハイエンド機に設定。
GXは、GX7シリーズだけ生き残って,それのバージョン
アップが繰り替えされている(いた)。
GMは、GM5をもって凍結(終了)と思われる。
GFは、引き続きエントリー層向けの展開を続けているが、
ボディ単体発売は無くなり、新製品も減っている。
Clik here to view.

DMC-GX7 MK2(2016年)、DC-GX7 MK3(2018年)と
この型番機体のみ、順次バージョンアップされていた。
他のシリーズでは、1から始まり順次番号が増えて
いくケースが大半だ(例:GF1~GF10)
下写真は、DMC-GF1(2009年)である。
Clik here to view.

略と思いきや、そうでもなく、LUMIX最初期の2001年
頃のコンパクト機でも、DMC型番となっていた為、
LUMIXの真ん中のMの字か、あるいは「松下」のMなのか?
または「デジタル・メディア・カメラ」説も有力だが、
その詳細は不明である。
ただ、3文字型番は、商標上の識別力が発生する可能性
がある。例えば、他社が「DMC」という企業名や
ブランド名で、その商標をその商品分野(カメラ等)で、
取得していたとすると、それの権利を主張された場合、
PANASONICは「DMC」銘の使用料を払わなくてはならなく
なるのだ。これは国内の話のみならず、全世界に輸出する
には、各国での商標取得状況を調査しなくてはならない。
これは大変な手間がかかるし、おまけに、ある時期は
OKであっても、ある国で、ある企業が、DMCの商標を
取得し、強引にPANASONICに使用料を請求する訴訟が
いつ起こってもおかしく無い。
まあ、そういう事例が実際にあったのか無かったかは
不明であるが、ともかく、それへの安全対策であろう。
商標としての識別力が発生しにくいと思われる2文字
型番に改められる事となり、2017年以降のPANA機では
旧来のDMC型番ではなく、DC型番に変更されている。
Clik here to view.

その国などにおいて、十分に知名度が高い英字2文字の
企業名やブランド銘では、意匠(デザイン)との
組み合わせで、商標を取得する事が出来る模様だ。
日本国内での具体例としては、「JR」(鉄道)や「JT」
(タバコ)、「au」(携帯電話)等があると聞く。
*所有LUMIX Gシリーズと、その全般的な特徴
私のLUMIX Gシリーズの所有機はさほど多くは無く
以下の通りである。
DMC-G1 (2008年)x2台 (ミラーレス第1回記事)
DMC-GF1(2009年)(ミラーレス第3回記事)
DMC-G5 (2012年)(ミラーレス第7回記事)
DMC-G6 (2013年)(ミラーレス第10回記事)
DMC-GX7(2013年)(ミラーレス第12回記事)
DC-G9 (2018年)(ミラーレス第?回記事、予定)
いずれも、ミラーレス・クラッシックスの各記事で
詳細(用途、長所、短所等)を紹介済み/予定である。
ミラーレス時代初期(2008年~2013年、私の
定義するところの、第一世代~第三世代)の機体が
殆どなのは、この時期のLUMIX Gシリーズは
前述の「操作系の充実」による完成度が高い事がまず
重要な長所であった事、そして性能もまずまずであり、
決して他社ミラーレス機にひけを取る事もなかった。
Clik here to view.

力の低いPANA製品であった事で、中古相場の下落が激しく、
2年前位の機種でも2万円くらいで安価に買う事が出来て
とてもコスパが良かった訳だ。
これはもう、当時であれば買うべき機体であっただろう。
*以降のLUMIX Gシリーズについて
しかし2015年以降、私が定義するミラーレス第四世代
(成熟期)に突入すると、LUMIX Gシリーズの主力機と
なりうる本格派機体の多くは、「超絶性能」を搭載した
「高付加価値型」商品となってしまった、つまり大きく
値上げされた訳であり、コスパの低下が甚だしい。
まあそれでも、前機種よりも様々な改善点が見られる
ならば、コスパの悪さに目をつぶり、パフォーマンス
だけを重視して購入する事もありうるだろう。
しかし、DMC-GX7以降の機体では、それまでのDMC-G
シリーズの特徴であった「無駄の無い操作系」という
職人芸的かつ優れた設計要素が無くなってしまっている。
前述の「設計思想」の話に強く関連するが、この時代
以降のLUMIX Gシリーズには、DMC-G1の時代の当初に
あった優れた設計思想が感じられない。これも推測だが、
当初の優れた設計陣は、異動とか退職とか昇進で、
もう残っていないのであろうか?だから設計思想が
変わってしまったのだと思われる事が1つ、
あるいは、もう市場での消費者層のニーズが、大幅に
変化してしまい、「写真を撮る」という行為が特別な
事ではなく、誰にでも行えるようにする為、あえて
「操作系」のダウングレードを続けているのかも知れない。
そういう事は、カメラを手にして十分に使ってみれば、
だいたい推測できる、どれだけカメラを「写真を撮る
道具」として作っているか否か、の差異は明白だ。
例えば、DMC-GX7は、カタログスペック上では
優秀な機体である。276万ドットEVFや、最速1/8000秒
シャッターは当時のミラーレス機としては最高クラスだ。
おまけにPANA機初の内蔵手ブレ補正まで搭載されている。
だが、写真を撮るカメラとしての性能がヘロヘロに低い。
AFはダメ、MFも使い難い、純正レンズを付けても
マウント・アダプターを使っても、どちらもダメ、
操作系は全然練れておらず、無駄なダイヤルが出たり
煩雑な操作が色々と発生する。旧来のバリアングル式
モニターも失われ、EVFとモニターが同じ縦方向に
ティルトしても、いったい何の意味があるのか・・?
すなわち全体的にカメラとしての完成度が低すぎるのだ。
Clik here to view.
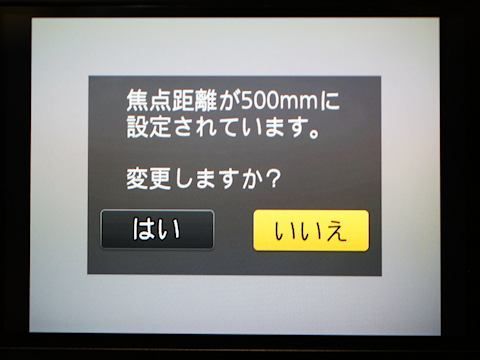
カメラの本質の部分が未成熟で、改良もされていない。
「これは、やはり設計チームが居なくなったな」と
私は推察し、これらの後継機を買い控えする事とした。
おまけに2018年のDC-G9は、PROのサブネームをつけた
典型的な高付加価値型商品となった。発売時実勢価格は
最初期のG1(2008年)からは何と約4倍(実質5万円台
→21万円)と、考えられない程の値上げ幅だ。
僅か10年で同様な商品の価格が4倍にもなった例は、
1970年代の10年間が「狂乱物価」と言われて、物価が
およそ3倍になった時の、それ以上の値上げ幅である。
その1970年代当時は、トイレットペーパーを買い溜め
するなど、市場は大騒ぎとなっていた。すなわち暴動が
起こってもかしく無いという事であり、DC-G9に限らず
他社のカメラでも起こっている近年の新機種の大幅な
値上げに対し、ユーザーや市場は何故冷静なのだろうか?
写真を撮る為の実質的な性能がほとんど向上していない
にも係わらず、カタログスペックだけ上げて、値上げを
繰り返していたら、「ふざけるな!」とユーザー層が
怒っても決して不思議では無い筈だ。
まあDC-G9に関しては、カタログスペックは高性能なので、
当初の市場での評価はなかなか良かったが、そうした
評価に関しても、非常に注意して聞く必要がある。
すなわち、高額商品となれば、それが売れれば、メーカー
や市場(流通、小売店)などは、どこも儲かって助かる。
そして、性能が高い商品を褒める事は、どこからも
文句が出ることは無い。だから、市場や評論家などは
高性能な高額商品を、いつの時代でも褒め称えるのだ。
でも、市場が儲かるという事は、ユーザー(消費者)は
損をしている訳だ。この状態を本ブログでは「ユーザー
の負け」と称している。上級の消費者(例:主婦層)で
あれば、「消費者の負け」となる買い物は絶対にしない。
「モノを高く買うのは負けである」という強い意識を
日常的に養っているからだ、当然ながら、それに伴う
「絶対的価値感覚」も持っている。
私も同様だ、コスパの悪い商品を買う事は絶対に無い。
まあでも、パフォーマンス(実用性能)が十分に高かったり
唯一無二の機能や性能を持っている場合では、その限り
では無い、パフォーマンスはコストよりも重要な要素だ。
で、市場での評価、評論家の評価、あるいは人気投票、
それらの評価は、本当にその機材を実際に所有して使って
いる人の評価であるか?は、とても重要なポイントとして
十分に注意を払う必要がある。持ってもいない機材に
ついて、色々と語っているだけではなかろうか・・?と、
疑念を持つ事は決して悪い事では無い。
DC-G9だが、後日、「本当にこれが高価格に見合う
パフォーマンスを持っているのか?」という観点から、
そして、PanasonicのフルサイズLマウント機の展開開始と
OLYMPUSの分社化により、μ4/3機の絶滅を危惧して
一応入手している。ただ、本記事執筆時点では評価が
間に合っていなかった為、詳細は別記事に譲ろう。
*LUMIX ミラーレス機 Gシリーズの総括
という事で、2008年~2013年頃のLUMIX Gシリーズ機に
ついては個人的な認識としても好評価であり、優れた
機体が多く、当然ながら所有機種数も多かった。
Clik here to view.

ついては、残念ながら興味を持てなくなってしまった。
(ちなみに、2019年からのフルサイズ LUMIX Sシリーズ
も、同様に全く興味が持てない)
でも、それは、PANASONICだけの話ではなく、あらゆる
メーカーの様々な世代(時代)のカメラで、同様に
繰り返し起こる歴史である。
なお、Gシリーズに関しては、以下の技術的革新がある。
2008年 DMC-G1 世界初のミラーレス機
2010年 DMC-G2 タッチパネル操作系搭載
2013年 DMC-G6 ピーキング機能の搭載
2013年 DMC-GX7 手ブレ補正機能の搭載
2014年 DMC-GH4 4K動画対応 空間認識AF搭載
2015年 DMC-GX8 Dual I.S. 機能搭載
様々な新機能は、ユーザーによっては有益なものも
あるだろう。ただ、勿論、それらの新機能を必要と
しないケース(例:4K動画は撮らない、等)も
あるだろうから、それによる「高付加価値化」
(すなわち、値上げ)は歓迎できない場合もある。
その新機能等が、「ユーザー側から見た付加価値」
(つまり製品を欲しいと思う魅力)に、なるか否か
は、結局のところ、ユーザーによりけりなのだろう。
そして、上記の年表では、2015年以降における、
Panasonicの特徴的な技術革新は記載されていない・・
本シリーズ記事「カメラの変遷」では、1970年頃~
2020年頃の、約50年間の各カメラメーカーのカメラ
の歴史を紹介しているのだが、中には、ある時代の
あるメーカーの、ある種類のカメラに魅力を感じずに、
その時代の機種を1台も所有していない事も良くある。
しかし、また後年に新機能の搭載等で、魅力のある
機種が出てくるのであれば、その時点で、そのメーカー
のカメラを、また買い始めれば良いだけの話である。
Clik here to view.

のカメラばかり買って使っていると、殆ど理解できない
感覚であろう。まあ、そのあたりは趣味の世界であれば、
個人の好き好きと言えるであろうが、趣味の範疇を超えて
実用的に、または業務上で、あるいはマニアックな観点で
カメラを使い続けようとする場合、その特定の時期の
特定のメーカーの「ビハインド状態」(=他社に比べて
遅れている。すなわち、性能や機能が劣っていたりして、
魅力が無い状態)があっては困る訳だ。それでは、
その期間、そのメーカーのカメラ(と交換レンズ)が
使えなくなる。あるいは我慢してストレスを持ちながら
使わざるを得なくなる。
その問題を避ける為にも、複数のメーカーのカメラを
併用して使わざるを得ない。
でも勿論、そのビハインド状態が永久に続く訳ではない。
もしそういう状態となったら、そのメーカーのカメラは
だんだんと評判を落として、事業が継続できなくなるから、
必然的に「盛り返し」の措置を図ってくる訳だ。
ただ、それもままならず、カメラ事業から全面撤退した
メーカーは、本シリーズ記事での50年間の歴史の中でも
残念ながらいくつもある。
Clik here to view.

思えば、買い控えをする「選択権」を持っているのだが、
メーカー側はそうはいかないであろう。カメラが売れなく
なって事業撤退ともなれば、その社員や関係者は路頭に
迷ってしまうかも知れない訳だ。
だから、メーカー側はカメラを作る事には真剣である。
それに応えるには、ユーザー側も真剣でなければならない、
ただ単に「値段の高いカメラは良いカメラだ」などと
思い込んでいるようだったら、ちょっと違うと思う。
ユーザーとして欲しいカメラのイメージや価値感覚を
ちゃんと養わなければならないし、あらゆる形でそうした
ユーザーニーズをアピールしていかないとならないだろう。
それは別に積極的に意見を言うとかのみならず、消極的な
スタンスとしても「気に入らないカメラは買わない」等
で、個人の価値感覚をしっかり持つ事だ。
「誰かが良いと言ったから買う」などの行為は勿論NGだ。
・・さもないと、どんどんと欲しくも無い類のカメラが
市場に蔓延してしまう事になる、そうなったら、カメラ
ファン層や市場関係者は、皆、誰もが困ってしまう訳だ。
(事実、そういう状況において中古カメラブームが起こり、
市場が混迷してしまった歴史もあるが、そのあたりは
本ブログや本シリーズでは何度も書いてきた事である)
さて、「さすがに最新の所有機種が2013年製迄では、
仕様的老朽化が酷い!」と感じ、本記事執筆後に
代替の後継機として、DC-G9(2018年)を購入した。
Clik here to view.

いずれ、「ミラーレス・クラッシックス」の記事で、
別途紹介する事とする。
ただし、高価すぎて、コスパがとても悪い機種なので、
あまり好評価にはならない事は、予め述べておく。
最後に、ここまで、主にGシリーズのカメラの説明を
して来たが・・ 2019年のSシリーズ(フルサイズ
Lマウント機)の発売以降は、Gシリーズ(μ4/3機)の
新発売は、動画向けのGHシリーズを除き、ほとんど無い。
----
さて、今回の記事は、このあたりまでで・・
次回記事に続く。