今回は補足編として、アポダイゼーション光学エレメント
を搭載した特殊レンズの所有機種4機種の内の2本、
新旧版の「STF」の対決記事としよう。
過去記事、「特殊レンズ・スーパーマニアックス第0回」の
「アポダイゼーション・グランドスラム」編でも、両レンズ
を取り上げているし、まあ、他にも本ブログでは過去記事で
複数回紹介しているレンズだ。
今回の記事では、個々のレンズの特徴等の詳細は何度も
説明済みであるので割愛し、また別の視点での記載としたい
のだが、そろそろ内容的にも書き尽くした感もある(汗)
「では、何故何度も紹介するのか?」と言えば、理由として
”レンズを死蔵させず、定期的に使ってあげる必要がある”や
”高性能レンズをたまに使い、性能判断価値感覚を維持する”
為である。
まあ、ともかく始めよう。
まずは1本目のSTFレンズ。これは1998年製だ。
![_c0032138_16193794.jpg]()
(新品購入価格 118,000円)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
MINOLTA/SONY α(A)マウント用(フルサイズ対応)の
MF単焦点望遠レンズ。APS-C機で使用の際は200mm相当と
やや長目の画角となるが、135mm単焦点レンズの中では、
BEST 5に入る最短撮影距離87cmの性能が強力な武器であり、
最大撮影倍率は、フルサイズ時1/4倍(0.25倍)、APS-C時
0.375倍、APS-C機(デジタル)テレコン1.4倍時約1/2倍、
同デジタルテレコン2倍時で3/4倍(0.75倍)、および
μ4/3機に装着+デジタルテレコン2倍時で等倍(1.0倍)
となる、マクロレンズ並みの近接撮影能力を誇る。
(注:本レンズよりも最短撮影距離が短い(72~80cm)
135mm単焦点レンズでも、仕様上の最大撮影倍率は、
同等の0.25倍に留まっている状態が殆どである)
この結果、人物ポートレート(焦点距離がやや長すぎる)
よりも、フィールド(屋外)自然観察用レンズとしての
用途が、本レンズの使いこなしの要となるであろう。
![_c0032138_16193707.jpg]()
この用語自体は、MINOLTA時代での同社による造語である。
これは、「アポダイゼーション光学エレメントを搭載した
レンズ」という意味である。この構造を持つレンズは、本STF
が世界初の発売であったので、新しい用語が作られたという
事なのであろう。
アポダイゼーションとは、グラデーション状に、順次周囲に
行く程に暗くなっていくフィルター(光学ガラス)であり、
レンズ内にそれを搭載すると「ボケ質」が極めて良くなる。
これの光学原理は非常に難解であり、例えばFUJIFILM社の
WEBにAPD(アポダイゼーション)の原理と効能が書かれて
いるので、それを参照してもらえれば良いとは思うが、ただし
多分に宣伝的内容であり、技術理解の視点では無いとも思う。
また、他の資料は、専門書等の範囲を含めても、ほとんど
見当たらず、仮にあったとしても、専門的ジャンルであるので、
その解説は難解であろう。
(注:レンズや光学に限らず、どの技術分野においても
専門家の解説ほどわかりにくいものは無い(汗) これは
何故なのだろうか? 自身の研究だけに夢中になって他者に
説明する経験や技能が少ないのか? あるいは教えたく無い
のであろうか? はたまた自身の持つ知識を自慢したいのか?
たいていの場合「本来は簡単な事を、わざと、わかりにくく
書いているのか?!」と、極めて不快になる事が殆どだ。
真の「専門家」であるならば、難しい事を、誰にでも理解
できるように上手に説明するスキルを持つ事が必須だと思う)
・・まあ、という状況なので、誰も上手く説明できないから、
消費者層は理解しずらいし、値段も高いし、スペックも凡庸
なので誰も買わないから、世の中おいてはアポダイゼーション
のレンズは評価や情報も多く無く、殆ど知られていない。
![_c0032138_16193770.jpg]()
このあたりの概念は、初級中級層では「ボケ味」といった、
極めて意味が曖昧な用語としてイメージが広まっている為、
いったい具体的に何が良くなるのか?が理解できない。
ちなみに、本ブログでは、そのあたりはちゃんと定義している。
(匠の写真用語辞典第13回記事参照)
簡単に言えば、ボケの度合いを表すのが「ボケ量」であり、
それは被写界深度と等価だ。「ボケ質」は、そのボケ部分の
品質的な良否であり、まあ「綺麗にボケる」という意味だ。
さらに言えば、「ボケ形状」という、あまり使わない用語も
一応定義していて、木漏れ日ボケとか、夜景ボケ、あるいは
逆光のゴースト等で、絞り部品(羽根)の形状が写真に写って
しまう事。それから「口径食」の発生により。夜景点光源等の
ボケがレモン形状等に変形してしまう事も指す。
なお「円形絞り機構」により、木漏れ日やゴーストにおける
「ボケ形状」は改善できるが、ここで定義する「ボケ質」の
向上へは、「円形絞り機構」は寄与しない。
メーカー側では「円形絞り」の効能として、わざわざ曖昧な
用語を使って「ボケ味が良くなる」と謳っているケースも
あるので要注意だ。すなわち「効能をはっきりと書きたく無い」
とも推察できるからだ。
(ここらへんの定義が曖昧だからか? 近年のビギナー層では
夜景点光源等で円形形状のボケが出ると、「玉ボケ」と言って
それを有りがたがり、あたかも偶然それが出る、または専門的
機材が無いと出せないものだ、と誤解してしまっている。
勿論、その状態は、どのレンズでも絞り開放で容易に発生する
ので、プログラムAEで撮らず、絞り優先AEを主に用いるべきだ。
ただし、中上級マニア層の一部では「円形ボケ」の中で、
特に輪郭線が残る状態を指してのみ「シャボン玉ボケ」又は
「バブルボケ」と呼ぶ。こちらの状態であれば、その特殊性は
あると思う→一部のオールドレンズ等でのみ発生する)
なお、本STF135/2.8ではSTFと書かれたT4.5-T6.7の範囲
においては、一応絞り羽根10枚の円形絞りを採用していて、
「ボケ形状」の改善についての配慮も見られる。
ただし、絞り環をA位置として自動絞りで使う場合には、
9枚羽根となる模様だ。(しかしながら、本レンズにおいて
自動絞りで、絞り込んで使う用途は、まず考えられない。
そういう撮り方をするならば、より新しい高解像力仕様の
中望遠レンズを使った方が有利であろう。レンズおよび
カメラも含めたシステムでは、その特徴を最大限に発揮した
使い方をしないと意味が無い訳だ)
それから、本STFはF2.8(T4.5)と小さい口径比ながら、
フィルター径φ72mmという、開放F2級に相当する大きな
(135mm÷φ72mm≒(F)1.87 この口径比はF2級だ)
前玉により瞳径(有効径)を十分に確保していて、いわゆる
「口径食」(注:多数の意味がある。ここでは、ボケ形状に
影響する要素を示す)は、発生しない模様だ。すなわち
「ボケ質やボケ形状」に係わる一般レンズの弱点を全て解消
しようとした、稀有な設計コンセプトである事が見て取れる。
![_c0032138_16193894.jpg]()
レンズ全般を通じてもさほど多くは無く、かつ、一般的には
様々な撮影条件において、常にボケ質に優れる訳でも無い。
(例:「ボケ質破綻」 匠の写真用語辞典第13回記事)
それに、ボケ質に優れたレンズは、比較的高価なものが多いし
初級中級者が欲しがるような人気のスペックのレンズでも無い。
よって、まず誰も買わないような特殊な仕様のレンズだけが、
ボケ質に優れるケースが多く、結果的に初級中級層においては
「ボケ質」が良好なレンズを所有したり、その描写を目にする
機会も殆ど無い。だから、いつまでたっても「ボケ質」への
概念理解は、残念ながら進まない。
また、一眼レフの場合は、多くのケースで開放測光であり、
撮影時に絞り込まれる状態でのボケ量やボケ質はファインダー
では確認が困難だ。かつ、ファインダー/スクリーンの仕様・
性能上、ボケ質については、殆どわからない。
よって、銀塩時代であれば現像後、デジタル時代でもPCに
取り込んで写真を見る段階となって、中上級マニア等では
「このレンズはボケ質が良い(悪い)」と語っていたのだが、
撮影状況の再現性が厳しい(絞り値のみならず、被写体距離、
背景(前景)距離、その絵柄等によってもボケ質は変化する)
ので、単に撮った写真を数枚だけ見ても、レンズのボケ質の
評価は困難または不可能であった訳だ。
ミラーレス機または高精細EVF搭載型一眼レフ(例えば、今回
使用のSONY α77Ⅱ等)であれば、僅かではあるが、撮影前に
ボケ量、ボケ質の事前確認が可能だ。よってボケ質が悪くなる
撮影状況を避ける「ボケ質破綻回避」の技法は、そうした現代
機材を使わない限りまず不可能であるし、機材があったとしても
高難易度の撮影技法となる為、初級中級層ではまず対処困難だ。
そんな状況なので「ボケ質」への理解や、それを意識する撮影
技法は、現代でもまったく普及していない。
・・で、そうだとしても、現代で4本(機種)だけ存在する、
アポダイゼーションレンズは、いずれもボケ質に優れたレンズ
であるし、様々な撮影シーンにおいて、ボケ質破綻が起こる
リスクも少なく、たいていの場合で、良好なボケ質が得られる
という、非常に貴重な特徴を持ったレンズ群である。
(追記:2019年発売のCANON RF85mm/F1.2 L USM DS
は、新規の「DSコーティング」を採用しているが、
どうやらこれはアポダイゼーション光学エレメントと
同等な効能を発揮する模様だ。
つまり史上5本目のアポダイゼーションレンズとなる。
これまでのSTF/APDを全部所有している私としては、
このレンズへの興味は強いが、しかし、発売時価格が
40万円程度の超高額レンズとなってしまった為、
まず絶対と言っていいほど買う事は無いであろう。
その金額を出すならば、残りの4本のAPD/STFレンズ
を(中古で)全て購入できる!)
![_c0032138_16194712.jpg]()
発売後20年以上を過ぎた状態においても、本レンズを
超える描写表現力を持つレンズは殆ど存在しない。
まあ、近年の新鋭レンズで、本レンズよりも解像力性能を
高めたものもあるのだが・・(例:SIGMA Art 135/1.8)
ボケ質も含めた(描写)表現力は、本レンズには敵わないで
あろうし、そもそも、使うカメラ機材側の仕様であるとか、
どんな被写体を、どのように撮りたいのか?で、解像力性能
を常に要求される訳でも無いであろう。
例えば、遠距離のビル等を撮影して、窓が写っているかどうか?
等の評価をしても意味が無いのだ。本STF135/2.8では、そもそも
そんな被写体を撮りたい等とは、絶対に思わないだろうからだ。
(=実際の使用条件を考慮しない評価手法は適切では無い)
逆光耐性、口径食、ボケ質破綻、コントラスト特性等における
弱点も全く無い。本レンズではたいていフードを装着しないで
使っているが、衝撃保護以外の観点では、逆光対応等でフード
を必要とする事は無い、それを使わないと写りがヘロヘロに
なってしまうような軟弱なレンズでは無いのだ。
![_c0032138_16194728.jpg]()
まず、大きく重く高価な三重苦レンズであるが故に、常に
これを持ち出したいとも思いにくい。
(価格的には、例えば近年の新鋭の高額レンズと比べると
安価に思うかも知れないが、新鋭レンズが高額すぎる事を
決して忘れてはならない。本レンズが発売されてから
20年ちょっとで、物価が3倍や4倍にもなっている訳では
無いのに、レンズの値上がり度合いは、まさしくそういう
比率だ、消費者側で、絶対的な価値感覚を再度認識する
必要があるだろう。まあ、近年のカメラ・レンズ市場が
大きく縮退している状況は良くわかってはいるが・・
だといって、メーカー側の対策として、単純に「値上げを
すれば良い」という話ではあるまい)
MF操作は、AFに慣れた現代のユーザー層には「かったるく」
思える事であろう、だだまあ、MFに慣れているマニア層の
御用達のようなレンズであるから、それはあまり欠点には
ならないだろう。
後、「描写力が高すぎる」という問題点も、本レンズの紹介
記事では毎回のように述べている。
勿論これは別に欠点では無いが、あまりテクニカルな要素を
用いなくても、普通に撮れば、誰でもが高描写力を得られる
という点だ、すなわち、これでは「差別化」も出来ないし、
(=初級者が撮っても良く写るので、スキルを活かせない)
「使いこなし」の楽しみが少なく、これが「エンジョイ度」
の評価で僅かな減点となる。
![_c0032138_16194785.jpg]()
光量がかなり減り、実効F値(すなわち「T値」)が暗い。
現代のカメラであれば、T4.5ごときは、超高感度とか、
内蔵手ブレ補正機能でなんとでもなるが、銀塩時代の低ISOの
フィルムかつ手ブレ補正無しでは、本レンズを室内中距離撮影、
(例えば結婚式の撮影等)で使うのは、少々厳しかった。
(注:各アポダイゼーションレンズは、その効能を最大限に
発揮する為には、「絞りを開放で使う」事が大原則である。
よって本STFのT4.5は、例えば、他の一般レンズをF5.6
程度まで絞って使う(=諸収差低減の目的)場合よりも、
むしろ実用的には明るいかも知れない。ただまあ、銀塩
時代ではあるまいし、現代レンズを常に絞って使うという
用法は、それが必ずしも適正な撮影技法だとは言い難い)
中距離人物撮影、という点においては、本STF135/2.8を、
APS-C機はもとより、フルサイズ機で使っても人物撮影用途
にはやや長目の画角となる。一般ポートレート撮影よりも
屋外遠距離ポートレートとか、室内イベント(結婚式や
ステージ(舞台)系等)に向く画角である。
だが、ステージ等の暗所では、デジタル時代においてもやや
厳しい。その目的には、大口径135mm/F1.8級レンズの方が、
AFである事も含めて、遥かに使い易いケースも多い。
だから人物撮影用途よりも、他の「用途開発」を模索する
事になるだろう。まあ、私の場合には、本レンズの高い近接
撮影能力と、完璧とも言えるボケ質を活用する意味でも、
自然観察用途が最適だと思ってはいるが、このあたりはユーザー
毎の被写体ジャンルそれぞれで用途開発を考えるべきであり、
ノラ猫とか、動物園、鉄道写真等にも画角的には向いている
と思われる。ただしMF操作が必須なので被写体が動体の場合は
それに対応できるMF撮影スキルが要求される事であろう。
まあ、描写力は完璧だが、用途や使いこなしが、やや難しい
レンズであるという事だ。・・とは言え、レンズ・マニアックス
第11回、第12回記事で特集した「使いこなしが難しいレンズ
のワースト・ランキング」に入るまでのレベルでは無く、
多少難しい、という感じであるから、中級層、中級マニア層
以上のスキルを持つならば何も問題は無い事であろう。
![_c0032138_16194710.jpg]()
でも良く見かけ、レア物とはなっていない。
MINOLTA時代・SONY時代も含め、7万円台の中古相場になって
来ていて、性能(描写表現力)からすれば割安感はある。
「トップクラスの描写表現力、最良のボケ質」というものが
どういうものであるかを理解したい、という中級者クラスで
あれば、購入の選択も悪くは無い。
----
そして、2本目のSTFレンズ。こちらは2017年発売だ。
![_c0032138_16195648.jpg]()
(SEL100F28GM)(中古購入価格 129,000円)
(以下、FE100/2.8STF)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
19年の時が過ぎ、その間、MINOLTA→KONICA MINOLTA→
SONYとメーカーは変わり、カメラも銀塩一眼レフから、
デジタル一眼レフへ、ミラーレス/フルサイズ・ミラーレス機
へと変遷を遂げたが、幸いな事に旧型STF135/2.8[T4.5]は、
ずっと継続販売され続けていた。
本FE100/2.8STFは、19年ぶりに新発売された、2本目の
STFレンズである。
旧型では、一般ユーザーではMFで使い難いと思われたので、
本レンズには、AFが搭載されている。
焦点距離もやや短くなって、フルサイズ機であれば人物撮影
にも適する等、汎用性の高い画角となるであろう。
![_c0032138_16195674.jpg]()
(注:暗いその値を書いてしまうと”開放F値が明るいレンズ
が高性能なのだ”と信じて疑わない初級中級層へのウケが
悪くなるから、あえて書かないのであろう。この点なんだか
MINOLTA時代の方が「良心的」であったように思える)
・・その実効F値だが、T5.6と、旧型のT4.5よりも、
さらに暗くなってしまった。
ただまあ、αミラーレス機専用であり、NEX以降のαの時代
では、全てのα(Eマウント)機にISO25600以上の高感度が
搭載されていると思うので、開放F値(T値)の暗さはあまり
問題点にはならないし、一応本レンズにはOSS(手ブレ補正)
も内蔵されている(注:α7系Ⅱ型機以降/α9系においては
ボディ内手ブレ補正搭載であり、その際には、5軸中2軸の
補正をOSSが担当し、残り3軸の補正をボディ側で担当する)
それに、T値が暗いという事は効果の強いアポダイゼーション
を使っている可能性も高く、その視点では問題は無い。
なお、SSM(超音波モーター)表記は無いが、「DDSSM」
(ダイレクトドライブSSM)というモーターを内蔵している。
これはまあ、ピエゾ系の圧電素子の応用なので、例えば
TAMRON社のレンズの一部に搭載された「PZD」と類似の
構造であろう。小型化・静音化・停止精度向上等に役立つ
との効能であるが・・
まあ、技術の内容はともかく、実用上では、本レンズの
AF速度はあまり迅速とは言えず、AF精度も悪く、もう一声
という感覚もある。ただまあ大きく重いレンズであるから、
AF駆動が遅くなるのも、やむを得ないかも知れない。
ちなみに新旧STFのサイズ感だが、どちらもフィルター径は
φ72mmと同じであり、重量は旧型が730g、新型が700gと、
大差は無い。
軽量化の代償か?新型はプラスチッキーで、やや高級感に
欠ける。
![_c0032138_16195635.jpg]()
87cmよりも短縮されているが、焦点距離が短くなっている
ので、最大撮影倍率は、どちらも1/4倍(0.25倍)である。
ただし、新型では、手動のマクロ切換リングを廻さないと
近接撮影が出来ず、
通常時 :0.85m~∞
マクロ時:0.57m~1m
という仕様だ。この「手動切換」は、リングも廻し難いし、
撮影距離制限が出るので、結構面倒に思える。
かつ、近接域ではAFの精度も落ちるので、MFを使いたいので
はあるが、シームレスMF時であっても、わざわざAF/MFの
スイッチを使って切り替えたとしても、「無限回転式」の
ピントリングで距離指標もない為、手指での最短撮影距離
での停止感触が無く、かなり使い難い。
近接域を含めたMFにおける操作性への配慮は、旧STFの方に
軍配が上がる。この操作性だけを見たら旧型の圧勝だが、
αミラーレス機では、優秀なピーキング機能があるし、
必要に応じて、EVF内に距離指標も表示できるので、
実用上では新型でもMFでの操作性があまり問題になる事は
無い。(まあ、しかしながら、一眼レフのαフタケタ機も
EVF仕様で、かつピーキング機能も効くので、どちらか?と
比較するならば、やはり旧型の方がMFが遥かに使い易い)
本ブログ、というか、私の評価データベースにおいては、
レンズの評価に「操作性・操作系」の項目は特に設けては
いないのだが、もし、それがあるならば、MFのみという
弱点があったとしても、やはり旧型の方が点数は上であろう。
![_c0032138_16195602.jpg]()
現代レンズらしく、旧型よりも解像感が増しているが、
まあここは前述のように、使用するカメラの仕様とか
どんな被写体を、どのように撮りたいか?で、その効能が
有益かどうかは、変わってくるとは思われる。
それから、本レンズは解像力が優れているので、大画素
からのトリミングの余裕が大きい。
まあ、本ブログでの全てのレンズ関連記事においては、実写
紹介の際には、カメラ側の搭載機能は自由に使っているが
カメラ内部のトリミング等の編集機能は使っておらず、かつ
事後のPCによる過度なアフターレタッチは禁止するルールと
している。(大きなトリミングもしてはならないルールだ)
まあ、レタッチで色々と画像をいじくり廻してしまったら、
レンズ紹介記事の意味が殆ど無くなってしまうからだ。
だが、レンズ紹介記事以外の実用撮影や趣味撮影においては
トリミングやレタッチは常識である。・・というか、編集作業
は必須(必然)であり、特に依頼撮影等の業務用途全般に
おいては、レタッチを行わないで納品する事など有り得ない。
そこまで手抜きをする事自体、許される事では無い訳だし、
他の例では、例えば女優や俳優がメイクをせずにすっぴんで
舞台等に立つ事は、業務上では、まずあってはならない事だ。
約20年前のデジタル転換期では、デジタルカメラの画素数が
まだまだ低い時代であったので、トリミングをすると、目的
とする用途の必要解像度に満たない事もあったのだが、現代
においては画素数はもう不足しておらず、トリミングをいかに
有効活用するかが、編集技能の分かれ目となり、写真納品
品質を左右する事や、編集効率(手間)にも直結する訳だ。
なお、そのデジタル転換期では、写真編集作業が出来ない
銀塩時代からのユーザー層も非常に多く、そうしたユーザー
が「編集するのは卑怯(不公平)だ!」と文句を言っていた、
という残念な時代でもあった。
まあ、「デジタル写真編集必須論」は、もう現代では誰でも
知っている事であり常識であるから、これ以上深堀りはするまい。
![_c0032138_16200375.jpg]()
レンズで撮った写真は、「大きくトリミングしても耐えうる
要素が大きい」という長所があるという事だ。
低解像力のレンズだと、ある程度、大画素から縮小して
「縮小効果」を期待する。これには色々な意味や難解な原理
があるが、つまり簡単に言えば、「2画素を1画素に縮小する
(まとめる)際に、輪郭線がはっきりする」という効果を含む
とも言える。まあつまり、ピントが甘かったり解像力が
低いレンズで撮った画像でも、大きく縮小してしまえば、
ピンボケや低解像感をごまかせる、という意味だ。
だからまあ、フルサイズの高画素機からの縮小写真を見て、
ビギナー層等は「画質が良い」と錯覚するのであるが、それは
そう単純な話では無く、被写体の状況(空間周波数分布)に
よっては、輪郭線等が強く出すぎて、表現したい用途や意図
とは逆効果になる場合もある。
どんどんと脱線しそうなので、少し元に戻す。
簡単に結論を述べよう、「解像力(感)の低い、古い時代の
レンズでは、トリミングを行うよりもデジタルズーム又は
デジタルテレコン機能で拡大した方が望ましく、
新世代の高解像力型レンズであれば、デジタル拡大機能よりも
大画素からのトリミングを使った方が実用的である」という事だ。
ただここもまあ、デジタル拡大の方式(アルゴリズムや
技術仕様)に多分に影響してくる話であり、そう簡単では無い。
この辺は、初級中級層はおろか上級層に至るまで、そう誰でも
画層処理の原理や詳細技術に精通してる訳では無いだろうから
このあたりをいくら詳しく述べても冗長だし、難解でもあろう。
ばっさり理由は割愛する、何か疑問点があれば、自分自身で
実験・研究して確かめてみれば良いと思う。
趣味にしても業務にしても、そういう事は自分で行うのが
基本中の基本だ。何も試しもせずに、頭で考えているだけとか、
単なる思い込みだけとか、誰かがそう言ったからとか、書籍等で
調べただけとか、そういうスタンスは全てNGである。どんな些細
な事でも必ず自分自身で実際に試行して確かめなければならない。
![_c0032138_16200314.jpg]()
いる訳では無い。それらの評価の点数よりも、どういう視点
で、そうした機材を見る(検証する)のか?、という部分や
その為のノウハウを開示する事がより重要だと思っているのだ。
だから、機器の通信販売サイト等で、ビギナーユーザー層が
自身の思い込みで、このレンズは良いとか悪いとか、好き勝手
に評価を書いている事にも全く賛同できないし、それを見て
機材を買うかどうかを決めるスタンスというのも不条理だ。
最終的に信じるべきは、他人の評価ではなく、自分自身の価値
感覚ではなかろうか? ビギナー層では、それを全く持って
いないから「高価なレンズは必ず高い描写力を持つのだ」等と、
ごく単純な思い込みによる大誤解をしてしまう訳だ。
さて、本当に余談が長くなった(汗)
本FE100/2.8STFであるが、操作性等に細かい弱点はあるが
描写表現力における不満点は全く無い。これは誰しもが
そう感じるだるう事であり、現代でトップクラスの高性能
(高描写力、高表現力)のレンズであると思う。
他の問題は価格が高い事だ、定価18万8000円+税は
かなりの高額であり、新品で買うのはよほどの覚悟が必要だ。
中古は稀に出ているが、相場の下落傾向はゆっくりであり、
現代で11万円台くらいか・・ まあ新品よりだいぶマシでは
あるが、依然高価である事は間違いは無い。
パフォーマンスが高いレンズではあるが、あくまで描写力に
係わる部分だけであり、あまり高価に買ってしまうと総合的
なコスパ点は低く評価せざるを得ない。
それと、「絞るとSTFの効果が減る」と書かれたレビューを
見た事があったが、アポダイゼーションの原理からは当然の
事であり、絞って使う用法は、レンズの特徴を消してしまう
為に、あり得ない。各STF/APDレンズは絞り値を「開放から
微動だに動かさない」位の覚悟(?)が必要なレンズである。
![_c0032138_16200364.jpg]()
殆ど使用する事ができない。(注:NIKON Zへは変換可能な
模様だ) まあ、近年の新型α機(フルサイズ)は、どれも
「高付加価値型商品」となって、高価になりすぎている課題も
あって、システムを成り立たせる為の出費も、非常に大きく
なってしまう事も弱点として上げておこう。
初級中級層では、機材へ投資する際に、カメラ本体の事しか
考えていないと思うが、実際には、全く逆に考えるのが良く、
「必要なレンズがあるから、カメラボディを買う」のである。
その際の金額配分比率は、レンズ4対カメラ1にするのが
理想であり(匠の写真用語辞典第16回記事)、旧来は
それを守る事も比較的容易であったのだが(=カメラが安価
であったから)近年においては、まともなカメラを買おうと
すると、下手をすれば本レンズよりも高価な相場だ(汗)
レンズとカメラを1対1の価格比とするのは好ましくなく、
ましてや本レンズのような高額レンズで、そうした
「オフサイド」(カメラ価格の方が突出する)になるのは、
さらに好ましく無い。本レンズは、できれば3万円程度の
ボデイに装着したいのだ。例えば、α6000あたりの
相場感が適正であろう、私は普段は結構そのシステムで使う
ケースも多いのだが、初級中級層だと「フルサイズ機で
なくちゃイヤだ!」と、ダダを捏ねるであろう・・汗
![_c0032138_16200362.jpg]()
「レンズの描写力が高すぎて、レンズに撮らされている
気分になってしまう」(=撮影者の主体性が保てない)
という微妙な弱点を持つ事は、念の為述べて置く。
----
では、最後に新旧STFの両レンズの点数評価をしてみよう。
これは、私が全所有レンズにつけている評価データベース
からの抜粋であるが、あまりレンズ関係の記事でこれを
公開する事は無い。
基本的に、こういう評価点はユーザーの個々の被写体選択、
機材の使用法、何を表現したいか?、何を求めているのか?
そして、利用者毎のスキル(技能)によっても評価は簡単に
変わってしまう。なので、書いてある点数だけが一人歩きを
するのは良く無い、と思っている訳である。
「レーダーチャート」とかで、こうした評価点数をまとめて
いる記事等もカメラ機材に限らず、良く見かけるが、一見
ちゃんと評価している様子であっても、良く良く見ると
そうでもなさそうだ(例:評価軸の項目がまちまちである等)
あくまで評価者個々の独断であろう。
まあ、例えば、ここに5点満点とあって、それをもし疑問に
思うならば、では実際に満点となるには、いったいどう機材を
使ったら良いのか? そもそもそれは信用するべき評価なのか?
・・そういう事を考えて練習や研究をすれば良い、という事だ。
結局、機材を評価するのは、あくまで自分自身なのだから・・
【描写表現力】両者5点満点(★★★★★)
【マニアック】両者5点満点(★★★★★)
【コスパ 】旧2.0点、新1.5点
【エンジョイ】旧4.5点、新4.0点
【必要度 】両者5点満点(★★★★★)
・評価平均値:旧型STF=4.3点、新型STF=4.1点
殆どの評価項目で両者5点満点であるが・・
やはりコスパが減点対象として大きい。約20年の時を経て
新型は旧型よりも勿論高価であり、定価20万円超えは、
そう簡単に誰もが買える金額では無くなっている。
まあでも、旧型の低得点は発売直後の新品購入であったから
であり、現代において旧型を中古で買えば、コスパ点はかなり
良くなり、3.5点程度にはなるだろう。依然高価ではあろうが
なにせパフォーマンスが物凄く高い。
新型のエンジョイ度が旧型よりも、やや低いのは、AF化された
事で、なんだか安直となった印象がある事。それからMFおよび
マクロの操作性が新型はあまり良く無い事が理由としてある。
まあでも、本ブログではレンズの評価点で平均4点を超えれば、
「名玉」としてノミネートされる状態であるので、両者いずれも
その条件には該当する。
どちらかを現代で購入するならば、人物撮影等で実用的に使いたい
のであれば新型のFEマウント版であろうが、より安価な中古相場
で、じっくりと自然観察等の用途で使いたいのであれば、旧型の
α(A)マウント版の選択が良いであろう。旧型の方がシステムを
成立させる為のトータルコストが、だいぶ安価になる利点もある。
----
さて、今回の記事は、このあたり迄とする。次回記事も、
また補足編として高性能レンズの対決記事とする予定だ。
を搭載した特殊レンズの所有機種4機種の内の2本、
新旧版の「STF」の対決記事としよう。
過去記事、「特殊レンズ・スーパーマニアックス第0回」の
「アポダイゼーション・グランドスラム」編でも、両レンズ
を取り上げているし、まあ、他にも本ブログでは過去記事で
複数回紹介しているレンズだ。
今回の記事では、個々のレンズの特徴等の詳細は何度も
説明済みであるので割愛し、また別の視点での記載としたい
のだが、そろそろ内容的にも書き尽くした感もある(汗)
「では、何故何度も紹介するのか?」と言えば、理由として
”レンズを死蔵させず、定期的に使ってあげる必要がある”や
”高性能レンズをたまに使い、性能判断価値感覚を維持する”
為である。
まあ、ともかく始めよう。
まずは1本目のSTFレンズ。これは1998年製だ。

(新品購入価格 118,000円)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
MINOLTA/SONY α(A)マウント用(フルサイズ対応)の
MF単焦点望遠レンズ。APS-C機で使用の際は200mm相当と
やや長目の画角となるが、135mm単焦点レンズの中では、
BEST 5に入る最短撮影距離87cmの性能が強力な武器であり、
最大撮影倍率は、フルサイズ時1/4倍(0.25倍)、APS-C時
0.375倍、APS-C機(デジタル)テレコン1.4倍時約1/2倍、
同デジタルテレコン2倍時で3/4倍(0.75倍)、および
μ4/3機に装着+デジタルテレコン2倍時で等倍(1.0倍)
となる、マクロレンズ並みの近接撮影能力を誇る。
(注:本レンズよりも最短撮影距離が短い(72~80cm)
135mm単焦点レンズでも、仕様上の最大撮影倍率は、
同等の0.25倍に留まっている状態が殆どである)
この結果、人物ポートレート(焦点距離がやや長すぎる)
よりも、フィールド(屋外)自然観察用レンズとしての
用途が、本レンズの使いこなしの要となるであろう。

この用語自体は、MINOLTA時代での同社による造語である。
これは、「アポダイゼーション光学エレメントを搭載した
レンズ」という意味である。この構造を持つレンズは、本STF
が世界初の発売であったので、新しい用語が作られたという
事なのであろう。
アポダイゼーションとは、グラデーション状に、順次周囲に
行く程に暗くなっていくフィルター(光学ガラス)であり、
レンズ内にそれを搭載すると「ボケ質」が極めて良くなる。
これの光学原理は非常に難解であり、例えばFUJIFILM社の
WEBにAPD(アポダイゼーション)の原理と効能が書かれて
いるので、それを参照してもらえれば良いとは思うが、ただし
多分に宣伝的内容であり、技術理解の視点では無いとも思う。
また、他の資料は、専門書等の範囲を含めても、ほとんど
見当たらず、仮にあったとしても、専門的ジャンルであるので、
その解説は難解であろう。
(注:レンズや光学に限らず、どの技術分野においても
専門家の解説ほどわかりにくいものは無い(汗) これは
何故なのだろうか? 自身の研究だけに夢中になって他者に
説明する経験や技能が少ないのか? あるいは教えたく無い
のであろうか? はたまた自身の持つ知識を自慢したいのか?
たいていの場合「本来は簡単な事を、わざと、わかりにくく
書いているのか?!」と、極めて不快になる事が殆どだ。
真の「専門家」であるならば、難しい事を、誰にでも理解
できるように上手に説明するスキルを持つ事が必須だと思う)
・・まあ、という状況なので、誰も上手く説明できないから、
消費者層は理解しずらいし、値段も高いし、スペックも凡庸
なので誰も買わないから、世の中おいてはアポダイゼーション
のレンズは評価や情報も多く無く、殆ど知られていない。

このあたりの概念は、初級中級層では「ボケ味」といった、
極めて意味が曖昧な用語としてイメージが広まっている為、
いったい具体的に何が良くなるのか?が理解できない。
ちなみに、本ブログでは、そのあたりはちゃんと定義している。
(匠の写真用語辞典第13回記事参照)
簡単に言えば、ボケの度合いを表すのが「ボケ量」であり、
それは被写界深度と等価だ。「ボケ質」は、そのボケ部分の
品質的な良否であり、まあ「綺麗にボケる」という意味だ。
さらに言えば、「ボケ形状」という、あまり使わない用語も
一応定義していて、木漏れ日ボケとか、夜景ボケ、あるいは
逆光のゴースト等で、絞り部品(羽根)の形状が写真に写って
しまう事。それから「口径食」の発生により。夜景点光源等の
ボケがレモン形状等に変形してしまう事も指す。
なお「円形絞り機構」により、木漏れ日やゴーストにおける
「ボケ形状」は改善できるが、ここで定義する「ボケ質」の
向上へは、「円形絞り機構」は寄与しない。
メーカー側では「円形絞り」の効能として、わざわざ曖昧な
用語を使って「ボケ味が良くなる」と謳っているケースも
あるので要注意だ。すなわち「効能をはっきりと書きたく無い」
とも推察できるからだ。
(ここらへんの定義が曖昧だからか? 近年のビギナー層では
夜景点光源等で円形形状のボケが出ると、「玉ボケ」と言って
それを有りがたがり、あたかも偶然それが出る、または専門的
機材が無いと出せないものだ、と誤解してしまっている。
勿論、その状態は、どのレンズでも絞り開放で容易に発生する
ので、プログラムAEで撮らず、絞り優先AEを主に用いるべきだ。
ただし、中上級マニア層の一部では「円形ボケ」の中で、
特に輪郭線が残る状態を指してのみ「シャボン玉ボケ」又は
「バブルボケ」と呼ぶ。こちらの状態であれば、その特殊性は
あると思う→一部のオールドレンズ等でのみ発生する)
なお、本STF135/2.8ではSTFと書かれたT4.5-T6.7の範囲
においては、一応絞り羽根10枚の円形絞りを採用していて、
「ボケ形状」の改善についての配慮も見られる。
ただし、絞り環をA位置として自動絞りで使う場合には、
9枚羽根となる模様だ。(しかしながら、本レンズにおいて
自動絞りで、絞り込んで使う用途は、まず考えられない。
そういう撮り方をするならば、より新しい高解像力仕様の
中望遠レンズを使った方が有利であろう。レンズおよび
カメラも含めたシステムでは、その特徴を最大限に発揮した
使い方をしないと意味が無い訳だ)
それから、本STFはF2.8(T4.5)と小さい口径比ながら、
フィルター径φ72mmという、開放F2級に相当する大きな
(135mm÷φ72mm≒(F)1.87 この口径比はF2級だ)
前玉により瞳径(有効径)を十分に確保していて、いわゆる
「口径食」(注:多数の意味がある。ここでは、ボケ形状に
影響する要素を示す)は、発生しない模様だ。すなわち
「ボケ質やボケ形状」に係わる一般レンズの弱点を全て解消
しようとした、稀有な設計コンセプトである事が見て取れる。

レンズ全般を通じてもさほど多くは無く、かつ、一般的には
様々な撮影条件において、常にボケ質に優れる訳でも無い。
(例:「ボケ質破綻」 匠の写真用語辞典第13回記事)
それに、ボケ質に優れたレンズは、比較的高価なものが多いし
初級中級者が欲しがるような人気のスペックのレンズでも無い。
よって、まず誰も買わないような特殊な仕様のレンズだけが、
ボケ質に優れるケースが多く、結果的に初級中級層においては
「ボケ質」が良好なレンズを所有したり、その描写を目にする
機会も殆ど無い。だから、いつまでたっても「ボケ質」への
概念理解は、残念ながら進まない。
また、一眼レフの場合は、多くのケースで開放測光であり、
撮影時に絞り込まれる状態でのボケ量やボケ質はファインダー
では確認が困難だ。かつ、ファインダー/スクリーンの仕様・
性能上、ボケ質については、殆どわからない。
よって、銀塩時代であれば現像後、デジタル時代でもPCに
取り込んで写真を見る段階となって、中上級マニア等では
「このレンズはボケ質が良い(悪い)」と語っていたのだが、
撮影状況の再現性が厳しい(絞り値のみならず、被写体距離、
背景(前景)距離、その絵柄等によってもボケ質は変化する)
ので、単に撮った写真を数枚だけ見ても、レンズのボケ質の
評価は困難または不可能であった訳だ。
ミラーレス機または高精細EVF搭載型一眼レフ(例えば、今回
使用のSONY α77Ⅱ等)であれば、僅かではあるが、撮影前に
ボケ量、ボケ質の事前確認が可能だ。よってボケ質が悪くなる
撮影状況を避ける「ボケ質破綻回避」の技法は、そうした現代
機材を使わない限りまず不可能であるし、機材があったとしても
高難易度の撮影技法となる為、初級中級層ではまず対処困難だ。
そんな状況なので「ボケ質」への理解や、それを意識する撮影
技法は、現代でもまったく普及していない。
・・で、そうだとしても、現代で4本(機種)だけ存在する、
アポダイゼーションレンズは、いずれもボケ質に優れたレンズ
であるし、様々な撮影シーンにおいて、ボケ質破綻が起こる
リスクも少なく、たいていの場合で、良好なボケ質が得られる
という、非常に貴重な特徴を持ったレンズ群である。
(追記:2019年発売のCANON RF85mm/F1.2 L USM DS
は、新規の「DSコーティング」を採用しているが、
どうやらこれはアポダイゼーション光学エレメントと
同等な効能を発揮する模様だ。
つまり史上5本目のアポダイゼーションレンズとなる。
これまでのSTF/APDを全部所有している私としては、
このレンズへの興味は強いが、しかし、発売時価格が
40万円程度の超高額レンズとなってしまった為、
まず絶対と言っていいほど買う事は無いであろう。
その金額を出すならば、残りの4本のAPD/STFレンズ
を(中古で)全て購入できる!)
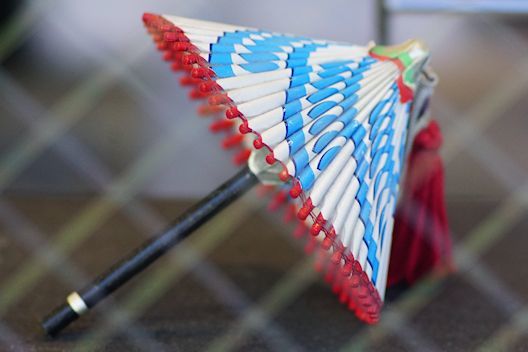
発売後20年以上を過ぎた状態においても、本レンズを
超える描写表現力を持つレンズは殆ど存在しない。
まあ、近年の新鋭レンズで、本レンズよりも解像力性能を
高めたものもあるのだが・・(例:SIGMA Art 135/1.8)
ボケ質も含めた(描写)表現力は、本レンズには敵わないで
あろうし、そもそも、使うカメラ機材側の仕様であるとか、
どんな被写体を、どのように撮りたいのか?で、解像力性能
を常に要求される訳でも無いであろう。
例えば、遠距離のビル等を撮影して、窓が写っているかどうか?
等の評価をしても意味が無いのだ。本STF135/2.8では、そもそも
そんな被写体を撮りたい等とは、絶対に思わないだろうからだ。
(=実際の使用条件を考慮しない評価手法は適切では無い)
逆光耐性、口径食、ボケ質破綻、コントラスト特性等における
弱点も全く無い。本レンズではたいていフードを装着しないで
使っているが、衝撃保護以外の観点では、逆光対応等でフード
を必要とする事は無い、それを使わないと写りがヘロヘロに
なってしまうような軟弱なレンズでは無いのだ。

まず、大きく重く高価な三重苦レンズであるが故に、常に
これを持ち出したいとも思いにくい。
(価格的には、例えば近年の新鋭の高額レンズと比べると
安価に思うかも知れないが、新鋭レンズが高額すぎる事を
決して忘れてはならない。本レンズが発売されてから
20年ちょっとで、物価が3倍や4倍にもなっている訳では
無いのに、レンズの値上がり度合いは、まさしくそういう
比率だ、消費者側で、絶対的な価値感覚を再度認識する
必要があるだろう。まあ、近年のカメラ・レンズ市場が
大きく縮退している状況は良くわかってはいるが・・
だといって、メーカー側の対策として、単純に「値上げを
すれば良い」という話ではあるまい)
MF操作は、AFに慣れた現代のユーザー層には「かったるく」
思える事であろう、だだまあ、MFに慣れているマニア層の
御用達のようなレンズであるから、それはあまり欠点には
ならないだろう。
後、「描写力が高すぎる」という問題点も、本レンズの紹介
記事では毎回のように述べている。
勿論これは別に欠点では無いが、あまりテクニカルな要素を
用いなくても、普通に撮れば、誰でもが高描写力を得られる
という点だ、すなわち、これでは「差別化」も出来ないし、
(=初級者が撮っても良く写るので、スキルを活かせない)
「使いこなし」の楽しみが少なく、これが「エンジョイ度」
の評価で僅かな減点となる。

光量がかなり減り、実効F値(すなわち「T値」)が暗い。
現代のカメラであれば、T4.5ごときは、超高感度とか、
内蔵手ブレ補正機能でなんとでもなるが、銀塩時代の低ISOの
フィルムかつ手ブレ補正無しでは、本レンズを室内中距離撮影、
(例えば結婚式の撮影等)で使うのは、少々厳しかった。
(注:各アポダイゼーションレンズは、その効能を最大限に
発揮する為には、「絞りを開放で使う」事が大原則である。
よって本STFのT4.5は、例えば、他の一般レンズをF5.6
程度まで絞って使う(=諸収差低減の目的)場合よりも、
むしろ実用的には明るいかも知れない。ただまあ、銀塩
時代ではあるまいし、現代レンズを常に絞って使うという
用法は、それが必ずしも適正な撮影技法だとは言い難い)
中距離人物撮影、という点においては、本STF135/2.8を、
APS-C機はもとより、フルサイズ機で使っても人物撮影用途
にはやや長目の画角となる。一般ポートレート撮影よりも
屋外遠距離ポートレートとか、室内イベント(結婚式や
ステージ(舞台)系等)に向く画角である。
だが、ステージ等の暗所では、デジタル時代においてもやや
厳しい。その目的には、大口径135mm/F1.8級レンズの方が、
AFである事も含めて、遥かに使い易いケースも多い。
だから人物撮影用途よりも、他の「用途開発」を模索する
事になるだろう。まあ、私の場合には、本レンズの高い近接
撮影能力と、完璧とも言えるボケ質を活用する意味でも、
自然観察用途が最適だと思ってはいるが、このあたりはユーザー
毎の被写体ジャンルそれぞれで用途開発を考えるべきであり、
ノラ猫とか、動物園、鉄道写真等にも画角的には向いている
と思われる。ただしMF操作が必須なので被写体が動体の場合は
それに対応できるMF撮影スキルが要求される事であろう。
まあ、描写力は完璧だが、用途や使いこなしが、やや難しい
レンズであるという事だ。・・とは言え、レンズ・マニアックス
第11回、第12回記事で特集した「使いこなしが難しいレンズ
のワースト・ランキング」に入るまでのレベルでは無く、
多少難しい、という感じであるから、中級層、中級マニア層
以上のスキルを持つならば何も問題は無い事であろう。

でも良く見かけ、レア物とはなっていない。
MINOLTA時代・SONY時代も含め、7万円台の中古相場になって
来ていて、性能(描写表現力)からすれば割安感はある。
「トップクラスの描写表現力、最良のボケ質」というものが
どういうものであるかを理解したい、という中級者クラスで
あれば、購入の選択も悪くは無い。
----
そして、2本目のSTFレンズ。こちらは2017年発売だ。

(SEL100F28GM)(中古購入価格 129,000円)
(以下、FE100/2.8STF)
カメラは、SONY α7(フルサイズ機)
19年の時が過ぎ、その間、MINOLTA→KONICA MINOLTA→
SONYとメーカーは変わり、カメラも銀塩一眼レフから、
デジタル一眼レフへ、ミラーレス/フルサイズ・ミラーレス機
へと変遷を遂げたが、幸いな事に旧型STF135/2.8[T4.5]は、
ずっと継続販売され続けていた。
本FE100/2.8STFは、19年ぶりに新発売された、2本目の
STFレンズである。
旧型では、一般ユーザーではMFで使い難いと思われたので、
本レンズには、AFが搭載されている。
焦点距離もやや短くなって、フルサイズ機であれば人物撮影
にも適する等、汎用性の高い画角となるであろう。

(注:暗いその値を書いてしまうと”開放F値が明るいレンズ
が高性能なのだ”と信じて疑わない初級中級層へのウケが
悪くなるから、あえて書かないのであろう。この点なんだか
MINOLTA時代の方が「良心的」であったように思える)
・・その実効F値だが、T5.6と、旧型のT4.5よりも、
さらに暗くなってしまった。
ただまあ、αミラーレス機専用であり、NEX以降のαの時代
では、全てのα(Eマウント)機にISO25600以上の高感度が
搭載されていると思うので、開放F値(T値)の暗さはあまり
問題点にはならないし、一応本レンズにはOSS(手ブレ補正)
も内蔵されている(注:α7系Ⅱ型機以降/α9系においては
ボディ内手ブレ補正搭載であり、その際には、5軸中2軸の
補正をOSSが担当し、残り3軸の補正をボディ側で担当する)
それに、T値が暗いという事は効果の強いアポダイゼーション
を使っている可能性も高く、その視点では問題は無い。
なお、SSM(超音波モーター)表記は無いが、「DDSSM」
(ダイレクトドライブSSM)というモーターを内蔵している。
これはまあ、ピエゾ系の圧電素子の応用なので、例えば
TAMRON社のレンズの一部に搭載された「PZD」と類似の
構造であろう。小型化・静音化・停止精度向上等に役立つ
との効能であるが・・
まあ、技術の内容はともかく、実用上では、本レンズの
AF速度はあまり迅速とは言えず、AF精度も悪く、もう一声
という感覚もある。ただまあ大きく重いレンズであるから、
AF駆動が遅くなるのも、やむを得ないかも知れない。
ちなみに新旧STFのサイズ感だが、どちらもフィルター径は
φ72mmと同じであり、重量は旧型が730g、新型が700gと、
大差は無い。
軽量化の代償か?新型はプラスチッキーで、やや高級感に
欠ける。

87cmよりも短縮されているが、焦点距離が短くなっている
ので、最大撮影倍率は、どちらも1/4倍(0.25倍)である。
ただし、新型では、手動のマクロ切換リングを廻さないと
近接撮影が出来ず、
通常時 :0.85m~∞
マクロ時:0.57m~1m
という仕様だ。この「手動切換」は、リングも廻し難いし、
撮影距離制限が出るので、結構面倒に思える。
かつ、近接域ではAFの精度も落ちるので、MFを使いたいので
はあるが、シームレスMF時であっても、わざわざAF/MFの
スイッチを使って切り替えたとしても、「無限回転式」の
ピントリングで距離指標もない為、手指での最短撮影距離
での停止感触が無く、かなり使い難い。
近接域を含めたMFにおける操作性への配慮は、旧STFの方に
軍配が上がる。この操作性だけを見たら旧型の圧勝だが、
αミラーレス機では、優秀なピーキング機能があるし、
必要に応じて、EVF内に距離指標も表示できるので、
実用上では新型でもMFでの操作性があまり問題になる事は
無い。(まあ、しかしながら、一眼レフのαフタケタ機も
EVF仕様で、かつピーキング機能も効くので、どちらか?と
比較するならば、やはり旧型の方がMFが遥かに使い易い)
本ブログ、というか、私の評価データベースにおいては、
レンズの評価に「操作性・操作系」の項目は特に設けては
いないのだが、もし、それがあるならば、MFのみという
弱点があったとしても、やはり旧型の方が点数は上であろう。

現代レンズらしく、旧型よりも解像感が増しているが、
まあここは前述のように、使用するカメラの仕様とか
どんな被写体を、どのように撮りたいか?で、その効能が
有益かどうかは、変わってくるとは思われる。
それから、本レンズは解像力が優れているので、大画素
からのトリミングの余裕が大きい。
まあ、本ブログでの全てのレンズ関連記事においては、実写
紹介の際には、カメラ側の搭載機能は自由に使っているが
カメラ内部のトリミング等の編集機能は使っておらず、かつ
事後のPCによる過度なアフターレタッチは禁止するルールと
している。(大きなトリミングもしてはならないルールだ)
まあ、レタッチで色々と画像をいじくり廻してしまったら、
レンズ紹介記事の意味が殆ど無くなってしまうからだ。
だが、レンズ紹介記事以外の実用撮影や趣味撮影においては
トリミングやレタッチは常識である。・・というか、編集作業
は必須(必然)であり、特に依頼撮影等の業務用途全般に
おいては、レタッチを行わないで納品する事など有り得ない。
そこまで手抜きをする事自体、許される事では無い訳だし、
他の例では、例えば女優や俳優がメイクをせずにすっぴんで
舞台等に立つ事は、業務上では、まずあってはならない事だ。
約20年前のデジタル転換期では、デジタルカメラの画素数が
まだまだ低い時代であったので、トリミングをすると、目的
とする用途の必要解像度に満たない事もあったのだが、現代
においては画素数はもう不足しておらず、トリミングをいかに
有効活用するかが、編集技能の分かれ目となり、写真納品
品質を左右する事や、編集効率(手間)にも直結する訳だ。
なお、そのデジタル転換期では、写真編集作業が出来ない
銀塩時代からのユーザー層も非常に多く、そうしたユーザー
が「編集するのは卑怯(不公平)だ!」と文句を言っていた、
という残念な時代でもあった。
まあ、「デジタル写真編集必須論」は、もう現代では誰でも
知っている事であり常識であるから、これ以上深堀りはするまい。

レンズで撮った写真は、「大きくトリミングしても耐えうる
要素が大きい」という長所があるという事だ。
低解像力のレンズだと、ある程度、大画素から縮小して
「縮小効果」を期待する。これには色々な意味や難解な原理
があるが、つまり簡単に言えば、「2画素を1画素に縮小する
(まとめる)際に、輪郭線がはっきりする」という効果を含む
とも言える。まあつまり、ピントが甘かったり解像力が
低いレンズで撮った画像でも、大きく縮小してしまえば、
ピンボケや低解像感をごまかせる、という意味だ。
だからまあ、フルサイズの高画素機からの縮小写真を見て、
ビギナー層等は「画質が良い」と錯覚するのであるが、それは
そう単純な話では無く、被写体の状況(空間周波数分布)に
よっては、輪郭線等が強く出すぎて、表現したい用途や意図
とは逆効果になる場合もある。
どんどんと脱線しそうなので、少し元に戻す。
簡単に結論を述べよう、「解像力(感)の低い、古い時代の
レンズでは、トリミングを行うよりもデジタルズーム又は
デジタルテレコン機能で拡大した方が望ましく、
新世代の高解像力型レンズであれば、デジタル拡大機能よりも
大画素からのトリミングを使った方が実用的である」という事だ。
ただここもまあ、デジタル拡大の方式(アルゴリズムや
技術仕様)に多分に影響してくる話であり、そう簡単では無い。
この辺は、初級中級層はおろか上級層に至るまで、そう誰でも
画層処理の原理や詳細技術に精通してる訳では無いだろうから
このあたりをいくら詳しく述べても冗長だし、難解でもあろう。
ばっさり理由は割愛する、何か疑問点があれば、自分自身で
実験・研究して確かめてみれば良いと思う。
趣味にしても業務にしても、そういう事は自分で行うのが
基本中の基本だ。何も試しもせずに、頭で考えているだけとか、
単なる思い込みだけとか、誰かがそう言ったからとか、書籍等で
調べただけとか、そういうスタンスは全てNGである。どんな些細
な事でも必ず自分自身で実際に試行して確かめなければならない。

いる訳では無い。それらの評価の点数よりも、どういう視点
で、そうした機材を見る(検証する)のか?、という部分や
その為のノウハウを開示する事がより重要だと思っているのだ。
だから、機器の通信販売サイト等で、ビギナーユーザー層が
自身の思い込みで、このレンズは良いとか悪いとか、好き勝手
に評価を書いている事にも全く賛同できないし、それを見て
機材を買うかどうかを決めるスタンスというのも不条理だ。
最終的に信じるべきは、他人の評価ではなく、自分自身の価値
感覚ではなかろうか? ビギナー層では、それを全く持って
いないから「高価なレンズは必ず高い描写力を持つのだ」等と、
ごく単純な思い込みによる大誤解をしてしまう訳だ。
さて、本当に余談が長くなった(汗)
本FE100/2.8STFであるが、操作性等に細かい弱点はあるが
描写表現力における不満点は全く無い。これは誰しもが
そう感じるだるう事であり、現代でトップクラスの高性能
(高描写力、高表現力)のレンズであると思う。
他の問題は価格が高い事だ、定価18万8000円+税は
かなりの高額であり、新品で買うのはよほどの覚悟が必要だ。
中古は稀に出ているが、相場の下落傾向はゆっくりであり、
現代で11万円台くらいか・・ まあ新品よりだいぶマシでは
あるが、依然高価である事は間違いは無い。
パフォーマンスが高いレンズではあるが、あくまで描写力に
係わる部分だけであり、あまり高価に買ってしまうと総合的
なコスパ点は低く評価せざるを得ない。
それと、「絞るとSTFの効果が減る」と書かれたレビューを
見た事があったが、アポダイゼーションの原理からは当然の
事であり、絞って使う用法は、レンズの特徴を消してしまう
為に、あり得ない。各STF/APDレンズは絞り値を「開放から
微動だに動かさない」位の覚悟(?)が必要なレンズである。

殆ど使用する事ができない。(注:NIKON Zへは変換可能な
模様だ) まあ、近年の新型α機(フルサイズ)は、どれも
「高付加価値型商品」となって、高価になりすぎている課題も
あって、システムを成り立たせる為の出費も、非常に大きく
なってしまう事も弱点として上げておこう。
初級中級層では、機材へ投資する際に、カメラ本体の事しか
考えていないと思うが、実際には、全く逆に考えるのが良く、
「必要なレンズがあるから、カメラボディを買う」のである。
その際の金額配分比率は、レンズ4対カメラ1にするのが
理想であり(匠の写真用語辞典第16回記事)、旧来は
それを守る事も比較的容易であったのだが(=カメラが安価
であったから)近年においては、まともなカメラを買おうと
すると、下手をすれば本レンズよりも高価な相場だ(汗)
レンズとカメラを1対1の価格比とするのは好ましくなく、
ましてや本レンズのような高額レンズで、そうした
「オフサイド」(カメラ価格の方が突出する)になるのは、
さらに好ましく無い。本レンズは、できれば3万円程度の
ボデイに装着したいのだ。例えば、α6000あたりの
相場感が適正であろう、私は普段は結構そのシステムで使う
ケースも多いのだが、初級中級層だと「フルサイズ機で
なくちゃイヤだ!」と、ダダを捏ねるであろう・・汗

「レンズの描写力が高すぎて、レンズに撮らされている
気分になってしまう」(=撮影者の主体性が保てない)
という微妙な弱点を持つ事は、念の為述べて置く。
----
では、最後に新旧STFの両レンズの点数評価をしてみよう。
これは、私が全所有レンズにつけている評価データベース
からの抜粋であるが、あまりレンズ関係の記事でこれを
公開する事は無い。
基本的に、こういう評価点はユーザーの個々の被写体選択、
機材の使用法、何を表現したいか?、何を求めているのか?
そして、利用者毎のスキル(技能)によっても評価は簡単に
変わってしまう。なので、書いてある点数だけが一人歩きを
するのは良く無い、と思っている訳である。
「レーダーチャート」とかで、こうした評価点数をまとめて
いる記事等もカメラ機材に限らず、良く見かけるが、一見
ちゃんと評価している様子であっても、良く良く見ると
そうでもなさそうだ(例:評価軸の項目がまちまちである等)
あくまで評価者個々の独断であろう。
まあ、例えば、ここに5点満点とあって、それをもし疑問に
思うならば、では実際に満点となるには、いったいどう機材を
使ったら良いのか? そもそもそれは信用するべき評価なのか?
・・そういう事を考えて練習や研究をすれば良い、という事だ。
結局、機材を評価するのは、あくまで自分自身なのだから・・
【描写表現力】両者5点満点(★★★★★)
【マニアック】両者5点満点(★★★★★)
【コスパ 】旧2.0点、新1.5点
【エンジョイ】旧4.5点、新4.0点
【必要度 】両者5点満点(★★★★★)
・評価平均値:旧型STF=4.3点、新型STF=4.1点
殆どの評価項目で両者5点満点であるが・・
やはりコスパが減点対象として大きい。約20年の時を経て
新型は旧型よりも勿論高価であり、定価20万円超えは、
そう簡単に誰もが買える金額では無くなっている。
まあでも、旧型の低得点は発売直後の新品購入であったから
であり、現代において旧型を中古で買えば、コスパ点はかなり
良くなり、3.5点程度にはなるだろう。依然高価ではあろうが
なにせパフォーマンスが物凄く高い。
新型のエンジョイ度が旧型よりも、やや低いのは、AF化された
事で、なんだか安直となった印象がある事。それからMFおよび
マクロの操作性が新型はあまり良く無い事が理由としてある。
まあでも、本ブログではレンズの評価点で平均4点を超えれば、
「名玉」としてノミネートされる状態であるので、両者いずれも
その条件には該当する。
どちらかを現代で購入するならば、人物撮影等で実用的に使いたい
のであれば新型のFEマウント版であろうが、より安価な中古相場
で、じっくりと自然観察等の用途で使いたいのであれば、旧型の
α(A)マウント版の選択が良いであろう。旧型の方がシステムを
成立させる為のトータルコストが、だいぶ安価になる利点もある。
----
さて、今回の記事は、このあたり迄とする。次回記事も、
また補足編として高性能レンズの対決記事とする予定だ。