本シリーズは、各カメラメーカーが発売した銀塩・デジタル
のカメラを、およそ1970年代から現代2020年代に至る迄の
約50年間の変遷の歴史を世情等と絡めて辿る記事である。
![_c0032138_16554842.jpg]()
機を中心に紹介するが、ご存知の通り、MINOLTAは銀塩時代
終焉頃にKONICAと合併して「KONICA MINOLTA」となって
いて、その後2006年には、カメラ事業から撤退している。
---
そして現在、私が保有しているMINOLTA機は1970年代以降の
物に限られる。それ以前の時代のMINOLTA機はデジタル時代に
入った頃に「実用価値なし」という判断で処分してしまった。
勿論それ以前から、MINOLTAはカメラを製造・販売している
老舗メーカーだ。まず、そのあたりを簡単に説明してから、
順次、各時代のMINOLTA機の変遷について紹介する。
なお、挿入している写真は、紹介機体の頃の時代のMINOLTA
製レンズで撮ったもので、本文内容とはあまり関係が無い。
![_c0032138_16554811.jpg]()
1930年代は日本やドイツで、いくつかの機械式カメラメーカー
による事業が立ち上がった時代である。日本ではそれ以前の
1900年代初頭(ライト兄弟の初飛行の頃)からコニカが
カメラを発売していたが、それは例外的だ。
(注:1930年代は第二次世界大戦前の世情であり、軍事
用途での光学機器の開発が要望されていたと思われる)
ミノルタは1928年頃~1933年頃には、まだ会社としての
組織形態も不定ではあったが、1933年の「セミミノルタ」
でブランド名としての「ミノルタ」が初めて登場した。
1937年頃にMINOLTAの母体となった「千代田光学精工」が
設立された。
また、写真用品を扱う「浅沼紹介」(KINGブランド)と提携
して、その流通経路で、様々なカメラ製品を販売している。
同時期には、国産初(?)の二眼レフカメラも発売、しかし
この頃に軍需工場に指定された為、その後の大戦の時期には
(民生用)カメラ製品の製造は少ない。
----
1940年代後半~1960年代 二眼レフ、各種フィルムカメラ
戦後は中判の二眼レフやスプリング式カメラ等を多数展開。
これらの型式のカメラは1960年代まで新規発売が継続される。
また、1950年代頃~1970年代頃には、16mm判フィルム。
1960年代頃には126判フィルム、そして1970年代頃には
110判フィルム等と、多様なフィルムフォーマット対応の
カメラを発売していた事もミノルタ(や、この時代の他社)
の特徴だ。
この時代1940年代後半より1950年代を通じて、ライカL39
マウント互換機がミノルタより発売されているが、多くの
製品はフィルムフォーマットが32mmx24mm判であった。
35mm判(ライカ判36mmx24mm)フィルム使用カメラは、
1950年代~1970年代にかけて、レンズ固定式、レンズ
交換式等、非常に多数のカメラを発売しているが、機種が
極めて多いので詳細の説明は省略する。
代表的な機種としては、ハイマチックシリーズ(1961年~
1982年、未所有)をあげておく。
なお、このシリーズはハイマチックAF(1979年)より、AF化
されている(注:AF一眼レフの「α-7000」より6年早い
が、「ジャスピンコニカ C35AF」1977年、よりは遅い)
----
1960年代~1970年代前半 一眼レフ SRシリーズ
1958年のSR-2から35mm判一眼レフの発売を開始。
以降、SR-1シリーズ、SR-3シリーズ、SR-7シリーズ等、
多数の一眼レフを1960年代前半にかけて展開している。
SR-7(1962年)は、世界初のCdS型露出計内蔵機であり、
加えて、この時期、コンパクト機「ハイマチック」が
米国宇宙船の「フレンドシップ7号」で使用された事にちなみ、
その後継機を「ハイマチック7」と呼んだ事で、以降ミノルタは
革新的で記念碑的な機種名を「7番機」とする慣習となった。
これは以降の時代を通じて続き、さらに2006年にカメラ事業が
SONYに引き継がれた後でも、同様に革新的な機種名を7番機
とする伝統が受け継がれている(例:SONY α7、2013年)
![_c0032138_16554846.jpg]()
商号変更している。
で、あいかわらずミノルタのカメラは数が多く、SRシリーズ
も同様だ、以降の時代は代表的な機種のみの説明にしよう。
1966年 SR-T101
初のTTL測光機、加えて、初の2分割測光(CLC)機能を搭載
している。
CLCは画面の上下半分づつを異なるCds素子で測光する方式、
空の明るさに露出が引っ張られてアンダー露出になるのを
補正するアイデアだ。(ただし縦位置撮影では効果は無い)
1973年 SR-T Super
ファインダー廻りを改良し、実用性を高めた人気機種。
この機体は銀塩時代に所有していて、2分割測光のCLCが
意外に露出精度が高かった印象がある。(現在未所有)
----
さて、ここからは現在も所有している一眼レフの時代に
到達した、実機を紹介していこう。
1970年代 一眼レフ Xシリーズ
![_c0032138_16554878.jpg]()
(銀塩一眼レフ・クラッシックス第4回記事参照)
化物のような異色のカメラ、ミノルタ初の旗艦機である。
「重厚長大」な事で、本ブログでは昔から「超弩級戦艦」と
呼んでいる。(注:この機体は小型ファインダー仕様だ)
レンズ付きでの定価は13万円台であり、現代の貨幣価値で
およそ50万円~60万円にもなる。(詳細後述)
なお、後年のX-1 Mortor(1976)は、「船底ファインダー」
仕様では、とんでも無い存在感を持つ異形のカメラであった
が、さらに高価で、X-1の2倍以上の価格であった。
(よって、ほとんど流通していない)
さて、値段は高いのだが・・ 必ずしも性能が高いとか
使い易いカメラでは無い。本機の入手は銀塩末期であったが
その操作性が独特すぎて、また重量も約1kgと重く、ほとんど
実用価値は無かった。ただ、歴史的に貴重な機種であるので
デジタル時代に入っても、処分せずに残した次第である。
![_c0032138_16555584.jpg]()
世情あるいは物価は、どんな感じだったのであろうか?
実は、1970年代は物価が大きく上昇した時代でもある。
わかり易いように、喫茶店のコーヒー代をあげてみよう。
1970年では120円、1971年130円、以下100円台後半から
1974年では200円を超え、1979年には300円となっていた。
初任給も同様だ、公務員では1970年頃の3万円台から
1979年には10万円近くまで跳ね上がる。
この他にも色々と商品の物価のデータは存在するが、
いずれも1970年代の10年間にかけて、およそ3倍程度の
値上がり率だ。
ちなみに、1971年に日本初上陸したマクドナルドの
ハンバーガーは80円で、新発売のカップヌードルは100円
であった、いずれも現代の価値では500円前後と、高価
ではあるが、東京の街でこれらを食べながら歩く若者が
急増し、新しい「文化」を築くきっかけになった模様だ。
で、現代の喫茶店のコーヒー代が平均600円位、そして
現代の大卒公務員初任給が約21万円位と考えると、
だいたい以下のような倍率を当時の価格に乗ずると、
現代の貨幣価値に換算できるのではなかろうか?
1970年代前期 6倍~4倍
1970年代中頃 4倍~3倍
1970年代後期 3倍~2倍
なお、一般的に言う「高度成長期」(好景気の時代)とは、
概ね、1954年末頃から1973年にかけてを言う。
その「高度成長期」の終焉の理由の1つが、原油(石油)
価格の高騰(オイルショック)である、
1973年には第一次オイルショックが起こり。日本も
これの影響で酷いインフレとなり、1年間で物価が23%も
上昇、1974年では、戦後初のマイナス成長となった。
この頃、生活必需品である「トイレットペーパーや洗剤が
無くなる」という噂(デマ)が流れ、日本全国でとんでも無い
パニックとなり、各商店には、それらを買い求める主婦達の
長蛇の行列が出来た。(近年のコロナ騒ぎの際と同様だ)
1979年には、世界情勢の変化から、第二次オイルショック
が起こったが、「トイレットペーパー騒動」の経験からか、
消費者やメディアは大騒ぎをせず、日曜日にガソリンスダンド
が休業する程度で済んだ模様だ。
この頃から「省エネ」(現代の「エコ」)の概念が消費者層
にも普及し、新内閣では「省エネルック」と呼ばれた半袖の
軽装を政治家達が着てアピールした(現代の「クールビス」)
ただ、消費者の混乱は少なかったのかもしれないが、この後の
時代は、しばらく不況が続く。
![_c0032138_16555554.jpg]()
Xシリーズは展開された訳だが、世情を考えると、この時代の
カメラの価格の上昇は、やむを得ない節もあり、加えて、
諸費者物価指数の上昇程の高騰も無いようにも思えてくる。
以下、続くミノルタXシリーズの一眼レフを紹介していこう。
![_c0032138_16555633.jpg]()
銀塩一眼レフ・クラッシックス第6回記事で紹介。
世界初の「両優先AE」機である。
これは、これまでの時代、各社は「シャッター優先」と
「絞り優先」の、いずれかのAE(自動露出)機能を備え、
「そのどちらが優れているか?」といった論争が真剣に
行われていた状況であったが、この機体、および翌年の
CANON A-1(1978)の登場で、そのいずれもが搭載された為、
ほど無く「絞り優先、シャッター優先論争」も終結した。
現代でも良く起こる「スペック競争、スペック論争」の
走りとも言える世情であるが、個人的な見解としては、
カメラの性能や機能がどうであったとしても
1)その機能の長所、短所をちゃんと見分けられるか?
2)機材に短所がある場合、それを回避する為の技法や
技能を使いこなせるか否か?
が、重要だと思っている。
だがまあ、これらの「両優先」カメラ以前では、ある意味
「様々な撮影状況に必要な最低限の機能」を搭載していない
場合も多々あった訳であり、まだ、この時代であれば、
スペックやらを強く気にしても、やむを得ない節はある。
しかし、この時代から既に40年以上が経過しているし、
現代の(デジタル)カメラにおいては、撮影の為に不足して
いる機能は、基本的な撮影技法の範囲内では一切無い。
当然、性能も十分であり、スペック競争も殆ど無意味だ。
だから、現代においては、カメラやレンズの基本性能だけに
頼って撮っている状態はNGであり、今時でも初級者が良く
言う「このカメラは色が悪い」とか「このレンズのAFは遅い」
とかの、機材側の基本性能に文句をつけるだけで、何の工夫も
しないスタンスは、褒められた話では無い、という事だ。
さて、このMINOLTA XDの発売時定価は78,000円だった。
現代の貨幣価値では20万円程になり、少々高価であったと
思うが、前述の「インフレ」の市場状況があったので、
ある程度は、やむを得ない。
また、XD系は後年の中古市場にあまり出て来なかったの
だが、それもまた「割高感」から、ユーザーが少なかった
からなのかも知れない。
![_c0032138_16555624.jpg]()
当時まだ21歳の宮崎美子さん(現:女優/クイズの女王)が
「木陰でGパン(ジーンズ)を脱いでビキニ姿になる」
というTV CMが社会現象的な話題となり、そのCM効果で
X-7は大ヒットカメラとなった。
このCM、およびCMソング(斉藤哲夫氏)は伝説的であり、
後年には、このシーンのフィギュアまで発売された程だ。
この機種の性能はXD等に比べて低い、「絞り優先専用機」
ではあるが、そういう事は多くの消費者層には無関係だ。
1970年代オイルショックの影響で割高になったカメラ価格
を1度下げる目的もあったと思われ、XDの価格の約半額の
本体39,500円(?推定。レンズ付きは59,500円)と
安価に販売された事も大ヒットの要因だ。
これも革新的な「7番機」ではあったが、他の7番機とは
ちょっとイメージが違う、あまりに「大衆的」な機種だ。
非常に著名なカメラではあるが、TV CM自体が度を越して
有名であるが故にか、その割りに、この機体の型番(X-7)
や、CMソングのアーティスト(斉藤哲夫氏)の名前を
覚えていて言える人は、後年には殆ど居なかった。
恐らく、ビギナー層は店頭で「宮崎美子のカメラを下さい」
と言って購入していた事であろう。
私は、この「歴史的価値」から、所有した事はあるが、
性能面やマニアック度が低い為、短期間で譲渡してしまった。
![_c0032138_16560283.jpg]()
銀塩一眼レフ・クラッシックス第10回記事で紹介。
ミノルタ初にして、ミノルタMF機唯一の「プログラムAE」
(MPS機能)を搭載した「7番機」である。
それまでの、XD,XD-S(1979)でも、「GGGシステム」や
「サイバネーションシステム」といった「擬似プログラムAE」
が搭載されてはいたが、X-700の「MPS」は、正規の
プログラムAEである。
1970年代インフレで高価になりすぎたカメラ(だからこの
時代ではX-1以降の旗艦機はミノルタには存在しないのか?)
そして一眼レフのAF化が目前に迫っている事(コンパクト機では
すでにAFは常識)、さらには前年の「X-7」の大ヒットなどの
要因を受け、あまり開発に手をかけていないカメラには見えるが
完成度はかなり高く、1999年頃まで18年間もの、異例の
ロングセラー機種となった。(注:既存MC/MDマウントと
互換性の無いα(AF)マウント機が主力となった為、「既存
MC/MDレンズユーザーの救済策として、X-700のみ販売が
継続された」という解釈も可能である→後述)
個人的には、後年に初めて入手した一眼レフがX-700であり、
銀塩時代を通じて、かなり愛用した機体である。
特にファンダー性能(倍率の高さ、スクリーンの見えの良さ)
は特筆すべきであり、初級者でもMF操作を難なく行える。
1/1000秒シャッター等、低スペックではあるが、不要な迄の
機能や性能を搭載しない事から、発売時定価も63,000円と、
XD系よりもだいぶ安価だ。
なお、この頃の他のミノルタXシリーズの詳細については、
銀塩一眼レフ・クラッシックス第4回(X-1)、第6回(XD)
第10回(X-700)に詳しいので、重複する為、割愛する。
![_c0032138_16560243.jpg]()
ミノルタが他社に先駆けて初めて実用的なAF一眼レフを
完成させた、いわゆる「αショック」は社会現象ともなった。
本ブログでは何十回も説明した事であり、詳細は割愛する。
また、この機体は歴史的価値が極めて高いが、個人的には
好みではなく、所有の機会に恵まれていない。
私は、もっぱら同年発売の上級機「α-9000」を銀塩時代を
通じて愛用したが、デジタル時代に入って故障(液晶の劣化)
の為、廃棄してしまった。(発売時定価12万円弱)
なお、αマウントは旧来のSR/MC/MD系マウントとは互換性
が無い為、前述の「X-700」は継続販売される事となった。
(この点については、αの性能が圧倒的であった為、
マウント変更の不満はユーザー層からは出て来なかった)
この後、数年間はこのα-7000(シリーズ)だけで
ミノルタのラインナップを支える事になる。
さらにその後、1990年頃~1997年頃には、バブル期の
世情の激変、特許訴訟等、ミノルタには色々とタイミング
の悪い不運な出来事が降りかかる。このあたりの歴史は
暗いので、マニア的な観点からは、あまり書きたく無い。
(興味があれば、銀塩一眼第23回α-9の記事に詳しい)
----
ミノルタの一眼レフ用交換レンズ群
ここの詳細を書き出すと、際限なく記事文字数が増えて
しまう、過去記事でも多数紹介しているし、またいずれ
機会があれば別記事で纏めて紹介しよう。
市場ではあまり好評価は無いが、レンズによっては
描写力が極めて優秀なものもあり、コスパが良いと思う。
![_c0032138_16560398.jpg]()
1970年代の「ハイマチック」シリーズは、後年1979年頃
からAF化している(ハイマチックAFシリーズ)、ただし
まだ初期の時代のAFであるから、精度はあまり高くなかった。
他社においても、この1970年代末のAFコンパクト機は、
AF試作機的な様相が強かった時代である。
後年1980年代においては、MINOLTA AFシリーズ(初号機は
AF-C:1983)を展開、AF-Sシリーズでは音声操作ガイド機能
を入れるなど、先進的ではあるが・・
これは後年の「過剰な多機能化」の前触れと言えるかも知れない。
1980年代後半では「MAC(マック)」シリーズを展開、
AF/AE搭載の単焦点又は二焦点機で、完全自動化されている。
また、この時代は「日付写しこみ機能」が普及し、ミノルタ
でも「クオーツデート」という名称を機種名につけている。
他は、あいかわらず機種数が多いので詳細は割愛する。
1990年代となると、バブル経済もピークとなったからか、
色々と「バブリーなカメラ」が出てくる。
MINOLTA PROD 20's(1990年)は、1920年代を思わせる
美しいクラッシックなデザインを施した全自動カメラ。
この機体は所有していたが、全自動でテクニカルな要素が
何も無かった事と、意外に大柄でハンドリング性が悪く、
写りもあまり良く無い等を理由として、ファッション的な
要素(人が集まる機会に、話題性の為に持ち出す)程度で
しか用途がなかった。
限定生産品であった筈なのに、後年、いくらでも新品在庫が
中古市場に流出し、中古流通業界でも「Prodは、もういいよ」
という風潮が出てきて、中古カメラブームの時代でさえも
不人気であった。私はデジタル時代に入って処分したのだが
実用価値の低さから、周囲のマニア層への直接譲渡は避け、
タダ同然で、中古店に引き取ってもらう事にした。
「バブリーなカメラ」と言えば、MINOLTA APEX(アペックス)
シリーズも酷い。これは自動ズーム(AFで測った距離から
例えば人物では、自動的に半身像となる画角とする)機能を
備えていて、そのモードにおいては撮影者が撮りたい画角に
すらならない、という非常におせっかいな仕様だ。
私はMINOLTA APEX 90(1992)を購入していたが、あまりに
「おせっかい」であった為、短期間で処分してしまった。
市場においても、この頃の一眼レフα-xiシリーズ(これも
バブリーな不要な機能を満載)と同様に酷評をくらい、
おまけに「特許訴訟」のネガティブなイメージと、バブル経済
崩壊の余波を受け、この頃のミノルタは不運な時代であった。
その後、1990年代後半~2000年代前半には「カピオス」
シリーズを展開するが、ありきたりのAF普及コンパクトで、
マニア層では既に「中古カメラブーム」に突入していた為、
まったく話題にも上らなかった。
特にマニア層では、α-xiや、APEX、Prod20's等の悪印象も
あったからか、この時代においては「ミノルタを買うのは
やめておけ」という、まるで「呪いのカメラ」でもあった
かのような悪評判が、マニア間で、まことしやかに囁き
続けられていた。
![_c0032138_16560349.jpg]()
マニア層での「呪いのミノルタカメラ」の悪印象を払拭した
高級コンパクト機。
同時代の「RICOH GR1」(1996)や「CONTAX G2」(1996)
と共に、高級コンパクト・高級レンジファインダー機の
大ブームを巻き起こすきっかけになった立役者。
TC-1は、買って使ってみると、色々とクセのあるカメラで、
個人的には、あまり思い入れが持てず、もっぱら興味は、
銀塩GRシリーズ(前身のR1シリーズから、ほとんどの機種を
所有していた)に向いてしまい、自然に手放してしまっていた。
余談だが、この頃、奈良県では色々な遺跡の発掘調査や新発見
が相次ぎ、私も興味があった為、それらの発掘現場に入れる
「現地説明会」に良く足を運んだ。
どこかの現地説明会で、発売されたばかりのTC-1を持って
来ていたシニアが居たが、彼は、ぬかるみの発掘現場で足を
取られ、新品のTC-1がドボンと泥水の中に水没してしまった!
このTC-1は、発売時定価148,000円と非常に高価なカメラ
であった為、「あちゃ~」と、目をそむけざるを得ず、
その様子がとても印象と記憶に残った。
(当然、修理しただろうが、ご愁傷様でした・・)
そして、後年2003年頃になって、黒塗装の「TC-1 Limited」
という限定販売機を中古市場で見かけ、TC-1がミノルタ唯一の
高級コンパクトであった事の歴史的価値の高さと、Limited
仕様でのマニアック度の高さを鑑み、購入しようか迷った。
やや高価(8万円位だったか?)で、1~2日悩み、買う気に
なって再度中古店を訪れると、既に売られてしまっていた。
地方の小さい中古店だが、中古カメラのブローカー(せどり)
という職業層も良く訪れる店だったので(つまり、店舗間での
わずかな相場の差を利益とする生業だ)その手の人が買って
いったのかもしれない(であれば、目利きはさすがである。
後年には軽く10万円を超える高額相場で取引されたからだ)
私は「TC-1とは、縁に恵まれなかった」と解釈して、その後は
この機体に興味を持つ事は無かった。
(注:この概念は「マニア道」としては、結構重要である。
「フラれた相手」に、いつまでも未練を持つ事は良く無い)
----
1997年 MINOLTA Dimage V(未所有)
ミノルタ初のデジタル・コンパクトカメラ。
ここでミノルタの初期デジタル機の説明をしだすと
限りなく文字数を消費するので、やむなく割愛するが、
以下、代表的な機種だけあげておく。
(注:1990年代の製品ではDimageと小文字表記)
DiMAGE 7(2001年)高画質高倍率ズームレンズ搭載
DiMAGE X(2002年)初の屈曲光学系採用
DiMAGE A1(2003年) 初の手ブレ補正内蔵機
----
1997年 MINOLTA VECTIS GX-4 (現在所在不明)
当時流行していたAPS(IX240)フィルム使用の水中機。
私は、APSコンパクトは沢山所有していた。理由は特定の
使用目的(超小型、ファッショナブル、マクロ、防水等)に
特化した個性的な機種が多かったからだ。
本機は、海やプールでのレジャー用途に購入、まあその目的
には十分活躍したが、固定焦点で、写りはイマイチであった。
この機体以外にもVECTISシリーズはいくつか存在するが、
詳細の説明は割愛しよう。現代となっては、APS機は
フィルムの入手も現像も、ほぼ不可能であるからだ。
(本機は、所有している筈だが、どこかにしまい込んで
所在不明だ。他にもそういう未発見機材がいくつかあって、
いずれ大規模な発掘調査を行わないとならない・・汗)
![_c0032138_16560949.jpg]()
銀塩一眼レフ・クラッシックス第23回記事で紹介。
「第一次中古カメラブーム」も真っ盛りの時代であり、
マニア層を中心としたユーザー層は、新規のAF一眼レフ
には殆ど興味が持てなかった。私も同様であり、前述の
1990年代ミノルタ機の(不当な)悪評判もあって、特に
α一眼レフ機は敬遠していた。もっぱら使っていたα機は
10年以上も前のα-9000であったが、そのマニアックな仕様
(例:AF機で唯一のフィルム手動巻上げ)に満足していた。
だが、ある時、中古店で、このα-9を見せてもらい、
それまでの価値観がひっくり返る程の衝撃を受けた。
このα-9は、カタログスペックからは全く読み取る事が
出来ない長所が満載のカメラであったからだ。
その詳細は、当該紹介記事に詳しいので割愛するが、
その記事は是非、初級マニア層等には読んでいただきたい。
α-9の中央測距点のAF精度、高性能スクリーンとファインダー
でのMF性能は超絶的であり、他社機と一線を画す他、この
MF性能には、後年の一眼レフ全てが太刀打ちできない。
私も、この機体を買うまでは「カタログスペック優先」
という初級マニアに過ぎなかったのが、このα-9での、
「スペックには現れない真の性能」を見てしまってからは、
多面的にカメラの良し悪しを見る視点や、その眼力が
養われていったと思う。
![_c0032138_16560976.jpg]()
銀塩一眼レフ・クラッシックス第29回記事でLimited版
を紹介。
前述のα-9で、私は、それまでのミノルタ機を敬遠して
いた事を後悔した。マニア層での「流言」に乗せられて
実機も触らず「呪いのカメラ」でもあったかのように
思い込んでしまった事も反省材料だ。
いったいいつ、どこで、α一眼レフがどのように進化して
いたのか? もう、それらの旧機種のカタログスペック
だけでは知るよしも無いし、今から古いαのxiやsiシリーズ
を購入する事も、最高のカメラ(α-9)を使っている限り
では、実用上では無意味だ。
で、α-9の超絶性能に「びっくりしながら」機嫌よく使って
いるところに、さらに、このα-7の登場だ。
こちらは「またしてもヤラれてしまった!」というのが
第一印象だ。
このα-7は、α-9ほどのAF性能もMF性能も持たない、
だから、ランクという点ではα-9の下位機種だ。
しかし、このα-7の「操作系」が化物的に凄かったのだ。
「操作系」という概念は、この時代まで、少なくとも私は
持っていなかったし、他のマニア層でも同様であろう。
また、業界での専門家層(職業写真家、職業評論家、
店舗販売員、他メーカーでの企画・開発者層)ですらも
殆ど持っていなかったに違い無い。
(その後、現代に至るまで、この状況は殆ど変わっていない)
![_c0032138_16560975.jpg]()
なるまでは、それまでの単機能操作子での「操作性」だけを
語ったり評価すれば良く、操作系の概念自体も不要ではあった。
その「操作系」については、本ブログでは何十回も説明して
いるので、ばっさりと割愛する。それにそれを理解するには
高度な撮影知識・経験・技能などが必要とされるので、
初級中級層には文章だけで理解できるようなものでは無い。
で、このα-7は「銀塩一眼レフ最良の操作系」を持つ機体
である事は勿論、その後のデジタル一眼レフ時代を含めても
依然、この機種にしか存在しない優秀な操作系機能もいくつか
あるので、少なくとも「銀塩AF一眼レフ最強の傑作機」で
ある事は疑いの余地も無く、下手をすれば、MF一眼レフから
現代に通じるデジタル一眼レフ迄を含めて、全ての世代の
一眼レフ中でも、かなりの上位(Best3)に入る機体である。
(いずれ、その手の「全カメラ・ランキング」記事を
纏めてみたいと思っている)
ただ惜しむらくは、この直後、一眼レフはデジタル時代に
突入してしまい、この傑作機も、だんだんと主力には
なりえなくなってしまった事だろう。
まあでも私としては、2000年代後半の銀塩完全終焉期の
ギリギリまで本機は活用していた。
![_c0032138_16560917.jpg]()
銀塩一眼レフ・クラッシックス第27回記事で紹介。
この時代のミノルタα機の完成度は、いわば「神がかって」
いるように思える。恐らくは優秀な設計・開発陣や優秀な
外部スタッフ等の人材に恵まれていたのであろう。
本α-SweetⅡは普及機ながら、恐ろしいまでの高性能を
詰め込んだ「スーパーサブ機」である。その高性能は、
銀塩一眼レフ・クラッシックスの性能評価で、並み居る
旗艦機や名機を押さえて、唯一の「5点満点」が与えられた。
ただ勿論、例えば最高シャッター速度は1/4000秒止まり等、
旗艦α-9の1/12000秒からすれば絶対性能は見劣りする。
だか、そういう単純なカタログスペック比較が通用する
時代では既に無くなっている。この時代2000年代前半には、
銀塩マニュアル露出機など非常に趣味的な要素が高いカメラ
が次々と新発売された時代なのだ。
それに、1/12000秒は「日中に大口径F1.4レンズを開放で
使用する」などの特殊な目的にしか使われない。
ましてやこの時代であれば、ND4(減光2段)フィルターを
併用する等で、最高シャッター速度の不足を解消する手段は
別途存在している。
で、そうした超絶性能を、小型機に詰め込んでいながら、
このα-SweetⅡの本体重量は、335gと極めて軽量であり、
恐らくは当時の(AF)一眼レフ最軽量であった。
値段も67,000円と、20年前のX-700と同等の安価である。
この超軽量・超高性能からのハンドリング性能は特筆
すべきであり、銀塩時代には、およそ毎回のように、
α-SweetⅡに小型レンズを装着し、他のメインとなる
一眼レフ等のサブ機として使用。さらには雨天等の過酷な
環境の趣味撮影においても、「いつ壊れても良いから」
(注:後年では中古価格は2万円台と、安価になっていた)
という消耗機として、銀塩時代を通じ、デジタル時代に
入ってもなお、2000年代中頃まで大活躍した。
![_c0032138_16561459.jpg]()
数年後にデジタル一眼レフに転換する事が市場では明白で
あった為、この時期に、ミノルタαマウントの一眼レフを
エントリー(入門、初級)層に普及させ、続くデジタルα
(注:実際にはミノルタではなく、KONICA MINOLTA製
になったが)を引き継いで使用して貰う戦略だ。
これはミノルタだけに限らず、CANONでも非常に多数の
Kissシリーズの普及機群を市場に集中投入し、ニコンでも
(不本意ながら?)uシリーズを複数発売、さらにPENTAXは
やや出遅れたのだが、銀塩末期に*istを発売している。
これらの「デジタル乗り換え機種群」は、一部には非常に
優秀な仕様を持つものがあり、このα-SweetⅡもその1台だ。
他にはNIKON u2も所有していて、同様にハンドリング性能
が高くて重宝した(現在未所有)
また、CANON EOS Kiss 7(2004)や PENTAX *ist(2003)
も、非常に性能が高い「スーパーサブ機」であったのだが、
既にデジタル時代に突入していた為、残念ながら見送った。
----
さて、今回の記事はこのあたりまでで・・
丁度銀塩時代が終焉した頃である。
他にもα機は多数存在しているが、現在での所有範囲は
ここまでだ。銀塩一眼レフ記事での当該αの記事群に、
より詳細を記載しているので興味があれば参照されたし。
次回記事は、MINOLTA編の後編として、KONICA MINOLTA
時代のデジタル機の変遷を紹介していこう。
のカメラを、およそ1970年代から現代2020年代に至る迄の
約50年間の変遷の歴史を世情等と絡めて辿る記事である。

機を中心に紹介するが、ご存知の通り、MINOLTAは銀塩時代
終焉頃にKONICAと合併して「KONICA MINOLTA」となって
いて、その後2006年には、カメラ事業から撤退している。
---
そして現在、私が保有しているMINOLTA機は1970年代以降の
物に限られる。それ以前の時代のMINOLTA機はデジタル時代に
入った頃に「実用価値なし」という判断で処分してしまった。
勿論それ以前から、MINOLTAはカメラを製造・販売している
老舗メーカーだ。まず、そのあたりを簡単に説明してから、
順次、各時代のMINOLTA機の変遷について紹介する。
なお、挿入している写真は、紹介機体の頃の時代のMINOLTA
製レンズで撮ったもので、本文内容とはあまり関係が無い。

1930年代は日本やドイツで、いくつかの機械式カメラメーカー
による事業が立ち上がった時代である。日本ではそれ以前の
1900年代初頭(ライト兄弟の初飛行の頃)からコニカが
カメラを発売していたが、それは例外的だ。
(注:1930年代は第二次世界大戦前の世情であり、軍事
用途での光学機器の開発が要望されていたと思われる)
ミノルタは1928年頃~1933年頃には、まだ会社としての
組織形態も不定ではあったが、1933年の「セミミノルタ」
でブランド名としての「ミノルタ」が初めて登場した。
1937年頃にMINOLTAの母体となった「千代田光学精工」が
設立された。
また、写真用品を扱う「浅沼紹介」(KINGブランド)と提携
して、その流通経路で、様々なカメラ製品を販売している。
同時期には、国産初(?)の二眼レフカメラも発売、しかし
この頃に軍需工場に指定された為、その後の大戦の時期には
(民生用)カメラ製品の製造は少ない。
----
1940年代後半~1960年代 二眼レフ、各種フィルムカメラ
戦後は中判の二眼レフやスプリング式カメラ等を多数展開。
これらの型式のカメラは1960年代まで新規発売が継続される。
また、1950年代頃~1970年代頃には、16mm判フィルム。
1960年代頃には126判フィルム、そして1970年代頃には
110判フィルム等と、多様なフィルムフォーマット対応の
カメラを発売していた事もミノルタ(や、この時代の他社)
の特徴だ。
この時代1940年代後半より1950年代を通じて、ライカL39
マウント互換機がミノルタより発売されているが、多くの
製品はフィルムフォーマットが32mmx24mm判であった。
35mm判(ライカ判36mmx24mm)フィルム使用カメラは、
1950年代~1970年代にかけて、レンズ固定式、レンズ
交換式等、非常に多数のカメラを発売しているが、機種が
極めて多いので詳細の説明は省略する。
代表的な機種としては、ハイマチックシリーズ(1961年~
1982年、未所有)をあげておく。
なお、このシリーズはハイマチックAF(1979年)より、AF化
されている(注:AF一眼レフの「α-7000」より6年早い
が、「ジャスピンコニカ C35AF」1977年、よりは遅い)
----
1960年代~1970年代前半 一眼レフ SRシリーズ
1958年のSR-2から35mm判一眼レフの発売を開始。
以降、SR-1シリーズ、SR-3シリーズ、SR-7シリーズ等、
多数の一眼レフを1960年代前半にかけて展開している。
SR-7(1962年)は、世界初のCdS型露出計内蔵機であり、
加えて、この時期、コンパクト機「ハイマチック」が
米国宇宙船の「フレンドシップ7号」で使用された事にちなみ、
その後継機を「ハイマチック7」と呼んだ事で、以降ミノルタは
革新的で記念碑的な機種名を「7番機」とする慣習となった。
これは以降の時代を通じて続き、さらに2006年にカメラ事業が
SONYに引き継がれた後でも、同様に革新的な機種名を7番機
とする伝統が受け継がれている(例:SONY α7、2013年)

商号変更している。
で、あいかわらずミノルタのカメラは数が多く、SRシリーズ
も同様だ、以降の時代は代表的な機種のみの説明にしよう。
1966年 SR-T101
初のTTL測光機、加えて、初の2分割測光(CLC)機能を搭載
している。
CLCは画面の上下半分づつを異なるCds素子で測光する方式、
空の明るさに露出が引っ張られてアンダー露出になるのを
補正するアイデアだ。(ただし縦位置撮影では効果は無い)
1973年 SR-T Super
ファインダー廻りを改良し、実用性を高めた人気機種。
この機体は銀塩時代に所有していて、2分割測光のCLCが
意外に露出精度が高かった印象がある。(現在未所有)
----
さて、ここからは現在も所有している一眼レフの時代に
到達した、実機を紹介していこう。
1970年代 一眼レフ Xシリーズ

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第4回記事参照)
化物のような異色のカメラ、ミノルタ初の旗艦機である。
「重厚長大」な事で、本ブログでは昔から「超弩級戦艦」と
呼んでいる。(注:この機体は小型ファインダー仕様だ)
レンズ付きでの定価は13万円台であり、現代の貨幣価値で
およそ50万円~60万円にもなる。(詳細後述)
なお、後年のX-1 Mortor(1976)は、「船底ファインダー」
仕様では、とんでも無い存在感を持つ異形のカメラであった
が、さらに高価で、X-1の2倍以上の価格であった。
(よって、ほとんど流通していない)
さて、値段は高いのだが・・ 必ずしも性能が高いとか
使い易いカメラでは無い。本機の入手は銀塩末期であったが
その操作性が独特すぎて、また重量も約1kgと重く、ほとんど
実用価値は無かった。ただ、歴史的に貴重な機種であるので
デジタル時代に入っても、処分せずに残した次第である。

世情あるいは物価は、どんな感じだったのであろうか?
実は、1970年代は物価が大きく上昇した時代でもある。
わかり易いように、喫茶店のコーヒー代をあげてみよう。
1970年では120円、1971年130円、以下100円台後半から
1974年では200円を超え、1979年には300円となっていた。
初任給も同様だ、公務員では1970年頃の3万円台から
1979年には10万円近くまで跳ね上がる。
この他にも色々と商品の物価のデータは存在するが、
いずれも1970年代の10年間にかけて、およそ3倍程度の
値上がり率だ。
ちなみに、1971年に日本初上陸したマクドナルドの
ハンバーガーは80円で、新発売のカップヌードルは100円
であった、いずれも現代の価値では500円前後と、高価
ではあるが、東京の街でこれらを食べながら歩く若者が
急増し、新しい「文化」を築くきっかけになった模様だ。
で、現代の喫茶店のコーヒー代が平均600円位、そして
現代の大卒公務員初任給が約21万円位と考えると、
だいたい以下のような倍率を当時の価格に乗ずると、
現代の貨幣価値に換算できるのではなかろうか?
1970年代前期 6倍~4倍
1970年代中頃 4倍~3倍
1970年代後期 3倍~2倍
なお、一般的に言う「高度成長期」(好景気の時代)とは、
概ね、1954年末頃から1973年にかけてを言う。
その「高度成長期」の終焉の理由の1つが、原油(石油)
価格の高騰(オイルショック)である、
1973年には第一次オイルショックが起こり。日本も
これの影響で酷いインフレとなり、1年間で物価が23%も
上昇、1974年では、戦後初のマイナス成長となった。
この頃、生活必需品である「トイレットペーパーや洗剤が
無くなる」という噂(デマ)が流れ、日本全国でとんでも無い
パニックとなり、各商店には、それらを買い求める主婦達の
長蛇の行列が出来た。(近年のコロナ騒ぎの際と同様だ)
1979年には、世界情勢の変化から、第二次オイルショック
が起こったが、「トイレットペーパー騒動」の経験からか、
消費者やメディアは大騒ぎをせず、日曜日にガソリンスダンド
が休業する程度で済んだ模様だ。
この頃から「省エネ」(現代の「エコ」)の概念が消費者層
にも普及し、新内閣では「省エネルック」と呼ばれた半袖の
軽装を政治家達が着てアピールした(現代の「クールビス」)
ただ、消費者の混乱は少なかったのかもしれないが、この後の
時代は、しばらく不況が続く。

Xシリーズは展開された訳だが、世情を考えると、この時代の
カメラの価格の上昇は、やむを得ない節もあり、加えて、
諸費者物価指数の上昇程の高騰も無いようにも思えてくる。
以下、続くミノルタXシリーズの一眼レフを紹介していこう。

銀塩一眼レフ・クラッシックス第6回記事で紹介。
世界初の「両優先AE」機である。
これは、これまでの時代、各社は「シャッター優先」と
「絞り優先」の、いずれかのAE(自動露出)機能を備え、
「そのどちらが優れているか?」といった論争が真剣に
行われていた状況であったが、この機体、および翌年の
CANON A-1(1978)の登場で、そのいずれもが搭載された為、
ほど無く「絞り優先、シャッター優先論争」も終結した。
現代でも良く起こる「スペック競争、スペック論争」の
走りとも言える世情であるが、個人的な見解としては、
カメラの性能や機能がどうであったとしても
1)その機能の長所、短所をちゃんと見分けられるか?
2)機材に短所がある場合、それを回避する為の技法や
技能を使いこなせるか否か?
が、重要だと思っている。
だがまあ、これらの「両優先」カメラ以前では、ある意味
「様々な撮影状況に必要な最低限の機能」を搭載していない
場合も多々あった訳であり、まだ、この時代であれば、
スペックやらを強く気にしても、やむを得ない節はある。
しかし、この時代から既に40年以上が経過しているし、
現代の(デジタル)カメラにおいては、撮影の為に不足して
いる機能は、基本的な撮影技法の範囲内では一切無い。
当然、性能も十分であり、スペック競争も殆ど無意味だ。
だから、現代においては、カメラやレンズの基本性能だけに
頼って撮っている状態はNGであり、今時でも初級者が良く
言う「このカメラは色が悪い」とか「このレンズのAFは遅い」
とかの、機材側の基本性能に文句をつけるだけで、何の工夫も
しないスタンスは、褒められた話では無い、という事だ。
さて、このMINOLTA XDの発売時定価は78,000円だった。
現代の貨幣価値では20万円程になり、少々高価であったと
思うが、前述の「インフレ」の市場状況があったので、
ある程度は、やむを得ない。
また、XD系は後年の中古市場にあまり出て来なかったの
だが、それもまた「割高感」から、ユーザーが少なかった
からなのかも知れない。

当時まだ21歳の宮崎美子さん(現:女優/クイズの女王)が
「木陰でGパン(ジーンズ)を脱いでビキニ姿になる」
というTV CMが社会現象的な話題となり、そのCM効果で
X-7は大ヒットカメラとなった。
このCM、およびCMソング(斉藤哲夫氏)は伝説的であり、
後年には、このシーンのフィギュアまで発売された程だ。
この機種の性能はXD等に比べて低い、「絞り優先専用機」
ではあるが、そういう事は多くの消費者層には無関係だ。
1970年代オイルショックの影響で割高になったカメラ価格
を1度下げる目的もあったと思われ、XDの価格の約半額の
本体39,500円(?推定。レンズ付きは59,500円)と
安価に販売された事も大ヒットの要因だ。
これも革新的な「7番機」ではあったが、他の7番機とは
ちょっとイメージが違う、あまりに「大衆的」な機種だ。
非常に著名なカメラではあるが、TV CM自体が度を越して
有名であるが故にか、その割りに、この機体の型番(X-7)
や、CMソングのアーティスト(斉藤哲夫氏)の名前を
覚えていて言える人は、後年には殆ど居なかった。
恐らく、ビギナー層は店頭で「宮崎美子のカメラを下さい」
と言って購入していた事であろう。
私は、この「歴史的価値」から、所有した事はあるが、
性能面やマニアック度が低い為、短期間で譲渡してしまった。

銀塩一眼レフ・クラッシックス第10回記事で紹介。
ミノルタ初にして、ミノルタMF機唯一の「プログラムAE」
(MPS機能)を搭載した「7番機」である。
それまでの、XD,XD-S(1979)でも、「GGGシステム」や
「サイバネーションシステム」といった「擬似プログラムAE」
が搭載されてはいたが、X-700の「MPS」は、正規の
プログラムAEである。
1970年代インフレで高価になりすぎたカメラ(だからこの
時代ではX-1以降の旗艦機はミノルタには存在しないのか?)
そして一眼レフのAF化が目前に迫っている事(コンパクト機では
すでにAFは常識)、さらには前年の「X-7」の大ヒットなどの
要因を受け、あまり開発に手をかけていないカメラには見えるが
完成度はかなり高く、1999年頃まで18年間もの、異例の
ロングセラー機種となった。(注:既存MC/MDマウントと
互換性の無いα(AF)マウント機が主力となった為、「既存
MC/MDレンズユーザーの救済策として、X-700のみ販売が
継続された」という解釈も可能である→後述)
個人的には、後年に初めて入手した一眼レフがX-700であり、
銀塩時代を通じて、かなり愛用した機体である。
特にファンダー性能(倍率の高さ、スクリーンの見えの良さ)
は特筆すべきであり、初級者でもMF操作を難なく行える。
1/1000秒シャッター等、低スペックではあるが、不要な迄の
機能や性能を搭載しない事から、発売時定価も63,000円と、
XD系よりもだいぶ安価だ。
なお、この頃の他のミノルタXシリーズの詳細については、
銀塩一眼レフ・クラッシックス第4回(X-1)、第6回(XD)
第10回(X-700)に詳しいので、重複する為、割愛する。
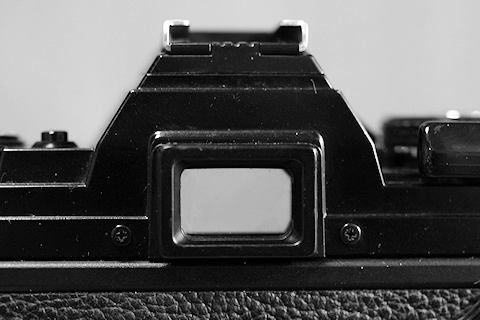
ミノルタが他社に先駆けて初めて実用的なAF一眼レフを
完成させた、いわゆる「αショック」は社会現象ともなった。
本ブログでは何十回も説明した事であり、詳細は割愛する。
また、この機体は歴史的価値が極めて高いが、個人的には
好みではなく、所有の機会に恵まれていない。
私は、もっぱら同年発売の上級機「α-9000」を銀塩時代を
通じて愛用したが、デジタル時代に入って故障(液晶の劣化)
の為、廃棄してしまった。(発売時定価12万円弱)
なお、αマウントは旧来のSR/MC/MD系マウントとは互換性
が無い為、前述の「X-700」は継続販売される事となった。
(この点については、αの性能が圧倒的であった為、
マウント変更の不満はユーザー層からは出て来なかった)
この後、数年間はこのα-7000(シリーズ)だけで
ミノルタのラインナップを支える事になる。
さらにその後、1990年頃~1997年頃には、バブル期の
世情の激変、特許訴訟等、ミノルタには色々とタイミング
の悪い不運な出来事が降りかかる。このあたりの歴史は
暗いので、マニア的な観点からは、あまり書きたく無い。
(興味があれば、銀塩一眼第23回α-9の記事に詳しい)
----
ミノルタの一眼レフ用交換レンズ群
ここの詳細を書き出すと、際限なく記事文字数が増えて
しまう、過去記事でも多数紹介しているし、またいずれ
機会があれば別記事で纏めて紹介しよう。
市場ではあまり好評価は無いが、レンズによっては
描写力が極めて優秀なものもあり、コスパが良いと思う。

1970年代の「ハイマチック」シリーズは、後年1979年頃
からAF化している(ハイマチックAFシリーズ)、ただし
まだ初期の時代のAFであるから、精度はあまり高くなかった。
他社においても、この1970年代末のAFコンパクト機は、
AF試作機的な様相が強かった時代である。
後年1980年代においては、MINOLTA AFシリーズ(初号機は
AF-C:1983)を展開、AF-Sシリーズでは音声操作ガイド機能
を入れるなど、先進的ではあるが・・
これは後年の「過剰な多機能化」の前触れと言えるかも知れない。
1980年代後半では「MAC(マック)」シリーズを展開、
AF/AE搭載の単焦点又は二焦点機で、完全自動化されている。
また、この時代は「日付写しこみ機能」が普及し、ミノルタ
でも「クオーツデート」という名称を機種名につけている。
他は、あいかわらず機種数が多いので詳細は割愛する。
1990年代となると、バブル経済もピークとなったからか、
色々と「バブリーなカメラ」が出てくる。
MINOLTA PROD 20's(1990年)は、1920年代を思わせる
美しいクラッシックなデザインを施した全自動カメラ。
この機体は所有していたが、全自動でテクニカルな要素が
何も無かった事と、意外に大柄でハンドリング性が悪く、
写りもあまり良く無い等を理由として、ファッション的な
要素(人が集まる機会に、話題性の為に持ち出す)程度で
しか用途がなかった。
限定生産品であった筈なのに、後年、いくらでも新品在庫が
中古市場に流出し、中古流通業界でも「Prodは、もういいよ」
という風潮が出てきて、中古カメラブームの時代でさえも
不人気であった。私はデジタル時代に入って処分したのだが
実用価値の低さから、周囲のマニア層への直接譲渡は避け、
タダ同然で、中古店に引き取ってもらう事にした。
「バブリーなカメラ」と言えば、MINOLTA APEX(アペックス)
シリーズも酷い。これは自動ズーム(AFで測った距離から
例えば人物では、自動的に半身像となる画角とする)機能を
備えていて、そのモードにおいては撮影者が撮りたい画角に
すらならない、という非常におせっかいな仕様だ。
私はMINOLTA APEX 90(1992)を購入していたが、あまりに
「おせっかい」であった為、短期間で処分してしまった。
市場においても、この頃の一眼レフα-xiシリーズ(これも
バブリーな不要な機能を満載)と同様に酷評をくらい、
おまけに「特許訴訟」のネガティブなイメージと、バブル経済
崩壊の余波を受け、この頃のミノルタは不運な時代であった。
その後、1990年代後半~2000年代前半には「カピオス」
シリーズを展開するが、ありきたりのAF普及コンパクトで、
マニア層では既に「中古カメラブーム」に突入していた為、
まったく話題にも上らなかった。
特にマニア層では、α-xiや、APEX、Prod20's等の悪印象も
あったからか、この時代においては「ミノルタを買うのは
やめておけ」という、まるで「呪いのカメラ」でもあった
かのような悪評判が、マニア間で、まことしやかに囁き
続けられていた。

マニア層での「呪いのミノルタカメラ」の悪印象を払拭した
高級コンパクト機。
同時代の「RICOH GR1」(1996)や「CONTAX G2」(1996)
と共に、高級コンパクト・高級レンジファインダー機の
大ブームを巻き起こすきっかけになった立役者。
TC-1は、買って使ってみると、色々とクセのあるカメラで、
個人的には、あまり思い入れが持てず、もっぱら興味は、
銀塩GRシリーズ(前身のR1シリーズから、ほとんどの機種を
所有していた)に向いてしまい、自然に手放してしまっていた。
余談だが、この頃、奈良県では色々な遺跡の発掘調査や新発見
が相次ぎ、私も興味があった為、それらの発掘現場に入れる
「現地説明会」に良く足を運んだ。
どこかの現地説明会で、発売されたばかりのTC-1を持って
来ていたシニアが居たが、彼は、ぬかるみの発掘現場で足を
取られ、新品のTC-1がドボンと泥水の中に水没してしまった!
このTC-1は、発売時定価148,000円と非常に高価なカメラ
であった為、「あちゃ~」と、目をそむけざるを得ず、
その様子がとても印象と記憶に残った。
(当然、修理しただろうが、ご愁傷様でした・・)
そして、後年2003年頃になって、黒塗装の「TC-1 Limited」
という限定販売機を中古市場で見かけ、TC-1がミノルタ唯一の
高級コンパクトであった事の歴史的価値の高さと、Limited
仕様でのマニアック度の高さを鑑み、購入しようか迷った。
やや高価(8万円位だったか?)で、1~2日悩み、買う気に
なって再度中古店を訪れると、既に売られてしまっていた。
地方の小さい中古店だが、中古カメラのブローカー(せどり)
という職業層も良く訪れる店だったので(つまり、店舗間での
わずかな相場の差を利益とする生業だ)その手の人が買って
いったのかもしれない(であれば、目利きはさすがである。
後年には軽く10万円を超える高額相場で取引されたからだ)
私は「TC-1とは、縁に恵まれなかった」と解釈して、その後は
この機体に興味を持つ事は無かった。
(注:この概念は「マニア道」としては、結構重要である。
「フラれた相手」に、いつまでも未練を持つ事は良く無い)
----
1997年 MINOLTA Dimage V(未所有)
ミノルタ初のデジタル・コンパクトカメラ。
ここでミノルタの初期デジタル機の説明をしだすと
限りなく文字数を消費するので、やむなく割愛するが、
以下、代表的な機種だけあげておく。
(注:1990年代の製品ではDimageと小文字表記)
DiMAGE 7(2001年)高画質高倍率ズームレンズ搭載
DiMAGE X(2002年)初の屈曲光学系採用
DiMAGE A1(2003年) 初の手ブレ補正内蔵機
----
1997年 MINOLTA VECTIS GX-4 (現在所在不明)
当時流行していたAPS(IX240)フィルム使用の水中機。
私は、APSコンパクトは沢山所有していた。理由は特定の
使用目的(超小型、ファッショナブル、マクロ、防水等)に
特化した個性的な機種が多かったからだ。
本機は、海やプールでのレジャー用途に購入、まあその目的
には十分活躍したが、固定焦点で、写りはイマイチであった。
この機体以外にもVECTISシリーズはいくつか存在するが、
詳細の説明は割愛しよう。現代となっては、APS機は
フィルムの入手も現像も、ほぼ不可能であるからだ。
(本機は、所有している筈だが、どこかにしまい込んで
所在不明だ。他にもそういう未発見機材がいくつかあって、
いずれ大規模な発掘調査を行わないとならない・・汗)

銀塩一眼レフ・クラッシックス第23回記事で紹介。
「第一次中古カメラブーム」も真っ盛りの時代であり、
マニア層を中心としたユーザー層は、新規のAF一眼レフ
には殆ど興味が持てなかった。私も同様であり、前述の
1990年代ミノルタ機の(不当な)悪評判もあって、特に
α一眼レフ機は敬遠していた。もっぱら使っていたα機は
10年以上も前のα-9000であったが、そのマニアックな仕様
(例:AF機で唯一のフィルム手動巻上げ)に満足していた。
だが、ある時、中古店で、このα-9を見せてもらい、
それまでの価値観がひっくり返る程の衝撃を受けた。
このα-9は、カタログスペックからは全く読み取る事が
出来ない長所が満載のカメラであったからだ。
その詳細は、当該紹介記事に詳しいので割愛するが、
その記事は是非、初級マニア層等には読んでいただきたい。
α-9の中央測距点のAF精度、高性能スクリーンとファインダー
でのMF性能は超絶的であり、他社機と一線を画す他、この
MF性能には、後年の一眼レフ全てが太刀打ちできない。
私も、この機体を買うまでは「カタログスペック優先」
という初級マニアに過ぎなかったのが、このα-9での、
「スペックには現れない真の性能」を見てしまってからは、
多面的にカメラの良し悪しを見る視点や、その眼力が
養われていったと思う。

銀塩一眼レフ・クラッシックス第29回記事でLimited版
を紹介。
前述のα-9で、私は、それまでのミノルタ機を敬遠して
いた事を後悔した。マニア層での「流言」に乗せられて
実機も触らず「呪いのカメラ」でもあったかのように
思い込んでしまった事も反省材料だ。
いったいいつ、どこで、α一眼レフがどのように進化して
いたのか? もう、それらの旧機種のカタログスペック
だけでは知るよしも無いし、今から古いαのxiやsiシリーズ
を購入する事も、最高のカメラ(α-9)を使っている限り
では、実用上では無意味だ。
で、α-9の超絶性能に「びっくりしながら」機嫌よく使って
いるところに、さらに、このα-7の登場だ。
こちらは「またしてもヤラれてしまった!」というのが
第一印象だ。
このα-7は、α-9ほどのAF性能もMF性能も持たない、
だから、ランクという点ではα-9の下位機種だ。
しかし、このα-7の「操作系」が化物的に凄かったのだ。
「操作系」という概念は、この時代まで、少なくとも私は
持っていなかったし、他のマニア層でも同様であろう。
また、業界での専門家層(職業写真家、職業評論家、
店舗販売員、他メーカーでの企画・開発者層)ですらも
殆ど持っていなかったに違い無い。
(その後、現代に至るまで、この状況は殆ど変わっていない)

なるまでは、それまでの単機能操作子での「操作性」だけを
語ったり評価すれば良く、操作系の概念自体も不要ではあった。
その「操作系」については、本ブログでは何十回も説明して
いるので、ばっさりと割愛する。それにそれを理解するには
高度な撮影知識・経験・技能などが必要とされるので、
初級中級層には文章だけで理解できるようなものでは無い。
で、このα-7は「銀塩一眼レフ最良の操作系」を持つ機体
である事は勿論、その後のデジタル一眼レフ時代を含めても
依然、この機種にしか存在しない優秀な操作系機能もいくつか
あるので、少なくとも「銀塩AF一眼レフ最強の傑作機」で
ある事は疑いの余地も無く、下手をすれば、MF一眼レフから
現代に通じるデジタル一眼レフ迄を含めて、全ての世代の
一眼レフ中でも、かなりの上位(Best3)に入る機体である。
(いずれ、その手の「全カメラ・ランキング」記事を
纏めてみたいと思っている)
ただ惜しむらくは、この直後、一眼レフはデジタル時代に
突入してしまい、この傑作機も、だんだんと主力には
なりえなくなってしまった事だろう。
まあでも私としては、2000年代後半の銀塩完全終焉期の
ギリギリまで本機は活用していた。

銀塩一眼レフ・クラッシックス第27回記事で紹介。
この時代のミノルタα機の完成度は、いわば「神がかって」
いるように思える。恐らくは優秀な設計・開発陣や優秀な
外部スタッフ等の人材に恵まれていたのであろう。
本α-SweetⅡは普及機ながら、恐ろしいまでの高性能を
詰め込んだ「スーパーサブ機」である。その高性能は、
銀塩一眼レフ・クラッシックスの性能評価で、並み居る
旗艦機や名機を押さえて、唯一の「5点満点」が与えられた。
ただ勿論、例えば最高シャッター速度は1/4000秒止まり等、
旗艦α-9の1/12000秒からすれば絶対性能は見劣りする。
だか、そういう単純なカタログスペック比較が通用する
時代では既に無くなっている。この時代2000年代前半には、
銀塩マニュアル露出機など非常に趣味的な要素が高いカメラ
が次々と新発売された時代なのだ。
それに、1/12000秒は「日中に大口径F1.4レンズを開放で
使用する」などの特殊な目的にしか使われない。
ましてやこの時代であれば、ND4(減光2段)フィルターを
併用する等で、最高シャッター速度の不足を解消する手段は
別途存在している。
で、そうした超絶性能を、小型機に詰め込んでいながら、
このα-SweetⅡの本体重量は、335gと極めて軽量であり、
恐らくは当時の(AF)一眼レフ最軽量であった。
値段も67,000円と、20年前のX-700と同等の安価である。
この超軽量・超高性能からのハンドリング性能は特筆
すべきであり、銀塩時代には、およそ毎回のように、
α-SweetⅡに小型レンズを装着し、他のメインとなる
一眼レフ等のサブ機として使用。さらには雨天等の過酷な
環境の趣味撮影においても、「いつ壊れても良いから」
(注:後年では中古価格は2万円台と、安価になっていた)
という消耗機として、銀塩時代を通じ、デジタル時代に
入ってもなお、2000年代中頃まで大活躍した。

数年後にデジタル一眼レフに転換する事が市場では明白で
あった為、この時期に、ミノルタαマウントの一眼レフを
エントリー(入門、初級)層に普及させ、続くデジタルα
(注:実際にはミノルタではなく、KONICA MINOLTA製
になったが)を引き継いで使用して貰う戦略だ。
これはミノルタだけに限らず、CANONでも非常に多数の
Kissシリーズの普及機群を市場に集中投入し、ニコンでも
(不本意ながら?)uシリーズを複数発売、さらにPENTAXは
やや出遅れたのだが、銀塩末期に*istを発売している。
これらの「デジタル乗り換え機種群」は、一部には非常に
優秀な仕様を持つものがあり、このα-SweetⅡもその1台だ。
他にはNIKON u2も所有していて、同様にハンドリング性能
が高くて重宝した(現在未所有)
また、CANON EOS Kiss 7(2004)や PENTAX *ist(2003)
も、非常に性能が高い「スーパーサブ機」であったのだが、
既にデジタル時代に突入していた為、残念ながら見送った。
----
さて、今回の記事はこのあたりまでで・・
丁度銀塩時代が終焉した頃である。
他にもα機は多数存在しているが、現在での所有範囲は
ここまでだ。銀塩一眼レフ記事での当該αの記事群に、
より詳細を記載しているので興味があれば参照されたし。
次回記事は、MINOLTA編の後編として、KONICA MINOLTA
時代のデジタル機の変遷を紹介していこう。