所有している一眼レフ用の50mm標準レンズを、AF/MFや
開放F値等によるカテゴリー別で予選を行い、最後に
決勝で最強の50mmレンズを決定するというシリーズ記事。
今回は、予選Nブロックとして「AF焦点距離違い」の
レンズを5本紹介(対戦)する。
なお「AF焦点距離違い」とは、レンズの実焦点距離
又はAPS-C機専用レンズでのフルサイズ換算焦点距離が
ぴったり50mmにはならず、おおむね30mm~45mm
(換算で45mm~60mm程度)の焦点距離(画角)となる
レンズ群を指す、少々ややこしいが、まあつまり中途半端な
焦点距離のAF標準レンズ群を集めたカテゴリーだ。
そもそも50mm=標準のルールを定めたのは、戦前1930
年代のライカ(ライツ社)であり、それは単に中途半端な
覚え難い数字を嫌っての措置だとも思われ、50mmを標準
とする、技術的あるいは生理学的な根拠は殆ど無いし、
そして、ずいぶんと古い時代のルールでもある。
---
さて、まずは今回最初のレンズ。
![_c0032138_18132341.jpg]()
レンズ購入価格:40,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第1回、第64回記事、
特殊レンズ超マニアックス第9回記事等で紹介の、
1990年代後半の銀塩・フルサイズ対応AF標準レンズ。
![_c0032138_18132456.jpg]()
これは(35mm判)フィルムの対角線長であり、PENTAXでは、
「これが本来の標準レンズである」という解釈をしていた。
しかし、ちょっと前述したような、ライカの「50mm=標準」
の古いルールに、ただ反発していただけかも知れない。
そして、50mmでも43mmでも、どちらでも標準レンズとは
言い難い点もある。すなわち「標準レンズ=人間の視野」
として考えるのであれば、人間の視野はもっとずっと
広いからだ。そしてフィルムの対角線長を焦点距離とする
原理的な意味(解釈)も余り無い。
(この話は、もう少し詳細を後述する)
さて、そういう曰くがあるものの、本FA43/1.9の
描写力そのものは、全く申し分の無い高性能レンズだ。
殆ど弱点は無い。銀塩時代であれば、恐らくは、
PENTAXの(35mm判)交換レンズ中、5本の指に入る描写力
と言えたであろう。
ただ、現代の視点からすると、さすがに本レンズは20年
以上の前の設計と古く、解像感等に若干の不満があると思う。
(しかし、ボケ質は良好で、逆光耐性も強いので、銀塩機
あるいは低画素デジタル機で使う上では何ら不満は無いで
あろう)
それから、絞り羽根が8枚と偶数構成で、被写体状況に
よっては、ボケ形状が乱れる場合がある。
ただし、これはあくまで「ボケ形状」だ、本ブログで言う
「ボケ質」とは直接は関係が無い。
余談だが、様々なレンズ製品において、「円形絞り」を
採用する事で「ボケ味が良くなる」という記述があるが、
私に言わせれば、これは限りなく「グレーな」表現である。
まず「ボケ味」という用語が良く無い、これでは何を示して
るのか、具体的な意味が不明だ。つまり、それを読む人の
それぞれで異なる解釈が出来てしまい、その事が、もし
消費者層の購買動機につながるならば、あまり公正な
販売のやりかたとは言い難いからだ。
本ブログでは、「ボケ味」の用語は非推奨である、
その代わりに以下のような用語群を使う。
ボケ量:背景等を、どれくらいの量(面積、比率、深さ)
でボケすか、これは「被写界深度(外)」と、
ほぼ等価の概念だ。
ボケ質:被写界深度外の部分において、ボケの画像的な
品質が良好か否か。これが悪いケースには、
一般に言われる「二線ボケ」「ぐるぐるボケ」等が
あるが、そうした言葉だけでは表現できないような
様々な品質劣化があり、本ブログでは、その状況を
総称して「ボケ質破綻」(が起こる)と言う。
ボケ形状:本ブログでも滅多に使わない用語であるが、
例えば、夜景における周辺ボケがレモン形状と
なるケース(これは「口径食」が原因だ)や、
木漏れ日のボケに絞り羽根の形状が出てしまう事等。
なお、後者はボケ以外にも、ゴーストを意図的に
あるいは意図せず発生した場合にも、絞りの形状が
出てしまうケースがある。
世間一般には、こうした明確な定義が存在していない為、
あえて「ボケ味」という曖昧な表現をメーカー等でも
使っているのかも知れないが、よくよく注意してみると
その「ボケ味の用語が曖昧である」事を逆用して、製品の
性能優位性を誇張するような、グレーな表現が見られる。
具体的には、「円形絞りを採用しているからボケ味が良い」
であり、これは正しくは「円形絞りにより、被写体条件や
絞り値に応じて、ボケ形状が良くなる可能性がある」に
過ぎない。
つまり、「ボケ量」や「ボケ質」には無関係な話だ。
そして、どんなレンズでも開放で使えば完全な円形絞りだ。
(=近年のビギナー層の用語では「玉ボケ」の状態。
ただし、中上級マニア層の用語では輪郭線の出る「円形ボケ」
状態のみを指して「玉ボケ」、「シャボン玉ボケ」あるいは
「バブルボケ」と呼ぶ。このあたりも定義が曖昧な俗語だ)
あるいは、ビギナー向けのカメラの機能で「ボケ味
コントロール」という設定もある。これを使うと、ボケ質
が見るみる良くなる・・ 等と言う事は勿論一切なく(汗)
これは、何と、絞り優先機能と同じであり、単に絞り値を
調整するだけのものであったりする。
この機能で変化するのは単に「被写界深度(≒ボケ量)」
だけであるし、おまけに、そうしたビギナー向けカメラには、
85mm/F1.4等といった、大口径でボケ量のコントロールの
自由度が高いレンズを装着する筈もない。(→有り得ない)
普通は、被写界深度が深い、つまり開放F値が暗くて、かつ
最短撮影距離も長い標準ズーム等を装着するので、その状態
では、絞り値をいくらあれこれと変更しても殆ど効果も無い。
初級者層へのカメラ原理の理解を促進させる名目もあった
のかも知れないが、「実態」とはちょっと連動していない。
むしろ「ボケ味コントロール」等という曖昧な表現をしたら
超ビギナーユーザーから「何の変化も起こらない」という
クレームに繋がってしまうのではなかろうか?
まあ結局、こういう表現の機能があったのは、限られた
時代(2010年前後)での話であり、今時のカメラには、
こういう曖昧な、あえて言えば、「グレーな」機能名称は、
殆ど用いられていないと思う。
![_c0032138_18132401.jpg]()
まあ前述のように、普通の利用法では特に不満も出る事も
無い高性能レンズだ。あえて欠点を言えば、古いレンズの
割りに新品販売も継続されていて、価格が少々高価な事と、
中古相場も、ずっと殆ど下がらない事だ。
(PENTAXが、HOYA、RICOHと親会社が変わって来た度に
本レンズも少しづつ値上げされている。そして中古相場は
その定価にも若干連動するからだ)
価格の面からは、ぶっちゃけ言えば本レンズを4万円弱で
中古購入するのは、現代の感覚からはコスパが若干悪い。
現代において4万円近くも出すのであれば、より高い
描写力の近代標準レンズの内の何種類かが中古で買える
価格帯(中古相場)である。
---
では、次のレンズ。
![_c0032138_18133867.jpg]()
レンズ購入価格:27,000円(中古)
使用カメラ:NIKON D70(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第75回記事で紹介の、
2005年発売の、APS-C機専用AF大口径準標準
(標準画角)レンズ。
今回は発売当時の雰囲気を味わう為に、前年2004年に
発売のNIKON D70に装着して使ってみよう。
![_c0032138_18133803.jpg]()
続けたが、2013年に、このレンズはArt Line の
30mm/f1.4 DC HSMにリニューアルされている。
さらに2016年にはミラーレス機用の30mm/f1.4 DC DN
が追加されているが、これは一眼レフには装着できない。
そして、何故かこちらは、Art Lineではなく
Contemporary Lineに属している。
(注:2013年より、SIGMAはユーザーの用途別に3つの
レンズラインナップを構成している。Art Lineは大口径
で高描写力で単焦点が大半。Contemporaryは現代的な
小型軽量レンズのカテゴリ-だが、ズームレンズが多い)
それそれのバージョンのレンズ構成や最短撮影距離等の
スペック、サイズ感や仕上げは、ずいぶんと異なる。
まあ各々全く別のレンズと考えておくのが良いであろう。
今回紹介するのは、最初期型の通称「EX型」である。
さて、本レンズ発売直前のカメラ市場であるが、旧来の銀塩
一眼レフから、デジタル一眼レフへの移行が急速に進んでいた。
特に2004年は各社から一般層でも購入可能な安価な価格帯の
デジタル一眼レフが出揃った時代である。(デジタル一眼レフ
クラッシックス第2回~第5回記事参照)
ところが、カメラはデジタル化したのだが、ユーザーの心情は
まだデジタル化されていない。デジタルの世界はアナログとは
根本的に原理が異なるが、それを理解できる人は、ほんのごく
一部のユーザーでしかなく、様々な誤解が世の中は蔓延していた。
まあそれはやむを得ないであろう、一般層はもとより、マニア層、
ハイアマチュア層、職業写真層、評論家層、そしてメーカーですら
アナログからデジタルの大変革に、そう簡単に対応できる訳では
無かったのだ。
そのころ良く言われた事は「フィルムの常識はデジタルの非常識」
という言葉(スローガン?)だ。これはまあその通りではあるが、
具体性が無い話なので何をどうすれば良いのか?は、わからない。
結局、個々のデジタル知識は、順次各ユーザー側が学んでいくしか
無い訳だ。
誤解には、画素数至上主義等はもとより、トリミング禁止だとか
レタッチ編集は邪道だとか、ありとあらゆる「迷信」がその時代に
蔓延していたのだ。その中で、本レンズに係わる事情としては
「APS-C機では、旧来の標準レンズが、皆、”望遠レンズ”に
なってしまう」という誤解であった。
これは単純に、35mm判フィルムとAPS-C型撮像素子のサイズ
の差から来る画角の変化であると、現代のカメラユーザーなら、
誰でもこの事は理解している。
しかし当時は違った。
「オレは昔から、ずっと標準レンズを使ってきたので、とても
使い易いのだが、それが全て望遠レンズになったら非常に困る、
デジタルの標準レンズって、いったい何処に売っているのだ?」
・・と変な誤解を持つ中級ユーザー等が後を絶たなかった。
その頃、一部のデジタルの理解が早いマニア層やメディア等から、
「デジタルでは1.5倍されているから、今までの35mmレンズが
標準レンズになるのだぞ」という話が広まる。
それは単に画角の話なので、ある意味どうでも良い原理だが、
これを真に受け、マニア層、中古流通業者、投機層などが、
2003年~2005年頃にかけ、銀塩時代のAF35mm級レンズを
買い漁(あさ)った。
NIKON AiAF35/2、CANON EF35/2、PENTAX FA35/2AL、
同FA31/1.8Limited、MINOLTA AF35/1.4、同AF35/2・・
これらは、銀塩時代であっても、元々あまり流通の多いレンズ
ではなかったし、すでに生産中止になっているレンズもあった。
中古市場からは瞬時にこれらの35mmレンズは消滅し、たまに
出てきても、とんでもなく高価なプレミアム価格となっていた。
(まあ、高く売る為に、品薄感を演出するのだから当然だろう。
近年であれば、(チケット等の)「転売禁止法」が一般商品に
まで拡張されたら、ひっかかってもおかしくない話ではあるが、
この場合、不条理な迄に高価となったモノを、欲しがる側にも
問題点がある。
何故、それが投機的な高額相場である事を見抜けないのだろう?
生活必需品では無いのだから、誰も買わずに、放置しておけば、
必然的に相場は下がる筈だ)
で、AFの35mmレンズが入手困難なので、MFの35mmレンズ
にまで購入(および買占め)の傾向が進んだ。
当然だが、ほとんどのMF35mmレンズは、デジタル機では
使用不可か使用困難であったにもかかわらずだ・・
(例えば、NIKON D1系/D2系+Ai NIKKORや、PENTAX
*istD/Ds +M42アダプター+SMC Takumar等の、限られた
組み合わせしか、銀塩MF(35mm)レンズを一般的な手法では
使えない。他の組み合わせは、それを無理に使う場合には、
高度な機材知識が必要か、あるいは、全く装着不可である)
まあつまり、皆、何もわからずに、MFの35mmレンズを購入
(または買占め)していた訳だ。
そんな状況の中、SIGMAが本レンズを発売したのだ。
「(APS-C)デジタル機で標準画角となる30mmの焦点距離、
しかも銀塩用の35mmレンズでは稀であった F1.4の開放F値、
換算画角45mm/F1.4 これぞ、デジタル時代の標準レンズだ!」
・・という感じで、本レンズは大きな期待を持って一般層に
受け入れられたのだが、すぐにマニア等から「ボケが汚い」
とかいった不満の声が聞こえるようになった。
![_c0032138_18133838.jpg]()
私としても目に付く不満点がいくつかあった。
・最短撮影距離が40cmと、「焦点距離10倍則」より長く、
あまり寄れない。
・ボケ質破綻が出やすい。
・ピントリングの回転角が極めて狭く、MF時に精密なピント
合わせが出来ない(注:大口径なので、なおさら問題である)
・無限回転式ヘリコイド(ただし距離指標有りのハイブリッド式)
であるので、最短や無限での停止感触が無い。上記の回転角が
狭い事とあいまって、MF操作性がかなり悪い。
・・と言う事で、上記の弱点は、本レンズの大口径という
特性からすると重欠点に近いものがある。
本レンズは、その後、あまり使用する事が無くなってしまった。
ただまあ、本レンズの登場により、上記の「35mmレンズの
買占めと投機」の世情は、ほど無くして終息している。
そういう意味では、本レンズは市場における「救世主」で
あったように、今では私は解釈している。
(まあ、皆がデジタルの仕組みを理解し、さらには、画角の
変化にも慣れた、というのも35mm投機終息の理由であろう)
なお、2013年からのArt型に関しては最短撮影距離は30cmに
まで短縮されているのだが、あいにく所有していないので
他の弱点も改善されているかどうかは不明だ。
(なんだか「ケチがついた」ので、新型は購入したく無い、
というのが本音の所だ)
---
では、次のレンズ。
![_c0032138_18135370.jpg]()
レンズ購入価格:12,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-01(APS-C機)
レンズ・マニアックス第6回、第28回記事等で紹介の、
2012年発売のAPS-C機用超薄型単焦点AF準標準レンズ。
重量は52gと、一眼レフ用交換レンズとしては、MFレンズも
含めて最軽量だ。
PENTAXではこれを「(パンケーキより薄い)ビスケットレンズ」
と呼んでいる。
![_c0032138_18135363.jpg]()
ので、今回は大幅に割愛しよう。
どちらかと言えば、デザイン性が優先のレンズであり、あまり
感動的と言えるような高描写力は持たないレンズだ。
さて、40mmレンズであるからAPS-C機では60mm相当の画角
となり、標準レンズと言うには、やや長目に感じるかも知れない。
ここで、前述の「標準レンズ=人間の視野角」説に係わる話を
さらに詳しく分析してみよう。
まず、文献によれば、人間の視野は、方向によって異なるが、
片目では約60度~約90度、両眼では左右120度と言われている。
まあ一眼レフは片目相当であるので、これをフルサイズ機の
対角線画角とするならば、その単眼レンズの焦点距離は、
およそ35mm~21mmくらいだ(!)
PENTAXの言う43mmでも、ライカの言う50mmレンズでも、
どっちでも人間の視野角に対しては狭すぎる。
まあ、カメラ(光学)分野は、かなり古くから発達して
きた為、生理学的な研究の進展よりも、フライング気味で
色々と定義や常識・定説が生まれたのかも知れない。
後年、生理学的な研究が進むと、カメラにおける、
「標準レンズとは、人間の目の視野と同等である」という
ルール(常識)が誤っている事が明白になってきた。
しかし、すでに十分すぎる程、カメラ界に、その「常識」は
広まっていた。これを擁護する為、後年、誰かが新しく言い
出した事が「標準レンズは人間が”凝視”した画角と等しい」
という、新たな仮説(弁明?)であった。
だが、これもいかにも曖昧な話だ。「凝視した画角」など、
恐らくは状況により、まちまちだろう。人間がどんな物体を
どの距離で見るかなど、厳密な定義は決めようが無いと
思われるからだ。
結局、「標準レンズ=人間の画角」説は、全く根拠の無い
ものなってしまった為、今時では、どのような写真の
教科書や参考書や資料を見ても書かれていないであろう。
もし、そうした事が書いてあったら、それは「古い内容」
であるから、無視するのは当然で、その資料等における、
それ以外の項目すら、全体的な信憑性が低まってしまう。
・・と言う事で、結論としては、「標準レンズ」なんて
別に何mmでも良いと思う。基本的には、どんな被写体を
どのように撮るかで、必要なレンズの画角は決まるし、
そうやって色々な被写体状況に応じてレンズを交換出来る
事自体が一眼レフの最大の特徴だ。
1本の単焦点レンズをつけたままで、どんな被写体にも
対応できる筈も無いし、そういう万能単焦点レンズは存在
しないのだ。(だからまあ、ズームレンズが発展した)
ただ、今時の中上級者であれば、単焦点を1本だけつけても、
そのレンズに見合う被写体を選択的に探す、という技術は
身につけているとは思うが・・![_c0032138_18135391.jpg]()
前記事で紹介した銀塩M40/2.8の子孫のようなレンズである。
レンズ構成は両者同じ4群5枚、ただしM型より30数年も後に
発売されたレンズであるから、新しい設計・製造技術を
色々と導入している。
1980年代からのAF化にM40/2.8は(薄すぎて)対応できな
かったが、1990年代末の薄型FA43/1.9(本記事で紹介)を
経て、このDA40/2.8XSでは、超薄型ながら難なくAFに対応。
最短撮影距離もM40/2.8の60cmからDA40/2.8系では
40cmまで短縮されている。同じレンズ構成でもパワー配置
(レンズの曲率)等の設計技法が異なるという事であろう。
しかし、描写力はスペシャルという訳でもなく、MF操作性
も良く無いので、近接で背景をボカす技法は使い難い。
あくまでデザイン優先で、「格好良いレンズ」という事だ。
なお銀色バージョンは限定版であり、若干入手性は悪い。
また、フィルター径はφ27mmと特殊な小径の為、
保護フィルターやフード等の入手性も良く無いであろう。
---
さらに、次のレンズ。
![_c0032138_18140583.jpg]()
レンズ購入価格:36,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df(フルサイズ機)
レンズ・マニアックス第7回記事、
特殊レンズ超マニアックス第8回記事等で紹介の、
2015年発売のフルサイズ対応単焦点AF標準レンズ。
![_c0032138_18140581.jpg]()
かなり大柄(フィルター径φ67mm)のレンズである。
この点は、描写力を優先とした設計の為に、レンズが大型化
したのだろう、と好意的に解釈しておこう。
(注:この時代より、TAMRONは単焦点レンズのフィルター
径をφ67mmで揃える戦略をスタートした、その一環での
大型化の措置だったのかも知れない。ただし、フィルター径
の標準化は、ユーザーメリットも大きく、好ましい傾向だ)
事実、本レンズの描写力はかなり良く、一般的な不満点は
まず無いと思われる。そして、開放F1.8に抑えている点も
描写力優先の印象を強めるスペックだ。
本シリーズでさんざん書いて来たように、銀塩時代の古くから
開放F1.4級の大口径標準レンズよりも、開放F1.8級の小口径
標準レンズの方が、たいてい描写力が優れているのだ。
ただ、世間一般的には、そういう感覚は無いであろう。
初級中級層の殆どは、同じ焦点距離のレンズがあれば、
F1.4級レンズの方が、全ての点で高性能(高描写力)であると
勘違いしてしまう。
初「だって、F1.4の方が値段も高いし、良いレンズに決まって
いるだろう?」
・・と言う論理になってしまい、疑う事も知らない訳だ。
で、その結果、本レンズは不人気である。定価は9万円+税と
このスペックにしては、やや高価に感じるのも、その不人気
の原因の1つであろう。
上級層やマニア層ならば、本レンズが非常に高い描写力を
持つ事に気づくかも知れないが、そういうユーザー層では、
標準レンズの2~3本は持っていて当然なので、あえて
本レンズを買い増ししようとは、まず思わないであろう。
つまり、初級中級層には、「スペックが弱い」と思われて、
上級層やマニア層には、あまり必要性が無いレンズとなる。
その事により、本レンズはあまり売れず、発売2~3年後には、
量販店でも、およそ半値の新品価格で売られるようになり、
中古市場においても、量販店等の新品価格よりも若干割安な
「新古品」が多数流通していた。
(新古品とは、量販店などでの展示品入れ替えとか、モデル
チェンジ前の旧型在庫処分や、勿論売れ残った場合もあるだろう
が、そういう場合に、未販売状態での新品同様品であっても、
中古品扱いとして、中古市場で流通販売する事である)
この状態になると、一般的な売買による中古品は、新古品より
値段を下げざるを得ない。だから本レンズの中古購入価格は、
およそ36,000円(税込)と、比較的安価であり、性能(描写力)
が高い事とあいまって、非常にコスパの良い買い物となった
![_c0032138_18140676.jpg]()
総合的な評価からはそうなる。
勿論、本シリーズ最強50mm編での決勝進出は確定的であり、
上位の順位も狙える強豪レンズだ。
---
では、今回ラストのレンズ。
![_c0032138_18141596.jpg]()
レンズ購入価格:11,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)
レンズ・マニアックス第10回、第27記事で紹介の、
2012年発売の、フルサイズ対応、単焦点AF薄型準標準
(エントリー)レンズ。
![_c0032138_18142024.jpg]()
為に割愛する。
弱点だけ簡潔に書いておくと、STM(ステッピングモーター)
内蔵の本レンズは、カメラ側から電源供給を行わないと
絞り制御はおろか、MFでのピントリングすら動かない。
このため、EOS機、ほぼ専用のレンズとなってしまう。
他社機で使う場合には、一般的なEFレンズ用マウント
アダプターでは無理で、高価な電子アダプターを購入する
必要があるが、そうするくらいならば、EOS機を使った方が
手っ取り早い。EOSフタケタD機あたりの、古いものだったら
1万円台からでも中古で購入でき、性能的にも殆ど不満は
無いだろうからだ。
あるいは他機では、EOS M/EOS Rシリーズのミラーレス機
に純正マウントアダプター経由で用いる事が出来るが、
これも下手をすると、マウントアダプターの価格でEOSの
旧型一眼レフが買えてしまう。
![_c0032138_18142099.jpg]()
しては最軽量である、EOSフルサイズ最軽量機のEOS 6Dと、
CANON EFレンズ(フルサイズ一眼用)最軽量(130g)の
本レンズだから必然的にそうなるのだが、実は、最軽量システム
には、もう1本別のEFレンズがあり、それはEF50mm/f1.8Ⅱも
また130gなのだ。
そのⅡ型はキヤノン党の初級層に神格化された超ロングセラー
(25年間)の製品なので所有している人は多いであろうから、
本EF40/2.8STMとの組み合わせでなくても、最軽量システムを
構築できる。
(注:EF50mm/f1.8Ⅱは未所有だが、EF50mm/f1.8Ⅰを
本シリーズ第2回記事で紹介している。また、EF50/1.8Ⅱ
のフルコピー品である「YONGNUO YN50/1.8」は、レンズ
マニアックス第20回記事で紹介済みだ)
![_c0032138_18142105.jpg]()
期待するのではなく、スタイリッシュな使用法(デザイン優先)
を意識するのが良いであろう。
なお、キヤノンは銀塩・デジタル時代を通じて、一眼レフ用
のパンケーキレンズは発売していなかった為、本レンズは
初のキヤノン製パンケーキである。
(他にも、ミラーレス機専用 EF-M 22mm/f2 STMが同年
2012年に発売された)
そういう意味では「歴史的価値」は高く、STMのMFの弱点を
容認しても購入に踏み切ったレンズである。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Nブロック「AF焦点距離違い」の記事は終了だ。
次回の本シリーズ記事は、予選O(オー)ブロック
「MFその他」編となる予定だ。
開放F値等によるカテゴリー別で予選を行い、最後に
決勝で最強の50mmレンズを決定するというシリーズ記事。
今回は、予選Nブロックとして「AF焦点距離違い」の
レンズを5本紹介(対戦)する。
なお「AF焦点距離違い」とは、レンズの実焦点距離
又はAPS-C機専用レンズでのフルサイズ換算焦点距離が
ぴったり50mmにはならず、おおむね30mm~45mm
(換算で45mm~60mm程度)の焦点距離(画角)となる
レンズ群を指す、少々ややこしいが、まあつまり中途半端な
焦点距離のAF標準レンズ群を集めたカテゴリーだ。
そもそも50mm=標準のルールを定めたのは、戦前1930
年代のライカ(ライツ社)であり、それは単に中途半端な
覚え難い数字を嫌っての措置だとも思われ、50mmを標準
とする、技術的あるいは生理学的な根拠は殆ど無いし、
そして、ずいぶんと古い時代のルールでもある。
---
さて、まずは今回最初のレンズ。

レンズ購入価格:40,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第1回、第64回記事、
特殊レンズ超マニアックス第9回記事等で紹介の、
1990年代後半の銀塩・フルサイズ対応AF標準レンズ。

これは(35mm判)フィルムの対角線長であり、PENTAXでは、
「これが本来の標準レンズである」という解釈をしていた。
しかし、ちょっと前述したような、ライカの「50mm=標準」
の古いルールに、ただ反発していただけかも知れない。
そして、50mmでも43mmでも、どちらでも標準レンズとは
言い難い点もある。すなわち「標準レンズ=人間の視野」
として考えるのであれば、人間の視野はもっとずっと
広いからだ。そしてフィルムの対角線長を焦点距離とする
原理的な意味(解釈)も余り無い。
(この話は、もう少し詳細を後述する)
さて、そういう曰くがあるものの、本FA43/1.9の
描写力そのものは、全く申し分の無い高性能レンズだ。
殆ど弱点は無い。銀塩時代であれば、恐らくは、
PENTAXの(35mm判)交換レンズ中、5本の指に入る描写力
と言えたであろう。
ただ、現代の視点からすると、さすがに本レンズは20年
以上の前の設計と古く、解像感等に若干の不満があると思う。
(しかし、ボケ質は良好で、逆光耐性も強いので、銀塩機
あるいは低画素デジタル機で使う上では何ら不満は無いで
あろう)
それから、絞り羽根が8枚と偶数構成で、被写体状況に
よっては、ボケ形状が乱れる場合がある。
ただし、これはあくまで「ボケ形状」だ、本ブログで言う
「ボケ質」とは直接は関係が無い。
余談だが、様々なレンズ製品において、「円形絞り」を
採用する事で「ボケ味が良くなる」という記述があるが、
私に言わせれば、これは限りなく「グレーな」表現である。
まず「ボケ味」という用語が良く無い、これでは何を示して
るのか、具体的な意味が不明だ。つまり、それを読む人の
それぞれで異なる解釈が出来てしまい、その事が、もし
消費者層の購買動機につながるならば、あまり公正な
販売のやりかたとは言い難いからだ。
本ブログでは、「ボケ味」の用語は非推奨である、
その代わりに以下のような用語群を使う。
ボケ量:背景等を、どれくらいの量(面積、比率、深さ)
でボケすか、これは「被写界深度(外)」と、
ほぼ等価の概念だ。
ボケ質:被写界深度外の部分において、ボケの画像的な
品質が良好か否か。これが悪いケースには、
一般に言われる「二線ボケ」「ぐるぐるボケ」等が
あるが、そうした言葉だけでは表現できないような
様々な品質劣化があり、本ブログでは、その状況を
総称して「ボケ質破綻」(が起こる)と言う。
ボケ形状:本ブログでも滅多に使わない用語であるが、
例えば、夜景における周辺ボケがレモン形状と
なるケース(これは「口径食」が原因だ)や、
木漏れ日のボケに絞り羽根の形状が出てしまう事等。
なお、後者はボケ以外にも、ゴーストを意図的に
あるいは意図せず発生した場合にも、絞りの形状が
出てしまうケースがある。
世間一般には、こうした明確な定義が存在していない為、
あえて「ボケ味」という曖昧な表現をメーカー等でも
使っているのかも知れないが、よくよく注意してみると
その「ボケ味の用語が曖昧である」事を逆用して、製品の
性能優位性を誇張するような、グレーな表現が見られる。
具体的には、「円形絞りを採用しているからボケ味が良い」
であり、これは正しくは「円形絞りにより、被写体条件や
絞り値に応じて、ボケ形状が良くなる可能性がある」に
過ぎない。
つまり、「ボケ量」や「ボケ質」には無関係な話だ。
そして、どんなレンズでも開放で使えば完全な円形絞りだ。
(=近年のビギナー層の用語では「玉ボケ」の状態。
ただし、中上級マニア層の用語では輪郭線の出る「円形ボケ」
状態のみを指して「玉ボケ」、「シャボン玉ボケ」あるいは
「バブルボケ」と呼ぶ。このあたりも定義が曖昧な俗語だ)
あるいは、ビギナー向けのカメラの機能で「ボケ味
コントロール」という設定もある。これを使うと、ボケ質
が見るみる良くなる・・ 等と言う事は勿論一切なく(汗)
これは、何と、絞り優先機能と同じであり、単に絞り値を
調整するだけのものであったりする。
この機能で変化するのは単に「被写界深度(≒ボケ量)」
だけであるし、おまけに、そうしたビギナー向けカメラには、
85mm/F1.4等といった、大口径でボケ量のコントロールの
自由度が高いレンズを装着する筈もない。(→有り得ない)
普通は、被写界深度が深い、つまり開放F値が暗くて、かつ
最短撮影距離も長い標準ズーム等を装着するので、その状態
では、絞り値をいくらあれこれと変更しても殆ど効果も無い。
初級者層へのカメラ原理の理解を促進させる名目もあった
のかも知れないが、「実態」とはちょっと連動していない。
むしろ「ボケ味コントロール」等という曖昧な表現をしたら
超ビギナーユーザーから「何の変化も起こらない」という
クレームに繋がってしまうのではなかろうか?
まあ結局、こういう表現の機能があったのは、限られた
時代(2010年前後)での話であり、今時のカメラには、
こういう曖昧な、あえて言えば、「グレーな」機能名称は、
殆ど用いられていないと思う。

まあ前述のように、普通の利用法では特に不満も出る事も
無い高性能レンズだ。あえて欠点を言えば、古いレンズの
割りに新品販売も継続されていて、価格が少々高価な事と、
中古相場も、ずっと殆ど下がらない事だ。
(PENTAXが、HOYA、RICOHと親会社が変わって来た度に
本レンズも少しづつ値上げされている。そして中古相場は
その定価にも若干連動するからだ)
価格の面からは、ぶっちゃけ言えば本レンズを4万円弱で
中古購入するのは、現代の感覚からはコスパが若干悪い。
現代において4万円近くも出すのであれば、より高い
描写力の近代標準レンズの内の何種類かが中古で買える
価格帯(中古相場)である。
---
では、次のレンズ。

レンズ購入価格:27,000円(中古)
使用カメラ:NIKON D70(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第75回記事で紹介の、
2005年発売の、APS-C機専用AF大口径準標準
(標準画角)レンズ。
今回は発売当時の雰囲気を味わう為に、前年2004年に
発売のNIKON D70に装着して使ってみよう。

続けたが、2013年に、このレンズはArt Line の
30mm/f1.4 DC HSMにリニューアルされている。
さらに2016年にはミラーレス機用の30mm/f1.4 DC DN
が追加されているが、これは一眼レフには装着できない。
そして、何故かこちらは、Art Lineではなく
Contemporary Lineに属している。
(注:2013年より、SIGMAはユーザーの用途別に3つの
レンズラインナップを構成している。Art Lineは大口径
で高描写力で単焦点が大半。Contemporaryは現代的な
小型軽量レンズのカテゴリ-だが、ズームレンズが多い)
それそれのバージョンのレンズ構成や最短撮影距離等の
スペック、サイズ感や仕上げは、ずいぶんと異なる。
まあ各々全く別のレンズと考えておくのが良いであろう。
今回紹介するのは、最初期型の通称「EX型」である。
さて、本レンズ発売直前のカメラ市場であるが、旧来の銀塩
一眼レフから、デジタル一眼レフへの移行が急速に進んでいた。
特に2004年は各社から一般層でも購入可能な安価な価格帯の
デジタル一眼レフが出揃った時代である。(デジタル一眼レフ
クラッシックス第2回~第5回記事参照)
ところが、カメラはデジタル化したのだが、ユーザーの心情は
まだデジタル化されていない。デジタルの世界はアナログとは
根本的に原理が異なるが、それを理解できる人は、ほんのごく
一部のユーザーでしかなく、様々な誤解が世の中は蔓延していた。
まあそれはやむを得ないであろう、一般層はもとより、マニア層、
ハイアマチュア層、職業写真層、評論家層、そしてメーカーですら
アナログからデジタルの大変革に、そう簡単に対応できる訳では
無かったのだ。
そのころ良く言われた事は「フィルムの常識はデジタルの非常識」
という言葉(スローガン?)だ。これはまあその通りではあるが、
具体性が無い話なので何をどうすれば良いのか?は、わからない。
結局、個々のデジタル知識は、順次各ユーザー側が学んでいくしか
無い訳だ。
誤解には、画素数至上主義等はもとより、トリミング禁止だとか
レタッチ編集は邪道だとか、ありとあらゆる「迷信」がその時代に
蔓延していたのだ。その中で、本レンズに係わる事情としては
「APS-C機では、旧来の標準レンズが、皆、”望遠レンズ”に
なってしまう」という誤解であった。
これは単純に、35mm判フィルムとAPS-C型撮像素子のサイズ
の差から来る画角の変化であると、現代のカメラユーザーなら、
誰でもこの事は理解している。
しかし当時は違った。
「オレは昔から、ずっと標準レンズを使ってきたので、とても
使い易いのだが、それが全て望遠レンズになったら非常に困る、
デジタルの標準レンズって、いったい何処に売っているのだ?」
・・と変な誤解を持つ中級ユーザー等が後を絶たなかった。
その頃、一部のデジタルの理解が早いマニア層やメディア等から、
「デジタルでは1.5倍されているから、今までの35mmレンズが
標準レンズになるのだぞ」という話が広まる。
それは単に画角の話なので、ある意味どうでも良い原理だが、
これを真に受け、マニア層、中古流通業者、投機層などが、
2003年~2005年頃にかけ、銀塩時代のAF35mm級レンズを
買い漁(あさ)った。
NIKON AiAF35/2、CANON EF35/2、PENTAX FA35/2AL、
同FA31/1.8Limited、MINOLTA AF35/1.4、同AF35/2・・
これらは、銀塩時代であっても、元々あまり流通の多いレンズ
ではなかったし、すでに生産中止になっているレンズもあった。
中古市場からは瞬時にこれらの35mmレンズは消滅し、たまに
出てきても、とんでもなく高価なプレミアム価格となっていた。
(まあ、高く売る為に、品薄感を演出するのだから当然だろう。
近年であれば、(チケット等の)「転売禁止法」が一般商品に
まで拡張されたら、ひっかかってもおかしくない話ではあるが、
この場合、不条理な迄に高価となったモノを、欲しがる側にも
問題点がある。
何故、それが投機的な高額相場である事を見抜けないのだろう?
生活必需品では無いのだから、誰も買わずに、放置しておけば、
必然的に相場は下がる筈だ)
で、AFの35mmレンズが入手困難なので、MFの35mmレンズ
にまで購入(および買占め)の傾向が進んだ。
当然だが、ほとんどのMF35mmレンズは、デジタル機では
使用不可か使用困難であったにもかかわらずだ・・
(例えば、NIKON D1系/D2系+Ai NIKKORや、PENTAX
*istD/Ds +M42アダプター+SMC Takumar等の、限られた
組み合わせしか、銀塩MF(35mm)レンズを一般的な手法では
使えない。他の組み合わせは、それを無理に使う場合には、
高度な機材知識が必要か、あるいは、全く装着不可である)
まあつまり、皆、何もわからずに、MFの35mmレンズを購入
(または買占め)していた訳だ。
そんな状況の中、SIGMAが本レンズを発売したのだ。
「(APS-C)デジタル機で標準画角となる30mmの焦点距離、
しかも銀塩用の35mmレンズでは稀であった F1.4の開放F値、
換算画角45mm/F1.4 これぞ、デジタル時代の標準レンズだ!」
・・という感じで、本レンズは大きな期待を持って一般層に
受け入れられたのだが、すぐにマニア等から「ボケが汚い」
とかいった不満の声が聞こえるようになった。

私としても目に付く不満点がいくつかあった。
・最短撮影距離が40cmと、「焦点距離10倍則」より長く、
あまり寄れない。
・ボケ質破綻が出やすい。
・ピントリングの回転角が極めて狭く、MF時に精密なピント
合わせが出来ない(注:大口径なので、なおさら問題である)
・無限回転式ヘリコイド(ただし距離指標有りのハイブリッド式)
であるので、最短や無限での停止感触が無い。上記の回転角が
狭い事とあいまって、MF操作性がかなり悪い。
・・と言う事で、上記の弱点は、本レンズの大口径という
特性からすると重欠点に近いものがある。
本レンズは、その後、あまり使用する事が無くなってしまった。
ただまあ、本レンズの登場により、上記の「35mmレンズの
買占めと投機」の世情は、ほど無くして終息している。
そういう意味では、本レンズは市場における「救世主」で
あったように、今では私は解釈している。
(まあ、皆がデジタルの仕組みを理解し、さらには、画角の
変化にも慣れた、というのも35mm投機終息の理由であろう)
なお、2013年からのArt型に関しては最短撮影距離は30cmに
まで短縮されているのだが、あいにく所有していないので
他の弱点も改善されているかどうかは不明だ。
(なんだか「ケチがついた」ので、新型は購入したく無い、
というのが本音の所だ)
---
では、次のレンズ。

レンズ購入価格:12,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-01(APS-C機)
レンズ・マニアックス第6回、第28回記事等で紹介の、
2012年発売のAPS-C機用超薄型単焦点AF準標準レンズ。
重量は52gと、一眼レフ用交換レンズとしては、MFレンズも
含めて最軽量だ。
PENTAXではこれを「(パンケーキより薄い)ビスケットレンズ」
と呼んでいる。

ので、今回は大幅に割愛しよう。
どちらかと言えば、デザイン性が優先のレンズであり、あまり
感動的と言えるような高描写力は持たないレンズだ。
さて、40mmレンズであるからAPS-C機では60mm相当の画角
となり、標準レンズと言うには、やや長目に感じるかも知れない。
ここで、前述の「標準レンズ=人間の視野角」説に係わる話を
さらに詳しく分析してみよう。
まず、文献によれば、人間の視野は、方向によって異なるが、
片目では約60度~約90度、両眼では左右120度と言われている。
まあ一眼レフは片目相当であるので、これをフルサイズ機の
対角線画角とするならば、その単眼レンズの焦点距離は、
およそ35mm~21mmくらいだ(!)
PENTAXの言う43mmでも、ライカの言う50mmレンズでも、
どっちでも人間の視野角に対しては狭すぎる。
まあ、カメラ(光学)分野は、かなり古くから発達して
きた為、生理学的な研究の進展よりも、フライング気味で
色々と定義や常識・定説が生まれたのかも知れない。
後年、生理学的な研究が進むと、カメラにおける、
「標準レンズとは、人間の目の視野と同等である」という
ルール(常識)が誤っている事が明白になってきた。
しかし、すでに十分すぎる程、カメラ界に、その「常識」は
広まっていた。これを擁護する為、後年、誰かが新しく言い
出した事が「標準レンズは人間が”凝視”した画角と等しい」
という、新たな仮説(弁明?)であった。
だが、これもいかにも曖昧な話だ。「凝視した画角」など、
恐らくは状況により、まちまちだろう。人間がどんな物体を
どの距離で見るかなど、厳密な定義は決めようが無いと
思われるからだ。
結局、「標準レンズ=人間の画角」説は、全く根拠の無い
ものなってしまった為、今時では、どのような写真の
教科書や参考書や資料を見ても書かれていないであろう。
もし、そうした事が書いてあったら、それは「古い内容」
であるから、無視するのは当然で、その資料等における、
それ以外の項目すら、全体的な信憑性が低まってしまう。
・・と言う事で、結論としては、「標準レンズ」なんて
別に何mmでも良いと思う。基本的には、どんな被写体を
どのように撮るかで、必要なレンズの画角は決まるし、
そうやって色々な被写体状況に応じてレンズを交換出来る
事自体が一眼レフの最大の特徴だ。
1本の単焦点レンズをつけたままで、どんな被写体にも
対応できる筈も無いし、そういう万能単焦点レンズは存在
しないのだ。(だからまあ、ズームレンズが発展した)
ただ、今時の中上級者であれば、単焦点を1本だけつけても、
そのレンズに見合う被写体を選択的に探す、という技術は
身につけているとは思うが・・
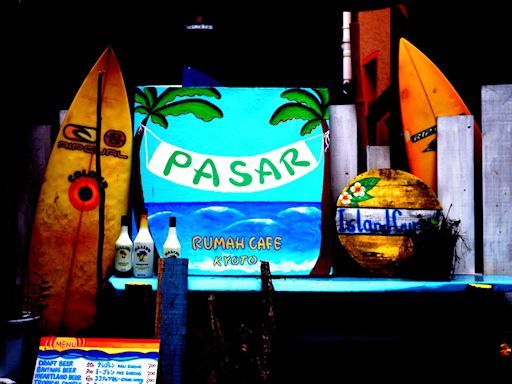
前記事で紹介した銀塩M40/2.8の子孫のようなレンズである。
レンズ構成は両者同じ4群5枚、ただしM型より30数年も後に
発売されたレンズであるから、新しい設計・製造技術を
色々と導入している。
1980年代からのAF化にM40/2.8は(薄すぎて)対応できな
かったが、1990年代末の薄型FA43/1.9(本記事で紹介)を
経て、このDA40/2.8XSでは、超薄型ながら難なくAFに対応。
最短撮影距離もM40/2.8の60cmからDA40/2.8系では
40cmまで短縮されている。同じレンズ構成でもパワー配置
(レンズの曲率)等の設計技法が異なるという事であろう。
しかし、描写力はスペシャルという訳でもなく、MF操作性
も良く無いので、近接で背景をボカす技法は使い難い。
あくまでデザイン優先で、「格好良いレンズ」という事だ。
なお銀色バージョンは限定版であり、若干入手性は悪い。
また、フィルター径はφ27mmと特殊な小径の為、
保護フィルターやフード等の入手性も良く無いであろう。
---
さらに、次のレンズ。

レンズ購入価格:36,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df(フルサイズ機)
レンズ・マニアックス第7回記事、
特殊レンズ超マニアックス第8回記事等で紹介の、
2015年発売のフルサイズ対応単焦点AF標準レンズ。

かなり大柄(フィルター径φ67mm)のレンズである。
この点は、描写力を優先とした設計の為に、レンズが大型化
したのだろう、と好意的に解釈しておこう。
(注:この時代より、TAMRONは単焦点レンズのフィルター
径をφ67mmで揃える戦略をスタートした、その一環での
大型化の措置だったのかも知れない。ただし、フィルター径
の標準化は、ユーザーメリットも大きく、好ましい傾向だ)
事実、本レンズの描写力はかなり良く、一般的な不満点は
まず無いと思われる。そして、開放F1.8に抑えている点も
描写力優先の印象を強めるスペックだ。
本シリーズでさんざん書いて来たように、銀塩時代の古くから
開放F1.4級の大口径標準レンズよりも、開放F1.8級の小口径
標準レンズの方が、たいてい描写力が優れているのだ。
ただ、世間一般的には、そういう感覚は無いであろう。
初級中級層の殆どは、同じ焦点距離のレンズがあれば、
F1.4級レンズの方が、全ての点で高性能(高描写力)であると
勘違いしてしまう。
初「だって、F1.4の方が値段も高いし、良いレンズに決まって
いるだろう?」
・・と言う論理になってしまい、疑う事も知らない訳だ。
で、その結果、本レンズは不人気である。定価は9万円+税と
このスペックにしては、やや高価に感じるのも、その不人気
の原因の1つであろう。
上級層やマニア層ならば、本レンズが非常に高い描写力を
持つ事に気づくかも知れないが、そういうユーザー層では、
標準レンズの2~3本は持っていて当然なので、あえて
本レンズを買い増ししようとは、まず思わないであろう。
つまり、初級中級層には、「スペックが弱い」と思われて、
上級層やマニア層には、あまり必要性が無いレンズとなる。
その事により、本レンズはあまり売れず、発売2~3年後には、
量販店でも、およそ半値の新品価格で売られるようになり、
中古市場においても、量販店等の新品価格よりも若干割安な
「新古品」が多数流通していた。
(新古品とは、量販店などでの展示品入れ替えとか、モデル
チェンジ前の旧型在庫処分や、勿論売れ残った場合もあるだろう
が、そういう場合に、未販売状態での新品同様品であっても、
中古品扱いとして、中古市場で流通販売する事である)
この状態になると、一般的な売買による中古品は、新古品より
値段を下げざるを得ない。だから本レンズの中古購入価格は、
およそ36,000円(税込)と、比較的安価であり、性能(描写力)
が高い事とあいまって、非常にコスパの良い買い物となった

総合的な評価からはそうなる。
勿論、本シリーズ最強50mm編での決勝進出は確定的であり、
上位の順位も狙える強豪レンズだ。
---
では、今回ラストのレンズ。

レンズ購入価格:11,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)
レンズ・マニアックス第10回、第27記事で紹介の、
2012年発売の、フルサイズ対応、単焦点AF薄型準標準
(エントリー)レンズ。

為に割愛する。
弱点だけ簡潔に書いておくと、STM(ステッピングモーター)
内蔵の本レンズは、カメラ側から電源供給を行わないと
絞り制御はおろか、MFでのピントリングすら動かない。
このため、EOS機、ほぼ専用のレンズとなってしまう。
他社機で使う場合には、一般的なEFレンズ用マウント
アダプターでは無理で、高価な電子アダプターを購入する
必要があるが、そうするくらいならば、EOS機を使った方が
手っ取り早い。EOSフタケタD機あたりの、古いものだったら
1万円台からでも中古で購入でき、性能的にも殆ど不満は
無いだろうからだ。
あるいは他機では、EOS M/EOS Rシリーズのミラーレス機
に純正マウントアダプター経由で用いる事が出来るが、
これも下手をすると、マウントアダプターの価格でEOSの
旧型一眼レフが買えてしまう。

しては最軽量である、EOSフルサイズ最軽量機のEOS 6Dと、
CANON EFレンズ(フルサイズ一眼用)最軽量(130g)の
本レンズだから必然的にそうなるのだが、実は、最軽量システム
には、もう1本別のEFレンズがあり、それはEF50mm/f1.8Ⅱも
また130gなのだ。
そのⅡ型はキヤノン党の初級層に神格化された超ロングセラー
(25年間)の製品なので所有している人は多いであろうから、
本EF40/2.8STMとの組み合わせでなくても、最軽量システムを
構築できる。
(注:EF50mm/f1.8Ⅱは未所有だが、EF50mm/f1.8Ⅰを
本シリーズ第2回記事で紹介している。また、EF50/1.8Ⅱ
のフルコピー品である「YONGNUO YN50/1.8」は、レンズ
マニアックス第20回記事で紹介済みだ)

期待するのではなく、スタイリッシュな使用法(デザイン優先)
を意識するのが良いであろう。
なお、キヤノンは銀塩・デジタル時代を通じて、一眼レフ用
のパンケーキレンズは発売していなかった為、本レンズは
初のキヤノン製パンケーキである。
(他にも、ミラーレス機専用 EF-M 22mm/f2 STMが同年
2012年に発売された)
そういう意味では「歴史的価値」は高く、STMのMFの弱点を
容認しても購入に踏み切ったレンズである。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Nブロック「AF焦点距離違い」の記事は終了だ。
次回の本シリーズ記事は、予選O(オー)ブロック
「MFその他」編となる予定だ。