所有している一眼レフ用の50mm標準レンズを、AF/MF、
開放F値等によるカテゴリー別で予選を行い、最後に決勝で
最強の50mmレンズを決定するという主旨のシリーズ記事。
本シリーズ記事は、元々、オリンピックイヤーにちなんで
数年前から準備(撮影、執筆)を行っていたものであるが
緊急事態宣言で、それどころでは無くなってしまった。
まあ、当面の間は知人等への安否確認の表明の意味もあり、
小まめに執筆済み記事の更新を続けていく事にしよう。
さて今回は、予選Hブロック「AF50mm Macro」であり、
主に銀塩時代の「AF標準マクロレンズ」を6本紹介
(対戦)する。
今回は紹介(出場)レンズ本数が多いので、各レンズ
あたりの掲載写真は2枚づつとする。
---
さて、まずは今回最初の標準マクロレンズ。
![_c0032138_11074907.jpg]()
レンズ購入価格:24,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-5(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第1回(第16位相当)
等の記事で紹介の、1990年代のAF標準等倍マクロレンズ。
![_c0032138_11074978.jpg]()
まず簡潔に特徴を述べるが、長所としては高い描写力を
誇る事だ。
そして短所は、鏡筒(鏡胴)デザインが古臭い事である。
デザイン上での見た目の問題のみならず、ピントリング
幅も狭い為、MF時では少々操作性が悪い。
最短撮影距離は19.5cm、等倍マクロ仕様だ。
(注:等倍とは36mmx24mmのフィルム面(センサー面)に
同じ撮影範囲の被写体が写る事、他には「1:1」とも言う。
センサーサイズが変われば、当然撮影倍率も変化する)
本レンズは、デジタル時代となってすぐ後継レンズが発売
されている。そちらはsmc PENTAX-D FA Macro 50mm/f2.8
(2004年)であるが、レンズ構成や最短撮影距離などの
カタログ的なスペックには変更が無く、DFA型の特徴と
しては、旧型よりも大幅に小型軽量化されている事だ
(旧)FA型 :フィルター径φ52mm 重量385g
(新)DFA型:フィルター径φ49mm、重量265g
また、新型はクイックシフト・フォーカス・システム
(つまり、AFとMFをシームレスに切り替える機能)を
搭載している。
後継のDFA型は、あいにく未所有であるので詳細の比較は
避けるが、本FA型に対してデザインおよびMF操作性上の
改善が見られるので、いずれ機会があれば買い増ししたい
とは思っている。
・・とは言うものの、本FA型でも描写力的には何ら不満は
無いし、新しいQSF機能は、ピントリングの構造次第では
MF操作性の悪化を招くリスクもある。なので、買い替えの
必然性はあまり無く、ずっと旧型を使っている状態だ。
なお、新旧どちらにも「クランプ機構」が搭載されている
旧型の本FA50/2.8では、クランプをONすると、AF時には
スカスカだったピントリングにブレーキ(トルク増加)を
掛けて「MF操作性を向上する」という狙いがあったのだが、
残念ながら、その効果はあまり高くない。
(注:故障あるいは経年劣化があるのかも知れないが、
他の銀塩時代のマクロレンズのクランプ機構も同様に、
あまり有益な効能が得られないケースが大半だ)
新型DFA型のクランプ機構ではピント位置を固定できるまで
強化された様子だが、所有していないので、その効果や
使用感は不明だ。
さて本FA50/2.8に限らず、1990年代頃にAF時代に入って
からの各社標準マクロ(50~60mm程度の焦点距離、等倍)
は、いずれも高描写力だ。
それ以前、1970~1980年代のMF時代の標準マクロが、
どれもイマイチの描写力であった事(おまけに撮影倍率も
1/2倍止まりだった)に対して、大きく性能改善が見られる。
この時代の技術革新に何があったのかの詳細は不明だが、
まあ、性能が良くなったので、何も文句は無い。
あるいは、1990年代のAF時代以降、2000年代のデジタル
時代頃までは、また、AF標準マクロの性能改善が止まって
しまったようにも感じられる。
さらにその後、2010年代のミラーレス時代に入って、
ミラーレス機用の標準又は標準画角マクロは、解像力の向上
等の改善が見られるが、それがやや過剰なケースもあるし、
ミラーレス機用レンズはピントリングが無限回転式なものが
殆どで、それはマクロレンズでも同様であり、AF/MFの
シームレスな移行機能については有効な物の、手指の感触で
最短撮影距離にセット不能な為、近接撮影時のMF性能を
大幅に悪化させてしまっている弱点も見受けられる。
(参考:例外として、ミラーレス機用、フォクトレンダー・
マクロ アポランター65mm/f2等は、MF仕様であり、
MF操作性にも当然配慮している。別途紹介済み)
2010年代のデジタル一眼用の新鋭標準マクロレンズは、
あまり本数を所有していない為(新製品自体、殆ど無い)
ここでの詳細の言及は避けるが、またこの時代のデジタル
一眼用(AF)マクロレンズを複数所有した頃に状況の分析を
してみよう。
![_c0032138_11074916.jpg]()
まず前述のデザインの悪さは、ちょっと困ってしまう。
いかにも古臭く、かつ大柄で不恰好だ。
MF操作性も劣る為、せっかくの描写力の高さを誇りながらも、
あまり外に持ち出して撮影したいという気にはなれない。
特に近代のPENTAXのデジタル一眼レフは、デザイン性を
重視したり、オーダーカラー制度(2010年代前半)や
特殊なカラーリング(2010年代後半)で、お洒落な
イメージを主張する機体が多く、それらと本レンズの
組み合わせは、デザイン的なアンバランスが酷い。
であれば、できるだけ2000年代の地味なPENTAX機との
組み合わせで本FA50/2.8レンズを使うのが適切だ。
今回も、地味なPENTAX K-5(黒)との組み合わせなので
あまりデザイン的なアンバランスを感じ難い。
描写力は高いのであるが、古い時代のAFレンズなので、
AF動作は「ガタピシ」言う感じで、合焦精度が不安だ。
母艦K-5のスクリーンは、さほど悪いものでは無いので
MFに切り替えるのが良さそうなのだが、前述のように
狭いピントリングでMF操作性はあまり良くなく、クランプ
機能を使っても、必要十分なMFトルク感は得られない。
なので、いっそデジタル一眼レフではなく、ミラーレス機
にアダプターを介して装着するのも良いであろう。
本FA50/2.8には、幸い、絞りリングが搭載されいるので
(注:後継機DFA50/2.8にも絞り環が存在する)
アダプターで使用時の操作性全般には問題は無い。
高精細EVF搭載ミラーレス機による、様々なMFアシスト機能
(例:画面拡大、ピーキング、デジタルスプリットイメージ)
を併用すれば、より精度の高いピント合わせが可能となる。
総括だが、描写性能的には不満は無い物の、いかにも古臭い
デザインイメージがあって、現代における本FA50.2,8の
新規購入は(相場は1万円台まで下がってはいるものの)
あまり推奨できない。
購入するのであれば、新型のDFA50/2.8の方が良いと思う。
ちなみに新型でも発売時期が2004年と古い為、中古相場は
2万円台前半と安価だ。
---
では、次のマクロレンズ。
![_c0032138_11080043.jpg]()
レンズ購入価格:15,000円(中古)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回(第4位相当)
等の記事で紹介の、1980年代後半のAF標準等倍マクロ。
![_c0032138_11080556.jpg]()
本レンズの紹介記事では毎回のように書いている事だが、
後継レンズのN型(1990年代)、D型(1990~2000年代)
SONY型(2000年代後半~)に至るまで、レンズ構成に
ほとんど変更が無いままバージョンアップされている。
すなわち初期型から完成度が高かった、と言う事実を
示しているのだが、初期型はさすがに30年以上も前の
レンズであるから、色々と課題はある。
まず、このレンズの時代は「αショック」(1985年)
の直後だ。すなわち、ミノルタが初の実用的AF一眼レフ
「α-7000」で他社を大きく先行したという歴史であり、
これは社会現象にもなった他、他社の一眼レフの
市場戦略にも、多大な影響を与えた訳だ。
この当時の世情は「AFは最新技術だ」「AFは万能だ」
「MF操作など、古臭くて格好悪い」という様相があり、
その結果、MF操作性や、その必要度を大幅に軽んじた
カメラやレンズ製品が多数発売された時代である。
本AF50/2.8(初期型)も、その世情を受け、ピント
リングについては、レンズ先端の廻し難い位置に、
僅かに幅4mm程度のものがついているだけだ。
ここは後年の後継機に至ると、少しづつ改善されていく
(まあつまり、AFが万能で無い事に、皆気づいた訳だ)
のではあるが、勿論中古相場も新型になる程高価になる。
本初期型であれば、現代での中古相場は1万円以下であり、
描写性能面からは極めてコスパが良いのであるが、
このやりにくいMF操作性をどう評価するか?で、本レンズ
AF50/2.8(初期型)の価値が変わってくる事であろう。
さて、本レンズは、フルサイズ対応、AF対応の等倍標準
マクロレンズであり、最短撮影距離は20.0cmである。
なお、各社の標準マクロレンズは、等倍仕様の場合、
その最短撮影距離は、おおよそ20cm前後になるのだが、
メーカーによって(つまり設計によって)若干の差異が
あり、同じ焦点距離で、同じ等倍仕様だからと言って、
常に全く同じ最短撮影距離になるとは限らない。
余談だが、数年前に話題になった事で、小学校の算数の
テストで、3.9+5.1の問題を、9.0と答えを書いたら
減点された(正解は9との事?)で、世間でその賛否が
話題になった事がある。
まあ教育(採点)方針の問題であるから、そこについては、
その詳細の言及は避けるが・・
カメラ等の工業製品において、エンジニアリング(工学的)
な視点から言えば、計測された仕様や性能等の数値には、
全て「有効数字」(有効ケタ数)という概念が存在する。
例えば、最短20cmと書くのと、最短20.0cmと書くのは
どちらでも良い訳ではなく、有効数字の視点からは意味が
異なってくるのだ。
具体的には、20.0cmであれば、仕様上、つまりメーカー
からの公式上、この数字は「小数点以下1ケタまでは
ちゃんと計測しましたよ」という意味であり。
20cmと書けば「小数点以下の精度は保証しませんよ」
という意味となる。
(同様に昔の標準レンズの焦点距離でも、50mmではなく
5cmと書いてある、これは「cmまでの単位しか精度は保証
しません」という意味である。実際では49mmであろうが
52mmであろうが、それは「5cm」と表記される事になる)
で、実は、本レンズの詳細なスペックはもう、ほとんど
情報が残っていない。しかし、この時代の標準マクロの
仕様は、cm単位では小数点以下1ケタの有効数字(つまり
mmまで)で表示している場合が多い(例、0.195m)
よって、本レンズでも暫定的に最短20.0cmとしておこう。
![_c0032138_11080577.jpg]()
ともかく描写力の観点では、この時代のAF標準マクロの
例に漏れず、MF時代の標準マクロよりも大幅に性能が
向上している。この性能水準は、1990年代のAF時代を
通じて、さらに2000年代のデジタル時代に入ってすらも
さらなる改善の必要性が少なかった位に完成度が高い。
よってユーザー側が、その撮影目的上、この性能水準で
十分な場合(例:近年のローパスレス機や超高画素機等で、
非常に高解像度の写真を撮る必要性が無い場合等)では
本レンズの安価な中古価格によるコスパの高さは、かなり
の高レベルとなる。
ミラーレス名玉編そしてハイコスパ名玉編で、いずれも
高い順位にランクインしたのは、この特徴から来る訳だ。
現代において、SONYのαはAマウント機よりもEマウント
のミラーレス機に主軸が移行している状況ではあるが、
Aマウント機も近代(2010年代以降)のαフタケタ機は
いずれも完成度が高く、高機能で高性能かつ操作系も良い。
(注:汎用OSの搭載により、操作性の鈍重さが目立つ
機体も多いが、ここでは、その弱点は無視しておく)
そうであれば、古いレンズでありながら、十分に現役で
使用可能という本AF50/2.8は、α Aマウントユーザーで
あれば、持っていても悪く無い選択だと思う。
なお、より後年の後継型とするのも、予算次第であるが、
その場合はMF操作性の面でミノルタD型以降を推奨する。
(最近では玉数が少ないが、あれば2万円程度からの
中古相場であろうか・・)
---
では、3本目の標準マクロ。
![_c0032138_11081832.jpg]()
レンズ購入価格:14,000円(中古)
使用カメラ:PANASONIC LUMIX DMC-GX7(μ4/3機)
ミラーレス・マニアックス第25回記事で紹介の、
1990年前後(?)のAF標準等倍マクロ。
![_c0032138_11081830.jpg]()
良く書いた通り、概ね1990年代のSIGMA製レンズは、
2000年頃以降のAF/デジタルのEOS機ではエラーが
発生して使用できない。これはキヤノン側がレンズと
ボディとの通信プロトコルを変更し、他社製レンズを
使えなくしてしまった可能性が高いが、まあその件は
他記事でも散々文句を書いたので、今回は割愛する。
(なお、2000年代以降のSIGMA製レンズは、2000年代
以降のEOS機で問題無く使用できる。また、2000年代
のフォーサーズ機の一部と、SIGMA製旧レンズでも
同様に通信エラーとなる場合もあると聞くが、当該
組み合わせを所有していないので、詳細は不明だ)
と言う事で、今回は本レンズSIGMA AF50/2.8をEOS機に
装着して撮影は出来ない、替わりに、ミラーレス機で使う
事とするが、ここでは「機械式絞り羽根内蔵アダプター」
を使用する。EFマウントのアダプターは色々と制限事項が
発生するが、そのあたりは過去記事に詳しいので割愛する。
さて、本レンズも他のAF標準マクロと同調に、等倍仕様
であり、勿論フルサイズ対応だ。
最短撮影距離は約19cm、しかしレンズの距離指標上では、
もう少しだけ廻す事もできる。前述の有効数字の点から
すると19.0cmではなく、あくまで約19cmだ。
なお、同じ撮影倍率であれば、最短撮影距離が短い方が
良い性能か?と言うと、そんな事はなく、あくまで同じ
大きさに写したいのであれば、最短撮影距離の差異は、
あまり関係が無い。
まあ細かい事を言えば、同じ撮影倍率で最短撮影距離が
長い方が、レンズ前から被写体までの距離、すなわち
「ワーキング・ディスタンス」(以下WD)を長くする事が
でき、要は被写体に近づかなくても大きく写せるので、
近寄りがたい被写体(例:柵等があって被写体に近づけない、
それと昆虫等で、近づくと危険であったり、または逃げる、
あるいは、あまり被写体に近づくとカメラやレンズの影が
出て被写体に写る場合等)では僅かだが役に立つ。
反面、WDが短い方が、被写体をありとあらゆる角度
(アングル、レベル)で撮影する事が可能となり、
構図上の自由度が高くなる。
まあつまりケースバイケースであるし、50mm等倍マクロ
での、最短撮影距離の差異における19cmや22cmは決して
大差では無いので、いずれであっても問題無いであろう。
さて、本AF50/2.8だが、前出のミノルタと標準マクロと
型番が被る。ミノルタは、前述のように、α(-7000)で
AF一眼レフ市場に先行参入したから、そのαの交換レンズ
群も、わかり易い「AF型番」を早いもの勝ちで取得した
のであろう。
なお、余談であるが「商標」の観点からはアルファベット
2文字からなる製品名は、原則的には商標登録できない。
これは単純すぎる為に、他の製品等と識別する事が困難で
あるからだ。ただし例外的に意匠(デザイン)と組み合わせ
たり、既に十分に有名である、という理由で商標登録できる
場合もあり、例えば「JR」(鉄道)や「JT」(タバコ)や
「au」(携帯電話)が、それで登録されている。
商標を登録しない場合は、アルファベット2文字は、単なる
製品としての型番にすぎない。まあ、一々全ての製品型番を
商標登録していたら、お金や手間がかかりすぎるので、
多くの工業製品は、そんな感じとなっている。
だからミノルタが「AF型番」を使っていたからと言って、
他社が同じAF型番を使っても問題は無い訳だ。
という事で、SIGMAやTAMRON,TOKINA等においても
AF型番を使用しているのだが、ミノルタとの関係上、
正規な型番とは言わず「このレンズはMFではなくAFですよ」
という観点で、レンズ上等に、さらっと「AF」と書いてある
場合も多い。本記事等では、便宜上、適宜メーカー名を
つけるなどして、こうしたケースを区別する事としよう。
さて、もう1つ、本レンズの型番だが、これ以降の時代の
SIGMAレンズに良くついている「EX」という型番が無い。
EXは、SIGMAでの本来の意味は「開放F値固定型レンズ」
という事だ、つまり一般的な初級ズーム等では、焦点距離
に応じて開放F値が変動し、高級ズーム等では開放F値が
固定になっている。
この為、EX仕様の方が高級品のように錯覚するが、まあ、
ズームはともかく、単焦点レンズは全て開放F値が固定
(変動しようがない)ので、どれもEXタイプである。
なお、EX型番がついた頃にSIGMAレンズの外装も若干変化
し、高級感のある仕上げとなっている。
まあ、EX型番ではないという事で、古い時代のレンズの
外観が本AF50/2.8にも残っている、ただ、後継のEX型番
であっても、レンズ構成に変化は無かった模様であり、
実質の性能的には初期型でも十分だ。
注意するべきは、EF(EOS)マウントだと後年のEOS機で
使用できない、という点であり、これを回避するには
初期型であっても、ニコンF(Ai)マウント品を買えば良い。
この時代1990年代および2000年代頃までのSIGMA製
レンズは、ニコン(F)用やペンタックス(K)用では絞り環
がまだついているので、後年のミラーレス機にマウント
アダプターを介して装着する際にも操作性を損なわない。
![_c0032138_11081914.jpg]()
の描写性能であるが、あまり問題点は無く、悪く無い。
まあこの時代のAF標準マクロは全て良いのであるが、
あくまで標準域マクロでの話だ。
ちなみに、SIGMAからもTAMRONと同じ仕様の90mm/2.8
マクロがこの時代か、やや昔の時代(1980年代)に発売
されていたのだが、そのレンズは1990年代に一度入手
したものの、描写力が気に入らず、譲渡してしまっていた。
また、2000年代には70mmマクロがあり、知人が使っていて
なかなか良さそうだったのだが、あいにくセミレア品と
なってしまっていた。
(注:70mm版は、2018年に「カミソリマクロ」として復刻
リニューアルされている、別記事で紹介済み。
また、旧製品のEX型「カミソリマクロ」も後日入手済み)
本50mmマクロは、比較的中古流通が多かったので、
2000年代には、ニコン初級ユーザーの何人かの知人に
薦めて1万円台程度で良く購入していた。
すなわち、ニコン機用では、やや高価なAiAF60/2.8等の
標準マクロを買うのは、初級層には予算的に厳しいのと
ニコン標準マクロは、どの時代のものもボケ質が固い
という課題を持つ為だ。
2010年代以降、現代においてはSIGMA 50mmマクロ
は各世代の製品を通じて、やや入手しにくいセミレアな
レンズとなっている。だがまあ、運よく中古があれば
1万円台という安価な相場であると思うので、コスパは
かなり良いと見なす事ができると思う。
(追記:本記事執筆後に、2000年代に発売のEX DG版
を約9000円で入手。そちらであれば、現代のEOS
デジタル一眼レフでも使用できる。後日別途紹介予定)
---
では、次のマクロ(マイクロ)レンズ。
![_c0032138_11083360.jpg]()
レンズ購入価格:38,000円(中古)
使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第57回記事で紹介の、
1993年発売のAF標準等倍マクロ(マイクロ)だ。
1990年代のAFレンズだが、ベースとなったMFレンズが
昔(1960年代)からあり、55/3.5→55/2.8と変化、
そして60/2.8でAF化された。
なお、Microのレンズ上での表記は時代で変わり、
だいたいだが、MF時代のものは「Micro-NIKKOR」
AF時代のものは「MICRO NIKKOR」と記載してある模様だ。
(注:これはNIKONの公式WEB上での表記とは異なる。
NIKONイメージングのサイトは、旧製品等における記載、
つまり大文字・小文字・ハイフンの区別が正確では無く、
引用するほどの信憑性が無い。私の場合では、所有する
実機(カメラやレンズ)を参照し、そこにある記載を
”ホンモノ”として引用する事にしている)
![_c0032138_11083321.jpg]()
1つのメーカーだけ特定の呼び名を使うのは好ましく無い
と良く本ブログでは書くのだが、この「マクロ」に限っては
ニコンの「マイクロ」の呼び方が本来の意味的に正しい。
「マクロ」では、「巨視的」という日本語に置き換え
られ、マイクロ(またはミクロ)の「微視的」とは
ほとんど反対の意味だ。
他には、大きい、長い、大規模という意味もあるが、
コンピューター用語では、複数の操作をまとめた処理を
自動化する際も「マクロ」と呼ばれる事がある。
(例:エクセルでのマクロ処理等)
まあ、普通に考えれば「マイクロ」が正解であろう。
だがまあ、間違った意味であっても、ここまでカメラの
世界では一般化してしまったので、もう「マクロ」と
呼ばさるを得ない。
ちなみに、Macroと英語では書くが、ツァイスレンズ等
では独語で「Makro」と書かれている。
さて、本レンズの最短撮影距離は21.9cm、勿論等倍だ。
描写特徴としては、ボケ質がやや固く、その替わり
ピント面の解像度が高い事だ。
これは、これ以前のAi型番等のMFマイクロレンズ
(55/3.5,55/2.8)では、さらにその傾向が顕著であり、
立体物の撮影には向かず、ほとんど「平面マクロ」という
状況であった。
この理由は、本ブログでは何度も述べているが、簡単に
言えば、1970年代では、まだコピー機が普及しておらず
その時代のマクロレンズは文書や図面などを写真で撮って
平面的に複写する目的に使われていたからである。
本AiAF60/2.8の時代1990年代ではコピー機があるので、
マクロレンズは、より一般的な描写傾向(例えば、花や
人物などを撮影しても背景ボケが柔らかくできる)に
改められてきている。が、本レンズでは、まだその
旧来の描写傾向が若干残っているのだ。
(注:まあ、急に特性を変えると、旧型のユーザー層から
「新型に買い換えたら写りが甘くなった」等のクレーム
が生じるかも知れない事を避ける処置であろう。
歴史とブランド力のあるメーカーの市場戦略上では、頭が
痛いところだと思う。でもユーザー側も、もっと理解力
を高めないとならない。マニア的な視点から言えば、
本レンズに限らず、様々な撮影機材の「買い増し」は
良いが「買い替え」は避けるべきであろう。全ての要素で
新型機材が旧型機材よりも優れている保証は無いからだ)
まあつまり、本レンズの特性を良く理解して、被写体や
背景を選んで使うのが良いレンズである。と言う事だ。
他の特徴としては「露出(露光)倍数」がかかる事だ。
「露出倍数」とは近接撮影で見かけ上のF値が低下する
事であるが、実は、原理的には、ほとんどのマクロ
レンズでそれは起こる。で、一般的には近接撮影をした
場合、同じ被写体の明るさ、同じF値でもシャッター速度が
低下していく(またはAUTO ISOの感度が上がっていく)
だが、本AiAF60/2.8の場合は、近接撮影時に、例えば
開放F2.8で撮っていても、F値の表示が3.3等に落ちる。
これは特にF値を落として表示する必要性は少ないのだが、
こういう表示方式の方が光学原理的にはわかりやすい。
まあ、ずいぶん生真面目に作ったレンズであるという事だ。
![_c0032138_11083336.jpg]()
回避すれば特に問題無いものの、コスパが悪い事は弱点だ。
まあ、1990年代に、比較的高価に買ってしまったのは
私の問題ではあるが、後年でもニコンというブランド故に
中古相場があまり下がらず、ずっと高値傾向だった。
他社の標準マクロに比べて、割高感が強く、それ故に
前述のように、ニコン機の初級ユーザーには、本レンズ
では無くSIGMA製の標準マクロを薦めていた訳だ。
現代においては、ニコンからはAPS-C機専用のエントリー
マクロとして、本AiAF60/2.8と同じ換算画角となる
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm/f2.8G が発売されている。
そのレンズはあいにく未所有なので詳細はわからないが、
若干安価なので、ニコンAPS-C(DX)機ユーザーであれば、
そちらを検討するのも良いかも知れない。
(追記:記事執筆後に入手済み。別記事で紹介予定だが、
簡単に言えば、本AiAF60/2.8のスケールダウン版の
ジェネリックレンズであり、描写傾向はそっくりだ)
---
では、5本目のマクロ。
![_c0032138_11084425.jpg]()
レンズ購入価格:10,000円(中古)
使用カメラ:KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第68回記事で紹介の
1980年代のAF標準ハーフマクロ。
この時代には珍しく、最大撮影倍率1/2倍に性能限定
されたAFマクロだ。
![_c0032138_11084456.jpg]()
と併売されていたのだが、仕様が近く、何故両者が同時に
ラインナップされていたのか? 理由が良くわからない。
もっとも、銀塩MF時代の(New)MDマクロでは、本レンズと
同じく50mm/F3.5で1/2倍仕様であったので、そのレンズの
AF版と言う事で発売されたのかも知れない。
(注:レンズ構成等はAF版とMF版では大きく異なる。
ただし、描写傾向はMF版とは若干似ている模様だ。
MF版は次回記事で紹介予定)
なお、本レンズが1/2倍である事だが、これはフルサイズ
換算での話だ、よってAPS-C機では0.75倍、μ4/3機では
1倍となるので、こういう用法であれば、”寄れない”
という不満は殆ど無い。
ちなみに最短撮影距離は約23cmとなっている(小数点以下の
数値は不明)ので、他の等倍マクロの20cm前後と大差は無い。
また、ミラーレス機あるいはSONY αフタケタ一眼レフ機では、
デジタル拡大機能を用いる事で、さらに見かけ上の撮影倍率を
上げられるので、1/2倍である事のデメリットは実は殆ど無い。
![_c0032138_11085194.jpg]()
まあ普通に良く写るが、感動的、という要素は全く無い。
ボケもやや固く、破綻の回避作業が必須となるだろう。
なお、発色が濃くてDレンジが低く感じるのは、今回の
母艦α-7 DIGITALは、2004年製と、デジタル一眼レフ
最初期の非常に古い機体であるからで、当時のデジタル
技術的な課題だ。(まあ、これはこれで面白い)
本レンズは、ミノルタで言うN型(ピントリング約8mm幅)
のみの発売で、他のバージョン(前期型や後継D型)は
存在しない。
現代の中古相場は、数千円と安価であるが、兄貴分の
F2.8版の初期型とあまり変わりは無いので、全ての点で、
F2.8版を買った方が有利であるように思える。
・・であれば本レンズの購入意義は少ないのであるが、
私の場合は単純に、このF3.5版がF2.8版と何処が違うのか?
という好奇心で購入したに過ぎない、まあ、あくまでマニア
向けのレンズであり、通常のα(A)ユーザー層においては、
各時代でのF2.8版の購入を推奨する。
---
では、今回ラストのマクロ。
![_c0032138_11090061.jpg]()
レンズ購入価格:22,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarrkⅡ Limited (μ4/3機)
アダプターは、OLYMPUS MMF-2(4/3→μ4/3電子式)
特殊レンズ・スーパーマニアックス第2回記事で紹介の
2003年発売のフォーサーズ用の1/2倍AFマクロレンズ。
4/3またはμ4/3機に装着時の画角は100mm相当となるが
実焦点距離を元に本カテゴリーに分類している。
また、本カテゴリー中、本レンズのみ、デジタル時代に
なってから新しく発売された製品である。
![_c0032138_11090025.jpg]()
本レンズを詳しく紹介しても、あまり意味を持たないかも
知れない。
ただまあ幸いな事に、電子アダプターを介して、現代の
μ4/3機でも、あまり不便を感じずに使用できる。
その際の制限事項は、AF速度、AF精度がやや落ちる事だが、
まあ、使用する母艦との相性もあるかも知れない。
私の感覚では、OM-D E-M5Ⅱで使うよりも、OM-D E-M1
での利用が、やや快適だ。(後者は像面位相差AF搭載)
本レンズの長所であるが、解像感とかボケ質に優れる
事である。この点では「マクロのオリンパス」の名に
恥じない。
弱点は、逆光耐性が低く、かつコントラストの低下が
甚だしい。軽いカビやクモリ等の様子もなく、こういう
描写特性なのだと思われる。毎回きちんとフードを装着し、
かつ、光線状況に留意して撮る必要がある。
また、カメラの電源をOFFすると、ピントリングが空回り
してしまうので、マクロ域の近接撮影をしていて、鏡筒が
伸びている状態で電源を切ると、レンズが伸びたまま
戻らなくなる、電源OFFの前に、都度、無限遠を撮るとか
MFでレンズを戻してから電源を切るのは煩雑な操作だ。
![_c0032138_11090037.jpg]()
規格仕様上の課題であり、本レンズに限らない。
でも、他の4/3レンズは、鏡筒が伸びっぱなしになる
ようなものは少ないのだが、本レンズはマクロなので
鏡筒長の変化が大きく、電源ON/OFF時で問題となる。
また、一部の一眼レフ用レンズにも同様にレンズ内
モーターが電源OFFで動かない仕様のものがあり、
(CANONの初期USM、同、近代のSTM、SIGMAでの
非HSM仕様のレンズ等)それが、ヘリコイド(鏡筒)が
伸びるマクロレンズであった場合は結構面倒な課題となる。
まあでも、現代において、今更4/3システムを使ったり
4/3レンズを買うのは、かなり酔狂な話であろう・・
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Hブロック「AF50mm Macro」の記事は終了だ。
次回の本シリーズ記事は、
予選Iブロック「MF50mm Macro」となる予定だ。
開放F値等によるカテゴリー別で予選を行い、最後に決勝で
最強の50mmレンズを決定するという主旨のシリーズ記事。
本シリーズ記事は、元々、オリンピックイヤーにちなんで
数年前から準備(撮影、執筆)を行っていたものであるが
緊急事態宣言で、それどころでは無くなってしまった。
まあ、当面の間は知人等への安否確認の表明の意味もあり、
小まめに執筆済み記事の更新を続けていく事にしよう。
さて今回は、予選Hブロック「AF50mm Macro」であり、
主に銀塩時代の「AF標準マクロレンズ」を6本紹介
(対戦)する。
今回は紹介(出場)レンズ本数が多いので、各レンズ
あたりの掲載写真は2枚づつとする。
---
さて、まずは今回最初の標準マクロレンズ。

レンズ購入価格:24,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-5(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第1回(第16位相当)
等の記事で紹介の、1990年代のAF標準等倍マクロレンズ。

まず簡潔に特徴を述べるが、長所としては高い描写力を
誇る事だ。
そして短所は、鏡筒(鏡胴)デザインが古臭い事である。
デザイン上での見た目の問題のみならず、ピントリング
幅も狭い為、MF時では少々操作性が悪い。
最短撮影距離は19.5cm、等倍マクロ仕様だ。
(注:等倍とは36mmx24mmのフィルム面(センサー面)に
同じ撮影範囲の被写体が写る事、他には「1:1」とも言う。
センサーサイズが変われば、当然撮影倍率も変化する)
本レンズは、デジタル時代となってすぐ後継レンズが発売
されている。そちらはsmc PENTAX-D FA Macro 50mm/f2.8
(2004年)であるが、レンズ構成や最短撮影距離などの
カタログ的なスペックには変更が無く、DFA型の特徴と
しては、旧型よりも大幅に小型軽量化されている事だ
(旧)FA型 :フィルター径φ52mm 重量385g
(新)DFA型:フィルター径φ49mm、重量265g
また、新型はクイックシフト・フォーカス・システム
(つまり、AFとMFをシームレスに切り替える機能)を
搭載している。
後継のDFA型は、あいにく未所有であるので詳細の比較は
避けるが、本FA型に対してデザインおよびMF操作性上の
改善が見られるので、いずれ機会があれば買い増ししたい
とは思っている。
・・とは言うものの、本FA型でも描写力的には何ら不満は
無いし、新しいQSF機能は、ピントリングの構造次第では
MF操作性の悪化を招くリスクもある。なので、買い替えの
必然性はあまり無く、ずっと旧型を使っている状態だ。
なお、新旧どちらにも「クランプ機構」が搭載されている
旧型の本FA50/2.8では、クランプをONすると、AF時には
スカスカだったピントリングにブレーキ(トルク増加)を
掛けて「MF操作性を向上する」という狙いがあったのだが、
残念ながら、その効果はあまり高くない。
(注:故障あるいは経年劣化があるのかも知れないが、
他の銀塩時代のマクロレンズのクランプ機構も同様に、
あまり有益な効能が得られないケースが大半だ)
新型DFA型のクランプ機構ではピント位置を固定できるまで
強化された様子だが、所有していないので、その効果や
使用感は不明だ。
さて本FA50/2.8に限らず、1990年代頃にAF時代に入って
からの各社標準マクロ(50~60mm程度の焦点距離、等倍)
は、いずれも高描写力だ。
それ以前、1970~1980年代のMF時代の標準マクロが、
どれもイマイチの描写力であった事(おまけに撮影倍率も
1/2倍止まりだった)に対して、大きく性能改善が見られる。
この時代の技術革新に何があったのかの詳細は不明だが、
まあ、性能が良くなったので、何も文句は無い。
あるいは、1990年代のAF時代以降、2000年代のデジタル
時代頃までは、また、AF標準マクロの性能改善が止まって
しまったようにも感じられる。
さらにその後、2010年代のミラーレス時代に入って、
ミラーレス機用の標準又は標準画角マクロは、解像力の向上
等の改善が見られるが、それがやや過剰なケースもあるし、
ミラーレス機用レンズはピントリングが無限回転式なものが
殆どで、それはマクロレンズでも同様であり、AF/MFの
シームレスな移行機能については有効な物の、手指の感触で
最短撮影距離にセット不能な為、近接撮影時のMF性能を
大幅に悪化させてしまっている弱点も見受けられる。
(参考:例外として、ミラーレス機用、フォクトレンダー・
マクロ アポランター65mm/f2等は、MF仕様であり、
MF操作性にも当然配慮している。別途紹介済み)
2010年代のデジタル一眼用の新鋭標準マクロレンズは、
あまり本数を所有していない為(新製品自体、殆ど無い)
ここでの詳細の言及は避けるが、またこの時代のデジタル
一眼用(AF)マクロレンズを複数所有した頃に状況の分析を
してみよう。

まず前述のデザインの悪さは、ちょっと困ってしまう。
いかにも古臭く、かつ大柄で不恰好だ。
MF操作性も劣る為、せっかくの描写力の高さを誇りながらも、
あまり外に持ち出して撮影したいという気にはなれない。
特に近代のPENTAXのデジタル一眼レフは、デザイン性を
重視したり、オーダーカラー制度(2010年代前半)や
特殊なカラーリング(2010年代後半)で、お洒落な
イメージを主張する機体が多く、それらと本レンズの
組み合わせは、デザイン的なアンバランスが酷い。
であれば、できるだけ2000年代の地味なPENTAX機との
組み合わせで本FA50/2.8レンズを使うのが適切だ。
今回も、地味なPENTAX K-5(黒)との組み合わせなので
あまりデザイン的なアンバランスを感じ難い。
描写力は高いのであるが、古い時代のAFレンズなので、
AF動作は「ガタピシ」言う感じで、合焦精度が不安だ。
母艦K-5のスクリーンは、さほど悪いものでは無いので
MFに切り替えるのが良さそうなのだが、前述のように
狭いピントリングでMF操作性はあまり良くなく、クランプ
機能を使っても、必要十分なMFトルク感は得られない。
なので、いっそデジタル一眼レフではなく、ミラーレス機
にアダプターを介して装着するのも良いであろう。
本FA50/2.8には、幸い、絞りリングが搭載されいるので
(注:後継機DFA50/2.8にも絞り環が存在する)
アダプターで使用時の操作性全般には問題は無い。
高精細EVF搭載ミラーレス機による、様々なMFアシスト機能
(例:画面拡大、ピーキング、デジタルスプリットイメージ)
を併用すれば、より精度の高いピント合わせが可能となる。
総括だが、描写性能的には不満は無い物の、いかにも古臭い
デザインイメージがあって、現代における本FA50.2,8の
新規購入は(相場は1万円台まで下がってはいるものの)
あまり推奨できない。
購入するのであれば、新型のDFA50/2.8の方が良いと思う。
ちなみに新型でも発売時期が2004年と古い為、中古相場は
2万円台前半と安価だ。
---
では、次のマクロレンズ。

レンズ購入価格:15,000円(中古)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回(第4位相当)
等の記事で紹介の、1980年代後半のAF標準等倍マクロ。

本レンズの紹介記事では毎回のように書いている事だが、
後継レンズのN型(1990年代)、D型(1990~2000年代)
SONY型(2000年代後半~)に至るまで、レンズ構成に
ほとんど変更が無いままバージョンアップされている。
すなわち初期型から完成度が高かった、と言う事実を
示しているのだが、初期型はさすがに30年以上も前の
レンズであるから、色々と課題はある。
まず、このレンズの時代は「αショック」(1985年)
の直後だ。すなわち、ミノルタが初の実用的AF一眼レフ
「α-7000」で他社を大きく先行したという歴史であり、
これは社会現象にもなった他、他社の一眼レフの
市場戦略にも、多大な影響を与えた訳だ。
この当時の世情は「AFは最新技術だ」「AFは万能だ」
「MF操作など、古臭くて格好悪い」という様相があり、
その結果、MF操作性や、その必要度を大幅に軽んじた
カメラやレンズ製品が多数発売された時代である。
本AF50/2.8(初期型)も、その世情を受け、ピント
リングについては、レンズ先端の廻し難い位置に、
僅かに幅4mm程度のものがついているだけだ。
ここは後年の後継機に至ると、少しづつ改善されていく
(まあつまり、AFが万能で無い事に、皆気づいた訳だ)
のではあるが、勿論中古相場も新型になる程高価になる。
本初期型であれば、現代での中古相場は1万円以下であり、
描写性能面からは極めてコスパが良いのであるが、
このやりにくいMF操作性をどう評価するか?で、本レンズ
AF50/2.8(初期型)の価値が変わってくる事であろう。
さて、本レンズは、フルサイズ対応、AF対応の等倍標準
マクロレンズであり、最短撮影距離は20.0cmである。
なお、各社の標準マクロレンズは、等倍仕様の場合、
その最短撮影距離は、おおよそ20cm前後になるのだが、
メーカーによって(つまり設計によって)若干の差異が
あり、同じ焦点距離で、同じ等倍仕様だからと言って、
常に全く同じ最短撮影距離になるとは限らない。
余談だが、数年前に話題になった事で、小学校の算数の
テストで、3.9+5.1の問題を、9.0と答えを書いたら
減点された(正解は9との事?)で、世間でその賛否が
話題になった事がある。
まあ教育(採点)方針の問題であるから、そこについては、
その詳細の言及は避けるが・・
カメラ等の工業製品において、エンジニアリング(工学的)
な視点から言えば、計測された仕様や性能等の数値には、
全て「有効数字」(有効ケタ数)という概念が存在する。
例えば、最短20cmと書くのと、最短20.0cmと書くのは
どちらでも良い訳ではなく、有効数字の視点からは意味が
異なってくるのだ。
具体的には、20.0cmであれば、仕様上、つまりメーカー
からの公式上、この数字は「小数点以下1ケタまでは
ちゃんと計測しましたよ」という意味であり。
20cmと書けば「小数点以下の精度は保証しませんよ」
という意味となる。
(同様に昔の標準レンズの焦点距離でも、50mmではなく
5cmと書いてある、これは「cmまでの単位しか精度は保証
しません」という意味である。実際では49mmであろうが
52mmであろうが、それは「5cm」と表記される事になる)
で、実は、本レンズの詳細なスペックはもう、ほとんど
情報が残っていない。しかし、この時代の標準マクロの
仕様は、cm単位では小数点以下1ケタの有効数字(つまり
mmまで)で表示している場合が多い(例、0.195m)
よって、本レンズでも暫定的に最短20.0cmとしておこう。

ともかく描写力の観点では、この時代のAF標準マクロの
例に漏れず、MF時代の標準マクロよりも大幅に性能が
向上している。この性能水準は、1990年代のAF時代を
通じて、さらに2000年代のデジタル時代に入ってすらも
さらなる改善の必要性が少なかった位に完成度が高い。
よってユーザー側が、その撮影目的上、この性能水準で
十分な場合(例:近年のローパスレス機や超高画素機等で、
非常に高解像度の写真を撮る必要性が無い場合等)では
本レンズの安価な中古価格によるコスパの高さは、かなり
の高レベルとなる。
ミラーレス名玉編そしてハイコスパ名玉編で、いずれも
高い順位にランクインしたのは、この特徴から来る訳だ。
現代において、SONYのαはAマウント機よりもEマウント
のミラーレス機に主軸が移行している状況ではあるが、
Aマウント機も近代(2010年代以降)のαフタケタ機は
いずれも完成度が高く、高機能で高性能かつ操作系も良い。
(注:汎用OSの搭載により、操作性の鈍重さが目立つ
機体も多いが、ここでは、その弱点は無視しておく)
そうであれば、古いレンズでありながら、十分に現役で
使用可能という本AF50/2.8は、α Aマウントユーザーで
あれば、持っていても悪く無い選択だと思う。
なお、より後年の後継型とするのも、予算次第であるが、
その場合はMF操作性の面でミノルタD型以降を推奨する。
(最近では玉数が少ないが、あれば2万円程度からの
中古相場であろうか・・)
---
では、3本目の標準マクロ。

レンズ購入価格:14,000円(中古)
使用カメラ:PANASONIC LUMIX DMC-GX7(μ4/3機)
ミラーレス・マニアックス第25回記事で紹介の、
1990年前後(?)のAF標準等倍マクロ。

良く書いた通り、概ね1990年代のSIGMA製レンズは、
2000年頃以降のAF/デジタルのEOS機ではエラーが
発生して使用できない。これはキヤノン側がレンズと
ボディとの通信プロトコルを変更し、他社製レンズを
使えなくしてしまった可能性が高いが、まあその件は
他記事でも散々文句を書いたので、今回は割愛する。
(なお、2000年代以降のSIGMA製レンズは、2000年代
以降のEOS機で問題無く使用できる。また、2000年代
のフォーサーズ機の一部と、SIGMA製旧レンズでも
同様に通信エラーとなる場合もあると聞くが、当該
組み合わせを所有していないので、詳細は不明だ)
と言う事で、今回は本レンズSIGMA AF50/2.8をEOS機に
装着して撮影は出来ない、替わりに、ミラーレス機で使う
事とするが、ここでは「機械式絞り羽根内蔵アダプター」
を使用する。EFマウントのアダプターは色々と制限事項が
発生するが、そのあたりは過去記事に詳しいので割愛する。
さて、本レンズも他のAF標準マクロと同調に、等倍仕様
であり、勿論フルサイズ対応だ。
最短撮影距離は約19cm、しかしレンズの距離指標上では、
もう少しだけ廻す事もできる。前述の有効数字の点から
すると19.0cmではなく、あくまで約19cmだ。
なお、同じ撮影倍率であれば、最短撮影距離が短い方が
良い性能か?と言うと、そんな事はなく、あくまで同じ
大きさに写したいのであれば、最短撮影距離の差異は、
あまり関係が無い。
まあ細かい事を言えば、同じ撮影倍率で最短撮影距離が
長い方が、レンズ前から被写体までの距離、すなわち
「ワーキング・ディスタンス」(以下WD)を長くする事が
でき、要は被写体に近づかなくても大きく写せるので、
近寄りがたい被写体(例:柵等があって被写体に近づけない、
それと昆虫等で、近づくと危険であったり、または逃げる、
あるいは、あまり被写体に近づくとカメラやレンズの影が
出て被写体に写る場合等)では僅かだが役に立つ。
反面、WDが短い方が、被写体をありとあらゆる角度
(アングル、レベル)で撮影する事が可能となり、
構図上の自由度が高くなる。
まあつまりケースバイケースであるし、50mm等倍マクロ
での、最短撮影距離の差異における19cmや22cmは決して
大差では無いので、いずれであっても問題無いであろう。
さて、本AF50/2.8だが、前出のミノルタと標準マクロと
型番が被る。ミノルタは、前述のように、α(-7000)で
AF一眼レフ市場に先行参入したから、そのαの交換レンズ
群も、わかり易い「AF型番」を早いもの勝ちで取得した
のであろう。
なお、余談であるが「商標」の観点からはアルファベット
2文字からなる製品名は、原則的には商標登録できない。
これは単純すぎる為に、他の製品等と識別する事が困難で
あるからだ。ただし例外的に意匠(デザイン)と組み合わせ
たり、既に十分に有名である、という理由で商標登録できる
場合もあり、例えば「JR」(鉄道)や「JT」(タバコ)や
「au」(携帯電話)が、それで登録されている。
商標を登録しない場合は、アルファベット2文字は、単なる
製品としての型番にすぎない。まあ、一々全ての製品型番を
商標登録していたら、お金や手間がかかりすぎるので、
多くの工業製品は、そんな感じとなっている。
だからミノルタが「AF型番」を使っていたからと言って、
他社が同じAF型番を使っても問題は無い訳だ。
という事で、SIGMAやTAMRON,TOKINA等においても
AF型番を使用しているのだが、ミノルタとの関係上、
正規な型番とは言わず「このレンズはMFではなくAFですよ」
という観点で、レンズ上等に、さらっと「AF」と書いてある
場合も多い。本記事等では、便宜上、適宜メーカー名を
つけるなどして、こうしたケースを区別する事としよう。
さて、もう1つ、本レンズの型番だが、これ以降の時代の
SIGMAレンズに良くついている「EX」という型番が無い。
EXは、SIGMAでの本来の意味は「開放F値固定型レンズ」
という事だ、つまり一般的な初級ズーム等では、焦点距離
に応じて開放F値が変動し、高級ズーム等では開放F値が
固定になっている。
この為、EX仕様の方が高級品のように錯覚するが、まあ、
ズームはともかく、単焦点レンズは全て開放F値が固定
(変動しようがない)ので、どれもEXタイプである。
なお、EX型番がついた頃にSIGMAレンズの外装も若干変化
し、高級感のある仕上げとなっている。
まあ、EX型番ではないという事で、古い時代のレンズの
外観が本AF50/2.8にも残っている、ただ、後継のEX型番
であっても、レンズ構成に変化は無かった模様であり、
実質の性能的には初期型でも十分だ。
注意するべきは、EF(EOS)マウントだと後年のEOS機で
使用できない、という点であり、これを回避するには
初期型であっても、ニコンF(Ai)マウント品を買えば良い。
この時代1990年代および2000年代頃までのSIGMA製
レンズは、ニコン(F)用やペンタックス(K)用では絞り環
がまだついているので、後年のミラーレス機にマウント
アダプターを介して装着する際にも操作性を損なわない。

の描写性能であるが、あまり問題点は無く、悪く無い。
まあこの時代のAF標準マクロは全て良いのであるが、
あくまで標準域マクロでの話だ。
ちなみに、SIGMAからもTAMRONと同じ仕様の90mm/2.8
マクロがこの時代か、やや昔の時代(1980年代)に発売
されていたのだが、そのレンズは1990年代に一度入手
したものの、描写力が気に入らず、譲渡してしまっていた。
また、2000年代には70mmマクロがあり、知人が使っていて
なかなか良さそうだったのだが、あいにくセミレア品と
なってしまっていた。
(注:70mm版は、2018年に「カミソリマクロ」として復刻
リニューアルされている、別記事で紹介済み。
また、旧製品のEX型「カミソリマクロ」も後日入手済み)
本50mmマクロは、比較的中古流通が多かったので、
2000年代には、ニコン初級ユーザーの何人かの知人に
薦めて1万円台程度で良く購入していた。
すなわち、ニコン機用では、やや高価なAiAF60/2.8等の
標準マクロを買うのは、初級層には予算的に厳しいのと
ニコン標準マクロは、どの時代のものもボケ質が固い
という課題を持つ為だ。
2010年代以降、現代においてはSIGMA 50mmマクロ
は各世代の製品を通じて、やや入手しにくいセミレアな
レンズとなっている。だがまあ、運よく中古があれば
1万円台という安価な相場であると思うので、コスパは
かなり良いと見なす事ができると思う。
(追記:本記事執筆後に、2000年代に発売のEX DG版
を約9000円で入手。そちらであれば、現代のEOS
デジタル一眼レフでも使用できる。後日別途紹介予定)
---
では、次のマクロ(マイクロ)レンズ。

レンズ購入価格:38,000円(中古)
使用カメラ:NIKON D500(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第57回記事で紹介の、
1993年発売のAF標準等倍マクロ(マイクロ)だ。
1990年代のAFレンズだが、ベースとなったMFレンズが
昔(1960年代)からあり、55/3.5→55/2.8と変化、
そして60/2.8でAF化された。
なお、Microのレンズ上での表記は時代で変わり、
だいたいだが、MF時代のものは「Micro-NIKKOR」
AF時代のものは「MICRO NIKKOR」と記載してある模様だ。
(注:これはNIKONの公式WEB上での表記とは異なる。
NIKONイメージングのサイトは、旧製品等における記載、
つまり大文字・小文字・ハイフンの区別が正確では無く、
引用するほどの信憑性が無い。私の場合では、所有する
実機(カメラやレンズ)を参照し、そこにある記載を
”ホンモノ”として引用する事にしている)

1つのメーカーだけ特定の呼び名を使うのは好ましく無い
と良く本ブログでは書くのだが、この「マクロ」に限っては
ニコンの「マイクロ」の呼び方が本来の意味的に正しい。
「マクロ」では、「巨視的」という日本語に置き換え
られ、マイクロ(またはミクロ)の「微視的」とは
ほとんど反対の意味だ。
他には、大きい、長い、大規模という意味もあるが、
コンピューター用語では、複数の操作をまとめた処理を
自動化する際も「マクロ」と呼ばれる事がある。
(例:エクセルでのマクロ処理等)
まあ、普通に考えれば「マイクロ」が正解であろう。
だがまあ、間違った意味であっても、ここまでカメラの
世界では一般化してしまったので、もう「マクロ」と
呼ばさるを得ない。
ちなみに、Macroと英語では書くが、ツァイスレンズ等
では独語で「Makro」と書かれている。
さて、本レンズの最短撮影距離は21.9cm、勿論等倍だ。
描写特徴としては、ボケ質がやや固く、その替わり
ピント面の解像度が高い事だ。
これは、これ以前のAi型番等のMFマイクロレンズ
(55/3.5,55/2.8)では、さらにその傾向が顕著であり、
立体物の撮影には向かず、ほとんど「平面マクロ」という
状況であった。
この理由は、本ブログでは何度も述べているが、簡単に
言えば、1970年代では、まだコピー機が普及しておらず
その時代のマクロレンズは文書や図面などを写真で撮って
平面的に複写する目的に使われていたからである。
本AiAF60/2.8の時代1990年代ではコピー機があるので、
マクロレンズは、より一般的な描写傾向(例えば、花や
人物などを撮影しても背景ボケが柔らかくできる)に
改められてきている。が、本レンズでは、まだその
旧来の描写傾向が若干残っているのだ。
(注:まあ、急に特性を変えると、旧型のユーザー層から
「新型に買い換えたら写りが甘くなった」等のクレーム
が生じるかも知れない事を避ける処置であろう。
歴史とブランド力のあるメーカーの市場戦略上では、頭が
痛いところだと思う。でもユーザー側も、もっと理解力
を高めないとならない。マニア的な視点から言えば、
本レンズに限らず、様々な撮影機材の「買い増し」は
良いが「買い替え」は避けるべきであろう。全ての要素で
新型機材が旧型機材よりも優れている保証は無いからだ)
まあつまり、本レンズの特性を良く理解して、被写体や
背景を選んで使うのが良いレンズである。と言う事だ。
他の特徴としては「露出(露光)倍数」がかかる事だ。
「露出倍数」とは近接撮影で見かけ上のF値が低下する
事であるが、実は、原理的には、ほとんどのマクロ
レンズでそれは起こる。で、一般的には近接撮影をした
場合、同じ被写体の明るさ、同じF値でもシャッター速度が
低下していく(またはAUTO ISOの感度が上がっていく)
だが、本AiAF60/2.8の場合は、近接撮影時に、例えば
開放F2.8で撮っていても、F値の表示が3.3等に落ちる。
これは特にF値を落として表示する必要性は少ないのだが、
こういう表示方式の方が光学原理的にはわかりやすい。
まあ、ずいぶん生真面目に作ったレンズであるという事だ。

回避すれば特に問題無いものの、コスパが悪い事は弱点だ。
まあ、1990年代に、比較的高価に買ってしまったのは
私の問題ではあるが、後年でもニコンというブランド故に
中古相場があまり下がらず、ずっと高値傾向だった。
他社の標準マクロに比べて、割高感が強く、それ故に
前述のように、ニコン機の初級ユーザーには、本レンズ
では無くSIGMA製の標準マクロを薦めていた訳だ。
現代においては、ニコンからはAPS-C機専用のエントリー
マクロとして、本AiAF60/2.8と同じ換算画角となる
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm/f2.8G が発売されている。
そのレンズはあいにく未所有なので詳細はわからないが、
若干安価なので、ニコンAPS-C(DX)機ユーザーであれば、
そちらを検討するのも良いかも知れない。
(追記:記事執筆後に入手済み。別記事で紹介予定だが、
簡単に言えば、本AiAF60/2.8のスケールダウン版の
ジェネリックレンズであり、描写傾向はそっくりだ)
---
では、5本目のマクロ。

レンズ購入価格:10,000円(中古)
使用カメラ:KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第68回記事で紹介の
1980年代のAF標準ハーフマクロ。
この時代には珍しく、最大撮影倍率1/2倍に性能限定
されたAFマクロだ。
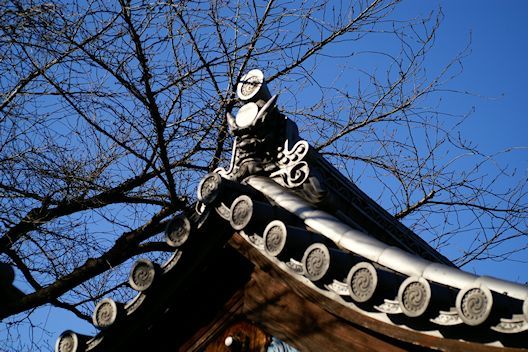
と併売されていたのだが、仕様が近く、何故両者が同時に
ラインナップされていたのか? 理由が良くわからない。
もっとも、銀塩MF時代の(New)MDマクロでは、本レンズと
同じく50mm/F3.5で1/2倍仕様であったので、そのレンズの
AF版と言う事で発売されたのかも知れない。
(注:レンズ構成等はAF版とMF版では大きく異なる。
ただし、描写傾向はMF版とは若干似ている模様だ。
MF版は次回記事で紹介予定)
なお、本レンズが1/2倍である事だが、これはフルサイズ
換算での話だ、よってAPS-C機では0.75倍、μ4/3機では
1倍となるので、こういう用法であれば、”寄れない”
という不満は殆ど無い。
ちなみに最短撮影距離は約23cmとなっている(小数点以下の
数値は不明)ので、他の等倍マクロの20cm前後と大差は無い。
また、ミラーレス機あるいはSONY αフタケタ一眼レフ機では、
デジタル拡大機能を用いる事で、さらに見かけ上の撮影倍率を
上げられるので、1/2倍である事のデメリットは実は殆ど無い。

まあ普通に良く写るが、感動的、という要素は全く無い。
ボケもやや固く、破綻の回避作業が必須となるだろう。
なお、発色が濃くてDレンジが低く感じるのは、今回の
母艦α-7 DIGITALは、2004年製と、デジタル一眼レフ
最初期の非常に古い機体であるからで、当時のデジタル
技術的な課題だ。(まあ、これはこれで面白い)
本レンズは、ミノルタで言うN型(ピントリング約8mm幅)
のみの発売で、他のバージョン(前期型や後継D型)は
存在しない。
現代の中古相場は、数千円と安価であるが、兄貴分の
F2.8版の初期型とあまり変わりは無いので、全ての点で、
F2.8版を買った方が有利であるように思える。
・・であれば本レンズの購入意義は少ないのであるが、
私の場合は単純に、このF3.5版がF2.8版と何処が違うのか?
という好奇心で購入したに過ぎない、まあ、あくまでマニア
向けのレンズであり、通常のα(A)ユーザー層においては、
各時代でのF2.8版の購入を推奨する。
---
では、今回ラストのマクロ。

レンズ購入価格:22,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarrkⅡ Limited (μ4/3機)
アダプターは、OLYMPUS MMF-2(4/3→μ4/3電子式)
特殊レンズ・スーパーマニアックス第2回記事で紹介の
2003年発売のフォーサーズ用の1/2倍AFマクロレンズ。
4/3またはμ4/3機に装着時の画角は100mm相当となるが
実焦点距離を元に本カテゴリーに分類している。
また、本カテゴリー中、本レンズのみ、デジタル時代に
なってから新しく発売された製品である。

本レンズを詳しく紹介しても、あまり意味を持たないかも
知れない。
ただまあ幸いな事に、電子アダプターを介して、現代の
μ4/3機でも、あまり不便を感じずに使用できる。
その際の制限事項は、AF速度、AF精度がやや落ちる事だが、
まあ、使用する母艦との相性もあるかも知れない。
私の感覚では、OM-D E-M5Ⅱで使うよりも、OM-D E-M1
での利用が、やや快適だ。(後者は像面位相差AF搭載)
本レンズの長所であるが、解像感とかボケ質に優れる
事である。この点では「マクロのオリンパス」の名に
恥じない。
弱点は、逆光耐性が低く、かつコントラストの低下が
甚だしい。軽いカビやクモリ等の様子もなく、こういう
描写特性なのだと思われる。毎回きちんとフードを装着し、
かつ、光線状況に留意して撮る必要がある。
また、カメラの電源をOFFすると、ピントリングが空回り
してしまうので、マクロ域の近接撮影をしていて、鏡筒が
伸びている状態で電源を切ると、レンズが伸びたまま
戻らなくなる、電源OFFの前に、都度、無限遠を撮るとか
MFでレンズを戻してから電源を切るのは煩雑な操作だ。

規格仕様上の課題であり、本レンズに限らない。
でも、他の4/3レンズは、鏡筒が伸びっぱなしになる
ようなものは少ないのだが、本レンズはマクロなので
鏡筒長の変化が大きく、電源ON/OFF時で問題となる。
また、一部の一眼レフ用レンズにも同様にレンズ内
モーターが電源OFFで動かない仕様のものがあり、
(CANONの初期USM、同、近代のSTM、SIGMAでの
非HSM仕様のレンズ等)それが、ヘリコイド(鏡筒)が
伸びるマクロレンズであった場合は結構面倒な課題となる。
まあでも、現代において、今更4/3システムを使ったり
4/3レンズを買うのは、かなり酔狂な話であろう・・
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Hブロック「AF50mm Macro」の記事は終了だ。
次回の本シリーズ記事は、
予選Iブロック「MF50mm Macro」となる予定だ。