本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に
紹介している。
今回の記事では、デジタル一眼レフ用の「エントリーレンズ」
を4本紹介しよう。
なお、内1本は、厳密にはエントリーレンズとしては
カテゴライズしにくいが、その件は理由があり、後述する。
----
まず、最初のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズは、SONY DT 50mm/f1.8 SAM (SAL50F18)
(中古購入価格 9,800円)(以下、DT50/1.8)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
最初に、「エントリーレンズとは何か?」であるが、
簡単に言えば「交換レンズ市場での販売促進を狙った
お試し的要素の強い安価なレンズ」であるのだが、
その詳細の説明は、意外に長くなるので割愛する。
例えば「匠の写真用語辞典第9回記事」に詳しいので
さらなる興味があれば参照されたし。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
エントリーレンズ(ここでは一眼レフ用を指す)は、
2010年前後に各社から集中して発売されてる。
この時代は、スマホやミラーレス機の急激な台頭により、
一眼レフや交換レンズ市場が喰われる事を危惧しての、
「囲い込み戦略」であった事だろう。
まあ、カメラ以外の、あらゆる市場分野でも「お試し版」
戦略は行われているので、極めて正当な市場戦略だ。
しかし、実際にエントリーレンズが一眼レフ交換レンズ
の販売促進に繋がったかどうかは不明だ、・・というか、
その効果を定量的に調べるのも難しかったに違い無い。
そうこうしているうちに、2013年前後にはミラーレス機
の販売数もピークに達し、一眼レフ用交換レンズ市場は
大きく縮退し、エントリーレンズ戦略よりも、もっと
「ドラスティックな改革」を迫られるようになった。
この時代から各社が始めたのは、「高付加価値化戦略」
である、これまでの交換レンズとは次元の異なる高性能を
提示し(注:それは実際の性能というよりも、ユーザーに
”非常に高性能だ”と思ってもらい、欲しくなってもらう、
という要素も多々含まれていると思う。
例えば、広角レンズに手ブレ補正はいらないし、マクロ
レンズに超音波モーターは必要ない。無駄な機能なのだ)
・・で、それらを付加価値として、製品価格も高価として、
販売数の減少を利益率でカバーしようという戦略である。
まあ、ユーザーから見れば”実質値上げ”の状況は、
たまった物ではないが、それでメーカー側は、なんとか
レンズ市場を維持できる訳だし、そして「高い!」と文句を
言いながらも、そうした「高付加価値型レンズ」は、やはり
旧製品よりは描写性能面等の優位性がある事は確かだった。
で、現代ではエントリーレンズは、そうと明確に定義できる
商品は殆ど無くなってしまった。結局のところ、安価な
レンズを売っても儲からないからであり、高額商品で、
もっと直接的に利益を得られる戦略を重視したからであろう。
(注:ミラーレス機用では、まだ何本かは存在している。
なお、近年の安価な海外製レンズはエントリーレンズでは無い、
それを売っても、次に繋げるべき自社カメラ等が無いからだ)
さて、そんな市場状況であるが、そのこと自体の是非は
問う必要は無いと思う、そうしないと市場が維持できない
という切実な問題だし、それ(値上げ)が気に入らなければ、
「買わない」という選択肢は、あくまで消費者側に残されている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
状況説明が長くなったが、やっと本DT50/1.8の紹介
に入る。
2009年に発売された、APS-C機専用標準(中望遠画角)
単焦点エントリーレンズである。
最大の特徴は安価である事。
発売時定価は22000円+税である、これでも十分安価だが
新品値引きもあったし、中古は、およそ1万円程度で
相場が推移し、現代では、8000円程度の価格帯だ。
まあ、典型的な「お試し版価格」である。
さらなる長所だが、最短撮影距離が34cmと、とても短い。
一般的な50mm標準レンズの大多数が、最短45cmである
事と比較すると、10cm以上も余分に寄れて撮影でき、
この状態で、最大撮影倍率は1/5倍となる。
さらに、近年のSONY α一眼レフに備わる、「スマート
テレコン機能」を用いれば、0.4倍と、だいたい準マクロ
レンズ並みのスペックとなるのだ。
それから、有限回転式ピントリングで、かつ距離指標も
存在する為、MF操作性に優れる。これは近接撮影時には
特に有効であろう。
なお、SAM(スムースAFモーター)仕様でありながらも、
α77Ⅱ等に備わるDMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)
機能が利用でき、AFからMFへのシームレスな移行が可能だ。
ただし、今回使用の母艦α65は、残念ながらDMF機能は
非搭載だ。
「では何故α77Ⅱを使わないのか?」という点だが、
DMFでMFに移行しても、α77Ⅱではピーキングが自動では
出ない。ピーキングを出すには、本DT50/1.8のレンズ側
切り替えスイッチで、AFからMFに切り替えないとならない。
・・であれば、操作系の問題でDMFの優位性が少しだけ
損なわれてしまい、α77Ⅱとの組み合わせは効率的な
システムでは無い。よって本記事では、DMFを持たない
α65を使用している訳だ。
α65であれば、「最初からMFで使う」と割り切れるし、
その際にも勿論ピーキングは出る。
まあ、MFがちゃんと使える仕様である事は幸いであり、
例えば本レンズを、マウントアダプターを介して、
APS-C型以下のミラーレス機で使用する事も可能だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21091316.jpg]()
弱点だが、まず非常に安っぽい作りである事だ。
だが、所有満足感が少ない事は、逆に、非常に過酷な
撮影環境等で、「壊しても惜しくない」レンズとして
使う事も可能であり、そういう「消耗用途」には適正だ。
それから、あまりスペシャルな描写力は持っていない事も
弱点であろうか。ただこの点は、近接撮影に持ち込んだり
あるいは必要とあればエフェクトもかけて、描写力の低さを
「うやむやにしてしまう」という回避法が存在する。
現代、SONYαの一眼レフ(Aマウント機)は、縮退の
一途であり、SONYの主力は、FEマウントのミラーレス機
α7/9系となっている状況だ、しかしながら、本記事で
母艦としているα65(デジタル一眼第13回記事)や、
α77Ⅱ(同第18回記事)は、高機能で、なかなか優れた
機体であるし、中古相場も下がっていて買い易い。
ミラーレス機ばかりに目を囚われず、こうしたAマウント
機で、本レンズのような安価で高性能のレンズを上手く
活用すれば、α7系でシステムを組む場合の、数分の1から
十数分の1の低廉なコスト投資でシステム構築が可能だ。
それは勿論「フルサイズ機でなくっちゃ嫌だ!」などと
言うビギナー層を対象とした提案ではなく、あくまで
「良くわかっている中上級層向け」の話である。
----
では、次のエントリーレンズ
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21094634.jpg]()
レンズは、NIKON AF-S DX NIKKOR 35mm/f1.8G
(中古購入価格 18,000円)(以下、DX35/1.8)
カメラは、NIKON D300 (APS-C機)
2009年に発売された、APS-C機(DXフォーマット)用
準広角(標準画角)エントリーレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21094645.jpg]()
ニコンでは、これ以前には、DX機専用単焦点レンズは
(魚眼レンズを除き)発売されていなかった。
その頃、2009年においては既にFX(フルサイズ機)も
色々と発売されていて、普及しかけてきた時代なのに、
「何故今更のDX専用レンズの発売?」とも、当時は思った
のであるが、実は、この直前の2008年には、初のμ4/3機
であるPANASONIC DMC-G1が発売されている。
将来的にミラーレス機市場が伸びてきて、一眼レフ市場が
喰われる事を警戒しての、本DX35/1.8の発売であれば、
まあ、これこそ近年のエントリーレンズ戦略の「先駆け」
とも言えるレンズであろう。
ちなみに、発売時定価は33,400円(+税)と、エントリー
レンズとしては高価であるが、殆どの商品が「高価すぎる」
ニコン製レンズにしては、かなり安価な部類だった。
つまり、「ニコンには、こんな風に、安価でも良いレンズ
があるんだよ、ミラーレス機なんかに興味を持たず、
ニコンのレンズを買いなさい」という「囲い込み戦略」である。
そうやって、上手く「こっちの世界」に誘導してしまえば
後は、より高価な交換レンズや、新しいNIKON一眼レフを
買って貰えれば良い。そうして、ある程度システムが揃って
きたら、もう今更、μ4/3機やNEXに買い換える筈も無い
だろうと・・ まあ、そういう市場戦略である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21094608.jpg]()
・・さて、本DX35/1.8の長所だが、
まずは、作りが良い事があげられる。
他社エントリーレンズのように、プラスチッキーな
安っぽさは一切なく、NIKON高級レンズと質感は大差無い
ようにも思える。
仕様的にも、あまり手を抜いていない。
SWM(超音波モーター)搭載、そしてM/Aモード(マニュアル
優先AF)では、シームレスなMF移行を実現する。
レンズ構成は、6群8枚。内1枚が非球面と、手を抜いては
おらず、描写力もそこそこ良い。
つまり、エントリーレンズであっても「仕様的差別化」は
最小限である、という事だ。
ニコンは一眼レフでは、ハイエンド機から、上級機、
中級機、普及機と、ラインナップが下位になるほど、
「仕様的差別化」が、はっきりと行われている事が特徴だ。
つまり、上位機種と見比べると、下位機種には必ず
見劣りする性能や仕様があって、物足りなく感じる。
これはまあ、ユーザーの目線を、上へ上へと誘導し、
少しでも高級で高価な一眼レフを買って貰いたいが為の
ラインナップ戦略であり、高付加価値型のメーカーで
あれば当然の措置であろう。(ただし、少々度が過ぎる)
殆ど全てのビギナー層は、「カメラ性能が不足すると
良い写真が撮れない」と大きな誤解をしているか、又は
「自分自身のスキルが低いから、高性能なカメラで無いと
良い写真が撮れないで周囲にバカにされる」と恐れていて、
「どうせ買うならば良い(高い)方を買おう」と、
どんどんと高級機に目がいくようになるからだ。
(この結果、近年では最新高級ニコン機を買うのは、
見事に、ビギナー層ばかりになってしまった)
まあ、だからこそ、このエントリーレンズDX35/1.8に
おける「仕様的差別化」の少なさは特筆するべき点なのだ。
弱点は特に無い。最短撮影距離が30cmと標準的で
あるとか、スペシャルと言う程の感動的な写りでは無い、
といった点はあるが、これらは欠点とも言えないであろう。
中古相場であるが、私の購入時(2016年頃)には、まだ
若干高価であった。
が、その後、2017年頃には一時的にさらに相場が上がり、
2万円台前半位にまで高騰したが(投機が入ったのか?)
さらにその後、2018年頃には、ガクンと相場が下がり、
現在では1万円台前半と、比較的安価な価格帯となっている。
(注:同様に、他のDX単焦点も相場が下がっている)
この相場の変動は直接的には理解不能だが、例えばニコンは、
この時代(2010年代後半)より、フルサイズ機を主力製品と
するようになってきた為であろうか? まあ、フルサイズ機
に本DX35/1.8を装着しても、単にクロップされるだけで
何ら問題なく使えるので、実質的には、本レンズを手放す
理由が見当たらない。
しかしながら、例によってニコン高級機の主力ユーザー層は
シニア層とかビギナー層が大半だ。
「FXとDXの、ボディとレンズの組み合わせの可否」について
あまり良くわかっていない人が大多数であり、例えば
「FXと書いてあるレンズを買いたいが、今持っている(DXの)
カメラをフルサイズに買い換えないとならないか?」という
何も基本原理がわかっていない質問を良く聞く。あるいは逆に
新たにフルサイズ機を買ったので、これまでの(DX)レンズは
「すべて使えない」と思い込んで、それらを処分してしまう。
そして、多少わかっていたとしても、FX機にDXレンズを
装着し、クロップされた状態で記録画素数が減る事に対して、
「画素数が下がったら、画質が落ちるじゃあないか!
そんなレンズはいらんよ!」と考えてしまうのだ。
まあ、画質とかは、実際にはそんな単純な話ではなく、
こういう考えは、あまりにレベルの低い話だが、それが現実に
おけるニコン高級機ユーザー層の実態なのだ。
まあ良い、そうやって、何もわかっていないユーザー層が
せっせと中古市場に本DX35/1.8や他のDXレンズを放出して
くれるのであれば、わかっているユーザーは、とても買い易く
なったそれらを安価に購入すれば良い、ただそれだけだ。
それに、「APS-C用レンズをフルサイズ機でも使える」
と言う事自体が、すいぶんとマシな話なのだ。
他社、例えばCANON EOSであれば、APS-C用のEF-Sレンズ
は、フルサイズEOSには装着不能だ。
(マウント部の形状を異ならせて、物理的に装着出来ない
ようになっている)
こういう状態だと、例えばAPS-C型のEOS(例:EOS 80D)
を使っているユーザーが、お金を貯めてフルサイズEOS
(例:EOS 6D MarkⅡ)に買い換えたら、それまで使っていた
EF-S型のレンズは全て使用不能になってしまうのだ、
これは、ずいぶんと理不尽な話であろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21094637.jpg]()
本DX35/1.8は、悪く無いエントリーレンズである。
そして(同様に)フルサイズ機人気により、安価になった
ニコンDX機中級機等を中古で買って装着すれば、ニコン
システムとしては、再強のコスパになるだろう。
例えば、今回母艦として使用しているD300(2007年)は
当時の高級機(DXのハイエンド機)であるが、現在の
中古相場は、1万円台後半と、二束三文だ。
つまり、今回使用のシステムは、合計3万円程度で
組めるという事になる、かつてのDXハイエンド機なので
性能的な不満は一切無い。ビギナー層が、その10倍以上も、
お金をかけてシステムを組んでいるの横目で見ながら
D300の高速連写性能で、気分良く撮影できる事であろう。
----
では、3本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21103396.jpg]()
レンズは、CANON EF50mm/f1.8 (初期型/Ⅰ型)
(中古購入価格11,000円)(以下、EF50/1.8)
カメラは、CANON EOS 7D (APS-C機)
1987年に発売された、AF単焦点小口径標準レンズ。
ただし、本レンズは「エントリーレンズ」では無い。
単に銀塩EOS機の発売に合わせて用意された標準レンズだ。
しかし、銀塩EOSのEFマウントは、それまでのFDマウントを
ばっさり切り捨てて変更された新マウントだ、その当時の
FDユーザー層における不満は極めて大きかった。
・・であれば、CANONとしては、この時代であっても、
「ユーザー層をEOSに囲い込み」しなくてはならない。
さもないと、特に機嫌の悪い旧キヤノンFD党は、皆が、
「ミノルタα」やら「NIKON F4」に乗り換えてしまう
かもしれないし、新規ユーザーもそちらに流れてしまう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21103885.jpg]()
そこで、本レンズを僅か3年で、ディスコン(生産中止)
として、大幅にコストダウンした「EF50mm/f1.8Ⅱ」を
1990年に発売する。このⅡ型が、私の定義するところの
「史上初のエントリーレンズ」である。
CANONの戦略はドンピシャに的中する。EF50/1.8Ⅱは
実売1万円以下で買えるレンズであり、ビギナー層等が
ビ「安いので試しに買ってみたら、びっくり! とても良く
写るレンズはないか。これだったら、高価なLレンズは、
いったいどんな素晴らしい写りになるのだろう?
よし、お金を貯めて、Lレンズを絶対買うぞ!」
となった訳だ。
まさしく、マーケティングのお手本通りの筋書きだ・・
近年、とある化粧品の「試供品」の話を、あえてTV CMで流し、
「当社では試供品でも一切品質を妥協しません」という主旨で
宣伝していた例がある。
でもまあ、これは当たり前の話であり、試供品で手を抜いて
いたら、それを入手してがっかりしたユーザー層は、二度と
そのメーカーの商品を買わなくなってしまう。
だから、必ず試供品やエントリーレンズは高品質・高性能で
なくてはならない。これはごく基本的な市場原理だ。
EF50/1.8Ⅱは、その後、何と25年間の超ロングセラーとなり、
やっと近年、2015年になって後継レンズのEF50/1.8STMに
リニューアルされた。(注:その後継レンズの発売も、
コピー品の流通等に係わるダークな裏事情があると推察される
のだが、その話の詳細は、現状、推測の域を出ないし、勿論
本記事とは無関係なので割愛する。けど、その件が無ければ、
EF50/1.8Ⅱは、販売が継続されていたかも知れない・・)
で、その25年の間、ずっとEF50/1.8Ⅱはビギナー層から
「神格化」される程に、定評と人気があった訳だが・・
まあ、その件については、
*他社の、どの5群6枚変形ガウス構成型のMF/AFの
50mm/f1.8級レンズも、たいてい非常に良く写る。
(というか、50mm/f1.4級よりも、むしろ高性能だ)
別に、EF50/1.8系だけが優れている訳では無い。
単に、他社の同等レンズの事を知らないだけの話だ。
(参考:別シリーズ「最強50mm選手権」記事を参照)
*エントリーレンズという市場戦略が存在する。
(これらを「良心的価格」だと勘違いしていると、
後で高いレンズを まんまと買わされてしまう)
の、「2つの要点を知らないビギナー層」による過剰評価だ。
そして私は、この「過剰評価」が極めて嫌いであった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21100639.jpg]()
EF50/1.8Ⅱは数十年も前から、常に中古市場に存在する。
相場も安価であり、いつでも7000円前後で購入できた。
けど、反面「絶対に買うまい」とも思っていた。
もし、EF50/1.8Ⅱを買って、それをカメラにつけて
写真を撮っていたら、撮影地などで他の初級マニア等から
初「そのレンズ、安いのに良く写りますよね~」
などと言われたら、このレンズのいきさつを、色々と
説明する訳にもいかず、応対に困ってしまう。
ましてや、
匠「いや、そんなに褒めるものでもないでしょう」などと
言おうものなら、
初「そんな馬鹿な! なんとか言うプロカメラマンの人も、
良いと言っていたし、誰もが認める良く写るレンズですよ」
などと反論されるだろう、が、そういう自分の意見では無い
言い方は、私はさらに嫌いなので、ますます気分が悪くなって
くる、そこで、
匠「なんとか言うカメラマンの評価? 他人の言う事を鵜呑みに
しているのですか? じゃあ、貴方はどう思うのですか?
ご自身の、このレンズに対する意見をお聞かせ下さい!」
・・下手をすれば、そこからエスカレートして大喧嘩だ(汗)
まあ、上記は、本ブログでは珍しく完全なフィクションの
内容だが、十分すぎるほど有り得る話だ。
「神格化」による「信仰」は重症であって、他人からの
意見を受け付ける事はない、何を言っても無駄なのだ。
まあつまり、そのEF50/1.8Ⅱは、変に有名であるが故に、
思い込みや誤解も多々あって、面倒くさいレンズなのだ。
だが、このEF50/1.8Ⅱを、ずっと無視しつづける訳にも
行かない。一応、1993年発売のEF50/1.4USMをずっと
使ってはいるが、そのレンズは、コスパが悪くて好きな
レンズでは無い。どう考えてもEF50/1.8Ⅱの方が遥かに
コスパが良いので、自身の好みには合う筈なのだ。
でも、変に面倒なレンズだ、出来れば買いたくは無い。
そこで私が考えたのは、「レアなEF50/1.8初期型(Ⅰ型)
を、なんとか見つけて入手する」という解決策であった。
初期型は発売期間が短く、価格もⅡ型よりもずっと高価で
あったので、不人気でレアなレンズだ。その代わりⅡ型
よりも、ずいぶんと作りが良く、距離指標もついている。
ただ、これが、やはりなかなか見つからない・・
たまに見かけても、レア品として2万円以上の高額相場だ、
さすがに、中身が同じレンズであるⅡ型の3倍ものコストは
支払えない、「それだったら、EF50/1.4USMのコスパの
悪さと、たいして変わらないではないか・・」と。
・・で、その状態が十数年間も続いた(汗)
近年、2010年代になって、やっと11,000円という妥当な
金額のEF50/1.8初期型を見つけて購入した次第だ。
本レンズEF50/1.8初期型は、厳密にはエントリーレンズ
ではない、しかし、初のエントリーレンズであると言える
EF50/1.8Ⅱ型の元祖のレンズである。こちらの初期型の
歴史的価値も、Ⅱ型と同様に高いのではなかろうか・・?
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21100666.jpg]()
さて、最後に余談だが、EF50/1.8Ⅱ型(1990年)の
「お試し版戦略」が、ズバリとハマったCANONでは、
レンズのみならずカメラにおいても、同様の市場開拓や
販売促進を意識して製品企画を行うようになった事だろう。
それが、恐らくは1993年の「EOS Kiss」の発売と、その
大成功に繋がったのだろう、と認識している。
バブル経済崩壊後の消費者価値観の変化と「EOS Kiss」
の発売タイミングは、これもまたドンピシャとハマった。
ファミリー層や女性層に「EOS Kiss」は受け入れられ
CANONは新たな市場開拓に成功した。
しかし、成功しすぎたかもしれない・・
1993~1999年頃の期間、一眼レフ界では「EOS Kiss」を
除き、ヒット製品は殆ど生まれていない。・・というか、
魅力的な機種が全くと言っていい程出てこなかったのだ。
マニア層等では「もう、EOS KissしかAF一眼レフが無いので
あれば、古いMF機を探して買おう」という心理に皆が一斉に
傾いてしまい、この時代は空前の「第一次中古カメラブーム」
となった訳だ。
その歴史が良かったのか、悪かったのかは良くわからない。
でもまあ、その「カメラバブル期勃発!」の、遠い原因と
なった製品が、もしかすると本EF50/1.8であったのかも
知れない訳だ(まあ、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な
遠因ではあるが・・)
----
では、今回ラストのシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21112301.jpg]()
レンズは、smc PENTAX-DA 35mm/f2.4 AL
(中古購入価格14,000円)(以下、DA35/2.4)
カメラは、PENTAX K-30 (APS-C機)
2010年発売のAPS-C機用標準画角エントリーレンズ。
AL型番は、非球面(アスフェリカル)レンズを採用
している、という意味だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21112311.jpg]()
PENTAXは、この当時、HOYAの傘下となっていた。
他社と同様、この時期のPENTAXも「エントリー戦略」
を行ったのだが、PENTAXの場合は、さらに顕著だった。
まず、デジタル一眼レフであるが、低価格帯の機種の
性能を向上。その代表格は、K-r(2010年、未所有)
であるが、最高ISO25600、連写毎秒6コマと、中級機
並みのスペックだ。
加えて、カメラボディやレンズに「オーダーカラー制」
を実施。ボディでは2色のコンビネーションにより、
100を超える組み合わせの配色が選べた。
また、本DA35/2.4レンズも同様に12色から選べる。
(注:PENTAXの親会社がHOYAからRICOHに変わった
数年後に、この「オーダーカラー制」は終了している)
そしで、ミラーレス機としてPENTAX Qシリーズ(2011年~)
および、PENTAX K-01(2012年)を発売。
続くQ10(2012年)ではオーダーカラーが可能になった。
それから、この時期はPENTAX機においては、ゆるキャラ、
歌手、アニメ等とのコラボ商品も色々と発売されている。
こうした徹底的なエントリー層向けの市場戦略により、
スマホやミラーレスの台頭を跳ね除けて、HOYA時代の
PENTAXは好調であったと聞く。
まあ、タイミングが良かったのかもしれない。他社は
この時期、スマホやミラーレスとの直接の勝負を避け
高付加価値化戦略に転換しつつある時代であった。
それは、さらなる高性能化と価格上昇も意味する物で
あるから、PENTAXの普及機種は、そこそこの性能ながら
割安感があり、コスパが良く感じられたのだと思う。
ただまあ、この期間、デジタル一眼レフ高級機の方は
ほとんどK-5(2010年)系列のみで支えていた状況であり
そちら(高級機)の戦略までは、手が回っていなかった
のではなかろうか・・?
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21113635.jpg]()
その後、PENTAXはRICOHの傘下になり、HOYA時代の
市場戦略が終わりつつあった2013年頃からは、
(注:今回使用の母艦K-30(2012)は、RICOHの傘下に
なってからの直後に発売された機種だが、その製品
コンセプトも設計もHOYA時代のものを踏襲している)
RICOHの技術主導戦略が始まり、高級機もガラリと変化
するようになっていく。
さて、本レンズDA35/2.4だが、エントリーレンズであり、
価格が安価、そしてデザインも良く、おまけに12色から
選ぶ事が出来る(注:2017年末まで出来た)
APS-C機専用単焦点で小型軽量、そこそこの描写力と
そこそこの性能、例えば開放F値(F2.4)、最短撮影
距離(30cm)、非球面レンズ使用(AL)と、まあ、
スペック的には優れていると言える。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21113601.jpg]()
ただ、ちょっと気になるのは逆光耐性の低さだ。
本レンズの数年後に発売された新型のHDコーディング
のレンズと比べて劣るのはやむを得ないのだが、
smcコーティング自体も、約40年間も続く、こなれた
技術であり、完成度が高い。
他の様々なsmc型レンズにおいては、これまであまり
逆光耐性について問題と思った事は無いので、
本レンズの課題が、余計に目につく。
ちなみに、同社の同様のエントリーレンズである
「smc PENTAX-DA 50mm/f1.8」も、逆光耐性が低く
感じる為、これらの廉価版レンズでは、何らかの
コストダウンが図られているのであろうか・・?
なお、逆光耐性が低い為にフードを装着したいのだが、
ここもコストダウンの弊害で、フードは別売である。
しかも、フードは恐らく黒色版しかないので、本レンズを
オーダーカラー品で買った場合、デザインがマッチしない。
あれこれと微妙に不満点があって、ちょっとクセがある
レンズではあるが、まあ、PENTAX機ユーザーであれば
持っていても悪く無いレンズだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_21114102.jpg]()
さて、エントリーレンズの総括であるが、2010年頃から
2015年頃にかけ、各メーカーから、2~3本づつつの
発売がある。中には未だ現行商品であるものも多いが
ただでさえ定価も安価な上に、長期間発売されている事で
さらに新品・中古とも安価になっていて、どのレンズも
1万円以下から高くても1万円台前半で中古入手可能だ。
エントリーレンズは、元々の基本性能に優れる。
その上安価であるから、とてつもなくコスパが良い。
細かい弱点を持つレンズも多いが、それは承知の上で
回避しながら使えば何ら問題の無いレンズばかりだ。
メーカー純正エントリーレンズは、「全て買い」と
思って間違い無いであろう。
エントリーレンズの、市場での「からくり」さえ理解
してしまえば、その後、コスパの悪い純正高級レンズを
買う必要は無い。高級レンズはメーカーが利益を確保
する為の手段であり、ファーストフード・ハンバーガー
店での、ポテトや限定企画バーガーと同じ位置づけだ。
それらは利益を得る為の商品なのだ。
だから、低価格帯ハンバーガー(エントリーバーガー?)
を単品で買うならば、さほどコスパは悪くならない。
「ポテトもいかがですか?」と、高付加価値型の商品を
美人の店員さんに薦められても(汗)強大な意思を持って
「いりません」と答えれば良いだけである。
それと同様に「エントリーレンズ」も単品で買って、
高級レンズを無視すれば、それで良いわけである。
消費者側がお買い得な商品だけを買っても、販売側は
文句の言い様が無い。
----
さて、今回の記事「エントリーレンズ特集」は、
このあたり迄で、次回記事に続く・・
紹介している。
今回の記事では、デジタル一眼レフ用の「エントリーレンズ」
を4本紹介しよう。
なお、内1本は、厳密にはエントリーレンズとしては
カテゴライズしにくいが、その件は理由があり、後述する。
----
まず、最初のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 9,800円)(以下、DT50/1.8)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
最初に、「エントリーレンズとは何か?」であるが、
簡単に言えば「交換レンズ市場での販売促進を狙った
お試し的要素の強い安価なレンズ」であるのだが、
その詳細の説明は、意外に長くなるので割愛する。
例えば「匠の写真用語辞典第9回記事」に詳しいので
さらなる興味があれば参照されたし。
Clik here to view.

2010年前後に各社から集中して発売されてる。
この時代は、スマホやミラーレス機の急激な台頭により、
一眼レフや交換レンズ市場が喰われる事を危惧しての、
「囲い込み戦略」であった事だろう。
まあ、カメラ以外の、あらゆる市場分野でも「お試し版」
戦略は行われているので、極めて正当な市場戦略だ。
しかし、実際にエントリーレンズが一眼レフ交換レンズ
の販売促進に繋がったかどうかは不明だ、・・というか、
その効果を定量的に調べるのも難しかったに違い無い。
そうこうしているうちに、2013年前後にはミラーレス機
の販売数もピークに達し、一眼レフ用交換レンズ市場は
大きく縮退し、エントリーレンズ戦略よりも、もっと
「ドラスティックな改革」を迫られるようになった。
この時代から各社が始めたのは、「高付加価値化戦略」
である、これまでの交換レンズとは次元の異なる高性能を
提示し(注:それは実際の性能というよりも、ユーザーに
”非常に高性能だ”と思ってもらい、欲しくなってもらう、
という要素も多々含まれていると思う。
例えば、広角レンズに手ブレ補正はいらないし、マクロ
レンズに超音波モーターは必要ない。無駄な機能なのだ)
・・で、それらを付加価値として、製品価格も高価として、
販売数の減少を利益率でカバーしようという戦略である。
まあ、ユーザーから見れば”実質値上げ”の状況は、
たまった物ではないが、それでメーカー側は、なんとか
レンズ市場を維持できる訳だし、そして「高い!」と文句を
言いながらも、そうした「高付加価値型レンズ」は、やはり
旧製品よりは描写性能面等の優位性がある事は確かだった。
で、現代ではエントリーレンズは、そうと明確に定義できる
商品は殆ど無くなってしまった。結局のところ、安価な
レンズを売っても儲からないからであり、高額商品で、
もっと直接的に利益を得られる戦略を重視したからであろう。
(注:ミラーレス機用では、まだ何本かは存在している。
なお、近年の安価な海外製レンズはエントリーレンズでは無い、
それを売っても、次に繋げるべき自社カメラ等が無いからだ)
さて、そんな市場状況であるが、そのこと自体の是非は
問う必要は無いと思う、そうしないと市場が維持できない
という切実な問題だし、それ(値上げ)が気に入らなければ、
「買わない」という選択肢は、あくまで消費者側に残されている。
Clik here to view.

に入る。
2009年に発売された、APS-C機専用標準(中望遠画角)
単焦点エントリーレンズである。
最大の特徴は安価である事。
発売時定価は22000円+税である、これでも十分安価だが
新品値引きもあったし、中古は、およそ1万円程度で
相場が推移し、現代では、8000円程度の価格帯だ。
まあ、典型的な「お試し版価格」である。
さらなる長所だが、最短撮影距離が34cmと、とても短い。
一般的な50mm標準レンズの大多数が、最短45cmである
事と比較すると、10cm以上も余分に寄れて撮影でき、
この状態で、最大撮影倍率は1/5倍となる。
さらに、近年のSONY α一眼レフに備わる、「スマート
テレコン機能」を用いれば、0.4倍と、だいたい準マクロ
レンズ並みのスペックとなるのだ。
それから、有限回転式ピントリングで、かつ距離指標も
存在する為、MF操作性に優れる。これは近接撮影時には
特に有効であろう。
なお、SAM(スムースAFモーター)仕様でありながらも、
α77Ⅱ等に備わるDMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)
機能が利用でき、AFからMFへのシームレスな移行が可能だ。
ただし、今回使用の母艦α65は、残念ながらDMF機能は
非搭載だ。
「では何故α77Ⅱを使わないのか?」という点だが、
DMFでMFに移行しても、α77Ⅱではピーキングが自動では
出ない。ピーキングを出すには、本DT50/1.8のレンズ側
切り替えスイッチで、AFからMFに切り替えないとならない。
・・であれば、操作系の問題でDMFの優位性が少しだけ
損なわれてしまい、α77Ⅱとの組み合わせは効率的な
システムでは無い。よって本記事では、DMFを持たない
α65を使用している訳だ。
α65であれば、「最初からMFで使う」と割り切れるし、
その際にも勿論ピーキングは出る。
まあ、MFがちゃんと使える仕様である事は幸いであり、
例えば本レンズを、マウントアダプターを介して、
APS-C型以下のミラーレス機で使用する事も可能だ。
Clik here to view.

だが、所有満足感が少ない事は、逆に、非常に過酷な
撮影環境等で、「壊しても惜しくない」レンズとして
使う事も可能であり、そういう「消耗用途」には適正だ。
それから、あまりスペシャルな描写力は持っていない事も
弱点であろうか。ただこの点は、近接撮影に持ち込んだり
あるいは必要とあればエフェクトもかけて、描写力の低さを
「うやむやにしてしまう」という回避法が存在する。
現代、SONYαの一眼レフ(Aマウント機)は、縮退の
一途であり、SONYの主力は、FEマウントのミラーレス機
α7/9系となっている状況だ、しかしながら、本記事で
母艦としているα65(デジタル一眼第13回記事)や、
α77Ⅱ(同第18回記事)は、高機能で、なかなか優れた
機体であるし、中古相場も下がっていて買い易い。
ミラーレス機ばかりに目を囚われず、こうしたAマウント
機で、本レンズのような安価で高性能のレンズを上手く
活用すれば、α7系でシステムを組む場合の、数分の1から
十数分の1の低廉なコスト投資でシステム構築が可能だ。
それは勿論「フルサイズ機でなくっちゃ嫌だ!」などと
言うビギナー層を対象とした提案ではなく、あくまで
「良くわかっている中上級層向け」の話である。
----
では、次のエントリーレンズ
Clik here to view.

(中古購入価格 18,000円)(以下、DX35/1.8)
カメラは、NIKON D300 (APS-C機)
2009年に発売された、APS-C機(DXフォーマット)用
準広角(標準画角)エントリーレンズ。
Clik here to view.

(魚眼レンズを除き)発売されていなかった。
その頃、2009年においては既にFX(フルサイズ機)も
色々と発売されていて、普及しかけてきた時代なのに、
「何故今更のDX専用レンズの発売?」とも、当時は思った
のであるが、実は、この直前の2008年には、初のμ4/3機
であるPANASONIC DMC-G1が発売されている。
将来的にミラーレス機市場が伸びてきて、一眼レフ市場が
喰われる事を警戒しての、本DX35/1.8の発売であれば、
まあ、これこそ近年のエントリーレンズ戦略の「先駆け」
とも言えるレンズであろう。
ちなみに、発売時定価は33,400円(+税)と、エントリー
レンズとしては高価であるが、殆どの商品が「高価すぎる」
ニコン製レンズにしては、かなり安価な部類だった。
つまり、「ニコンには、こんな風に、安価でも良いレンズ
があるんだよ、ミラーレス機なんかに興味を持たず、
ニコンのレンズを買いなさい」という「囲い込み戦略」である。
そうやって、上手く「こっちの世界」に誘導してしまえば
後は、より高価な交換レンズや、新しいNIKON一眼レフを
買って貰えれば良い。そうして、ある程度システムが揃って
きたら、もう今更、μ4/3機やNEXに買い換える筈も無い
だろうと・・ まあ、そういう市場戦略である。
Clik here to view.

まずは、作りが良い事があげられる。
他社エントリーレンズのように、プラスチッキーな
安っぽさは一切なく、NIKON高級レンズと質感は大差無い
ようにも思える。
仕様的にも、あまり手を抜いていない。
SWM(超音波モーター)搭載、そしてM/Aモード(マニュアル
優先AF)では、シームレスなMF移行を実現する。
レンズ構成は、6群8枚。内1枚が非球面と、手を抜いては
おらず、描写力もそこそこ良い。
つまり、エントリーレンズであっても「仕様的差別化」は
最小限である、という事だ。
ニコンは一眼レフでは、ハイエンド機から、上級機、
中級機、普及機と、ラインナップが下位になるほど、
「仕様的差別化」が、はっきりと行われている事が特徴だ。
つまり、上位機種と見比べると、下位機種には必ず
見劣りする性能や仕様があって、物足りなく感じる。
これはまあ、ユーザーの目線を、上へ上へと誘導し、
少しでも高級で高価な一眼レフを買って貰いたいが為の
ラインナップ戦略であり、高付加価値型のメーカーで
あれば当然の措置であろう。(ただし、少々度が過ぎる)
殆ど全てのビギナー層は、「カメラ性能が不足すると
良い写真が撮れない」と大きな誤解をしているか、又は
「自分自身のスキルが低いから、高性能なカメラで無いと
良い写真が撮れないで周囲にバカにされる」と恐れていて、
「どうせ買うならば良い(高い)方を買おう」と、
どんどんと高級機に目がいくようになるからだ。
(この結果、近年では最新高級ニコン機を買うのは、
見事に、ビギナー層ばかりになってしまった)
まあ、だからこそ、このエントリーレンズDX35/1.8に
おける「仕様的差別化」の少なさは特筆するべき点なのだ。
弱点は特に無い。最短撮影距離が30cmと標準的で
あるとか、スペシャルと言う程の感動的な写りでは無い、
といった点はあるが、これらは欠点とも言えないであろう。
中古相場であるが、私の購入時(2016年頃)には、まだ
若干高価であった。
が、その後、2017年頃には一時的にさらに相場が上がり、
2万円台前半位にまで高騰したが(投機が入ったのか?)
さらにその後、2018年頃には、ガクンと相場が下がり、
現在では1万円台前半と、比較的安価な価格帯となっている。
(注:同様に、他のDX単焦点も相場が下がっている)
この相場の変動は直接的には理解不能だが、例えばニコンは、
この時代(2010年代後半)より、フルサイズ機を主力製品と
するようになってきた為であろうか? まあ、フルサイズ機
に本DX35/1.8を装着しても、単にクロップされるだけで
何ら問題なく使えるので、実質的には、本レンズを手放す
理由が見当たらない。
しかしながら、例によってニコン高級機の主力ユーザー層は
シニア層とかビギナー層が大半だ。
「FXとDXの、ボディとレンズの組み合わせの可否」について
あまり良くわかっていない人が大多数であり、例えば
「FXと書いてあるレンズを買いたいが、今持っている(DXの)
カメラをフルサイズに買い換えないとならないか?」という
何も基本原理がわかっていない質問を良く聞く。あるいは逆に
新たにフルサイズ機を買ったので、これまでの(DX)レンズは
「すべて使えない」と思い込んで、それらを処分してしまう。
そして、多少わかっていたとしても、FX機にDXレンズを
装着し、クロップされた状態で記録画素数が減る事に対して、
「画素数が下がったら、画質が落ちるじゃあないか!
そんなレンズはいらんよ!」と考えてしまうのだ。
まあ、画質とかは、実際にはそんな単純な話ではなく、
こういう考えは、あまりにレベルの低い話だが、それが現実に
おけるニコン高級機ユーザー層の実態なのだ。
まあ良い、そうやって、何もわかっていないユーザー層が
せっせと中古市場に本DX35/1.8や他のDXレンズを放出して
くれるのであれば、わかっているユーザーは、とても買い易く
なったそれらを安価に購入すれば良い、ただそれだけだ。
それに、「APS-C用レンズをフルサイズ機でも使える」
と言う事自体が、すいぶんとマシな話なのだ。
他社、例えばCANON EOSであれば、APS-C用のEF-Sレンズ
は、フルサイズEOSには装着不能だ。
(マウント部の形状を異ならせて、物理的に装着出来ない
ようになっている)
こういう状態だと、例えばAPS-C型のEOS(例:EOS 80D)
を使っているユーザーが、お金を貯めてフルサイズEOS
(例:EOS 6D MarkⅡ)に買い換えたら、それまで使っていた
EF-S型のレンズは全て使用不能になってしまうのだ、
これは、ずいぶんと理不尽な話であろう。
Clik here to view.

そして(同様に)フルサイズ機人気により、安価になった
ニコンDX機中級機等を中古で買って装着すれば、ニコン
システムとしては、再強のコスパになるだろう。
例えば、今回母艦として使用しているD300(2007年)は
当時の高級機(DXのハイエンド機)であるが、現在の
中古相場は、1万円台後半と、二束三文だ。
つまり、今回使用のシステムは、合計3万円程度で
組めるという事になる、かつてのDXハイエンド機なので
性能的な不満は一切無い。ビギナー層が、その10倍以上も、
お金をかけてシステムを組んでいるの横目で見ながら
D300の高速連写性能で、気分良く撮影できる事であろう。
----
では、3本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格11,000円)(以下、EF50/1.8)
カメラは、CANON EOS 7D (APS-C機)
1987年に発売された、AF単焦点小口径標準レンズ。
ただし、本レンズは「エントリーレンズ」では無い。
単に銀塩EOS機の発売に合わせて用意された標準レンズだ。
しかし、銀塩EOSのEFマウントは、それまでのFDマウントを
ばっさり切り捨てて変更された新マウントだ、その当時の
FDユーザー層における不満は極めて大きかった。
・・であれば、CANONとしては、この時代であっても、
「ユーザー層をEOSに囲い込み」しなくてはならない。
さもないと、特に機嫌の悪い旧キヤノンFD党は、皆が、
「ミノルタα」やら「NIKON F4」に乗り換えてしまう
かもしれないし、新規ユーザーもそちらに流れてしまう。
Clik here to view.

として、大幅にコストダウンした「EF50mm/f1.8Ⅱ」を
1990年に発売する。このⅡ型が、私の定義するところの
「史上初のエントリーレンズ」である。
CANONの戦略はドンピシャに的中する。EF50/1.8Ⅱは
実売1万円以下で買えるレンズであり、ビギナー層等が
ビ「安いので試しに買ってみたら、びっくり! とても良く
写るレンズはないか。これだったら、高価なLレンズは、
いったいどんな素晴らしい写りになるのだろう?
よし、お金を貯めて、Lレンズを絶対買うぞ!」
となった訳だ。
まさしく、マーケティングのお手本通りの筋書きだ・・
近年、とある化粧品の「試供品」の話を、あえてTV CMで流し、
「当社では試供品でも一切品質を妥協しません」という主旨で
宣伝していた例がある。
でもまあ、これは当たり前の話であり、試供品で手を抜いて
いたら、それを入手してがっかりしたユーザー層は、二度と
そのメーカーの商品を買わなくなってしまう。
だから、必ず試供品やエントリーレンズは高品質・高性能で
なくてはならない。これはごく基本的な市場原理だ。
EF50/1.8Ⅱは、その後、何と25年間の超ロングセラーとなり、
やっと近年、2015年になって後継レンズのEF50/1.8STMに
リニューアルされた。(注:その後継レンズの発売も、
コピー品の流通等に係わるダークな裏事情があると推察される
のだが、その話の詳細は、現状、推測の域を出ないし、勿論
本記事とは無関係なので割愛する。けど、その件が無ければ、
EF50/1.8Ⅱは、販売が継続されていたかも知れない・・)
で、その25年の間、ずっとEF50/1.8Ⅱはビギナー層から
「神格化」される程に、定評と人気があった訳だが・・
まあ、その件については、
*他社の、どの5群6枚変形ガウス構成型のMF/AFの
50mm/f1.8級レンズも、たいてい非常に良く写る。
(というか、50mm/f1.4級よりも、むしろ高性能だ)
別に、EF50/1.8系だけが優れている訳では無い。
単に、他社の同等レンズの事を知らないだけの話だ。
(参考:別シリーズ「最強50mm選手権」記事を参照)
*エントリーレンズという市場戦略が存在する。
(これらを「良心的価格」だと勘違いしていると、
後で高いレンズを まんまと買わされてしまう)
の、「2つの要点を知らないビギナー層」による過剰評価だ。
そして私は、この「過剰評価」が極めて嫌いであった。
Clik here to view.

相場も安価であり、いつでも7000円前後で購入できた。
けど、反面「絶対に買うまい」とも思っていた。
もし、EF50/1.8Ⅱを買って、それをカメラにつけて
写真を撮っていたら、撮影地などで他の初級マニア等から
初「そのレンズ、安いのに良く写りますよね~」
などと言われたら、このレンズのいきさつを、色々と
説明する訳にもいかず、応対に困ってしまう。
ましてや、
匠「いや、そんなに褒めるものでもないでしょう」などと
言おうものなら、
初「そんな馬鹿な! なんとか言うプロカメラマンの人も、
良いと言っていたし、誰もが認める良く写るレンズですよ」
などと反論されるだろう、が、そういう自分の意見では無い
言い方は、私はさらに嫌いなので、ますます気分が悪くなって
くる、そこで、
匠「なんとか言うカメラマンの評価? 他人の言う事を鵜呑みに
しているのですか? じゃあ、貴方はどう思うのですか?
ご自身の、このレンズに対する意見をお聞かせ下さい!」
・・下手をすれば、そこからエスカレートして大喧嘩だ(汗)
まあ、上記は、本ブログでは珍しく完全なフィクションの
内容だが、十分すぎるほど有り得る話だ。
「神格化」による「信仰」は重症であって、他人からの
意見を受け付ける事はない、何を言っても無駄なのだ。
まあつまり、そのEF50/1.8Ⅱは、変に有名であるが故に、
思い込みや誤解も多々あって、面倒くさいレンズなのだ。
だが、このEF50/1.8Ⅱを、ずっと無視しつづける訳にも
行かない。一応、1993年発売のEF50/1.4USMをずっと
使ってはいるが、そのレンズは、コスパが悪くて好きな
レンズでは無い。どう考えてもEF50/1.8Ⅱの方が遥かに
コスパが良いので、自身の好みには合う筈なのだ。
でも、変に面倒なレンズだ、出来れば買いたくは無い。
そこで私が考えたのは、「レアなEF50/1.8初期型(Ⅰ型)
を、なんとか見つけて入手する」という解決策であった。
初期型は発売期間が短く、価格もⅡ型よりもずっと高価で
あったので、不人気でレアなレンズだ。その代わりⅡ型
よりも、ずいぶんと作りが良く、距離指標もついている。
ただ、これが、やはりなかなか見つからない・・
たまに見かけても、レア品として2万円以上の高額相場だ、
さすがに、中身が同じレンズであるⅡ型の3倍ものコストは
支払えない、「それだったら、EF50/1.4USMのコスパの
悪さと、たいして変わらないではないか・・」と。
・・で、その状態が十数年間も続いた(汗)
近年、2010年代になって、やっと11,000円という妥当な
金額のEF50/1.8初期型を見つけて購入した次第だ。
本レンズEF50/1.8初期型は、厳密にはエントリーレンズ
ではない、しかし、初のエントリーレンズであると言える
EF50/1.8Ⅱ型の元祖のレンズである。こちらの初期型の
歴史的価値も、Ⅱ型と同様に高いのではなかろうか・・?
Clik here to view.

「お試し版戦略」が、ズバリとハマったCANONでは、
レンズのみならずカメラにおいても、同様の市場開拓や
販売促進を意識して製品企画を行うようになった事だろう。
それが、恐らくは1993年の「EOS Kiss」の発売と、その
大成功に繋がったのだろう、と認識している。
バブル経済崩壊後の消費者価値観の変化と「EOS Kiss」
の発売タイミングは、これもまたドンピシャとハマった。
ファミリー層や女性層に「EOS Kiss」は受け入れられ
CANONは新たな市場開拓に成功した。
しかし、成功しすぎたかもしれない・・
1993~1999年頃の期間、一眼レフ界では「EOS Kiss」を
除き、ヒット製品は殆ど生まれていない。・・というか、
魅力的な機種が全くと言っていい程出てこなかったのだ。
マニア層等では「もう、EOS KissしかAF一眼レフが無いので
あれば、古いMF機を探して買おう」という心理に皆が一斉に
傾いてしまい、この時代は空前の「第一次中古カメラブーム」
となった訳だ。
その歴史が良かったのか、悪かったのかは良くわからない。
でもまあ、その「カメラバブル期勃発!」の、遠い原因と
なった製品が、もしかすると本EF50/1.8であったのかも
知れない訳だ(まあ、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な
遠因ではあるが・・)
----
では、今回ラストのシステム
Clik here to view.

(中古購入価格14,000円)(以下、DA35/2.4)
カメラは、PENTAX K-30 (APS-C機)
2010年発売のAPS-C機用標準画角エントリーレンズ。
AL型番は、非球面(アスフェリカル)レンズを採用
している、という意味だ。
Clik here to view.

他社と同様、この時期のPENTAXも「エントリー戦略」
を行ったのだが、PENTAXの場合は、さらに顕著だった。
まず、デジタル一眼レフであるが、低価格帯の機種の
性能を向上。その代表格は、K-r(2010年、未所有)
であるが、最高ISO25600、連写毎秒6コマと、中級機
並みのスペックだ。
加えて、カメラボディやレンズに「オーダーカラー制」
を実施。ボディでは2色のコンビネーションにより、
100を超える組み合わせの配色が選べた。
また、本DA35/2.4レンズも同様に12色から選べる。
(注:PENTAXの親会社がHOYAからRICOHに変わった
数年後に、この「オーダーカラー制」は終了している)
そしで、ミラーレス機としてPENTAX Qシリーズ(2011年~)
および、PENTAX K-01(2012年)を発売。
続くQ10(2012年)ではオーダーカラーが可能になった。
それから、この時期はPENTAX機においては、ゆるキャラ、
歌手、アニメ等とのコラボ商品も色々と発売されている。
こうした徹底的なエントリー層向けの市場戦略により、
スマホやミラーレスの台頭を跳ね除けて、HOYA時代の
PENTAXは好調であったと聞く。
まあ、タイミングが良かったのかもしれない。他社は
この時期、スマホやミラーレスとの直接の勝負を避け
高付加価値化戦略に転換しつつある時代であった。
それは、さらなる高性能化と価格上昇も意味する物で
あるから、PENTAXの普及機種は、そこそこの性能ながら
割安感があり、コスパが良く感じられたのだと思う。
ただまあ、この期間、デジタル一眼レフ高級機の方は
ほとんどK-5(2010年)系列のみで支えていた状況であり
そちら(高級機)の戦略までは、手が回っていなかった
のではなかろうか・・?
Clik here to view.

市場戦略が終わりつつあった2013年頃からは、
(注:今回使用の母艦K-30(2012)は、RICOHの傘下に
なってからの直後に発売された機種だが、その製品
コンセプトも設計もHOYA時代のものを踏襲している)
RICOHの技術主導戦略が始まり、高級機もガラリと変化
するようになっていく。
さて、本レンズDA35/2.4だが、エントリーレンズであり、
価格が安価、そしてデザインも良く、おまけに12色から
選ぶ事が出来る(注:2017年末まで出来た)
APS-C機専用単焦点で小型軽量、そこそこの描写力と
そこそこの性能、例えば開放F値(F2.4)、最短撮影
距離(30cm)、非球面レンズ使用(AL)と、まあ、
スペック的には優れていると言える。
Clik here to view.

本レンズの数年後に発売された新型のHDコーディング
のレンズと比べて劣るのはやむを得ないのだが、
smcコーティング自体も、約40年間も続く、こなれた
技術であり、完成度が高い。
他の様々なsmc型レンズにおいては、これまであまり
逆光耐性について問題と思った事は無いので、
本レンズの課題が、余計に目につく。
ちなみに、同社の同様のエントリーレンズである
「smc PENTAX-DA 50mm/f1.8」も、逆光耐性が低く
感じる為、これらの廉価版レンズでは、何らかの
コストダウンが図られているのであろうか・・?
なお、逆光耐性が低い為にフードを装着したいのだが、
ここもコストダウンの弊害で、フードは別売である。
しかも、フードは恐らく黒色版しかないので、本レンズを
オーダーカラー品で買った場合、デザインがマッチしない。
あれこれと微妙に不満点があって、ちょっとクセがある
レンズではあるが、まあ、PENTAX機ユーザーであれば
持っていても悪く無いレンズだ。
Clik here to view.
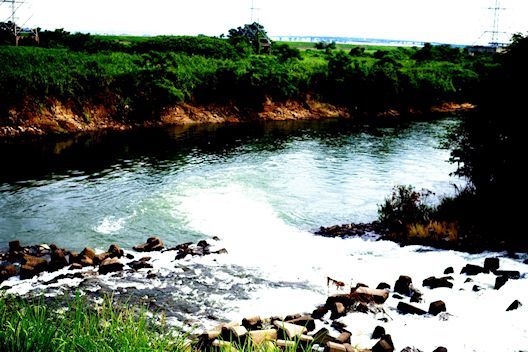
2015年頃にかけ、各メーカーから、2~3本づつつの
発売がある。中には未だ現行商品であるものも多いが
ただでさえ定価も安価な上に、長期間発売されている事で
さらに新品・中古とも安価になっていて、どのレンズも
1万円以下から高くても1万円台前半で中古入手可能だ。
エントリーレンズは、元々の基本性能に優れる。
その上安価であるから、とてつもなくコスパが良い。
細かい弱点を持つレンズも多いが、それは承知の上で
回避しながら使えば何ら問題の無いレンズばかりだ。
メーカー純正エントリーレンズは、「全て買い」と
思って間違い無いであろう。
エントリーレンズの、市場での「からくり」さえ理解
してしまえば、その後、コスパの悪い純正高級レンズを
買う必要は無い。高級レンズはメーカーが利益を確保
する為の手段であり、ファーストフード・ハンバーガー
店での、ポテトや限定企画バーガーと同じ位置づけだ。
それらは利益を得る為の商品なのだ。
だから、低価格帯ハンバーガー(エントリーバーガー?)
を単品で買うならば、さほどコスパは悪くならない。
「ポテトもいかがですか?」と、高付加価値型の商品を
美人の店員さんに薦められても(汗)強大な意思を持って
「いりません」と答えれば良いだけである。
それと同様に「エントリーレンズ」も単品で買って、
高級レンズを無視すれば、それで良いわけである。
消費者側がお買い得な商品だけを買っても、販売側は
文句の言い様が無い。
----
さて、今回の記事「エントリーレンズ特集」は、
このあたり迄で、次回記事に続く・・