所有している一眼レフ用の50mm(前後の)標準レンズを、
カテゴリー毎に予選を行い、最後に最強の50mmレンズを
決定する、というシリーズ記事。
今回は予選Fブロックとして「AF50mm/f1.4(Part2)」の
カテゴリーのレンズを5本(AF4本、および番外1本)
紹介(対戦)する。
ここまで5回の記事は、殆どが銀塩時代(~1990年代)の
標準レンズばかり紹介して来たのだが、どれも同じような
レンズ構成、描写傾向、性能仕様ばかりで、個性が無く、
書いている自身でさえ、少々嫌になってきていた。
記事を読む方も、さぞかし大変だったであろう(汗)
結局「どのメーカーの標準レンズを買っても同じ」という
事実は、嫌と言う程に理解したのではなかろうか・・?
だが、今回第6回記事は、全て2000年代以降の新世代の
標準レンズであり、これまでの時代の変形ダブルガウス型
構成では無いレンズが大半だ、やっとここで個性あるレンズ
群の紹介が出来ることになり、少々ほっとしている。
---
まず今回最初のレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズ名:SIGMA 50mm/f1.4 DG HSM | Art
レンズ購入価格:71,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ (APS-C機)
レンズマニアックス第2回記事等で紹介の、2014年発売の
大口径AF標準レンズ(以下A50/1.4と表記)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
まずレンズ構成を上げれば、8群13枚という、これまでに
無い複雑な構成となっている。変形ダブルガウス型とかの
そういう用語も全く当てはまらず、コンピューター設計の
申し子のような新世代の標準レンズである。
ただ、この複雑なレンズ構成により、本レンズの重量は
815gと極めて重い、これは過去の一般的な50mm標準
レンズの約3倍から7倍にも及ぶ重さだ。
フィルター径はφ77mmもあり、全体にかなり大柄だ。
おまけに価格も高い、発売時定価は税込みで14万円近くで、
標準レンズとしては、まさしく異例だ。
「大きく、重く、高価」この「三重苦(三悪)」により、
ハイコスパ名玉編には、ノミネートすらされなかった、
まあ、「コスパ面」では、お話にもならないレンズだ。
近年の一眼レフ市場の縮退により、当然、交換レンズの
販売本数も減っているであろう。
SIGMAのような(殆ど)レンズ専業メーカーでは、
交換レンズが売れないと事業が継続できない。
そこで、SIGMAは2013年頃から戦略転換をした。
これまで販売していたレンズ群の多くを生産中止として、
高級レンズ(すなわち、高性能なレンズであり、高価な値づけ
ができる。つまり数が売れなくても、1本売れば十分な利益が
出る製品)の開発に力を入れたのだ。
その最右翼が「Art Line」と呼ばれる、高性能単焦点
レンズ群だ、具体的に機種名を上げよう。
14mm/f1.8 DG HSM
20mm/f1.4 DG HSM
24mm/f1.4 DG HSM
28mm/f1.4 DG HSM
35mm/f1.4 DG HSM
35mm/f1.2 DG DN (注:ミラーレス機用のみ)
40mm/f1.4 DG HSM
50mm/f1.4 DG HSM
85mm/f1.4 DG HSM
105mm/f1.4 DG HSM
135mm/f1.8 DG HSM
これ以外にも、超大口径ズーム、マクロや、ミラーレス機用
の高性能単焦点(DNシリーズ)もArt Lineに属している。
単焦点は、ほとんどが開放F1.4級であり、超広角14mmと、
望遠135mmだけが開放F1.8だ。
これらの単焦点シリーズは、4本程所有している。
Art Line単焦点は確かに高価だとは思うが、思い切って
手ブレ補正機能を排除するなど、硬派な仕様である事が
個人的には気にいっている。
つまり「大口径レンズなので、軟弱な手ブレ補正などは
不要なので、その分、レンズ性能を上げてくれ」
という意味だ。その価値感覚を満たしてくれるコンセプト
であれば、それは直接的な購買動機に繋がる。
これは、かなり正当な「付加価値」である。
(注:Art Lineは、いずれも超重量級のレンズなので、
業務用途専用で、かつ三脚利用が前提の故に、手ブレ補正
無しの仕様なのかも知れないが、個人的には、基本的に
三脚は使用しないポリシーである)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14540257.jpg]()
消費者側から見て不当な付加価値とは、例えば「手ブレ補正
と超音波モーターを入れたから、その分値段が上がりました」
と言われても、こういう機能が本来の用途上からは不要な筈の
マクロや広角レンズに迄も、それらが入ってしまう等である。
カメラ側でも同様、「最高感度がISO160万になったから
高価なのです」等と言われても、実際にはノイズだらけで、
その高感度は使い物にならなかったりする。
つまり、カタログ上の数値や性能ばかりを強調して、中身や
実用性が伴っていない事等は、不当な付加価値だ。おまけに
それで高価になった製品を買わせられるのだから、たまった
ものではない。こういう矛盾点は、消費者側で見抜いて
「買わない」等の対処をする必要があるのだが、まあ皆が
それをしてしまうと、縮退したカメラ市場が崩壊する。
結局、「付加価値の正当性」を見抜けない消費者層には
そうした高価な製品を買ってもらわなければならない訳だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14540274.jpg]()
余談が長くなった・・
価格(定価)が高価である事が、直接的に描写性能に結びつく
訳では決して無いのであるが、本レンズの場合は、幸いな事に
描写性能的には、殆ど問題点は見られない。
解像感が高く、最短撮影距離も40cmと短く、ボケ質破綻も
起こりにくい、では申し分無いではないか?という点だが・・
最大の課題は、この「大きく、重く、高価」という三重苦を
ユーザー側で、どう評価するか?だ。
これらの課題が容認できるのであれば、悪く無いレンズだ。
---
では次のレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14542275.jpg]()
レンズ名:smc PENTAX-DA★55mm/f1.4 SDM
レンズ購入価格:42,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回(第3位)
ハイコスパ名玉編第10回(第9位)記事等で紹介した、
2009年発売のAPS-C機専用AF標準(中望遠画角)レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14542382.jpg]()
先のA50/1.4と同様、本レンズも超音波モーター(SDM)
搭載であるが、内蔵手ブレ補正機能は入ってない。
(注:PENTAX機用なので、ボディ内にその機能がある)
まあ、と言うか手ブレ補正が入っている標準(級)レンズ
は極めて限られていて、私が知る範囲では、2015年の
TAMRON SP 45mm/f1.8 Di VC USD (Model F013)
くらいしか知らない。(レンズマニアックス第7回記事)
本DA★55/1.4だが、過去紹介記事でいずれも評価点が
高かった名玉である。
比較的新しい設計でありながら、その後の2010年代製品
のような過度な高付加価値型ではなく、発売時の実勢価格は
およそ8万円程度。オープン価格であるので、その後の
新品価格は6万円台位まで低下、中古相場は4万円以下に
まで落ちてきているので、近代の高性能標準レンズに比べ
買いやすい価格帯である。すなわちコスパがなかなか良い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14542360.jpg]()
細かい特徴だが、smc銘であるが旧来のsmc型コーティング
に加えて、新方式のエアロ・ブライト・コーティングを
採用している。
ただ、ある新技術を搭載しているからと言って、だから良い、
とか言う理由にはならず、技術はあくまで結果を得る為の
1つの手段にしか過ぎない。肝心な事は、トータルで優れた
描写性能が得られているか否か?である。
そういう視点では、本レンズの描写力は満足の行くレベル
である。APS-C機専用レンズなので、中望遠画角になって
しまうのがちょっとしたネックではあるが、これは元々、
銀塩時代のPENTAX FA★85/1.4(ミラーレス名玉編第1回)
のAPS-C機用代替レンズとして企画され、同一設計者の手に
よるものであるから、換算画角が82.5mmとなるのは当然だ。
(注:恐らくは、FA85の構成を2/3にスケールダウンした、
ジェネリック型設計であろう)
その出自から、(現在となってはセミレア品となっている)
「幻の名玉FA★85/1.4」の、やや独特な雰囲気の描写力
(この事が、言葉では伝え難いのがなんとも歯がゆい、と、
当該レンズの紹介記事では何度か述べている)が、本レンズ
においても、よく再現されている。
本レンズや、FA★85/1.4、それからFA77/1.8あたりは
光学ファインダーで覗いて見るだけで、他のレンズとは
違う、何か独特の雰囲気を感じる事ができる。
PENTAXでは20年程前のカタログで、それを「空気感」と
表現していた。まあ、わからない感覚では無いが、やや
抽象的すぎる用語表現であろう。
本DA★55/14の弱点は、SDM超音波モーターの作動音が、
高周波の可聴帯域まで落ちてきていて、その「チーッ」と
いう音がうるさい事位であるが、他は概ね問題が無い。
APS-C機専用とした事で小型軽量化を実現、かつ高描写力で
近代レンズとしては、値段もさほど高価では無い事が
総合的には好評価に繋がる。
さらに新しい2018年発売のフルサイズ対応標準レンズ
HD PENTAX-D FA★50mm/f1.4 SDM AW
との差異が気になるかも知れないが、あいにくそちらは
未所有だ。
まあ、もし最新型の描写力がとても良かったとしても
「高付加価値型レンズ」の場合は、価格が高いので、
中古相場が十分下がるまで、指をくわえて見送るしかない。
それに比べて、本DA★55/1.4は、現在では比較的こなれた
中古相場で購入する事が可能だ。DFA型を入手する迄の間の
繋ぎで買っても問題無く、むしろ、本レンズの優れた描写力
を知れば、さらなる最新型レンズへの買い替えや買い増しは
不要、と思ってしまうかも知れない。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14542343.jpg]()
本DA★55/1.4は、コスパに優れた名レンズであると思う。
本50mm選手権シリーズ記事の終盤に予定されている決勝戦
あるいはB決勝(下位決勝)に進出する事は確実だとは思うが、
また決勝戦近くになったら、その組み合わせを発表しよう。
なお、決勝戦では、個々の標準レンズの多項目による
評価点をあげ、それで優勝レンズを決定する予定だ。
---
では、3本目のレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14543414.jpg]()
レンズ名:CONTAX N Planar T* 50mm/f1.4
レンズ購入価格:33,000円(新品在庫品)
使用カメラ:PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
ミラーレス・マニアックス第9回、第50回記事で紹介の、
2001年発売のCONTAX Nシステム用大口径AF標準レンズ。
(以下、NP50/1.4)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14544397.jpg]()
京セラ・コンタックスが2005年にカメラ事業から撤退して
しまう主因となった「CONTAX Nシステム」の悲運の歴史
については、本ブログの様々な過去記事で紹介済みだが、
近年の記事としては、「銀塩一眼レフ・クラッシックス
第24回 CONTAX N1」編に詳しい。
興味がある方は、当該記事等を参照していただきたいが、
そもそも、Nシステムを現代において再興させようとする
のは、かなり困難である事は最初に述べておく。
まず、機体が無い。Nシステムには銀塩35mm判、銀塩中判、
デジタル(フルサイズ)があるが、どれも現代では入手が
困難か、あるいは入手できても実用性が皆無だ。
レンズの方もセミレアであり、中古があったとしても
コレクター向けのプレミアム相場で、コスパが悪い。
そしてNマウントレンズをデジタル一眼レフやミラーレス
機で使用できるようにするのは、さらに困難である。
2000年代にはNマウントをEF(EOS)マウントに換装する
サービスが海外で行われていた模様だが、今はその話も
聞かない。
また、マウントアダプターは、ごく短期間だけ、いくつかの
メーカーから、電子接点型、および機械絞り羽根内蔵型が
発売されていたが、販売数が少なく、殆どが現在では生産
終了と思われ、アダプターの入手も困難だ。
それから、サポートあるいは情報収集も厳しい。
京セラがカメラ事業から撤退10年後の2015年には、サポート
(補修サービス)も終了し、現在の京セラのWEBページ
からは過去機の情報(取扱説明書含む)も削除されている。
WEB上にも(SNS等が普及前の時代であった為)、有力な
Nシステムに関する一次情報は殆ど見当たらない。
(注:スペック等を転記するだけの二次情報は稀に存在する)
なので、本ブログにおいて様々なNシステム関連の記事を
書く際には、手元にある限られた機材を触りながら、あるいは
記憶をたどりながら、はたまた同時代の他の写真機材環境から
類推しながら、「一次情報」をまとめていた状況である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14544352.jpg]()
さて本NP50/1.4であるが、大柄なレンズであるというのが
第一印象であろう。それでも、重量は310g程度に留まり、
本記事冒頭に紹介の(最)重量級標準SIGMA A50/1.4の
815gのおよそ1/3程度でしか無い。
前機種、RTSマウント版のPlanar T* 50/1.4
(本シリーズ第1回等)との比較であるが、レンズ構成は
同じ6群7枚であるが、レンズ後群の設計がずいぶんと異なる
ように見える。具体的には、旧来のP50/1.4は、後玉が
平面または少し凹だが、本NP50/1.4は後玉が凸面である。
これはデジタル化を見据えた、テレセントリック特性への
配慮だと思われる。
この設計の微妙な差異によるものか、本NP50/1.4は
旧来のP50/1.4よりも、ボケ質破綻(いわゆるプラナーボケ)
が出にくい。
この長所は実用上はかなり好ましく、1つは旧来のP50/1.4
は、撮影条件(撮影距離、絞り値、背景の図柄等)が整った
時にしか最良のボケ質を得る事が出来なかったのが、
本NP50/1.4では、多くの撮影条件で優れたボケ質を発揮
する事が出来る事だ。
もう1つは、これは使用機材の問題であるが、私が使用して
いるCONTAX N→μ4/3のマウントアダプターは、機械絞り羽根
内蔵型である、これはレンズ後群のさらに後ろに、絞り羽根が
存在する事となり(=視野絞り型)、後群からの光束を遮り、
露出値(光量)調整の意味はあるのだが、本来のレンズ内部に
絞り羽根が存在する状態(=開口絞り型)と比べて、絞り羽根に
よる被写界深度調整やボケ質のコントロールが殆ど効かない。
つまり絞り値によるボケ質破綻の回避の技法が使えない、という
事であり、もし旧来のP50/1.4のように、ボケ質破綻が頻繁に
発生するタイプのレンズだったら、このアダプター仕様では、
回避が困難で、お手上げであっただろうからだ。
ちなみに、何故、機械絞り羽根内蔵型のアダプターを使用
せざるを得ないか?と言えば、CONTAX Nマウントの絞り機構
は電子制御タイプであり、一般的なアダプターでは絞り羽根
が動かないからだ。
これは別にNマウントだけの仕様ではなく、他社のEOS EFや、
4/3(フォーサーズ)、ニコンE型レンズ(電磁絞り)等でも
同様である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14544325.jpg]()
さて、肝心の写りだが・・
初級マニア等であれば、CONTAXと名前が付けば、良く写る
レンズだと勘違いしてしまい、良く写るから高いのだと誤解
してしまい、さらにそれを無理して買えば、高く買ったの
だから良く写ると、どんどんと妄想の世界に入り込んでしまう。
冷静に本レンズの描写力を見れば、ここまで散々5回の記事で
紹介してきた数十本の「並の標準レンズ」と大差は無い。
だた、並だから、悪いのか?と言えば、そういう事も無く、
どの標準レンズでも普通に良く写る。
しかし、本NP50/1.4も、その範疇からは脱却できていない。
ちなみに、ほぼ同時期に発売されたNシステム用の
N Planar T* 85mm/f1.4(ミラーレス名玉編第3回、
第10位相当)は、とても気合を入れて開発されたレンズだった。
本レンズNP50/1.4は、当時のマニア層から
「旧型のRTS Planar 50mm/f1.4にAFの側を被せただけ」
と揶揄されていたのだが、それは間違った情報であった。
まあ、色々言っていた人達は、結局誰もNシステムを購入して
いなかったのだ。だから何が正しくて、何が間違っているの
かも、わかる筈も無い。
まあでも、正直言えば、そこまで悪く言う必要は無いが、
NP85/1.4への気合の入り方から比べると、本NP50/1.4は
少々手抜きして作られたレンズのようにも見えてしまう。
それは、旧来のP50/1.4に比較して、大幅に改善した点が
あまり見受けられないからだ。
で、何故NP85/1.4の場合は、旧来のP85/1.4に対して
相当に気合を入れて改良が計られたのか?と言えば、
それは、旧RTS Planar T* 85mm/f1.4が、初級マニア層
や金満家層から「神格化」されたレンズであったからだ。
RTS P85/1.4は、実際の性能的には様々な弱点を持つ
レンズではあるが、それをここで書いていくと際限なく
文字数が増えるので、ばっさり割愛しよう。
(以前の様々な記事でも、そこについては述べている)
でも神格化されていれば、CONTAXの「顔」(代表的な)
レンズである新型NシステムのNP85/1.4は、旧P85/1.4
の弱点を徹底的に改善しなければならない。
(そもそも、27年も発売時期が異なるのだ・・)
ボケ質破綻の改善や焦点移動の問題は、若干の改善が
図られたが、ピント精度による歩留まりの悪さの改善は
出来なかった。これはNP85/1.4に限らず、殆どの85/1.4級
レンズでの宿命であり、一般的に成功率は10%程度、つまり
10枚中9枚までは、ピントを外してしまう。
この問題の解決には、カメラ側にも新機能が搭載された。
CONTAX N1(2000年、銀塩一眼第24回記事)では、
「フォーカス・ブラケット」機能により、ピント位置を
わずかにずらしながら3連写を行う。
ここから、ピントの合っている写真を探す訳だ。
「その機能を使うと、フィルムが3倍無駄になる」等とは
言うなかれ、この機能を使わないと、前述のように、
10枚中9枚はピントが合わず、さらにフィルムが無駄に
なってしまうのだ(汗)
余談が長くなった、本P50/1.4は、NP85/1.4ほどには
気合を入れて作られたレンズでは無いが、とは言え、
問題があるレンズでは無い。ともかく銀塩用標準レンズは
どれも良く写るのだ。
---
では、4本目のレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14545723.jpg]()
レンズ名:FUJIFILM XF 56mm/f1.2[T1.7] R APD
レンズ購入価格:110,000円(中古品)
使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第3回(第6位)記事等
多数で紹介した、2014年発売のAPS-C機専用AF標準
(中望遠画角)アポダイゼーション・エレメント搭載型
特殊レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14545725.jpg]()
このレンズ、あるいは、アポダイゼーションについて
述べていくと際限なく文字数が増えてしまう。過去記事
でも色々と詳細を書いているので、今回は割愛しよう。
(特殊レンズ第0回「アポダイゼーション・グランド
スラム」編記事等を参照の事)
簡単に言えば、「ボケ質の大変良い」レンズである。
グラデーション状に透過率が変わる(周辺が暗い)
光学フィルターを内蔵していて、これをアポダイゼーション
光学エレメントと呼ぶ。
この機能を搭載している(交換)レンズは4本のみであり
1998年より長らくは、MINOLTA STF135/2.8[T4.5]
(後にSONY版)(ミラーレス・マニアックス第17回記事等)
のみであったが、2014年、突如本レンズが発売された。
その後も、中国製LAOWA 105mm/f2が2016年に、
(ハイコスパ名玉編第1回記事等)
2017年にはSONY FE100mm/f2.8 STF GM(グランドスラム
記事等)と、アポダイゼーション機構を持つレンズが続けて
発売された。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14550893.jpg]()
それと、本レンズ XF 56mm/f1.2[T1.7] R APDには
同スペックで、アポダイゼーションを搭載していない
XF 56mm/f1.2 Rが存在する。そちらは未所有なので
両者を比較する事はできないが、アポダイゼーションの
「付加価値」(=値段を高くする要素)が無いので、
新品定価はAPD版の20万6000円(+税)に対して、
ノーマル版は13万1000円(+税)と、かなり安目だ。
ノーマル版はアポダイゼーション光学エレメントが無い分、
実効F値であるT値を比較すると、T1.7対F1.2と明るい。
アポダイゼーションの有無により、解像度等、若干光学特性
が異なるかもしれず、ノーマル版もコスパ面では魅力的だ。
本APD版の弱点だが、極めて高価な事だ。
だがまあ、その点は「高付加価値型商品」であるから、
やむを得ない。
部品代の差は、アポダイゼーションの有無だけなので、
20世紀型のような製造原価からの定価決めの構造であれば
それだけで7万円も定価が上がる筈はなく、要は開発費の
減価償却が乗っている事とか、「この価格でも欲しい人は
買うだろうから」という市場原理上での値付けである。
これがまあ「高付加価値型商品」の特徴であり、
要は、「高くても売れる可能性がある商品だ」という事だ、
消費者側から見れば、どうしても欲しいと思えば、買うしか
無いし、コスパが悪すぎると思えば、買わないという選択だ。
では、このレンズを買う意味(意義)があるのかどうか?
そこは、コスパの感覚が多分に影響する事であろう。
「コスパ」を主要な購買論理とする私としては、
性能に比べて値段が高すぎる商品は買わない、という事が
殆どなのだが・・・
ここで言う「レンズの性能」とは、一般的に想像するだろう
写り(描写力)だけという訳ではなく、私の場合は、
他のレンズ評価記事で行うように、様々な評価要素を総合
して性能(価値)を決めていく。
本XF56/1.2APDの場合は、発売時には、史上2本目で16年
ぶりに新発売されたアポダイゼーションレンズであり、
かつ、史上初のAF対応だ(その後、SONY FE100/2.8STF
もAFで発売された)これらからの、マニアック度や
歴史的価値、所有必要度が高く、それらを総合的に考え、
購入を決めたのだが・・ 問題は価格であった。
定価税込み22万円強はさすがに高すぎる、新品市場価格は
18万円程であったが、それでも同様に非常に高価だ。
1年ほど中古が出るのを待って、税込み約11万円で、やっと
中古入手した次第である。
ちなみに、13万円を超える価格のレンズは、どんなに性能が
高くても買わないようなルールを設けている。
もしそういうレンズがあれば、中古が13万円より下がる迄、
何年でも待つのだ。(注:近年のレンズ価格の上昇を
鑑みて、最近、このルールは最大15万円迄に緩和した)
さて、描写性能的にはどうか? そこが優れていないと、
高価で買ったのが無駄になる、つまり、コスパの原点である
描写力が低ければ、どんなにマニアック度等が高くても
意味が無い。もし、そうなった場合は「ぼったくりレンズ」
として、個人的に嫌いなレンズの代表格となってしまい、
使わない、酷使して使い潰す、あるいは処分(譲渡)して
しまう、など、そういう措置になってしまうのだ。
「そんなもの(描写力)は、買う前にわかるだろう?」とは
言うなかれ、WEB上のレビュー記事などでの掲載作例等は
ある撮影条件で撮られたものであって、全ての撮影条件
まではカバーできないのは当然だ。
それに、良く写っている写真ばかりを掲載するのも、
まあ当然の措置であろう。であれば、例えば具体的には、
ボケ質破綻が発生する条件や、その場合の作例などは
いくらレビュー記事を検索しても、見つかる筈が無い。
結局、他人の評価は全く参考にする事が出来ず、自身で
購入後、しかも、何千枚も、何万枚も撮ってからでないと
レンズの真の性能(描写力)は見えてこないのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14550848.jpg]()
本XF56/1.2APDであるが、レンズ自体の性能として、
若干解像感が甘く感じ、ボケ質破綻も稀に発生する。
いくらアポダイゼーション・光学エレメントを搭載して
いるからと言って、ボケ質以外にも全てのレンズ性能が
向上する訳でも無い。むしろ、マスター(主)レンズの
基本性能が低いと、アポダイゼーションを搭載していても
意味が無い訳だ。まあ我慢できない程性能が低いという
訳では無いが、「高価なレンズなので、高い基本性能は
期待してしまう」という課題もある。
本レンズは、8群11枚のレンズ構成で、非球面レンズ1枚、
異常分散レンズ2枚と、まあ贅沢な設計ではあるが、
レンズ構成を複雑化するのと、性能が上がるのはイコール
だとは言い切れない。
なお、開放F1.2級の標準レンズは設計が難しいのか?
MF時代からも色々出ているが、あまり感動的という描写力
を持つレンズには、出くわした事は無い。
(次回記事で紹介予定)
ましてや、それ以上の大口径、F1.0やF0.95ともなれば
なおさらであり、大口径化と、様々な描写性能は、
トレードオフの関係(どちらかを優先すれば、どちらかが
成り立たない)ようにも思えてしまう。
本XF56/1.2APDは、悪くは無いレンズではあるが、
購入を検討する際は、コスパの悪さは覚悟しておく必要が
あるだろう。そのあたりも、購入側が、マニアック度や
歴史的価値をどう判断するか?のトレードオフだと思う。
---
では、今回ラストのレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14551759.jpg]()
レンズ名:COSINA Zeiss Milvus 50mm/f1.4 ZF2
レンズ購入価格: 85,000円(中古品)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)
(以下、Milvus50/1.4)
2016年に発売の高解像力仕様MF大口径標準レンズ。
レトロフォーカス(ツァイスで言う「ディスタコン」)
構成という極めて珍しい標準レンズだ。
MFレンズではあるが、新鋭レンズにつき、便宜上
この「AF50/1.4」のカテゴリーでの予選対戦とする。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14551770.jpg]()
ツァイスのブランド銘ではあるが、日本のコシナ製だ。
まあ、現代のカール・ツァイス銘の写真用交換レンズは
正式に公表されてはいないが、全て日本製(コシナ、他)
である。
さて、本レンズは「高付加価値型商品」である、つまり
一眼レフ市場の縮退を受け、メーカーや流通が利益を確保
する類の商品であるから、ユーザーから見たコスパは悪い。
そして、8群10枚というレンズ構成は、重く(約900g)
大きく(フィルター径φ67mm)、そして高価(定価が
税込み16万円以上)であり、おまけにMFレンズという
「四重苦」である。まあでも、一部はSIGMA A50/1.4
(前述)やOtus55/1.4(未所有)より若干はマシだ。
MFである点も、ZF2マウント(ニコン用)を買っておけば
ニコン機や他社機のほぼ全てで(アダプターを介して)
装着して全く問題なく使用できるという長所に繋がる。
では、何故このような「四重苦」レンズを購入するのか?
と言えば、これはディスタゴン構成の標準レンズへの
知的好奇心が大きい、つまり「研究用」なのだ。
別に「(有名な)ツァイスだから良く写る」などと
初級中級者の持つ誤解のような考えは持っていないし、
そのブランド力をアテにしたり、所有満足度を得る為の
購入では無いのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14551746.jpg]()
本Milvus50/1.4の長所であるが、実用十分の描写性能を
持つ事である。特に不満点はなく、普通にとても良く写る。
特に優れた点はコントラストの高さであり、使用カメラが
変わったかのような印象を受ける。
しかし、この長所は、やはりコスパを意識しないとならない
であろう、いくら良く写るレンズでも、とんでもなく高価で
あったらコスパ評価は極めて悪くなる。
現状、私の評価データベースでの本レンズのコスパ評価は
5点満点で2点である、つまり平均的よりやや低い。
ただ、「壊滅的にコスパが悪い」とは言い切れず、
まあ、SIGMA A50/1.4と同等のコスパ点、および他の
評価傾向も、ほぼ同一である。(いずれも総合点4点)
先日、量販店の店頭で、ツァイスの営業(販売)担当者
が居たので、わざと、ちょっと意地悪な質問をしてみた。
匠「MilvusやOtus、なかなか良さそうですねえ。
SIGMAのARTと迷っているのですが、どちらが良いですか?」
担「う~ん、SIGMAさんのARTシリーズも評判が良いですね」
まあ、そういう答えになるだろう。そこは予想済みだ。
結局、ツァイス側としても、SIGMA ART LINEは意識している
という、ライバル関係だと思われる。
私の評価では、どちらを買っても良いと思う。
AF(超音波モーター)で現代的な撮影技法を用い、
趣味撮影のみならず業務撮影用途も意識するならば、
SIGMA ART LINEが効率的だと思うし、
趣味撮影オンリーであれば、MFでマウント汎用性が高い
Milvusが好ましい。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_14553096.jpg]()
まあ、結局、レンズの性能としては、このクラスとも
なれば全く不満は無いだろうし、目につく弱点も無い。
消費者側としては、自身の用途に合わせて選択すれば良い
という事になる。迷って悩むならば、両方買ってしまう
という選択肢もある、多少強引で、予算も必要な話だが、
精神的にはそれで満足するだろうし、「最良のレベルの
標準レンズ」という価値観や判断基準が、どのあたりと
なるのか?も理解できる事であろう。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Fブロック「AF50mm/f1.4 Part2」の記事は終了だ、
なお、本記事の紹介レンズの中には、決勝進出の可能性
が高いものが多いだろう事は述べておく。
次回の本シリーズ記事は、
予選Gブロック「MF50mm/f1.2」となる予定だ。
カテゴリー毎に予選を行い、最後に最強の50mmレンズを
決定する、というシリーズ記事。
今回は予選Fブロックとして「AF50mm/f1.4(Part2)」の
カテゴリーのレンズを5本(AF4本、および番外1本)
紹介(対戦)する。
ここまで5回の記事は、殆どが銀塩時代(~1990年代)の
標準レンズばかり紹介して来たのだが、どれも同じような
レンズ構成、描写傾向、性能仕様ばかりで、個性が無く、
書いている自身でさえ、少々嫌になってきていた。
記事を読む方も、さぞかし大変だったであろう(汗)
結局「どのメーカーの標準レンズを買っても同じ」という
事実は、嫌と言う程に理解したのではなかろうか・・?
だが、今回第6回記事は、全て2000年代以降の新世代の
標準レンズであり、これまでの時代の変形ダブルガウス型
構成では無いレンズが大半だ、やっとここで個性あるレンズ
群の紹介が出来ることになり、少々ほっとしている。
---
まず今回最初のレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:71,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ (APS-C機)
レンズマニアックス第2回記事等で紹介の、2014年発売の
大口径AF標準レンズ(以下A50/1.4と表記)
Clik here to view.

無い複雑な構成となっている。変形ダブルガウス型とかの
そういう用語も全く当てはまらず、コンピューター設計の
申し子のような新世代の標準レンズである。
ただ、この複雑なレンズ構成により、本レンズの重量は
815gと極めて重い、これは過去の一般的な50mm標準
レンズの約3倍から7倍にも及ぶ重さだ。
フィルター径はφ77mmもあり、全体にかなり大柄だ。
おまけに価格も高い、発売時定価は税込みで14万円近くで、
標準レンズとしては、まさしく異例だ。
「大きく、重く、高価」この「三重苦(三悪)」により、
ハイコスパ名玉編には、ノミネートすらされなかった、
まあ、「コスパ面」では、お話にもならないレンズだ。
近年の一眼レフ市場の縮退により、当然、交換レンズの
販売本数も減っているであろう。
SIGMAのような(殆ど)レンズ専業メーカーでは、
交換レンズが売れないと事業が継続できない。
そこで、SIGMAは2013年頃から戦略転換をした。
これまで販売していたレンズ群の多くを生産中止として、
高級レンズ(すなわち、高性能なレンズであり、高価な値づけ
ができる。つまり数が売れなくても、1本売れば十分な利益が
出る製品)の開発に力を入れたのだ。
その最右翼が「Art Line」と呼ばれる、高性能単焦点
レンズ群だ、具体的に機種名を上げよう。
14mm/f1.8 DG HSM
20mm/f1.4 DG HSM
24mm/f1.4 DG HSM
28mm/f1.4 DG HSM
35mm/f1.4 DG HSM
35mm/f1.2 DG DN (注:ミラーレス機用のみ)
40mm/f1.4 DG HSM
50mm/f1.4 DG HSM
85mm/f1.4 DG HSM
105mm/f1.4 DG HSM
135mm/f1.8 DG HSM
これ以外にも、超大口径ズーム、マクロや、ミラーレス機用
の高性能単焦点(DNシリーズ)もArt Lineに属している。
単焦点は、ほとんどが開放F1.4級であり、超広角14mmと、
望遠135mmだけが開放F1.8だ。
これらの単焦点シリーズは、4本程所有している。
Art Line単焦点は確かに高価だとは思うが、思い切って
手ブレ補正機能を排除するなど、硬派な仕様である事が
個人的には気にいっている。
つまり「大口径レンズなので、軟弱な手ブレ補正などは
不要なので、その分、レンズ性能を上げてくれ」
という意味だ。その価値感覚を満たしてくれるコンセプト
であれば、それは直接的な購買動機に繋がる。
これは、かなり正当な「付加価値」である。
(注:Art Lineは、いずれも超重量級のレンズなので、
業務用途専用で、かつ三脚利用が前提の故に、手ブレ補正
無しの仕様なのかも知れないが、個人的には、基本的に
三脚は使用しないポリシーである)
Clik here to view.

と超音波モーターを入れたから、その分値段が上がりました」
と言われても、こういう機能が本来の用途上からは不要な筈の
マクロや広角レンズに迄も、それらが入ってしまう等である。
カメラ側でも同様、「最高感度がISO160万になったから
高価なのです」等と言われても、実際にはノイズだらけで、
その高感度は使い物にならなかったりする。
つまり、カタログ上の数値や性能ばかりを強調して、中身や
実用性が伴っていない事等は、不当な付加価値だ。おまけに
それで高価になった製品を買わせられるのだから、たまった
ものではない。こういう矛盾点は、消費者側で見抜いて
「買わない」等の対処をする必要があるのだが、まあ皆が
それをしてしまうと、縮退したカメラ市場が崩壊する。
結局、「付加価値の正当性」を見抜けない消費者層には
そうした高価な製品を買ってもらわなければならない訳だ。
Clik here to view.

価格(定価)が高価である事が、直接的に描写性能に結びつく
訳では決して無いのであるが、本レンズの場合は、幸いな事に
描写性能的には、殆ど問題点は見られない。
解像感が高く、最短撮影距離も40cmと短く、ボケ質破綻も
起こりにくい、では申し分無いではないか?という点だが・・
最大の課題は、この「大きく、重く、高価」という三重苦を
ユーザー側で、どう評価するか?だ。
これらの課題が容認できるのであれば、悪く無いレンズだ。
---
では次のレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:42,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回(第3位)
ハイコスパ名玉編第10回(第9位)記事等で紹介した、
2009年発売のAPS-C機専用AF標準(中望遠画角)レンズ。
Clik here to view.
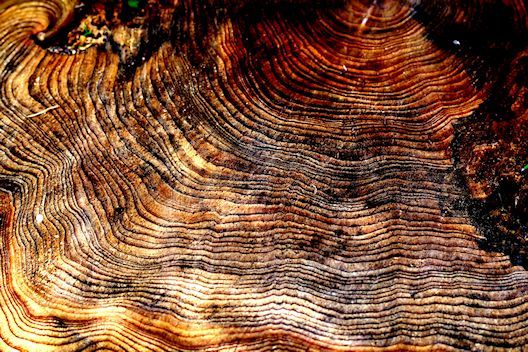
搭載であるが、内蔵手ブレ補正機能は入ってない。
(注:PENTAX機用なので、ボディ内にその機能がある)
まあ、と言うか手ブレ補正が入っている標準(級)レンズ
は極めて限られていて、私が知る範囲では、2015年の
TAMRON SP 45mm/f1.8 Di VC USD (Model F013)
くらいしか知らない。(レンズマニアックス第7回記事)
本DA★55/1.4だが、過去紹介記事でいずれも評価点が
高かった名玉である。
比較的新しい設計でありながら、その後の2010年代製品
のような過度な高付加価値型ではなく、発売時の実勢価格は
およそ8万円程度。オープン価格であるので、その後の
新品価格は6万円台位まで低下、中古相場は4万円以下に
まで落ちてきているので、近代の高性能標準レンズに比べ
買いやすい価格帯である。すなわちコスパがなかなか良い。
Clik here to view.

に加えて、新方式のエアロ・ブライト・コーティングを
採用している。
ただ、ある新技術を搭載しているからと言って、だから良い、
とか言う理由にはならず、技術はあくまで結果を得る為の
1つの手段にしか過ぎない。肝心な事は、トータルで優れた
描写性能が得られているか否か?である。
そういう視点では、本レンズの描写力は満足の行くレベル
である。APS-C機専用レンズなので、中望遠画角になって
しまうのがちょっとしたネックではあるが、これは元々、
銀塩時代のPENTAX FA★85/1.4(ミラーレス名玉編第1回)
のAPS-C機用代替レンズとして企画され、同一設計者の手に
よるものであるから、換算画角が82.5mmとなるのは当然だ。
(注:恐らくは、FA85の構成を2/3にスケールダウンした、
ジェネリック型設計であろう)
その出自から、(現在となってはセミレア品となっている)
「幻の名玉FA★85/1.4」の、やや独特な雰囲気の描写力
(この事が、言葉では伝え難いのがなんとも歯がゆい、と、
当該レンズの紹介記事では何度か述べている)が、本レンズ
においても、よく再現されている。
本レンズや、FA★85/1.4、それからFA77/1.8あたりは
光学ファインダーで覗いて見るだけで、他のレンズとは
違う、何か独特の雰囲気を感じる事ができる。
PENTAXでは20年程前のカタログで、それを「空気感」と
表現していた。まあ、わからない感覚では無いが、やや
抽象的すぎる用語表現であろう。
本DA★55/14の弱点は、SDM超音波モーターの作動音が、
高周波の可聴帯域まで落ちてきていて、その「チーッ」と
いう音がうるさい事位であるが、他は概ね問題が無い。
APS-C機専用とした事で小型軽量化を実現、かつ高描写力で
近代レンズとしては、値段もさほど高価では無い事が
総合的には好評価に繋がる。
さらに新しい2018年発売のフルサイズ対応標準レンズ
HD PENTAX-D FA★50mm/f1.4 SDM AW
との差異が気になるかも知れないが、あいにくそちらは
未所有だ。
まあ、もし最新型の描写力がとても良かったとしても
「高付加価値型レンズ」の場合は、価格が高いので、
中古相場が十分下がるまで、指をくわえて見送るしかない。
それに比べて、本DA★55/1.4は、現在では比較的こなれた
中古相場で購入する事が可能だ。DFA型を入手する迄の間の
繋ぎで買っても問題無く、むしろ、本レンズの優れた描写力
を知れば、さらなる最新型レンズへの買い替えや買い増しは
不要、と思ってしまうかも知れない。
Clik here to view.

本50mm選手権シリーズ記事の終盤に予定されている決勝戦
あるいはB決勝(下位決勝)に進出する事は確実だとは思うが、
また決勝戦近くになったら、その組み合わせを発表しよう。
なお、決勝戦では、個々の標準レンズの多項目による
評価点をあげ、それで優勝レンズを決定する予定だ。
---
では、3本目のレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:33,000円(新品在庫品)
使用カメラ:PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
ミラーレス・マニアックス第9回、第50回記事で紹介の、
2001年発売のCONTAX Nシステム用大口径AF標準レンズ。
(以下、NP50/1.4)
Clik here to view.

しまう主因となった「CONTAX Nシステム」の悲運の歴史
については、本ブログの様々な過去記事で紹介済みだが、
近年の記事としては、「銀塩一眼レフ・クラッシックス
第24回 CONTAX N1」編に詳しい。
興味がある方は、当該記事等を参照していただきたいが、
そもそも、Nシステムを現代において再興させようとする
のは、かなり困難である事は最初に述べておく。
まず、機体が無い。Nシステムには銀塩35mm判、銀塩中判、
デジタル(フルサイズ)があるが、どれも現代では入手が
困難か、あるいは入手できても実用性が皆無だ。
レンズの方もセミレアであり、中古があったとしても
コレクター向けのプレミアム相場で、コスパが悪い。
そしてNマウントレンズをデジタル一眼レフやミラーレス
機で使用できるようにするのは、さらに困難である。
2000年代にはNマウントをEF(EOS)マウントに換装する
サービスが海外で行われていた模様だが、今はその話も
聞かない。
また、マウントアダプターは、ごく短期間だけ、いくつかの
メーカーから、電子接点型、および機械絞り羽根内蔵型が
発売されていたが、販売数が少なく、殆どが現在では生産
終了と思われ、アダプターの入手も困難だ。
それから、サポートあるいは情報収集も厳しい。
京セラがカメラ事業から撤退10年後の2015年には、サポート
(補修サービス)も終了し、現在の京セラのWEBページ
からは過去機の情報(取扱説明書含む)も削除されている。
WEB上にも(SNS等が普及前の時代であった為)、有力な
Nシステムに関する一次情報は殆ど見当たらない。
(注:スペック等を転記するだけの二次情報は稀に存在する)
なので、本ブログにおいて様々なNシステム関連の記事を
書く際には、手元にある限られた機材を触りながら、あるいは
記憶をたどりながら、はたまた同時代の他の写真機材環境から
類推しながら、「一次情報」をまとめていた状況である。
Clik here to view.

第一印象であろう。それでも、重量は310g程度に留まり、
本記事冒頭に紹介の(最)重量級標準SIGMA A50/1.4の
815gのおよそ1/3程度でしか無い。
前機種、RTSマウント版のPlanar T* 50/1.4
(本シリーズ第1回等)との比較であるが、レンズ構成は
同じ6群7枚であるが、レンズ後群の設計がずいぶんと異なる
ように見える。具体的には、旧来のP50/1.4は、後玉が
平面または少し凹だが、本NP50/1.4は後玉が凸面である。
これはデジタル化を見据えた、テレセントリック特性への
配慮だと思われる。
この設計の微妙な差異によるものか、本NP50/1.4は
旧来のP50/1.4よりも、ボケ質破綻(いわゆるプラナーボケ)
が出にくい。
この長所は実用上はかなり好ましく、1つは旧来のP50/1.4
は、撮影条件(撮影距離、絞り値、背景の図柄等)が整った
時にしか最良のボケ質を得る事が出来なかったのが、
本NP50/1.4では、多くの撮影条件で優れたボケ質を発揮
する事が出来る事だ。
もう1つは、これは使用機材の問題であるが、私が使用して
いるCONTAX N→μ4/3のマウントアダプターは、機械絞り羽根
内蔵型である、これはレンズ後群のさらに後ろに、絞り羽根が
存在する事となり(=視野絞り型)、後群からの光束を遮り、
露出値(光量)調整の意味はあるのだが、本来のレンズ内部に
絞り羽根が存在する状態(=開口絞り型)と比べて、絞り羽根に
よる被写界深度調整やボケ質のコントロールが殆ど効かない。
つまり絞り値によるボケ質破綻の回避の技法が使えない、という
事であり、もし旧来のP50/1.4のように、ボケ質破綻が頻繁に
発生するタイプのレンズだったら、このアダプター仕様では、
回避が困難で、お手上げであっただろうからだ。
ちなみに、何故、機械絞り羽根内蔵型のアダプターを使用
せざるを得ないか?と言えば、CONTAX Nマウントの絞り機構
は電子制御タイプであり、一般的なアダプターでは絞り羽根
が動かないからだ。
これは別にNマウントだけの仕様ではなく、他社のEOS EFや、
4/3(フォーサーズ)、ニコンE型レンズ(電磁絞り)等でも
同様である。
Clik here to view.

初級マニア等であれば、CONTAXと名前が付けば、良く写る
レンズだと勘違いしてしまい、良く写るから高いのだと誤解
してしまい、さらにそれを無理して買えば、高く買ったの
だから良く写ると、どんどんと妄想の世界に入り込んでしまう。
冷静に本レンズの描写力を見れば、ここまで散々5回の記事で
紹介してきた数十本の「並の標準レンズ」と大差は無い。
だた、並だから、悪いのか?と言えば、そういう事も無く、
どの標準レンズでも普通に良く写る。
しかし、本NP50/1.4も、その範疇からは脱却できていない。
ちなみに、ほぼ同時期に発売されたNシステム用の
N Planar T* 85mm/f1.4(ミラーレス名玉編第3回、
第10位相当)は、とても気合を入れて開発されたレンズだった。
本レンズNP50/1.4は、当時のマニア層から
「旧型のRTS Planar 50mm/f1.4にAFの側を被せただけ」
と揶揄されていたのだが、それは間違った情報であった。
まあ、色々言っていた人達は、結局誰もNシステムを購入して
いなかったのだ。だから何が正しくて、何が間違っているの
かも、わかる筈も無い。
まあでも、正直言えば、そこまで悪く言う必要は無いが、
NP85/1.4への気合の入り方から比べると、本NP50/1.4は
少々手抜きして作られたレンズのようにも見えてしまう。
それは、旧来のP50/1.4に比較して、大幅に改善した点が
あまり見受けられないからだ。
で、何故NP85/1.4の場合は、旧来のP85/1.4に対して
相当に気合を入れて改良が計られたのか?と言えば、
それは、旧RTS Planar T* 85mm/f1.4が、初級マニア層
や金満家層から「神格化」されたレンズであったからだ。
RTS P85/1.4は、実際の性能的には様々な弱点を持つ
レンズではあるが、それをここで書いていくと際限なく
文字数が増えるので、ばっさり割愛しよう。
(以前の様々な記事でも、そこについては述べている)
でも神格化されていれば、CONTAXの「顔」(代表的な)
レンズである新型NシステムのNP85/1.4は、旧P85/1.4
の弱点を徹底的に改善しなければならない。
(そもそも、27年も発売時期が異なるのだ・・)
ボケ質破綻の改善や焦点移動の問題は、若干の改善が
図られたが、ピント精度による歩留まりの悪さの改善は
出来なかった。これはNP85/1.4に限らず、殆どの85/1.4級
レンズでの宿命であり、一般的に成功率は10%程度、つまり
10枚中9枚までは、ピントを外してしまう。
この問題の解決には、カメラ側にも新機能が搭載された。
CONTAX N1(2000年、銀塩一眼第24回記事)では、
「フォーカス・ブラケット」機能により、ピント位置を
わずかにずらしながら3連写を行う。
ここから、ピントの合っている写真を探す訳だ。
「その機能を使うと、フィルムが3倍無駄になる」等とは
言うなかれ、この機能を使わないと、前述のように、
10枚中9枚はピントが合わず、さらにフィルムが無駄に
なってしまうのだ(汗)
余談が長くなった、本P50/1.4は、NP85/1.4ほどには
気合を入れて作られたレンズでは無いが、とは言え、
問題があるレンズでは無い。ともかく銀塩用標準レンズは
どれも良く写るのだ。
---
では、4本目のレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:110,000円(中古品)
使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第3回(第6位)記事等
多数で紹介した、2014年発売のAPS-C機専用AF標準
(中望遠画角)アポダイゼーション・エレメント搭載型
特殊レンズ。
Clik here to view.

述べていくと際限なく文字数が増えてしまう。過去記事
でも色々と詳細を書いているので、今回は割愛しよう。
(特殊レンズ第0回「アポダイゼーション・グランド
スラム」編記事等を参照の事)
簡単に言えば、「ボケ質の大変良い」レンズである。
グラデーション状に透過率が変わる(周辺が暗い)
光学フィルターを内蔵していて、これをアポダイゼーション
光学エレメントと呼ぶ。
この機能を搭載している(交換)レンズは4本のみであり
1998年より長らくは、MINOLTA STF135/2.8[T4.5]
(後にSONY版)(ミラーレス・マニアックス第17回記事等)
のみであったが、2014年、突如本レンズが発売された。
その後も、中国製LAOWA 105mm/f2が2016年に、
(ハイコスパ名玉編第1回記事等)
2017年にはSONY FE100mm/f2.8 STF GM(グランドスラム
記事等)と、アポダイゼーション機構を持つレンズが続けて
発売された。
Clik here to view.

同スペックで、アポダイゼーションを搭載していない
XF 56mm/f1.2 Rが存在する。そちらは未所有なので
両者を比較する事はできないが、アポダイゼーションの
「付加価値」(=値段を高くする要素)が無いので、
新品定価はAPD版の20万6000円(+税)に対して、
ノーマル版は13万1000円(+税)と、かなり安目だ。
ノーマル版はアポダイゼーション光学エレメントが無い分、
実効F値であるT値を比較すると、T1.7対F1.2と明るい。
アポダイゼーションの有無により、解像度等、若干光学特性
が異なるかもしれず、ノーマル版もコスパ面では魅力的だ。
本APD版の弱点だが、極めて高価な事だ。
だがまあ、その点は「高付加価値型商品」であるから、
やむを得ない。
部品代の差は、アポダイゼーションの有無だけなので、
20世紀型のような製造原価からの定価決めの構造であれば
それだけで7万円も定価が上がる筈はなく、要は開発費の
減価償却が乗っている事とか、「この価格でも欲しい人は
買うだろうから」という市場原理上での値付けである。
これがまあ「高付加価値型商品」の特徴であり、
要は、「高くても売れる可能性がある商品だ」という事だ、
消費者側から見れば、どうしても欲しいと思えば、買うしか
無いし、コスパが悪すぎると思えば、買わないという選択だ。
では、このレンズを買う意味(意義)があるのかどうか?
そこは、コスパの感覚が多分に影響する事であろう。
「コスパ」を主要な購買論理とする私としては、
性能に比べて値段が高すぎる商品は買わない、という事が
殆どなのだが・・・
ここで言う「レンズの性能」とは、一般的に想像するだろう
写り(描写力)だけという訳ではなく、私の場合は、
他のレンズ評価記事で行うように、様々な評価要素を総合
して性能(価値)を決めていく。
本XF56/1.2APDの場合は、発売時には、史上2本目で16年
ぶりに新発売されたアポダイゼーションレンズであり、
かつ、史上初のAF対応だ(その後、SONY FE100/2.8STF
もAFで発売された)これらからの、マニアック度や
歴史的価値、所有必要度が高く、それらを総合的に考え、
購入を決めたのだが・・ 問題は価格であった。
定価税込み22万円強はさすがに高すぎる、新品市場価格は
18万円程であったが、それでも同様に非常に高価だ。
1年ほど中古が出るのを待って、税込み約11万円で、やっと
中古入手した次第である。
ちなみに、13万円を超える価格のレンズは、どんなに性能が
高くても買わないようなルールを設けている。
もしそういうレンズがあれば、中古が13万円より下がる迄、
何年でも待つのだ。(注:近年のレンズ価格の上昇を
鑑みて、最近、このルールは最大15万円迄に緩和した)
さて、描写性能的にはどうか? そこが優れていないと、
高価で買ったのが無駄になる、つまり、コスパの原点である
描写力が低ければ、どんなにマニアック度等が高くても
意味が無い。もし、そうなった場合は「ぼったくりレンズ」
として、個人的に嫌いなレンズの代表格となってしまい、
使わない、酷使して使い潰す、あるいは処分(譲渡)して
しまう、など、そういう措置になってしまうのだ。
「そんなもの(描写力)は、買う前にわかるだろう?」とは
言うなかれ、WEB上のレビュー記事などでの掲載作例等は
ある撮影条件で撮られたものであって、全ての撮影条件
まではカバーできないのは当然だ。
それに、良く写っている写真ばかりを掲載するのも、
まあ当然の措置であろう。であれば、例えば具体的には、
ボケ質破綻が発生する条件や、その場合の作例などは
いくらレビュー記事を検索しても、見つかる筈が無い。
結局、他人の評価は全く参考にする事が出来ず、自身で
購入後、しかも、何千枚も、何万枚も撮ってからでないと
レンズの真の性能(描写力)は見えてこないのだ。
Clik here to view.

若干解像感が甘く感じ、ボケ質破綻も稀に発生する。
いくらアポダイゼーション・光学エレメントを搭載して
いるからと言って、ボケ質以外にも全てのレンズ性能が
向上する訳でも無い。むしろ、マスター(主)レンズの
基本性能が低いと、アポダイゼーションを搭載していても
意味が無い訳だ。まあ我慢できない程性能が低いという
訳では無いが、「高価なレンズなので、高い基本性能は
期待してしまう」という課題もある。
本レンズは、8群11枚のレンズ構成で、非球面レンズ1枚、
異常分散レンズ2枚と、まあ贅沢な設計ではあるが、
レンズ構成を複雑化するのと、性能が上がるのはイコール
だとは言い切れない。
なお、開放F1.2級の標準レンズは設計が難しいのか?
MF時代からも色々出ているが、あまり感動的という描写力
を持つレンズには、出くわした事は無い。
(次回記事で紹介予定)
ましてや、それ以上の大口径、F1.0やF0.95ともなれば
なおさらであり、大口径化と、様々な描写性能は、
トレードオフの関係(どちらかを優先すれば、どちらかが
成り立たない)ようにも思えてしまう。
本XF56/1.2APDは、悪くは無いレンズではあるが、
購入を検討する際は、コスパの悪さは覚悟しておく必要が
あるだろう。そのあたりも、購入側が、マニアック度や
歴史的価値をどう判断するか?のトレードオフだと思う。
---
では、今回ラストのレンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格: 85,000円(中古品)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)
(以下、Milvus50/1.4)
2016年に発売の高解像力仕様MF大口径標準レンズ。
レトロフォーカス(ツァイスで言う「ディスタコン」)
構成という極めて珍しい標準レンズだ。
MFレンズではあるが、新鋭レンズにつき、便宜上
この「AF50/1.4」のカテゴリーでの予選対戦とする。
Clik here to view.

まあ、現代のカール・ツァイス銘の写真用交換レンズは
正式に公表されてはいないが、全て日本製(コシナ、他)
である。
さて、本レンズは「高付加価値型商品」である、つまり
一眼レフ市場の縮退を受け、メーカーや流通が利益を確保
する類の商品であるから、ユーザーから見たコスパは悪い。
そして、8群10枚というレンズ構成は、重く(約900g)
大きく(フィルター径φ67mm)、そして高価(定価が
税込み16万円以上)であり、おまけにMFレンズという
「四重苦」である。まあでも、一部はSIGMA A50/1.4
(前述)やOtus55/1.4(未所有)より若干はマシだ。
MFである点も、ZF2マウント(ニコン用)を買っておけば
ニコン機や他社機のほぼ全てで(アダプターを介して)
装着して全く問題なく使用できるという長所に繋がる。
では、何故このような「四重苦」レンズを購入するのか?
と言えば、これはディスタゴン構成の標準レンズへの
知的好奇心が大きい、つまり「研究用」なのだ。
別に「(有名な)ツァイスだから良く写る」などと
初級中級者の持つ誤解のような考えは持っていないし、
そのブランド力をアテにしたり、所有満足度を得る為の
購入では無いのだ。
Clik here to view.

持つ事である。特に不満点はなく、普通にとても良く写る。
特に優れた点はコントラストの高さであり、使用カメラが
変わったかのような印象を受ける。
しかし、この長所は、やはりコスパを意識しないとならない
であろう、いくら良く写るレンズでも、とんでもなく高価で
あったらコスパ評価は極めて悪くなる。
現状、私の評価データベースでの本レンズのコスパ評価は
5点満点で2点である、つまり平均的よりやや低い。
ただ、「壊滅的にコスパが悪い」とは言い切れず、
まあ、SIGMA A50/1.4と同等のコスパ点、および他の
評価傾向も、ほぼ同一である。(いずれも総合点4点)
先日、量販店の店頭で、ツァイスの営業(販売)担当者
が居たので、わざと、ちょっと意地悪な質問をしてみた。
匠「MilvusやOtus、なかなか良さそうですねえ。
SIGMAのARTと迷っているのですが、どちらが良いですか?」
担「う~ん、SIGMAさんのARTシリーズも評判が良いですね」
まあ、そういう答えになるだろう。そこは予想済みだ。
結局、ツァイス側としても、SIGMA ART LINEは意識している
という、ライバル関係だと思われる。
私の評価では、どちらを買っても良いと思う。
AF(超音波モーター)で現代的な撮影技法を用い、
趣味撮影のみならず業務撮影用途も意識するならば、
SIGMA ART LINEが効率的だと思うし、
趣味撮影オンリーであれば、MFでマウント汎用性が高い
Milvusが好ましい。
Clik here to view.

なれば全く不満は無いだろうし、目につく弱点も無い。
消費者側としては、自身の用途に合わせて選択すれば良い
という事になる。迷って悩むならば、両方買ってしまう
という選択肢もある、多少強引で、予算も必要な話だが、
精神的にはそれで満足するだろうし、「最良のレベルの
標準レンズ」という価値観や判断基準が、どのあたりと
なるのか?も理解できる事であろう。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Fブロック「AF50mm/f1.4 Part2」の記事は終了だ、
なお、本記事の紹介レンズの中には、決勝進出の可能性
が高いものが多いだろう事は述べておく。
次回の本シリーズ記事は、
予選Gブロック「MF50mm/f1.2」となる予定だ。