本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に
紹介している。
今回の記事では、Voigtlander(フォクトレンダー)
(注:記事記載の便宜上で通常のASCIIコードで書きたい為、
aの変母音(ウムラウト)の記号記載は省略する)の、
レンジファインダー機(以下、適宜、「レンジ機」と略す)
用の交換レンズを4本紹介しよう。
なお、ここで言う「フォクトレンダー製」とは、1999年に
その商標を取得した、日本のコシナ社製のものである。
それから、現代のコシナ・フォクトレンダーは、むしろ
レンジファインダー用のレンズよりも、ミラーレス機用の
高級レンズ(マクロ・アポランター等)のブランドとして
著名であろう。本シリーズでは、第11回記事で、既に、
その手のレンズの特集も行っているが、今回の記事では
レンジ機用のものに限定して紹介する。
----
まず最初のシステム
![_c0032138_19520184.jpg]()
(中古購入価格: 35,000円)(以下、SWH15/4.5)
カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)
1999年に発売された、高描写力単焦点超広角レンズ。
初期型であり、ライカLマウント(M39,L39と記載、現代の
ライカ製等のミラーレス機用Lマウントとは異なる)
対応品である。
その後、2005年頃にライカMマウント対応(VMマウント)
のⅡ型となり、距離計連動型となった。
2015年には、レンズ構成を改良した(注:やや大型化した)
Ⅲ型となり、VMマウント用の他、2016年には、SONY E(FE)
マウント版も追加された。
![_c0032138_19520194.jpg]()
まず、「フォクトレンダー」という最古の光学機器メーカー
のブランドが突如国産品として蘇ったのが衝撃的だ。
その当時は「中古カメラブーム」である。銀塩からデジタル
まで、あらゆるタイプのカメラが新規に発売された混迷期だ。
銀塩レンジファインダー機も勿論人気で、M型ライカや
バルナックライカはもとより、ニコンSシリーズ、旧CONTAX
ミノルタやコニカのレンジ機など、マニアあるいは投機層は
ありとあらゆる新旧機種を買い漁っていた時代だ。
世間では、「ニコンから復刻版Sシリーズが発売される」
という噂(注:S3ミレニアム、2000年、発売時48万円)
も流れていたくらいなので、新製品の銀塩レンジ機が
今更ながら新発売されたとしても誰も驚かない。
旧「フォクトレンダー」については、上級マニア層が注目
するブランドであった。レンジ機では無いが、ヴィトーや
ヴィテッサ等の、美しく格好良いカメラが中古で流通して
いたので、それらを入手するマニアも居た。
(余談:熱心なファンも居る人気機種である。後年2010年代
には、TVアニメ「有頂天家族2」でも作品中にヴィテッサが
登場している。中古カメラブームの際は高額ゆえに、入手が
出来なかったが、20年が経過した現代では、老舗中古専門店
等で2万円前後で見かける場合もある。→しかし、未所有)
コシナは老舗OEMメーカーである。OEMとは他のカメラメーカー
から依頼されて、そのメーカーのブランドでカメラやレンズを
製造するという意味だ。場合により設計も担当する訳であり、
自社ブランドの名前が世の中に出ないだけで、とても技術力の
高いメーカーであった。
(余談:銀塩時代でも、こういった風に、製造等は、様々な
企業で分業されている為、「ブランド」という意味は希薄だ。
ビギナーが良く言う「どこのメーカーのカメラが良いのか?」
という質問は意味が無く、結局、どこの物を買っても同じだ。
この傾向はデジタル時代に入ってさらに顕著となり、それは
とても1社だけでは作れず、各社共通の部品などを使いまわし、
もはや、カメラについているロゴ名だけが異なるという状況だ。
あるいは「自社製センサーだから」とか「XXという新技術
を搭載しているから」とかの細かい事は言わないのが賢明だ。
もし他社製品に比べて、明らかな性能差がある場合、そこは
「追いつけ、追い越せ」で、少し時間がたてば、必ず各社の
機器の性能は同等レベルに落ち着く次第だ)
コシナは1990年代までは、ブランドの知名度が無く、よって
たまにコシナ自社名で発売するカメラやレンズは、新品でも
「定価の7割引き」とかの不自然な価格で販売されていた。
つまり、そこまで安価にしないと売れない訳だ。すなわち皆、
「コシナなんてメーカーは知らない、どうせ性能も悪かろう。
まあ、7割引きなら試しに買ってみようか」
という感じであった。
これはコシナの高い技術力からすれば、とてもアンバランス
な状態だ。
まあ、不勉強な消費者側(コシナを知らない、ブランドを
意味も無く信奉する)にも問題点があるのも確かではあるが、
一部の上級マニア層では、こうした不条理な安値で売られて
いるコシナ製品を入手し「意外に良く写ってびっくり、しかも
とても安い、これはなかなかコスパが良い」と、夢中になった
人も数多く居た。
で、こんな状態なので、コシナは「ブランド」を強く欲した。
しかし、1970年代にヤシカが「CONTAX」のブランドを買った
際には(それだけが理由とは言い切れないが)、資金繰りが
厳しくなって、経営破綻してしまい、京セラの資本投下で
なんとかCONTAXの販売を継続できた、という歴史がある。
(ここも、初級マニアが良く言う「CONTAXって凄い性能なの
でしょう?」という思い込みに関連して、良く理解する必要が
ある歴史だ)
で、コシナが、またあまりに強力なブランドを高値で買って
しまうと同様に資金的な負担が過剰になってヤバい事となる。
で、その当時、宙に浮いていた適正(適価)なブランドが
「フォクトレンダー」であった、という事なのだろう。
が、日本では、この老舗ブランドもあまり知られていない。
中古カメラブームとは言え、海外カメラ市場などにも詳しい
マニアは、かなりの上級層であり、一般的には、NIKON、
ライカ、CONTAX(カール・ツァイス)しか、知られておらず
そうしたカメラは投機的要素で高値で売れるのだ。
(つまり、何もわかっていないビギナー層が高値で買うから、
売る側も高値で売ろうとする。あるいは、さらなる値上げを
期待して購入する。そうやって、どんどんと際限なく相場が
吊り上り、結果「カメラバブル」となった訳だ。これは勿論、
買う側がしっかりと製品価値を判断すれば止まる話だ)
まあしかし、コシナが出した新製品においては、
「フォクトレンダーとは・・」等と、その歴史を紹介する
雑誌等のメディアも多く、好意的に受け入れられた。
そこから、畳み掛けるようにコシナ社はフォクトレンダー
ブランドのカメラやレンズを2000年代前半にかけて非常に
多数展開する、その数は多すぎて紹介できないくらいだ。
すなわち、もうとっくにそれらの設計は完了していたので
あろう、「後は名前をつけるだけ」という状態だったと思う。
それに、恐らくは非常に高いお金を出して購入したブランドだ、
早く、沢山の製品を出して、そこにブランド名の利益を乗せて
購入金額を回収しないとならない、さもないと他社の前例の
ように資金繰りが悪化して経営がヤバくなる。
で、「ブランド」なんて、結局、そんなものなのだ。
例えば、現代のスマホのカメラでも、ごく普通の設計のレンズ
に有名光学機器メーカーの名前をつけて、それを「付加価値」
としているケースも多々ある。
それにより、機器販売側は、ブランドの使用料で払った分を
定価に上乗せして、そこで釣り合いを取る訳だ。
面白味の乏しい事業構造であるが、そういうブランド名を
ありがたがる初級ユーザーが居る事で、世の中は上手く回る
仕組みなので、そういう人達にせっせと業界に貢いでもらおう。
私はカメラ業界とは何も関係が無いが、欲しい機材を適価で
購入したいので、市場は潤ってもらうことが望ましい。
![_c0032138_19520110.jpg]()
マニアックであった。
まず「マニアを落とす事」が、このブランドでの基本戦略だ。
どうせビギナー層では、「フォクトレンダーやらを買っても
廻りの人達は知らないから自慢できない、買うならばニコン
やライカを買うよ」という超下世話な論理になってしまう。
マニナ層に受けるために、国産フォクトレンダーは初期から
現代までを通じて、極めてマニアックな仕様を貫いている。
ここは企画側が、マニア心理を非常によく理解していると
思われる。というか、コシナの殆どのメンバーがマニアなの
だろう。そうでないと、そういう製品企画は出来ない。
他の大メーカーの製品は、「優等生的」等とよく称されるが、
それは褒め言葉でもあるが、マニア的な視点からは
「何も面白味が無い製品」という状態と等価である。
まあ、マニア受けを狙わず、一般に誰にでも広く受け入れ
られる製品企画なのだろうと思う。(そして下手をすれば
大メーカーの企画や開発の担当者とは言っても、殆ど
写真など撮っていないかも知れないのだ。そう思う根拠
としては、そのカメラやレンズを持って、ものの1時間も
撮影すれば、誰でも気づくだろう重欠点を持つ機材等が、
平気で販売されている状況だからだ)
コシナ・フォクトレンダー最初期の機種、BESSA-L(1999年)
は、変わった仕様のレンジファインダー機だ。
(注:Bessa L等と、小文字で書いたりハイフン無しは間違い)
ファインダーを持たず、今回紹介レンズのSWH15/4.5との
セットで発売された状態では、「目測式カメラ」となる。
付属15mm用ファインダーは外付けが出来るが、近接撮影では
パララックス(視差)が発生するし、勿論このファインダーは
ピント合わせもボケ確認も出来ない、構図確認用の素通しだ。
よって、ノーファインダーで撮るマニアも多かった。
(ただし、このファインダー像は、とても綺麗で好ましい)
ピント合わせは、目測またはパンフォーカス技法を用いる。
露出計は内蔵されているが、機械式カメラ故に電池が無くても
撮影可能だ。パンフォーカス方式で絞りをF8~F16に設定
するのであれば、「Sunny Sixteen」や「感度分の16」による
「勘露出決定技法」が使えるため、最悪電池切れになっても
問題なく撮影が継続でき、さらにマニアックに使うならば
電池をあえて抜いてしまう。
そうすると、初級中級者では「どうやって撮るのだ?」という
撮影不能のカメラとなり、マニア層または上級者のみが使える
カメラとなる事で、周囲に対して鼻が高い(自慢できる)訳だ。
さて、BESSA-Lの余談が長くなった。
同時に発売された、本レンズSWH15/4.5は、非常にインパクト
のあるレンズであった。
これまでのレンジ機用超広角レンズと言えば、ツァイスの
Hologon(ホロゴン)が著名で、オリジナルは「幻のレンズ」
であった事から、1990年代の京セラCONTAXのGシリーズの
AFレンジ機用に新発売された「ホロゴン」にマニアは夢中に
なっていた。しかし、リバイバル版も定価20万円台という
極めて高価なレンズなので、おいそれと購入できない。
そんな中、本SWH15/4.5は、発売時定価の詳細はもう記録
が残っておらず不明ではあるが、恐らくは5万円台くらいの
定価だったと思うので、やっと普通に買える価格帯の
レンジ機用の高性能な超広角レンズが出た訳だ。
マニア層は、これを入手し「ホロゴンと同等の写りだ」
(「プアマンズ・ホロゴン」という呼び名も多かった)
と賞賛した。(注:本当にホロゴンを知っているかは疑問)
ホロゴンでは強くあった、レンズ設計上の「周辺減光」は
賛否両論あったが、特徴ではあった。
本SWH15/4.5でも比較的強い周辺減光が出る。
ただ、これについては、後年のデジタル時代では、周辺減光
の効果は、レタッチ(画像編集)でも簡単に後付けできるので
最初から周辺減光がある事は、あまり望ましくない場合もある。
この為、本SWH15/4.5もⅢ型あたりからは周辺減光が減って
いると聞く。(注:未所有)
今回、私の使用法では、本レンズをAPS-C機のFUJI X-E1に
装着し、周辺減光をある程度カットして使っている。
画角は超広角らしくない約22mm相当にまで狭くなるが
まあそれは、撮りたい被写体用途次第とも言え、15mmを
フルサイズ機で使うと、あまりに広すぎ、パースペクティブ
が大きく、その歪みもあって、被写体の制限が厳しすぎる
ケースもあるからだ。
![_c0032138_19520191.jpg]()
入手はまず不可能、欲しければ後年のレンジ機用のⅡ型か、
現行のミラーレス機用Ⅲ型を買うしか無い。
描写傾向はⅢ型では恐らく変わっているとは思うし、価格も
だいぶ高価にはなっているが、まあ、それもまたユーザーの
捉え方次第であろう。ともかくマニアックなレンズなのだ、
必須のレンズとは全く言い難いが、欲しければ買うしか無い。
----
では、次のシステム
![_c0032138_20092148.jpg]()
(新品購入価格: 44,000円)(以下、CS50/2.5)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
前記SWH15/4.5より後の2002年に発売された
レンジ機用Lマウント仕様の小口径高品質標準レンズ。
独フォクトレンダー時代の「スコパー」とは、テッサー型
の単純な3群4枚レンズ構成のものを示していたが、
本スコパーは6群7枚の変形ガウス型構成となっている。
小口径である事で、諸収差が良く補正されていると思われ、
きわめて良く写るレンズで、個人的にもお気に入りだ。
![_c0032138_19522270.jpg]()
長さは、本レンズの場合では75cmと、これは依然、
一眼レフ用の標準レンズの最短(平均)45cmより、だいぶ
長いのではあるが・・
それでも、望遠になればなるほど、その不満は緩和される
(例:90mmレンズで最短90cmならば、一眼レフもレンジ機も
同じだ)
それに現代は「ヘリコイドアダプター」や「デジタルズーム」
で、物理的または仮想的に最短撮影距離を短縮可能だ。
本記事で使用するアダプターはヘリコイド型では無いが、
優秀なデジタルズーム機能を持つNEX-7を使用し、その機能も
必要に応じて使う事とする。最短撮影距離は縮まらないが
そもそもAPS-C機で75mm相当の画角で最短75cmは標準的であり
デジタルズームで撮影倍率は、いくらでも上げる事ができる。
![_c0032138_19522264.jpg]()
レンズ自体の極めて高い質感や感触性能も、さらなる長所だ。
超小型でありながら真鍮製の鏡筒は、208gと
ずっしりとした重さがあり、ピントレバーがあって回転の
感触も極めて良い。
価格はそう高くない(発売時定価45,000円、銀色版)
のではあるが、開放F2.5と地味なスペックの標準レンズで
あるが故にか?あまり流通していないレンズであり、後年や
現代において中古で入手するのは結構困難であろうと思う。
あまり褒めてしまって、中古がプレミアム相場になって
しまったらかなわない。あまり褒めれらない要素もあげて
おくならば、本レンズそのものの欠点は殆ど無いものの、
この仕様であれば「世の中に代替できるレンズはいくらでも
存在する」という点だ。
たとえば、50mm/f1.8級の一眼レフ用小口径標準レンズで
本レンズに勝るとも劣らない描写力を持つものは、銀塩時代
1970年代以降のMFレンズにおいて、何本でも存在する。
そうした旧型のMF標準レンズは、現代ではジャンク価格で、
1000円から購入できるし、AB級のまともな個体でも5000円
も出せば十分だ。それらの小口径標準の方が、最短撮影距離
も開放F値も優れており、劣る部分はレンズの「質感」の
要素だけである。
![_c0032138_20092563.jpg]()
デジタルのライカを使わない限りでは、一眼レフやミラーレス
機で本レンズを使うくらいならば、一般的な一眼レフ用レンズ
を使った方が、はるかに実用的な利便性は高い。
まあ結局、本CS50/2.5も、極めて趣味性の高いレンズで
あるという事であろう。
----
では、次のシステム
![_c0032138_19523302.jpg]()
(新品購入価格: 30,000円)(以下、SC35/2.5)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
またしても歴史を語るのが面倒な(汗)レンズの登場だ。
前述の中古カメラブームを受け、ニコンがS3ミレニアムと、
後に復刻SPを発売した。
それに便乗して、コシナ・フォクトレンダーでも、NIKON S
マウントおよび旧CONTAX Cマウントの極めてマニアックな
カメラを発売した。
それがBESSA-R2S/R2C (2002年)であり、それにともない、
ニコンS機、コシナ新型機、および旧製品のNIKON S,CONTAX
C機で使用可能なレンズ群を、8種類ほど限定発売した内の
1本が本SC35/2.5である。(注:正確に言えば、本レンズ
等はR2S/R2C発売以前の、S3ミレニアムの時代からの製品)
SCとは、NIKON SおよびCONTAX Cで使える、という意味だ。
![_c0032138_19523342.jpg]()
だろう、とコシナは企画したのだろうが、蓋を開けてみると
SCシリーズは極めて不人気なレンズ群となってしまった。
その理由は、50万円以上と高価なNINKON Sシリーズを
購入するユーザー層は、ほとんどがコレクション(愛蔵品)
か、投機(転売による利益確保)を目的としたユーザー層で
「実際に写真を撮る」オーナー等は失礼ながら皆無であった
訳だ。事実、それらの機体で写真を撮っている人を、以降
発売後20余年、私は一度も見かけた事が無い。
コシナが「写真を撮る為の道具」としてカメラやレンズを
設計するのは、当然の論理だ。特に上級マニア層に向けての
製品戦略であれば、そこは必ず意識する必要がある。
しかし、市場のユーザーは、実際にはそうとも限らない、
特にこの手の機体では、誰も写真を撮らないし、愛蔵版
カメラ等では、使ったら価値が落ちるので、なおさらだ。
これはコシナ等のメーカー側からしてみれば「残念な事実」
だと思う(ただ、愛蔵版を作るニコンからは、それは想定内
の製品戦略だ。他に実用カメラを買って貰えれば、なお良い)
それにしても、せっかく買った機材を死蔵させてしまう事は、
マニア的視点からも残念な話だ。
で、「写真を撮らないのであれば、交換レンズも買わない」
この、ごくシンプルな理由で、これらのSCレンズ群は
各々数百本(800本位?)の少数限定販売でありながらも、
販売店側でも在庫を持て余すようになってくる。
発売から1~2年経った頃、在庫品を持て余した販売店から
「匠さん、SCレンズ買ってくれないかな? 安くしておくよ」
という申し出があった。
実は、その頃、前述の(超レア機)BESSA-R2Cも、その店で
新品購入していたので、店主は私が買う筈だと睨んだので
あろう。
でも私は、BESSA-R2Cには、旧ソ連KIEV(キエフ)用の
ジュピター・シリーズのレンズを装着して使うつもりで、
ボチボチとそれらを探し集めていたのだ。
ジュピター(ユピテル)は独ツァイス製品のデッドコピー
レンズであり、コスパが良くマニアックだ。
現代のコシナ・フォクトレンダー製品は、あまりに良く
写りすぎてしまうだろう事は明白で、私が想定している
機材利用コンセプトにそぐわないし、それにSCレンズは
そうした「富裕層」向けの「高付加価値型商品」であり
価格が高価すぎて、コスパが極めて悪い。
匠「う~ん、どうしようかなあ」と一旦は保留したが、
店主はさらに値引した価格を提示してきたので、
やむなく(笑)、本SC35/2.5と、後述のSC21/4を
合わせて購入する事にした。
さて、購入したSC35/2.5は、デザインが格好良く、
そこそこ作りは良い。しかし、既にライカL39マウント版で
発売されていたスコパー35/2.5と中身は同じレンズであり、
外観の変更だけで高価になっているのは、どうにも納得が
いかない。
![_c0032138_19523367.jpg]()
最短撮影距離は90cmと極めて長く(注:レンジ機での
距離計連動での制限)、中遠距離のスナップや風景など
ありきたりの撮影技法での、ありきたりの被写体にしか
向かず、急速に興味を失っていった。
(注:今回の使用では、μ4/3機+デジタルテレコンで
撮影倍率の低さの弱点を緩和している)
その直後にデジタル時代になった為、SCレンズや他の
レンジ機用レンズは、デジタル一眼レフでは使いようもなく、
たまにマニアの集まりに「珍品」として持ち出す程度で、
長年、防湿庫に眠る羽目となったが・・
さらに後年、2010年前後からミラーレス時代となり、
L39マウントやNIKON Sマウントのアダプターが発売される
ようになって、やっと復活する運びになった次第だ。
だが、いくらアダプターがあるとは言え、これらのSCレンズ
が主力となる事は有り得ない。最短撮影距離も長すぎるし、
SCレンズは、ピントの繰り出し量が中途半端な設計の為
(すなわち、NIKON SとCONTAX Cのマウントは形状互換
だが、ピント繰り出し量が異なり、完全な互換性は無い。
そこで、広角レンズのみ、被写界深度の深さで、どちらの
マウントにも対応できるような中間的な構造となっている)
・・の為、アダプター使用時のピント合わせも不自然な
状態となって使い難い。
結局、アダプター使用時にも、少し絞り込んで、
被写界深度を稼いで、ミラーレス機のピーキング便りに
撮るしか無く、結局中遠距離の被写体を、銀塩時代と
同じ技法で撮る事になり、テクニカルな要素が何もなく
エンジョイ度の極めて低いレンズとなってしまう訳だ。
まあ、レンジ機全てで、同様な課題があった事実は
私も、いくつかのレンジ機を銀塩時代に購入した時点で
良くわかっていた。「これらは、真面目に写真を撮る為の
道具ではなく、コレクション向きだ!」という感覚が強く
出た為、私は、フォクトレンダー系での最小限(2台)の
レンジ機と最小限の交換レンズを残し、他は全て処分(譲渡)
さらには、ライカや旧コンタックス等の、ある種の志向性は
全て封印(購入停止)する事とした。
![_c0032138_19523314.jpg]()
超レア品の為、いまさら中古市場に出てくるものでもないし
プレミアム価格で買うものでも無いし、さらにはっきり言えば
実用価値も全く無い。あくまでコレクション向けのレンズで
あると思う。
----
では、今回ラストのシステム
![_c0032138_19524125.jpg]()
(新品購入価格: 55,000円)(以下、SC21/4)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)
上記SC 35/2.5とまったく同じ出自の限定版超広角レンズ。
先に結論から言えば、本レンズも殆ど実用価値は無い。
![_c0032138_19524138.jpg]()
単なる「コレクション」になってしまう。
なんとか、このレンズの使い道が無いか?と、年に数回だが
持ち出して撮るようにもしている。
実は、こういう(レンジ機用レンズの)記事を書いている
のも、本レンズを使う意味を見出す為の理由もある。
さもなければ、本当に死蔵したままになってしまいそう
だからだ(汗)
まあ、撮影技法的には遠距離被写体を少し絞って撮る
だけなので、何ら面白味が無いのではあるが、それでも
本レンズの描写力が高い点は長所であろう。
周辺減光もフルサイズ機では良く現れるので、これを
作画上の特徴にしてしまうのも良いのではあるが、
この技法では、構図上の注目点を中央部に置かなければ
ならない。いわゆる「日の丸構図」であるから、その点でも
やはり普通すぎる撮り方にしかならない。
![_c0032138_19524177.jpg]()
高性能である事は確かだ。これは、一眼レフ用の広角レンズ
では、焦点距離の短いレンズでは、カメラのミラーボックス
の奥にあるフィルム面に焦点を結ばない為に、これを伸ばす
「レトロフォーカス型」設計を行わなければならない。
この為、どうしても余分なレンズ群が入ってしまい、その分
収差の補正等の性能面で不利な設計にならざるを得ない。
まあ、その事実から「レンジ機用の広角レンズは優れている」
と銀塩時代には、その事が「常識」ではあったのだが、
ただ、デジタル時代になっては、そうとも言い切れなくなって
いる。簡単な例を挙げれば、レンジ機よりもさらにフランジ
バックが短いミラーレス機用の広角レンズでは、レンジ機と
同様な設計メリットを得る事も出来るだろうからだ。
それに、そういう場合には、レンジ機の制限である距離計連動
上での最短撮影距離の長さ、という重欠点も回避可能である。
結局のところ現代において、レンジ機用レンズには、殆ど
実用的価値は無い訳だが、まあ、そういう「不便なレンズ」
を楽しむのも、一種のマニアックな使い方なのかも知れない。
でも、そういうマニア的な楽しみ方を語るならば、本SC21/4
のような近代的設計のレンズは、どうにも良く写りすぎる
ようにも感じてしまうのだ。
オールドやクラッシックなレンズであれば、それなりに
様々な弱点がある、それを許容して楽しむ事は、一般的には
「レンズの味を楽しむ」と言われるのだが、それだと曖昧
すぎるし、弱点がある事をはっきりといわず、オブラートで
包み込んで隠してしまっているような悪印象すらある。
だから、もっとはっきり言えば、「レンズの弱点は、それを
逆用して作画に生かす」と考えれば、よりポジティブだ。
それこそ、現代のレンズは、このSC21/4の時代よりも
20年近くを経過し、さらに描写力が高くなっている。
そんな中、オールドレンズの存在意義は高く、現代レンズ
では決して得られない描写が、たとえそれがレンズの欠点で
あっても得られる訳だ。
![_c0032138_19524115.jpg]()
写りは決してオールドでは無い、その点は、その時代に
おいては、クラッシックな機体の旧CONTAXや旧NIKON Sでも
現代的な写真が撮れるメリットではあったかも知れないが、
少し時代が経つと、また、そうとも言い切れなくなっている
という事だ。
本レンズは、使い方や、そこに何を求めるか?が、極めて
難しいレンズではあるが、まあ、歴史的価値は高く、
マニアック度も高いレンズだ。
決して今からの購入は推奨しないが、まあ、参考まで・・
----
さて、今回の記事「フォクトレンダー・レンジ機用レンズ」は、
このあたり迄で、次回記事に続く・・
紹介している。
今回の記事では、Voigtlander(フォクトレンダー)
(注:記事記載の便宜上で通常のASCIIコードで書きたい為、
aの変母音(ウムラウト)の記号記載は省略する)の、
レンジファインダー機(以下、適宜、「レンジ機」と略す)
用の交換レンズを4本紹介しよう。
なお、ここで言う「フォクトレンダー製」とは、1999年に
その商標を取得した、日本のコシナ社製のものである。
それから、現代のコシナ・フォクトレンダーは、むしろ
レンジファインダー用のレンズよりも、ミラーレス機用の
高級レンズ(マクロ・アポランター等)のブランドとして
著名であろう。本シリーズでは、第11回記事で、既に、
その手のレンズの特集も行っているが、今回の記事では
レンジ機用のものに限定して紹介する。
----
まず最初のシステム

(中古購入価格: 35,000円)(以下、SWH15/4.5)
カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)
1999年に発売された、高描写力単焦点超広角レンズ。
初期型であり、ライカLマウント(M39,L39と記載、現代の
ライカ製等のミラーレス機用Lマウントとは異なる)
対応品である。
その後、2005年頃にライカMマウント対応(VMマウント)
のⅡ型となり、距離計連動型となった。
2015年には、レンズ構成を改良した(注:やや大型化した)
Ⅲ型となり、VMマウント用の他、2016年には、SONY E(FE)
マウント版も追加された。

まず、「フォクトレンダー」という最古の光学機器メーカー
のブランドが突如国産品として蘇ったのが衝撃的だ。
その当時は「中古カメラブーム」である。銀塩からデジタル
まで、あらゆるタイプのカメラが新規に発売された混迷期だ。
銀塩レンジファインダー機も勿論人気で、M型ライカや
バルナックライカはもとより、ニコンSシリーズ、旧CONTAX
ミノルタやコニカのレンジ機など、マニアあるいは投機層は
ありとあらゆる新旧機種を買い漁っていた時代だ。
世間では、「ニコンから復刻版Sシリーズが発売される」
という噂(注:S3ミレニアム、2000年、発売時48万円)
も流れていたくらいなので、新製品の銀塩レンジ機が
今更ながら新発売されたとしても誰も驚かない。
旧「フォクトレンダー」については、上級マニア層が注目
するブランドであった。レンジ機では無いが、ヴィトーや
ヴィテッサ等の、美しく格好良いカメラが中古で流通して
いたので、それらを入手するマニアも居た。
(余談:熱心なファンも居る人気機種である。後年2010年代
には、TVアニメ「有頂天家族2」でも作品中にヴィテッサが
登場している。中古カメラブームの際は高額ゆえに、入手が
出来なかったが、20年が経過した現代では、老舗中古専門店
等で2万円前後で見かける場合もある。→しかし、未所有)
コシナは老舗OEMメーカーである。OEMとは他のカメラメーカー
から依頼されて、そのメーカーのブランドでカメラやレンズを
製造するという意味だ。場合により設計も担当する訳であり、
自社ブランドの名前が世の中に出ないだけで、とても技術力の
高いメーカーであった。
(余談:銀塩時代でも、こういった風に、製造等は、様々な
企業で分業されている為、「ブランド」という意味は希薄だ。
ビギナーが良く言う「どこのメーカーのカメラが良いのか?」
という質問は意味が無く、結局、どこの物を買っても同じだ。
この傾向はデジタル時代に入ってさらに顕著となり、それは
とても1社だけでは作れず、各社共通の部品などを使いまわし、
もはや、カメラについているロゴ名だけが異なるという状況だ。
あるいは「自社製センサーだから」とか「XXという新技術
を搭載しているから」とかの細かい事は言わないのが賢明だ。
もし他社製品に比べて、明らかな性能差がある場合、そこは
「追いつけ、追い越せ」で、少し時間がたてば、必ず各社の
機器の性能は同等レベルに落ち着く次第だ)
コシナは1990年代までは、ブランドの知名度が無く、よって
たまにコシナ自社名で発売するカメラやレンズは、新品でも
「定価の7割引き」とかの不自然な価格で販売されていた。
つまり、そこまで安価にしないと売れない訳だ。すなわち皆、
「コシナなんてメーカーは知らない、どうせ性能も悪かろう。
まあ、7割引きなら試しに買ってみようか」
という感じであった。
これはコシナの高い技術力からすれば、とてもアンバランス
な状態だ。
まあ、不勉強な消費者側(コシナを知らない、ブランドを
意味も無く信奉する)にも問題点があるのも確かではあるが、
一部の上級マニア層では、こうした不条理な安値で売られて
いるコシナ製品を入手し「意外に良く写ってびっくり、しかも
とても安い、これはなかなかコスパが良い」と、夢中になった
人も数多く居た。
で、こんな状態なので、コシナは「ブランド」を強く欲した。
しかし、1970年代にヤシカが「CONTAX」のブランドを買った
際には(それだけが理由とは言い切れないが)、資金繰りが
厳しくなって、経営破綻してしまい、京セラの資本投下で
なんとかCONTAXの販売を継続できた、という歴史がある。
(ここも、初級マニアが良く言う「CONTAXって凄い性能なの
でしょう?」という思い込みに関連して、良く理解する必要が
ある歴史だ)
で、コシナが、またあまりに強力なブランドを高値で買って
しまうと同様に資金的な負担が過剰になってヤバい事となる。
で、その当時、宙に浮いていた適正(適価)なブランドが
「フォクトレンダー」であった、という事なのだろう。
が、日本では、この老舗ブランドもあまり知られていない。
中古カメラブームとは言え、海外カメラ市場などにも詳しい
マニアは、かなりの上級層であり、一般的には、NIKON、
ライカ、CONTAX(カール・ツァイス)しか、知られておらず
そうしたカメラは投機的要素で高値で売れるのだ。
(つまり、何もわかっていないビギナー層が高値で買うから、
売る側も高値で売ろうとする。あるいは、さらなる値上げを
期待して購入する。そうやって、どんどんと際限なく相場が
吊り上り、結果「カメラバブル」となった訳だ。これは勿論、
買う側がしっかりと製品価値を判断すれば止まる話だ)
まあしかし、コシナが出した新製品においては、
「フォクトレンダーとは・・」等と、その歴史を紹介する
雑誌等のメディアも多く、好意的に受け入れられた。
そこから、畳み掛けるようにコシナ社はフォクトレンダー
ブランドのカメラやレンズを2000年代前半にかけて非常に
多数展開する、その数は多すぎて紹介できないくらいだ。
すなわち、もうとっくにそれらの設計は完了していたので
あろう、「後は名前をつけるだけ」という状態だったと思う。
それに、恐らくは非常に高いお金を出して購入したブランドだ、
早く、沢山の製品を出して、そこにブランド名の利益を乗せて
購入金額を回収しないとならない、さもないと他社の前例の
ように資金繰りが悪化して経営がヤバくなる。
で、「ブランド」なんて、結局、そんなものなのだ。
例えば、現代のスマホのカメラでも、ごく普通の設計のレンズ
に有名光学機器メーカーの名前をつけて、それを「付加価値」
としているケースも多々ある。
それにより、機器販売側は、ブランドの使用料で払った分を
定価に上乗せして、そこで釣り合いを取る訳だ。
面白味の乏しい事業構造であるが、そういうブランド名を
ありがたがる初級ユーザーが居る事で、世の中は上手く回る
仕組みなので、そういう人達にせっせと業界に貢いでもらおう。
私はカメラ業界とは何も関係が無いが、欲しい機材を適価で
購入したいので、市場は潤ってもらうことが望ましい。
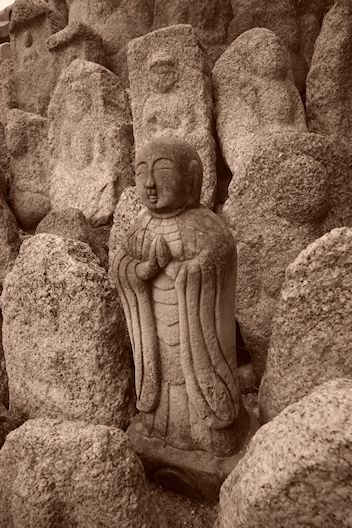
マニアックであった。
まず「マニアを落とす事」が、このブランドでの基本戦略だ。
どうせビギナー層では、「フォクトレンダーやらを買っても
廻りの人達は知らないから自慢できない、買うならばニコン
やライカを買うよ」という超下世話な論理になってしまう。
マニナ層に受けるために、国産フォクトレンダーは初期から
現代までを通じて、極めてマニアックな仕様を貫いている。
ここは企画側が、マニア心理を非常によく理解していると
思われる。というか、コシナの殆どのメンバーがマニアなの
だろう。そうでないと、そういう製品企画は出来ない。
他の大メーカーの製品は、「優等生的」等とよく称されるが、
それは褒め言葉でもあるが、マニア的な視点からは
「何も面白味が無い製品」という状態と等価である。
まあ、マニア受けを狙わず、一般に誰にでも広く受け入れ
られる製品企画なのだろうと思う。(そして下手をすれば
大メーカーの企画や開発の担当者とは言っても、殆ど
写真など撮っていないかも知れないのだ。そう思う根拠
としては、そのカメラやレンズを持って、ものの1時間も
撮影すれば、誰でも気づくだろう重欠点を持つ機材等が、
平気で販売されている状況だからだ)
コシナ・フォクトレンダー最初期の機種、BESSA-L(1999年)
は、変わった仕様のレンジファインダー機だ。
(注:Bessa L等と、小文字で書いたりハイフン無しは間違い)
ファインダーを持たず、今回紹介レンズのSWH15/4.5との
セットで発売された状態では、「目測式カメラ」となる。
付属15mm用ファインダーは外付けが出来るが、近接撮影では
パララックス(視差)が発生するし、勿論このファインダーは
ピント合わせもボケ確認も出来ない、構図確認用の素通しだ。
よって、ノーファインダーで撮るマニアも多かった。
(ただし、このファインダー像は、とても綺麗で好ましい)
ピント合わせは、目測またはパンフォーカス技法を用いる。
露出計は内蔵されているが、機械式カメラ故に電池が無くても
撮影可能だ。パンフォーカス方式で絞りをF8~F16に設定
するのであれば、「Sunny Sixteen」や「感度分の16」による
「勘露出決定技法」が使えるため、最悪電池切れになっても
問題なく撮影が継続でき、さらにマニアックに使うならば
電池をあえて抜いてしまう。
そうすると、初級中級者では「どうやって撮るのだ?」という
撮影不能のカメラとなり、マニア層または上級者のみが使える
カメラとなる事で、周囲に対して鼻が高い(自慢できる)訳だ。
さて、BESSA-Lの余談が長くなった。
同時に発売された、本レンズSWH15/4.5は、非常にインパクト
のあるレンズであった。
これまでのレンジ機用超広角レンズと言えば、ツァイスの
Hologon(ホロゴン)が著名で、オリジナルは「幻のレンズ」
であった事から、1990年代の京セラCONTAXのGシリーズの
AFレンジ機用に新発売された「ホロゴン」にマニアは夢中に
なっていた。しかし、リバイバル版も定価20万円台という
極めて高価なレンズなので、おいそれと購入できない。
そんな中、本SWH15/4.5は、発売時定価の詳細はもう記録
が残っておらず不明ではあるが、恐らくは5万円台くらいの
定価だったと思うので、やっと普通に買える価格帯の
レンジ機用の高性能な超広角レンズが出た訳だ。
マニア層は、これを入手し「ホロゴンと同等の写りだ」
(「プアマンズ・ホロゴン」という呼び名も多かった)
と賞賛した。(注:本当にホロゴンを知っているかは疑問)
ホロゴンでは強くあった、レンズ設計上の「周辺減光」は
賛否両論あったが、特徴ではあった。
本SWH15/4.5でも比較的強い周辺減光が出る。
ただ、これについては、後年のデジタル時代では、周辺減光
の効果は、レタッチ(画像編集)でも簡単に後付けできるので
最初から周辺減光がある事は、あまり望ましくない場合もある。
この為、本SWH15/4.5もⅢ型あたりからは周辺減光が減って
いると聞く。(注:未所有)
今回、私の使用法では、本レンズをAPS-C機のFUJI X-E1に
装着し、周辺減光をある程度カットして使っている。
画角は超広角らしくない約22mm相当にまで狭くなるが
まあそれは、撮りたい被写体用途次第とも言え、15mmを
フルサイズ機で使うと、あまりに広すぎ、パースペクティブ
が大きく、その歪みもあって、被写体の制限が厳しすぎる
ケースもあるからだ。

入手はまず不可能、欲しければ後年のレンジ機用のⅡ型か、
現行のミラーレス機用Ⅲ型を買うしか無い。
描写傾向はⅢ型では恐らく変わっているとは思うし、価格も
だいぶ高価にはなっているが、まあ、それもまたユーザーの
捉え方次第であろう。ともかくマニアックなレンズなのだ、
必須のレンズとは全く言い難いが、欲しければ買うしか無い。
----
では、次のシステム

(新品購入価格: 44,000円)(以下、CS50/2.5)
カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)
前記SWH15/4.5より後の2002年に発売された
レンジ機用Lマウント仕様の小口径高品質標準レンズ。
独フォクトレンダー時代の「スコパー」とは、テッサー型
の単純な3群4枚レンズ構成のものを示していたが、
本スコパーは6群7枚の変形ガウス型構成となっている。
小口径である事で、諸収差が良く補正されていると思われ、
きわめて良く写るレンズで、個人的にもお気に入りだ。

長さは、本レンズの場合では75cmと、これは依然、
一眼レフ用の標準レンズの最短(平均)45cmより、だいぶ
長いのではあるが・・
それでも、望遠になればなるほど、その不満は緩和される
(例:90mmレンズで最短90cmならば、一眼レフもレンジ機も
同じだ)
それに現代は「ヘリコイドアダプター」や「デジタルズーム」
で、物理的または仮想的に最短撮影距離を短縮可能だ。
本記事で使用するアダプターはヘリコイド型では無いが、
優秀なデジタルズーム機能を持つNEX-7を使用し、その機能も
必要に応じて使う事とする。最短撮影距離は縮まらないが
そもそもAPS-C機で75mm相当の画角で最短75cmは標準的であり
デジタルズームで撮影倍率は、いくらでも上げる事ができる。

レンズ自体の極めて高い質感や感触性能も、さらなる長所だ。
超小型でありながら真鍮製の鏡筒は、208gと
ずっしりとした重さがあり、ピントレバーがあって回転の
感触も極めて良い。
価格はそう高くない(発売時定価45,000円、銀色版)
のではあるが、開放F2.5と地味なスペックの標準レンズで
あるが故にか?あまり流通していないレンズであり、後年や
現代において中古で入手するのは結構困難であろうと思う。
あまり褒めてしまって、中古がプレミアム相場になって
しまったらかなわない。あまり褒めれらない要素もあげて
おくならば、本レンズそのものの欠点は殆ど無いものの、
この仕様であれば「世の中に代替できるレンズはいくらでも
存在する」という点だ。
たとえば、50mm/f1.8級の一眼レフ用小口径標準レンズで
本レンズに勝るとも劣らない描写力を持つものは、銀塩時代
1970年代以降のMFレンズにおいて、何本でも存在する。
そうした旧型のMF標準レンズは、現代ではジャンク価格で、
1000円から購入できるし、AB級のまともな個体でも5000円
も出せば十分だ。それらの小口径標準の方が、最短撮影距離
も開放F値も優れており、劣る部分はレンズの「質感」の
要素だけである。

デジタルのライカを使わない限りでは、一眼レフやミラーレス
機で本レンズを使うくらいならば、一般的な一眼レフ用レンズ
を使った方が、はるかに実用的な利便性は高い。
まあ結局、本CS50/2.5も、極めて趣味性の高いレンズで
あるという事であろう。
----
では、次のシステム

(新品購入価格: 30,000円)(以下、SC35/2.5)
カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)
またしても歴史を語るのが面倒な(汗)レンズの登場だ。
前述の中古カメラブームを受け、ニコンがS3ミレニアムと、
後に復刻SPを発売した。
それに便乗して、コシナ・フォクトレンダーでも、NIKON S
マウントおよび旧CONTAX Cマウントの極めてマニアックな
カメラを発売した。
それがBESSA-R2S/R2C (2002年)であり、それにともない、
ニコンS機、コシナ新型機、および旧製品のNIKON S,CONTAX
C機で使用可能なレンズ群を、8種類ほど限定発売した内の
1本が本SC35/2.5である。(注:正確に言えば、本レンズ
等はR2S/R2C発売以前の、S3ミレニアムの時代からの製品)
SCとは、NIKON SおよびCONTAX Cで使える、という意味だ。

だろう、とコシナは企画したのだろうが、蓋を開けてみると
SCシリーズは極めて不人気なレンズ群となってしまった。
その理由は、50万円以上と高価なNINKON Sシリーズを
購入するユーザー層は、ほとんどがコレクション(愛蔵品)
か、投機(転売による利益確保)を目的としたユーザー層で
「実際に写真を撮る」オーナー等は失礼ながら皆無であった
訳だ。事実、それらの機体で写真を撮っている人を、以降
発売後20余年、私は一度も見かけた事が無い。
コシナが「写真を撮る為の道具」としてカメラやレンズを
設計するのは、当然の論理だ。特に上級マニア層に向けての
製品戦略であれば、そこは必ず意識する必要がある。
しかし、市場のユーザーは、実際にはそうとも限らない、
特にこの手の機体では、誰も写真を撮らないし、愛蔵版
カメラ等では、使ったら価値が落ちるので、なおさらだ。
これはコシナ等のメーカー側からしてみれば「残念な事実」
だと思う(ただ、愛蔵版を作るニコンからは、それは想定内
の製品戦略だ。他に実用カメラを買って貰えれば、なお良い)
それにしても、せっかく買った機材を死蔵させてしまう事は、
マニア的視点からも残念な話だ。
で、「写真を撮らないのであれば、交換レンズも買わない」
この、ごくシンプルな理由で、これらのSCレンズ群は
各々数百本(800本位?)の少数限定販売でありながらも、
販売店側でも在庫を持て余すようになってくる。
発売から1~2年経った頃、在庫品を持て余した販売店から
「匠さん、SCレンズ買ってくれないかな? 安くしておくよ」
という申し出があった。
実は、その頃、前述の(超レア機)BESSA-R2Cも、その店で
新品購入していたので、店主は私が買う筈だと睨んだので
あろう。
でも私は、BESSA-R2Cには、旧ソ連KIEV(キエフ)用の
ジュピター・シリーズのレンズを装着して使うつもりで、
ボチボチとそれらを探し集めていたのだ。
ジュピター(ユピテル)は独ツァイス製品のデッドコピー
レンズであり、コスパが良くマニアックだ。
現代のコシナ・フォクトレンダー製品は、あまりに良く
写りすぎてしまうだろう事は明白で、私が想定している
機材利用コンセプトにそぐわないし、それにSCレンズは
そうした「富裕層」向けの「高付加価値型商品」であり
価格が高価すぎて、コスパが極めて悪い。
匠「う~ん、どうしようかなあ」と一旦は保留したが、
店主はさらに値引した価格を提示してきたので、
やむなく(笑)、本SC35/2.5と、後述のSC21/4を
合わせて購入する事にした。
さて、購入したSC35/2.5は、デザインが格好良く、
そこそこ作りは良い。しかし、既にライカL39マウント版で
発売されていたスコパー35/2.5と中身は同じレンズであり、
外観の変更だけで高価になっているのは、どうにも納得が
いかない。

最短撮影距離は90cmと極めて長く(注:レンジ機での
距離計連動での制限)、中遠距離のスナップや風景など
ありきたりの撮影技法での、ありきたりの被写体にしか
向かず、急速に興味を失っていった。
(注:今回の使用では、μ4/3機+デジタルテレコンで
撮影倍率の低さの弱点を緩和している)
その直後にデジタル時代になった為、SCレンズや他の
レンジ機用レンズは、デジタル一眼レフでは使いようもなく、
たまにマニアの集まりに「珍品」として持ち出す程度で、
長年、防湿庫に眠る羽目となったが・・
さらに後年、2010年前後からミラーレス時代となり、
L39マウントやNIKON Sマウントのアダプターが発売される
ようになって、やっと復活する運びになった次第だ。
だが、いくらアダプターがあるとは言え、これらのSCレンズ
が主力となる事は有り得ない。最短撮影距離も長すぎるし、
SCレンズは、ピントの繰り出し量が中途半端な設計の為
(すなわち、NIKON SとCONTAX Cのマウントは形状互換
だが、ピント繰り出し量が異なり、完全な互換性は無い。
そこで、広角レンズのみ、被写界深度の深さで、どちらの
マウントにも対応できるような中間的な構造となっている)
・・の為、アダプター使用時のピント合わせも不自然な
状態となって使い難い。
結局、アダプター使用時にも、少し絞り込んで、
被写界深度を稼いで、ミラーレス機のピーキング便りに
撮るしか無く、結局中遠距離の被写体を、銀塩時代と
同じ技法で撮る事になり、テクニカルな要素が何もなく
エンジョイ度の極めて低いレンズとなってしまう訳だ。
まあ、レンジ機全てで、同様な課題があった事実は
私も、いくつかのレンジ機を銀塩時代に購入した時点で
良くわかっていた。「これらは、真面目に写真を撮る為の
道具ではなく、コレクション向きだ!」という感覚が強く
出た為、私は、フォクトレンダー系での最小限(2台)の
レンジ機と最小限の交換レンズを残し、他は全て処分(譲渡)
さらには、ライカや旧コンタックス等の、ある種の志向性は
全て封印(購入停止)する事とした。

超レア品の為、いまさら中古市場に出てくるものでもないし
プレミアム価格で買うものでも無いし、さらにはっきり言えば
実用価値も全く無い。あくまでコレクション向けのレンズで
あると思う。
----
では、今回ラストのシステム

(新品購入価格: 55,000円)(以下、SC21/4)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)
上記SC 35/2.5とまったく同じ出自の限定版超広角レンズ。
先に結論から言えば、本レンズも殆ど実用価値は無い。

単なる「コレクション」になってしまう。
なんとか、このレンズの使い道が無いか?と、年に数回だが
持ち出して撮るようにもしている。
実は、こういう(レンジ機用レンズの)記事を書いている
のも、本レンズを使う意味を見出す為の理由もある。
さもなければ、本当に死蔵したままになってしまいそう
だからだ(汗)
まあ、撮影技法的には遠距離被写体を少し絞って撮る
だけなので、何ら面白味が無いのではあるが、それでも
本レンズの描写力が高い点は長所であろう。
周辺減光もフルサイズ機では良く現れるので、これを
作画上の特徴にしてしまうのも良いのではあるが、
この技法では、構図上の注目点を中央部に置かなければ
ならない。いわゆる「日の丸構図」であるから、その点でも
やはり普通すぎる撮り方にしかならない。

高性能である事は確かだ。これは、一眼レフ用の広角レンズ
では、焦点距離の短いレンズでは、カメラのミラーボックス
の奥にあるフィルム面に焦点を結ばない為に、これを伸ばす
「レトロフォーカス型」設計を行わなければならない。
この為、どうしても余分なレンズ群が入ってしまい、その分
収差の補正等の性能面で不利な設計にならざるを得ない。
まあ、その事実から「レンジ機用の広角レンズは優れている」
と銀塩時代には、その事が「常識」ではあったのだが、
ただ、デジタル時代になっては、そうとも言い切れなくなって
いる。簡単な例を挙げれば、レンジ機よりもさらにフランジ
バックが短いミラーレス機用の広角レンズでは、レンジ機と
同様な設計メリットを得る事も出来るだろうからだ。
それに、そういう場合には、レンジ機の制限である距離計連動
上での最短撮影距離の長さ、という重欠点も回避可能である。
結局のところ現代において、レンジ機用レンズには、殆ど
実用的価値は無い訳だが、まあ、そういう「不便なレンズ」
を楽しむのも、一種のマニアックな使い方なのかも知れない。
でも、そういうマニア的な楽しみ方を語るならば、本SC21/4
のような近代的設計のレンズは、どうにも良く写りすぎる
ようにも感じてしまうのだ。
オールドやクラッシックなレンズであれば、それなりに
様々な弱点がある、それを許容して楽しむ事は、一般的には
「レンズの味を楽しむ」と言われるのだが、それだと曖昧
すぎるし、弱点がある事をはっきりといわず、オブラートで
包み込んで隠してしまっているような悪印象すらある。
だから、もっとはっきり言えば、「レンズの弱点は、それを
逆用して作画に生かす」と考えれば、よりポジティブだ。
それこそ、現代のレンズは、このSC21/4の時代よりも
20年近くを経過し、さらに描写力が高くなっている。
そんな中、オールドレンズの存在意義は高く、現代レンズ
では決して得られない描写が、たとえそれがレンズの欠点で
あっても得られる訳だ。

写りは決してオールドでは無い、その点は、その時代に
おいては、クラッシックな機体の旧CONTAXや旧NIKON Sでも
現代的な写真が撮れるメリットではあったかも知れないが、
少し時代が経つと、また、そうとも言い切れなくなっている
という事だ。
本レンズは、使い方や、そこに何を求めるか?が、極めて
難しいレンズではあるが、まあ、歴史的価値は高く、
マニアック度も高いレンズだ。
決して今からの購入は推奨しないが、まあ、参考まで・・
----
さて、今回の記事「フォクトレンダー・レンジ機用レンズ」は、
このあたり迄で、次回記事に続く・・