本シリーズは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー
別に紹介している上級マニア層向けの記事である。
今回の記事では「変則的レンズ」を6本紹介しよう。
「変則(的)レンズとは何か?」と言うと、これを
ちゃんと定義する事は難しい。
まあ、あまり一般的では無い描写傾向を持っていたり、
あまり一般的では無いシステム構成のレンズである、
としておこう。
----
まず最初のシステム
![_c0032138_07044240.jpg]()
(新品購入価格 39,000円)(以下、TWIST)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)
2016年発売の「ぐるぐるボケ」特殊レンズ。
レンズマニアックス第2回記事、ハイコスパ名玉編
第3回記事等で紹介済みである為、本TWISTの仕様等に
ついては、ばっさりと割愛しよう。
最大の特徴は、その、なんとも言えない「ぐるぐるボケ」
の発生である。
これは「ぐるぐるボケ」の他「渦巻きボケ」と呼ばれる
事もあるが、言葉であれこれ説明するよりも、写真を
見てもらった方が一目瞭然であろう。
![_c0032138_07044206.jpg]()
μ4/3機よりも出易い。(像面湾曲と非点収差は、画角の
2乗に比例して増加するからだ)
本TWISTは各種一眼レフ/ミラーレス機用のマウントで
販売されているが、私の場合はNIKON (F)マウント版を
選択している。このマウントであれば、およそ他の
どのカメラにも(アダプターを介して)装着が可能だ。
(本レンズに限らず、特殊レンズ・変則レンズは
基本的に、NIKON F(/Ai)マウント品を購入するのが
他機種利用での汎用性を高める意味で効率的だ)
さて、本レンズの特徴は、その「ぐるぐるボケ」であるが、
この発生量は絞り値で制御できる。
「ぐるぐるボケ」の発生要因を説明や理解をする事は
高度で専門的な光学知識が必要となる為、割愛するが
まあ、簡単に言えば「収差」の類であり、基本的に収差は
絞りを絞り込む事で、それが低減するものも多い。
(絞ると、どの収差が、どれくらい低減するか?は、
近いうちに「匠の写真用語辞典」で解説する予定だ)
「ぐるぐるボケ」が発生する事で、TWISTは「トイレンズ」
の類だ、と勘違いされてしまう事も多いと思うが・・
本TWISTは、そんなに「Lo-Fi」な写りでは無い。
ピント面、あるいは画面中央部は極めてシャープであり、
他の一般レンズに勝るとも劣らない。
それもその筈、このレンズ構成の基礎となった設計は
1800年代(19世紀)に発明されて、20世紀半ば位
までは人物撮影用の写真レンズとして非常に長い期間
「定番」の構成であったのだ。(ペッツヴァール型構成)
ただし、それらの古い時代であっても、ここまでは
「ぐるぐるボケ」は酷くは無い、あくまで本レンズの
場合は、その特徴を誇張した設計になっている。
戦後(1950年頃)では、テッサー型やプラナー型と
いった、他のレンズ構成がポピュラーになってきた為、
ペッツヴァール型は減ってきたのだが、「画面中央部の
解像力が高い」という特徴から、望遠鏡(天体・地上)
や、写真用簡易望遠レンズの構成としては引き続き定番
として使用されている。
望遠鏡では、背景のボケ質を重視する必要がなく、多少
ぐるぐるボケが発生していても問題無いからだ。
なお、「(写真用)簡易望遠レンズ」とは何かと言うと、
天体望遠鏡のような2群4枚(ペッツヴァール型)等の
構成を正立像(注:天体望遠鏡は「倒立像」である)
となるようにした簡便で安価な構成の(超)望遠レンズ
である。(注:他のレンズ構成も勿論存在している)
1970年代~1980年代頃に、銀塩一眼レフが一般層にも
普及した際、ビギナー層には「望遠レンズが欲しい」
というニーズが大きかったが、メーカー純正のレンズは
「大きく重く高価」な三重苦なので、ビギナー層が買える
ものではなかった。そんな時、主に海外等の光学機器
(非カメラ)メーカー等から、安価に発売された事が
あった。(例:ミラーレス・マニアックス第63回記事で
紹介の「SP-500」(500mm/f8)、メーカー名等は不明)
同様な構造でカメラメーカー純正では「ニコンおもしろ
レンズ工房400mm/f8(どどっと400)」(ミラーレス・
マニアックス第38回記事、本シリーズ第11回記事)
もあった(下写真)
![_c0032138_07044226.jpg]()
長くなると、それに応じて鏡筒の全長も非常に長くなって
いく事であり、例えば「どどっと400」は、全長30cmも
ある為、そのままではハンドリング性能が悪く、分解し、
折りたたんで(入れ子にして)持ち運ぶのだ。
焦点距離に対して、レンズ全長が長いものは、すなわち
「望遠比(テレ比)が大きい」レンズとなる、
さらに言えば、焦点距離よりも短い全長となるような
設計を目指したものが「望遠レンズ」(まれに短焦点とも)
であり、これが「望遠」の本来の意味だ。
(注:「焦点距離とバックフォーカスの比である」という
解釈もあり、ちゃんと用語の定義が決まっていない)
つまり、「遠くの物を大きく写す」のが望遠レンズの
意味では無く、「焦点距離よりも全長が短いレンズ」
(又は、焦点距離よりもバックフォーカスが短いレンズ)
の事を、本来は「望遠レンズ」と言う訳だ。
だが、いつも記事で書くように「光学設計(専門)用語」
は、古くから発達してきた学術分野であるが故にか、用語の
統一が行われていない。光学用語は、研究者や実務者により、
さまざまな呼び方や意味があり、これが正解というものは
どうやら無い様子だ。ネット上の情報はもとより、専門書
毎でも、それぞれ用語の定義や呼び方が異なっているので、
この分野を勉強しようとすると、非常に困ってしまう他、
カメラマンのビギナー層等が様々な解釈で不正確な情報を
色々と流す為、ますます、光学分野に対する正確な知識が
世の中に定着していかない。これは残念な状況である。
![_c0032138_07044264.jpg]()
本TWISTの話に戻るが、この描写を言葉で色々と説明する
のは困難である、まあ、「こういう特殊な写りだ」
という事がわかれば、それで良いのではなかろうか?
私の場合、本レンズにおいて困っている事がある。
それは、購入以降、あまり「用途開発」が進んでいない事だ。
「用途開発」つまり、レンズをどんな用途(被写体の種類、
被写体の状況、撮り方、使用目的)に使うかを、考えたり
試したりしていく事なのだが・・
使用2~3年になるものの、これといった有益な使い方が
まだ見つかっていない(汗)
他記事でも書いたが、もし人物撮影に使った場合、
遊びやアート用途であれば良いが、依頼(業務)撮影では
この個性的な描写がクライアント等に受け入れて貰える
かは不明である(というか、まず無理だろう)
まあ、引き続き「用途開発」を進めていくしか無い、とも
思っている。
やや高価なレンズであり、中古はまず出ないと思う、
用途が難しいので、誰にでも推奨できるレンズでは無い。
----
さて、次のシステム
![_c0032138_07050298.jpg]()
(新品購入価格 5,000円 マウントアダプター付き価格)
カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)
2017年発売の、銀塩「レンズ付きフィルム・写ルンです」
(FUJIFILM製)の搭載レンズを再利用した単品トイレンズ。
この機種名の「Utulens」(うつれんず)は、その事を
由来としている。
銀塩「写ルンです」の写真の雰囲気そのままに撮れる、
というのが触れ込みではあるが・・
![_c0032138_07050239.jpg]()
を低減するために、フィルムを湾曲して装填する、という
トリッキーな特殊構造であったが、デジタルでは、それは
さすがに無理だ。(=現代の撮像センサーは湾曲しない。
ただ、近代では「曲がる太陽電池」も存在する模様なので、
将来、撮像センサーが曲がるようになっても驚かないが)
よって、そのまま「写ルンです」のレンズを使っても、
銀塩時代よりもデジタルの方が写りが悪くなってしまう。
この問題の対策の為、この「Utulens」では、簡易絞り
機構を設けて像面湾曲等の収差を低減している。
しかし、その分、銀塩「写ルンです」の口径比F10~F11
程度よりも若干暗くなって、本「Utulens」は、F16
相当の固定絞りである。
まあ、デジタル機で使う分には(開放)F値の暗さは、
ISO感度を上げる等で対応可能である。日中ではまず
手ブレ等は起きないし、カメラの機種によってはボデイ
内蔵手ブレ補正機能も利用できる。
ただ、ISO感度や手ブレ補正焦点距離等を正しく設定
しないと、日中晴天以外では、手ブレや被写体ブレの
リスクがある。
しかし、本レンズは基本的にはトイレンズである。
フィルム風の「Lo-Fi描写」を目的とするならば、
初級中級層であれば「偶然の手ブレ」等を作品の意図と
する事もできるであろうし、上級層であれば、意図的に
手ブレや被写体ブレを発生せる「Lo-Fi技法」すらも
使う事が出来るであろう。
本「Utulens」は、パンフォーカス設定であり、ピント
調整機構(ヘリコイド)は無い。
しかし、基本的にはLマウント(M39/L39)対応品なので、
Lマウントアダプター(付属または市販品)を使用すれば
アダプターへの装着時のねじ込みを緩める事で、ほんの
僅かだが近接撮影を行う事もできる。
ただし、この用法では最短数10cm程度と、思ったよりも
近接できていない事と、ねじ込みを緩める事で、レンズの
脱落(落下故障、紛失)のリスクが極めて高い。
まあ基本的には、そうした凝った使い方をせず、中遠距離
のパンフォーカス撮影に特化した方が賢明かつ安全である。
(または、Lマウント・ヘリコイドアダプターを使うかだ)
描写は結構「Lo-Fi」だ、確かにこれだと、銀塩の
「写ルンです」の方が良く写った印象もある。
まあ、「写ルンです」は、それなりに良く考えて設計
されていたという事であろう。
まあでも、「銀塩っぽい」描写表現力を得る事もできる。
ちなみに、2000年代後半~2010年代前半頃、主に
「女子カメラ層」「アート層」などで、フィルムカメラの
見直しのブームが起こりかけた事もあった。
まあ、銀塩カメラ自体は、とても安価になったから、
「機材にお金をかけたく無い層」(=アンチ「ブルジョア」、
これはいつの時代にも多い)にもウケるだろう、という
世情もあったし、世の中が皆デジタル写真で「Hi-Fi」化
したから、それに対抗する「Lo-Fi」の意味もあった。
しかし、私が気になったのは、それらの雑誌やWEB等で
「これがフィルム写真です」と紹介される写真の作品や
作例の画質が、「ウソだろう!」という位に、極めて
低画質であった事だ。
銀塩写真は、ちゃんとした機材(高性能レンズや高画質
フィルム)や現像環境を用いれば、現代のデジタル写真に
勝るとも劣らない位の高画質な写真を撮る事が出来る。
(参考:下写真は、ポジ(リバーサル)フィルムによる
撮影。フィルム撮影の証拠として、スキャン時にわざと
僅かにずらして、パーフォレーション(フィルム送り穴)
を画面内に入れている)
![_c0032138_07051715.jpg]()
そこまで低画質なのだろうか?
まあ考えられる原因は2つあり、1つは意図的にそうした
低画質(Lo-Fi)な写真を選んで掲載している状況だ。
それはまあ、「フィルムっぽい」という特徴や意図を
出す上では、デジタルのように綺麗に写っている写真を
載せたら区別ができないし、わざわざフィルムで撮る
意味も無いからだ。
もう1つは、そうした作品を提示して来るアマチュア層が、
必ずしも銀塩写真での、機材選択、撮影技法、DPEプロセス、
スキャン等でのデジタル化、画像編集等、の全ての工程に
精通している保証が無い、という事だ。
つまり、どこかで、いい加減な扱いをやっているから画質が
落ちてしまう。これは基本的にはスキル不足、あるいはミス
なのだが、まあでも、それはそれで上記1)の理由に合致し、
「フィルムっぽい」写真となる事から、それで何ら問題は
無い。あまり綺麗に写りすぎる(Hi-Fi)写真は、こうした
用途には適さないのだ。
![_c0032138_07051377.jpg]()
紹介済みなので、重複する説明は避けよう。
それに、トイレンズなので、あれこれと長所や短所を
語るべきものでもない。
ちなみに、今回の使用法は、FUJIFILM(ご存知、
「写ルンです」の製造元)のミラーレス機 X-E1との
組み合わせで、「デジタル写ルンです」の構成を意識して
使っている。
X-E1は、AF/MF性能に課題のある機種だが、こうした用法
では、それらの欠点が解消されて快適だ。
(注:勿論、システム構成上、それを意図している。
こうした措置を「弱点相殺型システム」と呼んでいる)
で、本来「Lo-Fi」撮影においては「エフェクト」の併用
が望ましいが、X-E1にはエフェクトは搭載されていない
ので、その優秀な「フィルムシミュレーション機能」を
代わりに使う事とした。
被写体条件などを上手く選んでカメラ設定にも留意すれば、
そこそこ、ちゃんと(Hi-Fiに)写す事も可能である。
![_c0032138_07051399.jpg]()
低いとは思うが、実際の用途があるかどうか?が
課題であろう、まあ、参考まで。
----
さて、3本目のシステム
![_c0032138_07052874.jpg]()
(中古購入価格 10,000円)(以下、LENSBABY 3G)
カメラは、SONY NEX-3 (APS-C機)
2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。
過去記事で何度も紹介している為、重複する説明は避けよう。
「逆アオリ」による、特殊な描写が得られるレンズである。
![_c0032138_07052823.jpg]()
相性が良く、私の手には良く馴染んでいる。
というのも本LENSBABY 3Gは、操作性および使いこなしが
極めて困難なレンズである為、どのカメラに装着するかに
よっても評価が変わってきてしまうのだ。
ただし、NEX-3はSONY最初期(2010年)のミラーレス機
である為、エフェクト等の付加機能が搭載されていない。
「トイレンズ母艦」として使っている上で、その点のみ
不満点であるのだが、代替できる適正な後継機が無い為、
ずっと、このクラッシックな機体を使い続けている。
(注:近年にα6000を購入していて、近い将来に、それを
トイレンズ母艦としてNEX-3と交替予定である)
本レンズは、発売時には4万円位と結構高価であった、
その後、KENKOが輸入代理店となった事等で、LENSBABY
シリーズの価格は少し下がったのだが、同時に、何度も
新製品にリニューアルした事で、都度、機能(仕様)の
改良とともに、価格も上昇してきている。
2010年代後半からは、交換レンズ市場の縮退を受けて、
LENSBABYも「高付加価値型商品」を主力とするようになった、
つまり、販売数の減少を利益でカバーしないと市場が維持
できない訳であり、この結果、新製品の価格帯は4万円~
8万円あたりまで高騰している。
反面、旧世代のLENSBABY製品、たとえば本3Gであるとか、
後で紹介の「MUSE」等は、1万円を切る安価な中古相場
となっている為、かなりお買い得感が強い。
(古い機種でも、ティルトとしての性能はほぼ同等だ)
まあでも、やはり本3Gも「特殊用途」のレンズである。
これを買ったとしても、よほどこの効果に入れ込んでいる
専門マニア(LENSBABYの言葉を借りれば「フリーク」と
言うべきか。まあ「マニア」の中でも、特定のジャンルに
非常に強く拘る人達を、世間一般的に「フリーク」と呼ぶ
場合もある。
なお、「フェチ」も似た意味の用語ではあるが、そちらは
身体の一部などを好む「嗜好」としての意味で使われる
事が多いから、レンズ等の用語としては、少々不適切だ)
・・・で、その「フリーク」では無い限り、ティルト系
レンズを常用する、という事は少ないであろう。
だから、本3Gや後継機種が必要かどうかは、個人の
嗜好次第である。
![_c0032138_07052854.jpg]()
LENSBABY製品となっている。私もちょっと「フリーク」が
入って来てしまっているかも知れない(汗)
近年、新型のLENSBABY製品が色々と出ているので、欲しい
という気持ちが強いのだが、前述のように高付加価値型
商品となって高価すぎる為、多数は所有できていない。
(2本程度は、後日、別記事で紹介予定だ)
まあでも、そうやって「フリーク」化したマニア達を
ターゲットに、高価なLENSBANBY製品を売るのだとすれば、
マーケティング戦略的には、とても正解なのだろう。
危ない危ない、新製品に目移りする事は、程ほどにして
おこう・・・
----
さて、次のシステム
![_c0032138_07054688.jpg]()
(中古購入価格 9,000円)(以下、AR105/4)
カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)
レンズそのものは、1970年台後半の発売と思われる
MF小口径中望遠マクロだが、レンズ単体では使用できず、
ベローズ(蛇腹状の延長鏡筒)または専用ヘリコイドを
必ず使用する必要がある。
本システムは、ベローズ付きで9,000円という安価な
中古価格であった、まあ現代において、これを利用する
適正な環境が無いので、一種の「ジャンク扱い」である。
ベローズをフルに使用すると、かなり大掛かりな構成と
なって、室内等の固定環境でしか使えない。
そこで、ベローズから不要な部品を全て取り外し、
(=ダイエット、と呼んでいる)屋外での手持ち利用を
可能とした状態が、上写真のシステム構成である。
![_c0032138_07055796.jpg]()
一応手持ち撮影は可能であるが、カメラバッグには、
これは入らず、ハンドリングが悪い。
さらに言えば、操作性的に撮影の難易度がかなり高く、
加えて、縦位置での手持ち撮影が相当に困難である事、
おまけに、システム全体の重心をホールドする場所が
無く、下手をすると、蛇腹を無意識に手で掴んでしまい
「ぐにゃり」とした感触で、慌てて、故障(破損)して
いないか?を疑う事の繰り返しだ。
描写力自体は悪く無い、しかし、レンズ構成やスペックが
NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4
(レンズマニアックス第16回記事)と、全く同じであり、
描写傾向も極めて酷似している。
なので、一般的なフィールド(屋外)撮影では、
Ai105/4の方が遥かに使い易い為に、本AR105/4を
わざわざベローズ付きで持ち出す理由が殆ど無い。
まあ、本AR105/4の方がAi105/4よりも最大撮影倍率は
高いし、おまけにWD(ワーキング・ディスタンス)を
長く取れる、という僅かな利点は存在する。
しかし、現代のミラーレス時代においては、デジタル
拡大機能の利用も容易である為、(マクロ)レンズ自体
の最大撮影倍率スペックは、あまり重要では無い。
それに、あまりに撮影倍率を上げて撮ろうとすると、
今度は、撮影技法そのものの超高難易度が襲いかかる。
(匠の写真用語辞典第3回「超マクロレンズ」参照)
![_c0032138_07055782.jpg]()
上級マニア、あるいは「好事家」向けであろう。
入手性も困難であるし、「指名買い」の必要性も無い。
別に「ヘキサノン」というブランドがあるから銘玉という
訳でも無いし・・ これであったら、全ての点でNIKONの
Ai105/4を購入した方がベターであろう。
ちなみに、Ai105/4は本ベローズシステムよりも安価な
8,000円(税込)で中古購入している。
----
さて、5本目のシステム
![_c0032138_07060879.jpg]()
(中古購入価格 4,000円)(以下、MUSE ZP)
カメラは、OLYMPUS E-410 (4/3機)
さて、また説明が非常にややこしいシステムだ(汗)
今回は「本MUSE オプテイックのゾーンプレートモードを
使用して撮影する」が、この時点で言葉の意味が何の事
やら、さっぱりわからないかも知れない(汗)
幸い「レンズ・マニアックス第4回記事」で、本システム
についての詳細を説明しているので、そちらを参考に
してもらえば良いと思う。
![_c0032138_07060876.jpg]()
これはこれで面白いのではあるが、やはり「有効な用途」が
見つけ難いレンズでもある。
それと、今回は、このMUSEのユニットが4/3機用の為
(注:終焉した4/3システム用であったため、在庫処分で
安価に新品購入する事ができた)OLYMPUS E-410の
4/3機を使用しているが、この機体は低感度である為、
少々使い勝手が悪い。
以降、レンズはそのままMUSE ZPを使用するが、
簡易4/3→Eマウントアダプター(電子接点なし)を
介して、カメラをSONY NEX-7 (APS-C機)に交換しよう。
![_c0032138_07063002.jpg]()
しないのだが、本MUSEの場合、そうした電気的なやり取り
が不要なトイレンズの為に、アダプターは単にマウント形状を
変換するだけの簡単な構造の物で良い。
NEX-7を母艦とするならば、優秀なエフェクト機能を
併用するのも面白いであろう。なお、さらにエフェクトが
優秀なオリンパスのミラーレス機(OM-D E-M1等)で使った
方が良かったかも知れないが、勿論搭載エフェクトの仕様は
機種毎に異なるので、まあ、使っているカメラの搭載範囲内
で選べば良いだけの話だ。エフェクトの件に限らないが、
カメラの機能や性能が高いからと言って、それを根拠に
良い写真が撮れる訳でも無い。あくまで、どの機能を、
どのように使うかが肝心である。
これは、ごく当たり前の話ではあるが、残念ながら多くの
初級者は、この事が理解できず、機能や性能仕様の高い
(しかし高額な)カメラばかりを欲しがってしまうのだ。
でも、10年前であれば、それは「腕に見合わず、格好悪い」
と、切り捨ててしまえたのだが、現代においては、カメラ
市場が極端に縮退してしまっている為、初級中級層に
高価な最新高性能カメラを買ってもらって市場を潤さないと
本当にカメラ市場が崩壊してしまう。そうなると、勿論
皆が困るので、せっせとビギナー層に高価な最新機材を
買ってもらって、私は、古くなってコスパがとても良く
なった旧世代の機材を、中古で買う事にしようか。
![_c0032138_07063018.jpg]()
特別な用途は考えにくいかも知れない。
だがまあ、今回の記事の「変則レンズ」は、全てが同様だ、
いずれの機材(レンズ)も、あまり特別な用途を持たない
ものばかりである。勿論、初級中級層に推奨できるような
ものは少なく、買ったとしても用途が無くて、持て余して
しまう事であろう。
まあ、あくまで「参考まで」というスタンスである。
----
では、今回ラストのシステム
![_c0032138_07064093.jpg]()
(中古購入価格 10,000円)(以下、DT30/2.8)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
ハイコスパ第14回記事等で紹介の、2009年発売のAPS-C機
専用AF単焦点準広角(標準画角)マクロレンズ。
エントリー・マクロレンズとしては優秀な類である。
一応等倍撮影が出来るし、有限回転式ピントリングの為に、
近接MF技法が使え、αフタケタ機に備わるピーキング機能
を併用する事で、快適なマクロ撮影を可能とする。
描写力は「感動的」という要素は無いが、悪いという話
でも無い。
![_c0032138_07064071.jpg]()
いるため、通常レンズに比較して近距離の撮影においては
「非常に描写力が優れる」という印象を持つ事が多い。
(注:「設計基準が最短側、無限遠側」と、ざっくりと区別
される事が多いが、「設計基準」では、あまりに広範囲で
曖昧な言葉なので、設計開発の実務を全く理解していない
門外漢の用語と判断し、本ブログでは滅多にそうは呼ばない)
まあ、その手の「本格的なマクロレンズ」に比べると、
本レンズの描写力は、やや物足りない印象もあるだろう。
しかし、1万円の中古価格(注:現代ではさらに相場が
安価になっている)で買えるレンズとして考えると、
極めてコスパが良い。
最大の特徴として、WD(ワーキング・ディスタンス)が
極めて短い(数cm)事がある。
まあ、準広角(標準画角)マクロで等倍仕様であれば、
だいたいWDは短くはなるが、それにしても、この短さは
トップクラスである(他にもミラーレス機用の、30mm級
等倍マクロ等も、同様にWDが非常に短いものがある)
WDが短い事は長所であるとは言い切れず、被写体に非常に
近接して撮影する場合、屋外撮影ではカメラやレンズの
影が被写体にかかってしまうとか、昆虫等は逃げてしまう
とか、誤って被写体に接触してしまう(例:花粉やら
料理の脂分等がレンズにつく、模型を壊してしまう等)
そもそも、どうしても被写体に接近できない環境もある
(例:花壇とか、頭上の木々の花等)だろう。
まあ、被写体に近接出来ないケースでは、中望遠マクロや
望遠マクロ等のWDが長い機材を使う必要があると言う事だ。
だが、WDが短い事を意外な長所にする事もできる。
それは、「ZENJIX soratama 72(宙玉)」の利用だ。
以降、SONY DT30/2.8を、マスター(主)レンズとして、、
そのアタッチメントをつけてみよう。
![_c0032138_07064050.jpg]()
第61回、第69回記事等の多数で紹介済みの、2010年代
発売の特殊アタッチメント型レンズである。
(新品購入価格 6,000円)
このアタッチメント(注:「付属品」という意味。勿論
アタッチメントには「フィルター径」という意味は無いが
WEB上で誤用が目立つ)は、ガラス玉(宙玉)に映る映像を
撮影するものだが、レンズ前部に非常に近接して「宙玉」を
配置しなければならない。たいていのレンズではWDが長い
為にピントが合わず、「宙玉」を、かなり遠い位置に置く
必要があり、その構造を工作する等が面倒であったり、
構造が脆くなったり、加えて「宙玉」が小さく写りすぎて
しまう。
![_c0032138_07064087.jpg]()
逆転して掲載している)
本DT30/2.8であれば、WDが数cmであるから、「宙玉」を
ある程度大きく写す事が可能であるし、装着する為の
構造もシンプルかつ小型化できるので、ハンドリングが楽だ。
それから「もっとWDが短いレンズは無いのか?」というと、
実は、そういったレンズも存在している。
具体的には、本シリーズ第17回記事等で紹介した、
LAOWA 15mm/f4 であり、その「等倍広角マクロ」では、
WDは数mm程度しかない。その場合「宙玉」を、ほとんど
ダイレクトにレンズ前に装着出来る為、さらにコンパクトに
なるのだが、「宙玉」自体の構造上、レンズ前数mmまで
近接しての配置ができず、むしろ「宙玉」が小さく写って
しまうという課題があった(当該記事参照)
まあ、やはり、本DT30/2.8が、「宙玉」のマスターレンズ
としては適正なのではなかろうか・・?
----
さて、今回の記事「変則レンズ特集」は、このあたり迄で、
次回記事に続く・・
別に紹介している上級マニア層向けの記事である。
今回の記事では「変則的レンズ」を6本紹介しよう。
「変則(的)レンズとは何か?」と言うと、これを
ちゃんと定義する事は難しい。
まあ、あまり一般的では無い描写傾向を持っていたり、
あまり一般的では無いシステム構成のレンズである、
としておこう。
----
まず最初のシステム

(新品購入価格 39,000円)(以下、TWIST)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)
2016年発売の「ぐるぐるボケ」特殊レンズ。
レンズマニアックス第2回記事、ハイコスパ名玉編
第3回記事等で紹介済みである為、本TWISTの仕様等に
ついては、ばっさりと割愛しよう。
最大の特徴は、その、なんとも言えない「ぐるぐるボケ」
の発生である。
これは「ぐるぐるボケ」の他「渦巻きボケ」と呼ばれる
事もあるが、言葉であれこれ説明するよりも、写真を
見てもらった方が一目瞭然であろう。

μ4/3機よりも出易い。(像面湾曲と非点収差は、画角の
2乗に比例して増加するからだ)
本TWISTは各種一眼レフ/ミラーレス機用のマウントで
販売されているが、私の場合はNIKON (F)マウント版を
選択している。このマウントであれば、およそ他の
どのカメラにも(アダプターを介して)装着が可能だ。
(本レンズに限らず、特殊レンズ・変則レンズは
基本的に、NIKON F(/Ai)マウント品を購入するのが
他機種利用での汎用性を高める意味で効率的だ)
さて、本レンズの特徴は、その「ぐるぐるボケ」であるが、
この発生量は絞り値で制御できる。
「ぐるぐるボケ」の発生要因を説明や理解をする事は
高度で専門的な光学知識が必要となる為、割愛するが
まあ、簡単に言えば「収差」の類であり、基本的に収差は
絞りを絞り込む事で、それが低減するものも多い。
(絞ると、どの収差が、どれくらい低減するか?は、
近いうちに「匠の写真用語辞典」で解説する予定だ)
「ぐるぐるボケ」が発生する事で、TWISTは「トイレンズ」
の類だ、と勘違いされてしまう事も多いと思うが・・
本TWISTは、そんなに「Lo-Fi」な写りでは無い。
ピント面、あるいは画面中央部は極めてシャープであり、
他の一般レンズに勝るとも劣らない。
それもその筈、このレンズ構成の基礎となった設計は
1800年代(19世紀)に発明されて、20世紀半ば位
までは人物撮影用の写真レンズとして非常に長い期間
「定番」の構成であったのだ。(ペッツヴァール型構成)
ただし、それらの古い時代であっても、ここまでは
「ぐるぐるボケ」は酷くは無い、あくまで本レンズの
場合は、その特徴を誇張した設計になっている。
戦後(1950年頃)では、テッサー型やプラナー型と
いった、他のレンズ構成がポピュラーになってきた為、
ペッツヴァール型は減ってきたのだが、「画面中央部の
解像力が高い」という特徴から、望遠鏡(天体・地上)
や、写真用簡易望遠レンズの構成としては引き続き定番
として使用されている。
望遠鏡では、背景のボケ質を重視する必要がなく、多少
ぐるぐるボケが発生していても問題無いからだ。
なお、「(写真用)簡易望遠レンズ」とは何かと言うと、
天体望遠鏡のような2群4枚(ペッツヴァール型)等の
構成を正立像(注:天体望遠鏡は「倒立像」である)
となるようにした簡便で安価な構成の(超)望遠レンズ
である。(注:他のレンズ構成も勿論存在している)
1970年代~1980年代頃に、銀塩一眼レフが一般層にも
普及した際、ビギナー層には「望遠レンズが欲しい」
というニーズが大きかったが、メーカー純正のレンズは
「大きく重く高価」な三重苦なので、ビギナー層が買える
ものではなかった。そんな時、主に海外等の光学機器
(非カメラ)メーカー等から、安価に発売された事が
あった。(例:ミラーレス・マニアックス第63回記事で
紹介の「SP-500」(500mm/f8)、メーカー名等は不明)
同様な構造でカメラメーカー純正では「ニコンおもしろ
レンズ工房400mm/f8(どどっと400)」(ミラーレス・
マニアックス第38回記事、本シリーズ第11回記事)
もあった(下写真)

長くなると、それに応じて鏡筒の全長も非常に長くなって
いく事であり、例えば「どどっと400」は、全長30cmも
ある為、そのままではハンドリング性能が悪く、分解し、
折りたたんで(入れ子にして)持ち運ぶのだ。
焦点距離に対して、レンズ全長が長いものは、すなわち
「望遠比(テレ比)が大きい」レンズとなる、
さらに言えば、焦点距離よりも短い全長となるような
設計を目指したものが「望遠レンズ」(まれに短焦点とも)
であり、これが「望遠」の本来の意味だ。
(注:「焦点距離とバックフォーカスの比である」という
解釈もあり、ちゃんと用語の定義が決まっていない)
つまり、「遠くの物を大きく写す」のが望遠レンズの
意味では無く、「焦点距離よりも全長が短いレンズ」
(又は、焦点距離よりもバックフォーカスが短いレンズ)
の事を、本来は「望遠レンズ」と言う訳だ。
だが、いつも記事で書くように「光学設計(専門)用語」
は、古くから発達してきた学術分野であるが故にか、用語の
統一が行われていない。光学用語は、研究者や実務者により、
さまざまな呼び方や意味があり、これが正解というものは
どうやら無い様子だ。ネット上の情報はもとより、専門書
毎でも、それぞれ用語の定義や呼び方が異なっているので、
この分野を勉強しようとすると、非常に困ってしまう他、
カメラマンのビギナー層等が様々な解釈で不正確な情報を
色々と流す為、ますます、光学分野に対する正確な知識が
世の中に定着していかない。これは残念な状況である。

本TWISTの話に戻るが、この描写を言葉で色々と説明する
のは困難である、まあ、「こういう特殊な写りだ」
という事がわかれば、それで良いのではなかろうか?
私の場合、本レンズにおいて困っている事がある。
それは、購入以降、あまり「用途開発」が進んでいない事だ。
「用途開発」つまり、レンズをどんな用途(被写体の種類、
被写体の状況、撮り方、使用目的)に使うかを、考えたり
試したりしていく事なのだが・・
使用2~3年になるものの、これといった有益な使い方が
まだ見つかっていない(汗)
他記事でも書いたが、もし人物撮影に使った場合、
遊びやアート用途であれば良いが、依頼(業務)撮影では
この個性的な描写がクライアント等に受け入れて貰える
かは不明である(というか、まず無理だろう)
まあ、引き続き「用途開発」を進めていくしか無い、とも
思っている。
やや高価なレンズであり、中古はまず出ないと思う、
用途が難しいので、誰にでも推奨できるレンズでは無い。
----
さて、次のシステム

(新品購入価格 5,000円 マウントアダプター付き価格)
カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機)
2017年発売の、銀塩「レンズ付きフィルム・写ルンです」
(FUJIFILM製)の搭載レンズを再利用した単品トイレンズ。
この機種名の「Utulens」(うつれんず)は、その事を
由来としている。
銀塩「写ルンです」の写真の雰囲気そのままに撮れる、
というのが触れ込みではあるが・・

を低減するために、フィルムを湾曲して装填する、という
トリッキーな特殊構造であったが、デジタルでは、それは
さすがに無理だ。(=現代の撮像センサーは湾曲しない。
ただ、近代では「曲がる太陽電池」も存在する模様なので、
将来、撮像センサーが曲がるようになっても驚かないが)
よって、そのまま「写ルンです」のレンズを使っても、
銀塩時代よりもデジタルの方が写りが悪くなってしまう。
この問題の対策の為、この「Utulens」では、簡易絞り
機構を設けて像面湾曲等の収差を低減している。
しかし、その分、銀塩「写ルンです」の口径比F10~F11
程度よりも若干暗くなって、本「Utulens」は、F16
相当の固定絞りである。
まあ、デジタル機で使う分には(開放)F値の暗さは、
ISO感度を上げる等で対応可能である。日中ではまず
手ブレ等は起きないし、カメラの機種によってはボデイ
内蔵手ブレ補正機能も利用できる。
ただ、ISO感度や手ブレ補正焦点距離等を正しく設定
しないと、日中晴天以外では、手ブレや被写体ブレの
リスクがある。
しかし、本レンズは基本的にはトイレンズである。
フィルム風の「Lo-Fi描写」を目的とするならば、
初級中級層であれば「偶然の手ブレ」等を作品の意図と
する事もできるであろうし、上級層であれば、意図的に
手ブレや被写体ブレを発生せる「Lo-Fi技法」すらも
使う事が出来るであろう。
本「Utulens」は、パンフォーカス設定であり、ピント
調整機構(ヘリコイド)は無い。
しかし、基本的にはLマウント(M39/L39)対応品なので、
Lマウントアダプター(付属または市販品)を使用すれば
アダプターへの装着時のねじ込みを緩める事で、ほんの
僅かだが近接撮影を行う事もできる。
ただし、この用法では最短数10cm程度と、思ったよりも
近接できていない事と、ねじ込みを緩める事で、レンズの
脱落(落下故障、紛失)のリスクが極めて高い。
まあ基本的には、そうした凝った使い方をせず、中遠距離
のパンフォーカス撮影に特化した方が賢明かつ安全である。
(または、Lマウント・ヘリコイドアダプターを使うかだ)
描写は結構「Lo-Fi」だ、確かにこれだと、銀塩の
「写ルンです」の方が良く写った印象もある。
まあ、「写ルンです」は、それなりに良く考えて設計
されていたという事であろう。
まあでも、「銀塩っぽい」描写表現力を得る事もできる。
ちなみに、2000年代後半~2010年代前半頃、主に
「女子カメラ層」「アート層」などで、フィルムカメラの
見直しのブームが起こりかけた事もあった。
まあ、銀塩カメラ自体は、とても安価になったから、
「機材にお金をかけたく無い層」(=アンチ「ブルジョア」、
これはいつの時代にも多い)にもウケるだろう、という
世情もあったし、世の中が皆デジタル写真で「Hi-Fi」化
したから、それに対抗する「Lo-Fi」の意味もあった。
しかし、私が気になったのは、それらの雑誌やWEB等で
「これがフィルム写真です」と紹介される写真の作品や
作例の画質が、「ウソだろう!」という位に、極めて
低画質であった事だ。
銀塩写真は、ちゃんとした機材(高性能レンズや高画質
フィルム)や現像環境を用いれば、現代のデジタル写真に
勝るとも劣らない位の高画質な写真を撮る事が出来る。
(参考:下写真は、ポジ(リバーサル)フィルムによる
撮影。フィルム撮影の証拠として、スキャン時にわざと
僅かにずらして、パーフォレーション(フィルム送り穴)
を画面内に入れている)
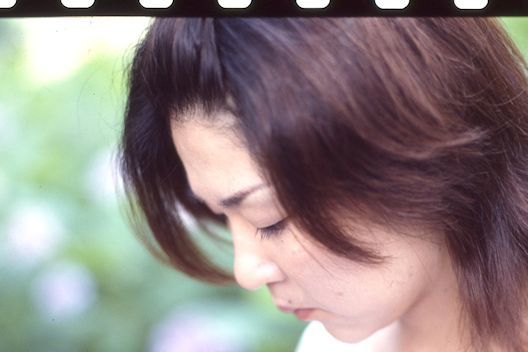
そこまで低画質なのだろうか?
まあ考えられる原因は2つあり、1つは意図的にそうした
低画質(Lo-Fi)な写真を選んで掲載している状況だ。
それはまあ、「フィルムっぽい」という特徴や意図を
出す上では、デジタルのように綺麗に写っている写真を
載せたら区別ができないし、わざわざフィルムで撮る
意味も無いからだ。
もう1つは、そうした作品を提示して来るアマチュア層が、
必ずしも銀塩写真での、機材選択、撮影技法、DPEプロセス、
スキャン等でのデジタル化、画像編集等、の全ての工程に
精通している保証が無い、という事だ。
つまり、どこかで、いい加減な扱いをやっているから画質が
落ちてしまう。これは基本的にはスキル不足、あるいはミス
なのだが、まあでも、それはそれで上記1)の理由に合致し、
「フィルムっぽい」写真となる事から、それで何ら問題は
無い。あまり綺麗に写りすぎる(Hi-Fi)写真は、こうした
用途には適さないのだ。

紹介済みなので、重複する説明は避けよう。
それに、トイレンズなので、あれこれと長所や短所を
語るべきものでもない。
ちなみに、今回の使用法は、FUJIFILM(ご存知、
「写ルンです」の製造元)のミラーレス機 X-E1との
組み合わせで、「デジタル写ルンです」の構成を意識して
使っている。
X-E1は、AF/MF性能に課題のある機種だが、こうした用法
では、それらの欠点が解消されて快適だ。
(注:勿論、システム構成上、それを意図している。
こうした措置を「弱点相殺型システム」と呼んでいる)
で、本来「Lo-Fi」撮影においては「エフェクト」の併用
が望ましいが、X-E1にはエフェクトは搭載されていない
ので、その優秀な「フィルムシミュレーション機能」を
代わりに使う事とした。
被写体条件などを上手く選んでカメラ設定にも留意すれば、
そこそこ、ちゃんと(Hi-Fiに)写す事も可能である。

低いとは思うが、実際の用途があるかどうか?が
課題であろう、まあ、参考まで。
----
さて、3本目のシステム

(中古購入価格 10,000円)(以下、LENSBABY 3G)
カメラは、SONY NEX-3 (APS-C機)
2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。
過去記事で何度も紹介している為、重複する説明は避けよう。
「逆アオリ」による、特殊な描写が得られるレンズである。

相性が良く、私の手には良く馴染んでいる。
というのも本LENSBABY 3Gは、操作性および使いこなしが
極めて困難なレンズである為、どのカメラに装着するかに
よっても評価が変わってきてしまうのだ。
ただし、NEX-3はSONY最初期(2010年)のミラーレス機
である為、エフェクト等の付加機能が搭載されていない。
「トイレンズ母艦」として使っている上で、その点のみ
不満点であるのだが、代替できる適正な後継機が無い為、
ずっと、このクラッシックな機体を使い続けている。
(注:近年にα6000を購入していて、近い将来に、それを
トイレンズ母艦としてNEX-3と交替予定である)
本レンズは、発売時には4万円位と結構高価であった、
その後、KENKOが輸入代理店となった事等で、LENSBABY
シリーズの価格は少し下がったのだが、同時に、何度も
新製品にリニューアルした事で、都度、機能(仕様)の
改良とともに、価格も上昇してきている。
2010年代後半からは、交換レンズ市場の縮退を受けて、
LENSBABYも「高付加価値型商品」を主力とするようになった、
つまり、販売数の減少を利益でカバーしないと市場が維持
できない訳であり、この結果、新製品の価格帯は4万円~
8万円あたりまで高騰している。
反面、旧世代のLENSBABY製品、たとえば本3Gであるとか、
後で紹介の「MUSE」等は、1万円を切る安価な中古相場
となっている為、かなりお買い得感が強い。
(古い機種でも、ティルトとしての性能はほぼ同等だ)
まあでも、やはり本3Gも「特殊用途」のレンズである。
これを買ったとしても、よほどこの効果に入れ込んでいる
専門マニア(LENSBABYの言葉を借りれば「フリーク」と
言うべきか。まあ「マニア」の中でも、特定のジャンルに
非常に強く拘る人達を、世間一般的に「フリーク」と呼ぶ
場合もある。
なお、「フェチ」も似た意味の用語ではあるが、そちらは
身体の一部などを好む「嗜好」としての意味で使われる
事が多いから、レンズ等の用語としては、少々不適切だ)
・・・で、その「フリーク」では無い限り、ティルト系
レンズを常用する、という事は少ないであろう。
だから、本3Gや後継機種が必要かどうかは、個人の
嗜好次第である。

LENSBABY製品となっている。私もちょっと「フリーク」が
入って来てしまっているかも知れない(汗)
近年、新型のLENSBABY製品が色々と出ているので、欲しい
という気持ちが強いのだが、前述のように高付加価値型
商品となって高価すぎる為、多数は所有できていない。
(2本程度は、後日、別記事で紹介予定だ)
まあでも、そうやって「フリーク」化したマニア達を
ターゲットに、高価なLENSBANBY製品を売るのだとすれば、
マーケティング戦略的には、とても正解なのだろう。
危ない危ない、新製品に目移りする事は、程ほどにして
おこう・・・
----
さて、次のシステム

(中古購入価格 9,000円)(以下、AR105/4)
カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)
レンズそのものは、1970年台後半の発売と思われる
MF小口径中望遠マクロだが、レンズ単体では使用できず、
ベローズ(蛇腹状の延長鏡筒)または専用ヘリコイドを
必ず使用する必要がある。
本システムは、ベローズ付きで9,000円という安価な
中古価格であった、まあ現代において、これを利用する
適正な環境が無いので、一種の「ジャンク扱い」である。
ベローズをフルに使用すると、かなり大掛かりな構成と
なって、室内等の固定環境でしか使えない。
そこで、ベローズから不要な部品を全て取り外し、
(=ダイエット、と呼んでいる)屋外での手持ち利用を
可能とした状態が、上写真のシステム構成である。

一応手持ち撮影は可能であるが、カメラバッグには、
これは入らず、ハンドリングが悪い。
さらに言えば、操作性的に撮影の難易度がかなり高く、
加えて、縦位置での手持ち撮影が相当に困難である事、
おまけに、システム全体の重心をホールドする場所が
無く、下手をすると、蛇腹を無意識に手で掴んでしまい
「ぐにゃり」とした感触で、慌てて、故障(破損)して
いないか?を疑う事の繰り返しだ。
描写力自体は悪く無い、しかし、レンズ構成やスペックが
NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4
(レンズマニアックス第16回記事)と、全く同じであり、
描写傾向も極めて酷似している。
なので、一般的なフィールド(屋外)撮影では、
Ai105/4の方が遥かに使い易い為に、本AR105/4を
わざわざベローズ付きで持ち出す理由が殆ど無い。
まあ、本AR105/4の方がAi105/4よりも最大撮影倍率は
高いし、おまけにWD(ワーキング・ディスタンス)を
長く取れる、という僅かな利点は存在する。
しかし、現代のミラーレス時代においては、デジタル
拡大機能の利用も容易である為、(マクロ)レンズ自体
の最大撮影倍率スペックは、あまり重要では無い。
それに、あまりに撮影倍率を上げて撮ろうとすると、
今度は、撮影技法そのものの超高難易度が襲いかかる。
(匠の写真用語辞典第3回「超マクロレンズ」参照)

上級マニア、あるいは「好事家」向けであろう。
入手性も困難であるし、「指名買い」の必要性も無い。
別に「ヘキサノン」というブランドがあるから銘玉という
訳でも無いし・・ これであったら、全ての点でNIKONの
Ai105/4を購入した方がベターであろう。
ちなみに、Ai105/4は本ベローズシステムよりも安価な
8,000円(税込)で中古購入している。
----
さて、5本目のシステム

(中古購入価格 4,000円)(以下、MUSE ZP)
カメラは、OLYMPUS E-410 (4/3機)
さて、また説明が非常にややこしいシステムだ(汗)
今回は「本MUSE オプテイックのゾーンプレートモードを
使用して撮影する」が、この時点で言葉の意味が何の事
やら、さっぱりわからないかも知れない(汗)
幸い「レンズ・マニアックス第4回記事」で、本システム
についての詳細を説明しているので、そちらを参考に
してもらえば良いと思う。

これはこれで面白いのではあるが、やはり「有効な用途」が
見つけ難いレンズでもある。
それと、今回は、このMUSEのユニットが4/3機用の為
(注:終焉した4/3システム用であったため、在庫処分で
安価に新品購入する事ができた)OLYMPUS E-410の
4/3機を使用しているが、この機体は低感度である為、
少々使い勝手が悪い。
以降、レンズはそのままMUSE ZPを使用するが、
簡易4/3→Eマウントアダプター(電子接点なし)を
介して、カメラをSONY NEX-7 (APS-C機)に交換しよう。

しないのだが、本MUSEの場合、そうした電気的なやり取り
が不要なトイレンズの為に、アダプターは単にマウント形状を
変換するだけの簡単な構造の物で良い。
NEX-7を母艦とするならば、優秀なエフェクト機能を
併用するのも面白いであろう。なお、さらにエフェクトが
優秀なオリンパスのミラーレス機(OM-D E-M1等)で使った
方が良かったかも知れないが、勿論搭載エフェクトの仕様は
機種毎に異なるので、まあ、使っているカメラの搭載範囲内
で選べば良いだけの話だ。エフェクトの件に限らないが、
カメラの機能や性能が高いからと言って、それを根拠に
良い写真が撮れる訳でも無い。あくまで、どの機能を、
どのように使うかが肝心である。
これは、ごく当たり前の話ではあるが、残念ながら多くの
初級者は、この事が理解できず、機能や性能仕様の高い
(しかし高額な)カメラばかりを欲しがってしまうのだ。
でも、10年前であれば、それは「腕に見合わず、格好悪い」
と、切り捨ててしまえたのだが、現代においては、カメラ
市場が極端に縮退してしまっている為、初級中級層に
高価な最新高性能カメラを買ってもらって市場を潤さないと
本当にカメラ市場が崩壊してしまう。そうなると、勿論
皆が困るので、せっせとビギナー層に高価な最新機材を
買ってもらって、私は、古くなってコスパがとても良く
なった旧世代の機材を、中古で買う事にしようか。

特別な用途は考えにくいかも知れない。
だがまあ、今回の記事の「変則レンズ」は、全てが同様だ、
いずれの機材(レンズ)も、あまり特別な用途を持たない
ものばかりである。勿論、初級中級層に推奨できるような
ものは少なく、買ったとしても用途が無くて、持て余して
しまう事であろう。
まあ、あくまで「参考まで」というスタンスである。
----
では、今回ラストのシステム

(中古購入価格 10,000円)(以下、DT30/2.8)
カメラは、SONY α65 (APS-C機)
ハイコスパ第14回記事等で紹介の、2009年発売のAPS-C機
専用AF単焦点準広角(標準画角)マクロレンズ。
エントリー・マクロレンズとしては優秀な類である。
一応等倍撮影が出来るし、有限回転式ピントリングの為に、
近接MF技法が使え、αフタケタ機に備わるピーキング機能
を併用する事で、快適なマクロ撮影を可能とする。
描写力は「感動的」という要素は無いが、悪いという話
でも無い。

いるため、通常レンズに比較して近距離の撮影においては
「非常に描写力が優れる」という印象を持つ事が多い。
(注:「設計基準が最短側、無限遠側」と、ざっくりと区別
される事が多いが、「設計基準」では、あまりに広範囲で
曖昧な言葉なので、設計開発の実務を全く理解していない
門外漢の用語と判断し、本ブログでは滅多にそうは呼ばない)
まあ、その手の「本格的なマクロレンズ」に比べると、
本レンズの描写力は、やや物足りない印象もあるだろう。
しかし、1万円の中古価格(注:現代ではさらに相場が
安価になっている)で買えるレンズとして考えると、
極めてコスパが良い。
最大の特徴として、WD(ワーキング・ディスタンス)が
極めて短い(数cm)事がある。
まあ、準広角(標準画角)マクロで等倍仕様であれば、
だいたいWDは短くはなるが、それにしても、この短さは
トップクラスである(他にもミラーレス機用の、30mm級
等倍マクロ等も、同様にWDが非常に短いものがある)
WDが短い事は長所であるとは言い切れず、被写体に非常に
近接して撮影する場合、屋外撮影ではカメラやレンズの
影が被写体にかかってしまうとか、昆虫等は逃げてしまう
とか、誤って被写体に接触してしまう(例:花粉やら
料理の脂分等がレンズにつく、模型を壊してしまう等)
そもそも、どうしても被写体に接近できない環境もある
(例:花壇とか、頭上の木々の花等)だろう。
まあ、被写体に近接出来ないケースでは、中望遠マクロや
望遠マクロ等のWDが長い機材を使う必要があると言う事だ。
だが、WDが短い事を意外な長所にする事もできる。
それは、「ZENJIX soratama 72(宙玉)」の利用だ。
以降、SONY DT30/2.8を、マスター(主)レンズとして、、
そのアタッチメントをつけてみよう。

第61回、第69回記事等の多数で紹介済みの、2010年代
発売の特殊アタッチメント型レンズである。
(新品購入価格 6,000円)
このアタッチメント(注:「付属品」という意味。勿論
アタッチメントには「フィルター径」という意味は無いが
WEB上で誤用が目立つ)は、ガラス玉(宙玉)に映る映像を
撮影するものだが、レンズ前部に非常に近接して「宙玉」を
配置しなければならない。たいていのレンズではWDが長い
為にピントが合わず、「宙玉」を、かなり遠い位置に置く
必要があり、その構造を工作する等が面倒であったり、
構造が脆くなったり、加えて「宙玉」が小さく写りすぎて
しまう。

逆転して掲載している)
本DT30/2.8であれば、WDが数cmであるから、「宙玉」を
ある程度大きく写す事が可能であるし、装着する為の
構造もシンプルかつ小型化できるので、ハンドリングが楽だ。
それから「もっとWDが短いレンズは無いのか?」というと、
実は、そういったレンズも存在している。
具体的には、本シリーズ第17回記事等で紹介した、
LAOWA 15mm/f4 であり、その「等倍広角マクロ」では、
WDは数mm程度しかない。その場合「宙玉」を、ほとんど
ダイレクトにレンズ前に装着出来る為、さらにコンパクトに
なるのだが、「宙玉」自体の構造上、レンズ前数mmまで
近接しての配置ができず、むしろ「宙玉」が小さく写って
しまうという課題があった(当該記事参照)
まあ、やはり、本DT30/2.8が、「宙玉」のマスターレンズ
としては適正なのではなかろうか・・?
----
さて、今回の記事「変則レンズ特集」は、このあたり迄で、
次回記事に続く・・