本シリーズでは、現在所有している一眼レフ用の50mmレンズ
(標準レンズ)を、AF/MF、開放F値等によるカテゴリー別で
予選を行い、最後に決勝で最強の50mmレンズを決定する
という趣旨のシリーズ記事である。
この「選手権」では色々なルールがあるが、詳しくは
本シリーズ第1回記事を参照されたし。
今回は、予選Bブロックとして「AF50mm/f1.8」レンズを
4本紹介(対戦)する。
---
まずは最初のレンズ。
![_c0032138_12351180.jpg]()
レンズ購入価格:5,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ)
1990年に発売されたニコンFマウント用のAF小口径標準レンズで
あるが、旧来1970年代のAiニッコール系50/1.8のAF版であり、
AF化においてレンズ構成には殆ど(全く?)変更が無かった。
その後2000年代前半に距離エンコーダー内蔵のD型となっているが、
ここでもレンズの中身は従来品(本レンズ)と同じものだ。
(参考:型番の最後に付く「S」は、シャッター優先やプログラム
AEに対応する「自動絞り」の意味で、MFのAi時代からの名称だ)
![_c0032138_12351193.jpg]()
つまり変更の必要が無かった、という事であれば、発売当初から
極めて完成度の高かったレンズ(構成)であるとも言える。
(参考:型番の冒頭につくAF-Sの「S」は、レンズ内に超音波
モーターを搭載しているという意味。NIKONデジタル一眼レフ
の低価格機ではボディ内モーターを持たないので、AF-S型(等)
で無いとAFが効かない。さらにちなみに、型番末尾の「G」は、
「絞り環の無いレンズ」という意味で、概ね1990年代以降の
NIKON銀塩/デジタル機で無いと、絞り値の設定が出来ない。
ただし、S,D,AF-S,G等の差異は、現代の各社ミラーレス機で
(G型対応等)マウントアダプターを介して装着するならば、
どの形式のレンズであっても問題なく使用する事ができる)
なお、実は、本記事で紹介の4本の50mm/f1.8レンズは、
フルサイズ対応が2本、APS-C機専用が2本、となっているが、
その全てのレンズが「5群6枚構成」と同じである。
これは「変形ダブルガウス型」等と呼ばれている銀塩時代からの
オーソドックスなレンズ構成であり、まあ、逆に言えば完成度が
非常に高い設計である。
が、今回記事の紹介レンズ群を初め、非常に多くの標準レンズが、
その同じ構成であるならば、メーカーあるいは個々の標準レンズ
の性能的な差異は「殆ど無い」とも言える。
レンズ構成が同じであっても、それでもまあ今回の記事群では、
APS-C機専用か、フルサイズ対応かという違いがあり、あるいは
銀塩時代においても、口径の差とか、コーテイングの優劣とか、
はたまた同じレンズ枚数・構成でも僅かにレンズ配置等の設計が
異なるとか、ガラス材質(屈折率、色分散)が異なるとか、
曲率の差とか、そんな風な微妙な違いがあり、ほんの少しだけ
性能差は出てくると思う。
だがそれは枝葉末節だ、特に小口径標準(50mmでF1.7~F2級)
は、銀塩時代から、どのメーカーのどのレンズを買って使って
みても、たいてい同様な写りで、どれも良く写る。
![_c0032138_12351179.jpg]()
いるが、同じレンズ構成であっても発売時期の差は大きい。
最も古い物では1987年発売、最も新しい物で2012年発売と、
およそ四半世紀もの時間差がある。
だが前述のように、いずれもほぼ同じレンズ構成である為、
時代の差ほどの性能差は無い訳だ。
「では、最強50mmなど、決めれないのでは無いのか?」
と言う疑問もあるだろう。
確かにその通り、もし50mm標準レンズが銀塩時代からの
変形ダブルガウス型設計の物ばかりであれば、殆どどれも
同じような写りであり、大差は無い。
それから、シニア層・ベテラン層などは、自身の使っている
カメラメーカーの標準レンズが最も良い、という評価を良く
口にするのだが、例えベテラン層とは言え、全てのメーカーの
様々な標準レンズを使い込んでいる人などは、殆ど皆無だ。
だから、人の言う事はあてにならない。あくまで自分自身の
目で確かめる事が重要だし、メーカー(ブランド)銘に囚われず
公平な評価・判断をしなければならない事も言うまでも無い。
で、最強50mが決めれないのでは? という件の回答だが、
実は、2000年代後半位から、従来の変形ダブルガウス型構成に
囚われずに新規に設計された標準レンズが、やっといくつか
出て来ている。
「やっと」と書いたのは、銀塩時代を通じ、そしてデジタル時代
に入ってまで、標準レンズの性能的改善がされない時代が延々と
続いていたのだ。まあこの理由は、変形ダブルガウス型の構成が
完成度が高かったので、あまり改良する必然性が無かった事と、
銀塩末期(AFの時代)~デジタル時代の初期はズームレンズの
発展改良期であった為、単焦点の標準レンズの研究および改良が
後回しにされていたのだと思う。
現代の新設計単焦点は、今までの標準レンズでは超高画素への
対応が難しくなったからだ(詳細は後述する)
だからまあ、待ち望んだ新世代の標準レンズが、「やっと」
近年になって出てきているという状況だ。
そして、オールドレンズ群には申し訳無いが、本シリーズでの
ラストに予定されている「決勝戦」は、その殆どが、新鋭の
50mmレンズになってしまう事であろう。まあ、標準レンズに
関しては、そういう歴史なので、それはやむを得ない事だ。
![_c0032138_12351194.jpg]()
運よく安価(中古で5000円)で入手できたレンズであり、
極めてコスパが良い。
そのおかげで「ハイコスパレンズBEST40編」では、25位相当
(同シリーズ第6回記事)にランクインした次第であった。
ただ本レンズは「エントリーレンズ」と言う位置づけでは無い、
冒頭に述べたように、銀塩MF時代の古くから長い歴史を持つ
伝統的かつ正統派のレンズだ。その為、安心感も高い、つまり
何十年もの間、レンズを殆ど改良しなくて済んだという事は、
当時から、もう完成されたレンズであった、という訳だ。
勿論、現代でも何ら問題なく使用できる。
「超高画素化に対応していない」と言う些細な心配があるのなら
少し前の時代でのローパスフィルター有りのデジタル一眼レフで、
あまり画素数を上げずに使えば良い、それだけの話だ。
ちなみに今回使用のNIKON Dfは、操作系に色々と重欠点を持つ
カメラではあるが、フルサイズ機で有効最大画素数が1600万画素
と少ない、この結果、ピクセルピッチ(1ピクセルあたりの大きさ)
が大きく、レンズ自身の高解像力はあまり必要としないカメラだ。
大面積ピクセルにより、高ダイナミックレンジと、超高感度性能
(最大ISO20万)を目指したカメラという訳である。
ちなみにローパスフィルター有りの仕様であり、オールドレンズ
等との相性は比較的良い。(たとえDfが問題児カメラであっても、
色々と使い道はある、と言う事だ)
---
では、次のレンズ。
![_c0032138_12352126.jpg]()
レンズ購入価格:9,800円(中古)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ (APS-C機)
2009年頃に発売された、APS-C機専用「エントリーレンズ」
本レンズの換算画角は75mm相当になり、標準(画角)レンズ
とは言い難いが、そのあたりは無視する事にしよう。
![_c0032138_12352157.jpg]()
の方が有利なのでは?」と思うかも知れないが、それはむしろ
逆の場合もある。
例えば、フルサイズ用のレンズでも、APS-C型センサーの
一眼レフに装着する事は勿論可能だ。
そして、フルサイズ用レンズをAPS-C機で使った方がレンズの
周辺収差等が消えて、APS-C機専用レンズをAPS-C機で使った
よりも画質面(画面全体の平均画質)では有利である。
だけど、そういう細かい点を一々気にしていたら始まらない、
問題は、レンズ自体の性能やコスパがどうか?という点だ。
本レンズDT50/1.8は、典型的なエントリーレンズであるが、
SONY α(A)マウントの50mm標準レンズは、他にSAL50F14と
SAL50F14Zと、合計3本がラインナップされている。
SAL50F14は、銀塩AF時代のαショック(1985年に完成度の高い
AF機のα-7000が発売された)の際の同時発売の標準レンズ
AF50/1.4からの長い歴史を持つオーソドックスな標準レンズだ。
(注:正確には、同AF50/1.4の基本設計は、1980年代初頭の
NMD50/1.4まで遡る、いずれもミラーレス・マニアックス記事で
紹介済み)
SAL50F14Zは、カールツァイスのブランド銘を関した高級レンズ
であるが、このレンズは未所有で詳細や出自も調べてはいない。
![_c0032138_12352187.jpg]()
知れないが、ところが本レンズの近接性能(最短撮影距離34cm)
は、他のSONY標準レンズを上回っているし、描写力的にも
他社標準レンズ群に対して劣る点はあまり無い。
まあ、エントリーレンズであるから、それを試す事でユーザーに
交換レンズの魅力に気付いてもらい、他の交換レンズを買って
もらう為の誘導をしなくてはならない重要な立場だ。これがもし、
がっかりする低性能であれば、ユーザーは二度とSONY製の
交換レンズを買ってくれなくなってしまう。
![_c0032138_12352101.jpg]()
過剰な程に優れている、すなわちコスパが極めて良い。
この為、コスパ評価を主体とする「ハイコスパBEST40」記事では、
上位の第6位にランクインした「強豪」のレンズとなっている。
ただ、個人的には、本レンズDT50/1.8は「感動的と言うような
高描写力は持たない」と感じていて、あまり好みのレンズでは
無い。確かにα(A)システムにおける必要性は非常に高いのだが、
最強50mmを決める本シリーズ記事で決勝戦にノミネートできるか
どうかは微妙な所だ。
----
では、次の50mmレンズ。
![_c0032138_12353100.jpg]()
レンズ購入価格:11,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ)
1987年に発売された銀塩EOS用初のAF小口径標準レンズ。
(ハイコスパレンズ・マニアックス第1回記事等で紹介)
![_c0032138_12353114.jpg]()
メーカー各社は一斉にAF化に追従した歴史だ。
キヤノンは当初、旧来のFDマウントのままAF化を試み「T80」
というカメラ(未所有)を発売したのだが・・
運悪くα-7000の発売時期と被ってしまい、両者の完成度の
差異から、T80は酷評されてしまい、事実上の失敗作となって
しまった。
実はαショック以前にも、各社から試作的な銀塩AF一眼レフは
発売されていたし、T80はそれらに劣る性能であった訳でも無い、
ただ、α-7000のインパクトが大きすぎただけだ。
この結果、T80は不運な事に「無かった事」にされ、歴史の
闇に葬られてしまった。
で、キヤノンはFDマウントを捨て、新たなEF(EOS)マウントの
開発の着手を始める。その開発期間の「繋ぎ」として、EOSの
原型とも言える極めて完成度の高い名機「T90」(過去所有)
を発売する。MF時代末期のキヤノンはNew F-1やT90を始め
名機と呼べる機体が多かったのだが、AF化において最初に
1987年に発売したEOS(620/650)は、旧来のFDマウントの
互換性を完全に排除してしまった為、それまでのFDマウント
機ユーザーから、そっぽを向かれてしまった。
ミノルタもまあ、αマウントと旧来のMC/MD系マウントには
全く互換性が無かったのだが、α-7000の性能が圧倒的であった
事や、旧来のMDマウントMF機、例えばX-700等は上級層や業務用
等で本格的に使うカメラでは無かった為、マウント変更は不問と
されたが、キヤノンの場合には、旧来のNew F-1等の旗艦機
よりも新型EOSでの信頼度やシステム性は低かった為、上級層
からの反感を買ってしまった訳だ。
ちなみに、ニコンとペンタックスは、AF化において旧来のMFの
マウント(F,PK)を変更していない。
さて、そんな時代背景において、新マウントEOS用の交換レンズ
の戦略は非常に重要だ。マウント互換性が無いという事は、
ユーザーは、旧来のFDレンズを使用できない。
だから新規のEFマウント用レンズを新規購入する事を、ある意味
「強要」されてしまう、であれば、そこで魅力的な性能のレンズ
が無ければ、一部のユーザーは「旧来のFDレンズの方が良いよ、
だったらEOSに乗り換えずに、F-1を使っていれば、それでいいや」
と思ってしまう事であろう。
本EF50/1.8だが、そういう重責を担ったレンズである。
ズームレンズは1980年代後半では、まだ技術的に発展途上期であり
AF一眼レフといえども、旧来のMF一眼レフ同様に50mm標準レンズ
とのセットで発売されていたケースも多い。
つまり50mm標準は各社の「顔」である、ここで低い性能のものを
出してしまうと、「キヤノンEOSは写りが悪い」などと悪評判が
立ってしまう。
ちなみに、この命題(50mmは各社の「顔」)があるから、
逆説的に言えば、各社の50mm標準レンズの性能差は殆ど無いのだ。
もし他社より性能が劣る50mmを売っていたら、評判が悪くなる。
だから、とっくに改良しているか、もしくは、もうカメラが全く
売れずに困った事になっていただろう。
当時の銀塩機では、カメラ自体の性能差よりも、レンズおよび
フィルム性能が、写真の仕上がりに影響する割合が極めて
大きいのだ。
![_c0032138_12353182.jpg]()
の性能は重要だ、本EF50/1.8は十分な高描写力を持つのだが、
多少インパクトに欠ける節もある、なにせ当時はバブル時代の
黎明期だ、「凄いもの、派手なもの」で無いと、世の中の人達は
誰も注目しなかったのだ。
そこでキヤノンは、2年後の1989年には、超大口径レンズである
EF50mm/f1.0L USMを発売する、高価でバブリーな製品だった
とも言える。このレンズは後年に中古を購入しようかどうか迷って、
中古店から短時間だけ借りてフィルム1本分だけ試写したのだが、
大きく重いレンズで、かつ、描写力もあまり好みでは無かった
ので購入を見送る事とした。(まあ、USM搭載最初期のレンズ
であり、「超音波モーター」自体もバブリーな仕様だった)
低価格帯の標準レンズはどうか?と言えば、本レンズEF50/1.8
が中途半端に目立たないレンズであった為、1990年に本レンズの
レンズ構成のまま、外装を簡略化したEF50/1.8Ⅱにリニューアル
される。同時に定価も大きく値下げした。
(注:ここで海外生産に切り替えた可能性も高い)
このEF50/1.8Ⅱは、いわば「エントーリレンズ」の元祖である
とも言える。ユーザー層へのEOS機の普及を狙って(その中には
依然、FDマウントの機体を頑なに使い、EOSを拒む層も含まれる)
戦略的に投入された秘密兵器であったのだ(当該レンズは未所有)
EF50/1.8Ⅱは作戦通り「とても安い割りに、極めて良く写る」
と、初級中級層から「神格化」される程となり、銀塩時代の
1990年代を通じ非常に多数が販売され、さらにはデジタル時代に
なってからも発売が継続され、2015年にEF50/F1.8STMに
リニューアルされるまで、実に25年間、四半世紀にも及ぶ
超ロングセラー製品となった。
まあつまり、ここでも、完成度が高かったから本EF50/1.8(Ⅰ)
のレンズ構成は改善する余地が無かったという事情となっている。
すなわち「どの標準レンズも同じだ」と繰り返し述べているのは、
こういう様々な歴史的な背景があるからだ。
![_c0032138_12353131.jpg]()
好きになれず、「どうしても初期型が欲しい」と長年拘り続けて
やっと2010年代に購入できた個体である、初期型は短期間だけの
発売で、中古での玉数が極端に少なかったのだ。
初期型である必然性は少ないが、Ⅱ型も含め、キヤノンEOSの
歴史を知る意味で必携のレンズであろう。
(参考:CANON EF50/1.8Ⅱのデッドコピー製品である、
中国製の「YONGNUO YN50/1.8」というレンズが存在する。
それは所有しているが、本シリーズ記事執筆時点では評価が
間に合っていなかった為、ノミネートは見送った。
レンズマニアックス第20回記事で既に紹介済みである)
---
では、本記事ラストのレンズ。
![_c0032138_12353822.jpg]()
レンズ購入価格: 9,200円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-30(APS-C機)
2012年に発売された、APS-C機専用小口径標準(中望遠画角)
レンズである、ペンタックスのWEBでは画角から「中望遠レンズ」
としてカテゴライズされている。
![_c0032138_12353827.jpg]()
APS-C機用なので、レンズ自体は小型化され軽量(122g)である。
ただ、あまり小さくは無く、一般的な標準レンズと同じサイズ感
(フィルター径φ52mm)となっている。
余談だが、ここで、前述したレンズ解像度の話を述べておこう。
銀塩時代からのこの手の小口径標準レンズの解像力であるが、
解像度チャート等を撮影して、写っている画像を見分ける事で
レンズの解像度(力)を計測する事が出来る。
私が実際に実験してみたところ、銀塩MF用の小口径標準レンズは
だいたい150本(LP)/mmという値が出てくる(注:これは絞り
の設定値にも依存し、かつ画面中央部等の最良の場合の値である。
またこれは標準的な性能のレンズの場合で、MF時代においても
高性能なものでは、180LP/mm位に達する場合もある)
LPとは「ラインペア」という意味であり、解像度チャート上には、
白と黒のライン(線)が描かれていて、撮影画像において、その
ペアを、どこまで見分けられるか?という計測手法である。
150LPと言えば、1mmの範囲で2倍の300本を解像(区別)できる。
これは別の言い方をすれば、1mmあたりで300本であるから
1本あたり判別の幅は、約0.0033mm=約3.3μmとなる。
この解像力が、デジタルカメラでのセンサーサイズ上での
ピクセルの幅(ピクセルピッチ)よりも小さければ問題無い訳だ。
では、ここで、いくつかの計算例を挙げてみよう。
2つの近代デジタル一眼レフで考えてみる。
*NIKON Df
フルサイズ 約36mmx24mmセンサー 約1600万画素
センサー横幅約36mm÷約5000ピクセル(最大画素数)
=約7.2μm
*PENTAX KP
APS-C機 約23.5mmx15.6mmセンサー 約2400万画素
センサー横幅約23.5mm÷約6000ピクセル(最大画素数)
=約3.9μm
すなわち、NIKON Dfのシステムでは、ピクセルピッチが約7μm
であるから、銀塩時代の古いレンズの解像力=約3μmでも、
全然余裕であり、レンズ性能の不足を感じる事が無い。
PENTAX KPは小さいAPS-Cセンサーで、かつ画素数が大きい、
この場合、ピクセルピッチはかなり小さくなり、約4μm程だ、
銀塩時代の低性能レンズと組み合わせると、ほぼ同等の解像力
となり、使用するのに、ぎりぎりの状況だ。
おまけにKPはローパスレスのカメラだ、ローパスフィルター
により細かすぎる画像(の空間周波数)を排除するという方針
では無い為、レンズの解像力は必然的に高いものが要求される。
余談だが、銀塩35mm判の画素数は当然アナログであるので不明だ、
だが、経験則や実験等で「だいたい2000万画素級である」と
言われている。この場合、1800x1200程度のピクセル数だと
仮定すると、35mm判フィルムで必要なレンズ解像力は
36mm幅÷1800=20μm →1mmあたり50本→25LP/mm
で十分という計算であり、トイレンズを除き、ほぼ全ての
銀塩写真用レンズは、この水準をクリアしている(いた)
で、もし、ピクセルピッチの方がレンズの解像力よりも小さいと
せっかくセンサー側では細かい画像に対応しようとしているのに
レンズの性能が追いついていない、という状況になってしまう。
これは現代のデジタル一眼レフとその交換レンズの場合は
あまり(ほとんど)問題にはならないが、もうこれ以上カメラ
のセンサーの画素数が上がると、そろそろヤバい状況だ。
この傾向はセンサーサイズが小さければ小さいほど顕著になる、
たとえば携帯電話搭載カメラとか、監視カメラなどでは、
センサーサイズが1/3型~1/5型(いずれも数mm角)と極めて
小さい。ここに何千万画素もの画素数を詰め込もうとすると
ピクセルピッチは、数μmとなり、それに対応する高解像力
のレンズが必要となるが、小型化された携帯や監視カメラ用の
レンズでは、とてもそこまでの解像力性能は出ない、せいぜいが
100LP/mmか、またはそれ以下であろう。
(注:近年の高級マシンビジョン用レンズでは、解像力は、
170LP/mm程度あるので、なかなか優秀だ)
つまり、小型センサーの映像機器の世界では、すでにレンズ
性能が不足している状況なのだ。
でもまあ、携帯カメラや監視カメラでは、そこまでの厳密な
性能(描写力)は要求されない。だが、写真用レンズでは困る。
そこで、例えば、近い将来の超高画素時代における必要レンズの
性能要件を考えてみよう。
*フルサイズ1億画素機=約12000x約8000ピクセル
センサー幅36mm÷12000ピクセル=ピクセルピッチ約3μm
*APS-C 4000万画素機=約8000x約5000ピクセル
センサー幅24mm÷ 8000ピクセル=ピクセルピッチ約3μm
いずれも、3μm程度のピクセルピッチが必要となった、
まあ、センサー製造上での技術は等しく進化していくから、
センサーサイズに係わらず、ピクセルピッチは同じとなる事で
あろう。
(注:小型センサー、すなわちμ4/3機用センサーや、産業・
監視カメラ用センサー、携帯系撮像センサー等では、製造の
プロセスが異なるのか? 上記のような一眼レフ用センサー
よりも、ずっと小さいピクセルピッチとなっている)
で、これはつまり1mm÷3μm=333であるから、330本の
ライン、すなわち「170本程度のLP値の性能を持つレンズで
あれば高画素化にも耐えられる」という事である。
しかし「あれ?」と思わないであろうか? 銀塩時代の
高性能レンズであれば、170LP/mm程度の高性能のものは
中にはある、そういうレンズは、フルサイズ1億画素や
APS-Cの4000万画素機でも使える、という事になるのだ。
(注:画面中央部など、最良の場合に限った話である)
だが、そういう超高性能な銀塩用レンズの存在は稀だと思う、
そして、今回紹介しているような銀塩時代の完成度の高い
変形ダブルガウス型標準レンズでは、わずかにこのレベルには
届かないかも知れない。
であれば、超高画素用の新たな標準レンズの開発が必須になる、
それが、2010年代において各社から登場している新時代の
標準レンズだ。
それらの新鋭レンズの解像力性能だが、きちんと自身で測った
訳では無いのだが、恐らくは最良で250LP/mm程度であろう。
そうであれば、1mm÷(250x2)=2μmの解像力があるから、
現状の高画素機のレベル(3~4μm)よりもだいぶ余裕がある。
計算上では、さらに画素数が上がって、フルサイズで2億画素
(1万8000x1万2000ピクセル)となってもまだ耐えられる訳だ。
長々と計算をしてきたが、ともかくこのあたりが、現代の標準
レンズがより高性能(高解像力)が求められる理由である。
(注:ここまでの計算手法は、あくまで概念的なものである。
実際のセンサーでは、原色/補色カラーフィルターの存在に
より全画素を均一に扱えない(色が飛び飛びである)事、
ローパスフィルターの存在、さらにはピクセル開口率の
差異、それから像面位相差AF等まであって、極めて複雑だ。
場合により計算困難(不能)であるかもしれず、たとえ光学
の専門家層であっても、統一見解が無いと思われる)
![_c0032138_12353844.jpg]()
高解像度の写真イコール良い写真、と言う図式が常に成り立つ
訳では無い。解像度は写真における映像再現性としては確かに
重要な要素だが、それは作品における表現性とイコールでは無い。
だから、新鋭の高価な標準レンズを使ったところで「良い写真」
が撮れるという保証も無い。そもそも、「良い写真とは綺麗に
写っている写真」という公式が成り立つ訳では無い。
今から50年から60年も昔の銀塩の1960年代であれば、カメラや
フィルムやレンズの性能や、撮り手の技能もまだ未成熟であり
綺麗に写真を撮れる事自体が「良い写真」の条件であったのだが、
既に、そこから半世紀以上が過ぎている。
今や、デジタル一眼レフやミラーレス機はもとより、コンパクト
機や携帯系カメラでも、誰でもシャッターを押すだけで綺麗な
写真を撮る事が出来る時代だ。
今の時代にまでなってなお「より綺麗に写っている写真」だけを
追い求めているとすれば、それは感覚の方向性が間違っている
という事になってしまう。普通に綺麗に写るのは当たり前、
そこから他の写真には無い何か(=表現)を加えていかない限り
写真の意味が無い。
ただ単に、珍しい被写体を探して綺麗に撮っただけでは、
「ふ~ん、だから何? それで何が言いたいの?」のように
撮り手の存在感が極めて希薄な写真にしかならない訳だ。
「その撮影者は何が言いたいのか?」 それが写真の表現に
直結する。
![_c0032138_12353873.jpg]()
繰り返し述べてきた通り、このクラスの小口径標準レンズの性能は
どれをとってもほぼ同じだ、個々の細かい差異を重箱の隅をつつく
ように洗い出したとしても、もはやそれは枝葉末節に過ぎないし
細かい欠点を一々あげる必要も無いくらい、どれも長い歴史を持つ
完成度の高い優秀なレンズばかりである。
欲しければ、予算や志向や機材環境に応じ、自分が好きな小口径
標準レンズを買えば良い、だたそれだけの話である。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Bブロック「AF50mm/f1.8」の記事は終了だ、
次回の本シリーズ記事は、
予選Cブロック「AF50mm/f1.4 Part1」となる予定だ。
(標準レンズ)を、AF/MF、開放F値等によるカテゴリー別で
予選を行い、最後に決勝で最強の50mmレンズを決定する
という趣旨のシリーズ記事である。
この「選手権」では色々なルールがあるが、詳しくは
本シリーズ第1回記事を参照されたし。
今回は、予選Bブロックとして「AF50mm/f1.8」レンズを
4本紹介(対戦)する。
---
まずは最初のレンズ。

レンズ購入価格:5,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ)
1990年に発売されたニコンFマウント用のAF小口径標準レンズで
あるが、旧来1970年代のAiニッコール系50/1.8のAF版であり、
AF化においてレンズ構成には殆ど(全く?)変更が無かった。
その後2000年代前半に距離エンコーダー内蔵のD型となっているが、
ここでもレンズの中身は従来品(本レンズ)と同じものだ。
(参考:型番の最後に付く「S」は、シャッター優先やプログラム
AEに対応する「自動絞り」の意味で、MFのAi時代からの名称だ)

つまり変更の必要が無かった、という事であれば、発売当初から
極めて完成度の高かったレンズ(構成)であるとも言える。
(参考:型番の冒頭につくAF-Sの「S」は、レンズ内に超音波
モーターを搭載しているという意味。NIKONデジタル一眼レフ
の低価格機ではボディ内モーターを持たないので、AF-S型(等)
で無いとAFが効かない。さらにちなみに、型番末尾の「G」は、
「絞り環の無いレンズ」という意味で、概ね1990年代以降の
NIKON銀塩/デジタル機で無いと、絞り値の設定が出来ない。
ただし、S,D,AF-S,G等の差異は、現代の各社ミラーレス機で
(G型対応等)マウントアダプターを介して装着するならば、
どの形式のレンズであっても問題なく使用する事ができる)
なお、実は、本記事で紹介の4本の50mm/f1.8レンズは、
フルサイズ対応が2本、APS-C機専用が2本、となっているが、
その全てのレンズが「5群6枚構成」と同じである。
これは「変形ダブルガウス型」等と呼ばれている銀塩時代からの
オーソドックスなレンズ構成であり、まあ、逆に言えば完成度が
非常に高い設計である。
が、今回記事の紹介レンズ群を初め、非常に多くの標準レンズが、
その同じ構成であるならば、メーカーあるいは個々の標準レンズ
の性能的な差異は「殆ど無い」とも言える。
レンズ構成が同じであっても、それでもまあ今回の記事群では、
APS-C機専用か、フルサイズ対応かという違いがあり、あるいは
銀塩時代においても、口径の差とか、コーテイングの優劣とか、
はたまた同じレンズ枚数・構成でも僅かにレンズ配置等の設計が
異なるとか、ガラス材質(屈折率、色分散)が異なるとか、
曲率の差とか、そんな風な微妙な違いがあり、ほんの少しだけ
性能差は出てくると思う。
だがそれは枝葉末節だ、特に小口径標準(50mmでF1.7~F2級)
は、銀塩時代から、どのメーカーのどのレンズを買って使って
みても、たいてい同様な写りで、どれも良く写る。

いるが、同じレンズ構成であっても発売時期の差は大きい。
最も古い物では1987年発売、最も新しい物で2012年発売と、
およそ四半世紀もの時間差がある。
だが前述のように、いずれもほぼ同じレンズ構成である為、
時代の差ほどの性能差は無い訳だ。
「では、最強50mmなど、決めれないのでは無いのか?」
と言う疑問もあるだろう。
確かにその通り、もし50mm標準レンズが銀塩時代からの
変形ダブルガウス型設計の物ばかりであれば、殆どどれも
同じような写りであり、大差は無い。
それから、シニア層・ベテラン層などは、自身の使っている
カメラメーカーの標準レンズが最も良い、という評価を良く
口にするのだが、例えベテラン層とは言え、全てのメーカーの
様々な標準レンズを使い込んでいる人などは、殆ど皆無だ。
だから、人の言う事はあてにならない。あくまで自分自身の
目で確かめる事が重要だし、メーカー(ブランド)銘に囚われず
公平な評価・判断をしなければならない事も言うまでも無い。
で、最強50mが決めれないのでは? という件の回答だが、
実は、2000年代後半位から、従来の変形ダブルガウス型構成に
囚われずに新規に設計された標準レンズが、やっといくつか
出て来ている。
「やっと」と書いたのは、銀塩時代を通じ、そしてデジタル時代
に入ってまで、標準レンズの性能的改善がされない時代が延々と
続いていたのだ。まあこの理由は、変形ダブルガウス型の構成が
完成度が高かったので、あまり改良する必然性が無かった事と、
銀塩末期(AFの時代)~デジタル時代の初期はズームレンズの
発展改良期であった為、単焦点の標準レンズの研究および改良が
後回しにされていたのだと思う。
現代の新設計単焦点は、今までの標準レンズでは超高画素への
対応が難しくなったからだ(詳細は後述する)
だからまあ、待ち望んだ新世代の標準レンズが、「やっと」
近年になって出てきているという状況だ。
そして、オールドレンズ群には申し訳無いが、本シリーズでの
ラストに予定されている「決勝戦」は、その殆どが、新鋭の
50mmレンズになってしまう事であろう。まあ、標準レンズに
関しては、そういう歴史なので、それはやむを得ない事だ。

運よく安価(中古で5000円)で入手できたレンズであり、
極めてコスパが良い。
そのおかげで「ハイコスパレンズBEST40編」では、25位相当
(同シリーズ第6回記事)にランクインした次第であった。
ただ本レンズは「エントリーレンズ」と言う位置づけでは無い、
冒頭に述べたように、銀塩MF時代の古くから長い歴史を持つ
伝統的かつ正統派のレンズだ。その為、安心感も高い、つまり
何十年もの間、レンズを殆ど改良しなくて済んだという事は、
当時から、もう完成されたレンズであった、という訳だ。
勿論、現代でも何ら問題なく使用できる。
「超高画素化に対応していない」と言う些細な心配があるのなら
少し前の時代でのローパスフィルター有りのデジタル一眼レフで、
あまり画素数を上げずに使えば良い、それだけの話だ。
ちなみに今回使用のNIKON Dfは、操作系に色々と重欠点を持つ
カメラではあるが、フルサイズ機で有効最大画素数が1600万画素
と少ない、この結果、ピクセルピッチ(1ピクセルあたりの大きさ)
が大きく、レンズ自身の高解像力はあまり必要としないカメラだ。
大面積ピクセルにより、高ダイナミックレンジと、超高感度性能
(最大ISO20万)を目指したカメラという訳である。
ちなみにローパスフィルター有りの仕様であり、オールドレンズ
等との相性は比較的良い。(たとえDfが問題児カメラであっても、
色々と使い道はある、と言う事だ)
---
では、次のレンズ。

レンズ購入価格:9,800円(中古)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ (APS-C機)
2009年頃に発売された、APS-C機専用「エントリーレンズ」
本レンズの換算画角は75mm相当になり、標準(画角)レンズ
とは言い難いが、そのあたりは無視する事にしよう。

の方が有利なのでは?」と思うかも知れないが、それはむしろ
逆の場合もある。
例えば、フルサイズ用のレンズでも、APS-C型センサーの
一眼レフに装着する事は勿論可能だ。
そして、フルサイズ用レンズをAPS-C機で使った方がレンズの
周辺収差等が消えて、APS-C機専用レンズをAPS-C機で使った
よりも画質面(画面全体の平均画質)では有利である。
だけど、そういう細かい点を一々気にしていたら始まらない、
問題は、レンズ自体の性能やコスパがどうか?という点だ。
本レンズDT50/1.8は、典型的なエントリーレンズであるが、
SONY α(A)マウントの50mm標準レンズは、他にSAL50F14と
SAL50F14Zと、合計3本がラインナップされている。
SAL50F14は、銀塩AF時代のαショック(1985年に完成度の高い
AF機のα-7000が発売された)の際の同時発売の標準レンズ
AF50/1.4からの長い歴史を持つオーソドックスな標準レンズだ。
(注:正確には、同AF50/1.4の基本設計は、1980年代初頭の
NMD50/1.4まで遡る、いずれもミラーレス・マニアックス記事で
紹介済み)
SAL50F14Zは、カールツァイスのブランド銘を関した高級レンズ
であるが、このレンズは未所有で詳細や出自も調べてはいない。

知れないが、ところが本レンズの近接性能(最短撮影距離34cm)
は、他のSONY標準レンズを上回っているし、描写力的にも
他社標準レンズ群に対して劣る点はあまり無い。
まあ、エントリーレンズであるから、それを試す事でユーザーに
交換レンズの魅力に気付いてもらい、他の交換レンズを買って
もらう為の誘導をしなくてはならない重要な立場だ。これがもし、
がっかりする低性能であれば、ユーザーは二度とSONY製の
交換レンズを買ってくれなくなってしまう。

過剰な程に優れている、すなわちコスパが極めて良い。
この為、コスパ評価を主体とする「ハイコスパBEST40」記事では、
上位の第6位にランクインした「強豪」のレンズとなっている。
ただ、個人的には、本レンズDT50/1.8は「感動的と言うような
高描写力は持たない」と感じていて、あまり好みのレンズでは
無い。確かにα(A)システムにおける必要性は非常に高いのだが、
最強50mmを決める本シリーズ記事で決勝戦にノミネートできるか
どうかは微妙な所だ。
----
では、次の50mmレンズ。

レンズ購入価格:11,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ)
1987年に発売された銀塩EOS用初のAF小口径標準レンズ。
(ハイコスパレンズ・マニアックス第1回記事等で紹介)

メーカー各社は一斉にAF化に追従した歴史だ。
キヤノンは当初、旧来のFDマウントのままAF化を試み「T80」
というカメラ(未所有)を発売したのだが・・
運悪くα-7000の発売時期と被ってしまい、両者の完成度の
差異から、T80は酷評されてしまい、事実上の失敗作となって
しまった。
実はαショック以前にも、各社から試作的な銀塩AF一眼レフは
発売されていたし、T80はそれらに劣る性能であった訳でも無い、
ただ、α-7000のインパクトが大きすぎただけだ。
この結果、T80は不運な事に「無かった事」にされ、歴史の
闇に葬られてしまった。
で、キヤノンはFDマウントを捨て、新たなEF(EOS)マウントの
開発の着手を始める。その開発期間の「繋ぎ」として、EOSの
原型とも言える極めて完成度の高い名機「T90」(過去所有)
を発売する。MF時代末期のキヤノンはNew F-1やT90を始め
名機と呼べる機体が多かったのだが、AF化において最初に
1987年に発売したEOS(620/650)は、旧来のFDマウントの
互換性を完全に排除してしまった為、それまでのFDマウント
機ユーザーから、そっぽを向かれてしまった。
ミノルタもまあ、αマウントと旧来のMC/MD系マウントには
全く互換性が無かったのだが、α-7000の性能が圧倒的であった
事や、旧来のMDマウントMF機、例えばX-700等は上級層や業務用
等で本格的に使うカメラでは無かった為、マウント変更は不問と
されたが、キヤノンの場合には、旧来のNew F-1等の旗艦機
よりも新型EOSでの信頼度やシステム性は低かった為、上級層
からの反感を買ってしまった訳だ。
ちなみに、ニコンとペンタックスは、AF化において旧来のMFの
マウント(F,PK)を変更していない。
さて、そんな時代背景において、新マウントEOS用の交換レンズ
の戦略は非常に重要だ。マウント互換性が無いという事は、
ユーザーは、旧来のFDレンズを使用できない。
だから新規のEFマウント用レンズを新規購入する事を、ある意味
「強要」されてしまう、であれば、そこで魅力的な性能のレンズ
が無ければ、一部のユーザーは「旧来のFDレンズの方が良いよ、
だったらEOSに乗り換えずに、F-1を使っていれば、それでいいや」
と思ってしまう事であろう。
本EF50/1.8だが、そういう重責を担ったレンズである。
ズームレンズは1980年代後半では、まだ技術的に発展途上期であり
AF一眼レフといえども、旧来のMF一眼レフ同様に50mm標準レンズ
とのセットで発売されていたケースも多い。
つまり50mm標準は各社の「顔」である、ここで低い性能のものを
出してしまうと、「キヤノンEOSは写りが悪い」などと悪評判が
立ってしまう。
ちなみに、この命題(50mmは各社の「顔」)があるから、
逆説的に言えば、各社の50mm標準レンズの性能差は殆ど無いのだ。
もし他社より性能が劣る50mmを売っていたら、評判が悪くなる。
だから、とっくに改良しているか、もしくは、もうカメラが全く
売れずに困った事になっていただろう。
当時の銀塩機では、カメラ自体の性能差よりも、レンズおよび
フィルム性能が、写真の仕上がりに影響する割合が極めて
大きいのだ。

の性能は重要だ、本EF50/1.8は十分な高描写力を持つのだが、
多少インパクトに欠ける節もある、なにせ当時はバブル時代の
黎明期だ、「凄いもの、派手なもの」で無いと、世の中の人達は
誰も注目しなかったのだ。
そこでキヤノンは、2年後の1989年には、超大口径レンズである
EF50mm/f1.0L USMを発売する、高価でバブリーな製品だった
とも言える。このレンズは後年に中古を購入しようかどうか迷って、
中古店から短時間だけ借りてフィルム1本分だけ試写したのだが、
大きく重いレンズで、かつ、描写力もあまり好みでは無かった
ので購入を見送る事とした。(まあ、USM搭載最初期のレンズ
であり、「超音波モーター」自体もバブリーな仕様だった)
低価格帯の標準レンズはどうか?と言えば、本レンズEF50/1.8
が中途半端に目立たないレンズであった為、1990年に本レンズの
レンズ構成のまま、外装を簡略化したEF50/1.8Ⅱにリニューアル
される。同時に定価も大きく値下げした。
(注:ここで海外生産に切り替えた可能性も高い)
このEF50/1.8Ⅱは、いわば「エントーリレンズ」の元祖である
とも言える。ユーザー層へのEOS機の普及を狙って(その中には
依然、FDマウントの機体を頑なに使い、EOSを拒む層も含まれる)
戦略的に投入された秘密兵器であったのだ(当該レンズは未所有)
EF50/1.8Ⅱは作戦通り「とても安い割りに、極めて良く写る」
と、初級中級層から「神格化」される程となり、銀塩時代の
1990年代を通じ非常に多数が販売され、さらにはデジタル時代に
なってからも発売が継続され、2015年にEF50/F1.8STMに
リニューアルされるまで、実に25年間、四半世紀にも及ぶ
超ロングセラー製品となった。
まあつまり、ここでも、完成度が高かったから本EF50/1.8(Ⅰ)
のレンズ構成は改善する余地が無かったという事情となっている。
すなわち「どの標準レンズも同じだ」と繰り返し述べているのは、
こういう様々な歴史的な背景があるからだ。

好きになれず、「どうしても初期型が欲しい」と長年拘り続けて
やっと2010年代に購入できた個体である、初期型は短期間だけの
発売で、中古での玉数が極端に少なかったのだ。
初期型である必然性は少ないが、Ⅱ型も含め、キヤノンEOSの
歴史を知る意味で必携のレンズであろう。
(参考:CANON EF50/1.8Ⅱのデッドコピー製品である、
中国製の「YONGNUO YN50/1.8」というレンズが存在する。
それは所有しているが、本シリーズ記事執筆時点では評価が
間に合っていなかった為、ノミネートは見送った。
レンズマニアックス第20回記事で既に紹介済みである)
---
では、本記事ラストのレンズ。

レンズ購入価格: 9,200円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-30(APS-C機)
2012年に発売された、APS-C機専用小口径標準(中望遠画角)
レンズである、ペンタックスのWEBでは画角から「中望遠レンズ」
としてカテゴライズされている。

APS-C機用なので、レンズ自体は小型化され軽量(122g)である。
ただ、あまり小さくは無く、一般的な標準レンズと同じサイズ感
(フィルター径φ52mm)となっている。
余談だが、ここで、前述したレンズ解像度の話を述べておこう。
銀塩時代からのこの手の小口径標準レンズの解像力であるが、
解像度チャート等を撮影して、写っている画像を見分ける事で
レンズの解像度(力)を計測する事が出来る。
私が実際に実験してみたところ、銀塩MF用の小口径標準レンズは
だいたい150本(LP)/mmという値が出てくる(注:これは絞り
の設定値にも依存し、かつ画面中央部等の最良の場合の値である。
またこれは標準的な性能のレンズの場合で、MF時代においても
高性能なものでは、180LP/mm位に達する場合もある)
LPとは「ラインペア」という意味であり、解像度チャート上には、
白と黒のライン(線)が描かれていて、撮影画像において、その
ペアを、どこまで見分けられるか?という計測手法である。
150LPと言えば、1mmの範囲で2倍の300本を解像(区別)できる。
これは別の言い方をすれば、1mmあたりで300本であるから
1本あたり判別の幅は、約0.0033mm=約3.3μmとなる。
この解像力が、デジタルカメラでのセンサーサイズ上での
ピクセルの幅(ピクセルピッチ)よりも小さければ問題無い訳だ。
では、ここで、いくつかの計算例を挙げてみよう。
2つの近代デジタル一眼レフで考えてみる。
*NIKON Df
フルサイズ 約36mmx24mmセンサー 約1600万画素
センサー横幅約36mm÷約5000ピクセル(最大画素数)
=約7.2μm
*PENTAX KP
APS-C機 約23.5mmx15.6mmセンサー 約2400万画素
センサー横幅約23.5mm÷約6000ピクセル(最大画素数)
=約3.9μm
すなわち、NIKON Dfのシステムでは、ピクセルピッチが約7μm
であるから、銀塩時代の古いレンズの解像力=約3μmでも、
全然余裕であり、レンズ性能の不足を感じる事が無い。
PENTAX KPは小さいAPS-Cセンサーで、かつ画素数が大きい、
この場合、ピクセルピッチはかなり小さくなり、約4μm程だ、
銀塩時代の低性能レンズと組み合わせると、ほぼ同等の解像力
となり、使用するのに、ぎりぎりの状況だ。
おまけにKPはローパスレスのカメラだ、ローパスフィルター
により細かすぎる画像(の空間周波数)を排除するという方針
では無い為、レンズの解像力は必然的に高いものが要求される。
余談だが、銀塩35mm判の画素数は当然アナログであるので不明だ、
だが、経験則や実験等で「だいたい2000万画素級である」と
言われている。この場合、1800x1200程度のピクセル数だと
仮定すると、35mm判フィルムで必要なレンズ解像力は
36mm幅÷1800=20μm →1mmあたり50本→25LP/mm
で十分という計算であり、トイレンズを除き、ほぼ全ての
銀塩写真用レンズは、この水準をクリアしている(いた)
で、もし、ピクセルピッチの方がレンズの解像力よりも小さいと
せっかくセンサー側では細かい画像に対応しようとしているのに
レンズの性能が追いついていない、という状況になってしまう。
これは現代のデジタル一眼レフとその交換レンズの場合は
あまり(ほとんど)問題にはならないが、もうこれ以上カメラ
のセンサーの画素数が上がると、そろそろヤバい状況だ。
この傾向はセンサーサイズが小さければ小さいほど顕著になる、
たとえば携帯電話搭載カメラとか、監視カメラなどでは、
センサーサイズが1/3型~1/5型(いずれも数mm角)と極めて
小さい。ここに何千万画素もの画素数を詰め込もうとすると
ピクセルピッチは、数μmとなり、それに対応する高解像力
のレンズが必要となるが、小型化された携帯や監視カメラ用の
レンズでは、とてもそこまでの解像力性能は出ない、せいぜいが
100LP/mmか、またはそれ以下であろう。
(注:近年の高級マシンビジョン用レンズでは、解像力は、
170LP/mm程度あるので、なかなか優秀だ)
つまり、小型センサーの映像機器の世界では、すでにレンズ
性能が不足している状況なのだ。
でもまあ、携帯カメラや監視カメラでは、そこまでの厳密な
性能(描写力)は要求されない。だが、写真用レンズでは困る。
そこで、例えば、近い将来の超高画素時代における必要レンズの
性能要件を考えてみよう。
*フルサイズ1億画素機=約12000x約8000ピクセル
センサー幅36mm÷12000ピクセル=ピクセルピッチ約3μm
*APS-C 4000万画素機=約8000x約5000ピクセル
センサー幅24mm÷ 8000ピクセル=ピクセルピッチ約3μm
いずれも、3μm程度のピクセルピッチが必要となった、
まあ、センサー製造上での技術は等しく進化していくから、
センサーサイズに係わらず、ピクセルピッチは同じとなる事で
あろう。
(注:小型センサー、すなわちμ4/3機用センサーや、産業・
監視カメラ用センサー、携帯系撮像センサー等では、製造の
プロセスが異なるのか? 上記のような一眼レフ用センサー
よりも、ずっと小さいピクセルピッチとなっている)
で、これはつまり1mm÷3μm=333であるから、330本の
ライン、すなわち「170本程度のLP値の性能を持つレンズで
あれば高画素化にも耐えられる」という事である。
しかし「あれ?」と思わないであろうか? 銀塩時代の
高性能レンズであれば、170LP/mm程度の高性能のものは
中にはある、そういうレンズは、フルサイズ1億画素や
APS-Cの4000万画素機でも使える、という事になるのだ。
(注:画面中央部など、最良の場合に限った話である)
だが、そういう超高性能な銀塩用レンズの存在は稀だと思う、
そして、今回紹介しているような銀塩時代の完成度の高い
変形ダブルガウス型標準レンズでは、わずかにこのレベルには
届かないかも知れない。
であれば、超高画素用の新たな標準レンズの開発が必須になる、
それが、2010年代において各社から登場している新時代の
標準レンズだ。
それらの新鋭レンズの解像力性能だが、きちんと自身で測った
訳では無いのだが、恐らくは最良で250LP/mm程度であろう。
そうであれば、1mm÷(250x2)=2μmの解像力があるから、
現状の高画素機のレベル(3~4μm)よりもだいぶ余裕がある。
計算上では、さらに画素数が上がって、フルサイズで2億画素
(1万8000x1万2000ピクセル)となってもまだ耐えられる訳だ。
長々と計算をしてきたが、ともかくこのあたりが、現代の標準
レンズがより高性能(高解像力)が求められる理由である。
(注:ここまでの計算手法は、あくまで概念的なものである。
実際のセンサーでは、原色/補色カラーフィルターの存在に
より全画素を均一に扱えない(色が飛び飛びである)事、
ローパスフィルターの存在、さらにはピクセル開口率の
差異、それから像面位相差AF等まであって、極めて複雑だ。
場合により計算困難(不能)であるかもしれず、たとえ光学
の専門家層であっても、統一見解が無いと思われる)
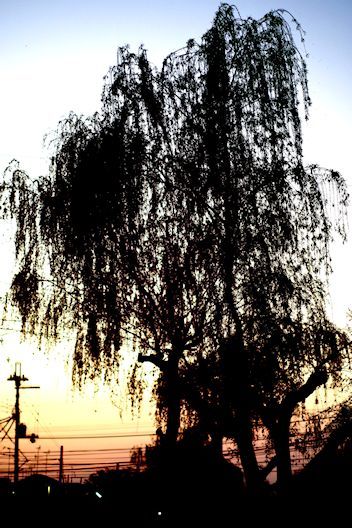
高解像度の写真イコール良い写真、と言う図式が常に成り立つ
訳では無い。解像度は写真における映像再現性としては確かに
重要な要素だが、それは作品における表現性とイコールでは無い。
だから、新鋭の高価な標準レンズを使ったところで「良い写真」
が撮れるという保証も無い。そもそも、「良い写真とは綺麗に
写っている写真」という公式が成り立つ訳では無い。
今から50年から60年も昔の銀塩の1960年代であれば、カメラや
フィルムやレンズの性能や、撮り手の技能もまだ未成熟であり
綺麗に写真を撮れる事自体が「良い写真」の条件であったのだが、
既に、そこから半世紀以上が過ぎている。
今や、デジタル一眼レフやミラーレス機はもとより、コンパクト
機や携帯系カメラでも、誰でもシャッターを押すだけで綺麗な
写真を撮る事が出来る時代だ。
今の時代にまでなってなお「より綺麗に写っている写真」だけを
追い求めているとすれば、それは感覚の方向性が間違っている
という事になってしまう。普通に綺麗に写るのは当たり前、
そこから他の写真には無い何か(=表現)を加えていかない限り
写真の意味が無い。
ただ単に、珍しい被写体を探して綺麗に撮っただけでは、
「ふ~ん、だから何? それで何が言いたいの?」のように
撮り手の存在感が極めて希薄な写真にしかならない訳だ。
「その撮影者は何が言いたいのか?」 それが写真の表現に
直結する。

繰り返し述べてきた通り、このクラスの小口径標準レンズの性能は
どれをとってもほぼ同じだ、個々の細かい差異を重箱の隅をつつく
ように洗い出したとしても、もはやそれは枝葉末節に過ぎないし
細かい欠点を一々あげる必要も無いくらい、どれも長い歴史を持つ
完成度の高い優秀なレンズばかりである。
欲しければ、予算や志向や機材環境に応じ、自分が好きな小口径
標準レンズを買えば良い、だたそれだけの話である。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Bブロック「AF50mm/f1.8」の記事は終了だ、
次回の本シリーズ記事は、
予選Cブロック「AF50mm/f1.4 Part1」となる予定だ。