本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に
紹介している。
今回の記事では、ミラーレス機であるPENTAX Qシリーズ
(2011年~2014年に展開、現在では生産完了)用の
PENTAX純正「トイレンズ」の全4本を紹介する。
なお、これら全体はPENTAXでは「トイレンズ」とは呼ばずに
「ユニークレンズ」と呼ばれているが、個々のレンズには
「TOY LENS」という表記もある、ややこしいが、本記事では
PENTAXでの呼称の「ユニークレンズ」に従う。
----
では、まず最初のシステム
![_c0032138_13452364.jpg]()
(中古購入価格 5,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
対角線魚眼風MFトイレンズ。ピントリングは存在している。
なお、今回の記事でのPENTAX Q用のレンズを使用できる
母艦はPENTAX Q,Q10,Q7,Q-S1の4機種しか存在しない。
私は、これらのカメラ機種の全てを所有している訳では
なく、QとQ7の2機種のみである。
よって、今回の記事では、4種類のレンズの母艦として
QとQ7を交互に使用する事にするが、若干だがレンズの
仕様や描写特性と、使用する母艦の相性は考慮している。
![_c0032138_13452317.jpg]()
写りが得られるユニークレンズである。
Q7装着時の画角は、フルサイズ換算16.5mm相当であるが、
実は魚眼レンズにおいては、レンズ焦点距離はあまり重要
では無く「何度の対角画角が得られるか?」がポイントだ。
これが180度であれば、まともな対角線魚眼レンズとなり、
160~170度くらいの場合は「(対角線)魚眼風レンズ」
と呼ばれる事もある。
本 03 FISH-EYEの画角だが、Q7装着時には、173度となり
まあ、「ほとんど魚眼レンズである」と言えるであろう。
最短撮影距離は、約9cmと、スペック上では短いが、
実のところ、これらの「ユニークレンズ」は、どれも
Q7での使用時、ほとんどピントを合わせる事が出来ない。
1つはシステムの性能であり、Q7の背面モニターは解像度が
低く、ピーキング機能はあるが精度が低い、よって
ピントが合っているかどうかが不明であり、おまけに、
レンズ側のピントリングを、近距離側、遠距離側にそれぞれ
いっぱいに廻しても、そこで最短や無限遠の距離にピントが
合う訳では無いのだ。
これは故障では無いのだが、その原因は理解しがたく、
まともな仕様であるとは思えない。
一説によると、「元々、これらユニークレンズはQ/Q10の
1/2.3型センサーのイメージサークルを基本に設計されたが
Q7から、センサーが1/1.7型に心持ち大型化された際、
イメージサークルが足りないので、まず1/2.3型対応で
撮影し、その後、画像処理的に1/1.7型にまで広げる」
との事である。
そうだとしたら、この画像処理は方法論(アルゴリズム)
的に複雑であり、「この処理プログラムにバグがあって、
ピントが合ったり合わなかったりするのか?」とも思ったが
画像拡大とピントは直接は関係が無いので、これそのものが
原因では無いであろう。
Q7単体を使っているだけでは、これの原因も対処法も
わからずに、後年にPENTAX Qを買い足したのだが、それも
また同様にピントが良くわからない(汗)
結局、何をやってもピントが合わないし、これは
これらの「ユニークレンズ」を使った場合のみの問題で、
純正高画質レンズとか、マシンビジョン用レンズを使った
際には、こうしたピントの問題は、殆ど起こり難いので
やはり原因不明だし、どうせトイレンズであるから、あまり
そのあたりの厳密性を求めても、しかたないかも知れない。
ただ、問題は他にもあり、Q7の場合、撮影直後にモニターに
映る自動再生画像が、所定の解像度が出ておらず、ボケて
表示されてしまう。
この問題は、PENTAX Q7(2013年)のみならず、同時代の
他のPENTAX機(例:K-01 2012年)や、他社のFUJIFILM
X-E1(2012年)等でも起こる為、この時代に各社共通で
使用されたモニター再生系部品の不良またはソフト的な
バグであると思われる。
この為、撮った写真がピントが合っていたか否かが
極めて判断しにくい状況だ。
本件のみならず、この時代(2011~2013年)には、機種間や
各社間で共通の不具合が、私が見つけた範囲だけでも
4件もあり、2011年の東日本大震災の影響で、部品調達が滞り、
低品質な代替部品や、代替外注先等を使ったのが、原因では
なかろうか?と推察している。(これを「持病」と呼んでいる)
結局、この時代のカメラを中古購入する際は慎重に「目利き」
を行う必要があるが、例えば「絞り制御ユニットの故障」
(PENTAX機で撮った写真が真っ黒に写る。ライブビューに
すると起こらず、連写すると一時的に復帰したりもする。
一部の初級マニア層では「黒死病」と呼ばれる状態だ)
などは、ある日突然に起こるので事前にわかりようも無い。
![_c0032138_13452345.jpg]()
魚眼レンズであるが故に、構図調整がかなり難しいレンズ
となっている。
いつも魚眼レンズの記事で書く事だが、「画面の中央から
周囲に放射線上に伸びる直線上に乗っている被写体は
曲がって写る事は無い」という点である。
具体例として、上写真の「ほこら」は、画面中央の縦横の
ラインはまっすぐであるが、画面周辺での、放射直線上に
乗らない部分は曲がって写る、という感じだ。
この特性に注目し、構図内のどの部分の直線性を維持し、
どの部分を曲げるか?で、写真の雰囲気や意図が大きく
変わるのであるが、ここがかなり難しい。
というのも、カメラを(例えば三脚を立てて)ただ水平に
すれば良いという訳ではなく、カメラの高さ(レベル)や
被写体に平行して正対できるかどうかや、アングル(角度)
をどうするか、など、三次元的に、少なくとも5つの軸
(シフトx2、ロール、ピッチ、ヨー)から、6軸(+距離)
での、カメラ位置の調整が、こうした技法では必須となる。
この技法は、常に三脚を立てて1軸の水平だけを調整して
撮っている習慣があると、永久に習得できない内容である為、
例えば「三脚族」から脱却したい初級層やシニア層がいると
すれば、まず、いずれかの対角線魚眼レンズを使って、
構図内で自分が狙った任意の部分を直線で撮れる練習を行う
事が極めて有効だ。
ただ、これは恐ろしく難しい。三次元的に少しでもカメラが
傾いてると(例えば、カメラは水平だが、被写体に対して
カメラの右側が少し前に出ている等だけでも)魚眼構図内の
直線性は維持できなくなる。
実際にやってみると、あまりの難しさに初級層ではメゲて
しまうかも知れないが、これはまあ「練習」であるし、
三脚を立てて「三分割」や「S字」といった、あまり意味の
無い構図練習をするよりも、百倍も役に立つ事は間違いない。
![_c0032138_13452367.jpg]()
良くある。これは慣れていても起こりうる事で、カメラの
位置調整や撮影設定変更を頻繁に行うと、カメラの持ち替えが
多々発生し、しかもQシステムは超小型カメラ故に、指の
置き場が無い。結局、思わず画面の隅に指が映りこんでしまう
のだが、明所で見え難い背面モニター上で、(変更した)構図
やら画像の設定に注目していると、僅かに指が写り込んでいる
事を見落としてしまう場合もある訳だ。
「ビギナーが起こし易い凡ミス」という風には考えずに
中上級者の場合も、十分に注意する必要があるだろう。
----
では、次のシステム
![_c0032138_13453198.jpg]()
(中古購入価格 3,000円)
カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)
その名の通り、望遠画角のMFトイレンズである。
センサーサイズが1/2.3型と小さいPENTAX Qに装着時の
画角は、約100mm相当となる。
![_c0032138_13453190.jpg]()
いない為、本レンズではこれ以上の望遠画角を得る事が
できない。それが必要であれば、トリミング編集を行う事
になるが、PC等で編集する他、PENTAX Qシリーズでは
カメラ本体内でも、画像再生時にトリミング編集を行う
事が可能だ。
なお、本レンズ05 TELEの最短撮影距離は、27cmとやや
長めである為、マクロレンズの代用には、ちょっと厳しい。
また、仮に寄れたとしても、前述の「ピント不明」の
問題があるので、結局、近接撮影は困難だ。
あと、そもそもPENTAX Q用純正レンズには、マクロレンズ
は存在していない。
近接撮影を行いたい場合は「マシンビジョンレンズ」
(本シリーズ第1回記事)の中で、近接に強いレンズを
選んで使う必要があるのだが、この用法は、マニアというか
それを超えた専門家向けのレベルの知識と技術が必要となり、
一般的な手法とは言えないであろう。
という事で、今回は一般被写体を選んだ撮影となるが、
例によって、ピントが良くわからない。
まあ、幸いPENTAX Q(2011年)は、Q7(2013年)と比べて、
撮影後の自動再生画像がボケて見える事が無い。
(この件は、東日本大震災=2011年、以前の調達部品である
と推察している、震災後の代替部品に問題があったのだろう)
・・なので、ピント確認は、PENTAX Qの方が安心して使用
できるのであるが、撮影前にピントが良く分からない点は
QもQ7も同様だ。
![_c0032138_13453145.jpg]()
「ユニークレンズ」を使用する際の、最大の課題ではあるが、
これの対処方として、近年では「手動ピントブラケット」を
行うようにしている。これはピントを少しづつずらして
複数枚の写真を撮り、後でPC上などで見て、ピントが合って
いる写真を選択する事だ。
なお、ピントが合っている写真を選ぶのみならず、あえて
多少ピンボケになっている写真の方が、トイレンズによる
Lo-Fi描写を狙う上では良い場合もある。
他の記事でも良く書く事で、以下がある
「トイレンズ描写は、アンコントーラブル(制御できない)
である事が、突然変異的に思いもよらない写真が撮れて良い」
という件だが、現代のデジタルカメラで、それを正しく使って
しまうと、トイレンズでありながら、ある程度まともな写真が
撮れてしまい、コントローラブルで、トイレンズらしくない。
という問題点に対応する為、「技法的にギリギリで破綻するか
しないかの限界点で撮影し、偶然性を狙う」という高度な
アンコントローラブル技法がありうる。と良く記事で書いている。
それは色々とあるが、今回紹介の「手動ピントブラケット」も
その技法の中の1つである。つまり、意図的に、ちょっとだけ
ピントが甘い描写の写真を選ぶ事が出来る訳だ。
なお、この技法においては、「連写中にピントリングを微妙に
廻す」のが簡便であろう、Qシステムで、ユニークレンズを
装着した場合は「電子シャッター」となり、モニターは映像が
表示されっぱなしなので、どのタイミングで写真が撮れて
いるかは不明だが、ここは大きな問題では無い。
(注:正確には、電子シャッターでの連写時は撮影1枚目のみ
ブラックアウトするが、2枚目以降は映像が出っ放し。
レンズシャッター使用時は高速連写時は完全ブラックアウトで
低速連写時は逆に映像が出っ放し)
![_c0032138_13453087.jpg]()
が発生する為、小さい手ブレや被写体ブレでも、撮影画像が
歪んで写る場合があるが、それすらも、トイレンズ撮影では
有益な「アンコントローラブル技法」の一環だ。
(これを起こりやすくする為、あえてシャッター速度を
低めに調整するという、さらに高度な技法も存在する)
「Lo-Fiでのアンコントローラブル技法」は、旧来の写真の
常識とは全く対極な位置づけなので、Hi-Fi志向の初級中級層
には、まず、概念とか、必要性の理解も困難だとは思うが、
これらはHi-Fi撮影技法よりも遥かに高度な内容であるので、
技術的または表現的な奥深さへの探求には繋がる事であろう。
初級中級層において、この概念の理解と、練習の実施は必ず
役に立つ。この困難な練習を続ければ、それが、Hi-Fi技法
にも、きっとフィードバックできるだろうからだ。
----
では、次のシステム
![_c0032138_13453952.jpg]()
(中古購入価格 4,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
こちらは広角タイプのユニークレンズである。
勿論MF、Q7装着時の画角は約29mm相当だ。
これら「ユニークレンズ」の価格だが、定価そのものは
どれも数千円程度と、さほど高価では無い。
が、私の購入時期は多少早めであったので、中古であっても
若干割高であった。
PENTAX Qシステムは新機種の発売こそ無いが、2020年現在、
依然、レンズは現行製品であって、発売後時間が経った現在に
おいてはユニークレンズは新品でも3000円台程度と価格が
こなれている。(注:03 FISH-EYEのみ、やや高価)
![_c0032138_13453971.jpg]()
単純に言えば、1/2.3型である PENTAX Q/Q10には望遠系の
レンズ(05,07)が適し、1/1.7型であるPENTAX Q7/Q-S1には
広角系のレンズ(03.04)が適している。
(注:07は収差を強調した特殊な描写なので、必ずしも
Q/Q10が良いとは限らないが・・ ここは後述する)
同様に純正の06望遠ズームは、1/2.3型機種が適し、
08広角ズームは1/1.7型機種が適していると思われるが、
これらは未所有であり、特に08広角ズームは、Qシステムの
中では飛びぬけて高価な為、あまり所有者は居ないであろう。
また、純正の、01標準、または02標準ズームは、どちらの
機種系列でも良い、という感じだと思う。
なお、Qシステムに、一眼レフ用の交換レンズをアダプターで
装着する利用法は、私は行っていない。その理由は2つあり、
例えば50mm標準レンズであっても、200mmを超える換算画角と
なって、望遠母艦としても、やや過剰である事。加えて
MF性能が貧弱なQシステムでは、MFレンズ装着時のピント精度
が期待できないからである。
もし「望遠母艦」としての用途が必要であれば、Qシステムでは
無く、デジタル拡大機能を備えたμ4/3機の方が有利であろう。
例えば、PANASONIC DMC-GX7等に200mmレンズを装着すれば、
容易に400mm~3200mmの範囲の超望遠画角を手ブレ補正付きで
得る事ができ、常時ピーキングでMFピント合わせも簡便である。
ただし、1000mm程度を超える超々望遠域の手持ち撮影では、
手ブレ補正は、まともに動作せず、そもそもファインダー内に
被写体を捉える事自体が困難であり、限度はある。
そして、Qシステムでは、アダプター使用時は電子シャッター
となる為、少しの手ブレでも「ローリングシャッター歪み」
が発生してしまう。(注:それを逆用する高度な技法はある)
それから、QシステムにCCTV・マシンビジョン用のレンズを
装着する場合は、焦点距離よりも対応センサーサイズの仕様
の方がより重要になる。(本シリーズ第1回、マシンビジョン
レンズ特集記事参照)
具体的には、
Q/Q10 1/2.3型で利用可能なCCTVレンズ
1型(以上)、2/3型、1/1.8型、1/2型対応。
Q7.Q-S1 1/1.7型で利用可能なCCTVレンズ
1型(以上)、2/3型、および1/1.8型対応の一部のレンズ。
いずれの場合でも、これより小さいイメージサークル
(例:1/3型、1/4型対応)のCCTVレンズは、画面周辺が
ケラれてしまう(まあ、そういう使い方も無い訳ではないが)
なお、前述のμ4/3機の場合は、2倍テレコンを常時掛けると、
4/3型÷2=2/3型となって、2/3型以上のCCTV用レンズを
ケラれずに使用可能となるのだが、常時2倍テレコンモードだと
機能制限が出る事もある(例:パナ機での画面拡大表示不可)
ので、良し悪しあるだろう。
いずれにしても、このあたりのCCTV系は原理が専門的で高度な
為に、マニア層であっても、あまり推奨できる使用法では無い。
![_c0032138_13453940.jpg]()
6.3mmの焦点距離は、1/2.3型機で約35mm
1/1.7型機で約29mmと、広角画角となる。
トイレンズで、この画角、というと、HOLGAの元祖120系が
およそ32mm(ただし1対1画面)なので、ほぼ同様な感じだ。
そこで、一計を案じ、Q7の記録アスペクト比をHOLGAと同じ
1;1とし、さらにQ7のエフェクト(デジタルフィルター)を
「トイカメラ」モードとすれば、HOLGAと同じような周辺光量
落ちが得られるのでは? と思って試してみたのだが・・
残念ながら、1対1アスペクトでは、周辺減光処理の領域が
カットされてしまい、HOLGAっぽい描写は得られなかった。
まあ、そういう効果が欲しい場合は、PCによるレタッチ編集
等で対応するか、あるいはもう、HOLGA LENS(HL-PQ 10mm/f8)
そのものを装着するか、となる。
すなわち、本PENTAX 04 WIDEでは、周辺減光の効果を持って
いない為、トイレンズっぽく使いたい上では、その効果が
得られない事が不満事項な訳だ。
ちなみに、毎回この手の記事で書いている事だが、周辺減光
(周辺光量落ち)を、「トンネル効果」と記載する事は、
あってはならない事だ。
その理由は、過去に同じ名称の、物理学(電子工学)上の、
著名かつ偉大な発明(ノーベル賞受賞、江崎玲於奈博士)
が、あった為であり、そちらが「元祖」だからである。
1970年代の、この科学史に残る偉大な功績を知らないで、
周辺減光を安易に「トンネル効果」と呼ぶ事は、科学分野に
まるで造詣が深く無いように思われ、非常に格好が悪い。
また、技術用語として「ヴィネット、ビグネット、口径食、
シェーディング」といった用語群が使われる場合もあるが、
それらの専門技術用語は「周辺減光」のみを表す訳ではなく、
他の現象を表す意味でも用いられる為、これらの専門用語の
使用も、曖昧になる為に非推奨である。
結局、シンプルに「周辺減光」あるいは「周辺光量落ち」と
記載する事が望ましい。(匠の用語辞典 第5回記事参照)
![_c0032138_13453985.jpg]()
「TOY LENS」と記載されている割には、Lo-Fi感に欠け、
そこそこ普通に写ってしまうことが課題だ。
まあでも、本04 WIDEに関しては「歪曲収差」が大きい事で、
かろうじてトイレンズらしさが出ているとは思う。
まあ、かつてカメラメーカーが純正でトイレンズを発売した
事は、殆ど無い(実質皆無)であるので、その状況で、どこまで
「写りの悪いレンズ」を出したら市場に受け入れられるかどうか
は、PENTAXとしても、わからなかったのだろうと想像できる。
つまり、トイレンズの本質(本シリーズ記事第3回HOLGA LENS
や、匠の用語辞典第5回「ローファイ」の項目を参照)とかが、
何もわかっていないユーザー層が、こうした「ユニークレンズ」
を買って「なんじゃこりゃ~! 不良品か? 返金しろ!」
等と、クレームが来たら、かなわないからだろう。
それに、売る側でも「これは酷い写りのレンズです」と説明を
行うのは簡単では無い、いったいそれをどう、お客さんに納得
してもらうのか?
結局、殆どのユーザー層や流通では、カメラやレンズはちゃんと
写るものだという固定観念がある、それを覆す事は容易では無い。
でも、トイレンズの必要性は、「恐ろしく写りが悪い」(Lo-Fi)
な事であり、そこそこちゃんと写るレンズは購入目的には
合わない。まあ、そこの矛盾は、市場におけるユーザー層の、
又は流通等の販売側の「未成熟」が最大の課題なのであろう。
次回、PENTAX、あるいは他のカメラメーカーで、こうした
トイレンズを発売するには、思いっきりLo-Fi描写の設計思想で
ある事を期待する、「これは、そういう類の物だ」というのは
販売時にちゃんと説明し、それが理解できるユーザーにのみ
販売すれば良いと思う。
(過去、こうした説明販売は、例えば銀塩時代でのミノルタで
α-9用のMⅡ型特殊スクリーンを購入する際、サービスセンター
にまで出向き、「これを装着すると、ピントの山が見えやすく
なりますが、開放F2.8より暗いレンズでは、暗すぎてむしろ
わかり難くなります、それでも交換しますか?」という注意事項
を聞いて、同意しないと購入できない、という前例があった。
まあ、一部の効能の強い薬を買う際、薬剤師の説明を受けないと
買えないような状態と同じであろう)
----
では、今回ラストのシステム
![_c0032138_13454687.jpg]()
(中古購入価格 4,000円)
カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)
固定焦点型(ピントリング無し)の標準画角特殊トイレンズ。
さて、前述の04 WIDEと05 TELEでは「Lo-Fi感が足りない」
という課題があったのだが、この07は若干後から発売された
ユニークレンズであり、ある意味、市場の認知度からは、
「限界ぎりぎりまで低画質を求めた」、とても意欲的な
レンズであると思う。
![_c0032138_13454641.jpg]()
もっとも、1群1枚や1群2枚という単純構成でも、非球面や
非球面メニスカス等の、複雑で現代的な設計製造を行えば、
そこそこ写真をHi-Fiに撮る事は可能であり、その代表例
としては、「写ルンです」等の「レンズ付きフィルム」が
存在する。
しかし、本レンズ07に関しては、そういう小細工を行って
おらず、普通の単玉レンズだ。
これを簡単に言えば、「虫眼鏡で中距離を見た」ような
描写が得られる。実際にそれをやってみれは理解は容易
だと思うが、画面周辺が流れるような独特の映像が見える。
この効果は、遠距離の風景などを平面的に見た場合には
若干得られ難い為、本07レンズを使用する際は、中距離
(およそ1~5m)で、画面中央部に主要被写体を置き、
画面周囲を流してしまうのが基本的な使用法だ。
ただし、あえてその基本を崩して、主要被写体を画面周辺
に置くと、それが流れているような独特の描写となる。
また、この効果は、センサーサイズが1/1.7型機のQ7と
Q-S1の方が、画角が広くて得られやすいのだが、あえて
画角の狭いQ/Q10で、控え目に使用する手法もある。
(注:Q7等では、内部画像拡大処理が入っているので、
そのように単純な話では無いが、あくまで概要の話だ)
さらに、とても贅沢な使用法だが、このトイレンズを使う
為に、異なるセンサーサイズの2系列のQ母艦を持ち出すとかも
有り得る。又は、Q7で撮って、周辺流れの効果の量を調整する
目的でトリミングを行う、という手法も勿論ありだろう。
![_c0032138_13454622.jpg]()
エフェクト(デジタルフィルター)と組み合わせる事で、
事前に想像できない「アンコントローラブル」な要素を
得る事ができる。
しかし、闇雲に撮っているだけでは無理であり、ちゃんと
このレンズの特性を理解しつつ使うのが望ましい。
感覚的にわかりやすい例を挙げれば、このレンズを使う場合、
「野球で言うところの、ストライクゾーンがある」と
思えば良い。
野球のストライクゾーンは、「バッターの肩の上部と
ズボンの上部との中間点に引いたラインを上限とし、
膝下部のラインを下限とするホームベース上の空間」といった
難しい定義があるが、まあ、「直方体の三次元空間」である、
という事は、野球観戦者の誰でもが知っているであろう。
(参考:近年の米国の野球中継では、ストライクゾーンが
画面にCG合成されて放映されている)
本レンズを使う場合、目の前の空間上に、「像が流れ難い
三次元空間」を頭の中でイメージする。これの厳密な定義は
難しいが、だいたいだが、各辺が、2~3mくらいの直方体や
立方体を思い浮かべればよい。
そして、主要被写体を、その仮想の「ストライクゾーン」の
中に収めるように、構図、撮影距離、アングルやレベルを
整えて撮れば、本レンズの特徴を活かした撮り方が出来る。
ここも勿論、トイレンズであるから、それをわかった上で、
あえて「ストライクゾーン」から外して撮るのも有りだ。
(「ボール」となる「遊び玉」を投げるというイメージだ)
そう簡単な話(技法)では無いとも言えるが、まあ全般に
トイレンズを使う上では、むしろ通常のHi-Fi写真撮影技法
よりも、はるかに高度なスキルが要求される訳だ。
まあ、銀塩末期の「トイカメラ」のブームの際は、写真の原理
を知らないビギナー層が、それを使って、偶然に面白い写真が
撮れる事が主流であったのかも知れないが、現代のデジタル時代
では撮ってすぐに画像が見れる、だから、撮り手がうまくその
「破綻」の具合をコントロールしないかぎり、トイレンズ等は
上手く使いこなせない、という訳だ。
これはビギナー層では困難であり、上級者向けの技法や内容では
あるが、逆に言えば、上級者であれば、こうしたトイレンズの
特性を、より引き出す事が出来る、「奥の深い撮影分野である」
という事にもなる。
![_c0032138_13454545.jpg]()
「玩具だ」とか「ビギナー用だ」「邪道だ」等とは思わず、
掘り下げて使ってみるのも、十分に意味がある事だと思う。
(上手くすれば、それまで、数十万円もするような高価な
「Hi-Fi機材」にしか目が行っていなかった状態から脱却し、
見識や価値観の幅を広める意味でも有意義に働くかも知れない。
加えて、光学原理や撮影技法、レンズの収差、長所短所等に
関する知識や理解、判断力の増強にも役に立つと思う)
それと、「ユニークレンズ」は、本記事で紹介した4本のみしか
発売されていない。今後の新製品の発売は期待が出来ない状態
ではあるが、また将来的に、PENTAXや他のカメラメーカーからも
こうしたコンセプトの商品が出てくる事を期待しよう。
なお、PENTAX以外の国内外製トイレンズについては、本シリーズ
記事や他のレンズ系記事でも、適宜紹介済み、あるいはまた別途
紹介予定である。それらは、ユニークレンズほど「控え目」な
特性ではなく、「思いっきりLo-Fiである」事も普通だ。
----
さて、今回の記事「PENTAX ユニークレンズ特集」は、
このあたり迄で、次回記事に続く・・
紹介している。
今回の記事では、ミラーレス機であるPENTAX Qシリーズ
(2011年~2014年に展開、現在では生産完了)用の
PENTAX純正「トイレンズ」の全4本を紹介する。
なお、これら全体はPENTAXでは「トイレンズ」とは呼ばずに
「ユニークレンズ」と呼ばれているが、個々のレンズには
「TOY LENS」という表記もある、ややこしいが、本記事では
PENTAXでの呼称の「ユニークレンズ」に従う。
----
では、まず最初のシステム

(中古購入価格 5,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
対角線魚眼風MFトイレンズ。ピントリングは存在している。
なお、今回の記事でのPENTAX Q用のレンズを使用できる
母艦はPENTAX Q,Q10,Q7,Q-S1の4機種しか存在しない。
私は、これらのカメラ機種の全てを所有している訳では
なく、QとQ7の2機種のみである。
よって、今回の記事では、4種類のレンズの母艦として
QとQ7を交互に使用する事にするが、若干だがレンズの
仕様や描写特性と、使用する母艦の相性は考慮している。

写りが得られるユニークレンズである。
Q7装着時の画角は、フルサイズ換算16.5mm相当であるが、
実は魚眼レンズにおいては、レンズ焦点距離はあまり重要
では無く「何度の対角画角が得られるか?」がポイントだ。
これが180度であれば、まともな対角線魚眼レンズとなり、
160~170度くらいの場合は「(対角線)魚眼風レンズ」
と呼ばれる事もある。
本 03 FISH-EYEの画角だが、Q7装着時には、173度となり
まあ、「ほとんど魚眼レンズである」と言えるであろう。
最短撮影距離は、約9cmと、スペック上では短いが、
実のところ、これらの「ユニークレンズ」は、どれも
Q7での使用時、ほとんどピントを合わせる事が出来ない。
1つはシステムの性能であり、Q7の背面モニターは解像度が
低く、ピーキング機能はあるが精度が低い、よって
ピントが合っているかどうかが不明であり、おまけに、
レンズ側のピントリングを、近距離側、遠距離側にそれぞれ
いっぱいに廻しても、そこで最短や無限遠の距離にピントが
合う訳では無いのだ。
これは故障では無いのだが、その原因は理解しがたく、
まともな仕様であるとは思えない。
一説によると、「元々、これらユニークレンズはQ/Q10の
1/2.3型センサーのイメージサークルを基本に設計されたが
Q7から、センサーが1/1.7型に心持ち大型化された際、
イメージサークルが足りないので、まず1/2.3型対応で
撮影し、その後、画像処理的に1/1.7型にまで広げる」
との事である。
そうだとしたら、この画像処理は方法論(アルゴリズム)
的に複雑であり、「この処理プログラムにバグがあって、
ピントが合ったり合わなかったりするのか?」とも思ったが
画像拡大とピントは直接は関係が無いので、これそのものが
原因では無いであろう。
Q7単体を使っているだけでは、これの原因も対処法も
わからずに、後年にPENTAX Qを買い足したのだが、それも
また同様にピントが良くわからない(汗)
結局、何をやってもピントが合わないし、これは
これらの「ユニークレンズ」を使った場合のみの問題で、
純正高画質レンズとか、マシンビジョン用レンズを使った
際には、こうしたピントの問題は、殆ど起こり難いので
やはり原因不明だし、どうせトイレンズであるから、あまり
そのあたりの厳密性を求めても、しかたないかも知れない。
ただ、問題は他にもあり、Q7の場合、撮影直後にモニターに
映る自動再生画像が、所定の解像度が出ておらず、ボケて
表示されてしまう。
この問題は、PENTAX Q7(2013年)のみならず、同時代の
他のPENTAX機(例:K-01 2012年)や、他社のFUJIFILM
X-E1(2012年)等でも起こる為、この時代に各社共通で
使用されたモニター再生系部品の不良またはソフト的な
バグであると思われる。
この為、撮った写真がピントが合っていたか否かが
極めて判断しにくい状況だ。
本件のみならず、この時代(2011~2013年)には、機種間や
各社間で共通の不具合が、私が見つけた範囲だけでも
4件もあり、2011年の東日本大震災の影響で、部品調達が滞り、
低品質な代替部品や、代替外注先等を使ったのが、原因では
なかろうか?と推察している。(これを「持病」と呼んでいる)
結局、この時代のカメラを中古購入する際は慎重に「目利き」
を行う必要があるが、例えば「絞り制御ユニットの故障」
(PENTAX機で撮った写真が真っ黒に写る。ライブビューに
すると起こらず、連写すると一時的に復帰したりもする。
一部の初級マニア層では「黒死病」と呼ばれる状態だ)
などは、ある日突然に起こるので事前にわかりようも無い。

魚眼レンズであるが故に、構図調整がかなり難しいレンズ
となっている。
いつも魚眼レンズの記事で書く事だが、「画面の中央から
周囲に放射線上に伸びる直線上に乗っている被写体は
曲がって写る事は無い」という点である。
具体例として、上写真の「ほこら」は、画面中央の縦横の
ラインはまっすぐであるが、画面周辺での、放射直線上に
乗らない部分は曲がって写る、という感じだ。
この特性に注目し、構図内のどの部分の直線性を維持し、
どの部分を曲げるか?で、写真の雰囲気や意図が大きく
変わるのであるが、ここがかなり難しい。
というのも、カメラを(例えば三脚を立てて)ただ水平に
すれば良いという訳ではなく、カメラの高さ(レベル)や
被写体に平行して正対できるかどうかや、アングル(角度)
をどうするか、など、三次元的に、少なくとも5つの軸
(シフトx2、ロール、ピッチ、ヨー)から、6軸(+距離)
での、カメラ位置の調整が、こうした技法では必須となる。
この技法は、常に三脚を立てて1軸の水平だけを調整して
撮っている習慣があると、永久に習得できない内容である為、
例えば「三脚族」から脱却したい初級層やシニア層がいると
すれば、まず、いずれかの対角線魚眼レンズを使って、
構図内で自分が狙った任意の部分を直線で撮れる練習を行う
事が極めて有効だ。
ただ、これは恐ろしく難しい。三次元的に少しでもカメラが
傾いてると(例えば、カメラは水平だが、被写体に対して
カメラの右側が少し前に出ている等だけでも)魚眼構図内の
直線性は維持できなくなる。
実際にやってみると、あまりの難しさに初級層ではメゲて
しまうかも知れないが、これはまあ「練習」であるし、
三脚を立てて「三分割」や「S字」といった、あまり意味の
無い構図練習をするよりも、百倍も役に立つ事は間違いない。

良くある。これは慣れていても起こりうる事で、カメラの
位置調整や撮影設定変更を頻繁に行うと、カメラの持ち替えが
多々発生し、しかもQシステムは超小型カメラ故に、指の
置き場が無い。結局、思わず画面の隅に指が映りこんでしまう
のだが、明所で見え難い背面モニター上で、(変更した)構図
やら画像の設定に注目していると、僅かに指が写り込んでいる
事を見落としてしまう場合もある訳だ。
「ビギナーが起こし易い凡ミス」という風には考えずに
中上級者の場合も、十分に注意する必要があるだろう。
----
では、次のシステム

(中古購入価格 3,000円)
カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)
その名の通り、望遠画角のMFトイレンズである。
センサーサイズが1/2.3型と小さいPENTAX Qに装着時の
画角は、約100mm相当となる。

いない為、本レンズではこれ以上の望遠画角を得る事が
できない。それが必要であれば、トリミング編集を行う事
になるが、PC等で編集する他、PENTAX Qシリーズでは
カメラ本体内でも、画像再生時にトリミング編集を行う
事が可能だ。
なお、本レンズ05 TELEの最短撮影距離は、27cmとやや
長めである為、マクロレンズの代用には、ちょっと厳しい。
また、仮に寄れたとしても、前述の「ピント不明」の
問題があるので、結局、近接撮影は困難だ。
あと、そもそもPENTAX Q用純正レンズには、マクロレンズ
は存在していない。
近接撮影を行いたい場合は「マシンビジョンレンズ」
(本シリーズ第1回記事)の中で、近接に強いレンズを
選んで使う必要があるのだが、この用法は、マニアというか
それを超えた専門家向けのレベルの知識と技術が必要となり、
一般的な手法とは言えないであろう。
という事で、今回は一般被写体を選んだ撮影となるが、
例によって、ピントが良くわからない。
まあ、幸いPENTAX Q(2011年)は、Q7(2013年)と比べて、
撮影後の自動再生画像がボケて見える事が無い。
(この件は、東日本大震災=2011年、以前の調達部品である
と推察している、震災後の代替部品に問題があったのだろう)
・・なので、ピント確認は、PENTAX Qの方が安心して使用
できるのであるが、撮影前にピントが良く分からない点は
QもQ7も同様だ。

「ユニークレンズ」を使用する際の、最大の課題ではあるが、
これの対処方として、近年では「手動ピントブラケット」を
行うようにしている。これはピントを少しづつずらして
複数枚の写真を撮り、後でPC上などで見て、ピントが合って
いる写真を選択する事だ。
なお、ピントが合っている写真を選ぶのみならず、あえて
多少ピンボケになっている写真の方が、トイレンズによる
Lo-Fi描写を狙う上では良い場合もある。
他の記事でも良く書く事で、以下がある
「トイレンズ描写は、アンコントーラブル(制御できない)
である事が、突然変異的に思いもよらない写真が撮れて良い」
という件だが、現代のデジタルカメラで、それを正しく使って
しまうと、トイレンズでありながら、ある程度まともな写真が
撮れてしまい、コントローラブルで、トイレンズらしくない。
という問題点に対応する為、「技法的にギリギリで破綻するか
しないかの限界点で撮影し、偶然性を狙う」という高度な
アンコントローラブル技法がありうる。と良く記事で書いている。
それは色々とあるが、今回紹介の「手動ピントブラケット」も
その技法の中の1つである。つまり、意図的に、ちょっとだけ
ピントが甘い描写の写真を選ぶ事が出来る訳だ。
なお、この技法においては、「連写中にピントリングを微妙に
廻す」のが簡便であろう、Qシステムで、ユニークレンズを
装着した場合は「電子シャッター」となり、モニターは映像が
表示されっぱなしなので、どのタイミングで写真が撮れて
いるかは不明だが、ここは大きな問題では無い。
(注:正確には、電子シャッターでの連写時は撮影1枚目のみ
ブラックアウトするが、2枚目以降は映像が出っ放し。
レンズシャッター使用時は高速連写時は完全ブラックアウトで
低速連写時は逆に映像が出っ放し)
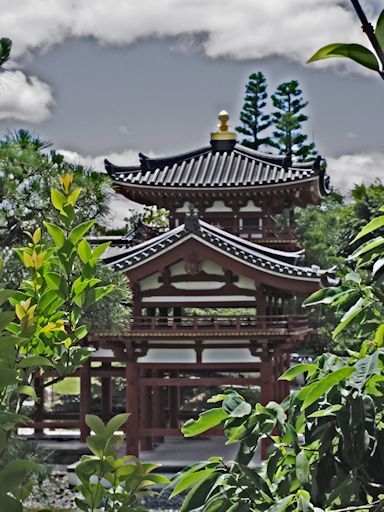
が発生する為、小さい手ブレや被写体ブレでも、撮影画像が
歪んで写る場合があるが、それすらも、トイレンズ撮影では
有益な「アンコントローラブル技法」の一環だ。
(これを起こりやすくする為、あえてシャッター速度を
低めに調整するという、さらに高度な技法も存在する)
「Lo-Fiでのアンコントローラブル技法」は、旧来の写真の
常識とは全く対極な位置づけなので、Hi-Fi志向の初級中級層
には、まず、概念とか、必要性の理解も困難だとは思うが、
これらはHi-Fi撮影技法よりも遥かに高度な内容であるので、
技術的または表現的な奥深さへの探求には繋がる事であろう。
初級中級層において、この概念の理解と、練習の実施は必ず
役に立つ。この困難な練習を続ければ、それが、Hi-Fi技法
にも、きっとフィードバックできるだろうからだ。
----
では、次のシステム

(中古購入価格 4,000円)
カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)
こちらは広角タイプのユニークレンズである。
勿論MF、Q7装着時の画角は約29mm相当だ。
これら「ユニークレンズ」の価格だが、定価そのものは
どれも数千円程度と、さほど高価では無い。
が、私の購入時期は多少早めであったので、中古であっても
若干割高であった。
PENTAX Qシステムは新機種の発売こそ無いが、2020年現在、
依然、レンズは現行製品であって、発売後時間が経った現在に
おいてはユニークレンズは新品でも3000円台程度と価格が
こなれている。(注:03 FISH-EYEのみ、やや高価)

単純に言えば、1/2.3型である PENTAX Q/Q10には望遠系の
レンズ(05,07)が適し、1/1.7型であるPENTAX Q7/Q-S1には
広角系のレンズ(03.04)が適している。
(注:07は収差を強調した特殊な描写なので、必ずしも
Q/Q10が良いとは限らないが・・ ここは後述する)
同様に純正の06望遠ズームは、1/2.3型機種が適し、
08広角ズームは1/1.7型機種が適していると思われるが、
これらは未所有であり、特に08広角ズームは、Qシステムの
中では飛びぬけて高価な為、あまり所有者は居ないであろう。
また、純正の、01標準、または02標準ズームは、どちらの
機種系列でも良い、という感じだと思う。
なお、Qシステムに、一眼レフ用の交換レンズをアダプターで
装着する利用法は、私は行っていない。その理由は2つあり、
例えば50mm標準レンズであっても、200mmを超える換算画角と
なって、望遠母艦としても、やや過剰である事。加えて
MF性能が貧弱なQシステムでは、MFレンズ装着時のピント精度
が期待できないからである。
もし「望遠母艦」としての用途が必要であれば、Qシステムでは
無く、デジタル拡大機能を備えたμ4/3機の方が有利であろう。
例えば、PANASONIC DMC-GX7等に200mmレンズを装着すれば、
容易に400mm~3200mmの範囲の超望遠画角を手ブレ補正付きで
得る事ができ、常時ピーキングでMFピント合わせも簡便である。
ただし、1000mm程度を超える超々望遠域の手持ち撮影では、
手ブレ補正は、まともに動作せず、そもそもファインダー内に
被写体を捉える事自体が困難であり、限度はある。
そして、Qシステムでは、アダプター使用時は電子シャッター
となる為、少しの手ブレでも「ローリングシャッター歪み」
が発生してしまう。(注:それを逆用する高度な技法はある)
それから、QシステムにCCTV・マシンビジョン用のレンズを
装着する場合は、焦点距離よりも対応センサーサイズの仕様
の方がより重要になる。(本シリーズ第1回、マシンビジョン
レンズ特集記事参照)
具体的には、
Q/Q10 1/2.3型で利用可能なCCTVレンズ
1型(以上)、2/3型、1/1.8型、1/2型対応。
Q7.Q-S1 1/1.7型で利用可能なCCTVレンズ
1型(以上)、2/3型、および1/1.8型対応の一部のレンズ。
いずれの場合でも、これより小さいイメージサークル
(例:1/3型、1/4型対応)のCCTVレンズは、画面周辺が
ケラれてしまう(まあ、そういう使い方も無い訳ではないが)
なお、前述のμ4/3機の場合は、2倍テレコンを常時掛けると、
4/3型÷2=2/3型となって、2/3型以上のCCTV用レンズを
ケラれずに使用可能となるのだが、常時2倍テレコンモードだと
機能制限が出る事もある(例:パナ機での画面拡大表示不可)
ので、良し悪しあるだろう。
いずれにしても、このあたりのCCTV系は原理が専門的で高度な
為に、マニア層であっても、あまり推奨できる使用法では無い。

6.3mmの焦点距離は、1/2.3型機で約35mm
1/1.7型機で約29mmと、広角画角となる。
トイレンズで、この画角、というと、HOLGAの元祖120系が
およそ32mm(ただし1対1画面)なので、ほぼ同様な感じだ。
そこで、一計を案じ、Q7の記録アスペクト比をHOLGAと同じ
1;1とし、さらにQ7のエフェクト(デジタルフィルター)を
「トイカメラ」モードとすれば、HOLGAと同じような周辺光量
落ちが得られるのでは? と思って試してみたのだが・・
残念ながら、1対1アスペクトでは、周辺減光処理の領域が
カットされてしまい、HOLGAっぽい描写は得られなかった。
まあ、そういう効果が欲しい場合は、PCによるレタッチ編集
等で対応するか、あるいはもう、HOLGA LENS(HL-PQ 10mm/f8)
そのものを装着するか、となる。
すなわち、本PENTAX 04 WIDEでは、周辺減光の効果を持って
いない為、トイレンズっぽく使いたい上では、その効果が
得られない事が不満事項な訳だ。
ちなみに、毎回この手の記事で書いている事だが、周辺減光
(周辺光量落ち)を、「トンネル効果」と記載する事は、
あってはならない事だ。
その理由は、過去に同じ名称の、物理学(電子工学)上の、
著名かつ偉大な発明(ノーベル賞受賞、江崎玲於奈博士)
が、あった為であり、そちらが「元祖」だからである。
1970年代の、この科学史に残る偉大な功績を知らないで、
周辺減光を安易に「トンネル効果」と呼ぶ事は、科学分野に
まるで造詣が深く無いように思われ、非常に格好が悪い。
また、技術用語として「ヴィネット、ビグネット、口径食、
シェーディング」といった用語群が使われる場合もあるが、
それらの専門技術用語は「周辺減光」のみを表す訳ではなく、
他の現象を表す意味でも用いられる為、これらの専門用語の
使用も、曖昧になる為に非推奨である。
結局、シンプルに「周辺減光」あるいは「周辺光量落ち」と
記載する事が望ましい。(匠の用語辞典 第5回記事参照)

「TOY LENS」と記載されている割には、Lo-Fi感に欠け、
そこそこ普通に写ってしまうことが課題だ。
まあでも、本04 WIDEに関しては「歪曲収差」が大きい事で、
かろうじてトイレンズらしさが出ているとは思う。
まあ、かつてカメラメーカーが純正でトイレンズを発売した
事は、殆ど無い(実質皆無)であるので、その状況で、どこまで
「写りの悪いレンズ」を出したら市場に受け入れられるかどうか
は、PENTAXとしても、わからなかったのだろうと想像できる。
つまり、トイレンズの本質(本シリーズ記事第3回HOLGA LENS
や、匠の用語辞典第5回「ローファイ」の項目を参照)とかが、
何もわかっていないユーザー層が、こうした「ユニークレンズ」
を買って「なんじゃこりゃ~! 不良品か? 返金しろ!」
等と、クレームが来たら、かなわないからだろう。
それに、売る側でも「これは酷い写りのレンズです」と説明を
行うのは簡単では無い、いったいそれをどう、お客さんに納得
してもらうのか?
結局、殆どのユーザー層や流通では、カメラやレンズはちゃんと
写るものだという固定観念がある、それを覆す事は容易では無い。
でも、トイレンズの必要性は、「恐ろしく写りが悪い」(Lo-Fi)
な事であり、そこそこちゃんと写るレンズは購入目的には
合わない。まあ、そこの矛盾は、市場におけるユーザー層の、
又は流通等の販売側の「未成熟」が最大の課題なのであろう。
次回、PENTAX、あるいは他のカメラメーカーで、こうした
トイレンズを発売するには、思いっきりLo-Fi描写の設計思想で
ある事を期待する、「これは、そういう類の物だ」というのは
販売時にちゃんと説明し、それが理解できるユーザーにのみ
販売すれば良いと思う。
(過去、こうした説明販売は、例えば銀塩時代でのミノルタで
α-9用のMⅡ型特殊スクリーンを購入する際、サービスセンター
にまで出向き、「これを装着すると、ピントの山が見えやすく
なりますが、開放F2.8より暗いレンズでは、暗すぎてむしろ
わかり難くなります、それでも交換しますか?」という注意事項
を聞いて、同意しないと購入できない、という前例があった。
まあ、一部の効能の強い薬を買う際、薬剤師の説明を受けないと
買えないような状態と同じであろう)
----
では、今回ラストのシステム

(中古購入価格 4,000円)
カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)
固定焦点型(ピントリング無し)の標準画角特殊トイレンズ。
さて、前述の04 WIDEと05 TELEでは「Lo-Fi感が足りない」
という課題があったのだが、この07は若干後から発売された
ユニークレンズであり、ある意味、市場の認知度からは、
「限界ぎりぎりまで低画質を求めた」、とても意欲的な
レンズであると思う。

もっとも、1群1枚や1群2枚という単純構成でも、非球面や
非球面メニスカス等の、複雑で現代的な設計製造を行えば、
そこそこ写真をHi-Fiに撮る事は可能であり、その代表例
としては、「写ルンです」等の「レンズ付きフィルム」が
存在する。
しかし、本レンズ07に関しては、そういう小細工を行って
おらず、普通の単玉レンズだ。
これを簡単に言えば、「虫眼鏡で中距離を見た」ような
描写が得られる。実際にそれをやってみれは理解は容易
だと思うが、画面周辺が流れるような独特の映像が見える。
この効果は、遠距離の風景などを平面的に見た場合には
若干得られ難い為、本07レンズを使用する際は、中距離
(およそ1~5m)で、画面中央部に主要被写体を置き、
画面周囲を流してしまうのが基本的な使用法だ。
ただし、あえてその基本を崩して、主要被写体を画面周辺
に置くと、それが流れているような独特の描写となる。
また、この効果は、センサーサイズが1/1.7型機のQ7と
Q-S1の方が、画角が広くて得られやすいのだが、あえて
画角の狭いQ/Q10で、控え目に使用する手法もある。
(注:Q7等では、内部画像拡大処理が入っているので、
そのように単純な話では無いが、あくまで概要の話だ)
さらに、とても贅沢な使用法だが、このトイレンズを使う
為に、異なるセンサーサイズの2系列のQ母艦を持ち出すとかも
有り得る。又は、Q7で撮って、周辺流れの効果の量を調整する
目的でトリミングを行う、という手法も勿論ありだろう。

エフェクト(デジタルフィルター)と組み合わせる事で、
事前に想像できない「アンコントローラブル」な要素を
得る事ができる。
しかし、闇雲に撮っているだけでは無理であり、ちゃんと
このレンズの特性を理解しつつ使うのが望ましい。
感覚的にわかりやすい例を挙げれば、このレンズを使う場合、
「野球で言うところの、ストライクゾーンがある」と
思えば良い。
野球のストライクゾーンは、「バッターの肩の上部と
ズボンの上部との中間点に引いたラインを上限とし、
膝下部のラインを下限とするホームベース上の空間」といった
難しい定義があるが、まあ、「直方体の三次元空間」である、
という事は、野球観戦者の誰でもが知っているであろう。
(参考:近年の米国の野球中継では、ストライクゾーンが
画面にCG合成されて放映されている)
本レンズを使う場合、目の前の空間上に、「像が流れ難い
三次元空間」を頭の中でイメージする。これの厳密な定義は
難しいが、だいたいだが、各辺が、2~3mくらいの直方体や
立方体を思い浮かべればよい。
そして、主要被写体を、その仮想の「ストライクゾーン」の
中に収めるように、構図、撮影距離、アングルやレベルを
整えて撮れば、本レンズの特徴を活かした撮り方が出来る。
ここも勿論、トイレンズであるから、それをわかった上で、
あえて「ストライクゾーン」から外して撮るのも有りだ。
(「ボール」となる「遊び玉」を投げるというイメージだ)
そう簡単な話(技法)では無いとも言えるが、まあ全般に
トイレンズを使う上では、むしろ通常のHi-Fi写真撮影技法
よりも、はるかに高度なスキルが要求される訳だ。
まあ、銀塩末期の「トイカメラ」のブームの際は、写真の原理
を知らないビギナー層が、それを使って、偶然に面白い写真が
撮れる事が主流であったのかも知れないが、現代のデジタル時代
では撮ってすぐに画像が見れる、だから、撮り手がうまくその
「破綻」の具合をコントロールしないかぎり、トイレンズ等は
上手く使いこなせない、という訳だ。
これはビギナー層では困難であり、上級者向けの技法や内容では
あるが、逆に言えば、上級者であれば、こうしたトイレンズの
特性を、より引き出す事が出来る、「奥の深い撮影分野である」
という事にもなる。

「玩具だ」とか「ビギナー用だ」「邪道だ」等とは思わず、
掘り下げて使ってみるのも、十分に意味がある事だと思う。
(上手くすれば、それまで、数十万円もするような高価な
「Hi-Fi機材」にしか目が行っていなかった状態から脱却し、
見識や価値観の幅を広める意味でも有意義に働くかも知れない。
加えて、光学原理や撮影技法、レンズの収差、長所短所等に
関する知識や理解、判断力の増強にも役に立つと思う)
それと、「ユニークレンズ」は、本記事で紹介した4本のみしか
発売されていない。今後の新製品の発売は期待が出来ない状態
ではあるが、また将来的に、PENTAXや他のカメラメーカーからも
こうしたコンセプトの商品が出てくる事を期待しよう。
なお、PENTAX以外の国内外製トイレンズについては、本シリーズ
記事や他のレンズ系記事でも、適宜紹介済み、あるいはまた別途
紹介予定である。それらは、ユニークレンズほど「控え目」な
特性ではなく、「思いっきりLo-Fiである」事も普通だ。
----
さて、今回の記事「PENTAX ユニークレンズ特集」は、
このあたり迄で、次回記事に続く・・