さて、2020年、オリンピックイヤーからの新シリーズの
開始である。
本シリーズ記事では所有している一眼レフ用等の50mm標準
レンズを、MF、AF、及び開放F値等により分類し、それぞれの
カテゴリー別に予選を行い、最後に決勝戦で「最強の50mm
標準レンズを決定する」という趣旨のシリーズ記事である。
なお、ここで言う50mm標準レンズとは、概ね40~60mmの
範囲の焦点距離を持つ主に一眼レフ用の交換レンズを指す。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
ただし、レンズ実写の為に使用するカメラ側のセンサーサイズ
(フルサイズ、APS-C、フォーサーズ系等)によっては
画角は標準画角にならない場合もある(例、50mmレンズを
APS-C機に装着すると、75~80mm相当の画角になる)
のだが、その点は気にしない事とする。
まあ厳密に言えば、換算画角の差異の他、レンズの画面周辺
収差(概ね周辺は画質が低下する)等により、小さいセンサー
サイズのカメラを使った方が画質的には有利な場合もある。
それと、フルサイズ一眼レフは、オールドを含めた全ての
標準レンズを扱えないというマウントの制約上の課題もある。
また(フルサイズ)ミラーレス機であっても、様々な種類の
マウントアダプターの手配が、なかなか困難だ。
さらには「APS-C機専用で換算画角が50mm前後になるレンズ」
というケースも、予選カテゴリーの一部では予定している。
いずれにしても、実写機のセンサーサイズはまちまちとなる。
なお、本シリーズ記事(や、過去のハイコスパ系記事)では、
紹介するレンズの単価が極めて安価なものが多く、カメラ本体
価格が突出する「オフサイド」を禁じるルールは緩和している。
それから、実写時でのカメラ側設定だが、JPEGでの小画素、
最低画質(高圧縮率)とする。
本ブログ掲載時の解像度は高々20万画素程度(と決めている)
なので、あまり高画素で撮っても意味は無いし、高画素からの
「縮小効果」として、画像処理での縮小アルゴリズムと、
対象画像の特徴との組み合わせの要素が強く出た場合には、
縮小後に画像の輪郭線の雰囲気等が大きく変わってしまう。
(よって、常に高画素で撮れば良いというものでは無い)
それから、画質というパラメーターでの実際のJPEGの圧縮率は
被写体条件(=画像の空間周波数の分布)にも大きく依存する。
加えて、ある程度以上の「低圧縮」としても、人間の見た目で
画質の差異は、感覚的にはわからなくなってしまう。
(つまり圧縮率を下げても、単純に画質が良くなる訳では無い)
なので、それを厳密に設定する事には、あまり重要な意味は無い。
それと、カメラ側にある固有の機能は自由に使う事とする。
(例、ピクチャースタイルや、エフェクト、デジタルズーム等)
だが、PC等による過度な事後編集は行わない事とし、画像縮小、
若干の輝度補正、若干のトリミング程度とする(これらの措置は、
本ブログでの他のレンズ紹介系記事でも全て同様)
いずれにしても、掲載画像は、あくまで雰囲気的な参考だ。
勿論、すべて同一機体(カメラ)で、同一カメラ設定で
実写を行った方が公平性は高いが、それができるカメラは
フルサイズ・ミラーレス機のSONY α7/α9系や、新鋭の
(まだ高価な)ニコンZ、CANON EOS R系しかない。
しかしα7系は、一部のオールドレンズで内部反射による
ゴースト発生などが起こりやすい事や、近代のレンズでは
マウントアダプターを使っても装着できないものもある。
(例:ニコン用の電磁絞り対応レンズ→絞りが動かない
や、特殊仕様モーター内蔵のレンズ等→MFが効かない)
まあ、こういう状況なので、レンズの実写パフォーマンスを
極端に下げるカメラとレンズの組み合わせを避ける為にも、
実写用カメラが複数になるのはやむを得ない。
すなわち、基本的には、実写作例などではレンズの性能
(描写力)の全てを計り知る事は不可能だ。
具体的な例をあげれば、「ボケ質の破綻」は、撮影距離
背景距離、背景の絵柄、レンズ側絞り値、などが複雑に
絡んで変化する為、よくWEBや雑誌での作例にあるような
「なんとか露出モード、露出補正いくつ、絞り値いくつ、
シャッター速度いくつ」といった情報だけでは撮影条件が
特定できず、全く参考にならないし、再現性も無い。
「レンズのボケの良し悪し」が銀塩時代の昔から、評価者に
よって個々に様々であったのは、前記の複雑な撮影条件を
均一化(標準化)して評価をする事が不可能だからだ。
ちゃんと評価をやろうとすれば、全く同一の撮影条件を作り、
しかも、それを無数(ほぼ無限)と言える条件の組み合わせで
各々検証しなければならないが、それは絶対に無理な話だ。
よって、世の中のレンズ実写例は、いつの時代においても
あくまで参考用でしか無い。そこはレンズを購入する際等で
留意するべき極めて重要なポイントなので、よく認識しておく
必要があるだろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17481073.jpg]()
さて、50mm標準レンズ選手権で、具体的に考えている予選の
時点でのカテゴリー分けだが
MF50mm/f1.4級,MF50mm/f1.8級,
AF50mm/f1.4級,AF50mm/f1.8級,
50mm標準マクロ(AF/MF)、換算で50mm相当となるレンズ群、
トイレンズ50mm相当、50mm近辺の焦点距離のレンズ群、
その他、等であり、これらによる予選ラウンドは、十数記事
(十数カテゴリー)となる予定だ。
で、予選勝ちあがり形式で準決勝等を行うと、重複紹介する
レンズが多々出てくる可能性があり冗長だ。よって、決勝は
評価点(多項目におよぶ)が優秀であったレンズ数本を
直接決勝で評価(対戦)する形式とする予定だ。
ただし、「B決勝」(=惜しくも決勝に残れなかったレンズ
による下位決勝、又は順位決定戦)は行うかも知れない。
---
それから、本シリーズ記事は、とりあえず、交換レンズ
としては基本中の基本である「50mm標準レンズ」に
スポットを当てている。
まあ「50mm標準レンズ」は、マニアであれば非常に多数
所有している事も普通であろう。
私の場合も、最も古い標準レンズで1960年代の製品から、
新しい物では2010年代後半の製品まで、実に半世紀もの
時代範囲で、数十本所有している。
よって、本シリーズの予選ラウンドは、1記事4レンズと
しても、かなり長くなる予定だ。
決勝戦まで無事終了したら、場合により、他の焦点距離、
例えば、85mm選手権や135mm選手権も構想段階にあるが、
それらは実現するとしても少々先の話になるであろう。
シリーズ中の各レンズの実写作例を撮り貯めたり、評価を
行うだけでも、1年や2年は平気で費やしてしまうのだ。
(そのように時間がかかる為、本シリーズ記事執筆後に
新たに購入した50mm級レンズも何本かあるが、それらは
評価が間に合わず、やむなくエントリーから外している)
---
さて、今回の記事では、3本のMF50mm/f1.4レンズを
紹介する。基本的に予選ラウンドでの1記事には、4本づつの
同じカテゴリーレンズを紹介する方式ではあるが、本記事では
本シリーズの趣旨説明があった事で、紹介1本分を減らす。
また、故障レンズ等で、実写紹介がやりにくい場合もあり
そういう場合は、当該レンズの紹介説明を最小限として
1記事に5本以上のレンズを紹介する場合もありうる。
---
・・と言う事で、予選リーグの初回記事は、
予選Aブロック「MF50mm/f1.4 Part1」とする。
では、まずは最初の標準レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17482014.jpg]()
レンズ名:CONTAX Planar T* 50mm/f1.4(Y/Cマウント)
レンズ購入価格:19,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ)
まずは、「Planar」(プラナー)という商品名(商標)は、
元々はカールツァイス財団が1897年という昔に発明した
レンズ構成(特許)であり、商標も同社が保有していたのだが、
1970年代のヤシカ(京セラ・コンタックス)を始め、
同年代のローライ、2000年代のコシナや2010年代のSONY等、
多数のメーカーが使用権を取得している商品名でもある。
したがってPlanar 50mmと言っても、実に多数の製品や
バリエーションがある。本レンズはヤシカ(後に京セラ)・
コンタックスが1975年に発売した「CONTAX RTS」
(銀塩一眼レフ・クラッシックス第5回記事参照)と
セット(キット)で販売された大口径標準レンズである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17482067.jpg]()
なお、2000年代くらいまで、カールツァイス系のレンズの
スペックは、焦点距離、開放絞り値の順番では表記せず
Planar T* F1.4/50mmのように逆順で書く事が普通であった。
この記法は「ドイツ式」と呼ばれる(他に様々な方式あり)
だが、これの元々の始まりは、恐らく1930年代のドイツにおける
「ライカ・コンタックス戦争」で、コンタックスのカメラの
仕様を、ことごとくライカと逆にした、というのが要因に
なっていると思われるのだが、本ブログでは特定のメーカーの
製品だけ他社と異なる慣習を用いる事には賛同しておらず、
従前からずっとCONTAX系(ツァイス系)レンズにおいても
焦点距離、開放絞り値の順番で記載している。
なお、近年2010年代では、SONY系のツァイス銘交換レンズ
(Aマウント、Eマウント)においては、現代での慣例に沿って
焦点距離、開放絞り値の順に記載があるが、他社のツァイス
系レンズや、旧CONTAXから流れを組むロシア(ソ連)や
東独系のレンズでも逆表記となっていて統一はされていない。
それから、「f値」が正しいか「F値」が正しいか?
と言えば、本来の光学用語的には「F値」と大文字が正しい。
ただ、依然、小文字の「f値」の記載を採用するメーカーも
ニコン等であるし、f値の前に「/」が来るか、後に来るか
など、業界全体においては、表記は統一はされていない。
(注:fは焦点距離を示す文字であり、口径比F値は、
F=焦点距離(f)÷瞳径(有効径)で決まる為、「f/」
つまり、"焦点距離を割る"という表記法なのであろう。
他には、1:2.8 のような表記法もレンズ上等では多い)
どの記載方法が正しいか否かは判断できない状況であるので、
本ブログにおいては、レンズ仕様は「50mm/f1.4」といった
表記方法で15年前の開設時の昔から統一しているのだが、
説明文書中では(正しい)「F値」表記も適宜使用して行く。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17482076.jpg]()
さて、余談が長くなったが、本レンズの話に進む。
本レンズは「プラナー」という高いブランド力において
初級マニア層等において「神格化」されている要素があった。
しかし、詳しく分析してみると、まず、この時代1970年代
後半の「CONTAX RTS」の登場で、世の中の一般的な撮影技法
が大きく変化した事実(歴史)がある、と思っている。
一眼レフカメラにおいて、「絞り優先露出」という自動化
スペックが普及したのは、この時代1970年代であり、
このころ、CONTAX(ヤシカ・京セラ)においては、その
露出モードを使用する事が、ツァイス系大口径レンズによる
「ボケ質の良好さ」をアピールする事に有効であると考え、
その技法を一般にも普及させていったのであろう。
つまり、それ以前の時代の一般的な撮影技法は、まず露出を
正しく設定する事が最重要であり、その時代のカメラの
最高シャッター速度が高々1/1000秒程度であった性能では、
(ASA100のフィルムで)「曇りではF5.6で1/250秒」
等といった露出決定技法しか、事実上では使えなかった。
これは中遠距離を平面的に撮影するスナップや風景撮影には
適した撮影技法となる。特に広角レンズ(28~35mm)
ではこうした撮り方が主流であり、50mm標準レンズを使う
際にも同様であっただろう。せっかくのF1.4という大口径も
暗所でなければ、カメラのシャッター性能的にも使えない。
しかし、この「CONTAX RTS」では、絞り優先AEの搭載と、
最高シャッター速度1/2000秒で絞り値設定の自由度が上がり、
加えて「ツァイスは(プラナーは)絞りを開けて使え」
という布教活動が功を奏したのか? この時代から、絞りを
開けて背景をボカす撮影技法が一般的になってきた。
絞りを開けて背景を大きくボカした写真は、当時の一般層
には新鮮だ、恐らく「さすがにコンタックス、ボケが綺麗だ」
という評価が一般ユーザー層に大きく広まっていった事だろう。
当時のCONTAX RTSが、かなり高価であった事(レンズ付き
ならば18万円くらい、注:諸説あり)もあいまって、
プレミアム感の演出はさらに高まった事であろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17482027.jpg]()
だが、実際の所を言えば、例えば、安価なPENTAX SPと
タクマー50mm/F1.4でも、あるいはミノルタやキヤノンでも
50mm/F1.4標準レンズを上手く使えば、同等の描写傾向を
得る事はできたのだ。
ツァイス(コンタックス)党であれば、
「他社のレンズとは、レンズ構成もコーティングも違うよ!」
と、高価に購入した本レンズのプレミアム感(=割高感)
を擁護する発言もあったのかも知れないが・・ とは言え、
標準レンズは、いずれも当時の各メーカーの「顔」である。
最初に付属で購入する、この手のレンズの描写力が低かったら、
カメラメーカー各社は市場競争についていけなくなる、
だから、基本的には標準レンズはどれも良く写り、メーカー
間の性能的な差異は、この当時から殆ど無かったのだ。
本レンズPlanar 50mm/f1.4 であるが、確かにボケ質等は
他社標準レンズに比べて、当時であれば一日の長があったと
思われる。しかし、現代の視点でよく見ると、結構ボケ質の
破綻が頻繁に発生するレンズであり、その回避が難しい。
すなわち「良いレンズではあるが、使いこなしが難しい」
という印象の強いレンズだ。
(なお、ボケ質破綻の回避には、デジタル一眼レフよりも
高精細EVFを搭載したミラーレス機での使用が若干有利だ)
現代においての中古相場は、他社MF標準F1.4級よりも
はるかに高価である。しかし既に40年以上も前の古いレンズ
である事や、ボケ質破綻の回避が難しい事もあり、誰にでも
推薦できるレンズでは無い事を最後に述べておく。
---
では、次の標準レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17483697.jpg]()
レンズ名:MINOLTA MC ROKKOR PG 50mm/f1.4
レンズ購入価格:10,000円(中古)
使用カメラ:SONY α7 (フルサイズ)
1970年前後に発売されたミノルタSR/MCマウント用の
標準レンズであるが、「MDマウント用」のアダプター使用
で、現代のミラーレス機には装着可能だ(注:一眼レフへは
装着は難しい)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17484456.jpg]()
中古購入価格が1万円と、やや高価なのは、まだ銀塩カメラ
が主流であった1990年代に購入したからであって、その後
2000年代からのデジタル時代には本レンズは一眼レフでは
使用が困難であった為、相場は大きく下落、ピークでは
2010年頃の「大放出時代」(他記事で何度も説明済み)
では、2000円前後の二束三文の中古相場まで落ち込んだ。
その後、2010年代では、ミラーレス機によるアダプターでの
利用が簡便である事から、本レンズの中古相場は、また上昇、
現代では、あまり中古を見かけないが、程度によって4000円
~9000円程度にまで上がってきているかも知れない。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17484493.jpg]()
本レンズは同スペックのままで、続くMD型(末所有)となり
以降、レンズ構成を変えてNew MD型(紹介予定)、AF対応の
α初期型(紹介予定)と、色々と変遷があるが、それはまた
各々の紹介記事で述べよう。
それから、1つ注意しておく点だが、今回母艦としている
SONY α7は、一部のオールドレンズ使用時にゴーストの発生が
酷く、レンズの性能を正しく評価しずらい、という弱点がある。
その詳しい原因は不明であるが、ゴーストの発生するレンズを
他社のフルサイズ機や、他社APS-C機、μ4/3機、あるいは
同じSONYでもAPS-C機(NEX-7、α77Ⅱ等)に装着した場合は、
問題が起こらない。
したがって、ゴーストはα7側の問題である事は明白なのだが、
その点は、そういう性能なので、やむを得ない。
本レンズ MC50/1.4を使用時にも、同様にゴーストが多々発生
するのだが、そこはもう目をつぶろう。
本記事の冒頭に
「フルサイズ機が必ずしも良く写るとは限らない」
と記載したのであるが、世間一般の初級中級ユーザー層では
そういう感覚は持っていない事であろう、
「フルサイズで画素数も大きく、高価なカメラだから、良く写る
に決まっている」と思い込んでいても不思議では無い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17484485.jpg]()
だけどまあ、私としても、フルサイズカメラが一般に普及して
事により、広角レンズをはじめ、魚眼レンズや、特殊効果系の
レンズ(シフトや、ぐるぐるボケ等)でフルサイズ機の方が
特徴が得やすい面もあり、何台かのフルサイズ機は必要だ。
ここは、一般ユーザーでのフルサイズ機の新品購入を促進して
もらう事で、縮退してきているカメラ業界が潤う事や、中古で
安価なフルサイズ機の相場が下がる事を期待して、フルサイズ
機を否定するような発言は最小限にする事としている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17485216.jpg]()
本レンズMC50/1.4の長所だが、比較的ボケ質に優れている事、
それと後年のNew MD50/1.4(小型化して、レンズ構成も変わり、
描写特性が変化)と比較して、本レンズの描写を好むマニアも
多く、結果的にマニアック度の高いレンズとなっている事だ。
弱点だが、ボケ質が良いと言っても、ボケ質の破綻は頻繁に
発生する事、それからレンズが少し大柄な点もある。
前記 Planar 50mm/f1.4と同様に、ボケ質の破綻には慎重に
対処する必要があるだろう。この技法は結構高難易度であるし
マニアック度の高さ、入手のしにくさも含めて、本レンズも、
あまり初級マニア等に推奨できるものでは無い。
---
では、次は本記事ラストの標準レンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17491673.jpg]()
レンズ名:OLYMPUS OM-SYSTEM Zuiko 50mm/f1.4
レンズ購入価格:11,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3)
1970年代~1990年代頃の、OMシリーズMF一眼レフ用の大口径
標準レンズ。本レンズはかなり初期のもので、おそらくは
1970年代製造のもの。中古購入価格が若干高価なのは、この
レンズも銀塩時代に購入したからであるが、現代でも恐らく
同様な相場であり、発売年度が古いから、程度(外観のキズ
や、内部のホコリ、カビ等)によっては、7000円~12000円
前後と、中古相場の幅はバラつく事であろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17491685.jpg]()
今回使用の母艦E-M5Ⅱはμ4/3機であるので、
装着時の換算画角は2倍、100mm相当となり、もはや標準
レンズの感覚で被写体を探す事は出来ない。
ただ、私個人としては、多数のμ4/3機を使用しており、
それらに50mm標準レンズを装着するケースも多々あるので
100mmの換算画角は慣れてはいる、だから別に50mmの画角に
拘る為にフルサイズ機を使用する意味はあまり無いと思って
いるのだ。
その事は、2000年代、まだフルサイズ機のデジタル一眼レフ
が普及しておらず、殆どの一眼レフが、APS-C型センサーで
50mmレンズを装着しても75~80mm程度になってしまった
場合と同様な感覚だ、最初は(銀塩から持ち換えたすぐは)
違和感があるが、沢山撮っていれば、短期間でその新しい
画角感覚にも慣れてしまう。
「単焦点使い」というのは、できるだけ多数の焦点距離の
単焦点レンズで、各々の画角感覚を掴む事とほぼイコールだ、
だから新たな画角感覚を1つ追加すれば済むという話だ。
なお、「ズーム使い」だと、単焦点派のような画角感覚が
なかなか身につかない。
これはまあ、現代の初級中級者層ではズームレンズ使用が、
99%にも達するだろうから「不要な技能だ」とも言えるかも
知れないのだが、「ズーム使い」であっても個々の焦点距離に
対応する画角感覚を持っていた方が望ましい事は確かだ。
例えば、一部の写真教室では、単焦点の画角感覚を養う為
単焦点を使う実習や、ズームレンズであってもガムテープ等で
焦点距離を固定して撮る練習を行う、という実例がある。
で、100mmの画角とはなるが、まあ同じ50mmレンズを
使用するので、「望遠効果」が発生する訳では無い。
他の影響としては、センサーサイズが小さくなると
ボケ量が減る(被写界深度が深くなる)というのが光学原理
ではあるのだが、デジタルにおける許容錯乱円の定義が
従前より、ずっと曖昧なままだ。オリンパスの公式見解では
「μ4/3機の許容錯乱円は、35mm判フィルムの丁度半分」
とWEB等に記載されているが、この値で計算しても、なんだか
実際の被写界深度の感覚とは、ずいぶん異ってしまう。
また冒頭に述べたような「縮小効果」なども絡んできて、
極めてややこしい。
被写界深度の件は深追いしないのが賢明だ。近年では私は、
全てフルサイズ換算として被写界深度を考慮している。
(=銀塩フルサイズ機での許容錯乱円を計算上用いる)
さて、μ4/3機に50mm標準レンズを装着して100mm相当の
画角で使う事は、その効果や弱点を十分に認識して使う
ならば、あまり問題にはならない。
が、弱点というのも特には無く、画角が変わる程度であるが
それは機材の弱点とは言えず、撮る側の感覚の問題であろう。
例えば、μ4/3機で使用時に「50mmの標準画角で使いたい」
という市場ニーズも確かにある為、25mmという焦点距離の
μ4/3用レンズも実際に存在している。私も何本かは所有して
いが、今度は、50mm標準画角なのに、あまり被写界深度
が浅くならない(=焦点距離が短い、開放F値があまり小さく
無い等の理由がある)場合もあって、逆に50mm/f1.4を
フルサイズ機(または銀塩35mm判)で使う場合に比べて、
違和感を持ってしまうのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17491608.jpg]()
余談が長くなったが、本OM50/1.4の話に戻ろう。
まず長所だが、F1.4という大口径レンズでありながら、
フィルター系がφ49mmと小型、そして軽量である事だ。
オリンパスのOM用交換レンズは、同一焦点距離でも
大口径版と小口径版が多く並行ラインナップされていて、
その殆どが、大口径版がφ55mm、小口径版がφ49mmに
フィルター径が統一されている。
これは当時の、天才と言われた設計技師「米谷氏」による
拘りの「標準化思想」であろう、1970年代の他社では、
いや、それ以降、現代に至るまで、各社において、
「交換レンズのフィルター径を統一する」という思想を
実現した例は他には殆ど無い。(注:銀塩時代のニコンが
多くの交換レンズをφ52mmで統一していた前例はある。
また、銀塩時代のキヤノンにも標準化思想はあった。
が、その後はそういう傾向は無い。1970年代前後の
高度成長期のような製造業の効率化のノウハウが、現代の
日本では失われてしまった事が理由なのかも知れない。
ただまあ、ごく近年のTAMRONでは、SP単焦点や、DiⅢ型
広角単焦点シリーズで、フィルター径統一の風潮がある)
で、本OM50/1.4は、スペック的には「大口径」の部類だが、
フィルター径は、小口径版のφ49mmだ。
ただ、ここからは短所の話だが、F1.4もの大口径レンズで
フィルター径を小型化する、すなわち前玉を小型化する
事は設計上からは難しいと思う。
F値の計算だが、レンズの焦点距離÷(有効)瞳径
で決まる。
焦点距離が50mmレンズの場合、瞳径(ほぼ前玉の直径だ)
がφ25mmであればF2、φ35mmであれば約F1.4となる。
つまり、フィルター径がφ49mmであれば、前玉として
φ35mm(以上)のレンズをその中に収めなければならず、
その余裕があまり無い訳だ。
それに、前玉の直径がそのまま有効瞳径になるという訳でも
なく、若干の効率の悪さがあるので、実際の設計上では
前玉はもう少し大きく余裕を持たせた構造になるだろう。
これがもしフィルター径φ55mmであれば、多少の大きさの
余裕があるので、レンズの設計上や構造上では楽な訳だ。
また、F値(口径比)以外でも、収差補正等に係わる前玉
レンズの屈折率の選択などで、色々と課題が出るだろう。
それを逆に言えば、前玉やフィルター径の小さい大口径
レンズは、必ず設計上で無理がある、という事に繋がる。
だから、本OM50mm/F1.4や類似スペックのMINOLTA New MD
50mm/F1.4という小型化レンズは、ボケ質の破綻が発生したり
逆光耐性や口径食が厳しい等、小型化に反して、複数の
問題点が発生する事は「トレードオフ」で、やむを得ない。
まあでも、この時代(1970年代)は、一眼レフの普及化を
狙って、小型化が推進された時代である。
その急先鋒はOLYMPUSの「OMシリーズ」であり、さらには
PENTAX Mシリーズ等が小型化に追従した歴史がある。
それらの小型軽量一眼レフに従来型の大型の標準レンズ
(例、前記MINOLTA MC50mm/f1.4 フィルター径φ55m)
を付けて売る訳にはいかない。
いかにもアンバランスだし、カメラだけ小型化しても
トータルの軽量化メリットが出ないからだ。
だから(MF一眼レフ)カメラの小型化には、必ずレンズの
小型化も必須なのだ、これは当時最軽量のOM-1を上回る
目標で開発されたPENTAX MXが、OM-1から4年も遅れて
発売された歴史も、その事実を示している。
すなわちMXだけであれば、恐らくもっと早く開発できた事
だろうが、同時に従来のP(K)型のPENTAX 交換レンズを
全て小型の「M型」に置き換える必要があったからだ。
これは極めて大変な開発作業であり、時間がかかったのも
やむを得ないと思う。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17491693.jpg]()
さて、また余談が長くなってしまった、本OM50/1.4は、
ちょっとマニア受けがしないレンズとなっている。
その理由は、小型軽量のOMシリーズに合わせるには、
本レンズよりもさらに軽量な、OM50/1.8が適切だからだ。
なお、OM50/1.8は、下手をすれば本OM50/1.4よりも描写力
に優れる銘レンズだと思う。同レンズは過去2度所有して
いたのだが、現在所有しているOM50/1.8は、カビの発生で
フレアなど描写力が低下している(ミラーレス・マニアックス
第26回記事)為、本シリーズ記事では、MFの50mm/f1.8の
予選リーグでは、「欠場」で、取り上げないかも知れない。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Aブロック「MF50mm/f1.4 Part1」の記事は終了だ、
次回の本シリーズ記事は、
予選Bブロック「AF50mm/f1.8級」となる予定だ。
開始である。
本シリーズ記事では所有している一眼レフ用等の50mm標準
レンズを、MF、AF、及び開放F値等により分類し、それぞれの
カテゴリー別に予選を行い、最後に決勝戦で「最強の50mm
標準レンズを決定する」という趣旨のシリーズ記事である。
なお、ここで言う50mm標準レンズとは、概ね40~60mmの
範囲の焦点距離を持つ主に一眼レフ用の交換レンズを指す。
Clik here to view.

(フルサイズ、APS-C、フォーサーズ系等)によっては
画角は標準画角にならない場合もある(例、50mmレンズを
APS-C機に装着すると、75~80mm相当の画角になる)
のだが、その点は気にしない事とする。
まあ厳密に言えば、換算画角の差異の他、レンズの画面周辺
収差(概ね周辺は画質が低下する)等により、小さいセンサー
サイズのカメラを使った方が画質的には有利な場合もある。
それと、フルサイズ一眼レフは、オールドを含めた全ての
標準レンズを扱えないというマウントの制約上の課題もある。
また(フルサイズ)ミラーレス機であっても、様々な種類の
マウントアダプターの手配が、なかなか困難だ。
さらには「APS-C機専用で換算画角が50mm前後になるレンズ」
というケースも、予選カテゴリーの一部では予定している。
いずれにしても、実写機のセンサーサイズはまちまちとなる。
なお、本シリーズ記事(や、過去のハイコスパ系記事)では、
紹介するレンズの単価が極めて安価なものが多く、カメラ本体
価格が突出する「オフサイド」を禁じるルールは緩和している。
それから、実写時でのカメラ側設定だが、JPEGでの小画素、
最低画質(高圧縮率)とする。
本ブログ掲載時の解像度は高々20万画素程度(と決めている)
なので、あまり高画素で撮っても意味は無いし、高画素からの
「縮小効果」として、画像処理での縮小アルゴリズムと、
対象画像の特徴との組み合わせの要素が強く出た場合には、
縮小後に画像の輪郭線の雰囲気等が大きく変わってしまう。
(よって、常に高画素で撮れば良いというものでは無い)
それから、画質というパラメーターでの実際のJPEGの圧縮率は
被写体条件(=画像の空間周波数の分布)にも大きく依存する。
加えて、ある程度以上の「低圧縮」としても、人間の見た目で
画質の差異は、感覚的にはわからなくなってしまう。
(つまり圧縮率を下げても、単純に画質が良くなる訳では無い)
なので、それを厳密に設定する事には、あまり重要な意味は無い。
それと、カメラ側にある固有の機能は自由に使う事とする。
(例、ピクチャースタイルや、エフェクト、デジタルズーム等)
だが、PC等による過度な事後編集は行わない事とし、画像縮小、
若干の輝度補正、若干のトリミング程度とする(これらの措置は、
本ブログでの他のレンズ紹介系記事でも全て同様)
いずれにしても、掲載画像は、あくまで雰囲気的な参考だ。
勿論、すべて同一機体(カメラ)で、同一カメラ設定で
実写を行った方が公平性は高いが、それができるカメラは
フルサイズ・ミラーレス機のSONY α7/α9系や、新鋭の
(まだ高価な)ニコンZ、CANON EOS R系しかない。
しかしα7系は、一部のオールドレンズで内部反射による
ゴースト発生などが起こりやすい事や、近代のレンズでは
マウントアダプターを使っても装着できないものもある。
(例:ニコン用の電磁絞り対応レンズ→絞りが動かない
や、特殊仕様モーター内蔵のレンズ等→MFが効かない)
まあ、こういう状況なので、レンズの実写パフォーマンスを
極端に下げるカメラとレンズの組み合わせを避ける為にも、
実写用カメラが複数になるのはやむを得ない。
すなわち、基本的には、実写作例などではレンズの性能
(描写力)の全てを計り知る事は不可能だ。
具体的な例をあげれば、「ボケ質の破綻」は、撮影距離
背景距離、背景の絵柄、レンズ側絞り値、などが複雑に
絡んで変化する為、よくWEBや雑誌での作例にあるような
「なんとか露出モード、露出補正いくつ、絞り値いくつ、
シャッター速度いくつ」といった情報だけでは撮影条件が
特定できず、全く参考にならないし、再現性も無い。
「レンズのボケの良し悪し」が銀塩時代の昔から、評価者に
よって個々に様々であったのは、前記の複雑な撮影条件を
均一化(標準化)して評価をする事が不可能だからだ。
ちゃんと評価をやろうとすれば、全く同一の撮影条件を作り、
しかも、それを無数(ほぼ無限)と言える条件の組み合わせで
各々検証しなければならないが、それは絶対に無理な話だ。
よって、世の中のレンズ実写例は、いつの時代においても
あくまで参考用でしか無い。そこはレンズを購入する際等で
留意するべき極めて重要なポイントなので、よく認識しておく
必要があるだろう。
Clik here to view.

時点でのカテゴリー分けだが
MF50mm/f1.4級,MF50mm/f1.8級,
AF50mm/f1.4級,AF50mm/f1.8級,
50mm標準マクロ(AF/MF)、換算で50mm相当となるレンズ群、
トイレンズ50mm相当、50mm近辺の焦点距離のレンズ群、
その他、等であり、これらによる予選ラウンドは、十数記事
(十数カテゴリー)となる予定だ。
で、予選勝ちあがり形式で準決勝等を行うと、重複紹介する
レンズが多々出てくる可能性があり冗長だ。よって、決勝は
評価点(多項目におよぶ)が優秀であったレンズ数本を
直接決勝で評価(対戦)する形式とする予定だ。
ただし、「B決勝」(=惜しくも決勝に残れなかったレンズ
による下位決勝、又は順位決定戦)は行うかも知れない。
---
それから、本シリーズ記事は、とりあえず、交換レンズ
としては基本中の基本である「50mm標準レンズ」に
スポットを当てている。
まあ「50mm標準レンズ」は、マニアであれば非常に多数
所有している事も普通であろう。
私の場合も、最も古い標準レンズで1960年代の製品から、
新しい物では2010年代後半の製品まで、実に半世紀もの
時代範囲で、数十本所有している。
よって、本シリーズの予選ラウンドは、1記事4レンズと
しても、かなり長くなる予定だ。
決勝戦まで無事終了したら、場合により、他の焦点距離、
例えば、85mm選手権や135mm選手権も構想段階にあるが、
それらは実現するとしても少々先の話になるであろう。
シリーズ中の各レンズの実写作例を撮り貯めたり、評価を
行うだけでも、1年や2年は平気で費やしてしまうのだ。
(そのように時間がかかる為、本シリーズ記事執筆後に
新たに購入した50mm級レンズも何本かあるが、それらは
評価が間に合わず、やむなくエントリーから外している)
---
さて、今回の記事では、3本のMF50mm/f1.4レンズを
紹介する。基本的に予選ラウンドでの1記事には、4本づつの
同じカテゴリーレンズを紹介する方式ではあるが、本記事では
本シリーズの趣旨説明があった事で、紹介1本分を減らす。
また、故障レンズ等で、実写紹介がやりにくい場合もあり
そういう場合は、当該レンズの紹介説明を最小限として
1記事に5本以上のレンズを紹介する場合もありうる。
---
・・と言う事で、予選リーグの初回記事は、
予選Aブロック「MF50mm/f1.4 Part1」とする。
では、まずは最初の標準レンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:19,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ)
まずは、「Planar」(プラナー)という商品名(商標)は、
元々はカールツァイス財団が1897年という昔に発明した
レンズ構成(特許)であり、商標も同社が保有していたのだが、
1970年代のヤシカ(京セラ・コンタックス)を始め、
同年代のローライ、2000年代のコシナや2010年代のSONY等、
多数のメーカーが使用権を取得している商品名でもある。
したがってPlanar 50mmと言っても、実に多数の製品や
バリエーションがある。本レンズはヤシカ(後に京セラ)・
コンタックスが1975年に発売した「CONTAX RTS」
(銀塩一眼レフ・クラッシックス第5回記事参照)と
セット(キット)で販売された大口径標準レンズである。
Clik here to view.

スペックは、焦点距離、開放絞り値の順番では表記せず
Planar T* F1.4/50mmのように逆順で書く事が普通であった。
この記法は「ドイツ式」と呼ばれる(他に様々な方式あり)
だが、これの元々の始まりは、恐らく1930年代のドイツにおける
「ライカ・コンタックス戦争」で、コンタックスのカメラの
仕様を、ことごとくライカと逆にした、というのが要因に
なっていると思われるのだが、本ブログでは特定のメーカーの
製品だけ他社と異なる慣習を用いる事には賛同しておらず、
従前からずっとCONTAX系(ツァイス系)レンズにおいても
焦点距離、開放絞り値の順番で記載している。
なお、近年2010年代では、SONY系のツァイス銘交換レンズ
(Aマウント、Eマウント)においては、現代での慣例に沿って
焦点距離、開放絞り値の順に記載があるが、他社のツァイス
系レンズや、旧CONTAXから流れを組むロシア(ソ連)や
東独系のレンズでも逆表記となっていて統一はされていない。
それから、「f値」が正しいか「F値」が正しいか?
と言えば、本来の光学用語的には「F値」と大文字が正しい。
ただ、依然、小文字の「f値」の記載を採用するメーカーも
ニコン等であるし、f値の前に「/」が来るか、後に来るか
など、業界全体においては、表記は統一はされていない。
(注:fは焦点距離を示す文字であり、口径比F値は、
F=焦点距離(f)÷瞳径(有効径)で決まる為、「f/」
つまり、"焦点距離を割る"という表記法なのであろう。
他には、1:2.8 のような表記法もレンズ上等では多い)
どの記載方法が正しいか否かは判断できない状況であるので、
本ブログにおいては、レンズ仕様は「50mm/f1.4」といった
表記方法で15年前の開設時の昔から統一しているのだが、
説明文書中では(正しい)「F値」表記も適宜使用して行く。
Clik here to view.

本レンズは「プラナー」という高いブランド力において
初級マニア層等において「神格化」されている要素があった。
しかし、詳しく分析してみると、まず、この時代1970年代
後半の「CONTAX RTS」の登場で、世の中の一般的な撮影技法
が大きく変化した事実(歴史)がある、と思っている。
一眼レフカメラにおいて、「絞り優先露出」という自動化
スペックが普及したのは、この時代1970年代であり、
このころ、CONTAX(ヤシカ・京セラ)においては、その
露出モードを使用する事が、ツァイス系大口径レンズによる
「ボケ質の良好さ」をアピールする事に有効であると考え、
その技法を一般にも普及させていったのであろう。
つまり、それ以前の時代の一般的な撮影技法は、まず露出を
正しく設定する事が最重要であり、その時代のカメラの
最高シャッター速度が高々1/1000秒程度であった性能では、
(ASA100のフィルムで)「曇りではF5.6で1/250秒」
等といった露出決定技法しか、事実上では使えなかった。
これは中遠距離を平面的に撮影するスナップや風景撮影には
適した撮影技法となる。特に広角レンズ(28~35mm)
ではこうした撮り方が主流であり、50mm標準レンズを使う
際にも同様であっただろう。せっかくのF1.4という大口径も
暗所でなければ、カメラのシャッター性能的にも使えない。
しかし、この「CONTAX RTS」では、絞り優先AEの搭載と、
最高シャッター速度1/2000秒で絞り値設定の自由度が上がり、
加えて「ツァイスは(プラナーは)絞りを開けて使え」
という布教活動が功を奏したのか? この時代から、絞りを
開けて背景をボカす撮影技法が一般的になってきた。
絞りを開けて背景を大きくボカした写真は、当時の一般層
には新鮮だ、恐らく「さすがにコンタックス、ボケが綺麗だ」
という評価が一般ユーザー層に大きく広まっていった事だろう。
当時のCONTAX RTSが、かなり高価であった事(レンズ付き
ならば18万円くらい、注:諸説あり)もあいまって、
プレミアム感の演出はさらに高まった事であろう。
Clik here to view.

タクマー50mm/F1.4でも、あるいはミノルタやキヤノンでも
50mm/F1.4標準レンズを上手く使えば、同等の描写傾向を
得る事はできたのだ。
ツァイス(コンタックス)党であれば、
「他社のレンズとは、レンズ構成もコーティングも違うよ!」
と、高価に購入した本レンズのプレミアム感(=割高感)
を擁護する発言もあったのかも知れないが・・ とは言え、
標準レンズは、いずれも当時の各メーカーの「顔」である。
最初に付属で購入する、この手のレンズの描写力が低かったら、
カメラメーカー各社は市場競争についていけなくなる、
だから、基本的には標準レンズはどれも良く写り、メーカー
間の性能的な差異は、この当時から殆ど無かったのだ。
本レンズPlanar 50mm/f1.4 であるが、確かにボケ質等は
他社標準レンズに比べて、当時であれば一日の長があったと
思われる。しかし、現代の視点でよく見ると、結構ボケ質の
破綻が頻繁に発生するレンズであり、その回避が難しい。
すなわち「良いレンズではあるが、使いこなしが難しい」
という印象の強いレンズだ。
(なお、ボケ質破綻の回避には、デジタル一眼レフよりも
高精細EVFを搭載したミラーレス機での使用が若干有利だ)
現代においての中古相場は、他社MF標準F1.4級よりも
はるかに高価である。しかし既に40年以上も前の古いレンズ
である事や、ボケ質破綻の回避が難しい事もあり、誰にでも
推薦できるレンズでは無い事を最後に述べておく。
---
では、次の標準レンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:10,000円(中古)
使用カメラ:SONY α7 (フルサイズ)
1970年前後に発売されたミノルタSR/MCマウント用の
標準レンズであるが、「MDマウント用」のアダプター使用
で、現代のミラーレス機には装着可能だ(注:一眼レフへは
装着は難しい)
Clik here to view.

が主流であった1990年代に購入したからであって、その後
2000年代からのデジタル時代には本レンズは一眼レフでは
使用が困難であった為、相場は大きく下落、ピークでは
2010年頃の「大放出時代」(他記事で何度も説明済み)
では、2000円前後の二束三文の中古相場まで落ち込んだ。
その後、2010年代では、ミラーレス機によるアダプターでの
利用が簡便である事から、本レンズの中古相場は、また上昇、
現代では、あまり中古を見かけないが、程度によって4000円
~9000円程度にまで上がってきているかも知れない。
Clik here to view.

以降、レンズ構成を変えてNew MD型(紹介予定)、AF対応の
α初期型(紹介予定)と、色々と変遷があるが、それはまた
各々の紹介記事で述べよう。
それから、1つ注意しておく点だが、今回母艦としている
SONY α7は、一部のオールドレンズ使用時にゴーストの発生が
酷く、レンズの性能を正しく評価しずらい、という弱点がある。
その詳しい原因は不明であるが、ゴーストの発生するレンズを
他社のフルサイズ機や、他社APS-C機、μ4/3機、あるいは
同じSONYでもAPS-C機(NEX-7、α77Ⅱ等)に装着した場合は、
問題が起こらない。
したがって、ゴーストはα7側の問題である事は明白なのだが、
その点は、そういう性能なので、やむを得ない。
本レンズ MC50/1.4を使用時にも、同様にゴーストが多々発生
するのだが、そこはもう目をつぶろう。
本記事の冒頭に
「フルサイズ機が必ずしも良く写るとは限らない」
と記載したのであるが、世間一般の初級中級ユーザー層では
そういう感覚は持っていない事であろう、
「フルサイズで画素数も大きく、高価なカメラだから、良く写る
に決まっている」と思い込んでいても不思議では無い。
Clik here to view.

事により、広角レンズをはじめ、魚眼レンズや、特殊効果系の
レンズ(シフトや、ぐるぐるボケ等)でフルサイズ機の方が
特徴が得やすい面もあり、何台かのフルサイズ機は必要だ。
ここは、一般ユーザーでのフルサイズ機の新品購入を促進して
もらう事で、縮退してきているカメラ業界が潤う事や、中古で
安価なフルサイズ機の相場が下がる事を期待して、フルサイズ
機を否定するような発言は最小限にする事としている。
Clik here to view.

それと後年のNew MD50/1.4(小型化して、レンズ構成も変わり、
描写特性が変化)と比較して、本レンズの描写を好むマニアも
多く、結果的にマニアック度の高いレンズとなっている事だ。
弱点だが、ボケ質が良いと言っても、ボケ質の破綻は頻繁に
発生する事、それからレンズが少し大柄な点もある。
前記 Planar 50mm/f1.4と同様に、ボケ質の破綻には慎重に
対処する必要があるだろう。この技法は結構高難易度であるし
マニアック度の高さ、入手のしにくさも含めて、本レンズも、
あまり初級マニア等に推奨できるものでは無い。
---
では、次は本記事ラストの標準レンズ。
Clik here to view.

レンズ購入価格:11,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3)
1970年代~1990年代頃の、OMシリーズMF一眼レフ用の大口径
標準レンズ。本レンズはかなり初期のもので、おそらくは
1970年代製造のもの。中古購入価格が若干高価なのは、この
レンズも銀塩時代に購入したからであるが、現代でも恐らく
同様な相場であり、発売年度が古いから、程度(外観のキズ
や、内部のホコリ、カビ等)によっては、7000円~12000円
前後と、中古相場の幅はバラつく事であろう。
Clik here to view.

装着時の換算画角は2倍、100mm相当となり、もはや標準
レンズの感覚で被写体を探す事は出来ない。
ただ、私個人としては、多数のμ4/3機を使用しており、
それらに50mm標準レンズを装着するケースも多々あるので
100mmの換算画角は慣れてはいる、だから別に50mmの画角に
拘る為にフルサイズ機を使用する意味はあまり無いと思って
いるのだ。
その事は、2000年代、まだフルサイズ機のデジタル一眼レフ
が普及しておらず、殆どの一眼レフが、APS-C型センサーで
50mmレンズを装着しても75~80mm程度になってしまった
場合と同様な感覚だ、最初は(銀塩から持ち換えたすぐは)
違和感があるが、沢山撮っていれば、短期間でその新しい
画角感覚にも慣れてしまう。
「単焦点使い」というのは、できるだけ多数の焦点距離の
単焦点レンズで、各々の画角感覚を掴む事とほぼイコールだ、
だから新たな画角感覚を1つ追加すれば済むという話だ。
なお、「ズーム使い」だと、単焦点派のような画角感覚が
なかなか身につかない。
これはまあ、現代の初級中級者層ではズームレンズ使用が、
99%にも達するだろうから「不要な技能だ」とも言えるかも
知れないのだが、「ズーム使い」であっても個々の焦点距離に
対応する画角感覚を持っていた方が望ましい事は確かだ。
例えば、一部の写真教室では、単焦点の画角感覚を養う為
単焦点を使う実習や、ズームレンズであってもガムテープ等で
焦点距離を固定して撮る練習を行う、という実例がある。
で、100mmの画角とはなるが、まあ同じ50mmレンズを
使用するので、「望遠効果」が発生する訳では無い。
他の影響としては、センサーサイズが小さくなると
ボケ量が減る(被写界深度が深くなる)というのが光学原理
ではあるのだが、デジタルにおける許容錯乱円の定義が
従前より、ずっと曖昧なままだ。オリンパスの公式見解では
「μ4/3機の許容錯乱円は、35mm判フィルムの丁度半分」
とWEB等に記載されているが、この値で計算しても、なんだか
実際の被写界深度の感覚とは、ずいぶん異ってしまう。
また冒頭に述べたような「縮小効果」なども絡んできて、
極めてややこしい。
被写界深度の件は深追いしないのが賢明だ。近年では私は、
全てフルサイズ換算として被写界深度を考慮している。
(=銀塩フルサイズ機での許容錯乱円を計算上用いる)
さて、μ4/3機に50mm標準レンズを装着して100mm相当の
画角で使う事は、その効果や弱点を十分に認識して使う
ならば、あまり問題にはならない。
が、弱点というのも特には無く、画角が変わる程度であるが
それは機材の弱点とは言えず、撮る側の感覚の問題であろう。
例えば、μ4/3機で使用時に「50mmの標準画角で使いたい」
という市場ニーズも確かにある為、25mmという焦点距離の
μ4/3用レンズも実際に存在している。私も何本かは所有して
いが、今度は、50mm標準画角なのに、あまり被写界深度
が浅くならない(=焦点距離が短い、開放F値があまり小さく
無い等の理由がある)場合もあって、逆に50mm/f1.4を
フルサイズ機(または銀塩35mm判)で使う場合に比べて、
違和感を持ってしまうのだ。
Clik here to view.
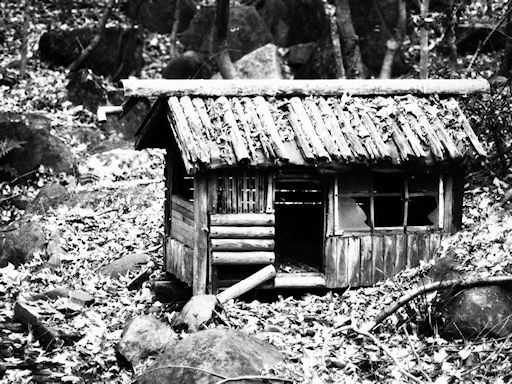
まず長所だが、F1.4という大口径レンズでありながら、
フィルター系がφ49mmと小型、そして軽量である事だ。
オリンパスのOM用交換レンズは、同一焦点距離でも
大口径版と小口径版が多く並行ラインナップされていて、
その殆どが、大口径版がφ55mm、小口径版がφ49mmに
フィルター径が統一されている。
これは当時の、天才と言われた設計技師「米谷氏」による
拘りの「標準化思想」であろう、1970年代の他社では、
いや、それ以降、現代に至るまで、各社において、
「交換レンズのフィルター径を統一する」という思想を
実現した例は他には殆ど無い。(注:銀塩時代のニコンが
多くの交換レンズをφ52mmで統一していた前例はある。
また、銀塩時代のキヤノンにも標準化思想はあった。
が、その後はそういう傾向は無い。1970年代前後の
高度成長期のような製造業の効率化のノウハウが、現代の
日本では失われてしまった事が理由なのかも知れない。
ただまあ、ごく近年のTAMRONでは、SP単焦点や、DiⅢ型
広角単焦点シリーズで、フィルター径統一の風潮がある)
で、本OM50/1.4は、スペック的には「大口径」の部類だが、
フィルター径は、小口径版のφ49mmだ。
ただ、ここからは短所の話だが、F1.4もの大口径レンズで
フィルター径を小型化する、すなわち前玉を小型化する
事は設計上からは難しいと思う。
F値の計算だが、レンズの焦点距離÷(有効)瞳径
で決まる。
焦点距離が50mmレンズの場合、瞳径(ほぼ前玉の直径だ)
がφ25mmであればF2、φ35mmであれば約F1.4となる。
つまり、フィルター径がφ49mmであれば、前玉として
φ35mm(以上)のレンズをその中に収めなければならず、
その余裕があまり無い訳だ。
それに、前玉の直径がそのまま有効瞳径になるという訳でも
なく、若干の効率の悪さがあるので、実際の設計上では
前玉はもう少し大きく余裕を持たせた構造になるだろう。
これがもしフィルター径φ55mmであれば、多少の大きさの
余裕があるので、レンズの設計上や構造上では楽な訳だ。
また、F値(口径比)以外でも、収差補正等に係わる前玉
レンズの屈折率の選択などで、色々と課題が出るだろう。
それを逆に言えば、前玉やフィルター径の小さい大口径
レンズは、必ず設計上で無理がある、という事に繋がる。
だから、本OM50mm/F1.4や類似スペックのMINOLTA New MD
50mm/F1.4という小型化レンズは、ボケ質の破綻が発生したり
逆光耐性や口径食が厳しい等、小型化に反して、複数の
問題点が発生する事は「トレードオフ」で、やむを得ない。
まあでも、この時代(1970年代)は、一眼レフの普及化を
狙って、小型化が推進された時代である。
その急先鋒はOLYMPUSの「OMシリーズ」であり、さらには
PENTAX Mシリーズ等が小型化に追従した歴史がある。
それらの小型軽量一眼レフに従来型の大型の標準レンズ
(例、前記MINOLTA MC50mm/f1.4 フィルター径φ55m)
を付けて売る訳にはいかない。
いかにもアンバランスだし、カメラだけ小型化しても
トータルの軽量化メリットが出ないからだ。
だから(MF一眼レフ)カメラの小型化には、必ずレンズの
小型化も必須なのだ、これは当時最軽量のOM-1を上回る
目標で開発されたPENTAX MXが、OM-1から4年も遅れて
発売された歴史も、その事実を示している。
すなわちMXだけであれば、恐らくもっと早く開発できた事
だろうが、同時に従来のP(K)型のPENTAX 交換レンズを
全て小型の「M型」に置き換える必要があったからだ。
これは極めて大変な開発作業であり、時間がかかったのも
やむを得ないと思う。
Clik here to view.

ちょっとマニア受けがしないレンズとなっている。
その理由は、小型軽量のOMシリーズに合わせるには、
本レンズよりもさらに軽量な、OM50/1.8が適切だからだ。
なお、OM50/1.8は、下手をすれば本OM50/1.4よりも描写力
に優れる銘レンズだと思う。同レンズは過去2度所有して
いたのだが、現在所有しているOM50/1.8は、カビの発生で
フレアなど描写力が低下している(ミラーレス・マニアックス
第26回記事)為、本シリーズ記事では、MFの50mm/f1.8の
予選リーグでは、「欠場」で、取り上げないかも知れない。
---
さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における
予選Aブロック「MF50mm/f1.4 Part1」の記事は終了だ、
次回の本シリーズ記事は、
予選Bブロック「AF50mm/f1.8級」となる予定だ。