高いコストパフォーマンスと付随する性能を持った優秀な
写真用交換レンズを、主にコスパ面から評価したBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回もランクインしたレンズを順に紹介して行こう。
(ランキングの決め方は第1回記事を参照)
---
第12位
評価得点 4.05 (内、コスパ点 4.0)
![c0032138_17114337.jpg]()
レンズ購入価格:18,000円(中古)
使用カメラ:PANASONIC LUMIX DMC-GX7(μ4/3機)
ハイコスパ第5回記事で紹介、またミラーレス名玉編第2回
記事では総合第13位にランクインした、2010年代のμ4/3
専用MF超望遠ミラーレンズ。
![c0032138_17114347.jpg]()
特に有名なのはTAMRON SP500mm/f8 (Model 55B,55BB)
であろうか?(ミラーレス・マニアックス第31回記事)
55Bシリーズは1979~2006年の長きに渡って生産が継続された。
超望遠レンズに対するニーズ(そこには、初級層における
「憧れ」もあるし、野鳥撮影等で実用的にそれを必要とする
ユーザー層も勿論居る)は、昔(銀塩時代)から強くある。
ただ、一般的な500mm級という超望遠レンズにおいては、
「大きく、重く、高価」というレンズであるから、一般層では
よほどの強い必要性が無いと、まず購入は無理だ。
そんな銀塩時代のニーズを簡便に満たしてくれたのが
「ミラーレンズ」である。レンズとは言うが、光学的には
ガラスレンズの光の屈折による製品では無く、主体は反射鏡
(ミラー)により光を収束させる「反射光学系」による物だ。
(勿論、一部にレンズも含まれている、後述の反射望遠鏡
での接眼部(アイピース)のような感じだ)
この原理はニュートンの反射望遠鏡(1668年)の発明による。
日本では江戸時代頃の昔の話だ。
で、MF時代のミラー(レンズ)は、描写力がスペシャルと
言う訳では無かった。が、勿論、ミラーレンズや反射望遠鏡
の全部が描写力に問題がある訳では無い。
現代における天体観測用の大型望遠鏡は、その殆ど全てが
反射式であり、屈折式はむしろ稀なのだ、それは製造上や設置
(重量)上の問題もあるだろうが、基本原理的には反射光学系
が屈折光学系に劣る訳では無い。
いやむしろ、ニュートンは屈折望遠鏡に発生する「色収差」
を嫌って、それを解消する為に反射望遠鏡を発明したのだ。
でもまあ、上記の写真用ミラーレンズ、例えば55B/55BBや
他社のミラー製品が、ガラスレンズの一般望遠レンズに対して
描写力等の課題があったのは確かだと思う。恐らくはコストや
製造技術上等の問題で、あまり高画質な仕様の製品を作る事が
出来なかったのであろう(それをすると、むしろガラスレンズ
型よりも高価になってしまうかも知れない)
まあそんな訳で、ミラー(レンズ)の人気は少しづつ翳りが
出てくる。AF対応製品を作るのが困難(唯一MINOLTAで実用化
したAF製品が1本ある。未所有)だった事もあり、1990年代の
AF時代以降は、忘れ去られたカテゴリーの製品となっていた。
2000年代位にはKENKO等から何機種かの安価なミラー(レンズ)
が発売されたが、その頃のデジタル時代の新規ユーザー層からは
「トイレンズの一種」と見なされてしまったかも知れない、
これらが話題になる事も殆ど無かった。
こういう状況の中、2010年代発売の本Reflex 300mm/f6.3
であるが、実にひさしぶりの本格派ミラー(レンズ)だ。
旧来のミラーよりも大幅に進化した点がいくつかあり、それは
小型軽量化、電子接点搭載、最短撮影距離の短縮、画質の改善、
通常フィルターの使用可、がある。
![c0032138_17114339.jpg]()
いる他、換算焦点距離が2倍となる事により、600mm相当の
超望遠画角が簡単に得られるという利点に繋がる。
なお、PANASONIC機に備わっている優秀なデジタル拡大機能
(デジタルズーム、デジタルテレコン)を併用すれば、
600mm~1200mm/F6.3(テレコン無し)
1200mm~2400mm/F6.3(テレコン2倍)
2400mm~4800mm/F6.3(テレコン4倍)
の、都合3種類の連続可変型超々望遠ズームとして実質的に
使用する事ができる。
なお、今回使用のDMC-GX7では内蔵手ブレ補正が入っているが
デジタル拡大使用時でも、拡大率に応じた手ブレ補正焦点距離
設定の再入力は必要ない。
過去記事でそうした記述があった場合は、誤りであるので
ここで訂正する(ミラーレス・クラッシックス第12回記事、
GX7の回で、その詳細を述べている)
ただ、本レンズで、2倍拡大での1200mmを超える焦点距離以上
では、実用的には長すぎて使用できないし、内蔵手ブレ補正
も精度の面で不安定となってくる。
手持ち撮影での実用限界は、手ブレ補正機能が有っても無くても、
経験的(実験的)には、およそ1500mm迄という所だ、
これを越える換算焦点距離は、まず使えない。
![c0032138_17114326.jpg]()
弱点の多くを解消している点だ。
特に最短撮影距離の短縮(80cm)は非常に大きな利点となり、
望遠型マクロ(ワーキング・ディスタンスを大きく取れる)
となる事で、フィールド(屋外)自然撮影全般に適している。
(遠くの野鳥等から、近くの花等まで、なんでも撮れる)
弱点もいくつかある、まず開放F値がF6.3と固定な事だ、
これはミラー(レンズ)全般に開放F値が固定であるが、
それにより被写界深度の調整が困難だ。
「困難」というのは「不可能」という話ではなく、例えば
被写界深度を深くしようとした際、たとえ絞りが無くても、
「撮影距離を離し、その分、デジタルズームで拡大する」
という高度なデジタル技法で代替できる。
(トリミングと等価ではあるが、後編集の手間が大幅に減る
事と、撮影時にボケ質破綻を確認・固定できる事が長所だ)
続く弱点だが、描写力はだいぶ改善されたとは言え、依然まだ
屈折光学系に比べると劣っている。
特に解像感が低く感じられる事、それからこれは作画上の意図
によりけりだが、ミラー特有の「リングボケ」が発生する事だ。
![c0032138_17114264.jpg]()
以降やDMC-G6以降のPANA機であれば、優秀なピーキング機能が
常時使える。OLYMPUS機では、OM-D E-M1以降の機種で
いずれかのファンクションボタンに、その機能を設定すれば
ピーキングでのMFアシストが可能だ、ただ、操作性の観点
から言えば、常時それが可能なPANA機の方が使い易いだろう。
(注:本レンズ使用に限り、電子接点からの情報伝達により
OM-D E-M1やE-M5 MarkⅡ等では、MFアシストの拡大OFF、
ピーキングONの設定で、ピーキング機能が常時利用可能)
そして、本Reflex 300mm/f6.3の様々な長所を考慮すれば
これらの弱点は微々たるものだ、
おまけに小型軽量で価格も安価である。
この為、ミラーレス名玉編でも、本ハイコスパ名玉編でも
どちらにも上位にランクインするという結果になっている。
本Reflex 300mm/f6.3は、μ4/3機ユーザーであれば、
初級層から上級層まで必携のレンズであろう。
---
第11位
評価得点 4.10 (内、コスパ点 4.5)
![c0032138_17115626.jpg]()
レンズ購入価格:20,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-5(APS-C機)
ハイコスパ第14回記事で紹介の、1990年代のAF単焦点
中望遠等倍マクロレンズ。
今更説明の必要も無い定番のマクロレンズだ。
![c0032138_17115679.jpg]()
(ミラーレス・マニアックス第8回記事)で、TAMRONの名を
世に知らしめた「90マクロ」シリーズは、その後AF化や
等倍化といったモデルチェンジを繰り返しながら、
現代に至るまで、およそ40年間もの超ロングセラー製品である。
当然、バリエーションも多いのだが、本72E型は1996年発売の、
「等倍」&「F2.8版」になった最初のレンズだ。
本72E型以降は、光学系に大きな変更は無いが、272E型
(2004年)では、レンズ後群にコーティングを施し、
デジタル一眼レフ対応の「Di型」と称している。
さらに、後年のF004型(2012~2013年発売)やF017型
(2016年)では、内蔵手ブレ補正や超音波モーターが加わって
いる。
(注:F004型では、異常低分散ガラスを採用する等、若干の
光学系の見直しも行われている)
この歴史を良く見ると、2004年から2012/3年まで約9年間も
この「90マクロ」のモデルチェンジが滞った時代がある。
これは恐らくだが、この時代は丁度デジタル一眼レフが
一般層に普及していった時代なのだが、その多くはAPS-C型
センサー機であった(デジタル一眼レフ・クラッシックスの
シリーズ記事群を参照)
APS-C機で使うと、このマクロは約135mm相当の画角となり、
ちょっと長すぎる、と言うイメージもあったのかも知れない。
まあ、だから2009年にはAPS-C機専用のSP60mm/f2 Macro
(Model G005、本シリーズ第9回記事)を発売したのであろう。
そのレンズであればAPS-C機で90mm相当の画角となる訳だ。
「90マクロ」は既に完成度も極めて高いレンズであったので、
慌ててモテルチェンジをする必要もあまり無かったのだろう。
![c0032138_17115697.jpg]()
が再開したか?と言うと、こちらも想像の範疇であるが、
その2012年は「フルサイズ元年」とも言われる程、各社から
多くのフルサイズ・デジタル一眼レフが発売された年である。
だからTAMRONとしても「また90マクロが主流になる」と判断し、
シリーズの強化を図ったのかも知れない。
あるいは、この時代から、一眼レフ市場の縮退が始まって
いて、各社のレンズは高付加価値化、すなわち値上げされた
訳であり、TAMRONもその為に手ブレ補正や超音波モーター
を搭載し「高付加価値化」したのであろう。
しかし、個人的な意見としては、「90マクロ」において
F004型から付加された手ブレ補正や超音波モーターの機能は、
ちょっと製品コンセプト的には矛盾を感じる。
何故ならば、マクロ撮影ではMFを使用するケースが主であり
AFの強化は中遠距離撮影にのみ効果がある事。それから、
マクロ撮影でのブレは、撮影者の手ブレよりも被写体ブレの
問題が遙かに大きい事。そして、撮影者側がブレるとしても
手ブレ補正機構が効果を発揮する上下左右方向のブレではなく、
むしろ被写体までの距離が微妙に変化する「前後ブレ」の方が
問題になるからだ。(それは手ブレ補正機構では防げない)
まあでも、メーカー側としては、手ブレ補正や超音波モーター
といった「付加価値」をつけないと、前モデルとの差別化が
出きず、すなわち値上げも出来ない。つまりモデルチェンジに
かかる費用を回収する為にも、あえて「付加価値」を付与して
結果的に利益を上げる(値上げする)必要がある訳だ。
(例:272E型の定価は68,000円、F004型の定価は90,000円)
![c0032138_17115521.jpg]()
無い事から、私は、20年以上も前の古いバージョン(72E型)を
いまだに使い続けている状態だ。
(しかも、2種類のマウントで保有している)
まあでも、レンズ構成の変更の必要が余り無いと言う事は、
それだけ光学系の完成度の高いレンズであると言う事であろう。
本レンズの特徴や注意点等の詳細は、ハイコスパ第14回記事や、
それ以前のミラーレス・マニアックス第31回、第53回記事に
詳しいので、重複する為に割愛する。
一言で言えば、描写力自体に不満は殆ど無いと思うが、
中古購入時に、どの時代のバージョンを買うか?という選択が
あると思う。ただ、前述のようにレンズの描写傾向に大きな
変更も無いし、付加価値要素も実用価値は微妙である。
結局、予算に応じて好きな時代(仕様)のものを選べば良い。
AF/F2.8版以降の中古相場は、バージョンや程度に応じて、
1万円台前半~6万円位になると思う。
まあ、バージョンの選択はともかく、一眼レフユーザーの
誰もが必携のマクロレンズだ。
・・とは言え、本レンズを所有していないマニアや中上級者を
探す方が難しいであろうが。
---
さて、ここからBEST10に突入だ。
第10位
評価得点 4.20 (内、コスパ点 5.0)
![c0032138_17120767.jpg]()
レンズ購入価格:8,000円(新古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
2012年に発売されたSIGMA初のミラーレス機専用交換レンズ
(DNシリーズ)のうちの1本(ハイコスパ第25回記事等で紹介)
μ4/3用とSONY E(NEX,APC-C専用)との2種類のマウント用
で発売されていたので、換算画角は、それぞれ60mmまたは
45mm相当の、ほぼ標準画角となる。
![c0032138_17120703.jpg]()
*エントリーレンズ並みの低価格
*小型軽量な単焦点レンズ
*高画質である。このDNシリーズのレンズ群の仕様や
レンズ構成はSIGMAの高級コンパクト(APS-Cセンサー)の
「DPシリーズ」の搭載レンズと同等の仕様のものが多い。
さて、本レンズは、発売後翌年に早くもリニューアルされ、
Art Lineと呼ばれるSIGMAの製品ラインナップの中では
高画質(高解像力)やボケ質などの描写性能を優先した
カテゴリーに属した、という歴史がある。
まず、本レンズの発売時2012年は、その前後の2010~2014年
頃にミラーレス機(ミラーレス一眼)が、市場シェアを大幅に
伸ばし、一眼レフ市場を喰い尽くす勢いであった事が背景に
ある。
μ4/3機の登場(2008年末)より、一眼レフ陣営の各社は、
当初、ミラーレス機の市場に懐疑的であったと思われるが、
実際の伸びは凄く、2012年の時点では、ほぼ全ての一眼レフ
メーカーもミラーレス機市場に参入せざるを得なくなっていた。
カメラメーカーは市場戦略が極めて難しかった時代ではあるが
レンズメーカーも同様だ。従来のように一眼レフ用のレンズ
だけを作っていて済む訳が無い。ミラーレス機用レンズへの
対応あるいは方針策定も急務であった事だろう。
ただ、ミラーレス機のユーザー層のニーズが良く掴めない。
これはカメラメーカー側でも同様であり、PANAのGシリーズや
SONY NEXシリーズの、この頃(2012年)迄の製品ターゲット
やコンセプトは、くるくると変化していたように思える。
そして、この年2012年から、一眼レフ陣営(コンパクト機を
含む)の巻き返しが図られる。
製造技術の進歩で、従来より低コストで大型化が可能となった
撮像素子(センサー)を搭載したフルサイズ・デジタル一眼
レフや、大型センサー搭載コンパクトが次々と市場にリリース
され始める。
ミラーレス陣営は、少なくともμ4/3は規格でセンサーサイズ
が4/3型に決められている為、この動きに追従できない。
まあそれが一眼レフ陣営が考えたミラーレス対抗策なのだ。
SONYでは2012年迄APS-Cセンサーで展開していたNEXシリーズ
を拡張し、同じEマウントでフルサイズ化したα7(/R)を
翌2013年にリリースする。(同時にシリーズ名もαに統一)
まあ、SONYは撮像センサーを他社に供給する立場だ、
センサー技術のロードマップ(注:製品が将来的に進化して
いく様子を年表化した開発計画の事)を自社では当然理解して
いたから、近い将来のフルサイズ化を見据えて、NEXの時代の
Eマウントはフルサイズセンサーが入る大きさで設計していた。
SIGMAも、一端ミラーレス用に傾きかけたレンズの市場戦略を
また一眼レフ用を主軸とする事に方向転換しなくてはならない。
なにせ今後は、フルサイズ機や、超高画素機が、次々と出て
くる状況が予想されるからだ。
SIGMAは自社のレンズ群を大幅に見直し、多くのレンズ機種を
ディスコン(生産中止)とし、新たに、アート、スポーツ、
コンテンポラリーの3つの分野にカテゴリー分けし、
ユーザー毎のレンズの使用目的を2013年頃に明確化した。
まあ、使用目的別というのは良い考え方ではあるのだが、
高付加価値化戦略(=利益の出ないレンズは作らない)も
あったと思う。
![c0032138_17120721.jpg]()
価格帯(25,000円程度)から言えば、高コスパをかかげる
「コンテンポラリー」に分類されてもおかしく無いのだが、
単焦点である事、高画質である事、等から「Art Line」に
分類される事になったのであろう。(自社高級コンパクトの
DPシリーズ搭載レンズもあったから、これをコンテンポラリー
とは呼び難い、DPシリーズの付加価値を落としてしまうからだ)
しかし、旧来と同じレンズを「これは今日からArt Lineです」
とは流石に言えない。
そこで、本レンズ EX DN型の弱点であった外観のチープさを
改善し、高級感のある外装でモデルチェンジした物が、
2013年発売のArt (A) 30mm/f2.8 DNである。
こういう場合に旧製品は、「新古品」扱いとして中古市場に
大量放出される事がある。とは、以前の記事でも述べた通り。
本レンズもそうなり、未使用の新古品として流通した。
結果的に僅かに8,000円という格安相場で入手出来た訳だ。
で、本レンズの描写力はあまり問題点を感じない。
低価格レンズながら、極めて良く写るレンズだ。
![c0032138_17120779.jpg]()
つまり開放F値がF2.8、最短撮影距離が30cmは、いずれも
平凡な仕様であり、被写界深度を浅くする撮影が困難だ。
近接撮影をすれば、勿論被写界深度を浅くできるのだが、
無限回転式のピントリングのMF操作性の弱点と、ミラーレス機
のコントラストAFの精度不足の問題が重くのしかかる。
AFについては、電源OFF時にレンズがカタカタと鳴るという
弱点がある、これは実用上は問題無しとも言えるのだが、
私は非常に気になるし、なんだか安っぽい。
安っぽいと言えば、外観のチープさもある。後継機のArt型
では若干改善されているが、本レンズでは少々問題だ。
また、DNシリーズでは、本30/2.8のみフードが付属して
おらず別売だ。
まあ、細かい弱点はあるが、価格から言えば、殆どが許せて
しまうハイコスパレンズである事は間違い無い。
---
第9位
評価得点 4.25 (内、コスパ点 4.0)
![c0032138_17121727.jpg]()
レンズ購入価格:42,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ハイコスパ第1回、ミラーレス名玉編第4回(総合第3位)
で紹介の、2009年発売のAPS-C機専用AF単焦点標準
(中望遠画角)レンズ。
特徴を一言で言うと、「高性能レンズ」である。
これは「★(スター)のマークが付いているから」といった
事が根拠なのではなく、そう言う事は、むしろどうでも良い。
(注:PENTAX では銀塩時代の昔から高性能レンズに★の
マークを付けて販売していた。同様の例として、他社では
CANONの「Lレンズ」、TAMRONの「SPレンズ」、
MINOLTA/SONYの「Gレンズ」、OLYMPUSの「PROレンズ」
等がある)
メーカーが高性能レンズの印(しるし)をつけて、どう言おうが
最終的に品質の判断をするのは、あくまでユーザー側だ。
性能の評価は、メーカーや評論家に押し付けられる物では無い。
むしろ、「そういう印をつけて価格を吊り上げている」と
いった悪印象があるので、個人的には、そうしたレンズを
出来るだけ買わないようにしている位だ。
![c0032138_17121757.jpg]()
FA★85mm/f1.4 (ミラーレス名玉編第1回、総合第18位)に
極めて良く似ている。本レンズはデジタル(APS-C)機で
82.5mm相当の換算画角となる事から、「FA★85/1.4の
デジタル代替レンズである」と個人的には定義している。
名玉FA★85/1.4は、1990年代末位にFA77mm/f1.8Limited
(ミラーレス名玉編第4回、総合第1位)に置き換わるように
市場から姿を消してしまった(生産中止)
まあFA77/1.8は確かにトップクラスの性能のレンズなのだが、
FA★85/1.4も捨てがたい。
そこで、デジタルでは使い難くなったFA★85/1.4
(注:この意味だが、PENTAXでは2016年のK-1の発売まで
全てのデジタル一眼レがAPS-機であった為、換算画角が
約127mm相当となるFA★85/1.4は、本来威力を発揮する
人物撮影の分野では、やや長すぎる焦点距離(画角)となる為)
を代替する、と言う点では、本DA★55/1.4は最適のレンズと
なった訳だ。
SDM(超音波モーター)仕様は、迅速なAF動作をもたらすが
AF精度がとても高いという訳でもない。
それとこの超音波モーターは、可聴域の高周波音を発する為
撮影中に「チーッ」と言う耳障りな音が聞こえる弱点を持つ。
まあでも、独特なボケ質などは好感が持てる、
SDMの弱点は不問としよう。
![c0032138_17121755.jpg]()
本レンズが発売された2000年代末では、50mm/f1.4級レンズは
銀塩時代からの設計を引き継いだ、古いが、技術がこなれていて
完成度の高い物ばかりで、当然ながら価格も安価であり、
中古でも2万円程度迄で「よりどりみどり」であった状況だ。
しかし、本レンズ以降の時代では、最新設計の非常に高価な
単焦点標準レンズも各社から色々と出始める。
代表的な新鋭AF標準レンズを2つほど上げれば・・
NIKON AF-S NIKKOR 58mm/f1.4G
(2013年発売、定価210,000円税別、後日紹介予定)
SIGMA Art 50mm/f1.4 DG HSM
(2014年発売、定価127,000円税別、レンズマニアックス第2回)
等がある。
それらに比べると本DA★55/1.4(発売時実勢価格約80,000円)
はまだ安価な方ではある。が、後年のそれらは、確かに高画質
なのかも知れないが、開発費の上乗せが大きいのだろうか?
そう安易に買える価格帯ではなくなってしまった。
なお、カールツァイスのブランドからは、さらに非常に高価な
新鋭単焦点標準レンズが発売されている。
また、さらに後年ではPENTAXやTOKINAからも、高価格の
標準レンズが次々と発売されている。
もし、こう言った価格帯が新標準レンズの「常識」となって
しまうと、正直困る。
「AF単焦点標準レンズは中古で2万円」これがほんの10年程前
までの常識(相場)であり、それでも、完成度の高いそれらは
十分に使えていたのだ。
まあ「高画素化時代への対応」と言う大義名分はあったのかも
知れないが、要は値段の高さは開発費のコスト回収が主であろう。
そして、あまり数が売れないと思われるカテゴリーのレンズ
だけに、余計にレンズ1本あたりの開発費上乗せが多額になる、
と言う厳しい状態だ。
ただまあ、本DA★55/1.4も、発売後10年を超えるくらいの
現代においては、それらの新鋭超高性能単焦点標準に比べると
解像度チャート等での数値評価上では、さすがに若干見劣り
する状態になってきたのであろう。
PENTAXも2016年にフルサイズ一眼レフを発売した所では
あるが、高性能なフルサイズ対応単焦点標準が存在しない。
FA50mm/f1.4(ミラーレス第23回記事)があるが、これは
銀塩時代の1990年代の古いレンズである、いくら当時から
完成度が高いレンズだとは言え、発売後四半世紀を超えれば
仕様的老朽化(周囲の新製品が皆、高性能化して来る)は、
どうしても避けられない。
PENTAXでは、2018年にHD PENTAX-D FA★50mm/f1.4
SDM AWを発売(末所有)、これも定価18万円と高価な
標準レンズで、超高画素対応(高解像力)をうたっている。
ちなみに、超高画素対応と言っても、現在のフルサイズ機の
最大5000万画素位での、ピクセルピッチと、レンズの
解像力(LP/mm)を計算してみると、まだ若干余裕がある。
すなわち、まだ従来レンズでも高性能な物を使えば何とか
なる状況なのだが・・もし近い将来に画素数の向上が急速に
進展した場合、そこから対応レンズを開発していたのでは
間に合わない。
間に合わないのは開発の時間のみならず、ユーザー側の
「意識」の変化も、それには急には追いつか無いのだ。
そこで、今のうちから早目に
「超高画素カメラには、新世代の高解像力レンズが必須!」
と言う新たな「常識」を、ユーザー層に刷り込んでいかなくては
ならない。
一般ユーザーで解像力の検証や計算が出来る人は皆無だろう。
だから、ちょっと凝ったマニア等により、ちゃんと計算されて、
その辺りが「あれ?」と疑問に思われない内に、ユーザーには、
そのように思い込んで貰わないとならないのであろう。
![c0032138_17121641.jpg]()
結局はユーザー側が、その価格や品質を納得して新型レンズを
買うならば、それで良い、という事だ。
「新製品は高性能だ、だから高いんだ」と、ユーザー層には
単純に、そう思い込んでもらって、メーカーに利益を還元して
いかないと、カメラ市場そのものが崩壊してしまう・・
さて、裏の事情はそのあたりまでで・・
ともかく、本DA★55/f1.4は見事にランキングのベスト10入り
を果たしたハイコスパレンズである。
まだ若干中古相場は高目の推移ではあるが、仮に3万円台
前半位で入手できるのであれば、もう文句の無い、お買い得
レンズとなると思う。
(追記:類似スペックの、新鋭中国製レンズ、「七工匠
55mm/F1.4」(2018年頃発売、実売16000円前後)も
悪く無い。これは銀塩時代のプラナー系85mm/F1.4構成を
スケールダウンしたAPS-C以下ミラーレス用MFレンズだ。
そのレンズも、これくらいの上位ランキングに入って来ても
おかしく無かったが、本記事執筆時点では、購入および
評価が間に合っていなかった→後日別記事で紹介予定)
----
今回はこのあたりまでで、次回記事では、いよいよBEST8
となる、引き続きランキングレンズを順次紹介していこう。
写真用交換レンズを、主にコスパ面から評価したBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回もランクインしたレンズを順に紹介して行こう。
(ランキングの決め方は第1回記事を参照)
---
第12位
評価得点 4.05 (内、コスパ点 4.0)

レンズ購入価格:18,000円(中古)
使用カメラ:PANASONIC LUMIX DMC-GX7(μ4/3機)
ハイコスパ第5回記事で紹介、またミラーレス名玉編第2回
記事では総合第13位にランクインした、2010年代のμ4/3
専用MF超望遠ミラーレンズ。

特に有名なのはTAMRON SP500mm/f8 (Model 55B,55BB)
であろうか?(ミラーレス・マニアックス第31回記事)
55Bシリーズは1979~2006年の長きに渡って生産が継続された。
超望遠レンズに対するニーズ(そこには、初級層における
「憧れ」もあるし、野鳥撮影等で実用的にそれを必要とする
ユーザー層も勿論居る)は、昔(銀塩時代)から強くある。
ただ、一般的な500mm級という超望遠レンズにおいては、
「大きく、重く、高価」というレンズであるから、一般層では
よほどの強い必要性が無いと、まず購入は無理だ。
そんな銀塩時代のニーズを簡便に満たしてくれたのが
「ミラーレンズ」である。レンズとは言うが、光学的には
ガラスレンズの光の屈折による製品では無く、主体は反射鏡
(ミラー)により光を収束させる「反射光学系」による物だ。
(勿論、一部にレンズも含まれている、後述の反射望遠鏡
での接眼部(アイピース)のような感じだ)
この原理はニュートンの反射望遠鏡(1668年)の発明による。
日本では江戸時代頃の昔の話だ。
で、MF時代のミラー(レンズ)は、描写力がスペシャルと
言う訳では無かった。が、勿論、ミラーレンズや反射望遠鏡
の全部が描写力に問題がある訳では無い。
現代における天体観測用の大型望遠鏡は、その殆ど全てが
反射式であり、屈折式はむしろ稀なのだ、それは製造上や設置
(重量)上の問題もあるだろうが、基本原理的には反射光学系
が屈折光学系に劣る訳では無い。
いやむしろ、ニュートンは屈折望遠鏡に発生する「色収差」
を嫌って、それを解消する為に反射望遠鏡を発明したのだ。
でもまあ、上記の写真用ミラーレンズ、例えば55B/55BBや
他社のミラー製品が、ガラスレンズの一般望遠レンズに対して
描写力等の課題があったのは確かだと思う。恐らくはコストや
製造技術上等の問題で、あまり高画質な仕様の製品を作る事が
出来なかったのであろう(それをすると、むしろガラスレンズ
型よりも高価になってしまうかも知れない)
まあそんな訳で、ミラー(レンズ)の人気は少しづつ翳りが
出てくる。AF対応製品を作るのが困難(唯一MINOLTAで実用化
したAF製品が1本ある。未所有)だった事もあり、1990年代の
AF時代以降は、忘れ去られたカテゴリーの製品となっていた。
2000年代位にはKENKO等から何機種かの安価なミラー(レンズ)
が発売されたが、その頃のデジタル時代の新規ユーザー層からは
「トイレンズの一種」と見なされてしまったかも知れない、
これらが話題になる事も殆ど無かった。
こういう状況の中、2010年代発売の本Reflex 300mm/f6.3
であるが、実にひさしぶりの本格派ミラー(レンズ)だ。
旧来のミラーよりも大幅に進化した点がいくつかあり、それは
小型軽量化、電子接点搭載、最短撮影距離の短縮、画質の改善、
通常フィルターの使用可、がある。

いる他、換算焦点距離が2倍となる事により、600mm相当の
超望遠画角が簡単に得られるという利点に繋がる。
なお、PANASONIC機に備わっている優秀なデジタル拡大機能
(デジタルズーム、デジタルテレコン)を併用すれば、
600mm~1200mm/F6.3(テレコン無し)
1200mm~2400mm/F6.3(テレコン2倍)
2400mm~4800mm/F6.3(テレコン4倍)
の、都合3種類の連続可変型超々望遠ズームとして実質的に
使用する事ができる。
なお、今回使用のDMC-GX7では内蔵手ブレ補正が入っているが
デジタル拡大使用時でも、拡大率に応じた手ブレ補正焦点距離
設定の再入力は必要ない。
過去記事でそうした記述があった場合は、誤りであるので
ここで訂正する(ミラーレス・クラッシックス第12回記事、
GX7の回で、その詳細を述べている)
ただ、本レンズで、2倍拡大での1200mmを超える焦点距離以上
では、実用的には長すぎて使用できないし、内蔵手ブレ補正
も精度の面で不安定となってくる。
手持ち撮影での実用限界は、手ブレ補正機能が有っても無くても、
経験的(実験的)には、およそ1500mm迄という所だ、
これを越える換算焦点距離は、まず使えない。

弱点の多くを解消している点だ。
特に最短撮影距離の短縮(80cm)は非常に大きな利点となり、
望遠型マクロ(ワーキング・ディスタンスを大きく取れる)
となる事で、フィールド(屋外)自然撮影全般に適している。
(遠くの野鳥等から、近くの花等まで、なんでも撮れる)
弱点もいくつかある、まず開放F値がF6.3と固定な事だ、
これはミラー(レンズ)全般に開放F値が固定であるが、
それにより被写界深度の調整が困難だ。
「困難」というのは「不可能」という話ではなく、例えば
被写界深度を深くしようとした際、たとえ絞りが無くても、
「撮影距離を離し、その分、デジタルズームで拡大する」
という高度なデジタル技法で代替できる。
(トリミングと等価ではあるが、後編集の手間が大幅に減る
事と、撮影時にボケ質破綻を確認・固定できる事が長所だ)
続く弱点だが、描写力はだいぶ改善されたとは言え、依然まだ
屈折光学系に比べると劣っている。
特に解像感が低く感じられる事、それからこれは作画上の意図
によりけりだが、ミラー特有の「リングボケ」が発生する事だ。

以降やDMC-G6以降のPANA機であれば、優秀なピーキング機能が
常時使える。OLYMPUS機では、OM-D E-M1以降の機種で
いずれかのファンクションボタンに、その機能を設定すれば
ピーキングでのMFアシストが可能だ、ただ、操作性の観点
から言えば、常時それが可能なPANA機の方が使い易いだろう。
(注:本レンズ使用に限り、電子接点からの情報伝達により
OM-D E-M1やE-M5 MarkⅡ等では、MFアシストの拡大OFF、
ピーキングONの設定で、ピーキング機能が常時利用可能)
そして、本Reflex 300mm/f6.3の様々な長所を考慮すれば
これらの弱点は微々たるものだ、
おまけに小型軽量で価格も安価である。
この為、ミラーレス名玉編でも、本ハイコスパ名玉編でも
どちらにも上位にランクインするという結果になっている。
本Reflex 300mm/f6.3は、μ4/3機ユーザーであれば、
初級層から上級層まで必携のレンズであろう。
---
第11位
評価得点 4.10 (内、コスパ点 4.5)

レンズ購入価格:20,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX K-5(APS-C機)
ハイコスパ第14回記事で紹介の、1990年代のAF単焦点
中望遠等倍マクロレンズ。
今更説明の必要も無い定番のマクロレンズだ。

(ミラーレス・マニアックス第8回記事)で、TAMRONの名を
世に知らしめた「90マクロ」シリーズは、その後AF化や
等倍化といったモデルチェンジを繰り返しながら、
現代に至るまで、およそ40年間もの超ロングセラー製品である。
当然、バリエーションも多いのだが、本72E型は1996年発売の、
「等倍」&「F2.8版」になった最初のレンズだ。
本72E型以降は、光学系に大きな変更は無いが、272E型
(2004年)では、レンズ後群にコーティングを施し、
デジタル一眼レフ対応の「Di型」と称している。
さらに、後年のF004型(2012~2013年発売)やF017型
(2016年)では、内蔵手ブレ補正や超音波モーターが加わって
いる。
(注:F004型では、異常低分散ガラスを採用する等、若干の
光学系の見直しも行われている)
この歴史を良く見ると、2004年から2012/3年まで約9年間も
この「90マクロ」のモデルチェンジが滞った時代がある。
これは恐らくだが、この時代は丁度デジタル一眼レフが
一般層に普及していった時代なのだが、その多くはAPS-C型
センサー機であった(デジタル一眼レフ・クラッシックスの
シリーズ記事群を参照)
APS-C機で使うと、このマクロは約135mm相当の画角となり、
ちょっと長すぎる、と言うイメージもあったのかも知れない。
まあ、だから2009年にはAPS-C機専用のSP60mm/f2 Macro
(Model G005、本シリーズ第9回記事)を発売したのであろう。
そのレンズであればAPS-C機で90mm相当の画角となる訳だ。
「90マクロ」は既に完成度も極めて高いレンズであったので、
慌ててモテルチェンジをする必要もあまり無かったのだろう。

が再開したか?と言うと、こちらも想像の範疇であるが、
その2012年は「フルサイズ元年」とも言われる程、各社から
多くのフルサイズ・デジタル一眼レフが発売された年である。
だからTAMRONとしても「また90マクロが主流になる」と判断し、
シリーズの強化を図ったのかも知れない。
あるいは、この時代から、一眼レフ市場の縮退が始まって
いて、各社のレンズは高付加価値化、すなわち値上げされた
訳であり、TAMRONもその為に手ブレ補正や超音波モーター
を搭載し「高付加価値化」したのであろう。
しかし、個人的な意見としては、「90マクロ」において
F004型から付加された手ブレ補正や超音波モーターの機能は、
ちょっと製品コンセプト的には矛盾を感じる。
何故ならば、マクロ撮影ではMFを使用するケースが主であり
AFの強化は中遠距離撮影にのみ効果がある事。それから、
マクロ撮影でのブレは、撮影者の手ブレよりも被写体ブレの
問題が遙かに大きい事。そして、撮影者側がブレるとしても
手ブレ補正機構が効果を発揮する上下左右方向のブレではなく、
むしろ被写体までの距離が微妙に変化する「前後ブレ」の方が
問題になるからだ。(それは手ブレ補正機構では防げない)
まあでも、メーカー側としては、手ブレ補正や超音波モーター
といった「付加価値」をつけないと、前モデルとの差別化が
出きず、すなわち値上げも出来ない。つまりモデルチェンジに
かかる費用を回収する為にも、あえて「付加価値」を付与して
結果的に利益を上げる(値上げする)必要がある訳だ。
(例:272E型の定価は68,000円、F004型の定価は90,000円)

無い事から、私は、20年以上も前の古いバージョン(72E型)を
いまだに使い続けている状態だ。
(しかも、2種類のマウントで保有している)
まあでも、レンズ構成の変更の必要が余り無いと言う事は、
それだけ光学系の完成度の高いレンズであると言う事であろう。
本レンズの特徴や注意点等の詳細は、ハイコスパ第14回記事や、
それ以前のミラーレス・マニアックス第31回、第53回記事に
詳しいので、重複する為に割愛する。
一言で言えば、描写力自体に不満は殆ど無いと思うが、
中古購入時に、どの時代のバージョンを買うか?という選択が
あると思う。ただ、前述のようにレンズの描写傾向に大きな
変更も無いし、付加価値要素も実用価値は微妙である。
結局、予算に応じて好きな時代(仕様)のものを選べば良い。
AF/F2.8版以降の中古相場は、バージョンや程度に応じて、
1万円台前半~6万円位になると思う。
まあ、バージョンの選択はともかく、一眼レフユーザーの
誰もが必携のマクロレンズだ。
・・とは言え、本レンズを所有していないマニアや中上級者を
探す方が難しいであろうが。
---
さて、ここからBEST10に突入だ。
第10位
評価得点 4.20 (内、コスパ点 5.0)

レンズ購入価格:8,000円(新古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
2012年に発売されたSIGMA初のミラーレス機専用交換レンズ
(DNシリーズ)のうちの1本(ハイコスパ第25回記事等で紹介)
μ4/3用とSONY E(NEX,APC-C専用)との2種類のマウント用
で発売されていたので、換算画角は、それぞれ60mmまたは
45mm相当の、ほぼ標準画角となる。
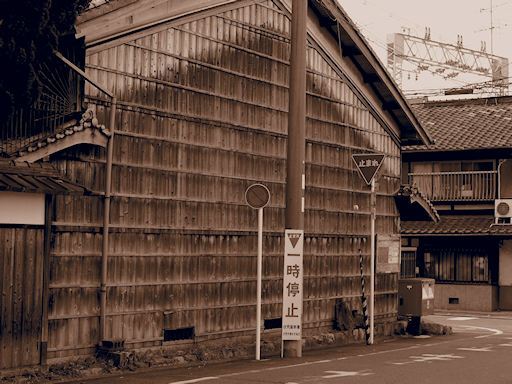
*エントリーレンズ並みの低価格
*小型軽量な単焦点レンズ
*高画質である。このDNシリーズのレンズ群の仕様や
レンズ構成はSIGMAの高級コンパクト(APS-Cセンサー)の
「DPシリーズ」の搭載レンズと同等の仕様のものが多い。
さて、本レンズは、発売後翌年に早くもリニューアルされ、
Art Lineと呼ばれるSIGMAの製品ラインナップの中では
高画質(高解像力)やボケ質などの描写性能を優先した
カテゴリーに属した、という歴史がある。
まず、本レンズの発売時2012年は、その前後の2010~2014年
頃にミラーレス機(ミラーレス一眼)が、市場シェアを大幅に
伸ばし、一眼レフ市場を喰い尽くす勢いであった事が背景に
ある。
μ4/3機の登場(2008年末)より、一眼レフ陣営の各社は、
当初、ミラーレス機の市場に懐疑的であったと思われるが、
実際の伸びは凄く、2012年の時点では、ほぼ全ての一眼レフ
メーカーもミラーレス機市場に参入せざるを得なくなっていた。
カメラメーカーは市場戦略が極めて難しかった時代ではあるが
レンズメーカーも同様だ。従来のように一眼レフ用のレンズ
だけを作っていて済む訳が無い。ミラーレス機用レンズへの
対応あるいは方針策定も急務であった事だろう。
ただ、ミラーレス機のユーザー層のニーズが良く掴めない。
これはカメラメーカー側でも同様であり、PANAのGシリーズや
SONY NEXシリーズの、この頃(2012年)迄の製品ターゲット
やコンセプトは、くるくると変化していたように思える。
そして、この年2012年から、一眼レフ陣営(コンパクト機を
含む)の巻き返しが図られる。
製造技術の進歩で、従来より低コストで大型化が可能となった
撮像素子(センサー)を搭載したフルサイズ・デジタル一眼
レフや、大型センサー搭載コンパクトが次々と市場にリリース
され始める。
ミラーレス陣営は、少なくともμ4/3は規格でセンサーサイズ
が4/3型に決められている為、この動きに追従できない。
まあそれが一眼レフ陣営が考えたミラーレス対抗策なのだ。
SONYでは2012年迄APS-Cセンサーで展開していたNEXシリーズ
を拡張し、同じEマウントでフルサイズ化したα7(/R)を
翌2013年にリリースする。(同時にシリーズ名もαに統一)
まあ、SONYは撮像センサーを他社に供給する立場だ、
センサー技術のロードマップ(注:製品が将来的に進化して
いく様子を年表化した開発計画の事)を自社では当然理解して
いたから、近い将来のフルサイズ化を見据えて、NEXの時代の
Eマウントはフルサイズセンサーが入る大きさで設計していた。
SIGMAも、一端ミラーレス用に傾きかけたレンズの市場戦略を
また一眼レフ用を主軸とする事に方向転換しなくてはならない。
なにせ今後は、フルサイズ機や、超高画素機が、次々と出て
くる状況が予想されるからだ。
SIGMAは自社のレンズ群を大幅に見直し、多くのレンズ機種を
ディスコン(生産中止)とし、新たに、アート、スポーツ、
コンテンポラリーの3つの分野にカテゴリー分けし、
ユーザー毎のレンズの使用目的を2013年頃に明確化した。
まあ、使用目的別というのは良い考え方ではあるのだが、
高付加価値化戦略(=利益の出ないレンズは作らない)も
あったと思う。

価格帯(25,000円程度)から言えば、高コスパをかかげる
「コンテンポラリー」に分類されてもおかしく無いのだが、
単焦点である事、高画質である事、等から「Art Line」に
分類される事になったのであろう。(自社高級コンパクトの
DPシリーズ搭載レンズもあったから、これをコンテンポラリー
とは呼び難い、DPシリーズの付加価値を落としてしまうからだ)
しかし、旧来と同じレンズを「これは今日からArt Lineです」
とは流石に言えない。
そこで、本レンズ EX DN型の弱点であった外観のチープさを
改善し、高級感のある外装でモデルチェンジした物が、
2013年発売のArt (A) 30mm/f2.8 DNである。
こういう場合に旧製品は、「新古品」扱いとして中古市場に
大量放出される事がある。とは、以前の記事でも述べた通り。
本レンズもそうなり、未使用の新古品として流通した。
結果的に僅かに8,000円という格安相場で入手出来た訳だ。
で、本レンズの描写力はあまり問題点を感じない。
低価格レンズながら、極めて良く写るレンズだ。

つまり開放F値がF2.8、最短撮影距離が30cmは、いずれも
平凡な仕様であり、被写界深度を浅くする撮影が困難だ。
近接撮影をすれば、勿論被写界深度を浅くできるのだが、
無限回転式のピントリングのMF操作性の弱点と、ミラーレス機
のコントラストAFの精度不足の問題が重くのしかかる。
AFについては、電源OFF時にレンズがカタカタと鳴るという
弱点がある、これは実用上は問題無しとも言えるのだが、
私は非常に気になるし、なんだか安っぽい。
安っぽいと言えば、外観のチープさもある。後継機のArt型
では若干改善されているが、本レンズでは少々問題だ。
また、DNシリーズでは、本30/2.8のみフードが付属して
おらず別売だ。
まあ、細かい弱点はあるが、価格から言えば、殆どが許せて
しまうハイコスパレンズである事は間違い無い。
---
第9位
評価得点 4.25 (内、コスパ点 4.0)

レンズ購入価格:42,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ハイコスパ第1回、ミラーレス名玉編第4回(総合第3位)
で紹介の、2009年発売のAPS-C機専用AF単焦点標準
(中望遠画角)レンズ。
特徴を一言で言うと、「高性能レンズ」である。
これは「★(スター)のマークが付いているから」といった
事が根拠なのではなく、そう言う事は、むしろどうでも良い。
(注:PENTAX では銀塩時代の昔から高性能レンズに★の
マークを付けて販売していた。同様の例として、他社では
CANONの「Lレンズ」、TAMRONの「SPレンズ」、
MINOLTA/SONYの「Gレンズ」、OLYMPUSの「PROレンズ」
等がある)
メーカーが高性能レンズの印(しるし)をつけて、どう言おうが
最終的に品質の判断をするのは、あくまでユーザー側だ。
性能の評価は、メーカーや評論家に押し付けられる物では無い。
むしろ、「そういう印をつけて価格を吊り上げている」と
いった悪印象があるので、個人的には、そうしたレンズを
出来るだけ買わないようにしている位だ。

FA★85mm/f1.4 (ミラーレス名玉編第1回、総合第18位)に
極めて良く似ている。本レンズはデジタル(APS-C)機で
82.5mm相当の換算画角となる事から、「FA★85/1.4の
デジタル代替レンズである」と個人的には定義している。
名玉FA★85/1.4は、1990年代末位にFA77mm/f1.8Limited
(ミラーレス名玉編第4回、総合第1位)に置き換わるように
市場から姿を消してしまった(生産中止)
まあFA77/1.8は確かにトップクラスの性能のレンズなのだが、
FA★85/1.4も捨てがたい。
そこで、デジタルでは使い難くなったFA★85/1.4
(注:この意味だが、PENTAXでは2016年のK-1の発売まで
全てのデジタル一眼レがAPS-機であった為、換算画角が
約127mm相当となるFA★85/1.4は、本来威力を発揮する
人物撮影の分野では、やや長すぎる焦点距離(画角)となる為)
を代替する、と言う点では、本DA★55/1.4は最適のレンズと
なった訳だ。
SDM(超音波モーター)仕様は、迅速なAF動作をもたらすが
AF精度がとても高いという訳でもない。
それとこの超音波モーターは、可聴域の高周波音を発する為
撮影中に「チーッ」と言う耳障りな音が聞こえる弱点を持つ。
まあでも、独特なボケ質などは好感が持てる、
SDMの弱点は不問としよう。

本レンズが発売された2000年代末では、50mm/f1.4級レンズは
銀塩時代からの設計を引き継いだ、古いが、技術がこなれていて
完成度の高い物ばかりで、当然ながら価格も安価であり、
中古でも2万円程度迄で「よりどりみどり」であった状況だ。
しかし、本レンズ以降の時代では、最新設計の非常に高価な
単焦点標準レンズも各社から色々と出始める。
代表的な新鋭AF標準レンズを2つほど上げれば・・
NIKON AF-S NIKKOR 58mm/f1.4G
(2013年発売、定価210,000円税別、後日紹介予定)
SIGMA Art 50mm/f1.4 DG HSM
(2014年発売、定価127,000円税別、レンズマニアックス第2回)
等がある。
それらに比べると本DA★55/1.4(発売時実勢価格約80,000円)
はまだ安価な方ではある。が、後年のそれらは、確かに高画質
なのかも知れないが、開発費の上乗せが大きいのだろうか?
そう安易に買える価格帯ではなくなってしまった。
なお、カールツァイスのブランドからは、さらに非常に高価な
新鋭単焦点標準レンズが発売されている。
また、さらに後年ではPENTAXやTOKINAからも、高価格の
標準レンズが次々と発売されている。
もし、こう言った価格帯が新標準レンズの「常識」となって
しまうと、正直困る。
「AF単焦点標準レンズは中古で2万円」これがほんの10年程前
までの常識(相場)であり、それでも、完成度の高いそれらは
十分に使えていたのだ。
まあ「高画素化時代への対応」と言う大義名分はあったのかも
知れないが、要は値段の高さは開発費のコスト回収が主であろう。
そして、あまり数が売れないと思われるカテゴリーのレンズ
だけに、余計にレンズ1本あたりの開発費上乗せが多額になる、
と言う厳しい状態だ。
ただまあ、本DA★55/1.4も、発売後10年を超えるくらいの
現代においては、それらの新鋭超高性能単焦点標準に比べると
解像度チャート等での数値評価上では、さすがに若干見劣り
する状態になってきたのであろう。
PENTAXも2016年にフルサイズ一眼レフを発売した所では
あるが、高性能なフルサイズ対応単焦点標準が存在しない。
FA50mm/f1.4(ミラーレス第23回記事)があるが、これは
銀塩時代の1990年代の古いレンズである、いくら当時から
完成度が高いレンズだとは言え、発売後四半世紀を超えれば
仕様的老朽化(周囲の新製品が皆、高性能化して来る)は、
どうしても避けられない。
PENTAXでは、2018年にHD PENTAX-D FA★50mm/f1.4
SDM AWを発売(末所有)、これも定価18万円と高価な
標準レンズで、超高画素対応(高解像力)をうたっている。
ちなみに、超高画素対応と言っても、現在のフルサイズ機の
最大5000万画素位での、ピクセルピッチと、レンズの
解像力(LP/mm)を計算してみると、まだ若干余裕がある。
すなわち、まだ従来レンズでも高性能な物を使えば何とか
なる状況なのだが・・もし近い将来に画素数の向上が急速に
進展した場合、そこから対応レンズを開発していたのでは
間に合わない。
間に合わないのは開発の時間のみならず、ユーザー側の
「意識」の変化も、それには急には追いつか無いのだ。
そこで、今のうちから早目に
「超高画素カメラには、新世代の高解像力レンズが必須!」
と言う新たな「常識」を、ユーザー層に刷り込んでいかなくては
ならない。
一般ユーザーで解像力の検証や計算が出来る人は皆無だろう。
だから、ちょっと凝ったマニア等により、ちゃんと計算されて、
その辺りが「あれ?」と疑問に思われない内に、ユーザーには、
そのように思い込んで貰わないとならないのであろう。

結局はユーザー側が、その価格や品質を納得して新型レンズを
買うならば、それで良い、という事だ。
「新製品は高性能だ、だから高いんだ」と、ユーザー層には
単純に、そう思い込んでもらって、メーカーに利益を還元して
いかないと、カメラ市場そのものが崩壊してしまう・・
さて、裏の事情はそのあたりまでで・・
ともかく、本DA★55/f1.4は見事にランキングのベスト10入り
を果たしたハイコスパレンズである。
まだ若干中古相場は高目の推移ではあるが、仮に3万円台
前半位で入手できるのであれば、もう文句の無い、お買い得
レンズとなると思う。
(追記:類似スペックの、新鋭中国製レンズ、「七工匠
55mm/F1.4」(2018年頃発売、実売16000円前後)も
悪く無い。これは銀塩時代のプラナー系85mm/F1.4構成を
スケールダウンしたAPS-C以下ミラーレス用MFレンズだ。
そのレンズも、これくらいの上位ランキングに入って来ても
おかしく無かったが、本記事執筆時点では、購入および
評価が間に合っていなかった→後日別記事で紹介予定)
----
今回はこのあたりまでで、次回記事では、いよいよBEST8
となる、引き続きランキングレンズを順次紹介していこう。