「TAMRON SPレンズ40周年記念記事」
本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に
紹介している。
今回の記事では、TAMRON製の「SP」銘の単焦点レンズを、
5本紹介しよう。
![c0032138_17563743.jpg]()
1979年より続く、「高描写力のレンズである事」を
示す称号だ。
その名を冠したレンズはかなり多いし、私も多数のSP銘の
レンズを所有してはいるが、今回の記事では、その代表的
な物(注:単焦点のみ)を厳選して紹介する。
それと、最初に述べておくが、私は、メーカー側が、
こうして型番で性能を区別して高画質を謳うスタンスには、
あまり賛同ができない。
性能を評価するのは、あくまで購入(ユーザー)側だからだ。
レンズの使い方も、ユーザー毎により様々であろう。
よって、「SPやらLやらARTやらPROやらGMやらライカやら
ツァイスやら」という、「いかにも特別なレンズ」という
名称をつけて、その結果、価格を吊り上げているならば、
そういうレンズは、むしろあまり買いたいとは思わない。
何故ならば、そんな称号や型番がついていなくても、
安くて良く写るレンズは、他にいくらでも存在するからだ。
その事実は、中上級層やマニア層ならば誰でも知っている。
ただ、TAMRONの場合には、高性能でコスパが良いレンズを
探していくと、”たまたま「SP」銘に行き当たった”という
感じである。値段もさほど高価では無い為、ここで取り上げる
「SP」銘レンズについては、「そんなの名前だけだ!」と
目くじらを立てる必要も無いであろう。
----
では、まず最初のSPシステム
![c0032138_17565193.jpg]()
(中古購入価格 41,000円)(以下、SP35/1.8)
カメラは、NIKON D2H (APS-C機)
【注意】このカメラとレンズの組み合わせは時代が10年以上
も異なる。一応写真は撮れるが、稀にエラーや動作不良が
起こる為、これは「非推奨」の組み合わせとしておく。
----
2015年に発売された、高描写力単焦点準広角レンズ。
フルサイズ対応品であるが、今回、古いAPS-C機に装着
しているのは、それなりに意味があり、そこは後述する。
![c0032138_17565163.jpg]()
しかし、どうも、このシリーズ(35mm,45mm,85mm)は
市場で人気が無い模様で、特に本SP35/1.8やSP45/1.8は、
発売から2年ほど経った2017年頃から、中古市場に
大量に新古品(在庫処分品)が流通していた。
こういう状況は、モデルチェンジ前か、または、その商品
が、あまり人気が無い場合か、たいていどちらかである。
本レンズSP35/1.8の、その後のモデルチェンジは無いので
やはり人気が無かったのであろう。
(追記:本記事執筆後にSP35mm/f1.4 Di USDが発売された。
その発売理由も本記事での分析内容に密接に関係して来る。
ここでの本レンズSP35/1.8の話は、数ヶ月前のSP35/1.4
未発表の状況での分析と思っていただければ良いだろう)
で、何故人気が無いか?は、理由が想像できる。
まず、2010年代での、スマホやミラーレス機の台頭による
一眼レフ市場の縮退は、毎回のように説明している事だ。
そういう「飽和市場」では、販売数が少なくても利益が
得られる「高付加価値型商品」を出さないとやっていけない。
これは現代では、TAMRONに限らず、他のカメラメーカーや
レンズメーカーも全てが実施している戦略だ。
単純に言えば、2010年代におけるカメラ・レンズ製品は
ユーザーが欲しいと思うように「凄いスペックを並べ立て
その分、製品価格を値上げしている」という事だ。
言い方は多少悪いが、これは純然たる事実である。
で、現代のカメラ市場の主要ユーザー層は「初級中級者」
である。何故ならば、昔からカメラをやっているような
ベテラン層、上級層、マニア層などは、現代のカメラや
レンズが「割高である」と感じている。だから、旧機種を
できるだけ長く使おうとしたり、買い控えを行っている訳だ。
旧来より遥かに高価になった新製品を、そう簡単に次々と
買う気にはなれない。
それに、35mm,45mm,85mmは中級層以上では、本SP
シリーズで無くても、代替できる似た仕様のレンズを必ず
所有している、むやみに買い換える必然性も殆ど無い。
また、職業写真家層であっても、使用する機材が”企業等の
所属組織やメーカー等から提供される”といった、恵まれた
環境以外の場合は、高価になりすぎた機材を自腹で買って
いたら、収支が見合わないケースも多々出てくるであろう。
高性能な最新機材では無くても撮れるだけの、高いスキルや
経験値を持っていればいるほど、最新の「高付加価値型」の
製品は買う必要は無い。(職業写真家層等が、そうした新鋭
レンズを使っている状況は、「広告塔」としての立場の場合も
多々ある事も、ユーザー側は良く認識しておく必要がある)
![c0032138_17565152.jpg]()
レンズである、その定価は9万円と、かなり高額である。
例えば、少し前の時代の他社の同等スペックの製品では
SONY製DT35/1.8(SAL35F18)の定価は2万4000円で、
実売価格は、新品で1万円台後半であった。
(注:まあDT35/1.8はAPS-C機専用レンズであるから、
正当な比較とは言い難いが・・)
それから、ライバルのSIGMAには35mm/f1.4 DG HSM | Art
が存在する、こちらは定価11万8000円と、本SP35/1.8
よりさらに高価であるが、なんと言っても開放F1.4が光る。
ビギナー層における、機材評価の論理は以下の通りだ
初「SIGMAの方は開放F1.4だから、TAMRONのF1.8より
高性能なんでしょう? だから値段も高いのでしょう?
当然SIGMAの方が良く写るよね?
だったら、多少高くてもSIGMAを買う事にするよ」
この論理の何処がおかしいか? まあビギナー層以外
(つまり、中上級層、マニア層、職業写真家層、評論家層
そしてメーカー関係者、市場(流通)関係者等)であれば
誰でも簡単に、「そうとは言い切れない」と断言できる。
つまり、ごく単純に「カタログスペックの数字だけを見て
商品の性能や価値を評価するなかれ」という大原則だ。
特に「開放F1.4が、開放F1.8より優れている」というのが
最大の「思い込み」だ。
開放F1.4を実現するには、開放F1.8のレンズよりも、
設計が困難であったり、コストが増加したり、大きく重く
なったり、最短撮影距離が伸びたり、そして場合により
画質も低下する等、様々なデメリットが発生するのだ。
(特に、「球面収差」は有効径の3乗に比例して大きくなり、
「コマ収差」も有効径の2乗に比例する為、大口径レンズで
これらの収差の発生を抑える設計は非常に困難となる)
そして、銀塩から近代に至るまで、同一メーカーの同時代
の製品で、50mmや85mm等の同じ焦点距離で、F1.4版と
F1.8(or F1.7)版が並存してラインナップ(併売)されて
いる場合、ほぼ100%、F1.8版の方が写りが良い。
(注:ごく近年の高付加価値型F1.4版製品のケースを除く。
が、そういう場合にはF1.4版はF1.8版の数倍から十数倍の
高額定価になる事も多々あり、「それらは根本的に違う物」
という事で、区別する事や理解は容易であろう)
で、「F1.8版の方が100%写りが良い」という根拠であるが
両者が同様な設計・製造プロセスで、しかも定価にもあまり
差が無く、2倍以内程度の差であれば・・
ここで、もしF1.4版が全ての性能要素で優れているならば、
両者を同時にラインナップ(併売)する意味が無い。
つまりF1.4版に一本化し、F1.8版を製造中止にすれば
良い訳だ、その方がラインナップ維持の様々な負担が減る。
そうできないのは、F1.8版の方が実は高描写力であったり
又は描写力が同等であっても、小型軽量化や最短撮影距離
短縮等の他の性能上のメリットがあるからだ。
では、同一メーカー間ではなく、他のメーカー同士の
同等スペックの製品の場合はどうか?
この場合は、たいてい、ライバル製品に対して、後から
発売された方が優れている。
何故ならば、既に市場には他社のライバル製品が存在
しているのに、後から、それより性能の低い製品を
出しても、全く勝ち目が無く、無意味だからだ。
先のSIGMAとTAMRONの例を見れば、SIGMA A35/1.4が
2013年頃の発売、TAMRON SP35/1.8が2015年の発売と
なれば、TAMRONは当然、SIGMAの製品を研究しつくし、
それを超える性能のものを開発する時間的な余裕が
あった筈だ。
そこで、仕事をサボって「安かろう、悪かろう」という
製品を後から出せる筈が無い。設計担当者の問題だけでは
なく、沢山の関係者が見守っている中で製品が出てくる訳
だから、「後だしジャンケンで負ける」ような話などは、
完全に有り得ないシナリオでは無いか・・・
で、ここまで読んで来て、初級中級者層は思うであろう
初「ならば、実はTAMRONの方が性能が良いのか?」
いや、それも早計な考え方だ。SIGMAとTAMRONは同じ
35mmで開放F値が微妙に異なるのみならず、製品の
企画コンセプトが、まるで違う。
なお、ここでSIGMA A35/1.4の性能の詳細について断言
できないのは、現状、私はA35/1.4は未所有だからだ。
一応、「購入予定リスト」に入っているレンズであるが
まだ自身で想定している購入希望中古相場よりも高価で
買えていない。(まあ、近い将来に入手するであろう)
で、スペック上での話をするならば、特に差異があるのは、
本SP35/1.8の最短撮影距離が20cmと異常な迄に短い事だ。
これは近代の35mmレンズの中でマクロを除いて、完全なる
第1位であり、各社がこれまで35mmレンズにおいて
最短23~26cmあたりで凌ぎを削ってきた中、ダントツの
1位のスペックである。(注:海外製では、18cmという
最短撮影距離の35mmレンズが、オールドレンズおよび近年
のローコスト中国製レンズで存在していた→後日紹介予定)
おまけに本SP35/1.8は、手ブレ補正内蔵だ。
つまり、SIGMA版は、F1.4と明るい大口径レンズで
明所から暗所まで、汎用的な被写体状況に対応する事を
コンセプトとした正統派で硬派なレンズであると思われ、
本SP35/1.8は、開放F値をわずかに犠牲にしても、最良の
描写力と最高の近接性能を与え、おまけに手ブレ補正で
暗所への対応までを可能とした、という方向性の差異だ。
だが、この差異は用途面からは大きく、両レンズにおいて、
被写体の選び方からして異なってしまう・・
(それと、前述のように、本記事執筆後に、TAMRONからも
SIGMA版と全く同じコンセプトのSP35/1.4が発売された、
まあ、F1.8版を失敗と見なし、戦略転換したのであろう)
![c0032138_17565181.jpg]()
APS-C機であるNIKON D2Hを使っている。
(注:冒頭に説明したように、この組み合わせは非推奨)
このかなり古い時代(2003年製)の機体に装着した場合でも
一応手ブレ補正は有効な模様で、換算52.5mmの標準画角で、
最大撮影倍率は、何と0.6倍!と、ほとんどマクロレンズ
並みの性能となる。
よって、今回は近接撮影を主体とした写真を掲載している。
まあ、こういう使い方をするならば、レンズの解放F値が
F1.4だろうが、F1.8だろうが、どうても良い事になる。
SIGMA A35/1.4と本SP35/1.8は、それぞれは用途が違う
レンズだ、こうした場合は、どちらかを選ぶものではなく
必要な方を買うか、あるいは両方を買うしか無いでは
ないか・・・
「でも、どちらが良いのだ?」とは聞くなかれ、それは、
それぞれのユーザーが、どんな目的で、どんな被写体を
どんな技法で撮るか?等で異なり、そんな事は他人では
知りようが無いので、答えようも無い。
それこそ、「気になる位ならば、両方買ってしまえば・・」
とも思う。勿論、コストは、かなり余計にかかるだろうが、
後になって「あちらの方が良かったかも?」等と、後悔や
疑念を持つ事は絶対に無いし、様々な被写体条件に合わせて
より適正なレンズを選んで使う等は、初級中級層における
勉強や練習にも役立つと思う。
----
では、次のシステム
![c0032138_17570646.jpg]()
(Model 172E)(中古購入価格 20,000円)
カメラは、PENTAX K-30(APS-C機)
言わずと知れた「90マクロ」シリーズの製品である。
本172E型は、1999年に発売された銀塩時代では最終の
バージョンであり、この後継機の272E型(2004年)からは、
「Di」(デジタル)対応として、後玉のコーティングを
改良している。
なお、前機種72E(1996年)との差異は、(PENTAX版では)
外観のほんの僅かな差だけなので、ほとんど同じものと
見なして良い。
![c0032138_17570797.jpg]()
マクロ」と呼ばれて賞賛された SP 90mm/f2.5 (52B)
(1979年)である。(ハイコスパ第15回記事等)
TAMRONは1960年代位から様々な写真用交換レンズを
発売していたが、この52B型が発売された1979年には、
「アダプトールⅡ」式交換マウントを採用し、MODEL名も
整理、そして、一部のレンズに初めて「SP」の名称を与えた。
この1979年に、TAMRONに何らかの転機があったのかも
知れないが、その詳細はわからない。(米国に現地法人を
作ったとか、経営体制が変わったとか、そんな感じか?)
だが、1979年だけで「SP」銘のレンズは、90マクロを含め
5本も発売され、中には500mmミラーとか17mm超広角とか
もある。これらもSP銘ではあるが、いずれも私は所有して
いるものの、特に写りがスペシャル(SP)だとは思えない。
まあ、500mmや17mmはスペックが特殊なので、SPとなった
のかもしれないが、後年の感覚で、高描写力を期待すると
ちょっとあてが外れる印象だ。
また、1980年代前半を通じて、さらに大量のSP銘レンズが
発売されたので、もうなんだか「SPの大安売り」という
感じだった事も否定できない。
しかし、その後の2000年代からのデジタル時代、特に、
2010年代については、TAMRONでSP銘の付与されている
レンズは、確かに、文句のつけようが無い高描写力と
なっているので、安心してSPレンズを購入できるとともに、
「SP」のブランド価値も、明確に存在するようになった。
例えば、2017年発売の超望遠ズーム100-400mm/f4.5-6.3
(Model A035)は、とても良く写るレンズであるが、
これにはSP銘がついていない。個人的には、このレンズでも
十分な描写性能なのに、これでもTAMRONは妥協できないので
あれば、「SP」銘は、かなり厳しい条件をクリアしないと
与えられない称号になってきているのだろう。
(だからまあ、メーカー側が提唱する、SPやらLやらGMやら
PROやらの呼称は、ユーザー側では気にする必要は無い。
性能や描写力を評価するのは、あくまでユーザー側であり
メーカーや評論家から、高性能である(「だから高価だ」、
又は「良いものだから買え」)と、押し付けられる要素は
何も無い)
![c0032138_17570663.jpg]()
発売されている。
F2.8版の72系Modelであれば、どの時代のレンズを買っても
基本的なレンズ構成は同じなので、描写力には大差は無いと
思うが、後年の機種(F004以降)では、レンズ構成が若干
変わり、かつ手ブレ補正や超音波モーターが内蔵されている。
(故に高価だ=高付加価値型商品)
まあ、予算に応じて、Modelを選択する必要はあるが、
マニアあるいは中級者以上であれば、いずれかの時代の
「90マクロ」は必携である、この非常に著名かつ、必要性
の高いレンズを持っていないマニアなんて居ないと思うし、
「SP」を語る上で、このシリーズのマクロを無視する事は
有り得ない話だ。
----
では、3本目のSPレンズ
![c0032138_17571625.jpg]()
(中古購入価格 36,000円)(以下、SP45/1.8)
カメラは、NIKON D500 (APS-C機)
2015年に発売された、高描写力単焦点標準レンズ。
冒頭のSP35/1.8(F012)の兄弟レンズであり、同時発売だ。
こちらもフルサイズ対応品である。
APS-C機に装着しているのは、まあ、あまり深い意味は無く
フルサイズ機の母艦を、そんなに沢山持っていないからだ。
![c0032138_17571634.jpg]()
最強クラスである。これに類するものは(APS-C専用だが)
SONY DT50/1.8(SAL50F18)が最短34cmと、かなり優れるが、
それすらも軽々と上回る。
(追記:2019年発売の、SIGMA 45mm/f2.8 DG DN |
Contemporaryは、最短24cmと、本レンズを上回る)
後、手ブレ補正内蔵も、恐らくは標準レンズ史上初であろう。
だが、これもSP35/1.8と同様に不人気なレンズだ。
何故不人気であるかは、「初級中級者層が、開放F1.8は
開放F1.4に比べて、低性能なレンズだと誤解するからだ」
と前述したが、では、ここでは、不人気になった事による
状況や影響について述べよう。
本レンズの定価は、SP35/1.8同様に9万円と高価だ。
「量販店」等では、発売当初は高額であるが、商品が
あまり売れないと見ると、急激に価格を値下げする。
その際、噂によると、量販店が下げた分の差額は
メーカー側が負担する模様だ。つまり、量販店側に
価格決定の主導権があるという事だろう。
なお、本レンズには一応定価が存在するが、現代では、
多くの他の商品は「オープン価格」となっているので、
さらに販売店側の価格主導権が強いと思う。
さて仮に、本レンズを発売初期に、ある程度高価に購入
したユーザー層が、なんらかの事情で、これを売却した
とする。その個体は中古扱いになるが、レンズ・サード
パーティの商品の中古相場は、特別な人気商品を除いて、
とりあえず定価の半額くらいと決められる。
つまり、本レンズの初期中古相場は、約45,000円前後だ。
で、その後、商品の販売計画よりも、実売数が少ない場合
(つまり、人気が無い場合)は、メーカーも流通も在庫品を
持て余す状況となる。
「量販店」では、そうした場合、価格を下げて在庫品を
捌いていこうとする。本レンズの場合は、発売後2~3年
程で、その新品販売価格は、前述の初期中古相場と同様の
定価のほぼ半額位まで下がった。
そうなると中古流通にある商品の相場も下げなくては
ならない、量販店で新品で購入するのと大差なければ
中古品は売れないからだ・・
ユーザーから見たら、このタイミングが買い頃だ。
つまり、本レンズの市場原理からの適正相場は3万円台
後半という事になるが、実際には「価値感覚」(つまり
コスパ感覚)からの適正相場を意識しなればならない。
これは、「F1.8級の小口径標準レンズを、3万円台後半
も出して買う意味があるのか?」という点だ。
だがまあ、本レンズは「非常に高いと予想される描写力」
「群を抜く最短撮影距離」「手ブレ補正と超音波モーター」
という、スペック的な特徴を鑑みれば、もうこれは購入に
値する、というコスパ感覚で正解であろう。
ちなみに中古4万円前後の価格の標準レンズ、といえば、
「smc PENTAX-FA 43mm/f1.9 Limited」とか、
「smc PENTAX-DA ★55mm/f1.4 SDM」(APS-C機専用)
「COSINA PLANAR T* 50mm/f1.4」(MFレンズ)
等が他に存在する。
これらが価格面での「ライバルレンズ」であると同時に
「価値感覚」(コスパ感覚)を比べる為の指標となる。
で、これら同価格帯の他のライバルレンズも大変良く写る。
(と言うか、全て「名玉」である。過去のレンズ系記事で
各々紹介済み。注:コシナPlanarはCONTAX版と中身は同じ)
![c0032138_17571673.jpg]()
弱点を持つが、描写力そのものは、上記名玉群に比べても
勝るとも劣らない。そして、最短撮影距離の短さは
他の追従を許さず、AFはもとより、手ブレ補正と超音波
モーターを搭載する「現代的フルスペック標準レンズ」だ。
いったい本レンズの何処が不満で、何故不人気なのだろう?
もし「最強の標準レンズ」を決める決定戦をやるとすれば
間違いなく決勝進出し、BEST5に確実に入る標準レンズだ。
(いつか、その手の記事を書いてみよう・・)
以下、単焦点標準レンズの歴史の余談だが、
銀塩時代、1970年代末には標準レンズの性能はF1.4版も
F1.8(F1.7)版も、ほぼ完成の域にまで到達していた。
(変形ダブルガウス型の構成により、完成度が高まった)
続く1980年代に、一眼レフのAF化と単焦点からズームへの
変革期を迎えると、開発リソース(資源)が足りなかった
からか?あるいは旧来のMF標準レンズの完成度が高かった
からか?各社AF標準レンズは、殆どがMF時代のレンズ構成
をそのまま踏襲していた(=AF化しただけ)
1990年代はユーザーニーズの激変期であり、ここでも各社は
新規標準レンズを作る余裕も無く、その市場ニーズも無い。
(ズームレンズが発展し、主力となりつつある時代だ)
2000年代に入ると、デジタル化の荒波が押し寄せ、ここでも
各社は新型標準レンズを開発する余裕が全く無い。
2010年頃には、各社「エントリー標準レンズ」という企画
コンセプトで、ミラーレス機やスマホの台頭に対抗するが
その戦略では「高性能化」よりも「低価格化」が優先された。
2010年代後半になって、やっと各社より「高付加価値型」の
新世代標準レンズが数十年ぶりに発売された状況なのだ。
本SP45/1.8は、1960年代からの長いTAMRONの歴史において
殆ど初めての「標準レンズ」の発売である、これまでの
1960年代~2010年代前半では、他社の、原価がこなれていて
ローコストで完成度が高く、メーカー純正でブランド力を
持つMF/AF標準レンズと勝負しても意味が無い、と思って
いた事であろう。
やっと現代になって、新世代の標準レンズのコンセプトが
生まれ、それが今後将来の「スタンダード」に変わる
直前の状況な訳だ。
その結果、価格が極めて高くなってしまった事は大問題
ではあるが、メーカーが市場(ビジネス)を維持する為には、
値上げは、やむを得ないとも言える。
もう3年かそこら経過したら、各社の新世代の高性能標準
レンズの定価が軒並み20万円もしても、もう誰も驚かなく
なっているか知れない(事実、既にそうなりつつある)
まあ、(標準)レンズの高性能化は、コンピューター
光学設計手法の普及もある。ただ、必ずしもそれが良い
事ばかりとは限らない(=高い性能レベルの計算結果を
要望するならば、必然的に”三重苦レンズ”が出来あがる)
この話は深堀りするとキリが無い為、一部は後述するが
詳しくは、また別の記事に譲ろう。
----
では、次のシステム
![c0032138_17573111.jpg]()
(Model G005) (中古購入価格 20,000円)
(以下、SP60/2)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2009年に発売された、APS-C機専用、中望遠画角
大口径AF等倍マクロレンズ。
本レンズの後、2010年代後半には、デジタル機市場は、
フルサイズ機が主流となった為、本レンズは現行製品
ながらも、製品寿命的には自然終了している状況だ。
ただ、写真撮影上では「フルサイズ機でなくてはならない」
という理由は全く無い。初級中級層がフルサイズ機ばかりに
価値を見い出すから、APS-C機専用で、かつ手ブレ補正も
超音波モーターも無い本レンズが、不人気となる理由も
わからないでは無いが・・
ても、現実はその真逆だ。
本レンズSP60/2の描写力は一級品であり、解像力や、ボケ質
(およびその破綻状況)や、逆光耐性など、どこをとっても
何も不満は無い。
![c0032138_17573189.jpg]()
90マクロの代替、として企画開発されたレンズなのだろう。
(すなわち、APS-C機装着時の画角が90mm程度になる)
銘マクロの代替(APS-C版)なのだから性能が悪い筈が無い、
もしイマイチの写りだったら、90マクロの評判にも傷が付くし、
「高描写力マクロのタムロン」というブランドイメージをも
低下させてしまう。(勿論メーカーとしては愚策となる)
おまけに、マクロレンズとしては希少な開放F2の大口径で
かつ、これまでF2級マクロで等倍仕様であった製品は、
恐らくは皆無であったと思われ、本レンズの性能面からの
優位点は多く、歴史的価値もとても高い。
「APS-C機専用」や「超音波モーターが無い」という点は、
先のSP35/1.8等での「大口径F1.4では無い」という事と同様に、
ビギナー層以外においては、気にする必要も無い事であり、
当然ながら欠点では無い。
でも、そういう点を誤解したり、スペックだけを気にする
人(=ビギナー層)のみが、現代においては主力ユーザー
(お金を使って新製品を買ってくれる人達)なのだろう。
結果的に本レンズは不人気で、中古市場では2万円以下の
格安相場だ。
これは、カタログスペックに惑わされないビギナー層以外
の人達から見れば、逆に「極めてコスパの良いレンズ」と
見なされる事は間違いない。
![c0032138_17573139.jpg]()
少し固目の描写の為に被写体を選ぶ事、等だが、いずれも
中級者以上の人達には「言わずもがな」のレベルであろう。
勿論、これらは重欠点では無い。
なお、本レンズはSONY機用なので、勿論手ブレ補正は無い。
SONY機やPENTAX機にはボディ内手ブレ補正があるからだ。
よって、サードパーティ製の旧レンズ購入時は、それらの
マウントを選択するのも良い。ただし、2010年代中頃からの
サードパーティ製のレンズは、SONYα (A)版や、PENTAX KAF
版が発売されないケースも多く、困ったものである。
(ただし、残ったそれらのマウントの中古レンズは、
近年、急速に中古相場が下落している。メーカーのみならず
中古流通でも、それらのマウントの縮退を意識しているの
であろう。安価になっていれば買い頃とも言える)
----
では、今回ラストのシステム
![c0032138_17574058.jpg]()
(中古購入価格 70,000円)(以下、SP85/1.8)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
2016年に発売された、高描写力単焦点AF中望遠レンズ。
SP35/1.8(F012)やSP45/1.8(F013)より、半年ほど遅く
発売されているが、同一のシリーズ商品である。
これも勿論フルサイズ対応。
85mmは人物撮影に適した焦点距離であるという通説がある。
まあ、必ずしもそうだとは言い切れないが、あまり換算の
焦点距離を長くしない為にも、今回の母艦はフルサイズ機を
使用する。
![c0032138_17574043.jpg]()
個人的な購入目的としては、銀塩時代の超名玉の
「smc PENTAX-FA 77mm/f1.8 Limited」の代替用途だ。
「ナナナナ」は屋外・屋内・ステージ等での人物撮影の
どのシーンでも、最良の描写力と、抜群の歩留まりの良さ
(ボケ質破綻の発生が無く、逆光耐性が高く、ピントを
外す場合が少なく、成功率が高い為、安心して使える)
を誇ったレンズで、長年の実用(業務・依頼)撮影で
極めて重宝した。
だが、さすがの「ナナナナ」も発売から15年を過ぎると、
現代レンズに比較して、解像感等の点で見劣りが出てくる。
そこで「本レンズSP85/1.8が、が後継になるのでは?」
と踏んだ次第だ。
長所は、事前の予想通りの素晴らしい描写力であり、
何も文句のつけようがない。「ナナナナ」の代用に十分に
なりうる、まあこの時点で、すでに「名玉」であろう。
「F1.4では無い」という点は、色々書いてきたように全く
問題は無い、・・と言うか、85mm/f1.4級のレンズは
10本程所有しているが、むしろ、どれも「歩留まり」が
かなり悪くて、実用撮影には使用できなかったのだ。
F1.8級中望遠の方が実用上で使えるシーンが遥かに多い。
ピクセルピッチが7.2μmと大きいNIKON Dfで使用する際は
高解像力は、あまり差意が出ないと思うが、より高画素で
ローパスレスの機種で使う場合は、本レンズの解像力が
より際立つであろう。
![c0032138_17574091.jpg]()
レンズである事だ、
もっとも、価格については「ナナナナ」と同レベルなので
あまり不満は無いのだが、大きく重いのは、ちょっと困る。
まあ、描写力を優先した設計の為に、F1.8級ながら異常な
までの大きいサイズ感となったのだろうが、やや過剰だ。
それから、ニコンFマウント用で「電磁絞り」を採用して
いる事。これではニコン旧機種や他社機で使用不能のため、
汎用性を失っている。他社よりも操作系のビハインド(遅れ)
があるニコン機でしか、本レンズが使えない点は不満だ。
(注:EOSマウント版を選んでも、他社機に装着しずらい。
まあでも、いずれEF版も予備レンズとして買うべきか?)
なお、海外だったか?どこかのレビューで「焦点移動」が
出る事を弱点としてあげていたが、それは的外れな評価だ。
本レンズの用途上、絞って使う事は有り得ない。
F1.8~F4の間で使うのが基本であり、焦点移動は無視できる。
・・と言うか、設計の時点で焦点移動の発生は確実にわかる。
それでも、あえてそれを残したのは、焦点移動の補正よりも
優先すべき事項(例:解像力やボケ質)があったからであり、
どれかを優先すれば他が犠牲になる「トレードオフ」関係だ。
メーカー側は、ユーザー側の百倍も千倍も、色々と考えて
レンズを設計している訳だ。エンジニアが毎日毎日、何ヶ月
もの間、朝から晩まで頑張って開発しているから当然だ。
ユーザーが、買ったばかりのレンズを喜んで、2~3日撮って
レビューしている状況とはまるで違う時間の「重み」がある。
ユーザーの中級者等が、製品のわずかな弱点を見つけて、
「鬼の首を取ったかのように」騒ぎ立てる必要は、まるで
無いし、むしろ「長所が見えないのか?」と、格好悪い。
製品の細かい弱点がわかるだけのスキルを持っているならば、
それを回避して有益に使うのが上級ユーザーの責務であろう。
「弘法筆をえらばず」という故事があるが、このことわざの
真意は「道具にあれこれと文句をつけるな(使いこなせ)」
という意味だ。
レンズ設計において、全ての弱点を無くす事は不可能だし、
仮に諸収差を全て良好に補正しても三重苦レンズとなるし、
収差が無い事は、高描写力である事とはイコールでは無い。
例えば、前述の名玉FA77/1.8も、手動に近い設計手法で
諸収差をあえて残しながらも、実用上に極めて優れた
「バランス点」を意図して設計されている。
現代では、もうほぼ全てがコンピューター設計になって
しまった為、このような「職人芸的」な設計技法による
レンズ設計は、もう誰もできなくなってしまったのだろう。
・・であれば、あとは、どの収差を優先的に補正するかは、
もう設計者(企画者)の「センス」に依存する。
現代の設計ソフトでは、設計したレンズの評価値(メリット関数)
が表示されるが、ただ単に、その数値を高めようとするだけでは、
バランスの良いレンズ設計には成り得ない、やはり設計者の
センス(バランス感覚)やノウハウが、とても重要なのだ。
だが、「高付加価値化」した利益率の高い製品を作らないと
レンズ市場が維持できない、というメーカー側での大命題も
ある為、ともかく全ての収差を無くす事を目指し、結果的に
十数群十数枚と言う単焦点レンズが出来て、大きく重くなる
のは止むを得ず、また、それにより高価になる事は、むしろ
狙い通り、とメーカー側は考えてしまうだろう。
その事実を、どう判断・評価するかは、ユーザー次第だ、
値段に見合う価値があると思えば購入すれば良いし、
高価すぎる!と思えば、見送るか、または、中古を待って、
自分が希望する価格帯まで値段が下がった頃に買えば良い。
![c0032138_17574048.jpg]()
ビギナー層が「カタログスペックだけを気にする」といった
不当な理由により、不人気となって、早めに相場が下がる
事も、前述のように多々ありうる。
特に、SP35mm,45mm,85mmは、不当な不人気の商品で
あるから、早々に価格が下がっていて、コスパがとても良い。
中級層以上のユーザーであれば、一応、それらに代替できる
類似スペックの旧レンズを持っているとは思うが、
これらSP単焦点は、旧製品とは次元の違う高描写力を持つ。
しかるべきタイミングで入手しておくのが良いであろう。
特に本SP85/1.8は、私の購入時点よりも、近年ではさらに
中古相場の下落が大きいので、推奨しやすいレンズだ。
----
さて、今回の記事「TAMRON SPレンズ特集」は、
このあたり迄。他にも紹介したいSPレンズが何本もあった
のだが、記事が冗長になる為、やむなく他記事に廻そう。
では、次回記事に続く・・
本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に
紹介している。
今回の記事では、TAMRON製の「SP」銘の単焦点レンズを、
5本紹介しよう。
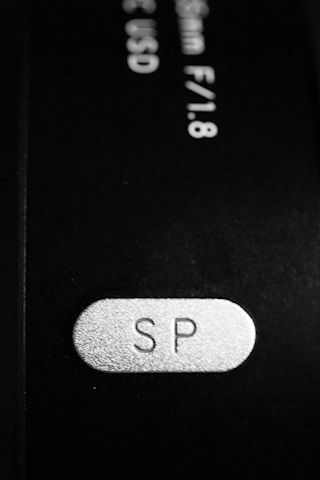
1979年より続く、「高描写力のレンズである事」を
示す称号だ。
その名を冠したレンズはかなり多いし、私も多数のSP銘の
レンズを所有してはいるが、今回の記事では、その代表的
な物(注:単焦点のみ)を厳選して紹介する。
それと、最初に述べておくが、私は、メーカー側が、
こうして型番で性能を区別して高画質を謳うスタンスには、
あまり賛同ができない。
性能を評価するのは、あくまで購入(ユーザー)側だからだ。
レンズの使い方も、ユーザー毎により様々であろう。
よって、「SPやらLやらARTやらPROやらGMやらライカやら
ツァイスやら」という、「いかにも特別なレンズ」という
名称をつけて、その結果、価格を吊り上げているならば、
そういうレンズは、むしろあまり買いたいとは思わない。
何故ならば、そんな称号や型番がついていなくても、
安くて良く写るレンズは、他にいくらでも存在するからだ。
その事実は、中上級層やマニア層ならば誰でも知っている。
ただ、TAMRONの場合には、高性能でコスパが良いレンズを
探していくと、”たまたま「SP」銘に行き当たった”という
感じである。値段もさほど高価では無い為、ここで取り上げる
「SP」銘レンズについては、「そんなの名前だけだ!」と
目くじらを立てる必要も無いであろう。
----
では、まず最初のSPシステム

(中古購入価格 41,000円)(以下、SP35/1.8)
カメラは、NIKON D2H (APS-C機)
【注意】このカメラとレンズの組み合わせは時代が10年以上
も異なる。一応写真は撮れるが、稀にエラーや動作不良が
起こる為、これは「非推奨」の組み合わせとしておく。
----
2015年に発売された、高描写力単焦点準広角レンズ。
フルサイズ対応品であるが、今回、古いAPS-C機に装着
しているのは、それなりに意味があり、そこは後述する。

しかし、どうも、このシリーズ(35mm,45mm,85mm)は
市場で人気が無い模様で、特に本SP35/1.8やSP45/1.8は、
発売から2年ほど経った2017年頃から、中古市場に
大量に新古品(在庫処分品)が流通していた。
こういう状況は、モデルチェンジ前か、または、その商品
が、あまり人気が無い場合か、たいていどちらかである。
本レンズSP35/1.8の、その後のモデルチェンジは無いので
やはり人気が無かったのであろう。
(追記:本記事執筆後にSP35mm/f1.4 Di USDが発売された。
その発売理由も本記事での分析内容に密接に関係して来る。
ここでの本レンズSP35/1.8の話は、数ヶ月前のSP35/1.4
未発表の状況での分析と思っていただければ良いだろう)
で、何故人気が無いか?は、理由が想像できる。
まず、2010年代での、スマホやミラーレス機の台頭による
一眼レフ市場の縮退は、毎回のように説明している事だ。
そういう「飽和市場」では、販売数が少なくても利益が
得られる「高付加価値型商品」を出さないとやっていけない。
これは現代では、TAMRONに限らず、他のカメラメーカーや
レンズメーカーも全てが実施している戦略だ。
単純に言えば、2010年代におけるカメラ・レンズ製品は
ユーザーが欲しいと思うように「凄いスペックを並べ立て
その分、製品価格を値上げしている」という事だ。
言い方は多少悪いが、これは純然たる事実である。
で、現代のカメラ市場の主要ユーザー層は「初級中級者」
である。何故ならば、昔からカメラをやっているような
ベテラン層、上級層、マニア層などは、現代のカメラや
レンズが「割高である」と感じている。だから、旧機種を
できるだけ長く使おうとしたり、買い控えを行っている訳だ。
旧来より遥かに高価になった新製品を、そう簡単に次々と
買う気にはなれない。
それに、35mm,45mm,85mmは中級層以上では、本SP
シリーズで無くても、代替できる似た仕様のレンズを必ず
所有している、むやみに買い換える必然性も殆ど無い。
また、職業写真家層であっても、使用する機材が”企業等の
所属組織やメーカー等から提供される”といった、恵まれた
環境以外の場合は、高価になりすぎた機材を自腹で買って
いたら、収支が見合わないケースも多々出てくるであろう。
高性能な最新機材では無くても撮れるだけの、高いスキルや
経験値を持っていればいるほど、最新の「高付加価値型」の
製品は買う必要は無い。(職業写真家層等が、そうした新鋭
レンズを使っている状況は、「広告塔」としての立場の場合も
多々ある事も、ユーザー側は良く認識しておく必要がある)

レンズである、その定価は9万円と、かなり高額である。
例えば、少し前の時代の他社の同等スペックの製品では
SONY製DT35/1.8(SAL35F18)の定価は2万4000円で、
実売価格は、新品で1万円台後半であった。
(注:まあDT35/1.8はAPS-C機専用レンズであるから、
正当な比較とは言い難いが・・)
それから、ライバルのSIGMAには35mm/f1.4 DG HSM | Art
が存在する、こちらは定価11万8000円と、本SP35/1.8
よりさらに高価であるが、なんと言っても開放F1.4が光る。
ビギナー層における、機材評価の論理は以下の通りだ
初「SIGMAの方は開放F1.4だから、TAMRONのF1.8より
高性能なんでしょう? だから値段も高いのでしょう?
当然SIGMAの方が良く写るよね?
だったら、多少高くてもSIGMAを買う事にするよ」
この論理の何処がおかしいか? まあビギナー層以外
(つまり、中上級層、マニア層、職業写真家層、評論家層
そしてメーカー関係者、市場(流通)関係者等)であれば
誰でも簡単に、「そうとは言い切れない」と断言できる。
つまり、ごく単純に「カタログスペックの数字だけを見て
商品の性能や価値を評価するなかれ」という大原則だ。
特に「開放F1.4が、開放F1.8より優れている」というのが
最大の「思い込み」だ。
開放F1.4を実現するには、開放F1.8のレンズよりも、
設計が困難であったり、コストが増加したり、大きく重く
なったり、最短撮影距離が伸びたり、そして場合により
画質も低下する等、様々なデメリットが発生するのだ。
(特に、「球面収差」は有効径の3乗に比例して大きくなり、
「コマ収差」も有効径の2乗に比例する為、大口径レンズで
これらの収差の発生を抑える設計は非常に困難となる)
そして、銀塩から近代に至るまで、同一メーカーの同時代
の製品で、50mmや85mm等の同じ焦点距離で、F1.4版と
F1.8(or F1.7)版が並存してラインナップ(併売)されて
いる場合、ほぼ100%、F1.8版の方が写りが良い。
(注:ごく近年の高付加価値型F1.4版製品のケースを除く。
が、そういう場合にはF1.4版はF1.8版の数倍から十数倍の
高額定価になる事も多々あり、「それらは根本的に違う物」
という事で、区別する事や理解は容易であろう)
で、「F1.8版の方が100%写りが良い」という根拠であるが
両者が同様な設計・製造プロセスで、しかも定価にもあまり
差が無く、2倍以内程度の差であれば・・
ここで、もしF1.4版が全ての性能要素で優れているならば、
両者を同時にラインナップ(併売)する意味が無い。
つまりF1.4版に一本化し、F1.8版を製造中止にすれば
良い訳だ、その方がラインナップ維持の様々な負担が減る。
そうできないのは、F1.8版の方が実は高描写力であったり
又は描写力が同等であっても、小型軽量化や最短撮影距離
短縮等の他の性能上のメリットがあるからだ。
では、同一メーカー間ではなく、他のメーカー同士の
同等スペックの製品の場合はどうか?
この場合は、たいてい、ライバル製品に対して、後から
発売された方が優れている。
何故ならば、既に市場には他社のライバル製品が存在
しているのに、後から、それより性能の低い製品を
出しても、全く勝ち目が無く、無意味だからだ。
先のSIGMAとTAMRONの例を見れば、SIGMA A35/1.4が
2013年頃の発売、TAMRON SP35/1.8が2015年の発売と
なれば、TAMRONは当然、SIGMAの製品を研究しつくし、
それを超える性能のものを開発する時間的な余裕が
あった筈だ。
そこで、仕事をサボって「安かろう、悪かろう」という
製品を後から出せる筈が無い。設計担当者の問題だけでは
なく、沢山の関係者が見守っている中で製品が出てくる訳
だから、「後だしジャンケンで負ける」ような話などは、
完全に有り得ないシナリオでは無いか・・・
で、ここまで読んで来て、初級中級者層は思うであろう
初「ならば、実はTAMRONの方が性能が良いのか?」
いや、それも早計な考え方だ。SIGMAとTAMRONは同じ
35mmで開放F値が微妙に異なるのみならず、製品の
企画コンセプトが、まるで違う。
なお、ここでSIGMA A35/1.4の性能の詳細について断言
できないのは、現状、私はA35/1.4は未所有だからだ。
一応、「購入予定リスト」に入っているレンズであるが
まだ自身で想定している購入希望中古相場よりも高価で
買えていない。(まあ、近い将来に入手するであろう)
で、スペック上での話をするならば、特に差異があるのは、
本SP35/1.8の最短撮影距離が20cmと異常な迄に短い事だ。
これは近代の35mmレンズの中でマクロを除いて、完全なる
第1位であり、各社がこれまで35mmレンズにおいて
最短23~26cmあたりで凌ぎを削ってきた中、ダントツの
1位のスペックである。(注:海外製では、18cmという
最短撮影距離の35mmレンズが、オールドレンズおよび近年
のローコスト中国製レンズで存在していた→後日紹介予定)
おまけに本SP35/1.8は、手ブレ補正内蔵だ。
つまり、SIGMA版は、F1.4と明るい大口径レンズで
明所から暗所まで、汎用的な被写体状況に対応する事を
コンセプトとした正統派で硬派なレンズであると思われ、
本SP35/1.8は、開放F値をわずかに犠牲にしても、最良の
描写力と最高の近接性能を与え、おまけに手ブレ補正で
暗所への対応までを可能とした、という方向性の差異だ。
だが、この差異は用途面からは大きく、両レンズにおいて、
被写体の選び方からして異なってしまう・・
(それと、前述のように、本記事執筆後に、TAMRONからも
SIGMA版と全く同じコンセプトのSP35/1.4が発売された、
まあ、F1.8版を失敗と見なし、戦略転換したのであろう)

APS-C機であるNIKON D2Hを使っている。
(注:冒頭に説明したように、この組み合わせは非推奨)
このかなり古い時代(2003年製)の機体に装着した場合でも
一応手ブレ補正は有効な模様で、換算52.5mmの標準画角で、
最大撮影倍率は、何と0.6倍!と、ほとんどマクロレンズ
並みの性能となる。
よって、今回は近接撮影を主体とした写真を掲載している。
まあ、こういう使い方をするならば、レンズの解放F値が
F1.4だろうが、F1.8だろうが、どうても良い事になる。
SIGMA A35/1.4と本SP35/1.8は、それぞれは用途が違う
レンズだ、こうした場合は、どちらかを選ぶものではなく
必要な方を買うか、あるいは両方を買うしか無いでは
ないか・・・
「でも、どちらが良いのだ?」とは聞くなかれ、それは、
それぞれのユーザーが、どんな目的で、どんな被写体を
どんな技法で撮るか?等で異なり、そんな事は他人では
知りようが無いので、答えようも無い。
それこそ、「気になる位ならば、両方買ってしまえば・・」
とも思う。勿論、コストは、かなり余計にかかるだろうが、
後になって「あちらの方が良かったかも?」等と、後悔や
疑念を持つ事は絶対に無いし、様々な被写体条件に合わせて
より適正なレンズを選んで使う等は、初級中級層における
勉強や練習にも役立つと思う。
----
では、次のシステム

(Model 172E)(中古購入価格 20,000円)
カメラは、PENTAX K-30(APS-C機)
言わずと知れた「90マクロ」シリーズの製品である。
本172E型は、1999年に発売された銀塩時代では最終の
バージョンであり、この後継機の272E型(2004年)からは、
「Di」(デジタル)対応として、後玉のコーティングを
改良している。
なお、前機種72E(1996年)との差異は、(PENTAX版では)
外観のほんの僅かな差だけなので、ほとんど同じものと
見なして良い。

マクロ」と呼ばれて賞賛された SP 90mm/f2.5 (52B)
(1979年)である。(ハイコスパ第15回記事等)
TAMRONは1960年代位から様々な写真用交換レンズを
発売していたが、この52B型が発売された1979年には、
「アダプトールⅡ」式交換マウントを採用し、MODEL名も
整理、そして、一部のレンズに初めて「SP」の名称を与えた。
この1979年に、TAMRONに何らかの転機があったのかも
知れないが、その詳細はわからない。(米国に現地法人を
作ったとか、経営体制が変わったとか、そんな感じか?)
だが、1979年だけで「SP」銘のレンズは、90マクロを含め
5本も発売され、中には500mmミラーとか17mm超広角とか
もある。これらもSP銘ではあるが、いずれも私は所有して
いるものの、特に写りがスペシャル(SP)だとは思えない。
まあ、500mmや17mmはスペックが特殊なので、SPとなった
のかもしれないが、後年の感覚で、高描写力を期待すると
ちょっとあてが外れる印象だ。
また、1980年代前半を通じて、さらに大量のSP銘レンズが
発売されたので、もうなんだか「SPの大安売り」という
感じだった事も否定できない。
しかし、その後の2000年代からのデジタル時代、特に、
2010年代については、TAMRONでSP銘の付与されている
レンズは、確かに、文句のつけようが無い高描写力と
なっているので、安心してSPレンズを購入できるとともに、
「SP」のブランド価値も、明確に存在するようになった。
例えば、2017年発売の超望遠ズーム100-400mm/f4.5-6.3
(Model A035)は、とても良く写るレンズであるが、
これにはSP銘がついていない。個人的には、このレンズでも
十分な描写性能なのに、これでもTAMRONは妥協できないので
あれば、「SP」銘は、かなり厳しい条件をクリアしないと
与えられない称号になってきているのだろう。
(だからまあ、メーカー側が提唱する、SPやらLやらGMやら
PROやらの呼称は、ユーザー側では気にする必要は無い。
性能や描写力を評価するのは、あくまでユーザー側であり
メーカーや評論家から、高性能である(「だから高価だ」、
又は「良いものだから買え」)と、押し付けられる要素は
何も無い)

発売されている。
F2.8版の72系Modelであれば、どの時代のレンズを買っても
基本的なレンズ構成は同じなので、描写力には大差は無いと
思うが、後年の機種(F004以降)では、レンズ構成が若干
変わり、かつ手ブレ補正や超音波モーターが内蔵されている。
(故に高価だ=高付加価値型商品)
まあ、予算に応じて、Modelを選択する必要はあるが、
マニアあるいは中級者以上であれば、いずれかの時代の
「90マクロ」は必携である、この非常に著名かつ、必要性
の高いレンズを持っていないマニアなんて居ないと思うし、
「SP」を語る上で、このシリーズのマクロを無視する事は
有り得ない話だ。
----
では、3本目のSPレンズ

(中古購入価格 36,000円)(以下、SP45/1.8)
カメラは、NIKON D500 (APS-C機)
2015年に発売された、高描写力単焦点標準レンズ。
冒頭のSP35/1.8(F012)の兄弟レンズであり、同時発売だ。
こちらもフルサイズ対応品である。
APS-C機に装着しているのは、まあ、あまり深い意味は無く
フルサイズ機の母艦を、そんなに沢山持っていないからだ。

最強クラスである。これに類するものは(APS-C専用だが)
SONY DT50/1.8(SAL50F18)が最短34cmと、かなり優れるが、
それすらも軽々と上回る。
(追記:2019年発売の、SIGMA 45mm/f2.8 DG DN |
Contemporaryは、最短24cmと、本レンズを上回る)
後、手ブレ補正内蔵も、恐らくは標準レンズ史上初であろう。
だが、これもSP35/1.8と同様に不人気なレンズだ。
何故不人気であるかは、「初級中級者層が、開放F1.8は
開放F1.4に比べて、低性能なレンズだと誤解するからだ」
と前述したが、では、ここでは、不人気になった事による
状況や影響について述べよう。
本レンズの定価は、SP35/1.8同様に9万円と高価だ。
「量販店」等では、発売当初は高額であるが、商品が
あまり売れないと見ると、急激に価格を値下げする。
その際、噂によると、量販店が下げた分の差額は
メーカー側が負担する模様だ。つまり、量販店側に
価格決定の主導権があるという事だろう。
なお、本レンズには一応定価が存在するが、現代では、
多くの他の商品は「オープン価格」となっているので、
さらに販売店側の価格主導権が強いと思う。
さて仮に、本レンズを発売初期に、ある程度高価に購入
したユーザー層が、なんらかの事情で、これを売却した
とする。その個体は中古扱いになるが、レンズ・サード
パーティの商品の中古相場は、特別な人気商品を除いて、
とりあえず定価の半額くらいと決められる。
つまり、本レンズの初期中古相場は、約45,000円前後だ。
で、その後、商品の販売計画よりも、実売数が少ない場合
(つまり、人気が無い場合)は、メーカーも流通も在庫品を
持て余す状況となる。
「量販店」では、そうした場合、価格を下げて在庫品を
捌いていこうとする。本レンズの場合は、発売後2~3年
程で、その新品販売価格は、前述の初期中古相場と同様の
定価のほぼ半額位まで下がった。
そうなると中古流通にある商品の相場も下げなくては
ならない、量販店で新品で購入するのと大差なければ
中古品は売れないからだ・・
ユーザーから見たら、このタイミングが買い頃だ。
つまり、本レンズの市場原理からの適正相場は3万円台
後半という事になるが、実際には「価値感覚」(つまり
コスパ感覚)からの適正相場を意識しなればならない。
これは、「F1.8級の小口径標準レンズを、3万円台後半
も出して買う意味があるのか?」という点だ。
だがまあ、本レンズは「非常に高いと予想される描写力」
「群を抜く最短撮影距離」「手ブレ補正と超音波モーター」
という、スペック的な特徴を鑑みれば、もうこれは購入に
値する、というコスパ感覚で正解であろう。
ちなみに中古4万円前後の価格の標準レンズ、といえば、
「smc PENTAX-FA 43mm/f1.9 Limited」とか、
「smc PENTAX-DA ★55mm/f1.4 SDM」(APS-C機専用)
「COSINA PLANAR T* 50mm/f1.4」(MFレンズ)
等が他に存在する。
これらが価格面での「ライバルレンズ」であると同時に
「価値感覚」(コスパ感覚)を比べる為の指標となる。
で、これら同価格帯の他のライバルレンズも大変良く写る。
(と言うか、全て「名玉」である。過去のレンズ系記事で
各々紹介済み。注:コシナPlanarはCONTAX版と中身は同じ)

弱点を持つが、描写力そのものは、上記名玉群に比べても
勝るとも劣らない。そして、最短撮影距離の短さは
他の追従を許さず、AFはもとより、手ブレ補正と超音波
モーターを搭載する「現代的フルスペック標準レンズ」だ。
いったい本レンズの何処が不満で、何故不人気なのだろう?
もし「最強の標準レンズ」を決める決定戦をやるとすれば
間違いなく決勝進出し、BEST5に確実に入る標準レンズだ。
(いつか、その手の記事を書いてみよう・・)
以下、単焦点標準レンズの歴史の余談だが、
銀塩時代、1970年代末には標準レンズの性能はF1.4版も
F1.8(F1.7)版も、ほぼ完成の域にまで到達していた。
(変形ダブルガウス型の構成により、完成度が高まった)
続く1980年代に、一眼レフのAF化と単焦点からズームへの
変革期を迎えると、開発リソース(資源)が足りなかった
からか?あるいは旧来のMF標準レンズの完成度が高かった
からか?各社AF標準レンズは、殆どがMF時代のレンズ構成
をそのまま踏襲していた(=AF化しただけ)
1990年代はユーザーニーズの激変期であり、ここでも各社は
新規標準レンズを作る余裕も無く、その市場ニーズも無い。
(ズームレンズが発展し、主力となりつつある時代だ)
2000年代に入ると、デジタル化の荒波が押し寄せ、ここでも
各社は新型標準レンズを開発する余裕が全く無い。
2010年頃には、各社「エントリー標準レンズ」という企画
コンセプトで、ミラーレス機やスマホの台頭に対抗するが
その戦略では「高性能化」よりも「低価格化」が優先された。
2010年代後半になって、やっと各社より「高付加価値型」の
新世代標準レンズが数十年ぶりに発売された状況なのだ。
本SP45/1.8は、1960年代からの長いTAMRONの歴史において
殆ど初めての「標準レンズ」の発売である、これまでの
1960年代~2010年代前半では、他社の、原価がこなれていて
ローコストで完成度が高く、メーカー純正でブランド力を
持つMF/AF標準レンズと勝負しても意味が無い、と思って
いた事であろう。
やっと現代になって、新世代の標準レンズのコンセプトが
生まれ、それが今後将来の「スタンダード」に変わる
直前の状況な訳だ。
その結果、価格が極めて高くなってしまった事は大問題
ではあるが、メーカーが市場(ビジネス)を維持する為には、
値上げは、やむを得ないとも言える。
もう3年かそこら経過したら、各社の新世代の高性能標準
レンズの定価が軒並み20万円もしても、もう誰も驚かなく
なっているか知れない(事実、既にそうなりつつある)
まあ、(標準)レンズの高性能化は、コンピューター
光学設計手法の普及もある。ただ、必ずしもそれが良い
事ばかりとは限らない(=高い性能レベルの計算結果を
要望するならば、必然的に”三重苦レンズ”が出来あがる)
この話は深堀りするとキリが無い為、一部は後述するが
詳しくは、また別の記事に譲ろう。
----
では、次のシステム

(Model G005) (中古購入価格 20,000円)
(以下、SP60/2)
カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)
2009年に発売された、APS-C機専用、中望遠画角
大口径AF等倍マクロレンズ。
本レンズの後、2010年代後半には、デジタル機市場は、
フルサイズ機が主流となった為、本レンズは現行製品
ながらも、製品寿命的には自然終了している状況だ。
ただ、写真撮影上では「フルサイズ機でなくてはならない」
という理由は全く無い。初級中級層がフルサイズ機ばかりに
価値を見い出すから、APS-C機専用で、かつ手ブレ補正も
超音波モーターも無い本レンズが、不人気となる理由も
わからないでは無いが・・
ても、現実はその真逆だ。
本レンズSP60/2の描写力は一級品であり、解像力や、ボケ質
(およびその破綻状況)や、逆光耐性など、どこをとっても
何も不満は無い。

90マクロの代替、として企画開発されたレンズなのだろう。
(すなわち、APS-C機装着時の画角が90mm程度になる)
銘マクロの代替(APS-C版)なのだから性能が悪い筈が無い、
もしイマイチの写りだったら、90マクロの評判にも傷が付くし、
「高描写力マクロのタムロン」というブランドイメージをも
低下させてしまう。(勿論メーカーとしては愚策となる)
おまけに、マクロレンズとしては希少な開放F2の大口径で
かつ、これまでF2級マクロで等倍仕様であった製品は、
恐らくは皆無であったと思われ、本レンズの性能面からの
優位点は多く、歴史的価値もとても高い。
「APS-C機専用」や「超音波モーターが無い」という点は、
先のSP35/1.8等での「大口径F1.4では無い」という事と同様に、
ビギナー層以外においては、気にする必要も無い事であり、
当然ながら欠点では無い。
でも、そういう点を誤解したり、スペックだけを気にする
人(=ビギナー層)のみが、現代においては主力ユーザー
(お金を使って新製品を買ってくれる人達)なのだろう。
結果的に本レンズは不人気で、中古市場では2万円以下の
格安相場だ。
これは、カタログスペックに惑わされないビギナー層以外
の人達から見れば、逆に「極めてコスパの良いレンズ」と
見なされる事は間違いない。

少し固目の描写の為に被写体を選ぶ事、等だが、いずれも
中級者以上の人達には「言わずもがな」のレベルであろう。
勿論、これらは重欠点では無い。
なお、本レンズはSONY機用なので、勿論手ブレ補正は無い。
SONY機やPENTAX機にはボディ内手ブレ補正があるからだ。
よって、サードパーティ製の旧レンズ購入時は、それらの
マウントを選択するのも良い。ただし、2010年代中頃からの
サードパーティ製のレンズは、SONYα (A)版や、PENTAX KAF
版が発売されないケースも多く、困ったものである。
(ただし、残ったそれらのマウントの中古レンズは、
近年、急速に中古相場が下落している。メーカーのみならず
中古流通でも、それらのマウントの縮退を意識しているの
であろう。安価になっていれば買い頃とも言える)
----
では、今回ラストのシステム

(中古購入価格 70,000円)(以下、SP85/1.8)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
2016年に発売された、高描写力単焦点AF中望遠レンズ。
SP35/1.8(F012)やSP45/1.8(F013)より、半年ほど遅く
発売されているが、同一のシリーズ商品である。
これも勿論フルサイズ対応。
85mmは人物撮影に適した焦点距離であるという通説がある。
まあ、必ずしもそうだとは言い切れないが、あまり換算の
焦点距離を長くしない為にも、今回の母艦はフルサイズ機を
使用する。

個人的な購入目的としては、銀塩時代の超名玉の
「smc PENTAX-FA 77mm/f1.8 Limited」の代替用途だ。
「ナナナナ」は屋外・屋内・ステージ等での人物撮影の
どのシーンでも、最良の描写力と、抜群の歩留まりの良さ
(ボケ質破綻の発生が無く、逆光耐性が高く、ピントを
外す場合が少なく、成功率が高い為、安心して使える)
を誇ったレンズで、長年の実用(業務・依頼)撮影で
極めて重宝した。
だが、さすがの「ナナナナ」も発売から15年を過ぎると、
現代レンズに比較して、解像感等の点で見劣りが出てくる。
そこで「本レンズSP85/1.8が、が後継になるのでは?」
と踏んだ次第だ。
長所は、事前の予想通りの素晴らしい描写力であり、
何も文句のつけようがない。「ナナナナ」の代用に十分に
なりうる、まあこの時点で、すでに「名玉」であろう。
「F1.4では無い」という点は、色々書いてきたように全く
問題は無い、・・と言うか、85mm/f1.4級のレンズは
10本程所有しているが、むしろ、どれも「歩留まり」が
かなり悪くて、実用撮影には使用できなかったのだ。
F1.8級中望遠の方が実用上で使えるシーンが遥かに多い。
ピクセルピッチが7.2μmと大きいNIKON Dfで使用する際は
高解像力は、あまり差意が出ないと思うが、より高画素で
ローパスレスの機種で使う場合は、本レンズの解像力が
より際立つであろう。

レンズである事だ、
もっとも、価格については「ナナナナ」と同レベルなので
あまり不満は無いのだが、大きく重いのは、ちょっと困る。
まあ、描写力を優先した設計の為に、F1.8級ながら異常な
までの大きいサイズ感となったのだろうが、やや過剰だ。
それから、ニコンFマウント用で「電磁絞り」を採用して
いる事。これではニコン旧機種や他社機で使用不能のため、
汎用性を失っている。他社よりも操作系のビハインド(遅れ)
があるニコン機でしか、本レンズが使えない点は不満だ。
(注:EOSマウント版を選んでも、他社機に装着しずらい。
まあでも、いずれEF版も予備レンズとして買うべきか?)
なお、海外だったか?どこかのレビューで「焦点移動」が
出る事を弱点としてあげていたが、それは的外れな評価だ。
本レンズの用途上、絞って使う事は有り得ない。
F1.8~F4の間で使うのが基本であり、焦点移動は無視できる。
・・と言うか、設計の時点で焦点移動の発生は確実にわかる。
それでも、あえてそれを残したのは、焦点移動の補正よりも
優先すべき事項(例:解像力やボケ質)があったからであり、
どれかを優先すれば他が犠牲になる「トレードオフ」関係だ。
メーカー側は、ユーザー側の百倍も千倍も、色々と考えて
レンズを設計している訳だ。エンジニアが毎日毎日、何ヶ月
もの間、朝から晩まで頑張って開発しているから当然だ。
ユーザーが、買ったばかりのレンズを喜んで、2~3日撮って
レビューしている状況とはまるで違う時間の「重み」がある。
ユーザーの中級者等が、製品のわずかな弱点を見つけて、
「鬼の首を取ったかのように」騒ぎ立てる必要は、まるで
無いし、むしろ「長所が見えないのか?」と、格好悪い。
製品の細かい弱点がわかるだけのスキルを持っているならば、
それを回避して有益に使うのが上級ユーザーの責務であろう。
「弘法筆をえらばず」という故事があるが、このことわざの
真意は「道具にあれこれと文句をつけるな(使いこなせ)」
という意味だ。
レンズ設計において、全ての弱点を無くす事は不可能だし、
仮に諸収差を全て良好に補正しても三重苦レンズとなるし、
収差が無い事は、高描写力である事とはイコールでは無い。
例えば、前述の名玉FA77/1.8も、手動に近い設計手法で
諸収差をあえて残しながらも、実用上に極めて優れた
「バランス点」を意図して設計されている。
現代では、もうほぼ全てがコンピューター設計になって
しまった為、このような「職人芸的」な設計技法による
レンズ設計は、もう誰もできなくなってしまったのだろう。
・・であれば、あとは、どの収差を優先的に補正するかは、
もう設計者(企画者)の「センス」に依存する。
現代の設計ソフトでは、設計したレンズの評価値(メリット関数)
が表示されるが、ただ単に、その数値を高めようとするだけでは、
バランスの良いレンズ設計には成り得ない、やはり設計者の
センス(バランス感覚)やノウハウが、とても重要なのだ。
だが、「高付加価値化」した利益率の高い製品を作らないと
レンズ市場が維持できない、というメーカー側での大命題も
ある為、ともかく全ての収差を無くす事を目指し、結果的に
十数群十数枚と言う単焦点レンズが出来て、大きく重くなる
のは止むを得ず、また、それにより高価になる事は、むしろ
狙い通り、とメーカー側は考えてしまうだろう。
その事実を、どう判断・評価するかは、ユーザー次第だ、
値段に見合う価値があると思えば購入すれば良いし、
高価すぎる!と思えば、見送るか、または、中古を待って、
自分が希望する価格帯まで値段が下がった頃に買えば良い。

ビギナー層が「カタログスペックだけを気にする」といった
不当な理由により、不人気となって、早めに相場が下がる
事も、前述のように多々ありうる。
特に、SP35mm,45mm,85mmは、不当な不人気の商品で
あるから、早々に価格が下がっていて、コスパがとても良い。
中級層以上のユーザーであれば、一応、それらに代替できる
類似スペックの旧レンズを持っているとは思うが、
これらSP単焦点は、旧製品とは次元の違う高描写力を持つ。
しかるべきタイミングで入手しておくのが良いであろう。
特に本SP85/1.8は、私の購入時点よりも、近年ではさらに
中古相場の下落が大きいので、推奨しやすいレンズだ。
----
さて、今回の記事「TAMRON SPレンズ特集」は、
このあたり迄。他にも紹介したいSPレンズが何本もあった
のだが、記事が冗長になる為、やむなく他記事に廻そう。
では、次回記事に続く・・