高いコストパフォーマンスと付随する性能を持った優秀な
写真用交換レンズを、コスパ面からの評価点でのBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回もまた、ランクインしたレンズを順次紹介して行こう。
---
第16位
評価得点 3.95 (内、コスパ点 4.0)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズ名: OLYMPUS Body Cap Lens BCL-0980 9mm/f8
レンズ購入価格:8,000円(新品)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
ハイコスパ第5回記事で紹介の2010年代のμ4/3専用魚眼レンズ。
ボデイキャップ型レンズであるが、ちゃんとピントレバーを持つ
MFレンズである。また、この薄さでも4群5枚という、まともな
レンズ構成となっている。ただし絞り機構は無く、F8固定だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
本BCL-0980は、対角線魚眼風の写りが得られる。
なお、上写真での「周辺減光」は、エフェクトによるもので、
レンズ自体の問題点では無い。
被写界深度がかなり深い為、ピントレバーを用いる必要は
ほとんど無く、中遠距離撮影の際はパンフォーカス位置
(クリックストップがある)に固定しておけば良い。
近接撮影時は、勿論ピントを正しく合わせる必要がある。
何故ならば、被写界深度は撮影距離が短くなると浅くなる為だ。
その際の最短撮影距離は20cmと、もう一声寄れて欲しいが、
まあ、昔から魚眼レンズの最短撮影距離はこれ位のものである。
レンズの厚みは12.8mmと薄く、重量は30gと、まあ数値だけ
見れば相当に軽いが、同シリーズの15mm/f8(BCL-1580)
(ミラーレス第0回等)の22gと比べると、これでもちょっと
厚く、重く感じる。
当然、この重量の数値はデジタル一眼レフ用の最軽量レンズ
(smc PENTAX-DA40mm/f2.8XS 52g,本シリーズ第1回
記事)よりも軽い。
レンズを小型化できる事が、ミラーレス機、特にμ4/3機の
特徴である。
また、μ4/3機でアダプターを用いて、フルサイズ用魚眼
レンズを装着すると、画角が狭く、殆ど魚眼効果が出ないが
そういう点でも、μ4/3専用魚眼レンズは貴重だ。
各種フィルターは装着する事が出来ない。この点はBCL-1580も
同様である。ちなみに上記DA40/2.8XSは、φ27mmと特殊な
径ながらもフィルター使用は可能だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
本BCL-0980は、一見玩具のようだが、トイレンズでは無い。
トイレンズの魚眼というのは種類が多く、例えば過去記事
ではPENTAX 03 FISH-EYE(本シリーズ第5回記事)や
Lomography Experimental Lens Kitの中の魚眼レンズ
(ミラーレス・マニアックス第15回記事)等がある。
本BCL-0980の描写力は、それらのトイレンズとは異なり、
通常レンズに近いものがある。つまり、まともに写る魚眼で
ある、という事だ。
旧来、こうしたトイ系レンズは、μ4/3マウント用の場合は
μ4/3「トイレンズ母艦」としての、OLYMPUS E-PL2に
装着して使う事が殆どだった。
が、そのE-PL2(2011年)も、使用5年を過ぎたあたりから、
少々不調(動作不良)となり、まだ使える事は確かだが、
安心しては使え無い事や、仕様老朽化寿命が厳しくなって
きたので、新たなトイレンズ母艦が必要な状況であった。
ただ、その用途に適切なカメラにはまだ代替が出来ておらず、
今回はやむなく、高級機のE-M5 MarkⅡを使っている次第だ。
なお、トイレンズ母艦の条件としては、
1)AF/MF性能があまり優れていない事
(つまり、ピント合わせの負担が少ないトイレンズを
使うのであれば、カメラの弱点を相殺できる)
2)μ4/3機(または他マウント機)で安価な機体である事
3)できればフラッシュ(ストロボ)を内蔵している事
4)高感度(ISO6400以上)が使え、AUTO ISO設定のままでも
そうした高感度域に到達する事
5)ボディ内蔵手ブレ補正がある事
6)できれば多数のエフェクト(画像加工)機能を内蔵している事
7)小型軽量である事
8)EVF非搭載機でも良いが、できればピーキングや拡大操作系
等のMFアシスト性能が高い事。
9)多くのマウントアダプターが使用できるマウントである事
を想定している、いずれも私にとっては意味がある条件で
あるのだが、実のところ、この条件に当てはまるカメラは
そう多くは無い。
旧来は、ほぼE-PL2しか、この条件の多くを満たすカメラは
なかったと思う。
近年では、例えばOLYMPUS機ではE-M10系や、E-PL9
PANA機ならばDMC-GF7以降ならば、殆ど全ての条件に
当てはまるのだが、いずれも、検討時点では、まだ中古
相場が若干高価であったのが問題だった。(むしろE-M1等の
旧型旗艦機の方が、中古相場が安価な時期もあったので、
その機種を購入し、トイレンズ母艦の代用としている事もある)
高価なカメラでは(今回のケースもそうだ)レンズの価格よりも
カメラ本体の価格が突出する「オフサイドルール」の持論に
ひっかかってしまうが、まあハイコスパ編なのでやむを得ない。
(ただ、普段使いの場合は、ちょっと意識する必要がある)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19345356.jpg]()
トイレンズ母艦の話が長くなった。
本レンズBCL-0980であるが、実のところ、あまり書く事が無い、
長所短所などは、過去記事でも色々書いてあるので重複するし
そもそも、そういう事を気にするような価格帯のレンズでは無い。
オリンパスでは、これはレンズではなく「アクセサリー」の
分類としているのだ。
課題としては、以前の記事でも書いたが、実際に魚眼撮影の
用途があるか?あるいは、その頻度が高いか?という点だろう。
実際には魚眼レンズの用途は、さほど多くはないと思うので、
必要度は少ないかも知れないが、まあこの価格帯であれば
魚眼レンズに対する興味本位で「お試し版」的に買っても
なんら問題は無い事であろう。
---
第15位
評価得点 4.00 (内、コスパ点 4.0)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19350353.jpg]()
レンズ名:TAMRON SPAF60mm/f2 DiⅡ LD IF
Macro 1:1 (Model G005)
レンズ購入価格:19,000円(中古)
使用カメラ:SONY α65(APS-C機)
ハイコスパ第14回記事で紹介した2009年発売のAPS-C機
専用AF大口径単焦点標準(中望遠画角)マクロレンズ。
最大の特徴だが、F2という明るい開放F値のマクロは希少だ。
そういう仕様の他のレンズは、全て1/2倍以下の撮影倍率で
あったのが、本レンズは唯一、等倍(1:1)を実現している。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19350386.jpg]()
本レンズは、非常に長い名前であるが、2010年のTAMRONの
60周年記念モデル、SP70-300mm/f4-5.6 Di USD (A005)
(本シリーズ第8回記事)の時代より、LDやらIFやらの性能を
示す余計な文字が消えてすっきりするようになったが、
その直前に発売されたレンズであるので、ともかく長い。
1:1という型番名も、本レンズが希少な「F2級等倍マクロ」で
ある事を強調する為であろう。
結局「G005」とか「A005」とかのTAMRON独自の「Model名」で
呼んだ方がずっと楽なのだが、これでは、仮に上級マニアで
あったとしても、このModel名からレンズ機種を特定する事は
ほぼ不可能であろう。このModel名には命名の規則性は無いので、
TAMRONの全種類のレンズとModel名の対応を一々覚える必要が
ある、それは大変な事だ。
LD(Low Dispersion=特殊低分散ガラスを使用)とか
VC(Vibration Compensation=光学手ブレ補正内蔵)とか
そういう表記を付けていって、結果的にレンズ名称が物凄く
長くなってしまう事は、いちがいにメーカー側だけの責任
という訳でもない。
すなわち、そういうスペックは「付加価値」であるから
ユーザー側としては、「それが気になってしかたが無い」
人もかなり多い、という事実だ。
例えば「超音波モーターが入ってなくちゃイヤだ」とか
「内蔵手ブレ補正は絶対に必要だ」とか、そういうユーザー層
の事である。
で、そういうユーザー層が世の中の大半であるが為に、各々の
レンズには、手ブレ補正や超音波モーターや低分散ガラスを
使っている事などを示す長々とした名前が必要な訳だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19350355.jpg]()
だが、根本的な疑問がある、本当にそれらの付加機能は
必要なのだろうか?
SIGMAには「Art Line」という高性能単焦点レンズ群がある。
例えばArt 50mm/f1.4 DG HSM(レンズマニアックス第2回)
やArt 135mm/f1.8 DG HSM(レンズマニアックス第6回)
等であるが、これらは内蔵手ブレ補正機構を持たない。
私は、これらのレンズが「手ブレ補正を持たない」事で、
むしろ、それが気に入って購入したのだ。
まあ、これらのレンズは高性能ではあるが、かなり高価な
単焦点レンズであるし、用途も極めて限られる。
よって、今時の初級中級層が欲しがるようなレンズでは無く、
上級者/業務用途専用レンズとも言える。
ここで考えてみよう、手ブレ補正が入っていなくても問題は
無いのか?・・その答えは「概ね問題無し」である。
よほどの限界状態で無い限り、ISO感度を必要に応じて高める
等の、ごく簡単な措置により手ブレは減る。
まあ、こういう事は中上級者ならば誰でも知っている。
すなわち「手ブレ補正が無くちゃ、超音波モーターでなくちゃ」
と言うのは、「限界状況でも撮影しなければならない」必要性
がある職業写真家層を除いては、初級者層しか言わない事だ。
レンズやカメラ側の性能に頼る、というのは、自身のスキル
(技術、技能、経験、知識等)に自信を持てない初級者層の
特徴である。
職業写真家層が最高の性能の機材を使うのは、当たり前の話だ。
彼らはどんなに条件が悪い状況でも、写真を撮らないと商売に
ならない。だから、そうした限界状況においても、少しでも
ちゃんと撮れる確率を増やす為に、最高性能の機材を使うのだ。
(まあ機材購入費で収支が赤字にならない、という条件付きだ。
でもこれは、近年重要なポイントとなってきていて、新鋭機が
高価すぎる為、それを使わない職業写真家層が増えて来ている)
ところが、最高級機材を欲しがるのは、初級中級者層も
また同様である、銀塩時代の昔からも、そうした傾向は
若干あったのだが、近年は特にその傾向が強い。
シニアの写真クラブのような団体を見ていると、ほぼ全員が
最新機種と高級レンズで武装している。
ところがカメラやレンズを持つ構えとか、撮っている被写体と、
その画角・構図(構図とかは、外から見ていてるだけでも
だいたいはわかる)とかを見ると、どうみても、まったくの
超ビギナーばかりだ。
これは「腕前と機材のバランスが取れていない状態」である。
以前ならば「お金が余っているのだろうな・・ あるいは、
そういう機材を買って周囲に自慢したいのか? はたまた、
廻りの人が”これが良い”と言ったので、訳もわからずに
言われるがままに、高いものを買わされているのか・・?」
等と、そんな風に見ていたのだが、確かにそういう理由は強い
だろうが、近年は、またちょっと違う状況が見えて来ている。
彼らは「自分のスキルに自信を持てない」のだ、だから、
最高の性能の機材を買って、その課題をカバーしようと
している事が良くわかってきた。(この事は、多数の
初級者層からのヒアリング等による確かな情報である)
で、この話はシニア層のみならず、若い人も同様だ。
若年層の方が可処分所得(自由に使えるお金)が少ない為、
高級機材を買う事は、余計に大変な事であろう。
でも、例えばボ-ナスをつぎ込んで、そうした機材を買う訳だ。
初級者層では「数年前の機材を使っている人が誰も居ない」
という状況が、その事を如実に表している。
5~6年前の機材を十分に使いこなしている様子が見れれば
「ああ、この人は、もう5~6年写真をやっているのだな、
中級レベルだろうか・・?」と、外から見て取れるのだが・・
初級者層は、たとえ実際に写真を5~6年もやっていたとしても、
古い機材を使わない。何故ならば、「古いカメラは性能が低い
から撮れる写真が良く無い、カメラの性能をカバーできる程の
腕前は持っていない」と自身で強く思い込み、まだまだ現役で
十分に使える機材を処分して、最新型の機材に買い換えて
しまうのだ・・
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19350494.jpg]()
レンズでの話もまったくの同様だ、
「手ブレ補正が入ってないと・・」等と言う人は、殆どが
初級者である。つまり、どのような状況において、手ブレが
発生するかが理解できていないから、機材に頼らざるを得ない。
それは彼らに直接話を聞いてみれば、その事が良くわかる。
「超音波モーター」もしかり、初級者はMFが上手く出来ない
事はもとより、一般的なAFモーターでも怖いのだ、何故ならば
ピンボケというリスク(危険性)が増大すると思い込むからだ。
もう1つ、じゃあ手ブレとかピンボケを何故そこまで恐れるか?
と言えば、それも答えは簡単だ。
つまり、初級者においては「ピンボケや手ブレは、悪い写真だ。
もしそういう写真を撮ってしまったら、周囲から”下手だ”と
思われてしまう、それが怖い」という強迫観念を持っている。
そもそもブレやピンボケが入っていれば必ずダメな写真なのか?
いや、そう言う単純な話では無いのは誰でも知っている事であろう。
じゃあ何故そう言われるのか? それは写真を見る側のスキルの
不足だろう。ブレやピンボケは誰でも見ればすぐわかる、だから
そこだけを「問題だ!」と指摘し、その他の評価を行わない。
写真の良し悪しの評価は、相当に経験や感受性や価値感覚が
無いとわからない、かなりの高難易度の作業だ。
結局、写真のアート的な側面について評価できないビギナー層が、
「ビンボケだからダメな写真だ」と簡単に言ってしまう訳だ。
ちなみに、こういう事はアート的な要素を持つ写真学校等で
学んでみればすぐわかる。そういう所では、経験を積んだ
講師等が、写真の「表現」についての評価を主に行うが、
その際、ブレているからダメだ、等とは一言も言わない。
そこは重要な事ではなく、評価するべきは「何を、どう撮ろうと
したのか?」という部分なのだ。
つまりは、ピンボケやブレしか評価できない事自体が、完全な
ビギナーレベルでしか無いという事になる。
ここまで様々な側面からの多面的な話をしてきたが、
結局のところ、初級中級層は、写真の本質とは全く違う方向性
を見ていて、その事が間接的に高価な最新機材を欲しがる事に
繋がっていく。
う~ん、これはもう、何と言うか・・
これらの総合的な状況は、一言で言えば「残念な話である」
・・としか言いようが無いが、でもまあ、別の側面から見れば、
こういうユーザー層が居てくれるからこそ、せっせと新製品を
買ってくれて、現代において縮退した一眼レフやミラーレス機
の市場を支えてくれている状況だ。
そうしたカメラ界全体の現状やらの、大きな話を考え無くても、
個人的なレベルにおいても関係はある。
初級中級層が、そうやって最新機種に買い換えた後、
古いカメラやレンズは中古市場に流れてくるのだ。
私としては、一世代や二世代古い機材でも何ら不満は無い、
だから、そういうちょっと古いカメラを中古で安く買う為にも
どんどんと初級中級層には最新機種を買い続けて貰いたい訳だ。
結局、「残念な話」ではあるが、誰も損はしない。
まあ、だから、あまり気にしないようにしよう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19350344.jpg]()
余談が極めて長くなった(汗)
でも、こういう事は重要な「一次情報」だ、他にはそういう
情報はどこからも得られない。
レンズの性能や仕様の話等は、そういうのが好きな人に
まかせておけば良い話だ。
さて、本レンズSP60/2であるが、輪郭がやや硬い描写傾向があり
これは被写体を選ぶ事にも繋がるのだが、総合的には、とても
秀逸なマクロレンズだ。
APS-C機専用なので、そこを嫌がる人も居るかも知れないが、
「フルサイズでなくちゃイヤだ」というのも、ここまで散々
述べてきた初級中級層の問題点と同じ事だ。
フルサイズ対応で無い事は、本レンズの重欠点とは言えない。
・・まあ、だからこそ第15位という高い順位にランキング
されているレンズなのだ。
換算画角が90mm相当と同じになるTAMRON SP90/2.8との
住み分けはやや難しい、描写傾向は違うとは言えるのだが
SP90/2.8はロングセラーで年代により色々なバージョンが
あるので、一概には比較できない。
そこが気になるならば、あれこれ悩まずに両方買ってしまう
と言う選択肢もある。
本レンズは、そんなに高価なレンズでは無いのだ。
その事が、ハイコスパレンズという真髄であろう。
---
第14位
評価得点 4.00 (内、コスパ点 3.5)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19351926.jpg]()
レンズ名:フォクトレンダー APO-LANTHER 90mm/f3.5 SL
レンズ購入価格:47,000円(新品)
使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回記事で、
栄光の第5位に輝いた、2000年代初頭のMF単焦点中望遠。
まあ、一言で言えば、とても高品位(高性能)なレンズである。
ただし、若干入手価格が高価であったので従来の「ハイコスパ」
のシリーズ記事では紹介を見送っていた。
高価であったのは、発売直後に新品で購入したのが理由だ。
ただ、本レンズの中古流通は少なく、後年ではセミレアと
なってしまったので、早目に買っておいて良かったとも言える。
まあ、コシナ製品は、こういうケース(後年では入手不能)が
多い事も想定しての新品買いでもあった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19351923.jpg]()
本ランキングは「入手不能のレンズは対象外」とするのだが、
本レンズはギリギリの状況だ、このバージョンは、もう入手
不能かも知れないが、比較的近年まで後継バージョンが発売
されていたので、それであれば、まだかろうじて入手可能で
あるかも知れないのだ。
さて、90mmでF3.5は、ちょっと地味なスペックである。
ビギナー層は「開放F値の明るいレンズの方が高価なので、
それは良く写る性能の良いレンズだ」と思い込んでいるかも
知れないが、実際には、まるでそんな事は無い。
むしろ、開放F値を抑えたレンズというものが存在する意義を
考えてみると良い、ビギナー層等が、F値が明るいレンズを
欲しがる中、何故、わざわざこういう仕様のレンズが
発売されるのか?
その理由は「設計において、非常に拘りを持っているから」
だと考えるのが正解であろう。つまり、口径比を明るく
すると、諸収差のオンパレードとなる。だが、開放F値が
明るく無いと、初級中級ユーザー層は良いレンズだとは
思わず、買ってくれなくなる。でも、本レンズでは、あえて
性能(収差補正)を重視し、「わかる人だけが買えば良い」
という、拘りの製品企画コンセプトとなっている訳だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19351982.jpg]()
本レンズは、発売後に、とある雑誌で収差等の数値性能を
調べた際、弱点が一切無い、ほぼ完璧な性能のレンズとして
評価された。
まあでも、数値評価が、必ずしも良い写りに直結するという
事も無い、何故ならば、数値で表せる要素は、レンズ性能の
ごくごく一部でしか無いからだ。
さて、そういう視点から本レンズを捉えてみると・・
確かに弱点は何も無い。解像感、コントラスト、逆光耐性、
ボケ質、ボケ質の破綻頻度、MF感触、重量やサイズ、
そして最短撮影距離も50cmと極めて短い。
つまり、全ての点で満足がいくレンズだ。
ちなみに本レンズの私の性能評価は「5点満点」となっている。
本ランキングの対象となっているおよそ320本のレンズの内、
描写表現力の評価が5点満点のレンズは14本しか存在しない。
本アポランター90/3.5は、その中の1本だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19351819.jpg]()
弱点は特に無い、あえて言えば、セミレアになっていて
入手が困難な事が、やはり課題であろうか・・
でも、厳しい事を言えば、近年まで売っていたのだから
その時に買わない方が問題だ、という見方もある。
つまり「F3.5という暗い開放F値だから、たいした事が無い
レンズだ」と思い込んでしまい、興味をもてず、本レンズの
本質が見抜けなかったという事だ。
誰かが「良い」と言ったからと、手に入り難くなってから、
慌てて探す、と言うのでは、ちょっとズレてしまっている。
そして、コシナ社の製品は、たいていが初回生産の1ロット
だけで打ち止めであり、あまり再生産や継続生産をしない
事は、マニアであれば知っているであろう。
自身の価値観を持ち、正しい評価感覚を持ち、欲しいものは
買える時に買っておく、それがマニアにおける鉄則だ。
まあ、初級層が必要とするレンズでは無い事は確かであろう。
あくまでマニア向けだからこそ、そういう厳しい話になる訳だ。
「アーティストが亡くなってから、慌ててCDを買いに走る人」
等は、当然、マニアとは見なされ無い事は言うまでも無い。
---
第13位
評価得点 4.00 (内、コスパ点 4.0)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19352760.jpg]()
レンズ名:smc PENTAX-FA Macro 50mm/f2.8
レンズ購入価格:24,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第1回記事で総合16位に
ランクインした1990年代のAF標準等倍マクロレンズ。
本シリーズでは少しだけランクが上がっている。
24,000円の価格で、コスパ4点は、ちょっと甘い評価かも
知れない。
ただしこのレンズは1990年代の、発売間もないタイミングで
購入したので若干高目であった。近年であれば軽く2万円を
切る中古相場になっているので、そういう状況も考慮しての、
コスパ評価点の若干の加点である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19352877.jpg]()
以前の記事で「このランキングの上位は、マクロと
エントリーレンズばかりになって来る」と書いたが、
だんだんそうした状況に近くなってきている。
まあ、結局のところハイコスパという観点からは、そういう
結果になるのであろう。
ただまあ、実際にそうなってしまったら、ランキングも
「予定調和」となって、あまり面白味も無い。
まあ、たまに意外なレンズもランクインする予定であるので
そこが楽しみであろう。
---
本レンズFA Macro 50mm/f2.8の話に戻るが、
この時代(1990年代)の標準マクロは高性能な製品が多い、
例えば、MINOLTA AF50/2.8やSIGMA AF50/2.8がそうであり、
本レンズも同様に描写表現力が、かなり高い。
これ以前の時代(1980年代)のMFマクロから比べると、
等倍マクロになった事とAFになった事に加えて、描写力の
改善要素が非常に大きく、何らかの大きな「技術革新」が、
この時代にあったのだろうと想像している。
そういえば、TAMRON SP90/2.5の、AF版(F2.8版、等倍)
への改良(Model 72E)も、この時代(1996年)であった。
1つのメーカーが何らかの技術革新を行うと、他社もその先行
製品を研究しつくし、そこに追従しようとする。
だから数年で、その新技術は一般化して、メーカー間の性能の
差は殆ど無くなるのだ。
(よって「メーカーによる性能の差なんて無い」と、本ブログ
では、いつも言っている)
そして、最初にその技術を開発したメーカーは、その分、名前
を上げる事ができる、それはブランドイメージとも言える。
例えば「マクロを買うならばTAMRON製が良い」といった感じだ。
新技術の先行優位性は、ごく短期間だけだ。その間に、いかに
優位性をユーザー層にアピールして、それを購買欲やブランド
力に転換していくかが、メーカー側の市場戦略の要となる訳だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19352843.jpg]()
さて、本レンズは、そういう時代背景の中での完成度の高い
マクロであるから、性能的な不満や弱点は感じ難い事であろう。
実質的な弱点は2点、まずAFの精度や速度がこの時代の製品故に
見劣りする事だが、この点はマクロレンズなのでMFを中心と
した撮影になるだろうから、重欠点とは言えない。
第二に、デザイン(見た目)が壊滅的に悪い事だ。
そういうのは個人の好き嫌いもあるかもしれないが、これは
「誰が見てもダメだ」というレベルに近い。
ただ、この点については、後年2000年代の後継レンズ
smc PENTAX-D FA Macro 50mm/f2.8 が存在する(未所有)
これは本レンズと、ほぼ同じレンズ構成やスペックであるが
デジタル対応で様々な小改良がある事が想像され、絞り環も
ちゃんと存在するし、なによりデザインが良くなっている。
DFA型の中古相場は、本FA50/2.8よりも1万円ほど高価に
なるが、旧型のデザインがどうしても気になるならば、
そういう選択肢もあるだろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19352721.jpg]()
なお、この時代(1990年代前半)のFA型のレンズは、どれも
デザインが非常に悪い。ただ、明らかにそういう弱点がある事は
当然メーカー側でも認識されていた為、例えば1990年代末での
FA-Limited型レンズ等は、大幅にデザインと高級感が増している。
それに続く現代のPENTAXのレンズ群も同様にデザイン面での
課題は少なくなっている。
要は、課題が誰の目にも明らかである方が、思い切った対応が
しやすいという事であろう。1990年代でのPENTAX AF一眼レフ
のデザインや操作系の改善(Zシリーズ→MZシリーズ)や、
同時代のMINOLTA α一眼レフの操作系の大幅な改善も、
旧機種のそれに大きな問題があったからだ。
なお、その背景では、1990年代初頭のバブル崩壊、1995年の
阪神淡路大震災によるユーザー層のマインド(心理や価値観)
の変化も無視できないが、その話は冗長になるので他記事に譲る。
で、課題があまり大きな問題と見なされないと、ずるずると
弱点を長期間引きずったままになってしまっているメーカーも
現代に至るまで非常に多い。
----
今回はこのあたりまでで、次回記事も、引き続き
ランキングレンズを順次紹介していこう。
写真用交換レンズを、コスパ面からの評価点でのBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回もまた、ランクインしたレンズを順次紹介して行こう。
---
第16位
評価得点 3.95 (内、コスパ点 4.0)
Clik here to view.

レンズ購入価格:8,000円(新品)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)
ハイコスパ第5回記事で紹介の2010年代のμ4/3専用魚眼レンズ。
ボデイキャップ型レンズであるが、ちゃんとピントレバーを持つ
MFレンズである。また、この薄さでも4群5枚という、まともな
レンズ構成となっている。ただし絞り機構は無く、F8固定だ。
Clik here to view.

なお、上写真での「周辺減光」は、エフェクトによるもので、
レンズ自体の問題点では無い。
被写界深度がかなり深い為、ピントレバーを用いる必要は
ほとんど無く、中遠距離撮影の際はパンフォーカス位置
(クリックストップがある)に固定しておけば良い。
近接撮影時は、勿論ピントを正しく合わせる必要がある。
何故ならば、被写界深度は撮影距離が短くなると浅くなる為だ。
その際の最短撮影距離は20cmと、もう一声寄れて欲しいが、
まあ、昔から魚眼レンズの最短撮影距離はこれ位のものである。
レンズの厚みは12.8mmと薄く、重量は30gと、まあ数値だけ
見れば相当に軽いが、同シリーズの15mm/f8(BCL-1580)
(ミラーレス第0回等)の22gと比べると、これでもちょっと
厚く、重く感じる。
当然、この重量の数値はデジタル一眼レフ用の最軽量レンズ
(smc PENTAX-DA40mm/f2.8XS 52g,本シリーズ第1回
記事)よりも軽い。
レンズを小型化できる事が、ミラーレス機、特にμ4/3機の
特徴である。
また、μ4/3機でアダプターを用いて、フルサイズ用魚眼
レンズを装着すると、画角が狭く、殆ど魚眼効果が出ないが
そういう点でも、μ4/3専用魚眼レンズは貴重だ。
各種フィルターは装着する事が出来ない。この点はBCL-1580も
同様である。ちなみに上記DA40/2.8XSは、φ27mmと特殊な
径ながらもフィルター使用は可能だ。
Clik here to view.

トイレンズの魚眼というのは種類が多く、例えば過去記事
ではPENTAX 03 FISH-EYE(本シリーズ第5回記事)や
Lomography Experimental Lens Kitの中の魚眼レンズ
(ミラーレス・マニアックス第15回記事)等がある。
本BCL-0980の描写力は、それらのトイレンズとは異なり、
通常レンズに近いものがある。つまり、まともに写る魚眼で
ある、という事だ。
旧来、こうしたトイ系レンズは、μ4/3マウント用の場合は
μ4/3「トイレンズ母艦」としての、OLYMPUS E-PL2に
装着して使う事が殆どだった。
が、そのE-PL2(2011年)も、使用5年を過ぎたあたりから、
少々不調(動作不良)となり、まだ使える事は確かだが、
安心しては使え無い事や、仕様老朽化寿命が厳しくなって
きたので、新たなトイレンズ母艦が必要な状況であった。
ただ、その用途に適切なカメラにはまだ代替が出来ておらず、
今回はやむなく、高級機のE-M5 MarkⅡを使っている次第だ。
なお、トイレンズ母艦の条件としては、
1)AF/MF性能があまり優れていない事
(つまり、ピント合わせの負担が少ないトイレンズを
使うのであれば、カメラの弱点を相殺できる)
2)μ4/3機(または他マウント機)で安価な機体である事
3)できればフラッシュ(ストロボ)を内蔵している事
4)高感度(ISO6400以上)が使え、AUTO ISO設定のままでも
そうした高感度域に到達する事
5)ボディ内蔵手ブレ補正がある事
6)できれば多数のエフェクト(画像加工)機能を内蔵している事
7)小型軽量である事
8)EVF非搭載機でも良いが、できればピーキングや拡大操作系
等のMFアシスト性能が高い事。
9)多くのマウントアダプターが使用できるマウントである事
を想定している、いずれも私にとっては意味がある条件で
あるのだが、実のところ、この条件に当てはまるカメラは
そう多くは無い。
旧来は、ほぼE-PL2しか、この条件の多くを満たすカメラは
なかったと思う。
近年では、例えばOLYMPUS機ではE-M10系や、E-PL9
PANA機ならばDMC-GF7以降ならば、殆ど全ての条件に
当てはまるのだが、いずれも、検討時点では、まだ中古
相場が若干高価であったのが問題だった。(むしろE-M1等の
旧型旗艦機の方が、中古相場が安価な時期もあったので、
その機種を購入し、トイレンズ母艦の代用としている事もある)
高価なカメラでは(今回のケースもそうだ)レンズの価格よりも
カメラ本体の価格が突出する「オフサイドルール」の持論に
ひっかかってしまうが、まあハイコスパ編なのでやむを得ない。
(ただ、普段使いの場合は、ちょっと意識する必要がある)
Clik here to view.

本レンズBCL-0980であるが、実のところ、あまり書く事が無い、
長所短所などは、過去記事でも色々書いてあるので重複するし
そもそも、そういう事を気にするような価格帯のレンズでは無い。
オリンパスでは、これはレンズではなく「アクセサリー」の
分類としているのだ。
課題としては、以前の記事でも書いたが、実際に魚眼撮影の
用途があるか?あるいは、その頻度が高いか?という点だろう。
実際には魚眼レンズの用途は、さほど多くはないと思うので、
必要度は少ないかも知れないが、まあこの価格帯であれば
魚眼レンズに対する興味本位で「お試し版」的に買っても
なんら問題は無い事であろう。
---
第15位
評価得点 4.00 (内、コスパ点 4.0)
Clik here to view.

Macro 1:1 (Model G005)
レンズ購入価格:19,000円(中古)
使用カメラ:SONY α65(APS-C機)
ハイコスパ第14回記事で紹介した2009年発売のAPS-C機
専用AF大口径単焦点標準(中望遠画角)マクロレンズ。
最大の特徴だが、F2という明るい開放F値のマクロは希少だ。
そういう仕様の他のレンズは、全て1/2倍以下の撮影倍率で
あったのが、本レンズは唯一、等倍(1:1)を実現している。
Clik here to view.

60周年記念モデル、SP70-300mm/f4-5.6 Di USD (A005)
(本シリーズ第8回記事)の時代より、LDやらIFやらの性能を
示す余計な文字が消えてすっきりするようになったが、
その直前に発売されたレンズであるので、ともかく長い。
1:1という型番名も、本レンズが希少な「F2級等倍マクロ」で
ある事を強調する為であろう。
結局「G005」とか「A005」とかのTAMRON独自の「Model名」で
呼んだ方がずっと楽なのだが、これでは、仮に上級マニアで
あったとしても、このModel名からレンズ機種を特定する事は
ほぼ不可能であろう。このModel名には命名の規則性は無いので、
TAMRONの全種類のレンズとModel名の対応を一々覚える必要が
ある、それは大変な事だ。
LD(Low Dispersion=特殊低分散ガラスを使用)とか
VC(Vibration Compensation=光学手ブレ補正内蔵)とか
そういう表記を付けていって、結果的にレンズ名称が物凄く
長くなってしまう事は、いちがいにメーカー側だけの責任
という訳でもない。
すなわち、そういうスペックは「付加価値」であるから
ユーザー側としては、「それが気になってしかたが無い」
人もかなり多い、という事実だ。
例えば「超音波モーターが入ってなくちゃイヤだ」とか
「内蔵手ブレ補正は絶対に必要だ」とか、そういうユーザー層
の事である。
で、そういうユーザー層が世の中の大半であるが為に、各々の
レンズには、手ブレ補正や超音波モーターや低分散ガラスを
使っている事などを示す長々とした名前が必要な訳だ。
Clik here to view.

必要なのだろうか?
SIGMAには「Art Line」という高性能単焦点レンズ群がある。
例えばArt 50mm/f1.4 DG HSM(レンズマニアックス第2回)
やArt 135mm/f1.8 DG HSM(レンズマニアックス第6回)
等であるが、これらは内蔵手ブレ補正機構を持たない。
私は、これらのレンズが「手ブレ補正を持たない」事で、
むしろ、それが気に入って購入したのだ。
まあ、これらのレンズは高性能ではあるが、かなり高価な
単焦点レンズであるし、用途も極めて限られる。
よって、今時の初級中級層が欲しがるようなレンズでは無く、
上級者/業務用途専用レンズとも言える。
ここで考えてみよう、手ブレ補正が入っていなくても問題は
無いのか?・・その答えは「概ね問題無し」である。
よほどの限界状態で無い限り、ISO感度を必要に応じて高める
等の、ごく簡単な措置により手ブレは減る。
まあ、こういう事は中上級者ならば誰でも知っている。
すなわち「手ブレ補正が無くちゃ、超音波モーターでなくちゃ」
と言うのは、「限界状況でも撮影しなければならない」必要性
がある職業写真家層を除いては、初級者層しか言わない事だ。
レンズやカメラ側の性能に頼る、というのは、自身のスキル
(技術、技能、経験、知識等)に自信を持てない初級者層の
特徴である。
職業写真家層が最高の性能の機材を使うのは、当たり前の話だ。
彼らはどんなに条件が悪い状況でも、写真を撮らないと商売に
ならない。だから、そうした限界状況においても、少しでも
ちゃんと撮れる確率を増やす為に、最高性能の機材を使うのだ。
(まあ機材購入費で収支が赤字にならない、という条件付きだ。
でもこれは、近年重要なポイントとなってきていて、新鋭機が
高価すぎる為、それを使わない職業写真家層が増えて来ている)
ところが、最高級機材を欲しがるのは、初級中級者層も
また同様である、銀塩時代の昔からも、そうした傾向は
若干あったのだが、近年は特にその傾向が強い。
シニアの写真クラブのような団体を見ていると、ほぼ全員が
最新機種と高級レンズで武装している。
ところがカメラやレンズを持つ構えとか、撮っている被写体と、
その画角・構図(構図とかは、外から見ていてるだけでも
だいたいはわかる)とかを見ると、どうみても、まったくの
超ビギナーばかりだ。
これは「腕前と機材のバランスが取れていない状態」である。
以前ならば「お金が余っているのだろうな・・ あるいは、
そういう機材を買って周囲に自慢したいのか? はたまた、
廻りの人が”これが良い”と言ったので、訳もわからずに
言われるがままに、高いものを買わされているのか・・?」
等と、そんな風に見ていたのだが、確かにそういう理由は強い
だろうが、近年は、またちょっと違う状況が見えて来ている。
彼らは「自分のスキルに自信を持てない」のだ、だから、
最高の性能の機材を買って、その課題をカバーしようと
している事が良くわかってきた。(この事は、多数の
初級者層からのヒアリング等による確かな情報である)
で、この話はシニア層のみならず、若い人も同様だ。
若年層の方が可処分所得(自由に使えるお金)が少ない為、
高級機材を買う事は、余計に大変な事であろう。
でも、例えばボ-ナスをつぎ込んで、そうした機材を買う訳だ。
初級者層では「数年前の機材を使っている人が誰も居ない」
という状況が、その事を如実に表している。
5~6年前の機材を十分に使いこなしている様子が見れれば
「ああ、この人は、もう5~6年写真をやっているのだな、
中級レベルだろうか・・?」と、外から見て取れるのだが・・
初級者層は、たとえ実際に写真を5~6年もやっていたとしても、
古い機材を使わない。何故ならば、「古いカメラは性能が低い
から撮れる写真が良く無い、カメラの性能をカバーできる程の
腕前は持っていない」と自身で強く思い込み、まだまだ現役で
十分に使える機材を処分して、最新型の機材に買い換えて
しまうのだ・・
Clik here to view.

「手ブレ補正が入ってないと・・」等と言う人は、殆どが
初級者である。つまり、どのような状況において、手ブレが
発生するかが理解できていないから、機材に頼らざるを得ない。
それは彼らに直接話を聞いてみれば、その事が良くわかる。
「超音波モーター」もしかり、初級者はMFが上手く出来ない
事はもとより、一般的なAFモーターでも怖いのだ、何故ならば
ピンボケというリスク(危険性)が増大すると思い込むからだ。
もう1つ、じゃあ手ブレとかピンボケを何故そこまで恐れるか?
と言えば、それも答えは簡単だ。
つまり、初級者においては「ピンボケや手ブレは、悪い写真だ。
もしそういう写真を撮ってしまったら、周囲から”下手だ”と
思われてしまう、それが怖い」という強迫観念を持っている。
そもそもブレやピンボケが入っていれば必ずダメな写真なのか?
いや、そう言う単純な話では無いのは誰でも知っている事であろう。
じゃあ何故そう言われるのか? それは写真を見る側のスキルの
不足だろう。ブレやピンボケは誰でも見ればすぐわかる、だから
そこだけを「問題だ!」と指摘し、その他の評価を行わない。
写真の良し悪しの評価は、相当に経験や感受性や価値感覚が
無いとわからない、かなりの高難易度の作業だ。
結局、写真のアート的な側面について評価できないビギナー層が、
「ビンボケだからダメな写真だ」と簡単に言ってしまう訳だ。
ちなみに、こういう事はアート的な要素を持つ写真学校等で
学んでみればすぐわかる。そういう所では、経験を積んだ
講師等が、写真の「表現」についての評価を主に行うが、
その際、ブレているからダメだ、等とは一言も言わない。
そこは重要な事ではなく、評価するべきは「何を、どう撮ろうと
したのか?」という部分なのだ。
つまりは、ピンボケやブレしか評価できない事自体が、完全な
ビギナーレベルでしか無いという事になる。
ここまで様々な側面からの多面的な話をしてきたが、
結局のところ、初級中級層は、写真の本質とは全く違う方向性
を見ていて、その事が間接的に高価な最新機材を欲しがる事に
繋がっていく。
う~ん、これはもう、何と言うか・・
これらの総合的な状況は、一言で言えば「残念な話である」
・・としか言いようが無いが、でもまあ、別の側面から見れば、
こういうユーザー層が居てくれるからこそ、せっせと新製品を
買ってくれて、現代において縮退した一眼レフやミラーレス機
の市場を支えてくれている状況だ。
そうしたカメラ界全体の現状やらの、大きな話を考え無くても、
個人的なレベルにおいても関係はある。
初級中級層が、そうやって最新機種に買い換えた後、
古いカメラやレンズは中古市場に流れてくるのだ。
私としては、一世代や二世代古い機材でも何ら不満は無い、
だから、そういうちょっと古いカメラを中古で安く買う為にも
どんどんと初級中級層には最新機種を買い続けて貰いたい訳だ。
結局、「残念な話」ではあるが、誰も損はしない。
まあ、だから、あまり気にしないようにしよう。
Clik here to view.

でも、こういう事は重要な「一次情報」だ、他にはそういう
情報はどこからも得られない。
レンズの性能や仕様の話等は、そういうのが好きな人に
まかせておけば良い話だ。
さて、本レンズSP60/2であるが、輪郭がやや硬い描写傾向があり
これは被写体を選ぶ事にも繋がるのだが、総合的には、とても
秀逸なマクロレンズだ。
APS-C機専用なので、そこを嫌がる人も居るかも知れないが、
「フルサイズでなくちゃイヤだ」というのも、ここまで散々
述べてきた初級中級層の問題点と同じ事だ。
フルサイズ対応で無い事は、本レンズの重欠点とは言えない。
・・まあ、だからこそ第15位という高い順位にランキング
されているレンズなのだ。
換算画角が90mm相当と同じになるTAMRON SP90/2.8との
住み分けはやや難しい、描写傾向は違うとは言えるのだが
SP90/2.8はロングセラーで年代により色々なバージョンが
あるので、一概には比較できない。
そこが気になるならば、あれこれ悩まずに両方買ってしまう
と言う選択肢もある。
本レンズは、そんなに高価なレンズでは無いのだ。
その事が、ハイコスパレンズという真髄であろう。
---
第14位
評価得点 4.00 (内、コスパ点 3.5)
Clik here to view.

レンズ購入価格:47,000円(新品)
使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回記事で、
栄光の第5位に輝いた、2000年代初頭のMF単焦点中望遠。
まあ、一言で言えば、とても高品位(高性能)なレンズである。
ただし、若干入手価格が高価であったので従来の「ハイコスパ」
のシリーズ記事では紹介を見送っていた。
高価であったのは、発売直後に新品で購入したのが理由だ。
ただ、本レンズの中古流通は少なく、後年ではセミレアと
なってしまったので、早目に買っておいて良かったとも言える。
まあ、コシナ製品は、こういうケース(後年では入手不能)が
多い事も想定しての新品買いでもあった。
Clik here to view.

本レンズはギリギリの状況だ、このバージョンは、もう入手
不能かも知れないが、比較的近年まで後継バージョンが発売
されていたので、それであれば、まだかろうじて入手可能で
あるかも知れないのだ。
さて、90mmでF3.5は、ちょっと地味なスペックである。
ビギナー層は「開放F値の明るいレンズの方が高価なので、
それは良く写る性能の良いレンズだ」と思い込んでいるかも
知れないが、実際には、まるでそんな事は無い。
むしろ、開放F値を抑えたレンズというものが存在する意義を
考えてみると良い、ビギナー層等が、F値が明るいレンズを
欲しがる中、何故、わざわざこういう仕様のレンズが
発売されるのか?
その理由は「設計において、非常に拘りを持っているから」
だと考えるのが正解であろう。つまり、口径比を明るく
すると、諸収差のオンパレードとなる。だが、開放F値が
明るく無いと、初級中級ユーザー層は良いレンズだとは
思わず、買ってくれなくなる。でも、本レンズでは、あえて
性能(収差補正)を重視し、「わかる人だけが買えば良い」
という、拘りの製品企画コンセプトとなっている訳だ。
Clik here to view.

調べた際、弱点が一切無い、ほぼ完璧な性能のレンズとして
評価された。
まあでも、数値評価が、必ずしも良い写りに直結するという
事も無い、何故ならば、数値で表せる要素は、レンズ性能の
ごくごく一部でしか無いからだ。
さて、そういう視点から本レンズを捉えてみると・・
確かに弱点は何も無い。解像感、コントラスト、逆光耐性、
ボケ質、ボケ質の破綻頻度、MF感触、重量やサイズ、
そして最短撮影距離も50cmと極めて短い。
つまり、全ての点で満足がいくレンズだ。
ちなみに本レンズの私の性能評価は「5点満点」となっている。
本ランキングの対象となっているおよそ320本のレンズの内、
描写表現力の評価が5点満点のレンズは14本しか存在しない。
本アポランター90/3.5は、その中の1本だ。
Clik here to view.
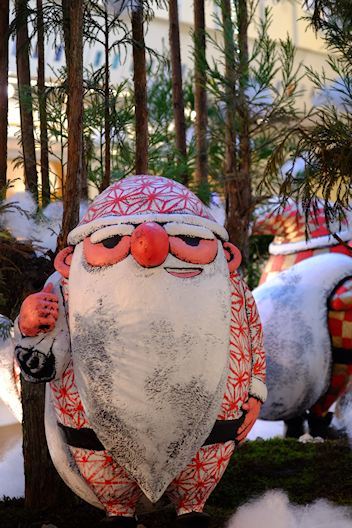
入手が困難な事が、やはり課題であろうか・・
でも、厳しい事を言えば、近年まで売っていたのだから
その時に買わない方が問題だ、という見方もある。
つまり「F3.5という暗い開放F値だから、たいした事が無い
レンズだ」と思い込んでしまい、興味をもてず、本レンズの
本質が見抜けなかったという事だ。
誰かが「良い」と言ったからと、手に入り難くなってから、
慌てて探す、と言うのでは、ちょっとズレてしまっている。
そして、コシナ社の製品は、たいていが初回生産の1ロット
だけで打ち止めであり、あまり再生産や継続生産をしない
事は、マニアであれば知っているであろう。
自身の価値観を持ち、正しい評価感覚を持ち、欲しいものは
買える時に買っておく、それがマニアにおける鉄則だ。
まあ、初級層が必要とするレンズでは無い事は確かであろう。
あくまでマニア向けだからこそ、そういう厳しい話になる訳だ。
「アーティストが亡くなってから、慌ててCDを買いに走る人」
等は、当然、マニアとは見なされ無い事は言うまでも無い。
---
第13位
評価得点 4.00 (内、コスパ点 4.0)
Clik here to view.

レンズ購入価格:24,000円(中古)
使用カメラ:PENTAX KP(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第1回記事で総合16位に
ランクインした1990年代のAF標準等倍マクロレンズ。
本シリーズでは少しだけランクが上がっている。
24,000円の価格で、コスパ4点は、ちょっと甘い評価かも
知れない。
ただしこのレンズは1990年代の、発売間もないタイミングで
購入したので若干高目であった。近年であれば軽く2万円を
切る中古相場になっているので、そういう状況も考慮しての、
コスパ評価点の若干の加点である。
Clik here to view.

エントリーレンズばかりになって来る」と書いたが、
だんだんそうした状況に近くなってきている。
まあ、結局のところハイコスパという観点からは、そういう
結果になるのであろう。
ただまあ、実際にそうなってしまったら、ランキングも
「予定調和」となって、あまり面白味も無い。
まあ、たまに意外なレンズもランクインする予定であるので
そこが楽しみであろう。
---
本レンズFA Macro 50mm/f2.8の話に戻るが、
この時代(1990年代)の標準マクロは高性能な製品が多い、
例えば、MINOLTA AF50/2.8やSIGMA AF50/2.8がそうであり、
本レンズも同様に描写表現力が、かなり高い。
これ以前の時代(1980年代)のMFマクロから比べると、
等倍マクロになった事とAFになった事に加えて、描写力の
改善要素が非常に大きく、何らかの大きな「技術革新」が、
この時代にあったのだろうと想像している。
そういえば、TAMRON SP90/2.5の、AF版(F2.8版、等倍)
への改良(Model 72E)も、この時代(1996年)であった。
1つのメーカーが何らかの技術革新を行うと、他社もその先行
製品を研究しつくし、そこに追従しようとする。
だから数年で、その新技術は一般化して、メーカー間の性能の
差は殆ど無くなるのだ。
(よって「メーカーによる性能の差なんて無い」と、本ブログ
では、いつも言っている)
そして、最初にその技術を開発したメーカーは、その分、名前
を上げる事ができる、それはブランドイメージとも言える。
例えば「マクロを買うならばTAMRON製が良い」といった感じだ。
新技術の先行優位性は、ごく短期間だけだ。その間に、いかに
優位性をユーザー層にアピールして、それを購買欲やブランド
力に転換していくかが、メーカー側の市場戦略の要となる訳だ。
Clik here to view.

マクロであるから、性能的な不満や弱点は感じ難い事であろう。
実質的な弱点は2点、まずAFの精度や速度がこの時代の製品故に
見劣りする事だが、この点はマクロレンズなのでMFを中心と
した撮影になるだろうから、重欠点とは言えない。
第二に、デザイン(見た目)が壊滅的に悪い事だ。
そういうのは個人の好き嫌いもあるかもしれないが、これは
「誰が見てもダメだ」というレベルに近い。
ただ、この点については、後年2000年代の後継レンズ
smc PENTAX-D FA Macro 50mm/f2.8 が存在する(未所有)
これは本レンズと、ほぼ同じレンズ構成やスペックであるが
デジタル対応で様々な小改良がある事が想像され、絞り環も
ちゃんと存在するし、なによりデザインが良くなっている。
DFA型の中古相場は、本FA50/2.8よりも1万円ほど高価に
なるが、旧型のデザインがどうしても気になるならば、
そういう選択肢もあるだろう。
Clik here to view.

デザインが非常に悪い。ただ、明らかにそういう弱点がある事は
当然メーカー側でも認識されていた為、例えば1990年代末での
FA-Limited型レンズ等は、大幅にデザインと高級感が増している。
それに続く現代のPENTAXのレンズ群も同様にデザイン面での
課題は少なくなっている。
要は、課題が誰の目にも明らかである方が、思い切った対応が
しやすいという事であろう。1990年代でのPENTAX AF一眼レフ
のデザインや操作系の改善(Zシリーズ→MZシリーズ)や、
同時代のMINOLTA α一眼レフの操作系の大幅な改善も、
旧機種のそれに大きな問題があったからだ。
なお、その背景では、1990年代初頭のバブル崩壊、1995年の
阪神淡路大震災によるユーザー層のマインド(心理や価値観)
の変化も無視できないが、その話は冗長になるので他記事に譲る。
で、課題があまり大きな問題と見なされないと、ずるずると
弱点を長期間引きずったままになってしまっているメーカーも
現代に至るまで非常に多い。
----
今回はこのあたりまでで、次回記事も、引き続き
ランキングレンズを順次紹介していこう。