本シリーズでは、主に本ブログの範囲でのみ使われる、
あまり一般的では無い写真関連の用語を解説している。
今回も「補足編」として、テーマを「文化・歴史編」とする。
では、早速始めよう。
![c0032138_18231857.jpg]()
★カメラ形態15年~20年寿命説
独自概念。
カメラは今から100年以上も前に発売が開始されている
歴史の長い機器だ。
コニカ(六桜社)が日本で最初に発売した「チェリー」は、
1903年製で、これはライト兄弟が初飛行した年でもある。
先年、TVの鑑定番組で「チェリー」の2型が登場した。
かなり痛んではいたが、100万円の鑑定価格であった。
このカメラの歴史的価値は非常に高いのであろう。
さて、「カメラ」であるが、長い発売期間の間に進化を続け
旧来は「精密機械」であったものが、現在では全く異なる
「デジタル・デバイス」となって、家電製品化している。
で、カメラが次の形態に進化すると、当然ながら旧形態の
ものは不人気となり廃れてしまう。
歴史をさかのぼると、この次の形態へ変化していく期間、
すなわち同じ形態のカメラが発売されている期間は、
いずれの形態でも、概ね15年~20年間である模様だ。
以下、具体例を挙げる。(注:35mm判が主体だ)
1930年代~1950年代
バルナックライカや旧CONTAXの時代。職人芸的な
精密機械であり非常に高価であった。
なお、第二次大戦により開発や販売が止まった期間がある。
1950年代後半~1960年代
一眼レフの登場。およびレンジファインダー式機械カメラが
多数存在した時代。
いずれも純機械式カメラであり、露出計等の電気・電子化は
まだされていない。
製造プロセスが機械工業製品であった為、国内でも多数の
カメラメーカーが林立した時代だ。
1960年代~1970年代
電気化一眼レフの登場、露出計が搭載された。
1970年代~1980年代
電子化一眼レフの登場、AE(自動露出)機構が搭載された。
代表的機種として、PENTAX ES(1971)や、NIKON F3(1980)
CANON New F-1(1981)を挙げておく。
電子化により、従来の精密機械とは開発や製造の方法論も
全くの別物になった。
この結果、多数あったカメラメーカーは淘汰される。
![c0032138_18231862.jpg]()
ピント合わせを自動化したAF一眼レフの登場。
代表的機種として、MINOLTA α-7000(1985)、
CANON EOS-1(1989),MINOLTA α-7(2000)を挙げておく。
この時代は機械と電子の融合、すなわちメカトロ技術
であると言える。ここもまた製造プロセスの大変革だ。
![c0032138_18231833.jpg]()
デジタル一眼レフの登場。従来の銀塩一眼レフとは
形状こそ類似しているが、中身はデジタル機器であり
全くの別物である。これはもう旧来の銀塩カメラとは
開発や製造面では、同じ視点で語る事は不可能だ。
2010年前後~
ミラーレス(一眼)の登場。レンズ交換式カメラとしては
一眼レフの変化形で類似の印象があるが、構造や原理は
ずいぶんと異なり、一眼レフとは別物と考えておくのが
良いだろう。
![c0032138_18231869.jpg]()
20年の期間で、次の形態のカメラに変化(進化)している。
カメラの形態が変化すると、開発や製造のプロセスは、
それまでと全く異なる。よって、各変革期には、それまでの
カメラメーカーが必ずと言っていい程、いくつかが事業撤退
している。(注:新たなカメラに事業形態が合致して、
新規参入するメーカーも稀にある)
この結果、現代のデジタル時代では、カメラメーカーは数える
程しか残っておらず、かつ、1つのメーカーで全ての内部構成
部品が製造できる事も無く、各社共通の部品も使われている。
(だから「ブランド」という意味や価値が希薄化している)
また、各形態の期間の後期では、性能もピークにまで進化
してしまい、それ以上の発展の余地が無くなってくる事と、
同時に、魅力的な新規の付加価値が減ってくる事で、消費者の
ニーズ(購買欲)も減少し、事業が縮退してしまい、いずれに
しても新しい形態のカメラに変革せざるを得なくなって来る。
近年では、ミラーレス機のフルサイズ化(SONY α 2013年
NIKON Z/CANON R 2018年、PANASONIC S 2019年等)
があり、一眼レフからの転換の様相が出始めている。
また、2016年以降、各社からの目を引くデジタル一眼レフ
の新製品発売は殆ど無く、寂しい市場状況が続いている。
★中古カメラブーム
一般用語。
上記の「形態の変化」に伴い、新しい形態のカメラは
常に万人に歓迎されるものでは無いかも知れない。
特にその差異(違和感)が大きかったのは、AF一眼レフ時代
の後期(1990年代後半~2000年代初頭)であった。
この時代の直前には「バブル崩壊」(1992年頃)と
「阪神淡路大震災」(1995年)があり、これらの出来事は、
消費者のニーズや価値観を大きく変貌させてしまった。
ここに旧来の「イケイケドンドン」的なバブリーなイメージ
の高機能化を「付加価値」としたAF一眼レフを発売しても
ユーザーのニーズには合い難い。
勿論メーカーもその点には気がつき、華美なスペックを廃した
カメラを企画開発するのだが、若干手遅れな要素もあった。
この状況から、新機種のAF一眼が売れず、1990年代後半には
空前の「第一次中古カメラブーム」が起こる。
マニアを中心に始まったこのブームは、それより古い時代の
AE一眼レフや、機械式一眼レフ、レンジファインダー機等に
より高い魅力があるというニーズに繋がり、これら旧製品が
中古市場で大人気となり、古い形態のカメラも新製品として
発売される等、このブームは社会現象にもなった。
(新規中古店が林立したり、沢山の中古カメラ誌が刊行された)
![c0032138_18232742.jpg]()
そういう希少なカメラを転売して利益を得る「投機層」も
現れた。結果、中古カメラの相場は際限なく上昇した。
まあつまり「カメラ・バブル」が起こった訳だ。
デジタル期に入った2000年代初頭にはこの中古カメラブーム
も終息し、その後は銀塩中古カメラの相場は大暴落した。
その後10年程して、μ4/3機(2000年代末)を皮切りに、
フルサイズミラーレス機の登場(α7/R,2013年)という
状況は、旧来のオールドレンズのほぼ全てを使用可能とした。
この結果、マニア層を中心に「第二次中古(レンズ)ブーム」
が2010年代前半に起こるが、この流れは一般層にまで波及
する事は無く、マニア層の範疇で留まった。
思えば、カメラ界にとどまらず、他の、息の長い市場分野
(例:ファッションや音楽界等)においても、新しい様式が
現れ、それが普及してしまうと、もう目新しさが無く、
それ以前の時代の様式が再度見直される事が良くある。
これらは「流行周期20年説」のように分析される事も
一般的である。
これは前項目の「カメラ形態15~20年説」に絡んで
興味深い。中古カメラブームと言うものも、もしかすると
新型形態のカメラに目新しさや魅力が無くなった状況に
おいて、ちょうど様々な世情や環境の変化とあいまって
突発的・爆発的に起こるのかも知れない。
前述のように、ミラーレス機のフルサイズ化(高付加価値化)
が2018年にNIKONとCANONにより行われて、今後それらの
形態がカメラの主流となってくるのであれば・・
これらは高付加価値商品であり、縮退したデジタル一眼レフ
市場を補填する意味で高価である。だからこれらをコスパが
悪いと見なすユーザーも多いであろう、そんな際に、旧来の
デジタル一眼レフの中古相場が安価になれば、デジタル一眼の
中古カメラブームが起こる可能性もあるのだ。
なお、「中古ブーム」は、実用派マニア層にとってみれば
必ずしも歓迎できるものでは無い。特に問題なのは、
中古機器の売買で利益を得る「投機層」が現れ、機器の
中古相場が異常なまでに高騰してしまう事だ。
(注:ただ、これについては「高価でも買いたい」と思う
ユーザー層の存在にも、多大な責任がある。そのユーザーも
また投機層となり、転売を狙うなどで連鎖してしまうのだ)
が、実際に実用的に必要とする、あるいは欲しいと思う
カメラやレンズの中古価格が上がってしまうのは、どうにも
困った話である。
★αショック
一般用語。
1985年に発売された、史上初の実用的AF一眼レフ
MINOLTA α-7000(未所有)は、社会現象的な
インパクトがあった。
一眼レフでは、それ以前の数年前からも、AF機が発売
されていたが、試作機的であり、実用には苦しかったのだ。
また銀塩コンパクト機では、1970年代末から既にAF機が
実用化されていて、この時代では、もうAFは普通だった。
旧来「使いこなしが難しい」と、一般的なイメージがあった
一眼レフにおいて、AEやAFの搭載で「誰でも、シャッター
を押すだけで高画質な写真が撮れる」という付加価値は
一般ユーザーにとっては、大きな福音であっただろう。
市場におけるインパクトのみならず、このαショックは、
カメラメーカーにも「大激震」を与えた。
他社は、いっせいに「αに追いつけ、追い越せ」とばかり
一眼レフのAF化を推進、その開発が上手く軌道に乗った
メーカーもあれば、残念ながら失敗してしまい、一眼レフ
の市場から撤退したメーカーもいくつかあった。
確かに一眼レフのAF化は、大きな構造改革であり、これは
非常に大変だったと思うのだが、実は、この後、2000年代
初頭の「銀塩からデジタルへ変革」の方が、事業構造の
面では、より大きな変化であったと思う。
銀塩からデジタル化では、まるっきりカメラの企画、開発、
製造のプロセスが異なる。けど、カメラとしての見かけは
銀塩機とデジタル一眼では大きな差が無かった為、
ここで一般市場は「なんとかショック」のような用語は
特に言われず、ある程度自然に移行が進んだような印象が
あったと思う。
けど、AF化では、それに失敗してもカメラメーカーが
完全に市場から撤退してしまう程のダメージは無く、
コンパクト機やMF一眼を製造販売して生きながらえていた
メーカーもいくつかあったのだが、デジタル化ではそれに
失敗すると致命的だ。デジタル化初期の2000年代前半に
いくつかの老舗メーカーが、カメラ事業から撤退して
しまったのは残念な事実ではあるが、まあ実際にはそれほど
の大変革であり、大激震であったのだ。
いずれも、もう昔の話、ではあるが、カメラファンとしては
これらの歴史については知っておく必要はあるだろう。
★マウント変更
ややマニアックな一般用語。
上記「αショック」、つまりAF化の「大変革」において
各メーカーは、旧来のMF一眼レフ用マウントの仕様や規格
ではそれが困難だった例がある。(例:CANON FDマウント)
AF化に先駆けて、AE化においても同様に旧来マウントでは
その実現が難しかった例もある(例:PENTAX等のM42)
これらのケースにおいて、カメラメーカーは苦渋の決断で
それまで自社が使っていたマウントを諦め、新規のマウント
に変更したケースがいくつかある。
具体的には、PENTAXをはじめとするM42マウント陣営が
AE化により、それぞれ独自のバヨネット式マウントに変更
(例:PENTAX Kマウント 1975年)
そしてミノルタがAF化でMD系からαマウントに変更(1985年)
さらには、キヤノンもAF化でFDからEF(EOS)に変更(1987年)
デジタル時代においても、CONTAXがY/CからNに変更(2000年)
さらにはオリンパスが、OMから4/3に変更(2003年)や
4/3からμ4/3に変更(2008~2009年)などの例がある。
また、完全変更ではなく、「併売」という状況も近年の
ミラーレス機において、いくらでも事例がある。
AE化やAF化で旧来のマウントとは大きく性能が進化し、
かつ旧来のマウントと互換性が高いケースであれば、
ユーザーの不満は殆ど無い(例:PENTAX M42→K)
あるいは、旧来のマウントとは時代が大きく離れていても
あまり問題は無いであろう(例:OLYMPUS,CONTAX)
また、新マウント機が圧倒的に高性能であれば、それも
あまり問題は無い(例:MINOLTA MD→α)
そして、同一メーカーの一眼レフとミラーレス機が異なる
マウントであっても大きな問題は無い(例:NIKON F/1/Z)
そして、大きく関連するのは、旧来マウントのユーザー層の
実数がある。特にPENTAX系M42マウント機は数百万台という
膨大なユーザー数があった為、マウント変更は互換性を
保ちながら慎重に行う必要があった事だろう。
さて、逆に、旧来のマウントがそこそこ人気であり
かつ新マウントが旧マウントと互換性が無く、さらに
新マウントの機体があまり魅力的な仕様や性能では無い場合
ユーザー層の不満が一気に爆発する事となる。
![c0032138_18232766.jpg]()
FD系には新旧F-1,A-1,T90等の非常に優れた銀塩一眼レフが
多く、それらのユーザー層は、多数のFD系レンズとともに
それらを愛用していたのだが、ある日突然、新しいマウント
に変化し、もう旧マウント製品は作らないという。
初期EOSには魅力的な機体は無く、EOS機の性能優位性が
顕著になるのは、数年後の、およそ1990年前後からだ。
これでは、さすがにユーザーは怒るのが当然だ。
事実、1987年~1990年代初頭くらいまでの間は、CANONの
この措置に、旧来のCANON党はブーイングの嵐であったと聞く。
まあでも、10年かそこらもすれば、こうした不満も収まる、
何故ならば、カメラの進化により、新機種には圧倒的と
言える性能が搭載され、旧機種の「仕様的老朽化」が激しく
なるからだ。例えばCANONではEOS-1NやEOS-3等の超高性能
機が1990年代後半には登場している。New F-1は確かに
名機ではあるが、もう15年以上も前の時代の機種だ、単純に
性能面だけ見れば、これら新鋭機に対して勝ち目は無い。
でもまあ、そういう風に時期を待つのも、ユーザー層に
おいては辛い。こういう場合は、いさぎよくFD機をもう
諦め(気に入らないからEOSを買わず)ニコンやミノルタに
鞍替えしてしまうユーザーも多かった事であろう。
それと、ちょうどこの時代、前述の中古カメラブームが
あって、趣味撮影を行うアマチュア層では、もう業務用途
機として肥大化した性能の新鋭一眼レフ(例:EOS-1N/V
やNIKON F5等)には興味が持てず、カメラらしい外観と
性能での、存在感や所有満足度が高い旧時代の旗艦機に
興味が行ってしまった訳だ。
マウント変更の件は、こうして時代がすぎれば「うやむや」
になってしまうが、まあでも、一時代をとってみれば、
これはメーカーのブランドイメージの低下が大きい。
近年では、このような、大幅なマウント変更は各社とも
よほどの事がなければ行わない。まあ一眼レフと並行して
ミラーレス機が販売される場合は、小型化、および高性能化
(フルサイズ、高画素数等)を理由とした新マウント機発売も
多々あるが、これらが従来の一眼レフとの互換性が無くても、
別ジャンルの商品であるから、ユーザーは、そこに不満は無い
事であろう。困るのはむしろ(旧)製品ラインナップの廃止
(製造中止)だ。
![c0032138_18232645.jpg]()
ニコンはFマウントをおよそ60年、ペンタックスはKマウントを
約45年も続けているが、時代の変化とともに、同じマウント
形状であっても、電子化等で、その互換性は高いとは言い難い。
例えば現代のニコン(F)機で、非Aiのレンズを装着できる機体は
NIKON Dfしか存在せず、しかもその機体の操作系では絞り値
の二重操作が発生する等で、非Aiレンズの実用は苦しい。
FやKのマウント仕様(規格)の変化は、複雑怪奇であり、
各時代のレンズを装着可能か否かは、一般ユーザー層では
その理解は困難か不可能。これがわかっているのは一部の
上級マニアか、専門中古店のベテラン販売員だけであろう。
いずれにしてもマウント変更は色々と問題がある訳だ。
★レガシー/絶滅危惧種
やや独自の用語。
「レガシー」とは、近年には人気政治家が使った事でも
著名になった言葉であるが、元々の意味としては
「遺産、(先人の)遺物」という意味が肯定的な内容で
使われ、逆に否定的な意味では「時代遅れ」がある。
PC(パソコン)等の分野では、旧型式の規格や構造を指す
用語として、昔(1990年代頃~)から使われている。
具体的な例をあげれば、RS-232Cシリアルポートとか、
VGA端子、フロッピーディスクなど、多数ある。
これらは「レガシー・デバイス」と呼ばれていて、
新技術による規格に置き換わった際、これらをどう扱うか
は、PC界においては、なかなか頭の痛いところであろう、
旧来の規格は、まだ特定の分野(例、工場の生産ライン等)
では使われている場合もあり、完全に無視する事は出来ない。
なので、この場合は「レガシー」は、肯定とも否定とも
つかない意味で使われている。
本ブログにおいても、カメラ機能や、その操作系において
「レガシー」という用語を使う場合があり、これはむしろ
「古い、時代遅れ」という否定的な意味である事が殆どだ。
で、あまりに「レガシー」が進むと、今度は「絶滅危惧種」
という表現を用いる事もある、ただ、これはこれで、むしろ
「貴重であって、できれば残したい」という意味も出てくる。
![c0032138_18232771.jpg]()
やや独自概念。
旧来、情報とは、それを積極的に調べる行動を伴わないと
得れるものではなかった。しかし1990年代くらいになって
インターネット等が普及すると、そういう機器を使える層と
そうでは無い一般層との間で、情報を得る為の格差が大きく、
「デジタル・デバイド」や「情報ヒエラルキー」といった
用語が出て来て社会問題となった。
だが、その後、PCやスマホの普及により、WEBやSNS等による
情報化が一般にも広まってきた2000年代~2010年代に
おいては、デジタル・デバイドは解消されつつはあるが、
むしろ増えすぎた情報に対して、一般層は、その取捨選択が
大変難しい状態になっている。
いやむしろ、そうした情報弱者に対しての「情報操作」を
行う事も、現代のビジネスモデルにおいては重要な点だ。
(例えば、誰かのオススメがあれば、皆、簡単に信じてしまう。
それは意図的に流された好評価であったとしてもだ・・)
そうした「情報操作」の是非は微妙なところだ、市場維持の
為に当然とも言えるかも知れないし、あくどい、と思う事も
多々あるだろう。いずれにしても肝心なのは、情報利用者が
その情報の意味、価値、信憑性などを正しく判断する術を
身につける事だ。
だが、それが難しい事は言うまでも無い、一般層は、簡単に
世の中にある情報に振り回されてしまうのだ。
その顕著な例が、私が言うところの「一極集中化現象」
である、TV等の公共メディアはもとより、インターネット等
で発信された情報に、多くの一般層が群がるようにして
1つの場所や商品や同じ価値観に集中してしまう現象だ。
![c0032138_18233715.jpg]()
「そこまで単純に振り回されてしまって良いのだろうか?」
という意味である。
一箇所に人が集まると行列などができて時間が無駄になり
混雑して交通や往来にも多大な影響が出たり、あるいは
マナーが低下して、その場所や近隣の住民にも様々な迷惑を
かけてしまう。
グルメ店などに限らず、カメラ分野でも同じ被写体に多数の
人が三脚を立てて群がったり、絵画などでも、多数の人が
イーゼルを立てて場所を占領するなど、迷惑でマナー違反だ。
あるいはグルメや、商品等では、評判がよければどんどんと
価格が上がってしまい不条理だし、中古商品等では、下手を
すれば値上がりや転売を期待する投機層が現れる。
ただ、そうした情報に乗る人達にとってみれば、今度は逆に
「今、巷で流行っている、あるいは有名な、場所や店舗に行った
事で周囲に自慢できる」という要素があるようだ。
その事で、SNSなどで「イイネ」をもらいたいのであろう。
けど、あまりに受動的だ。美味しい店の料理は、作った人が
偉い/凄いのであって、それを食べた人が自慢するべき物
ではない。また、そんな主張に共感する方もどうだろうか?
他に、自分自身の力では、主張したり共感を得れる要素は、
何もないのだろうか?と情けなく思えてしまう。
写真や絵画だってそうだ、同じ場所で皆と同じ写真を撮ったり
していても、「個性」も「表現」も、何も出て来ない。
まあ、どうみてもネガティブな要素が大きい為、私自身は
対策として、これらの「一極集中化現象」を逆情報として
利用する事にしている。
簡単な例を挙げれば、「今年の桜の名所」として、様々な
メディア(TVやポスター、情報誌、WEB等)で取り上げられた
場所は、「一極集中化」が起こる事が明白だ、そうした
場所には一切近寄らない事がベターである。
メディアで取り上げる方も、様々な相乗効果により
そこでビジネスチャンスを起こしたい訳だ、他のごく簡単な
例を挙げれば、映画公開や新ドラマの前には、大御所俳優
すらもTVのバラエティ番組に出演するでは無いか、それにより
メディア・ミックスの効果を期待するからだ。
![c0032138_18233777.jpg]()
グルメ、ファッション、商品の流行、そしてカメラやレンズ
ですらもこれが起こりうる。
いずれにしても、少なくとも私にとってみれば、あまり
乗るべき対象でもないし、むしろ逆に「情報に振り回される
のは、褒められた話では無い」とも思ってしまう。
様々に溢れる情報に対しても「自身の価値観を持って対処する」
という点が重要なのだろうと思う。
これもまた、新しい「情報ヒエラルキー」の一種だとも思う、
現代では、一部の階層で情報が不足する状況は解消したが、
情報の価値や真の意味がわからない階層が、損をしている
と言う事になるからだ。
★ビハインド
独自用語。
元々の英語では、「背後」という意味が大きいと思うが
スポーツ競技では、対戦相手に対しての点差や時間差が
ある(つまり、負けている)という意味で良く使われる。
本ブログにおいては、カメラやレンズの性能や仕様が
同時代の他社製品に対して、劣っているまたは遅れている
際にこの用語を良く使っている。
具体例は、その製品を使っているユーザーにとっては
不快な情報であろうから、今回は割愛する。
なお、普通は、いつまでもビハインドは続かない、それが
市場で明白ならば、その機器は売れなくなってしまうからだ、
だから遅れている他社は、その性能差を巻き返そうとする、
新製品ではビハインドを取り返して、むしろ他社より性能が
優れているケースも多々ある。
よって、長い目で見れば、ビハインド状態が機材購入において
あまり問題となる事も無い訳だ。むしろ不人気であった事で
後年に中古相場が大きく下落し、絶対性能に対して、コスパが
極めて良くなっている場合すらある。
(注:逆に、ユーザー層が、その機材の「ビハインド状態」に
気づかず、発売後いつまでも人気があり高値相場である場合も
ある。そういった場合には「コスパが極めて悪い」と無視する
のが良いが、それを判断する事は、一般層にはやや難しい)
★バブリーなカメラ
独自用語。
バブル期の1980年代後半から1990年代初頭にかけて
企画・開発されたカメラの多くは、華美なスペックを
並べた高機能・高性能至上主義の製品が多かった。
別に高性能である事は悪い商品企画では無いのだが・・
バブル崩壊とともに、ユーザー側のニーズや価値観も変化
してしまい、必ずしも高性能を目指したカメラが良い物だ
とはユーザー側で思い難くなってしまった時期があった。
この歴史を指して、バブル期開発のカメラを「バブリーな
カメラ」と本ブログでは呼ぶ事がある。
ここも具体例は多すぎるので割愛するが、他の記事でも
色々と実例を挙げている。
![c0032138_18233784.jpg]()
「カメラ形態15~20年説」での各形態の末期においては、
華美で過剰とも言えるスペックを並べて、縮退したユーザー
層のニーズ(購買欲)を喚起するケースがある。
現代のデジタル一眼レフ市場でも、普及からおよそ15年が
経過し、すでに市場は飽和状態であり、2015年以降の
新機種では、超絶的と言えるスペック(本シリーズ第1回
記事参照)を、「付加価値」(=値上げや利益確保の理由)
として与えられている。(そもそも、一眼レフ新製品の
発売ペースが非常に鈍化している)
また、一眼レフだけでは無く、ミラーレス機もフルサイズ化
などの超絶性能を持たせた新製品が登場している。
これもまた「バブリーなカメラ」の一種なのかも知れない、
こうした思想や指向性がユーザーニーズに合っているか
否かは、その時代の中では判断しにくい。
数年あるいは10年が経過して、その時代の市場や世情や
評価を冷静に振り返る事で、それが正解だったのか否かは
判断できるであろう。
例えば商品が高価すぎて売れないならば、ビジネスにならない
ので、市場には必ず低価格な商品が投入され、市場は自ら
バランス点を求めて推移していく。
まあでも、どんな結果になったとしても、それもまた
「カメラの歴史」の1ページではあるだろう。
どんな商品でも常に順風満帆な時代が続く訳では無いのだ。
★パラダイムシフト
一般用語。
元々は科学分野で、ある科学者が「パラダイム」という
概念を唱え、1960年代~1970年代に出始めた言葉だが、
1980~1990年代には拡大解釈されて一般化した用語だ。
拡大解釈においての「パラダイムシフト」とは、
「それまで当然の事として認識されていた概念や価値観が
劇的に変化する事」を指す。
これは主に、科学の分野で使われるべき用語ではあった、
科学分野では、古くからこれは起こっており、例えば有名な
例を挙げれば、天動説から地動説に変化した等がある。
そこまで極端な例ではなくても、科学分野では頻繁にこれは
起こる事で、新技術、新発見などで起こる「科学の革命」は
様々な事例がある。(CPU、デジタル化、青色LED、携帯電話、
インターネット、AI等、いくらでも前例がある)
学術研究以外にも、企業における新製品開発などでも、
良く「パラダイムシフト」がスローガンとして掲げられる
事がある、これはデジタル化やインターネット化、AI等の
大きな新技術分野が出て来た際に、それらの新技術の応用は
従来の古い概念や常識に囚われていたら難しいので、それの
企画・開発側あるいは商品を利用する側にも、概念の大きな
変革が必要になる、という意味だ。
科学分野に限らず、現代においては「パラダイムシフト」は
社会的な価値観の変革など、様々に用いられる事がある。
先年では、やはり前述の人気政治家が、この用語を使った
事で有名となっている。ただ、この用語自体は古くから
上記の状況で使われてきている。良く勉強はしていると
言えるのだが、用語の解釈は市場分野毎に様々に有りうる
ので、使う側でも捉える側でも、要注意だ。
本ブログにおいては、ごく稀にこの用語を使う場合がある、
市場全体での話ではなく、個人的な価値感の激変についてだ。
1つの例としては、ミノルタα-9(1998年)の記事
(銀塩一眼レフ第23回)がある。
![c0032138_18233740.jpg]()
たいした事が無いが、カタログに直接現れない面の多くが
優れていた(例:操作系、耐久性、実用性能(精度)など)
「α-9を見て、それまでカタログの仕様に現れない性能など
あるはずが無いと思っていたのが、その概念がひっくり返った
これは”パラダイムシフト”であると言える」という感じだ。
その他の時代、あるいは近年のカメラでは、あまりそうした
パラダイムシフトを感じさせてくれるような機種は、
殆ど出てきていない、ある意味、残念な話なのかも知れない。
![c0032138_18234766.jpg]()
となるが、内容は未定としておく。
あまり一般的では無い写真関連の用語を解説している。
今回も「補足編」として、テーマを「文化・歴史編」とする。
では、早速始めよう。

★カメラ形態15年~20年寿命説
独自概念。
カメラは今から100年以上も前に発売が開始されている
歴史の長い機器だ。
コニカ(六桜社)が日本で最初に発売した「チェリー」は、
1903年製で、これはライト兄弟が初飛行した年でもある。
先年、TVの鑑定番組で「チェリー」の2型が登場した。
かなり痛んではいたが、100万円の鑑定価格であった。
このカメラの歴史的価値は非常に高いのであろう。
さて、「カメラ」であるが、長い発売期間の間に進化を続け
旧来は「精密機械」であったものが、現在では全く異なる
「デジタル・デバイス」となって、家電製品化している。
で、カメラが次の形態に進化すると、当然ながら旧形態の
ものは不人気となり廃れてしまう。
歴史をさかのぼると、この次の形態へ変化していく期間、
すなわち同じ形態のカメラが発売されている期間は、
いずれの形態でも、概ね15年~20年間である模様だ。
以下、具体例を挙げる。(注:35mm判が主体だ)
1930年代~1950年代
バルナックライカや旧CONTAXの時代。職人芸的な
精密機械であり非常に高価であった。
なお、第二次大戦により開発や販売が止まった期間がある。
1950年代後半~1960年代
一眼レフの登場。およびレンジファインダー式機械カメラが
多数存在した時代。
いずれも純機械式カメラであり、露出計等の電気・電子化は
まだされていない。
製造プロセスが機械工業製品であった為、国内でも多数の
カメラメーカーが林立した時代だ。
1960年代~1970年代
電気化一眼レフの登場、露出計が搭載された。
1970年代~1980年代
電子化一眼レフの登場、AE(自動露出)機構が搭載された。
代表的機種として、PENTAX ES(1971)や、NIKON F3(1980)
CANON New F-1(1981)を挙げておく。
電子化により、従来の精密機械とは開発や製造の方法論も
全くの別物になった。
この結果、多数あったカメラメーカーは淘汰される。

ピント合わせを自動化したAF一眼レフの登場。
代表的機種として、MINOLTA α-7000(1985)、
CANON EOS-1(1989),MINOLTA α-7(2000)を挙げておく。
この時代は機械と電子の融合、すなわちメカトロ技術
であると言える。ここもまた製造プロセスの大変革だ。

デジタル一眼レフの登場。従来の銀塩一眼レフとは
形状こそ類似しているが、中身はデジタル機器であり
全くの別物である。これはもう旧来の銀塩カメラとは
開発や製造面では、同じ視点で語る事は不可能だ。
2010年前後~
ミラーレス(一眼)の登場。レンズ交換式カメラとしては
一眼レフの変化形で類似の印象があるが、構造や原理は
ずいぶんと異なり、一眼レフとは別物と考えておくのが
良いだろう。

20年の期間で、次の形態のカメラに変化(進化)している。
カメラの形態が変化すると、開発や製造のプロセスは、
それまでと全く異なる。よって、各変革期には、それまでの
カメラメーカーが必ずと言っていい程、いくつかが事業撤退
している。(注:新たなカメラに事業形態が合致して、
新規参入するメーカーも稀にある)
この結果、現代のデジタル時代では、カメラメーカーは数える
程しか残っておらず、かつ、1つのメーカーで全ての内部構成
部品が製造できる事も無く、各社共通の部品も使われている。
(だから「ブランド」という意味や価値が希薄化している)
また、各形態の期間の後期では、性能もピークにまで進化
してしまい、それ以上の発展の余地が無くなってくる事と、
同時に、魅力的な新規の付加価値が減ってくる事で、消費者の
ニーズ(購買欲)も減少し、事業が縮退してしまい、いずれに
しても新しい形態のカメラに変革せざるを得なくなって来る。
近年では、ミラーレス機のフルサイズ化(SONY α 2013年
NIKON Z/CANON R 2018年、PANASONIC S 2019年等)
があり、一眼レフからの転換の様相が出始めている。
また、2016年以降、各社からの目を引くデジタル一眼レフ
の新製品発売は殆ど無く、寂しい市場状況が続いている。
★中古カメラブーム
一般用語。
上記の「形態の変化」に伴い、新しい形態のカメラは
常に万人に歓迎されるものでは無いかも知れない。
特にその差異(違和感)が大きかったのは、AF一眼レフ時代
の後期(1990年代後半~2000年代初頭)であった。
この時代の直前には「バブル崩壊」(1992年頃)と
「阪神淡路大震災」(1995年)があり、これらの出来事は、
消費者のニーズや価値観を大きく変貌させてしまった。
ここに旧来の「イケイケドンドン」的なバブリーなイメージ
の高機能化を「付加価値」としたAF一眼レフを発売しても
ユーザーのニーズには合い難い。
勿論メーカーもその点には気がつき、華美なスペックを廃した
カメラを企画開発するのだが、若干手遅れな要素もあった。
この状況から、新機種のAF一眼が売れず、1990年代後半には
空前の「第一次中古カメラブーム」が起こる。
マニアを中心に始まったこのブームは、それより古い時代の
AE一眼レフや、機械式一眼レフ、レンジファインダー機等に
より高い魅力があるというニーズに繋がり、これら旧製品が
中古市場で大人気となり、古い形態のカメラも新製品として
発売される等、このブームは社会現象にもなった。
(新規中古店が林立したり、沢山の中古カメラ誌が刊行された)

そういう希少なカメラを転売して利益を得る「投機層」も
現れた。結果、中古カメラの相場は際限なく上昇した。
まあつまり「カメラ・バブル」が起こった訳だ。
デジタル期に入った2000年代初頭にはこの中古カメラブーム
も終息し、その後は銀塩中古カメラの相場は大暴落した。
その後10年程して、μ4/3機(2000年代末)を皮切りに、
フルサイズミラーレス機の登場(α7/R,2013年)という
状況は、旧来のオールドレンズのほぼ全てを使用可能とした。
この結果、マニア層を中心に「第二次中古(レンズ)ブーム」
が2010年代前半に起こるが、この流れは一般層にまで波及
する事は無く、マニア層の範疇で留まった。
思えば、カメラ界にとどまらず、他の、息の長い市場分野
(例:ファッションや音楽界等)においても、新しい様式が
現れ、それが普及してしまうと、もう目新しさが無く、
それ以前の時代の様式が再度見直される事が良くある。
これらは「流行周期20年説」のように分析される事も
一般的である。
これは前項目の「カメラ形態15~20年説」に絡んで
興味深い。中古カメラブームと言うものも、もしかすると
新型形態のカメラに目新しさや魅力が無くなった状況に
おいて、ちょうど様々な世情や環境の変化とあいまって
突発的・爆発的に起こるのかも知れない。
前述のように、ミラーレス機のフルサイズ化(高付加価値化)
が2018年にNIKONとCANONにより行われて、今後それらの
形態がカメラの主流となってくるのであれば・・
これらは高付加価値商品であり、縮退したデジタル一眼レフ
市場を補填する意味で高価である。だからこれらをコスパが
悪いと見なすユーザーも多いであろう、そんな際に、旧来の
デジタル一眼レフの中古相場が安価になれば、デジタル一眼の
中古カメラブームが起こる可能性もあるのだ。
なお、「中古ブーム」は、実用派マニア層にとってみれば
必ずしも歓迎できるものでは無い。特に問題なのは、
中古機器の売買で利益を得る「投機層」が現れ、機器の
中古相場が異常なまでに高騰してしまう事だ。
(注:ただ、これについては「高価でも買いたい」と思う
ユーザー層の存在にも、多大な責任がある。そのユーザーも
また投機層となり、転売を狙うなどで連鎖してしまうのだ)
が、実際に実用的に必要とする、あるいは欲しいと思う
カメラやレンズの中古価格が上がってしまうのは、どうにも
困った話である。
★αショック
一般用語。
1985年に発売された、史上初の実用的AF一眼レフ
MINOLTA α-7000(未所有)は、社会現象的な
インパクトがあった。
一眼レフでは、それ以前の数年前からも、AF機が発売
されていたが、試作機的であり、実用には苦しかったのだ。
また銀塩コンパクト機では、1970年代末から既にAF機が
実用化されていて、この時代では、もうAFは普通だった。
旧来「使いこなしが難しい」と、一般的なイメージがあった
一眼レフにおいて、AEやAFの搭載で「誰でも、シャッター
を押すだけで高画質な写真が撮れる」という付加価値は
一般ユーザーにとっては、大きな福音であっただろう。
市場におけるインパクトのみならず、このαショックは、
カメラメーカーにも「大激震」を与えた。
他社は、いっせいに「αに追いつけ、追い越せ」とばかり
一眼レフのAF化を推進、その開発が上手く軌道に乗った
メーカーもあれば、残念ながら失敗してしまい、一眼レフ
の市場から撤退したメーカーもいくつかあった。
確かに一眼レフのAF化は、大きな構造改革であり、これは
非常に大変だったと思うのだが、実は、この後、2000年代
初頭の「銀塩からデジタルへ変革」の方が、事業構造の
面では、より大きな変化であったと思う。
銀塩からデジタル化では、まるっきりカメラの企画、開発、
製造のプロセスが異なる。けど、カメラとしての見かけは
銀塩機とデジタル一眼では大きな差が無かった為、
ここで一般市場は「なんとかショック」のような用語は
特に言われず、ある程度自然に移行が進んだような印象が
あったと思う。
けど、AF化では、それに失敗してもカメラメーカーが
完全に市場から撤退してしまう程のダメージは無く、
コンパクト機やMF一眼を製造販売して生きながらえていた
メーカーもいくつかあったのだが、デジタル化ではそれに
失敗すると致命的だ。デジタル化初期の2000年代前半に
いくつかの老舗メーカーが、カメラ事業から撤退して
しまったのは残念な事実ではあるが、まあ実際にはそれほど
の大変革であり、大激震であったのだ。
いずれも、もう昔の話、ではあるが、カメラファンとしては
これらの歴史については知っておく必要はあるだろう。
★マウント変更
ややマニアックな一般用語。
上記「αショック」、つまりAF化の「大変革」において
各メーカーは、旧来のMF一眼レフ用マウントの仕様や規格
ではそれが困難だった例がある。(例:CANON FDマウント)
AF化に先駆けて、AE化においても同様に旧来マウントでは
その実現が難しかった例もある(例:PENTAX等のM42)
これらのケースにおいて、カメラメーカーは苦渋の決断で
それまで自社が使っていたマウントを諦め、新規のマウント
に変更したケースがいくつかある。
具体的には、PENTAXをはじめとするM42マウント陣営が
AE化により、それぞれ独自のバヨネット式マウントに変更
(例:PENTAX Kマウント 1975年)
そしてミノルタがAF化でMD系からαマウントに変更(1985年)
さらには、キヤノンもAF化でFDからEF(EOS)に変更(1987年)
デジタル時代においても、CONTAXがY/CからNに変更(2000年)
さらにはオリンパスが、OMから4/3に変更(2003年)や
4/3からμ4/3に変更(2008~2009年)などの例がある。
また、完全変更ではなく、「併売」という状況も近年の
ミラーレス機において、いくらでも事例がある。
AE化やAF化で旧来のマウントとは大きく性能が進化し、
かつ旧来のマウントと互換性が高いケースであれば、
ユーザーの不満は殆ど無い(例:PENTAX M42→K)
あるいは、旧来のマウントとは時代が大きく離れていても
あまり問題は無いであろう(例:OLYMPUS,CONTAX)
また、新マウント機が圧倒的に高性能であれば、それも
あまり問題は無い(例:MINOLTA MD→α)
そして、同一メーカーの一眼レフとミラーレス機が異なる
マウントであっても大きな問題は無い(例:NIKON F/1/Z)
そして、大きく関連するのは、旧来マウントのユーザー層の
実数がある。特にPENTAX系M42マウント機は数百万台という
膨大なユーザー数があった為、マウント変更は互換性を
保ちながら慎重に行う必要があった事だろう。
さて、逆に、旧来のマウントがそこそこ人気であり
かつ新マウントが旧マウントと互換性が無く、さらに
新マウントの機体があまり魅力的な仕様や性能では無い場合
ユーザー層の不満が一気に爆発する事となる。

FD系には新旧F-1,A-1,T90等の非常に優れた銀塩一眼レフが
多く、それらのユーザー層は、多数のFD系レンズとともに
それらを愛用していたのだが、ある日突然、新しいマウント
に変化し、もう旧マウント製品は作らないという。
初期EOSには魅力的な機体は無く、EOS機の性能優位性が
顕著になるのは、数年後の、およそ1990年前後からだ。
これでは、さすがにユーザーは怒るのが当然だ。
事実、1987年~1990年代初頭くらいまでの間は、CANONの
この措置に、旧来のCANON党はブーイングの嵐であったと聞く。
まあでも、10年かそこらもすれば、こうした不満も収まる、
何故ならば、カメラの進化により、新機種には圧倒的と
言える性能が搭載され、旧機種の「仕様的老朽化」が激しく
なるからだ。例えばCANONではEOS-1NやEOS-3等の超高性能
機が1990年代後半には登場している。New F-1は確かに
名機ではあるが、もう15年以上も前の時代の機種だ、単純に
性能面だけ見れば、これら新鋭機に対して勝ち目は無い。
でもまあ、そういう風に時期を待つのも、ユーザー層に
おいては辛い。こういう場合は、いさぎよくFD機をもう
諦め(気に入らないからEOSを買わず)ニコンやミノルタに
鞍替えしてしまうユーザーも多かった事であろう。
それと、ちょうどこの時代、前述の中古カメラブームが
あって、趣味撮影を行うアマチュア層では、もう業務用途
機として肥大化した性能の新鋭一眼レフ(例:EOS-1N/V
やNIKON F5等)には興味が持てず、カメラらしい外観と
性能での、存在感や所有満足度が高い旧時代の旗艦機に
興味が行ってしまった訳だ。
マウント変更の件は、こうして時代がすぎれば「うやむや」
になってしまうが、まあでも、一時代をとってみれば、
これはメーカーのブランドイメージの低下が大きい。
近年では、このような、大幅なマウント変更は各社とも
よほどの事がなければ行わない。まあ一眼レフと並行して
ミラーレス機が販売される場合は、小型化、および高性能化
(フルサイズ、高画素数等)を理由とした新マウント機発売も
多々あるが、これらが従来の一眼レフとの互換性が無くても、
別ジャンルの商品であるから、ユーザーは、そこに不満は無い
事であろう。困るのはむしろ(旧)製品ラインナップの廃止
(製造中止)だ。

ニコンはFマウントをおよそ60年、ペンタックスはKマウントを
約45年も続けているが、時代の変化とともに、同じマウント
形状であっても、電子化等で、その互換性は高いとは言い難い。
例えば現代のニコン(F)機で、非Aiのレンズを装着できる機体は
NIKON Dfしか存在せず、しかもその機体の操作系では絞り値
の二重操作が発生する等で、非Aiレンズの実用は苦しい。
FやKのマウント仕様(規格)の変化は、複雑怪奇であり、
各時代のレンズを装着可能か否かは、一般ユーザー層では
その理解は困難か不可能。これがわかっているのは一部の
上級マニアか、専門中古店のベテラン販売員だけであろう。
いずれにしてもマウント変更は色々と問題がある訳だ。
★レガシー/絶滅危惧種
やや独自の用語。
「レガシー」とは、近年には人気政治家が使った事でも
著名になった言葉であるが、元々の意味としては
「遺産、(先人の)遺物」という意味が肯定的な内容で
使われ、逆に否定的な意味では「時代遅れ」がある。
PC(パソコン)等の分野では、旧型式の規格や構造を指す
用語として、昔(1990年代頃~)から使われている。
具体的な例をあげれば、RS-232Cシリアルポートとか、
VGA端子、フロッピーディスクなど、多数ある。
これらは「レガシー・デバイス」と呼ばれていて、
新技術による規格に置き換わった際、これらをどう扱うか
は、PC界においては、なかなか頭の痛いところであろう、
旧来の規格は、まだ特定の分野(例、工場の生産ライン等)
では使われている場合もあり、完全に無視する事は出来ない。
なので、この場合は「レガシー」は、肯定とも否定とも
つかない意味で使われている。
本ブログにおいても、カメラ機能や、その操作系において
「レガシー」という用語を使う場合があり、これはむしろ
「古い、時代遅れ」という否定的な意味である事が殆どだ。
で、あまりに「レガシー」が進むと、今度は「絶滅危惧種」
という表現を用いる事もある、ただ、これはこれで、むしろ
「貴重であって、できれば残したい」という意味も出てくる。

やや独自概念。
旧来、情報とは、それを積極的に調べる行動を伴わないと
得れるものではなかった。しかし1990年代くらいになって
インターネット等が普及すると、そういう機器を使える層と
そうでは無い一般層との間で、情報を得る為の格差が大きく、
「デジタル・デバイド」や「情報ヒエラルキー」といった
用語が出て来て社会問題となった。
だが、その後、PCやスマホの普及により、WEBやSNS等による
情報化が一般にも広まってきた2000年代~2010年代に
おいては、デジタル・デバイドは解消されつつはあるが、
むしろ増えすぎた情報に対して、一般層は、その取捨選択が
大変難しい状態になっている。
いやむしろ、そうした情報弱者に対しての「情報操作」を
行う事も、現代のビジネスモデルにおいては重要な点だ。
(例えば、誰かのオススメがあれば、皆、簡単に信じてしまう。
それは意図的に流された好評価であったとしてもだ・・)
そうした「情報操作」の是非は微妙なところだ、市場維持の
為に当然とも言えるかも知れないし、あくどい、と思う事も
多々あるだろう。いずれにしても肝心なのは、情報利用者が
その情報の意味、価値、信憑性などを正しく判断する術を
身につける事だ。
だが、それが難しい事は言うまでも無い、一般層は、簡単に
世の中にある情報に振り回されてしまうのだ。
その顕著な例が、私が言うところの「一極集中化現象」
である、TV等の公共メディアはもとより、インターネット等
で発信された情報に、多くの一般層が群がるようにして
1つの場所や商品や同じ価値観に集中してしまう現象だ。

「そこまで単純に振り回されてしまって良いのだろうか?」
という意味である。
一箇所に人が集まると行列などができて時間が無駄になり
混雑して交通や往来にも多大な影響が出たり、あるいは
マナーが低下して、その場所や近隣の住民にも様々な迷惑を
かけてしまう。
グルメ店などに限らず、カメラ分野でも同じ被写体に多数の
人が三脚を立てて群がったり、絵画などでも、多数の人が
イーゼルを立てて場所を占領するなど、迷惑でマナー違反だ。
あるいはグルメや、商品等では、評判がよければどんどんと
価格が上がってしまい不条理だし、中古商品等では、下手を
すれば値上がりや転売を期待する投機層が現れる。
ただ、そうした情報に乗る人達にとってみれば、今度は逆に
「今、巷で流行っている、あるいは有名な、場所や店舗に行った
事で周囲に自慢できる」という要素があるようだ。
その事で、SNSなどで「イイネ」をもらいたいのであろう。
けど、あまりに受動的だ。美味しい店の料理は、作った人が
偉い/凄いのであって、それを食べた人が自慢するべき物
ではない。また、そんな主張に共感する方もどうだろうか?
他に、自分自身の力では、主張したり共感を得れる要素は、
何もないのだろうか?と情けなく思えてしまう。
写真や絵画だってそうだ、同じ場所で皆と同じ写真を撮ったり
していても、「個性」も「表現」も、何も出て来ない。
まあ、どうみてもネガティブな要素が大きい為、私自身は
対策として、これらの「一極集中化現象」を逆情報として
利用する事にしている。
簡単な例を挙げれば、「今年の桜の名所」として、様々な
メディア(TVやポスター、情報誌、WEB等)で取り上げられた
場所は、「一極集中化」が起こる事が明白だ、そうした
場所には一切近寄らない事がベターである。
メディアで取り上げる方も、様々な相乗効果により
そこでビジネスチャンスを起こしたい訳だ、他のごく簡単な
例を挙げれば、映画公開や新ドラマの前には、大御所俳優
すらもTVのバラエティ番組に出演するでは無いか、それにより
メディア・ミックスの効果を期待するからだ。
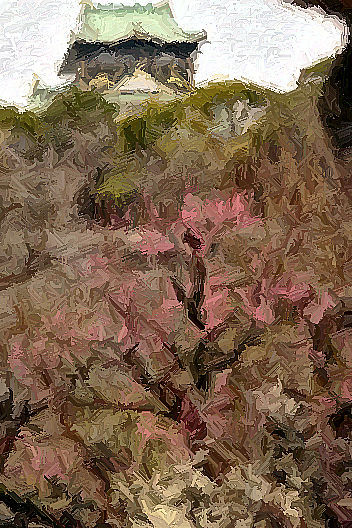
グルメ、ファッション、商品の流行、そしてカメラやレンズ
ですらもこれが起こりうる。
いずれにしても、少なくとも私にとってみれば、あまり
乗るべき対象でもないし、むしろ逆に「情報に振り回される
のは、褒められた話では無い」とも思ってしまう。
様々に溢れる情報に対しても「自身の価値観を持って対処する」
という点が重要なのだろうと思う。
これもまた、新しい「情報ヒエラルキー」の一種だとも思う、
現代では、一部の階層で情報が不足する状況は解消したが、
情報の価値や真の意味がわからない階層が、損をしている
と言う事になるからだ。
★ビハインド
独自用語。
元々の英語では、「背後」という意味が大きいと思うが
スポーツ競技では、対戦相手に対しての点差や時間差が
ある(つまり、負けている)という意味で良く使われる。
本ブログにおいては、カメラやレンズの性能や仕様が
同時代の他社製品に対して、劣っているまたは遅れている
際にこの用語を良く使っている。
具体例は、その製品を使っているユーザーにとっては
不快な情報であろうから、今回は割愛する。
なお、普通は、いつまでもビハインドは続かない、それが
市場で明白ならば、その機器は売れなくなってしまうからだ、
だから遅れている他社は、その性能差を巻き返そうとする、
新製品ではビハインドを取り返して、むしろ他社より性能が
優れているケースも多々ある。
よって、長い目で見れば、ビハインド状態が機材購入において
あまり問題となる事も無い訳だ。むしろ不人気であった事で
後年に中古相場が大きく下落し、絶対性能に対して、コスパが
極めて良くなっている場合すらある。
(注:逆に、ユーザー層が、その機材の「ビハインド状態」に
気づかず、発売後いつまでも人気があり高値相場である場合も
ある。そういった場合には「コスパが極めて悪い」と無視する
のが良いが、それを判断する事は、一般層にはやや難しい)
★バブリーなカメラ
独自用語。
バブル期の1980年代後半から1990年代初頭にかけて
企画・開発されたカメラの多くは、華美なスペックを
並べた高機能・高性能至上主義の製品が多かった。
別に高性能である事は悪い商品企画では無いのだが・・
バブル崩壊とともに、ユーザー側のニーズや価値観も変化
してしまい、必ずしも高性能を目指したカメラが良い物だ
とはユーザー側で思い難くなってしまった時期があった。
この歴史を指して、バブル期開発のカメラを「バブリーな
カメラ」と本ブログでは呼ぶ事がある。
ここも具体例は多すぎるので割愛するが、他の記事でも
色々と実例を挙げている。

「カメラ形態15~20年説」での各形態の末期においては、
華美で過剰とも言えるスペックを並べて、縮退したユーザー
層のニーズ(購買欲)を喚起するケースがある。
現代のデジタル一眼レフ市場でも、普及からおよそ15年が
経過し、すでに市場は飽和状態であり、2015年以降の
新機種では、超絶的と言えるスペック(本シリーズ第1回
記事参照)を、「付加価値」(=値上げや利益確保の理由)
として与えられている。(そもそも、一眼レフ新製品の
発売ペースが非常に鈍化している)
また、一眼レフだけでは無く、ミラーレス機もフルサイズ化
などの超絶性能を持たせた新製品が登場している。
これもまた「バブリーなカメラ」の一種なのかも知れない、
こうした思想や指向性がユーザーニーズに合っているか
否かは、その時代の中では判断しにくい。
数年あるいは10年が経過して、その時代の市場や世情や
評価を冷静に振り返る事で、それが正解だったのか否かは
判断できるであろう。
例えば商品が高価すぎて売れないならば、ビジネスにならない
ので、市場には必ず低価格な商品が投入され、市場は自ら
バランス点を求めて推移していく。
まあでも、どんな結果になったとしても、それもまた
「カメラの歴史」の1ページではあるだろう。
どんな商品でも常に順風満帆な時代が続く訳では無いのだ。
★パラダイムシフト
一般用語。
元々は科学分野で、ある科学者が「パラダイム」という
概念を唱え、1960年代~1970年代に出始めた言葉だが、
1980~1990年代には拡大解釈されて一般化した用語だ。
拡大解釈においての「パラダイムシフト」とは、
「それまで当然の事として認識されていた概念や価値観が
劇的に変化する事」を指す。
これは主に、科学の分野で使われるべき用語ではあった、
科学分野では、古くからこれは起こっており、例えば有名な
例を挙げれば、天動説から地動説に変化した等がある。
そこまで極端な例ではなくても、科学分野では頻繁にこれは
起こる事で、新技術、新発見などで起こる「科学の革命」は
様々な事例がある。(CPU、デジタル化、青色LED、携帯電話、
インターネット、AI等、いくらでも前例がある)
学術研究以外にも、企業における新製品開発などでも、
良く「パラダイムシフト」がスローガンとして掲げられる
事がある、これはデジタル化やインターネット化、AI等の
大きな新技術分野が出て来た際に、それらの新技術の応用は
従来の古い概念や常識に囚われていたら難しいので、それの
企画・開発側あるいは商品を利用する側にも、概念の大きな
変革が必要になる、という意味だ。
科学分野に限らず、現代においては「パラダイムシフト」は
社会的な価値観の変革など、様々に用いられる事がある。
先年では、やはり前述の人気政治家が、この用語を使った
事で有名となっている。ただ、この用語自体は古くから
上記の状況で使われてきている。良く勉強はしていると
言えるのだが、用語の解釈は市場分野毎に様々に有りうる
ので、使う側でも捉える側でも、要注意だ。
本ブログにおいては、ごく稀にこの用語を使う場合がある、
市場全体での話ではなく、個人的な価値感の激変についてだ。
1つの例としては、ミノルタα-9(1998年)の記事
(銀塩一眼レフ第23回)がある。

たいした事が無いが、カタログに直接現れない面の多くが
優れていた(例:操作系、耐久性、実用性能(精度)など)
「α-9を見て、それまでカタログの仕様に現れない性能など
あるはずが無いと思っていたのが、その概念がひっくり返った
これは”パラダイムシフト”であると言える」という感じだ。
その他の時代、あるいは近年のカメラでは、あまりそうした
パラダイムシフトを感じさせてくれるような機種は、
殆ど出てきていない、ある意味、残念な話なのかも知れない。

となるが、内容は未定としておく。