所有している銀塩カメラの名機を紹介するシリーズ記事。
今回は第四世代(趣味の時代、世代定義は第1回記事参照)の
Voigtlander BESSA-T(2001年)を紹介する。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
装着レンズは、Voigtlander COLOR-SKOPAR 50mm/f2.5
(ミラーレス・マニアックス第1回記事参照)
さて、いきなり読めない単語だらけだと思う。
まずは読み方だけ最初に述べておく。
Voigtlander=フォクトレンダー(注:原語は変母音有り)
BESSA=ベッサ
COLOR-SKOPAR=カラースコパー
本シリーズでは紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わずに、
デジタルの実写シミュレーター機を使用する。
今回は、まずフルサイズ機SONY α7を使用するが、記事後半
では別のカメラに変えてみよう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
以降はシミュレーターでの撮影写真と、本機BESSA-Tの
機能紹介写真を交えて記事を進める。
さて、本シリーズで「第四世代」は「趣味の時代」と定義
しているのだが、前回第24回記事では「CONTAX N1」と言う
極めて正統派のAF一眼レフを紹介した。
今回のフォクトレンダー BESSA-Tは、前回とはうって変わって
完璧な「趣味のカメラ」である。
それと、本機は「一眼レフ」ではなく「レンジファインダー機」
である。これまで本シリーズでは全て「一眼レフ」を紹介して
きたが、この第四世代においては、その制限を緩和する事とする。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
まずレンジファインダー機の定義だが、
「視差式の距離計を内蔵していて、測定した距離に連動して
装着レンズのピント位置を変えられるカメラ」である。
一眼レフのように「ミラー」は持たず、ファインダー像も
レンズを通した状態(TTL)ではなく、別建てになっている。
そして、そもそも本機BESSA-Tは、ファインダーを持たない
特殊機である。
「これの何がメリットであるか?」と言うと、実の所、殆ど無い。
あくまで一眼レフ以前の旧世代のカメラだ。
1960年代頃から一眼レフが一般的になると、入れ替わるように
姿を消してしまい、本シリーズ記事の時代(概ね1970~1990年代)
では、ライカを除き、殆ど販売されていなかった形式のカメラだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
今回紹介のBESSA-Tは、通常の基本形態ではなく、
トリガーワインダー装備、ボトムグリップ装備、
Lマウントレンズをアダプターで使用、専用ビューファインダー
という、かなりマニアックな形態を取っている。
現代の一般カメラユーザーには、さっぱり意味がわからないと
思うが、わかろうとする必要は無い、これは極端に趣味性の
強いカメラの話なのだ・・
Image may be NSFW.
Clik here to view.
次に機種名の話だ。
BESSA-Tはハイフンが入るのが正解、あいからずこのあたりは
様々なWEB等では、いい加減だ。
特に「BessaT」という誤記が多い、ボディにはちゃんと
BESSAが大文字で、ハイフンが入って書かれている。
つまり、そのカメラを持ってもおらず、見た事も無いのに、
記事や情報をまとめたりする人が居る事が問題なのであろう。
(注:出展を記載しても意味が無い。その出展情報が
間違っていないという保証は、何処にあるのだろうか?)
そして、Voigtlander(フォクトレンダー)(注:PC表示での
便宜上、スペル上の変母音(ウムラウト)は省略してある)
とは、オーストリアおよびドイツにかつて存在したカメラ
メーカーであり、世界最古の光学機器メーカーであると
言われている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
この「フォクトレンダー」の読みは独語なので正確では無い、
戦前の日本に同社製のカメラが入ってきた際には、読めずに
「ホ(イ)クトレンデル」などの表記もあった模様だ。
コシナ社の公式WEBにおいては「フォクトレンダー」の読みが
推奨されている模様なので、以下もそれに従う。
フォクトレンダー社の創業はなんと1756年、これは日本では
江戸時代であり、第9代将軍徳川家重の時代・・と言っても
わかりにくいので、「田沼意次が力を伸ばしてきた時代」と
言う方がわかりやすいか?
(注:田沼意次は、かつては「賄賂政治家」として悪名が
高かったが、これは「失脚後に意図的に広められた悪評で
あった」という解釈が、現代では、むしろ一般的になって
来ている(教科書等でも、賄賂の話等はもう載っていない)
まあ、飛鳥時代の蘇我一族でも、戦国時代の明智光秀でも
そうだが、敗者は後年に反対勢力や新政権からボロクソに
言われてしまう訳だ。
まあ、勝ち組が好き勝手言うのは当然の話であり、そういう
一方的な視点による資料等を、簡単に信じてしまう方にも
色々と問題があるのだろう。これは歴史の解釈のみならず
あらゆる分野で同様の話だ。カメラにおいても、メーカー
や市場や評論家による、一方的な「美辞麗句」を簡単に
信じてはならない、これはユーザー側の重大な責務である。
加えて、カメラ関連の古い情報も、必ずしも全てが正しい
保証は無い、いや、むしろ、明らかに間違った情報も多々
見かける。だから、前述のように「出展(情報)」が
あるからと言って、その情報が正しい保証は全く無い。)
あるいは西洋史で言えば、イギリスの産業革命(蒸気機関の発明)
よりも僅かに早い時代。又は「アメリカ独立戦争」の20年前位だ。
さらには、「モーツァルト」の生誕年と同じ年であり、
「マリー・アントワネット」(ベルばらのオスカルも・笑)の
生誕年の翌年である。
本機BESSA-Tの背面にも「Since 1756」と印字されている。
1800年代のオーストリアは国際情勢の激変や戦況なども
色々とあったからか? フォクトレンダーは1862年に
ドイツ(ブラウンシュヴァイク)へ移転する。
オーストリア(ウイーン)からドイツへの移転後・・
独フォクトレンダー社は1900年頃には「ヘリアー」そして
1926年頃には「スコパー」という銘レンズを設計したが、
これらの名称が、その後の本記事の時代まで使われている。
第二次世界大戦では運よく戦禍を免れ、戦後の1949年には、
「カラーヘリアー」「カラースコパー」(今回使用レンズと
同一名称)を発表、その後続けざまに「ウルトロン」
「ノクトン」「アポランター」を発表、これらは現代の
コシナ製フォクトレンダーブランドのレンズ製品名にも使われて
いるので、現代のユーザーでも耳にした事がある名前であろう。
(過去のレンズ系シリーズ記事では、これらの名前を冠した
現代レンズを色々紹介している)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19132255.jpg]()
1950年代から1960年代にかけては、「ヴィトー」シリーズの
スプリングカメラ(レンズ交換不可)や、「ヴィテッサ」
(レンズ固定型、最終型はレンズ交換可)を多数発売、
後年1990年代の第一次中古カメラブームの際には国内市場でも
人気があった。
「ヴィテッサ」が著名な点は、煙突のようにカメラ上部から
突き出す「プランジャー」と呼ばれる巻上げ機構の存在だ。
私は、このあたりのカメラは所有する機会に恵まれなかったが
美しく、非常に格好良いカメラだと思う。
ずっと人気があるのか?近年ではTVアニメ「有頂天家族2」の
オープニングシーンと本編で、主人公の「下鴨矢三郎」が、
「ヴィテッサ」を使って写真を撮って、「プランジャー」を
押し下げるシーンが出てきている(注:アニメでは手振れを
起こしているように見えるが、巻き上げなので関係無い・笑)
フォクトレンダー社だが、この頃から日本製カメラの台頭が
始まり、1956年には経営が悪化し、カール・ツァイス社の
傘下となってしまう。
1960年には、世界初のズームレンズ「ズーマー」(注:この
名前が、現代の「ズーム」の名称の由来となった)を発売。
だが、このレンズは実は、その1年前にキルフィット社により
開発されていたものだ、
(関連:ハイコスパレンズ・マニアックス第19回記事)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19132163.jpg]()
1960年代からまた経営が悪化し、ツァイス・イコン等の傘下
を転々とし、最終的に1972年には操業停止に追い込まれた、
これは親会社の「ツァイス・イコン」自体がカメラ事業から
撤退した為もある。
この時点で「フォクトレンダー」のブランドと「CONTAX」の
ブランドが宙に浮いた。
日本の「ヤシカ」は、すぐさま「CONTAX」のブランド(商標)
を取得、その後1975年に国産CONTAXの一号機「CONTAX RTS」
が発売される事になる(本シリーズ第5回記事)
(注:ここが、栄光のブランド「CONTAX」の悲劇の始まり
である。初級マニア層等が思い込むように「CONTAX」は
順風満帆では無いし、「神格化」される要素も無いのだ。
→関連記事:本シリーズ第24回記事「CONTAX N1」参照)
しかし「フォクトレンダー」については、日本メーカーではなく
「ローライ」が取得した。二眼レフで有名な「ローライ」は
元々、フォクトレンダー社を退社した方が1920年に創業した
と聞いている。
で、1970年代後半には一眼レフの「ローライフレックスSL」
を別途、フォクトレンダーブランドでも販売していた。
(フォクトレンダー版一眼レフは、銀塩時代に中古店から借りて
使っていた事がある、購入候補の事前チェックの為だ。しかし
レンズ性能が気に入らず、汎用性も無かった為に購入を保留した)
なお、ローライはカール・ツァイスのレンズ名商標も取得
していて、一眼、二眼、コンパクト(ローライ35等)にも、
テッサー、プラナー、ゾナー等のレンズ名称が使われた為
後年、一部のマニアの間では「ローライのカメラは良く写る」
という評価が広まる。(注:カール・ツァイスとは直接関係が
無い話であり、これも単なる「思い込み」の類だ)
で、ここまで述べてきたように、ブランド銘やレンズ名は
単に「商標」であり、色々な企業を転々としている訳だ。
だから、その名前だけを見て性能が高いと判断する事は
出来ない事は言うまでも無い。(まあでも、商標を売る
(使用権を与える)方も、あまりに性能の酷いレンズに
名前を使わせる事も無い為、そこそこは高性能である)
この1970年代後半は、国産カメラがAE化で大きく進化した
時代である、
この為、ローライも経営が悪化し、1981年に倒産してしまう。
だが、その後「ローライ」のブランドもまた、色々な会社に
引き継がれていく。なんでも2000年代位までは、まだ
二眼レフを生産していた模様だが、現在ではどうなっている
のか話は聞かない・・
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19142054.jpg]()
さて「フォクトレンダー」のブランドは、三度(みたび)
宙に浮く、1981年からはカメラメーカーでは無さそうな会社が
商標権を取得していた模様であるが、そこに目をつけたのが
日本のコシナである。
技術力は高いが知名度が低いコシナ社が「ブランド」を強く
欲していた事は、様々な記事に書いてきた通りだが、
本シリーズでは第18回記事「YASHICA FX-3 Super2000」
や、第22回「OM2000」のあたりに詳しい。
さて1999年にコシナ社は、無事「フォクトレンダー」ブランド
を取得、そこから畳み掛けるように、同ブランドでの多数の
カメラ・レンズ展開を始める、恐らくはもうとっくに設計は
完了していたのであろう、「後は名前だけ」という状態だ。
しかし、こういう話を読んでいくと、「ブランド信奉」が
ガラガラと音をたてて崩れていかないだろうか?
老舗メーカーがずっと作り続けている服飾品などのブランド
とは異なり、カメラのブランドは、その多くが紆余曲折が
あったものばかりだ(その理由は日本製カメラの台頭もある)
で、その時代により、設計した所も、作っている所も、まるで
異なる訳なので、ブランド銘だけを聞いても、その性能などは
判断できる筈も無い。(そんな事を言うのはビギナー層だけだ)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19134397.jpg]()
さて、「ブランド」を入手したコシナは、やっとここで
その本来持っていた技術力を遺憾なく発揮できる状態になった。
ただ、勿論ブランド銘が付いた分、価格は高くなってしまった。
これはまあ、高く売りたいが為に、高いお金を出してブランドを
買ったので、やむを得ない、つまり、そういう「仕組み」である。
しかし実の所、現代のコシナ・フォクトレンダーのブランドの
レンズは、どれも高品質、高性能で非常に良く写る。
私が、かなり沢山のフォクトレンダー銘のレンズを所有して
いるのも、その事実の表れであろう。
私自身、ブランド信奉は全く無いので、殆ど全てのメーカーの
カメラやレンズを購入している。ただ、どう考えてもコスパが悪い
と見なせる物は買っていない。過去、まったく紹介記事に出て
きていないメーカーあるいはシリーズ機種群がいくつかあるのは、
そういう理由だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19142049.jpg]()
ここで、ごく簡単に、コシナ社がフォクトレンダーブランドを
取得後に、本機BESSA-Tより前に発売された機種名を紹介する。
<1999年>
BESSA-L Lマウント、ファインダー非搭載の目測式カメラ
<2000年>
BESSA-R Lマウント、距離計連動型
<2001年>
BESSA-T VMマウント(本機)
ちなみに、Lマウントとは、φ39mmのねじ込み式マウントで、
L型ライカと互換である。ライカの他、第二次大戦後の国内では
非常に多数のLマウント・レンジ機(ライカコピー品)が発売
されていた。
(注:近年のミラーレス機用のLマウントとは異なる為、
ごく最近では、旧LマウントをL39と記載し、明確に区別する
習慣が始まりかけている)
VMマウントとは、同じくライカのバヨネット式Mマウント互換だ。
なお、ライカ(エルンスト・ライツ社)は、1972年発表の
「OLYMPUS M-1」に、「Mは使うな」とケチをつけて強引に
OM-1にさせてしまった前科がある。(本シリーズ第13回
OM-4Tiの記事参照)明らかな言いがかりであり、現代の観点
から見れば気持ちの良い話では無いのだが・・
まあ、もし、また何か言われたらかなわない。コシナも安全の為、
フォクトレンダーの頭文字のVをつけて「VMマウント」と称した
のであろうか・・
なお、上記の年表において、コシナは多数のフォクトレンダー
ブランドのレンズを、この時期2000年頃より発売している。
L/VMマウントのレンジ機用はもとより、一眼レフ用レンズもだ。
そのあたりは書いていくときりが無いので、やむなく割愛する。
---
さて、本機BESSA-Tであるが、とてつもなく捻くれた(汗)
コンセプトのカメラである。
(銀塩)写真を撮る為の三要素、と言えば、絞り、シャッター、
ピントである。で、BESSAシステムの場合、絞り環はレンズに
ついている。シャッター速度はBESSA-Tに入っている露出計を
用いて、ISO感度を合わせて、三点合致(赤・緑・赤)の
LEDを頼りに露出を合わせる、これはつまりマニュアル露出機だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19142044.jpg]()
ちなみに、露出計はレンズの光を直接測るTTL方式であり、
レンズを絞ると、絞り込み測光になるのだが、そもそも本機は
ファインダーを持たず、一眼レフのようにTTL方式で直接
レンズからの映像を見る事は出来無い。
次にピントだが、距離計が入っている。この距離計は
レンズ側のレバーに連動する為、視差の二重合致式(まあ
一眼レフで言う「水平スプリット」のようなもの)を用いて、
ピント合わせ専用の小窓を覗きながらピントを合わせる。
(この小窓はTTLファインダーでは無いので、レンズを交換しても
見える画像はいつも同じ範囲(画角)だ)
小窓には視度補正が一応ついている、なお、これを覗きながら
では露出計が見えないのだが、LEDが光っているのは、なんとなく
横目で見える為、小窓を見ながらの露出合わせは可能だ。
露出とピントが合ったら、外付けのビューファインダーを見て
構図を決める。このビューファインダーはレンズの各焦点距離
専用で画角が決まるので、レンズ交換をしたらファインダーも
交換しなければならない、さもなければ「勘」(あるいは
ノーファインダー技法)で撮るかだ。
小窓でのピント距離と、この時点ではズレているかも知れない、
しかし、そういう細かい点は気にしない事だ(汗)
そもそも、レンジ機のほぼ全ての機種は、画面中央部でしか
ピント合わせが出来ない。例えMFロック技法(構図を変えて
MFをする)をしても、構図を戻したら「コサイン誤差」が
出てしまい、ピント距離が変わる、しかしここもまた、気に
しない事だ(笑) いくらピント精度に優れた本機であっても
被写界深度が浅いレンズの使用や、そうした撮影状況はレンジ機
では作り出してはならない(そういう撮影は現代のミラーレス機
で行うべきである)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19142036.jpg]()
近距離撮影では、ファインダーの位置とレンズの位置に差が
ある為、構図がずれてしまう。これを防ぐ為、ファインダー内
には、視差(パララックス)の補正マークがある、しかし、
撮影距離に連動した正確なものでは無いので、ここもあくまで
勘で構図を決めるしか無い。
構図が決まればシャッターをレリーズする、なお、もたもたと
時間がかかるので、太陽が翳ったりして、露出値が変わる事も
あるだろう、そういう場合は露出値設定を、絞り値または
シャッター速度の変更でやり直しだ。
シャッターを切って撮影が終わると、フィルム巻上げだ、
本機の使用形態では、通常の巻上げレバーを使うか、又は
ボディ下部のグリップを握って、トリガーワインダーを用いて
レバーを引いて、一気に巻き上げる。
(これがなかなか気持ち良い操作だ)
以降、写真を1枚撮るたびに、この操作の繰り返しだ。
「なんという面倒臭い操作が必要なカメラだ!」
と言う意見も勿論あるだろう、それは当然だ、本機BESSA-Tは、
「この面倒臭さを自虐的に楽しむ為のカメラである」と
言っても過言では無い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19134315.jpg]()
時代は、AEだ、AFだ、とか言って、どんどんと便利なカメラが
発売されていた、どんなビギナーでも、シャッターを半押し
すればピントも露出も合って、簡単に写真が撮れてしまう。
けど、本機BESSA-Tは、ビギナーでは絶対に使う事が出来ない。
面倒臭いのは確かだが、選ばれた中上級者だけが、写真を撮る
事ができる、極めて専門的なカメラなのだ。
そして、写真撮影の原理がわかっていれば、意外にスピーディ
に撮れるカメラだ。たとえば広角レンズをパンフォーカスに
設定しておけば、ピントを合わせる必要はほとんど無い、
合焦時間=ゼロ秒は、どんな高性能のAF一眼レフも及ばない。
露出もネガフィルムであれば、勘で決めれば十分だ、
一応ちゃんとしたTTL露出計が入っているので、自分で決めた
値が間違っていたら、すぐわかる。ちなみに機械式シャッター
カメラなので、電池が無くても撮影が可能だ。
また、トリガーワインダーを駆使すれば、秒2コマから秒3コマ
位は撮影する事ができてしまう。初級一眼レフの電動ワインダー
よりも、むしろ速いかも知れない。
BESSA-Tを格好良く使おうとするなら、上記の3点を守る事だ、
びっくりする程、素早く写真が撮れる。最高性能の旗艦機を
持ち出してくる初級マニアの鼻をあかすには最適だ(笑)
彼らがモタモタと高級機の撮影準備をしている間に、本機
であれば、およそ1秒以内に「抜き撃ち」撮影が可能だ。
条件を整えれば、カメラの設定は殆ど不要であるから、
熟練すれば、ゴルゴ13や、次元大介、「シティーハンター」
の冴羽、「シェーン」のアラン・ラッド、それから、
「ドラえもん」の野比のび太(笑)並みのコンマ何秒という
「早撃ちスナップショット」も可能となるだろう。
なお、基本的に「撮影技能」(スキル)と、撮影準備時間
は反比例する。つまり、上級者になるほど、速やかに撮影
を行える。どんな高級カメラを持っていたとしても、構えて
から撮る迄、何十秒も、下手をすれば1分以上もかかって
いたら完全な超ビギナーである事がまるわかりだ。
現代機を使う場合でも、構えてから撮るまでは3秒以内が
とりあえず上級レベルとしての目標値だろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19142061.jpg]()
レンズについても少し述べておく。
COLOR-SKOPAR 50mm/f2.5は、コシナ・フォクトレンダー
初期のL(39)マウント版レンズだ。
初期と言う物の、2002年の発売なので、正確に言えば、
本機BESSA-Tの翌年の製品だ。
最短撮影距離は75cm弱である。本機本機BESSA-Tでは、仕様上
では0.9mからの距離計連動範囲となっているが、それを超えて
なんとか使える。
真鍮製鏡筒(鏡胴)により、非常に高級感が高く、小型レンズ
でありながら、ずっしりと重い。
「スコパー」は元々は1926年にテッサー型(3群4枚)で
発明されたレンズだが、本レンズは6群7枚と本格的な構成だ。
開放F値を暗めに抑えた設計で、極めて良好な描写力を持つ。
レンジ機で使用する際は、ファインダー像が見れないので
そのあたりは全くわからないが、高精細なEVFを持つ現代の
ミラーレス機に装着すると、EVF越しであってもクリアな映像が
感じられ、いわゆる「良く写る空気感を持つ」レンズである。
(この感覚を言葉で説明する事は難しい)
ボケ質破綻が僅かに出る場合があるが、ミラーレス機で使う
のであればボケ質を確認しながら、絞り調整、撮影距離調整、
デジタルズームによる構図の微調整を含めた、高度なボケ質
破綻の回避技法が使える。なお、レンジ機では構造原理上、
こうした回避技法の利用は不可能である。
で、一眼レフやミラーレス用の50mm標準レンズとして考えると、
最短撮影距離75cmは低性能である。このあたりがレンジ機用
レンズ全てでの不満に繋がる。距離計連動の制約があり
たとえ広角レンズでも70cmないし90cmが最短撮影距離と
なる訳だ、これでは現代的な撮影技法には全く適さない為、
近年のL/Mマウント→ミラーレス機用マウントアダプターでは
ヘリコイドを内蔵し、最短撮影距離を短縮できるものもあるが、
一般に、通常アダプターよりもかなり高価になる。
また、ヘリコイドを繰り出すと無限遠撮影が不能となるのと、
ヘリコイド回転角が大きい場合が多く、迅速なピント操作性に、
重大な制約が出る。
後、このレンズには、フォーカス用レバー(突起)が
ついている。BESSA-Tでオプションの下部(ボトム)グリップ
を使う場合は、このフォーカスレバーを左人差し指の側面に
引っ掛けるように使うと、フォーカシングが楽に行える。
なお、ミラーレス機でこのレンズを使用する場合には、この
レバーを親指と人差し指で摘むようにするのが使い易いのだが、
その際、右手のみでカメラをホールド(維持)できるような
重量と形状のミラーレス機で無いと苦しいであろう。
このレンズの発売時価格は、シルバー版で48,600円だった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19134382.jpg]()
さて、このあたりで本機BESSA-Tの仕様の紹介だが、
数値スペックは意味が無いカメラだ、最小限にとどめておこう。
BESSA-T(2001年)
距離計連動型35mmフォーカルプレーンシャッター式カメラ
最高シャッター速度:1/2000秒
シャッターダイヤル:1秒~1/2000秒,Bulb
フラッシュ:非内蔵 X接点1/125秒
ファインダー:無し(外付け)
距離計連動範囲:0.9m~∞
距離計像倍率:1.5倍(視度補正機能付き)
使用可能レンズ:フォクトレンダーVMマウント
巻き上げ角:不明、分割巻上げ可、トリガーワインダー装着可
露出計:TTL型三点合致LED方式
露出計電源:SR44/LR44 2個使用
ISO感度:手動 ISO25~1600(1/3段ステップ) DXコード非対応
本体重量:385g(電池除く)
発売時定価:55,000円(税抜き)
----
ここでシミュレーター機のSONY α7の使用をやめる。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19135550.jpg]()
代わりに、μ4/3機PANASONIC DMC-GX7を使ってみよう。
画角は狭くなるが、軽快さが出て格好も良くなる。
加えて、撮影倍率の不満が軽減し、フォーカスレバーの
操作も快適だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19135517.jpg]()
ここで本機BESSA-Tの長所だが・・
ここも書くべきかどうか、微妙な所だ。
長所短所は、一眼レフ同士などであれば、比較的容易だが、
本機のような唯一無二のマニアックな機体で、それをどう
評価すれば良いのであろうか?
まあ、あえて言えば、基線長が長く、倍率も1.5倍ある
有効基線長は53.7mmという資料もあり、他のレンジ機より
ダントツに長い。
すなわち、レンジファインダー機の弱点である「望遠レンズを
使った際にピントが合い難くなる」と言う点を、本機BESSA-T
では解消している事になる。噂によるとBESSA-Tの「T」は、
「テレ」すなわち「望遠」という意味だ、という説もある。
(しかし、「だからどうした?」という気もする。
カメラの弱点を助長するような使い方をする筈も無く、
望遠が必要であったら、一眼レフか、または現代であれば
ミラーレス機を持ち出せば済む話なのだ・・
カメラとレンズによる「システム」は、最大効率を得る
為の組み合わせを模索するものだ。両者の長所を活かせず
逆に欠点を助長するようなシステムを組んでしまうようでは
ビギナーでしか無い、という事となる)
それと「BESSA」の方の意味だが、独フォクトレンダー社に
おいて、中判カメラの名称に使われていた物が由来な模様だ。
(その単語の意味までは、調べていないので不明だ・・)
本機の最大の長所は、その「マニアックさ」であろうか。
でもこれも、人によっては「こんな面倒でややこしいカメラ
なんて使えるか!」と、まったく逆の印象となる事もあろう。
それと、AFやAEに慣れた(銀塩でもデジタル機でも)初級層
では絶対に使い方がわからないカメラである、それ故に
「どうだ、このカメラで写せるか?」という意地悪な
クイズを出す事もできるという、捻くれた楽しみもある。
・・いや、意地悪ではなく、写真撮影の基本を理解する為の
「教材」にする事もできるカメラであるかも知れない。
けどまあ、なんとも長所が見つけ難い、不思議なカメラである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19135520.jpg]()
本機BESSA-Tの弱点であるが、
BESSAシリーズのベースとなった機体はOM2000等のコシナOEM
一眼レフの場合と同じ、その昔の「コシナCT-1」系一眼である。
これには勿論ミラーがあったので、BESSAシリーズ開発の際、
ミラーBOXを取り除いた。で、そのままではフィルムが感光して
しまうので、二重露光防止シャッター構造とした模様だ。
まあ、それはそれで良いのであるが、構成部品(シャッター等)
の品質が、元々低価格機であったため、どうにも、感触性能に
劣ってしまう。
シャッター音、シャッターフィール、巻き上げ感などは、
旧来のOEM一眼レフタイプと同様に、Bクラスでしか無い。
だが、ミラーBOXを取り除いた事で、CT-1系の弱点であった
「ミラーショックの大きさ」が見事に解消されている。
それと、巻き上げ感の問題は本機BESSA-Tでは、マニアッックな
トリガーワインダーを使用しているため、むしろ気持ちが良い。
(ラチェットのキリキリと言う音が、精密感があって最高だ)
他の弱点だが、良く分からない。比較の対象が無いのだ・・
結局「使いにくさ」以外、他の弱点が見つけ難いカメラと
なっている。
なお、レンジ機自身の構造的問題点については不問とする、
それを書き出すと長くなるし、本機のような特殊機でその事を
言い出すのは無粋だとも思う。
客観的には長所も短所も無く、あくまで主観的に判断するべき
カメラであろう。そう、これぞまさしく「趣味の時代」の
カメラの典型的な特徴の1つでもあるように思える。
カタログスペックとか、他機との比較など、どうでも良いのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_19135549.jpg]()
さて、最後に本機BESSA-Tの総合評価をしてみよう。
評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)
----
Voigtlander BESSA-T (2001年)
【基本・付加性能】★★
【操作性・操作系】★
【ファインダー 】★★★☆(連動距離計として評価)
【感触性能全般 】★★☆
【質感・高級感 】★★★
【マニアック度 】★★★★★
【エンジョイ度 】★★★★
【購入時コスパ 】★★★☆ (中古購入価格:26,000円)
【完成度(当時)】★★★
【歴史的価値 】★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】3.1点
意外な事に標準値3点を上回った、不思議な評価傾向である。
基本性能は低く、操作性も悪く、感触性能もイマイチだ、
写真を撮る上ではどうしようも無く不便で面倒で出来の悪い
カメラなのに、何故か使っていて、とても楽しい。
マニアック度満載であり、デジタル時代に入ってからも
マニアの集まりなどの際に、たまに持ち出した事もあった。
実用性能は評価不能だ、面白いと思う人は使えば良いし
こんな不便なカメラは嫌だと思えば、使わなければ良い。
使う側(ユーザー)の方向性、嗜好性、コンセプトなどに
極めて大きく影響されるカメラであろう。
勿論現代のビギナーには全く推奨できない、ただ本機は最初から
基本性能が低いカメラであり、現代の視点で見ても、これ以上
性能が(相対的に)古くなる事は無いし、そもそも性能を見て
買うかどうかを決めるようなカメラでも無い、
まあ、欲しければ買うしか無いし、全く関係無い世界だと
思えば、無視して忘れておけば良い、ただそれだけだ。
次回記事では、引き続き第四世代の銀塩カメラを紹介する。
今回は第四世代(趣味の時代、世代定義は第1回記事参照)の
Voigtlander BESSA-T(2001年)を紹介する。
Clik here to view.

(ミラーレス・マニアックス第1回記事参照)
さて、いきなり読めない単語だらけだと思う。
まずは読み方だけ最初に述べておく。
Voigtlander=フォクトレンダー(注:原語は変母音有り)
BESSA=ベッサ
COLOR-SKOPAR=カラースコパー
本シリーズでは紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わずに、
デジタルの実写シミュレーター機を使用する。
今回は、まずフルサイズ機SONY α7を使用するが、記事後半
では別のカメラに変えてみよう。
Clik here to view.

機能紹介写真を交えて記事を進める。
さて、本シリーズで「第四世代」は「趣味の時代」と定義
しているのだが、前回第24回記事では「CONTAX N1」と言う
極めて正統派のAF一眼レフを紹介した。
今回のフォクトレンダー BESSA-Tは、前回とはうって変わって
完璧な「趣味のカメラ」である。
それと、本機は「一眼レフ」ではなく「レンジファインダー機」
である。これまで本シリーズでは全て「一眼レフ」を紹介して
きたが、この第四世代においては、その制限を緩和する事とする。
Clik here to view.

「視差式の距離計を内蔵していて、測定した距離に連動して
装着レンズのピント位置を変えられるカメラ」である。
一眼レフのように「ミラー」は持たず、ファインダー像も
レンズを通した状態(TTL)ではなく、別建てになっている。
そして、そもそも本機BESSA-Tは、ファインダーを持たない
特殊機である。
「これの何がメリットであるか?」と言うと、実の所、殆ど無い。
あくまで一眼レフ以前の旧世代のカメラだ。
1960年代頃から一眼レフが一般的になると、入れ替わるように
姿を消してしまい、本シリーズ記事の時代(概ね1970~1990年代)
では、ライカを除き、殆ど販売されていなかった形式のカメラだ。
Clik here to view.

トリガーワインダー装備、ボトムグリップ装備、
Lマウントレンズをアダプターで使用、専用ビューファインダー
という、かなりマニアックな形態を取っている。
現代の一般カメラユーザーには、さっぱり意味がわからないと
思うが、わかろうとする必要は無い、これは極端に趣味性の
強いカメラの話なのだ・・
Clik here to view.

BESSA-Tはハイフンが入るのが正解、あいからずこのあたりは
様々なWEB等では、いい加減だ。
特に「BessaT」という誤記が多い、ボディにはちゃんと
BESSAが大文字で、ハイフンが入って書かれている。
つまり、そのカメラを持ってもおらず、見た事も無いのに、
記事や情報をまとめたりする人が居る事が問題なのであろう。
(注:出展を記載しても意味が無い。その出展情報が
間違っていないという保証は、何処にあるのだろうか?)
そして、Voigtlander(フォクトレンダー)(注:PC表示での
便宜上、スペル上の変母音(ウムラウト)は省略してある)
とは、オーストリアおよびドイツにかつて存在したカメラ
メーカーであり、世界最古の光学機器メーカーであると
言われている。
Clik here to view.
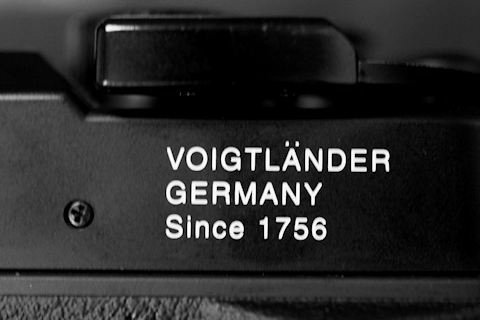
戦前の日本に同社製のカメラが入ってきた際には、読めずに
「ホ(イ)クトレンデル」などの表記もあった模様だ。
コシナ社の公式WEBにおいては「フォクトレンダー」の読みが
推奨されている模様なので、以下もそれに従う。
フォクトレンダー社の創業はなんと1756年、これは日本では
江戸時代であり、第9代将軍徳川家重の時代・・と言っても
わかりにくいので、「田沼意次が力を伸ばしてきた時代」と
言う方がわかりやすいか?
(注:田沼意次は、かつては「賄賂政治家」として悪名が
高かったが、これは「失脚後に意図的に広められた悪評で
あった」という解釈が、現代では、むしろ一般的になって
来ている(教科書等でも、賄賂の話等はもう載っていない)
まあ、飛鳥時代の蘇我一族でも、戦国時代の明智光秀でも
そうだが、敗者は後年に反対勢力や新政権からボロクソに
言われてしまう訳だ。
まあ、勝ち組が好き勝手言うのは当然の話であり、そういう
一方的な視点による資料等を、簡単に信じてしまう方にも
色々と問題があるのだろう。これは歴史の解釈のみならず
あらゆる分野で同様の話だ。カメラにおいても、メーカー
や市場や評論家による、一方的な「美辞麗句」を簡単に
信じてはならない、これはユーザー側の重大な責務である。
加えて、カメラ関連の古い情報も、必ずしも全てが正しい
保証は無い、いや、むしろ、明らかに間違った情報も多々
見かける。だから、前述のように「出展(情報)」が
あるからと言って、その情報が正しい保証は全く無い。)
あるいは西洋史で言えば、イギリスの産業革命(蒸気機関の発明)
よりも僅かに早い時代。又は「アメリカ独立戦争」の20年前位だ。
さらには、「モーツァルト」の生誕年と同じ年であり、
「マリー・アントワネット」(ベルばらのオスカルも・笑)の
生誕年の翌年である。
本機BESSA-Tの背面にも「Since 1756」と印字されている。
1800年代のオーストリアは国際情勢の激変や戦況なども
色々とあったからか? フォクトレンダーは1862年に
ドイツ(ブラウンシュヴァイク)へ移転する。
オーストリア(ウイーン)からドイツへの移転後・・
独フォクトレンダー社は1900年頃には「ヘリアー」そして
1926年頃には「スコパー」という銘レンズを設計したが、
これらの名称が、その後の本記事の時代まで使われている。
第二次世界大戦では運よく戦禍を免れ、戦後の1949年には、
「カラーヘリアー」「カラースコパー」(今回使用レンズと
同一名称)を発表、その後続けざまに「ウルトロン」
「ノクトン」「アポランター」を発表、これらは現代の
コシナ製フォクトレンダーブランドのレンズ製品名にも使われて
いるので、現代のユーザーでも耳にした事がある名前であろう。
(過去のレンズ系シリーズ記事では、これらの名前を冠した
現代レンズを色々紹介している)
Clik here to view.

スプリングカメラ(レンズ交換不可)や、「ヴィテッサ」
(レンズ固定型、最終型はレンズ交換可)を多数発売、
後年1990年代の第一次中古カメラブームの際には国内市場でも
人気があった。
「ヴィテッサ」が著名な点は、煙突のようにカメラ上部から
突き出す「プランジャー」と呼ばれる巻上げ機構の存在だ。
私は、このあたりのカメラは所有する機会に恵まれなかったが
美しく、非常に格好良いカメラだと思う。
ずっと人気があるのか?近年ではTVアニメ「有頂天家族2」の
オープニングシーンと本編で、主人公の「下鴨矢三郎」が、
「ヴィテッサ」を使って写真を撮って、「プランジャー」を
押し下げるシーンが出てきている(注:アニメでは手振れを
起こしているように見えるが、巻き上げなので関係無い・笑)
フォクトレンダー社だが、この頃から日本製カメラの台頭が
始まり、1956年には経営が悪化し、カール・ツァイス社の
傘下となってしまう。
1960年には、世界初のズームレンズ「ズーマー」(注:この
名前が、現代の「ズーム」の名称の由来となった)を発売。
だが、このレンズは実は、その1年前にキルフィット社により
開発されていたものだ、
(関連:ハイコスパレンズ・マニアックス第19回記事)
Clik here to view.

を転々とし、最終的に1972年には操業停止に追い込まれた、
これは親会社の「ツァイス・イコン」自体がカメラ事業から
撤退した為もある。
この時点で「フォクトレンダー」のブランドと「CONTAX」の
ブランドが宙に浮いた。
日本の「ヤシカ」は、すぐさま「CONTAX」のブランド(商標)
を取得、その後1975年に国産CONTAXの一号機「CONTAX RTS」
が発売される事になる(本シリーズ第5回記事)
(注:ここが、栄光のブランド「CONTAX」の悲劇の始まり
である。初級マニア層等が思い込むように「CONTAX」は
順風満帆では無いし、「神格化」される要素も無いのだ。
→関連記事:本シリーズ第24回記事「CONTAX N1」参照)
しかし「フォクトレンダー」については、日本メーカーではなく
「ローライ」が取得した。二眼レフで有名な「ローライ」は
元々、フォクトレンダー社を退社した方が1920年に創業した
と聞いている。
で、1970年代後半には一眼レフの「ローライフレックスSL」
を別途、フォクトレンダーブランドでも販売していた。
(フォクトレンダー版一眼レフは、銀塩時代に中古店から借りて
使っていた事がある、購入候補の事前チェックの為だ。しかし
レンズ性能が気に入らず、汎用性も無かった為に購入を保留した)
なお、ローライはカール・ツァイスのレンズ名商標も取得
していて、一眼、二眼、コンパクト(ローライ35等)にも、
テッサー、プラナー、ゾナー等のレンズ名称が使われた為
後年、一部のマニアの間では「ローライのカメラは良く写る」
という評価が広まる。(注:カール・ツァイスとは直接関係が
無い話であり、これも単なる「思い込み」の類だ)
で、ここまで述べてきたように、ブランド銘やレンズ名は
単に「商標」であり、色々な企業を転々としている訳だ。
だから、その名前だけを見て性能が高いと判断する事は
出来ない事は言うまでも無い。(まあでも、商標を売る
(使用権を与える)方も、あまりに性能の酷いレンズに
名前を使わせる事も無い為、そこそこは高性能である)
この1970年代後半は、国産カメラがAE化で大きく進化した
時代である、
この為、ローライも経営が悪化し、1981年に倒産してしまう。
だが、その後「ローライ」のブランドもまた、色々な会社に
引き継がれていく。なんでも2000年代位までは、まだ
二眼レフを生産していた模様だが、現在ではどうなっている
のか話は聞かない・・
Clik here to view.

宙に浮く、1981年からはカメラメーカーでは無さそうな会社が
商標権を取得していた模様であるが、そこに目をつけたのが
日本のコシナである。
技術力は高いが知名度が低いコシナ社が「ブランド」を強く
欲していた事は、様々な記事に書いてきた通りだが、
本シリーズでは第18回記事「YASHICA FX-3 Super2000」
や、第22回「OM2000」のあたりに詳しい。
さて1999年にコシナ社は、無事「フォクトレンダー」ブランド
を取得、そこから畳み掛けるように、同ブランドでの多数の
カメラ・レンズ展開を始める、恐らくはもうとっくに設計は
完了していたのであろう、「後は名前だけ」という状態だ。
しかし、こういう話を読んでいくと、「ブランド信奉」が
ガラガラと音をたてて崩れていかないだろうか?
老舗メーカーがずっと作り続けている服飾品などのブランド
とは異なり、カメラのブランドは、その多くが紆余曲折が
あったものばかりだ(その理由は日本製カメラの台頭もある)
で、その時代により、設計した所も、作っている所も、まるで
異なる訳なので、ブランド銘だけを聞いても、その性能などは
判断できる筈も無い。(そんな事を言うのはビギナー層だけだ)
Clik here to view.

その本来持っていた技術力を遺憾なく発揮できる状態になった。
ただ、勿論ブランド銘が付いた分、価格は高くなってしまった。
これはまあ、高く売りたいが為に、高いお金を出してブランドを
買ったので、やむを得ない、つまり、そういう「仕組み」である。
しかし実の所、現代のコシナ・フォクトレンダーのブランドの
レンズは、どれも高品質、高性能で非常に良く写る。
私が、かなり沢山のフォクトレンダー銘のレンズを所有して
いるのも、その事実の表れであろう。
私自身、ブランド信奉は全く無いので、殆ど全てのメーカーの
カメラやレンズを購入している。ただ、どう考えてもコスパが悪い
と見なせる物は買っていない。過去、まったく紹介記事に出て
きていないメーカーあるいはシリーズ機種群がいくつかあるのは、
そういう理由だ。
Clik here to view.

取得後に、本機BESSA-Tより前に発売された機種名を紹介する。
<1999年>
BESSA-L Lマウント、ファインダー非搭載の目測式カメラ
<2000年>
BESSA-R Lマウント、距離計連動型
<2001年>
BESSA-T VMマウント(本機)
ちなみに、Lマウントとは、φ39mmのねじ込み式マウントで、
L型ライカと互換である。ライカの他、第二次大戦後の国内では
非常に多数のLマウント・レンジ機(ライカコピー品)が発売
されていた。
(注:近年のミラーレス機用のLマウントとは異なる為、
ごく最近では、旧LマウントをL39と記載し、明確に区別する
習慣が始まりかけている)
VMマウントとは、同じくライカのバヨネット式Mマウント互換だ。
なお、ライカ(エルンスト・ライツ社)は、1972年発表の
「OLYMPUS M-1」に、「Mは使うな」とケチをつけて強引に
OM-1にさせてしまった前科がある。(本シリーズ第13回
OM-4Tiの記事参照)明らかな言いがかりであり、現代の観点
から見れば気持ちの良い話では無いのだが・・
まあ、もし、また何か言われたらかなわない。コシナも安全の為、
フォクトレンダーの頭文字のVをつけて「VMマウント」と称した
のであろうか・・
なお、上記の年表において、コシナは多数のフォクトレンダー
ブランドのレンズを、この時期2000年頃より発売している。
L/VMマウントのレンジ機用はもとより、一眼レフ用レンズもだ。
そのあたりは書いていくときりが無いので、やむなく割愛する。
---
さて、本機BESSA-Tであるが、とてつもなく捻くれた(汗)
コンセプトのカメラである。
(銀塩)写真を撮る為の三要素、と言えば、絞り、シャッター、
ピントである。で、BESSAシステムの場合、絞り環はレンズに
ついている。シャッター速度はBESSA-Tに入っている露出計を
用いて、ISO感度を合わせて、三点合致(赤・緑・赤)の
LEDを頼りに露出を合わせる、これはつまりマニュアル露出機だ。
Clik here to view.

レンズを絞ると、絞り込み測光になるのだが、そもそも本機は
ファインダーを持たず、一眼レフのようにTTL方式で直接
レンズからの映像を見る事は出来無い。
次にピントだが、距離計が入っている。この距離計は
レンズ側のレバーに連動する為、視差の二重合致式(まあ
一眼レフで言う「水平スプリット」のようなもの)を用いて、
ピント合わせ専用の小窓を覗きながらピントを合わせる。
(この小窓はTTLファインダーでは無いので、レンズを交換しても
見える画像はいつも同じ範囲(画角)だ)
小窓には視度補正が一応ついている、なお、これを覗きながら
では露出計が見えないのだが、LEDが光っているのは、なんとなく
横目で見える為、小窓を見ながらの露出合わせは可能だ。
露出とピントが合ったら、外付けのビューファインダーを見て
構図を決める。このビューファインダーはレンズの各焦点距離
専用で画角が決まるので、レンズ交換をしたらファインダーも
交換しなければならない、さもなければ「勘」(あるいは
ノーファインダー技法)で撮るかだ。
小窓でのピント距離と、この時点ではズレているかも知れない、
しかし、そういう細かい点は気にしない事だ(汗)
そもそも、レンジ機のほぼ全ての機種は、画面中央部でしか
ピント合わせが出来ない。例えMFロック技法(構図を変えて
MFをする)をしても、構図を戻したら「コサイン誤差」が
出てしまい、ピント距離が変わる、しかしここもまた、気に
しない事だ(笑) いくらピント精度に優れた本機であっても
被写界深度が浅いレンズの使用や、そうした撮影状況はレンジ機
では作り出してはならない(そういう撮影は現代のミラーレス機
で行うべきである)
Clik here to view.

ある為、構図がずれてしまう。これを防ぐ為、ファインダー内
には、視差(パララックス)の補正マークがある、しかし、
撮影距離に連動した正確なものでは無いので、ここもあくまで
勘で構図を決めるしか無い。
構図が決まればシャッターをレリーズする、なお、もたもたと
時間がかかるので、太陽が翳ったりして、露出値が変わる事も
あるだろう、そういう場合は露出値設定を、絞り値または
シャッター速度の変更でやり直しだ。
シャッターを切って撮影が終わると、フィルム巻上げだ、
本機の使用形態では、通常の巻上げレバーを使うか、又は
ボディ下部のグリップを握って、トリガーワインダーを用いて
レバーを引いて、一気に巻き上げる。
(これがなかなか気持ち良い操作だ)
以降、写真を1枚撮るたびに、この操作の繰り返しだ。
「なんという面倒臭い操作が必要なカメラだ!」
と言う意見も勿論あるだろう、それは当然だ、本機BESSA-Tは、
「この面倒臭さを自虐的に楽しむ為のカメラである」と
言っても過言では無い。
Clik here to view.

発売されていた、どんなビギナーでも、シャッターを半押し
すればピントも露出も合って、簡単に写真が撮れてしまう。
けど、本機BESSA-Tは、ビギナーでは絶対に使う事が出来ない。
面倒臭いのは確かだが、選ばれた中上級者だけが、写真を撮る
事ができる、極めて専門的なカメラなのだ。
そして、写真撮影の原理がわかっていれば、意外にスピーディ
に撮れるカメラだ。たとえば広角レンズをパンフォーカスに
設定しておけば、ピントを合わせる必要はほとんど無い、
合焦時間=ゼロ秒は、どんな高性能のAF一眼レフも及ばない。
露出もネガフィルムであれば、勘で決めれば十分だ、
一応ちゃんとしたTTL露出計が入っているので、自分で決めた
値が間違っていたら、すぐわかる。ちなみに機械式シャッター
カメラなので、電池が無くても撮影が可能だ。
また、トリガーワインダーを駆使すれば、秒2コマから秒3コマ
位は撮影する事ができてしまう。初級一眼レフの電動ワインダー
よりも、むしろ速いかも知れない。
BESSA-Tを格好良く使おうとするなら、上記の3点を守る事だ、
びっくりする程、素早く写真が撮れる。最高性能の旗艦機を
持ち出してくる初級マニアの鼻をあかすには最適だ(笑)
彼らがモタモタと高級機の撮影準備をしている間に、本機
であれば、およそ1秒以内に「抜き撃ち」撮影が可能だ。
条件を整えれば、カメラの設定は殆ど不要であるから、
熟練すれば、ゴルゴ13や、次元大介、「シティーハンター」
の冴羽、「シェーン」のアラン・ラッド、それから、
「ドラえもん」の野比のび太(笑)並みのコンマ何秒という
「早撃ちスナップショット」も可能となるだろう。
なお、基本的に「撮影技能」(スキル)と、撮影準備時間
は反比例する。つまり、上級者になるほど、速やかに撮影
を行える。どんな高級カメラを持っていたとしても、構えて
から撮る迄、何十秒も、下手をすれば1分以上もかかって
いたら完全な超ビギナーである事がまるわかりだ。
現代機を使う場合でも、構えてから撮るまでは3秒以内が
とりあえず上級レベルとしての目標値だろう。
Clik here to view.

COLOR-SKOPAR 50mm/f2.5は、コシナ・フォクトレンダー
初期のL(39)マウント版レンズだ。
初期と言う物の、2002年の発売なので、正確に言えば、
本機BESSA-Tの翌年の製品だ。
最短撮影距離は75cm弱である。本機本機BESSA-Tでは、仕様上
では0.9mからの距離計連動範囲となっているが、それを超えて
なんとか使える。
真鍮製鏡筒(鏡胴)により、非常に高級感が高く、小型レンズ
でありながら、ずっしりと重い。
「スコパー」は元々は1926年にテッサー型(3群4枚)で
発明されたレンズだが、本レンズは6群7枚と本格的な構成だ。
開放F値を暗めに抑えた設計で、極めて良好な描写力を持つ。
レンジ機で使用する際は、ファインダー像が見れないので
そのあたりは全くわからないが、高精細なEVFを持つ現代の
ミラーレス機に装着すると、EVF越しであってもクリアな映像が
感じられ、いわゆる「良く写る空気感を持つ」レンズである。
(この感覚を言葉で説明する事は難しい)
ボケ質破綻が僅かに出る場合があるが、ミラーレス機で使う
のであればボケ質を確認しながら、絞り調整、撮影距離調整、
デジタルズームによる構図の微調整を含めた、高度なボケ質
破綻の回避技法が使える。なお、レンジ機では構造原理上、
こうした回避技法の利用は不可能である。
で、一眼レフやミラーレス用の50mm標準レンズとして考えると、
最短撮影距離75cmは低性能である。このあたりがレンジ機用
レンズ全てでの不満に繋がる。距離計連動の制約があり
たとえ広角レンズでも70cmないし90cmが最短撮影距離と
なる訳だ、これでは現代的な撮影技法には全く適さない為、
近年のL/Mマウント→ミラーレス機用マウントアダプターでは
ヘリコイドを内蔵し、最短撮影距離を短縮できるものもあるが、
一般に、通常アダプターよりもかなり高価になる。
また、ヘリコイドを繰り出すと無限遠撮影が不能となるのと、
ヘリコイド回転角が大きい場合が多く、迅速なピント操作性に、
重大な制約が出る。
後、このレンズには、フォーカス用レバー(突起)が
ついている。BESSA-Tでオプションの下部(ボトム)グリップ
を使う場合は、このフォーカスレバーを左人差し指の側面に
引っ掛けるように使うと、フォーカシングが楽に行える。
なお、ミラーレス機でこのレンズを使用する場合には、この
レバーを親指と人差し指で摘むようにするのが使い易いのだが、
その際、右手のみでカメラをホールド(維持)できるような
重量と形状のミラーレス機で無いと苦しいであろう。
このレンズの発売時価格は、シルバー版で48,600円だった。
Clik here to view.

数値スペックは意味が無いカメラだ、最小限にとどめておこう。
BESSA-T(2001年)
距離計連動型35mmフォーカルプレーンシャッター式カメラ
最高シャッター速度:1/2000秒
シャッターダイヤル:1秒~1/2000秒,Bulb
フラッシュ:非内蔵 X接点1/125秒
ファインダー:無し(外付け)
距離計連動範囲:0.9m~∞
距離計像倍率:1.5倍(視度補正機能付き)
使用可能レンズ:フォクトレンダーVMマウント
巻き上げ角:不明、分割巻上げ可、トリガーワインダー装着可
露出計:TTL型三点合致LED方式
露出計電源:SR44/LR44 2個使用
ISO感度:手動 ISO25~1600(1/3段ステップ) DXコード非対応
本体重量:385g(電池除く)
発売時定価:55,000円(税抜き)
----
ここでシミュレーター機のSONY α7の使用をやめる。
Clik here to view.

画角は狭くなるが、軽快さが出て格好も良くなる。
加えて、撮影倍率の不満が軽減し、フォーカスレバーの
操作も快適だ。
Clik here to view.

ここも書くべきかどうか、微妙な所だ。
長所短所は、一眼レフ同士などであれば、比較的容易だが、
本機のような唯一無二のマニアックな機体で、それをどう
評価すれば良いのであろうか?
まあ、あえて言えば、基線長が長く、倍率も1.5倍ある
有効基線長は53.7mmという資料もあり、他のレンジ機より
ダントツに長い。
すなわち、レンジファインダー機の弱点である「望遠レンズを
使った際にピントが合い難くなる」と言う点を、本機BESSA-T
では解消している事になる。噂によるとBESSA-Tの「T」は、
「テレ」すなわち「望遠」という意味だ、という説もある。
(しかし、「だからどうした?」という気もする。
カメラの弱点を助長するような使い方をする筈も無く、
望遠が必要であったら、一眼レフか、または現代であれば
ミラーレス機を持ち出せば済む話なのだ・・
カメラとレンズによる「システム」は、最大効率を得る
為の組み合わせを模索するものだ。両者の長所を活かせず
逆に欠点を助長するようなシステムを組んでしまうようでは
ビギナーでしか無い、という事となる)
それと「BESSA」の方の意味だが、独フォクトレンダー社に
おいて、中判カメラの名称に使われていた物が由来な模様だ。
(その単語の意味までは、調べていないので不明だ・・)
本機の最大の長所は、その「マニアックさ」であろうか。
でもこれも、人によっては「こんな面倒でややこしいカメラ
なんて使えるか!」と、まったく逆の印象となる事もあろう。
それと、AFやAEに慣れた(銀塩でもデジタル機でも)初級層
では絶対に使い方がわからないカメラである、それ故に
「どうだ、このカメラで写せるか?」という意地悪な
クイズを出す事もできるという、捻くれた楽しみもある。
・・いや、意地悪ではなく、写真撮影の基本を理解する為の
「教材」にする事もできるカメラであるかも知れない。
けどまあ、なんとも長所が見つけ難い、不思議なカメラである。
Clik here to view.

BESSAシリーズのベースとなった機体はOM2000等のコシナOEM
一眼レフの場合と同じ、その昔の「コシナCT-1」系一眼である。
これには勿論ミラーがあったので、BESSAシリーズ開発の際、
ミラーBOXを取り除いた。で、そのままではフィルムが感光して
しまうので、二重露光防止シャッター構造とした模様だ。
まあ、それはそれで良いのであるが、構成部品(シャッター等)
の品質が、元々低価格機であったため、どうにも、感触性能に
劣ってしまう。
シャッター音、シャッターフィール、巻き上げ感などは、
旧来のOEM一眼レフタイプと同様に、Bクラスでしか無い。
だが、ミラーBOXを取り除いた事で、CT-1系の弱点であった
「ミラーショックの大きさ」が見事に解消されている。
それと、巻き上げ感の問題は本機BESSA-Tでは、マニアッックな
トリガーワインダーを使用しているため、むしろ気持ちが良い。
(ラチェットのキリキリと言う音が、精密感があって最高だ)
他の弱点だが、良く分からない。比較の対象が無いのだ・・
結局「使いにくさ」以外、他の弱点が見つけ難いカメラと
なっている。
なお、レンジ機自身の構造的問題点については不問とする、
それを書き出すと長くなるし、本機のような特殊機でその事を
言い出すのは無粋だとも思う。
客観的には長所も短所も無く、あくまで主観的に判断するべき
カメラであろう。そう、これぞまさしく「趣味の時代」の
カメラの典型的な特徴の1つでもあるように思える。
カタログスペックとか、他機との比較など、どうでも良いのだ。
Clik here to view.

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)
----
Voigtlander BESSA-T (2001年)
【基本・付加性能】★★
【操作性・操作系】★
【ファインダー 】★★★☆(連動距離計として評価)
【感触性能全般 】★★☆
【質感・高級感 】★★★
【マニアック度 】★★★★★
【エンジョイ度 】★★★★
【購入時コスパ 】★★★☆ (中古購入価格:26,000円)
【完成度(当時)】★★★
【歴史的価値 】★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】3.1点
意外な事に標準値3点を上回った、不思議な評価傾向である。
基本性能は低く、操作性も悪く、感触性能もイマイチだ、
写真を撮る上ではどうしようも無く不便で面倒で出来の悪い
カメラなのに、何故か使っていて、とても楽しい。
マニアック度満載であり、デジタル時代に入ってからも
マニアの集まりなどの際に、たまに持ち出した事もあった。
実用性能は評価不能だ、面白いと思う人は使えば良いし
こんな不便なカメラは嫌だと思えば、使わなければ良い。
使う側(ユーザー)の方向性、嗜好性、コンセプトなどに
極めて大きく影響されるカメラであろう。
勿論現代のビギナーには全く推奨できない、ただ本機は最初から
基本性能が低いカメラであり、現代の視点で見ても、これ以上
性能が(相対的に)古くなる事は無いし、そもそも性能を見て
買うかどうかを決めるようなカメラでも無い、
まあ、欲しければ買うしか無いし、全く関係無い世界だと
思えば、無視して忘れておけば良い、ただそれだけだ。
次回記事では、引き続き第四世代の銀塩カメラを紹介する。