本シリーズは、所有しているミラーレス機の本体の詳細を
世代別に紹介して行く記事だ。
今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代の定義は第一回
記事参照)のFUJIFILM X-T1(2014年)を紹介しよう。
![c0032138_17050318.jpg]()
(中古購入価格 112,000円)
(ミラーレス・マニアックス第17回、第30回、名玉編第3回
ハイコスパ第21回、アポダイゼーション・グランドスラム等
で紹介)を使用する。
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進める。
![c0032138_17050332.jpg]()
シルバー・エディションという特別塗装を施したバージョンで、
ノーマル版のX-T1から9ヶ月後の2014年11月に発売された
モデルである。
ノーマルのX-T1との違いは、塗装の他、ストラップ等の付属品が
高級なバージョンになっている事くらいだ。発売時には、最新の
ファームウェアを搭載していた事でノーマル機との差別化を
図ったのだが、そのファームアップはノーマル機でも行う事が
出来たし、その後のさらなるファームアップで両者同等となり、
現時点での実質的な両者の差異は、外観くらいでしか無い。
![c0032138_17050340.jpg]()
FUJIFILM X-E1が、FUJI最初のミラーレス機であった事等を
理由として完成度が低く、実使用上に多大な問題があり、
何らかの後継機でそれを代替する必要があった為だ。
なお、X-E1については持論の減価償却のルール(この時代の
安価なミラーレス機では1枚2円の法則)をクリアしていた。
ちなみに旧機種は、私の場合処分する事はなく、予備機として
使用を続ける事としている。
そのX-E1の問題点だが、AF/MF性能と操作系が大きな2つの
課題であった。
本機X-T1購入時に、それらをチェックしたのだが、まず、
AF性能は、像面位相差AFを新たに搭載した事で、完璧とは
言えないまでも、X-E1から改善が図られている。
![c0032138_17045465.jpg]()
であるXF 56mm/f1.2APD(2014年、本記事で使用)を使う
という、ただその1点であったのだが、レンズ側のAF性能にも
課題が多い同レンズを、本機X-T1の新型AFでカバーできるか
どうか?については購入前には調べようがなかった。
まあ、その点は本記事で検証していく事としよう。
![c0032138_17052140.jpg]()
依然使い難さが残っている。この点に関してはFUJIFILM社自身に
さほどカメラ開発のノウハウが蓄積されていないであろう事が
原因と思われる(FUJIのカメラ開発の歴史については第6回
記事を参照)
本機X-T1の操作系が不十分である事は購入前から覚悟の上だが、
その代わりX-T1には多数のアナログダイヤルが搭載されている。
これらによる「操作性」については、悪く無いだろう事が予想
できた。
なお、「操作系」と「操作性」を区別している事は、本ブログの
過去の様々な記事でも書いてきた通りだ。
「操作系」は、デジタル写真を撮る上で、必要となる様々な
カメラ設定が効率的に(無駄が無く、素早く)出来るかどうかの
要素であり、これが優秀なカメラは、他社機を含めて見渡しても、
さほど多くは無い。
![c0032138_17041148.jpg]()
3つのアナログダイヤルと、2つのアナログレバー(これらは
有限回転式)と、2つのデジタルダイヤル(無限回転式)による
アナログライク(似ている)な「操作性」のコンセプトだ。
アナログダイヤルとデジタルダイヤルの長所短所については、
本シリーズ第6回のX-E1の記事、および「匠の写真用語辞典
第4回記事」でも詳しく書いてあるので今回は省略するが、
すなわち、どちらも一長一短あって、どの設定操作に
それらを割り振るかで全体の操作系設計の優劣が出てくる。
![c0032138_17043814.jpg]()
アナログダイヤル1:ISO感度
ISO感度が常時直接変更できる機能を持つデジタルカメラは
極めて少ない、例えばNIKON Df、RICOH GXR、SONY NEX/α
PENTAX KP等、および、コントロールリング等にISO変更を
アサイン可能なFUJIFILM XQ1等のコンパクト機であるが、
いずれにしても数える程しかない。
そういう点では、本機X-T1(X-T2以降も)は希少なカメラだ。
ただし問題がある。ISO6400の上は、HI1,HI2となって
いるのだが、ここにはISO12800,25600,51200の3つの内
いずれか2つしかアサインできない。
ISOいくつをアサインしたかは、いちいち覚えておけない。
(その操作をすれば、モニターに表示は出る)
まあ、HI3を儲けたら済んだ話なのであるが、使用部品
の接点数が足りなかったのであろう。(X-T2/X-T3では、
さらに設定可能感度が1つ減った)
ただまあ、旧機種X-E1ではISO変更ボタンが無い(忘れた?)
という、非常にお粗末な仕様であったので、それに比べたら
進歩している。
ISOをアナログダイヤルに常設した事で、メニューからの
ISO変更は、両者に矛盾が生じる為できない。
しかし、軍艦部(カメラ上部の事)の左側にあるダイヤルは、
左手でも右手でも廻し難いという課題があり、頻繁にISO感度
を変えながら撮影する、というスタイルには適さない。
なお、この「頻繁に変更できない」が、アナログ操作子の
弱点であり、フィルム時代は、こういうダイヤル操作子でも
まあよかったのだが(のんびり撮っても良い)現代の撮影
技法には適していない点もある(スピーディで無い)
また、このダイヤルにはロック機構があって廻し難い事は
大きな欠点である(注:X-T2以降では、このロック機構の
ON/OFFが切り替えられるようになった、これは良い改良点だ)
![c0032138_17052194.jpg]()
シャッター速度を手動で設定する、という撮影スタイルは
被写体状況が極めて限られている為、あまり用途の無い
ダイヤルである。
絞り環が有るRレンズで、A位置を持ち、レンズ側のA位置と
組み合わせて使う事で「PSAMダイヤル」を廃する事ができる
という点は長所であるが、本機が最初という訳ではなく、
古くはMINOLTA XD(1977)やMAMIYA ZE-X(1981),
PENTAX MZ-5/3シリーズ(1995~1997)や、本機以前の
FUJIのミラーレス機でも採用されていた。
なお、シャッター速度を任意に変更してしまった際に
AUTO ISOでの感度が、設定した絞り値とシャッター速度に
できるだけ追従してくれるように動いたら、このダイヤルには
少し意味が出てくるのであるが、FUJIFILMの機体に、その機能
は無く、NIKONやPENTAX,SONY等の一部のメーカーのカメラのみ
でしかISO追従は実現されていない。
それと、1段刻みは精度不足であり、NIKON Df(2013)のように
デジタルダイヤルで1/3段の微調整を行える機能は無い。
![c0032138_17041180.jpg]()
ボディ側の機能では無いのだが、Xマウント用高級レンズには
絞り環が存在している物が殆どなので(注:R型番のもの)
上記シャッターダイヤルとの組み合わせでアナログライクな
露出操作性が実現する。
ただし、レンズ側の絞り値の変化ステップは、装着レンズの
仕様に依存する。高級レンズは恐らく殆どが1/3段ステップに
なっていると思われ、本記事で使用のXF56/1.2R APDも1/3段だ。
しかし、レンズ側絞り値が1/3段刻みで変化したとしても
例えば上記シャッター速度ダイヤルは1段刻みでしか変化しない、
また、AUTO ISOあるいは手動ISOも1段刻みなので、レンズ側で
細かく調整した場合において、M露出モードでは、ぴったりの
適正露出値が得られ無い場合が多々ある。
これもアナログ操作子(操作性)の弱点であると言える。
すなわち、あまり精密な設定が出来ないのだ。
(注:NIKON Dfでは、シャッターダイヤルは1段刻みだが
後部電子ダイヤルで1/3段ステップの微調整が出来る)
![c0032138_17052228.jpg]()
ここも1/3段ステップ固定である、X-E1の記事でも書いたが、
不用意に動いてしまう事が良くあるので、モニター/EVFの
露出補正インジケーターには常に注意を払う必要がある。
なお、1/2段ステップに変更する事はできない。
(ミノルタα-7,KONICA MINOLTA α-7 Digital,CONTAX N1
の3機種のみ1/2段、1/3段切り替え式のアナログダイヤルが
付いていた)
アナログダイヤルでの切り替えステップ精度不足を補う為か、
本機X-T1では、多彩なブラケットモードが搭載されている。
例えば、露出(AE)ブラケットは1/3.2/3,1段刻みが出来る。
その他、ISOブラケット、フィルムシミュレーションブラケット、
ホワイトバランスブラケットも可能だが、同時にはどれか1つ
しか選択できない。
また、露出補正ダイヤルは、露出(AE)ブラケットにアドオン
される、例えば、露出補正+2として、±1段のブラケットを
行うと、+1,+2,+3の3枚の写真が連続して撮れる。
(注:連写モードにする必要は無く、1回のレリーズ操作で
3枚の写真が連続して撮れる、この仕様は良し悪しがある)
しかし、露出補正+ブラケットが、どの値に効いているかは
わからない。他社機では、露出補正インジケーター上に
ブラケットで設定された複数の露出値が表示される場合が
多いのに、本機は、そのあたりに対する操作系配慮が無い。
![c0032138_17043827.jpg]()
連写、ブラケット、アドバンスドフィルター(エフェクト)
パノラマ、を切り替える事ができる。
ただ、これらのモードのアイコンはモニター内では小さくて
見え難く、アナログレバーを意図せず動かしてしまった際に、
分かり難い。
それから「連写+エフェクト」が出来ない、というのは、
このレバーで、それを変更する理由になっていると思うのだが、
そもそも連写でエフェクトが使えないという制限が問題だ。
本機にはデジタルズーム機能はない(注:それもまた問題だ)が
それ(超解像)があるFUJIのコンパクト機のX-S1やXQ1では
連写モードとすると、デジタルズームが効かなくなり、
何故それが出来ないのか?が疑問であると同時に、カメラ操作中に
機能が働かない原因がわからず、慌ててしまう場合もある。
これらは連写モード時でも、エフェクトや超解像が効くように
改善すれば良いだけの話ではなかろうか?
そうすれば、ドライブモードレバー上にアドバンスドフィルター
機能がある、という「操作系上の欠点」も改善できる。
エフェクトは掛けたい時にすぐ掛けられる状態になっている
必要がある、これはまあ、旧機種X-E1ではエフェクト機能が
無く、それ以降に搭載された新機能であるので、そのあたりの
必然性が設計側でも良く分かっていないのだと思われる。
要は、操作系の設計とは、設計者が写真を撮る事に精通して
いない限り、使い易い設計は出来ないのだ。機能を、ただ
「追加しました」では不十分である事が殆どだ。
![c0032138_17043837.jpg]()
この機能も上記ドライブモードと同様に、設定を変えた際での
アイコンが小さく見え難い。変えたつもりが無くても、不用意に
動かしてしまう事もある訳だ。
なお、例えばメニューからでも、これらの機能を変更できる
ようにしたとする、この場合、アナログレバーの設定と
メニューからの操作に矛盾が生じるので、そういうメニューを
追加することが出来ず、必ずレバーやダイヤルで操作しなければ
ならない、時にそれは、カメラの構えを解く必要があり不合理だ。
これがアナログ操作子の弱点となる。
なお、音響や電子楽器の世界では、アナログのレバー(操作子)
の設定を記憶できる機能が求められた1980~1990年代には、
記憶した設定値と現在のレバー等の値が異なる場合、モーター
動力を用いて、自動的に記憶値までレバーを動かす装置が
作られた事がある(デジタルミキサーでのモーターフェーダー等)
カメラでも、設定値をメニューから変えたり記憶値を呼び出した
際に、アナログ・ダイヤルやレバーがその値まで自動的に動いて
くれれば面白いが、まあ、カメラのような小型機械ではそうした
大がかりな仕掛けを入れる事は無理であろう。
なお、その後の電子楽器では有限回転式アナログダイヤル等の
値と、記憶値を呼び出した状態との指標の差異の矛盾を容認し、
再度そのアナログダイヤル等に触れた場合のみ、新規の設定値と
する方式が考え出された、これは合理的な操作系である。
電源OFF時や再度起動した際に若干の矛盾も出てはくるが、
楽器では音色等のプリセット群で、そこを解決している。
ここはカメラでも検討の余地がある操作系思想だ。
電子楽器はカメラよりも15年も早くデジタル化されている。
他の市場分野での優れた発想は大いに参考にするべきであろう。
写真機材において、「前機種を改良する事」しか考えていない
という企画開発スタイルは、あまり褒められたものでは無い。
近年のカメラが皆、そうなってしまったのは残念な限りだ。
新しい発想を入れて行かない限り、良い製品は出来ないのだ。
![c0032138_17052187.jpg]()
これは無限回転式のダイヤルだ、前後2つあるが、絞り値と
シャッター速度にしかアサインできない物足りない仕様だ。
(注:R型番では無い、絞り環の無い普及レンズへの対応の
意味があるのだろうが、そう固定するのは良く無いと思う)
これらのデジタルダイヤルを、例えばホワイトバランスや
連写速度設定(注:後者を実用化した機種は存在していない)
等の任意の機能にアサインできたならば、相当に使い易い
カメラとなっていたはずなのに、残念な仕様である。
絞りとシャッター速度はそれぞれレンズと本体に専用の操作子
があるため、前後ダイヤルは基本的には全く用途が無いのだが、
絞りとシャッターの両者をA位置としたプログラム露出モード時
においてのみ、これら前後ダイヤルでプログラムシフト操作が
可能になる、これはPENTAXにおける「ハイパープログラム」と
類似の操作系となるので、まあマニアックではあるが、実際
にはプログラムシフトは、1ダイヤルだけで実現できる機能で
ある為、2つのダイヤルをこの目的に使うのは勿体無い。
(注:R型番で無いFUJIのレンズでは、絞り環を備えていない為
その際は、このダイヤルを使用する意味が出てくる)
加えて、プログラムシフト動作時は、誤操作防止の意味からか、
最初のダイヤル回転では、すぐにそれは動作せず、2~3回
廻して、初めてプログラムシフトが効くようになる。
これは少々不要な「安全対策」であり、即時動いた方が良い
であろう(しかし、ロック機構があるよりだいぶマシだ)
まあ、X-T1の用途やユーザー層を考えると、絞り環のある
R型レンズでは、前後ダイヤルで絞りやシャッター速度を
調整する事はまず無いであろう。
![c0032138_17052172.jpg]()
これも上記前ダイヤルと同じで、殆ど用途が無い。
ただ、「Qメニュー」という一種のコントロールパネル機能を
表示して、設定値の一覧表をGUI的に操作する際には、設定
項目の上下移動を(2次元操作子とも言える)十字キーで変更し、
設定値の変更を、後ダイヤル(注:前ダイヤルでも可能)で
操作する。
慣れれば右手親指で十字キーを操作し、右手中指で前ダイヤル
を操作して設定変更するのが最も効率的だが、カメラをホールド
するのが難しく、少々やりにくい。
なお、絞り環つきRレンズを主体とした使用法においては、
この目的のみに前後ダイヤルを使うのは、少々馬鹿馬鹿しい。
操作系的に言えば(ボタンを押す手数は増えるが)十字キー
中央のOK(MENU)ボタンを押してから設定値を変更する方が、
パソコン等におけるマウス等を用いた一般的GUI操作系と概念が
共通化出来てわかりやすいと思う。
前後ダイヤルの用途が殆ど無いので、このような仕様となって
いるのかも知れないが、使いやすさを優先するべきである事は
言うまでもなく、使い道の無いダイヤルは無い方がマシだと思う。
(この思想から、本機の後続使用機をX-T2系とする事はやめて、
ダイヤルが減ったX-T10としている。後日紹介予定)
例えば、本機X-T1の連写は速いので、このダイヤルで連写中の
連写速度設定が可能であれば、かなり使い易いだろうが、
残念ながらそういう操作が可能な機種は存在しない模様だ。
![c0032138_17043871.jpg]()
程に使い易いものでは無いが、これに加えて十字キーの上下
左右の全てをFn(ファンクション)にアサインできるという
機能が付いた。
これは、旧機種X-E1の際に、それが出来ない為、さんざん
「使い難い」と各記事に書いたのであるが、やっと改善された
事になる。ただし他社機のように何処のFnに何の機能をアサイン
したかの一覧を表示する機能は無いので、「押してみるまで
何が入っていたか思い出せない」という、不十分な仕様だ。
他、アナログ操作系(操作子)との矛盾が出るため、これらの
Fnに設定するべき機能はあまり無く、せっかく、合計7つもの
Fnが出来たのにもかかわわず、有効な操作系にカスタマイズ
する事ができない。
つまりは「なんだか良くわからない使い難いカメラ」にしか
ならない訳であり、操作系の設計コンセプトが練れていない
事が、ここでもまた問題となっている。
![c0032138_17053703.jpg]()
メモリーすらなく、どういう設計方針なのか理解に苦しむ。
ちなみに、撮影メニューと設定メニューは縦にカスケードに
並んでいるが、設定メニューに送るには、毎回、撮影メニューを
全て経由しなくてはならない。ここの操作系は好ましく無い。
(注1:逆廻りは可能だが、煩雑である事は変わらない。
注2:X-T2以降では、階層構造メニューになっている。)
という事で、本機X-T1や、そのアナログライクな外観や仕様から
類推できる程には使い易いカメラではなく、あくまで銀塩一眼
レフ的な機構のみが操作性コンセプトの長所であり、それすらも
また、現代的なデジタル撮影のスタイルに必要な操作系要素と
イコールでは無いので、使い難さを感じてしまう。
ただまあ、ここからは個人的な見解だが・・
「アナログ操作系は、格好良い」という点は言えるかも知れない。
実際に使い易いか否かは別として、沢山のダイヤルが並んでいて
各種の設定が一目瞭然、おまけに、電源を切っている時にすら
その設定を変更する事ができるので、電源ONで、すぐに所望する
絞り値や露出補正値の設定が出来ている点は好ましい。
だが、暗所等においては、手探りだけでダイヤル等の設定は
出来ないので、その場合は電源をONしてからモニター上等で
設定値を確認する必要はあるが・・
![c0032138_17053713.jpg]()
されている、倍率は高く、ピーキング機能の精度もだいぶ向上
している(ただし大口径レンズでは厳しい)
期待した「デジタル・スプリット・イメージ」は、思ったよりも
精度が出ておらず、しかもピーキングと2者択一であったので、
ピーキングを常用する事とした。
まあでも、MF全般の性能が高くなったのは確かだと思う。
他には、問題であったマクロ手動切り替えだが、ファームウェア
のVer 3あたりから、やっとオートマクロ機能が搭載された。
ただ、期待していた割には、精度があまり高くなく、相変わらず
近接撮影でAF精度がかなり落ち込んでしまう。
つまりピント距離が分からない状態では、距離エンコード表を
近接用の物に差し替える事は出来ず、技術的に若干矛盾がある
状態だ。(そもそも、レンズ側の距離エンコード・テーブルを
遠近で二重化している事が仕様設計上の大きな課題だ。
結局のところ、AFシステム設計のノウハウ不足を感じる)
X-E1との組み合わせては壊滅的な低性能しか得られなかった
今回使用のXF56/1.2APDレンズとの組み合わせは、像面位相差
AF機能の新搭載によりX-E1よりはだいぶ改善されたものの、
依然一眼レフ等に比べて、AF速度、精度の低さを感じてしまう。
ただまあ、MF性能すら壊滅的であったX-E1とは異なり、
本機X-T1ではMF性能が若干改善されているので、AFが合わない
際にもMFで対応する事は、まあ可能となった。
![c0032138_17053711.jpg]()
ピーキングが出ず、シャッター半押しでピーキングが停止する。
AFレンズでは、A&MFモードで、半押し状態でピントリングを
廻すとMFとなり、その際にはピーキングが出るが、今度は
シャッター半押しを解除するとピーキングが消えてしまう。
また、アドバンスドフィルター使用時はピーキングが出ない。
これらの動作は、ちょっとややこしく、ピーキングが常時出て
いても良かったように思う。また旧機種X-E1とも微妙に動作が
異なり、仕様の決め方に一貫性が無い。
これは、改善をしたことで、そうなったのか、それとも機種毎に
個別に仕様を決めていて、偶然そうなったのか良くわからない。
私は、FUJIFILMのカメラは銀塩時代から多数使ってはいるが、
機種毎の仕様のばらつきが大きく、操作系などは勿論のこと、
例えばバッテリー1つとっても機種毎にバラバラで互換性が無く
メーカーとしてのトータルの設計思想が殆ど感じられず、あまり
好ましく無いと常々思っていた。その原因は殆どの機種が自社製造
ではなく、他社OEM開発な事も影響していると思われ、設計思想の
一貫性や開発ノウハウの蓄積が難しい状況であるのだろう。
あまりに酷いと思えば、「購入しない」という選択肢も勿論ある
・・というか、それがユーザー側からできる唯一の対抗手段だ。
近年のカメラ市場の低迷から、市場の崩壊を防ぐ必要があり、
新製品については、どのメディアも褒める傾向が強く、メディア
からの情報は一切参考に出来ない状況なので、ユーザー側で
その新製品の真の実力を見抜く事は極めて難しいのであるが、
ビギナー層はともかく、マニアや上級層であれば、質の悪い
カメラを自力で見抜く能力は必要だと思う。
が、カメラの短所ばかりを責めていても、撮影が楽しく無くなって
しまう、どのカメラにも必ず長所があり、それをちゃんと把握して
活かして使うこともまた、ユーザー側に必要とされる能力だし
「それがユーザーの責務だ」とも言えるであろう。
![c0032138_17053794.jpg]()
近年のFUJIFILM社のカメラは、2010年代のXシリーズとなって
から、コンパクト機もミラーレス機も、概ね絵作りが良い。
発色がよく、ローパスレス化で解像感も高い、ただし、被写体に
よっては色が濃すぎると感じたり、輪郭強調されたような画に
なったり、明暗差が薄っぺらく感じたり、モアレが発生して
しまう場合もある。
ただまあ、そのあたりは優秀なフィルムシミュレーション機能や
又は本機から搭載されたアドバンスドフィルター(エフェクト)
機能等を状況に応じて組み合わせ、気になる点を個々に回避する
事は可能だ。
![c0032138_17041181.jpg]()
訳では無い、簡単にあげてみよう。
APS-C型CMOSセンサー、1630万画素
ローパスレス(X-TRANSⅡ)像面位相差AF
ISO感度100~51200(拡張時)
最高シャッター速度1/4000秒(電子シャッター可)
高速連写秒8枚、低速3枚(変更不可)、
高速連写時最大連続撮影47枚(画質、メモリーカードに依存)
AFフレーム49点
EVFは倍率0,77倍、236万ドット
モニターは104万ドット(上下チルトのみ)
フィルムシミュレーション有り、
アドバンスドフィルター(エフェクト)搭載、
ぐるっとパノラマモード
本体重量390g
まあ、全般的に可も無く不可も無い標準的な性能だ、
できれば1/8000秒シャッターを搭載して欲しかったが、
いざとなれば、電子シャッターが1/32000秒まで動作する。
電子シャッターには被写体制限も多いが、F1.2級の大口径
レンズを使っても、シャッター速度オーバーにはならない。
(高速シャッター時に、自動で電子シャッターに切り替わる
機能も入っている)
操作系全般は、あまり褒められた状態では無いが、致命的な
欠点とは言えず、アナログ操作性の分かり易さがむしろ長所に
なりうるであろう。
![c0032138_17043821.jpg]()
本シリーズ第8回記事のNEX-7と同等とみなすこともできるのだが、
その機種であれば3万円を切る中古価格で購入する事ができる。
X-T1購入時はノーマル機であっても5万円前後からの中古相場で
あったので、これが3万円程度まで落ちれば適正価格であろう。
なお、グラファイト仕様機は発売時定価で2万6000円のアップ
中古市場においては、ノーマル機より、およそ1万円高だ。
(注:これらは本機購入時点での2016年頃の話。
現在では中古相場が下落し、買い易い価格帯となっている)
それと、デジタル拡大系機能が一切無い点は大いに不満だ。
その他、内蔵フラッシュが無い(外付けフラッシュ付属)事も
問題点としてあげておく。
また、カメラ本体のみならず、FUJIFILM社の交換レンズ群は
高性能なものは、どれも高価すぎて、コスパが悪く感じる。
高価で数が売れずに、レンズ1本あたりの開発・製造の費用の
償却が大きくなれば、ますます高価となり、悪循環だ。
多数のレンズ群を使用したシステム上でのラインナップが
極めて組み難い事も、FUJIFILM Xシステムの弱点であろう。
![c0032138_17053763.jpg]()
評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★★☆
【描写力・表現力】★★★★
【操作性・操作系】★★★
【アダプター適性】★★
【マニアック度 】★★★★
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★☆ (中古購入価格:68,000円)
【完成度(当時)】★★☆
【仕様老朽化寿命】★★★☆
【歴史的価値 】★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.9点
評価点は、ほぼ平均値。
見た目あるいはカタログ的な仕様は悪くないのだが、実際に
使うと様々な小さい欠点が目立つカメラだ。
価格の高さから上級者・マニア向けの製品ラインナップの位置
付けだが、正直、この全体仕様であれば、上級者やマニアでは
物足りなく感じる事であろう。
全体に趣味性が強い仕様で、瞬発的な性能に欠ける事、加えて
現代的なスピーディな設定による撮影スタイルにも不適切であり、
高級機でありながら、業務用途等に用いるには苦しい。
実際には、銀塩時代からの操作性等との違和感を感じずに使える
中級クラスの、シニアやベテラン層向けのカメラであると思う。
中古相場の高さは、少々問題なので、もし購入するとしても
さらに年月が過ぎて十分に安価になってからがお勧めだ。
(注:前述のように、現在では結構相場が下がって買い頃だ)
幸いにして後継機X-T2においても、シャッター速度1/8000秒
自在アングルモニター、ダイヤルロック機構のON/OFF可能
メニュー階層構造、あたり以外の大きな改良点は見られず、
そういう点においては、長く使える(=仕様老朽化寿命が
優れている)カメラだと思う。
---
さて、本記事はこのあたりまでで。
次回記事では、引き続き第三世代の機体を紹介する。
世代別に紹介して行く記事だ。
今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代の定義は第一回
記事参照)のFUJIFILM X-T1(2014年)を紹介しよう。

(中古購入価格 112,000円)
(ミラーレス・マニアックス第17回、第30回、名玉編第3回
ハイコスパ第21回、アポダイゼーション・グランドスラム等
で紹介)を使用する。
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進める。

シルバー・エディションという特別塗装を施したバージョンで、
ノーマル版のX-T1から9ヶ月後の2014年11月に発売された
モデルである。
ノーマルのX-T1との違いは、塗装の他、ストラップ等の付属品が
高級なバージョンになっている事くらいだ。発売時には、最新の
ファームウェアを搭載していた事でノーマル機との差別化を
図ったのだが、そのファームアップはノーマル機でも行う事が
出来たし、その後のさらなるファームアップで両者同等となり、
現時点での実質的な両者の差異は、外観くらいでしか無い。

FUJIFILM X-E1が、FUJI最初のミラーレス機であった事等を
理由として完成度が低く、実使用上に多大な問題があり、
何らかの後継機でそれを代替する必要があった為だ。
なお、X-E1については持論の減価償却のルール(この時代の
安価なミラーレス機では1枚2円の法則)をクリアしていた。
ちなみに旧機種は、私の場合処分する事はなく、予備機として
使用を続ける事としている。
そのX-E1の問題点だが、AF/MF性能と操作系が大きな2つの
課題であった。
本機X-T1購入時に、それらをチェックしたのだが、まず、
AF性能は、像面位相差AFを新たに搭載した事で、完璧とは
言えないまでも、X-E1から改善が図られている。

であるXF 56mm/f1.2APD(2014年、本記事で使用)を使う
という、ただその1点であったのだが、レンズ側のAF性能にも
課題が多い同レンズを、本機X-T1の新型AFでカバーできるか
どうか?については購入前には調べようがなかった。
まあ、その点は本記事で検証していく事としよう。

依然使い難さが残っている。この点に関してはFUJIFILM社自身に
さほどカメラ開発のノウハウが蓄積されていないであろう事が
原因と思われる(FUJIのカメラ開発の歴史については第6回
記事を参照)
本機X-T1の操作系が不十分である事は購入前から覚悟の上だが、
その代わりX-T1には多数のアナログダイヤルが搭載されている。
これらによる「操作性」については、悪く無いだろう事が予想
できた。
なお、「操作系」と「操作性」を区別している事は、本ブログの
過去の様々な記事でも書いてきた通りだ。
「操作系」は、デジタル写真を撮る上で、必要となる様々な
カメラ設定が効率的に(無駄が無く、素早く)出来るかどうかの
要素であり、これが優秀なカメラは、他社機を含めて見渡しても、
さほど多くは無い。

3つのアナログダイヤルと、2つのアナログレバー(これらは
有限回転式)と、2つのデジタルダイヤル(無限回転式)による
アナログライク(似ている)な「操作性」のコンセプトだ。
アナログダイヤルとデジタルダイヤルの長所短所については、
本シリーズ第6回のX-E1の記事、および「匠の写真用語辞典
第4回記事」でも詳しく書いてあるので今回は省略するが、
すなわち、どちらも一長一短あって、どの設定操作に
それらを割り振るかで全体の操作系設計の優劣が出てくる。

アナログダイヤル1:ISO感度
ISO感度が常時直接変更できる機能を持つデジタルカメラは
極めて少ない、例えばNIKON Df、RICOH GXR、SONY NEX/α
PENTAX KP等、および、コントロールリング等にISO変更を
アサイン可能なFUJIFILM XQ1等のコンパクト機であるが、
いずれにしても数える程しかない。
そういう点では、本機X-T1(X-T2以降も)は希少なカメラだ。
ただし問題がある。ISO6400の上は、HI1,HI2となって
いるのだが、ここにはISO12800,25600,51200の3つの内
いずれか2つしかアサインできない。
ISOいくつをアサインしたかは、いちいち覚えておけない。
(その操作をすれば、モニターに表示は出る)
まあ、HI3を儲けたら済んだ話なのであるが、使用部品
の接点数が足りなかったのであろう。(X-T2/X-T3では、
さらに設定可能感度が1つ減った)
ただまあ、旧機種X-E1ではISO変更ボタンが無い(忘れた?)
という、非常にお粗末な仕様であったので、それに比べたら
進歩している。
ISOをアナログダイヤルに常設した事で、メニューからの
ISO変更は、両者に矛盾が生じる為できない。
しかし、軍艦部(カメラ上部の事)の左側にあるダイヤルは、
左手でも右手でも廻し難いという課題があり、頻繁にISO感度
を変えながら撮影する、というスタイルには適さない。
なお、この「頻繁に変更できない」が、アナログ操作子の
弱点であり、フィルム時代は、こういうダイヤル操作子でも
まあよかったのだが(のんびり撮っても良い)現代の撮影
技法には適していない点もある(スピーディで無い)
また、このダイヤルにはロック機構があって廻し難い事は
大きな欠点である(注:X-T2以降では、このロック機構の
ON/OFFが切り替えられるようになった、これは良い改良点だ)

シャッター速度を手動で設定する、という撮影スタイルは
被写体状況が極めて限られている為、あまり用途の無い
ダイヤルである。
絞り環が有るRレンズで、A位置を持ち、レンズ側のA位置と
組み合わせて使う事で「PSAMダイヤル」を廃する事ができる
という点は長所であるが、本機が最初という訳ではなく、
古くはMINOLTA XD(1977)やMAMIYA ZE-X(1981),
PENTAX MZ-5/3シリーズ(1995~1997)や、本機以前の
FUJIのミラーレス機でも採用されていた。
なお、シャッター速度を任意に変更してしまった際に
AUTO ISOでの感度が、設定した絞り値とシャッター速度に
できるだけ追従してくれるように動いたら、このダイヤルには
少し意味が出てくるのであるが、FUJIFILMの機体に、その機能
は無く、NIKONやPENTAX,SONY等の一部のメーカーのカメラのみ
でしかISO追従は実現されていない。
それと、1段刻みは精度不足であり、NIKON Df(2013)のように
デジタルダイヤルで1/3段の微調整を行える機能は無い。

ボディ側の機能では無いのだが、Xマウント用高級レンズには
絞り環が存在している物が殆どなので(注:R型番のもの)
上記シャッターダイヤルとの組み合わせでアナログライクな
露出操作性が実現する。
ただし、レンズ側の絞り値の変化ステップは、装着レンズの
仕様に依存する。高級レンズは恐らく殆どが1/3段ステップに
なっていると思われ、本記事で使用のXF56/1.2R APDも1/3段だ。
しかし、レンズ側絞り値が1/3段刻みで変化したとしても
例えば上記シャッター速度ダイヤルは1段刻みでしか変化しない、
また、AUTO ISOあるいは手動ISOも1段刻みなので、レンズ側で
細かく調整した場合において、M露出モードでは、ぴったりの
適正露出値が得られ無い場合が多々ある。
これもアナログ操作子(操作性)の弱点であると言える。
すなわち、あまり精密な設定が出来ないのだ。
(注:NIKON Dfでは、シャッターダイヤルは1段刻みだが
後部電子ダイヤルで1/3段ステップの微調整が出来る)

ここも1/3段ステップ固定である、X-E1の記事でも書いたが、
不用意に動いてしまう事が良くあるので、モニター/EVFの
露出補正インジケーターには常に注意を払う必要がある。
なお、1/2段ステップに変更する事はできない。
(ミノルタα-7,KONICA MINOLTA α-7 Digital,CONTAX N1
の3機種のみ1/2段、1/3段切り替え式のアナログダイヤルが
付いていた)
アナログダイヤルでの切り替えステップ精度不足を補う為か、
本機X-T1では、多彩なブラケットモードが搭載されている。
例えば、露出(AE)ブラケットは1/3.2/3,1段刻みが出来る。
その他、ISOブラケット、フィルムシミュレーションブラケット、
ホワイトバランスブラケットも可能だが、同時にはどれか1つ
しか選択できない。
また、露出補正ダイヤルは、露出(AE)ブラケットにアドオン
される、例えば、露出補正+2として、±1段のブラケットを
行うと、+1,+2,+3の3枚の写真が連続して撮れる。
(注:連写モードにする必要は無く、1回のレリーズ操作で
3枚の写真が連続して撮れる、この仕様は良し悪しがある)
しかし、露出補正+ブラケットが、どの値に効いているかは
わからない。他社機では、露出補正インジケーター上に
ブラケットで設定された複数の露出値が表示される場合が
多いのに、本機は、そのあたりに対する操作系配慮が無い。

連写、ブラケット、アドバンスドフィルター(エフェクト)
パノラマ、を切り替える事ができる。
ただ、これらのモードのアイコンはモニター内では小さくて
見え難く、アナログレバーを意図せず動かしてしまった際に、
分かり難い。
それから「連写+エフェクト」が出来ない、というのは、
このレバーで、それを変更する理由になっていると思うのだが、
そもそも連写でエフェクトが使えないという制限が問題だ。
本機にはデジタルズーム機能はない(注:それもまた問題だ)が
それ(超解像)があるFUJIのコンパクト機のX-S1やXQ1では
連写モードとすると、デジタルズームが効かなくなり、
何故それが出来ないのか?が疑問であると同時に、カメラ操作中に
機能が働かない原因がわからず、慌ててしまう場合もある。
これらは連写モード時でも、エフェクトや超解像が効くように
改善すれば良いだけの話ではなかろうか?
そうすれば、ドライブモードレバー上にアドバンスドフィルター
機能がある、という「操作系上の欠点」も改善できる。
エフェクトは掛けたい時にすぐ掛けられる状態になっている
必要がある、これはまあ、旧機種X-E1ではエフェクト機能が
無く、それ以降に搭載された新機能であるので、そのあたりの
必然性が設計側でも良く分かっていないのだと思われる。
要は、操作系の設計とは、設計者が写真を撮る事に精通して
いない限り、使い易い設計は出来ないのだ。機能を、ただ
「追加しました」では不十分である事が殆どだ。

この機能も上記ドライブモードと同様に、設定を変えた際での
アイコンが小さく見え難い。変えたつもりが無くても、不用意に
動かしてしまう事もある訳だ。
なお、例えばメニューからでも、これらの機能を変更できる
ようにしたとする、この場合、アナログレバーの設定と
メニューからの操作に矛盾が生じるので、そういうメニューを
追加することが出来ず、必ずレバーやダイヤルで操作しなければ
ならない、時にそれは、カメラの構えを解く必要があり不合理だ。
これがアナログ操作子の弱点となる。
なお、音響や電子楽器の世界では、アナログのレバー(操作子)
の設定を記憶できる機能が求められた1980~1990年代には、
記憶した設定値と現在のレバー等の値が異なる場合、モーター
動力を用いて、自動的に記憶値までレバーを動かす装置が
作られた事がある(デジタルミキサーでのモーターフェーダー等)
カメラでも、設定値をメニューから変えたり記憶値を呼び出した
際に、アナログ・ダイヤルやレバーがその値まで自動的に動いて
くれれば面白いが、まあ、カメラのような小型機械ではそうした
大がかりな仕掛けを入れる事は無理であろう。
なお、その後の電子楽器では有限回転式アナログダイヤル等の
値と、記憶値を呼び出した状態との指標の差異の矛盾を容認し、
再度そのアナログダイヤル等に触れた場合のみ、新規の設定値と
する方式が考え出された、これは合理的な操作系である。
電源OFF時や再度起動した際に若干の矛盾も出てはくるが、
楽器では音色等のプリセット群で、そこを解決している。
ここはカメラでも検討の余地がある操作系思想だ。
電子楽器はカメラよりも15年も早くデジタル化されている。
他の市場分野での優れた発想は大いに参考にするべきであろう。
写真機材において、「前機種を改良する事」しか考えていない
という企画開発スタイルは、あまり褒められたものでは無い。
近年のカメラが皆、そうなってしまったのは残念な限りだ。
新しい発想を入れて行かない限り、良い製品は出来ないのだ。

これは無限回転式のダイヤルだ、前後2つあるが、絞り値と
シャッター速度にしかアサインできない物足りない仕様だ。
(注:R型番では無い、絞り環の無い普及レンズへの対応の
意味があるのだろうが、そう固定するのは良く無いと思う)
これらのデジタルダイヤルを、例えばホワイトバランスや
連写速度設定(注:後者を実用化した機種は存在していない)
等の任意の機能にアサインできたならば、相当に使い易い
カメラとなっていたはずなのに、残念な仕様である。
絞りとシャッター速度はそれぞれレンズと本体に専用の操作子
があるため、前後ダイヤルは基本的には全く用途が無いのだが、
絞りとシャッターの両者をA位置としたプログラム露出モード時
においてのみ、これら前後ダイヤルでプログラムシフト操作が
可能になる、これはPENTAXにおける「ハイパープログラム」と
類似の操作系となるので、まあマニアックではあるが、実際
にはプログラムシフトは、1ダイヤルだけで実現できる機能で
ある為、2つのダイヤルをこの目的に使うのは勿体無い。
(注:R型番で無いFUJIのレンズでは、絞り環を備えていない為
その際は、このダイヤルを使用する意味が出てくる)
加えて、プログラムシフト動作時は、誤操作防止の意味からか、
最初のダイヤル回転では、すぐにそれは動作せず、2~3回
廻して、初めてプログラムシフトが効くようになる。
これは少々不要な「安全対策」であり、即時動いた方が良い
であろう(しかし、ロック機構があるよりだいぶマシだ)
まあ、X-T1の用途やユーザー層を考えると、絞り環のある
R型レンズでは、前後ダイヤルで絞りやシャッター速度を
調整する事はまず無いであろう。

これも上記前ダイヤルと同じで、殆ど用途が無い。
ただ、「Qメニュー」という一種のコントロールパネル機能を
表示して、設定値の一覧表をGUI的に操作する際には、設定
項目の上下移動を(2次元操作子とも言える)十字キーで変更し、
設定値の変更を、後ダイヤル(注:前ダイヤルでも可能)で
操作する。
慣れれば右手親指で十字キーを操作し、右手中指で前ダイヤル
を操作して設定変更するのが最も効率的だが、カメラをホールド
するのが難しく、少々やりにくい。
なお、絞り環つきRレンズを主体とした使用法においては、
この目的のみに前後ダイヤルを使うのは、少々馬鹿馬鹿しい。
操作系的に言えば(ボタンを押す手数は増えるが)十字キー
中央のOK(MENU)ボタンを押してから設定値を変更する方が、
パソコン等におけるマウス等を用いた一般的GUI操作系と概念が
共通化出来てわかりやすいと思う。
前後ダイヤルの用途が殆ど無いので、このような仕様となって
いるのかも知れないが、使いやすさを優先するべきである事は
言うまでもなく、使い道の無いダイヤルは無い方がマシだと思う。
(この思想から、本機の後続使用機をX-T2系とする事はやめて、
ダイヤルが減ったX-T10としている。後日紹介予定)
例えば、本機X-T1の連写は速いので、このダイヤルで連写中の
連写速度設定が可能であれば、かなり使い易いだろうが、
残念ながらそういう操作が可能な機種は存在しない模様だ。

程に使い易いものでは無いが、これに加えて十字キーの上下
左右の全てをFn(ファンクション)にアサインできるという
機能が付いた。
これは、旧機種X-E1の際に、それが出来ない為、さんざん
「使い難い」と各記事に書いたのであるが、やっと改善された
事になる。ただし他社機のように何処のFnに何の機能をアサイン
したかの一覧を表示する機能は無いので、「押してみるまで
何が入っていたか思い出せない」という、不十分な仕様だ。
他、アナログ操作系(操作子)との矛盾が出るため、これらの
Fnに設定するべき機能はあまり無く、せっかく、合計7つもの
Fnが出来たのにもかかわわず、有効な操作系にカスタマイズ
する事ができない。
つまりは「なんだか良くわからない使い難いカメラ」にしか
ならない訳であり、操作系の設計コンセプトが練れていない
事が、ここでもまた問題となっている。

メモリーすらなく、どういう設計方針なのか理解に苦しむ。
ちなみに、撮影メニューと設定メニューは縦にカスケードに
並んでいるが、設定メニューに送るには、毎回、撮影メニューを
全て経由しなくてはならない。ここの操作系は好ましく無い。
(注1:逆廻りは可能だが、煩雑である事は変わらない。
注2:X-T2以降では、階層構造メニューになっている。)
という事で、本機X-T1や、そのアナログライクな外観や仕様から
類推できる程には使い易いカメラではなく、あくまで銀塩一眼
レフ的な機構のみが操作性コンセプトの長所であり、それすらも
また、現代的なデジタル撮影のスタイルに必要な操作系要素と
イコールでは無いので、使い難さを感じてしまう。
ただまあ、ここからは個人的な見解だが・・
「アナログ操作系は、格好良い」という点は言えるかも知れない。
実際に使い易いか否かは別として、沢山のダイヤルが並んでいて
各種の設定が一目瞭然、おまけに、電源を切っている時にすら
その設定を変更する事ができるので、電源ONで、すぐに所望する
絞り値や露出補正値の設定が出来ている点は好ましい。
だが、暗所等においては、手探りだけでダイヤル等の設定は
出来ないので、その場合は電源をONしてからモニター上等で
設定値を確認する必要はあるが・・

されている、倍率は高く、ピーキング機能の精度もだいぶ向上
している(ただし大口径レンズでは厳しい)
期待した「デジタル・スプリット・イメージ」は、思ったよりも
精度が出ておらず、しかもピーキングと2者択一であったので、
ピーキングを常用する事とした。
まあでも、MF全般の性能が高くなったのは確かだと思う。
他には、問題であったマクロ手動切り替えだが、ファームウェア
のVer 3あたりから、やっとオートマクロ機能が搭載された。
ただ、期待していた割には、精度があまり高くなく、相変わらず
近接撮影でAF精度がかなり落ち込んでしまう。
つまりピント距離が分からない状態では、距離エンコード表を
近接用の物に差し替える事は出来ず、技術的に若干矛盾がある
状態だ。(そもそも、レンズ側の距離エンコード・テーブルを
遠近で二重化している事が仕様設計上の大きな課題だ。
結局のところ、AFシステム設計のノウハウ不足を感じる)
X-E1との組み合わせては壊滅的な低性能しか得られなかった
今回使用のXF56/1.2APDレンズとの組み合わせは、像面位相差
AF機能の新搭載によりX-E1よりはだいぶ改善されたものの、
依然一眼レフ等に比べて、AF速度、精度の低さを感じてしまう。
ただまあ、MF性能すら壊滅的であったX-E1とは異なり、
本機X-T1ではMF性能が若干改善されているので、AFが合わない
際にもMFで対応する事は、まあ可能となった。

ピーキングが出ず、シャッター半押しでピーキングが停止する。
AFレンズでは、A&MFモードで、半押し状態でピントリングを
廻すとMFとなり、その際にはピーキングが出るが、今度は
シャッター半押しを解除するとピーキングが消えてしまう。
また、アドバンスドフィルター使用時はピーキングが出ない。
これらの動作は、ちょっとややこしく、ピーキングが常時出て
いても良かったように思う。また旧機種X-E1とも微妙に動作が
異なり、仕様の決め方に一貫性が無い。
これは、改善をしたことで、そうなったのか、それとも機種毎に
個別に仕様を決めていて、偶然そうなったのか良くわからない。
私は、FUJIFILMのカメラは銀塩時代から多数使ってはいるが、
機種毎の仕様のばらつきが大きく、操作系などは勿論のこと、
例えばバッテリー1つとっても機種毎にバラバラで互換性が無く
メーカーとしてのトータルの設計思想が殆ど感じられず、あまり
好ましく無いと常々思っていた。その原因は殆どの機種が自社製造
ではなく、他社OEM開発な事も影響していると思われ、設計思想の
一貫性や開発ノウハウの蓄積が難しい状況であるのだろう。
あまりに酷いと思えば、「購入しない」という選択肢も勿論ある
・・というか、それがユーザー側からできる唯一の対抗手段だ。
近年のカメラ市場の低迷から、市場の崩壊を防ぐ必要があり、
新製品については、どのメディアも褒める傾向が強く、メディア
からの情報は一切参考に出来ない状況なので、ユーザー側で
その新製品の真の実力を見抜く事は極めて難しいのであるが、
ビギナー層はともかく、マニアや上級層であれば、質の悪い
カメラを自力で見抜く能力は必要だと思う。
が、カメラの短所ばかりを責めていても、撮影が楽しく無くなって
しまう、どのカメラにも必ず長所があり、それをちゃんと把握して
活かして使うこともまた、ユーザー側に必要とされる能力だし
「それがユーザーの責務だ」とも言えるであろう。

近年のFUJIFILM社のカメラは、2010年代のXシリーズとなって
から、コンパクト機もミラーレス機も、概ね絵作りが良い。
発色がよく、ローパスレス化で解像感も高い、ただし、被写体に
よっては色が濃すぎると感じたり、輪郭強調されたような画に
なったり、明暗差が薄っぺらく感じたり、モアレが発生して
しまう場合もある。
ただまあ、そのあたりは優秀なフィルムシミュレーション機能や
又は本機から搭載されたアドバンスドフィルター(エフェクト)
機能等を状況に応じて組み合わせ、気になる点を個々に回避する
事は可能だ。
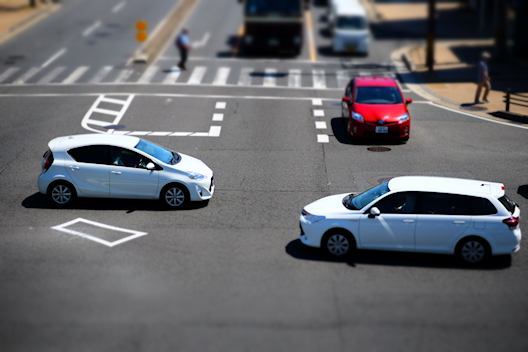
訳では無い、簡単にあげてみよう。
APS-C型CMOSセンサー、1630万画素
ローパスレス(X-TRANSⅡ)像面位相差AF
ISO感度100~51200(拡張時)
最高シャッター速度1/4000秒(電子シャッター可)
高速連写秒8枚、低速3枚(変更不可)、
高速連写時最大連続撮影47枚(画質、メモリーカードに依存)
AFフレーム49点
EVFは倍率0,77倍、236万ドット
モニターは104万ドット(上下チルトのみ)
フィルムシミュレーション有り、
アドバンスドフィルター(エフェクト)搭載、
ぐるっとパノラマモード
本体重量390g
まあ、全般的に可も無く不可も無い標準的な性能だ、
できれば1/8000秒シャッターを搭載して欲しかったが、
いざとなれば、電子シャッターが1/32000秒まで動作する。
電子シャッターには被写体制限も多いが、F1.2級の大口径
レンズを使っても、シャッター速度オーバーにはならない。
(高速シャッター時に、自動で電子シャッターに切り替わる
機能も入っている)
操作系全般は、あまり褒められた状態では無いが、致命的な
欠点とは言えず、アナログ操作性の分かり易さがむしろ長所に
なりうるであろう。

本シリーズ第8回記事のNEX-7と同等とみなすこともできるのだが、
その機種であれば3万円を切る中古価格で購入する事ができる。
X-T1購入時はノーマル機であっても5万円前後からの中古相場で
あったので、これが3万円程度まで落ちれば適正価格であろう。
なお、グラファイト仕様機は発売時定価で2万6000円のアップ
中古市場においては、ノーマル機より、およそ1万円高だ。
(注:これらは本機購入時点での2016年頃の話。
現在では中古相場が下落し、買い易い価格帯となっている)
それと、デジタル拡大系機能が一切無い点は大いに不満だ。
その他、内蔵フラッシュが無い(外付けフラッシュ付属)事も
問題点としてあげておく。
また、カメラ本体のみならず、FUJIFILM社の交換レンズ群は
高性能なものは、どれも高価すぎて、コスパが悪く感じる。
高価で数が売れずに、レンズ1本あたりの開発・製造の費用の
償却が大きくなれば、ますます高価となり、悪循環だ。
多数のレンズ群を使用したシステム上でのラインナップが
極めて組み難い事も、FUJIFILM Xシステムの弱点であろう。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★★☆
【描写力・表現力】★★★★
【操作性・操作系】★★★
【アダプター適性】★★
【マニアック度 】★★★★
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★☆ (中古購入価格:68,000円)
【完成度(当時)】★★☆
【仕様老朽化寿命】★★★☆
【歴史的価値 】★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.9点
評価点は、ほぼ平均値。
見た目あるいはカタログ的な仕様は悪くないのだが、実際に
使うと様々な小さい欠点が目立つカメラだ。
価格の高さから上級者・マニア向けの製品ラインナップの位置
付けだが、正直、この全体仕様であれば、上級者やマニアでは
物足りなく感じる事であろう。
全体に趣味性が強い仕様で、瞬発的な性能に欠ける事、加えて
現代的なスピーディな設定による撮影スタイルにも不適切であり、
高級機でありながら、業務用途等に用いるには苦しい。
実際には、銀塩時代からの操作性等との違和感を感じずに使える
中級クラスの、シニアやベテラン層向けのカメラであると思う。
中古相場の高さは、少々問題なので、もし購入するとしても
さらに年月が過ぎて十分に安価になってからがお勧めだ。
(注:前述のように、現在では結構相場が下がって買い頃だ)
幸いにして後継機X-T2においても、シャッター速度1/8000秒
自在アングルモニター、ダイヤルロック機構のON/OFF可能
メニュー階層構造、あたり以外の大きな改良点は見られず、
そういう点においては、長く使える(=仕様老朽化寿命が
優れている)カメラだと思う。
---
さて、本記事はこのあたりまでで。
次回記事では、引き続き第三世代の機体を紹介する。