所有しているデジタル一眼レフの評価を行うシリーズ記事。
![c0032138_12582401.jpg]()
取り上げる。なお、記事の順番と発売年が1年程前後する
場合があるが、同一メーカーの機種を続けて紹介しない
為であり、他意はない。
装着レンズは2種類用意している。まずは、中国製の
YONGNUO(ヨンヌオ) YN 50mm/f1.8(中古購入価格:
4000円と安価、他記事では未紹介)を使用する。
![c0032138_12582451.jpg]()
色々といわくつきだ。まあでも、それは本記事の内容とは
無関係な為、いずれ他の記事で詳しく解説しよう。
なお、レンズフードは「ハマカク」(hama製角型フード)
を装着している。
このシステムで撮影した写真を交えながら本機EOS 8000D
の特徴について紹介していくが、記事後半では別のレンズ
に交換する。またEOS 8000Dの本体機能であるエフェクト
(クリエィティブフィルター)等は自由に使う事とする。
ただし、本記事の内容は、単純なカメラの性能評価等に
留まらず、現代のカメラ市場や、市場全体における、
本機の位置付け等、全体的かつ多面的な視点での紹介を
主とし、いつもより長目の記事となる。
![c0032138_12582435.jpg]()
初の機体である。
現代における、EOSデジタル一眼レフのラインナップを
独自に整理してみよう。
入門機:EOS Kiss (Digital)(X)シリーズ
普及機:EOS 四桁Dシリーズ(8000D,9000D)
中級機:EOS 二桁Dシリーズ(10D~80D)
上級機:EOS 6Dシリーズ、EOS 7Dシリーズ
高級機:EOS 5Dシリーズ
旗艦機:EOS-1Dシリーズ
・・まあ、カメラ市場縮退の現代においては、これらは
ラインナップの段階が少々細かすぎるような気もする。
つまり、そんなに細かく分けても販売台数が増えるとは
思い難いし、新商品の開発経費も嵩み、製造・流通・在庫
面においても色々と面倒な事であろう・・
![c0032138_12582465.jpg]()
受けていると思われる。特にCANONの場合、銀塩時代の
1993年から続く「Kiss」の系譜は、女性やファミリー層
という新たなユーザー層を新規開拓した重要なシリーズ
ではあるが、その名称からも男性ユーザーには受け入れ
難い要素もあったと思う。(注:国内市場での名称。
米国向けはKissでは無くREBEL、欧州向けは数字型番だ)
そこで男性ユーザー層に向けてのエントリーモデルとして、
上位のEOSフタ桁Dシリーズに相当する2ダイヤル操作系や、
上部液晶等を備えた、中間ランクのEOS四桁Dシリーズを
新設し、付加価値、つまり利益アップを狙ったのであろう。
ちなみに、EOS 8000Dでの主力商品はレンズキットであり、
下位機種のKiss X8iとは、キットレンズの種類を変えて、
その価値の差をわからなくさせてはいるが、発売時には、
およそ3万円以上もの実売価格差があった(結構高い)
また、その結果として上位の中級機の次世代機(EOS 80D
2016年)の価格も連動して押し上げる事が出来るように
なる。まあつまり、意図的に追加されたラインナップ戦略
という訳だ。
![c0032138_12582381.jpg]()
分類である。お互いラインナップに抜けがあると、それを
必要とするピンポイントのターゲット・ユーザーを逃がして
しまうという考え方であろうか? まあ、ユーザーニーズが
多様化している現代では、わからない話では無い。
そして、細かくラインナップ間での仕様を差別化すれば、
縮退した市場でのユーザー層の目線を、上へ上へと、
上位機種の販売に誘導する事もできるようになるだろう。
(=安い機種を買っても性能が低いから、どうせ買うなら
一番性能の高い物が欲しい、と、ユーザー心理を誘導する)
参考の為、以下にNIKON機のラインナップも整理してみる。
入門機:D3000シリーズ
普及機:D5000シリーズ
中級機:D7000シリーズ、D600シリーズ
上級機:D700シリーズ
高級機:D800シリーズ、D500、Df
旗艦機:Dヒトケタシリーズ
なお、勿論ここにはミラーレス機は含まれていないし、
APS-C機かフルサイズかの差異も書いていない、そのような
事は「常識」であるので割愛しよう。
そして、当然であるが、これらは高価格な機種である程
性能や機能が高い。
いや、正確に言えば、機種毎に異なる部品を開発していたら
面倒でやっていられないので、同じ部品を使ったとしても
下位機種では、その性能を制限している(=仕様的差別化)
まあでも、高速連写等を実現する為には、それなりに
パワーのある機構部や高速処理電子部品などが必要と
なるし、センサーサイズや画素数の差もある為、完全に
どの機体も同じクラスの部品を使う、という訳でも無い。
ただ、部品代の差よりも「いくらなら売れるか?」という
市場戦略上の視点で機体価格が決められている事については
ユーザー層は必ず知っておく必要がある。
![c0032138_12584037.jpg]()
の区分が曖昧であるように感じるかも知れない。
ただ、私個人的には、ここには明確な差異があり、まあ
高級機とは、「高付加価値型の高価な製品」という事だ。
定価で言えば25万円以上、中古価格も10万円を下回らない
相場だ(注:年月が経てば中古相場は必ず安価となる)
今時のユーザーが使う市場用語であれば、高付加価値型
商品よりも「プレミアムな商品」と呼ぶのであろう。
たたし、ここからは重要なポイントであるが、高付加価値
とかプレミアムとかは、カメラに限らず、現代の一般市場に
おける商品やサービスでは「実用範囲を超えて無駄に高価で
コスパが極めて悪い」という意味と、ほぼ等価であろう。
私もまあ、上記における「高級機」に分類されるものを
いくつか買ってしまっているのだが、やはり値段が高ければ
高い程、より安価な製品と同様の弱点を持つ場合、その
欠点に対する評価の低下が物凄く厳しくなる。
つまり「値段が高い機種のくせに、これくらいの欠点すら
直っていないのか、ふざけた製品だ!」という厳しい評価と
なり、たいていの場合、これは極めて精神衛生上良く無い。
カメラ等に限らず、つまりまあ、プレミアムな商品は、どの
市場分野においても、そうした付加価値(性能やら、味やら
サービス等)に、何も疑問を感じないビギナー層向けの
商品であり、少なくとも自身が詳しい(精通している)市場
分野では、そういう類の商品に過度な期待を持つのは禁物だ。
(例:高価な食品を食べて「不味い」と感じた事は多いだろう)
ともかく、カメラについては「実用上では上級機まで、それ
以上の高額商品は不用」というのが、近年の私の持論である。
![c0032138_12584083.jpg]()
そういう機体を必要とするか?の購入動機の説明だが・・
まず、本機EOS 8000Dは「かなり小型軽量である」という
大きな特徴を持っている。本体のみ520gは、まあ実用的な
(=入門機等を除いた)一眼レフ中では、トップでは無いが、
勿論上位に入ってくる。
そういう視点では、勿論ミラーレス機の方が小型軽量だ、
本機の半分程度の重さのミラーレス機はいくらでもある。
ただ、ミラーレス機を必要とする状況と、一眼レフを必要
とする状況は異なる。だから両方必要とされるのは、現代
においては当然の話だ。まあ、ミラーレス機が出始めた
10年程前においては、「一眼レフとミラーレス、どちらが
優れていて、どちらが買いか?」みたいな意味の無い比較が
世間では多かったが、両者は構造も特性も用途も全く異なる
訳だから、別のモノを同一の価値観で比較してはならない。
(例:「ラーメンとカレー、どちらが美味しいか?」の
ような、結論が出ない無意味な議論となってしまう)
それから、本機には上級機には無い「エフェクト」
(クリエィティブ・フィルター)が入っている。
ここはむしろ写真における「表現力」の増強という点で
期待が持てる。しかし、ミラーレス機のように撮影時に
エフェクトは使えない。(注:一般的な一眼レフでは
エフェクトは再生時の後掛けとなり、撮影前確認が出来ない
状況だ。ただし、一部にEVF搭載一眼レフやライブビュー・
エフェクトは存在している)
![c0032138_12584018.jpg]()
「市場状況の変化」の理由も大きい。ここからは長い話に
なるが、ここはユーザー層は理解しておくべきポイントだ。
で、一眼レフの範囲で言えば、私の使用しているCANON機
は、近年ではEOS 7D/6D/7D MarkⅡが主力機種であった。
これらは2009年~2014年の発売である。それより古い
時代の機体も何台か所有しているが、もう仕様老朽化寿命
(持論では発売後10年まで)が来ていて実用には厳しい。
上記の主力機種群は「上級機」にカテゴライズされる。
つまり実用上では「最良のコスパを発揮するクラスの機体」
ではあるのだ。ただ、近年のCANON機の、これらのクラスの
製品寿命サイクルは約5年と伸びている。つまり、滅多に
新製品を出さないし、その結果、中古相場もあまり下がらず
発売後5年程で新製品が出て、さらに1~2年を経過しない
限り旧機種の中古相場はあまり下がらない。
すると、手ごろな相場になるまで7年程もかかってしまい、
前述の「仕様老朽化寿命」を、発売後10年とすれば、
もう3年程しか活躍期間が無い事となる。
「ではもっと早く買えば良いではないか?」と思うかも
知れないが、私の場合、新機種の性能・機能や操作系等は
発売時から、ちゃんと調査してあり、その性能や仕様等に
見合う「想定購入価格」を、ある程度決めている。
その自分で決めた価格になるまで中古相場が下がらない限り、
それよりも高価に買ってしまうと、「コスパが悪い」と
見なしてしまう訳だ。
コスパの悪い製品(商品)の購入は、私が最も嫌う事だ、
「それをする位ならば買わない」というポリシーがある。
しかし、2010年代ではカメラ(一眼レフ)市場の縮退の
傾向がとても強く、新製品は高付加価値化で値上げされ、
中古流通も安売りしていたら崩壊してしまうので、これも
ずっと高値相場、と、ユーザー側から見てあまり好ましく
無い状況が続いた。ここで「相場下落待ち」をしてしまうと、
それこそ発売10年を超えた、とんてもなく古い機体しか
買えなくなってしまう。あるいは入門機等ならば、相場の
下落が速いが、それらはさすがに実用範囲以下の性能だ。
だから、自身の機材購入ポリシーを緩和して、若干コストが
高い機材でも、パフォーマンスが高ければ買うように
してきている。結果の「コスト・パフォーマンス」は勿論
低下し、私の評価データベースで標準点(3点)を超える実用
カメラやレンズは、残念ながらもう殆ど存在しない状況だが、
ここはやむを得ない。コスパ点が1点対2点等の、レベルの
低い戦いで機種間の相対的な評価を行うしか無い状態だ。
まあ、一眼レフ市場が縮退してしまったのは、スマホや
ミラーレス機の台頭だとかの理由も勿論あるのだが、
魅力的な新製品が出て来なかったという事も大きな問題だ。
減少した売り上げをカバーする為に、高付加価値という名の
実際には必要としない性能や機能を色々と入れて、その結果
としての値上げが発生しているならば、中上級者やマニアは
もう新機種に興味は持てない。
この結果、中上級者はもとより職業写真家層ですら新機種を
買っておらず、少し古い世代の機種を使い続けている。
だってそれでも十分写真は撮れるし、しかも業務撮影だったら、
高価すぎる新機種を次々と買っていたら収支が確実に赤字と
なり、ビジネス(商売)には成り得ない。
仮に自腹では無く、企業等の経費で買って貰ったとしても、
企業等の全体で見たら、大きな「支出」となってしまう。
(まあ、写真家等にメーカーから貸与する等を行った場合は、
「私もこのカメラを愛用しています」と宣伝させる意味での
市場効果はあるだろう。だが、その事も、例えば有名女優が
化粧品のCMをしているようなもので、ありふれた広告戦略だし、
今時はそういう事情は皆が知っていて、宣伝効果があまり無い)
結局、高価な新製品を買って使っているのは、コスト感覚が
弱かったり、広告宣伝等に過剰に反応しやすいビギナー層
ばかり、という極めて不自然な市場状況となった。
だが、この感覚はデジャビュ(既視感)がある、第一次
中古カメラブームが起こる直前の1990年代中頃の話だ。
この頃、バブルの崩壊、そして阪神淡路大震災等の影響で
市場は大きく冷え込んだ。だが、新製品の銀塩AFカメラは
バブル時代に企画された、華美なスペックを盛り込んだ、
イケイケムードのバブリーなカメラばかりとなっていた。
新規ビギナーユーザー層は、それらのカメラを買ったが
その他の層は、そうした新製品カメラに、まったく興味が
沸かず、銀塩中古カメラや新カテゴリーの高級コンパクトに
興味を持ち、そこから空前の「第一次中古カメラブーム」に
突入したのだ。
このままでは現代においても「中古デジタル一眼レフブーム」
が起こる可能性もある。と言うのも、新製品は高いだけで、
あまり魅力的では無いからだ。
なお、既に別の「ムーブメント」(動向)も起こっている。
具体的には、2018年頃から急速に中国製等の海外製の
安価な交換レンズが非常に多数、市場に流通し始めている。
今回使用のYONGNUO(ヨンヌオ)も、その中の一つである。
これは「高価になりすぎて、コスパが極めて悪い」という
国産交換レンズの新製品の市場戦略上の弱点を突いて、
あえて、この時期に低価格帯市場に参入したのであろう。
(SAMYANG、中一光学、LAOWA等は数年前より市場参入済みだ)
他のマニア層の購買行動は良く知らないが、少なくとも私は
興味深々である。既に、七工匠やMeike等の、こうした最新鋭
海外製レンズを何本か購入しているし、コスパ面では満足して
使っているので、きっと今後も買い続けるであろう。
つまり、高価すぎる国産新鋭レンズには、もう興味が持てず、
「新勢力」に目線が行ってしまっているのだ。この状態もまた、
1990年代の中古カメラブームの際のユーザー心理と、ほぼ
同様である。まあ、これら最新鋭海外レンズについては、
追々、レンズ・マニアックス等の別記事で紹介して行こう。
![c0032138_12584082.jpg]()
である。画素数もAF測距点もISO感度も連写速度も付加機能も
もう2010年代後半では全て性能的に頭打ち状態だ。
だが、メーカー側も無策では無い。一眼レフがもう限界ならば
ミラーレス機に移行すれば、まだそこでは色々と技術革新の
余地がある。そうした市場背景もあって、2018年秋からの、
各社一斉のフルサイズ・ミラーレス機への戦略転換であろう。
・・・しかし、ここもまた「ユーザー不在」の話だ。
またミラーレス機で、一眼レフで今までやってきた事と
同様の「段階的性能追加戦略」をしていくのだろうか?
それは2012年のデジタル一眼レフの「フルサイズ化元年」
から、2018年頃にいたるまで、高速連写や高感度性能を
段階的に搭載していって、だんだんと値上げをしていった
事を、またミラーレス機でやる、という事なのだろう。
(既にSONY α7系ミラーレス機でも、そういう状況があった)
おまけに新鋭ミラーレス機であれば、一眼レフよりも利益率を
高める事ができる、つまりメーカーは良く儲かり、縮退した
カメラ市場を、その戦略で支える事ができる。
勿論、カメラ本体のみならず、新マウント規格への対応
レンズを新たに作って高価に売りたい、という戦略も大きい。
しかし、これでは完全に「消費者の負け」の状況だ・・
ただ、だから良いとか悪いとかでは無い、これがカメラ市場
を維持する為に必須の措置であれば、メーカー側や流通側は、
そうするしか無い。
後は、ユーザー側の価値判断だけだ。新機種を魅力的だと
思えば買えば良いし、コスパが悪いと見なせば、買わないか
または価格が下がった頃に買えば良い。
あるいは、もう見限って、新鋭海外レンズ等で、しばらくの
期間は遊んで、市場の変化を待っておくか、だ。
市場におけるコスト高状態が続けば、必ず市場は自ら適正な
価格帯に自動的に修復される、つまり高すぎて売れなければ、
安価な商品を市場に投入せざるを得なくなるからだ。
現代に限らず、過去のカメラ史においては何度もあった事で
あるし、カメラ以外の市場でも、それは必然の市場原理だ。
![c0032138_12584019.jpg]()
いこう。
すなわち現代の高性能一眼レフは、基本的にどれもコスパが
悪い。でも、旧世代の安価な機種を使い続けていたら、
すぐに、それは古くなってしまう(仕様老朽化寿命が来る)
そんな中で、どのように機材をローテーションしていくかは
非常に難しい判断だ。(注:いつまでも古いカメラを使い
続ける事は出来ず、必ず新機種を追加/代替する必要がある)
これまで私は、その1つの目安として、カメラにおける持論の
「1枚3円の法則」で「元を取る」まで次のカメラを買わない
または「1枚3円をクリアしたら次の機種を買う」という
方針であったが、もう段々と、その持論が守れなくなって
来ている。
機体の価格が上がっていけば、1枚3円をクリアするには
時間がかかる。例えば高級機を中古で15万円で買ったら、
5万枚を撮らなければならない。
連写が効かないフルサイズ機等でそれを実現するには、
とても年月がかかる。
元が取れる頃には、もう「博物館行き」の古いカメラと
なっているだろう(汗)
あるいは高速連写機を買ったとする、例えばEOS 7D MarkⅡ
を中古で9万円で買った場合、3万枚がノルマだが、これを
実用撮影等で使うと3万枚はあっと言う間だ、1~2年程度で
クリアしてしまう。しかし元を取ったと言っても、後継機が
まだ発売されていないのだ。仮に出てきたとしても、とても
高価になっている、これでは旧機種を限界を超えるまで
何十万枚も撮影を続け、酷使するしか無いでは無いか・・
(参考:近年、中古市場に出て来る、やや古い高級・旗艦級の
カメラは、このように業務用途で何十万枚も撮影し続けて酷使
された機体が多い。前述のように、職業写真家層であっても、
高価な新機種に、そう簡単には買い換える事が出来ないからだ)
![c0032138_12585519.jpg]()
せっかくそこに行くのだから、と、Panasonic機では
最も歴史的価値の高いカメラである、世界初のミラーレス機
「DMC-G1」を首から掛けて見学していたのだが・・
展示品の中にDMC-G1が当然あった。たまたま機体色も同じ
青である。専用・特注のガラスのショーケースの中に
大切そうに展示してある、手元と全く同じカメラを見て、
私の感想は、
匠「なんだ・・ まだ発売後10年も経っていないのに、
もう”博物館行き”の扱いかよ・・
こっちはまだG1は現役機としてガンガン使っているのに
過去の遺物扱いとは、こういう市場って正しいのか?」
という感じであった。
「カメラ市場が、もう不条理だ」、数年前から薄々感じて
いた事だが、ここに来て、その思いはとても強くなった。
価格対性能比、つまりコスパもデタラメ、購買層も本来は
腕前に応じて高性能機を使うべきなのに、まるっきりそれが
逆転して、ビギナーが高級機を買い、仕事では普及機を使う。
(今時の新聞記者や企業広報担当者等は、自腹又は経費購入の
一眼レフは、いずれも初級機か、良くて中級機である)
まあ、これでは、これまでの時代のように機材購入ポリシー
を持って、論理的で合理的な購買行動を起こすなど不可能だ。
ならば、こうした不条理な市場に対応する、新しい機材購入
ポリシーを導入するしか無いでは無いか・・
![c0032138_12585514.jpg]()
本機は普及機である、しかも入門機のEOS Kiss X8iと
ほとんど同じ性能の姉妹機だ、つまりまあ一眼レフとしては
最底辺の低性能なカテゴリーの機体だ。
ある意味、高付加価値型商品の対極にある「低付加価値型
カメラ」とも言えるであろう。
(注:このシリーズは型番「8000」からの開始であるが、
これはKiss X8i等と、番号を揃えたという事であろう。
以前、他社では、シリーズ最初の機体を1番機としたが、
他のシリーズ機体が既に6番機とかになっていた為、
「発売が古い機種だ」と勘違いされてしまった前例がある。
ただまあ、CANONにおいても、後継機EOS 9000Dの次は、
いったい、どんな型番にするのであろうか・・? 汗)
で、これまで「こういう機体はビギナーが買うものだ」
と敬遠してきた心理的な要素も、もう「不条理な市場」で
ある以上、そうした先入観念を持つ事は良く無い。
「外に持っていったら格好悪い」と卑屈に思う必要も無い、
世の中の現実的には、高級機を持っているのは、カメラの
正しい構えすらも、おぼつかないビギナー層ばかりだ。
この機体を入手し、厳密に評価する。当然様々な弱点は存在
するだろう、より上位の機種と差別化する為、わざと性能や
機能を落としているからだ(=仕様的差別化)
また、冒頭にも少し書いたように、本機は、CANONでの
ラインナップ全体の価格を押し上げる為に、旧来のランクに
無理やりインサート(挿入)されたクラスであるとも言える。
だが、それらの事はすべて承知の上で、もし、性能面や
機能面での問題点回避の方法が存在するのであれば・・・
もう「上級機や高級機がコスパが悪い」等と、嘆く必要は
なくなるではないか。中古相場が適価に下がって来た頃に、
こうした安価な一眼レフを買ったとしても、十分に実用的に
写真は撮れるだろうからだ。
さて、ここで使用レンズを交換してみよう。
![c0032138_12585516.jpg]()
こちらは、EOS 8000Dの本体の2倍以上も重く、価格も
2倍以上も高価な、本格派の業務用レンズだ。
こういった、これまでの常識的には「絶対に有り得ない」
とも言えるアンバランスなシステムをあえて組んでみて、
もし、これが実用的であれば、もう母艦は何でも良い
(上級機や高級機でなくても良い)という事になるだろう。
![c0032138_12585500.jpg]()
あると評価できるのであれば、他にも、ちょっと気になって
いたNIKON D5000シリーズ等も、購入を躊躇う必要も無い、
PENTAX機だって、Kフタケタ機で十分だろうし・・
(そういう判断で、既にそれらを入手して使っている)
あるいはミラーレス機だって、もうビギナー層向けの安価な
機種で十分だとわかれば、それらを安価に買えばコスパ的
には何の問題も無くなる。(既にそうしつつある)
おまけに、近年のこうした低価格機は、上位機種に吊られて
基本性能が上がっている。だから、もしかすると性能的にも
不満はなく、むしろ、やや古い時代の上級機・高級機よりも、
新鋭機の初級機の方が高性能かも知れないのだ。
(=「下克上」が発生している)
この「新戦略」は、おかしくなった(と見ている)カメラ
市場への個人的な対抗策である。もうビギナー層しか
高級機や旗艦機を買わないならば、そういう機体を使って
いたらむしろ格好悪い。「自分のスキルに自信を持てない
人達が、機材の性能でカバーしようとしている」という
新しい情報分析がもう出てきているし、それがいずれは
市場における「常識」になるかも知れないのだ。
勿論それは不自然な話だ、でも趣味撮影の分野においては、
現実は既にそうなりつつある状況だ。
もし前述の「中古デジタルカメラブーム」が来たら、
その新しい価値感はいっきに表面化して一般化するだろう。
つまり、マニア層や上級層は、古いデジタルカメラを使い
マ「君達初心者には、こういう古くて性能の低いカメラは
使いこなせないでしょう? だから、最新の高性能の
カメラを使っているのだよね? フフフ・・(冷笑)」
という、やや捻くれた価値観が生じる。
![c0032138_12590634.jpg]()
第一次中古カメラブームの際にも起こっていたのだ。
マニア層や上級層は、ビギナーでは絶対に使えないだろう
複雑怪奇な操作を必要とする古いカメラで写真を撮って
いたわけだ。単に「優越感を得たい」と言うよりも、もう
市場全体で、それが「格好良い事」という価値観となり、
露出計すら無い非常に古いNIKON Fを使うのは上級マニアで、
最新旗艦機で誰でも撮れるNIKON F5を使うのは初級マニア層、
という風に暗黙の住み分けが出来ていた。
まあ細かい話は良い。ともかく普及機クラスの低価格機で
何も不満が無く使えるのであれば、これは現代の不条理な
カメラ市場の価値感覚をひっくり返せる「パラダイム・
シフト」(=今まで当然だと思っていた価値感覚が劇的に
変化する事)になり得る。
メーカーや市場側にとっては困った話になるかも知れないが
誰もがそうする筈も無いだろうし、この意味がわからない人は、
わからないなりに、好きに新鋭機を買えば良い訳だ。
それに私からすれば、コスパが良く魅力的な新製品を
出せないのはメーカー側の問題だ、とも解釈している。
黙ってその状況に従うつもりは無い。
現に、過去60年間以上の一眼レフの歴史を全て調べて
いくと、その時代の経済水準に比べて、カメラの価格が
高価すぎる時期が続くと、今度は低価格化の時代が必ず
来ている。高価すぎて売れないカメラをいつまでも作り
続ける訳には行かないから、前述のように「市場」自体が
適正価格のバランス点を求めて推移していくのだ。
(それと、前述のように、ここ数年で中国製等の安価な
交換レンズが、急速に国内市場に浸透してきている。
これは、高価になりすぎた日本製交換レンズの弱点を突いた
市場戦略であり、市場の一部が低価格化にシフトしつつある)
ただしユーザー側全般が、そうした「価値判断」が出来なく
なってしまうと、バブリーなまでに商品価格はどんどんと
高騰していく。そしていつか必ずバブルは弾け、その後の
市場はグチャブチャに混迷してしまう訳だ。
まあ、こういう風に歴史は繰り返していく・・
![c0032138_12590655.jpg]()
まず基本スペックに係わる長所であるが、
事前に想像していた(普及機は性能が低いと思い込んでいた)
よりも、ずっと高性能・高機能であった事である。
最大ISO感度は25600で、実用レベルとして十分。
一部の他機のように感度を上げても連写性能が低下する事は
無い(ただし、歪曲収差補正をONすると連写性能が落ちる)
連写速度は秒5コマで、まあ2010年代前半のフルサイズ機
相当だ。ここは若干不満だが、実用上で必要とあれば他に
高速連写機は色々と所有している。それに軽量機に無理に
高速連写機能を持たせると、機体重量が増えて、本来の
製品の特徴が失われてしまうので、これはこれで良い。
バースト枚数(=最大連写枚数)は、中画素数以下ならば
SD系カードいっぱいまで無制限に撮れる。
(注:最大のJPEG Large/Fineでは180枚迄)
最高シャッター速度は1/4000秒、まあこのクラスの
機体であれば、これは一般的なスペックである。
大口径レンズ使用時にはNDフィルターを併用すれば良い。
バッテリーの持ちはCIPA規格で440枚、これは私の場合
この5~6倍は撮れるので、2500枚以上となり、まあ十分だ。
(1000枚以上撮ってもバッテリーの3段階残量目盛りが
減る事は無い。ただしバッテリーの残量は%表示では無い)
他の仕様は、まあどうでも良い、その他の細かい数値性能や
付加機能の差が実用上で問題になった事は殆ど無いのだ。
これで軽量(本体のみ520g)であれば、十分であろう。
操作系だが、上位機種と同等の2ダイヤル操作子を持つ。
これは本機購入の最大の理由となった点であり、
EOS Kiss系の1ダイヤルでは実用撮影には向かないのだ。
(同様な理由で、2ダイヤルのPENTAX中級機K-30を購入
している。後日、本シリーズ記事で紹介予定)
ただ、バリアングルの背面モニターはミラーレス機程の
メリットは無い、これを収納位置にするとメニュー設定が
出来無いからだ。上部液晶の新設で若干はカバー可能だが、
操作系面における不足は確かだし、バリアングル状態での
静止画撮影はライブビューAFとなり合焦精度不足が起こる。
しかし、背面モニター(104万ドット)は、恐ろしく綺麗
であり、ここ数年間での技術の進歩を感じる。
まあ、もしかすると、再生画像が綺麗である事でビギナーが
「良く写るカメラだ」と錯覚する為、それを狙って集中的に
この分野の技術革新を優先させたのかも知れないが・・
(注:このあたりの仕様・性能の全般は、NIKONの普及機
D5000番台の機体と、ほとんど同様である)
![c0032138_12590658.jpg]()
まず、低速連写モードが無いが、これについては、
静音連続撮影を選ぶと、秒3コマまで落とせる。
高速連写が必要で無い、静かなイベント撮影等の場合、
本機で十分であり、むしろ適正な機材となる。
(高級機や旗艦機は、シャッター音がうるさい機種が多く、
様々な撮影シーンで顰蹙を買っている状態だ)
エフェクトがある事で描写表現力のバリエーションが
増加する。いったい誰が「本格的な写真は普通に綺麗に
撮った物でなくてはならない」と言い出したのだろうか?
20年前ならば、そういう価値観はあったが、現代では
もうそんな古臭い事を考える人は誰も居ない筈だ。
さもないと、写真がデジタル化された意味・意義・恩恵が
半減されてしまう。デジタル写真は用途に応じて加工して
使うものであり、撮ったままで使うならば銀塩写真で十分だ。
エフェクトの種類は少ないが、実用的なものが多く、
おまけに、エフェクトの二重掛け、三重掛け・・も可能で
あり、さらには過去画像に遡って処理を行う事も出来るので、
非常に好ましい仕様である(一部の他社機でもこれは可能)
一眼レフ系のエフェクトでは、従前はPENTAX機やSONY機の
機能が個人的には好評価であったが、本機のような近年の
CANON下位機種の方が、むしろ優秀に思えて来た。
![c0032138_12590648.jpg]()
「写真とは、真を写すと書く」といった、古くて保守的な
価値観を持つ人達がエフェクトを「子供騙しだ」と嫌う為に、
CANONもNIKONも上級機以上(シニア層が主力ユーザーだ)
では、エフェクトを搭載する事が出来ない、という非常に
不条理な市場状況である。
上位機種にもエフェクトの搭載を希望する次第である。
(SONY,PENTAX,OLYMPUS,PANA,FUJI等ではそれが常識だ)
それと今回、SIGMA A135/1.8という、業務専用レンズ
と言えるものを装着して「限界性能」を試しているが、
重量アンバランス等も許容範囲である。
ただし、本レンズには手ブレ補正が内蔵されておらず、
勿論、EOS本体側にも入っていない。
重量級レンズであるが故に、後述の、ISO低速限界設定や
セイフティシフト機能が無い事とあいまって、なかなか
困難なレンズとなる。これらの課題を理解して使いこなす
には上級レベルの知識・経験と技能が必要になるだろう。
それから、基本的に私はAF性能が低下するライブビュー
モードは使用しないが、試しに使ってみると、事前に
予想していたよりも遥かにAFは高速だ。
これは像面位相差(デュアル・ピクセルCMOS)AFでは
無いものの、ハイブリッドCMOS AF(Ⅲ)という新技術の
恩恵と思われる。が、まあそれでも、ピント精度は余り
高く無い為、大口径レンズ使用時等では、これを常用
したいと言う気にはなれない(主に動画用途であろう)
ただまあ、CANONの場合は、撮像素子は自社製CMOSで
ある為、「システム・オンチップ構成」での、この辺の
設計自由度は高く、他社機に対するアドバンテージは有る。
(将来的な性能アップ、あるいはローコストな構成も
作れるという事だ)
その他、全般に低性能ではあるが、実用上の不満点は
意外に少ない、これであれば、条件によっては業務撮影
にすらも使用可能であろう。
プラスチッキーな量産品という外観で、所有満足度は
欠片も無いが、むしろ過酷な撮影環境で「消耗機」と
してしまうには、思い入れが少ない分、適正だ。
(ただし、1度本機でボート系イベントを撮影した事が
あるが、その際、SDHCカードが故障してしまい、およそ
1000枚の写真が読み出せ無くなってしまった。これは
カメラ側の耐久性等の問題とは全く無関係だとは思うが
かなり酷使した使い方をしたので、少々危なっかしい。
今のところ別のSDカードを入れて問題なく動いているが
本機そのものの信頼性や耐久性は、もう少し長期に
渡っての検証が必要だ)
![c0032138_12592371.jpg]()
まず、MFで使用するのは不可能に近い程困難である。
ファインダーおよびスクリーンの性能が低すぎて、
レンズのMF操作、又はアダプターを介したMFレンズでは
壊滅的だ、後者はより深刻で、フォーカスエイドも
出ないし、どうしようも無い。(注:NIKONの普及機以下
では、この用法でさえも使えない。AF-S系やCPU搭載の
レンズを装着しないと、シャッターすら切れないのだ)
AFだが、精密ピント型レンズ(大口径やマクロ)との
組み合わせでは、ピントを外す確率が高い(=精度が悪い)
上記MFの欠点も影響し、ピントを外していてもファインダー
で確認の術(すべ)が無いので厳しい。標準ズームなどの
被写界深度が深いレンズの専用機になる雰囲気だが、まあ
それにしても、上位機種では、ちゃんとピントが合うので
これは「仕様的差別化」であろうが、あまり好ましく無い。
それと、ISO低速限界設定や、セイフティシフトといった
細かい設定項目が省略されている。確かにこれらは
初級中級者では理解不能(用途不明)なものだから
しかた無いかも知れないが、この結果、ISO感度、絞り値、
シャッター速度のカメラ設定には慎重にならざるを得ない、
だが、勿論これは重欠点では無い。
その他、上級機と比べたら至らぬ点は当然様々にある。
AFの精度は低いし、ファインダーもMFでは低性能だ、
よって「ピント歩留まり」は全体的に低下するであろう。
ISO低速限界が無いので、手ブレ補正無しのレンズでは
シャッター速度とISO感度に留意しないと手ブレし易い。
でもそれらが、スペック上の高級機との「仕様的差別化」
である事を完全に見抜いているならば、そうした差別に
負けないように本機を使いこなせば良いだけだ。
例えば、ISO低速限界設定が無くてAF精度が悪い事で
ビギナーでは手ブレ又はピンボケを起こしてしまうから、
「もっと高価なレンズやカメラを買え」と、メーカー側
からは無言の圧力をかけてきている、という「意地悪な
仕掛け」が良くわかっているならば、それを技能で回避して
使えば良い訳だ。まあ、幸いにして本機には、ISO設定
専用ボタンもあるし、ファインダー内表示を見ながらでも
ISO設定のエディットが可能だ(=構えを解く必要は無い)
AF精度に関しては、連写中のシームレスMFブラケットと
いった高度な撮影技法を用いて問題回避する事も出来る。
後、中古相場が若干高価な事も問題点であろう。
でもこれは、エントリークラスの中での高付加価値型
商品だし、比較的新しい機種でもあるのでやむを得ない。
本機の性能・機能からの適正な中古相場は、25,000円
程度迄である。しかし、その相場低下を待っていたら、
本機が、「仕様老朽化寿命」を気にせずに、快適に使用
できる期間(時代)を過ぎてしまう。
つまり、今迄の私の購買行動ポリシーに加えて、市場動向
を見た「買い頃」という時間的要素(タイミング)を
加えなければならない、という事になる。
まあ、結果としてのコスパの悪化は、もうやむを得ない。
CANONの旧機種の代替となる適正な機体も他に無い為、
「機種数は増えたが適切な選択肢が無い」という不条理が
ここでも起こっている訳だ。
![c0032138_12592389.jpg]()
銀塩時代に、本機に対応するカテゴリーのEOS機は
存在しなかったように思われる。
あえて挙げるならば、EOS 100 QD(1991年)あたりだが、
その機体は使っていたが、譲渡により現在は未所有だ。
または、EOS Kiss 7(2004年)も、立ち位置が類似
していると思うが、完全に銀塩末期の機体(銀塩
EOS Kissの最終機)であったので購入はしていない。
やむなく、今回は対応銀塩機の紹介は見送ろう。
最後にCANON EOS 8000Dの総合評価をしてみよう。
(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)
【基本・付加性能】★★☆
【描写力・表現力】★★★☆
【操作性・操作系】★★☆
【マニアック度 】★★
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★★☆ (中古購入価格:44,000円)
【完成度(当時)】★★★
【歴史的価値 】★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.8点
予想通り標準点をやや下回る評価となり、高得点は
得られていない。
だが、フルサイズ上級機EOS 6D(本シリーズ第16回記事)
と、ほぼ同等の評価得点である。
まあつまり、安価な普及機(初級機)でも十分に使える、
という結果となった、とも言える。
![c0032138_12592338.jpg]()
ある種の「呪縛」から逃れられるかも知れない。
ただ、AF/MFの弱点は少々気になるところだ、業務用途等に
おける「ピント歩留まり」は、長期間の実用経験から再度
評価の微調整をしていく事にしよう・・
次回記事では、引き続き「第五世代」のデジタル一眼を
紹介する。

取り上げる。なお、記事の順番と発売年が1年程前後する
場合があるが、同一メーカーの機種を続けて紹介しない
為であり、他意はない。
装着レンズは2種類用意している。まずは、中国製の
YONGNUO(ヨンヌオ) YN 50mm/f1.8(中古購入価格:
4000円と安価、他記事では未紹介)を使用する。

色々といわくつきだ。まあでも、それは本記事の内容とは
無関係な為、いずれ他の記事で詳しく解説しよう。
なお、レンズフードは「ハマカク」(hama製角型フード)
を装着している。
このシステムで撮影した写真を交えながら本機EOS 8000D
の特徴について紹介していくが、記事後半では別のレンズ
に交換する。またEOS 8000Dの本体機能であるエフェクト
(クリエィティブフィルター)等は自由に使う事とする。
ただし、本記事の内容は、単純なカメラの性能評価等に
留まらず、現代のカメラ市場や、市場全体における、
本機の位置付け等、全体的かつ多面的な視点での紹介を
主とし、いつもより長目の記事となる。

初の機体である。
現代における、EOSデジタル一眼レフのラインナップを
独自に整理してみよう。
入門機:EOS Kiss (Digital)(X)シリーズ
普及機:EOS 四桁Dシリーズ(8000D,9000D)
中級機:EOS 二桁Dシリーズ(10D~80D)
上級機:EOS 6Dシリーズ、EOS 7Dシリーズ
高級機:EOS 5Dシリーズ
旗艦機:EOS-1Dシリーズ
・・まあ、カメラ市場縮退の現代においては、これらは
ラインナップの段階が少々細かすぎるような気もする。
つまり、そんなに細かく分けても販売台数が増えるとは
思い難いし、新商品の開発経費も嵩み、製造・流通・在庫
面においても色々と面倒な事であろう・・
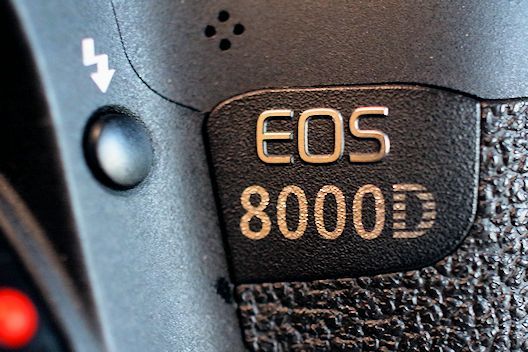
受けていると思われる。特にCANONの場合、銀塩時代の
1993年から続く「Kiss」の系譜は、女性やファミリー層
という新たなユーザー層を新規開拓した重要なシリーズ
ではあるが、その名称からも男性ユーザーには受け入れ
難い要素もあったと思う。(注:国内市場での名称。
米国向けはKissでは無くREBEL、欧州向けは数字型番だ)
そこで男性ユーザー層に向けてのエントリーモデルとして、
上位のEOSフタ桁Dシリーズに相当する2ダイヤル操作系や、
上部液晶等を備えた、中間ランクのEOS四桁Dシリーズを
新設し、付加価値、つまり利益アップを狙ったのであろう。
ちなみに、EOS 8000Dでの主力商品はレンズキットであり、
下位機種のKiss X8iとは、キットレンズの種類を変えて、
その価値の差をわからなくさせてはいるが、発売時には、
およそ3万円以上もの実売価格差があった(結構高い)
また、その結果として上位の中級機の次世代機(EOS 80D
2016年)の価格も連動して押し上げる事が出来るように
なる。まあつまり、意図的に追加されたラインナップ戦略
という訳だ。

分類である。お互いラインナップに抜けがあると、それを
必要とするピンポイントのターゲット・ユーザーを逃がして
しまうという考え方であろうか? まあ、ユーザーニーズが
多様化している現代では、わからない話では無い。
そして、細かくラインナップ間での仕様を差別化すれば、
縮退した市場でのユーザー層の目線を、上へ上へと、
上位機種の販売に誘導する事もできるようになるだろう。
(=安い機種を買っても性能が低いから、どうせ買うなら
一番性能の高い物が欲しい、と、ユーザー心理を誘導する)
参考の為、以下にNIKON機のラインナップも整理してみる。
入門機:D3000シリーズ
普及機:D5000シリーズ
中級機:D7000シリーズ、D600シリーズ
上級機:D700シリーズ
高級機:D800シリーズ、D500、Df
旗艦機:Dヒトケタシリーズ
なお、勿論ここにはミラーレス機は含まれていないし、
APS-C機かフルサイズかの差異も書いていない、そのような
事は「常識」であるので割愛しよう。
そして、当然であるが、これらは高価格な機種である程
性能や機能が高い。
いや、正確に言えば、機種毎に異なる部品を開発していたら
面倒でやっていられないので、同じ部品を使ったとしても
下位機種では、その性能を制限している(=仕様的差別化)
まあでも、高速連写等を実現する為には、それなりに
パワーのある機構部や高速処理電子部品などが必要と
なるし、センサーサイズや画素数の差もある為、完全に
どの機体も同じクラスの部品を使う、という訳でも無い。
ただ、部品代の差よりも「いくらなら売れるか?」という
市場戦略上の視点で機体価格が決められている事については
ユーザー層は必ず知っておく必要がある。
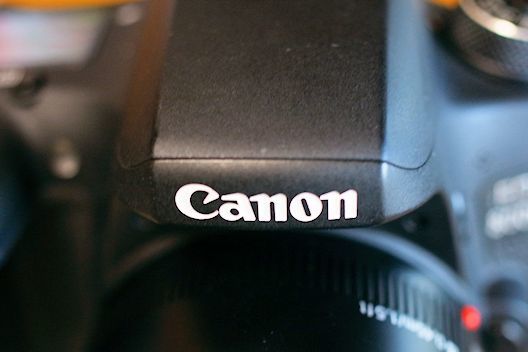
の区分が曖昧であるように感じるかも知れない。
ただ、私個人的には、ここには明確な差異があり、まあ
高級機とは、「高付加価値型の高価な製品」という事だ。
定価で言えば25万円以上、中古価格も10万円を下回らない
相場だ(注:年月が経てば中古相場は必ず安価となる)
今時のユーザーが使う市場用語であれば、高付加価値型
商品よりも「プレミアムな商品」と呼ぶのであろう。
たたし、ここからは重要なポイントであるが、高付加価値
とかプレミアムとかは、カメラに限らず、現代の一般市場に
おける商品やサービスでは「実用範囲を超えて無駄に高価で
コスパが極めて悪い」という意味と、ほぼ等価であろう。
私もまあ、上記における「高級機」に分類されるものを
いくつか買ってしまっているのだが、やはり値段が高ければ
高い程、より安価な製品と同様の弱点を持つ場合、その
欠点に対する評価の低下が物凄く厳しくなる。
つまり「値段が高い機種のくせに、これくらいの欠点すら
直っていないのか、ふざけた製品だ!」という厳しい評価と
なり、たいていの場合、これは極めて精神衛生上良く無い。
カメラ等に限らず、つまりまあ、プレミアムな商品は、どの
市場分野においても、そうした付加価値(性能やら、味やら
サービス等)に、何も疑問を感じないビギナー層向けの
商品であり、少なくとも自身が詳しい(精通している)市場
分野では、そういう類の商品に過度な期待を持つのは禁物だ。
(例:高価な食品を食べて「不味い」と感じた事は多いだろう)
ともかく、カメラについては「実用上では上級機まで、それ
以上の高額商品は不用」というのが、近年の私の持論である。

そういう機体を必要とするか?の購入動機の説明だが・・
まず、本機EOS 8000Dは「かなり小型軽量である」という
大きな特徴を持っている。本体のみ520gは、まあ実用的な
(=入門機等を除いた)一眼レフ中では、トップでは無いが、
勿論上位に入ってくる。
そういう視点では、勿論ミラーレス機の方が小型軽量だ、
本機の半分程度の重さのミラーレス機はいくらでもある。
ただ、ミラーレス機を必要とする状況と、一眼レフを必要
とする状況は異なる。だから両方必要とされるのは、現代
においては当然の話だ。まあ、ミラーレス機が出始めた
10年程前においては、「一眼レフとミラーレス、どちらが
優れていて、どちらが買いか?」みたいな意味の無い比較が
世間では多かったが、両者は構造も特性も用途も全く異なる
訳だから、別のモノを同一の価値観で比較してはならない。
(例:「ラーメンとカレー、どちらが美味しいか?」の
ような、結論が出ない無意味な議論となってしまう)
それから、本機には上級機には無い「エフェクト」
(クリエィティブ・フィルター)が入っている。
ここはむしろ写真における「表現力」の増強という点で
期待が持てる。しかし、ミラーレス機のように撮影時に
エフェクトは使えない。(注:一般的な一眼レフでは
エフェクトは再生時の後掛けとなり、撮影前確認が出来ない
状況だ。ただし、一部にEVF搭載一眼レフやライブビュー・
エフェクトは存在している)

「市場状況の変化」の理由も大きい。ここからは長い話に
なるが、ここはユーザー層は理解しておくべきポイントだ。
で、一眼レフの範囲で言えば、私の使用しているCANON機
は、近年ではEOS 7D/6D/7D MarkⅡが主力機種であった。
これらは2009年~2014年の発売である。それより古い
時代の機体も何台か所有しているが、もう仕様老朽化寿命
(持論では発売後10年まで)が来ていて実用には厳しい。
上記の主力機種群は「上級機」にカテゴライズされる。
つまり実用上では「最良のコスパを発揮するクラスの機体」
ではあるのだ。ただ、近年のCANON機の、これらのクラスの
製品寿命サイクルは約5年と伸びている。つまり、滅多に
新製品を出さないし、その結果、中古相場もあまり下がらず
発売後5年程で新製品が出て、さらに1~2年を経過しない
限り旧機種の中古相場はあまり下がらない。
すると、手ごろな相場になるまで7年程もかかってしまい、
前述の「仕様老朽化寿命」を、発売後10年とすれば、
もう3年程しか活躍期間が無い事となる。
「ではもっと早く買えば良いではないか?」と思うかも
知れないが、私の場合、新機種の性能・機能や操作系等は
発売時から、ちゃんと調査してあり、その性能や仕様等に
見合う「想定購入価格」を、ある程度決めている。
その自分で決めた価格になるまで中古相場が下がらない限り、
それよりも高価に買ってしまうと、「コスパが悪い」と
見なしてしまう訳だ。
コスパの悪い製品(商品)の購入は、私が最も嫌う事だ、
「それをする位ならば買わない」というポリシーがある。
しかし、2010年代ではカメラ(一眼レフ)市場の縮退の
傾向がとても強く、新製品は高付加価値化で値上げされ、
中古流通も安売りしていたら崩壊してしまうので、これも
ずっと高値相場、と、ユーザー側から見てあまり好ましく
無い状況が続いた。ここで「相場下落待ち」をしてしまうと、
それこそ発売10年を超えた、とんてもなく古い機体しか
買えなくなってしまう。あるいは入門機等ならば、相場の
下落が速いが、それらはさすがに実用範囲以下の性能だ。
だから、自身の機材購入ポリシーを緩和して、若干コストが
高い機材でも、パフォーマンスが高ければ買うように
してきている。結果の「コスト・パフォーマンス」は勿論
低下し、私の評価データベースで標準点(3点)を超える実用
カメラやレンズは、残念ながらもう殆ど存在しない状況だが、
ここはやむを得ない。コスパ点が1点対2点等の、レベルの
低い戦いで機種間の相対的な評価を行うしか無い状態だ。
まあ、一眼レフ市場が縮退してしまったのは、スマホや
ミラーレス機の台頭だとかの理由も勿論あるのだが、
魅力的な新製品が出て来なかったという事も大きな問題だ。
減少した売り上げをカバーする為に、高付加価値という名の
実際には必要としない性能や機能を色々と入れて、その結果
としての値上げが発生しているならば、中上級者やマニアは
もう新機種に興味は持てない。
この結果、中上級者はもとより職業写真家層ですら新機種を
買っておらず、少し古い世代の機種を使い続けている。
だってそれでも十分写真は撮れるし、しかも業務撮影だったら、
高価すぎる新機種を次々と買っていたら収支が確実に赤字と
なり、ビジネス(商売)には成り得ない。
仮に自腹では無く、企業等の経費で買って貰ったとしても、
企業等の全体で見たら、大きな「支出」となってしまう。
(まあ、写真家等にメーカーから貸与する等を行った場合は、
「私もこのカメラを愛用しています」と宣伝させる意味での
市場効果はあるだろう。だが、その事も、例えば有名女優が
化粧品のCMをしているようなもので、ありふれた広告戦略だし、
今時はそういう事情は皆が知っていて、宣伝効果があまり無い)
結局、高価な新製品を買って使っているのは、コスト感覚が
弱かったり、広告宣伝等に過剰に反応しやすいビギナー層
ばかり、という極めて不自然な市場状況となった。
だが、この感覚はデジャビュ(既視感)がある、第一次
中古カメラブームが起こる直前の1990年代中頃の話だ。
この頃、バブルの崩壊、そして阪神淡路大震災等の影響で
市場は大きく冷え込んだ。だが、新製品の銀塩AFカメラは
バブル時代に企画された、華美なスペックを盛り込んだ、
イケイケムードのバブリーなカメラばかりとなっていた。
新規ビギナーユーザー層は、それらのカメラを買ったが
その他の層は、そうした新製品カメラに、まったく興味が
沸かず、銀塩中古カメラや新カテゴリーの高級コンパクトに
興味を持ち、そこから空前の「第一次中古カメラブーム」に
突入したのだ。
このままでは現代においても「中古デジタル一眼レフブーム」
が起こる可能性もある。と言うのも、新製品は高いだけで、
あまり魅力的では無いからだ。
なお、既に別の「ムーブメント」(動向)も起こっている。
具体的には、2018年頃から急速に中国製等の海外製の
安価な交換レンズが非常に多数、市場に流通し始めている。
今回使用のYONGNUO(ヨンヌオ)も、その中の一つである。
これは「高価になりすぎて、コスパが極めて悪い」という
国産交換レンズの新製品の市場戦略上の弱点を突いて、
あえて、この時期に低価格帯市場に参入したのであろう。
(SAMYANG、中一光学、LAOWA等は数年前より市場参入済みだ)
他のマニア層の購買行動は良く知らないが、少なくとも私は
興味深々である。既に、七工匠やMeike等の、こうした最新鋭
海外製レンズを何本か購入しているし、コスパ面では満足して
使っているので、きっと今後も買い続けるであろう。
つまり、高価すぎる国産新鋭レンズには、もう興味が持てず、
「新勢力」に目線が行ってしまっているのだ。この状態もまた、
1990年代の中古カメラブームの際のユーザー心理と、ほぼ
同様である。まあ、これら最新鋭海外レンズについては、
追々、レンズ・マニアックス等の別記事で紹介して行こう。

である。画素数もAF測距点もISO感度も連写速度も付加機能も
もう2010年代後半では全て性能的に頭打ち状態だ。
だが、メーカー側も無策では無い。一眼レフがもう限界ならば
ミラーレス機に移行すれば、まだそこでは色々と技術革新の
余地がある。そうした市場背景もあって、2018年秋からの、
各社一斉のフルサイズ・ミラーレス機への戦略転換であろう。
・・・しかし、ここもまた「ユーザー不在」の話だ。
またミラーレス機で、一眼レフで今までやってきた事と
同様の「段階的性能追加戦略」をしていくのだろうか?
それは2012年のデジタル一眼レフの「フルサイズ化元年」
から、2018年頃にいたるまで、高速連写や高感度性能を
段階的に搭載していって、だんだんと値上げをしていった
事を、またミラーレス機でやる、という事なのだろう。
(既にSONY α7系ミラーレス機でも、そういう状況があった)
おまけに新鋭ミラーレス機であれば、一眼レフよりも利益率を
高める事ができる、つまりメーカーは良く儲かり、縮退した
カメラ市場を、その戦略で支える事ができる。
勿論、カメラ本体のみならず、新マウント規格への対応
レンズを新たに作って高価に売りたい、という戦略も大きい。
しかし、これでは完全に「消費者の負け」の状況だ・・
ただ、だから良いとか悪いとかでは無い、これがカメラ市場
を維持する為に必須の措置であれば、メーカー側や流通側は、
そうするしか無い。
後は、ユーザー側の価値判断だけだ。新機種を魅力的だと
思えば買えば良いし、コスパが悪いと見なせば、買わないか
または価格が下がった頃に買えば良い。
あるいは、もう見限って、新鋭海外レンズ等で、しばらくの
期間は遊んで、市場の変化を待っておくか、だ。
市場におけるコスト高状態が続けば、必ず市場は自ら適正な
価格帯に自動的に修復される、つまり高すぎて売れなければ、
安価な商品を市場に投入せざるを得なくなるからだ。
現代に限らず、過去のカメラ史においては何度もあった事で
あるし、カメラ以外の市場でも、それは必然の市場原理だ。

いこう。
すなわち現代の高性能一眼レフは、基本的にどれもコスパが
悪い。でも、旧世代の安価な機種を使い続けていたら、
すぐに、それは古くなってしまう(仕様老朽化寿命が来る)
そんな中で、どのように機材をローテーションしていくかは
非常に難しい判断だ。(注:いつまでも古いカメラを使い
続ける事は出来ず、必ず新機種を追加/代替する必要がある)
これまで私は、その1つの目安として、カメラにおける持論の
「1枚3円の法則」で「元を取る」まで次のカメラを買わない
または「1枚3円をクリアしたら次の機種を買う」という
方針であったが、もう段々と、その持論が守れなくなって
来ている。
機体の価格が上がっていけば、1枚3円をクリアするには
時間がかかる。例えば高級機を中古で15万円で買ったら、
5万枚を撮らなければならない。
連写が効かないフルサイズ機等でそれを実現するには、
とても年月がかかる。
元が取れる頃には、もう「博物館行き」の古いカメラと
なっているだろう(汗)
あるいは高速連写機を買ったとする、例えばEOS 7D MarkⅡ
を中古で9万円で買った場合、3万枚がノルマだが、これを
実用撮影等で使うと3万枚はあっと言う間だ、1~2年程度で
クリアしてしまう。しかし元を取ったと言っても、後継機が
まだ発売されていないのだ。仮に出てきたとしても、とても
高価になっている、これでは旧機種を限界を超えるまで
何十万枚も撮影を続け、酷使するしか無いでは無いか・・
(参考:近年、中古市場に出て来る、やや古い高級・旗艦級の
カメラは、このように業務用途で何十万枚も撮影し続けて酷使
された機体が多い。前述のように、職業写真家層であっても、
高価な新機種に、そう簡単には買い換える事が出来ないからだ)

せっかくそこに行くのだから、と、Panasonic機では
最も歴史的価値の高いカメラである、世界初のミラーレス機
「DMC-G1」を首から掛けて見学していたのだが・・
展示品の中にDMC-G1が当然あった。たまたま機体色も同じ
青である。専用・特注のガラスのショーケースの中に
大切そうに展示してある、手元と全く同じカメラを見て、
私の感想は、
匠「なんだ・・ まだ発売後10年も経っていないのに、
もう”博物館行き”の扱いかよ・・
こっちはまだG1は現役機としてガンガン使っているのに
過去の遺物扱いとは、こういう市場って正しいのか?」
という感じであった。
「カメラ市場が、もう不条理だ」、数年前から薄々感じて
いた事だが、ここに来て、その思いはとても強くなった。
価格対性能比、つまりコスパもデタラメ、購買層も本来は
腕前に応じて高性能機を使うべきなのに、まるっきりそれが
逆転して、ビギナーが高級機を買い、仕事では普及機を使う。
(今時の新聞記者や企業広報担当者等は、自腹又は経費購入の
一眼レフは、いずれも初級機か、良くて中級機である)
まあ、これでは、これまでの時代のように機材購入ポリシー
を持って、論理的で合理的な購買行動を起こすなど不可能だ。
ならば、こうした不条理な市場に対応する、新しい機材購入
ポリシーを導入するしか無いでは無いか・・

本機は普及機である、しかも入門機のEOS Kiss X8iと
ほとんど同じ性能の姉妹機だ、つまりまあ一眼レフとしては
最底辺の低性能なカテゴリーの機体だ。
ある意味、高付加価値型商品の対極にある「低付加価値型
カメラ」とも言えるであろう。
(注:このシリーズは型番「8000」からの開始であるが、
これはKiss X8i等と、番号を揃えたという事であろう。
以前、他社では、シリーズ最初の機体を1番機としたが、
他のシリーズ機体が既に6番機とかになっていた為、
「発売が古い機種だ」と勘違いされてしまった前例がある。
ただまあ、CANONにおいても、後継機EOS 9000Dの次は、
いったい、どんな型番にするのであろうか・・? 汗)
で、これまで「こういう機体はビギナーが買うものだ」
と敬遠してきた心理的な要素も、もう「不条理な市場」で
ある以上、そうした先入観念を持つ事は良く無い。
「外に持っていったら格好悪い」と卑屈に思う必要も無い、
世の中の現実的には、高級機を持っているのは、カメラの
正しい構えすらも、おぼつかないビギナー層ばかりだ。
この機体を入手し、厳密に評価する。当然様々な弱点は存在
するだろう、より上位の機種と差別化する為、わざと性能や
機能を落としているからだ(=仕様的差別化)
また、冒頭にも少し書いたように、本機は、CANONでの
ラインナップ全体の価格を押し上げる為に、旧来のランクに
無理やりインサート(挿入)されたクラスであるとも言える。
だが、それらの事はすべて承知の上で、もし、性能面や
機能面での問題点回避の方法が存在するのであれば・・・
もう「上級機や高級機がコスパが悪い」等と、嘆く必要は
なくなるではないか。中古相場が適価に下がって来た頃に、
こうした安価な一眼レフを買ったとしても、十分に実用的に
写真は撮れるだろうからだ。
さて、ここで使用レンズを交換してみよう。

こちらは、EOS 8000Dの本体の2倍以上も重く、価格も
2倍以上も高価な、本格派の業務用レンズだ。
こういった、これまでの常識的には「絶対に有り得ない」
とも言えるアンバランスなシステムをあえて組んでみて、
もし、これが実用的であれば、もう母艦は何でも良い
(上級機や高級機でなくても良い)という事になるだろう。

あると評価できるのであれば、他にも、ちょっと気になって
いたNIKON D5000シリーズ等も、購入を躊躇う必要も無い、
PENTAX機だって、Kフタケタ機で十分だろうし・・
(そういう判断で、既にそれらを入手して使っている)
あるいはミラーレス機だって、もうビギナー層向けの安価な
機種で十分だとわかれば、それらを安価に買えばコスパ的
には何の問題も無くなる。(既にそうしつつある)
おまけに、近年のこうした低価格機は、上位機種に吊られて
基本性能が上がっている。だから、もしかすると性能的にも
不満はなく、むしろ、やや古い時代の上級機・高級機よりも、
新鋭機の初級機の方が高性能かも知れないのだ。
(=「下克上」が発生している)
この「新戦略」は、おかしくなった(と見ている)カメラ
市場への個人的な対抗策である。もうビギナー層しか
高級機や旗艦機を買わないならば、そういう機体を使って
いたらむしろ格好悪い。「自分のスキルに自信を持てない
人達が、機材の性能でカバーしようとしている」という
新しい情報分析がもう出てきているし、それがいずれは
市場における「常識」になるかも知れないのだ。
勿論それは不自然な話だ、でも趣味撮影の分野においては、
現実は既にそうなりつつある状況だ。
もし前述の「中古デジタルカメラブーム」が来たら、
その新しい価値感はいっきに表面化して一般化するだろう。
つまり、マニア層や上級層は、古いデジタルカメラを使い
マ「君達初心者には、こういう古くて性能の低いカメラは
使いこなせないでしょう? だから、最新の高性能の
カメラを使っているのだよね? フフフ・・(冷笑)」
という、やや捻くれた価値観が生じる。

第一次中古カメラブームの際にも起こっていたのだ。
マニア層や上級層は、ビギナーでは絶対に使えないだろう
複雑怪奇な操作を必要とする古いカメラで写真を撮って
いたわけだ。単に「優越感を得たい」と言うよりも、もう
市場全体で、それが「格好良い事」という価値観となり、
露出計すら無い非常に古いNIKON Fを使うのは上級マニアで、
最新旗艦機で誰でも撮れるNIKON F5を使うのは初級マニア層、
という風に暗黙の住み分けが出来ていた。
まあ細かい話は良い。ともかく普及機クラスの低価格機で
何も不満が無く使えるのであれば、これは現代の不条理な
カメラ市場の価値感覚をひっくり返せる「パラダイム・
シフト」(=今まで当然だと思っていた価値感覚が劇的に
変化する事)になり得る。
メーカーや市場側にとっては困った話になるかも知れないが
誰もがそうする筈も無いだろうし、この意味がわからない人は、
わからないなりに、好きに新鋭機を買えば良い訳だ。
それに私からすれば、コスパが良く魅力的な新製品を
出せないのはメーカー側の問題だ、とも解釈している。
黙ってその状況に従うつもりは無い。
現に、過去60年間以上の一眼レフの歴史を全て調べて
いくと、その時代の経済水準に比べて、カメラの価格が
高価すぎる時期が続くと、今度は低価格化の時代が必ず
来ている。高価すぎて売れないカメラをいつまでも作り
続ける訳には行かないから、前述のように「市場」自体が
適正価格のバランス点を求めて推移していくのだ。
(それと、前述のように、ここ数年で中国製等の安価な
交換レンズが、急速に国内市場に浸透してきている。
これは、高価になりすぎた日本製交換レンズの弱点を突いた
市場戦略であり、市場の一部が低価格化にシフトしつつある)
ただしユーザー側全般が、そうした「価値判断」が出来なく
なってしまうと、バブリーなまでに商品価格はどんどんと
高騰していく。そしていつか必ずバブルは弾け、その後の
市場はグチャブチャに混迷してしまう訳だ。
まあ、こういう風に歴史は繰り返していく・・

まず基本スペックに係わる長所であるが、
事前に想像していた(普及機は性能が低いと思い込んでいた)
よりも、ずっと高性能・高機能であった事である。
最大ISO感度は25600で、実用レベルとして十分。
一部の他機のように感度を上げても連写性能が低下する事は
無い(ただし、歪曲収差補正をONすると連写性能が落ちる)
連写速度は秒5コマで、まあ2010年代前半のフルサイズ機
相当だ。ここは若干不満だが、実用上で必要とあれば他に
高速連写機は色々と所有している。それに軽量機に無理に
高速連写機能を持たせると、機体重量が増えて、本来の
製品の特徴が失われてしまうので、これはこれで良い。
バースト枚数(=最大連写枚数)は、中画素数以下ならば
SD系カードいっぱいまで無制限に撮れる。
(注:最大のJPEG Large/Fineでは180枚迄)
最高シャッター速度は1/4000秒、まあこのクラスの
機体であれば、これは一般的なスペックである。
大口径レンズ使用時にはNDフィルターを併用すれば良い。
バッテリーの持ちはCIPA規格で440枚、これは私の場合
この5~6倍は撮れるので、2500枚以上となり、まあ十分だ。
(1000枚以上撮ってもバッテリーの3段階残量目盛りが
減る事は無い。ただしバッテリーの残量は%表示では無い)
他の仕様は、まあどうでも良い、その他の細かい数値性能や
付加機能の差が実用上で問題になった事は殆ど無いのだ。
これで軽量(本体のみ520g)であれば、十分であろう。
操作系だが、上位機種と同等の2ダイヤル操作子を持つ。
これは本機購入の最大の理由となった点であり、
EOS Kiss系の1ダイヤルでは実用撮影には向かないのだ。
(同様な理由で、2ダイヤルのPENTAX中級機K-30を購入
している。後日、本シリーズ記事で紹介予定)
ただ、バリアングルの背面モニターはミラーレス機程の
メリットは無い、これを収納位置にするとメニュー設定が
出来無いからだ。上部液晶の新設で若干はカバー可能だが、
操作系面における不足は確かだし、バリアングル状態での
静止画撮影はライブビューAFとなり合焦精度不足が起こる。
しかし、背面モニター(104万ドット)は、恐ろしく綺麗
であり、ここ数年間での技術の進歩を感じる。
まあ、もしかすると、再生画像が綺麗である事でビギナーが
「良く写るカメラだ」と錯覚する為、それを狙って集中的に
この分野の技術革新を優先させたのかも知れないが・・
(注:このあたりの仕様・性能の全般は、NIKONの普及機
D5000番台の機体と、ほとんど同様である)

まず、低速連写モードが無いが、これについては、
静音連続撮影を選ぶと、秒3コマまで落とせる。
高速連写が必要で無い、静かなイベント撮影等の場合、
本機で十分であり、むしろ適正な機材となる。
(高級機や旗艦機は、シャッター音がうるさい機種が多く、
様々な撮影シーンで顰蹙を買っている状態だ)
エフェクトがある事で描写表現力のバリエーションが
増加する。いったい誰が「本格的な写真は普通に綺麗に
撮った物でなくてはならない」と言い出したのだろうか?
20年前ならば、そういう価値観はあったが、現代では
もうそんな古臭い事を考える人は誰も居ない筈だ。
さもないと、写真がデジタル化された意味・意義・恩恵が
半減されてしまう。デジタル写真は用途に応じて加工して
使うものであり、撮ったままで使うならば銀塩写真で十分だ。
エフェクトの種類は少ないが、実用的なものが多く、
おまけに、エフェクトの二重掛け、三重掛け・・も可能で
あり、さらには過去画像に遡って処理を行う事も出来るので、
非常に好ましい仕様である(一部の他社機でもこれは可能)
一眼レフ系のエフェクトでは、従前はPENTAX機やSONY機の
機能が個人的には好評価であったが、本機のような近年の
CANON下位機種の方が、むしろ優秀に思えて来た。

「写真とは、真を写すと書く」といった、古くて保守的な
価値観を持つ人達がエフェクトを「子供騙しだ」と嫌う為に、
CANONもNIKONも上級機以上(シニア層が主力ユーザーだ)
では、エフェクトを搭載する事が出来ない、という非常に
不条理な市場状況である。
上位機種にもエフェクトの搭載を希望する次第である。
(SONY,PENTAX,OLYMPUS,PANA,FUJI等ではそれが常識だ)
それと今回、SIGMA A135/1.8という、業務専用レンズ
と言えるものを装着して「限界性能」を試しているが、
重量アンバランス等も許容範囲である。
ただし、本レンズには手ブレ補正が内蔵されておらず、
勿論、EOS本体側にも入っていない。
重量級レンズであるが故に、後述の、ISO低速限界設定や
セイフティシフト機能が無い事とあいまって、なかなか
困難なレンズとなる。これらの課題を理解して使いこなす
には上級レベルの知識・経験と技能が必要になるだろう。
それから、基本的に私はAF性能が低下するライブビュー
モードは使用しないが、試しに使ってみると、事前に
予想していたよりも遥かにAFは高速だ。
これは像面位相差(デュアル・ピクセルCMOS)AFでは
無いものの、ハイブリッドCMOS AF(Ⅲ)という新技術の
恩恵と思われる。が、まあそれでも、ピント精度は余り
高く無い為、大口径レンズ使用時等では、これを常用
したいと言う気にはなれない(主に動画用途であろう)
ただまあ、CANONの場合は、撮像素子は自社製CMOSで
ある為、「システム・オンチップ構成」での、この辺の
設計自由度は高く、他社機に対するアドバンテージは有る。
(将来的な性能アップ、あるいはローコストな構成も
作れるという事だ)
その他、全般に低性能ではあるが、実用上の不満点は
意外に少ない、これであれば、条件によっては業務撮影
にすらも使用可能であろう。
プラスチッキーな量産品という外観で、所有満足度は
欠片も無いが、むしろ過酷な撮影環境で「消耗機」と
してしまうには、思い入れが少ない分、適正だ。
(ただし、1度本機でボート系イベントを撮影した事が
あるが、その際、SDHCカードが故障してしまい、およそ
1000枚の写真が読み出せ無くなってしまった。これは
カメラ側の耐久性等の問題とは全く無関係だとは思うが
かなり酷使した使い方をしたので、少々危なっかしい。
今のところ別のSDカードを入れて問題なく動いているが
本機そのものの信頼性や耐久性は、もう少し長期に
渡っての検証が必要だ)

まず、MFで使用するのは不可能に近い程困難である。
ファインダーおよびスクリーンの性能が低すぎて、
レンズのMF操作、又はアダプターを介したMFレンズでは
壊滅的だ、後者はより深刻で、フォーカスエイドも
出ないし、どうしようも無い。(注:NIKONの普及機以下
では、この用法でさえも使えない。AF-S系やCPU搭載の
レンズを装着しないと、シャッターすら切れないのだ)
AFだが、精密ピント型レンズ(大口径やマクロ)との
組み合わせでは、ピントを外す確率が高い(=精度が悪い)
上記MFの欠点も影響し、ピントを外していてもファインダー
で確認の術(すべ)が無いので厳しい。標準ズームなどの
被写界深度が深いレンズの専用機になる雰囲気だが、まあ
それにしても、上位機種では、ちゃんとピントが合うので
これは「仕様的差別化」であろうが、あまり好ましく無い。
それと、ISO低速限界設定や、セイフティシフトといった
細かい設定項目が省略されている。確かにこれらは
初級中級者では理解不能(用途不明)なものだから
しかた無いかも知れないが、この結果、ISO感度、絞り値、
シャッター速度のカメラ設定には慎重にならざるを得ない、
だが、勿論これは重欠点では無い。
その他、上級機と比べたら至らぬ点は当然様々にある。
AFの精度は低いし、ファインダーもMFでは低性能だ、
よって「ピント歩留まり」は全体的に低下するであろう。
ISO低速限界が無いので、手ブレ補正無しのレンズでは
シャッター速度とISO感度に留意しないと手ブレし易い。
でもそれらが、スペック上の高級機との「仕様的差別化」
である事を完全に見抜いているならば、そうした差別に
負けないように本機を使いこなせば良いだけだ。
例えば、ISO低速限界設定が無くてAF精度が悪い事で
ビギナーでは手ブレ又はピンボケを起こしてしまうから、
「もっと高価なレンズやカメラを買え」と、メーカー側
からは無言の圧力をかけてきている、という「意地悪な
仕掛け」が良くわかっているならば、それを技能で回避して
使えば良い訳だ。まあ、幸いにして本機には、ISO設定
専用ボタンもあるし、ファインダー内表示を見ながらでも
ISO設定のエディットが可能だ(=構えを解く必要は無い)
AF精度に関しては、連写中のシームレスMFブラケットと
いった高度な撮影技法を用いて問題回避する事も出来る。
後、中古相場が若干高価な事も問題点であろう。
でもこれは、エントリークラスの中での高付加価値型
商品だし、比較的新しい機種でもあるのでやむを得ない。
本機の性能・機能からの適正な中古相場は、25,000円
程度迄である。しかし、その相場低下を待っていたら、
本機が、「仕様老朽化寿命」を気にせずに、快適に使用
できる期間(時代)を過ぎてしまう。
つまり、今迄の私の購買行動ポリシーに加えて、市場動向
を見た「買い頃」という時間的要素(タイミング)を
加えなければならない、という事になる。
まあ、結果としてのコスパの悪化は、もうやむを得ない。
CANONの旧機種の代替となる適正な機体も他に無い為、
「機種数は増えたが適切な選択肢が無い」という不条理が
ここでも起こっている訳だ。

銀塩時代に、本機に対応するカテゴリーのEOS機は
存在しなかったように思われる。
あえて挙げるならば、EOS 100 QD(1991年)あたりだが、
その機体は使っていたが、譲渡により現在は未所有だ。
または、EOS Kiss 7(2004年)も、立ち位置が類似
していると思うが、完全に銀塩末期の機体(銀塩
EOS Kissの最終機)であったので購入はしていない。
やむなく、今回は対応銀塩機の紹介は見送ろう。
最後にCANON EOS 8000Dの総合評価をしてみよう。
(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)
【基本・付加性能】★★☆
【描写力・表現力】★★★☆
【操作性・操作系】★★☆
【マニアック度 】★★
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★★☆ (中古購入価格:44,000円)
【完成度(当時)】★★★
【歴史的価値 】★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.8点
予想通り標準点をやや下回る評価となり、高得点は
得られていない。
だが、フルサイズ上級機EOS 6D(本シリーズ第16回記事)
と、ほぼ同等の評価得点である。
まあつまり、安価な普及機(初級機)でも十分に使える、
という結果となった、とも言える。

ある種の「呪縛」から逃れられるかも知れない。
ただ、AF/MFの弱点は少々気になるところだ、業務用途等に
おける「ピント歩留まり」は、長期間の実用経験から再度
評価の微調整をしていく事にしよう・・
次回記事では、引き続き「第五世代」のデジタル一眼を
紹介する。