
レンズはTAMRON SP85mm/f1.8 Di VC USD (Model F016)
(他記事では未紹介)を使用する。
このシステムで撮影した写真を交えながら、Nikon Dfの特徴に
ついて紹介していこう。
まず最初に述べておかなければならない事がある。
本記事での本機Dfの評価は相当に厳しい状態になるという点だ。
「ニコン党」にとっては信じられない内容であろうが、これは
あくまで事実である、他社機と比べれば容易に実感できる事だ。
俗っぽい例を挙げれば「美人だから、と付き合ってみたら、
相当な悪女だった!」と言う事である(汗)
まあ、「美人」つまり、美しく格好良いカメラである事は、
本機Dfの最大の特徴ではある。

様々というのは、1つは使用レンズや主要被写体が何であるか?
又、撮影技法はどのようにするのか?
そして2つ目に重要な事は、利用者の撮影スキルである。
単純に言えば、初級者なのか上級者なのか?と言う事だ。
さらには3つ目として、その撮影は「業務用途」の撮影なのか
あるいは完全なる「趣味の撮影」か?
まあ、そういった諸々の状況があるという事だ。

しかし「人それぞれだから何とも言えない」と結論を濁す
論理は成り立たない筈だ、「絶対的価値観」は必ず存在する。

最大の目的は、銀塩名機のNIKON F4の代替である。
F4は旗艦機としては、あまり銀塩カメラらしく無いデザインで
好き嫌いがあるのと、AF性能が貧弱な故に不人気のカメラだった。
だが、私は高く評価するカメラである。

MFレンズであってもマルチパターン測光が使用可能で、勿論、
シャッター速度1/8000秒や高速連写性能はそのまま活用できる。
さらには、非Aiレンズもプレビューボタンを押す絞り込み測光で
絞り優先でもM露出でも使用可能だ。
ニコンにしては比較的優秀なスクリーンでピント合わせも容易で、
DXコード対応のネガフィルムを用いて絞り優先で撮れば、
露出補正、手動感度調整、シャッターダイヤルの全てに
「ロック機構」があると言う「重欠点」を、ほぼ回避できる。
つまり「F4の代替」というのは、高いレンズ汎用性を持ち、
MF中心での「趣味の撮影」において高性能が得られるカメラ
と言う事だ。
最も楽しみであった点は、本機Dfでの「非Aiレンズの使用」だ。
しかし、その点についてはミラーレス機でニコンFマウント用の
アダプターを使えば、別に苦労せずとも撮影が可能だ。
だがまあ、銀塩一眼のニコン機を彷彿させるデザインとアナログ
ライクな操作性を持つカメラを使った方がマニアックであろう。
非Aiレンズが使用できるNIKON機は、1988年のF4以来、
Dfは実に25年ぶりの登場なのだ。
さて、到着したNIKON Dfに早速非Aiレンズを装着してみよう。

存在していたが、Dfではロックピンが省略してある。
「よしよし、良い傾向だ、何せニコンの旗艦機級には
F3の時代以降、ずっと過剰なまでの”安全機構”が存在し、
それは”重欠点”そのものであったからな・・」
しかしロック機構が無いのは、そこだけであって、露出補正や
シャッターダイヤルの一部の値、そして露出モード変更には、
銀塩旗艦機以来、あいかわらずの余計なロック機構が存在
している。
そしてISO感度ダイヤルにもロックがある、これは困ったものだ!

あったのだ。それが可能なデジタルカメラは数える程しか無い。
NIKON Df,RICOH GXR,SONY NEX-7系/α7系,FUJIFILM X-T1系
PENTAXのハイパー操作系搭載機のSVモード時(例:K10D,K-5)
PENTAXで機能ダイヤルを持つ機種(例:KP)
アサイナブルダイヤルにISO感度を割りふれるコンパクト機
(例:FUJIFILM XQ1)
他にも若干あったかとは思うが、私は上記にあげた機種群を全て
所有している。と言うかISO感度が常時直接変更できる機種という
点が、私のカメラ購入の際の重要な条件となっているからだ。
で、この機種群の中で「一々ロックを解除しないとISO感度が
変更できない」という不親切な仕様のカメラは、FUJI X-T1と、
本機NIKON Dfだけという残念な状況だ。
このISOダイヤルロックは「ファインダーを覗きながら」では、
左手だけの操作では、まず外れない。
慣れれば左手だけで廻せるかも知れないが、それではまるで
「靴に足を合わせろ!」的な発想で、使い易いとは言い難い。
そして本機DfにはISOダイヤル上にAUTO位置が無く、別メニュー
となっている。これは操作系上の矛盾であるが、これはつまり
M露出モード時にISO感度が追従する機能を目指したNIKON機と
PENTAX機における課題だ(本来、M露出の時だけそうすれば良い、
近年のSONY機では、M露出時のみ、その機能が働く)
ただ、本機では「感度自動制御」をONしておけば、ダイヤルで
ISO感度を変えても、その値を基準として高感度方向に自動で
ISOが上がるので、重欠点では無い。

NIKON Dfに「非Aiレンズ」を装着する、まず絞り値が表示されない。
まあこれは銀塩F4でも同様だ、光学絞り値表示窓があっても、
非Aiレンズでは、それに対応する絞り値が書かれていない。
でも、光学絞り窓はともかく、Dfのファインダー内LCDにも
絞り値が表示されない・・
この場合NIKONデジタル一眼高級機では「レンズ情報手動設定」
を行う、これによりファインダー内に開放絞り値が表示される。
次いでレンズの絞り環を廻す、でも、ファインダー内絞り値表示は
開放のままだ。まあここもやむを得ない、Aiレンズだったらこれで
露出計連動を行えるが、このレンズは「非Ai」だ。
が、この状態でもDfではレンズ側の絞りは開放のままだ。
F4の場合、この状態からは「プレビュー(絞り込み)」ボタンを
押す。ただし、押しにくい位置にあり、しかも重い!

M露出の場合は「プレビューボタンを押しながらシャッターダイヤル
が廻せない」という劣悪な操作性だ。なので現実的にはA露出しか
使用できないが、一々プレビューを押すのはかなり面倒だ。
NIKON Dfではどうか?その点改良されているのだろうか?
Dfの場合「プレビュー(絞り込み)」ボタンは電子的なスイッチ
となっているのでF4より遥かに軽い。しかし、あいかわらず
カメラ前面にあるので、右手のグリップホールデイングに力が
入らないが、まあやむを得ない、なにせNIKON機の操作子の配置
設計は他社機より軽く15年は遅れているのだ。
これ位では驚くには至らない・・

しかし、なんと絞り込んだ写真の方は真っ黒である。
つまり「絞り込み測光」になっておらず、いったいどうやったら
露出値が正しく反映されるのかわからない(汗)
試しに「ライブビューモード」に切り替えて使ってみる。これは
絞り込み測光だ。これだと絞り値に応じて正しい露出値となる。
しかしライブビューのみでは使い勝手が悪い、ライブビューでは
カメラを正しく構える事が出来ないのと、AFでもMFでもピントが
合わないのと、Dfの背面モニターが固定式で動かないので、
お話にならないのだ。
ちなみにMFでのライブビュー時にピントを確認しようとし、
拡大ボタンを押すと便利なのだが、なんと拡大解除ボタンが
存在しないし、シャッター半押しでの拡大解除も出来ない。
ここは、劣悪な操作系で「重欠点」である。
だが、本当にライブビューでしか露出が合わないのだろうか?
慌てて取扱説明書を読んでみる、すると、そこでわかったのは
なんと、レンズ側の絞り環を設定したら、「その絞り値と同じ
数値になるまで、絞り制御用デジタルダイヤルを廻せ」と
書いてあるのだ!
この「二重操作」は、極めてやり難く無駄な操作系だ。
まるで1973年のKONICA AutoReflex T3と同様な操作性である。
そのカメラも露出計で読み取った絞り値と同じ値にまで絞り環を
手動で廻す必要があったのだ。(銀塩一眼第3回記事)
「なんだいこりゃ、40年も昔のカメラと同じレベルか・・?」
と悪態をつきながら、電子ダイヤルで絞り値を設定しようとしたら、
この電子ダイヤルは、露出ステップが「常に1/3段刻み」であった。
つまり、非Aiのレンズ側の絞り幅は、通常1段刻みだ、
レンズ絞り値がファインダー内で一切確認できないのであれば、
手指の感触で、何段絞りを変えたか類推するしかない。
で、左手で絞り値を2段変えたら、右手でダイヤルを2段変えれば
この40年前と同等の酷い二重操作性でも、かろうじて使えない
訳では無い。だが、ダイヤル側が1/3段ステップではダメだ。
片方を1段変えたら、もう1方が3回の操作になる、これではまるで
ワルツのリズムとなり、感覚的なタイミング同期が得られない。
ダイヤルの絞り値変更幅を1/3段→1段にすれば使えるか?と思い
メニューを全部確認する、しかしその設定が、何と存在しない!
説明書を読んでも、それが出来るとは書かれていない。
「もしかしてファームアップがあったか?」と思って調べたら、
発売後既に4年も経っているのに殆どファームアップが無い!
(注:2018年2月に4年ぶりのファームアップがあったが、
特定レンズとの不具合解消だけで、機能面の向上は皆無だ)
「ああ、もうわかった、こういうカメラなのね・・(怒)」
瞬時に全てを察した、このカメラはニコンで設計したのでは無い
という話は予め聞いていた。しかし、この酷い操作系設計や
様々な操作系上の矛盾、そしてロック機構による使い難さや、
ファームアップが殆ど無いなど、これらを総合すると、
このカメラは、頭の中で、こうすれば動く、と設計されていて、
実際にこのNIKON Dfで写真を撮ってみて使い難さや問題点を
洗い出して改良していって発売された物では無いのであろう。
昔からのニコン機の欠点ばかりを集約したような酷いカメラだ。
何故、こうしたカメラが「仕様検討会議」等を通過して市場に
出てきてしまうのか?まあ、そこには何か他者が反論しずらい
「大人の事情」があるのだろうと推察される。

全く練れてないものはいくらでもあった。けど、それらは
頑として改善される事はなかったし、デジタル時代に入って
からも、過剰なハードウェアロック機構は改善の方向があったが
「ソフトウェア操作系」での「安全対策」は大問題であった。
NIKONデジタル機の場合、メニュー全般における操作系概念の
他社機に対する遅れは、もう致命的なレベルであって、これは
「重欠点」と呼べるものであろう。
ファンクション設定が殆ど無く、メニューはただ単にダラダラと
続くだけで、階層構造が不足しているばかりか、使用頻度で分類
する概念もなく、メニューのカスタマイズ性も弱い。
登録した「マイメニュー」はメニューから呼び出すしかなく、
ショートカットが出来ない。そもそもここはメニューセットを
4x4組程度にグルーピングして それを「Iボタン」から
呼び出せるようにすれば良いだけの話であった。

本機Dfの場合は、銀塩時代のNIKON旗艦機(上写真)のように
殆どのダイヤルやレバー類にまで、ハードウェア・ロック機構が
存在するのだ。
ロック機構を電子スイッチにして、ON/OFFを選択できるように
するのはCANON機では30年も前から実現している。
また、近年のOLYMPUSミラーレス機等では押し込むだけでON/OFF
の切り替えが可能な機械的トグル・ロック機構を採用している。
本機Dfでは、何故、常にロックが解除できない状況を「ユーザー
側に強要する」のだろうか?
例えば、露出補正のアナログダイヤルにロックがある事だが、
前後電子ダイヤルを露出補正に使うと、露出補正ダイヤルと
矛盾するので設計がしにくい。けど、このままでは露出補正を
掛けたかったら、常にロックを解除せざるを得ない。
ちなみに、他社機、例えばSONY α7では専用露出補正ダイヤル
を持つが、「ダイヤル露出補正」機能をONとすれば、
専用露出補正ダイヤルが±0の場合にのみ、電子ダイヤルで
露出補正が効き、全体に矛盾なく操作系が成り立っている。
こういう工夫が何故本機Dfではできないのだろうか?
まあ、メニュー操作系に係わる基幹ソフトウェア部分は、
本機の開発チームでは恐らく変更できず、他機ど同等のまま
矛盾が生じたままで製品化が進んでしまったのであろう。
でも、であれば、古臭い「ロック機構」を絶対に外すべきだ。
それから、操作子の配置も問題が多々ある。
例えば、カメラを構えながらでも左手のみで操作できるか?
右手でグリップをホールドしたまま右手指で操作できるか?
等の概念が非常に重要だが、この「動線」への配慮が無い。
(例:前部Fnボタンを押しながら、前後ダイヤルを廻す操作系
は特にNGだ)
関連する話だが、銀塩旗艦機のF3は特に報道分野で良く使われた
つまり、そのカメラは、その用途であれば殆どが手持ち撮影だ、
その際、F3では、カメラを構えながら左手のみで露出補正の
ロックを外す事がほぼ不可能という重欠点を持つカメラであった。
(銀塩一眼第8回記事参照)

F4でもF5でも改善されず、デジタル時代になって少しマシになった
と思ったのだが、それはアナログダイヤルを廃して電子ダイヤルに
なったからロック機構が外れただけであって、根本的な「概念」
そのものは表面化されずに、水面下でくすぶっていただけだ、
本機Dfで、アナログダイヤルが復活採用された結果、その長い間
眠ってた問題点が、またいっきに表面化されてしまった。
せっかくアナログライクで格好良いデザインと操作子を持って
いるのに、この劣悪な操作系では、まったくもってNGだ。
誰がこれを使えるのであろうか? 何もカメラ設定を操作しない
超初級者だろうか・・? あるいは、三脚を立てて、のんびりと
30分に1枚程度撮影をする趣味人であろうか・・?

とても古い設計思想のカメラである事は良くわかった。
だが、本機以外にも操作系が劣悪なカメラは多数存在している。
そんな場合はどうするか?と言えば、問題点を出来るだけ回避
できるレンズや撮影技法を使えば良い。
以下、本機Dfの「重欠点」の回避手法だ
1)非Aiレンズを使う際に、絞りの二重操作を強いられる
→非Aiレンズを使わない事しか対処方法が無い。
2)ISO感度ダイヤルにロック機構があり容易に変更出来ない他、
ISO感度ダイヤル上にAUTO位置が存在せず、「感度自動制御」
設定が深い位置の別メニューとなり、矛盾ど使い難さがある。
→ISO自動制御をONし、ダイヤル側を低ISO設定とし、
ISO上昇方向のみの半自動ISOで使うしか無い。
幸い本機Dfの場合はAUTO ISOの最大追従感度が約20万と高く、
ISO感度が切り替わるシャッター速度を手動で設定できる、
という長所を持つ。
注1:この回避法の概念は初級者には難解だ。
注2:この「低速限界設定」は、何故かマイメニューに
登録不可、という不条理な制限事項がある。
3)露出補正ダイヤルにロック機構が存在し、かつ軍艦部左上に
存在する為、カメラをホールドする右手のみに負担がかかるか、
または、そもそも左手だけでのブラインド操作が困難。
→露出補正を頻繁にしないしか無い。できるだけその必然性の
少ない被写体を選ぶ、あるいは高度なAEロック代用技法で
対応する、又はPC上での輝度補正レタッチで対応する。
注:電子ダイヤルでも露出補正を並列的に可能とする仕様と
すれば改善出来たはず(例:SONYミラーレス機)
4)メニューの階層構造が練れておらず、かつカスタイマイズ性も
かなり弱い。そして、コンパネ的GUI操作系になっていない。
iボタンを用いてショートカットしようとしても、
そのメニュー群が全く変更できないというお粗末さだ。
→学習型または登録型マイメニュー機能が存在するので、それを
上手く利用する。ただし相当に使い難い事は確かだ。
5)ライブビューでの画面拡大解除キーが存在しない。
及びライブビューでの設定変更メニュー項目が変えられない。
→構図確認を諦めて拡大状態のままシャッターを切る、または
一々縮小ボタンを拡大回数の分だけ押して戻すという不便を
受け入れる。
ライブビュー時のメニュー項目が固定である事については、
必ずライブビュー開始前に、全てのカメラ設定を行ってから
ライブビューモードに移行する事。
あるいは固定式背面モニターでは、そもそもライブビューは
「使えないもの」として一切使用しない。
6)各操作子の配置が悪い、すなわち「使用頻度」に対応する
「操作性」の設計が練られていない事と、手指の動線を意識せず
設計している為、操作を行う際に右手や左手にカメラ重量が集中
してホールディングが厳しい、あるいは片手操作が出来ない。
→操作子ダイヤルをできるだけ使わない撮影技法に頼るしかない。
7)測光パターン変更ダイヤル、露出モード変更ダイヤル、そして
AFモード変更ダイヤルのいずれも、ファンダーを覗いたまま
での設定変更が困難で、いったん構えを解き、場合によっては
カメラの向きを変える、あるいはどこかに置く等しないと
設定できない。
→これらの操作子をできるだけ使わないようにするしか無い。
8)カメラ前部にあるプレビューボタンとFnボタンは、これらを
押す為には右手のグリップ・ホールディングを緩めるしか
方法が無く、方向的に力が入り難く、加えてこれらのボタンを
押しながら他のダイヤルを廻し難く、そもそもアサイナブルな
ボタンの数が少ない上に、メニュー項目のショートカットも
出来ない為、自由度が極めて少ない。
→これらの操作子の設定は、プレビュー程度に留めておき、
かつ、できだけこれらに頼らないようにするしか無い。
9)「infoボタン」による設定一覧表示は、直接的に設定変更が
可能になっていない(他社機ではコンパネとしてGUI的に可能)
また「iボタン」による直接設定機能は8項目しかなく、しかも
設定内容が固定で一切変更出来ない。
→もう対処不能である、できるだけメニューから設定変更する
しか無いが、メニュー階層も練れておらず、最悪だ。
10)電子化スクリーンでのMFでのピントの山がわからない、
またファインダーを覗く角度を変えると表示が見え難い。
→MF撮影は行わないか、又はフォーカスエイドに頼る。

使って、しかも何もカメラ設定を変更せずに使うしか無い。
(今回の記事で、安直な現代レンズを使っているのもその為だ)
そう「MFレンズ母艦」とする当初の意図は瓦解したのみならず、
せっかくの格好良いアナログダイヤルは、全て使う事が出来ない
のだ。
まあ、ガンダムでの「ジオン」のエンジニアであれば、きっと
「ダイヤルなんて、ただの飾りです・・」と言った事であろう。

まず、格好良い事だ、これはある意味、「趣味性の高いカメラ」
としては最大の長所であろう。
銀色ボディは銀塩時代は良くあったが、デジタル一眼レフでは
珍しく、ニコンでは本機位か?
そして基本性能が高い事だ。
画素数は1600万画素と控え目であるが、これはフルサイズである
事とあいまって、画素ピッチが大きく、ピクセル面積が広いので、
ダイナミックレンジの増大、すなわち階調表現力やノイズ耐性に
優れる。
感度も広く、拡張時にISO50から高感度側はISO約20万まで広げられ、
趣味撮影においては十分すぎる程の性能である。
これらは画像処理エンジンも含めて旗艦機D4と同等の仕様だ。
ただ、D4と同等と言いながらもドライブ性能は貧弱で連写コマ数
は遅く、最高シャッター速度も1/4000秒でしか無い。
これらはNIKONフルサイズのローエンド機のD600系と同等だ。
次期旗艦機D5の開発で余った旧D4のエンジン部を使いまわし、
高いカタログスペックを維持しながら、低価格機の機構部品を
流用し、コストダウン(利益確保)を実現したという事であろう。
実際に連写を行うと、近年の高速連写機(一眼レフ/ミラーレス)
と比べると、かなりのんびりとした印象がある。
それに連写音は音質的に品が無く、音量も大きいので、静かな
場所では使えない(静音撮影モードが存在するが効果は少ない)

重量は軽量化されていて、本体のみ710gだ。
この重量はD610より軽いのでNIKONフルサイズ機では最軽量か?
が、ボディは大柄で、特に厚みがある為、軽さとあいまって
なんだか「スカスカ」な印象となる。厚みがある事も、せっかく
銀塩機ライクな格好良さが台無しだ。
なお、小型のバッテリーを使用している割には良く持ち、
3000枚や4000枚の撮影は余裕だ。ただ、バッテリー消費を
抑える為には、それなりの技法も必要となるので念の為。

設定の多くを視認できる事は長所である。
ただ、さんざん書いてきたようにロック機構により設定が
やりにくいので長所が帳消しだ。
そしてロック機構があっても、露出補正ダイヤルでは僅かに
接点の「遊び」が生じていて、ロックしたままでも+0.3段等に
露出値が動いてしまう場合がある。
まあ、操作性を追及するならば、全てのダイヤルでのロック機構
は完全に不要である。
なお、ロック機構だけが問題なのでは無い、本機での操作系の
最大の問題は、アナログ操作系(操作子)とデジタル操作系が
上手く融合できていない事だ。
つまり、デジタルダイヤルを廻すと、アナロク操作子との矛盾が
当然発生する、他社では、そこを矛盾なく操作できる仕様として
いる場合があるが、本期Dfでは「アナログ操作子優先」という
安直な解決策を取ってしまっているのだ。
「DfのfはFusion(融合)のf」と言いながら、実際には融合が
出来ていないのは困ったものだ。なお、機種名を「DF」に出来な
かったのはブランドイメージの低下を嫌っての事だと聞く。
それから、若干のエフェクト(画像編集)機能が存在しているが、
一眼レフでこの手の機能は基本的には使い難いものの、前の撮影
画像に遡ってエフェクト処理が出来る点は良く、むしろこの点に
おいては、エフェクトを得意とするPENTAX一眼レフのエフェクト
操作系よりも使い易く感じる。
ここは比較的新しい機能だから操作系が良いのであろうか?
つまり、旧来のカメラ操作に係わる部分がNGで、新しい部分が
OKという事は、基本設計思想が古いのだ。
その他の長所はあまり無い、本来のカメラとしての性能は十分に
高いのに、多数の欠点が目立ってしまい、長所が見えて来ない
事は非常に残念だ。

冒頭に述べたように NIKON F4をあげておこう。
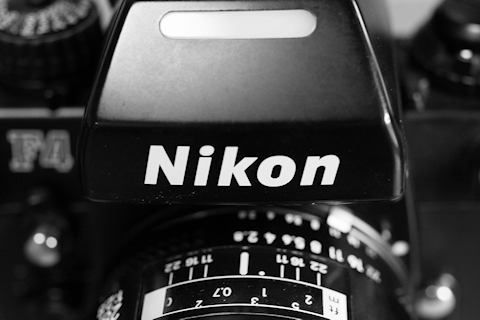
うっとうしいが、ネガフィルムを用いて、MFレンズを装着し、
いっそそれらの操作子の殆どを使わない事で、逆説的に操作系の
課題を回避する事ができた。
F4でも本機同様にファインダー視点の角度を変えると液晶表示が
全く見えなくなる重欠点はあったが、F4のスクリーンのMF性能は、
電子化で性能を落とした本機Dfよりずっとマシだ。

高価でコスパが悪いのも、また大きな問題点となる。
最後にNIKON Df の総合評価をしてみよう。
(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)
【基本・付加性能】★★★★
【描写力・表現力】★★★
【操作性・操作系】★
【マニアック度 】★★★★
【エンジョイ度 】★★
【購入時コスパ 】☆
【完成度(当時)】★★
【歴史的価値 】★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.5点
残念ながら本シリーズ記事での最低評価点になってしまった。
最大の問題は、作る側の「伝えたい事」がちゃんと具現化できて
おらず、その物足りない点が全て低評価に直結している。
アナログダイヤルによる「操作性」の向上を狙ったコンセプトで
ありながら、実際の所ではアナログとデジタルの切り分けや
各種設定の有機的な連携が出来ておらず、結果的に「操作系」を
大幅に悪化させてしまった。本機はフィルム機では無いのだから
フィルム時代の操作性の考え方をそのまま踏襲する事は出来ない
事は言うまでも無い。つまり設計思想が古くて頑固なのだ。
まあ、アナログ感覚を取り入れようとした事自体は評価できるが、
それが上手くまとめられておらず、多数の矛盾が発生してしまって
いて、不要なロック機構と合わせて非常に使い難くなっている。
ただまあ、外観としての格好は極めて良いカメラだ。
写真を撮らずに「持って歩くだけ」、あるいは使えない操作子で
凝った設定をあえてしようとはせずに、カメラまかせでオートで
適当に撮るならば良いであろう。
すなわち本機は「超初級者向けカメラ」であり、中上級者の
「趣味的な玩具」には決して成り得ないカメラだ、という事だ。
冒頭に挙げた下世話な例で言えば、「美人であるから
デートの相手として連れ歩くには最高だが、性格が悪いので、
結婚は絶対にしたくない!」というタイプのカメラであろうか・・

納得が行かない事であろう。
ビギナー目線やシニア目線からすると、本機は、性能が高い、
あるいは使い易いカメラだと錯覚してしまうだろうからだ。
だが、それがとんでもない思い込みである事は、本記事で
様々な問題点を事実として詳しく述べてきた通りである。
残念な結果だが、これが本機Dfの真実だ。
まあでも本機は「美人」である事は確かなので、私の場合は
処分せず、とにかく元が取れるまで使い潰すつもりだ。
既に2万枚以上を本機で撮影している、メゲずに頑張って
もう少しだけ付き合ってみよう・・
次回シリーズ記事に続く。