まだまだ続く今年2017年の「熱い季節」ドラゴンボート記事
だが、今回はODBA(大阪府ドラゴンボート協会)関連大会だ。
ODBAは旧来、大阪の「北港ヨットハーバー」を練習拠点として
活動していたが、3~4年程前に、同施設が様々な政治的事情で
廃止となってしまい、その活動拠点を無くしてしまっていた。
当時ODBAで保有していたドラゴン艇やモーターボート救命艇
等もやむなく譲渡処分。ここ数年間は、琵琶湖の練習施設まで
わざわざ足を伸ばして練習するか、あるいは、大阪近郊の
ドラゴンチームで所有・保管している艇を、お願いして借りて
練習するなど、不便を強いられていた。
いつまでもこの状況ではいけないのは当然だ、練習拠点を探す
必要がある、だが重要な要素としてドラゴンを保管する為の
「艇庫」に空きがある事が条件だ。
大阪・高石市にある漕艇場(大阪府立漕艇センター、旧来から
”堺泉北ドラゴンボート大会”が行われている場所)が候補には
上がっていたが、この漕艇場は学校や民間などのチームや団体で、
様々なボート競技全般で使用する為、多数のカヌー等が保管されて
いて、なかなか空きが無い。今年2017年になって、やっと空きが
出た、という事で、ODBAでは、新しいドラゴン艇を購入し、
ここ大阪府立漕艇センターを新たな練習拠点とする事となった。
![c0032138_17221373.jpg]()
さあ、真新しいドラゴンボート艇2艘が、大阪府立漕艇センターの
艇庫から運び出される。
これは、つい先週、中国から輸送されて来てここに届いたものだ。
「新艇が到着したら進水式と大会(レース)を行う」予定では
あったが、中国からの到着・通関日時がなかなか正確に決まらず、
この時期(ドラゴンは普通、10月くらい迄でシーズンオフだ)
に迄、ずれこんでしまった。
まあでも良い、今日は幸い11月にしては暖かく、17~18℃
あたりまで気温が上がっている。選手達や関係者、そして私も、
寒さを予想してかなり着こんできているが、むしろ暑い位であった。
晴天、風も微風だ、絶好のドラゴン日和と言えよう。
![c0032138_17221381.jpg]()
赤の艇が進水した、ちゃんと浮いている(当たり前か・笑)
大会直前に初めて水に浮かべる段取りであったので
スタッフの間では、
「進水式ならぬ、”浸水”式になったら困るなあ・汗」
「よせやい、縁起でも無い・笑」
と、ブラックジョークの会話が飛ぶ。
まあでも、近年の中国製製品のクオリティは高い、
たとえば私も、カメラ機材として、10本近くの中国製の
交換レンズを所有しているが、品質的には何ら問題無いのだ。
まあ、昔のように「安かろう、悪かろう」のような品質の
製品を作っていたら、今時の国際競争には生き残れない訳だ。
![c0032138_17221344.jpg]()
太鼓の止め具が旧来の同型艇でのプラスチック製から金属製に
変更されている、等のいくつかの細かい差異が、スタッフから
報告される。
ふうむ、やはり、品質改良の為、ロット(=まとめて製造を
する単位の事、1ロットに決まった数字は無く、たとえば大きな
物であれば数十台とか、小さい部品や大量に売れる物等では、
1ロットは数万台(個)にもなる等、製品によりまちまちだ)
・・そのロットによって、細かく仕様をバージョンアップして
いるのであろう。
日本の製品であれば、こういう事(製品の小改良)は昔から
当たり前の事で、設計者やエンジニアはもとより、工場で働く
作業者に至る迄、「QC活動」のような合言葉が定着していた。
「QC」とは「クオリティ・コントロール」の訳語で、
つまり「品質管理」という意味だ。
これには広い目的があり「要求されている製造品質を維持する」
という、作業者に本来必要とされている責任範囲を超えて
「製品そのものを改善していく」というレベルにまで発言権が
及ぶ事がある、つまり製造現場側の意見で、製品がバージョン
アップする事も「QC活動」の上では良くある、という事だ。
まあこういった、旧来(20世紀)には日本の「お家芸」とも
言えたであろう製造のシステムは、現代では世界各国の製造現場
にまで広がっていって、各地で同じような事が行われていると
思われる。そもそも製造に係わる部分の大半が、海外にシフト
していったのは、国内では、工場設置費用(土地代、建築費)や
工場運営の為のコスト(賃金、人件費、光熱費など)が高くなり
すぎて、安価に製造を行う事が困難になってしまっているからだ。
現代では、たとえ「Made in Japan」と言っても、国内で最終的な
組み立てやチェックをするだけで、ほとんど全ての製造工程が
海外生産になっているのが現状だ。だから逆に言えば、現代では
海外での生産が全て品質が低いわけでも無い、という事になる。
ここは旧来(20世紀)に皆が思っていたような「ブランド信奉」
の崩壊にも繋がっている事なので、「市場」を知る上で重要な
要素である。
簡単に言えば、工業製品等では「どこかのメーカーの製品が
特に優れている」というケースは、もはや無いのだ。
すなわち、もし他社より明らかに品質や性能が劣る製品展開を
していたら、市場競争力を失ってしまい、どんな有名メーカー
でも、シェアや売り上げの低下に耐えられない事になるだろう。
仮に、ある時点で品質や性能が劣っていても、他社製品の様子
を見ながら、必ず数年で同レベルにまで追いついてしまう。
結局、その時点では品質や性能の差異は無い、そうしないと
生き残れないから、この競争は工業製品では常に行われている。
「どのメーカーのカメラ(他の工業製品も)が良いのですか?」
と言う質問は、現代では無意味だ。
![c0032138_17221205.jpg]()
これであれば、このまますぐにレース(大会)に移行できる。
![c0032138_17221220.jpg]()
関係者も集まってきた、
まあでも、今日は「進水式」がメインであり、レースの方に
参加するチーム数は少数である。
なにせ先週に艇が到着して、今週のレースだ、そんなに急に
参加チームを募る訳にも行かない。
それと、余談だが、この「漕艇センター」には、「まだ若干
ドラゴン艇が置ける」との話を聞いている。施設運営側の方の
お話では「ドラゴンチーム、大歓迎」との事であるので、
「艇が欲しいが艇庫が無い」と思っているチームには朗報で
あろう。
![c0032138_17222223.jpg]()
この「舟にお酒をかける」という儀式の起源は、物凄く
古くからあり、具体的には、古代ローマ時代から、ワインを
かける事が行われていた模様であるし、近代において大型船の
進水式で「船にシャンパンの瓶をぶつける」のは、18世紀の
イギリスから行われているという事だ。
日本ではシャンパンの他、日本酒を使う場合もある。
次いで「入魂式」(にゅうこんしき)、これは「ドラゴンに
魂を入れる」という意味で行っている儀式であり、習字用の
朱色の墨を筆につけて、ドラゴン艇の龍の目に主を入れる。
主に大阪を中心としたドラゴン大会で昔から良く行われたので
あるが、他地区では殆ど見ないし、近年では大阪の大会でも
「入魂式」は少なくなってしまった。
「入魂式」の最中には、ドラゴン艇にはすでに選手達が
乗り込んでいて、太鼓をかきならし、「ウォーッ」と大声を
あげながら、パドルを高く持ち上げる、という慣わしだ。
![c0032138_17222342.jpg]()
不明なのだが、やっぱ、これをやると、選手達にも関係者にも
「さあ、これからレースだぞ!」と「気合が入る」のは確かだ。
これは例えば、大相撲における「仕切り」のようなものだから、
選手(力士)にも、観客にも、この所作は気持ちを盛り上げる
為には必要な事だ。
できるだけ、この「入魂式」は続けていくのが良い、と個人的
には思っている。
![c0032138_17222312.jpg]()
として行われる。これは今年に限った事ではなく、毎年の主に
秋の季節に実施されるものだ。
例えば昨年等は、琵琶湖の「OPAL」で「大阪府民体育大会」
が行われた、この為、そこを練習拠点とする滋賀県のチームも
多数参加していだき、なかなか盛況であった。
昨年は「Rスポーツマンクラブ」(大阪)と、「小寺製作所」
(滋賀)が決勝で当たり・・
「大阪府民体育大会なのに滋賀県が勝ったらどうするの?」
という心配があったのだが、ここは無難に「R」が優勝、
なんとか面目を保ったのだが、実はそれ以前に、京都府の
チーム「すいすい丸」が同大会で優勝した事もあったのだ。
別に「大阪府民体育大会」だからと言って、大阪のチームが
勝たなくてはならない理由は無いし、他府県のチームが参加
しても何ら問題は無い筈だ、遠慮は無用、どんどんと参加して
いただきたいと思う。
![c0032138_17222290.jpg]()
この艇では初めてのレースだ、ここは重要であり、もし艇に
なんらかの不具合があったら、すぐさま対応や対策を
施さなければならない。
が、その心配は無用で、どちらの艇も、まったく問題なく
快調に進んでいく・・
![c0032138_17222233.jpg]()
大会なので、運営と記録は重要だ。
![c0032138_17223078.jpg]()
配置されていて、スタートの号令、フライングの有無、進路妨害
の有無、その他、公正にレースが行われたか、さらにゴールの
確認、タイムの計測、など、一連の判断が行われる。
・・まあとは言え、どのドラゴン大会でも行っている事と同じだ、
しかも、ODBAのスタッフは皆、ベテランばかりだ、年間で数大会
それを10年、20年と続けているスタッフは少なく無い、だから
各自で平均しても、おそらく100を越える大会運営経験がある
という事で、運営は極めてスムースだ。
実はこれはドラゴンボート大会の隠れた長所であり、
例えば、他のスポーツイベントの運営関係者等が、ドラゴンの
大会を見学に来ると、あまりにスムースな運営に、皆、驚きを
隠せず、口をそろえて「見事な運営です」という感想を述べる
事がかなり多い。
逆に、私などが、他のスポーツイベントを見学した場合に、
細かい点がちゃんと決まっておらず、いきあたりばったりの
運営であったり、突発的に発生した事態に、対応できずに
右往左往している様子を見たりする。
ドラゴン大会においても、様々なアクシデントは勿論発生する、
しかし、大きな事故等になった事は過去1度も無いし、
天候等のレース環境上、あるいはレースにおける進路妨害等の
ルール上における小さい事件があった場合でも、すぐさま公正
に対応して、事無きを得る、という見事な運営手腕だ。
これはドラゴン界が誇りを持って良い事だと常々思っている。
![c0032138_17223025.jpg]()
(最高気温はもっと上がるだろうが、今はまだ午前中だ)
風は微風、と、ドラゴンのレースには極めて好条件だが、
写真撮影は少々厳しい。
この会場は東向きであり、天気が良いと午前中は酷い逆光と
なるのだ。
逆光では、上写真のように対象となる被写体(この場合は
勿論ドラゴン艇だ)が、真っ黒に写ってしまう。
この理由は、周囲の空等の背景の光が強いから、カメラはその
周囲の明るさに合わせて露出を決定してしまう、その状態では
周囲は正しい明るさで撮れるが、相対的にボートは暗く写る。
では、カメラの決めた(提示した)露出値を無視して、
「露出補正」を用いるか、または手動(マニュアル)露出で
撮れば済むのか? と言えば、事はそう単純では無い。
デジタル写真(フィルムも同じ)には、明るいところから
暗いところまで「写せる範囲」というものがあり、それは
一般的に人間が目で見ている明暗差よりも遥かに小さい。
人間にはボートは明るく見えていても、写真にはそれが明るく
写らない訳だ。
で、もしこの状態で、露出補正などをかけて、ボートを普通に
明るく撮ろうとしたら、全体に明るくなるという事で、背景は
完全に真っ白になってしまう、まあ、それでもやむなしとするか
それでは見た目の雰囲気と全然違うから、嫌だ、とするか、
その選択が難しい。
よく「写真は人間が見たままを写すのだ、だから”真を写す”と
書くのだ」という、もっともらしい意見を言う昔の世代の人が
居るが、フィルムでもデジタルでも、それが表現できる明暗差
(ダイナミック・レンジ)を考察すれば、そんな風に見たままに
写す事は絶対に不可能なのだ。
じゃあ、どうするか? まあ時間が過ぎて、逆光条件が
緩和されるのを待つのが基本だ。
だが、今日はレースは午前中だけだ、逆光条件が回避されるのは
午後からであろう、結局、そこまで時間を待てない場合は
できるだけ逆光条件にならないアングルで撮るしか無い、
その為、レースの模様を撮りたくても撮れない場合もあるが、
それはもう、真っ黒のまま写すか、撮らないか、究極の選択だ。
が、レースでは無くても、被写体はいくらでもある筈だ、
選手達のスナップ撮影はもとより、レースに向ったり、
帰ってきたりするポイントとかも逆光にならない場合は多い。
![c0032138_17223057.jpg]()
それは簡単に言えば「できるだけ長い焦点距離の望遠レンズを
使う事」である。
先に説明した「逆光」となる条件では、「背景や周囲がとても
明るく、被写体が小さくて、相対的に暗くなってしまう」
が問題であった。
つまり、被写体が小さいから、背景の明るい部分が多くなって
しまうのだ。だから、被写体をできるだけ大きく、ものすごく
大きく撮って、背景等ほとんど入らないようにしてしまえば
カメラの露出計は、その大きな被写体(ボートや選手)を
主体に、正しい明るさで撮ろうとする為、逆光になりにくい。
今日私が使用しているレンズはSIGMA C100-400mm/f5-6.3
と言う小型軽量の超望遠ズームで、これをAPS-Cサイズの
センサーを持つ CANON EOS 7D MarkⅡに装着している。
これを最大望遠にした場合、フルサイズ(銀塩35mm判)換算で
約640mm の画角(焦点距離)に相当する。
具体的には、縦横比3対2での撮影の場合、640mm相当での
対角線の画角(写る角度)は、約3.8度となる。
この640mm相当の画角だと、たとえば今回使用のドラゴン・
スモール艇の全長を約9mとすれば、カメラを横位置で構えると
160m先で丁度、写真の真横いっぱいにドラゴン艇が写る。
けど、それではまだ背景がスカスカで、逆光を回避できない、
実際には、画面いっぱいに乗艇選手達が写る距離、つまりは
撮影距離60m程度(これで3.3m横幅の範囲が写る)くらいの
近さで無いと、逆光は回避できない。
あるいは、400mm級超望遠よりさらにテレ端(望遠端)の長い
500mm級、600mm級の超望遠ズームを使うか?という選択だが、
これらの機材は非常に重く、手持ちでの長時間の撮影が困難だ。
(今年は、一部のドラゴン選手、またはチームの応援撮影選手で
600mmの超望遠を持っている人を3人見かけた、これは有効な
機材ではあるが、相当に重たい。だから特定のチームのレース
のみ短時間だけならば撮れるが「1日中はかなり大変ですよ」と
それぞれのオーナーカメラマンには伝えている)
なお、重たいのが大変だと言っても三脚や一脚は使用できない、
撮らなければならない被写体は、様々な位置の様々なアングルで
あるからだし、レースにおけるチームの組み合わせによっても、
レースの展開(順位等)によっても推奨撮影位置は変化するのだ。
よって、一箇所に留まる訳にはいかず、三脚で撮影範囲を予め
固定する事も出来ない、だから、手持ちで無いと、ドラゴンや
ペーロン等、各種のボートのレースの撮影は不可能だ。
他の逆光回避手段は、近年のごく一部のデジタル一眼レフや
多くのミラーレス機で採用されている「デジタルズーム機能」
を使う方法がある。
この機能では、見かけ上、写る範囲を狭くして、背景を無くし、
明るさを適正にし、逆光を回避する事に有効だ。
私はこの手法は頻繁に用い、特に、さらに逆光条件の酷い
夏の琵琶湖の大会では、このデジタルズーム機能を多用する。
ただ、今回使用のCANON EOS 7D MarkⅡでは、残念ながら
この機能が入っていない(カメラの構造上、搭載が困難)
で、この機能を使うと一般に画素数が減るので、初級中級者は
嫌うのであるが、逆光で撮れないならば、そもそも写真を撮る
意味が無い、あれこれ言わずに、有効な機能は全て使うべきだ。
さて、様々な対策を施したところで、撮影が難しい事は
変わりが無い、一応、予選レースは一通り撮っているが、
本記事での紹介は最小限とする。
余談が長くなったが、今日のレースは6レース行われた、
次は、いよいよ本日ラストの決勝戦(順位決定戦)だ。
![c0032138_17222985.jpg]()
(レーン順、手前が1レーン)
1:Rスポーツマンクラブ
2:近畿車輛電龍・チーム未来(混成)
1レーンの「R」は、超ベテランである。メンバーの平均
年齢は現役チームとしては最も高いと思われるが、昨年の
本大会で優勝している、つまり「百戦錬磨」のチームである。
例年、琵琶湖で行われる「グランドシニア大会」は、年齢
ハンデ戦なので「R」に有利だ。毎年優勝候補筆頭であり、
事実、勝って来ているのだが、今年のその大会は、あいにく
台風の来襲で中止になってしまった。
今年はまだ勝利(優勝)が無い、本大会で是非とも勝って、
昨年に引き続いて2連覇、と行きたいところであろう。
2レーンは混成チームだが、メンバーの大半は「近畿車輛電龍」
である。
「近畿車輛電龍」は、2012年の本大会で優勝しているのだが、
同チームは、本来「近畿車輛」という電車の車体(車両)を
製造する会社の企業チームである。
本大会での優勝当時では、東南アジアからの若い外国人研修生
がメンバーの中心で、かなりパワフルなチームであった。
が、海外研修生達は2013~2015年にかけて研修終了で帰国し、
その後は近畿車輛への新入社員(日本人達)を入れて、チームを
再編していた時期が続いた。2015~2016年における各大会は、
少々苦戦していたが、今年2017年くらいになって、ようやく新人
選手達も慣れて実力もつき、往時のチームの勢いを取り戻そうと
している状態だ。
さあ、レーススタートだ。このレースは、接戦が予想される、
撮影場所は、170m地点(200m戦のゴール前、数10m)あたり
にしよう。
![c0032138_17223042.jpg]()
写真ではほぼ同等か、手前1レーンの「R」が有利のように
見えるが、これは「角度がついた撮影」である。
ゴール地点から見れば、奥の2レーン「近畿車輛電龍」が
若干前に出ているように見える筈で、これが真の順位だ。
つまり「撮影アングルの錯覚」を利用している訳だ。
実際のところは、予選タイムなどを参考にすると「近車」が
若干速い事がデータとして出ていたので、私の予想では
決勝は1~2秒程度の差で「近車」が前になると思っていた。
しかし「接戦のように撮りたい」が為に、あえて、この地点を
選んで撮影していた。
![c0032138_17223607.jpg]()
5年ぶりの優勝、おめでとうございます!
本大会は、いきなりの開催やシーズンオフなど、様々な理由が
あって参加チーム数が少なかったりしたし、また混成チームでも
あったが、まあ、これは公式戦であるので、優勝としての記録が
残る事は確かである。
![c0032138_17223629.jpg]()
ここには歴代のチーム名が書かれていて、このトロフィーは
後に返却する。
副賞は、本大会独自の「お菓子詰め合わせであり」全チームに
授与されるが、勿論順位によってその量は異なる。
![c0032138_17223587.jpg]()
3位ではあっても、持ちきれないほどの大量のお菓子だ。
なお、1位はもっと凄い量で、なかなかのものだ。
![c0032138_17223508.jpg]()
「縮小」(注:”圧縮”では無い。解像度(画素数)を下げるのが
”縮小”であり、同じ解像度のまま容量を下げるのが”圧縮”だ)
をしているので、輪郭線が強くなりすぎる「縮小効果」が出て
しまっている。つまり画質が極端に低下した状態に見えるが、
もうこれはやむを得ない。
「縮小効果」は一眼レフの背面モニター上等では適宜に働き、
画素数が大きいカメラの方が縮小されて綺麗に見える事がある
しかし、大画素のままWEBやSNS上に掲載すると、表示される際に
大きく縮小されてしまい、画質が低下してしまう場合がある。
結局、表示方式(または印刷サイズなども含む)に応じて
適正な解像度(画素数)や、縮小の限界点があるし、ブラウザ等
で勝手に縮小されないように、予め必要なサイズに自身で縮小
するなど、色々と対応や、考えるべき事は多いのであるが、
世間一般には「画素数が大きいカメラの方が良く写る」という
誤解が蔓延している。本来ならば、画素数は写真の用途や閲覧
方法に応じて、適正に設定しないとならないのだ。
なお、上写真においては、ODBA(大阪協会)へ送付した分は
個々の選手の顔が十分に見分けられる程度の解像度(およそ
600万画素)となっているが、FaceBook等からのダウンロードの
場合、解像度が100~200万画素程度に制限されてしまうので、
その点のみ要注意だ(印刷用途等で高解像度データが必要ならば、
別途オリジナルの画像を入手するしか無い、という意味)
![c0032138_17223609.jpg]()
準優勝の「Rスポーツマンクラブ」
運営側では、メンバーで分配しやすいように、小分けされた袋に
入っているものを選んで賞品としているとの事。
まあ、お酒(ビール等)でも良いのだろうが、飲まない選手も
居るだろうし、お酒では意外に単価も高くつく、ここODBAの、
近年の伝統では、賞品は「お菓子」となっているのだ。
さて「R」から、私も賞品の「お裾分け」を頂いたところで
帰途につくとしよう。
例年、この大会では、終了後に「BBQ」が行われる慣習だが、
今回は、さすがに先週に艇の到着で開催が今日、という状況では
「BBQ」の準備も、ままならなかった、との事だ。
これまで、活動拠点が無かった時期が数年続いたが、他の場所
で大会をやっても「BBQ」は会場環境的等の理由で出来なかった。
本会場(大阪府立漕艇センター)は「BBQ」が可能な場所だ。
来年以降の本大会での「BBQ」の復活を期待するとともに、
来シーズンに向けては、やっと新艇や活動拠点が揃ったことで、
よりいっそう、ODBA所属チームの実力アップや、新メンバーの
補充を期待する点、それから、イベント企画(体験乗船等)の
自由度も高くなるので、それらもまた適宜考えていただきたいと
思う次第だ。
また、この「漕艇センター」において行われる「堺泉北大会」
では、旧来4艘建てであったのが、この新艇を追加して、
6艘建てレースも可能となる、広い会場なので、そういう事も
また考えていただければ幸いだ。
さて、ドラゴンボートとしての大会は、これで本シーズンは
終了であるが、まだ1つドラゴン関連イベントが残っている。
次回記事では、それについて紹介する予定だ。
だが、今回はODBA(大阪府ドラゴンボート協会)関連大会だ。
ODBAは旧来、大阪の「北港ヨットハーバー」を練習拠点として
活動していたが、3~4年程前に、同施設が様々な政治的事情で
廃止となってしまい、その活動拠点を無くしてしまっていた。
当時ODBAで保有していたドラゴン艇やモーターボート救命艇
等もやむなく譲渡処分。ここ数年間は、琵琶湖の練習施設まで
わざわざ足を伸ばして練習するか、あるいは、大阪近郊の
ドラゴンチームで所有・保管している艇を、お願いして借りて
練習するなど、不便を強いられていた。
いつまでもこの状況ではいけないのは当然だ、練習拠点を探す
必要がある、だが重要な要素としてドラゴンを保管する為の
「艇庫」に空きがある事が条件だ。
大阪・高石市にある漕艇場(大阪府立漕艇センター、旧来から
”堺泉北ドラゴンボート大会”が行われている場所)が候補には
上がっていたが、この漕艇場は学校や民間などのチームや団体で、
様々なボート競技全般で使用する為、多数のカヌー等が保管されて
いて、なかなか空きが無い。今年2017年になって、やっと空きが
出た、という事で、ODBAでは、新しいドラゴン艇を購入し、
ここ大阪府立漕艇センターを新たな練習拠点とする事となった。

さあ、真新しいドラゴンボート艇2艘が、大阪府立漕艇センターの
艇庫から運び出される。
これは、つい先週、中国から輸送されて来てここに届いたものだ。
「新艇が到着したら進水式と大会(レース)を行う」予定では
あったが、中国からの到着・通関日時がなかなか正確に決まらず、
この時期(ドラゴンは普通、10月くらい迄でシーズンオフだ)
に迄、ずれこんでしまった。
まあでも良い、今日は幸い11月にしては暖かく、17~18℃
あたりまで気温が上がっている。選手達や関係者、そして私も、
寒さを予想してかなり着こんできているが、むしろ暑い位であった。
晴天、風も微風だ、絶好のドラゴン日和と言えよう。

赤の艇が進水した、ちゃんと浮いている(当たり前か・笑)
大会直前に初めて水に浮かべる段取りであったので
スタッフの間では、
「進水式ならぬ、”浸水”式になったら困るなあ・汗」
「よせやい、縁起でも無い・笑」
と、ブラックジョークの会話が飛ぶ。
まあでも、近年の中国製製品のクオリティは高い、
たとえば私も、カメラ機材として、10本近くの中国製の
交換レンズを所有しているが、品質的には何ら問題無いのだ。
まあ、昔のように「安かろう、悪かろう」のような品質の
製品を作っていたら、今時の国際競争には生き残れない訳だ。

太鼓の止め具が旧来の同型艇でのプラスチック製から金属製に
変更されている、等のいくつかの細かい差異が、スタッフから
報告される。
ふうむ、やはり、品質改良の為、ロット(=まとめて製造を
する単位の事、1ロットに決まった数字は無く、たとえば大きな
物であれば数十台とか、小さい部品や大量に売れる物等では、
1ロットは数万台(個)にもなる等、製品によりまちまちだ)
・・そのロットによって、細かく仕様をバージョンアップして
いるのであろう。
日本の製品であれば、こういう事(製品の小改良)は昔から
当たり前の事で、設計者やエンジニアはもとより、工場で働く
作業者に至る迄、「QC活動」のような合言葉が定着していた。
「QC」とは「クオリティ・コントロール」の訳語で、
つまり「品質管理」という意味だ。
これには広い目的があり「要求されている製造品質を維持する」
という、作業者に本来必要とされている責任範囲を超えて
「製品そのものを改善していく」というレベルにまで発言権が
及ぶ事がある、つまり製造現場側の意見で、製品がバージョン
アップする事も「QC活動」の上では良くある、という事だ。
まあこういった、旧来(20世紀)には日本の「お家芸」とも
言えたであろう製造のシステムは、現代では世界各国の製造現場
にまで広がっていって、各地で同じような事が行われていると
思われる。そもそも製造に係わる部分の大半が、海外にシフト
していったのは、国内では、工場設置費用(土地代、建築費)や
工場運営の為のコスト(賃金、人件費、光熱費など)が高くなり
すぎて、安価に製造を行う事が困難になってしまっているからだ。
現代では、たとえ「Made in Japan」と言っても、国内で最終的な
組み立てやチェックをするだけで、ほとんど全ての製造工程が
海外生産になっているのが現状だ。だから逆に言えば、現代では
海外での生産が全て品質が低いわけでも無い、という事になる。
ここは旧来(20世紀)に皆が思っていたような「ブランド信奉」
の崩壊にも繋がっている事なので、「市場」を知る上で重要な
要素である。
簡単に言えば、工業製品等では「どこかのメーカーの製品が
特に優れている」というケースは、もはや無いのだ。
すなわち、もし他社より明らかに品質や性能が劣る製品展開を
していたら、市場競争力を失ってしまい、どんな有名メーカー
でも、シェアや売り上げの低下に耐えられない事になるだろう。
仮に、ある時点で品質や性能が劣っていても、他社製品の様子
を見ながら、必ず数年で同レベルにまで追いついてしまう。
結局、その時点では品質や性能の差異は無い、そうしないと
生き残れないから、この競争は工業製品では常に行われている。
「どのメーカーのカメラ(他の工業製品も)が良いのですか?」
と言う質問は、現代では無意味だ。

これであれば、このまますぐにレース(大会)に移行できる。

関係者も集まってきた、
まあでも、今日は「進水式」がメインであり、レースの方に
参加するチーム数は少数である。
なにせ先週に艇が到着して、今週のレースだ、そんなに急に
参加チームを募る訳にも行かない。
それと、余談だが、この「漕艇センター」には、「まだ若干
ドラゴン艇が置ける」との話を聞いている。施設運営側の方の
お話では「ドラゴンチーム、大歓迎」との事であるので、
「艇が欲しいが艇庫が無い」と思っているチームには朗報で
あろう。

この「舟にお酒をかける」という儀式の起源は、物凄く
古くからあり、具体的には、古代ローマ時代から、ワインを
かける事が行われていた模様であるし、近代において大型船の
進水式で「船にシャンパンの瓶をぶつける」のは、18世紀の
イギリスから行われているという事だ。
日本ではシャンパンの他、日本酒を使う場合もある。
次いで「入魂式」(にゅうこんしき)、これは「ドラゴンに
魂を入れる」という意味で行っている儀式であり、習字用の
朱色の墨を筆につけて、ドラゴン艇の龍の目に主を入れる。
主に大阪を中心としたドラゴン大会で昔から良く行われたので
あるが、他地区では殆ど見ないし、近年では大阪の大会でも
「入魂式」は少なくなってしまった。
「入魂式」の最中には、ドラゴン艇にはすでに選手達が
乗り込んでいて、太鼓をかきならし、「ウォーッ」と大声を
あげながら、パドルを高く持ち上げる、という慣わしだ。

不明なのだが、やっぱ、これをやると、選手達にも関係者にも
「さあ、これからレースだぞ!」と「気合が入る」のは確かだ。
これは例えば、大相撲における「仕切り」のようなものだから、
選手(力士)にも、観客にも、この所作は気持ちを盛り上げる
為には必要な事だ。
できるだけ、この「入魂式」は続けていくのが良い、と個人的
には思っている。
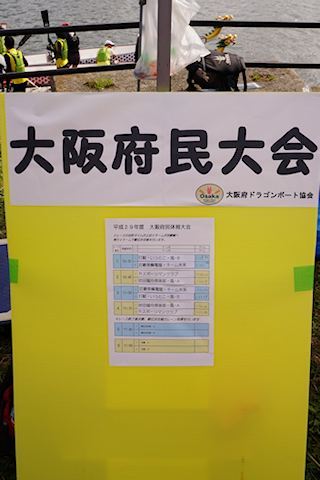
として行われる。これは今年に限った事ではなく、毎年の主に
秋の季節に実施されるものだ。
例えば昨年等は、琵琶湖の「OPAL」で「大阪府民体育大会」
が行われた、この為、そこを練習拠点とする滋賀県のチームも
多数参加していだき、なかなか盛況であった。
昨年は「Rスポーツマンクラブ」(大阪)と、「小寺製作所」
(滋賀)が決勝で当たり・・
「大阪府民体育大会なのに滋賀県が勝ったらどうするの?」
という心配があったのだが、ここは無難に「R」が優勝、
なんとか面目を保ったのだが、実はそれ以前に、京都府の
チーム「すいすい丸」が同大会で優勝した事もあったのだ。
別に「大阪府民体育大会」だからと言って、大阪のチームが
勝たなくてはならない理由は無いし、他府県のチームが参加
しても何ら問題は無い筈だ、遠慮は無用、どんどんと参加して
いただきたいと思う。

この艇では初めてのレースだ、ここは重要であり、もし艇に
なんらかの不具合があったら、すぐさま対応や対策を
施さなければならない。
が、その心配は無用で、どちらの艇も、まったく問題なく
快調に進んでいく・・

大会なので、運営と記録は重要だ。

配置されていて、スタートの号令、フライングの有無、進路妨害
の有無、その他、公正にレースが行われたか、さらにゴールの
確認、タイムの計測、など、一連の判断が行われる。
・・まあとは言え、どのドラゴン大会でも行っている事と同じだ、
しかも、ODBAのスタッフは皆、ベテランばかりだ、年間で数大会
それを10年、20年と続けているスタッフは少なく無い、だから
各自で平均しても、おそらく100を越える大会運営経験がある
という事で、運営は極めてスムースだ。
実はこれはドラゴンボート大会の隠れた長所であり、
例えば、他のスポーツイベントの運営関係者等が、ドラゴンの
大会を見学に来ると、あまりにスムースな運営に、皆、驚きを
隠せず、口をそろえて「見事な運営です」という感想を述べる
事がかなり多い。
逆に、私などが、他のスポーツイベントを見学した場合に、
細かい点がちゃんと決まっておらず、いきあたりばったりの
運営であったり、突発的に発生した事態に、対応できずに
右往左往している様子を見たりする。
ドラゴン大会においても、様々なアクシデントは勿論発生する、
しかし、大きな事故等になった事は過去1度も無いし、
天候等のレース環境上、あるいはレースにおける進路妨害等の
ルール上における小さい事件があった場合でも、すぐさま公正
に対応して、事無きを得る、という見事な運営手腕だ。
これはドラゴン界が誇りを持って良い事だと常々思っている。

(最高気温はもっと上がるだろうが、今はまだ午前中だ)
風は微風、と、ドラゴンのレースには極めて好条件だが、
写真撮影は少々厳しい。
この会場は東向きであり、天気が良いと午前中は酷い逆光と
なるのだ。
逆光では、上写真のように対象となる被写体(この場合は
勿論ドラゴン艇だ)が、真っ黒に写ってしまう。
この理由は、周囲の空等の背景の光が強いから、カメラはその
周囲の明るさに合わせて露出を決定してしまう、その状態では
周囲は正しい明るさで撮れるが、相対的にボートは暗く写る。
では、カメラの決めた(提示した)露出値を無視して、
「露出補正」を用いるか、または手動(マニュアル)露出で
撮れば済むのか? と言えば、事はそう単純では無い。
デジタル写真(フィルムも同じ)には、明るいところから
暗いところまで「写せる範囲」というものがあり、それは
一般的に人間が目で見ている明暗差よりも遥かに小さい。
人間にはボートは明るく見えていても、写真にはそれが明るく
写らない訳だ。
で、もしこの状態で、露出補正などをかけて、ボートを普通に
明るく撮ろうとしたら、全体に明るくなるという事で、背景は
完全に真っ白になってしまう、まあ、それでもやむなしとするか
それでは見た目の雰囲気と全然違うから、嫌だ、とするか、
その選択が難しい。
よく「写真は人間が見たままを写すのだ、だから”真を写す”と
書くのだ」という、もっともらしい意見を言う昔の世代の人が
居るが、フィルムでもデジタルでも、それが表現できる明暗差
(ダイナミック・レンジ)を考察すれば、そんな風に見たままに
写す事は絶対に不可能なのだ。
じゃあ、どうするか? まあ時間が過ぎて、逆光条件が
緩和されるのを待つのが基本だ。
だが、今日はレースは午前中だけだ、逆光条件が回避されるのは
午後からであろう、結局、そこまで時間を待てない場合は
できるだけ逆光条件にならないアングルで撮るしか無い、
その為、レースの模様を撮りたくても撮れない場合もあるが、
それはもう、真っ黒のまま写すか、撮らないか、究極の選択だ。
が、レースでは無くても、被写体はいくらでもある筈だ、
選手達のスナップ撮影はもとより、レースに向ったり、
帰ってきたりするポイントとかも逆光にならない場合は多い。

それは簡単に言えば「できるだけ長い焦点距離の望遠レンズを
使う事」である。
先に説明した「逆光」となる条件では、「背景や周囲がとても
明るく、被写体が小さくて、相対的に暗くなってしまう」
が問題であった。
つまり、被写体が小さいから、背景の明るい部分が多くなって
しまうのだ。だから、被写体をできるだけ大きく、ものすごく
大きく撮って、背景等ほとんど入らないようにしてしまえば
カメラの露出計は、その大きな被写体(ボートや選手)を
主体に、正しい明るさで撮ろうとする為、逆光になりにくい。
今日私が使用しているレンズはSIGMA C100-400mm/f5-6.3
と言う小型軽量の超望遠ズームで、これをAPS-Cサイズの
センサーを持つ CANON EOS 7D MarkⅡに装着している。
これを最大望遠にした場合、フルサイズ(銀塩35mm判)換算で
約640mm の画角(焦点距離)に相当する。
具体的には、縦横比3対2での撮影の場合、640mm相当での
対角線の画角(写る角度)は、約3.8度となる。
この640mm相当の画角だと、たとえば今回使用のドラゴン・
スモール艇の全長を約9mとすれば、カメラを横位置で構えると
160m先で丁度、写真の真横いっぱいにドラゴン艇が写る。
けど、それではまだ背景がスカスカで、逆光を回避できない、
実際には、画面いっぱいに乗艇選手達が写る距離、つまりは
撮影距離60m程度(これで3.3m横幅の範囲が写る)くらいの
近さで無いと、逆光は回避できない。
あるいは、400mm級超望遠よりさらにテレ端(望遠端)の長い
500mm級、600mm級の超望遠ズームを使うか?という選択だが、
これらの機材は非常に重く、手持ちでの長時間の撮影が困難だ。
(今年は、一部のドラゴン選手、またはチームの応援撮影選手で
600mmの超望遠を持っている人を3人見かけた、これは有効な
機材ではあるが、相当に重たい。だから特定のチームのレース
のみ短時間だけならば撮れるが「1日中はかなり大変ですよ」と
それぞれのオーナーカメラマンには伝えている)
なお、重たいのが大変だと言っても三脚や一脚は使用できない、
撮らなければならない被写体は、様々な位置の様々なアングルで
あるからだし、レースにおけるチームの組み合わせによっても、
レースの展開(順位等)によっても推奨撮影位置は変化するのだ。
よって、一箇所に留まる訳にはいかず、三脚で撮影範囲を予め
固定する事も出来ない、だから、手持ちで無いと、ドラゴンや
ペーロン等、各種のボートのレースの撮影は不可能だ。
他の逆光回避手段は、近年のごく一部のデジタル一眼レフや
多くのミラーレス機で採用されている「デジタルズーム機能」
を使う方法がある。
この機能では、見かけ上、写る範囲を狭くして、背景を無くし、
明るさを適正にし、逆光を回避する事に有効だ。
私はこの手法は頻繁に用い、特に、さらに逆光条件の酷い
夏の琵琶湖の大会では、このデジタルズーム機能を多用する。
ただ、今回使用のCANON EOS 7D MarkⅡでは、残念ながら
この機能が入っていない(カメラの構造上、搭載が困難)
で、この機能を使うと一般に画素数が減るので、初級中級者は
嫌うのであるが、逆光で撮れないならば、そもそも写真を撮る
意味が無い、あれこれ言わずに、有効な機能は全て使うべきだ。
さて、様々な対策を施したところで、撮影が難しい事は
変わりが無い、一応、予選レースは一通り撮っているが、
本記事での紹介は最小限とする。
余談が長くなったが、今日のレースは6レース行われた、
次は、いよいよ本日ラストの決勝戦(順位決定戦)だ。

(レーン順、手前が1レーン)
1:Rスポーツマンクラブ
2:近畿車輛電龍・チーム未来(混成)
1レーンの「R」は、超ベテランである。メンバーの平均
年齢は現役チームとしては最も高いと思われるが、昨年の
本大会で優勝している、つまり「百戦錬磨」のチームである。
例年、琵琶湖で行われる「グランドシニア大会」は、年齢
ハンデ戦なので「R」に有利だ。毎年優勝候補筆頭であり、
事実、勝って来ているのだが、今年のその大会は、あいにく
台風の来襲で中止になってしまった。
今年はまだ勝利(優勝)が無い、本大会で是非とも勝って、
昨年に引き続いて2連覇、と行きたいところであろう。
2レーンは混成チームだが、メンバーの大半は「近畿車輛電龍」
である。
「近畿車輛電龍」は、2012年の本大会で優勝しているのだが、
同チームは、本来「近畿車輛」という電車の車体(車両)を
製造する会社の企業チームである。
本大会での優勝当時では、東南アジアからの若い外国人研修生
がメンバーの中心で、かなりパワフルなチームであった。
が、海外研修生達は2013~2015年にかけて研修終了で帰国し、
その後は近畿車輛への新入社員(日本人達)を入れて、チームを
再編していた時期が続いた。2015~2016年における各大会は、
少々苦戦していたが、今年2017年くらいになって、ようやく新人
選手達も慣れて実力もつき、往時のチームの勢いを取り戻そうと
している状態だ。
さあ、レーススタートだ。このレースは、接戦が予想される、
撮影場所は、170m地点(200m戦のゴール前、数10m)あたり
にしよう。

写真ではほぼ同等か、手前1レーンの「R」が有利のように
見えるが、これは「角度がついた撮影」である。
ゴール地点から見れば、奥の2レーン「近畿車輛電龍」が
若干前に出ているように見える筈で、これが真の順位だ。
つまり「撮影アングルの錯覚」を利用している訳だ。
実際のところは、予選タイムなどを参考にすると「近車」が
若干速い事がデータとして出ていたので、私の予想では
決勝は1~2秒程度の差で「近車」が前になると思っていた。
しかし「接戦のように撮りたい」が為に、あえて、この地点を
選んで撮影していた。

5年ぶりの優勝、おめでとうございます!
本大会は、いきなりの開催やシーズンオフなど、様々な理由が
あって参加チーム数が少なかったりしたし、また混成チームでも
あったが、まあ、これは公式戦であるので、優勝としての記録が
残る事は確かである。

ここには歴代のチーム名が書かれていて、このトロフィーは
後に返却する。
副賞は、本大会独自の「お菓子詰め合わせであり」全チームに
授与されるが、勿論順位によってその量は異なる。

3位ではあっても、持ちきれないほどの大量のお菓子だ。
なお、1位はもっと凄い量で、なかなかのものだ。

「縮小」(注:”圧縮”では無い。解像度(画素数)を下げるのが
”縮小”であり、同じ解像度のまま容量を下げるのが”圧縮”だ)
をしているので、輪郭線が強くなりすぎる「縮小効果」が出て
しまっている。つまり画質が極端に低下した状態に見えるが、
もうこれはやむを得ない。
「縮小効果」は一眼レフの背面モニター上等では適宜に働き、
画素数が大きいカメラの方が縮小されて綺麗に見える事がある
しかし、大画素のままWEBやSNS上に掲載すると、表示される際に
大きく縮小されてしまい、画質が低下してしまう場合がある。
結局、表示方式(または印刷サイズなども含む)に応じて
適正な解像度(画素数)や、縮小の限界点があるし、ブラウザ等
で勝手に縮小されないように、予め必要なサイズに自身で縮小
するなど、色々と対応や、考えるべき事は多いのであるが、
世間一般には「画素数が大きいカメラの方が良く写る」という
誤解が蔓延している。本来ならば、画素数は写真の用途や閲覧
方法に応じて、適正に設定しないとならないのだ。
なお、上写真においては、ODBA(大阪協会)へ送付した分は
個々の選手の顔が十分に見分けられる程度の解像度(およそ
600万画素)となっているが、FaceBook等からのダウンロードの
場合、解像度が100~200万画素程度に制限されてしまうので、
その点のみ要注意だ(印刷用途等で高解像度データが必要ならば、
別途オリジナルの画像を入手するしか無い、という意味)

準優勝の「Rスポーツマンクラブ」
運営側では、メンバーで分配しやすいように、小分けされた袋に
入っているものを選んで賞品としているとの事。
まあ、お酒(ビール等)でも良いのだろうが、飲まない選手も
居るだろうし、お酒では意外に単価も高くつく、ここODBAの、
近年の伝統では、賞品は「お菓子」となっているのだ。
さて「R」から、私も賞品の「お裾分け」を頂いたところで
帰途につくとしよう。
例年、この大会では、終了後に「BBQ」が行われる慣習だが、
今回は、さすがに先週に艇の到着で開催が今日、という状況では
「BBQ」の準備も、ままならなかった、との事だ。
これまで、活動拠点が無かった時期が数年続いたが、他の場所
で大会をやっても「BBQ」は会場環境的等の理由で出来なかった。
本会場(大阪府立漕艇センター)は「BBQ」が可能な場所だ。
来年以降の本大会での「BBQ」の復活を期待するとともに、
来シーズンに向けては、やっと新艇や活動拠点が揃ったことで、
よりいっそう、ODBA所属チームの実力アップや、新メンバーの
補充を期待する点、それから、イベント企画(体験乗船等)の
自由度も高くなるので、それらもまた適宜考えていただきたいと
思う次第だ。
また、この「漕艇センター」において行われる「堺泉北大会」
では、旧来4艘建てであったのが、この新艇を追加して、
6艘建てレースも可能となる、広い会場なので、そういう事も
また考えていただければ幸いだ。
さて、ドラゴンボートとしての大会は、これで本シーズンは
終了であるが、まだ1つドラゴン関連イベントが残っている。
次回記事では、それについて紹介する予定だ。