コストパフォーマンスに優れたマニアックなレンズを
カテゴリー別に紹介するシリーズの第9回目は、
MFズームレンズを4本紹介していこう。
AFズームに並びMFのズームも非常に広いカテゴリーだ。
銀塩MF時代初期の1960~1970年代前半の一眼レフには、
単焦点レンズを組み合わせる事が一般的だったが、
1970年代後半~1980年代前半に銀塩MF一眼レフが一般
ユーザーレベルにまで普及したのは、ある意味、MFズーム
レンズの進歩も、その背景にあったかも知れない。
ただ、現代2010年代の中古市場では、それらMF一眼レフの
普及に非常に寄与したMFズームレンズ群は、用途も無く、
マニアにさえも人気が無い為、実際の中古相場は、殆どが
二束三文という状況だ。
そういう意味では、多くのMFズームレンズは「コスパが良い」
と言える。さて、どのレンズを紹介するべきか?迷う所では
あるが、まあ、順次紹介していこう・・
まず、最初のシステム、
![c0032138_19112602.jpg]()
レンズは、CANON New FD 70-210mm/f4
(中古購入価格 2,000円)
ミラーレス・マニアックス第52回記事で紹介した、
1980年代のMF望遠ズームレンズ。
![c0032138_19112628.jpg]()
まず、その描写力、これは他の同時代の同様なスペックの
レンズ(多数ある)と比べても、なかなか優れている。
解像感が高く、ボケ質破綻も出にくく、逆光耐性も良い。
そして直進ズームであり、ズーミングとピント合わせの
操作が同時にできる。しかもズーミングで全長が変化しない
タイプなので、重心が移動することもない、これらは
MFズームならではの構造であり極めて使い易い。
さらには、開放f値がf4固定であり、ズーミングでf値が
変動しないメリットも大きい。
最短撮影距離も1.2mと短く、さらにマクロモードで
広角端でおよそ50cm以下程度まで寄ることができる。
![c0032138_19112604.jpg]()
なのだが、欠点は殆ど無い。
おまけに中古購入価格は、2010年代に(税込み)2000円
と超格安であった、外観やレンズの程度が特に悪い訳でもなく、
記事冒頭に述べたような、この時代のMFズームレンズ特有の
「二束三文」の相場なのである。
本レンズの用途は、母艦となるカメラのフォーマット
(現代のデジタル時代では、センサーサイズと考えて良い)に
よって異なる。
今回使用しているボディDMC-G6 は、μ4/3機であるので、
その換算画角は、140-420mm/f4相当となる。
フィールド撮影に適した焦点域であるが、特に近接撮影にも
強いレンズなので、花や昆虫も含め、よりいっそうフィールド
用としての特徴が活かせるであろう。
望遠域は、野鳥等の超遠距離被写体にはやや不足するが、
望遠アダプター母艦であるDMC-G6を使用する場合、優れた
デジタル拡大操作系により、デジタルテレコンで望遠端を
840mmあるいは1680mmまで簡単に拡張でき、しかも
デジタルズーム機能を併用すれば連続的にも画角を変化
させる事ができる。
デジタルズームとアナログ(光学)ズームの併用は極めて
効果的であり、光学ズームでボケ量、ボケ質を決定、それを
維持したまま、デジタルズームで、構図(被写体のサイズ)
の微調整が可能である。
しかもこのレンズの場合、f値固定型であるから、すなわち
絞り値、シャッター速度、ISO感度という全ての露出設定条件を
キープしたまま、光学・デジタルズームで構図が調整可能だ。
![c0032138_19112667.jpg]()
望遠母艦 DMC-G6 も含めたシステムとして、全体の操作系や
使い勝手という面をも加味して、最強クラスのコスパの
システムと言えると思う。
なお、本レンズと類似のスペックで、高級バージョンの
New FD 80-200mm/f4Lというものが存在する、そちらは
1990年代に一時所有していた事があったが、悪くない性能の
レンズだ、ただし、かなり割高であったので、仮に現在まで
所有していたとしても、本シリーズで取り上げる事は
無かったと思う。
----
さて、次のシステム
![c0032138_19112500.jpg]()
レンズは、NIKON Ai ZOOM NIKKOR 43-86mm/f3.5
(中古購入価格 3,000円)
ミラーレス・マニアックス第75回記事で紹介した、
1970年代のMF望遠ズームレンズ。
同記事で本レンズの出自は詳しく述べているが、
簡単にまとめると、本レンズの前身は、1963年に発売された
Zoom Nikkor Auto 43-86mm/f3.5 であり、
これは、日本初の「標準ズーム」である。
![c0032138_19112570.jpg]()
一応あることはあったが、望遠系ズームばかりで、50mmを
下回る焦点距離のズームは無かった。1961年にはニコンより
35-85mmのレンズが試作・発表された模様だが、それは発売
されていない。描写力等に問題があったのかも知れない。
なぜ50mm以下のズームが難しいか?と言えば、これは
一眼レフの「フランジバック」の長さに影響を受けるからだ。
フィルムまたはセンサー面から、マウントまでの距離を
「フランジバック(長)」と呼ぶ。
「フランジ」とは、円筒などから周囲にはみ出す部分、
いわゆる「耳」を意味する用語だ。
「バック」は距離の測り方を意味する技術用語、レンズ用語
では「バックフォーカス」等が他にある,
で、ニコンFマウントのフランジバック長は46.5mmである、
これは、1959年にニコン初の銀塩一眼レフ「NIKON F」に
採用されて以来、およそ60年経った現代でも変更されていない。
さてここで仮定だが、まず1枚の凸レンズを思い浮かべて貰う、
その仮想レンズをニコン機のマウント部にちょうと嵌るように
置いたとする、そして、その際にフィルムまたはセンサー面に
光が収束されて焦点を結ぶとする。
このレンズの「焦点距離」はいくつか?
![c0032138_19114510.gif]()
これはフランジバックと同じ距離、46.5mmのレンズとなる。
実際の写真用レンズでは、たった1枚のレンズしか使われていない
ケースは稀で、最低でも数枚の凸や凹レンズを組み合わせて構成
するが、まあ、だいたいフランジバック長近辺にそれらのレンズ
を集中配置させた場合、薄型で焦点距離が45mm前後のレンズ
となる。
これがいわゆる「パンケーキ」(薄型)レンズの基本原理であり、
ニコン45mm 、CONTAXテッサー45mm、PENTAX 40mm等、
各時代に様々なタイプが各社から発売され、1990年代後半には
一大「パンケーキブーム」を引き起こした。
では、これより長い焦点距離のレンズ、つまり望遠レンズを作る
際にはどうしたら良いか?これは比較的簡単で上図のマウント面
(フランジバックの距離)にあったレンズを、前に出してカメラ
から離せばよい。
フィルム又はセンサー面から10cmの位置にそのようなレンズ群
があって、フィルム面等に焦点が合えば、そのレンズの焦点距離
は10cm、つまり100mmのレンズとなる。
20cmの位置では200mm・・となるが、この方式だと望遠になる程、
どんどんとレンズ長が焦点距離分だけ伸びて、使い難くなる。
なので、実際にはレンズ構成を複雑化し、望遠レンズでもレンズ
全長をあまり長くしないようにする(注:この方式を、やや特殊
な技術用語で”短焦点型レンズ”と呼ぶ。ただしあまり一般的な
用語では無い。それとビギナーが広角や単焦点と混同しやすい)
望遠の原理はだいたいわかった、では広角ではどうするのか?
・・これが難しいのである、46.5mmのフランジバック長で
28mmの広角レンズを作ろうとしたら、上記の原理に従えば、
マウント部の中にレンズを押し込んで、フィルム面から28mm
近辺の位置にレンズ群を置かなくてはならない。
だが、一眼レフの場合「ミラー」が存在する、そんな場所に
レンズを置いたら、ミラーが当たって動かない。
なので、一眼レフでフランジバック長以下の焦点距離の広角
レンズを作ろうとしたら、レンズの後部に凹レンズをつけて、
焦点を伸ばしてやらないとならない。
このタイプのレンズを「逆望遠型」または「レトロフォーカス」
と呼ぶ(「レトロ」とは「遅れた」という意味である)
これは余計なレンズ構成が入るので、性能はどうしても落ちる。
ちなみに、ライカ等のレンジファインダー機や、コンパクト機、
現代のミラーレス機等はミラーが無いので、フランジバック長
をかなり短くできる。
この為、広角レンズでもレンズ構成を単純化し、高性能化や
小型軽量化を目指す設計が可能となる。
これが銀塩時代、レンジファインダー機等で28,35mm等の
広角レンズが好んで使われた根源的な理由だ。
ただ、レンジ機はその構造上(距離計連動)近接撮影に弱く
広角レンズでも近接撮影が出来ない。この結果、広角レンズを
やや絞って中遠距離を撮影する、つまり、スナップや風景撮影的
な技法が発達した訳だ。
私が言う「広角での中遠距離撮影は現代的撮影技法とは言えない」
というのは、この部分が理由にある。
現代の一部の一眼用広角レンズでは、マクロレンズ並みの近接
撮影が可能となるものも多数あるわけで、これは新しい時代の
レンズ性能(特徴)であるから、「それを活用するべきである」
という考え方だ。
余談が長くなってきたが、初の標準ズーム43-86mmの話に戻る。
ニコンのフランジバック長46.5mmを下回る広角レンズを作るのは
レンズ構成が複雑化する、という事であり、ズームレンズでは
なおさらである。望遠側ではまったく不要な凹レンズを、ズーム
を広角側にした際に、どこかから持ってこないとならない。
まあ、ズームレンズの内部で、レンズをつけたり外したりは勿論
出来ないから、内部で複雑なレンズ構成を焦点距離の矛盾なく
動かさなければならない。
この技術開発が難しく、結局、フランジバック長を下回る焦点距離
を含む「標準ズーム」がなかなか発売されなかった原因となる。
![c0032138_19113526.jpg]()
クリアして、初の標準ズームを発売した。
ニコンF発売の4年後の事である。
まあ、しかし、1961年に試作した35-85mmが失敗に終わった為、
ニコレックス(レンズ交換不可の一眼レフ)用に設計されていた
43-86mmレンズを急遽Fマウント用に転用したのかも知れない。
(NIKKOREX ZOOM35という名前で、同じ1963年に発売されている)
このレンズには、すぐに「ヨンサン・ハチロク」という愛称が
つき、ニコンFやニコマート等のユーザーに歓迎され、ヒット
商品となった。
だが、無理をした設計により、レンズの性能は満足いくべき
ものではなかった。
開放f値はf3.5固定とは言え、当時の単焦点レンズの
f1.4~f2.8に比較するとはるかに暗い。
フィルムの感度も低かった当時では開放f値の暗いレンズは
だいぶ不利だったのだ。
そして、最短撮影距離も1.2mと長い、例えば当時の50mmレンズ
では最短は60cm程度であった。
さらには収差が多い、歪曲収差や諸収差により画面周辺の性能は
低く、中上級ユーザーにおいては満足すべきレンズではなかった
のだ。
「ヨンサン・ハチロクはダメなレンズだ」という話は、その後
数十年間にわたって、マニア等の間で囁かれ続けた。
私も、その噂を聞き「そんなに酷いレンズなのか?」という
「怖いもの見たさ」により1990年代に1度このレンズを購入した、
当時の銀塩ニコン機に装着して使ってみたが、確かに描写力が
酷く、すぐに知人に譲渡してしまっていたのだ。
けどまあ、これは可哀想な話ではある、というのも、ニコンでも、
いつまでも同じ性能のレンズを作り続けている訳ではないからだ。
初期型の発売から13年たった1976年に描写力を改善した改良型
となった。開放f値や最短撮影距離のスペックは同じなものの、
内部のレンズ構成は、7群9枚から 8群11枚に進化、描写力は
大幅に改善された。
そして、それをAi対応にしたのが、1977年発売の本レンズ
Ai ZOOM NIKKOR 43-86mm/f3.5である。
結局約20年間にわたり発売し続けられたレンズであるが、
1976年以降の改良型は印象が薄かったのであろう。
なにせ、その当時は、標準ズームなどはすでに当たり前の
時代であり、43mm始まり、と広角が足りず、ズーム比も2倍
でしか無いものは、不人気だったと思われるからだ。
しかも、初期型の評判が悪かった為、その口コミがあったので
買い控えた様相もあったかも知れない。
近年、2010年代になってから、私は中古屋のジャンクコーナー
に3000円で置かれているこのレンズを見つけ、
「ああ、後期型かあ、珍しいな。これは描写力が改善されて
いた筈だけど、実際どんなものなのか?」
と、またしても「怖いもの見たさ」で購入してしまったのだ。
![c0032138_19113544.jpg]()
の描写力である。
諸収差は改善され、特に現代のAPS-C又はμ4/3系のセンサー機
で使う上では周辺が写らずカットされるので周辺収差の面でも
ほとんど問題は無くなっている。ミラーレス・マニアックス
第75回記事では、ローパスレスで描写力の高い FIJI X-E1との
組み合わせで使ったが、特に気になる大きな問題は見当たらず、
高コスパレンズとして評価した。
これまでの本レンズの歴史を振り返ってみて、もう、細かい
欠点を一々あげるのはやめておこう。コスパうんぬんよりも、
マニアックさが上回るレンズだからである。
ある意味、一眼レフの歴史に残る記念碑的なレンズだ。
----
さて、次のシステム、
![c0032138_19113566.jpg]()
レンズは、TAMRON 80-210mm/f3.8-4
(中古購入価格 1,000円)
ミラーレス・マニアックス第55回記事で紹介した、
恐らくは1970年代のMF望遠ズームレンズ。
本記事冒頭で紹介したCANON New FD 70-210mm/f4
と同等の構造の逆直進式ズームで、スペックも良く似ている。
MF時に極めて使いやすい、というのは既に述べたとおり。
カメラボディも望遠母艦のDMC-G5であり、G6と同等の
デジタル拡大操作系を持つ為、その点でもシステマチックに
トータルでの快適な望遠操作系を持たせる事が可能だ。
G6とG5の違いはいくつかあるが、まあ使用する上での違いで
最も大きいのは、G5にはピーキング機能が無い点だ。
が、その分、G5にはピントの山の見分けやすい旧来のEVFが
用いられている、G6の新EVFは見易いがMF性能的には改悪だ。
NFD 70-210/4と、本TAMRON 80-210/3.8-4は仕様的には
良く似ているがレンズ構成は大きく異なり、最短撮影距離も
非マクロモードで比べると、本レンズの方が0.9mと短い。
そして、マクロ非搭載ながら、望遠端でも0.9mの近接撮影
が効く(注:NFDは広角端でしかマクロモードが使えない)
![c0032138_19113450.jpg]()
周辺収差はカットされ、画面中心部の美味しい部分だけを
使える為、まったく弱点は気にならない。
ただし、この時代(1970~1980年代初頭)の全ての70-200mm
f4級ズームレンズが高描写性能であるか?と言えば
そういう訳でもない。現代ではジャンクレンズとして極めて
安価に販売されているので、何本ものこのクラスのレンズを
購入してみたが、中には使えないものも多々あり、逆に言えば
冒頭のNFDや本TAMRONくらいしか、まともな物は無い感じだ。
まあでも、NFDが2000円、本TAMRONが1000円!(税込み)と
ともかく恐ろしく安価だ。
中古でも5万円~10万円もしてしまう現代の 70-200mm f4級
のレンズの購入を検討する際、一度このようなジャンク望遠を
買って使ってみたらどうだろう? そして、その最新レンズを
購入した際に、その描写力と比べてみたらどうだろうか?
現代のレンズには、勿論AFや超音波モーター、手ブレ補正等の
「付加価値」が入っているとは言え、レンズの光学系自体の
性能差は殆ど無い事に気がつくはずだ。
![c0032138_19113473.jpg]()
気にする必要もあまり無い、何故ならば、そうした欠点が理解
または判定できる「眼力」を持つ中上級ユーザーであれば、
そうした欠点を回避しながら、レンズの性能の美味しい部分だけ
を発揮できるように使う「技能」もまた持っている筈だからだ。
特に、この時代の望遠ズームでは、現代の同クラスレンズには
無い、マクロ域までをシームレスに利用できるスペックや、
ミラーレス機のデジタルズーム機能と組み合わせた構図自由度
の極めて高い撮影技法を用いる限り、逆に現代の望遠ズームには
興味が持てなくなってしまうかも知れない。
短所をとがめずに、長所だけを使うという概念は、オールド
レンズを使う際に最も重要な考え方だ。
第二次オールドレンズブームといわれる2010年代では、ただ単に
高性能母艦に適当な古いレンズを選んで使っているケースも
多々見受けられるが、レンズとボディとのそれぞれの特徴・長所
による「シナジー効果」で、よりパフォーマンスの高いシステム
を”開発”していく(考えて、見つけて、実現していく)という
考え方が、むしろ重要だ。
だから、カメラとレンズの両者の長所を殺しあってしまうような
組み合わせは「格好悪い」と、以前から何度も言っている訳だ、
両者の特徴を何も理解していないように見えてしまう。
本ブログのシリーズ記事でも、ミラーレス・マニアックスに
おいては、特にそのあたりに留意して最適なシステムを常に
模索していた。
本「ハイコスパ」のシリーズでは、そのあたりのカメラボディ
との親和性は若干無視している、性能あるいはボディとレンズ
の価格といったミラーレス記事での判断基準よりも、とちらか
といえば、マニアックさやパフォーマンス重視という、別種の
「こだわり」で、組み合わせ(システム)を決定している。
![c0032138_19113523.jpg]()
レンズだ。、
繰り返すが、わずかに1000円で購入できるレンズである。
「コスパ」という概念からは、これ以上のものは無いであろう。
----
次は今回ラストのシステム、
![c0032138_19114252.jpg]()
レンズは、TOKINA 60-300mm/f4.5-5.6
(中古購入価格 1,000円?)
ミラーレス・マニアックス第47回記事で紹介した、
恐らくは、1980年代のMF望遠ズームレンズ。
詳しい出自が不明なレンズだ、2010年代にジャンクコーナーで
サルベージした(引きあげた)レンズであり、購入価格すら
良く覚えていなかったレンズである。
どうでも良いレンズとして、テストするつもりで購入した物だ、
同クラスには、他にTAMORON SP60-300mm/f3.8-5.4
が存在しているが、ミラーレス第58回記事で紹介したそれは、
高性能を示す「SP」仕様でありながら、写りはイマイチであった、
ちなみに、いずれもジャンク品であるから、カビや劣化等の
理由で、レンズ性能に個体差が現れる場合もある、ただ、
このあたりのレンズは、複数回購入している場合あり、
単一の固体での評価はしていない事もある。
![c0032138_19114243.jpg]()
前半に、安価になった中古ミラーレス機を周囲の知人友人が、
多数購入した。
それは私からの影響(情報)もあったのだと思うが、1万円台
でレンズ交換ができるカメラが購入できる事は、知人たちに
とっても魅力的な事実であったのだろう。
その多くには当時は「大放出時代」であったので、MF小口径
標準をセットして見繕った。
「大放出時代」とは、2010年前後、地方等のカメラ店で従来の
銀塩のDPEビジネス(現像等)が成り立たず、廃業などが多く
発生した時代であり、それらの店舗で抱えられていた中古機が
中央(チェーン展開カメラ店等)に集められ、レンズ群は選別
され、程度の良いものは再整備して適価で販売、程度の悪い物は
ジャンクとして大量放出された時代である、という背景だ。
この頃のジャンクMF標準レンズの売価は、1000円~2000円
という安価な相場であり、ジャンクといえども、ちょっと
キズがある程度のものも多く、私も多数それらを買い込んだ。
数年でそれらは完売されてしまい、現代2010年代後半では
それらはもう中古市場には残っていない。
標準レンズを見繕った知人達の中には「せっかくレンズ交換
できるカメラだから、望遠が欲しい」と言ってくる人も多数
居た。その際、私は大放出時代に、標準レンズと同様に販売
されていたジャンクMF望遠ズームに着目し、それらも多数
購入し、知人に薦める前に撮影し、テストを行っていたのだ。
そのMF望遠ズームの多くは、弱点を抱えるものであったが、
弱点を説明した上で(例えば”逆光には弱いよ”とか)、
適価で、知人達に譲渡したのであった。
同じレンズを複数回購入する、という事も、そういう意味で
あった。
中には特に写りが良いMFズームもあったが、それらは譲渡せず
に手元に残したり、あるいは、また同じレンズを購入して、
それを譲渡したりしていた。
別にそれで儲けるとか言う意味は無く(1000円で購入した物を
1500円で売っても、あまり儲からない・笑)
購入価格そのままか、あるいは無償でギフト(贈答品)代わり
にもしていたのだ。
で、私としては、ほとんどコストがかからず、様々なレンズの
実写テストができるので、マニア的な観点からは、美味しい
やり方だ。
こういうテストマニア的な手法は、後で手元に多数のレンズが
残って途方に暮れることが多いが、この場合は譲渡が前提なので
手元にレンズがあまり残らず、その点でも良かったわけだ。
![c0032138_19114276.jpg]()
まったく期待しないで購入したものの、撮ってみてびっくり、
という類のレンズであった。
今回使用するカメラは、アダプター母艦としては、極めて優れた
操作系が特徴なSONY NEX-7である。フルサイズ機α7人気の影で、
ほとんど目だない機種だが、傑作機として私の評価は高い。
ただ、その複雑で高度な操作系は、上級者向けだと、念のため
定義しておく、ビギナーには決して使いこなせないカメラなのだ。
(だから続くα7では操作系を簡略化して一般向けとしたのだろう)
![c0032138_19114136.jpg]()
90-450mm/f4.5-5.6である、ズーム比が大きく、望遠端も
それなりに長くなるので、ブレ等は要注意だ。
カメラにもレンズにも手ブレ補正機能はなく、もしカメラ側に
内蔵手ブレ補正があったとしても、レンズ側から焦点距離情報が
入ってこないMFレンズでは、ズームを動かす度に、焦点距離が
変動してしまい、手動焦点距離設定入力があったとしても、
その操作性は煩雑になりすぎて実用的ではない、つまり内蔵
手ブレ補正機能は使用できない。
もう1つのブレ低減効果としてのAUTO ISOだが、SONY機の多くは、
高感度ノイズ発生を嫌って、自動では高感度域まで上がらない
仕様となっている為、ここも期待できない。
そのため、ISO感度もズーミングと光源状況に合わせて撮影中に
随時変更する必要がある、ISOが常時直接変更可能な操作系を
持つカメラは数える程しかなく、NEX-7はそのうちの1台である。
![c0032138_19114102.jpg]()
やボタン一発で動作可能な連続デジタルズーム(無劣化ではない
ので微調整程度にする)による、光学・デジタルズーム相乗効果
(前述)と、あいまって快適な操作系で撮影を行う事ができる。
もう1つの母艦の可能性としては、望遠母艦、DMC-G6の使用が
考えられるが、本記事では、冒頭ですでにG6を使っているので
重複使用は見送った。
----
さて、今回の記事は、このあたりまでとする。
次回は、AF単焦点広角レンズを紹介していく事にする。
カテゴリー別に紹介するシリーズの第9回目は、
MFズームレンズを4本紹介していこう。
AFズームに並びMFのズームも非常に広いカテゴリーだ。
銀塩MF時代初期の1960~1970年代前半の一眼レフには、
単焦点レンズを組み合わせる事が一般的だったが、
1970年代後半~1980年代前半に銀塩MF一眼レフが一般
ユーザーレベルにまで普及したのは、ある意味、MFズーム
レンズの進歩も、その背景にあったかも知れない。
ただ、現代2010年代の中古市場では、それらMF一眼レフの
普及に非常に寄与したMFズームレンズ群は、用途も無く、
マニアにさえも人気が無い為、実際の中古相場は、殆どが
二束三文という状況だ。
そういう意味では、多くのMFズームレンズは「コスパが良い」
と言える。さて、どのレンズを紹介するべきか?迷う所では
あるが、まあ、順次紹介していこう・・
まず、最初のシステム、

レンズは、CANON New FD 70-210mm/f4
(中古購入価格 2,000円)
ミラーレス・マニアックス第52回記事で紹介した、
1980年代のMF望遠ズームレンズ。

まず、その描写力、これは他の同時代の同様なスペックの
レンズ(多数ある)と比べても、なかなか優れている。
解像感が高く、ボケ質破綻も出にくく、逆光耐性も良い。
そして直進ズームであり、ズーミングとピント合わせの
操作が同時にできる。しかもズーミングで全長が変化しない
タイプなので、重心が移動することもない、これらは
MFズームならではの構造であり極めて使い易い。
さらには、開放f値がf4固定であり、ズーミングでf値が
変動しないメリットも大きい。
最短撮影距離も1.2mと短く、さらにマクロモードで
広角端でおよそ50cm以下程度まで寄ることができる。

なのだが、欠点は殆ど無い。
おまけに中古購入価格は、2010年代に(税込み)2000円
と超格安であった、外観やレンズの程度が特に悪い訳でもなく、
記事冒頭に述べたような、この時代のMFズームレンズ特有の
「二束三文」の相場なのである。
本レンズの用途は、母艦となるカメラのフォーマット
(現代のデジタル時代では、センサーサイズと考えて良い)に
よって異なる。
今回使用しているボディDMC-G6 は、μ4/3機であるので、
その換算画角は、140-420mm/f4相当となる。
フィールド撮影に適した焦点域であるが、特に近接撮影にも
強いレンズなので、花や昆虫も含め、よりいっそうフィールド
用としての特徴が活かせるであろう。
望遠域は、野鳥等の超遠距離被写体にはやや不足するが、
望遠アダプター母艦であるDMC-G6を使用する場合、優れた
デジタル拡大操作系により、デジタルテレコンで望遠端を
840mmあるいは1680mmまで簡単に拡張でき、しかも
デジタルズーム機能を併用すれば連続的にも画角を変化
させる事ができる。
デジタルズームとアナログ(光学)ズームの併用は極めて
効果的であり、光学ズームでボケ量、ボケ質を決定、それを
維持したまま、デジタルズームで、構図(被写体のサイズ)
の微調整が可能である。
しかもこのレンズの場合、f値固定型であるから、すなわち
絞り値、シャッター速度、ISO感度という全ての露出設定条件を
キープしたまま、光学・デジタルズームで構図が調整可能だ。

望遠母艦 DMC-G6 も含めたシステムとして、全体の操作系や
使い勝手という面をも加味して、最強クラスのコスパの
システムと言えると思う。
なお、本レンズと類似のスペックで、高級バージョンの
New FD 80-200mm/f4Lというものが存在する、そちらは
1990年代に一時所有していた事があったが、悪くない性能の
レンズだ、ただし、かなり割高であったので、仮に現在まで
所有していたとしても、本シリーズで取り上げる事は
無かったと思う。
----
さて、次のシステム

レンズは、NIKON Ai ZOOM NIKKOR 43-86mm/f3.5
(中古購入価格 3,000円)
ミラーレス・マニアックス第75回記事で紹介した、
1970年代のMF望遠ズームレンズ。
同記事で本レンズの出自は詳しく述べているが、
簡単にまとめると、本レンズの前身は、1963年に発売された
Zoom Nikkor Auto 43-86mm/f3.5 であり、
これは、日本初の「標準ズーム」である。

一応あることはあったが、望遠系ズームばかりで、50mmを
下回る焦点距離のズームは無かった。1961年にはニコンより
35-85mmのレンズが試作・発表された模様だが、それは発売
されていない。描写力等に問題があったのかも知れない。
なぜ50mm以下のズームが難しいか?と言えば、これは
一眼レフの「フランジバック」の長さに影響を受けるからだ。
フィルムまたはセンサー面から、マウントまでの距離を
「フランジバック(長)」と呼ぶ。
「フランジ」とは、円筒などから周囲にはみ出す部分、
いわゆる「耳」を意味する用語だ。
「バック」は距離の測り方を意味する技術用語、レンズ用語
では「バックフォーカス」等が他にある,
で、ニコンFマウントのフランジバック長は46.5mmである、
これは、1959年にニコン初の銀塩一眼レフ「NIKON F」に
採用されて以来、およそ60年経った現代でも変更されていない。
さてここで仮定だが、まず1枚の凸レンズを思い浮かべて貰う、
その仮想レンズをニコン機のマウント部にちょうと嵌るように
置いたとする、そして、その際にフィルムまたはセンサー面に
光が収束されて焦点を結ぶとする。
このレンズの「焦点距離」はいくつか?
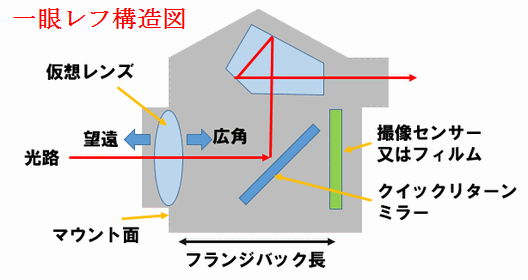
これはフランジバックと同じ距離、46.5mmのレンズとなる。
実際の写真用レンズでは、たった1枚のレンズしか使われていない
ケースは稀で、最低でも数枚の凸や凹レンズを組み合わせて構成
するが、まあ、だいたいフランジバック長近辺にそれらのレンズ
を集中配置させた場合、薄型で焦点距離が45mm前後のレンズ
となる。
これがいわゆる「パンケーキ」(薄型)レンズの基本原理であり、
ニコン45mm 、CONTAXテッサー45mm、PENTAX 40mm等、
各時代に様々なタイプが各社から発売され、1990年代後半には
一大「パンケーキブーム」を引き起こした。
では、これより長い焦点距離のレンズ、つまり望遠レンズを作る
際にはどうしたら良いか?これは比較的簡単で上図のマウント面
(フランジバックの距離)にあったレンズを、前に出してカメラ
から離せばよい。
フィルム又はセンサー面から10cmの位置にそのようなレンズ群
があって、フィルム面等に焦点が合えば、そのレンズの焦点距離
は10cm、つまり100mmのレンズとなる。
20cmの位置では200mm・・となるが、この方式だと望遠になる程、
どんどんとレンズ長が焦点距離分だけ伸びて、使い難くなる。
なので、実際にはレンズ構成を複雑化し、望遠レンズでもレンズ
全長をあまり長くしないようにする(注:この方式を、やや特殊
な技術用語で”短焦点型レンズ”と呼ぶ。ただしあまり一般的な
用語では無い。それとビギナーが広角や単焦点と混同しやすい)
望遠の原理はだいたいわかった、では広角ではどうするのか?
・・これが難しいのである、46.5mmのフランジバック長で
28mmの広角レンズを作ろうとしたら、上記の原理に従えば、
マウント部の中にレンズを押し込んで、フィルム面から28mm
近辺の位置にレンズ群を置かなくてはならない。
だが、一眼レフの場合「ミラー」が存在する、そんな場所に
レンズを置いたら、ミラーが当たって動かない。
なので、一眼レフでフランジバック長以下の焦点距離の広角
レンズを作ろうとしたら、レンズの後部に凹レンズをつけて、
焦点を伸ばしてやらないとならない。
このタイプのレンズを「逆望遠型」または「レトロフォーカス」
と呼ぶ(「レトロ」とは「遅れた」という意味である)
これは余計なレンズ構成が入るので、性能はどうしても落ちる。
ちなみに、ライカ等のレンジファインダー機や、コンパクト機、
現代のミラーレス機等はミラーが無いので、フランジバック長
をかなり短くできる。
この為、広角レンズでもレンズ構成を単純化し、高性能化や
小型軽量化を目指す設計が可能となる。
これが銀塩時代、レンジファインダー機等で28,35mm等の
広角レンズが好んで使われた根源的な理由だ。
ただ、レンジ機はその構造上(距離計連動)近接撮影に弱く
広角レンズでも近接撮影が出来ない。この結果、広角レンズを
やや絞って中遠距離を撮影する、つまり、スナップや風景撮影的
な技法が発達した訳だ。
私が言う「広角での中遠距離撮影は現代的撮影技法とは言えない」
というのは、この部分が理由にある。
現代の一部の一眼用広角レンズでは、マクロレンズ並みの近接
撮影が可能となるものも多数あるわけで、これは新しい時代の
レンズ性能(特徴)であるから、「それを活用するべきである」
という考え方だ。
余談が長くなってきたが、初の標準ズーム43-86mmの話に戻る。
ニコンのフランジバック長46.5mmを下回る広角レンズを作るのは
レンズ構成が複雑化する、という事であり、ズームレンズでは
なおさらである。望遠側ではまったく不要な凹レンズを、ズーム
を広角側にした際に、どこかから持ってこないとならない。
まあ、ズームレンズの内部で、レンズをつけたり外したりは勿論
出来ないから、内部で複雑なレンズ構成を焦点距離の矛盾なく
動かさなければならない。
この技術開発が難しく、結局、フランジバック長を下回る焦点距離
を含む「標準ズーム」がなかなか発売されなかった原因となる。

クリアして、初の標準ズームを発売した。
ニコンF発売の4年後の事である。
まあ、しかし、1961年に試作した35-85mmが失敗に終わった為、
ニコレックス(レンズ交換不可の一眼レフ)用に設計されていた
43-86mmレンズを急遽Fマウント用に転用したのかも知れない。
(NIKKOREX ZOOM35という名前で、同じ1963年に発売されている)
このレンズには、すぐに「ヨンサン・ハチロク」という愛称が
つき、ニコンFやニコマート等のユーザーに歓迎され、ヒット
商品となった。
だが、無理をした設計により、レンズの性能は満足いくべき
ものではなかった。
開放f値はf3.5固定とは言え、当時の単焦点レンズの
f1.4~f2.8に比較するとはるかに暗い。
フィルムの感度も低かった当時では開放f値の暗いレンズは
だいぶ不利だったのだ。
そして、最短撮影距離も1.2mと長い、例えば当時の50mmレンズ
では最短は60cm程度であった。
さらには収差が多い、歪曲収差や諸収差により画面周辺の性能は
低く、中上級ユーザーにおいては満足すべきレンズではなかった
のだ。
「ヨンサン・ハチロクはダメなレンズだ」という話は、その後
数十年間にわたって、マニア等の間で囁かれ続けた。
私も、その噂を聞き「そんなに酷いレンズなのか?」という
「怖いもの見たさ」により1990年代に1度このレンズを購入した、
当時の銀塩ニコン機に装着して使ってみたが、確かに描写力が
酷く、すぐに知人に譲渡してしまっていたのだ。
けどまあ、これは可哀想な話ではある、というのも、ニコンでも、
いつまでも同じ性能のレンズを作り続けている訳ではないからだ。
初期型の発売から13年たった1976年に描写力を改善した改良型
となった。開放f値や最短撮影距離のスペックは同じなものの、
内部のレンズ構成は、7群9枚から 8群11枚に進化、描写力は
大幅に改善された。
そして、それをAi対応にしたのが、1977年発売の本レンズ
Ai ZOOM NIKKOR 43-86mm/f3.5である。
結局約20年間にわたり発売し続けられたレンズであるが、
1976年以降の改良型は印象が薄かったのであろう。
なにせ、その当時は、標準ズームなどはすでに当たり前の
時代であり、43mm始まり、と広角が足りず、ズーム比も2倍
でしか無いものは、不人気だったと思われるからだ。
しかも、初期型の評判が悪かった為、その口コミがあったので
買い控えた様相もあったかも知れない。
近年、2010年代になってから、私は中古屋のジャンクコーナー
に3000円で置かれているこのレンズを見つけ、
「ああ、後期型かあ、珍しいな。これは描写力が改善されて
いた筈だけど、実際どんなものなのか?」
と、またしても「怖いもの見たさ」で購入してしまったのだ。

の描写力である。
諸収差は改善され、特に現代のAPS-C又はμ4/3系のセンサー機
で使う上では周辺が写らずカットされるので周辺収差の面でも
ほとんど問題は無くなっている。ミラーレス・マニアックス
第75回記事では、ローパスレスで描写力の高い FIJI X-E1との
組み合わせで使ったが、特に気になる大きな問題は見当たらず、
高コスパレンズとして評価した。
これまでの本レンズの歴史を振り返ってみて、もう、細かい
欠点を一々あげるのはやめておこう。コスパうんぬんよりも、
マニアックさが上回るレンズだからである。
ある意味、一眼レフの歴史に残る記念碑的なレンズだ。
----
さて、次のシステム、

レンズは、TAMRON 80-210mm/f3.8-4
(中古購入価格 1,000円)
ミラーレス・マニアックス第55回記事で紹介した、
恐らくは1970年代のMF望遠ズームレンズ。
本記事冒頭で紹介したCANON New FD 70-210mm/f4
と同等の構造の逆直進式ズームで、スペックも良く似ている。
MF時に極めて使いやすい、というのは既に述べたとおり。
カメラボディも望遠母艦のDMC-G5であり、G6と同等の
デジタル拡大操作系を持つ為、その点でもシステマチックに
トータルでの快適な望遠操作系を持たせる事が可能だ。
G6とG5の違いはいくつかあるが、まあ使用する上での違いで
最も大きいのは、G5にはピーキング機能が無い点だ。
が、その分、G5にはピントの山の見分けやすい旧来のEVFが
用いられている、G6の新EVFは見易いがMF性能的には改悪だ。
NFD 70-210/4と、本TAMRON 80-210/3.8-4は仕様的には
良く似ているがレンズ構成は大きく異なり、最短撮影距離も
非マクロモードで比べると、本レンズの方が0.9mと短い。
そして、マクロ非搭載ながら、望遠端でも0.9mの近接撮影
が効く(注:NFDは広角端でしかマクロモードが使えない)

周辺収差はカットされ、画面中心部の美味しい部分だけを
使える為、まったく弱点は気にならない。
ただし、この時代(1970~1980年代初頭)の全ての70-200mm
f4級ズームレンズが高描写性能であるか?と言えば
そういう訳でもない。現代ではジャンクレンズとして極めて
安価に販売されているので、何本ものこのクラスのレンズを
購入してみたが、中には使えないものも多々あり、逆に言えば
冒頭のNFDや本TAMRONくらいしか、まともな物は無い感じだ。
まあでも、NFDが2000円、本TAMRONが1000円!(税込み)と
ともかく恐ろしく安価だ。
中古でも5万円~10万円もしてしまう現代の 70-200mm f4級
のレンズの購入を検討する際、一度このようなジャンク望遠を
買って使ってみたらどうだろう? そして、その最新レンズを
購入した際に、その描写力と比べてみたらどうだろうか?
現代のレンズには、勿論AFや超音波モーター、手ブレ補正等の
「付加価値」が入っているとは言え、レンズの光学系自体の
性能差は殆ど無い事に気がつくはずだ。

気にする必要もあまり無い、何故ならば、そうした欠点が理解
または判定できる「眼力」を持つ中上級ユーザーであれば、
そうした欠点を回避しながら、レンズの性能の美味しい部分だけ
を発揮できるように使う「技能」もまた持っている筈だからだ。
特に、この時代の望遠ズームでは、現代の同クラスレンズには
無い、マクロ域までをシームレスに利用できるスペックや、
ミラーレス機のデジタルズーム機能と組み合わせた構図自由度
の極めて高い撮影技法を用いる限り、逆に現代の望遠ズームには
興味が持てなくなってしまうかも知れない。
短所をとがめずに、長所だけを使うという概念は、オールド
レンズを使う際に最も重要な考え方だ。
第二次オールドレンズブームといわれる2010年代では、ただ単に
高性能母艦に適当な古いレンズを選んで使っているケースも
多々見受けられるが、レンズとボディとのそれぞれの特徴・長所
による「シナジー効果」で、よりパフォーマンスの高いシステム
を”開発”していく(考えて、見つけて、実現していく)という
考え方が、むしろ重要だ。
だから、カメラとレンズの両者の長所を殺しあってしまうような
組み合わせは「格好悪い」と、以前から何度も言っている訳だ、
両者の特徴を何も理解していないように見えてしまう。
本ブログのシリーズ記事でも、ミラーレス・マニアックスに
おいては、特にそのあたりに留意して最適なシステムを常に
模索していた。
本「ハイコスパ」のシリーズでは、そのあたりのカメラボディ
との親和性は若干無視している、性能あるいはボディとレンズ
の価格といったミラーレス記事での判断基準よりも、とちらか
といえば、マニアックさやパフォーマンス重視という、別種の
「こだわり」で、組み合わせ(システム)を決定している。

レンズだ。、
繰り返すが、わずかに1000円で購入できるレンズである。
「コスパ」という概念からは、これ以上のものは無いであろう。
----
次は今回ラストのシステム、

レンズは、TOKINA 60-300mm/f4.5-5.6
(中古購入価格 1,000円?)
ミラーレス・マニアックス第47回記事で紹介した、
恐らくは、1980年代のMF望遠ズームレンズ。
詳しい出自が不明なレンズだ、2010年代にジャンクコーナーで
サルベージした(引きあげた)レンズであり、購入価格すら
良く覚えていなかったレンズである。
どうでも良いレンズとして、テストするつもりで購入した物だ、
同クラスには、他にTAMORON SP60-300mm/f3.8-5.4
が存在しているが、ミラーレス第58回記事で紹介したそれは、
高性能を示す「SP」仕様でありながら、写りはイマイチであった、
ちなみに、いずれもジャンク品であるから、カビや劣化等の
理由で、レンズ性能に個体差が現れる場合もある、ただ、
このあたりのレンズは、複数回購入している場合あり、
単一の固体での評価はしていない事もある。

前半に、安価になった中古ミラーレス機を周囲の知人友人が、
多数購入した。
それは私からの影響(情報)もあったのだと思うが、1万円台
でレンズ交換ができるカメラが購入できる事は、知人たちに
とっても魅力的な事実であったのだろう。
その多くには当時は「大放出時代」であったので、MF小口径
標準をセットして見繕った。
「大放出時代」とは、2010年前後、地方等のカメラ店で従来の
銀塩のDPEビジネス(現像等)が成り立たず、廃業などが多く
発生した時代であり、それらの店舗で抱えられていた中古機が
中央(チェーン展開カメラ店等)に集められ、レンズ群は選別
され、程度の良いものは再整備して適価で販売、程度の悪い物は
ジャンクとして大量放出された時代である、という背景だ。
この頃のジャンクMF標準レンズの売価は、1000円~2000円
という安価な相場であり、ジャンクといえども、ちょっと
キズがある程度のものも多く、私も多数それらを買い込んだ。
数年でそれらは完売されてしまい、現代2010年代後半では
それらはもう中古市場には残っていない。
標準レンズを見繕った知人達の中には「せっかくレンズ交換
できるカメラだから、望遠が欲しい」と言ってくる人も多数
居た。その際、私は大放出時代に、標準レンズと同様に販売
されていたジャンクMF望遠ズームに着目し、それらも多数
購入し、知人に薦める前に撮影し、テストを行っていたのだ。
そのMF望遠ズームの多くは、弱点を抱えるものであったが、
弱点を説明した上で(例えば”逆光には弱いよ”とか)、
適価で、知人達に譲渡したのであった。
同じレンズを複数回購入する、という事も、そういう意味で
あった。
中には特に写りが良いMFズームもあったが、それらは譲渡せず
に手元に残したり、あるいは、また同じレンズを購入して、
それを譲渡したりしていた。
別にそれで儲けるとか言う意味は無く(1000円で購入した物を
1500円で売っても、あまり儲からない・笑)
購入価格そのままか、あるいは無償でギフト(贈答品)代わり
にもしていたのだ。
で、私としては、ほとんどコストがかからず、様々なレンズの
実写テストができるので、マニア的な観点からは、美味しい
やり方だ。
こういうテストマニア的な手法は、後で手元に多数のレンズが
残って途方に暮れることが多いが、この場合は譲渡が前提なので
手元にレンズがあまり残らず、その点でも良かったわけだ。

まったく期待しないで購入したものの、撮ってみてびっくり、
という類のレンズであった。
今回使用するカメラは、アダプター母艦としては、極めて優れた
操作系が特徴なSONY NEX-7である。フルサイズ機α7人気の影で、
ほとんど目だない機種だが、傑作機として私の評価は高い。
ただ、その複雑で高度な操作系は、上級者向けだと、念のため
定義しておく、ビギナーには決して使いこなせないカメラなのだ。
(だから続くα7では操作系を簡略化して一般向けとしたのだろう)

90-450mm/f4.5-5.6である、ズーム比が大きく、望遠端も
それなりに長くなるので、ブレ等は要注意だ。
カメラにもレンズにも手ブレ補正機能はなく、もしカメラ側に
内蔵手ブレ補正があったとしても、レンズ側から焦点距離情報が
入ってこないMFレンズでは、ズームを動かす度に、焦点距離が
変動してしまい、手動焦点距離設定入力があったとしても、
その操作性は煩雑になりすぎて実用的ではない、つまり内蔵
手ブレ補正機能は使用できない。
もう1つのブレ低減効果としてのAUTO ISOだが、SONY機の多くは、
高感度ノイズ発生を嫌って、自動では高感度域まで上がらない
仕様となっている為、ここも期待できない。
そのため、ISO感度もズーミングと光源状況に合わせて撮影中に
随時変更する必要がある、ISOが常時直接変更可能な操作系を
持つカメラは数える程しかなく、NEX-7はそのうちの1台である。

やボタン一発で動作可能な連続デジタルズーム(無劣化ではない
ので微調整程度にする)による、光学・デジタルズーム相乗効果
(前述)と、あいまって快適な操作系で撮影を行う事ができる。
もう1つの母艦の可能性としては、望遠母艦、DMC-G6の使用が
考えられるが、本記事では、冒頭ですでにG6を使っているので
重複使用は見送った。
----
さて、今回の記事は、このあたりまでとする。
次回は、AF単焦点広角レンズを紹介していく事にする。