ミラーレス・マニアックスの補足編、その5。
このシリーズでは、ミラーレスマニアックス本編記事で紹介
できなかったレンズや、機材の課題の回避、特殊な使用法での
テスト等の補足を行っている。
まず最初は、本編では未紹介のレンズだ。

カメラは、LUMIX DMC-GX7
レンズは、キヤノン EF 50mm/f1.8 (初期型)
1987年発売の、AF小口径標準単焦点レンズである。
最初期の銀塩EOSと同時期のAFレンズだ。
で、これまでキヤノンの標準(50mm)単焦点レンズとしては、
MF時代のものは、
New FD 50mm/f1.2L(第 3回記事)
FD 50mm/f1.4 (第12回記事)
New FD 50mm/f1.8 (第74回記事)
AF時代のものは、
EF 50mm/f1.4 USM (第69回記事)
を、既にシリーズ本編各記事で紹介している。
まあしかし、どの標準レンズも、比較的良くは写るものの、
これといった特徴の無いものが多かった。
あえて選ぶならば、第74回記事で紹介したNFD50/1.8は、
2000円という格安の中古価格ながら、それなりに問題無く写り、
これらのキヤノンの標準レンズの中では、一番のお気に入りと
言えるかもしれない。
そして、その第74回記事ではNFD50/1.8の後継レンズであるとも
言える(但しレンズ構成は異なる)「EF50/1.8の初期型を探している」
と書いたが、初期型は、ややレアで、なかなか見つからなかったし、
あったとしても、相場が高すぎたり(2万円以上)していた。
ちなみに、EF50/1.8のⅡ型(1990年発売)は、コストダウンの
為か、レンズの作りがかなり安っぽくなってしまった。外装は
もとよりマウントの素材もプラスチック製だ。また、フードも簡単
には装着出来ない模様である。
中古市場にはいくらでも安価なⅡ型はあるが、どうもそれらは
買う気にはなれなかった。
わずか3年間しか販売されなかったのも、初期型が見つかり難い
理由だったのかもしれない。(ちなみに、初期型の中でも前期型と
後期型があり、微妙に仕様が違う模様だが、そこまでのこだわりは
無い)
で、最近、やっと適切な相場の初期型の中古を見つけたので、
やった!とばかりに購入した次第である。
MFでの操作性についてだが、Ⅱ型では省略されたピント窓が
本レンズにはあるが、まあ、あって当たり前であり、特にそれを
見ながら写真を撮る訳では無いのだが、無いとむしろ不安であろう。
しかし、ピントリングはレンズ鏡筒中央部にあるものの、幅が狭く、
かつ回転感触も、ザラついた感じで良く無い。
Ⅱ型ではなく初期型に拘ったのは、MF操作性が少しは良いか?と
予想しての事だが、ちょっとこの点はがっかりだ。
個体差または経年変化か?とも思い、グリースを注入してみたが
回転感触は、あまり改善はされない模様であった。

最短撮影距離は45cmと、50mm標準としてはノーマルな性能だ。
ちなみに、小口径版(f1.8前後)標準は大口径版(f1.4前後)との
ラインナップ差別化の為に、最短撮影距離を60cm程度まで伸ばして
しまっている場合も多々ある(前述のNFD50mm/f1.8も60cmだ)
つまり、開放f値の差と最短撮影距離の差により、
「ほらね、やっぱり、f1.4の方が良く背景がボケるでしょう?
だから、こちらのf1.4版は高いんですよ」という、メーカーの
営業マンのセールストークが効くという意味だ。まあ、そんな事には
騙される訳も無いのだが、シンプルに45cmの最短は歓迎しておこう。

弱点として「ボケ質破綻」については、絞り開放近くで僅かに出る。
しかし、少し絞ったり撮影距離を変える程度で回避できる場合が
多い模様だ。まあ、でも、解像力優先の設計の模様で、ボケ質自体は
あまり良いとは思えない。
本レンズをミラーレス機で使用する上では、高価な電子アダプターを
使わない限り、絞りを制御できない。私が使っているのは、機械絞り
羽根内蔵アダプターだが、この機構では、絞りについての光学的な
意味合いが変わってしまい、光量調整をメインとするくらいで、
被写界深度ならびに収差低減やボケ質破綻の微調整は、やりずらい。
ただし、それもレンズ光学系によりけりな模様であり、
本レンズでは、レンズ後群以降に絞り羽根があるアダプターに
おいても、本来のレンズ内の絞りと同様な効果が出易い模様だ。
で、一眼(EOS)ユーザーであれば開放測光であり、仮にプレビュー
(絞り込み)機能を用いても、ボケ質破綻の回避は絶望的に困難だ。
なので、絞り制御が完璧では無くてもミラーレス機で使う方が、
一眼で使うよりも、まだマシなようにも思えてしまう。
まあ、ボケ質破綻等の弱点は仔細な事である、全般的には良い
レンズであり、少し絞れば解像度も高く、逆光性能も問題ない。
私はこれまでEF(EOS)マウントでは、50mm標準は銀塩時代より
ずっと、f1.4版を使っていた。
まあ普通に考えれば、f1.4版の方が中古でもf1.8版より3~5倍
程度高価であるし、良く写って当然、と思う事であろう。
私も昔はそう考えて、1990年代にf1.4版を購入していたのだ。
だが、本シリーズ記事では、同一焦点距離で複数の開放f値のレンズ
が複数ラインナップされている場合、それぞれを撮り比べると、
「たいてい、小口径版の方が良く写る」という結果が出てきている。
だから、値段が高いものが良いレンズだ、という訳では決して無い。
最初からそれがわかっていたら、無駄な高価なレンズを沢山買う事も
なかっただろうが、やはり、同一のメーカーの同一の焦点距離で
開放f値や、あるいは仕様や年代が異なる単焦点レンズを複数買う、
などといった酔狂な事が出来るマニアでないかぎり、そういう事実は
なかなか見えてこないのだろうと思う。
まあ、その事を再度痛感するような、本レンズの描写力であった。

EF50/1.8初期型の中古購入価格は、本年2016年に11000円台
であった。
(ちなみに、初期型の発売時定価は25000円程度していた模様だ)
まあコストの点から考えれば、Ⅱ型だったら新品定価がそれ位で
中古は6~7000円も出せばいくらでも見つかるので、そちらの方が
さらにコスパが良いであろう。(ちなみに、Ⅱ型も中身は同じレンズ
である)ただ、あえて初期型に拘って入手したレンズであるので、
コスパはさておき、所有満足度やマニアック度は高いレンズである。
余談だが、近年EF50/1.8Ⅱは、EF50/1.8STMにリニューアルされて
いる。このレンズは、STMの名の通り、ステッピングモーター仕様と
なっている。Ⅱ型との最大の差は最短撮影距離が35cmと、10cm
も短縮されている事だ。質感も若干は上がっている模様だが、依然
安っぽさは拭えず、かつ、STM仕様のレンズは、恐らくはマウント
アダプターで使用時にはMFが全く効かないだろう。
(第61回記事でEF85mm/f1.2L USMを紹介時に、EOSボディで
無いとピントが動かず、結局ミラーレス機では使用不能であった)
自社のカメラにしか使えないようにしてしまう、という排他的な
製品コンセプトには賛同できない。ただでさえ、カメラ業界では
各社は、未だにマウントすら統一できないでいる。他の電子機器
業界で、こんな状況であれば、ユーザーからそっぽを向かれる事は
必至だ(例えば、USBメモリーが各社のPC用で異なるとか)
現代の感覚においては”製品がユニバーサル(汎用的)である事”
は一般常識とも言える。
まあ、新型のSTMレンズは今後も購入する事は無いであろう・・
-----
さて、次のシステムは、レンズ性能の再確認だ。
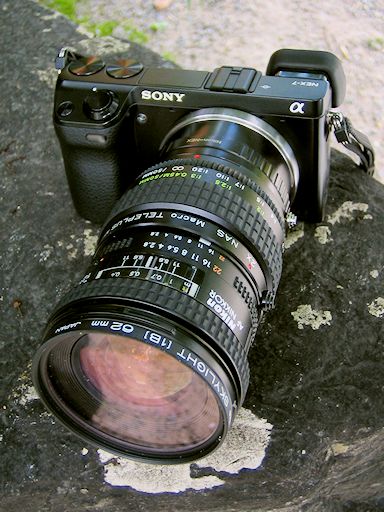
カメラは、SONY NEX-7
レンズは、NIKON AiAF20mm/f2.8S
第53回記事で紹介した、1989年発売のAF広角単焦点レンズ。
だが、その際にはMFでのピント性能に重欠点を抱える X-E1
との組み合わせであって、結局本レンズのパフォーマンスの
チェックを行えていなかった。
加えて、個人的には好きなレンズでは無い。何故ならば1990年代
の中古購入価格が30000円と、レンズ性能からは、あまり納得が
行かないコスパの悪いレンズだったからだ。
(本シリーズでは、コスパは最重要のレンズ評価項目だ)
で、今回は、使い難いX-E1をやめて、アダプター母艦として適正な
NEX-7で撮ってみることが補足編で再登場の理由の1つだ、
そして、もう1つの理由だが、ニコンに、DX40mm/f2.8という
APS-C専用の準広角マクロレンズが存在している。そのレンズは
比較的近年に発売された、いわば「準エントリーレンズ」である。
(つまり、お試し版レンズという事で、低価格でかつ性能が良い)
そのレンズを買うかどうか?という事前検証を行いたい訳だ。
私は40mmのマクロというのは所有していない。
NEX用のE30mm/f3.5(第72回、補足編2)や、50mmの標準
マクロについてはいくらでもあるが、40mmズバリが無いので、
ちょっと感覚がわかりにくい。
そして、SONY E30/3.5の描写が気に入らないのだ(補足編2参照)
その為、E30/3.5の代替の意味も含めて、40mmマクロの使い勝手
を似たようなものでシミレーションしてみようかと思った次第だ。
その為に必要な機材は「KENKO マクロテレプラス MC7」である、
既に、いくつかの記事で紹介しているので、詳細は割愛する。
簡単に言えば、MF銀塩時代の「接写用ヘリコイドアダプター」だと
思ってもらえれば良い。
MC7は、MF時代のアクセサリーだが、本レンズの時代(1990年代)
のニコンAF(AiAF)レンズであっても問題無く使用できる。
(注:絞り環があれば良い。絞り環が無いGタイプ等は使用不可)
AiAF20mm/f2.8にMC7を装着すると、焦点距離も開放f値も
2倍となり、スペック的には、40mm/f5.6のマクロレンズとなる。
なお、NEX-7もAPS-C機であるので、換算画角は60mm相当だ。
これで開放f値の他は、DX Micro 40mm/f2.8と同等になる。

余談だが、ニコンのマクロは「マイクロ」と呼ばれている。
私は、特定のメーカーだけ他社と異なる呼称をしている事に
ついては、前述の「ユニバーサルで無い」という状況と同じと見て
全く賛同できない。なので、本ブログにおいては昔から、
「マイクロニッコール」であろうが「マクロ」と頑なに呼んでいる。
けど、思うに、本来の英語の意味からしたら、何故、マクロ
(巨視的な)が、近接撮影用レンズの名称になったのだろうか?
「ミクロ」あるいは「マイクロ」の方が適正な名称ではなかろうか?
まあでも、「マクロ」が間違った表現であっても、それが一般的に
なって広まってしまったのであればやむを得ないのかも知れない。
間違った技術用語を使う事も、個人的には大嫌いな事であるが、
もうここまで広まってしまっていたら”文句を言う方がおかしい”
という理不尽な状況になってしまっている。
さて、余談はともかく本システムにおける最短撮影距離(撮影倍率)
は、MC7へ装着時では詳細は不明だが、AiAF20/2.8単体では
25cmの最短撮影距離なので、恐らく18cm程度までには縮まって
いる事であろう。
DX 40/2.8が、最短16.3cmで等倍マクロであるので、まあ、
両者、ほぼ同等の使い勝手となるであろう。
さあ、これで、DX40mmマクロもどきの出来上がりだ。

実際の撮影感覚上では、40mmマクロ(APS-C機で換算60mm相当)
はマクロとしては、やや広角だ。しかし、GR Digital等コンパクトや、
SIGMA 20mm/f1.8を使った場合のような、換算28mm級の広角
マクロとは明らかに違う狭い画角であり、背景を広く取り込むタイプの
広角マクロ的な撮影は本レンズでは厳しい。
そして、マクロ撮影と言えば、一般的には、被写体が単体であり、
比較的作画上の狙いがはっきりしているので、そういう感覚に
おいては、画角が中途半端に広く思えてしまう。
まあ、でも、それは慣れもあるし、長らくデジタルのAPS-C機で
90mmマクロ等を使っていたのも仇になっているかも知れない。
結局、銀塩時代の50~60mmマクロと大差無い画角とも言えるので、
そういう目線で被写体を探せば近接撮影では問題はなさそうだ。

まあしかし、換算60mm相当の画角は中遠距離での画角感覚的には、
ちょっと中途半端に感じる場合もある。銀塩時代においても、
60mmのレンズはさほど多くなかったし、加えて個人的には、
換算60mmの画角が、どうも好みに合わない模様だ。
あるいは「20mmレンズを持ち出している」という意識が何処かに
あるので、余計に60mm相当の画角に違和感が生じるのかも
知れない。
さて、40mmマクロの感覚は掴めた、ちょっと好みでは無い感じだ。
そして、近接撮影ばかりでは、肝心の AiAF20/2.8本来の性能が
良くわからないので、マクロテレプラスMC7を外してみよう。

20mm単体、すなわちASP-Cで30mm相当とすると、とたんに
ピントが怪しくなってくる。これは銀塩一眼時代から感じていたの
だが、超広角レンズをMFで使うと、光学ファインダーでもEVFでも、
どこにピントが合っているのか、よくわからないのだ。
これはNEX-7の優秀なピーキング機能を用いても同様だ。
絞りは撮影毎に結構大きく変える、f2.8開放からf11程度までは
行ったり来たりフルレンジ使用だ。その際に、少し絞るとピーキング
が過剰に反応する。が、肉眼でもピント位置がわからない位なので、
まあ機械が判定するのは難しいとは思うが、ピントの不安は拭えず、
安全の為、絞り込んで被写界深度を稼ぐような面白味の無い設定
にも結びついてしまうのだ。
結局のところ、MF性能に問題の無いNEX-7を用いても、
AiAF20mm/f2.8のパフォーマンスは良くわからない。
本レンズの中古購入価格は、前述の通り30000円、
同等のスペックで、ミノルタα用 AF20/2.8が存在する
(第62回記事)
そちらは、1990年代に中古で36000円と、さらに高価であった、
まあ、いずれも銀塩時代であり、その頃の20mmといえば、超広角の
特殊レンズの扱いであった。ミノルタα純正では20/2.8が最広角の
単焦点であった位だ。まあ、そういう事情もあってか、当時の
定価や中古相場が高値であったのであろう。しかし、いずれも現代に
おいてAPS-C機やμ4/3機で使う上では平凡な広角画角となって
しまうし、最短撮影距離も、いずれも25cmと長く(20cm以下が望ましい)
描写力そのものも、「感動的」という要素は欠片も無いので、面白みに
欠けるレンズである。
銀塩またはフルサイズ機ならまだしも、センサーサイズの小さい
カメラでは超広角レンズの魅力は大幅に減退されてしまう・・
ちなみに、ミラーレス・マニアックス記事を書くまで、10年以上
使っていなかったレンズでもある。
最後に使ったのは、確か、雷(稲妻)の撮影であり、いつ何処に
落ちるかわからない雷を、広めの画角のレンズで、カシャリ、カシャリ
と撮っていた訳だ。が、つまらなかったので、それ以降はやっていない
のだが、仮に、そういう目的であっても、より広角な10mm台からの
ズームとかの方が現代においては便利であろう。
銀塩やフルサイズ機で使うにしても、現代の撮影技法においては、
10mm台の広角の方がダイナミックな画が撮れて良いかもしれない、
昔はそういう超広角レンズは、あまり無かったり、高価だったり
したが、現代では入手しやすくなってきているのだ。
こりゃあ、20mmは、いらないレンズになりそうだなあ・・(汗)
-----
さて、次のシステムは、レンズの新たなる使い方だ。

カメラは、PENTAX K-01
レンズは、KENKO PINHOLE 02 である。
第59回記事で紹介した2000年代の市販ピンホールである、
(市販と言っているのは、ピンホールは自作する事も可能で、
むしろそれが一般的である為だ)
ピンホールレンズは、一眼レフでは様々な制約があって使い難いが、
(光学ファインダーが真っ暗で見えない、ライブビューを使っても
ゲイン(明るさを稼ぐ倍率)が、そこまで上がらず、暗い場合が多い)
K-01では、ISOがAUTOのまま25600まで上がり、日中なら手持ちで
十分に撮影可能、で、いざとなれば内蔵手ブレ補正も効くし、かつ、
モニターも暗くならないので、ピンホールとの相性は極めて良い事が、
当該第59回記事で明らかになった。
(注;K-01の背面モニターの輝度ゲインにも限界がある為、暗所
での撮影では輝度が上がらず、暗くなってしまう場合もある)

その後、第66回記事では、本ピンホールと、他の市販ピンホール
であるRISING との比較を行った。
(本レンズは、ピンホールにしては、なかなか良く写るという結論)
また、補足編2では本ピンホールをティルトアダプターで使ってみた。
(これは残念ながら、ティルト効果無し)
まあ、普通にK-01で使うのが良さそうなのだが、K-01の最大の
特徴は「エフェクト母艦」である。様々なエフェクトと、その設定の
バリエーションが多く、また、エフェクト操作系も悪くない。
したがって、ピンホール撮影の場合でも、エフェクトを活用する
べきであろう。今回はそうした撮影を行ってみるとする。
ピンポール撮影であっても、勿論エフェクトは有効だ。

かつてピンホールは銀塩一眼レフユーザーの趣味的な要素で
あったのが一般的で、デジタルになってからは、あまり流行して
いないように思える。
撮像素子上のゴミが写りこむのが、やはり気になるからであろうか?
同様に、ミラーレス機でピンホールを使う事も少ないと思う。
これはミラーレス機ユーザーの大半がビギナー層であり、こうした
ピンホールの存在を知らないか、知っていたとしても、どうやったら
使えるのか?がわからないからであろう。まあでも、ミラーレス機と
ピンホールは相性抜群である事は明白だ、いまさら一眼でピンホール
撮影をやろうという気には、全くなれない。
しかし、相変わらずだが、ピンホール撮影はセンサーのゴミが写る。
(大きいものについては、レタッチで消している)
K-01には、手ブレ補正機構を応用した振動式ダストリムーバル機能
がついている、一応それをかけているが、あまり効果は無い模様だ。
(電源投入時にそれを動かすというオリンパスの特許があったと
思うが、他社では電源OFF時に掃除したり、いつするかを選択できる
ようにして特許を回避している模様だ)

余談だが、今回K-01を使用中に、ちょっとしたトラブルが発生。
電源スイッチのカバー部品が外れて落ちてしまった。
K-01は海外のデザイナーが、あまり製造の事を意識せずデザイン
したモデル故に構造上の弱点が多数存在する。
モードダイヤルや電源スイッチは接着で乗せているだけだし、
カードスロットのカバーは単なる嵌め込みだ。
以前はモードダイヤルが脱落し、それは接着剤で補修した。
今回もまた同様だ、夏場の暑さで接着力が弱まってしまったので
あろう。部品を拾って、帰宅後、電源スイッチを瞬間接着剤で
固定したが、はみ出た接着剤が、同軸となっているシャッターに
干渉し、シャッターが切れなくなってしまった(汗)
やむなくシャッターボタンのカバーを外し、内部を精密ドライバーで
削り取り、シャッターカバーも紙やすりで削り、リチウムグリースを
流し込んで、やっと動くようになったが、この修理に1時間半も
かかってしまった・・
近年の日本の工業製品だと、製造の事を考えて、あまりこういう
無茶な設計をする事は無いのだろうが、K-01の開発秘話のような
記事を読むと、デザイナーが凄く拘っていたので(頑固だったので)、
PENTAX側は設計変更の余地が無かったという様子であった。
まあ、有名海外デザイナーの起用も良し悪しあるという事だろう。

本ピンホールの購入価格は、2010年代に新品で3000円程度、
まあ、自作の場合はここまでピンホールの精度が出ないと思うので、
画質は悪くなってしまう。ピンホール撮影に興味がある場合は、
新品を購入してしまうのも無難で良いかも知れない。
-----
さて、今回の最後は、未紹介のシステムだ。

カメラは、LUMIX DMC-G5
レンズは、MINOLTA AF Macro 100mm/f2.8 (NEW)
1990年代のAF中望遠等倍マクロレンズである。
本レンズは銀塩時代に、これ以前の初期型を使っていた事があるが、
TAMRON SP90mm/f2.8 Macro にリプレイスした為、そのレンズ
は譲渡した。しかし、後にして思えば、確かに TAMRON90マクロは
優れたレンズではあるが、ミノルタ100マクロも捨てたものでは
なかったな、と思い出していた。
で、「いつか買いなおそう」と思って、以来、十数年が経過したのだが、
最近、相場より安価な中古の出物があったので、これを購入した次第だ。

NEW TYPE となっているので、初期型の非常に細いピントリングよりは
若干改善されているのだが、依然ピントリングは細く、操作性は悪い。
これ以降の D型(ミノルタ最終型)となれば、十分な広さのピント
リングがあるのだが、あいにく中古価格が1万円以上高くなってしまう。
(SONY型も、ミノルタ型と同一のレンズ構成で、さらに高価だ。
これは、ミノルタαレンズをSONYブランドで再生産した際に、
定価を軒並み15~25%程度も上乗せしたからだ)
いずれのレンズも光学系は全て8群8枚で同一と思われるので、
まあ微妙な選択ではあるが、NEWを選んだ次第である。
(初期型は殆ど見かけない)

レンズの写りだが、ちょっと微妙な感じだ。
ボケ質の破綻が発生しやすい、それとハイライト部に滲み
(ハロあるいは収差)が出やすいように思える。
また、近接撮影はともかく、中距離あたりから解像度が低下する
ような雰囲気もある。
レンズの落下痕やアタリ等の様子は無く、光軸ズレなどの故障も
無い模様であるが、では、これはこういう性能なのだろうか?
銀塩時代に初期型を使っていた記憶では、もう少し良かったと思う。

まあしかし、銀塩時代は一眼レフの光学ファインダーでは開放測光
である事からも、ボケ質その他の厳密なチェックは出来なかったし、
撮影後に現像して、たまたま良く写っている写真を見て、
「これは良いレンズだ」と思い込んでしまう事も多々あったであろう。
勿論、本レンズにおいても、ちゃんと写る場合も多い、
けど、その歩留まり(成功率)が悪いという弱点があれば、それは
ちょっと気になる問題点だ。

本レンズの中古購入価格であるが、本年2016年に18000円台で
あった。
本来の中古相場25000円前後よりも若干安いし、この値段であれば、
中望遠銘マクロの両雄 すなわち
TAMRON SP90/2.8(第31回=PK用、第63回=α用)
SIGMA AF105/2.8Macro(第41回=EF用、第63回=AiAF用)
の各旧型レンズの中古購入価格である20000~25000円程度よりも
安価であり、その点においては、コスパは良いと言えよう。
ちなみに、京セラ・コンタックスのRTS MAKRO PLANAR 100/2.8
(第16回記事)は、操作性の良く無いレンズであるが、1990年代の
購入時に中古で82000円もしたし(汗)現在の相場も同様に高価だ。
それに比べると、本レンズは同等の描写力で価格は1/4以下と
なっている。
TAMRON/SIGMAのマクロがあれば不要なレンズかも知れないが、
α(A)マウントユーザーであれば、購入検討の余地はあるレンズだ。
----
さて、今回はこのあたりまでで、次回補足編に続く。