今回は補足編として「100mm(級)マクロ・マニアックス」
という主旨とする。
ここの定義であるが「実焦点距離が100mm~110mmの
フルサイズ対応、1/2倍以上のマクロレンズ」とし、
この条件で6本、およびAPS-C機で換算100mm程度となる
レンズを1本、計7本を紹介するが、いずれも過去記事で
紹介済みのレンズである。
また、この条件に当てはまるレンズは、もっとずっと
多数を所有しているが、全てを紹介するのも冗長であるし
ここでは、あまり他記事での登場回数が少ないものを
中心に、ローテーション使用(できるだけ多くの所有
レンズを、定期的に使ってあげる事)の観点での選択と
しよう。
----
まず、今回最初の100mm(級)マクロレンズ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズは、COSINA (MC) MACRO 100mm/f3.5
(新品購入価格 14,000円)
カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)
詳細不明、恐らくは1980~1990年代頃のMF中望遠
1/2倍マクロレンズ。(注:下写真はエフェクト使用)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
新品価格は極めて安価であるが、これは他記事でも
良く書く「コシナの7割引戦略」であったからだ。
このレンズの発売当時から、コシナは大手OEMメーカー
ではあったが、ブランド銘が一般層に全く知られて
おらず、「7割引!」のような極端な値引き戦略を
取らないと、誰もコシナ製のレンズを買わなかった
訳である。
ちなみに、本記事のラストで紹介する、同じコシナ製
Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5
は、新品購入価格が本レンズのおよそ10倍であるが、
スペックもある意味似たようなものだし、そちらが
10倍も写りが優れている訳でも無い。
この値段差が「ブランドの付加価値」であり、
メーカー(コシナ)側は、そのように高価で高品質な
レンズを売っていかないと、今時の縮退したレンズ
市場で、かつMFレンズなどでは、やっていけない訳だ。
だから、「フォクトレンダー」や「カールツァイス」の
高級ブランド商標を取得して頑張っている訳だが、勿論
これらは同じ工場の同じ生産ラインで製造された
同様の金属とガラスとプラスチックの塊である。
値段が10倍も違う、というのは、あくまでブランド代
な訳なのだ。
(注:「非球面レンズや異常部分分散ガラスレンズを
使っていて高性能だから高価なのだ」と言う、もっとも
らしい意見はあるだろうが、多少の高額部品を使っても
製品の原価が10倍にも跳ね上がる訳では無い。
むしろ、それらの特殊硝材は、ガラスモールド非球面等
の製造技術の進歩で、年々コストダウンしている状況だ。
さらに言えば、その10倍高価なMAP110/2.5は、
非球面レンズは、1枚も使用していない。
だが、少しでも原価が上がると、商品価格も上昇し、
結果、生産・販売数が減り、量産効果が出ないでコスト
アップするばかりか、設計・開発費の償却も、少ない
生産本数に割り振る為に高額にならざるを得ない。
要は、どんどんと価格が上がる「悪循環」に陥る訳だ。
でも、その高価格でも売らざるを得ないから、よって
「ブランド・バリューの付加価値に頼るしか無い」
という状況だ。つまり、基本的に「良い素材を使って
いるから高価なのだ」という理屈は、有り得ない話だ。
これはレンズに限らず、どの商品分野でも同じ事だが、
近代では、「プレミアム」とかいう意味不明な言葉で、
その事実は隠されてしまっている事が殆どだ)
・・ただまあ、本レンズは「7割引戦略」と言っても、
最初から1万円台で売る事を想定されて設計された
「ローコスト」レンズである。レンズ構成は恐らく
とても簡素なものであり、当然、非球面レンズとか、
低分散ガラス等の、金のかかる部材は使われていない。
よって、描写傾向も独特である。これは本ブログで
言うところの「平面マクロ」の特性を持つ。
(匠の写真用語辞典第5回記事参照、および
特殊レンズ第20回「平面マクロ」編参照)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17421547.jpg]()
私は、銀塩時代には、こうした「平面マクロ」特性を
持つレンズが嫌いで、せっかく入手した、この手の
マクロレンズを何本か手放してしまっていた。
だが、近年になって、そうした「平面マクロ」を
再購入するケースも増えている。
それは、現代的な、殆ど弱点が無いマクロレンズ
(例えば、後述のマクロアポランター110/2.5等)
では「使いこなし」の為のテクニカルな「エンジョイ度」
が低く、そして、誰が撮っても綺麗に撮れてしまうから
「差別化要因」が少ない。さらに言えば、銀塩時代に、
こうした「平面マクロ」を上手く使いこなせなかった
のは、自身が「レンズの言うがまま」に撮っていたから
であって、それはレンズの弱点では無く、ユーザー自身の
責任である事を近年になって思うようになったからだ。
まあつまり「平面マクロ」である事がわかっているならば、
それは使いこなし次第では、何ら問題が無い訳であるし、
さらに言うならば、全て高描写力なレンズばかりで
優等生的になってしまった(かつ高価な)現代レンズ
では有り得ないような描写が得られる可能性がある事も、
そうしたレンズの弱点を逆に利用する、という視点にも
繋がるだろう。その手の措置は、極めて高度なスキルを
要求される話なのだが、その困難にチャレンジしてみる
事は、マニアックで、テクニカルな「エンジョイ度」を
高める意味で、価値があるのではなかろうか・・?
----
では、次のレンズ
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17421546.jpg]()
レンズは、NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4
(中古購入価格 8,000円)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
1977年発売のMF小口径中望遠1/2倍マクロレンズ。
さて、こちらも「平面マクロ」特性を若干持つ
レンズである、もしかすると、この時代1970年代~
1980年代の各社MFマクロレンズの大半は、その描写
傾向を持つ訳であり、それは、やはり簡素なレンズ構成
からくるのだと思われる。技術的な未成熟とも言える
要素もあり、そこが改善されて、マクロレンズが
様々な被写体条件で高描写表現力を発揮できるように
なるのは、概ね、1990年代のAF等倍マクロの時代
以降の話である。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17422497.jpg]()
ただ、「平面マクロ」の特徴とも言える
「シャープな描写傾向」を活用できるのであれば、
この手のオールドマクロレンズも悪くない。
特に本レンズの場合は、1960年代~1970年代の
ニッコール銘マイクロ(マクロ)レンズに対し、
市場が要求したニーズである「資料複写」の目的には、
良くマッチしている特性だ。
他記事でも良く書くが、この時代は、まだコピー機が
普及していなかったので、各種重要資料の複写には
写真が使われた事も良くあった訳である。
その代償として、平面マクロはボケが固い。それは
つまり設計上では「重要視しなかった」からであり、
この時代に「ピント面はシャープでボケも綺麗」と
いった完璧な性能のレンズを作るのは困難であるし
たとえそうしたとしても、非常に高価なレンズで
あれば、それは売れなくなってしまう。
(まあ、現代の高性能レンズでも、高価すぎて
売れないもは多々あると思われるが・・)
なお、これより後年のニコン製マイクロのF2.8版
(MF/AF)では、平面マクロ特性はだいぶ薄れている
と思われるが、所有していないので詳細についての
言及は避ける。
(追記:本記事執筆後に、全てのNIKKOR 105mm
マイクロを、研究目的で購入している。
いずれ、別記事で詳細の比較を行おう)
ともかく、開放F値の違いは、性能や値段の差別化
では無く、描写傾向そのものが、全くの別物となる
ケースが大変多い事も、ユーザー層は良く知って
おく必要があるだろう。まあすなわち、
「値段が高くて、開放F値が明るいから、と言って、
必ずしも、それが良い(良く写る)レンズだとは
限らない」という大原則である。
本レンズの総括だが、不人気で相場が安価だ。
Ai NIKKORは、中古相場が高いのが特徴(弱点)で
あるが、これは「オールドファン層」が注目するのと、
一部、投機的観点も加わっているからだ。
しかし、本レンズは、F4という暗い開放F値により
「F2.8版よりも低性能だ」という、ビギナー層や
初級マニア層での誤まった認識がある為か、中古相場
が安価である事がコスパの良さに繋がっている。
「主要被写体をシャープに写す」という目的であれば、
本レンズは十分に使えるし、むしろその特徴が強い、
ユニークなレンズだ。
さらにマニアックな話をするならば、本レンズは
3群5枚の「ヘリアー型」構成である。
これは1900年に、旧フォクトレンダー社で開発された
当時としては極めて優秀な特性を持つレンズである。
だが、意外な事に、写真用(交換)レンズの構成と
して、純粋な「ヘリアー」型が採用された例は
極めて少なく、数える程しか存在しない。
(名前だけ「ヘリアー」という物は、色々ある。
いずれ、ヘリアーを集めて特集記事を組む予定だ)
この、「レジェンド」とも言える特性を味わう事、
描写力を体感する事は、マニアとして興味を持たない
筈が無いではないか・・
まあ、使いこなせるならば悪く無いレンズだ。
----
さて、3本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17422416.jpg]()
レンズは、CONTAX Makro-Planar T* 100mm/f2.8 AEJ
(Y/Cマウント)(中古購入価格 82,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited (μ4/3機)
1980年代後半頃に発売と思われるMF中望遠等倍マクロ。
定価が確か198,000円(+税)もしたので、CONTAX党の
初級中級層からは「神格化」されたレンズである。
すなわち「値段が高いものは良いモノに違い無い」
という誤解だ。勿論「必ずしもそういう訳では無い」
事は、もう本ブログでは何百回書いた事だろうか・・
もし、その誤解を持ち続けているならば、もうそれは
永久にビギナーのままであり、何の進歩も無い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17422402.jpg]()
本レンズは、その発売時点においては、前述の
他社マクロレンズの大半が、
「MF、1/2倍、小口径(F3.5~F4)、平面マクロ特性」
であった、という状況に対し、それ以降の時代の
「(AF)、等倍、大口径(F2.8)、ボケ質も重視した特性」
という特徴において、AF化以外の点で、他社マクロに
先駆け、いち早く現代的な特性を実現した事が、特徴に
なっていたと思われる。
しかし、その特性は他社からも注目されたと思われ、
本レンズの特性を参考とした新時代のAFマクロレンズが
1990年代に出揃った、とも言えるかも知れない。
本マクロプラナーの弱点は、劣悪とも言えるMF操作性
であり、私が言う「修行レンズ」に近いものがある。
(本シリーズ第11回「使いこなしが難しいレンズ編」
では、ワースト5位を、本レンズが記録している)
発売時点ではともかく、数年後においては、例えば
TAMRON SP 90mm/F2.8(72E型、1996年)が登場
したあたりからは、やはり新型AFマクロの圧倒的な
使用利便性に市場での軍配が上がった事であろう。
で、ご存知のようにRTS(Y/C)系ツァイスレンズは、AF化に
移行できず、MFのまま銀塩時代を終えてしまっていたのだ。
(注:Nマウントに関しては、銀塩一眼第24回記事
「CONTAX N1」編等を参照。ただし、あまり喜ばしい
歴史では無く、ちょっと悲劇的な結末となっている)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17422467.jpg]()
ただまあ、MF操作性とコスパの減点を除き、
本レンズの他の個人評価点は悪くなく、個人DB(データ
ベース)での総合点は、3.8点と、名玉(総合4点以上)
に、あと一歩という状態である。
----
では、4本目のシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17423162.jpg]()
レンズは、SIGMA AF MACRO 105mm/f2.8 EX DG
(中古購入価格 5,000円)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
2000年代前半に発売と思われる、AF中望遠等倍マクロ。
購入価格5000円は安価すぎるが、これはAF故障品を
購入した為であり、本レンズはAFが効かない。
同型レンズ(完動品)を異マウントで同時期に購入して
いて、そちらは25,000円の中古取得価格であった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17423105.jpg]()
MFのみでの撮影となるが、大きな瑕疵とは見なして
いない。近接撮影では、AFよりもMFを多用する場合が
通例であるからだ。
よって、さらにこの後の時代、2000年代後半より
2010年代においては、マクロレンズであっても、
内蔵手ブレ補正機構や、超音波系のモーターを搭載し
高付加価値を狙った製品が後継機種として発売され
始めた状況ではあったが、個人的には、「どうせMFで
撮るのだから、超音波モーター等は不用」と思って
いて、その手の機能の入っているマクロレンズは
殆ど購入していない。無駄と思われる機能に代金は
払いたく無いからであって、これは「コスパ至上主義」
の一環でもある。(注:超音波モーターを入れて
シームレスMF機構とすると、MF操作性が極端に悪化
する事も、重要な理由の1つである)
ちなみに、内蔵手ブレ補正だが、これも不要だ。
何故ならば、
1)近接撮影では、手ブレ補正機能では補正できない
前後方向への「距離ブレ」が多く発生する。
2)屋外撮影等では、自分がブレるよりも、風を起因と
したり、昆虫等の被写体が動くといった理由による
被写体ブレが良く発生し、当然、手ブレ補正では、
それらを抑える事は出来ない。
事が理由である。
ここも同様に、無駄な機能に1円たりとも代金を払う
つもりは毛頭無い。
両者が併売されていたら、迷わず安価な手ブレ補正無し版
を購入するだろう。そして、場合により、レンズ構成等に
よる描写力・描写傾向は、その両者で、全く同じである
ケースもあるからだ。
さて、故障問題についてだが、本レンズより前に
完動品(故障なし)を先行して購入していたのだが、
その優秀な特性(レンズ総合評価3.8点、名玉1手前、
前述のMakro-Planar 100/2.8と同得点)
に感心し、本レンズのAF故障品を異マウントで
見つけた際、「このレンズだったら2本持っていても
悪く無い」と思っての購入に繋がった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17423156.jpg]()
SIGMA製のマクロは、1990年代以前のものは、性能が
気に入らず、手放してしまった事もあったのだが、
1990年代を通じてかなりの描写力改良が行われた
模様であり、2000年代以降のマクロに関しては、
悪く無いので、複数本を購入し、愛用している。
(参考:特殊レンズ第42回「伝説のSIGMA MACRO編」)
----
さて、5本目の100mmマクロシステム
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17423118.jpg]()
レンズは、TOKINA AF 100mm/f3.5 MACRO
(中古購入価格 3,000円)
カメラは、NIKON D300 (APS-C機)
正式型番不明、発売年不明、恐らくは1990年代と
思われる小型軽量AF中望遠1/2倍マクロレンズ。
冒頭で紹介したCOSINA 100/3.5(MF版)の、AF版の
OEMのような製品にも思われる。仕様や描写傾向が酷似
しているからである。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17423909.jpg]()
最初からローコストを狙った設計であり、高級感が
全く無いのが、手にして目に付く弱点であろうか・・
中古店での販売価格は、当初もう少し高価であった
のだが、行き付けの中古店で、予約購入前に店長が
このレンズをチェックして、「少し曇りがありますね、
どうされますか?」という話があり、私がチェック
してみると、さほどでも無かったので「値引きして
いただければ引き取りますよ」と応え、安価に入手
する事ができた。
個人的には、あまりに酷い物を除き、多少のクモリとか、
ゴミ等は気にしない、問題は、価格に見合う性能が
得られるかどうか?(コスパが良いか否か?)の、
ただそれ1点なのだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17423923.jpg]()
さて、本レンズは「平面マクロ」である。
まあ、平面マクロの場合、本来は(デジタル)一眼
レフよりも、ミラーレス機で実絞り(絞り込み)測光
で用いた方が望ましい。何故ならば、「平面マクロ」
の弱点である、ボケ質(の固さ、破綻)の課題を回避
するとしても、逆用するとしても、絞り値に対応する
ボケ質傾向を、高精細のEVF等で確認しながら撮影する
必要があるからだ。これを行わないで、一眼レフでの
開放測光では、どんなボケ質となって写るかは、
撮影前に判断する事は困難か不可能であるからだ。
ただまあ、平面マクロではあるが結構シャープな写りを
するレンズであり、AF動作が「ガタピシ」と、スムース
では無い弱点も、MFで撮れば何も問題は無い。
安価で購入した事から結果的にコスパも良くなっている。
悪く無いレンズだ。
----
では、6本目のシステム、こちらは100mm級では無い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17423944.jpg]()
レンズは、SIGMA MACRO 70mm/f2.8 EX DG
(中古購入価格 28,000円)
カメラは、EOS 8000D (APS-C機)
2006年発売のフルサイズ対応中望遠AF等倍マクロレンズ。
本シリーズ第29回記事では、フルサイズ機で使用したが、
今回はAPS-C機とし、換算画角はEOS機では112mm、
一般的APS-C機ではx1.5倍で、105mm相当となる。
当該第29回記事では新鋭SIGMA 70mm/f2.8 DG | Art
とも比較していて、これは新旧の「カミソリマクロ」
対決の様相もあった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17424072.jpg]()
「カミソリマクロ」とは、その呼び方がマニア層に
定着している訳では無いのだが、初出の頃の評価記事で
評論家が、その名称を使った事を発端としているので
あろう。
SIGMAでは、その呼び方が気にいったのか、後継のART
型の発売時に「伝説のカミソリマクロが復活」という
キャッチコピーを新型マクロ(ART型)に付けた訳だ。
ただまあ、2000年代~2010年代のSIGMAを含めた
各社のマクロレンズの大半は、多かれ少なかれ
「カミソリ」的な描写傾向を持っている。
だが、多数の近代(2010年代以降)マクロを所有して
いる訳では無いし、むしろ近代マクロは前述のような
余計な付加価値(手ブレ補正や超音波モーター等)が
入っている事が嫌いで、あまり購入していないので、
あまり全般的かつ詳細な話は避ける事としょう。
でも、実際のところ、この新旧「カミソリマクロ」
よりも、キレッキレのマクロレンズは何本か存在
している。ただまあ、そのあたりも設計のコンセプト
次第であり、例えば、カリカリ、キレキレの描写を
得る為に、(トレードオフ関係になりやすい)ボケ質の
悪化などが顕著になってしまったら、それはもう
「カミソリか否か」というよりも、全体のバランスを
崩してしまっている設計と言わざるを得ない。
やはり、まずはボケ質や中遠距離描写等を含めた、
レンズの基本描写性能が高い事が望ましく、その上で
さらにシャープな解像感を持つならば、それは真の
「カミソリマクロ」と言えるのかも知れない。
それと、マクロであっても、望遠焦点距離になれば
なる程、あるいは撮影倍率を高める程、絞りを開ける
程、背景ボケを大きく(被写界深度を浅く)取る事が
可能となる。この内、絞りの要素は、開ける事で諸収差が
増大するケースが多く(注:そうならない類の収差も
存在する)その事と「カミソリ感」は矛盾するケースも
あるのだが、他の、望遠にする、近接する、の要素は、
それらにより被写界深度を極めて浅い状態にする事も
容易である。そこまで背景や前景を「大ボケ」にして
しまい、その設定においても、場合により「ボケ質破綻」
は回避が可能だ、つまり、ボケすぎる状態を作り出せば、
ボケ質の多少の悪化は気にならない、という訳だ。
そうすると、絞り値の利用自由度も若干高まるので、
少し絞って諸収差を低減し、解像感を稼ぎつつも、背景
等のボケ質は、固くなったり破綻せずに済む状態を
作り出せる可能性も高い。だから、中望遠や望遠マクロ
の中には、一見、極めて高性能な「カミソリマクロ」的
な描写を得やすいレンズも多い訳である。
ただし、ここも良く注意していないと、そのように
諸条件を整えて撮影が出来るケースも、そう多くは無い
という事であり、かつ、一眼レフ使用等で、ボケ質等に
厳密性や精密性の無い、ラフな使い方をしてしまうと、
そういう細かい設定条件に上手く当たる確率は極めて
低い、という点である。
だから、レンズの描写力はユーザーの使い方によって
大きく変わってしまい、たった数枚とかの、たまたま
写りが良い(悪い)写真を見て、「このレンズの写りは
良い(悪い)」といった評価を下す事は出来ない。
何千枚も、下手をすれば何万枚も、様々な条件で写して
みない限り、まともな評価は出来ず、それは場合により
何年も、あるいは10年以上もかかってしまう事もある。
だからまあ、本ブログにおいては、あまりに発売された
ばかりの、新しいレンズを取り上げる事は、非常に稀で
あり、たいていは発売後数年位は、色々と撮った上で
レンズの評価をしている。
あるいは、たまたまそうした発売直後での紹介のケース
があったとしても、長く使っていないと分からないような
性能については、その言及を避け、「追加検証が必要」
等の結論や総括にしている場合も多い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17424592.jpg]()
それと、本レンズの場合は、今回使用の普及機(EOS
8000D)等においては、ピント精度が怪しいケースも
出てくるので要注意だ。普及機における仕様的差別化
なのか?AFの精度は高く無いし、MFで使おうにも、
壊滅的とも言えるファインダーやスクリーンの低性能
で全くMFに向かない。
よって、マクロレンズはMFでミラーレス機で使うのが
あくまで基本ではあるのだが、AF一眼レフ用のレンズ等で、
ミラーレス機での使用が適さないマクロの場合には、
一眼レフで使う上では、出来るだけ、AF/MF性能に優れた
機種を選択するのが無難であろう。
CANON EOS(一眼レフ)機で、その条件を満たすものは
多く無いが、MF用のスーパープレシジョンマットに換装
された、やや古いEOS 5D Mark2/6Dあたりの機体が向く
かも知れない。(注:それらの後継機では、スクリーン
交換が不可な機体が殆どである)
----
では、次は今回ラストのマクロシステム。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17424596.jpg]()
レンズは、Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5
(注:変母音記載省略)(新品購入価格 138,000円)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
2018年発売の、MF等倍マクロレンズ。
コシナ史上3本目のマクロアポランターであり、現状では
SONY E(FE)マウント対応品しか発売されていない。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17424537.jpg]()
非常に高価な入手(販売)価格がネックとなる製品であり、
見るからにコスパが悪い。
ただ、高価なのはレンズ市場が縮退している事が最大の
原因であり、誰もレンズを買わないから、値上げした
商品を売らないと、メーカーも流通も、ビジネスを維持
していけない。しかし「高いから皆、買わない」という
悪循環が発生している。
それでも新品で買ってしまっているのは、第一に、コシナ
(特にフォクトレンダー)製品は、販売(製造ロット)
数量が少なく、いつの間にか売り切れになって、後年では
入手困難となるケースがとても多いからだ。
特に、本レンズの前機種である、2001年発売の
MACRO APO-LANTHAR 125mm/f2.5 SLは極めて販売数
が少なく、後年の中古市場で「投機対象」となってしまい、
新品販売時点での最安値の4倍以上、というべらぼうな
プレミアム価格となってしまっている。
当該レンズに、そこまでの価値は無く、むしろ、使い
難いレンズの代表格だ。
(本シリーズ第12回「使いこなしが難しいレンズ」
特集でワーストワン。
また、特殊レンズ第11回「マクロアポランター・
グランドスラム」編記事等を参照)
「希少なレンズだ」という理由で、後から高値で購入
する事は望まないので、気になるならば、なんとしても
販売期間中に入手するしか無い。
また、この手のレンズのユーザーはかなりのマニアであり、
そう簡単に手放す事も稀で、中古市場ではまず見かけない。
本レンズや姉妹レンズの65mm/F2版は、ごく稀に中古市場に
出ては来たのだが、やはり玉数は少なく、かつあまり相場も
安価では無かったので、買い難い状況である点は一緒だ。
(追記:近年では、65mm/F2版の中古流通数は多いが、
110mm/F2.5版の中古流通は極めて少ない)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17424500.jpg]()
それと、この手の「マニアックすぎる」レンズは、
市場(流通やメディア)でも、あまり評価や情報が無い。
何故ならば、市場では、売りたいレンズ、売れるレンズを
ユーザーに勧めた方が、売り上げを伸ばす意味では
正当であって、何も「売り難い、売れない」レンズの
評価や宣伝に、時間や金を掛ける事は、したくない訳だ。
(→宣伝記事を書くならば、初級中級層に人気の「大三元」
レンズの話をした方が、販売側としては得策であろう)
でも、そうなると「誰かが良いと言ったから買う」という
受動的スタンスのユーザーが大半である現代の世情では、
誰も何も言っていないレンズを「怖いもの見たさ(笑)」
で入手しようとする奇特なユーザー層の比率は限りなく
低く、結局、より一層、この手のレンズは売れなくなる
という悪循環だ。
そういう市場状況は発売前から見込んであるだろうから
企画台数(生産本数)も少なく、結局、開発や製造に
係わる多額な経費を、少ない販売本数で償却せざるを
得ず、個々のレンズの価格は、どうしても割高となる。
だから、コスパが悪い事は必至であり、よってこの手の
マニアック度が高い(あまり売れない)レンズは、
本ブログの「ハイコスパ」系の記事には登場しないし、
「名レンズ編」等でも、コスパの悪さがネックとなって
総合上位にはランクインできない状況である。
しかし、本レンズの場合等では、値段以外に弱点は
殆ど無く、これが唯一無二の性能を持つものであれば
パフォーマンスが高く、結果としてのコスト高は
ある程度は相殺される。
まあでも、このあたりは、ユーザーにおけるレンズの
利用目的等にも依存するのも確かだ。
そして、今時、E(FE)マウント機でMFのみで、「瞳AF」
や「ファストハイブリッドAF」も利用できないならば、
そういう「不便なレンズ」に興味を持つ、αユーザーも
極めて少ない事であろう。
まあでも、本レンズは、壊滅的なコスパの悪さ以外は
大きな弱点を持たない。その「描写表現力」評価点は、
400本程度の所有レンズ中、十数本しか無い5点満点
であるし、総合評価点も、3.9点と、名玉の条件の
4点以上に、あと一歩である。
中古購入が出来て、コスパ点が、もう少し良かったら
評価点は、4点を越え、様々な「名玉記事」に
ノミネートやランクインをしていた事であろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![_c0032138_17425062.jpg]()
値段が高い事を除いては、かなり好評価のレンズで
あるという状況なので、MF操作を厭わず、かつコスト
高に目をつぶれる中級者層以上であれば、今回紹介の
100mm級マクロレンズの中では、唯一推奨できるレンズ
だと言えるかも知れない(他のマクロは、多少マニアック
すぎる点がある・汗)
参考関連記事:
特殊レンズ第11回「マクロアポランター・グランドスラム」
本シリーズ第32回補足編「新旧マクロアポランター対決」
----
さて、今回の「100mm(級)マクロ・マニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。
という主旨とする。
ここの定義であるが「実焦点距離が100mm~110mmの
フルサイズ対応、1/2倍以上のマクロレンズ」とし、
この条件で6本、およびAPS-C機で換算100mm程度となる
レンズを1本、計7本を紹介するが、いずれも過去記事で
紹介済みのレンズである。
また、この条件に当てはまるレンズは、もっとずっと
多数を所有しているが、全てを紹介するのも冗長であるし
ここでは、あまり他記事での登場回数が少ないものを
中心に、ローテーション使用(できるだけ多くの所有
レンズを、定期的に使ってあげる事)の観点での選択と
しよう。
----
まず、今回最初の100mm(級)マクロレンズ。
Clik here to view.

(新品購入価格 14,000円)
カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)
詳細不明、恐らくは1980~1990年代頃のMF中望遠
1/2倍マクロレンズ。(注:下写真はエフェクト使用)
Clik here to view.
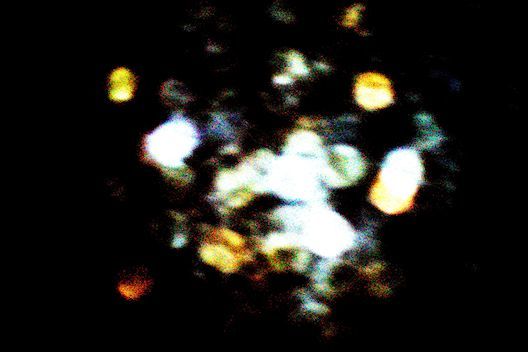
良く書く「コシナの7割引戦略」であったからだ。
このレンズの発売当時から、コシナは大手OEMメーカー
ではあったが、ブランド銘が一般層に全く知られて
おらず、「7割引!」のような極端な値引き戦略を
取らないと、誰もコシナ製のレンズを買わなかった
訳である。
ちなみに、本記事のラストで紹介する、同じコシナ製
Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5
は、新品購入価格が本レンズのおよそ10倍であるが、
スペックもある意味似たようなものだし、そちらが
10倍も写りが優れている訳でも無い。
この値段差が「ブランドの付加価値」であり、
メーカー(コシナ)側は、そのように高価で高品質な
レンズを売っていかないと、今時の縮退したレンズ
市場で、かつMFレンズなどでは、やっていけない訳だ。
だから、「フォクトレンダー」や「カールツァイス」の
高級ブランド商標を取得して頑張っている訳だが、勿論
これらは同じ工場の同じ生産ラインで製造された
同様の金属とガラスとプラスチックの塊である。
値段が10倍も違う、というのは、あくまでブランド代
な訳なのだ。
(注:「非球面レンズや異常部分分散ガラスレンズを
使っていて高性能だから高価なのだ」と言う、もっとも
らしい意見はあるだろうが、多少の高額部品を使っても
製品の原価が10倍にも跳ね上がる訳では無い。
むしろ、それらの特殊硝材は、ガラスモールド非球面等
の製造技術の進歩で、年々コストダウンしている状況だ。
さらに言えば、その10倍高価なMAP110/2.5は、
非球面レンズは、1枚も使用していない。
だが、少しでも原価が上がると、商品価格も上昇し、
結果、生産・販売数が減り、量産効果が出ないでコスト
アップするばかりか、設計・開発費の償却も、少ない
生産本数に割り振る為に高額にならざるを得ない。
要は、どんどんと価格が上がる「悪循環」に陥る訳だ。
でも、その高価格でも売らざるを得ないから、よって
「ブランド・バリューの付加価値に頼るしか無い」
という状況だ。つまり、基本的に「良い素材を使って
いるから高価なのだ」という理屈は、有り得ない話だ。
これはレンズに限らず、どの商品分野でも同じ事だが、
近代では、「プレミアム」とかいう意味不明な言葉で、
その事実は隠されてしまっている事が殆どだ)
・・ただまあ、本レンズは「7割引戦略」と言っても、
最初から1万円台で売る事を想定されて設計された
「ローコスト」レンズである。レンズ構成は恐らく
とても簡素なものであり、当然、非球面レンズとか、
低分散ガラス等の、金のかかる部材は使われていない。
よって、描写傾向も独特である。これは本ブログで
言うところの「平面マクロ」の特性を持つ。
(匠の写真用語辞典第5回記事参照、および
特殊レンズ第20回「平面マクロ」編参照)
Clik here to view.

持つレンズが嫌いで、せっかく入手した、この手の
マクロレンズを何本か手放してしまっていた。
だが、近年になって、そうした「平面マクロ」を
再購入するケースも増えている。
それは、現代的な、殆ど弱点が無いマクロレンズ
(例えば、後述のマクロアポランター110/2.5等)
では「使いこなし」の為のテクニカルな「エンジョイ度」
が低く、そして、誰が撮っても綺麗に撮れてしまうから
「差別化要因」が少ない。さらに言えば、銀塩時代に、
こうした「平面マクロ」を上手く使いこなせなかった
のは、自身が「レンズの言うがまま」に撮っていたから
であって、それはレンズの弱点では無く、ユーザー自身の
責任である事を近年になって思うようになったからだ。
まあつまり「平面マクロ」である事がわかっているならば、
それは使いこなし次第では、何ら問題が無い訳であるし、
さらに言うならば、全て高描写力なレンズばかりで
優等生的になってしまった(かつ高価な)現代レンズ
では有り得ないような描写が得られる可能性がある事も、
そうしたレンズの弱点を逆に利用する、という視点にも
繋がるだろう。その手の措置は、極めて高度なスキルを
要求される話なのだが、その困難にチャレンジしてみる
事は、マニアックで、テクニカルな「エンジョイ度」を
高める意味で、価値があるのではなかろうか・・?
----
では、次のレンズ
Clik here to view.

(中古購入価格 8,000円)
カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)
1977年発売のMF小口径中望遠1/2倍マクロレンズ。
さて、こちらも「平面マクロ」特性を若干持つ
レンズである、もしかすると、この時代1970年代~
1980年代の各社MFマクロレンズの大半は、その描写
傾向を持つ訳であり、それは、やはり簡素なレンズ構成
からくるのだと思われる。技術的な未成熟とも言える
要素もあり、そこが改善されて、マクロレンズが
様々な被写体条件で高描写表現力を発揮できるように
なるのは、概ね、1990年代のAF等倍マクロの時代
以降の話である。
Clik here to view.

「シャープな描写傾向」を活用できるのであれば、
この手のオールドマクロレンズも悪くない。
特に本レンズの場合は、1960年代~1970年代の
ニッコール銘マイクロ(マクロ)レンズに対し、
市場が要求したニーズである「資料複写」の目的には、
良くマッチしている特性だ。
他記事でも良く書くが、この時代は、まだコピー機が
普及していなかったので、各種重要資料の複写には
写真が使われた事も良くあった訳である。
その代償として、平面マクロはボケが固い。それは
つまり設計上では「重要視しなかった」からであり、
この時代に「ピント面はシャープでボケも綺麗」と
いった完璧な性能のレンズを作るのは困難であるし
たとえそうしたとしても、非常に高価なレンズで
あれば、それは売れなくなってしまう。
(まあ、現代の高性能レンズでも、高価すぎて
売れないもは多々あると思われるが・・)
なお、これより後年のニコン製マイクロのF2.8版
(MF/AF)では、平面マクロ特性はだいぶ薄れている
と思われるが、所有していないので詳細についての
言及は避ける。
(追記:本記事執筆後に、全てのNIKKOR 105mm
マイクロを、研究目的で購入している。
いずれ、別記事で詳細の比較を行おう)
ともかく、開放F値の違いは、性能や値段の差別化
では無く、描写傾向そのものが、全くの別物となる
ケースが大変多い事も、ユーザー層は良く知って
おく必要があるだろう。まあすなわち、
「値段が高くて、開放F値が明るいから、と言って、
必ずしも、それが良い(良く写る)レンズだとは
限らない」という大原則である。
本レンズの総括だが、不人気で相場が安価だ。
Ai NIKKORは、中古相場が高いのが特徴(弱点)で
あるが、これは「オールドファン層」が注目するのと、
一部、投機的観点も加わっているからだ。
しかし、本レンズは、F4という暗い開放F値により
「F2.8版よりも低性能だ」という、ビギナー層や
初級マニア層での誤まった認識がある為か、中古相場
が安価である事がコスパの良さに繋がっている。
「主要被写体をシャープに写す」という目的であれば、
本レンズは十分に使えるし、むしろその特徴が強い、
ユニークなレンズだ。
さらにマニアックな話をするならば、本レンズは
3群5枚の「ヘリアー型」構成である。
これは1900年に、旧フォクトレンダー社で開発された
当時としては極めて優秀な特性を持つレンズである。
だが、意外な事に、写真用(交換)レンズの構成と
して、純粋な「ヘリアー」型が採用された例は
極めて少なく、数える程しか存在しない。
(名前だけ「ヘリアー」という物は、色々ある。
いずれ、ヘリアーを集めて特集記事を組む予定だ)
この、「レジェンド」とも言える特性を味わう事、
描写力を体感する事は、マニアとして興味を持たない
筈が無いではないか・・
まあ、使いこなせるならば悪く無いレンズだ。
----
さて、3本目のシステム
Clik here to view.

(Y/Cマウント)(中古購入価格 82,000円)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited (μ4/3機)
1980年代後半頃に発売と思われるMF中望遠等倍マクロ。
定価が確か198,000円(+税)もしたので、CONTAX党の
初級中級層からは「神格化」されたレンズである。
すなわち「値段が高いものは良いモノに違い無い」
という誤解だ。勿論「必ずしもそういう訳では無い」
事は、もう本ブログでは何百回書いた事だろうか・・
もし、その誤解を持ち続けているならば、もうそれは
永久にビギナーのままであり、何の進歩も無い。
Clik here to view.

他社マクロレンズの大半が、
「MF、1/2倍、小口径(F3.5~F4)、平面マクロ特性」
であった、という状況に対し、それ以降の時代の
「(AF)、等倍、大口径(F2.8)、ボケ質も重視した特性」
という特徴において、AF化以外の点で、他社マクロに
先駆け、いち早く現代的な特性を実現した事が、特徴に
なっていたと思われる。
しかし、その特性は他社からも注目されたと思われ、
本レンズの特性を参考とした新時代のAFマクロレンズが
1990年代に出揃った、とも言えるかも知れない。
本マクロプラナーの弱点は、劣悪とも言えるMF操作性
であり、私が言う「修行レンズ」に近いものがある。
(本シリーズ第11回「使いこなしが難しいレンズ編」
では、ワースト5位を、本レンズが記録している)
発売時点ではともかく、数年後においては、例えば
TAMRON SP 90mm/F2.8(72E型、1996年)が登場
したあたりからは、やはり新型AFマクロの圧倒的な
使用利便性に市場での軍配が上がった事であろう。
で、ご存知のようにRTS(Y/C)系ツァイスレンズは、AF化に
移行できず、MFのまま銀塩時代を終えてしまっていたのだ。
(注:Nマウントに関しては、銀塩一眼第24回記事
「CONTAX N1」編等を参照。ただし、あまり喜ばしい
歴史では無く、ちょっと悲劇的な結末となっている)
Clik here to view.

本レンズの他の個人評価点は悪くなく、個人DB(データ
ベース)での総合点は、3.8点と、名玉(総合4点以上)
に、あと一歩という状態である。
----
では、4本目のシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 5,000円)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
2000年代前半に発売と思われる、AF中望遠等倍マクロ。
購入価格5000円は安価すぎるが、これはAF故障品を
購入した為であり、本レンズはAFが効かない。
同型レンズ(完動品)を異マウントで同時期に購入して
いて、そちらは25,000円の中古取得価格であった。
Clik here to view.

いない。近接撮影では、AFよりもMFを多用する場合が
通例であるからだ。
よって、さらにこの後の時代、2000年代後半より
2010年代においては、マクロレンズであっても、
内蔵手ブレ補正機構や、超音波系のモーターを搭載し
高付加価値を狙った製品が後継機種として発売され
始めた状況ではあったが、個人的には、「どうせMFで
撮るのだから、超音波モーター等は不用」と思って
いて、その手の機能の入っているマクロレンズは
殆ど購入していない。無駄と思われる機能に代金は
払いたく無いからであって、これは「コスパ至上主義」
の一環でもある。(注:超音波モーターを入れて
シームレスMF機構とすると、MF操作性が極端に悪化
する事も、重要な理由の1つである)
ちなみに、内蔵手ブレ補正だが、これも不要だ。
何故ならば、
1)近接撮影では、手ブレ補正機能では補正できない
前後方向への「距離ブレ」が多く発生する。
2)屋外撮影等では、自分がブレるよりも、風を起因と
したり、昆虫等の被写体が動くといった理由による
被写体ブレが良く発生し、当然、手ブレ補正では、
それらを抑える事は出来ない。
事が理由である。
ここも同様に、無駄な機能に1円たりとも代金を払う
つもりは毛頭無い。
両者が併売されていたら、迷わず安価な手ブレ補正無し版
を購入するだろう。そして、場合により、レンズ構成等に
よる描写力・描写傾向は、その両者で、全く同じである
ケースもあるからだ。
さて、故障問題についてだが、本レンズより前に
完動品(故障なし)を先行して購入していたのだが、
その優秀な特性(レンズ総合評価3.8点、名玉1手前、
前述のMakro-Planar 100/2.8と同得点)
に感心し、本レンズのAF故障品を異マウントで
見つけた際、「このレンズだったら2本持っていても
悪く無い」と思っての購入に繋がった。
Clik here to view.

気に入らず、手放してしまった事もあったのだが、
1990年代を通じてかなりの描写力改良が行われた
模様であり、2000年代以降のマクロに関しては、
悪く無いので、複数本を購入し、愛用している。
(参考:特殊レンズ第42回「伝説のSIGMA MACRO編」)
----
さて、5本目の100mmマクロシステム
Clik here to view.

(中古購入価格 3,000円)
カメラは、NIKON D300 (APS-C機)
正式型番不明、発売年不明、恐らくは1990年代と
思われる小型軽量AF中望遠1/2倍マクロレンズ。
冒頭で紹介したCOSINA 100/3.5(MF版)の、AF版の
OEMのような製品にも思われる。仕様や描写傾向が酷似
しているからである。
Clik here to view.

全く無いのが、手にして目に付く弱点であろうか・・
中古店での販売価格は、当初もう少し高価であった
のだが、行き付けの中古店で、予約購入前に店長が
このレンズをチェックして、「少し曇りがありますね、
どうされますか?」という話があり、私がチェック
してみると、さほどでも無かったので「値引きして
いただければ引き取りますよ」と応え、安価に入手
する事ができた。
個人的には、あまりに酷い物を除き、多少のクモリとか、
ゴミ等は気にしない、問題は、価格に見合う性能が
得られるかどうか?(コスパが良いか否か?)の、
ただそれ1点なのだ。
Clik here to view.

まあ、平面マクロの場合、本来は(デジタル)一眼
レフよりも、ミラーレス機で実絞り(絞り込み)測光
で用いた方が望ましい。何故ならば、「平面マクロ」
の弱点である、ボケ質(の固さ、破綻)の課題を回避
するとしても、逆用するとしても、絞り値に対応する
ボケ質傾向を、高精細のEVF等で確認しながら撮影する
必要があるからだ。これを行わないで、一眼レフでの
開放測光では、どんなボケ質となって写るかは、
撮影前に判断する事は困難か不可能であるからだ。
ただまあ、平面マクロではあるが結構シャープな写りを
するレンズであり、AF動作が「ガタピシ」と、スムース
では無い弱点も、MFで撮れば何も問題は無い。
安価で購入した事から結果的にコスパも良くなっている。
悪く無いレンズだ。
----
では、6本目のシステム、こちらは100mm級では無い。
Clik here to view.

(中古購入価格 28,000円)
カメラは、EOS 8000D (APS-C機)
2006年発売のフルサイズ対応中望遠AF等倍マクロレンズ。
本シリーズ第29回記事では、フルサイズ機で使用したが、
今回はAPS-C機とし、換算画角はEOS機では112mm、
一般的APS-C機ではx1.5倍で、105mm相当となる。
当該第29回記事では新鋭SIGMA 70mm/f2.8 DG | Art
とも比較していて、これは新旧の「カミソリマクロ」
対決の様相もあった。
Clik here to view.

定着している訳では無いのだが、初出の頃の評価記事で
評論家が、その名称を使った事を発端としているので
あろう。
SIGMAでは、その呼び方が気にいったのか、後継のART
型の発売時に「伝説のカミソリマクロが復活」という
キャッチコピーを新型マクロ(ART型)に付けた訳だ。
ただまあ、2000年代~2010年代のSIGMAを含めた
各社のマクロレンズの大半は、多かれ少なかれ
「カミソリ」的な描写傾向を持っている。
だが、多数の近代(2010年代以降)マクロを所有して
いる訳では無いし、むしろ近代マクロは前述のような
余計な付加価値(手ブレ補正や超音波モーター等)が
入っている事が嫌いで、あまり購入していないので、
あまり全般的かつ詳細な話は避ける事としょう。
でも、実際のところ、この新旧「カミソリマクロ」
よりも、キレッキレのマクロレンズは何本か存在
している。ただまあ、そのあたりも設計のコンセプト
次第であり、例えば、カリカリ、キレキレの描写を
得る為に、(トレードオフ関係になりやすい)ボケ質の
悪化などが顕著になってしまったら、それはもう
「カミソリか否か」というよりも、全体のバランスを
崩してしまっている設計と言わざるを得ない。
やはり、まずはボケ質や中遠距離描写等を含めた、
レンズの基本描写性能が高い事が望ましく、その上で
さらにシャープな解像感を持つならば、それは真の
「カミソリマクロ」と言えるのかも知れない。
それと、マクロであっても、望遠焦点距離になれば
なる程、あるいは撮影倍率を高める程、絞りを開ける
程、背景ボケを大きく(被写界深度を浅く)取る事が
可能となる。この内、絞りの要素は、開ける事で諸収差が
増大するケースが多く(注:そうならない類の収差も
存在する)その事と「カミソリ感」は矛盾するケースも
あるのだが、他の、望遠にする、近接する、の要素は、
それらにより被写界深度を極めて浅い状態にする事も
容易である。そこまで背景や前景を「大ボケ」にして
しまい、その設定においても、場合により「ボケ質破綻」
は回避が可能だ、つまり、ボケすぎる状態を作り出せば、
ボケ質の多少の悪化は気にならない、という訳だ。
そうすると、絞り値の利用自由度も若干高まるので、
少し絞って諸収差を低減し、解像感を稼ぎつつも、背景
等のボケ質は、固くなったり破綻せずに済む状態を
作り出せる可能性も高い。だから、中望遠や望遠マクロ
の中には、一見、極めて高性能な「カミソリマクロ」的
な描写を得やすいレンズも多い訳である。
ただし、ここも良く注意していないと、そのように
諸条件を整えて撮影が出来るケースも、そう多くは無い
という事であり、かつ、一眼レフ使用等で、ボケ質等に
厳密性や精密性の無い、ラフな使い方をしてしまうと、
そういう細かい設定条件に上手く当たる確率は極めて
低い、という点である。
だから、レンズの描写力はユーザーの使い方によって
大きく変わってしまい、たった数枚とかの、たまたま
写りが良い(悪い)写真を見て、「このレンズの写りは
良い(悪い)」といった評価を下す事は出来ない。
何千枚も、下手をすれば何万枚も、様々な条件で写して
みない限り、まともな評価は出来ず、それは場合により
何年も、あるいは10年以上もかかってしまう事もある。
だからまあ、本ブログにおいては、あまりに発売された
ばかりの、新しいレンズを取り上げる事は、非常に稀で
あり、たいていは発売後数年位は、色々と撮った上で
レンズの評価をしている。
あるいは、たまたまそうした発売直後での紹介のケース
があったとしても、長く使っていないと分からないような
性能については、その言及を避け、「追加検証が必要」
等の結論や総括にしている場合も多い。
Clik here to view.

8000D)等においては、ピント精度が怪しいケースも
出てくるので要注意だ。普及機における仕様的差別化
なのか?AFの精度は高く無いし、MFで使おうにも、
壊滅的とも言えるファインダーやスクリーンの低性能
で全くMFに向かない。
よって、マクロレンズはMFでミラーレス機で使うのが
あくまで基本ではあるのだが、AF一眼レフ用のレンズ等で、
ミラーレス機での使用が適さないマクロの場合には、
一眼レフで使う上では、出来るだけ、AF/MF性能に優れた
機種を選択するのが無難であろう。
CANON EOS(一眼レフ)機で、その条件を満たすものは
多く無いが、MF用のスーパープレシジョンマットに換装
された、やや古いEOS 5D Mark2/6Dあたりの機体が向く
かも知れない。(注:それらの後継機では、スクリーン
交換が不可な機体が殆どである)
----
では、次は今回ラストのマクロシステム。
Clik here to view.

(注:変母音記載省略)(新品購入価格 138,000円)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
2018年発売の、MF等倍マクロレンズ。
コシナ史上3本目のマクロアポランターであり、現状では
SONY E(FE)マウント対応品しか発売されていない。
Clik here to view.

見るからにコスパが悪い。
ただ、高価なのはレンズ市場が縮退している事が最大の
原因であり、誰もレンズを買わないから、値上げした
商品を売らないと、メーカーも流通も、ビジネスを維持
していけない。しかし「高いから皆、買わない」という
悪循環が発生している。
それでも新品で買ってしまっているのは、第一に、コシナ
(特にフォクトレンダー)製品は、販売(製造ロット)
数量が少なく、いつの間にか売り切れになって、後年では
入手困難となるケースがとても多いからだ。
特に、本レンズの前機種である、2001年発売の
MACRO APO-LANTHAR 125mm/f2.5 SLは極めて販売数
が少なく、後年の中古市場で「投機対象」となってしまい、
新品販売時点での最安値の4倍以上、というべらぼうな
プレミアム価格となってしまっている。
当該レンズに、そこまでの価値は無く、むしろ、使い
難いレンズの代表格だ。
(本シリーズ第12回「使いこなしが難しいレンズ」
特集でワーストワン。
また、特殊レンズ第11回「マクロアポランター・
グランドスラム」編記事等を参照)
「希少なレンズだ」という理由で、後から高値で購入
する事は望まないので、気になるならば、なんとしても
販売期間中に入手するしか無い。
また、この手のレンズのユーザーはかなりのマニアであり、
そう簡単に手放す事も稀で、中古市場ではまず見かけない。
本レンズや姉妹レンズの65mm/F2版は、ごく稀に中古市場に
出ては来たのだが、やはり玉数は少なく、かつあまり相場も
安価では無かったので、買い難い状況である点は一緒だ。
(追記:近年では、65mm/F2版の中古流通数は多いが、
110mm/F2.5版の中古流通は極めて少ない)
Clik here to view.

市場(流通やメディア)でも、あまり評価や情報が無い。
何故ならば、市場では、売りたいレンズ、売れるレンズを
ユーザーに勧めた方が、売り上げを伸ばす意味では
正当であって、何も「売り難い、売れない」レンズの
評価や宣伝に、時間や金を掛ける事は、したくない訳だ。
(→宣伝記事を書くならば、初級中級層に人気の「大三元」
レンズの話をした方が、販売側としては得策であろう)
でも、そうなると「誰かが良いと言ったから買う」という
受動的スタンスのユーザーが大半である現代の世情では、
誰も何も言っていないレンズを「怖いもの見たさ(笑)」
で入手しようとする奇特なユーザー層の比率は限りなく
低く、結局、より一層、この手のレンズは売れなくなる
という悪循環だ。
そういう市場状況は発売前から見込んであるだろうから
企画台数(生産本数)も少なく、結局、開発や製造に
係わる多額な経費を、少ない販売本数で償却せざるを
得ず、個々のレンズの価格は、どうしても割高となる。
だから、コスパが悪い事は必至であり、よってこの手の
マニアック度が高い(あまり売れない)レンズは、
本ブログの「ハイコスパ」系の記事には登場しないし、
「名レンズ編」等でも、コスパの悪さがネックとなって
総合上位にはランクインできない状況である。
しかし、本レンズの場合等では、値段以外に弱点は
殆ど無く、これが唯一無二の性能を持つものであれば
パフォーマンスが高く、結果としてのコスト高は
ある程度は相殺される。
まあでも、このあたりは、ユーザーにおけるレンズの
利用目的等にも依存するのも確かだ。
そして、今時、E(FE)マウント機でMFのみで、「瞳AF」
や「ファストハイブリッドAF」も利用できないならば、
そういう「不便なレンズ」に興味を持つ、αユーザーも
極めて少ない事であろう。
まあでも、本レンズは、壊滅的なコスパの悪さ以外は
大きな弱点を持たない。その「描写表現力」評価点は、
400本程度の所有レンズ中、十数本しか無い5点満点
であるし、総合評価点も、3.9点と、名玉の条件の
4点以上に、あと一歩である。
中古購入が出来て、コスパ点が、もう少し良かったら
評価点は、4点を越え、様々な「名玉記事」に
ノミネートやランクインをしていた事であろう。
Clik here to view.

あるという状況なので、MF操作を厭わず、かつコスト
高に目をつぶれる中級者層以上であれば、今回紹介の
100mm級マクロレンズの中では、唯一推奨できるレンズ
だと言えるかも知れない(他のマクロは、多少マニアック
すぎる点がある・汗)
参考関連記事:
特殊レンズ第11回「マクロアポランター・グランドスラム」
本シリーズ第32回補足編「新旧マクロアポランター対決」
----
さて、今回の「100mm(級)マクロ・マニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。