今回記事も補足編として、COSINA Voigtlander(コシナ・
フォクトレンダー。 注:独語綴り上の変母音は省略する)
の望遠マクロレンズ2本、具体的にはMACRO APO-LANTHAR
銘の新旧MF望遠マクロ、125mm/F2.5(旧版、2001年)と、
110mm/F2.5(新版、2018年)の対決記事とする。
なお、前記事「新旧STF対決」は、「アポダイゼーション光学
エレメント」を搭載した特殊レンズでの、全交換レンズ中に
おける「ツートップによる頂上決戦」であったのだが・・
今回は、アポダイゼーションでは無い、通常タイプの中望遠
マクロレンズでの頂上決戦という感じだ。
勿論、ここで「頂上」とは「凄いレンズ」という意味だ。
ただ、最初に述べておくが、この対決は新版(110mm/F2.5)
の勝利となる事は確定している。17年の時を隔てて新開発
された新型は、さすがに旧型の様々な弱点を良く解消して
いる次第だ。
ではまず、最初のマクロ・アポランター
![_c0032138_15520376.jpg]()
(読み:フォクトレンダー マクロ アポランター)
(新品購入価格 79,000円)(以下、MAP125/2.5)
カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)
2001年に発売された、フルサイズ対応MF等倍望遠マクロ
レンズ。
本レンズは、過去記事で何度も何度も紹介しているが、
近年の記事では、特殊レンズ・スーパーマニアックス第11回、
「マクロアポランター・グランドスラム」特集記事および、
本シリーズ第22回「高マニアック・高描写力レンズ特集」
記事に詳しい。
また、さらに参考記事として、本シリーズ第12回記事
「使いこなしが難しいレンズ特集(後編)」においては、
本MAP125/2.5が、数百本の全所有レンズ中、ワースト・ワン
の不名誉な記録を残している。
まあでも、そのランキングは「使いこなすのが難しい」順位
であって、勿論、本レンズの描写力が悪い訳では無い。
![_c0032138_15520363.jpg]()
既に、たいていの長所、短所は書き尽くしている。
それらを簡単に言えば、長所は高い描写力とマニアック度。
短所は操作性が極めて悪い事と、それに関連して使いこなし
が大変な事だ。過去の紹介記事では、たいてい「修行レンズ」
と本MAP125/2.5を称し、すなわち「使う事自体が、修行の
ように困難な事である」という意味だ。
では、本記事では、また別の視点で、例えば、本レンズを
取り巻く時代や市場の状況等について述べていくとしよう。
![_c0032138_15520343.jpg]()
交換レンズ(主にMF)のOEMメーカーであった。
OEMとは「他社から依頼を受けて、そのブランドの製品を
製造する」という意味である。
勿論、カメラやレンズの世界では常識的な生産スタイルであり、
カメラに限らず他の様々な市場分野の製品(例:イヤホン等)
でも当たり前である。
しかし、世の中の多くの商品が「OEM」である事は、世間一般
の消費者層には知られていない。何故ならば、世の中では
依然「ブランド」という概念が重要視されていて、皆が、
「誰でも知っている有名ブランドの商品」を欲しがり、だから
そうした商品は高価でも売れ、高くてもそれらを買ってしまう
消費者は、その事で所有満足感を得たり、周囲にそれを自慢し、
自身のステータスを高めたりする事が出来る。
それが世の中の仕組みであるから、実際には、それらの商品
が「必ずしも、そのメーカー等で作られていない」という、
その「大人の事情」を、世間の皆が知ってしまうと、世の中が
上手く廻らずに、まずい事になってしまう。
だから「OEM商品」である事は、メーカーや流通は、ひた隠し、
OEMメーカーは、たとえ、どんなに巨大な企業であっても、
その名を世間が知る事は殆ど無い。
例えば、軽く前述した「イヤホン」であるが、この分野には
世界的な超巨大メーカーが存在する。その生産数は、月産で
1800万本(!)以上と言われていて、世界各国の有名ブランド
イヤホンであっても、低価格帯の物は、このOEM企業で生産
されている場合も良くあると聞く。
ただし、"低価格だから品質や性能が悪い"という訳でも無い。
むしろ非常に多数のイヤホンを生産している事で安定した品質で、
コストダウンが出来る事、かつ、こなれた(バランスの良い)
設計のものが多いと思う。まあ「コスパが良い」という事だ。
事実、私がこのメーカーのイヤホンを購入して評価した後、
他の(有名)音響メーカーの低価格帯のものを買った際、その
音質傾向が、ほぼ同等であり、恐らくはOEM製品だと推測できた。
(注:私は音響分野に関しては、かつて専門職であったので、
音を聞けば、だいたいその特性等がわかる。特にイヤホンは
60本以上を所有していて、個々に音質の詳細評価をしている)
ところが、その(有名)音響メーカーの高価格帯商品を買うと
なんとOEM品よりも音質が悪い。つまり恐らくは音響メーカーの
自社で開発したものなのだろうが、設計がこなれたOEMの大量
生産品に、完全に性能で負けてしまっている状態なのだ。
でもまあ、安いイヤホンを買ったとしても高音質であるから、
そのメーカーのブランドイメージには傷が付かない。むしろ
エントリー戦略としては、ブランド信奉を高める為に有益だ。
(=「安い製品なのに、良い音がするメーカーだ」と・・)
後で、そのメーカーの高級品を買っても、音が悪い事に気づく
絶対的評価感覚を持っているユーザーはとても少ない。だから、
「高級品は、やはりちょっと違うな!」とか言って、満足して
しまうユーザーが大半という状況な訳だ。まあ「不条理」では
あるのだが、それで世の中は上手く廻っているので問題無い。
なお、他者の評価などは参考にしても無意味だ。何故ならば
その「大人の事情」があるから、イヤホンにしても、カメラや
レンズにしても、「高価なものは性能が優れた良いものだ!」
という論理を、市場や流通やユーザーの誰もが強く打ち出そう
としている、そうしないと、安い商品の方が良い事がわかって
しまったら市場倫理が崩壊してしまい、誰の得にもならない。
したがって、そんな事(OEM生産)に目くじらを立てる必要も
まるで無く、あくまでユーザー各々の「絶対的価値感覚」で
個々の商品を正当に評価しなければならない。
![_c0032138_15520493.jpg]()
悪いカメラを作ってた訳でもなく、むしろ他の著名メーカーの
カメラですらも一部がコシナで作られていた事は、マニア層等
には、とても良く知られた事実であった。
なお、コシナ以外にも著名なOEM(カメラ/レンズ)メーカーは、
いくつかあるし、時代によっても、それは異なる場合もある。
(例:デジタル時代に入ってから、国内の大半のメーカーの
コンパクト・デジタルカメラを生産する巨大OEMメーカーが現れて、
一時は世界シェアの何割をも占める膨大な生産数があった模様だ)
で、1990年代のコシナは、世に名前が知られていない。
だから自社ブランドのカメラやレンズを稀に発売しても、
一般(初級中級)消費者層は、誰も欲しいとは思わない。
消「何? コシナ? 知らないな、三流メーカーか?」
となった。
よって、コシナ自社ブランドのレンズは、なんと定価の
7割引き(定価が5万円と書かれているが、新品販売価格は
15,000円前後等)といった、無茶な値付けで販売されていた。
まあ、そこまで「超お買い得品」と思ってもらわない限り、
本当に誰も買わなかったわけだし、そうしたとしても、
一部のブランド信奉が強い消費者層では、
消「安かろう悪かろう。安物買いの銭失い!」とか言って、
それらコシナ製品を手に取る事も無かった。
そして、買った(初級)ユーザーもまた、レンズを評価する
経験も術(すべ)も持っていない。
ユ「安かったから買ったが、やはりたいした事無いなあ・・」
等と、値段から来る印象や「思い込み」で物事を語っていた。
まあ、本ブログでは、何本かのコシナ銘のレンズを過去記事で
紹介しているが、どれも「コスパが良い」という評価だ。
(後日、特殊レンズ超マニアックス記事で、コシナ銘レンズを
まとめて紹介予定だ)
で、一部の中上級マニア層では、こうしたコシナ銘レンズを
たまたま購入し「思ったより良く写る」等の好評価を下した。
極めて妥当な評価であろう。ただまあ「とても良い」という
評価が出来ない事も事実である。何故ならば、定価の7割引き
等で販売する前提であれば、設計も製造も、コストを掛ける
訳にはいかない、その実売価格で売っても儲けが出る程に、
ローコストな仕様にせざるを得なかったからだ。
・・まあ、ここまでは従前の記事でも何度か説明してきた事
だが、今回はさらに当時の状況を追加分析してみよう。
![_c0032138_15521022.jpg]()
銀塩MF機であり、「AF機があった」という記録や情報は無い。
レンズだが、これも殆どがMFレンズである。AFのレンズは稀に
存在していて、所有もしているが、「Licenced by Minolta」
等と書かれていて、AFレンズメーカーからの技術供与を受けて
いた模様だ。
それもそうであろう、当時のコシナの生産ラインは、恐らくは
MFレンズに特化したもので、そうであればレンズ部品や鏡筒を
組み立てるだけで済み、大量に高品質のレンズが作れる訳だ。
だが、そこにAFレンズが入って来ると、電子部品とかモーター
とか、そういう異質の部材が製造現場に入ってくるし、製造の
組み立て体制も製品検査体制も、それらAFレンズには対応して
いなかったかも知れない訳だ。
さて、でもまあ、1990年代と言っても、依然MFカメラやMF
レンズは流通していたし、その時代にコシナ製OEM機が新発売
された実例もある(例:OLYMPUS OM2000、1997年、
銀塩一眼レフ・クラッシックス第22回記事参照)
ずっと銀塩時代が続いていたならば、コシナのOEM事業は
縮小傾向ながらも安泰だったかも知れない。
だが、この時代(1990年代後半)、市場にはヒタヒタと
「デジタル化」の荒波の予兆が始まっていた。
既に1995年には、CASIOよりヒット作デジタルカメラの
QV-10が発売されていて、OLYMPUS,FUJIFILM,MINOLTA等
も、デジタル(コンパクト)機の販売へ追従しようとしていた。
もしデジタル時代となると、コシナのOEMビジネスは危機的
状況に陥ってしまう。もう、どのメーカーからも、銀塩MF
一眼レフや、MFレンズの製造の注文など入って来なくなる
だろうからだ。・・であれば、コシナは自社の力でなんとか
カメラやレンズを開発・生産して、それを沢山売って儲け、
なんとかそれでビジネスを継続しなくてはならない。
その為に必要なものは何か・・? まあ生産設備も既にあるし、
設計もお手の物だ。そして技術力も品質も高い、なにせ他の
有名メーカーに製品を納めても、何も文句を言われる事が
無かった訳だ。(先のイヤホンの例では、むしろ音響メーカー
自社で開発した高級イヤホンが、大量生産のOEMイヤホンに
対して性能(音質)的に劣ってしまっていた位だ)
・・そう、新たに必要なものは、「ブランド力」つまり、
「知名度」だけであった訳だ。
だから、コシナは1990年代に「ブランド」を強く欲した。
世界(特に、旧来から光学機器の”メッカ”であるドイツ等)
を見渡してみると、世界最古の光学機器メーカーである
「フォクトレンダー」(1756年創業、モーツァルトの生誕年)
の名前が宙に浮いて余っていた。
・・まあ、とは言え、日本製カメラの世界的な台頭により、
1970年代には既に、CONTAXも、ローライも、ライカも
そうした独国ビッグネームが、カメラ市場から撤退または
日本メーカーと協業しながら、かろうじて事業継続して
いた状態だ。フォクトレンダーも同様に、もうカメラを
作っていなかった訳だし、他のビッグブランドでも、その
「名前」自体を他企業に売って(=ライセンス供与して)
生きながらえていたに過ぎない。
で、その事実自体も、国内では中上級マニア以外には殆ど
知られておらず、1990年代の中古カメラブームの際にも
初級層や金満家では「ドイツ製のカメラやレンズは凄い!」
等の、(”いったい何十年前の話だ?”、”それ、いったい
何処で作った製品なの?”といったように・・)
あまり正確では無い認識しか広まってなかった訳だ。
さて、で、コシナ社は無事「フォクトレンダー」のブランド
を手に入れる事に成功した。1999年(以前?)の事である。
コシナは、そこから畳み掛けるように、カメラでは、BESSA
(ベッサ)シリーズのレンジファインダー機や、一眼レフを。
交換レンズでは、レンジファインダー機用マウント及び、
(MF)一眼レフ用マウントのレンズ群を、その後の数年間で、
数え切れない程の多数、怒涛のように新発売したのだ。
恐らくは、とっくにそれらの設計は完了していたのであろう、
さもなければ、数年間で数え切れない程の新製品は作れない、
「後は名前だけ」の状態であった、との推察は容易だ。
新規の高級ブランド「フォクトレンダー」は、一般層にも
そこそこのインパクトを与えた。だが、当然ながらブランド
の使用料が新製品に上乗せされた為、定価もそれまでの
コシナ製品の倍以上も高価になり、かつ7割引き等の無茶な
値引きも出来る筈が無い。実質的には、それまで1万円台
で新品購入できていたのが、5万円~10万円も出さないと
フォクトレンダー銘のレンズ(カメラも)は、買えなく
なってしまった。
だから、上級マニア層等で、旧来のコシナ時代における
その「コスパの良さ」に注目していたユーザー層の一部は
「名前が変わっただけなのに、そんな高いレンズは買えない」
と、敬遠するケースも多かったかも知れない。
まあでも、2000年代初頭の最初期のフォクトレンダー製の
一眼レフ用レンズは、「カラーヘリアー75mm/f2.5SL」
「アポランター90mm/f3.5SL」「ウルトロン40mm/f2SL」
「アポランター180mm/f4SL」等では、定価も5万円前後と
さほど、”高価すぎる”という状況では無かったし、
かつ描写性能においても、極めて高いものが殆どであり、
値段が高くなっても、その分、パフォーマンス(性能)が
向上していた為、「コスパが悪くなった」とは思わなかった。
(上記の4本は、いずれ他記事でまとめて紹介する予定)
そして、2000年代前半の一般層は、新規デジタルカメラ、
銀塩高級コンパクト、中古銀塩カメラ等のカメラ本体のみに
注目し、レンズはあまりマニアックで魅力的なものは新発売
されていない。あえて挙げれば、PENTAX-FA Limitedや、
NIKON Ai45/2.8P、SIGMA広角F1.8三兄弟・・ 程度であり、
まあフォクトレンダーを含めて、それらのマニア向けレンズ
を全て買ってしまう事は、無理な話では無かった訳だ。
![_c0032138_15521035.jpg]()
何故急にフォクトレンダー時代での描写力が高くなったのか?
と言えば、ここの理由は極めて簡単で明白だ。
つまり、コシナ時代は、その販売価格から、製造コストが
制限されていた訳であり、安いものを作らざるを得なかった
状況だ。まあ、コシナは各社のカメラやレンズを、ずっと
OEM生産していた訳だから、そのメーカーから「XX円位で
作ってくれ」と言われたら、そのコストに応じた性能や
仕様を設定する事くらいは、容易に対応出来ていた訳だ。
フォクトレンダーのブランドを取得して、安売りする必要が
無くなったのであれば、コシナはその柔軟かつ高い設計力を
遺憾なく発揮し、高性能レンズを堂々と高価に作る事が出来る
ようになった訳だ。
ちなみに、その技術力の高さは、かのカール・ツァイス社にも
高く評価され、後年2006年からはコシナはカール・ツァイス
ブランドのレンズも生産。現在においては、ツァイス社自身の
Web等に掲載(販売)されている同社の高級レンズ群の殆どは
コシナ製である。つまり、コシナはついに世界のカール・
ツァイスのOEMメーカーとなった訳なのだが・・ まあ、とは
言うものの、ツァイスも、もう50年も昔の1970年頃からは
自社で写真用レンズを製造していないと思われる。
(注:旧来のツァイス系工場の救済の為か?または、全てが
日本製であるとブランドイメージが低下する為か?、一部の
京セラ・CONTAXブランドレンズを1980年代頃までドイツで
製造していた事はある。ただ、両者の使用部品は同じであろう)
現代において、60万円以上もする高額高性能レンズを作って
売れる状況は、「ツァイス」のブランド力とコシナの技術力の
組み合わせでしか有り得ないという訳だ。
![_c0032138_15521098.jpg]()
発売されており、当時のSLレンズ(一眼レフ用)としては
高額レンズである。つまり、他のカラーヘリアー75/2.5等が
記憶に頼れば、5万円程度の定価であったのに、本レンズは
およそ2倍の95,000円程度だったと覚えている。
この値段だと、マニア層であっても、ちょっと買う人も、
少ないのではなかろうか?
しかし、他の初期フォクトレンダーSLレンズが、どれも
MFマウント(Ai,FD,PK,OM,M42等)で発売されていたのが、
本MAP125/2.5では、α、EF(EOS)のAF一眼レフ用マウント
でも発売されていた。これはまあ、高級(高額)レンズ
であるから、当時、チラホラと販売が始まっていた
「デジタル一眼レフ」での使用も意識し、ターゲットと
する消費者範囲を広めたとも思われる(まあ、お金のある
消費者層に狙いを定めた、という事であろう)
基本的には、MFである事も含めてマニア層向けのレンズだが、
でも結局、このMAP125/2.5は、販売数が少ないレア物レンズと
なってしまった。まあ「高すぎる」という市場認識であろう。
しかし、後年2000年代後半では、神戸の中古カメラ専門店で、
本レンズの海外逆輸入新品を定価のおよそ半額の48,000円
程度で販売していた位なので、買おうとさえ思えば、さほど
負担なく買える価格帯ではあったと思う。
つまりまあ、販売数が少ないので、誰からも評判を聞く事が
出来ず、雑誌等で特集される事も少なかったので、まあ一般
消費者層や初級マニア層等では、「誰かが、”良い”と言った
から買う」という受動的な購買行動に頼る為、そうした情報が
一切なければ、買うような事も無かったのだろう。
![_c0032138_15521054.jpg]()
という事で、残念ながら「投機対象」となってしまった。
つまり、「高くても買いたい」あるいは「もっと高く売れる
かも知れない」という消費者層が居る為に、本レンズを
高額取引の対象として、15万円とか20万円とかの相場で
売買する、という意味である。
まあ、本記事では、一切、本MAP125/2.5の性能評価等は
行わない事とする。たいてい過去記事に長所も短所も書いて
あるし、冒頭に書いた通り「使いこなしワースト・ワンの
修行レンズ」である故、実用価値はあまり高く無いレンズだ。
単に希少だから、という理由で投機対象となってしまう事には
全く賛同できない。レンズはあくまで写真を撮る為の実用品だ。
モノの本質を見極める「絶対的価値感覚」を、多くの
消費者層に身につけてもらいたい、と切望する次第である。
----
さて、では新型マクロアポランターの話に進もう。
![_c0032138_15521688.jpg]()
(新品購入価格 138,000円)(以下、MAP110/2.5)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
旧型から17年の歳月を隔て、2018年末に発売された新型
マクロアポランターである。当然、MFでフルサイズ対応だ。
当初2018年夏に発売予定であったのだが、遅れに遅れた発売と
なった。このレンズは発売後すぐに新品購入する予定(後述の
理由あり)だったので、やきもきする状況であった。
なお、前年2017年にコシナ史上2本目のマクロアポランター
65mm/F2が発売されているが(本シリーズ第10回記事等参照)
その中望遠マクロの紹介は本記事では割愛する。
本記事では、あくまで「望遠のマクロアポランター」に
特化しよう。
![_c0032138_15521614.jpg]()
レンズだから、AFが搭載されていない事はむしろメリットだ。
現代的な仕様のAFレンズは、近接域では非常に使い難い。
(例:超音波モーター搭載のマクロは実用的とは言い難い)
それと、コシナ社にも、それほどAFレンズ開発のノウハウが
蓄積されている訳でも無い。であれば、無理にAF化する
必然性は無く、MFである事がむしろ潔い。
操作性等、旧型MAP125/2.5からの弱点は良く解消されている。
描写力も高く、勿論年月を隔て、諸収差は大変良く補正されて
いて解像力等もかなり高目だ。又、コントラスト特性も極めて
良好で、ここは特筆すべてきであろう。
ただ、このあたりの高性能の理由は、本レンズは完全な
コンピューター光学設計になっているような気がする。
その確証は無いが・・ 個人的な感覚での話をするならば、
コンピューター設計は、「メリット(評価)関数」を高める
ように計算機が、どんどんと複雑なレンズ構成を提示してしまう。
結果、性能が良いレンズは出来るのだが、”大きく重く高価”な
「三重苦」レンズとなってしまう次第だ。
![_c0032138_15521604.jpg]()
構成であり、異常低(部分)分散ガラスを、何と8枚も使用
している。手計算の設計では、ここまで複雑なレンズは
設計の手間が掛りすぎてしまうから無理であろう。
ただ、非球面レンズは使用していないので、僅かなりとも
設計者の主張(コンセプト)はコンピューター設計上でも
加わっていると思える。・・なんと言うか、もし完全に計算
機まかせの設計となると、単に諸収差を補正する事のみが
主体となってしまい、無機質な(=特徴や主張の無い)
雰囲気の強いレンズが出来上がってしまう事があるのだ。
(他社で、そういう無機質な新鋭高性能レンズは良くある)
コンピューターもまた、あくまで「道具」であるから、
使用者(設計者)の意思が介在され、その用法の差があって
結果としての製品に個性が出て来る事が好ましい。
つまり「設計もアートである」からだ。それが無く、単に
計算機や設計ソフトに振り回されている状況だと良く無い。
まあ、この事は、カメラを使う人でも同様であり、最新の
高価な超絶性能機を購入して、フルオートのままで使い
「ただシャッターを押すだけ、カメラに使われているだけ」
の状態になってしまったら、全く好ましく無い訳だ。
![_c0032138_15521693.jpg]()
しまった。サイズ感だが、フィルター径は新旧とも同じ
φ58mm、重量は旧型690g。新型は771gと、やや重い。
しかし、新型はフランジバック長の極めて短いSONY E
マウント(フルサイズ対応FEマウント)専用であるから、
将来の一眼レフ版への転用も意識して、バックフォーカス
を稼ぐ長目の鏡筒となっている可能性も高く、それによる
若干の重量増があるかも知れない。
(例:SIGMA ART Lineレンズ等では、一眼レフ用と比べて
SONY Eマウント版等は、後部にマウントアダプターを装着
したような形状となり、重量も増えている)
また、この仕様からか?本MAP110/25は、鏡筒中央部が
太く、前後がすぼまっているファット(太った)な
デザインとなっている。これは少々好みでは無いのだが
結果として、ピントリングは幅広の大型で廻しやすくなり、
回転角も適正となった為(=最大持ち替え回数8~9回)
旧型MAP125/2.5よりも操作性は雲泥の差で向上した。
![_c0032138_15522288.jpg]()
フルサイズ機で使うよりも、周辺がカットされるAPS-C機
で使う方が、さらに画質的に有利であるし、仮にピクセル
ピッチが狭いAPS-C型の高画素機が出てきても、レンズの
解像性能とのバランスは乱れる事は無いであろう。
望遠マクロを、より望遠として特徴を強調する点においても
APS-C機での使用は望ましく、今回は、その検証の意味でも
APS-C機のSONY α6000を母艦として使用している。
勿論、描写力的な課題は何もなく、重量バランスは、やや
トップヘビーとはなるが、丁度重心位置に太いピントリング
が来るので、MFシステムとして使い易い。
ピントの歩留まりの問題も、SONY機の優秀なピーキング機能
でアシスト可能ではあるが、最短撮影距離付近では、極薄の
被写界深度となり、ピーキングすらも出ない場合があるし、
勿論撮影技法的にも、非常に困難な状況となる。
逆説的だが、等倍マクロ仕様ながら、あまり極端な近接撮影
は避けておくのも賢明かも知れない。(そういう意味では、
フルサイズ機での使用もありだろう)
あと、遠距離撮影では、僅かながら解像感が低下する
印象を持つが、重欠点では無い。
![_c0032138_15522210.jpg]()
「三重苦」ではあるが、幸いにして操作性やハンドリングは
「修行」という程の覚悟はまるでいらない程度で済んでいる。
コストの高さは、レンズ市場縮退による高付加価値型商品で
あるので、若干やむを得ない。まあ、旧型の約2倍の新品
購入価格は、新型のパフォーマンスの高さを鑑みて、容認
せざるを得ないが、それでもコスパ評価は相当に低くなる。
![_c0032138_15522208.jpg]()
も少なく、知らない間に売り切れて販売終了となってしまう
事も大変多い。 だから、初級マニア層や好事家等が、手に
入らなくなった頃に大騒ぎをして、それを受けて投機層等が、
相場高騰を狙った買占めに走ってしまう訳だ。
なお、もし不自然なまでの好評価等がある場合は、それは
相場高騰を狙った情報操作であるケースも残念ながらあり得る
話なので、消費者層は正しい価値感覚と判断力を身につける
必要がある。ここは、とても重要な事だ。
本ブログの毎回のレンズ紹介記事で、必ず購入価格を記載
しているのは、高く買ったり安く買ったりした事を自慢する
意味ではなく、「適正な相場感覚」を読者層に意識して
もらいたいからである。基本的には新品・中古相場は時間
とともに下がっていくものであるから、後年にこれらの
レンズを購入する場合、本ブログに書いてある価格以上で
購入してしまう事は、基本的には好ましく無い状態なのだ。
で、こうしたフォクトレンダー製レンズを必要だと思った
ならば、なんとしても販売期間中に入手しなければならない。
だから私も、本レンズも発売後速やかに新品購入している訳だ。
しかし、その結果として満足する場合も、不満足の場合も
あるだろうが、それもまた経験であるし、容認リスクである
とも言える。
すなわち、旧型のMAP110/2.5を買って失敗したとも思っても
新型でそれを帳消しに出来れば良い訳だ。
20年間以上使えて合計20万円、月に千円以下の「使用料」
だと思えば、両マクロアポランターを保有するのも悪く無い。
![_c0032138_15522372.jpg]()
私個人の評価データベースから引用して公開しておく。
例によって、この点数だけが一人歩きする事は好ましく無い。
評価点は評価者によりけりで依存するし、あくまで評価とは
ユーザー毎に自分自身で行う事が大原則だ。
もしそれが出来ず、「他人の評価を参考にするしか無い」と
言うならば、そこからいくら時間をかけても、お金を使っても
それが自力で出来るように、と目標設定をして、それに向けて
精進して頑張っていくしか無いでは無いか・・
それをやらずしては「何の為の趣味なんだ?」となってしまう。
趣味を続ける上で「向上心」や「探究心」は必須の要素だ。
では評価点だ。
旧製品:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 125mm/f2.5 SL
【描写表現力】★★★★☆
【マニアック】★★★★★
【コスパ 】★★☆(新品79,000円)
【エンジョイ】★☆
【必要度 】★★★★
・評価平均値:3.5
(★=1点、☆=0.5点)
新製品:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5
【描写表現力】★★★★★
【マニアック】★★★★★
【コスパ 】★☆ (新品138,000円)
【エンジョイ】★★★☆
【必要度 】★★★★☆
・評価平均値:3.9
(★=1点、☆=0.5点)
一目瞭然の評価結果だ。両者、高性能でマニアック度も高く、
その点は全所有レンズの中でも十数本しか無いトップクラスの
高評価で、その点に不満は無く、所有するに値するレンズだ。
弱点だが、旧型の場合は、操作性の悪さ等を主因とする
「修行レンズ」とも言えるまでの「エンジョイ度」の低さだ。
新型の場合は、「何故こんなに高価になった?」と思える程の
コスパの悪さである。
まあ、それらの欠点に目をつぶるとしても、旧型ではあまり
楽しめない事は確かであり、新型の勝利は明白だ。
そして、両者とも評価平均値が4点に満たないので、
いわゆる「名玉」にはノミネートし難い状態である。
本ブログで「名玉」と呼ばれる条件は、上記の評価項目を
全て高得点で乗り切り、全くと言っていい程、弱点が無い
状況にならないと無理である。それは容易な事ではなく、
評価平均点が4点を超えるレンズは、さほど多くない。
また、初級中級者や初級マニア層等が指向する「有名で
人気がある高額なレンズ」等は、上記の評価手法では
全く点数が伸びず、「名玉」にノミネートできる可能性が
皆無である事も理解できるであろう。まあだから、私は
そうした「コスパが悪い」と容易に予想できるレンズは、
事前の「書類審査」の段階で「落選」となってしまって
一切購入していない訳だ。
まあでも、そこもユーザーの好き好きであろう、つまり
この評価手法に疑問があるならば、自身の機材購入コンセプト
に合わせて、新たにユーザー個々に評価項目を設定すれば良い。
例えば、「所有満足感」とか「業務用途適正」など、色々と
考えられると思う(ただ、この評価項目でも、それらは若干
ながら意識してはいる。そして、マクロアポランターでの
「業務用途」は、まず有り得ない)
ここもまあ「評価は個人毎にそれぞれ」「評価は自分で行う」
という真理に直結する事だと思う。
----
さて、今回の記事は、このあたり迄とする。
次回記事は、また通常の新規レンズ紹介を予定している。
フォクトレンダー。 注:独語綴り上の変母音は省略する)
の望遠マクロレンズ2本、具体的にはMACRO APO-LANTHAR
銘の新旧MF望遠マクロ、125mm/F2.5(旧版、2001年)と、
110mm/F2.5(新版、2018年)の対決記事とする。
なお、前記事「新旧STF対決」は、「アポダイゼーション光学
エレメント」を搭載した特殊レンズでの、全交換レンズ中に
おける「ツートップによる頂上決戦」であったのだが・・
今回は、アポダイゼーションでは無い、通常タイプの中望遠
マクロレンズでの頂上決戦という感じだ。
勿論、ここで「頂上」とは「凄いレンズ」という意味だ。
ただ、最初に述べておくが、この対決は新版(110mm/F2.5)
の勝利となる事は確定している。17年の時を隔てて新開発
された新型は、さすがに旧型の様々な弱点を良く解消して
いる次第だ。
ではまず、最初のマクロ・アポランター

(読み:フォクトレンダー マクロ アポランター)
(新品購入価格 79,000円)(以下、MAP125/2.5)
カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)
2001年に発売された、フルサイズ対応MF等倍望遠マクロ
レンズ。
本レンズは、過去記事で何度も何度も紹介しているが、
近年の記事では、特殊レンズ・スーパーマニアックス第11回、
「マクロアポランター・グランドスラム」特集記事および、
本シリーズ第22回「高マニアック・高描写力レンズ特集」
記事に詳しい。
また、さらに参考記事として、本シリーズ第12回記事
「使いこなしが難しいレンズ特集(後編)」においては、
本MAP125/2.5が、数百本の全所有レンズ中、ワースト・ワン
の不名誉な記録を残している。
まあでも、そのランキングは「使いこなすのが難しい」順位
であって、勿論、本レンズの描写力が悪い訳では無い。

既に、たいていの長所、短所は書き尽くしている。
それらを簡単に言えば、長所は高い描写力とマニアック度。
短所は操作性が極めて悪い事と、それに関連して使いこなし
が大変な事だ。過去の紹介記事では、たいてい「修行レンズ」
と本MAP125/2.5を称し、すなわち「使う事自体が、修行の
ように困難な事である」という意味だ。
では、本記事では、また別の視点で、例えば、本レンズを
取り巻く時代や市場の状況等について述べていくとしよう。

交換レンズ(主にMF)のOEMメーカーであった。
OEMとは「他社から依頼を受けて、そのブランドの製品を
製造する」という意味である。
勿論、カメラやレンズの世界では常識的な生産スタイルであり、
カメラに限らず他の様々な市場分野の製品(例:イヤホン等)
でも当たり前である。
しかし、世の中の多くの商品が「OEM」である事は、世間一般
の消費者層には知られていない。何故ならば、世の中では
依然「ブランド」という概念が重要視されていて、皆が、
「誰でも知っている有名ブランドの商品」を欲しがり、だから
そうした商品は高価でも売れ、高くてもそれらを買ってしまう
消費者は、その事で所有満足感を得たり、周囲にそれを自慢し、
自身のステータスを高めたりする事が出来る。
それが世の中の仕組みであるから、実際には、それらの商品
が「必ずしも、そのメーカー等で作られていない」という、
その「大人の事情」を、世間の皆が知ってしまうと、世の中が
上手く廻らずに、まずい事になってしまう。
だから「OEM商品」である事は、メーカーや流通は、ひた隠し、
OEMメーカーは、たとえ、どんなに巨大な企業であっても、
その名を世間が知る事は殆ど無い。
例えば、軽く前述した「イヤホン」であるが、この分野には
世界的な超巨大メーカーが存在する。その生産数は、月産で
1800万本(!)以上と言われていて、世界各国の有名ブランド
イヤホンであっても、低価格帯の物は、このOEM企業で生産
されている場合も良くあると聞く。
ただし、"低価格だから品質や性能が悪い"という訳でも無い。
むしろ非常に多数のイヤホンを生産している事で安定した品質で、
コストダウンが出来る事、かつ、こなれた(バランスの良い)
設計のものが多いと思う。まあ「コスパが良い」という事だ。
事実、私がこのメーカーのイヤホンを購入して評価した後、
他の(有名)音響メーカーの低価格帯のものを買った際、その
音質傾向が、ほぼ同等であり、恐らくはOEM製品だと推測できた。
(注:私は音響分野に関しては、かつて専門職であったので、
音を聞けば、だいたいその特性等がわかる。特にイヤホンは
60本以上を所有していて、個々に音質の詳細評価をしている)
ところが、その(有名)音響メーカーの高価格帯商品を買うと
なんとOEM品よりも音質が悪い。つまり恐らくは音響メーカーの
自社で開発したものなのだろうが、設計がこなれたOEMの大量
生産品に、完全に性能で負けてしまっている状態なのだ。
でもまあ、安いイヤホンを買ったとしても高音質であるから、
そのメーカーのブランドイメージには傷が付かない。むしろ
エントリー戦略としては、ブランド信奉を高める為に有益だ。
(=「安い製品なのに、良い音がするメーカーだ」と・・)
後で、そのメーカーの高級品を買っても、音が悪い事に気づく
絶対的評価感覚を持っているユーザーはとても少ない。だから、
「高級品は、やはりちょっと違うな!」とか言って、満足して
しまうユーザーが大半という状況な訳だ。まあ「不条理」では
あるのだが、それで世の中は上手く廻っているので問題無い。
なお、他者の評価などは参考にしても無意味だ。何故ならば
その「大人の事情」があるから、イヤホンにしても、カメラや
レンズにしても、「高価なものは性能が優れた良いものだ!」
という論理を、市場や流通やユーザーの誰もが強く打ち出そう
としている、そうしないと、安い商品の方が良い事がわかって
しまったら市場倫理が崩壊してしまい、誰の得にもならない。
したがって、そんな事(OEM生産)に目くじらを立てる必要も
まるで無く、あくまでユーザー各々の「絶対的価値感覚」で
個々の商品を正当に評価しなければならない。

悪いカメラを作ってた訳でもなく、むしろ他の著名メーカーの
カメラですらも一部がコシナで作られていた事は、マニア層等
には、とても良く知られた事実であった。
なお、コシナ以外にも著名なOEM(カメラ/レンズ)メーカーは、
いくつかあるし、時代によっても、それは異なる場合もある。
(例:デジタル時代に入ってから、国内の大半のメーカーの
コンパクト・デジタルカメラを生産する巨大OEMメーカーが現れて、
一時は世界シェアの何割をも占める膨大な生産数があった模様だ)
で、1990年代のコシナは、世に名前が知られていない。
だから自社ブランドのカメラやレンズを稀に発売しても、
一般(初級中級)消費者層は、誰も欲しいとは思わない。
消「何? コシナ? 知らないな、三流メーカーか?」
となった。
よって、コシナ自社ブランドのレンズは、なんと定価の
7割引き(定価が5万円と書かれているが、新品販売価格は
15,000円前後等)といった、無茶な値付けで販売されていた。
まあ、そこまで「超お買い得品」と思ってもらわない限り、
本当に誰も買わなかったわけだし、そうしたとしても、
一部のブランド信奉が強い消費者層では、
消「安かろう悪かろう。安物買いの銭失い!」とか言って、
それらコシナ製品を手に取る事も無かった。
そして、買った(初級)ユーザーもまた、レンズを評価する
経験も術(すべ)も持っていない。
ユ「安かったから買ったが、やはりたいした事無いなあ・・」
等と、値段から来る印象や「思い込み」で物事を語っていた。
まあ、本ブログでは、何本かのコシナ銘のレンズを過去記事で
紹介しているが、どれも「コスパが良い」という評価だ。
(後日、特殊レンズ超マニアックス記事で、コシナ銘レンズを
まとめて紹介予定だ)
で、一部の中上級マニア層では、こうしたコシナ銘レンズを
たまたま購入し「思ったより良く写る」等の好評価を下した。
極めて妥当な評価であろう。ただまあ「とても良い」という
評価が出来ない事も事実である。何故ならば、定価の7割引き
等で販売する前提であれば、設計も製造も、コストを掛ける
訳にはいかない、その実売価格で売っても儲けが出る程に、
ローコストな仕様にせざるを得なかったからだ。
・・まあ、ここまでは従前の記事でも何度か説明してきた事
だが、今回はさらに当時の状況を追加分析してみよう。

銀塩MF機であり、「AF機があった」という記録や情報は無い。
レンズだが、これも殆どがMFレンズである。AFのレンズは稀に
存在していて、所有もしているが、「Licenced by Minolta」
等と書かれていて、AFレンズメーカーからの技術供与を受けて
いた模様だ。
それもそうであろう、当時のコシナの生産ラインは、恐らくは
MFレンズに特化したもので、そうであればレンズ部品や鏡筒を
組み立てるだけで済み、大量に高品質のレンズが作れる訳だ。
だが、そこにAFレンズが入って来ると、電子部品とかモーター
とか、そういう異質の部材が製造現場に入ってくるし、製造の
組み立て体制も製品検査体制も、それらAFレンズには対応して
いなかったかも知れない訳だ。
さて、でもまあ、1990年代と言っても、依然MFカメラやMF
レンズは流通していたし、その時代にコシナ製OEM機が新発売
された実例もある(例:OLYMPUS OM2000、1997年、
銀塩一眼レフ・クラッシックス第22回記事参照)
ずっと銀塩時代が続いていたならば、コシナのOEM事業は
縮小傾向ながらも安泰だったかも知れない。
だが、この時代(1990年代後半)、市場にはヒタヒタと
「デジタル化」の荒波の予兆が始まっていた。
既に1995年には、CASIOよりヒット作デジタルカメラの
QV-10が発売されていて、OLYMPUS,FUJIFILM,MINOLTA等
も、デジタル(コンパクト)機の販売へ追従しようとしていた。
もしデジタル時代となると、コシナのOEMビジネスは危機的
状況に陥ってしまう。もう、どのメーカーからも、銀塩MF
一眼レフや、MFレンズの製造の注文など入って来なくなる
だろうからだ。・・であれば、コシナは自社の力でなんとか
カメラやレンズを開発・生産して、それを沢山売って儲け、
なんとかそれでビジネスを継続しなくてはならない。
その為に必要なものは何か・・? まあ生産設備も既にあるし、
設計もお手の物だ。そして技術力も品質も高い、なにせ他の
有名メーカーに製品を納めても、何も文句を言われる事が
無かった訳だ。(先のイヤホンの例では、むしろ音響メーカー
自社で開発した高級イヤホンが、大量生産のOEMイヤホンに
対して性能(音質)的に劣ってしまっていた位だ)
・・そう、新たに必要なものは、「ブランド力」つまり、
「知名度」だけであった訳だ。
だから、コシナは1990年代に「ブランド」を強く欲した。
世界(特に、旧来から光学機器の”メッカ”であるドイツ等)
を見渡してみると、世界最古の光学機器メーカーである
「フォクトレンダー」(1756年創業、モーツァルトの生誕年)
の名前が宙に浮いて余っていた。
・・まあ、とは言え、日本製カメラの世界的な台頭により、
1970年代には既に、CONTAXも、ローライも、ライカも
そうした独国ビッグネームが、カメラ市場から撤退または
日本メーカーと協業しながら、かろうじて事業継続して
いた状態だ。フォクトレンダーも同様に、もうカメラを
作っていなかった訳だし、他のビッグブランドでも、その
「名前」自体を他企業に売って(=ライセンス供与して)
生きながらえていたに過ぎない。
で、その事実自体も、国内では中上級マニア以外には殆ど
知られておらず、1990年代の中古カメラブームの際にも
初級層や金満家では「ドイツ製のカメラやレンズは凄い!」
等の、(”いったい何十年前の話だ?”、”それ、いったい
何処で作った製品なの?”といったように・・)
あまり正確では無い認識しか広まってなかった訳だ。
さて、で、コシナ社は無事「フォクトレンダー」のブランド
を手に入れる事に成功した。1999年(以前?)の事である。
コシナは、そこから畳み掛けるように、カメラでは、BESSA
(ベッサ)シリーズのレンジファインダー機や、一眼レフを。
交換レンズでは、レンジファインダー機用マウント及び、
(MF)一眼レフ用マウントのレンズ群を、その後の数年間で、
数え切れない程の多数、怒涛のように新発売したのだ。
恐らくは、とっくにそれらの設計は完了していたのであろう、
さもなければ、数年間で数え切れない程の新製品は作れない、
「後は名前だけ」の状態であった、との推察は容易だ。
新規の高級ブランド「フォクトレンダー」は、一般層にも
そこそこのインパクトを与えた。だが、当然ながらブランド
の使用料が新製品に上乗せされた為、定価もそれまでの
コシナ製品の倍以上も高価になり、かつ7割引き等の無茶な
値引きも出来る筈が無い。実質的には、それまで1万円台
で新品購入できていたのが、5万円~10万円も出さないと
フォクトレンダー銘のレンズ(カメラも)は、買えなく
なってしまった。
だから、上級マニア層等で、旧来のコシナ時代における
その「コスパの良さ」に注目していたユーザー層の一部は
「名前が変わっただけなのに、そんな高いレンズは買えない」
と、敬遠するケースも多かったかも知れない。
まあでも、2000年代初頭の最初期のフォクトレンダー製の
一眼レフ用レンズは、「カラーヘリアー75mm/f2.5SL」
「アポランター90mm/f3.5SL」「ウルトロン40mm/f2SL」
「アポランター180mm/f4SL」等では、定価も5万円前後と
さほど、”高価すぎる”という状況では無かったし、
かつ描写性能においても、極めて高いものが殆どであり、
値段が高くなっても、その分、パフォーマンス(性能)が
向上していた為、「コスパが悪くなった」とは思わなかった。
(上記の4本は、いずれ他記事でまとめて紹介する予定)
そして、2000年代前半の一般層は、新規デジタルカメラ、
銀塩高級コンパクト、中古銀塩カメラ等のカメラ本体のみに
注目し、レンズはあまりマニアックで魅力的なものは新発売
されていない。あえて挙げれば、PENTAX-FA Limitedや、
NIKON Ai45/2.8P、SIGMA広角F1.8三兄弟・・ 程度であり、
まあフォクトレンダーを含めて、それらのマニア向けレンズ
を全て買ってしまう事は、無理な話では無かった訳だ。

何故急にフォクトレンダー時代での描写力が高くなったのか?
と言えば、ここの理由は極めて簡単で明白だ。
つまり、コシナ時代は、その販売価格から、製造コストが
制限されていた訳であり、安いものを作らざるを得なかった
状況だ。まあ、コシナは各社のカメラやレンズを、ずっと
OEM生産していた訳だから、そのメーカーから「XX円位で
作ってくれ」と言われたら、そのコストに応じた性能や
仕様を設定する事くらいは、容易に対応出来ていた訳だ。
フォクトレンダーのブランドを取得して、安売りする必要が
無くなったのであれば、コシナはその柔軟かつ高い設計力を
遺憾なく発揮し、高性能レンズを堂々と高価に作る事が出来る
ようになった訳だ。
ちなみに、その技術力の高さは、かのカール・ツァイス社にも
高く評価され、後年2006年からはコシナはカール・ツァイス
ブランドのレンズも生産。現在においては、ツァイス社自身の
Web等に掲載(販売)されている同社の高級レンズ群の殆どは
コシナ製である。つまり、コシナはついに世界のカール・
ツァイスのOEMメーカーとなった訳なのだが・・ まあ、とは
言うものの、ツァイスも、もう50年も昔の1970年頃からは
自社で写真用レンズを製造していないと思われる。
(注:旧来のツァイス系工場の救済の為か?または、全てが
日本製であるとブランドイメージが低下する為か?、一部の
京セラ・CONTAXブランドレンズを1980年代頃までドイツで
製造していた事はある。ただ、両者の使用部品は同じであろう)
現代において、60万円以上もする高額高性能レンズを作って
売れる状況は、「ツァイス」のブランド力とコシナの技術力の
組み合わせでしか有り得ないという訳だ。

発売されており、当時のSLレンズ(一眼レフ用)としては
高額レンズである。つまり、他のカラーヘリアー75/2.5等が
記憶に頼れば、5万円程度の定価であったのに、本レンズは
およそ2倍の95,000円程度だったと覚えている。
この値段だと、マニア層であっても、ちょっと買う人も、
少ないのではなかろうか?
しかし、他の初期フォクトレンダーSLレンズが、どれも
MFマウント(Ai,FD,PK,OM,M42等)で発売されていたのが、
本MAP125/2.5では、α、EF(EOS)のAF一眼レフ用マウント
でも発売されていた。これはまあ、高級(高額)レンズ
であるから、当時、チラホラと販売が始まっていた
「デジタル一眼レフ」での使用も意識し、ターゲットと
する消費者範囲を広めたとも思われる(まあ、お金のある
消費者層に狙いを定めた、という事であろう)
基本的には、MFである事も含めてマニア層向けのレンズだが、
でも結局、このMAP125/2.5は、販売数が少ないレア物レンズと
なってしまった。まあ「高すぎる」という市場認識であろう。
しかし、後年2000年代後半では、神戸の中古カメラ専門店で、
本レンズの海外逆輸入新品を定価のおよそ半額の48,000円
程度で販売していた位なので、買おうとさえ思えば、さほど
負担なく買える価格帯ではあったと思う。
つまりまあ、販売数が少ないので、誰からも評判を聞く事が
出来ず、雑誌等で特集される事も少なかったので、まあ一般
消費者層や初級マニア層等では、「誰かが、”良い”と言った
から買う」という受動的な購買行動に頼る為、そうした情報が
一切なければ、買うような事も無かったのだろう。

という事で、残念ながら「投機対象」となってしまった。
つまり、「高くても買いたい」あるいは「もっと高く売れる
かも知れない」という消費者層が居る為に、本レンズを
高額取引の対象として、15万円とか20万円とかの相場で
売買する、という意味である。
まあ、本記事では、一切、本MAP125/2.5の性能評価等は
行わない事とする。たいてい過去記事に長所も短所も書いて
あるし、冒頭に書いた通り「使いこなしワースト・ワンの
修行レンズ」である故、実用価値はあまり高く無いレンズだ。
単に希少だから、という理由で投機対象となってしまう事には
全く賛同できない。レンズはあくまで写真を撮る為の実用品だ。
モノの本質を見極める「絶対的価値感覚」を、多くの
消費者層に身につけてもらいたい、と切望する次第である。
----
さて、では新型マクロアポランターの話に進もう。

(新品購入価格 138,000円)(以下、MAP110/2.5)
カメラは、SONY α6000(APS-C機)
旧型から17年の歳月を隔て、2018年末に発売された新型
マクロアポランターである。当然、MFでフルサイズ対応だ。
当初2018年夏に発売予定であったのだが、遅れに遅れた発売と
なった。このレンズは発売後すぐに新品購入する予定(後述の
理由あり)だったので、やきもきする状況であった。
なお、前年2017年にコシナ史上2本目のマクロアポランター
65mm/F2が発売されているが(本シリーズ第10回記事等参照)
その中望遠マクロの紹介は本記事では割愛する。
本記事では、あくまで「望遠のマクロアポランター」に
特化しよう。
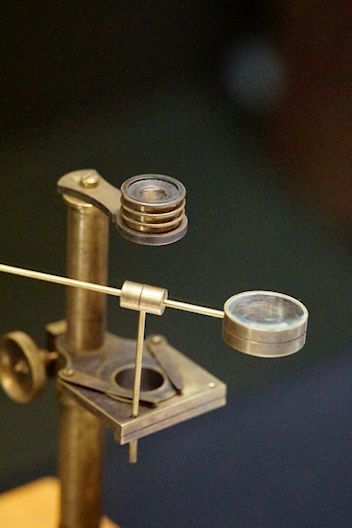
レンズだから、AFが搭載されていない事はむしろメリットだ。
現代的な仕様のAFレンズは、近接域では非常に使い難い。
(例:超音波モーター搭載のマクロは実用的とは言い難い)
それと、コシナ社にも、それほどAFレンズ開発のノウハウが
蓄積されている訳でも無い。であれば、無理にAF化する
必然性は無く、MFである事がむしろ潔い。
操作性等、旧型MAP125/2.5からの弱点は良く解消されている。
描写力も高く、勿論年月を隔て、諸収差は大変良く補正されて
いて解像力等もかなり高目だ。又、コントラスト特性も極めて
良好で、ここは特筆すべてきであろう。
ただ、このあたりの高性能の理由は、本レンズは完全な
コンピューター光学設計になっているような気がする。
その確証は無いが・・ 個人的な感覚での話をするならば、
コンピューター設計は、「メリット(評価)関数」を高める
ように計算機が、どんどんと複雑なレンズ構成を提示してしまう。
結果、性能が良いレンズは出来るのだが、”大きく重く高価”な
「三重苦」レンズとなってしまう次第だ。

構成であり、異常低(部分)分散ガラスを、何と8枚も使用
している。手計算の設計では、ここまで複雑なレンズは
設計の手間が掛りすぎてしまうから無理であろう。
ただ、非球面レンズは使用していないので、僅かなりとも
設計者の主張(コンセプト)はコンピューター設計上でも
加わっていると思える。・・なんと言うか、もし完全に計算
機まかせの設計となると、単に諸収差を補正する事のみが
主体となってしまい、無機質な(=特徴や主張の無い)
雰囲気の強いレンズが出来上がってしまう事があるのだ。
(他社で、そういう無機質な新鋭高性能レンズは良くある)
コンピューターもまた、あくまで「道具」であるから、
使用者(設計者)の意思が介在され、その用法の差があって
結果としての製品に個性が出て来る事が好ましい。
つまり「設計もアートである」からだ。それが無く、単に
計算機や設計ソフトに振り回されている状況だと良く無い。
まあ、この事は、カメラを使う人でも同様であり、最新の
高価な超絶性能機を購入して、フルオートのままで使い
「ただシャッターを押すだけ、カメラに使われているだけ」
の状態になってしまったら、全く好ましく無い訳だ。

しまった。サイズ感だが、フィルター径は新旧とも同じ
φ58mm、重量は旧型690g。新型は771gと、やや重い。
しかし、新型はフランジバック長の極めて短いSONY E
マウント(フルサイズ対応FEマウント)専用であるから、
将来の一眼レフ版への転用も意識して、バックフォーカス
を稼ぐ長目の鏡筒となっている可能性も高く、それによる
若干の重量増があるかも知れない。
(例:SIGMA ART Lineレンズ等では、一眼レフ用と比べて
SONY Eマウント版等は、後部にマウントアダプターを装着
したような形状となり、重量も増えている)
また、この仕様からか?本MAP110/25は、鏡筒中央部が
太く、前後がすぼまっているファット(太った)な
デザインとなっている。これは少々好みでは無いのだが
結果として、ピントリングは幅広の大型で廻しやすくなり、
回転角も適正となった為(=最大持ち替え回数8~9回)
旧型MAP125/2.5よりも操作性は雲泥の差で向上した。

フルサイズ機で使うよりも、周辺がカットされるAPS-C機
で使う方が、さらに画質的に有利であるし、仮にピクセル
ピッチが狭いAPS-C型の高画素機が出てきても、レンズの
解像性能とのバランスは乱れる事は無いであろう。
望遠マクロを、より望遠として特徴を強調する点においても
APS-C機での使用は望ましく、今回は、その検証の意味でも
APS-C機のSONY α6000を母艦として使用している。
勿論、描写力的な課題は何もなく、重量バランスは、やや
トップヘビーとはなるが、丁度重心位置に太いピントリング
が来るので、MFシステムとして使い易い。
ピントの歩留まりの問題も、SONY機の優秀なピーキング機能
でアシスト可能ではあるが、最短撮影距離付近では、極薄の
被写界深度となり、ピーキングすらも出ない場合があるし、
勿論撮影技法的にも、非常に困難な状況となる。
逆説的だが、等倍マクロ仕様ながら、あまり極端な近接撮影
は避けておくのも賢明かも知れない。(そういう意味では、
フルサイズ機での使用もありだろう)
あと、遠距離撮影では、僅かながら解像感が低下する
印象を持つが、重欠点では無い。

「三重苦」ではあるが、幸いにして操作性やハンドリングは
「修行」という程の覚悟はまるでいらない程度で済んでいる。
コストの高さは、レンズ市場縮退による高付加価値型商品で
あるので、若干やむを得ない。まあ、旧型の約2倍の新品
購入価格は、新型のパフォーマンスの高さを鑑みて、容認
せざるを得ないが、それでもコスパ評価は相当に低くなる。

も少なく、知らない間に売り切れて販売終了となってしまう
事も大変多い。 だから、初級マニア層や好事家等が、手に
入らなくなった頃に大騒ぎをして、それを受けて投機層等が、
相場高騰を狙った買占めに走ってしまう訳だ。
なお、もし不自然なまでの好評価等がある場合は、それは
相場高騰を狙った情報操作であるケースも残念ながらあり得る
話なので、消費者層は正しい価値感覚と判断力を身につける
必要がある。ここは、とても重要な事だ。
本ブログの毎回のレンズ紹介記事で、必ず購入価格を記載
しているのは、高く買ったり安く買ったりした事を自慢する
意味ではなく、「適正な相場感覚」を読者層に意識して
もらいたいからである。基本的には新品・中古相場は時間
とともに下がっていくものであるから、後年にこれらの
レンズを購入する場合、本ブログに書いてある価格以上で
購入してしまう事は、基本的には好ましく無い状態なのだ。
で、こうしたフォクトレンダー製レンズを必要だと思った
ならば、なんとしても販売期間中に入手しなければならない。
だから私も、本レンズも発売後速やかに新品購入している訳だ。
しかし、その結果として満足する場合も、不満足の場合も
あるだろうが、それもまた経験であるし、容認リスクである
とも言える。
すなわち、旧型のMAP110/2.5を買って失敗したとも思っても
新型でそれを帳消しに出来れば良い訳だ。
20年間以上使えて合計20万円、月に千円以下の「使用料」
だと思えば、両マクロアポランターを保有するのも悪く無い。

私個人の評価データベースから引用して公開しておく。
例によって、この点数だけが一人歩きする事は好ましく無い。
評価点は評価者によりけりで依存するし、あくまで評価とは
ユーザー毎に自分自身で行う事が大原則だ。
もしそれが出来ず、「他人の評価を参考にするしか無い」と
言うならば、そこからいくら時間をかけても、お金を使っても
それが自力で出来るように、と目標設定をして、それに向けて
精進して頑張っていくしか無いでは無いか・・
それをやらずしては「何の為の趣味なんだ?」となってしまう。
趣味を続ける上で「向上心」や「探究心」は必須の要素だ。
では評価点だ。
旧製品:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 125mm/f2.5 SL
【描写表現力】★★★★☆
【マニアック】★★★★★
【コスパ 】★★☆(新品79,000円)
【エンジョイ】★☆
【必要度 】★★★★
・評価平均値:3.5
(★=1点、☆=0.5点)
新製品:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 110mm/f2.5
【描写表現力】★★★★★
【マニアック】★★★★★
【コスパ 】★☆ (新品138,000円)
【エンジョイ】★★★☆
【必要度 】★★★★☆
・評価平均値:3.9
(★=1点、☆=0.5点)
一目瞭然の評価結果だ。両者、高性能でマニアック度も高く、
その点は全所有レンズの中でも十数本しか無いトップクラスの
高評価で、その点に不満は無く、所有するに値するレンズだ。
弱点だが、旧型の場合は、操作性の悪さ等を主因とする
「修行レンズ」とも言えるまでの「エンジョイ度」の低さだ。
新型の場合は、「何故こんなに高価になった?」と思える程の
コスパの悪さである。
まあ、それらの欠点に目をつぶるとしても、旧型ではあまり
楽しめない事は確かであり、新型の勝利は明白だ。
そして、両者とも評価平均値が4点に満たないので、
いわゆる「名玉」にはノミネートし難い状態である。
本ブログで「名玉」と呼ばれる条件は、上記の評価項目を
全て高得点で乗り切り、全くと言っていい程、弱点が無い
状況にならないと無理である。それは容易な事ではなく、
評価平均点が4点を超えるレンズは、さほど多くない。
また、初級中級者や初級マニア層等が指向する「有名で
人気がある高額なレンズ」等は、上記の評価手法では
全く点数が伸びず、「名玉」にノミネートできる可能性が
皆無である事も理解できるであろう。まあだから、私は
そうした「コスパが悪い」と容易に予想できるレンズは、
事前の「書類審査」の段階で「落選」となってしまって
一切購入していない訳だ。
まあでも、そこもユーザーの好き好きであろう、つまり
この評価手法に疑問があるならば、自身の機材購入コンセプト
に合わせて、新たにユーザー個々に評価項目を設定すれば良い。
例えば、「所有満足感」とか「業務用途適正」など、色々と
考えられると思う(ただ、この評価項目でも、それらは若干
ながら意識してはいる。そして、マクロアポランターでの
「業務用途」は、まず有り得ない)
ここもまあ「評価は個人毎にそれぞれ」「評価は自分で行う」
という真理に直結する事だと思う。
----
さて、今回の記事は、このあたり迄とする。
次回記事は、また通常の新規レンズ紹介を予定している。