高いコストパフォーマンスと付随する性能を持った優秀な
写真用交換レンズを、主にコスパ面からの評価点による
BEST40レンズをランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回もまた、BEST40にランクインしたレンズを下位から
順に紹介して行こう。
(ランキングの決め方は第1回記事を参照、なお、評価
得点が同点の場合は、適宜、順位を決定している)
それと、今まで下位ランキングのレンズでは、マニアック
すぎて一般的では無いレンズも多々登場している。
一応「入手性が悪いレンズ」は、ランキングの対象外と
しているのだが、マニアックなものは入って来てしまう。
本記事あたりの中位ランキングから、少しづつマニアック
過ぎるものは影を潜め、一般的なレンズが多くはなってくるが、
初級中級層が想像するような、有名ブランドレンズ等での
値段が高いものは、当然コスパの観点からは本ランキングには
絶対に入り得ない。そういう類のレンズは今後ランキング記事
には出て来ないし、そもそも私は、その手のレンズを現在は、
1本も所有してもいない、コスパの悪いものは私の機材使用の
コンセプトにおいては成り立たないのだ。
(だから、そうしたレンズは最初から購入対象外だ)
---
第28位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 4.0)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
レンズ名:OLYMPUS M.Zuiko Digital 45mm/f1.8
レンズ購入価格:16,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)
ハイコスパ第4回記事で紹介の2010年代のμ4/3専用
AF単焦点レンズ。(以下MZ45/1.8)
一言で言えば「優れた描写力を特徴とする本格派レンズ」
である。おまけに小型軽量、価格も安価でコスパが良い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
μ4/3機専用で、フルサイズ換算90mmの画角となる事から
オリンパスでは人物撮影の用途を前提としている模様で、
「ママのためのファミリー・ポートレートレンズ」という
キャッチフレーズが付いている。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
定価は35,000円+税とさほど高目ではなく、これは「エントリー
(お試し版)レンズ」の価格帯だが、それにしては描写力が高い。
まあ、エントリーレンズで画質が悪ければ、初級層は二度と
交換レンズを買わなくなる道理なので、エントリーレンズは
どんな場合でも、コストを超越した高描写力を持っている。
さて、OLYMPUSではμ4/3レンズのカテゴリーを3つに分けていて、
M.ZUIKO PRO、M.ZUIKO PREMIUM、M.ZUIKO と分類される。
これは、初級マニア層等では「松・竹・梅」と言われる事もある。
本MZ45/1.8は、「竹」の「M.ZUIKO PREMIUM」のカテゴリーに
入っているのだが・・必ずしもこの松竹梅の順に描写力が高い
という訳でも無いであろう。
現代のレンズの価格の大半は開発費等の償却で決まるので、
多額の費用をかけて開発し、かつ販売本数が少ない場合は、
価格を上げざるを得ない。
だからまあ、一般的に様々なメーカーのレンズを比べる際には、
値段と性能は比例しないのだ。
だがまあ、メーカーが自社レンズ群を、そのように分類している
場合には、高級品が低価格品に負けていたら困った事になるので、
ある程度、描写力等でのカテゴライズには根拠はあると思う。
でも、あまり気にする必要はない、あくまでこうした措置は
初級中級層に向けての「わかりやすさ」の一環であるからだ。
上級者やマニアであれば、自分の撮影用途に必要なレンズを
買うだけであり、メーカーや販売店の言う事は、基本的には
関係が無い(むしろ個人的には、メーカーから「高画質だ」
と、押し付けがましい仕様型番が記載されているレンズは
好まない、それにより値段を上げている事が明白だからだ)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
余談だが、先年、撮影スポットで初級マニアと見られる男性と
出会った。そこで出た質問だが
男「高いレンズの方が良いレンズなのでしょうか?」
匠「いえ、そんな事はありません。
高いレンズは、開発費やらが沢山かかっているのを販売数で
振り分けるので、売れる数が少なければ高くなるのですよ」
男「・・・(しばらく考えて)
ああ、なるほど! そういう事なのでしたか!」
匠「ちなみに、高いと販売本数が減るし、本数が減ると
余計高くなります、これは悪循環ですね・・」
男「ふうむ、そういう考え方もありますね」
(いや、これは私個人の考え方ではなく、経済原理、つまり
世の中の理屈であり、事実であり、常識なんだけどなあ・・
マニアとは言え、こういう事を知らないと、きっと損すると思う)
まあ、確かにレンズの開発というのはお金がかかる、
人件費としての研究費、マーケティング費、設計用ソフトウェア
の購入や開発・改良、光学設計の実働時間は勿論の事、
加えて、筐体デザイン、電子設計、機構設計、ハードウェア試作、
原材料の性能改善についての研究費と部材代、ファームウェア開発、
デバッグ、各種性能検証、他社製品との比較検証。
そして無事生産に漕ぎ着けたとしても、金型代、生産ラインの
改善や整備、部品代、試験費用、加工代、梱包費、輸送費・・
さらには、カタログ原稿、同デザイン、印刷、各種営業経費、
広告、キャッチ、WEBページ制作等の販売促進費用・・
そうやって苦労して作った「製品」(モノ)が、もし予定して
いる程には売れなかったら大打撃だ。
日本においては、企画された予測販売数まで、いっぱいいっぱい
生産を行う。品切れ等は起こり難いが、売れ残り、無駄な生産に
なってしまうケースも多い事であろう。
新製品に係わる様々な経費を下げるには、このμ4/3であれば、
OLYMPUSとPANASONICおよびレンズメーカーとの協業で
共通仕様のレンズを作る手段もあるだろう、勿論一部では
そうしていると思うが、大半はそうでは無い。
本MZ45/1.8 に近いスペックのPANA製レンズは、G42.5mm/f1.7
があるのだが、そちらの定価は、50,000円+税と
本レンズよりも多少割高だ。
レンズのラインナップ全体を見渡してもOLYMPUSとPANASONIC
は、上手くスペックが被らないようになっているように見える。
で、本来、μ4/3は各社共通の「オープン規格」として提唱
されたものであるが、マウントはともかく、レンズやらは、
完全に同じスペックにしてしまう事は困難であろう。
メーカー毎での市場戦略上の考えの差異が色々と出てくる事は
やむを得ない。ただ、この状態があまりに酷くなると、
1960年代頃に、共通マウント規格として多くのカメラメーカー
が採用した「M42マウント」が、1970年頃には「絞り優先露出」
等の新機能の搭載の為、各社勝手にM42の仕様を自社向けに
変更して、他社互換性が完全に薄れてしまい、同じM42なのに
他社カメラに、装着できない、外れないというトラブルもあった。
(ミラーレス・マニアック第45回記事参照)
またそういう状況が再発し、μ4/3規格が各社独自にバラバラに
なっていかない事を願うばかりだが、すでに「空間認識AF」や
「像面位相差ハイブリッドAF」等、新しい独自技術が採用され
て来ているし、今後、それに対応しているレンズでないと動作
しないケースが頻発するようになってしまえば、μ4/3陣営内
でも、互換性・汎用性が失われてしまう事になりかねない。
まあ、他陣営のカメラの性能が日々進歩して行く状況では
そうなるのもやむを得ないが、実際にそこまでの超絶性能が
全てのユーザー層に必要な訳でも無い。下手をするとユーザー
不在で際限なくスペックが上がってしまう事も極めて良くある
(例:画素数競争、高感度競争、連写速度競争)のだが、
総合的に、なかなかそのあたりは、どの方針が正解というのは
決め難いかも知れない。
また、Panasonicは近年ではμ4/3機以外にも、フルサイズ
のミラーレス機をライカ社やSIGMA社と組んで展開している、
ここもまた、μ4/3陣営の足並みが乱れている感じであり
μ4/3機のユーザー側としては不安事項だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15551683.jpg]()
余談ばかりで、本MZ45/1.8の話がちっとも出て来なかったが
描写力的には全く問題の無いレンズだ。
課題は、MF操作性が悪い事だ。ただこれは本レンズのみならず
無限回転式ピントリングの殆どのミラーレス用レンズで同様だ。
本レンズだけの問題としては、フィルター径がφ37mmと
小さすぎて、市販品の選択肢が少ない事である。
しかし総合的には良いレンズだ。初級中級者向けのみならず、
小型軽量かつ高コスパレンズとしてマニア層にもおすすめだ。
---
第27位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 3,5)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15553173.jpg]()
レンズ名:TAMRON SP AF 200-500mm/f5-6.3 LD (A08)
レンズ購入価格:33,000円(中古)(NIKON版での価格)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第66回記事等で紹介の、
2004年発売のAF超望遠ズームレンズ。
本レンズはα(A)、NIKON Fの異マウントで2本所有しており、
ほぼ100%、ドラゴンボート競技撮影専用のレンズだ。
(一般的には、野鳥、動物園、運動会、航空機等での手持ち
撮影分野に向くと思う)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15553158.jpg]()
最大の特徴は、テレ端500mmの超望遠ズームレンズとしては
最軽量の1200g台という点であり、三脚座を外すとさらに
軽量となる。この状態では、前モデルTAMRON 75D等の
望遠端400mmの超望遠ズームより軽量である場合もあり、
ハンドリング性能に優れる。
課題は、手ブレ補正機構を内蔵していない事だ。
画角が500mm、あるいはAPS-C機では750mmもの超望遠域に
達するレンズであるので、その点では苦しいと思うかも知れない。
だが、手ブレ補正が無い点については回避法が2つあり、
まず1つ目は、SONYのα(A)マウント機で使用する上では、
ボディ内手ブレ補正機構があり、こうしたサードパーテイー製
レンズでもそれは有効な事だ。(注:PENTAX機用は未発売)
第二に、手ブレ補正が無かったとしても、換算画角の焦点距離を
分母としたシャッター速度(例、1/500秒~1/750秒)以上
がキープできていれば、原理的に手ブレは起こり難い事がある。
この「(換算)焦点距離分の1秒のシャッター速度」は
「手ブレ限界速度」と言い、一般的な初級ユーザーであれば
少なくとも、それを守れば良い。また中上級者であれば、
スキル(技術)を活用し、なるべく手ブレを起こしにくい構えや
状況(何処かにもたれる等)を作り出す事で、この「手ブレ限界
速度」よりも1~2段(半分~1/4)遅いシャッター速度でも
手ブレを抑える事が出来る。
なお、一部のメーカーの機体では、AUTO ISO時に、ISO感度
の切り替わりタイミングの設定ができる(=低速限界設定)
これを上手く用いる事で、手ブレの課題の大半は解決できる。
必要シャッター速度だが、例えば、ボート競技等が行われる、
日中晴天時の状況で考えてみよう。
フィルム時代での、一般的な「カン露出」の法則では、
晴天時、ISO100で絞りF11で、1/125秒の露出値だ。
これだと手ブレ限界よりも、シャッター速度が遅いので、
設定変更が必要だ。
まず本レンズの開放絞り値は、F5~F6.3 となっている。
開放F値変動型のズームレンズであるので、こういった場合は
最も暗い絞り値あるいは、それよりやや絞った状態を基本に
して使えば、ズーミングの変化で絞り値が変動しなくなる。
本レンズの場合、概ねF7.1~F8程度で使うのが望ましい。
記録撮影の場合、あまり作画表現等は深く考える必要は無いし、
撮影距離(遠距離)での被写界深度も考えると、やはりF8程度
が良いであろう、計算も簡単なので、これで算出してみると・・
晴天時、ISO400で絞りF8で、1/1000秒の露出値となる。
(注:カン露出の語呂合わせで「センパチ」と呼ばれる値)
これは、本レンズを最大望遠の500mm端で使用した場合の
換算画角(APS-C機では750mm相当)の、手ブレ限界速度の
1/750秒を上回る為、この条件(ISO400、F8)にセットして
おけば、手ブレの心配は殆ど不要だ。
日が翳ったり、夕方になった場合等は、1/1000秒を目安に
それをキープできるようにISO感度を少しづつ高めていく。
さらには、絞りを少しでも開けていく、あるいは、僅かな
マイナス露出に補正する(=シャッター速度が少し上がる)
はたまた、レンズの構え方を、もう少し慎重にしていく・・
そのような様々な技法を複合的に用いれば、相当暗い状態でも
手ブレ補正機能無しで超望遠ズームを扱う事が出来る。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15553100.jpg]()
まあ、そういう練習は、ボート競技の撮影のみならず、野鳥撮影
とか動物園等でも行う事ができる、そういう経験を沢山積んで、
超望遠の使用にスキルと自信をつけておく事が重要だ。
さもないと、一般ユーザー層では、こうした超望遠レンズを
買ったとしても用途が殆ど無い為、普段は持ち出す事も無い。
が、稀に、スポーツやフィールド(屋外)撮影で、超望遠が
必要になった場合、滅多に扱わない超望遠を、いきなりの
本番撮影で使うのは、どう考えても無理がある。
たとえ業務撮影では無くても、家族や知人の出場するスポーツ
競技の撮影(屋外では、運動会、野球、サッカー、テニス等、
屋内ではバレーボール、バスケ、卓球等)で、上手く望遠
レンズを扱えなくて、失敗写真を連発してたら、家族や知人に
対しても立場が無い事であろう。
家族や友人知人が、本格的に写真を撮らない一般層だったら、
高いカメラを持っていれば良く写るものだと思っているだろうし、
超望遠撮影がいかに難しいか、等と言う事は全く何も知らない。
「ちゃんと撮れていて当然である」と思っているだろうから、
もし失敗写真ばかりだったら、非難される事が必至だ(汗)
だから、そういう滅多に無いケースに備えて、いや、滅多に
無いならば、そうであればある程、超望遠撮影の練習は入念に
しておくのが良いと思う。
さて、一般に超望遠レンズは高価だと言うイメージもあるかも
知れないが、本レンズのような少しだけ古い時代(2000年代)
のレンズであれば、3万円台のお手頃な中古相場だ。
以前愛用していた1990年代発売の400mm級ズームは、今時では
滅多に見かけないのだが、あれば1万円台という格安相場だ。
超望遠が高価すぎて買えない、という事も無いであろう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15553169.jpg]()
注意点だが、超望遠の使いこなしには「ハンドリング性能」
という要素あって、これはズバリ重量だ。
撮影者のスキル、体格、そして撮影時間や体力、あるいは
撮影スタイル、また組み合わせるカメラによっても若干異なって
くると思うが、自身で限界重量を決めておくのが良い。
私の場合、カメラとレンズの合計装備重量が、2.3kgを越えない
事が手持ちでの長時間(8時間以上)撮影での限界と決めている。
この為、レンズ単体では、1300gまでが限度としている。
そのルールでは、残念ながら近年の望遠端600mm級ズームは
実用対象外だ、これらは性能も良く、中古流通も豊富だし、
相場も少しづつ下がって来ていて買いやすい状況ではあるが、
私の用途では、重すぎるのでNGなのだ。
(短時間だけの使用ならば可能だが、持ち運びが面倒だ)
そういう点から、所定の限られた条件内で、500mmという
最も長い焦点距離が得られるズームは、本レンズしか無い。
ただし、近年では少しだけ様相が変わってきている。
それは、今回使用しているα77Ⅱ等の、αフタケタ機、あるいは
ニコン機であれば、デジタルテレコンバーター又はクロップ機能
を使う事で、見かけ上の画角(換算焦点距離)を、さらに伸ばす
事が出来る。
本レンズ+α77Ⅱでは、テレ端は、750mm,1125mm,1500mm
にボタン一発で切り替える事が出来る。
デジタルテレコンは、原理的にはトリミングと等価であるが
実用的には撮影後の写真編集の手間が減る為、有効な機能だ。
(トリミング編集は、縦横比を意識すると、意外に手間だ)
しかし上記の1000mmオーバーの焦点距離は、さすがに冗長だ。
例えば1000mmを越えると、もうレンズを向けた場所に被写体を
捉える事自体が至難の業となるし、さらに1500mmともなると、
どんなに優秀な手ブレ補正機能が入っていても、現実的には
被写体が大きく揺れてフレーミング内に入れる事もままならず、
実用手持ち限界を超えてしまっている。
・・であれば、70-300mm級の描写力が優秀な望遠ズーム
(これは各社にある、ただし、このクラスは廉価版レンズも
多い焦点域なので、ちゃんと写るものを選ぶ必要がある)
を使用して、デジタルテレコンと組み合わせる方が
ハンドリング的には優れているであろう。
具体的には、α77Ⅱで300mm端では換算450mm,630mm,
900mm相当の画角が得られるが、これは望遠すぎる事は無い。
そして、優秀な描写力を持つレンズでも、1kgを越える事は
まず無いので、ハンドリング性能に優れるという訳だ。
また、ハンドリング性能という意味には「撮影時に振り回せる
か否か?」という要素もある。しかし、残念ながら初級中級層
で(超)望遠レンズを手持ち撮影する際、正しいまたは合理的
な構えが出来ている人は殆ど見かけない。
これは、レンズとカメラを含めた総合重心を常に下から支える、
という簡単な技能なので、是非身に付けて貰いたいと思う。
(注:普段では三脚を使用していると、こういう手持ちでの
構えがいつまでも身に付かない)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15553182.jpg]()
色々と余談が長くなったが、実焦点距離が望遠端500mmの
超望遠ズーム中では、本レンズが最軽量で快適に使用でき、
コスパの面でも十分に優れたレンズである。
---
第26位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 4.0)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15555155.jpg]()
レンズ名:FUJIFILM FILTER LENS XM-FL(S) 24mm/f8
レンズ購入価格:5,000円(中古)
使用カメラ:FUJIFIM X-T1(APS-C機)
ハイコスパ第4回記事等で何度か紹介した2010年代の
FUJI Xマウントミラーレス機専用アクセサリーレンズ。
何度も紹介しているので内容が被るし、あまり多くの機能を
持ったレンズでもない、今回の記事では最小限の説明として
おこう。
まず、本レンズは、ボデイキャップ型であり、ヘリコイド等の
MFピント合わせ機構を持たない「固定焦点」仕様だ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15555174.jpg]()
面白いのは、ノーマルの写りの他、内蔵フィルターを切り替える
事で、クロス効果とソフト効果が得られる事だ。
小型軽量で持ち運びの負担は無く、おまけに安価である。
まあ、いわゆる「ボディキャップ型」というカテゴリーの
レンズは近年ではいくつか出てきているが、悪い傾向では無い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15555163.jpg]()
弱点だが、固定焦点と言っても、被写界深度の計算上、
そして実写上でも、完全なパンフォーカスレンズにはなって
おらず、中距離の被写体にしかピントが合っていない。
また、写りは、あまり本格的な物ではなく、通常レンズと
トイレンズの中間のような描写力だ。
ただ、これらの弱点は、本レンズの性格上、あまり気にする
ような物でも無いであろう。
むしろ、ちょっとユルい写りを利点と見て、ソフト効果の
表現力と組み合わせてみたり、カメラ本体のエフェクト
(アドバンスドフィルターやフィルムシミュレーション)と
組み合わせて使う事が、マニア的観点からは面白い。
従来、本レンズはFUJIFILM初期のミラーレス機X-E1で
使う事が多かった、その機体は、AF/MF性能に劣る為、
大口径レンズ等の本格的レンズの使用は厳しかったのだ。
本レンズではAF/MFは不要な為、X-E1の弱点は解消される。
が、X-E1にはエフェクトが一切搭載されていなかった為、
本レンズを使用する為の有効な母艦とはなりえなかった。
今回は後継機のX-T1で使用している、こちらの機種では
やっとエフェクト機能が搭載された為、それを使って
表現力のバリエーションを得る事は可能だ。
ただ、X-T1では、像面位相差AFを搭載し、AF性能が従来機
より上がっているので、こうしたAFでは無いトイレンズを
使うのは、ある意味勿体無い。(=オフサイド状態)
まあ、このように、カメラとレンズの特性を色々考えて
組み合わせを選ぶ事はとても重要だ。相互の弱点が消える
有効な組み合わせがいつでも得られるという保証は無いが、
それを考えているのと、考えていないのでは大きな差がある。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15555169.jpg]()
本レンズだが、必携のレンズという訳では無い。
しかし、安価であるし、小型軽量なので持ち運びの負担も無く、
カメラバッグに常に入れておいて、あるいはボディキャップ
代わりにしておき、必要に応じて、ソフトやクロス効果で
遊んでみる・・と、まあ、そういう用途であろうか。
FUJI Xマウント用単焦点レンズには安価のものが無いので、
そういう意味では、持っておくのも良いかも知れない。
---
第25位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 4.0)
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15560443.jpg]()
レンズ名:NIKON AiAF NIKKOR 50mm/f1.8S
レンズ購入価格: 5,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df(フルサイズ機)
ハイコスパ第1回記事で紹介の、1990年発売のAF単焦点
標準レンズ。
これ以前のMF時代からのAiニッコール等の50mm/f1.8として
完成度が高かった設計を踏襲したものだ。(注;本レンズ
には初期型(1986年製)が存在する模様である)
これは近年2010年代に、レンズ構成の異なる
AF-S NIKKOR 50mm/f1.8Gとしてリニューアルされるまで
かなりの長期(30年以上)にわたって使われていた基本設計
であるから、まあ信頼度や完成度が高いと言えよう。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15560491.jpg]()
これは他のレンズ記事にも書いた事だが「モデルチェンジの
際にレンズ構成を変えなかった物は高品質な設計である事が
保証されている」という話だ。
ただ、これもよく注意しておかないと、レンズの新開発の
費用をかけれなかったので、やむなくそのまま、という
ケースもある。
特に、50mm単焦点標準の小口径(F1.7~F2級)レンズ等は、
花形レンズでは無い地味なラインナップな為、あまり新規開発に
力を入れる事は難しいであろう。事実、MFレンズがAFレンズに
置き換わった1980年代後半とか、銀塩からデジタルに変わった
2000年代前半においても、この手のレンズが新設計に変わった
例は、むしろ極めて少ない。
そして安いレンズである。安いというのは部品代の差とかも
あるのだが、そこはあまり重要では無い。基本的にはレンズは
ガラスと金属とプラスチックの塊だ、いくら品質の良いものを
使ったとして、最終的な定価が何十倍も差が開く訳は無いでは
ないか(例えば、実売1万円台の50mmレンズもあれば、
50万円の50mmレンズもある)
この値段の違いは、前述のように殆どが開発費等だ。
レンズを1本開発するには膨大な経費が必要だ、それを販売本数
で割って償却しなければならない。
販売本数が多ければ1本あたりの開発費償却は少なくなるし
長期間発売が続いてれば、後の方では殆ど開発費は乗ってこない。
本レンズのように、何十年も作り続けられたレンズでは、
もう開発費や金型代など、とうに回収できている。
だから安価になるのであって、別に品質が悪いから安いという
訳では無いのだ。
で、まあ逆に言えば、安価な価格帯のレンズを無理に新設計
して開発費の償却で、やむなく価格が上がって、というのは
不合理な話であろう。新設計の結果、性能が格段に向上し、
高くても沢山売れるのであれば良いのだが、なかなかそういう
ケースも少ないであろう。
ユーザー層の誰もが欲しがるような魅力的な要素は、50mmの
小口径標準レンズには殆ど無いからだ。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15560465.jpg]()
こんな状況ではあるが、じゃあ、50mm小口径というのは
ダメなレンズなのか? というと、そんな事はまるで無い。
むしろ、技術が最もこなれており、銀塩MF時代の古い設計の
ままでも現代に通用する描写力を持つ完成度の高さから、
極めて安価で、かつ性能がそこそこ良いという、コスパの
良さを実感できるレンズ群となる。
この事はニコンに限らず、他社でも同様だ。
例えば、有名な例としては、CANON EF50mm/f1.8(Ⅰ/Ⅱ型)
は超ハイコスパレンズとして、中上級層やマニアであれば
知らない人は居ない(そのレンズは、さらに上位の
ランキングで登場予定)
それから、同一メーカーで同時代に、大口径(F1.4級)標準と、
小口径(F1.7~F2級)標準が同時に併売されている場合、
たいてい小口径版の方が写りが良い。
これは、感覚的な話のみならず、私も、実際にそれらの何組かの
レンズを解像度チャート等を写してみて実験したのだが、
絞りを開けた状態では小口径版の方が解像力が高いのだ。
(理由は、大口径化で諸収差の増大が甚だしいからである)
ここまでの基本性能があるのであれば、AF化やデジタル化の
際に、これを無理してお金をかけて新設計する必要は無い。
元々の基本設計のままで十分通用するからだ。
余った開発リソース(時間、金、人等)は、発展途上であった
ズームレンズ等の開発に廻せばよい、もう50mm小口径は、
放置しておいても大丈夫だった訳だ。
これらの状況から、つまり、50mm小口径は、コスパの面から
言えば申し分の無いレンズとなる。
今後、このランキングでも、数本の50mm小口径がランクイン
する事は確定している。なお、それでも若干選別している
状態であり、もしちゃんと全てを載せようとしたら、ランキング
が殆ど50mm小口径標準レンズで埋まってしまうからだ(汗)
それでは、さすがに面白く無い。
Image may be NSFW.
Clik here to view.![c0032138_15560366.jpg]()
結局、50mm小口径は全てのユーザー層に必携レンズと言えよう。
それをリファレンズ(他のレンズと比べて良し悪しを比較する
為の元になる製品)とする事で、レンズ評価の絶対的価値観が
身についてくる事であろう。
メーカー、あるいは時代により、価格(新品や中古も含む)は
多少ばらつきはあるとは思うが、気にする必要は無い、
どれを買っても、だいたい内部のレンズ構成は同じような物で
あるし、メーカーによる性能の差も殆ど無い。
あえて比較対象を上げるとしたら、ごく近代(2010年代後半以降)
の、最新設計の高性能標準レンズ群であるが、これらは高価格で
あり、銀塩用小口径標準の、およそ数倍~十数倍もの価格に
なってしまう、だからコスパの面では比較の対象にすらならない。
まあでも、それらの最新高性能標準レンズと写りを比較してみる
のも面白いかも知れない。
その描写力は、価格の差ほどには、大差はつかない事にも
気がつくであろう・・
注意点としては、モーター非内蔵のレンズであるから、
NIKON D5000シリーズ、D3000シリーズ等の下位機種では
AFが動かないし、仮にMFで撮ろうにも、これら下位機種の
ファインダー(スクリーン)性能は「仕様的差別化」に
より「劣悪」なのでMF撮影は、ほぼ不可能だ。
本レンズをNIKON上位機種に装着する事は、「オフサイドの
法則」からはアンバランスになるが、まあ、やむを得ない。
----
では、今回はこのあたりまでで、次回記事では、引き続き
ランキングレンズを下位より順次紹介していこう。
写真用交換レンズを、主にコスパ面からの評価点による
BEST40レンズをランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回もまた、BEST40にランクインしたレンズを下位から
順に紹介して行こう。
(ランキングの決め方は第1回記事を参照、なお、評価
得点が同点の場合は、適宜、順位を決定している)
それと、今まで下位ランキングのレンズでは、マニアック
すぎて一般的では無いレンズも多々登場している。
一応「入手性が悪いレンズ」は、ランキングの対象外と
しているのだが、マニアックなものは入って来てしまう。
本記事あたりの中位ランキングから、少しづつマニアック
過ぎるものは影を潜め、一般的なレンズが多くはなってくるが、
初級中級層が想像するような、有名ブランドレンズ等での
値段が高いものは、当然コスパの観点からは本ランキングには
絶対に入り得ない。そういう類のレンズは今後ランキング記事
には出て来ないし、そもそも私は、その手のレンズを現在は、
1本も所有してもいない、コスパの悪いものは私の機材使用の
コンセプトにおいては成り立たないのだ。
(だから、そうしたレンズは最初から購入対象外だ)
---
第28位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 4.0)
Clik here to view.

レンズ購入価格:16,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)
ハイコスパ第4回記事で紹介の2010年代のμ4/3専用
AF単焦点レンズ。(以下MZ45/1.8)
一言で言えば「優れた描写力を特徴とする本格派レンズ」
である。おまけに小型軽量、価格も安価でコスパが良い。
Clik here to view.

オリンパスでは人物撮影の用途を前提としている模様で、
「ママのためのファミリー・ポートレートレンズ」という
キャッチフレーズが付いている。
Clik here to view.

(お試し版)レンズ」の価格帯だが、それにしては描写力が高い。
まあ、エントリーレンズで画質が悪ければ、初級層は二度と
交換レンズを買わなくなる道理なので、エントリーレンズは
どんな場合でも、コストを超越した高描写力を持っている。
さて、OLYMPUSではμ4/3レンズのカテゴリーを3つに分けていて、
M.ZUIKO PRO、M.ZUIKO PREMIUM、M.ZUIKO と分類される。
これは、初級マニア層等では「松・竹・梅」と言われる事もある。
本MZ45/1.8は、「竹」の「M.ZUIKO PREMIUM」のカテゴリーに
入っているのだが・・必ずしもこの松竹梅の順に描写力が高い
という訳でも無いであろう。
現代のレンズの価格の大半は開発費等の償却で決まるので、
多額の費用をかけて開発し、かつ販売本数が少ない場合は、
価格を上げざるを得ない。
だからまあ、一般的に様々なメーカーのレンズを比べる際には、
値段と性能は比例しないのだ。
だがまあ、メーカーが自社レンズ群を、そのように分類している
場合には、高級品が低価格品に負けていたら困った事になるので、
ある程度、描写力等でのカテゴライズには根拠はあると思う。
でも、あまり気にする必要はない、あくまでこうした措置は
初級中級層に向けての「わかりやすさ」の一環であるからだ。
上級者やマニアであれば、自分の撮影用途に必要なレンズを
買うだけであり、メーカーや販売店の言う事は、基本的には
関係が無い(むしろ個人的には、メーカーから「高画質だ」
と、押し付けがましい仕様型番が記載されているレンズは
好まない、それにより値段を上げている事が明白だからだ)
Clik here to view.

出会った。そこで出た質問だが
男「高いレンズの方が良いレンズなのでしょうか?」
匠「いえ、そんな事はありません。
高いレンズは、開発費やらが沢山かかっているのを販売数で
振り分けるので、売れる数が少なければ高くなるのですよ」
男「・・・(しばらく考えて)
ああ、なるほど! そういう事なのでしたか!」
匠「ちなみに、高いと販売本数が減るし、本数が減ると
余計高くなります、これは悪循環ですね・・」
男「ふうむ、そういう考え方もありますね」
(いや、これは私個人の考え方ではなく、経済原理、つまり
世の中の理屈であり、事実であり、常識なんだけどなあ・・
マニアとは言え、こういう事を知らないと、きっと損すると思う)
まあ、確かにレンズの開発というのはお金がかかる、
人件費としての研究費、マーケティング費、設計用ソフトウェア
の購入や開発・改良、光学設計の実働時間は勿論の事、
加えて、筐体デザイン、電子設計、機構設計、ハードウェア試作、
原材料の性能改善についての研究費と部材代、ファームウェア開発、
デバッグ、各種性能検証、他社製品との比較検証。
そして無事生産に漕ぎ着けたとしても、金型代、生産ラインの
改善や整備、部品代、試験費用、加工代、梱包費、輸送費・・
さらには、カタログ原稿、同デザイン、印刷、各種営業経費、
広告、キャッチ、WEBページ制作等の販売促進費用・・
そうやって苦労して作った「製品」(モノ)が、もし予定して
いる程には売れなかったら大打撃だ。
日本においては、企画された予測販売数まで、いっぱいいっぱい
生産を行う。品切れ等は起こり難いが、売れ残り、無駄な生産に
なってしまうケースも多い事であろう。
新製品に係わる様々な経費を下げるには、このμ4/3であれば、
OLYMPUSとPANASONICおよびレンズメーカーとの協業で
共通仕様のレンズを作る手段もあるだろう、勿論一部では
そうしていると思うが、大半はそうでは無い。
本MZ45/1.8 に近いスペックのPANA製レンズは、G42.5mm/f1.7
があるのだが、そちらの定価は、50,000円+税と
本レンズよりも多少割高だ。
レンズのラインナップ全体を見渡してもOLYMPUSとPANASONIC
は、上手くスペックが被らないようになっているように見える。
で、本来、μ4/3は各社共通の「オープン規格」として提唱
されたものであるが、マウントはともかく、レンズやらは、
完全に同じスペックにしてしまう事は困難であろう。
メーカー毎での市場戦略上の考えの差異が色々と出てくる事は
やむを得ない。ただ、この状態があまりに酷くなると、
1960年代頃に、共通マウント規格として多くのカメラメーカー
が採用した「M42マウント」が、1970年頃には「絞り優先露出」
等の新機能の搭載の為、各社勝手にM42の仕様を自社向けに
変更して、他社互換性が完全に薄れてしまい、同じM42なのに
他社カメラに、装着できない、外れないというトラブルもあった。
(ミラーレス・マニアック第45回記事参照)
またそういう状況が再発し、μ4/3規格が各社独自にバラバラに
なっていかない事を願うばかりだが、すでに「空間認識AF」や
「像面位相差ハイブリッドAF」等、新しい独自技術が採用され
て来ているし、今後、それに対応しているレンズでないと動作
しないケースが頻発するようになってしまえば、μ4/3陣営内
でも、互換性・汎用性が失われてしまう事になりかねない。
まあ、他陣営のカメラの性能が日々進歩して行く状況では
そうなるのもやむを得ないが、実際にそこまでの超絶性能が
全てのユーザー層に必要な訳でも無い。下手をするとユーザー
不在で際限なくスペックが上がってしまう事も極めて良くある
(例:画素数競争、高感度競争、連写速度競争)のだが、
総合的に、なかなかそのあたりは、どの方針が正解というのは
決め難いかも知れない。
また、Panasonicは近年ではμ4/3機以外にも、フルサイズ
のミラーレス機をライカ社やSIGMA社と組んで展開している、
ここもまた、μ4/3陣営の足並みが乱れている感じであり
μ4/3機のユーザー側としては不安事項だ。
Clik here to view.

描写力的には全く問題の無いレンズだ。
課題は、MF操作性が悪い事だ。ただこれは本レンズのみならず
無限回転式ピントリングの殆どのミラーレス用レンズで同様だ。
本レンズだけの問題としては、フィルター径がφ37mmと
小さすぎて、市販品の選択肢が少ない事である。
しかし総合的には良いレンズだ。初級中級者向けのみならず、
小型軽量かつ高コスパレンズとしてマニア層にもおすすめだ。
---
第27位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 3,5)
Clik here to view.

レンズ購入価格:33,000円(中古)(NIKON版での価格)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス第66回記事等で紹介の、
2004年発売のAF超望遠ズームレンズ。
本レンズはα(A)、NIKON Fの異マウントで2本所有しており、
ほぼ100%、ドラゴンボート競技撮影専用のレンズだ。
(一般的には、野鳥、動物園、運動会、航空機等での手持ち
撮影分野に向くと思う)
Clik here to view.

最軽量の1200g台という点であり、三脚座を外すとさらに
軽量となる。この状態では、前モデルTAMRON 75D等の
望遠端400mmの超望遠ズームより軽量である場合もあり、
ハンドリング性能に優れる。
課題は、手ブレ補正機構を内蔵していない事だ。
画角が500mm、あるいはAPS-C機では750mmもの超望遠域に
達するレンズであるので、その点では苦しいと思うかも知れない。
だが、手ブレ補正が無い点については回避法が2つあり、
まず1つ目は、SONYのα(A)マウント機で使用する上では、
ボディ内手ブレ補正機構があり、こうしたサードパーテイー製
レンズでもそれは有効な事だ。(注:PENTAX機用は未発売)
第二に、手ブレ補正が無かったとしても、換算画角の焦点距離を
分母としたシャッター速度(例、1/500秒~1/750秒)以上
がキープできていれば、原理的に手ブレは起こり難い事がある。
この「(換算)焦点距離分の1秒のシャッター速度」は
「手ブレ限界速度」と言い、一般的な初級ユーザーであれば
少なくとも、それを守れば良い。また中上級者であれば、
スキル(技術)を活用し、なるべく手ブレを起こしにくい構えや
状況(何処かにもたれる等)を作り出す事で、この「手ブレ限界
速度」よりも1~2段(半分~1/4)遅いシャッター速度でも
手ブレを抑える事が出来る。
なお、一部のメーカーの機体では、AUTO ISO時に、ISO感度
の切り替わりタイミングの設定ができる(=低速限界設定)
これを上手く用いる事で、手ブレの課題の大半は解決できる。
必要シャッター速度だが、例えば、ボート競技等が行われる、
日中晴天時の状況で考えてみよう。
フィルム時代での、一般的な「カン露出」の法則では、
晴天時、ISO100で絞りF11で、1/125秒の露出値だ。
これだと手ブレ限界よりも、シャッター速度が遅いので、
設定変更が必要だ。
まず本レンズの開放絞り値は、F5~F6.3 となっている。
開放F値変動型のズームレンズであるので、こういった場合は
最も暗い絞り値あるいは、それよりやや絞った状態を基本に
して使えば、ズーミングの変化で絞り値が変動しなくなる。
本レンズの場合、概ねF7.1~F8程度で使うのが望ましい。
記録撮影の場合、あまり作画表現等は深く考える必要は無いし、
撮影距離(遠距離)での被写界深度も考えると、やはりF8程度
が良いであろう、計算も簡単なので、これで算出してみると・・
晴天時、ISO400で絞りF8で、1/1000秒の露出値となる。
(注:カン露出の語呂合わせで「センパチ」と呼ばれる値)
これは、本レンズを最大望遠の500mm端で使用した場合の
換算画角(APS-C機では750mm相当)の、手ブレ限界速度の
1/750秒を上回る為、この条件(ISO400、F8)にセットして
おけば、手ブレの心配は殆ど不要だ。
日が翳ったり、夕方になった場合等は、1/1000秒を目安に
それをキープできるようにISO感度を少しづつ高めていく。
さらには、絞りを少しでも開けていく、あるいは、僅かな
マイナス露出に補正する(=シャッター速度が少し上がる)
はたまた、レンズの構え方を、もう少し慎重にしていく・・
そのような様々な技法を複合的に用いれば、相当暗い状態でも
手ブレ補正機能無しで超望遠ズームを扱う事が出来る。
Clik here to view.

とか動物園等でも行う事ができる、そういう経験を沢山積んで、
超望遠の使用にスキルと自信をつけておく事が重要だ。
さもないと、一般ユーザー層では、こうした超望遠レンズを
買ったとしても用途が殆ど無い為、普段は持ち出す事も無い。
が、稀に、スポーツやフィールド(屋外)撮影で、超望遠が
必要になった場合、滅多に扱わない超望遠を、いきなりの
本番撮影で使うのは、どう考えても無理がある。
たとえ業務撮影では無くても、家族や知人の出場するスポーツ
競技の撮影(屋外では、運動会、野球、サッカー、テニス等、
屋内ではバレーボール、バスケ、卓球等)で、上手く望遠
レンズを扱えなくて、失敗写真を連発してたら、家族や知人に
対しても立場が無い事であろう。
家族や友人知人が、本格的に写真を撮らない一般層だったら、
高いカメラを持っていれば良く写るものだと思っているだろうし、
超望遠撮影がいかに難しいか、等と言う事は全く何も知らない。
「ちゃんと撮れていて当然である」と思っているだろうから、
もし失敗写真ばかりだったら、非難される事が必至だ(汗)
だから、そういう滅多に無いケースに備えて、いや、滅多に
無いならば、そうであればある程、超望遠撮影の練習は入念に
しておくのが良いと思う。
さて、一般に超望遠レンズは高価だと言うイメージもあるかも
知れないが、本レンズのような少しだけ古い時代(2000年代)
のレンズであれば、3万円台のお手頃な中古相場だ。
以前愛用していた1990年代発売の400mm級ズームは、今時では
滅多に見かけないのだが、あれば1万円台という格安相場だ。
超望遠が高価すぎて買えない、という事も無いであろう。
Clik here to view.

という要素あって、これはズバリ重量だ。
撮影者のスキル、体格、そして撮影時間や体力、あるいは
撮影スタイル、また組み合わせるカメラによっても若干異なって
くると思うが、自身で限界重量を決めておくのが良い。
私の場合、カメラとレンズの合計装備重量が、2.3kgを越えない
事が手持ちでの長時間(8時間以上)撮影での限界と決めている。
この為、レンズ単体では、1300gまでが限度としている。
そのルールでは、残念ながら近年の望遠端600mm級ズームは
実用対象外だ、これらは性能も良く、中古流通も豊富だし、
相場も少しづつ下がって来ていて買いやすい状況ではあるが、
私の用途では、重すぎるのでNGなのだ。
(短時間だけの使用ならば可能だが、持ち運びが面倒だ)
そういう点から、所定の限られた条件内で、500mmという
最も長い焦点距離が得られるズームは、本レンズしか無い。
ただし、近年では少しだけ様相が変わってきている。
それは、今回使用しているα77Ⅱ等の、αフタケタ機、あるいは
ニコン機であれば、デジタルテレコンバーター又はクロップ機能
を使う事で、見かけ上の画角(換算焦点距離)を、さらに伸ばす
事が出来る。
本レンズ+α77Ⅱでは、テレ端は、750mm,1125mm,1500mm
にボタン一発で切り替える事が出来る。
デジタルテレコンは、原理的にはトリミングと等価であるが
実用的には撮影後の写真編集の手間が減る為、有効な機能だ。
(トリミング編集は、縦横比を意識すると、意外に手間だ)
しかし上記の1000mmオーバーの焦点距離は、さすがに冗長だ。
例えば1000mmを越えると、もうレンズを向けた場所に被写体を
捉える事自体が至難の業となるし、さらに1500mmともなると、
どんなに優秀な手ブレ補正機能が入っていても、現実的には
被写体が大きく揺れてフレーミング内に入れる事もままならず、
実用手持ち限界を超えてしまっている。
・・であれば、70-300mm級の描写力が優秀な望遠ズーム
(これは各社にある、ただし、このクラスは廉価版レンズも
多い焦点域なので、ちゃんと写るものを選ぶ必要がある)
を使用して、デジタルテレコンと組み合わせる方が
ハンドリング的には優れているであろう。
具体的には、α77Ⅱで300mm端では換算450mm,630mm,
900mm相当の画角が得られるが、これは望遠すぎる事は無い。
そして、優秀な描写力を持つレンズでも、1kgを越える事は
まず無いので、ハンドリング性能に優れるという訳だ。
また、ハンドリング性能という意味には「撮影時に振り回せる
か否か?」という要素もある。しかし、残念ながら初級中級層
で(超)望遠レンズを手持ち撮影する際、正しいまたは合理的
な構えが出来ている人は殆ど見かけない。
これは、レンズとカメラを含めた総合重心を常に下から支える、
という簡単な技能なので、是非身に付けて貰いたいと思う。
(注:普段では三脚を使用していると、こういう手持ちでの
構えがいつまでも身に付かない)
Clik here to view.

超望遠ズーム中では、本レンズが最軽量で快適に使用でき、
コスパの面でも十分に優れたレンズである。
---
第26位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 4.0)
Clik here to view.

レンズ購入価格:5,000円(中古)
使用カメラ:FUJIFIM X-T1(APS-C機)
ハイコスパ第4回記事等で何度か紹介した2010年代の
FUJI Xマウントミラーレス機専用アクセサリーレンズ。
何度も紹介しているので内容が被るし、あまり多くの機能を
持ったレンズでもない、今回の記事では最小限の説明として
おこう。
まず、本レンズは、ボデイキャップ型であり、ヘリコイド等の
MFピント合わせ機構を持たない「固定焦点」仕様だ。
Clik here to view.

事で、クロス効果とソフト効果が得られる事だ。
小型軽量で持ち運びの負担は無く、おまけに安価である。
まあ、いわゆる「ボディキャップ型」というカテゴリーの
レンズは近年ではいくつか出てきているが、悪い傾向では無い。
Clik here to view.

そして実写上でも、完全なパンフォーカスレンズにはなって
おらず、中距離の被写体にしかピントが合っていない。
また、写りは、あまり本格的な物ではなく、通常レンズと
トイレンズの中間のような描写力だ。
ただ、これらの弱点は、本レンズの性格上、あまり気にする
ような物でも無いであろう。
むしろ、ちょっとユルい写りを利点と見て、ソフト効果の
表現力と組み合わせてみたり、カメラ本体のエフェクト
(アドバンスドフィルターやフィルムシミュレーション)と
組み合わせて使う事が、マニア的観点からは面白い。
従来、本レンズはFUJIFILM初期のミラーレス機X-E1で
使う事が多かった、その機体は、AF/MF性能に劣る為、
大口径レンズ等の本格的レンズの使用は厳しかったのだ。
本レンズではAF/MFは不要な為、X-E1の弱点は解消される。
が、X-E1にはエフェクトが一切搭載されていなかった為、
本レンズを使用する為の有効な母艦とはなりえなかった。
今回は後継機のX-T1で使用している、こちらの機種では
やっとエフェクト機能が搭載された為、それを使って
表現力のバリエーションを得る事は可能だ。
ただ、X-T1では、像面位相差AFを搭載し、AF性能が従来機
より上がっているので、こうしたAFでは無いトイレンズを
使うのは、ある意味勿体無い。(=オフサイド状態)
まあ、このように、カメラとレンズの特性を色々考えて
組み合わせを選ぶ事はとても重要だ。相互の弱点が消える
有効な組み合わせがいつでも得られるという保証は無いが、
それを考えているのと、考えていないのでは大きな差がある。
Clik here to view.

しかし、安価であるし、小型軽量なので持ち運びの負担も無く、
カメラバッグに常に入れておいて、あるいはボディキャップ
代わりにしておき、必要に応じて、ソフトやクロス効果で
遊んでみる・・と、まあ、そういう用途であろうか。
FUJI Xマウント用単焦点レンズには安価のものが無いので、
そういう意味では、持っておくのも良いかも知れない。
---
第25位
評価得点 3.70 (内、コスパ点 4.0)
Clik here to view.

レンズ購入価格: 5,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df(フルサイズ機)
ハイコスパ第1回記事で紹介の、1990年発売のAF単焦点
標準レンズ。
これ以前のMF時代からのAiニッコール等の50mm/f1.8として
完成度が高かった設計を踏襲したものだ。(注;本レンズ
には初期型(1986年製)が存在する模様である)
これは近年2010年代に、レンズ構成の異なる
AF-S NIKKOR 50mm/f1.8Gとしてリニューアルされるまで
かなりの長期(30年以上)にわたって使われていた基本設計
であるから、まあ信頼度や完成度が高いと言えよう。
Clik here to view.
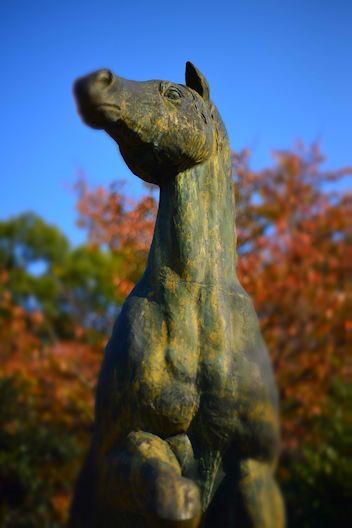
際にレンズ構成を変えなかった物は高品質な設計である事が
保証されている」という話だ。
ただ、これもよく注意しておかないと、レンズの新開発の
費用をかけれなかったので、やむなくそのまま、という
ケースもある。
特に、50mm単焦点標準の小口径(F1.7~F2級)レンズ等は、
花形レンズでは無い地味なラインナップな為、あまり新規開発に
力を入れる事は難しいであろう。事実、MFレンズがAFレンズに
置き換わった1980年代後半とか、銀塩からデジタルに変わった
2000年代前半においても、この手のレンズが新設計に変わった
例は、むしろ極めて少ない。
そして安いレンズである。安いというのは部品代の差とかも
あるのだが、そこはあまり重要では無い。基本的にはレンズは
ガラスと金属とプラスチックの塊だ、いくら品質の良いものを
使ったとして、最終的な定価が何十倍も差が開く訳は無いでは
ないか(例えば、実売1万円台の50mmレンズもあれば、
50万円の50mmレンズもある)
この値段の違いは、前述のように殆どが開発費等だ。
レンズを1本開発するには膨大な経費が必要だ、それを販売本数
で割って償却しなければならない。
販売本数が多ければ1本あたりの開発費償却は少なくなるし
長期間発売が続いてれば、後の方では殆ど開発費は乗ってこない。
本レンズのように、何十年も作り続けられたレンズでは、
もう開発費や金型代など、とうに回収できている。
だから安価になるのであって、別に品質が悪いから安いという
訳では無いのだ。
で、まあ逆に言えば、安価な価格帯のレンズを無理に新設計
して開発費の償却で、やむなく価格が上がって、というのは
不合理な話であろう。新設計の結果、性能が格段に向上し、
高くても沢山売れるのであれば良いのだが、なかなかそういう
ケースも少ないであろう。
ユーザー層の誰もが欲しがるような魅力的な要素は、50mmの
小口径標準レンズには殆ど無いからだ。
Clik here to view.

ダメなレンズなのか? というと、そんな事はまるで無い。
むしろ、技術が最もこなれており、銀塩MF時代の古い設計の
ままでも現代に通用する描写力を持つ完成度の高さから、
極めて安価で、かつ性能がそこそこ良いという、コスパの
良さを実感できるレンズ群となる。
この事はニコンに限らず、他社でも同様だ。
例えば、有名な例としては、CANON EF50mm/f1.8(Ⅰ/Ⅱ型)
は超ハイコスパレンズとして、中上級層やマニアであれば
知らない人は居ない(そのレンズは、さらに上位の
ランキングで登場予定)
それから、同一メーカーで同時代に、大口径(F1.4級)標準と、
小口径(F1.7~F2級)標準が同時に併売されている場合、
たいてい小口径版の方が写りが良い。
これは、感覚的な話のみならず、私も、実際にそれらの何組かの
レンズを解像度チャート等を写してみて実験したのだが、
絞りを開けた状態では小口径版の方が解像力が高いのだ。
(理由は、大口径化で諸収差の増大が甚だしいからである)
ここまでの基本性能があるのであれば、AF化やデジタル化の
際に、これを無理してお金をかけて新設計する必要は無い。
元々の基本設計のままで十分通用するからだ。
余った開発リソース(時間、金、人等)は、発展途上であった
ズームレンズ等の開発に廻せばよい、もう50mm小口径は、
放置しておいても大丈夫だった訳だ。
これらの状況から、つまり、50mm小口径は、コスパの面から
言えば申し分の無いレンズとなる。
今後、このランキングでも、数本の50mm小口径がランクイン
する事は確定している。なお、それでも若干選別している
状態であり、もしちゃんと全てを載せようとしたら、ランキング
が殆ど50mm小口径標準レンズで埋まってしまうからだ(汗)
それでは、さすがに面白く無い。
Clik here to view.

それをリファレンズ(他のレンズと比べて良し悪しを比較する
為の元になる製品)とする事で、レンズ評価の絶対的価値観が
身についてくる事であろう。
メーカー、あるいは時代により、価格(新品や中古も含む)は
多少ばらつきはあるとは思うが、気にする必要は無い、
どれを買っても、だいたい内部のレンズ構成は同じような物で
あるし、メーカーによる性能の差も殆ど無い。
あえて比較対象を上げるとしたら、ごく近代(2010年代後半以降)
の、最新設計の高性能標準レンズ群であるが、これらは高価格で
あり、銀塩用小口径標準の、およそ数倍~十数倍もの価格に
なってしまう、だからコスパの面では比較の対象にすらならない。
まあでも、それらの最新高性能標準レンズと写りを比較してみる
のも面白いかも知れない。
その描写力は、価格の差ほどには、大差はつかない事にも
気がつくであろう・・
注意点としては、モーター非内蔵のレンズであるから、
NIKON D5000シリーズ、D3000シリーズ等の下位機種では
AFが動かないし、仮にMFで撮ろうにも、これら下位機種の
ファインダー(スクリーン)性能は「仕様的差別化」に
より「劣悪」なのでMF撮影は、ほぼ不可能だ。
本レンズをNIKON上位機種に装着する事は、「オフサイドの
法則」からはアンバランスになるが、まあ、やむを得ない。
----
では、今回はこのあたりまでで、次回記事では、引き続き
ランキングレンズを下位より順次紹介していこう。