本シリーズは、所有しているミラーレス機の本体の詳細を
世代別に紹介して行く記事だ。
今回はミラーレス第四世代・成熟期(注:世代の定義は第一回
記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(2015年)
について紹介しよう。
なお、2018年よりミラーレス機のフルサイズ化が一気に進み、
この第四世代(2015年~)は、現在では既に第五世代に
突入していると思えるが、新しい世代定義は、もう数年程度、
市場の様子を見てからとする。
![c0032138_07173303.jpg]()
(レンズ・マニアックス第7回)を使用する。
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、
記事後半では、本機の特性に合致した別のレンズを使う。
![c0032138_07173482.jpg]()
限定モデルであり、ノーマル版の数ヶ月後に発売されている。
限定販売数は7000台である。
ノーマル版との違いは、限定版では1994年発売の「OM-3Ti」
の本体色を彷彿させる「チタンカラー」塗装が施されて
いる事、そして本革ストラップと本革カードケース等が
付属している事くらいであり、本体の機能に差異は無い。
定価はオープンだが、発売時の実勢価格でノーマル版より
2万円高くらいであった。レンズキット(14-150mmが付属)
のみの販売であり、約18万円というのは結構な高額商品だ。
中古の場合は、本体のみの相場でノーマル版より、およそ
2~3万円高となっていた。(注:購入時点2017年頃の話)
![c0032138_07173480.jpg]()
と言う意見もあるだろう、ごもっともな話だ。
ノーマル版であれば、だいぶ安価に購入できるし、どうせ
使い潰すのであれば、減価償却の面(1枚2~3円のルール)
でも楽になる。また高価で希少な限定版は、ラフに扱えず
実用目的(ここでは、業務用途と言う意味では無く、
コレクション機ではなく実際に大量の写真を撮る、という
意味)にはだいぶ不利になってしまう等、良い事は殆ど無い。
(とは言え、本機は高速連写機でもあるので、2年以上使用
した現状において、減価償却ルールをクリアしている)
それでも本機を選んだ理由だが、最大の購入目的は、
「OM-3Ti(チタン)へのノスタルジー」である。
私は1990年代の銀塩時代に、OMヒトケタ機を全部所有しよう
として、それらの中古を探して順次購入していた。
それらの中で「OM-3」「OM-3Ti」の両機は入手が困難な
機種であった。
「OM-3Ti」は1994年発売と、OMシリーズの中では最も新しい。
OMヒトケタ機は1972年のM-1(OM-1)から始まり、実質的な
最終機種は1983年のOM-4や1984年のOM-2SP,OM-3等であるが、
その後のOM-3Tiの発売までに、およそ10年間の開きがあった。
![c0032138_07173341.jpg]()
殆ど無かったか?と言えば、歴史的な「αショック」
(1985年に、ミノルタが世界初の実用的AF一眼レフの
α-7000を発売し、他社より大きく先行した。
これに対して、カメラメーカー全社が、AF化に追従するか、
又は断念して一眼レフ市場から撤退したという事件)
・・において、オリンパスは一眼レフのAF化に事実上失敗し、
1980年代後半より、新規一眼レフを開発する余力を失って
しまった事がある。
ただ、AFコンパクト機等の販売は好調であったので、
オリンパスはカメラ事業を継続する事が出来た。
OMシリーズも一応併売はされていたが、AF機では無い為、
だんだんと「好事家」向けになっていく。そんな中で、
旧機種OM-3(1984年)は特に希少人気であり、その市場
ニーズを受け、外装をチタン化、他、フラッシュ機能を
強化して、1994年に発売されたのが「OM-3Ti」であった。
本体価格は20万円と、かなり高額なカメラである。
(開発費の償却や市場でのニーズにより高価となったので
あろう、性能が高いから値段が高い、と言う訳では無い)
この時代、第一次中古カメラブームが始まる頃であったが
OM-3Ti以外にも、チタン外装のカメラは少なくはなかった。
それらは中古ブームの際によく見かけたが、OM-3Tiは
全然中古が出て来ない。
何年待っていても中古が1台も出ないので、やむなく、
新品で購入する事とした、若干値引きしてもらったが
それでも、14万円前後したと思う。
![c0032138_07175693.jpg]()
なかった模様であり、これくらい少数だと好事家やマニア層が
コレクションや投機目的で死蔵したり、あるいは実用機として
使って消耗させてしまったりと、ほとんど中古市場に機体が
流れてくる事は無い訳だ。
さて、これで手元にOMヒトケタ機が4台揃った。ところが、
中でも、この「OM-3Ti」は、どうにも使い難いカメラであった。
最大の課題は、機械式シャッターのマニュアル露出機であり
絞り値とシャッター速度の変更操作が、レンズとマウント部で
いずれも左手操作になる事だ(OM-1も同様)
この事自体は「オリンパス左手思想」として、天才技術者の
「米谷氏」が考え出した操作性コンセプトであり、ある意味
では合理的だ。(匠の写真用語辞典第1回記事参照)
しかし、そのコンセプトは1970年頃のOM-1(M-1)の開発時に
考え出された事であり、別の言い方をすれば、撮影コストも
高いから、「のんびりと写真が撮れた」時代の話である。
それから四半世紀が過ぎた1990年代後半では、
フィルム現像は、ネガであれば「0円プリント」であり、
カメラは、すでにNIKON F5やCANON EOS-1Nも存在して
いる時代であって、それらの高級機では、ファインダーを
覗きながら電子ダイヤルと内部表示で、速やかな絞り値や
露出補正の操作が可能で、そのまま高速連写が出来た。
また、高級機に限らず、AF一眼レフの多くも同様に操作性の
改善がなされた時代であった。
つまり、実用機としては、スピーディなカメラ設定操作が
出来ないと、お話にもならない時代であったのだ。
具体的には、マニュアル露出機では絞り値操作とシャッター
速度操作が同時に逆方向に行えないと不便だ。
つまり「マニュアルシフト」の操作が手動で必須だからだ。
一般的なマニュアル露出機では、絞り環がレンズ側にあり、
シャッターダイヤルが軍艦部にある。この場合、手指の操作で
少々無理をすれば、マニュアルシフトは出来ない事は無い。
しかし「左手思想」では、それが同時に出来ない。
そしてOMでは、レンズ先端とマウント部の2箇所に、手指を
動かして操作せざるを得ず、「動線」が悪い。
OM-3Tiは「実用価値無し」と見なし、その後しばらくして、
OM好きのマニアに譲渡してしまった。
さらに数年して、デジタル時代に突入した、その頃までに
私のOMヒトケタ熱は完全に醒めていて、結局OM-4Ti(白)を
残して、他のOMヒトケタ機は譲渡や売却等で雲散霧消して
しまっていた。
なお、ごく近年になって「父親のカメラだった」と言って、
美品のOM-1を、無償で譲ってくれる、という人が現れたが
匠「お父様の形見だったら、持っていた方が良いですよ」
と言って断った。が、実際の理由は、OM-1系もOM-3系と
同様にマニュアルシフト操作が出来ずに使い難いからだ。
![c0032138_07175675.jpg]()
最も気になるOMヒトケタ機が「OM-3Ti」であった。
他の機種は、中古カメラブームの時代でも、あるいは
現代でも、まだ入手は可能ではある。
けど「OM-3Ti」は、もう入手困難だ(ごく稀に中古を
見かけても、かなりのプレミアム相場となっている)
そもそも、今更フィルム機を実用目的で買うはずも無い、
だから、絶対に2度と買わないカメラが「OM-3Ti」である。
「気にはなるが、買えない」そういう状態なのであった。
そうした中、やっと本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」
の話になるが、これは、まさしく「OM-3Ti」の雰囲気を
踏襲したカメラだ。勿論「OM-3Ti」での課題であった
マニュアル左手操作等の古い概念はすべて払拭されている
最新のミラーレス機だ、これは多少高くても、買うべき
であろうと思った。
コスパの悪さは「マニアック度」等で相殺できると思った、
限定版の本機がある事を知っていながら、ノーマル版の
E-M5 MarkⅡを買うのは、むしろ、そちらの方が後悔する
だろうとも思ったのだ。
![c0032138_07175643.jpg]()
本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」(以下E-M5ⅡLtd)
の話だが・・
まず、外観的には「OM-3Ti」の雰囲気を良く再現している、
ただし、金属(チタン)ボディの、ひんやりした感触とか
ずっしりとした凝縮感、精密感等(すなわち「感触性能」)
は残念ながら殆ど無い。
本機では軍幹部右上のダイヤル廻りがゴチャゴチャとして
いるが、これは元々のOM-3Tiでもスポット測光系の機能で、
そこだけ複雑であったので、印象的には類似している。
サイズ感だが「E-M5ⅡLtd」は「OM-3Ti」に対して一回り
ほど小さく、重量はかなり軽い。
(本体のみ417g、これは OM-3Tiより100g近く軽い)
まあ、感触性能は低いが「OM-3Ti」のイメージを良く
作り上げている。
背面モニターは自在アングル方式なので、普段は裏返して
おくと銀塩機の雰囲気により近くなる。
さてここで、使用するレンズを銀塩OM時代のレンズに
換えてみよう。
![c0032138_07175612.jpg]()
OLYMPUS OM SYSTEM Zuiko Macro 90mm/f2
(ハイコスパレンズ・マニアックス第18回記事等)
に変更する。
こうしたOM SYSTEM用のオールドレンズを使う際、
やはり本機のような雰囲気を持つカメラとの組み合わせが
マッチする。
それと、OM90/2はOM用レンズの中ではかなり大柄な方で
あり、絞り環の位置も通常のOM用レンズとは異なり
マウント部に近い位置にある(通常のOMレンズでは先端部)
銀塩OMシステムで使う上では、使い難いレンズであったのは
確かであるが、本機E-M5ⅡLtdで使用する際は重量バランス的
にやや悪いが、まあ基本的には問題無い。
![c0032138_07182211.jpg]()
まずEVFだが、236万ドットタイプであり、これは
他社の同時代のミラーレス機でも良く使われている部品だが、
MFでのピントの山の判別は、及第点か、やや不足する感じだ
(画面拡大またはピーキング機能の併用が必須)
![c0032138_07182242.jpg]()
ミラーレス機の中では大きい値だ。ただしこれはμ4/3機で
2倍相当だから、フルサイズに換算すると半分の0.74倍程度
となり、銀塩AF一眼レフ並みの値である。
(注:他のμ4/3機、例えばOM-D E-M1/MarkⅡや PANAの
DMC-G8では本機と同じ1.48倍、それから、PANAのDC-G9や
OM-D E-M1Xでは、本機より大きい1.66倍である)
ちなみに、銀塩MF一眼レフのファインダー倍率は、0.8倍~
0.9倍程度が要求されていた。勿論MF性能を高める為である。
AF時代になってMFの必要性は少し減少した為、AF一眼レフの
ファインダー性能はスペックダウンしてしまった。
だから、たとえ現代のミラーレス機やデジタル一眼レフに
比べて大きい方である本機E-M5ⅡLtdのファインダー倍率も
MFで使うには、スペック上では、やや物足りない印象はある
のだが、まあ実用的には殆ど問題は無い。
なお、オリンパス4/3時代の機体で愛用していた、拡大用の
「マグニファイヤーアイカップ ME-1」は、本機には嵌らず、
使用できない(本機用の拡大アイカップは見当たらない模様だ)
で、MFを補助する為の重要な機能は拡大とピーキングがある。
他社のミラーレス機で、これに優れるのは、PANASONICの
近年(2013年~)のμ4/3機と、SONYのEマウント機のNEX後期
(NEX-7等、2012年)や、以後のα系(2013年~)がある。
PANA機では、MF時の拡大操作系が流れるようにスムースであり、
追加されたピーキング機能も常時表示可能で、精度も高い。
後期NEX/α系では、拡大操作系は拡大枠位置選択操作が煩雑
なのと、一部のα機では、MF設定時で無いと拡大が出来ない、
また拡大解除操作が面倒であるなど、イマイチではあるが、
ピーキングの精度が高く、実質ピーキング機能だけを主体に
すればMFのピント合わせは事足りる。![c0032138_20391948.jpg]()
使う場合、「S-AF+MFでのMFアシスト拡大有り」の設定では、
ピントリングに触れるだけでそれが可能で、またAF時での
拡大操作は測距点と連動した「拡大枠AF」となっているので、
さらに精密な測距点を選べる事(スーパースポットAF)となり、
その点では優れている。
しかし、アダプター利用でMFレンズ等を使用時には、
この拡大の操作系が練れていない。
本機で拡大を行う際、まず、どこかのFnボタンに拡大操作を
アサインする。そして、そのFnボタンを押すと拡大枠が表示され、
さらに再度Fnボタンを押して初めて拡大となる。
拡大枠の移動は十字キーで可能であるが、拡大の解除には、
もう1度Fnボタンを押さなくてはならず、シャッターボタンでの
拡大解除は出来ない(=結果、撮影前構図確認がやりにくい)
これらはEVFを覗きながらの操作である故、全て「手探り」
である。ちゃんと目的のボタンを押せれば良いが、万が一
間違って別のFnボタン等を押し、HDRやデジタルテレコンが
有効になったりすると、ぐちゃぐちゃだ、もう撮影を諦めて
電源を切って画面拡大操作をリセットしなければならない。
まあ、このあたりは、ニコン製デジタル一眼レフでの
ライブビュー時のそれ(一々縮小ボタンを何度も押して
拡大倍率を下げる)と同様に、劣悪な操作系だ。
カメラの設計時に実際に写真を撮る際の操作の流れを良く考察
しないと、単に「その機能が何処かに存在していれば良い」
等の”問題あり”の操作系になってしまう。
品質の悪い操作系設計は、結局利用者側の負担になるのだ。
![c0032138_07182254.jpg]()
AF+MF設定であれば、シームレスMF時にピーキングが表示
されるが、アダプターでMFレンズ使用時には常時表示されず、
またしても希少なFnボタンのいずれかに同機能をアサインし、
それを押してからで無いとピーキングが効かない。
この機能は電源OFFで解除されてしまうので、ほぼ毎回、
MF操作の前に、ピーキング用Fnボタンを押す必要がある。
あるいは、モードダイヤルを廻しても、ピーキングが解除
されてしまい、再度Fnボタンを押さなくてはならない。
(注:本機のピーキング機能は、一応強度調整が可能だが、
精度はやや悪く、過剰に反応しやすい。この為、ピーキング
頼りでピントを合わせても、若干ピンボケになる場合もある。
まあ、ここはレンズによりけりの要素もあるが、レンズ個別
での調整は煩雑で、やや困難だ。
また、「ピーキング背景の輝度調整」機能があり、これは
少しでもピーキング色を見やすくする為の機能だが、これを
数ヶ月間試してみたが、使っても劇的な改善は無く、むしろ
画面全体の輝度が撮影時の物と変わってしまうので、厳密な
作画上ではマイナス要因である為、現在ではOFFにしている)
そして、Fnボタンはボデイ上面右部に3つもある為、他機から
持ち替えた際、どのボタンに何の機能をアサインしていたかを
忘れる場合もある。画面拡大操作では、それを間違って押した
場合でも、シャッター半押しで解除できるのであれば良いが、
それが出来ず、再度「間違えて押したボタン」を手さぐりで
探して押す必要性が出てくる。同様に2倍テレコンをアサイン
した場合でも、間違えて押すと戻すのが面倒だ。
このあたり全般の操作系仕様設計は非常に不満である。
まるで、30年も昔の銀塩OM-3/OM-4系でのスポット測光
機能部(本機と同じ右上部の位置にある)の劣悪な
操作系を思い出してしまう。
(銀塩一眼レフ第13回「OM-4Ti」(1986年)記事参照)
ピーキングの操作系に関しては、オリンパスとしては、
μ4/3用以外の他社等のレンズを本機で使用する事は想定外
(対象外、または排他的仕様)であるのかも知れない。
自社の純正レンズを使ってもらわないと商売(カメラ事業)
が成り立たないからである。
これはオリンパスに限らず、現代では殆どのメーカーの
カメラ(一眼レフ、ミラーレス)でも、自社製レンズで無いと
最大のパフォーマンスを発揮できない、という風に、
エクスクルーシブ(排他的)な仕様となっている場合が多い。
しかし、例えばPANASONIC機では「オールドMFレンズを使った
際にも無駄の無い操作系が得られる」という設計思想を、
初のミラーレス機DMC-G1(2008年)の時代から踏襲している。
その結果、2010年代初頭にはマニア層を中心に第二次オールド
レンズブームを巻き起こし、ミラーレス機の売り上げ増加に
貢献した歴史もあるのだ。
パナの新製品の説明にも「オールドレンズを使った場合でも・・」
等の特徴を記載してある(他社では、その用法をわざと隠す
ような状況も多々ある)
まあ、パナの場合には、過去資産が無く、自社レンズのブランド
力も弱いので、そういうコンセプトになるのだろうが・・
(注:ブランド力が無いので、ライカよりブランドを購入して
使っているが、その分、たとえ同じパナ製品でもライカ銘がつく
だけで非常に高額になるという不条理な状態になっている)
なお、パナの近年のμ4/3機の操作系仕様は、DMC-G1~G6の
時代より悪化している部分もあり、新鋭機を購入していない。
何故操作系が悪化しているのかは、開発チームの変遷もある
だろうが、撮影の実用上の課題においては、開発側も利用者
側においても、気づいていない部分もあると思われる。
(注:最初期のGシリーズでは、銀塩傑作機MINOLTA α-7
の優秀な設計メンバーが関与していたという噂もある)
いくつかの課題については、量販店等で営業マンに伝えては
いるが、はたして改善されるかどうかは不明だ・・
で、各社とも、自社製品だけによるシステム性や利益構造のみに
とらわれず、もっとオープンな発想にならないものだろうか?
![c0032138_07183402.jpg]()
あるが、オリンパスの現在の製品ラインナップの中核は、
PEN/PEN-F,OMと、これらはいずれも銀塩MF時代の名機の
商品名と同じであり(注:銀塩PEN Fは、ハイフン無し)
それらのデザイン感覚やコンセプトを踏襲している、これは
マニア層を意識しているという訳だったのではなかろうか?
事実、「OM-3Tiの雰囲気が欲しかったから、本機E-M5ⅡLtd
を購入した」というマニアックなユーザーも、ここに居る。
銀塩名機の名称や意匠やコンセプトを再利用するのであれば
新規にカメラやレンズを買う新しいユーザー層のみならず、
旧来からのオリンパスファン層やマニア層にも、様々な配慮を
行う事が必要だと思う。
ちなみに、私が本機購入時に迷った他機種には「PEN-F」が
あったのだが、そちらには銀塩PEN Fにあった「Fの花文字」
という重要な意匠(デザイン)上の特徴が欠けていたので、
同機の購入を保留し、本機E-M5ⅡLtdを選択した次第なのだ。
マニアの意識というのは、そういう仔細な点にも拘りがある、
(注:PEN-Fの店頭ポップにはFの花文字が書いてあるのに、
実際の機体を手にすると、それが無くて、がっかりする。
ちなみに、他社から「Fの花文字ステッカー」が市販されて
いる模様だ)
マニアを納得させる製品作り、というのは、必要な要素で
あるのだろうと思う。それがメーカーへの信頼度を増し、
現代のSNS時代では、口コミ等での好評価にも影響し、
結果的に新製品等の売り上げ増加にも繋がるのだと思う。
(さらに余談だが、近年のヨドバシカメラでは「店内撮影OK」
である、SNSで拡散して宣伝して欲しい、との理由のようだ。
旧来のように店舗内やアート作品、舞台・パフォーマンス系
等の撮影を禁止する文化は、現代では失われて来ている。
まあ、どうせ、そのように禁止しても、マナーや倫理感の
無いスマホユーザーが大半なので無意味だ。
そうであれば、情報の拡散を狙った方が、ずっと現代的だ。
ただ、そういう事が、又は他の飲食店等での「SNS映え」と
いう状況が、その店舗等の商売を無意識に手伝っている、
という認識を忘れてはならない。)
![c0032138_07183446.jpg]()
すなわち、MFレンズでも使い易く無いと、本機をMF母艦に
する事は難しい。私が所有している沢山のMFレンズ、
特にOM用レンズを使う際に、OM-3Ti風のE-M5ⅡLtdは
デザインマッチングとしては最適な筈である。
それが「見かけだけ」になってしまったら意味が無い、
実用的にはPANA機のDMC-G6やSONY NEX-7/α7を使った
方が遥かに使い易い状況だ。これではちょっと困ってしまう。
ただ、本機E-M5ⅡLtdには、さらに重要な長所があり、
それは内蔵手ブレ補正機能が(仕様上)優れている点だ。
これは、オールドレンズをアダプターで使用した際にも
有効であり、オリンパスでは旧来からこの仕様となっていた
のだが、この第四世代ミラーレス機の時代から、他社機でも
こうした機能は一般的になりつつある。
他社機では、レンズからの情報を得られないオールドレンズ
での「焦点距離入力操作」が、電源ON時に毎回表示されて
鬱陶しい場合があるが、オリンパスでは「記憶方式」なので、
それは面倒では無い。ただしレンズ交換をした際に利用者自身
が忘れずに焦点距離変更操作をしないとならないのは当然だ。
なお、純正レンズの場合は、ファインダー内に焦点距離が
表示されるが、アダプター使用時は、焦点距離の手動設定を
行ってもファインダー内に設定後の表示が出ない事は不満だ。
(レンズ交換時に焦点距離の設定変更を忘れる事が良くある為)
それと、GX7の記事(本シリーズ第12回)で述べたが、デジタル
テレコン(本機では2倍のみ)を使用しても、手ブレ補正に係わる
焦点距離の設定を2倍に変更する必要は無い(注:GX7では4倍以上
のデジタル拡大が可能だが、その状態ではさすがに手ブレ補正は
不安定だった。この問題があり、その原因が不明だったので、
以前は手ブレ補正の焦点距離も都度、長く設定をしなおして
いたが、厳密な検証により、不安定なのは、超々望遠領域での
手ブレ補正の精度不足に起因する物であり、デジタル拡大機能
使用時の焦点距離再設定は基本的には不要である事がわかった)
「5軸手ブレ補正」は原理的には強力な仕様ではあるが、
マクロレンズ等を使った近接撮影でよく発生する
「被写体に対する前後方向へのブレ」には、勿論対応は
できない、さすがにカメラ(やセンサー)が自動で前後する
ような機構は現時点では搭載できないからだ。
ただし「フォーカスブラケット」という機能により、ピント
位置が異なる画像を連続取得できるが、AFレンズ用の機能で
あり、当然ながらMFレンズではこの機能は使用できない。
実は今回、OM90/2という大型マクロレンズを使用して
いるのは、手ブレ補正の限界性能テストの意味もある、
換算180mmなので、シャッター速度によってはブレ易く、
かつ近接撮影での前後ブレなどが頻繁に発生し、
勿論、手ブレ以上に、風などによる被写体ブレが極めて多数
発生するマクロ(近接)撮影だ。本機の強力な手ブレ補正
機能でも完全にそれらを全てカバーできる訳では勿論無いが、
どこまで近接撮影での課題をサポートしてくれるのか?
それがポイントであった訳だ。
(ちなみに、冒頭に、MZ30/3.5の高倍率マクロレンズを
使ったのも同様の検証の意味がある)
その評価だが、まあ、やはり「近接撮影では、最先端の
手ブレ補正性能でも十分なサポートは出来ない」という
印象である。
それから本記事では使っていないが、200mm以上の焦点距離
の(MF)望遠レンズでは、AUTO ISOのままでは、低速限界
(切り替わり)シャッター速度が低すぎて、優秀な手ブレ
補正でもカバーしきれない程にシャッター速度が低下する。
(注:換算400mm以上となるので、手ブレ補正機能の
精度も足りていないのであろう)
(追記:結局のところ、望遠系レンズでは本機の手ブレ補正
は有効に働いておらず、手ブレ補正が必要となる望遠撮影で
効かないならば殆ど意味が無く、なんだかカタログスペック
上での見かけ倒しのように思えてきている)
加えて、高速機械シャッター時には内部の機械振動も多い。
結果、ブレを誘発する為、こうした場合には、手動ISOと
するが、ISO感度の頻繁な変更操作が発生して面倒だ。
さらに、ISOを高めると連写時の連続撮影枚数の限界値が
下がってしまう弱点があるので、もう滅茶苦茶だ。
望遠レンズでの手ブレのし易さは、本機の本体形状の問題
もあるので、そういう場合は、OM-D E-M1等を使用する方
が若干マシであろう。(E-M1では、高感度時の連写性能
低下も、本機E-M5Ⅱよりも出にくい。本シリーズ第14回
記事参照)
結局、様々な特殊な撮影条件においては、本機の内蔵手ブレ
補正は、その威力を十分に発揮する事は難しい。
ただ勿論、通常撮影においては、AFは勿論、MFレンズでも
本機の高性能手ブレ補正は十分に有効なので、念の為。
![c0032138_07183444.jpg]()
ついては2010年代以降の殆どのミラーレス機や一眼レフも
同様に超多機能だ。ただ、初級中級層はもとより、上級者層に
おいても使いこなせない機能もあると思われ、ちょっと過剰な
までの、カタログスペッック優先的な仕様だとも思われる。
エフェクト(アートフィルター)は種類が充実している。
特に「アートフィルターブラケット」は有効な機能で、
設定した多数のエフェクトを1度のシャッター、同一構図で
並列的にかけられ、従来のように掛けるエフェクトの種類を
色々と悩みながら選ぶ必要は無い(ただし、PENTAX機やCANON
機のような画像効果の二重掛けや詳細な露出設定は出来ない)
![c0032138_07183459.jpg]()
簡便だが、このダイヤルのロック機構は、ON/OFFの設定が
トグル式の機械式構造なのがとても良い。
他社のアナログダイヤルでは、ロックが解除できない状態を
常に強いられてしまう(例、NIKON Df,FUJIFILM X-T1等)
まあ、CANON機のように電子的にロックを行う方法論もあるが
それはデジタルダイヤルにしか効かず、アナログダイヤルの
場合は、本機のやりかたがシンプルかつ遥かに使いやすい。
![c0032138_07184833.jpg]()
秒10コマの高速連写機能があげられる。
ただ、これについては、この第四世代のミラーレス機では、
E-M1 MarkⅡ,SONY α9,α7/RⅢ,PANASONIC DC-G9 Pro
などでも搭載されている機能であり、目新しさは無く、
むしろ新機種に比べて、本機の秒コマ数等は見劣りする。
(注:本機以上の連写速度を持つ機種では、電子シャッター
利用であったり、高速連写時の機能制限が生じる場合もある)
しかし、たとえ秒10コマであっても、デジタル一眼レフと
比べればトップクラスの性能であり、ミラー駆動動作が不要な
ミラーレス機の特徴を最大限に活かしていると言えよう。
(注:だが、前述のように高速連写時の機械振動は大きい)
これはフルサイズ化等のセンサーサイズ差でμ4/3機と差別化
しようとしている一眼レフ陣営との競争においては、大きな
武器となっているであろう。
ただし実用上では、秒10コマは、速過ぎる事も多い
(沢山撮りすぎ、後で編集や選別で手間がかかる)のだが、
本機の秒コマ数は、高速、低速ともに自由に設定可能であり、
かつ、静音連写および低振動連写でも秒コマ数設定が可能で、
このあたりの仕様はとても良い。
例えば、連写中にダイヤルで秒コマ数が可変できたら、さらに
良かったとも思う(その機能は他機を含め実現されていない)
なお、高速連写時の最大コマ数は、JPEGで約19コマと
物足りず、これでは高速連写が約2秒で途絶え、その後は
低速化してしまう為、あまり実用的とは言えない。
また、ISO感度を高めると、さらに連続連写コマ数が減り、
ここは重欠点である(NIKON D300でも同様の欠点があった)
他の色々な記事でも書いたが、実用的には概ね8秒間以上の
連続連写性能が欲しい所だ。ちなみに、この時代の前後以降の
他社機では、バッファメモリーの容量増加等で、連続連写性能
を100枚以上確保している。(注:これ以前の旗艦E-M1では
本機以上のバースト性能を持つ=本シリーズ第14回記事)
それと、秒10コマの連写速度は、旗艦E-M1と同じスペック
であるが、両者のシャッター音は明らかに異なり、違う
ユニットなのであろうか? また、E-M1ではISOを高めても
連写性能は落ちない。それから、同一連写速度でもE-M1の
方が僅かに速く感じるのは気のせいか?
バッテリーは良く持つ。一眼レフも含め、2010年代の
高速連写機では1日の撮影枚数が数千枚にも及ぶ事が
良くあるが、本機においても一種の高速連写機であり、
そのレベルの撮影枚数には対応可能だ。
ただ、これは撮影者のスキルにもよる(ライブビューで
長時間画面を見たり、1枚1枚撮影後に再生確認すれば
当然バッテリー消費は速い。ちなみにワンシーンの撮影後に
すぐ電源をOFFする電池消耗防止の習慣がついている為、
前述のMFレンズでのピーキング機能の電源OFFでの解除が
大きな問題になっている)
なお、充電にかかる時間は結構長くなっている。
![c0032138_07184853.jpg]()
しまうのであるが、スーパーコンパネをカスタマイズできる
程の編集自由度は無い(SONY,PANASONIC,FUJI,PENTAX等
では、それが可能だ)
何故それが必要か?と言えば、増えた新機能(例:フォーカス
ブラケット等)が、メニューの奥深くにある為、速やかに
呼び出したり、細かい設定が出来ない、だから、なんらかの
ショートカット方法が無いとやっていられないのだ。
オリンパス機のスーパーコンパネは旧来、使い易い機能では
あったが、何年たってもそれが進化せず、追加機能ばかりが
増えてしまって、その操作系改善が追いついていない。
それと、フォーカスブラケットと密接な関係のある
「深度合成」機能だが、これを使うには対応レンズを買い、
しかも本機単体では出来ず、外部ソフトを使用する必要がある
という不十分な仕様だ(注:2018年2月のファームェアVer4.0
で、やっと本体内での深度合成が出来るようになった)
また、AFであるが、OM-D E-M1(2013年、本シリーズ第14回)
よりも、本機が後発であるにも係わらず、E-M1にあった
像面位相差AF(DUAL FAST AF)が本機には搭載されておらず、
一般的なコントラストAFのみである。
まあでも、ここは上位機種との「仕様的差別化」であろう。
「カラークリエイター」は色相と彩度が個別に調整でき、
一見有益な機能だが、マルチFnから、これを簡便に呼び出した
として、まず設定可変幅が大きくて、微調整が出来ない。
それと、これを使用すると、それまで手動で設定していた、
ホワイトバランスとピクチャーモード(Vivid等)が解除されて
しまうので、またそれらの設定を手動で戻さなくてはならない。
色相と彩度調整は、これに頼らず、PC上での画像編集が簡便だ。
それから、ISO AUTO時の感度切り替え低速限界シャッター速度
は変更できない。MF望遠レンズ等、レンズの焦点距離に応じて
適正な値を選ぶ為には、この機能は重要なのだが・・
(注:翌年のPEN-Fや、E-M1 MarkⅡでは可能になったが、
1/250秒単速であったり、撮影モードの制限がある模様だ。
OLYMPUSにおけるこの機能は、まだ仕様が練れていない段階だ。
また、同時代のPANA機では、AFレンズではこの値が焦点距離に
応じて自動的に変化するが、アダプター使用時では、低速で
固定となり、手動でも変える事が出来ない)
この問題の回避には、頻繁な手動ISO変更が必須だが、専用の
ISO変更ボタンやISOダイヤルが無く、十字キーへ一旦アサイン
してから前後ダイヤル操作との併用、あるいは1/2機能切換
レバーを変更して前ダイヤルでの操作が必要なので、煩雑だ。
なお、取扱説明書は、肥大化を嫌ったのか?簡易なものであるが、
この程度の内容では多機能を使いこなす為に十分な情報量とは
言えない。例えば「スポット測光」は中央固定となっているが、
これが移動可能か?測距点に連動できるか?などの詳細は
書かれていない。
この状況だと、大半(9割以上)のユーザーは本機の多機能を
使いこなす事は無理であろう。
その他の欠点だが、特に見当たらず、まあ概ね優秀なカメラ
だと言えるであろう。
![c0032138_07184778.jpg]()
評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★★★
【描写力・表現力】★★★☆
【操作性・操作系】★★☆
【アダプター適性】★★☆
【マニアック度 】★★★★★
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★ (中古購入価格:83,000円)
【完成度(当時)】★★★
【仕様老朽化寿命】★★★★☆
【歴史的価値 】★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】3.3点
概ね好評価点だ。
評価点が低かったのは「コスパ」と「操作性・操作系」だ。
コスパは、まあ限定版なので、高価なのはやむを得ない。
その課題を相殺できる要素として「マニアック度」や
「仕様老朽化寿命」の高さを期待して購入したのだ。
「仕様老朽化寿命」が何故高い得点なのか?と言えば、
これはもう「OM-3Tiライク(似ている)」なカメラは
この先、まず出て来ないだろうから、周囲の新製品と比べて
も古くならない事が想定されるからだ。
「操作性・操作系」の弱点は気になるが、それについては、
ミラーレス機全般で、増えすぎた新機能に操作系の整備が
追いついていないのは確かだ。
まあ他社機で、操作系が優秀な機体をいくつか所有しているが
それらはむしろ稀である。
実際の所は本機では
「ピーキング機能のFnボタンアサインが必須」および
「拡大操作系が良く無い」というMF時の弱点が目立つ位で
これらはAF時には問題が無く、重欠点とは言い難い。
だが、この弱点は、MFのオールドレンズを使う際には
大きな課題となりうるので、「アダプター適性」の評価を
少し減点した。
他の項目は概ね平均点、でもまあ、悪くは無いカメラだ。
本機ではAFレンズを主体にするか、あるいは、不便を我慢
しつつMFレンズを使うか?そこは良く考えて使用して
いきたいと思う。
しかし、基本的には「OM-3Ti風のMFレンズ母艦」を
目的に購入したカメラだ、MFでの使用を避ける事はできない、
そこに矛盾があるが、まあ、やむを得ないであろう・・
----
さて、本記事はこのあたりまでで、
次回もまた、第四世代のミラーレス機を紹介しよう。
世代別に紹介して行く記事だ。
今回はミラーレス第四世代・成熟期(注:世代の定義は第一回
記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(2015年)
について紹介しよう。
なお、2018年よりミラーレス機のフルサイズ化が一気に進み、
この第四世代(2015年~)は、現在では既に第五世代に
突入していると思えるが、新しい世代定義は、もう数年程度、
市場の様子を見てからとする。

(レンズ・マニアックス第7回)を使用する。
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、
記事後半では、本機の特性に合致した別のレンズを使う。

限定モデルであり、ノーマル版の数ヶ月後に発売されている。
限定販売数は7000台である。
ノーマル版との違いは、限定版では1994年発売の「OM-3Ti」
の本体色を彷彿させる「チタンカラー」塗装が施されて
いる事、そして本革ストラップと本革カードケース等が
付属している事くらいであり、本体の機能に差異は無い。
定価はオープンだが、発売時の実勢価格でノーマル版より
2万円高くらいであった。レンズキット(14-150mmが付属)
のみの販売であり、約18万円というのは結構な高額商品だ。
中古の場合は、本体のみの相場でノーマル版より、およそ
2~3万円高となっていた。(注:購入時点2017年頃の話)

と言う意見もあるだろう、ごもっともな話だ。
ノーマル版であれば、だいぶ安価に購入できるし、どうせ
使い潰すのであれば、減価償却の面(1枚2~3円のルール)
でも楽になる。また高価で希少な限定版は、ラフに扱えず
実用目的(ここでは、業務用途と言う意味では無く、
コレクション機ではなく実際に大量の写真を撮る、という
意味)にはだいぶ不利になってしまう等、良い事は殆ど無い。
(とは言え、本機は高速連写機でもあるので、2年以上使用
した現状において、減価償却ルールをクリアしている)
それでも本機を選んだ理由だが、最大の購入目的は、
「OM-3Ti(チタン)へのノスタルジー」である。
私は1990年代の銀塩時代に、OMヒトケタ機を全部所有しよう
として、それらの中古を探して順次購入していた。
それらの中で「OM-3」「OM-3Ti」の両機は入手が困難な
機種であった。
「OM-3Ti」は1994年発売と、OMシリーズの中では最も新しい。
OMヒトケタ機は1972年のM-1(OM-1)から始まり、実質的な
最終機種は1983年のOM-4や1984年のOM-2SP,OM-3等であるが、
その後のOM-3Tiの発売までに、およそ10年間の開きがあった。

殆ど無かったか?と言えば、歴史的な「αショック」
(1985年に、ミノルタが世界初の実用的AF一眼レフの
α-7000を発売し、他社より大きく先行した。
これに対して、カメラメーカー全社が、AF化に追従するか、
又は断念して一眼レフ市場から撤退したという事件)
・・において、オリンパスは一眼レフのAF化に事実上失敗し、
1980年代後半より、新規一眼レフを開発する余力を失って
しまった事がある。
ただ、AFコンパクト機等の販売は好調であったので、
オリンパスはカメラ事業を継続する事が出来た。
OMシリーズも一応併売はされていたが、AF機では無い為、
だんだんと「好事家」向けになっていく。そんな中で、
旧機種OM-3(1984年)は特に希少人気であり、その市場
ニーズを受け、外装をチタン化、他、フラッシュ機能を
強化して、1994年に発売されたのが「OM-3Ti」であった。
本体価格は20万円と、かなり高額なカメラである。
(開発費の償却や市場でのニーズにより高価となったので
あろう、性能が高いから値段が高い、と言う訳では無い)
この時代、第一次中古カメラブームが始まる頃であったが
OM-3Ti以外にも、チタン外装のカメラは少なくはなかった。
それらは中古ブームの際によく見かけたが、OM-3Tiは
全然中古が出て来ない。
何年待っていても中古が1台も出ないので、やむなく、
新品で購入する事とした、若干値引きしてもらったが
それでも、14万円前後したと思う。

なかった模様であり、これくらい少数だと好事家やマニア層が
コレクションや投機目的で死蔵したり、あるいは実用機として
使って消耗させてしまったりと、ほとんど中古市場に機体が
流れてくる事は無い訳だ。
さて、これで手元にOMヒトケタ機が4台揃った。ところが、
中でも、この「OM-3Ti」は、どうにも使い難いカメラであった。
最大の課題は、機械式シャッターのマニュアル露出機であり
絞り値とシャッター速度の変更操作が、レンズとマウント部で
いずれも左手操作になる事だ(OM-1も同様)
この事自体は「オリンパス左手思想」として、天才技術者の
「米谷氏」が考え出した操作性コンセプトであり、ある意味
では合理的だ。(匠の写真用語辞典第1回記事参照)
しかし、そのコンセプトは1970年頃のOM-1(M-1)の開発時に
考え出された事であり、別の言い方をすれば、撮影コストも
高いから、「のんびりと写真が撮れた」時代の話である。
それから四半世紀が過ぎた1990年代後半では、
フィルム現像は、ネガであれば「0円プリント」であり、
カメラは、すでにNIKON F5やCANON EOS-1Nも存在して
いる時代であって、それらの高級機では、ファインダーを
覗きながら電子ダイヤルと内部表示で、速やかな絞り値や
露出補正の操作が可能で、そのまま高速連写が出来た。
また、高級機に限らず、AF一眼レフの多くも同様に操作性の
改善がなされた時代であった。
つまり、実用機としては、スピーディなカメラ設定操作が
出来ないと、お話にもならない時代であったのだ。
具体的には、マニュアル露出機では絞り値操作とシャッター
速度操作が同時に逆方向に行えないと不便だ。
つまり「マニュアルシフト」の操作が手動で必須だからだ。
一般的なマニュアル露出機では、絞り環がレンズ側にあり、
シャッターダイヤルが軍艦部にある。この場合、手指の操作で
少々無理をすれば、マニュアルシフトは出来ない事は無い。
しかし「左手思想」では、それが同時に出来ない。
そしてOMでは、レンズ先端とマウント部の2箇所に、手指を
動かして操作せざるを得ず、「動線」が悪い。
OM-3Tiは「実用価値無し」と見なし、その後しばらくして、
OM好きのマニアに譲渡してしまった。
さらに数年して、デジタル時代に突入した、その頃までに
私のOMヒトケタ熱は完全に醒めていて、結局OM-4Ti(白)を
残して、他のOMヒトケタ機は譲渡や売却等で雲散霧消して
しまっていた。
なお、ごく近年になって「父親のカメラだった」と言って、
美品のOM-1を、無償で譲ってくれる、という人が現れたが
匠「お父様の形見だったら、持っていた方が良いですよ」
と言って断った。が、実際の理由は、OM-1系もOM-3系と
同様にマニュアルシフト操作が出来ずに使い難いからだ。

最も気になるOMヒトケタ機が「OM-3Ti」であった。
他の機種は、中古カメラブームの時代でも、あるいは
現代でも、まだ入手は可能ではある。
けど「OM-3Ti」は、もう入手困難だ(ごく稀に中古を
見かけても、かなりのプレミアム相場となっている)
そもそも、今更フィルム機を実用目的で買うはずも無い、
だから、絶対に2度と買わないカメラが「OM-3Ti」である。
「気にはなるが、買えない」そういう状態なのであった。
そうした中、やっと本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」
の話になるが、これは、まさしく「OM-3Ti」の雰囲気を
踏襲したカメラだ。勿論「OM-3Ti」での課題であった
マニュアル左手操作等の古い概念はすべて払拭されている
最新のミラーレス機だ、これは多少高くても、買うべき
であろうと思った。
コスパの悪さは「マニアック度」等で相殺できると思った、
限定版の本機がある事を知っていながら、ノーマル版の
E-M5 MarkⅡを買うのは、むしろ、そちらの方が後悔する
だろうとも思ったのだ。

本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」(以下E-M5ⅡLtd)
の話だが・・
まず、外観的には「OM-3Ti」の雰囲気を良く再現している、
ただし、金属(チタン)ボディの、ひんやりした感触とか
ずっしりとした凝縮感、精密感等(すなわち「感触性能」)
は残念ながら殆ど無い。
本機では軍幹部右上のダイヤル廻りがゴチャゴチャとして
いるが、これは元々のOM-3Tiでもスポット測光系の機能で、
そこだけ複雑であったので、印象的には類似している。
サイズ感だが「E-M5ⅡLtd」は「OM-3Ti」に対して一回り
ほど小さく、重量はかなり軽い。
(本体のみ417g、これは OM-3Tiより100g近く軽い)
まあ、感触性能は低いが「OM-3Ti」のイメージを良く
作り上げている。
背面モニターは自在アングル方式なので、普段は裏返して
おくと銀塩機の雰囲気により近くなる。
さてここで、使用するレンズを銀塩OM時代のレンズに
換えてみよう。

OLYMPUS OM SYSTEM Zuiko Macro 90mm/f2
(ハイコスパレンズ・マニアックス第18回記事等)
に変更する。
こうしたOM SYSTEM用のオールドレンズを使う際、
やはり本機のような雰囲気を持つカメラとの組み合わせが
マッチする。
それと、OM90/2はOM用レンズの中ではかなり大柄な方で
あり、絞り環の位置も通常のOM用レンズとは異なり
マウント部に近い位置にある(通常のOMレンズでは先端部)
銀塩OMシステムで使う上では、使い難いレンズであったのは
確かであるが、本機E-M5ⅡLtdで使用する際は重量バランス的
にやや悪いが、まあ基本的には問題無い。

まずEVFだが、236万ドットタイプであり、これは
他社の同時代のミラーレス機でも良く使われている部品だが、
MFでのピントの山の判別は、及第点か、やや不足する感じだ
(画面拡大またはピーキング機能の併用が必須)

ミラーレス機の中では大きい値だ。ただしこれはμ4/3機で
2倍相当だから、フルサイズに換算すると半分の0.74倍程度
となり、銀塩AF一眼レフ並みの値である。
(注:他のμ4/3機、例えばOM-D E-M1/MarkⅡや PANAの
DMC-G8では本機と同じ1.48倍、それから、PANAのDC-G9や
OM-D E-M1Xでは、本機より大きい1.66倍である)
ちなみに、銀塩MF一眼レフのファインダー倍率は、0.8倍~
0.9倍程度が要求されていた。勿論MF性能を高める為である。
AF時代になってMFの必要性は少し減少した為、AF一眼レフの
ファインダー性能はスペックダウンしてしまった。
だから、たとえ現代のミラーレス機やデジタル一眼レフに
比べて大きい方である本機E-M5ⅡLtdのファインダー倍率も
MFで使うには、スペック上では、やや物足りない印象はある
のだが、まあ実用的には殆ど問題は無い。
なお、オリンパス4/3時代の機体で愛用していた、拡大用の
「マグニファイヤーアイカップ ME-1」は、本機には嵌らず、
使用できない(本機用の拡大アイカップは見当たらない模様だ)
で、MFを補助する為の重要な機能は拡大とピーキングがある。
他社のミラーレス機で、これに優れるのは、PANASONICの
近年(2013年~)のμ4/3機と、SONYのEマウント機のNEX後期
(NEX-7等、2012年)や、以後のα系(2013年~)がある。
PANA機では、MF時の拡大操作系が流れるようにスムースであり、
追加されたピーキング機能も常時表示可能で、精度も高い。
後期NEX/α系では、拡大操作系は拡大枠位置選択操作が煩雑
なのと、一部のα機では、MF設定時で無いと拡大が出来ない、
また拡大解除操作が面倒であるなど、イマイチではあるが、
ピーキングの精度が高く、実質ピーキング機能だけを主体に
すればMFのピント合わせは事足りる。

使う場合、「S-AF+MFでのMFアシスト拡大有り」の設定では、
ピントリングに触れるだけでそれが可能で、またAF時での
拡大操作は測距点と連動した「拡大枠AF」となっているので、
さらに精密な測距点を選べる事(スーパースポットAF)となり、
その点では優れている。
しかし、アダプター利用でMFレンズ等を使用時には、
この拡大の操作系が練れていない。
本機で拡大を行う際、まず、どこかのFnボタンに拡大操作を
アサインする。そして、そのFnボタンを押すと拡大枠が表示され、
さらに再度Fnボタンを押して初めて拡大となる。
拡大枠の移動は十字キーで可能であるが、拡大の解除には、
もう1度Fnボタンを押さなくてはならず、シャッターボタンでの
拡大解除は出来ない(=結果、撮影前構図確認がやりにくい)
これらはEVFを覗きながらの操作である故、全て「手探り」
である。ちゃんと目的のボタンを押せれば良いが、万が一
間違って別のFnボタン等を押し、HDRやデジタルテレコンが
有効になったりすると、ぐちゃぐちゃだ、もう撮影を諦めて
電源を切って画面拡大操作をリセットしなければならない。
まあ、このあたりは、ニコン製デジタル一眼レフでの
ライブビュー時のそれ(一々縮小ボタンを何度も押して
拡大倍率を下げる)と同様に、劣悪な操作系だ。
カメラの設計時に実際に写真を撮る際の操作の流れを良く考察
しないと、単に「その機能が何処かに存在していれば良い」
等の”問題あり”の操作系になってしまう。
品質の悪い操作系設計は、結局利用者側の負担になるのだ。

AF+MF設定であれば、シームレスMF時にピーキングが表示
されるが、アダプターでMFレンズ使用時には常時表示されず、
またしても希少なFnボタンのいずれかに同機能をアサインし、
それを押してからで無いとピーキングが効かない。
この機能は電源OFFで解除されてしまうので、ほぼ毎回、
MF操作の前に、ピーキング用Fnボタンを押す必要がある。
あるいは、モードダイヤルを廻しても、ピーキングが解除
されてしまい、再度Fnボタンを押さなくてはならない。
(注:本機のピーキング機能は、一応強度調整が可能だが、
精度はやや悪く、過剰に反応しやすい。この為、ピーキング
頼りでピントを合わせても、若干ピンボケになる場合もある。
まあ、ここはレンズによりけりの要素もあるが、レンズ個別
での調整は煩雑で、やや困難だ。
また、「ピーキング背景の輝度調整」機能があり、これは
少しでもピーキング色を見やすくする為の機能だが、これを
数ヶ月間試してみたが、使っても劇的な改善は無く、むしろ
画面全体の輝度が撮影時の物と変わってしまうので、厳密な
作画上ではマイナス要因である為、現在ではOFFにしている)
そして、Fnボタンはボデイ上面右部に3つもある為、他機から
持ち替えた際、どのボタンに何の機能をアサインしていたかを
忘れる場合もある。画面拡大操作では、それを間違って押した
場合でも、シャッター半押しで解除できるのであれば良いが、
それが出来ず、再度「間違えて押したボタン」を手さぐりで
探して押す必要性が出てくる。同様に2倍テレコンをアサイン
した場合でも、間違えて押すと戻すのが面倒だ。
このあたり全般の操作系仕様設計は非常に不満である。
まるで、30年も昔の銀塩OM-3/OM-4系でのスポット測光
機能部(本機と同じ右上部の位置にある)の劣悪な
操作系を思い出してしまう。
(銀塩一眼レフ第13回「OM-4Ti」(1986年)記事参照)
ピーキングの操作系に関しては、オリンパスとしては、
μ4/3用以外の他社等のレンズを本機で使用する事は想定外
(対象外、または排他的仕様)であるのかも知れない。
自社の純正レンズを使ってもらわないと商売(カメラ事業)
が成り立たないからである。
これはオリンパスに限らず、現代では殆どのメーカーの
カメラ(一眼レフ、ミラーレス)でも、自社製レンズで無いと
最大のパフォーマンスを発揮できない、という風に、
エクスクルーシブ(排他的)な仕様となっている場合が多い。
しかし、例えばPANASONIC機では「オールドMFレンズを使った
際にも無駄の無い操作系が得られる」という設計思想を、
初のミラーレス機DMC-G1(2008年)の時代から踏襲している。
その結果、2010年代初頭にはマニア層を中心に第二次オールド
レンズブームを巻き起こし、ミラーレス機の売り上げ増加に
貢献した歴史もあるのだ。
パナの新製品の説明にも「オールドレンズを使った場合でも・・」
等の特徴を記載してある(他社では、その用法をわざと隠す
ような状況も多々ある)
まあ、パナの場合には、過去資産が無く、自社レンズのブランド
力も弱いので、そういうコンセプトになるのだろうが・・
(注:ブランド力が無いので、ライカよりブランドを購入して
使っているが、その分、たとえ同じパナ製品でもライカ銘がつく
だけで非常に高額になるという不条理な状態になっている)
なお、パナの近年のμ4/3機の操作系仕様は、DMC-G1~G6の
時代より悪化している部分もあり、新鋭機を購入していない。
何故操作系が悪化しているのかは、開発チームの変遷もある
だろうが、撮影の実用上の課題においては、開発側も利用者
側においても、気づいていない部分もあると思われる。
(注:最初期のGシリーズでは、銀塩傑作機MINOLTA α-7
の優秀な設計メンバーが関与していたという噂もある)
いくつかの課題については、量販店等で営業マンに伝えては
いるが、はたして改善されるかどうかは不明だ・・
で、各社とも、自社製品だけによるシステム性や利益構造のみに
とらわれず、もっとオープンな発想にならないものだろうか?

あるが、オリンパスの現在の製品ラインナップの中核は、
PEN/PEN-F,OMと、これらはいずれも銀塩MF時代の名機の
商品名と同じであり(注:銀塩PEN Fは、ハイフン無し)
それらのデザイン感覚やコンセプトを踏襲している、これは
マニア層を意識しているという訳だったのではなかろうか?
事実、「OM-3Tiの雰囲気が欲しかったから、本機E-M5ⅡLtd
を購入した」というマニアックなユーザーも、ここに居る。
銀塩名機の名称や意匠やコンセプトを再利用するのであれば
新規にカメラやレンズを買う新しいユーザー層のみならず、
旧来からのオリンパスファン層やマニア層にも、様々な配慮を
行う事が必要だと思う。
ちなみに、私が本機購入時に迷った他機種には「PEN-F」が
あったのだが、そちらには銀塩PEN Fにあった「Fの花文字」
という重要な意匠(デザイン)上の特徴が欠けていたので、
同機の購入を保留し、本機E-M5ⅡLtdを選択した次第なのだ。
マニアの意識というのは、そういう仔細な点にも拘りがある、
(注:PEN-Fの店頭ポップにはFの花文字が書いてあるのに、
実際の機体を手にすると、それが無くて、がっかりする。
ちなみに、他社から「Fの花文字ステッカー」が市販されて
いる模様だ)
マニアを納得させる製品作り、というのは、必要な要素で
あるのだろうと思う。それがメーカーへの信頼度を増し、
現代のSNS時代では、口コミ等での好評価にも影響し、
結果的に新製品等の売り上げ増加にも繋がるのだと思う。
(さらに余談だが、近年のヨドバシカメラでは「店内撮影OK」
である、SNSで拡散して宣伝して欲しい、との理由のようだ。
旧来のように店舗内やアート作品、舞台・パフォーマンス系
等の撮影を禁止する文化は、現代では失われて来ている。
まあ、どうせ、そのように禁止しても、マナーや倫理感の
無いスマホユーザーが大半なので無意味だ。
そうであれば、情報の拡散を狙った方が、ずっと現代的だ。
ただ、そういう事が、又は他の飲食店等での「SNS映え」と
いう状況が、その店舗等の商売を無意識に手伝っている、
という認識を忘れてはならない。)

すなわち、MFレンズでも使い易く無いと、本機をMF母艦に
する事は難しい。私が所有している沢山のMFレンズ、
特にOM用レンズを使う際に、OM-3Ti風のE-M5ⅡLtdは
デザインマッチングとしては最適な筈である。
それが「見かけだけ」になってしまったら意味が無い、
実用的にはPANA機のDMC-G6やSONY NEX-7/α7を使った
方が遥かに使い易い状況だ。これではちょっと困ってしまう。
ただ、本機E-M5ⅡLtdには、さらに重要な長所があり、
それは内蔵手ブレ補正機能が(仕様上)優れている点だ。
これは、オールドレンズをアダプターで使用した際にも
有効であり、オリンパスでは旧来からこの仕様となっていた
のだが、この第四世代ミラーレス機の時代から、他社機でも
こうした機能は一般的になりつつある。
他社機では、レンズからの情報を得られないオールドレンズ
での「焦点距離入力操作」が、電源ON時に毎回表示されて
鬱陶しい場合があるが、オリンパスでは「記憶方式」なので、
それは面倒では無い。ただしレンズ交換をした際に利用者自身
が忘れずに焦点距離変更操作をしないとならないのは当然だ。
なお、純正レンズの場合は、ファインダー内に焦点距離が
表示されるが、アダプター使用時は、焦点距離の手動設定を
行ってもファインダー内に設定後の表示が出ない事は不満だ。
(レンズ交換時に焦点距離の設定変更を忘れる事が良くある為)
それと、GX7の記事(本シリーズ第12回)で述べたが、デジタル
テレコン(本機では2倍のみ)を使用しても、手ブレ補正に係わる
焦点距離の設定を2倍に変更する必要は無い(注:GX7では4倍以上
のデジタル拡大が可能だが、その状態ではさすがに手ブレ補正は
不安定だった。この問題があり、その原因が不明だったので、
以前は手ブレ補正の焦点距離も都度、長く設定をしなおして
いたが、厳密な検証により、不安定なのは、超々望遠領域での
手ブレ補正の精度不足に起因する物であり、デジタル拡大機能
使用時の焦点距離再設定は基本的には不要である事がわかった)
「5軸手ブレ補正」は原理的には強力な仕様ではあるが、
マクロレンズ等を使った近接撮影でよく発生する
「被写体に対する前後方向へのブレ」には、勿論対応は
できない、さすがにカメラ(やセンサー)が自動で前後する
ような機構は現時点では搭載できないからだ。
ただし「フォーカスブラケット」という機能により、ピント
位置が異なる画像を連続取得できるが、AFレンズ用の機能で
あり、当然ながらMFレンズではこの機能は使用できない。
実は今回、OM90/2という大型マクロレンズを使用して
いるのは、手ブレ補正の限界性能テストの意味もある、
換算180mmなので、シャッター速度によってはブレ易く、
かつ近接撮影での前後ブレなどが頻繁に発生し、
勿論、手ブレ以上に、風などによる被写体ブレが極めて多数
発生するマクロ(近接)撮影だ。本機の強力な手ブレ補正
機能でも完全にそれらを全てカバーできる訳では勿論無いが、
どこまで近接撮影での課題をサポートしてくれるのか?
それがポイントであった訳だ。
(ちなみに、冒頭に、MZ30/3.5の高倍率マクロレンズを
使ったのも同様の検証の意味がある)
その評価だが、まあ、やはり「近接撮影では、最先端の
手ブレ補正性能でも十分なサポートは出来ない」という
印象である。
それから本記事では使っていないが、200mm以上の焦点距離
の(MF)望遠レンズでは、AUTO ISOのままでは、低速限界
(切り替わり)シャッター速度が低すぎて、優秀な手ブレ
補正でもカバーしきれない程にシャッター速度が低下する。
(注:換算400mm以上となるので、手ブレ補正機能の
精度も足りていないのであろう)
(追記:結局のところ、望遠系レンズでは本機の手ブレ補正
は有効に働いておらず、手ブレ補正が必要となる望遠撮影で
効かないならば殆ど意味が無く、なんだかカタログスペック
上での見かけ倒しのように思えてきている)
加えて、高速機械シャッター時には内部の機械振動も多い。
結果、ブレを誘発する為、こうした場合には、手動ISOと
するが、ISO感度の頻繁な変更操作が発生して面倒だ。
さらに、ISOを高めると連写時の連続撮影枚数の限界値が
下がってしまう弱点があるので、もう滅茶苦茶だ。
望遠レンズでの手ブレのし易さは、本機の本体形状の問題
もあるので、そういう場合は、OM-D E-M1等を使用する方
が若干マシであろう。(E-M1では、高感度時の連写性能
低下も、本機E-M5Ⅱよりも出にくい。本シリーズ第14回
記事参照)
結局、様々な特殊な撮影条件においては、本機の内蔵手ブレ
補正は、その威力を十分に発揮する事は難しい。
ただ勿論、通常撮影においては、AFは勿論、MFレンズでも
本機の高性能手ブレ補正は十分に有効なので、念の為。

ついては2010年代以降の殆どのミラーレス機や一眼レフも
同様に超多機能だ。ただ、初級中級層はもとより、上級者層に
おいても使いこなせない機能もあると思われ、ちょっと過剰な
までの、カタログスペッック優先的な仕様だとも思われる。
エフェクト(アートフィルター)は種類が充実している。
特に「アートフィルターブラケット」は有効な機能で、
設定した多数のエフェクトを1度のシャッター、同一構図で
並列的にかけられ、従来のように掛けるエフェクトの種類を
色々と悩みながら選ぶ必要は無い(ただし、PENTAX機やCANON
機のような画像効果の二重掛けや詳細な露出設定は出来ない)
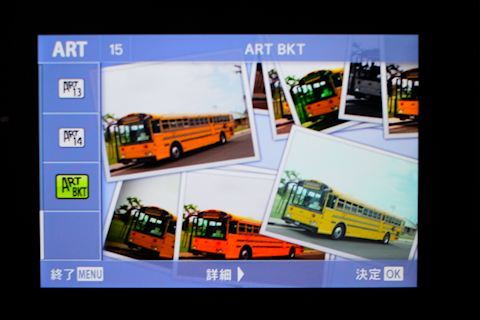
簡便だが、このダイヤルのロック機構は、ON/OFFの設定が
トグル式の機械式構造なのがとても良い。
他社のアナログダイヤルでは、ロックが解除できない状態を
常に強いられてしまう(例、NIKON Df,FUJIFILM X-T1等)
まあ、CANON機のように電子的にロックを行う方法論もあるが
それはデジタルダイヤルにしか効かず、アナログダイヤルの
場合は、本機のやりかたがシンプルかつ遥かに使いやすい。

秒10コマの高速連写機能があげられる。
ただ、これについては、この第四世代のミラーレス機では、
E-M1 MarkⅡ,SONY α9,α7/RⅢ,PANASONIC DC-G9 Pro
などでも搭載されている機能であり、目新しさは無く、
むしろ新機種に比べて、本機の秒コマ数等は見劣りする。
(注:本機以上の連写速度を持つ機種では、電子シャッター
利用であったり、高速連写時の機能制限が生じる場合もある)
しかし、たとえ秒10コマであっても、デジタル一眼レフと
比べればトップクラスの性能であり、ミラー駆動動作が不要な
ミラーレス機の特徴を最大限に活かしていると言えよう。
(注:だが、前述のように高速連写時の機械振動は大きい)
これはフルサイズ化等のセンサーサイズ差でμ4/3機と差別化
しようとしている一眼レフ陣営との競争においては、大きな
武器となっているであろう。
ただし実用上では、秒10コマは、速過ぎる事も多い
(沢山撮りすぎ、後で編集や選別で手間がかかる)のだが、
本機の秒コマ数は、高速、低速ともに自由に設定可能であり、
かつ、静音連写および低振動連写でも秒コマ数設定が可能で、
このあたりの仕様はとても良い。
例えば、連写中にダイヤルで秒コマ数が可変できたら、さらに
良かったとも思う(その機能は他機を含め実現されていない)
なお、高速連写時の最大コマ数は、JPEGで約19コマと
物足りず、これでは高速連写が約2秒で途絶え、その後は
低速化してしまう為、あまり実用的とは言えない。
また、ISO感度を高めると、さらに連続連写コマ数が減り、
ここは重欠点である(NIKON D300でも同様の欠点があった)
他の色々な記事でも書いたが、実用的には概ね8秒間以上の
連続連写性能が欲しい所だ。ちなみに、この時代の前後以降の
他社機では、バッファメモリーの容量増加等で、連続連写性能
を100枚以上確保している。(注:これ以前の旗艦E-M1では
本機以上のバースト性能を持つ=本シリーズ第14回記事)
それと、秒10コマの連写速度は、旗艦E-M1と同じスペック
であるが、両者のシャッター音は明らかに異なり、違う
ユニットなのであろうか? また、E-M1ではISOを高めても
連写性能は落ちない。それから、同一連写速度でもE-M1の
方が僅かに速く感じるのは気のせいか?
バッテリーは良く持つ。一眼レフも含め、2010年代の
高速連写機では1日の撮影枚数が数千枚にも及ぶ事が
良くあるが、本機においても一種の高速連写機であり、
そのレベルの撮影枚数には対応可能だ。
ただ、これは撮影者のスキルにもよる(ライブビューで
長時間画面を見たり、1枚1枚撮影後に再生確認すれば
当然バッテリー消費は速い。ちなみにワンシーンの撮影後に
すぐ電源をOFFする電池消耗防止の習慣がついている為、
前述のMFレンズでのピーキング機能の電源OFFでの解除が
大きな問題になっている)
なお、充電にかかる時間は結構長くなっている。
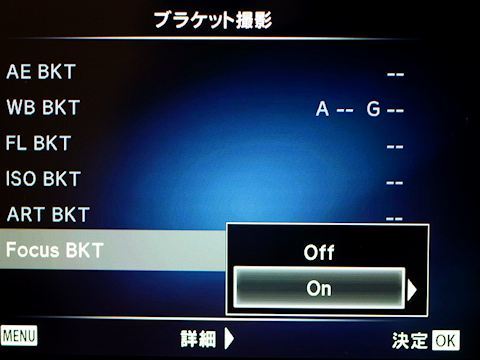
しまうのであるが、スーパーコンパネをカスタマイズできる
程の編集自由度は無い(SONY,PANASONIC,FUJI,PENTAX等
では、それが可能だ)
何故それが必要か?と言えば、増えた新機能(例:フォーカス
ブラケット等)が、メニューの奥深くにある為、速やかに
呼び出したり、細かい設定が出来ない、だから、なんらかの
ショートカット方法が無いとやっていられないのだ。
オリンパス機のスーパーコンパネは旧来、使い易い機能では
あったが、何年たってもそれが進化せず、追加機能ばかりが
増えてしまって、その操作系改善が追いついていない。
それと、フォーカスブラケットと密接な関係のある
「深度合成」機能だが、これを使うには対応レンズを買い、
しかも本機単体では出来ず、外部ソフトを使用する必要がある
という不十分な仕様だ(注:2018年2月のファームェアVer4.0
で、やっと本体内での深度合成が出来るようになった)
また、AFであるが、OM-D E-M1(2013年、本シリーズ第14回)
よりも、本機が後発であるにも係わらず、E-M1にあった
像面位相差AF(DUAL FAST AF)が本機には搭載されておらず、
一般的なコントラストAFのみである。
まあでも、ここは上位機種との「仕様的差別化」であろう。
「カラークリエイター」は色相と彩度が個別に調整でき、
一見有益な機能だが、マルチFnから、これを簡便に呼び出した
として、まず設定可変幅が大きくて、微調整が出来ない。
それと、これを使用すると、それまで手動で設定していた、
ホワイトバランスとピクチャーモード(Vivid等)が解除されて
しまうので、またそれらの設定を手動で戻さなくてはならない。
色相と彩度調整は、これに頼らず、PC上での画像編集が簡便だ。
それから、ISO AUTO時の感度切り替え低速限界シャッター速度
は変更できない。MF望遠レンズ等、レンズの焦点距離に応じて
適正な値を選ぶ為には、この機能は重要なのだが・・
(注:翌年のPEN-Fや、E-M1 MarkⅡでは可能になったが、
1/250秒単速であったり、撮影モードの制限がある模様だ。
OLYMPUSにおけるこの機能は、まだ仕様が練れていない段階だ。
また、同時代のPANA機では、AFレンズではこの値が焦点距離に
応じて自動的に変化するが、アダプター使用時では、低速で
固定となり、手動でも変える事が出来ない)
この問題の回避には、頻繁な手動ISO変更が必須だが、専用の
ISO変更ボタンやISOダイヤルが無く、十字キーへ一旦アサイン
してから前後ダイヤル操作との併用、あるいは1/2機能切換
レバーを変更して前ダイヤルでの操作が必要なので、煩雑だ。
なお、取扱説明書は、肥大化を嫌ったのか?簡易なものであるが、
この程度の内容では多機能を使いこなす為に十分な情報量とは
言えない。例えば「スポット測光」は中央固定となっているが、
これが移動可能か?測距点に連動できるか?などの詳細は
書かれていない。
この状況だと、大半(9割以上)のユーザーは本機の多機能を
使いこなす事は無理であろう。
その他の欠点だが、特に見当たらず、まあ概ね優秀なカメラ
だと言えるであろう。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★★★
【描写力・表現力】★★★☆
【操作性・操作系】★★☆
【アダプター適性】★★☆
【マニアック度 】★★★★★
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★ (中古購入価格:83,000円)
【完成度(当時)】★★★
【仕様老朽化寿命】★★★★☆
【歴史的価値 】★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】3.3点
概ね好評価点だ。
評価点が低かったのは「コスパ」と「操作性・操作系」だ。
コスパは、まあ限定版なので、高価なのはやむを得ない。
その課題を相殺できる要素として「マニアック度」や
「仕様老朽化寿命」の高さを期待して購入したのだ。
「仕様老朽化寿命」が何故高い得点なのか?と言えば、
これはもう「OM-3Tiライク(似ている)」なカメラは
この先、まず出て来ないだろうから、周囲の新製品と比べて
も古くならない事が想定されるからだ。
「操作性・操作系」の弱点は気になるが、それについては、
ミラーレス機全般で、増えすぎた新機能に操作系の整備が
追いついていないのは確かだ。
まあ他社機で、操作系が優秀な機体をいくつか所有しているが
それらはむしろ稀である。
実際の所は本機では
「ピーキング機能のFnボタンアサインが必須」および
「拡大操作系が良く無い」というMF時の弱点が目立つ位で
これらはAF時には問題が無く、重欠点とは言い難い。
だが、この弱点は、MFのオールドレンズを使う際には
大きな課題となりうるので、「アダプター適性」の評価を
少し減点した。
他の項目は概ね平均点、でもまあ、悪くは無いカメラだ。
本機ではAFレンズを主体にするか、あるいは、不便を我慢
しつつMFレンズを使うか?そこは良く考えて使用して
いきたいと思う。
しかし、基本的には「OM-3Ti風のMFレンズ母艦」を
目的に購入したカメラだ、MFでの使用を避ける事はできない、
そこに矛盾があるが、まあ、やむを得ないであろう・・
----
さて、本記事はこのあたりまでで、
次回もまた、第四世代のミラーレス機を紹介しよう。