高いコストパフォーマンスと付随する性能を持った優秀な
写真用交換レンズを、コスパ面からの評価点のBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
なお、本シリーズ第1回記事および第2回(本記事)では、
惜しくもBEST40から漏れた、ランキング番外レンズのうち
どうしても紹介したいレンズを計7本紹介する記事としている。
ランキングについては私が実際に購入し、現在も所有していて、
実写紹介が可能な交換レンズ群およそ360本の中からに限定して
いる。以前所有していたが現在持っていないレンズについては
実写が出来ないという理由で、本シリーズ記事では対象外だ。
また、2018年位から急速に国内市場に流通している、中国製
等の「新鋭海外製レンズ」の多くはコスパに大変優れるが・・
それらは十何本か所有しているものの、本シリーズ記事執筆
時点では評価が間に合っていなかった、後からそれらを
ランキングに飛び入りさせる訳にも行かず、残念ながら
それら新鋭海外製レンズのランクインは見送る事とする。
これら以外にも、勿論優秀なレンズは存在しているだろうが、
市場の全てのレンズの性能を把握する事は当然不可能であるし、
自身でお金を出して購入しないレンズの事をあれこれ評価する
というスタンスは、全く賛同できないので、所有していない
レンズの事は一切評価しない。
まあ私が持っていない、という事は、そもそも「コスパ的に
買うに値しないレンズである」という事と等価であるから、
初級者等が、自分が信奉するブランドのレンズが出て来ない、
と言ったとしても、それはそもそもハイコスパのランキング
には入り得ないレンズであると解釈した方が良いであろう。
そもそも初級者の考える「値段が高いレンズ=良く写るレンズ」
という点が、極めて大きな誤解なのだ。
(だから、本シリーズ記事を書いている)
レンズの価格だけで性能が決まると思っていたら大間違いだ。
まあ、他のWeb等で、そんなようなスタンスが見れるならば、
それは「超ビギナーの書いた評価だ」と簡単にわかってしまう。
さもなければ、市場関係者や投機層が、広告宣伝とか、相場の
吊り上げの為に、過剰なまでの好評価を行っているという事だ。
いずれにしても、そんなトリックに乗せられるのは初級層だけだ。
それから、入手性についても考慮している。このランキングでは
現在入手が困難なレア物のレンズは対象外だ。
その他、評価の基準や定義等は、シリーズ初回記事を参照の事。
---
では、今回もランキング外レンズを順次4本紹介していく。
番外レンズ(4) 約210位相当
![c0032138_17400213.jpg]()
レンズ名:SIGMA Contemporary 100-400mm/f5-6.3
DG OS HSM
レンズ購入価格:68,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)
またしても下位レンズである。
そもそも高価なので、コスパ上位には入り得ないのだが、
まあこれは発売年度が2017年と新しく、発売後すぐに購入
した事もあるかも知れない。後年、より安価に入手できれば
コスパ点はどんどん高くなるレンズだ。
![c0032138_17400263.jpg]()
ただ、評価を行う事にも、スキルや経験や知識が必要だ。
すなわち、近年では、超望遠ズームは皆150~600mmとかの
やや過剰な焦点距離で、かつ重量も2~3kgに達していた中で、
初めてビギナー層にも扱える重さ(1150g)の超望遠ズーム
が発売されたのだ。まあ、およそ20年前の2000年前後では
もっと軽量又は同等の400mm級超望遠ズームはMINOLTA,
TOKINA,TAMRONからの3本が存在していたのだが、最近カメラ
を始めたビギナー層は、そんな昔の歴史の事は、まるで知らない。
だからまあ「軽くて良く写る超望遠ズームが出た」と騒いで
いるのかも知れないが、軽い、という事はさておき、良く写る、
というのも、いったい何と比較して言っているのか良く分からない。
ビギナーは絶対的判断基準を持たないし、評価が出来たとしても
他の物と比較する相対判断であるから、基本的には、言っている
事の大半は「思い込み」に過ぎず、殆どあてにならない。
よくもまあ、通販サイト等でのビギナー層の評価コメントを信用
して買う人が居る事が不思議でならない、もしそれが大ハズレの
評価であったら、購入した商品が完全に無駄になってしまう。
ちなみに、本レンズの「描写表現力」の私の評価点は、5点満点
中の4点であり、この評価点は、所有レンズ延べ約360本中、
約50~120位程度の範囲に留まる。つまり、もっと描写力が高い
レンズは、私が所有している範疇でも50本以上ある訳だ。
![c0032138_17400259.jpg]()
現代風のレンズによくある「輪郭がやや強い」印象なので
その点では注意が必要だ。
「注意」というのは、大画素で撮った写真を小画素に縮小処理を
行う場合、そのソフトウェア(編集ソフトやブラウザ等)や
アプリ等での縮小の方式(アルゴリズムと言う、Lanczos3法や
バイキュービック法が一般的)によっては、縮小時にその輪郭が
強く残り、縮小すればするほどパキパキの固い印象の画像になる。
(これは専門的には、”縮小効果”と呼ばれる)
したがって、対策としては、写真の用途として必要な画素数
(例、ポスターや写真展などの大伸ばし用、小型印刷物用、
WEB閲覧用など)に応じて、画素数を必要以上に上げずに撮り、
編集や掲載における縮小処理をできるだけしないか、少ない範囲
に留めるように意識する。または自身による編集作業時に、
輪郭を残す編集パラメータを調整する等をして、目視で適切な
シャープネスを決定する。
カメラ内部にも輪郭調整パラメーター(またはシャープネス)
がある場合が殆どなので、必要に応じてそれも調整する。
ただし、カメラ内部のパラメーターによる調整でも、機種毎に
その画像処理エンジンによるアルゴリズムの差(種類)があったり、
あるいはパラメーターの決め方が異なる為、これも必要に応じて
自身の使用カメラで予め縮小時や撮影時の輪郭処理傾向を掴んで
おく。
パラメーターの決め方の差というのは、たとえばシャープネスの
設定があったとして、それが-2,-1,0,+1,+2の5段階だったとする。
その際、0に調整したら、常に「無処理」であるから安心なのか?
と言えば、どうもそうでも無い模様だ。
カメラの機種によっては、-2に相当する値がゼロの無処理となり、
そこからどんどんと輪郭処理が強くなる。
したがって、±0に調整したつもりでも、既にこれは3段階目の
強さだったりする訳だ。
このあたり、実際の各機種での内部処理手法は公開されておらず
仕様表にも勿論乗っていない。高度な検証作業が必要であるが、
輪郭を気にするならば、このあたりを確認しつつ、調整してみる
のも良いだろう。
それから、カメラのセンサーの画素ピッチとレンズの解像力
との関連、さらにはローパスフィルターの有無なども、この
問題に大きく関連するが、専門的かつ難解になりすぎる為、
その影響については割愛するが、ごく簡単には後述する。
![c0032138_17400235.jpg]()
「超高画素対応」だからだ。
昔の銀塩35mm判フィルムは、アナログではあるが、これの解像度
はデジタルに換算すると、およそ2000万画素相当であると言われて
いる。これの具体的な検証は、アナログとデジタルの概念が全く
異なるので出来ないのだが、その説を信じる場合、これは
約5400x3600ピクセルとなる。
35mm判フィルムのサイズは、36mmx24mmなので、
これは、ピクセルピッチが約1/150mmつまり、0.0066mmで
まあ、約7μm(マイクロメートル、旧ミクロン)という事だ。
銀塩時代の交換レンズの解像力もだいたいこのフィルムの
解像度を基準に設計されていた。
1/150mmの解像力が必要という場合、レンズの解像力テストでは、
白と黒の線のペア(ラインペア)が、分離して見えるか?を
チェクする。つまり1mmあたり150本の解像度の場合、その半分
の75ラインペア(/mm) (LP/mm)のレンズ解像力が必要だという
事になる。
銀塩時代のレンズを解像度チャートを撮影して実測した場合
(これは比較的簡単に自分で出来る)まずレンズの種類により
ずいぶんと異なり、一般にズームよりも単焦点レンズが優れる。
さらには絞り値の設定でも大きく変化する事が良くわかると思う。
通常、開放では甘く、絞り込むと解像力は向上し、レンズによって
はF5.6ないしF8程度でピークに達し、それ以上は向上しない。
さらに絞り込み過ぎると、むしろ解像力は劣化する。
(これは、デジタルでは回折現象(小絞りボケ)も影響する)
なお、同メーカーの同一焦点距離のレンズでは、小口径レンズの
方が開放付近での解像力が高い事が多いのは面白い傾向だ。
つまり、撮影条件によっては、安いレンズの方が良く写った、
という事になる。(=口径比が大きくなると、様々な収差が
急激に増大する事が主な理由だ)
性能の低い銀塩用レンズでは、その解像力は60~100LP/mm程度、
高性能のレンズでも、最良時で180LP/mmを超えるものは稀で
あろう。
で、銀塩時代はこれで良かったのだが、近年、35mm判フィルム
の換算画素数の2000万画素を超えるデジタルカメラが多く発売
されている。
たとえば5000万画素のカメラがあったとする、
これは約8700x5800ピクセルとなり、画素ピッチは約4.2μm
必要なレンズ解像力は1/240mm、つまり120LP/mmだ。
これだと、銀塩時代のレンズを使うのは、低性能な物だと
解像力が不足してしまう。(注:いずれも最良の値、
一般的には、画面周辺になると解像力は低下する)
この為、近年のレンズは、解像力を従来のものより大幅に
アップしている、けど、それが輪郭が強いという副作用を発して
しまうのだと思われる(注:カメラのセンサー仕様にも依存する)
なお、ここまでの計算はフルサイズ(35mm判)で行っている、
センサーのサイズが小さい場合、さらにこの計算は厳しいものに
なるのは容易に想像つくであろう。特に、センサーサイズが
極めて小さい携帯・スマホ系カメラの場合、画素数を上げると
物凄い高解像力のレンズ使用が必須となる、しかし当然そこまで
の高性能なものは、技術的にも、コスト的にも、大きさ的にも、
携帯等には搭載できない。だから画素数が高い意味が殆ど無い、
という現状にも気がつくであろう。
![c0032138_17400105.jpg]()
カテゴリー名は「コンテンポラリー」だ。
その名の意味の通り「現代的」なレンズであるが、現代的な
技術の進歩という事が、全ての面において歓迎できる物でも無い。
新しい技術やその内容を理解し、その長所を活かし、短所を回避
して使いこなす事が非常に重要だ。
なお、2017年にはTAMRONからも、本レンズとほぼ同等のスペック
の軽量レンズ 100-400mm/f4.5-6.3(A035)が発売された。
こちらも所有しているが、ほぼ同等の性能なので、一般的には、
どちらかを所有しておけば十分であろう(注:SIGMA製が、やや
操作性に優れている)
---
番外レンズ(5) 約150位相当
![c0032138_17402017.jpg]()
レンズ名:SONY E16mm/f2.8 (SEL16F28)
レンズ購入価格:7,000円相当(中古)
使用カメラ: SONY NEX-7(APS-C機)
SONYの最初期のミラーレス機、「NEX-3/5」のキットレンズ
であり、2010年の発売だ。
現代のα7/9系Eマウントミラーレスはフルサイズセンサーだが
NEXの時代、あるいは現代のα5000系/α6000系ミラーレス
機は同じEマウントでもAPS-CサイズCMOSを採用している。
型番にEと名前が付くSONYレンズはAPS-C専用であり、フルサイズ
のα(FE)機で使用する場合は、自動又は手動で、APS-Cモード
として使う。
![c0032138_17402061.jpg]()
こんなレンズをキットにして大丈夫か(使えるのか?)という
疑問が、発売当初にはあった事であろう。
初期NEXのターゲットユーザーは不明瞭だった模様だ。
つまり当時は、ミラーレスの市場はまだ始まったばかりであり、
誰が買うのか良くわからなかった時代だった。
まあでも、例えばNEX-3とのセット(NEX-3A)の発売時の実勢
価格(注:定価はオープンだ)は、65,000円前後であり、
この価格帯だとビギナー層が対象であろう。
銀塩時代には、28mm単焦点を搭載したコンパクト機、例えば
NIKON MINI,RICOH GR1,MINOLTA TC-1等はベテランかマニア
層向けと呼ばれていた、つまり、「広角だけのカメラは初級中級者
には使いこなしが困難である」という意味だ。
だが、NEX-3Aは24mm(超)広角単焦点、昔とは時代が違うとは
言え、ビギナーが簡単に使いこなせる画角ではないであろう。
なので、NEX-3/5(以降のNEXやαも同じ)には、デジタルズーム
機能が搭載されている、これを用いると最大10倍の拡大ができる。
つまり、換算24mmの広角から換算240mmの望遠域までを
本レンズ1本で使える訳だ。
ビギナー層に対しては、これで「(光学)ズームが無い」という
問題点や不満への対策となる。
ただし、SONYのプレシジョン・デジタルズームは画質無劣化の
方式では無いので、4倍あたりから上は画質劣化が甚だしく、
実用的には厳しい状況となる。(この為、後年のSONY機には、
10倍迄もの過剰なデジタルズーム範囲は搭載されていない)
また、電源OFFで必ず拡大無しの状態にリセットされてしまい、
やや使い難い。
このような広角レンズをキットレンズとしたのは、その当時
(2010年頃)のミラーレス機のAF技術にも関係がある。
例えば、OLYMPUSはE-P1のキットレンズを17mm/f2.8とし、
PANASONICもDMC-GF2のキットレンズをG14mm/f2.5とした。
すなわちこの時代のAFは各社ともコントラスト検出式AFであり、
これは一眼レフの位相差検出方式に比べて、精度も速度も低い。
これらの(超)広角レンズであれば、基本的に被写界深度が深い
為、ピント精度が若干向上する(=AFを外し難い)またレンズを
小型化する事で、AFモーターの駆動の負担を減らし、合焦速度も
若干向上すると思う。
つまり、AFの技術的限界から、これらの小型(超)広角レンズを
キットレンズとせざるを得ない時代であったのだ。
本レンズE16/2.8の時代背景はそんな感じだ。
描写力も実のところたいした事は無い、けど、不満という点は
無いので、広角撮影が必要な際、たとえば舞台系の全体撮影とか
人物集合写真等で非常に役にたったレンズである。
まあ、あまり絞らなくても、ある程度深い被写界深度が得られる
という事だ。
![c0032138_17402169.jpg]()
αは、元々1985年のミノルタの初号機から、2000年代にSONYに
引き継いだAF一眼レフのブランド(シリーズ)名称であったが、
2013年、一眼とミラーレスを統合したシリーズ名となった。
で、その2013年からα(E)はフルサイズ機が主力となった為、
現代においては、APS-C専用レンズ(FEではなく、E名称)の
レンズは比較的中古相場が安価である。
本レンズE16/2.8も1万円程度の安価な相場で豊富な中古流通の
玉数があり、買いやすい。
なお、フルサイズ用レンズでなくては(自分のα7等に)使えない、
と思っている初級ユーザーもいるかもしれないが、
α7系の「APS-Cサイズ撮影」設定を、「AUTO」又は「入り」に
しておくとレンズ装着時に何の違和感も無く使用できる。
(注:EVFはクロップされずフル画面で見られる。なお、記録
画素数が大幅に減るので、用途によってはその点だけ注意だ)
![c0032138_17402057.jpg]()
無い、まあ、ボデイとのセットで中古購入価格は安価であったが
コスパ点をあまり高く評価していないのは「そこそこ写る普通の
レンズ」と言う枠から出ていないからだ。
まあでも、α(E)ユーザーであれば、持っていて損は無いレンズ
ではあるとは思う。
----
番外レンズ(6) 約170位相当
![c0032138_17403394.jpg]()
レンズ名:LENSBABY MUSE Double Glass Optic
レンズ購入価格:8,000円相当(新品+中古)
使用カメラ:SONY NEX-3 (APS-C機)
LENSBABYのティルト型レンズは、3GやMUSE等、過去記事で
何度も紹介している。
![c0032138_17403348.jpg]()
一般撮影(風景や人物等)には勿論全く向かない。
使いこなしも難しい。ビギナー層では、原理や操作性の面で
「偶然」以外ではティルトレンズをコントロールする事は出来ず、
また中上級者層であっても、ティルトの原理は知っていたとしても
その効果を想像しながらの作画が困難である(つまり、どう
写るかわからない、あるいは逆に、こう写したいという考えが
あっても、その通りには上手く撮れない)
すなわち、誰もがどうやっても、使うのが難しいレンズである。
そういう意味では、コスパはともかく、マニアック度が極めて
高いレンズになるであろう。
しかし、エンジョイ度が高いかどうかは、ユーザーのスキルに
よりけりだ、本レンズの難しい「操作性」や「作画意図」に
おいて、それを楽しいと思って撮れるかどうかがポイントになる。
一般的には「こんなに撮るのが難しくて、しかもどう写るか
良くわからないレンズなんて、楽しめないよ!」と思っても
不思議では無いであろう。
だから、そういう難しいものを使いこなそうとする事に楽しさを
感じる事ができるかどうか?が、まず本レンズを使う為の条件と
なってくる、すなわちかなりのマニアックなレンズという訳だ。
(特に、「テクニカル・マニア」向けである)
![c0032138_17403377.jpg]()
MUSEのDouble Glass Opticでは、F5.6前後の絞りプレート
(付属品、磁力交換式)を装着する事で、トイレンズよりも
むしろ実用レンズに近い高い描写力(画質)を得る事ができる。
ただ、高画質である事が本レンズの使用目的に合うかどうかは
微妙だ。・・という事で、MUSEでは、より写りが「ユルい」
つまりトイレンズの写りに近い「プラスチック・オプテック」と
いった光学系(レンズ)に交換する事ができる。
ただ、私の感覚では「プラスチック・オプテック」を使った
ケースでは、ちょっと「ユルすぎて」好みに合わない。
さらにMUSEには「ピンホール&ゾーンプレート」が存在するが、
これらもさらにボケボケの写りで、撮影用途を選ぶのが大変だ。
(レンズマニアックス第1回、第4回記事参照)
なので、写りの良い Double Glass Opticや3Gを持ち出す事が
多くなっている。
カメラ母艦に常にNEX-3を使用しているのは、このボディ形状が、
MUSEや3Gを手持ちで使うのに適しているからだ。
ただこのあたりは、利用者の手の大きさや形により、使い易さ
は変わってくるかも知れない。
本来こうしたトイレンズ系の場合、エフェクトを組み合せる
のが表現力の増強目的では望ましいが、残念ながらNEX-3には、
殆どエフェクトが搭載されていない。
この為、後期NEX/αのAPS-C機を「Eマウント・トイレンズ母艦」
として使うのが望ましいと思い、代替機を狙っていたが、
なかなか適正な候補機種が見当たらなかった。
(追記:現在ではα6000を入手し、この用途にあてている)
それと、フルサイズ機α7が「オールドレンズでゴーストの頻発」
という重欠点を抱えていて、オールドレンズ母艦としての目的には
適さないので、これを使い潰した後(減価償却完了後)トイレンズ
母艦用に格下げにしようかとも思っている。
まあその為には、次期フルサイズ・オールドレンズ母艦が必要と
なるが、その後のα7/9系列は高付加価値型商品となってしまい、
今のところ、その目的に合致して適価で買える機種が出てきて
おらず、なかなか苦しい所だ。
![c0032138_17403366.jpg]()
おまけに、一般的な写真撮影における必要度もゼロに近い。
そして、旧機種の中古や在庫処分を狙えば適正な価格帯にはなるが、
新品購入では後継機(コンポーザーPRO等)は、かなり高価だ。
まあ、というわけで、コスパの観点からも「名玉」にはランクイン
は元々無理なレンズではあるが、特殊レンズとしての存在感は高く
マニアック度も高いので、今回紹介に至った次第だ。
---
さて、次は「プロローグ編」のラストのレンズである。
番外レンズ(7) 約170位相当
![c0032138_17404653.jpg]()
レンズ名:TAMRON SP 85mm/f1.8 Di VC USD (Model F016)
レンズ購入価格:70,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)
2016年発売の大口径中望遠単焦点レンズ。焦点距離から言って
ポートレート用途が適正であろうが、私はライブや舞台撮影
での中距離人物撮影に、よく本レンズを使っている。
![c0032138_17404689.jpg]()
本レンズを購入したからであり、時代が下がれば、もう少し
本レンズの中古相場は下がり、コスパ点も上がるであろう。
・・と言うのも、初級中級層にとっては85mmレンズはF1.4が
王道であり、F1.8というだけで人気薄になってしまうからだ。
私は銀塩時代から多数の85mmレンズを所有している。ある意味
85mmマニアでると言っても過言では無い。そうして購入した
85mmの中には、F1.4版も当然いくつも混じっている、けど
それらが、いつでも写りが良いかどうかは、ちょっと疑問なのだ。
開放F値を1.8ないし2に抑えた設計の物の方が良く写るケースも
多々あったし、そもそも、F1.4版で最短撮影距離付近(1m前後)
の撮影を絞り開放近くで行った場合、被写界深度が1cm程度と
極めて浅く、おまけにそれが人物であったり草花等であった場合、
被写体のブレ(動き)が生じて、浅い被写界深度では間違いなく
ピントを外してしまう。そのピント歩留まり(成功率)は、
経験上10%以下、つまり10枚に9枚は失敗してしまうのだ。
これは、AFでもMFでも同様である、こちら側(カメラ)の精度
の問題も大きいが、それのみならず被写体側の問題もあるからだ。
さらに言えば、F1.4版はボケ質破綻が頻繁に発生するレンズも
多く、F1.8版より慎重に、その回避技法を用いる必要もある。
(すなわち、成功率がさらに悪化し、ボケ質破綻回避の為の
無駄打ちを行わざるを得ず、レンズによっては、歩留まりは
1%程度にまで低下する)
結局、85mm/f1.4は必然的にあまり持ち出さないレンズと
なってしまう、失敗する事が明白だから、重要な撮影には
使えないのだ。
けど、大口径中望遠(70~120mm前後の焦点距離)は様々な
撮影シーンにおいて必要だ。
この為、私はこの目的では、たとえばMFレンズであれば、
CONTAX Planar 100mm/f2や、OLYMPUS OM 100mm/f2
PENTAX 120mm/f2.8、LAOWA 105mm/f2等を良く使い。
AFでは、NIKON DC105mm/f2,同AiAF85mm/f1.8 、
PENTAX FA77/1.8Limited等を使う場合が多かった。
あるいは、AFの90mmないし105mmマクロをこの目的に
充てる事もあった。
これらはそれぞれ、ミラーレス・マニアックスやハイコスパの
シリーズ記事で紹介しており、「良く出来たレンズ」として
実用性能の高さや必要度の高さを誇っている。
AFレンズで最も良く使用したのは、NIKON AiAF85mm/f1.8と
PENTAX FA77/1.8Limitedであったと思う。
人物撮影や屋内撮影、ライブ等イベント撮影まで汎用性が
極めて高く、長年にわたって重宝してきたレンズである。
しかし、AiAF85/1.8はもとよりFA77/1.8も古い時代のレンズだ、
およそ20年近くも使っていれば、近年の最新レンズに比べて
どうしても各種性能(解像力や、AF性能、手ブレ補正等)が
見劣りしてしまう。
最新レンズでFA77/1.8等の代替となるレンズをずっと探して
いたが、なかなかそれが存在しないし、新発売もされない。
なにせFA77/1.8はミラーレス・マニアックス名玉編で堂々の
第1位に輝いた栄光のレンズだ、それを超えるものなど、
そう簡単に出てくる筈も無い。
近年になって、TAMRONから本レンズSP85/1.8が発売された、
「このレンズならば、もしかして・・」
という期待を込めての購入となった次第である。
![c0032138_17404614.jpg]()
描写力的な不満は感じられない、解像感も高いが、他の近代レンズ
のようにカリカリな輪郭ではなく、人物撮影によくマッチするように
設計されている、ボケ質も良く、ボケ質破綻も気にならない。
F1.8ということで、F1.4級に比べて初級中級者が着目しない分、
マニアック度も高い。
やや重量級で持ち出しが不便ではあるが、まあ重欠点と呼べる程
のものではなく、実使用上でのエンジョイも高い。
注意点は1点だけ、NIKON用でも電磁絞り採用(E型と等価)の
レンズであり、ニコン機以外での(マウントアダプター等)使用が
困難(ほぼ不可能)な事だ、が、ここも重欠点とは言えない。
まあすなわち、殆どの項目で高得点であるレンズだ。
・・ただ、やはり値段が高かった(汗)
コスパ点は、一応最小限の減点として、2.5点としたが
それ以上与えるのは無理だ。年月が経て中古相場がさらに下がった
としても、コスパは3点から3.5点が限界であろう。
という事で、総合平均4.0以上が主に対象となる本シリーズ記事
ではコスパ面を主因としてランクインできないレンズである。
![c0032138_17404501.jpg]()
FA77/1.8の代替となりうる高性能レンズである事は確かだ。
ちなみに、本シリーズ記事では、FA77/1.8は1位になれない事は
確定している。何故ならばそのレンズも高価であり、コスパ点が
3点止まりであるからだ。
ただ、他の項目の評価点が高いので、ランキングの中位くらい
には入ってくるとは思われる。
----
さて、「プロローグ編」での、ランキング外レンズの7本の
紹介はこのあたりまでで、次回第3回記事では、「本編」として
ランキングレンズを下位より順次紹介していこう。
写真用交換レンズを、コスパ面からの評価点のBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
なお、本シリーズ第1回記事および第2回(本記事)では、
惜しくもBEST40から漏れた、ランキング番外レンズのうち
どうしても紹介したいレンズを計7本紹介する記事としている。
ランキングについては私が実際に購入し、現在も所有していて、
実写紹介が可能な交換レンズ群およそ360本の中からに限定して
いる。以前所有していたが現在持っていないレンズについては
実写が出来ないという理由で、本シリーズ記事では対象外だ。
また、2018年位から急速に国内市場に流通している、中国製
等の「新鋭海外製レンズ」の多くはコスパに大変優れるが・・
それらは十何本か所有しているものの、本シリーズ記事執筆
時点では評価が間に合っていなかった、後からそれらを
ランキングに飛び入りさせる訳にも行かず、残念ながら
それら新鋭海外製レンズのランクインは見送る事とする。
これら以外にも、勿論優秀なレンズは存在しているだろうが、
市場の全てのレンズの性能を把握する事は当然不可能であるし、
自身でお金を出して購入しないレンズの事をあれこれ評価する
というスタンスは、全く賛同できないので、所有していない
レンズの事は一切評価しない。
まあ私が持っていない、という事は、そもそも「コスパ的に
買うに値しないレンズである」という事と等価であるから、
初級者等が、自分が信奉するブランドのレンズが出て来ない、
と言ったとしても、それはそもそもハイコスパのランキング
には入り得ないレンズであると解釈した方が良いであろう。
そもそも初級者の考える「値段が高いレンズ=良く写るレンズ」
という点が、極めて大きな誤解なのだ。
(だから、本シリーズ記事を書いている)
レンズの価格だけで性能が決まると思っていたら大間違いだ。
まあ、他のWeb等で、そんなようなスタンスが見れるならば、
それは「超ビギナーの書いた評価だ」と簡単にわかってしまう。
さもなければ、市場関係者や投機層が、広告宣伝とか、相場の
吊り上げの為に、過剰なまでの好評価を行っているという事だ。
いずれにしても、そんなトリックに乗せられるのは初級層だけだ。
それから、入手性についても考慮している。このランキングでは
現在入手が困難なレア物のレンズは対象外だ。
その他、評価の基準や定義等は、シリーズ初回記事を参照の事。
---
では、今回もランキング外レンズを順次4本紹介していく。
番外レンズ(4) 約210位相当

レンズ名:SIGMA Contemporary 100-400mm/f5-6.3
DG OS HSM
レンズ購入価格:68,000円(中古)
使用カメラ:CANON EOS 7D MarkⅡ(APS-C機)
またしても下位レンズである。
そもそも高価なので、コスパ上位には入り得ないのだが、
まあこれは発売年度が2017年と新しく、発売後すぐに購入
した事もあるかも知れない。後年、より安価に入手できれば
コスパ点はどんどん高くなるレンズだ。

ただ、評価を行う事にも、スキルや経験や知識が必要だ。
すなわち、近年では、超望遠ズームは皆150~600mmとかの
やや過剰な焦点距離で、かつ重量も2~3kgに達していた中で、
初めてビギナー層にも扱える重さ(1150g)の超望遠ズーム
が発売されたのだ。まあ、およそ20年前の2000年前後では
もっと軽量又は同等の400mm級超望遠ズームはMINOLTA,
TOKINA,TAMRONからの3本が存在していたのだが、最近カメラ
を始めたビギナー層は、そんな昔の歴史の事は、まるで知らない。
だからまあ「軽くて良く写る超望遠ズームが出た」と騒いで
いるのかも知れないが、軽い、という事はさておき、良く写る、
というのも、いったい何と比較して言っているのか良く分からない。
ビギナーは絶対的判断基準を持たないし、評価が出来たとしても
他の物と比較する相対判断であるから、基本的には、言っている
事の大半は「思い込み」に過ぎず、殆どあてにならない。
よくもまあ、通販サイト等でのビギナー層の評価コメントを信用
して買う人が居る事が不思議でならない、もしそれが大ハズレの
評価であったら、購入した商品が完全に無駄になってしまう。
ちなみに、本レンズの「描写表現力」の私の評価点は、5点満点
中の4点であり、この評価点は、所有レンズ延べ約360本中、
約50~120位程度の範囲に留まる。つまり、もっと描写力が高い
レンズは、私が所有している範疇でも50本以上ある訳だ。

現代風のレンズによくある「輪郭がやや強い」印象なので
その点では注意が必要だ。
「注意」というのは、大画素で撮った写真を小画素に縮小処理を
行う場合、そのソフトウェア(編集ソフトやブラウザ等)や
アプリ等での縮小の方式(アルゴリズムと言う、Lanczos3法や
バイキュービック法が一般的)によっては、縮小時にその輪郭が
強く残り、縮小すればするほどパキパキの固い印象の画像になる。
(これは専門的には、”縮小効果”と呼ばれる)
したがって、対策としては、写真の用途として必要な画素数
(例、ポスターや写真展などの大伸ばし用、小型印刷物用、
WEB閲覧用など)に応じて、画素数を必要以上に上げずに撮り、
編集や掲載における縮小処理をできるだけしないか、少ない範囲
に留めるように意識する。または自身による編集作業時に、
輪郭を残す編集パラメータを調整する等をして、目視で適切な
シャープネスを決定する。
カメラ内部にも輪郭調整パラメーター(またはシャープネス)
がある場合が殆どなので、必要に応じてそれも調整する。
ただし、カメラ内部のパラメーターによる調整でも、機種毎に
その画像処理エンジンによるアルゴリズムの差(種類)があったり、
あるいはパラメーターの決め方が異なる為、これも必要に応じて
自身の使用カメラで予め縮小時や撮影時の輪郭処理傾向を掴んで
おく。
パラメーターの決め方の差というのは、たとえばシャープネスの
設定があったとして、それが-2,-1,0,+1,+2の5段階だったとする。
その際、0に調整したら、常に「無処理」であるから安心なのか?
と言えば、どうもそうでも無い模様だ。
カメラの機種によっては、-2に相当する値がゼロの無処理となり、
そこからどんどんと輪郭処理が強くなる。
したがって、±0に調整したつもりでも、既にこれは3段階目の
強さだったりする訳だ。
このあたり、実際の各機種での内部処理手法は公開されておらず
仕様表にも勿論乗っていない。高度な検証作業が必要であるが、
輪郭を気にするならば、このあたりを確認しつつ、調整してみる
のも良いだろう。
それから、カメラのセンサーの画素ピッチとレンズの解像力
との関連、さらにはローパスフィルターの有無なども、この
問題に大きく関連するが、専門的かつ難解になりすぎる為、
その影響については割愛するが、ごく簡単には後述する。

「超高画素対応」だからだ。
昔の銀塩35mm判フィルムは、アナログではあるが、これの解像度
はデジタルに換算すると、およそ2000万画素相当であると言われて
いる。これの具体的な検証は、アナログとデジタルの概念が全く
異なるので出来ないのだが、その説を信じる場合、これは
約5400x3600ピクセルとなる。
35mm判フィルムのサイズは、36mmx24mmなので、
これは、ピクセルピッチが約1/150mmつまり、0.0066mmで
まあ、約7μm(マイクロメートル、旧ミクロン)という事だ。
銀塩時代の交換レンズの解像力もだいたいこのフィルムの
解像度を基準に設計されていた。
1/150mmの解像力が必要という場合、レンズの解像力テストでは、
白と黒の線のペア(ラインペア)が、分離して見えるか?を
チェクする。つまり1mmあたり150本の解像度の場合、その半分
の75ラインペア(/mm) (LP/mm)のレンズ解像力が必要だという
事になる。
銀塩時代のレンズを解像度チャートを撮影して実測した場合
(これは比較的簡単に自分で出来る)まずレンズの種類により
ずいぶんと異なり、一般にズームよりも単焦点レンズが優れる。
さらには絞り値の設定でも大きく変化する事が良くわかると思う。
通常、開放では甘く、絞り込むと解像力は向上し、レンズによって
はF5.6ないしF8程度でピークに達し、それ以上は向上しない。
さらに絞り込み過ぎると、むしろ解像力は劣化する。
(これは、デジタルでは回折現象(小絞りボケ)も影響する)
なお、同メーカーの同一焦点距離のレンズでは、小口径レンズの
方が開放付近での解像力が高い事が多いのは面白い傾向だ。
つまり、撮影条件によっては、安いレンズの方が良く写った、
という事になる。(=口径比が大きくなると、様々な収差が
急激に増大する事が主な理由だ)
性能の低い銀塩用レンズでは、その解像力は60~100LP/mm程度、
高性能のレンズでも、最良時で180LP/mmを超えるものは稀で
あろう。
で、銀塩時代はこれで良かったのだが、近年、35mm判フィルム
の換算画素数の2000万画素を超えるデジタルカメラが多く発売
されている。
たとえば5000万画素のカメラがあったとする、
これは約8700x5800ピクセルとなり、画素ピッチは約4.2μm
必要なレンズ解像力は1/240mm、つまり120LP/mmだ。
これだと、銀塩時代のレンズを使うのは、低性能な物だと
解像力が不足してしまう。(注:いずれも最良の値、
一般的には、画面周辺になると解像力は低下する)
この為、近年のレンズは、解像力を従来のものより大幅に
アップしている、けど、それが輪郭が強いという副作用を発して
しまうのだと思われる(注:カメラのセンサー仕様にも依存する)
なお、ここまでの計算はフルサイズ(35mm判)で行っている、
センサーのサイズが小さい場合、さらにこの計算は厳しいものに
なるのは容易に想像つくであろう。特に、センサーサイズが
極めて小さい携帯・スマホ系カメラの場合、画素数を上げると
物凄い高解像力のレンズ使用が必須となる、しかし当然そこまで
の高性能なものは、技術的にも、コスト的にも、大きさ的にも、
携帯等には搭載できない。だから画素数が高い意味が殆ど無い、
という現状にも気がつくであろう。

カテゴリー名は「コンテンポラリー」だ。
その名の意味の通り「現代的」なレンズであるが、現代的な
技術の進歩という事が、全ての面において歓迎できる物でも無い。
新しい技術やその内容を理解し、その長所を活かし、短所を回避
して使いこなす事が非常に重要だ。
なお、2017年にはTAMRONからも、本レンズとほぼ同等のスペック
の軽量レンズ 100-400mm/f4.5-6.3(A035)が発売された。
こちらも所有しているが、ほぼ同等の性能なので、一般的には、
どちらかを所有しておけば十分であろう(注:SIGMA製が、やや
操作性に優れている)
---
番外レンズ(5) 約150位相当

レンズ名:SONY E16mm/f2.8 (SEL16F28)
レンズ購入価格:7,000円相当(中古)
使用カメラ: SONY NEX-7(APS-C機)
SONYの最初期のミラーレス機、「NEX-3/5」のキットレンズ
であり、2010年の発売だ。
現代のα7/9系Eマウントミラーレスはフルサイズセンサーだが
NEXの時代、あるいは現代のα5000系/α6000系ミラーレス
機は同じEマウントでもAPS-CサイズCMOSを採用している。
型番にEと名前が付くSONYレンズはAPS-C専用であり、フルサイズ
のα(FE)機で使用する場合は、自動又は手動で、APS-Cモード
として使う。
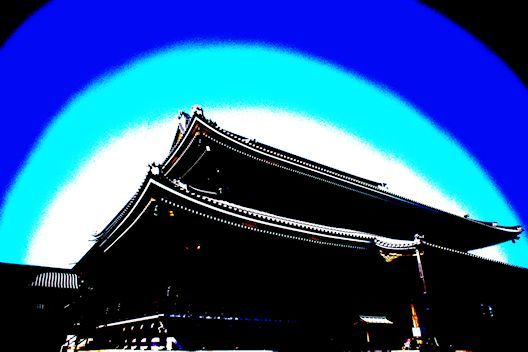
こんなレンズをキットにして大丈夫か(使えるのか?)という
疑問が、発売当初にはあった事であろう。
初期NEXのターゲットユーザーは不明瞭だった模様だ。
つまり当時は、ミラーレスの市場はまだ始まったばかりであり、
誰が買うのか良くわからなかった時代だった。
まあでも、例えばNEX-3とのセット(NEX-3A)の発売時の実勢
価格(注:定価はオープンだ)は、65,000円前後であり、
この価格帯だとビギナー層が対象であろう。
銀塩時代には、28mm単焦点を搭載したコンパクト機、例えば
NIKON MINI,RICOH GR1,MINOLTA TC-1等はベテランかマニア
層向けと呼ばれていた、つまり、「広角だけのカメラは初級中級者
には使いこなしが困難である」という意味だ。
だが、NEX-3Aは24mm(超)広角単焦点、昔とは時代が違うとは
言え、ビギナーが簡単に使いこなせる画角ではないであろう。
なので、NEX-3/5(以降のNEXやαも同じ)には、デジタルズーム
機能が搭載されている、これを用いると最大10倍の拡大ができる。
つまり、換算24mmの広角から換算240mmの望遠域までを
本レンズ1本で使える訳だ。
ビギナー層に対しては、これで「(光学)ズームが無い」という
問題点や不満への対策となる。
ただし、SONYのプレシジョン・デジタルズームは画質無劣化の
方式では無いので、4倍あたりから上は画質劣化が甚だしく、
実用的には厳しい状況となる。(この為、後年のSONY機には、
10倍迄もの過剰なデジタルズーム範囲は搭載されていない)
また、電源OFFで必ず拡大無しの状態にリセットされてしまい、
やや使い難い。
このような広角レンズをキットレンズとしたのは、その当時
(2010年頃)のミラーレス機のAF技術にも関係がある。
例えば、OLYMPUSはE-P1のキットレンズを17mm/f2.8とし、
PANASONICもDMC-GF2のキットレンズをG14mm/f2.5とした。
すなわちこの時代のAFは各社ともコントラスト検出式AFであり、
これは一眼レフの位相差検出方式に比べて、精度も速度も低い。
これらの(超)広角レンズであれば、基本的に被写界深度が深い
為、ピント精度が若干向上する(=AFを外し難い)またレンズを
小型化する事で、AFモーターの駆動の負担を減らし、合焦速度も
若干向上すると思う。
つまり、AFの技術的限界から、これらの小型(超)広角レンズを
キットレンズとせざるを得ない時代であったのだ。
本レンズE16/2.8の時代背景はそんな感じだ。
描写力も実のところたいした事は無い、けど、不満という点は
無いので、広角撮影が必要な際、たとえば舞台系の全体撮影とか
人物集合写真等で非常に役にたったレンズである。
まあ、あまり絞らなくても、ある程度深い被写界深度が得られる
という事だ。

αは、元々1985年のミノルタの初号機から、2000年代にSONYに
引き継いだAF一眼レフのブランド(シリーズ)名称であったが、
2013年、一眼とミラーレスを統合したシリーズ名となった。
で、その2013年からα(E)はフルサイズ機が主力となった為、
現代においては、APS-C専用レンズ(FEではなく、E名称)の
レンズは比較的中古相場が安価である。
本レンズE16/2.8も1万円程度の安価な相場で豊富な中古流通の
玉数があり、買いやすい。
なお、フルサイズ用レンズでなくては(自分のα7等に)使えない、
と思っている初級ユーザーもいるかもしれないが、
α7系の「APS-Cサイズ撮影」設定を、「AUTO」又は「入り」に
しておくとレンズ装着時に何の違和感も無く使用できる。
(注:EVFはクロップされずフル画面で見られる。なお、記録
画素数が大幅に減るので、用途によってはその点だけ注意だ)

無い、まあ、ボデイとのセットで中古購入価格は安価であったが
コスパ点をあまり高く評価していないのは「そこそこ写る普通の
レンズ」と言う枠から出ていないからだ。
まあでも、α(E)ユーザーであれば、持っていて損は無いレンズ
ではあるとは思う。
----
番外レンズ(6) 約170位相当

レンズ名:LENSBABY MUSE Double Glass Optic
レンズ購入価格:8,000円相当(新品+中古)
使用カメラ:SONY NEX-3 (APS-C機)
LENSBABYのティルト型レンズは、3GやMUSE等、過去記事で
何度も紹介している。

一般撮影(風景や人物等)には勿論全く向かない。
使いこなしも難しい。ビギナー層では、原理や操作性の面で
「偶然」以外ではティルトレンズをコントロールする事は出来ず、
また中上級者層であっても、ティルトの原理は知っていたとしても
その効果を想像しながらの作画が困難である(つまり、どう
写るかわからない、あるいは逆に、こう写したいという考えが
あっても、その通りには上手く撮れない)
すなわち、誰もがどうやっても、使うのが難しいレンズである。
そういう意味では、コスパはともかく、マニアック度が極めて
高いレンズになるであろう。
しかし、エンジョイ度が高いかどうかは、ユーザーのスキルに
よりけりだ、本レンズの難しい「操作性」や「作画意図」に
おいて、それを楽しいと思って撮れるかどうかがポイントになる。
一般的には「こんなに撮るのが難しくて、しかもどう写るか
良くわからないレンズなんて、楽しめないよ!」と思っても
不思議では無いであろう。
だから、そういう難しいものを使いこなそうとする事に楽しさを
感じる事ができるかどうか?が、まず本レンズを使う為の条件と
なってくる、すなわちかなりのマニアックなレンズという訳だ。
(特に、「テクニカル・マニア」向けである)

MUSEのDouble Glass Opticでは、F5.6前後の絞りプレート
(付属品、磁力交換式)を装着する事で、トイレンズよりも
むしろ実用レンズに近い高い描写力(画質)を得る事ができる。
ただ、高画質である事が本レンズの使用目的に合うかどうかは
微妙だ。・・という事で、MUSEでは、より写りが「ユルい」
つまりトイレンズの写りに近い「プラスチック・オプテック」と
いった光学系(レンズ)に交換する事ができる。
ただ、私の感覚では「プラスチック・オプテック」を使った
ケースでは、ちょっと「ユルすぎて」好みに合わない。
さらにMUSEには「ピンホール&ゾーンプレート」が存在するが、
これらもさらにボケボケの写りで、撮影用途を選ぶのが大変だ。
(レンズマニアックス第1回、第4回記事参照)
なので、写りの良い Double Glass Opticや3Gを持ち出す事が
多くなっている。
カメラ母艦に常にNEX-3を使用しているのは、このボディ形状が、
MUSEや3Gを手持ちで使うのに適しているからだ。
ただこのあたりは、利用者の手の大きさや形により、使い易さ
は変わってくるかも知れない。
本来こうしたトイレンズ系の場合、エフェクトを組み合せる
のが表現力の増強目的では望ましいが、残念ながらNEX-3には、
殆どエフェクトが搭載されていない。
この為、後期NEX/αのAPS-C機を「Eマウント・トイレンズ母艦」
として使うのが望ましいと思い、代替機を狙っていたが、
なかなか適正な候補機種が見当たらなかった。
(追記:現在ではα6000を入手し、この用途にあてている)
それと、フルサイズ機α7が「オールドレンズでゴーストの頻発」
という重欠点を抱えていて、オールドレンズ母艦としての目的には
適さないので、これを使い潰した後(減価償却完了後)トイレンズ
母艦用に格下げにしようかとも思っている。
まあその為には、次期フルサイズ・オールドレンズ母艦が必要と
なるが、その後のα7/9系列は高付加価値型商品となってしまい、
今のところ、その目的に合致して適価で買える機種が出てきて
おらず、なかなか苦しい所だ。

おまけに、一般的な写真撮影における必要度もゼロに近い。
そして、旧機種の中古や在庫処分を狙えば適正な価格帯にはなるが、
新品購入では後継機(コンポーザーPRO等)は、かなり高価だ。
まあ、というわけで、コスパの観点からも「名玉」にはランクイン
は元々無理なレンズではあるが、特殊レンズとしての存在感は高く
マニアック度も高いので、今回紹介に至った次第だ。
---
さて、次は「プロローグ編」のラストのレンズである。
番外レンズ(7) 約170位相当

レンズ名:TAMRON SP 85mm/f1.8 Di VC USD (Model F016)
レンズ購入価格:70,000円(中古)
使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)
2016年発売の大口径中望遠単焦点レンズ。焦点距離から言って
ポートレート用途が適正であろうが、私はライブや舞台撮影
での中距離人物撮影に、よく本レンズを使っている。

本レンズを購入したからであり、時代が下がれば、もう少し
本レンズの中古相場は下がり、コスパ点も上がるであろう。
・・と言うのも、初級中級層にとっては85mmレンズはF1.4が
王道であり、F1.8というだけで人気薄になってしまうからだ。
私は銀塩時代から多数の85mmレンズを所有している。ある意味
85mmマニアでると言っても過言では無い。そうして購入した
85mmの中には、F1.4版も当然いくつも混じっている、けど
それらが、いつでも写りが良いかどうかは、ちょっと疑問なのだ。
開放F値を1.8ないし2に抑えた設計の物の方が良く写るケースも
多々あったし、そもそも、F1.4版で最短撮影距離付近(1m前後)
の撮影を絞り開放近くで行った場合、被写界深度が1cm程度と
極めて浅く、おまけにそれが人物であったり草花等であった場合、
被写体のブレ(動き)が生じて、浅い被写界深度では間違いなく
ピントを外してしまう。そのピント歩留まり(成功率)は、
経験上10%以下、つまり10枚に9枚は失敗してしまうのだ。
これは、AFでもMFでも同様である、こちら側(カメラ)の精度
の問題も大きいが、それのみならず被写体側の問題もあるからだ。
さらに言えば、F1.4版はボケ質破綻が頻繁に発生するレンズも
多く、F1.8版より慎重に、その回避技法を用いる必要もある。
(すなわち、成功率がさらに悪化し、ボケ質破綻回避の為の
無駄打ちを行わざるを得ず、レンズによっては、歩留まりは
1%程度にまで低下する)
結局、85mm/f1.4は必然的にあまり持ち出さないレンズと
なってしまう、失敗する事が明白だから、重要な撮影には
使えないのだ。
けど、大口径中望遠(70~120mm前後の焦点距離)は様々な
撮影シーンにおいて必要だ。
この為、私はこの目的では、たとえばMFレンズであれば、
CONTAX Planar 100mm/f2や、OLYMPUS OM 100mm/f2
PENTAX 120mm/f2.8、LAOWA 105mm/f2等を良く使い。
AFでは、NIKON DC105mm/f2,同AiAF85mm/f1.8 、
PENTAX FA77/1.8Limited等を使う場合が多かった。
あるいは、AFの90mmないし105mmマクロをこの目的に
充てる事もあった。
これらはそれぞれ、ミラーレス・マニアックスやハイコスパの
シリーズ記事で紹介しており、「良く出来たレンズ」として
実用性能の高さや必要度の高さを誇っている。
AFレンズで最も良く使用したのは、NIKON AiAF85mm/f1.8と
PENTAX FA77/1.8Limitedであったと思う。
人物撮影や屋内撮影、ライブ等イベント撮影まで汎用性が
極めて高く、長年にわたって重宝してきたレンズである。
しかし、AiAF85/1.8はもとよりFA77/1.8も古い時代のレンズだ、
およそ20年近くも使っていれば、近年の最新レンズに比べて
どうしても各種性能(解像力や、AF性能、手ブレ補正等)が
見劣りしてしまう。
最新レンズでFA77/1.8等の代替となるレンズをずっと探して
いたが、なかなかそれが存在しないし、新発売もされない。
なにせFA77/1.8はミラーレス・マニアックス名玉編で堂々の
第1位に輝いた栄光のレンズだ、それを超えるものなど、
そう簡単に出てくる筈も無い。
近年になって、TAMRONから本レンズSP85/1.8が発売された、
「このレンズならば、もしかして・・」
という期待を込めての購入となった次第である。

描写力的な不満は感じられない、解像感も高いが、他の近代レンズ
のようにカリカリな輪郭ではなく、人物撮影によくマッチするように
設計されている、ボケ質も良く、ボケ質破綻も気にならない。
F1.8ということで、F1.4級に比べて初級中級者が着目しない分、
マニアック度も高い。
やや重量級で持ち出しが不便ではあるが、まあ重欠点と呼べる程
のものではなく、実使用上でのエンジョイも高い。
注意点は1点だけ、NIKON用でも電磁絞り採用(E型と等価)の
レンズであり、ニコン機以外での(マウントアダプター等)使用が
困難(ほぼ不可能)な事だ、が、ここも重欠点とは言えない。
まあすなわち、殆どの項目で高得点であるレンズだ。
・・ただ、やはり値段が高かった(汗)
コスパ点は、一応最小限の減点として、2.5点としたが
それ以上与えるのは無理だ。年月が経て中古相場がさらに下がった
としても、コスパは3点から3.5点が限界であろう。
という事で、総合平均4.0以上が主に対象となる本シリーズ記事
ではコスパ面を主因としてランクインできないレンズである。

FA77/1.8の代替となりうる高性能レンズである事は確かだ。
ちなみに、本シリーズ記事では、FA77/1.8は1位になれない事は
確定している。何故ならばそのレンズも高価であり、コスパ点が
3点止まりであるからだ。
ただ、他の項目の評価点が高いので、ランキングの中位くらい
には入ってくるとは思われる。
----
さて、「プロローグ編」での、ランキング外レンズの7本の
紹介はこのあたりまでで、次回第3回記事では、「本編」として
ランキングレンズを下位より順次紹介していこう。