本シリーズ記事では、所有しているミラーレス機の本体の
詳細を世代別に紹介している。
今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代の定義は第一回
記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M1(2013年)を紹介しよう。
言うまでも無いが、μ4/3(マイクロフォーサーズ)機である。
装着レンズは、各種マウントの物を3本用意してある。
![c0032138_16590791.jpg]()
を使用する。(μ4/3用AFレンズ、ハイコスパ第4回記事等)
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、
記事の途中で適宜、別のレンズに交換する。
![c0032138_16590790.jpg]()
「従来型一眼レフを統合するミラーレスのフラッグシップ機」
と書かれていた。
まあ、これは「直接には書きたく無い事」の「婉曲表現」で
あろう。つまりは「フォーサーズとマイクロフォーサーズ
のシステムを統合する」という意味であり、さらに言えば
「もうフォーサーズ(システム)は作りません」と宣言して
いる事と等価だ。
事実、本機発売の2013年以降、オリンパスは、4/3機や
4/3用レンズを新規に発売していない。
当時の市場背景であるが、前年2012年は「フルサイズ元年」
と私が定義しているくらい、多数のフルサイズ・デジタル
一眼レフが発売された。
具体的には、CANON EOS 6D,EOS 5D MarkⅢ,NIKON D600
D800/E,SONY α99等であるが、これらの中には比較的安価
な機体もあり、それまでの「フルサイズ機は業務用途だ」
という常識を打ち破って、一般層にまでフルサイズ・デジタル
一眼レフの普及が始まった年であった。
2000年代のデジタルカメラでは「画素数が大きいカメラが
良く写るカメラだ」という方向性と概念を、市場(メーカー、
流通、評価情報等)より、「常識」として一般ユーザーに
対し(悪い言葉を使えば)「植え付けて」来たのであるが、
2012年からは「センサーが大きいカメラは良く写るカメラだ」
という風に、その植え付け概念の内容が変わってきている。
これの背景はまあ、2010年前後にミラーレス機が爆発的に
普及し、その全てが小型センサー(1型以下、1型、4/3型、
APS-C型)であった事から、一眼レフ陣営が「起死回生の
戦略」としてセンサーの大型化を始めた事からだ。
まあ、製造技術が発達して、大型(フルサイズ)センサーの
歩留まりが向上した事も理由であろう。(あるいはAPS-C型
センサーでは、もう画素数向上が限界に達していたという
理由もある)まあつまり、従来よりも安価になった大型の
センサー部品を使って「フルサイズは良い」という付加価値
から、カメラを高価に売る事が出来るならば、ミラーレス機に
押されて販売数が不利になった(デジタル)一眼レフ市場を
利益構造で巻き返す事ができるわけだ。
一眼レフがフルサイズ化したので、今度は、メーカー等は
それの優位点をミラーレス機陣営に対してアピール(攻撃)
する事ができる。
つまり、「カメラは、センサーが大きい方が高画質だから、
センサーの小さいμ4/3などは、良く写るはずが無い!」
と、市場(メーカー等)は、こういう攻撃的な売り文句が
出来る訳だ。(事実、当時のネット上等には、恐らくは市場
関係者とも思われる、そうした主旨の書き込みが多かった)
それに対し、今度はμ4/3陣営等では、「センサーサイズ
こそ小さいが、レンズを含めたシステム全体の画質は、一切
妥協していない」などの論旨で応戦する訳だ。
だが、これらは明らかにユーザー不在の「舌戦」であろう。
実のところ、センサーサイズなんて、どうでも良いのだ。
私の感覚で言えば、それの差よりも使用する個々のレンズの
性能差の方が遥かに大きい。
初級者層はフルサイズの高額カメラを買うよりも、まずは
高性能・高描写力のレンズを買うべきだ、とも思っている。
まあでも、その後の時代で、さらに一眼レフ市場は縮退して
しまったので、高付加価値型の高価なカメラをビギナー層に
買ってもらわないと、もう市場の維持が出来ない厳しい状況だ。
事の本質が良くわかっていない初級者層が、せっせと高価な
新鋭機を買ってくれない限り、一眼レフ市場は崩壊してしまう。
(あるいは、もう限界であるから、2018年秋より各社一斉に
高額なフルサイズ・ミラーレス機に戦略転換したのだろうか?)
で、実際のところは、2012年時点では、この「舌戦」は
一眼レフ陣営の勝ちだ。世の中の一般ユーザーは、結局は
「フルサイズ機が高画質だ」と思い込んで信じた訳であり、
そうした仕様の新鋭機に注目が集中した時代であった。
だとすると、正直言えば、もう4/3機(一眼レフの方)は、
寿命的にアウトだ。フォーサーズという規格はセンサーが
4/3型である事は決まっていて、これをフルサイズ化
する事は出来ないので、オリンパスとしても不利な土俵で
いつまでも相撲を取り続けていても意味が無い。
幸いにして市場ではPENやOM-Dが新規ユーザー層に好調だ、
もうここは4/3機を潔く諦め、μ4/3に統合した方が得策で
あろう。
ただ、上級ユーザーがフルサイズ一眼レフの方に向かうのは
少しでも歯止めしなければならない。
このタイミングで新規に出すμ4/3機は、上級機(ハイエンド
機、フラッグシップ機)しか無いではないか。
よって、ここで本機E-M1の登場である。
![c0032138_16590737.jpg]()
市場状況の激変により、オリンパスの戦略転換の要となった
重要な機種であるからだ。
ちなみに、銀塩時代まで遡って考えても、オリンパスの
銀塩OMヒトケタ機は旗艦(フラッグシップ)機とはちょっと
言い難い立ち位置のカメラであり、まあ、独自の路線だった。
オリンパスの旗艦機は、4/3時代のE-1(2003年、未所有)
しか存在していなかった。
したがって、本機E-M1の存在意義や、ミラーレス市場に
与えたインパクトは非常に大きい。
![c0032138_16590715.jpg]()
それは、本機E-M1の発売直後の2013年末に、史上初の
フルサイズ・ミラーレス機 SONY α7/Rが発売されたのだ。
例えば、α7(本シリーズ第13回=前回記事。注:記事掲載の
便宜上、発売順序通りにはなっていない)では、フルサイズ
の一眼レフとは比較にならない小型軽量であり、おおよそ
半分程度の重さしかない。
加えて価格も安価で、α7と本機E-M1の発売時実勢価格は
どちらも約15万円、これは例えば、安価な類のフルサイズ
デジタル一眼レフ CANON EOS 6D(デジタル一眼第16回)
の発売時価格、約18万5000円よりも安価だ。
ただ、α7のこの低価格は戦略的な要素もあったと思う。
まず、本機E-M1の対抗価格だった可能性があるし、
それとα7/Rでは、交換レンズは新規のFEマウントの
物をユーザーは新たに買わなければならないからだ。
つまり、カメラでは儲けず、レンズで儲ける仕組みだ。
まあしかし、この戦略はマニア層には見抜かれてしまい、
マニアは皆、α7を「オールドレンズのフルサイズ母艦」
として使って、高価なFEレンズを買い控えした。
ついでに余談だが、その後α7Ⅱ、α7Ⅲとモデルチェンジ
の度に、およそ5万円づつも定価が上がっていくのは、どう
見ても不条理で納得がいかない。手ブレ補正が内蔵された、
高速連写が付いた、という理由はあるが、そういう機能は
他社機であれば、最初の機体から入っている事もある。
本機E-M1も、まあ、そういう類の、出し惜しみをしていない
高性能機体だ。
![c0032138_16590781.jpg]()
宙ぶらりんになってしまったと思う。
初級層から上級層まで、あるいは職業写真家層まで、
どのユーザー層の志向を見ても、フルサイズ一眼レフか、
又はフルサイズミラーレスに魅力を感じるだろうからだ。
まあ、本機E-M1は連写性能やAF性能もそこそこ高いので、
業務用途を含む「望遠母艦」としてならば、使えない事は
無いだろう、その目的であれば、一眼レフシステムよりも、
総重量を圧倒的に軽減可能だから、(業務上等の)用途に
よっては、ハンドリング性能に遥かに優れる訳だ。
ただ、そうだとしても、そういう用途がある人達は、
すでに一眼レフ用の(超)望遠レンズ等を「資産」として
所有しているだろう。わざわざ新規にμ4/3機に買い換えて、
(高価な)μ4/3用(超/高性能)望遠を買うはずも無い。
![c0032138_16592109.jpg]()
居なかったかも知れない。
機体の性能は十分なので、μ4/3システムとして使っても
良いし、マウントアダプターを介して「銀塩MF望遠レンズ
母艦」としても十分すぎる程の性能を持つ。
まあ、その用途にはまさしくぴったりとハマるカメラである。
私も旧来は「望遠母艦」として、PANASONIC DMC-G6
(本シリーズ第10回)を愛用してきたが、老朽化が進み、
もう少しだけ「瞬発力」と高耐久性のあるボディが必要だと
思っていて、発売からやや年月が過ぎ、後継機E-M1 MarkⅡの
発売後に中古相場が安価となった本機を購入した次第である。
すなわち、私の本機の購入目的は「高性能望遠レンズ母艦」
である。ただし、本機を業務用途撮影に使う気は無い、
絶対的な「瞬発力」(AF性能、連写性能等)は、いくら
「像面位相差AF」を(初)搭載した本機とは言え、まだまだ
(APS-C型デジタル)一眼レフに優位性があるからだ。
(デジタル一眼第18回SONY α77Ⅱ,同19回CANON EOS 7D
MarkⅡ,同20回NIKON D500の各記事を参照)
交換レンズ群のバリエーションも、銀塩一眼レフ時代から
脈々と続く長期間の保有資産が、それらのデジタル一眼
レフでも勿論使える訳だ。
さて、ここで使用レンズを交換しよう。
![c0032138_16592157.jpg]()
を使用する。(他記事では未紹介)
4/3用レンズなので、電子アダプター「OLYMPUS MMF-2」を
介して本機E-M1に装着している。
![c0032138_16592198.jpg]()
された「Dual Fast AF」(像面位相差AF)が有効となり、
フォーサーズレンズの場合、コントラストAFではなく、
(像面)位相差AFでピント合わせが行われる。
合焦原理的には、4/3一眼レフと同様、という事になるが、
さすがに一眼レフ程の合焦速度や精度は得られない。
「4/3とμ4/3を統合した」とメーカーが主張するならば
もう少し頑張ってもらいたいようにも思うが、まあ技術的
レベルの限界点というものはある。
けれど、このシステムの場合には、S-AF+MF,MFアシストの
ピーキングON設定などで、シームレスにMFに切り替えて
マクロ撮影が出来るので、近接域で合わないAFにイライラ
するよりは、MFで撮影すれば特に問題は無い。
ただし、むしろ問題点なのは、4/3システムのレンズの多くは
「カメラ本体からの電源供給が止まるとMFでもピントリング
が動かない」という重欠点とも言える仕様を持つ事であり、
マクロレンズでMF近接撮影をしてからカメラの電源を切ると
「ヘリコイドが伸びっぱなしで、引っ込めることができない」
という間が抜けた状況になってしまう事だ(汗)
(この手のDCモーター内蔵レンズに対しては、他社機の一部
では「電源OFF時にレンズを収納位置に引っ込める」という
設定メニューが、その対策として存在する場合がある)
勿論、MFでヘリコイドを廻しながら電源を入れて速やかに
撮影準備が出来る、という高度なMF技法も使えない。
![c0032138_16592153.jpg]()
本機は、当時のμ4/3機の市場を上級者層向けにシフト
する為に投入された戦略的な機種である為、その当時の
技術として考えられる要素を全て惜しみなく投入している。
後年の新鋭機(例:OM-D E-M5Ⅱ 2015年、後日紹介予定)
と見比べても、新型機の技術の進歩による「下克上」は
殆ど発生しておらず、古くても見劣りする部分は殆ど無い。
(注:本機では小まめなファームウェアのバージョンアップ
があり、後継機で搭載された機能も、都度、追加されている
点もあるだろう)
あるいは、本機の後継機であるOM-D E-M1 MarkⅡ(2016年
未所有)とスペックを比較しても、本機の古さはあまり
感じられない。例えば、電子シャッター連写が、本機の
秒11コマからMarkⅡでは秒18コマに速くなったと言っても
私の用途では電子シャッターをまず使わないので、それを
魅力や付加価値に感じる事は無い。他にもMarKⅡでは
小改良点が勿論いくつもあるが、どれも、あまりピンと
くるものでは無かったし、その小さい差のために、中古
相場が3倍から4倍も高価なMarkⅡを買う事は、コスパ的
にも有り得ない話だった。まあ、MarkⅡを買うならば、
MarkⅢ等が発売されて、MarkⅡの中古相場が下がってから
の話だ。が、少なくとも、ここ数年間くらいの期間ならば、
本機E-M1の性能優位性は保たれていると見なせ、結果的に
仕様老朽化寿命(匠の用語辞典第8回参照)も、あまり
低くはないカメラとなっている。
![c0032138_16592086.jpg]()
WEB上、どこでも参照できるので割愛する。
実は、そういう、どこにでもある情報だけで、自分では
所有すらしていないカメラを評価する事も可能なのだ。
(事実、そうだと思われる情報はいくらでも世の中にある)
だけど、それでは情報提供の意味や価値や信憑性が無い。
本ブログでは特に「一次情報」の発信を主眼としている訳だ。
![c0032138_16595622.jpg]()
まずは、本機は「ミラーレス初の高速連写機」である
と言えるだろう。
私が言う「高速連写機」とは、一眼レフでもミラーレスでも
秒8コマ以上で80枚以上の連続撮影(バースト枚数)が
あるものだ。
できれば機械式シャッターで動き(電子シャッターでは無い)
ミラー等でのブラックアウト時間が少ない事が理想だ。
AF追従性などは拘らない、特に優れた高速連写機ならば
連写中のMFすら可能なのだ。
ただAE追従性は欲しい、連写中に大きく構図をパンすると
露出も大きく変わるからだ、けど、実はそれ(AE追従)が
出来る機種は殆ど無い(ごく一部の旗艦機くらいか?)
本機E-M1以前の時代の僅かな期間でのミラーレス機でも
高速連写は可能な機体があった。まあミラーレス機は構造上
連写に向くからだ。しかしそれらは電子シャッター利用で
あったり、バッファメモリーが少なく、ほんの20枚程度で
連写が打ち止めになったり低速化してしまっていた。
本機では、私の多くの使用条件において、秒10コマで、
連続数十コマの撮影が可能(注:スペック通りの96コマ
は無理だと思う)で、高速連写機の要件を満たす。
ただし注意しなければならないのは、ISO感度を高めたり
各種収差補正等をONとすると、とたんに連写速度や連続
撮影枚数が低下する機体が、他社機にもオリンパス機にも
色々とある事だ。
AF追従とレンズのAF速度(超音波モーターの有無や開放F値
の暗さ)による連写速度低下はやむを得ないし、それは
MFやAF技法と設定等の複合で回避も可能だ。収差補正は
使うレンズの選択で回避が出来るが、ISOだけはどうしようも
無い、これを高めないと撮れない場合も多々あるからだ。
だが、本機E-M1の場合はISO感度を高めても連写性能の
低下は殆ど起こらない、まあ実用範囲と言えよう。
(ただし、ISO6400以上に高めると、連写時のコマ毎の
AWBが非常にバラつき、色味がデタラメになる。でもまあ
偽色発生等、技術的限界もあるので、これは重欠点とは
言えないであろう)
他の特徴だが、一般に良く言われるローパスレスとか
防塵・防滴等の高耐久性はどうでも良い事だろう、
それらは本機だけの唯一の特徴では無いし、必要な
撮影状況に応じて、カメラを使い分ければ良いだけだ。
機能、性能面では、ほとんど不足を感じないし、
頻繁なファームアップで新鋭機(例:E-M5 MarkⅡ等)
と同等の新機能も搭載されてきている。
本機は2013年製(本シリーズ記事で定義する第三世代機)
ではあるが、後年2015年以降の第四世代機と比べても性能上
の遜色は殆ど無く、高性能化の先駆けとなった機種である。
![c0032138_20084530.jpg]()
アートフィルター(エフェクト)の充実が好ましい。
個々のエフェクトはパラメーターが微調整可能であり、
作画のバリエーションがかなり大きく、おまけに
「アートフィルターブラケット」により、利用者が
思いもしない偶発的な表現効果を得る事も可能だ。
(=アンコントローラブル技法、Lo-Fi技法、等に関連)
![c0032138_20085442.jpg]()
である。ボディ前面にもアサイナブルボタンが存在するし
ボタンやダイヤルのカスタマイズ性は高く、動画録画開始
ボタンも他機能に変更可なので、静止画主体の使用法で
役に立つ。
ただし、多機能ゆえに、旧来からのメニュー操作系では
もう階層が深くなりすぎていて、操作系全般はあまり
優れているとは言えない。
オリンパス機伝統の「スーパーコンパネ」ですらも、もう
はみ出して入らない機能が多々あるし、そういうGUI部分の
カスタマイズ性は皆無だ(注:他社機はたいてい編集可)
ただまあ、スーパーコンパネがEVF内に表示できて、
十字キーを用いて「ファインダーを覗いたままカメラ設定
の変更操作が可能」という点は、本機およびミラーレス機
全般での大きな長所だ。
特に本機は「望遠母艦」にしたい、と考えていたので、
これが出来ないと、一々カメラの構えを解いて、背面の
モニターを見て選んでは非効率的だし、最悪なのは
「タッチパネルでないと操作ができない」といった仕様だ。
それは、構え、視線、動線、重量バランス等、全ての点で、
そんな操作系は有り得ない。なお、本機の場合はタッチ
パネルでしか操作が出来ない設定項目は無いので、勿論、
タッチパネル操作機能は無効化して封印している。
それと、一眼レフでは、SONYのαフタケタEVF機以外では
ファインダー内の設定変更操作が(殆ど)出来ない。
よって、頻繁にカメラ設定を変更しなければならない撮影
用途においては、実は一眼レフはあまり有益な機材では無い。
ましてや重たいシステムだ、大型の望遠レンズを装着時に
一々ファインダーを覗く構えを解かないと何もカメラ設定が
できないのは、撮影効率の面からは好ましく無い話なのだ。
三脚を立ててならば問題回避できるのだろうが、本ブログ
では開設当初から概算で99.8%は三脚は使用していないし、
現代では三脚を使うユーザーの方がむしろ稀である。
いつまでも古い撮影技法を元にカメラを設計するならば、
(=他社では良くある)それが最も大きな問題点であろう。
![c0032138_16595647.jpg]()
優れた方式だ。他社機では、ダイヤルの物理的なロックを
強要される場合があり、それは論外の機構と操作性だ。
総合的には本機の操作性・操作系はギリギリセーフでは
あると思うが、勿論、高得点を与えられる状態では無い。
他の特徴としては、この時代の前後の多くのオリンパス機
はバッテリー(BLN-1)が共通で使えるメリットがある。
本機の中古を私が選択した理由の1つで、この機体には
バッテリーが3個も付いていたからだ、他機への流用を
含め、これで予備バッテリー数としては十分だ。
なお、本機E-M1の撮影可能枚数は、CIPA準拠では350枚
との仕様で、少々物足りないように思うかも知れないが、
いつも言うように、まず、この値の5~6倍は撮る事が
目標値である。
本機の場合は、フラッシュを一切使わない事や、高速
連写機でもある事から、2000枚以上は楽に撮れる。
個人的なルール上としてはこれで合格だが、高速連写機
における業務用途でのバッテリーの持ちとしては、1日で
6000枚位が必要なケースもあるので、そうした際には
予備バッテリーは必須であろう。
それから、保存されるファイル名だが、下4ケタが連番
になるのは普通だが、本機では上3ケタを撮影日にする
事が出来る、これは写真整理の際になかなか便利だ。
なお、1日に1000枚以上の撮影をした場合でも、フォルダー
は自動更新される事は無い。(これはこれで良い、他社機
では、大量に撮影すると、勝手にフォルダーが更新される
事があるが、何故それが必要なのか全く意味不明だ)
----
さて、このあたりで再度使用レンズを交換しよう。
![c0032138_16595591.jpg]()
(ハイコスパ第16回記事等)
MF時代のオールドレンズである。本機E-M1装着時には
OM→μ4/3アダプターを用いれば良い。
電子接点でのやり取りは無い為、電子アダプターの
必要性は無い(そもそもOM用の電子アダプターは無い)
![c0032138_16595532.jpg]()
よっては手ブレ補正機能が欲しくなると思う。
本機E-M1では、手動で焦点距離を設定すれば、一応
内蔵手ブレ補正機能が有効になる。
ただし、設定は毎回強要される訳ではなく、メニューの
奥から掘り出して設定する必要があるので、レンズ交換
時の入力忘れは要注意だし、入力後もファイダー内に
設定した焦点距離が表示されない(純正レンズの場合のみ
焦点距離が表示される)という、お粗末で排他的な仕様
なので、ますます設定忘れは要注意だ。
本機E-M1には、AUTO ISO時の感度切り替えシャッター速度
(=低速限界)の設定が無く、概ね1/125秒前後で固定的に
切り替わる。よって、撮影条件によっては、このクラスの
(100mm以上)望遠レンズでは、内蔵手ブレ補正機能が
あっても、初級者層等では手ブレしてしまう恐れがあるし
撮影条件によっては、中上級層でも手ブレ対策は必須だ。
![c0032138_17001237.jpg]()
最大の課題と感じるのは、本機の「排他的仕様」だ。
「排他的仕様」の意味詳細は長くなるので割愛する。
(いずれ匠の写真用語辞典記事で解説予定)
まあつまり、オリンパス純正(又はμ4/3規格準拠)
かつ、特定の仕様条件を満たすレンズ等を使わない限り、
最高性能(性能仕様、便利機能、操作性、操作系等)
が発揮できない、という事である。
チラリと前述したが、銀塩用OMレンズをアダプターで
使用しただけで、本機の性能は、もうヘロヘロに落ちる。
細かい操作系上の矛盾や機能制限が多々発生する為、
あまり汎用的な母艦としての用途には向かない。
(注:この点では、同時代の PANASONIC DMC-G6 2013年
本シリーズ第10回記事、の方が、やはり「望遠母艦」と
して向いている様子だ)
![c0032138_17001391.jpg]()
まずは機能面。
ISO感度だが、ベース感度が200と高目である、
一応マニュアル感度変更でISO100が使えるのだが、
AUTOではそれは無理なので、大口径レンズとの相性が
良く無い。ISO感度変更の操作性も、あまり便利という
訳でも無い。
また、前述のようにAUTO ISOの低速限界(切り替わりの
シャッター速度)が変更できない。(なお、この問題は
後年のオリンパス機の一部では若干の改善が見られる)
これにより、アダプターでMF望遠レンズ使用時等では、
手ブレのリスクが増大してしまう。
内蔵手ブレ補正機能は有効だが、(機械式)マウント
アダプター使用時には、前述のように入力操作が煩雑だ。
加えて、どうも内蔵手ブレ補正は、カタログ通りの
高性能では無く、望遠+高速連写等、厳しい条件では容易に
ブレが発生、手動でISO感度を適正に変更する必要がある。
OVFシミュレーションの機能が新設されているが、これの
有効な使い道は、個人的には良くわからない(汗)
EVF自体の解像度は236万画素で、この時代としては、
トップクラスであろう。
また、EVFの倍率も高くて良い。ただし仕様の1.48倍は
フルサイズ換算では0.74倍となるので、MFで使う
ケースも考えると、もう少しだけ大きい方が望ましい。
(銀塩MF機では0.8倍~0.9倍が普通だ)
この仕様は、後年のE-M5 MarkⅡ等と同じであるが、
銀塩機並、を目論んだとしても、いずれの機体用にも
(別売の)「拡大アイカップ」オプションが存在しない。
なお、旧来の4/3機のEシリーズでは、マグニファイヤー
(拡大)アイカップ「ME-1」が利用可能であった。
それと、EVFの色味やコントラストが悪い。
新鋭レンズを装着していても、なんだかコントラストが
低いオールドレンズを使っている雰囲気で好ましく無い。
これは、同時期の他社機と同じ236万ドット部品を使って
いるのにもかかわらず、他社機よりも劣る印象だ。
前述のOVFシミュレーションや、ピーキング時の背景輝度
調整機能、その他が新設された事で、EVFの表示画像に
対して、色味や輝度を調整する構造や、その画像処理の
アルゴリズムが入っているだろうから、そこの未成熟か?
(注:設定を色々変えても改善されない、それから、
同様な構造の、後年のOM-D E-M5 MarkⅡでも大きな
改善は無い)
![c0032138_17001341.jpg]()
メニューおよびモードダイアル動作が電子的に重い。
つまり操作してからワンテンポ遅れて反応するという感じ
であり、こういう点はフラッグシップ機としては、あまり
好ましく無い弱点である。
高級機であればあるほど、贅沢なCPUや電子回路を用いて
操作性、操作系的なレスポンスを上げる必要があるのだ。
さらに言えば、アートフィルターブラケットや連写機能を
用いて、バッファメモリーから記録メディアへの書き込みが
行われている最中には、露出モード変更等の操作が遅れて
反応する、この書き込み&モード変更の間の時間帯では、
結局のところ、ほぼ撮影が不能となる。
それと、背面の十字キーも形状が悪く、押しにくい事や
ボタン配置もどうも直感的では無いので、上記の操作の
反応の悪さと絡んで、ちょっとイラっとする場合がある。
また、マウントアダプター利用時には、ピーキング機能が
自動的には使えない、必ずどこかのFnキーにその機能を
アサインし、電源ONの度に、それを押さないと使えない。
加えて、モードダイヤルを廻し、ARTモード等に変更した
際にも、ピーキングが消え、Fnキーで再度呼び出さないと
ならない。
![c0032138_17001327.jpg]()
(例:VIVID等)は無効化するので、一々、元の設定に
戻す必要がある。
なお、マルチFn機能は操作系が若干不便で、ちょっとした
誤操作で、こうした機能がすぐ有効になり、一度でも
間違えて呼び出したら、もう上記と同じ状況だ。
また、メニューを送っていくと解説文が現れて鬱陶しい。
「モードガイド表示」をOFFにしてもこの文章は消えない。
別途調べると「INFO」ボタンを長押しする事で消える事が
わかったが、操作系的に不合理で非直感的だ、すなわち
こうした細かい点は、良く練れていない。
ボデイ本体の課題だが、大型レンズを装着する可能性も
ある為、もう少し大型の方が好ましい。
特にグリップサイズが小さい事が気になる。(なお、この
点は後継機E-M1 MarkⅡでは若干改善されている)
それから、背面モニターがティルト式であり、バリアングル
では無いので、裏返せない(過酷な撮影環境とか、暗所での
イベント系の撮影時、モニターを光らせたくない、撮った
写真を周囲の観客見られたくない場合等で不便だし、
勿論、「縦位置ローアングル撮影」も厳しくなる)
まあ、総合的には「排他的仕様」により、μ4/3以外の
レンズを汎用的に使おうとした場合に、操作系等に細かい
課題が沢山出てくる。
本記事では、μ4/3レンズ、4/3レンズ、OMレンズの
3本を使用しているが、どうも、本機E-M1を「望遠母艦」と
する目論見は、上手く行きそうにない(汗)
![c0032138_17001257.jpg]()
評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★★★☆
【描写力・表現力】★★★☆
【操作性・操作系】★★☆
【アダプター適性】★★
【マニアック度 】★★★☆
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★★★☆ (中古購入価格:43,000円)
【完成度(当時)】★★★☆
【仕様老朽化寿命】★★★☆
【歴史的価値 】★★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】3.4点
総合点は悪い点数では無く、性能面や機能面では
あまり不満は無い事であろう。
だが、フラッグシップと言う割りには、操作系を始めと
して、細かいところに目が行き届いた配慮は感じられず、
「さすが高級機!」と思える要素は殆ど無い。
μ4/3純正レンズを使った際に、優れた高性能を発揮
できるのだが、かと言って、業務用機として使える
レベルあるいは機材環境では無い。
(注:レンズ環境については、後年にM.ZUIKO PRO
シリーズのラインナップを展開して充実しつつあるが
高付加価値化商品のためにコスパが悪すぎるので、
現状では購入していない。同等のスペックであれば
一眼レフ用での過去資産があるからだ)
高性能な趣味撮影専用機体としての目的が良くマッチする
機体ではあるが、逆にMFレンズをアダプターで使用時の
課題が多く、母艦性能に劣る(この点が上記の評価では、
「アダプター適性」の評価の低さに繋がっている)
ちょっと中途半端な立ち位置に思える。対策としては、
本機を、どういった目的に使うのがベストなのか?という
「用途開発」が試行錯誤的に必要になってくるだろう。
まあでも、歴史的価値の高いカメラだ
発売後時間が経って中古相場も十分こなれていて、コスパ
が良い、減価償却ルール(1枚2円の法則等)も、あっと
言う間に完了しているので、そこから後は、高耐久性を
活用して過酷な環境での使い潰し型のカメラにしてしまえば
良い。まあ、オリンパス党であれば必携のカメラだと思う。
---
次回記事は、引き続き第三世代のミラーレス機を紹介する、
詳細を世代別に紹介している。
今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代の定義は第一回
記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M1(2013年)を紹介しよう。
言うまでも無いが、μ4/3(マイクロフォーサーズ)機である。
装着レンズは、各種マウントの物を3本用意してある。

を使用する。(μ4/3用AFレンズ、ハイコスパ第4回記事等)
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、
記事の途中で適宜、別のレンズに交換する。

「従来型一眼レフを統合するミラーレスのフラッグシップ機」
と書かれていた。
まあ、これは「直接には書きたく無い事」の「婉曲表現」で
あろう。つまりは「フォーサーズとマイクロフォーサーズ
のシステムを統合する」という意味であり、さらに言えば
「もうフォーサーズ(システム)は作りません」と宣言して
いる事と等価だ。
事実、本機発売の2013年以降、オリンパスは、4/3機や
4/3用レンズを新規に発売していない。
当時の市場背景であるが、前年2012年は「フルサイズ元年」
と私が定義しているくらい、多数のフルサイズ・デジタル
一眼レフが発売された。
具体的には、CANON EOS 6D,EOS 5D MarkⅢ,NIKON D600
D800/E,SONY α99等であるが、これらの中には比較的安価
な機体もあり、それまでの「フルサイズ機は業務用途だ」
という常識を打ち破って、一般層にまでフルサイズ・デジタル
一眼レフの普及が始まった年であった。
2000年代のデジタルカメラでは「画素数が大きいカメラが
良く写るカメラだ」という方向性と概念を、市場(メーカー、
流通、評価情報等)より、「常識」として一般ユーザーに
対し(悪い言葉を使えば)「植え付けて」来たのであるが、
2012年からは「センサーが大きいカメラは良く写るカメラだ」
という風に、その植え付け概念の内容が変わってきている。
これの背景はまあ、2010年前後にミラーレス機が爆発的に
普及し、その全てが小型センサー(1型以下、1型、4/3型、
APS-C型)であった事から、一眼レフ陣営が「起死回生の
戦略」としてセンサーの大型化を始めた事からだ。
まあ、製造技術が発達して、大型(フルサイズ)センサーの
歩留まりが向上した事も理由であろう。(あるいはAPS-C型
センサーでは、もう画素数向上が限界に達していたという
理由もある)まあつまり、従来よりも安価になった大型の
センサー部品を使って「フルサイズは良い」という付加価値
から、カメラを高価に売る事が出来るならば、ミラーレス機に
押されて販売数が不利になった(デジタル)一眼レフ市場を
利益構造で巻き返す事ができるわけだ。
一眼レフがフルサイズ化したので、今度は、メーカー等は
それの優位点をミラーレス機陣営に対してアピール(攻撃)
する事ができる。
つまり、「カメラは、センサーが大きい方が高画質だから、
センサーの小さいμ4/3などは、良く写るはずが無い!」
と、市場(メーカー等)は、こういう攻撃的な売り文句が
出来る訳だ。(事実、当時のネット上等には、恐らくは市場
関係者とも思われる、そうした主旨の書き込みが多かった)
それに対し、今度はμ4/3陣営等では、「センサーサイズ
こそ小さいが、レンズを含めたシステム全体の画質は、一切
妥協していない」などの論旨で応戦する訳だ。
だが、これらは明らかにユーザー不在の「舌戦」であろう。
実のところ、センサーサイズなんて、どうでも良いのだ。
私の感覚で言えば、それの差よりも使用する個々のレンズの
性能差の方が遥かに大きい。
初級者層はフルサイズの高額カメラを買うよりも、まずは
高性能・高描写力のレンズを買うべきだ、とも思っている。
まあでも、その後の時代で、さらに一眼レフ市場は縮退して
しまったので、高付加価値型の高価なカメラをビギナー層に
買ってもらわないと、もう市場の維持が出来ない厳しい状況だ。
事の本質が良くわかっていない初級者層が、せっせと高価な
新鋭機を買ってくれない限り、一眼レフ市場は崩壊してしまう。
(あるいは、もう限界であるから、2018年秋より各社一斉に
高額なフルサイズ・ミラーレス機に戦略転換したのだろうか?)
で、実際のところは、2012年時点では、この「舌戦」は
一眼レフ陣営の勝ちだ。世の中の一般ユーザーは、結局は
「フルサイズ機が高画質だ」と思い込んで信じた訳であり、
そうした仕様の新鋭機に注目が集中した時代であった。
だとすると、正直言えば、もう4/3機(一眼レフの方)は、
寿命的にアウトだ。フォーサーズという規格はセンサーが
4/3型である事は決まっていて、これをフルサイズ化
する事は出来ないので、オリンパスとしても不利な土俵で
いつまでも相撲を取り続けていても意味が無い。
幸いにして市場ではPENやOM-Dが新規ユーザー層に好調だ、
もうここは4/3機を潔く諦め、μ4/3に統合した方が得策で
あろう。
ただ、上級ユーザーがフルサイズ一眼レフの方に向かうのは
少しでも歯止めしなければならない。
このタイミングで新規に出すμ4/3機は、上級機(ハイエンド
機、フラッグシップ機)しか無いではないか。
よって、ここで本機E-M1の登場である。

市場状況の激変により、オリンパスの戦略転換の要となった
重要な機種であるからだ。
ちなみに、銀塩時代まで遡って考えても、オリンパスの
銀塩OMヒトケタ機は旗艦(フラッグシップ)機とはちょっと
言い難い立ち位置のカメラであり、まあ、独自の路線だった。
オリンパスの旗艦機は、4/3時代のE-1(2003年、未所有)
しか存在していなかった。
したがって、本機E-M1の存在意義や、ミラーレス市場に
与えたインパクトは非常に大きい。

それは、本機E-M1の発売直後の2013年末に、史上初の
フルサイズ・ミラーレス機 SONY α7/Rが発売されたのだ。
例えば、α7(本シリーズ第13回=前回記事。注:記事掲載の
便宜上、発売順序通りにはなっていない)では、フルサイズ
の一眼レフとは比較にならない小型軽量であり、おおよそ
半分程度の重さしかない。
加えて価格も安価で、α7と本機E-M1の発売時実勢価格は
どちらも約15万円、これは例えば、安価な類のフルサイズ
デジタル一眼レフ CANON EOS 6D(デジタル一眼第16回)
の発売時価格、約18万5000円よりも安価だ。
ただ、α7のこの低価格は戦略的な要素もあったと思う。
まず、本機E-M1の対抗価格だった可能性があるし、
それとα7/Rでは、交換レンズは新規のFEマウントの
物をユーザーは新たに買わなければならないからだ。
つまり、カメラでは儲けず、レンズで儲ける仕組みだ。
まあしかし、この戦略はマニア層には見抜かれてしまい、
マニアは皆、α7を「オールドレンズのフルサイズ母艦」
として使って、高価なFEレンズを買い控えした。
ついでに余談だが、その後α7Ⅱ、α7Ⅲとモデルチェンジ
の度に、およそ5万円づつも定価が上がっていくのは、どう
見ても不条理で納得がいかない。手ブレ補正が内蔵された、
高速連写が付いた、という理由はあるが、そういう機能は
他社機であれば、最初の機体から入っている事もある。
本機E-M1も、まあ、そういう類の、出し惜しみをしていない
高性能機体だ。

宙ぶらりんになってしまったと思う。
初級層から上級層まで、あるいは職業写真家層まで、
どのユーザー層の志向を見ても、フルサイズ一眼レフか、
又はフルサイズミラーレスに魅力を感じるだろうからだ。
まあ、本機E-M1は連写性能やAF性能もそこそこ高いので、
業務用途を含む「望遠母艦」としてならば、使えない事は
無いだろう、その目的であれば、一眼レフシステムよりも、
総重量を圧倒的に軽減可能だから、(業務上等の)用途に
よっては、ハンドリング性能に遥かに優れる訳だ。
ただ、そうだとしても、そういう用途がある人達は、
すでに一眼レフ用の(超)望遠レンズ等を「資産」として
所有しているだろう。わざわざ新規にμ4/3機に買い換えて、
(高価な)μ4/3用(超/高性能)望遠を買うはずも無い。

居なかったかも知れない。
機体の性能は十分なので、μ4/3システムとして使っても
良いし、マウントアダプターを介して「銀塩MF望遠レンズ
母艦」としても十分すぎる程の性能を持つ。
まあ、その用途にはまさしくぴったりとハマるカメラである。
私も旧来は「望遠母艦」として、PANASONIC DMC-G6
(本シリーズ第10回)を愛用してきたが、老朽化が進み、
もう少しだけ「瞬発力」と高耐久性のあるボディが必要だと
思っていて、発売からやや年月が過ぎ、後継機E-M1 MarkⅡの
発売後に中古相場が安価となった本機を購入した次第である。
すなわち、私の本機の購入目的は「高性能望遠レンズ母艦」
である。ただし、本機を業務用途撮影に使う気は無い、
絶対的な「瞬発力」(AF性能、連写性能等)は、いくら
「像面位相差AF」を(初)搭載した本機とは言え、まだまだ
(APS-C型デジタル)一眼レフに優位性があるからだ。
(デジタル一眼第18回SONY α77Ⅱ,同19回CANON EOS 7D
MarkⅡ,同20回NIKON D500の各記事を参照)
交換レンズ群のバリエーションも、銀塩一眼レフ時代から
脈々と続く長期間の保有資産が、それらのデジタル一眼
レフでも勿論使える訳だ。
さて、ここで使用レンズを交換しよう。

を使用する。(他記事では未紹介)
4/3用レンズなので、電子アダプター「OLYMPUS MMF-2」を
介して本機E-M1に装着している。
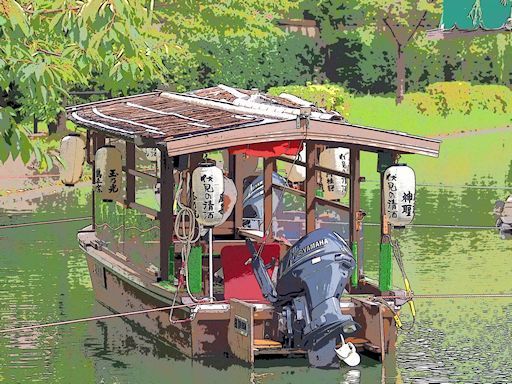
された「Dual Fast AF」(像面位相差AF)が有効となり、
フォーサーズレンズの場合、コントラストAFではなく、
(像面)位相差AFでピント合わせが行われる。
合焦原理的には、4/3一眼レフと同様、という事になるが、
さすがに一眼レフ程の合焦速度や精度は得られない。
「4/3とμ4/3を統合した」とメーカーが主張するならば
もう少し頑張ってもらいたいようにも思うが、まあ技術的
レベルの限界点というものはある。
けれど、このシステムの場合には、S-AF+MF,MFアシストの
ピーキングON設定などで、シームレスにMFに切り替えて
マクロ撮影が出来るので、近接域で合わないAFにイライラ
するよりは、MFで撮影すれば特に問題は無い。
ただし、むしろ問題点なのは、4/3システムのレンズの多くは
「カメラ本体からの電源供給が止まるとMFでもピントリング
が動かない」という重欠点とも言える仕様を持つ事であり、
マクロレンズでMF近接撮影をしてからカメラの電源を切ると
「ヘリコイドが伸びっぱなしで、引っ込めることができない」
という間が抜けた状況になってしまう事だ(汗)
(この手のDCモーター内蔵レンズに対しては、他社機の一部
では「電源OFF時にレンズを収納位置に引っ込める」という
設定メニューが、その対策として存在する場合がある)
勿論、MFでヘリコイドを廻しながら電源を入れて速やかに
撮影準備が出来る、という高度なMF技法も使えない。

本機は、当時のμ4/3機の市場を上級者層向けにシフト
する為に投入された戦略的な機種である為、その当時の
技術として考えられる要素を全て惜しみなく投入している。
後年の新鋭機(例:OM-D E-M5Ⅱ 2015年、後日紹介予定)
と見比べても、新型機の技術の進歩による「下克上」は
殆ど発生しておらず、古くても見劣りする部分は殆ど無い。
(注:本機では小まめなファームウェアのバージョンアップ
があり、後継機で搭載された機能も、都度、追加されている
点もあるだろう)
あるいは、本機の後継機であるOM-D E-M1 MarkⅡ(2016年
未所有)とスペックを比較しても、本機の古さはあまり
感じられない。例えば、電子シャッター連写が、本機の
秒11コマからMarkⅡでは秒18コマに速くなったと言っても
私の用途では電子シャッターをまず使わないので、それを
魅力や付加価値に感じる事は無い。他にもMarKⅡでは
小改良点が勿論いくつもあるが、どれも、あまりピンと
くるものでは無かったし、その小さい差のために、中古
相場が3倍から4倍も高価なMarkⅡを買う事は、コスパ的
にも有り得ない話だった。まあ、MarkⅡを買うならば、
MarkⅢ等が発売されて、MarkⅡの中古相場が下がってから
の話だ。が、少なくとも、ここ数年間くらいの期間ならば、
本機E-M1の性能優位性は保たれていると見なせ、結果的に
仕様老朽化寿命(匠の用語辞典第8回参照)も、あまり
低くはないカメラとなっている。

WEB上、どこでも参照できるので割愛する。
実は、そういう、どこにでもある情報だけで、自分では
所有すらしていないカメラを評価する事も可能なのだ。
(事実、そうだと思われる情報はいくらでも世の中にある)
だけど、それでは情報提供の意味や価値や信憑性が無い。
本ブログでは特に「一次情報」の発信を主眼としている訳だ。

まずは、本機は「ミラーレス初の高速連写機」である
と言えるだろう。
私が言う「高速連写機」とは、一眼レフでもミラーレスでも
秒8コマ以上で80枚以上の連続撮影(バースト枚数)が
あるものだ。
できれば機械式シャッターで動き(電子シャッターでは無い)
ミラー等でのブラックアウト時間が少ない事が理想だ。
AF追従性などは拘らない、特に優れた高速連写機ならば
連写中のMFすら可能なのだ。
ただAE追従性は欲しい、連写中に大きく構図をパンすると
露出も大きく変わるからだ、けど、実はそれ(AE追従)が
出来る機種は殆ど無い(ごく一部の旗艦機くらいか?)
本機E-M1以前の時代の僅かな期間でのミラーレス機でも
高速連写は可能な機体があった。まあミラーレス機は構造上
連写に向くからだ。しかしそれらは電子シャッター利用で
あったり、バッファメモリーが少なく、ほんの20枚程度で
連写が打ち止めになったり低速化してしまっていた。
本機では、私の多くの使用条件において、秒10コマで、
連続数十コマの撮影が可能(注:スペック通りの96コマ
は無理だと思う)で、高速連写機の要件を満たす。
ただし注意しなければならないのは、ISO感度を高めたり
各種収差補正等をONとすると、とたんに連写速度や連続
撮影枚数が低下する機体が、他社機にもオリンパス機にも
色々とある事だ。
AF追従とレンズのAF速度(超音波モーターの有無や開放F値
の暗さ)による連写速度低下はやむを得ないし、それは
MFやAF技法と設定等の複合で回避も可能だ。収差補正は
使うレンズの選択で回避が出来るが、ISOだけはどうしようも
無い、これを高めないと撮れない場合も多々あるからだ。
だが、本機E-M1の場合はISO感度を高めても連写性能の
低下は殆ど起こらない、まあ実用範囲と言えよう。
(ただし、ISO6400以上に高めると、連写時のコマ毎の
AWBが非常にバラつき、色味がデタラメになる。でもまあ
偽色発生等、技術的限界もあるので、これは重欠点とは
言えないであろう)
他の特徴だが、一般に良く言われるローパスレスとか
防塵・防滴等の高耐久性はどうでも良い事だろう、
それらは本機だけの唯一の特徴では無いし、必要な
撮影状況に応じて、カメラを使い分ければ良いだけだ。
機能、性能面では、ほとんど不足を感じないし、
頻繁なファームアップで新鋭機(例:E-M5 MarkⅡ等)
と同等の新機能も搭載されてきている。
本機は2013年製(本シリーズ記事で定義する第三世代機)
ではあるが、後年2015年以降の第四世代機と比べても性能上
の遜色は殆ど無く、高性能化の先駆けとなった機種である。
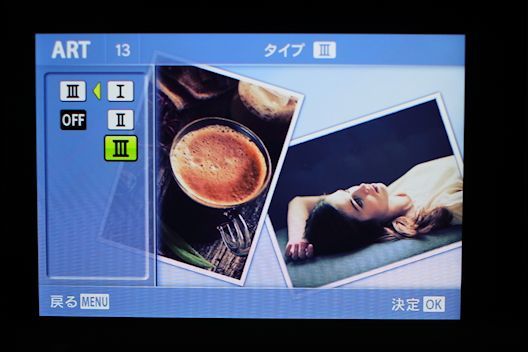
アートフィルター(エフェクト)の充実が好ましい。
個々のエフェクトはパラメーターが微調整可能であり、
作画のバリエーションがかなり大きく、おまけに
「アートフィルターブラケット」により、利用者が
思いもしない偶発的な表現効果を得る事も可能だ。
(=アンコントローラブル技法、Lo-Fi技法、等に関連)

である。ボディ前面にもアサイナブルボタンが存在するし
ボタンやダイヤルのカスタマイズ性は高く、動画録画開始
ボタンも他機能に変更可なので、静止画主体の使用法で
役に立つ。
ただし、多機能ゆえに、旧来からのメニュー操作系では
もう階層が深くなりすぎていて、操作系全般はあまり
優れているとは言えない。
オリンパス機伝統の「スーパーコンパネ」ですらも、もう
はみ出して入らない機能が多々あるし、そういうGUI部分の
カスタマイズ性は皆無だ(注:他社機はたいてい編集可)
ただまあ、スーパーコンパネがEVF内に表示できて、
十字キーを用いて「ファインダーを覗いたままカメラ設定
の変更操作が可能」という点は、本機およびミラーレス機
全般での大きな長所だ。
特に本機は「望遠母艦」にしたい、と考えていたので、
これが出来ないと、一々カメラの構えを解いて、背面の
モニターを見て選んでは非効率的だし、最悪なのは
「タッチパネルでないと操作ができない」といった仕様だ。
それは、構え、視線、動線、重量バランス等、全ての点で、
そんな操作系は有り得ない。なお、本機の場合はタッチ
パネルでしか操作が出来ない設定項目は無いので、勿論、
タッチパネル操作機能は無効化して封印している。
それと、一眼レフでは、SONYのαフタケタEVF機以外では
ファインダー内の設定変更操作が(殆ど)出来ない。
よって、頻繁にカメラ設定を変更しなければならない撮影
用途においては、実は一眼レフはあまり有益な機材では無い。
ましてや重たいシステムだ、大型の望遠レンズを装着時に
一々ファインダーを覗く構えを解かないと何もカメラ設定が
できないのは、撮影効率の面からは好ましく無い話なのだ。
三脚を立ててならば問題回避できるのだろうが、本ブログ
では開設当初から概算で99.8%は三脚は使用していないし、
現代では三脚を使うユーザーの方がむしろ稀である。
いつまでも古い撮影技法を元にカメラを設計するならば、
(=他社では良くある)それが最も大きな問題点であろう。

優れた方式だ。他社機では、ダイヤルの物理的なロックを
強要される場合があり、それは論外の機構と操作性だ。
総合的には本機の操作性・操作系はギリギリセーフでは
あると思うが、勿論、高得点を与えられる状態では無い。
他の特徴としては、この時代の前後の多くのオリンパス機
はバッテリー(BLN-1)が共通で使えるメリットがある。
本機の中古を私が選択した理由の1つで、この機体には
バッテリーが3個も付いていたからだ、他機への流用を
含め、これで予備バッテリー数としては十分だ。
なお、本機E-M1の撮影可能枚数は、CIPA準拠では350枚
との仕様で、少々物足りないように思うかも知れないが、
いつも言うように、まず、この値の5~6倍は撮る事が
目標値である。
本機の場合は、フラッシュを一切使わない事や、高速
連写機でもある事から、2000枚以上は楽に撮れる。
個人的なルール上としてはこれで合格だが、高速連写機
における業務用途でのバッテリーの持ちとしては、1日で
6000枚位が必要なケースもあるので、そうした際には
予備バッテリーは必須であろう。
それから、保存されるファイル名だが、下4ケタが連番
になるのは普通だが、本機では上3ケタを撮影日にする
事が出来る、これは写真整理の際になかなか便利だ。
なお、1日に1000枚以上の撮影をした場合でも、フォルダー
は自動更新される事は無い。(これはこれで良い、他社機
では、大量に撮影すると、勝手にフォルダーが更新される
事があるが、何故それが必要なのか全く意味不明だ)
----
さて、このあたりで再度使用レンズを交換しよう。

(ハイコスパ第16回記事等)
MF時代のオールドレンズである。本機E-M1装着時には
OM→μ4/3アダプターを用いれば良い。
電子接点でのやり取りは無い為、電子アダプターの
必要性は無い(そもそもOM用の電子アダプターは無い)

よっては手ブレ補正機能が欲しくなると思う。
本機E-M1では、手動で焦点距離を設定すれば、一応
内蔵手ブレ補正機能が有効になる。
ただし、設定は毎回強要される訳ではなく、メニューの
奥から掘り出して設定する必要があるので、レンズ交換
時の入力忘れは要注意だし、入力後もファイダー内に
設定した焦点距離が表示されない(純正レンズの場合のみ
焦点距離が表示される)という、お粗末で排他的な仕様
なので、ますます設定忘れは要注意だ。
本機E-M1には、AUTO ISO時の感度切り替えシャッター速度
(=低速限界)の設定が無く、概ね1/125秒前後で固定的に
切り替わる。よって、撮影条件によっては、このクラスの
(100mm以上)望遠レンズでは、内蔵手ブレ補正機能が
あっても、初級者層等では手ブレしてしまう恐れがあるし
撮影条件によっては、中上級層でも手ブレ対策は必須だ。

最大の課題と感じるのは、本機の「排他的仕様」だ。
「排他的仕様」の意味詳細は長くなるので割愛する。
(いずれ匠の写真用語辞典記事で解説予定)
まあつまり、オリンパス純正(又はμ4/3規格準拠)
かつ、特定の仕様条件を満たすレンズ等を使わない限り、
最高性能(性能仕様、便利機能、操作性、操作系等)
が発揮できない、という事である。
チラリと前述したが、銀塩用OMレンズをアダプターで
使用しただけで、本機の性能は、もうヘロヘロに落ちる。
細かい操作系上の矛盾や機能制限が多々発生する為、
あまり汎用的な母艦としての用途には向かない。
(注:この点では、同時代の PANASONIC DMC-G6 2013年
本シリーズ第10回記事、の方が、やはり「望遠母艦」と
して向いている様子だ)

まずは機能面。
ISO感度だが、ベース感度が200と高目である、
一応マニュアル感度変更でISO100が使えるのだが、
AUTOではそれは無理なので、大口径レンズとの相性が
良く無い。ISO感度変更の操作性も、あまり便利という
訳でも無い。
また、前述のようにAUTO ISOの低速限界(切り替わりの
シャッター速度)が変更できない。(なお、この問題は
後年のオリンパス機の一部では若干の改善が見られる)
これにより、アダプターでMF望遠レンズ使用時等では、
手ブレのリスクが増大してしまう。
内蔵手ブレ補正機能は有効だが、(機械式)マウント
アダプター使用時には、前述のように入力操作が煩雑だ。
加えて、どうも内蔵手ブレ補正は、カタログ通りの
高性能では無く、望遠+高速連写等、厳しい条件では容易に
ブレが発生、手動でISO感度を適正に変更する必要がある。
OVFシミュレーションの機能が新設されているが、これの
有効な使い道は、個人的には良くわからない(汗)
EVF自体の解像度は236万画素で、この時代としては、
トップクラスであろう。
また、EVFの倍率も高くて良い。ただし仕様の1.48倍は
フルサイズ換算では0.74倍となるので、MFで使う
ケースも考えると、もう少しだけ大きい方が望ましい。
(銀塩MF機では0.8倍~0.9倍が普通だ)
この仕様は、後年のE-M5 MarkⅡ等と同じであるが、
銀塩機並、を目論んだとしても、いずれの機体用にも
(別売の)「拡大アイカップ」オプションが存在しない。
なお、旧来の4/3機のEシリーズでは、マグニファイヤー
(拡大)アイカップ「ME-1」が利用可能であった。
それと、EVFの色味やコントラストが悪い。
新鋭レンズを装着していても、なんだかコントラストが
低いオールドレンズを使っている雰囲気で好ましく無い。
これは、同時期の他社機と同じ236万ドット部品を使って
いるのにもかかわらず、他社機よりも劣る印象だ。
前述のOVFシミュレーションや、ピーキング時の背景輝度
調整機能、その他が新設された事で、EVFの表示画像に
対して、色味や輝度を調整する構造や、その画像処理の
アルゴリズムが入っているだろうから、そこの未成熟か?
(注:設定を色々変えても改善されない、それから、
同様な構造の、後年のOM-D E-M5 MarkⅡでも大きな
改善は無い)

メニューおよびモードダイアル動作が電子的に重い。
つまり操作してからワンテンポ遅れて反応するという感じ
であり、こういう点はフラッグシップ機としては、あまり
好ましく無い弱点である。
高級機であればあるほど、贅沢なCPUや電子回路を用いて
操作性、操作系的なレスポンスを上げる必要があるのだ。
さらに言えば、アートフィルターブラケットや連写機能を
用いて、バッファメモリーから記録メディアへの書き込みが
行われている最中には、露出モード変更等の操作が遅れて
反応する、この書き込み&モード変更の間の時間帯では、
結局のところ、ほぼ撮影が不能となる。
それと、背面の十字キーも形状が悪く、押しにくい事や
ボタン配置もどうも直感的では無いので、上記の操作の
反応の悪さと絡んで、ちょっとイラっとする場合がある。
また、マウントアダプター利用時には、ピーキング機能が
自動的には使えない、必ずどこかのFnキーにその機能を
アサインし、電源ONの度に、それを押さないと使えない。
加えて、モードダイヤルを廻し、ARTモード等に変更した
際にも、ピーキングが消え、Fnキーで再度呼び出さないと
ならない。

(例:VIVID等)は無効化するので、一々、元の設定に
戻す必要がある。
なお、マルチFn機能は操作系が若干不便で、ちょっとした
誤操作で、こうした機能がすぐ有効になり、一度でも
間違えて呼び出したら、もう上記と同じ状況だ。
また、メニューを送っていくと解説文が現れて鬱陶しい。
「モードガイド表示」をOFFにしてもこの文章は消えない。
別途調べると「INFO」ボタンを長押しする事で消える事が
わかったが、操作系的に不合理で非直感的だ、すなわち
こうした細かい点は、良く練れていない。
ボデイ本体の課題だが、大型レンズを装着する可能性も
ある為、もう少し大型の方が好ましい。
特にグリップサイズが小さい事が気になる。(なお、この
点は後継機E-M1 MarkⅡでは若干改善されている)
それから、背面モニターがティルト式であり、バリアングル
では無いので、裏返せない(過酷な撮影環境とか、暗所での
イベント系の撮影時、モニターを光らせたくない、撮った
写真を周囲の観客見られたくない場合等で不便だし、
勿論、「縦位置ローアングル撮影」も厳しくなる)
まあ、総合的には「排他的仕様」により、μ4/3以外の
レンズを汎用的に使おうとした場合に、操作系等に細かい
課題が沢山出てくる。
本記事では、μ4/3レンズ、4/3レンズ、OMレンズの
3本を使用しているが、どうも、本機E-M1を「望遠母艦」と
する目論見は、上手く行きそうにない(汗)

評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★★★☆
【描写力・表現力】★★★☆
【操作性・操作系】★★☆
【アダプター適性】★★
【マニアック度 】★★★☆
【エンジョイ度 】★★★☆
【購入時コスパ 】★★★☆ (中古購入価格:43,000円)
【完成度(当時)】★★★☆
【仕様老朽化寿命】★★★☆
【歴史的価値 】★★★★☆
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】3.4点
総合点は悪い点数では無く、性能面や機能面では
あまり不満は無い事であろう。
だが、フラッグシップと言う割りには、操作系を始めと
して、細かいところに目が行き届いた配慮は感じられず、
「さすが高級機!」と思える要素は殆ど無い。
μ4/3純正レンズを使った際に、優れた高性能を発揮
できるのだが、かと言って、業務用機として使える
レベルあるいは機材環境では無い。
(注:レンズ環境については、後年にM.ZUIKO PRO
シリーズのラインナップを展開して充実しつつあるが
高付加価値化商品のためにコスパが悪すぎるので、
現状では購入していない。同等のスペックであれば
一眼レフ用での過去資産があるからだ)
高性能な趣味撮影専用機体としての目的が良くマッチする
機体ではあるが、逆にMFレンズをアダプターで使用時の
課題が多く、母艦性能に劣る(この点が上記の評価では、
「アダプター適性」の評価の低さに繋がっている)
ちょっと中途半端な立ち位置に思える。対策としては、
本機を、どういった目的に使うのがベストなのか?という
「用途開発」が試行錯誤的に必要になってくるだろう。
まあでも、歴史的価値の高いカメラだ
発売後時間が経って中古相場も十分こなれていて、コスパ
が良い、減価償却ルール(1枚2円の法則等)も、あっと
言う間に完了しているので、そこから後は、高耐久性を
活用して過酷な環境での使い潰し型のカメラにしてしまえば
良い。まあ、オリンパス党であれば必携のカメラだと思う。
---
次回記事は、引き続き第三世代のミラーレス機を紹介する、