本シリーズでは、所有しているミラーレス機の本体の詳細を
世代順に紹介している。
今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は第一回
記事参照)のFUJIFILM X-E1(2012年)について紹介しよう。
![c0032138_17401875.jpg]()
Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を選択する。
(ミラーレス・マニアックス第74回、名玉編第2回記事)
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進める。
![c0032138_17401771.jpg]()
まず、基本的にFUJIFILM社はフィルムメーカーである。
カメラも多数販売しているが、全てが自社製品であるとは
思い難い、つまり他社OEM製品の場合も多々あるという事だ。
![c0032138_17401812.jpg]()
コラボレーションである。その為、一般的な35mm判フィルム
(135フィルム)用のカメラは勿論、
110フィルム(ワンテン),120フィルム(ブローニー)、
ハーフ判、IX240フィルム(APS)、8x11mm判(ミノックス)、
インスタントフィルム(チェキ)、8mmフィルム、
パノラマ判(TXシリーズ)そして、ご存知「写ルンです」等、
実に多種多様のフィルムフォーマットに対応したカメラが
過去に発売されていた。
本機X-E1の源流を探ろうとすれば、まあ、やはり35mm判
フィルム使用のMF一眼レフであろうか。
まずは1970年、フジカST-701というM42マウントの
MF一眼レフが発売される、露出計もAE機構も無いシンプルな
カメラであった。M42は、それ以前からユニバーサル(汎用的)
マウントとして、PENTAXを始め多くのメーカーが採用していた。
(その時点では他社とのレンズ互換性があった)
だが、時代は既にM42マウントの終焉期であった、
M42陣営以外の、バヨネット・マウントを採用するメーカー
(例:ニコン等)では、この頃から開放測光、AE(絞り優先)
等の自動化新機能をカメラに搭載していく。
![c0032138_17401782.jpg]()
M42陣営の各社も、本来汎用的であった筈のM42に独自の改良を
加えて自社専用のマウントとし、それで絞り優先AE等に対応
しようとする(代表的機種として1971年のPENTAX ESがある)
FUJIFILMもこのトレンド(時流)に乗る為、M42マウントを
自社独自で改良、開放測光のフジカST-801(1972年)や、
絞り優先機のST-901(1974年)を発売する。
うち、ST-801は所有していた事があったが、デジタル時代に
なって、もう使わないだろうと譲渡してしまった。
ST-901を購入しなかったのは独自性が強く、M42の他社互換性
が無かったからである。
以降、1970年代を通じて、このM42改マウントMF一眼レフが
FIJIからは発売され続けた。
![c0032138_17401808.jpg]()
後期の特殊M42マウント版が「EBCフジノン」という名称に
変わっているが、この後期型レンズはM42マウントと酷似した
形状だが、FUJI独自のものである。
この為、他社のM42マウントのカメラボディ、あるいは簡易な
アダプターで一眼レフに装着するのは極めて危険である。
装着できない、又は外れなくなる、というリスクがあるので
使うとしても、安全なミラーレス機用M42マウントアダプター
を用いるのが良い。それらは、仮に外れなくなったとしても
アダプターが1個、そのレンズ専用になるだけで、カメラ本体
への影響は無い。
(過去関連記事:ミラーレス・マニアックス第45回
「E.ZUIKO AUTO-T 200/4がRTSⅢから外れなくなった事件」、
およびミラーレス第73回、フジノンT 135mm/f3.5参照)
![c0032138_17402383.jpg]()
(注:本家のPENTAXも既にKマウントに移行済み)
FUJIFILMは独自のバヨネットマウント(AXマウント)機の
発売を始める、しかし、このシリーズは1980年代前半迄で
販売が終了し、その後、時代は1985年のミノルタα-7000
より、一気にAF一眼レフ全盛期となってしまう。
他社もいっせいにAF一眼レフ化に追従したが、FUJIFILMは
この流れには乗らなかった、以降、1980年代から2000年代を
通じ、FUJIは35mm判銀塩一眼レフを発売していない。
![c0032138_17402339.jpg]()
含む)等、大衆向けだが、どこかマニアックなコンパクト機
(35mm判)を多数発売していた。
私は、トラベルミニ(2焦点)、ディアラ(広角高画質機)、
ビューン(特殊連写機)等を所有していて、結構この頃の
FUJIFILMのコンパクト機は好みであった。
1990年後半からは、当時流行したIX240(APS)フィルム機と
して多数の「エピオン」シリーズが発売される。
まあ、フィルムメーカーであるから、APSフィルム販売促進の
為にも、APS判のカメラを沢山作る必要があったのだろう。
(同様に、中判カメラの発売も継続されていた)
ちなみに、これらのAPSカメラは2000年頃には極めて安価な
在庫処分価格となっていた、カメラ本体では儲けず、
フィルムや現像代で儲ける、という「損して得取れ」的な
ビジネスモデルが出てきた(例:携帯電話本体は無料だが
通話料で儲ける)のは1990年代後半以降の市場の特徴だ。
APSの登場とともに、システマチックな自動現像機が普及し、
巷では「0円プリント」方式が普及したのも、この時代だ。
![c0032138_17402402.jpg]()
発売を始める、最初のカメラはFinePix700(1998年)であり、
高画質であった事から人気があり、当時のデジカメ市場では、
カシオ、オリンパスと共にシェアを分け合っていたと思う。
まあでも、フィルムメーカーがデジカメを発売するというのは
大英断だろう。なかなか自社のこれまでのビジネスモデルを
否定するような商品は出しにくい。しかしこの英断は正解で
あったと思う、もし銀塩フィルムだけにしがみついていたら、
その後10年でFUJIFILM社は間違いなくジリ貧だ。
まあ、デジタル時代が来る事は明白であったので、当時から
FIUIFILMも経営の多角化を初めていた、産業用フィルムとか、
医療、化粧品等の分野への技術応用である。
それでもフィルム機の発売はフィルムメーカーである以上、
簡単に辞めるわけにはいかない、2000年代に入ってからも、
マニアックな高級機KLASSE(クラッセ)シリーズ、高機能な
SILVI(シルヴィ)、さらに、やや特殊なNATURA(ナチュラ)
シリーズ(ISO1600のナチュラフィルムを使うのが前提)等を、
2000年代後半まで発売を継続していた。
![c0032138_17402345.jpg]()
FinePix F10(2005年、デジタル・コンパクト・クラッシックス
第2回記事参照)など、Fフタケタシリーズの販売を継続、
また、スタイリッシュな「Z」シリーズも人気があった。
(注:この時代のFUJI機は、xDカード使用の為、現在では
記録メディアの入手が難しい)
2000年代後半にはロングズーム機 Sシリーズの発売も開始
S200EXR(2009年,コンパクト第3回記事)等がある。
(注:この頃からはSD系カードが使用可能だ)
その後、2010年代にはXシリーズとして高級路線に転進、
2011年には、ハイエンドコンパクトのX100や、高級機X10、
ロングズーム機X-S1を市場に集中投下する。
これらの高級コンパクト機の翌年に発売されたレンズ交換式
(すなわちミラーレス)一眼カメラが、X-Pro1(2012年)と
本機X-E1(2012年)である。
![c0032138_17402377.jpg]()
時代に到達した。
すなわち、FUJIのレンズ交換式カメラは(中判カメラの
G系シリーズと特殊なTXシリーズを除き)1980年代前半の
AXシリーズから、およそ30年ぶりの発売になる訳だ。
この間FUJIは、一般的な35mm判銀塩一眼レフもデジタル一眼
レフも1台も発売していない。(注:NIKON機ほぼそのものの
FinePix Proシリーズのデジタル一眼レフは存在した)
他記事でオリンパスが2003年に約20年弱ぶりにフォーサーズ
機で(デジタル)一眼レフ市場に参入した事を「後発だ」と
書いたのであるが、FUJIの場合は、それ以上の間隔だ。
私は、2011年の高級コンパクト機X100等発売の時は
「ふむふむ、FUJIもやるなあ」と好意的な印象で捉えていた、
なにせ、ミラーレス機やスマホの台頭により普及コンパクト機
の未来は無いと思っていたから、このような戦略転換は必須で
あろう。
そして、フィルムの絶滅という大危機を見事に乗り越えた
フィルムメーカーであるから、そのあたりの変わり身の早さは
見事だとも思っていた。
![c0032138_17402932.jpg]()
なると「大丈夫かいな?」と、むしろ心配であった。
まあ、2000年代末に、パナソニック、オリンパスが順次
ミラーレス(μ4/3)市場に参入、2010年代になってからも、
ソニー(NEXが2010年)、ペンタックス(Qが2011年)、
ニコン(V1等が2011年)と各社の市場参入が相次ぎ、私が
ミラーレス第二世代と定義した「普及期」になったのだが、
まさかFUJIまで参入するとは思っていなかった。
「だって、何十年も一眼など作っていなかったでは無いか」
という印象であったし、その間に作っていた銀塩AFコンパクト
やデジタルコンパクト機も、完全な自社開発とは思えず、
他社OEMであった事は、巷では良く知られた話だったからだ。
![c0032138_17403062.jpg]()
興味の対象は、むしろFUJIコンパクト機の方のXシリーズ
であり、ロングズーム機X-S1(コンパクト第4回記事)や、
超高性能の隠れた名機XQ1(2013年、コンパクト第4回記事)
を入手して、実用機として機嫌良く使っていた。
しかし、2014年、予想すらしていなかった事件が起こる。
FIJIがXマウントで、ミノルタSTF135/2.8以来16年ぶり
となる、アポダイゼーション光学エレメントを搭載した
初のAFレンズ、XF56mm/f1.2R APDを発売したのだ。
(ミラーレス・マニアックス第17回、第30回、名玉編第3回
等で実写紹介、LAOWA記事でも紹介)
これは衝撃的な事件だ、まあでもそのあたりはこの仕組みの
レンズの事に詳しくない人には、全く関係無い話でもあった
であろう(興味がある人は、上記記事群を参照されたし)
XF56/1.2R APDは、定価20万6000円+税と非常に高価なレンズ
であったので1年くらいは指を銜えて見ているだけであったが
2015年になって中古が出てきたので、それを購入した次第だ。
レンズはこれで良い。ボディだがXマウントの何かを購入する
しか無い、Xマウントレンズは他社機には装着不能だからだ。
最初期のX-E1が中古市場で適価な相場で販売されていたので
レンズと合わせて購入した次第だ。
だが、未成熟なカメラである事は、事前に予想はついていた、
だからこそ、しばらくこのシリーズは無視していたのだ。
![c0032138_17403753.jpg]()
あった。その事については、ミラーレス・マニアックスの
シリーズ記事で、さんざん酷評したので、もうあまり書く気が
しない。何十年ぶりに一眼を作ったのでは、まあやむを得ず、
むしろ少々可哀想になってきたのだ。
それに、大体分かっていながら購入したのは自分自身の問題だ、
「悪女」である事は、およそ知っていたのに、XF56/1.2APDの
「色香」に、フラフラと吸い寄せられてしまったのだ(汗)
まあしかたない、後継機を買えば良さそうなのだが、実の所
後継機も、私の求めるカメラの水準には達してはいない。
結局、X-E1は少なくも減価償却が終わるまでは、その低性能に
付き合わないとならない、それが購入した責任だ。
(注:減価償却は既に終了して、後継機も所有している)
![c0032138_17403094.jpg]()
どんなカメラでも欠点ばかりという訳ではないのだ。
まず、この時代では珍しい高精細EVFを搭載している事、
この点ではミラーレス機として使い易い部類となる。
ただし色々とクセがある、ピーキング機能は低精度であるし、
半押しでそれは無効となる、そして半押しはプレビュー動作
や、勿論AF駆動、そしてAEロックなど、様々に関連するが、
そのあたり全般の動作を良く理解して使う必要がある、
絵作りはとても良い。特にベルビア(高彩度)モードや
モノクロ系モードは、なかなかの発色で、他のミラーレス機と
比べてもアドバンテージがある、さすがフィルムメーカーだ。
ただしエフェクト(デジタルフィルター系)は一切無いので
レガシー(注:この場合では”古い”という意味だ)な
写真撮影技法にしか使えない。
ところで、FUJIFILMは2018年に、モノクロフィルムの販売を
終了する予定であり。もはやFUJIのモノクロの発色は
デジタル機の中でしか味わえないという事だ。
まあでも、電子楽器の世界でも、今では生産されておらず
入手も困難な古い楽器の名機の音色をサンプリングして、
現代のシンセ等に搭載している事はごく普通であるが・・
![c0032138_17403856.jpg]()
シャッターダイヤルとの組み合わせて、各々のA(自動)位置
を選択することで、P/S/A/M切り替えを不要とする。
この仕組みは私の記憶している限りでは、ミノルタXD(1977年)
やマミヤZE-X(1981年)に搭載されていた。(ZE-Xは所有して
いたが故障廃棄)
XDやZE-XではA位置の組み合わせ式以外にも、クロスオーバー・
システムといった、極端な絞りやシャッター速度設定で露出値が
限界を超えて合わなくなった際に、自動的にそのいずれかを
調整して対応するという先進的な露出機構が内蔵されていた。
次いでの搭載機はPENTAX MZ-5/3シリーズ(1995~1997年)
であっただろうか? これらの機種は、それ以前のZシリーズに
搭載された特異な露出機構「ハイパー操作系」が極めて難解で
あった為(デジタル一眼クラッシックス第6回K10D参照)
より安易な操作系にダウングレードされたカメラだ。
(銀塩一眼レフ第21回記事、予定)
で、この方式は、PSAMダイヤルを廃する事が出来るので、
X-E1では、その代わりに露出補正が直接制御できる
アナログ式ダイヤルを備えている。
![c0032138_17513308.jpg]()
とアナログダイヤルとは大きくその効能が違う。
どちらが良い、悪いではなく、それぞれ長所短所があるのだ。
アナログダイヤルの長所=
・ダイヤルを見ただけで設定値が視認できる
・電源を切っても、設定値がずっと残っている(不揮発性)
・電源OFF時にも設定操作が可能
・指の感触などで操作がしやすい
デジタル(電子)ダイヤルの長所=
・設定値を電子的に記憶(セーブ)でき、それを任意に
呼び出す事(ロード)ができる、その際、ダイヤルには
指標が無いので、見た目と実際の設定値に矛盾が起きない
・絶対値が異なる複数の設定変更に対応できる、
例をあげれば、開放f値1.4のレンズを、開放f値4のレンズ
に交換したとしても、絞り変更ダイヤルは、そのままの位置
で両者の数値に対応できる
短所については、お互いの長所を逆にしてみればわかる。
また、これはダイヤルに限らず、ピントリング等も同様だ。
ピントリングをデジタル式ダイヤル、つまり、無限回転式に
した場合は、ピント絶対位置の記憶と呼び出しに矛盾が無い為
AFとMFを任意のタイミングで切り替えるシームレス操作が出来る。
反面、見た目ではピント位置がわからず、加えて指の感触でも
ピント位置がわからない(最短や無限遠で止める事ができない)
これが、それぞれの長所短所である。
X-E1のダイヤル操作性は、アナログの長所を持つのであるが
上記の観点からは短所にもなりうる、例えば、カメラを
運搬中や構えた際等で、知らないうちに露出補正ダイヤルが
動いてしまっている事がある。これは不揮発性、つまり、
ずっと維持されてしまうから、露出補正がかかったままで
撮影してしまう可能性もある。まあ、露出補正スケールの
インジケーターが常にEVF内に表示されているから、
それを見れば露出補正がかかっている事はわかるのだが、
自分が動かした覚えがないのに動いてしまっている場合は、
そのインジケーターを見落としてしまうリスクもあるだろう。
あるいは「1枚だけ露出補正をかけ、次の写真や電源OFF時には
自動で露出補正ゼロに戻る」という自動機能が実現できない。
別のケースだが、通常は絞り優先AEとして使う為にシャッター
ダイヤルはA位置で用いる。そして絞りを手動で廻すのだが
この際、絞り値の最小値を1段越えた所がA位置となるので
その際は、A+Aで、露出モードはP(プログラムAE)となる。
しかし、レンズによって絞りの最小値は異なり、f16の場合も
あればf22やf32の場合もある、なので、スローシャッター
表現等を狙って、カチカチと、できるだけ絞り込んで行くと
(絞り過ぎの回折現象での解像度低下は気にする必要は無い、
画質よりも、あくまで表現を優先するべき事は言うまでも無い)
最小絞り値を越えて廻しすぎてしまい、Pモードに入って
しまって、勝手にf5.6とかになり「なんじゃこりゃ」と
思う場合もある。
![c0032138_17403831.jpg]()
機構があると良いかもしれない、そうであれば指の感触で
絞りを最小から最大まで自在に使える。
なお「EVFの中に絞り値くらい出るだろう?」とは思うなかれ、
EVFはカメラを構えてから見るものだが、効率的なカメラ操作は
カメラを構える前に、必要と思われる絞り値を想定し、それを
指の感触又は直接絞り値を見て設定し、さらに、MFレンズの
場合であれば、被写体距離に応じピントリングも指の感触で
だいたいの位置に変えながらカメラを構えてEVFやファインダー
を覗く、その時点では絞りもピントも殆ど合っている状態に
なっているので、もう一々様々な設定値は見る必要も殆ど無い、
この流れにより、短時間で撮影を行う事ができるのだ。
ズームレンズ等を、ファインダーを見ながら画角を色々と
変えたり、絞りを変えてみたりするのでは時間がかかって
しかたがない。ビギナークラスで、やたらシャッターを切る
タイミングが遅いのは、写真を撮影する前に「どんな写真を
撮りたいのか」を、何も考えていないからであろう。
写真は、カメラを構えてから数秒以内に撮る事が望ましい、
そうでないと重要な撮影機会(注:あえてシャッターチャンス
とは言わない、その用語は一般的な意味においては適切では
無いと思うからだ=被写体に振り回されている印象が強いから)
を逃してしまう。
![c0032138_17531487.jpg]()
あるものの、アナログライク(似ている)で、悪くない。
ただ「操作系」すなわち(デジタル)写真を撮る為に必要な
様々な設定操作全体の構造(ユーザーインターフェース)は
劣悪だ。ただ、その話は、さんざん他記事で説明しているので、
ばっさり割愛する。
![c0032138_17403852.jpg]()
写真を撮るという行為に精通していないと作り込めない。
「何十年も一眼を作っていないメーカーが、そう簡単にカメラ
を作れるはずが無い」という第一印象は、そういう意味も多々
あったからだ。
なお、本機X-E1の最大の問題点を一応あげておけば、
AF/MFとも写真撮影の為に必要な性能を持っていない点である。
前述の本機を買うきっかけとなったXF56mm/f1.2R APD
を装着した場合は特に酷く、AFでもMFでもピントをちゃんと
合わせる事ができない。
その時点で迷った事は、
1)Xマウントのレンズをそれ1本だけでやめておき、被害(?)
を最小限に留めるのか、あるいは
2)カメラを新型の高価なもの(例えば像面位相差AF搭載機)に
買い換え性能アップさせるか、はたまた、
3)AF負担が少ないレンズを若干買い足して、早期に減価償却を
完了させ、その頃に、相場が下がった後継機を買うか、
という選択肢であった。
結局3)を選び、Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を買い足した
次第である。本機X-E1は描写力は優れているので、発色等の
傾向に優れたレンズを用いれば、さらに本機の長所が強調され
結果的に撮るのが楽しくなり、減価償却が推進されるという
理屈である。
![c0032138_17401813.jpg]()
精度はだいぶマシであるが、それでも厳しい事は確かだ。
なお、Touit 32mm/f1.8だが、描写力は悪くは無いけど、
逆光耐性が低く、かつ価格が高くてコスパが悪い。
よって、ミラーレス・マニアックスのシリーズでは、名玉編に
ノミネートされたのであったが、ハイコスパレンズの記事には
登場する事が無かったレンズだ。
![c0032138_17550124.jpg]()
XマウントレンズはFUJI専用で他機との互換性やアダプターでは
使用出来ない、ただし勿論Xマウントにアダプターを介して
MFレンズ等を装着する事は可能だ。
約1600万画素、X-Trans CMOS(ローパスレス)
感度はISO100~25600(拡張時)、ただしAUTO ISOでは
上限も下限も制限される。これは大口径レンズ等使用時に
低ISOが必要な場合、極めて使い難い。
ISO感度自動切り替えシャッター速度の低速限界が設定できる
本機には手ブレ補正機能が無いので、望遠レンズ使用時には
これを適宜高めておくと便利だ。
なお、「ISO変更ボタンが無い」という困った仕様であり、
たった1個しかない貴重なFnボタンをそれにアサインするか、
コンパネから変えるか、メニューから直接変更するしかない。
![c0032138_17403859.jpg]()
お粗末さだ、ちなみにAF精度が足りない為、通常レンズでも
近接撮影時には固定十字キーでマクロモードに切り替えなくては
ならないし、かつ1種類のマクロしかないのに選択操作が必要だ。
1990年代のAFコンパクト機なみの古い操作系仕様だ。
最高シャッター速度1/4000秒、低ISOが使い難いので不満だ。
なお、電子シャッター機能は搭載されていない。
ドライブ性能は、高速秒6コマ、低速秒3コマ、
これらは何故か非公開だ、仕様表に載せるのを忘れていたので
あろう、だがまあ悪くは無い。
ドライブ切り替えでは、動画は勿論、ぐるっとパノラマモード
もある。
![c0032138_17402387.jpg]()
低い、そしてこの時代のモニター表示部品(ソフト?)には
バグがある模様で、本機および他社の数機種では、JPEG画像
の再生時に本来の解像度が得られていない(プログレッシブ
JPEG形式が途中で再生停止してしまうような感じ)このため
撮影後のピント確認がわからず、ますますAF/MF性能が落ちる
という困った状態になっている。
エフェクトは一切無いが、前述のとおり優れたフィルム
シミュレーションモードがある。
![c0032138_17403822.jpg]()
だが、ダイヤル併用で指の位置が飛び、意外に使い勝手が悪い。
なお、通常メニューはメニュー位置記憶すらなく極めて不便だ。
![c0032138_17571830.jpg]()
カメラの仕様上では、単焦点レンズを使うのが適切であるから、
ここは大いに不満である。
そして、数値スペックに関しては、本記事で述べてきた
使用上の長所短所からすると、ある意味、どうでも良い事だ、
こういうカタログスペックだけを見て、カメラを評価する事は
絶対に無理である事は言うまでも無い。
![c0032138_17402968.jpg]()
評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★
【描写力・表現力】★★★★
【操作性・操作系】★★
【アダプター適性】★★
【マニアック度 】★★★
【エンジョイ度 】★★
【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:26,000円)
【完成度(当時)】★
【仕様老朽化寿命】★☆
【歴史的価値 】★★★
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.3点
残念ながら低得点だ、描写力・表現力以外の項目が全て
平均以下となってしまっている。
私自身、早目に後継機へリプレイス(交代)するのが良いと
思っていた(既にそうしている)
現在では中古も安価な機体ではあるが、今からの購入は
推奨できない。
購入していた場合であっても、本機の弱点を相殺できるような
適切なレンズ(広角気味の被写界深度が深いレンズ等)を
選んで装着する必要があるだろう。
次回記事は、引き続き第二世代のミラーレス機を紹介する、
世代順に紹介している。
今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は第一回
記事参照)のFUJIFILM X-E1(2012年)について紹介しよう。

Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を選択する。
(ミラーレス・マニアックス第74回、名玉編第2回記事)
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進める。

まず、基本的にFUJIFILM社はフィルムメーカーである。
カメラも多数販売しているが、全てが自社製品であるとは
思い難い、つまり他社OEM製品の場合も多々あるという事だ。

コラボレーションである。その為、一般的な35mm判フィルム
(135フィルム)用のカメラは勿論、
110フィルム(ワンテン),120フィルム(ブローニー)、
ハーフ判、IX240フィルム(APS)、8x11mm判(ミノックス)、
インスタントフィルム(チェキ)、8mmフィルム、
パノラマ判(TXシリーズ)そして、ご存知「写ルンです」等、
実に多種多様のフィルムフォーマットに対応したカメラが
過去に発売されていた。
本機X-E1の源流を探ろうとすれば、まあ、やはり35mm判
フィルム使用のMF一眼レフであろうか。
まずは1970年、フジカST-701というM42マウントの
MF一眼レフが発売される、露出計もAE機構も無いシンプルな
カメラであった。M42は、それ以前からユニバーサル(汎用的)
マウントとして、PENTAXを始め多くのメーカーが採用していた。
(その時点では他社とのレンズ互換性があった)
だが、時代は既にM42マウントの終焉期であった、
M42陣営以外の、バヨネット・マウントを採用するメーカー
(例:ニコン等)では、この頃から開放測光、AE(絞り優先)
等の自動化新機能をカメラに搭載していく。

M42陣営の各社も、本来汎用的であった筈のM42に独自の改良を
加えて自社専用のマウントとし、それで絞り優先AE等に対応
しようとする(代表的機種として1971年のPENTAX ESがある)
FUJIFILMもこのトレンド(時流)に乗る為、M42マウントを
自社独自で改良、開放測光のフジカST-801(1972年)や、
絞り優先機のST-901(1974年)を発売する。
うち、ST-801は所有していた事があったが、デジタル時代に
なって、もう使わないだろうと譲渡してしまった。
ST-901を購入しなかったのは独自性が強く、M42の他社互換性
が無かったからである。
以降、1970年代を通じて、このM42改マウントMF一眼レフが
FIJIからは発売され続けた。

後期の特殊M42マウント版が「EBCフジノン」という名称に
変わっているが、この後期型レンズはM42マウントと酷似した
形状だが、FUJI独自のものである。
この為、他社のM42マウントのカメラボディ、あるいは簡易な
アダプターで一眼レフに装着するのは極めて危険である。
装着できない、又は外れなくなる、というリスクがあるので
使うとしても、安全なミラーレス機用M42マウントアダプター
を用いるのが良い。それらは、仮に外れなくなったとしても
アダプターが1個、そのレンズ専用になるだけで、カメラ本体
への影響は無い。
(過去関連記事:ミラーレス・マニアックス第45回
「E.ZUIKO AUTO-T 200/4がRTSⅢから外れなくなった事件」、
およびミラーレス第73回、フジノンT 135mm/f3.5参照)

(注:本家のPENTAXも既にKマウントに移行済み)
FUJIFILMは独自のバヨネットマウント(AXマウント)機の
発売を始める、しかし、このシリーズは1980年代前半迄で
販売が終了し、その後、時代は1985年のミノルタα-7000
より、一気にAF一眼レフ全盛期となってしまう。
他社もいっせいにAF一眼レフ化に追従したが、FUJIFILMは
この流れには乗らなかった、以降、1980年代から2000年代を
通じ、FUJIは35mm判銀塩一眼レフを発売していない。

含む)等、大衆向けだが、どこかマニアックなコンパクト機
(35mm判)を多数発売していた。
私は、トラベルミニ(2焦点)、ディアラ(広角高画質機)、
ビューン(特殊連写機)等を所有していて、結構この頃の
FUJIFILMのコンパクト機は好みであった。
1990年後半からは、当時流行したIX240(APS)フィルム機と
して多数の「エピオン」シリーズが発売される。
まあ、フィルムメーカーであるから、APSフィルム販売促進の
為にも、APS判のカメラを沢山作る必要があったのだろう。
(同様に、中判カメラの発売も継続されていた)
ちなみに、これらのAPSカメラは2000年頃には極めて安価な
在庫処分価格となっていた、カメラ本体では儲けず、
フィルムや現像代で儲ける、という「損して得取れ」的な
ビジネスモデルが出てきた(例:携帯電話本体は無料だが
通話料で儲ける)のは1990年代後半以降の市場の特徴だ。
APSの登場とともに、システマチックな自動現像機が普及し、
巷では「0円プリント」方式が普及したのも、この時代だ。

発売を始める、最初のカメラはFinePix700(1998年)であり、
高画質であった事から人気があり、当時のデジカメ市場では、
カシオ、オリンパスと共にシェアを分け合っていたと思う。
まあでも、フィルムメーカーがデジカメを発売するというのは
大英断だろう。なかなか自社のこれまでのビジネスモデルを
否定するような商品は出しにくい。しかしこの英断は正解で
あったと思う、もし銀塩フィルムだけにしがみついていたら、
その後10年でFUJIFILM社は間違いなくジリ貧だ。
まあ、デジタル時代が来る事は明白であったので、当時から
FIUIFILMも経営の多角化を初めていた、産業用フィルムとか、
医療、化粧品等の分野への技術応用である。
それでもフィルム機の発売はフィルムメーカーである以上、
簡単に辞めるわけにはいかない、2000年代に入ってからも、
マニアックな高級機KLASSE(クラッセ)シリーズ、高機能な
SILVI(シルヴィ)、さらに、やや特殊なNATURA(ナチュラ)
シリーズ(ISO1600のナチュラフィルムを使うのが前提)等を、
2000年代後半まで発売を継続していた。

FinePix F10(2005年、デジタル・コンパクト・クラッシックス
第2回記事参照)など、Fフタケタシリーズの販売を継続、
また、スタイリッシュな「Z」シリーズも人気があった。
(注:この時代のFUJI機は、xDカード使用の為、現在では
記録メディアの入手が難しい)
2000年代後半にはロングズーム機 Sシリーズの発売も開始
S200EXR(2009年,コンパクト第3回記事)等がある。
(注:この頃からはSD系カードが使用可能だ)
その後、2010年代にはXシリーズとして高級路線に転進、
2011年には、ハイエンドコンパクトのX100や、高級機X10、
ロングズーム機X-S1を市場に集中投下する。
これらの高級コンパクト機の翌年に発売されたレンズ交換式
(すなわちミラーレス)一眼カメラが、X-Pro1(2012年)と
本機X-E1(2012年)である。

時代に到達した。
すなわち、FUJIのレンズ交換式カメラは(中判カメラの
G系シリーズと特殊なTXシリーズを除き)1980年代前半の
AXシリーズから、およそ30年ぶりの発売になる訳だ。
この間FUJIは、一般的な35mm判銀塩一眼レフもデジタル一眼
レフも1台も発売していない。(注:NIKON機ほぼそのものの
FinePix Proシリーズのデジタル一眼レフは存在した)
他記事でオリンパスが2003年に約20年弱ぶりにフォーサーズ
機で(デジタル)一眼レフ市場に参入した事を「後発だ」と
書いたのであるが、FUJIの場合は、それ以上の間隔だ。
私は、2011年の高級コンパクト機X100等発売の時は
「ふむふむ、FUJIもやるなあ」と好意的な印象で捉えていた、
なにせ、ミラーレス機やスマホの台頭により普及コンパクト機
の未来は無いと思っていたから、このような戦略転換は必須で
あろう。
そして、フィルムの絶滅という大危機を見事に乗り越えた
フィルムメーカーであるから、そのあたりの変わり身の早さは
見事だとも思っていた。

なると「大丈夫かいな?」と、むしろ心配であった。
まあ、2000年代末に、パナソニック、オリンパスが順次
ミラーレス(μ4/3)市場に参入、2010年代になってからも、
ソニー(NEXが2010年)、ペンタックス(Qが2011年)、
ニコン(V1等が2011年)と各社の市場参入が相次ぎ、私が
ミラーレス第二世代と定義した「普及期」になったのだが、
まさかFUJIまで参入するとは思っていなかった。
「だって、何十年も一眼など作っていなかったでは無いか」
という印象であったし、その間に作っていた銀塩AFコンパクト
やデジタルコンパクト機も、完全な自社開発とは思えず、
他社OEMであった事は、巷では良く知られた話だったからだ。

興味の対象は、むしろFUJIコンパクト機の方のXシリーズ
であり、ロングズーム機X-S1(コンパクト第4回記事)や、
超高性能の隠れた名機XQ1(2013年、コンパクト第4回記事)
を入手して、実用機として機嫌良く使っていた。
しかし、2014年、予想すらしていなかった事件が起こる。
FIJIがXマウントで、ミノルタSTF135/2.8以来16年ぶり
となる、アポダイゼーション光学エレメントを搭載した
初のAFレンズ、XF56mm/f1.2R APDを発売したのだ。
(ミラーレス・マニアックス第17回、第30回、名玉編第3回
等で実写紹介、LAOWA記事でも紹介)
これは衝撃的な事件だ、まあでもそのあたりはこの仕組みの
レンズの事に詳しくない人には、全く関係無い話でもあった
であろう(興味がある人は、上記記事群を参照されたし)
XF56/1.2R APDは、定価20万6000円+税と非常に高価なレンズ
であったので1年くらいは指を銜えて見ているだけであったが
2015年になって中古が出てきたので、それを購入した次第だ。
レンズはこれで良い。ボディだがXマウントの何かを購入する
しか無い、Xマウントレンズは他社機には装着不能だからだ。
最初期のX-E1が中古市場で適価な相場で販売されていたので
レンズと合わせて購入した次第だ。
だが、未成熟なカメラである事は、事前に予想はついていた、
だからこそ、しばらくこのシリーズは無視していたのだ。

あった。その事については、ミラーレス・マニアックスの
シリーズ記事で、さんざん酷評したので、もうあまり書く気が
しない。何十年ぶりに一眼を作ったのでは、まあやむを得ず、
むしろ少々可哀想になってきたのだ。
それに、大体分かっていながら購入したのは自分自身の問題だ、
「悪女」である事は、およそ知っていたのに、XF56/1.2APDの
「色香」に、フラフラと吸い寄せられてしまったのだ(汗)
まあしかたない、後継機を買えば良さそうなのだが、実の所
後継機も、私の求めるカメラの水準には達してはいない。
結局、X-E1は少なくも減価償却が終わるまでは、その低性能に
付き合わないとならない、それが購入した責任だ。
(注:減価償却は既に終了して、後継機も所有している)

どんなカメラでも欠点ばかりという訳ではないのだ。
まず、この時代では珍しい高精細EVFを搭載している事、
この点ではミラーレス機として使い易い部類となる。
ただし色々とクセがある、ピーキング機能は低精度であるし、
半押しでそれは無効となる、そして半押しはプレビュー動作
や、勿論AF駆動、そしてAEロックなど、様々に関連するが、
そのあたり全般の動作を良く理解して使う必要がある、
絵作りはとても良い。特にベルビア(高彩度)モードや
モノクロ系モードは、なかなかの発色で、他のミラーレス機と
比べてもアドバンテージがある、さすがフィルムメーカーだ。
ただしエフェクト(デジタルフィルター系)は一切無いので
レガシー(注:この場合では”古い”という意味だ)な
写真撮影技法にしか使えない。
ところで、FUJIFILMは2018年に、モノクロフィルムの販売を
終了する予定であり。もはやFUJIのモノクロの発色は
デジタル機の中でしか味わえないという事だ。
まあでも、電子楽器の世界でも、今では生産されておらず
入手も困難な古い楽器の名機の音色をサンプリングして、
現代のシンセ等に搭載している事はごく普通であるが・・

シャッターダイヤルとの組み合わせて、各々のA(自動)位置
を選択することで、P/S/A/M切り替えを不要とする。
この仕組みは私の記憶している限りでは、ミノルタXD(1977年)
やマミヤZE-X(1981年)に搭載されていた。(ZE-Xは所有して
いたが故障廃棄)
XDやZE-XではA位置の組み合わせ式以外にも、クロスオーバー・
システムといった、極端な絞りやシャッター速度設定で露出値が
限界を超えて合わなくなった際に、自動的にそのいずれかを
調整して対応するという先進的な露出機構が内蔵されていた。
次いでの搭載機はPENTAX MZ-5/3シリーズ(1995~1997年)
であっただろうか? これらの機種は、それ以前のZシリーズに
搭載された特異な露出機構「ハイパー操作系」が極めて難解で
あった為(デジタル一眼クラッシックス第6回K10D参照)
より安易な操作系にダウングレードされたカメラだ。
(銀塩一眼レフ第21回記事、予定)
で、この方式は、PSAMダイヤルを廃する事が出来るので、
X-E1では、その代わりに露出補正が直接制御できる
アナログ式ダイヤルを備えている。

とアナログダイヤルとは大きくその効能が違う。
どちらが良い、悪いではなく、それぞれ長所短所があるのだ。
アナログダイヤルの長所=
・ダイヤルを見ただけで設定値が視認できる
・電源を切っても、設定値がずっと残っている(不揮発性)
・電源OFF時にも設定操作が可能
・指の感触などで操作がしやすい
デジタル(電子)ダイヤルの長所=
・設定値を電子的に記憶(セーブ)でき、それを任意に
呼び出す事(ロード)ができる、その際、ダイヤルには
指標が無いので、見た目と実際の設定値に矛盾が起きない
・絶対値が異なる複数の設定変更に対応できる、
例をあげれば、開放f値1.4のレンズを、開放f値4のレンズ
に交換したとしても、絞り変更ダイヤルは、そのままの位置
で両者の数値に対応できる
短所については、お互いの長所を逆にしてみればわかる。
また、これはダイヤルに限らず、ピントリング等も同様だ。
ピントリングをデジタル式ダイヤル、つまり、無限回転式に
した場合は、ピント絶対位置の記憶と呼び出しに矛盾が無い為
AFとMFを任意のタイミングで切り替えるシームレス操作が出来る。
反面、見た目ではピント位置がわからず、加えて指の感触でも
ピント位置がわからない(最短や無限遠で止める事ができない)
これが、それぞれの長所短所である。
X-E1のダイヤル操作性は、アナログの長所を持つのであるが
上記の観点からは短所にもなりうる、例えば、カメラを
運搬中や構えた際等で、知らないうちに露出補正ダイヤルが
動いてしまっている事がある。これは不揮発性、つまり、
ずっと維持されてしまうから、露出補正がかかったままで
撮影してしまう可能性もある。まあ、露出補正スケールの
インジケーターが常にEVF内に表示されているから、
それを見れば露出補正がかかっている事はわかるのだが、
自分が動かした覚えがないのに動いてしまっている場合は、
そのインジケーターを見落としてしまうリスクもあるだろう。
あるいは「1枚だけ露出補正をかけ、次の写真や電源OFF時には
自動で露出補正ゼロに戻る」という自動機能が実現できない。
別のケースだが、通常は絞り優先AEとして使う為にシャッター
ダイヤルはA位置で用いる。そして絞りを手動で廻すのだが
この際、絞り値の最小値を1段越えた所がA位置となるので
その際は、A+Aで、露出モードはP(プログラムAE)となる。
しかし、レンズによって絞りの最小値は異なり、f16の場合も
あればf22やf32の場合もある、なので、スローシャッター
表現等を狙って、カチカチと、できるだけ絞り込んで行くと
(絞り過ぎの回折現象での解像度低下は気にする必要は無い、
画質よりも、あくまで表現を優先するべき事は言うまでも無い)
最小絞り値を越えて廻しすぎてしまい、Pモードに入って
しまって、勝手にf5.6とかになり「なんじゃこりゃ」と
思う場合もある。

機構があると良いかもしれない、そうであれば指の感触で
絞りを最小から最大まで自在に使える。
なお「EVFの中に絞り値くらい出るだろう?」とは思うなかれ、
EVFはカメラを構えてから見るものだが、効率的なカメラ操作は
カメラを構える前に、必要と思われる絞り値を想定し、それを
指の感触又は直接絞り値を見て設定し、さらに、MFレンズの
場合であれば、被写体距離に応じピントリングも指の感触で
だいたいの位置に変えながらカメラを構えてEVFやファインダー
を覗く、その時点では絞りもピントも殆ど合っている状態に
なっているので、もう一々様々な設定値は見る必要も殆ど無い、
この流れにより、短時間で撮影を行う事ができるのだ。
ズームレンズ等を、ファインダーを見ながら画角を色々と
変えたり、絞りを変えてみたりするのでは時間がかかって
しかたがない。ビギナークラスで、やたらシャッターを切る
タイミングが遅いのは、写真を撮影する前に「どんな写真を
撮りたいのか」を、何も考えていないからであろう。
写真は、カメラを構えてから数秒以内に撮る事が望ましい、
そうでないと重要な撮影機会(注:あえてシャッターチャンス
とは言わない、その用語は一般的な意味においては適切では
無いと思うからだ=被写体に振り回されている印象が強いから)
を逃してしまう。

あるものの、アナログライク(似ている)で、悪くない。
ただ「操作系」すなわち(デジタル)写真を撮る為に必要な
様々な設定操作全体の構造(ユーザーインターフェース)は
劣悪だ。ただ、その話は、さんざん他記事で説明しているので、
ばっさり割愛する。

写真を撮るという行為に精通していないと作り込めない。
「何十年も一眼を作っていないメーカーが、そう簡単にカメラ
を作れるはずが無い」という第一印象は、そういう意味も多々
あったからだ。
なお、本機X-E1の最大の問題点を一応あげておけば、
AF/MFとも写真撮影の為に必要な性能を持っていない点である。
前述の本機を買うきっかけとなったXF56mm/f1.2R APD
を装着した場合は特に酷く、AFでもMFでもピントをちゃんと
合わせる事ができない。
その時点で迷った事は、
1)Xマウントのレンズをそれ1本だけでやめておき、被害(?)
を最小限に留めるのか、あるいは
2)カメラを新型の高価なもの(例えば像面位相差AF搭載機)に
買い換え性能アップさせるか、はたまた、
3)AF負担が少ないレンズを若干買い足して、早期に減価償却を
完了させ、その頃に、相場が下がった後継機を買うか、
という選択肢であった。
結局3)を選び、Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を買い足した
次第である。本機X-E1は描写力は優れているので、発色等の
傾向に優れたレンズを用いれば、さらに本機の長所が強調され
結果的に撮るのが楽しくなり、減価償却が推進されるという
理屈である。

精度はだいぶマシであるが、それでも厳しい事は確かだ。
なお、Touit 32mm/f1.8だが、描写力は悪くは無いけど、
逆光耐性が低く、かつ価格が高くてコスパが悪い。
よって、ミラーレス・マニアックスのシリーズでは、名玉編に
ノミネートされたのであったが、ハイコスパレンズの記事には
登場する事が無かったレンズだ。

XマウントレンズはFUJI専用で他機との互換性やアダプターでは
使用出来ない、ただし勿論Xマウントにアダプターを介して
MFレンズ等を装着する事は可能だ。
約1600万画素、X-Trans CMOS(ローパスレス)
感度はISO100~25600(拡張時)、ただしAUTO ISOでは
上限も下限も制限される。これは大口径レンズ等使用時に
低ISOが必要な場合、極めて使い難い。
ISO感度自動切り替えシャッター速度の低速限界が設定できる
本機には手ブレ補正機能が無いので、望遠レンズ使用時には
これを適宜高めておくと便利だ。
なお、「ISO変更ボタンが無い」という困った仕様であり、
たった1個しかない貴重なFnボタンをそれにアサインするか、
コンパネから変えるか、メニューから直接変更するしかない。

お粗末さだ、ちなみにAF精度が足りない為、通常レンズでも
近接撮影時には固定十字キーでマクロモードに切り替えなくては
ならないし、かつ1種類のマクロしかないのに選択操作が必要だ。
1990年代のAFコンパクト機なみの古い操作系仕様だ。
最高シャッター速度1/4000秒、低ISOが使い難いので不満だ。
なお、電子シャッター機能は搭載されていない。
ドライブ性能は、高速秒6コマ、低速秒3コマ、
これらは何故か非公開だ、仕様表に載せるのを忘れていたので
あろう、だがまあ悪くは無い。
ドライブ切り替えでは、動画は勿論、ぐるっとパノラマモード
もある。

低い、そしてこの時代のモニター表示部品(ソフト?)には
バグがある模様で、本機および他社の数機種では、JPEG画像
の再生時に本来の解像度が得られていない(プログレッシブ
JPEG形式が途中で再生停止してしまうような感じ)このため
撮影後のピント確認がわからず、ますますAF/MF性能が落ちる
という困った状態になっている。
エフェクトは一切無いが、前述のとおり優れたフィルム
シミュレーションモードがある。

だが、ダイヤル併用で指の位置が飛び、意外に使い勝手が悪い。
なお、通常メニューはメニュー位置記憶すらなく極めて不便だ。
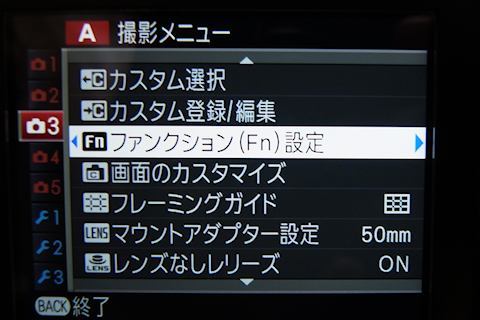
カメラの仕様上では、単焦点レンズを使うのが適切であるから、
ここは大いに不満である。
そして、数値スペックに関しては、本記事で述べてきた
使用上の長所短所からすると、ある意味、どうでも良い事だ、
こういうカタログスペックだけを見て、カメラを評価する事は
絶対に無理である事は言うまでも無い。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★★
【描写力・表現力】★★★★
【操作性・操作系】★★
【アダプター適性】★★
【マニアック度 】★★★
【エンジョイ度 】★★
【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:26,000円)
【完成度(当時)】★
【仕様老朽化寿命】★☆
【歴史的価値 】★★★
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.3点
残念ながら低得点だ、描写力・表現力以外の項目が全て
平均以下となってしまっている。
私自身、早目に後継機へリプレイス(交代)するのが良いと
思っていた(既にそうしている)
現在では中古も安価な機体ではあるが、今からの購入は
推奨できない。
購入していた場合であっても、本機の弱点を相殺できるような
適切なレンズ(広角気味の被写界深度が深いレンズ等)を
選んで装着する必要があるだろう。
次回記事は、引き続き第二世代のミラーレス機を紹介する、