安価な中古ミラーレス機にマニアックなレンズを装着し、
コスパの良いアダプター遊びを楽しむシリーズ、第74弾。
今回は、まず、このシステムから。

カメラは、お馴染み LUMIX DMC-G1
レンズは、CANON New FD50mm/f1.8
1980年頃に発売のMF小口径標準レンズ。
他の記事でも何本か紹介しているが、CANONのFL/FD/
New FDのMF標準レンズは非常に種類が多い。
New FDの時代だけをみても、50/1.2,50/1.2L,50/1.4,
50/1.8.50/2と5種類もあり、他に標準マクロも存在する。
内、本レンズ50/1.8と50/2は、4群6枚構成、最短撮影距離
60cmと、見た目のスペックは全く同じとなっている。
なお、AF時代に入ってからのEF50mm/f1.8(1987年-)は
安価で良く写る(=コスパが良い)と定評のあるレンズであるが
本レンズとはレンズ構成が異なっている。
私は近年、そのEF501/8の初期型を探しているものの、
なかなか出てこないので、今のところ未所有だ。
ちなみに後期型のEF50/1.8Ⅱというのは、いくらでも中古市場に
あるが、ピントリングが簡略化され、MFの操作性は初期型の方が
上の模様である。
さらにちなみに、最新型のEF50/1.8STM(2015年発売)という
レンズは最短撮影距離が驚異の35cmまで短縮されているが、
STM(ステッピングモーター)仕様なので(未確認だが)
恐らくEOS一眼以外に装着時はMFが動かないであろう。
よってミラーレス機で自在には使えないし、そもそもそういう
排他的な仕様には賛同できないので購入対象外としている。
さて、それらの名(迷?)レンズEF50/1.8シリーズの元祖である、
本レンズ New FD50/1.8の写りはいかに・・

最短撮影距離が60cmというのは、標準レンズとしては不満であるが、
まあそれでも近接撮影すれば、大きな背景ボケ量を得ることができる。
DMC-G1は旧機種ではあるものの自在可変型の背面モニターを
搭載しているのて、縦位置ローアングル撮影が得意だ。
これが一般的な上下ティルト式モニターでは、縦位置での
ローアングル撮影は不可能に近い。なお、こうした撮影の際の
MFピント合わせは背面モニターのみに頼る事となるが、DMC-G1
の優秀な拡大操作系は、EVFのみならず背面モニターでも有効だ。
でも、表示解像度が低いので、できればピーキング機能が欲しい。
他に所有しているDMC-GX7にはピーキング機能が入っているが、
ティルト式モニターなので、縦位置ローアングル撮影不可だ。
すると、DMC-G6/G7あたりが良いのだが現在未所有。そろそろ
中古が安価になってきたので、次期μ4/3候補機としておこう。
さて、本レンズだが、ボケ質が破綻しやすいので、最低でも
絞り値の制御によるボケ質破綻回避の操作が必要だ。
だが、逆光耐性はさほど悪くない。

中距離被写体、中間絞りにおいては、シャープネスさも
長所となってくる。
このあたり、各社MF小口径(f1.7~f2)標準レンズに共通の
特徴であり、たいていどれを買っても写りにハズレは無い。

まあでも、最短撮影距離の長さは若干の不満となる。
今回は、使用カメラがDMC-G1なので、デジタルズーム機能は
搭載されていないが、それのある機種の場合は(ボケ量は変わら
ないものの)構図微調整により最短の長さをカバーできる。
ただ、その場合は、価格バランスという別の問題が発生する、
それは本シリーズ記事でのコンセプトの1つの、
「レンズの価格(価値)よりも、ボディを高くしすぎない」
という持論である。すなわち、高価なボディに安価なレンズを
装着するのは好ましくなく、その逆を是とする、という意味だ。
本レンズは安価なジャンクレンズなので、ボディもそれに
応じて安価なDMC-G1(購入時約12000円)としている。
なお、本レンズにはND4(減光)フィルターを装着しているが
日中でf2級レンズの場合、ISO100が使えるボディであれば、
ND2でもなんとかOKで、かなり明るい被写体では絞りを
ちょっと絞れば良い。が、ND4だと暗い被写体では絞りを開けて
かつISO感度を高める必要がある。
あるいは暗い被写体の場合のみMD4を外せば良いのだが、
フィルターの付け外しは面倒だ。
f2級レンズ+ND2でも、最高シャッター速度1/8000秒の
ミラーレス機を使えば良いのだが、そういうスペックの
カメラはかなり少なく、あっても、ベース感度がISO100では
なく、もっと高目だったりする場合が多い。
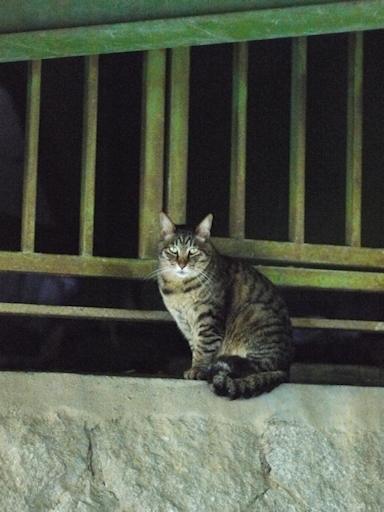
暗い被写体というのはこういう場合だ、高架下の猫が
好きそうな場所。日陰でかなり暗い。
ここでf1.8+ND4だと、かなりISO感度を高める必要があり、
ISOボタンこそあるものの、ISO専用ダイヤルを持たない
DMC-G1では操作に若干手間をとられる。
ちなみにND4を外すのは不可だ、その隙に確実に猫は逃げる。
----
本レンズであるが、最短の長さと若干のボケ質破綻の他には
殆ど不満な点は無い。さすがにMF小口径標準、他社の例にも
漏れず、CANON New FDもまた、良く写るレンズだ。
本レンズの中古購入価格だが、2010年代に2000円であった。
「ジャンク大放出時代」よりも少し後だったので、これでも
多少高目な位であったのだが(笑)勿論コスパは十分良い。
----
さて、次のシステム

カメラは、OLYMPUS E-PL2
コスパの良い非EVF型μ4/3機だが、MF性能は若干問題有りで、
もっぱら「トイレンズ母艦」として使用している。
レンズは、トイレンズではないが超広角単焦点
COSINA 20mm/f3.8 (Macro)である。
既に第14回記事で紹介しているが、そのレンズはFDマウント版
であり、本レンズはMDマウント版で、個体が異なる。
まあ1980~1990年代頃によくあった、各サードパーティ製
MF超広角レンズの1本であり、マニア好みのレンズだ。

何がマニア好みか?といえば、まず超広角である事、当時は
各社純正超広角は高価すぎてなかなか入手できなかったのだ。
まあでも、せっかくの超広角20mmも、現代にμ4/3機で使うと
40mm相当の画角と、準標準レンズと変わらないが・・
そして、そこそこ良く写ること。
画面周辺に収差が出るのは、銀塩時代に良く話題になったのだが、
μ4/3機では、そのあたりの周辺収差はすべてカットされる。
さらには、最短20cmまで寄る事ができる。まあCOSINAでは
Macroとは言っていたが、さすがに、1/2倍とかそういうレベル
では無く、現代の感覚であればマクロとは呼びにくいであろう。
で、なによりも価格が安い事。
新品でも1万円台前半で購入できたのが最大の特徴である。
すなわち、マニア好みとは、コスパの極めて良いレンズで
あった事なのだ。
最短20cmは結構寄れるし、その状態では開放f3.8の暗いレンズ
で超広角ながら、背景ボケを得ることもできる。

ところで、何故FDとMDの2つのマウントで同じレンズを持っているか?
といえば、前述の「純正超広角は高価」という点と大いに関係がある。
具体的にはCANONの場合、FD/New FDには、14mm,17mm.
20mmの超広角が存在したが、どれも高価であった。
ちなみに、FD以前のFLでは、19mm/ff3.5というのも存在したが、
FLレンズは、ちょっとMF一眼では使い難いという問題があった。
このあたりの事情はMINOLTA でもほぼ同様であり、
MCは、17mm,20mm.21mmがあったし、MD以降は、
17mmと20mmに整理された。
しかし、これらの超広角は、中古はいずれもレアであったのだ、
しかも1990年代の「第一次中古カメラブーム」の時代には、
レアものレンズは強気な値付けとなっていたので、高価で入手困難
であった。
したがって一般的に入手可能な純正中古MF広角は、24mm迄であり、
それ以下の超広角は、サードパーティ製を使わざるを得なかった。
が、嬉しい事に、タムロンには、アダプトール2という
ユーザーが自在にマウント交換できるMFシステムがあった。
例えば、タムロンSP 17mm/f3.5(第8回記事)は、どんな
MFマウントでも使える超広角として非常に重宝したレンズである。
本レンズは、そんな銀塩MF時代において、安価で新品入手可能な
超広角として、各マウントでの20mmの穴を埋める為に、どうしても
必要なレンズであったのだ。
なので、マウント毎に複数の本レンズを所有するマニアも
当時は少なくはなかったのではなかろうかと思う。

本レンズの購入価格は、1990年代に新品で13000円程であった。
安価ではあるが、まあしかし現代においての必要性は微妙な所。
例えば、APS-C機やμ4/3機では、超広角とは言いがたい
30mmや40mm相当の画角となる。
またフルサイズ機では、本来の20mmの画角が得られるが、
ここでも問題が・・まず周辺収差が出る事と、加えて
現代のデジタル時代に必要と思われる解像度が出ていない事、
つまり画質に問題ありなのだ。
そして、高価なフルサイズ機に装着するには価格バランズが悪い事だ。
このあたりのコンセプトは前述のFD50/1.8の所で書いた通りである。
で、中古を探すにも、結構現在ではレアになってしまっている
安価なレンズであるし、マニア向けでもあったので、その多くは、
安く下取りする事もなく死蔵しているのかも知れない・・
----
さて、次のシステムはトイレンズだ。

カメラは、望遠アダプター母艦の LUMIX DMC-G5
レンズは・・ メーカー不明、詳細不明の謎の超々望遠ズーム。
レンズに記載されている銘をそのまま書けば、
DM-50 SKY-VIEW Zoom Scoope
8x20x50 400mm-1000mm
加えて、800-2000mmという付属アダプターを装着している、
すなわち、μ4/3のDMC-G5に装着時 1600-4000mmの
画角の超々々望遠ズームになるという事だ。
レンズに記載の 8x20x50は誤記であろう、これは双眼鏡で
言うところの「倍率x口径」の表現である筈だから、
8~20x50が正しいと思う。
双眼鏡での倍率は、カメラで言うところの標準50mmレンズを
約1倍として換算する。8倍から20倍のズームというのは
すなわち、400mm~1000mmのズームとなり、表記どおりだ。
スペックからすると凄いのだが、写りはトイレンズ並み、
いや、それ以下か・・(汗)

これでピントが合っている状態、これ以上の解像度は得られない。
ボケボケの画(え)であるが、まあトイレンズであるので
しかたが無い。
ちなみに、焦点距離が短めの400-1000mmで使いたかった
のであるが、800-2000mmアダプターを外した際に、何か別の
部品が必要になるみたいで、その部品が見つからず、結局
800-2000mmアダプターを装着した状態でしか使えなかった。
もしかすると、400-1000mmモードでは、特殊な部品を使って、
50mm標準レンズのフロントコンバーターとして用い、
800-2000mmアダプターでは、Tマウントとなって、一般の
一眼レフにそのまま装着できる仕様だったかも知れない。
(長期間使わなかったので忘れてしまった・・汗)
なので、800-2000mmアダプターを使わざるを得なく、この
状態でDMC-G5に装着時、最低でも1600mm相当の画角から、
という恐ろしいスペックのレンズとなる。
本シリーズ記事での超々望遠撮影の際に良く書いているのは
「1500mm相当の画角を超えると手持ち撮影は、ほぼ不可能」
という事であるが、すでにそれを超えている。
これ以上ズームを伸ばして4000mm相当などとなると、もう
絶対に撮影は無理であるので、今回の撮影では、すべてズームを
ワイド端いっぱいとした1600mm画角オンリーである。

最短撮影距離は2.5mと比較的短い、これで1600mm相当の
画角であるから、マクロレンズ並みとなる。
開放f値は不明だ、レンズ記載の表示から、8-20x50が
50mm口径という事であれば、開放f値は、1000mm時には、
1000÷50=f20 、2000mm時には、2000÷50=f40となる。
だが、ISO感度(G5の限度128000までいっぱいに上げている)
とシャッター速度との関係からすると、1000mm時でf27相当、
2000mmm時でf45相当あたりに思える。
つまりは、口径が表示どおりの50mmではなく、2000mm÷f45
で、44mm程度しか無いという事になるだろう、それはまあ、
t値の計算は厳密にはレンズ口径(開口径)ではなく
有効口径(瞳径)であるから、そんなものかも知れない。
ちなみに、トイレンズであるから絞りは無い、
まあ、これ以上絞れても、どうせ使いようが無いが・・
----
ところで、本レンズで言うところの倍率とは、50mm標準レンズを
1倍としているので、双眼鏡などとも互換性のある表記なので
わからない訳でもない。
しかし、いつも書いていることで、カメラ業界での倍率表現の
問題点がある。
特に、近年のロングズームコンパクト機等で言うところの
「何倍ズーム」というのは、こうした意味のある基準ではなく、
単純に、テレ(望遠)端焦点距離÷ワイド(広角)端焦点距離の
比でしかなく、これは写真用レンズとしては意味不明の表記である。
いつの述べているように、広角端焦点距離に差があれば
写真用レンズとしての用途がまったく変わってしまう。
例えば、同じ10倍ズームでも10mm~100mmの超広角ズームと
100kmm~1000mmの超望遠ズームでは用途がまるで違う。
勿論こういうスペックのズームレンズやコンパクト機は殆ど
存在しない。(NIKON 1用で10-100mmはある)
一般的には、広角端24mmからの30倍ズームとか、古くは、
広角端35mmからの20倍ズームとかであったと思う。
で、これらの望遠端焦点距離は、24x30=720mmとか、
35x20=700mmである、この時、初心者のほぼ100%は、
30倍ズームと言えば「肉眼の30倍の大きさで写る」と誤解してしまう。
これは、双眼鏡で言えば、50mm標準画角x30倍=1500mm相当
なので、確かに本物の超々望遠ズーム(望遠鏡並み)なのだが、
実際には、700mm望遠ズームでしか無い訳だ。
つまり、ビギナーユーザーに誤解を招く表現をあえてして、
「凄いカメラ(ズーム)だ!」と思わせているという事だ。
なので、この「何倍ズーム」というスペック表記には悪意を
感じてしまい、賛同できないのである。
まあ、スペックの記載方法はともかくとして、本レンズは
画質的には見ていられないほど酷いものだ。あくまで
「超々々望遠トイレンズ」という位置づけでしか無いであろう。

本レンズの中古購入価格だが、2000年頃に9000円であった、
勿論高く買いすぎたが、中古店での「珍しいブツが入ったよ」
という甘い言葉に騙されて・・(汗)
まあ、私は「珍しいもの、唯一のもの」というのに目が無い
という弱点があって、誰でも持っているようなレンズは、殆ど
欲しいとは思わないが、皆が見た事も無いようなものには俄然
興味が湧いてしまう(汗)
まあ性能からする本来の価値的には、トイレンズ相当の3000円迄
という感じであろう。この画質であれば、一般的撮影には全く
向かないし、トイレンズとして扱うには個性がなく、
単に性能が低い、という事だけであり、魅力は全く感じない。
----
さて、次はトイレンズとはうって変わって本格派。

カメラは、FUJIFILM X-E1である。
再三書いてきているように、AF/MF性能・操作系に致命的とも
言える問題点を抱えるカメラである。
で、本来は、XF56mm/f1.2R APD(第17回、第30回記事)
を利用するために購入した専用ボディであるのだが、
その大柄な特殊レンズでのAF性能は酷いものであった。
なので、これまで様々なMFレンズを装着してX-E1の利用価値を
探していたのだが、いずれのMFレンズにおいてもX-E1の低い
MF性能・操作系では、利用に適する事はなかった。
なお、後継機でも操作系の殆どは改善されていない。
ただしAFは、以降の後継機では像面位相差センサーを用いて
いるので、性能(精度と速度)の向上が見られるという可能性は
あるのだが。私は、すでにその技術を用いたXQ1というコンパクト機
を使っていて、その使用感上では、その技術による大きなAFメリット
は感じられなかった為、X-E1の後継機の購入は現状控えている。
もう打つ手無しか・・とも考えていたのだが。
「どうせ無理ならば、ちょっと冒険してみるか」という事で、
小型軽量で高性能なAFレンズを1本購入してみる事にした。
それが本レンズ Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8である。
購入において、XF35mm/f1.4Rとだいぶ迷ったが、
2015年7月のドラゴンボート日本選手権大会において、
フィリピン代表チームのカメラ好きの選手が本レンズを持っていて、
私に見せてくれた(その模様は当時の記事に書いてある)
その時、直感的に「相当良さそうなレンズだ」と思ったので
最終的にはこちらを選択した訳である。
ちなみに、カール・ツァイス等の焦点距離/f値表記は
一般とは逆の1.8/32のように記載されているが、
「カメラ業界は、メーカー間の標準化が何十年たってもできない」
という点が非常に腹立たしい為、あるメーカーだけそうした
特別な記法をする事には反対である。
まず各メーカーで規格を決め、それに各メーカーがちゃんと
従うのは当然であろう、電球でも乾電池でVHSビデオでも、
CDでもDVDでもメモリーカードでも、USBでもブルートゥースでも、
PCのキーボードでも、携帯電話の番号ボタンでも、日常のたいてい
のものは、ごく普通に規格により「標準化」できている。
なのに、何故にカメラだけ、各メーカー毎のマウント互換性が
無いとか、用語が統一されていないとか、そういう問題が何十年も
続いているのか?それが今の世の中の感覚からすると、どうにも
信じられないのだ・・
さて、余談が長くなったが、Touit (トゥイート)の写りは・・

Touitは、2013年発売のミラーレス機用(APS-C用)
AF単焦点レンズ群である。12mm/f2.8,32mm/f1.8
そして50mm/f2.8 Macroの3本がラインナップされており、
マウントは、SONY E(α/NEXのAPS-C機)用と、FUJI X用である。
「プラナー」と併記されているが、レンズ構成は、5群8枚と
確かにプラナーっぽい。
で、カール・ツァイスだからと言って、良いレンズであるとは
限らないのは、過去何本もツァイスレンズを紹介してきた
通りであり、ブランド名だけで特別視する必要は全く無い。
「さすがツァイス」などと言うありきたりのブランドイメージ的
感想は本シリーズではまず無いし、中にはちょっと我慢できない
ような性能のツァイスもあり、そういうレンズでは「コスパが悪い」
という重欠点が必然的に浮上し、嫌いなレンズの代表格となる。
さて、本レンズは嫌いなレンズとなるのかどうか・・

描写力は思ったより悪くない。
けど、その多くは、X-E1の数少ない長所である
「絵作りが良い」という点に助けられている事であろう。
X-E1は、ローパスレスであると同時に、フィルムメーカーで
あった FUJIFILMの絵作りコンセプトが強く出ているカメラだ、
だから吐き出す画(え)には、ほとんど不満は無い。
アナログライクな「操作性」もまた良いのだが、ピント性能や
操作系については、残念ながら「未完成機」と言うレベルでしか無い。
で、本レンズでのAF性能は思ったほど悪くない。
すなわち、小型軽量の一般AFレンズであれば、ボディ内モーター
のX-E1でも、ある程度使えるのでは?という、かすかな希望が
あったのが、まずまず期待通りであった、という事であろう。
例の劣悪な「マクロモード手動切換え」操作も、APDレンズの
ように毎回必須という訳ではなく、遠距離レンジのままでも
マクロ域でピントが合う事もある(ただし確実性は無い)

ボケ質破綻はほとんど出ない、プラナーであるから、ボケ質破綻
の問題点は「あって当然」と、ちょっと覚悟していたのだが、
そのあたりは幸いであった。
X-E1は、開放測光であるが、絞込み(プレビュー)をするには、
シャッターボタンを半押しすれば良い。
これで、ボケ量もボケ質も、EVFで確認が出来る(背面モニター
でも見れるが、解像度が低い)
これは、AF/MFのいずれのモードでも効くのだが、本来ならば
MFの時は、一々半押しをしないでも絞込みが効いて欲しかった。
なお、半押しというのはAF動作が通常伴う。だが、AF動作を
せずにプレビューが効かないか?と調べてみると、一応「絞込み」
機能が存在するようだ。が、それを他のボタンにアサインする時は、
それが可能なボタンは2箇所しかなく(Fnキーと下十字キー)
それらには、普段は他の重要な機能をアサインしているので、
この設定は実用的では無い。
仮に、無理してFnキーを一時的にプレビューに設定する、すると、
絞り込んだ場合、EVFやモニターが真っ暗になってしまうのだ!
ミラーレス機だったら、絞りを変えても表示輝度はキープするのが
当然ではなかろうか?これでは一眼レフと同等でありミラーレス機
のメリットを生かせていない。
で、Touit 32/1.8には、絞り環がついているので、もしかしたら
何も操作しなくても絞込み測光になるのではないか?と淡い期待が
あったが、それは流石に無理であった(FUJI純正レンズでも同様だ)
でもまあ、やはり「ボケ確認は、MFレンズで絞込み測光に限る」
ということなのであろう、まあ、Xマウントや、SONY Eマウント
では、ややましだが、μ4/3機ではプレビュー操作をしないと
ボケ量やボケ質の確認ができない。
(デジタル)一眼レフでは、さらに深刻で、プレビュー操作で
画面が暗くなってしまう為、それらの詳細の確認は困難だ。
それと、下十字キーに機能をアサインする、と前述したが、
左右十字キーは、何も機能をアサインできない。他社機の場合
このようにボタンが無駄になる状態というのは殆ど無いので、
ここもX-E1の操作系上の弱点であろう。

本レンズは、描写力に優れたX-E1とあいまって、かなりの
好みの絵を吐き出してくれる良好な性能のレンズだ。
シャープネスやボケ質もそこそこで、小型軽量で取り回しも良い。
ただし弱点もあり、その1つは逆光に極めて弱い事。
太陽をある角度に入れると内面反射でフレアが結構出る。
当初、逆光耐性チェックの為にフード無しで使っていたのだが
フレアの問題が発覚した為、「フード装着必須レンズ」と
する事にした。
それから、ピントリングや絞り環がゴム製であり、高級感に欠け、
デザイン的にイマイチなところだ。そこそこ高価なレンズであるので、
こうした安っぽい作りはNGだ。
あとの弱点は、その価格であろうか・・
本レンズの中古購入価格は、本年2016年に54000円程であった。
正直高い、例えば第60回記事で紹介した SONY DT35/1.8は
本レンズと類似のスペックだが、描写力にそこそこ優れ、
ボケ質も良く、最短撮影距離も23cmと短い(本レンズは30cmだ)
で、購入価格は12000円弱であったので、コスパが極めて良い。
逆に本レンズよりコスパが悪い類似仕様のレンズとしては、
例えば FA31/1.8 Limited であり、こちらは9万円もしたのに、
総合的には本レンズほどには魅力を感じない。
けど中古5万円オーバーにしては、逆光耐性などはかなりお粗末。
まあでも、気軽なスナップ用レンズとして、X-E1の減価償却の
為にも、本レンズには、せっせと働いてもらうとしよう。

今回はこのあたりまでで、次回記事に続く・・