海外製のレンズを紹介するシリーズ記事。
今回は「YONGNUOマニアックス」という主旨とし、
同社製の4本のレンズを紹介する。
(全て、他記事で紹介済みのレンズの再掲であるが
実写掲載写真は、全て新規のものを使用している)
![_c0032138_11503160.jpg]()
光学機器メーカー(のブランド銘)であり、2010年代
後半から、格安の高性能AF(単焦点)レンズ数機種で
日本市場に参入している。
・・とは言え、その全てのレンズは1990年代のCANON
製EF単焦点レンズ群の、フル(完全)コピー製品だ。
なんだか裏の事情が想像できるが、そこはさておき
これらのレンズが、実用的に使えるものなのかどうか?
そこを本記事では検証していこう。
紹介レンズ4本は、すべてAFで、かつフルサイズ対応の
単焦点レンズだ。(銀塩/デジタル一眼レフ用)
----
ではまず、今回最初のYONGNUOレンズ。
![_c0032138_11503142.jpg]()
(中古購入価格 14,000円)(以下、YN85/1.8)
カメラは、CANON EOS 8000D(APS-C機)
2017~2018年頃(?)に発売された、単焦点AF小口径
中望遠レンズ。
![_c0032138_11503227.jpg]()
のコピー品であるが、オリジナル品との大きな違いとして、
USM(超音波モーター)がYN85/1.8では内蔵されておらず、
この結果、CANON版にあった「フルタイムMF機能」つまり
AFで合焦中に、任意にピントリングを廻す事で、即時に
MFへ移行する事が「仕様上では」出来ない(詳細後述)
本YN85/1.8ではCANON EF版各レンズに存在するAF/MF
切換スイッチと同等の仕様により、MFで使用する場合は、
このスイッチをMF側に倒してあげる必要がある。
ただし、これは正規の使い方であり、「裏技」がある。
それは、このスイッチをAFのままにしておいても、強引に
ピントリングを廻す事で、USM仕様では無い本レンズでも、
シームレス(つなぎ目なし)な強制MF移行(すなわち
CANONで言うフルタイムMF)が、一応可能なのだ。
(注:有限距離指標+無限回転式ピントリング型)
しかしながら、これは「仕様外」の用法である。
この場合の課題は、EOS機にある「フォーカスエイド機能」
(ピントが合っているという状態を黄緑色の○表示で示す)
がちゃんと動作せず、最初にAFが合って○印が表示されたら
MFでピント位置を変えても、ずっと○印が表示されたままだ。
すなわち「強制MF」時には、フォーカスエイドが使用できず、
ピントが合っているか否かは、EOS機の光学ファインダーの
フォーカシングスクリーン上で、目視で確認するしか無い。
この時、EOS 6D/5D+Eg-S(MF用スクリーン換装)等では、
なんとか、スクリーン上でのピントの山が確認可能だが、
今回使用のEOS 8000D(初級機、スクリーン交換不可)
では低性能な為、MFでの利用は、ほぼ不可能となる。
なお、YN85/1.8のレンズ側AF/MF切換スイッチをMF側に
倒した際には、EOS (8000D)機側でのフォーカスエイド
機能は有効になり、MF合焦すれば○印が表示されるので、
カメラ側ファインダー(スクリーン)性能の低さによる
MFのやりにくさは、若干軽減できる。
ただし、この場合のフォーカスエイドは、AF測距点に
連動しているので、画面の端の被写体にMFで合焦確認を
行いたいのであれば、AF測距点を変更する操作が必要だ。
この為には数回のボタン操作が必要となり、操作性が悪化
するので、通常はこの操作を行わず、画面中央の測距点で
MF合焦を行い、構図を振って被写体を画面の端等とする。
(=MFロックという技法。匠の写真用語辞典第29回記事)
しかしながら、MFロック措置を行うと、撮影距離が変化し
ピンボケとなる恐れがある。
(コサイン誤差/セカント誤差。匠の写真用語辞典第29回)
これについては、本YN85/1.8といった被写界深度が浅く
なる可能性があるレンズでは無視できない可能性もある。
「匠の写真用語辞典第29回」記事での試算においては、
「撮影距離2m以上、又は絞り値F2以上」の、いずれかの
条件を満たせば、大口径85mmレンズでもMFロック操作時に、
被写界深度によりコサイン(セカント)誤差を起因とする
ピンボケは(計算上)起こらない事が確認済みだ。
ただまあ・・ そもそもフォーカスエイドの精度の課題や
低性能EOS機におけるスクリーンのMF精度の低さにより、
MFでの撮影全般では、ピントを外すリスクが極めて高い。
かと言って、AFでの使用でも同様だ。これはUSM非搭載
でのDCモーターによる、AFモーター停止精度不足および
初級機カメラ側での、AFアルゴリズム判定精度不足等が
あいまって、ピンボケを連発し、ピント歩留まりは悪い。
簡単な解決法としては、できるだけAF精度・性能の高い
機体、具体的にはCANON EOS 7D/7D MarkⅡ等を
母艦とする事だ。これらであれば、AFでのピント精度は
だいぶマシになるが、これらの機体でもMF性能は全く
期待できないので、似たり寄ったりの状況であろう。
しかしながら、EOS 7D系機体では高速連写が効くので、
高速連写MFブラケット(匠の写真用語辞典第35回/予定)
により、「下手な鉄砲、数撃てば当たる」方式でピントの
歩留まりを向上させる事は、一応可能だ。
![_c0032138_11503245.jpg]()
YN85/1.8の描写表現力であるが、個人評価では特に問題は
無いレベルである。ただし「良好」とまでは言い切れず、
個人評価DBでは、5点満点中3.5点の得点である。
というのも、各社の85mm小口径(開放F1.7~F2.8)は
描写力に特に優れるものが多く、例えば近年のTAMRON
SP85/1.8(F016、2016年)が、その筆頭格だが、
古今東西で、その傾向は同様だ(例:Jupiter-9 85/2、
smc PENTAX-FA77/1.8、NIKON AiAF85/1.8D、
中一光学 CREATOR 85/2、SONY SAM85/2.8、
Voigtlander APO-LANTHER 90/3.5等)
そうした、85mm級の小口径名玉に比較すると、
本YN85/1.8の描写表現力は、少しだけ見劣りする。
これは、元となったレンズのCANON EF85/1.8USM
(1992年)の描写性能に起因しているかどうか?は不明だ。
残念ながら、EF85/1.8は所有の機会に恵まれておらず、
詳細な性能比較が出来ないからだ。
(EF85/1.8の購入を辞め、本YN85/1.8で代替した)
![_c0032138_11504290.jpg]()
であると思われる。安価であれば、例えば今回購入時での
1万円台前半程度の中古品であれば、コスパはかなり良いと
判断する事が出来るであろう(コスパ評価4点)
初級中級マニア層に向けては推奨できるレンズだ。
ただし、上記ピント問題は、一般初級中級層には回避
が困難だと思われるので、実践派のマニア層以外には
非推奨だ。
---
では、次のYONGNUOレンズ。
![_c0032138_11504285.jpg]()
(中古購入価格 8,000円)(以下、YN35/2)
カメラは、NIKON D5300(APS-C機)
2018年頃(?)に発売された、フルサイズ対応AF準広角
レンズ。
![_c0032138_11504239.jpg]()
していたEF35mm/F2の完全(デッド)コピー品である。
ただしCANON EFマウント品では無く、NIKON Fマウント
版(N型番)としての購入だ(勿論EF版も存在する)
これのオリジナル品、CANON EF35mm/F2については
所有していて、レンズマニアックス第35回記事で
両レンズを比較検証済みである。
EF35/2は、後年にはUSM仕様となったが、初期型は
USMでは無く、DC(直流)モーター仕様である。
YONGNUOの完全コピー品の製造の「仕掛け」は、
だいたい分析が済んではいるが、あまり表立っては言えない
裏の事情もあるだろうから、そこについては言及しない。
1つ言える事は「YONGNUOはUSM(超音波モーター)
(やSTM)は搭載(調達)できていないのでは?」という
点だ。(注:STM等は、現代では中国で主に生産されて
いるので、いずれ、これらも搭載されるかも知れない)
だが、初代EF35/2には、USMが搭載されていなかった
ので、その点については、YN35/2もUSM無しで、完全
な同等品となる。
しかも、DCモーターが内蔵されている事で、ニコンF
マウント版(YN35/2N等)を製造した際にも、これを
NIKON初級中級機(D3000系、D5000系等。今回
使用のD5300も同様)においても、AFが動作する。
ここの詳細は、NIKON D3000系、D5000系等に
おいては仕様的差別化」により、AFモーター非内蔵の
AFレンズ(NIKON AF-S型では無いAiAF等の旧型レンズや、
レンズ・サードパーテイ製2000年代レンズの一部等)
では、AFが効かない(かつ、MF性能は恐ろしく低い)
という課題があるのだが、本YN35/2Nでは、幸いその
仕様的差別化の制限には掛らず使用できる、という事だ。
ただし、NIKON機での操作性仕様は他社機とは逆である
(1930年代~1950年代の旧CONTAX機の仕様を真似て
NIKON機(レンジ機、一眼レフ)が設計された為、
近代に至るまで、NIKON機での多くの操作性が他社と
逆となっているという問題点)・・その、逆である為、
EF35/2をベースとした本レンズでは、ピントリングの
回転方向と距離指標が逆に動く、という気持ち悪さ
(操作性の悪化とエンジョイ度の減少)が存在している。
これについては、本YN35/2は準広角レンズであり、
前述のYN85/1.8のような、技法上の精密ピント合わせ
操作を要求されない(AFで中遠距離被写体をスナップ
的に撮れば良い)という点で、仕様上の気持ち悪さは
あまり気にならなくなるとは思う。
![_c0032138_11504205.jpg]()
としている為、当然ながらフルサイズ対応レンズだ。
しかしながら、EF35/2とYN35/2は、像面湾曲収差や
非点収差の補正が行き届いていない、だから、ボケ質
の破綻が若干出る。
これを低減するには、まず前述のように中遠距離撮影
に特化してボケを出さない事。そして、ボカす場合は
ボケ質破綻の回避技法(匠の写真用語辞典第13回記事)
を用いる他、フルサイズ機では無くAPS-C型以下の機体を
用い、画面周辺収差のカットを図る事、等が望ましい。
つまり、この場合フルサイズ機では無く、APS-C機の
方が画面全体での描写力の均一性が改善される訳だ。
おまけにピクセルピッチが狭く、ローパスレス仕様でも
ある、母艦NIKON D5300であれば、本YN35/2との
仕様的マッチングに優れる(=弱点相殺(型)システム。
匠の写真用語辞典第1回記事参照)
ただまあ、これらのレンズやカメラの仕様・性能上の
詳細を理解し、弱点を緩和する為の適正なシステムを組む、
という発想は上級マニア層以上向けの話であり、他の一般
ユーザー層には、とても困難であると思う。
でも、ビギナー層等で「フルサイズ機の方が写りが良い」
と思い込んでいるユーザーには是非理解して貰いたい事だ。
![_c0032138_11504946.jpg]()
1990年頃に設計された「セミ・オールドレンズ」ながら、
当時の技術水準からは、他社同等品に対しての性能的な
優位点は存在していたと思われる。
ただまあ、やはり古い。例えば、近代設計による、
TAMRON SP35/1.8(F012、2015年)と比較すると、
あらゆる点(描写力、最短撮影距離、ボケ質、ピント精度、
手ブレ補正等)で見劣りしてしまうのは確かであろう。
本レンズの最適な用途は「使いつぶし」型であろう。
安価であるので、過酷な撮影環境(雨天や酷寒・猛暑等)
で、あまり故障を気にせず、ガンガンに使うのが良い。
そういう意味では、中級層以上には推奨できるレンズだ。
----
さて、3本目のYONGNUOレンズシステム。
![_c0032138_11504959.jpg]()
(中古購入価格 4,000円)(以下、YN50/1.8)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
2014年頃? に発売された、小口径AF標準レンズ。
発売は少し古いが、国内流通が活性化したのは
後年の2017~2018年頃だと思われる。
![_c0032138_11504942.jpg]()
初の「エントリーレンズ」であり、EOS機の普及と
ユーザー層のCANON製品への「囲い込み」を目指した
戦略的低価格帯レンズ。以降の時代の初級中級層には
「安価なのに写りが良い」と「神格化」されている)
のフル(完全)コピー品である。
両者の違いは、絞り羽根の枚数くらいであり、それに
よる描写力の差も、木漏れ日や夜景ボケの形状の差と
光条等の差くらいの微々たるものであり、一般的撮影に
おける描写力の差は、ほとんど無い。
完全コピー品というよりは、同一部品を同一生産設備
で組み立てられた物、という様相がかなり強いのだが
そのあたりは、中国生産を辞めた、などの裏事情が
色々とある、と推察される為、その出自については、
あまり詮索しないようにしよう。
(注:電子部品が異なる模様であり、電子マウント
アダプターを使用した場合、オリジナル品とは動作が
異なる。詳細は長くなるので、他記事で説明する)
なお、YONGNUOの50mmレンズには、他にCANON
EF50/1.4 USMのコピー品のYN50/1.4や、本レンズの
改良品のYN50/1.8Ⅱがあると聞くが、それらは未所有だ。
そう何本も似たようなレンズは不要だし、YN50/1.4は
USMが未搭載である(かつEF50/1.4USMは所有している)
まあ、個人的にはYONGNUOの50mmは、本YN50/1.8で
打ち止めとしておこう。
![_c0032138_11504937.jpg]()
持つレンズである為、EOS 7D/7DMarkⅡ等の高性能
AF機と組み合わせた方が弱点を相殺できて無難だ。
しかし、中古価格4000円と安価な本レンズを、高性能
機体で使うのも、アンバランスであり、これは持論の
「オフサイドの法則」(匠の写真用語辞典第16回)に
ひっかかる。
今回は「限界性能テスト」(匠の写真用語辞典第27回)
の意味を含め、フルサイズ機のEOS 6D(2012年)を
使用する。
すなわち、1990年代の銀塩時代において、高描写力
を好評価されたEF50/1.8Ⅱであるから、フルサイズ機
で使用した場合でも、描写力上の欠点(例:周辺収差)
は目立たないのではなかろうか? という検証だ。
なお、何故「周辺収差」と呼ばれる問題が課題となる
かは、レンズはその性能上、画角に比例または累乗で
増加する収差の類が多く存在するからである。
(匠の写真用語辞典第29回記事参照)
具体的には、歪曲収差、コマ収差、像面湾曲、非点収差
等がそれであり、中には絞りを絞り込んでも解消されない
収差も存在するし、収差以外にも、「口径食」等による
周辺減光もある為、簡便な改善方法としては、フルサイズ
対応レンズであってもフルサイズ機を使わず、APS-C機や
μ4/3機に装着して用いると良い。
他分野の簡単な事例で言えば、肉や果実等での中央部の
「美味しい部位」だけを贅沢に食べる、という感覚だ。
特に、オールドレンズ等で周辺収差が大きく、実用性能に
満たないレンズであっても、μ4/3機に装着するだけで
周辺収差が目立たず、なんとか実用範囲に収まる例もある。
まあ要は、レンズの性能や特性次第では、常にフルサイズ
機では使わない方が良い結果を得られる場合も多々ある
という事実であり、逆に言えば、フルサイズ機で欠点を
さらけだしてしまえば、そのレンズの性能的な限界点を
知る事にもなる。まあそれが「限界性能テスト」としての
今回やろうとしている事だ。
で、EF50/1.8(注:私が所有しているのは、EF50/1.8Ⅱ
型ではなく、光学系が同一の初期型=1987年である)も、
本YN50/1.8も、若干の逆光耐性の低さと、軽微なボケ質
破綻が発生する。
ただまあ、逆光耐性については、多くの銀塩時代の
レンズで同様であり、当時はビギナー層や一般層ですら
「カメラは逆光で撮ると写りが悪い」という認識を
持っていた。だから、皆に逆光を回避して撮影する習慣が
あった為、現代のスマホカメラの一般層よりも、この時代
(1990年代)の一般層の方が、逆光回避技能に優れ、
逆光時の描写力低下(フレア、ゴースト、低コントラスト
化等)については、むしろ寛容であったと思われる。
(=「逆光なので、しかたが無い」という認識)
また、当時の銀塩EOS初級中級機では、最高シャッター
速度が1/2000秒~1/4000秒止まりであった。
よって、ND(減光)フィルターを使わない限りは、
日中晴天時、ISO100の低感度フィルムを使った際でも、
絞りを最大F4(1/2000秒機)又はF2.8(1/4000秒機)
までしか開けれない(開放F1.8を使うと、シャッター
速度オーバーとなる)また当時は、ISO400等の中感度
フィルムを使う事も一般的であり(つまり、ビギナー層
では、露出の原理を知らずして、数値が大きいフィルム
の方が、単純に「良い」と思ってしまう) ISO400の
フィルムでは、さらに、F5.6~F8程度までしか、
絞りを開けて使う事が出来ない。
この環境であると、EF50/1.8(Ⅱ)を使って、日中に
背景をボカした(被写界深度が浅い)撮影は、ほぼ不可能だ。
しかし絶妙な事に、このEF50/1.8(Ⅱ)の、5群6枚
変形ダブルガウス型構成では、絞りをF4~F5.6まで
絞り込む事により解像感が向上する、という優れた特性を
持っている。
(注:EF50/1.8系に限らず、他社銀塩用AF50mm/F1.8級
レンズと、1970年代~1980年代の殆ど全ての各社の
MF50mm/F1.8級、5群6枚型構成で同様の描写特性を持つ。
別シリーズ「最強50mm選手権」、第2回AF50mm/F1.8級、
第4回MF50mm/F1.8級の対戦記事を参照。
また、近年の中国製ジェネリックレンズや、国内の
一眼レフ用エントリーレンズでは、この優秀な銀塩用
50mm/F1.8級構成をスケールダウンし、25~35mm級の
APS-C機以下用F1.8級レンズに設計変更して販売している)
すなわち、EF50/1.8(Ⅱ)の、この特性は、当時の銀塩
機材環境では、「確信犯」的に、必然的に高描写力が
得られる用法になる訳である。これを無理した利用法で
被写界深度を浅め、結果、像面湾曲や非点収差により
「ボケ質破綻」が発生してしまうケースは考え難い。
つまり、初級中級層においては、CANON EF50/1.8(Ⅱ)
や、本YN50/1.8は、多くの使用条件で、高描写力が
発揮できる事となり、結果として、EF50/1.8(Ⅱ)
が当時の銀塩機材環境において、EF50/1.8(Ⅱ)の
その特性が高く評価され、結果的にそのレンズが、
初級中級層により「神格化」されてしまったのであろう。
まあでも、別に何ら問題がある話では無い、当時の
機材環境に適切な仕様のレンズを提供した「企画上の
勝利」である。
EF50/1.8の価格が比較的安価なのも当然であり、
(1970年代より)もう、20年間近くも作り続けた、
極めて完成度の高い「5群6枚変形ダブルガウス型」
レンズ構成である。
高価な非球面レンズも異常低分散ガラスも、その光学系
には不要であるし、設計費も製造設備原価も、とっくの
昔に元が取れている状態だ、これを高価に売ろうとしたら、
むしろそれは「ぼったくり」であろう。
でも、囲い込み用途があるとは言え、安価なレンズでは、
やはり製品単独で見た場合では利益が出にくい(大きな
黒字には成り得ない)状態となってしまう。
そこで、CANONにおける初期型EF50/1.8は、国内生産で
2万円以上の定価販売となってはいたが、ここを低価格
化しようとした際、続くEF50/1.8Ⅱでは、海外(中国)
生産として、製造原価をさらに下げながらも、約1万円
の定価販売でも十分に利益が出るような原価構造にした
のだろう、と容易に想像できる。
その海外生産工場が、YONGNUO(永諾撮影器材株式有限
会社)だったか否か? そこは当然非公開であるから、
実際のところは不明である。
ただ、1990年代であれば中国での人件費は、日本の
1/10以下と言われていた。だが、2010年代前半には、
中国での人件費が高騰し(数年間で数倍となった)
海外生産がやりにくくなった、とも推察される。
(他に、勿論、2010年代からのカメラ・レンズ市場
の大幅縮退により、大量生産スタイルが効率的では
無くなってきている)
![_c0032138_11505966.jpg]()
ほぼEF50/1.8Ⅱと同一である。
だから描写力も同様、長所も弱点も同様である。
あえてYN50/1.8の弱点をあげておけば
1)逆光耐性の低さ (撮影技法で回避可能。
または、下写真のように適当なフードを装着する)
2)軽微なボケ質破綻(高度な撮影技法で緩和可能)
3)若干のAF精度不足(母艦の選択で若干緩和可能)
となるのだが、これらはいずれも軽微な弱点であるから
重欠点とは言い難い。
![_c0032138_11505976.jpg]()
(相場7000円前後)よりも安価に入手する機会がある
場合のみ推奨できるレンズである。
EF50/1.8Ⅱよりも高価であったら、中身はほぼ同じ物で
あるから入手する必然性は無い。
中級層以上であれば、誰にでも推奨できるレンズでは
あるが、これを「やはり安物の中華レンズだ、良く写る
筈が無い」などの、思い込み評価しかしない(できない)
ビギナー層に対しては非推奨だ。思い込み思想で満足感を
得たいならば、CANON純正品を買えば良いであろう。
----
では、次は今回ラストのYONGUNOシステム
![_c0032138_11505930.jpg]()
(新古購入価格 19,000円)(以下、YN100/2)
カメラは、NIKON D300(APS-C機)
2018年頃(?)に発売された、フルサイズ対応AF中望遠
レンズ。
![_c0032138_11505937.jpg]()
オリジナルとなったのは、CANON EF100mm/F2 USM
(1991年発売。現在未所有)である。
ただし、前述の状況から、本YN100/2(N)には、
USM(超音波モーター)は搭載されていない。
しかし、DCモーター内蔵であるからNIKON Fマウント
版の本レンズであっても初級機(D3000系、D5000系)
でAFが効く。
だが、NIKON Fマウント版においては、前述のEF版
(YN85/1.8)のように「強制MF」操作には対応して
おらず、本YN100/2NでAF合焦後にピントリングを
廻しても、空回りするだけでMFは効かない。
MFにしたい場合は、レンズのAF/MF切換スイッチを
MF側に倒すしか無い状態であり、面倒な操作性だ。
本レンズのオリジナル品、EF100/2USMは、銀塩時代
に使用していたのだが、事情があって銀塩時代の末期に
知人に譲渡してしまっていた。写りは気に入っていて
後年に買いなおそうとしていたのだが、中古相場が
ずっと3万円以上と高値安定であったので、コスパを
考えると、やや買い難い状況が続いていた。
そんな状況の中、近年に本YN100/2(N)の中古品を
見かけた次第だが、新古品(新品?)で、ほぼ定価販売だ。
あまり割安感を感じなかったが、NIKON Fマウント版
は、元々若干定価が高価であったし、これでもCANON
EF100/2USMの中古より安いし、あるいはあまり多くの
YONGNUOレンズを全てEF版で買うのも躊躇いがあった
ので、若干の高値相場は許容し、これを購入した。
![_c0032138_11510795.jpg]()
銀塩時代のEF100/2USMが手元に残っていれば比較が
容易だったが、残念ながらそれは無い。
銀塩MF時代のNew FD100mm/F2ならば、所有しては
いるが、そのレンズは恐ろしく描写表現力が低いので
AF時代に入って、EF100/2USMに改良されたのであろう。
CANONは、そのメーカーのイメージからは意外なほどに
レンズ構成の小改良をこまめに行っている。
普通、大企業(大カメラメーカー)と言えば、
そういう手間や費用のかかる改善をあまりせず、利益を
優先する傾向があるし、ユーザー優先ではなく、メーカー
の都合で事を運ぶ傾向が極めて強い。そういう点が
目につくと、大メーカーの戦略に反発する要因となって
しまうのだ、そういう例はカメラ界ではいくらでも存在
しているし、本ブログ記事での評価では、そうした
メーカー側の姿勢を問う内容も多くなっている。
だが、CANONにおいては、他の機材での企画はともかく
として、レンズにおいては性能が低いと(自社でも)認識
されたものは、ちゃんとその改良をこまめに行っている
点は良いと思う。これはユーザー側から見た評価とも
ほぼ連動しており、「このレンズはちょっとなあ・・」
と感じるものは、短期間でそれを改善した後継機が
発売されている。
逆に言えば、CANON製レンズでロングセラーとなっている
ものは、メーカー側においても「改良の必要性が低い」
と認識されていると思われ、そういうレンズは完成度
が高く、かつ昔から販売されているから、後年において
中古相場が下落しており、購入においてコスパが抜群に
良いものが出てくる訳だ。
この製品価値判断手法は、上級マニア向けとは言えるが、
とは言え、レンズの製造年代を調べるだけで済むので
初級マニア層でも可能であろう。参考にされたし。
ただ、誰もが、そういう「えげつない」機材購入手法を
取ってしまうと新品が売れず、CANONはカメラ事業を
続ける事が難しくなり、次期新製品が、とんでも無く
高価に値上げされてしまったり、あるいは最悪では
「もう儲からないから」と、カメラ市場から撤退して
しまう危険性もある、そうなってしまうとユーザー
側でも困る(2000年代のCONTAXやKONICA MINOLTA
のカメラ事業撤退は、本当に困った状況であった)
なので、ここは申し訳ないが、「事の本質」を良く
わかっていないビギナー層等に、高価な最新鋭機材を
買ってもらい、メーカーや流通市場を潤してもらう
しか無い。ビギナーでは旗艦機や大三元レンズを
使う必要性も無いし、使いこなせない事は明白だが、
ビギナー層の、そうした無駄な出費(業界への献金)
により、カメラ市場が崩壊せずに続いているという
現状を良く鑑みれば、そういう出費は好ましい。
まあつまり、わかっている人は、無駄を無くすような
購買行動をすれば良い、そうでない人達も、好きに
購買行動を起こせば良い訳だ、それで世の中は上手く
廻っている。「自分が損をしている」(「ユーザーの
負けの状態」である)は、自身が気がついていなければ、
それはそれで、何も問題は無い。
自分でも、ずいぶんとドライな意見だとは思うが、
それが現代の世の中の真実である以上、個人的な感覚は
挟む必要も無いであろう。
余談が長くなった、本YN100/2の描写力等の詳細で
あるが、まず課題となるのは、本レンズと多くの
NIKON機との組み合わせで露出が不安定(アンダー
気味)となる事だ。
これの回避は、機種によっては、露出補正を掛けるか、
場合により、中央重点測光モードに切り替える措置も
有効な事がある。NIKON機の機種によっては安定露出
が得られる場合もあるので、レンズ側では無く、
NIKON機側の露出決定アルゴリズム上の問題点だ。
(=近代のNIKON機で、純正以外の他社製レンズの一部
でアンダー露出となる露出制御プログラム上のバグ、
または、意図的な「排他的仕様」だと思われる。
なお、このようなソフトウェア的な改変は、外部から
では認識や確認が困難だが、私の分析では、NIKON一眼
レフにおいて2007年/2013年/2016年/2020年に
行われている。注:2020年のケースは未所有で、推測
これを調べるのは難しくなく、SIGMA/TAMRON/TOKINA
等の発表で「NIKON機 xxに対する不具合の対応について」
というニュース記事を見かけたらチェックするだけだ)
後、遠距離被写体でやや解像感が落ちる印象があるが
概ね気になる程では無いと思う。これはもしかすると
解像力の問題では無く、ピント精度(DCモーターの
停止精度)かも知れず、他のYONGNUOレンズと同様の
課題であるが、本YN100/2Nは、強制MFが使えないので
他のEFマウント版レンズよりも減点対象となる。
また、組み合わせる機種(例:NIKON D500)に
よっては、AF動作が不安定になり、AFが使用できない
ケースもあった。(これもNIKON機側の問題であろう。
他にも、NIKON D5300&SIGMA製2010年代レンズ
等の組み合わせでAFが動作しない場合もある)
ボケ質破綻は起こり難い。この点、EF100/2の旧型
New FD100/2でのボケ質破綻の頻発、とは大きな
違いである。(注:NFD100/2は、さらに古い時代の
数十年前の設計を踏襲していたからだろう)
![_c0032138_11510763.jpg]()
高目であったので、コスパ評価は辛目の3.5点だ。
CANON純正EF版の方が、シームレスMFが使える為
本レンズよりも優位に思えるが、いざとなれば
本レンズはミラーレス機等に装着してMFオンリーで
使ってしまえば、弱点は若干回避可能だ。
・・まあ、であっても、1万円台前半あたりまでが
適正相場であろう、2万円、となると、ちょっと
価格優位面を評価する事は厳しいと思われる。
他にも、銀塩時代から優秀な100mm/F2級レンズは
多数あるので、本レンズでなければならない理由は
さほど多くは無い。
また、組み合わせる機体によっては、露出やAF等の
問題が発生しやすい為、あくまで中上級マニア向け、
という結論にしておこう。
----
では、今回の「YONGNUOマニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。
今回は「YONGNUOマニアックス」という主旨とし、
同社製の4本のレンズを紹介する。
(全て、他記事で紹介済みのレンズの再掲であるが
実写掲載写真は、全て新規のものを使用している)
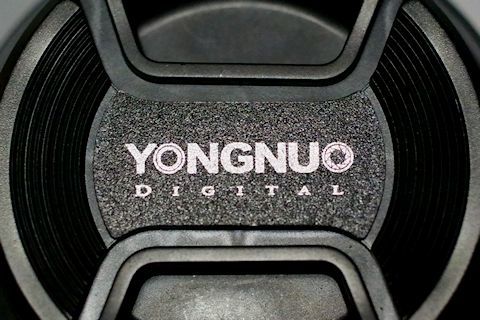
光学機器メーカー(のブランド銘)であり、2010年代
後半から、格安の高性能AF(単焦点)レンズ数機種で
日本市場に参入している。
・・とは言え、その全てのレンズは1990年代のCANON
製EF単焦点レンズ群の、フル(完全)コピー製品だ。
なんだか裏の事情が想像できるが、そこはさておき
これらのレンズが、実用的に使えるものなのかどうか?
そこを本記事では検証していこう。
紹介レンズ4本は、すべてAFで、かつフルサイズ対応の
単焦点レンズだ。(銀塩/デジタル一眼レフ用)
----
ではまず、今回最初のYONGNUOレンズ。

(中古購入価格 14,000円)(以下、YN85/1.8)
カメラは、CANON EOS 8000D(APS-C機)
2017~2018年頃(?)に発売された、単焦点AF小口径
中望遠レンズ。

のコピー品であるが、オリジナル品との大きな違いとして、
USM(超音波モーター)がYN85/1.8では内蔵されておらず、
この結果、CANON版にあった「フルタイムMF機能」つまり
AFで合焦中に、任意にピントリングを廻す事で、即時に
MFへ移行する事が「仕様上では」出来ない(詳細後述)
本YN85/1.8ではCANON EF版各レンズに存在するAF/MF
切換スイッチと同等の仕様により、MFで使用する場合は、
このスイッチをMF側に倒してあげる必要がある。
ただし、これは正規の使い方であり、「裏技」がある。
それは、このスイッチをAFのままにしておいても、強引に
ピントリングを廻す事で、USM仕様では無い本レンズでも、
シームレス(つなぎ目なし)な強制MF移行(すなわち
CANONで言うフルタイムMF)が、一応可能なのだ。
(注:有限距離指標+無限回転式ピントリング型)
しかしながら、これは「仕様外」の用法である。
この場合の課題は、EOS機にある「フォーカスエイド機能」
(ピントが合っているという状態を黄緑色の○表示で示す)
がちゃんと動作せず、最初にAFが合って○印が表示されたら
MFでピント位置を変えても、ずっと○印が表示されたままだ。
すなわち「強制MF」時には、フォーカスエイドが使用できず、
ピントが合っているか否かは、EOS機の光学ファインダーの
フォーカシングスクリーン上で、目視で確認するしか無い。
この時、EOS 6D/5D+Eg-S(MF用スクリーン換装)等では、
なんとか、スクリーン上でのピントの山が確認可能だが、
今回使用のEOS 8000D(初級機、スクリーン交換不可)
では低性能な為、MFでの利用は、ほぼ不可能となる。
なお、YN85/1.8のレンズ側AF/MF切換スイッチをMF側に
倒した際には、EOS (8000D)機側でのフォーカスエイド
機能は有効になり、MF合焦すれば○印が表示されるので、
カメラ側ファインダー(スクリーン)性能の低さによる
MFのやりにくさは、若干軽減できる。
ただし、この場合のフォーカスエイドは、AF測距点に
連動しているので、画面の端の被写体にMFで合焦確認を
行いたいのであれば、AF測距点を変更する操作が必要だ。
この為には数回のボタン操作が必要となり、操作性が悪化
するので、通常はこの操作を行わず、画面中央の測距点で
MF合焦を行い、構図を振って被写体を画面の端等とする。
(=MFロックという技法。匠の写真用語辞典第29回記事)
しかしながら、MFロック措置を行うと、撮影距離が変化し
ピンボケとなる恐れがある。
(コサイン誤差/セカント誤差。匠の写真用語辞典第29回)
これについては、本YN85/1.8といった被写界深度が浅く
なる可能性があるレンズでは無視できない可能性もある。
「匠の写真用語辞典第29回」記事での試算においては、
「撮影距離2m以上、又は絞り値F2以上」の、いずれかの
条件を満たせば、大口径85mmレンズでもMFロック操作時に、
被写界深度によりコサイン(セカント)誤差を起因とする
ピンボケは(計算上)起こらない事が確認済みだ。
ただまあ・・ そもそもフォーカスエイドの精度の課題や
低性能EOS機におけるスクリーンのMF精度の低さにより、
MFでの撮影全般では、ピントを外すリスクが極めて高い。
かと言って、AFでの使用でも同様だ。これはUSM非搭載
でのDCモーターによる、AFモーター停止精度不足および
初級機カメラ側での、AFアルゴリズム判定精度不足等が
あいまって、ピンボケを連発し、ピント歩留まりは悪い。
簡単な解決法としては、できるだけAF精度・性能の高い
機体、具体的にはCANON EOS 7D/7D MarkⅡ等を
母艦とする事だ。これらであれば、AFでのピント精度は
だいぶマシになるが、これらの機体でもMF性能は全く
期待できないので、似たり寄ったりの状況であろう。
しかしながら、EOS 7D系機体では高速連写が効くので、
高速連写MFブラケット(匠の写真用語辞典第35回/予定)
により、「下手な鉄砲、数撃てば当たる」方式でピントの
歩留まりを向上させる事は、一応可能だ。

YN85/1.8の描写表現力であるが、個人評価では特に問題は
無いレベルである。ただし「良好」とまでは言い切れず、
個人評価DBでは、5点満点中3.5点の得点である。
というのも、各社の85mm小口径(開放F1.7~F2.8)は
描写力に特に優れるものが多く、例えば近年のTAMRON
SP85/1.8(F016、2016年)が、その筆頭格だが、
古今東西で、その傾向は同様だ(例:Jupiter-9 85/2、
smc PENTAX-FA77/1.8、NIKON AiAF85/1.8D、
中一光学 CREATOR 85/2、SONY SAM85/2.8、
Voigtlander APO-LANTHER 90/3.5等)
そうした、85mm級の小口径名玉に比較すると、
本YN85/1.8の描写表現力は、少しだけ見劣りする。
これは、元となったレンズのCANON EF85/1.8USM
(1992年)の描写性能に起因しているかどうか?は不明だ。
残念ながら、EF85/1.8は所有の機会に恵まれておらず、
詳細な性能比較が出来ないからだ。
(EF85/1.8の購入を辞め、本YN85/1.8で代替した)

であると思われる。安価であれば、例えば今回購入時での
1万円台前半程度の中古品であれば、コスパはかなり良いと
判断する事が出来るであろう(コスパ評価4点)
初級中級マニア層に向けては推奨できるレンズだ。
ただし、上記ピント問題は、一般初級中級層には回避
が困難だと思われるので、実践派のマニア層以外には
非推奨だ。
---
では、次のYONGNUOレンズ。

(中古購入価格 8,000円)(以下、YN35/2)
カメラは、NIKON D5300(APS-C機)
2018年頃(?)に発売された、フルサイズ対応AF準広角
レンズ。

していたEF35mm/F2の完全(デッド)コピー品である。
ただしCANON EFマウント品では無く、NIKON Fマウント
版(N型番)としての購入だ(勿論EF版も存在する)
これのオリジナル品、CANON EF35mm/F2については
所有していて、レンズマニアックス第35回記事で
両レンズを比較検証済みである。
EF35/2は、後年にはUSM仕様となったが、初期型は
USMでは無く、DC(直流)モーター仕様である。
YONGNUOの完全コピー品の製造の「仕掛け」は、
だいたい分析が済んではいるが、あまり表立っては言えない
裏の事情もあるだろうから、そこについては言及しない。
1つ言える事は「YONGNUOはUSM(超音波モーター)
(やSTM)は搭載(調達)できていないのでは?」という
点だ。(注:STM等は、現代では中国で主に生産されて
いるので、いずれ、これらも搭載されるかも知れない)
だが、初代EF35/2には、USMが搭載されていなかった
ので、その点については、YN35/2もUSM無しで、完全
な同等品となる。
しかも、DCモーターが内蔵されている事で、ニコンF
マウント版(YN35/2N等)を製造した際にも、これを
NIKON初級中級機(D3000系、D5000系等。今回
使用のD5300も同様)においても、AFが動作する。
ここの詳細は、NIKON D3000系、D5000系等に
おいては仕様的差別化」により、AFモーター非内蔵の
AFレンズ(NIKON AF-S型では無いAiAF等の旧型レンズや、
レンズ・サードパーテイ製2000年代レンズの一部等)
では、AFが効かない(かつ、MF性能は恐ろしく低い)
という課題があるのだが、本YN35/2Nでは、幸いその
仕様的差別化の制限には掛らず使用できる、という事だ。
ただし、NIKON機での操作性仕様は他社機とは逆である
(1930年代~1950年代の旧CONTAX機の仕様を真似て
NIKON機(レンジ機、一眼レフ)が設計された為、
近代に至るまで、NIKON機での多くの操作性が他社と
逆となっているという問題点)・・その、逆である為、
EF35/2をベースとした本レンズでは、ピントリングの
回転方向と距離指標が逆に動く、という気持ち悪さ
(操作性の悪化とエンジョイ度の減少)が存在している。
これについては、本YN35/2は準広角レンズであり、
前述のYN85/1.8のような、技法上の精密ピント合わせ
操作を要求されない(AFで中遠距離被写体をスナップ
的に撮れば良い)という点で、仕様上の気持ち悪さは
あまり気にならなくなるとは思う。

としている為、当然ながらフルサイズ対応レンズだ。
しかしながら、EF35/2とYN35/2は、像面湾曲収差や
非点収差の補正が行き届いていない、だから、ボケ質
の破綻が若干出る。
これを低減するには、まず前述のように中遠距離撮影
に特化してボケを出さない事。そして、ボカす場合は
ボケ質破綻の回避技法(匠の写真用語辞典第13回記事)
を用いる他、フルサイズ機では無くAPS-C型以下の機体を
用い、画面周辺収差のカットを図る事、等が望ましい。
つまり、この場合フルサイズ機では無く、APS-C機の
方が画面全体での描写力の均一性が改善される訳だ。
おまけにピクセルピッチが狭く、ローパスレス仕様でも
ある、母艦NIKON D5300であれば、本YN35/2との
仕様的マッチングに優れる(=弱点相殺(型)システム。
匠の写真用語辞典第1回記事参照)
ただまあ、これらのレンズやカメラの仕様・性能上の
詳細を理解し、弱点を緩和する為の適正なシステムを組む、
という発想は上級マニア層以上向けの話であり、他の一般
ユーザー層には、とても困難であると思う。
でも、ビギナー層等で「フルサイズ機の方が写りが良い」
と思い込んでいるユーザーには是非理解して貰いたい事だ。

1990年頃に設計された「セミ・オールドレンズ」ながら、
当時の技術水準からは、他社同等品に対しての性能的な
優位点は存在していたと思われる。
ただまあ、やはり古い。例えば、近代設計による、
TAMRON SP35/1.8(F012、2015年)と比較すると、
あらゆる点(描写力、最短撮影距離、ボケ質、ピント精度、
手ブレ補正等)で見劣りしてしまうのは確かであろう。
本レンズの最適な用途は「使いつぶし」型であろう。
安価であるので、過酷な撮影環境(雨天や酷寒・猛暑等)
で、あまり故障を気にせず、ガンガンに使うのが良い。
そういう意味では、中級層以上には推奨できるレンズだ。
----
さて、3本目のYONGNUOレンズシステム。

(中古購入価格 4,000円)(以下、YN50/1.8)
カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)
2014年頃? に発売された、小口径AF標準レンズ。
発売は少し古いが、国内流通が活性化したのは
後年の2017~2018年頃だと思われる。

初の「エントリーレンズ」であり、EOS機の普及と
ユーザー層のCANON製品への「囲い込み」を目指した
戦略的低価格帯レンズ。以降の時代の初級中級層には
「安価なのに写りが良い」と「神格化」されている)
のフル(完全)コピー品である。
両者の違いは、絞り羽根の枚数くらいであり、それに
よる描写力の差も、木漏れ日や夜景ボケの形状の差と
光条等の差くらいの微々たるものであり、一般的撮影に
おける描写力の差は、ほとんど無い。
完全コピー品というよりは、同一部品を同一生産設備
で組み立てられた物、という様相がかなり強いのだが
そのあたりは、中国生産を辞めた、などの裏事情が
色々とある、と推察される為、その出自については、
あまり詮索しないようにしよう。
(注:電子部品が異なる模様であり、電子マウント
アダプターを使用した場合、オリジナル品とは動作が
異なる。詳細は長くなるので、他記事で説明する)
なお、YONGNUOの50mmレンズには、他にCANON
EF50/1.4 USMのコピー品のYN50/1.4や、本レンズの
改良品のYN50/1.8Ⅱがあると聞くが、それらは未所有だ。
そう何本も似たようなレンズは不要だし、YN50/1.4は
USMが未搭載である(かつEF50/1.4USMは所有している)
まあ、個人的にはYONGNUOの50mmは、本YN50/1.8で
打ち止めとしておこう。

持つレンズである為、EOS 7D/7DMarkⅡ等の高性能
AF機と組み合わせた方が弱点を相殺できて無難だ。
しかし、中古価格4000円と安価な本レンズを、高性能
機体で使うのも、アンバランスであり、これは持論の
「オフサイドの法則」(匠の写真用語辞典第16回)に
ひっかかる。
今回は「限界性能テスト」(匠の写真用語辞典第27回)
の意味を含め、フルサイズ機のEOS 6D(2012年)を
使用する。
すなわち、1990年代の銀塩時代において、高描写力
を好評価されたEF50/1.8Ⅱであるから、フルサイズ機
で使用した場合でも、描写力上の欠点(例:周辺収差)
は目立たないのではなかろうか? という検証だ。
なお、何故「周辺収差」と呼ばれる問題が課題となる
かは、レンズはその性能上、画角に比例または累乗で
増加する収差の類が多く存在するからである。
(匠の写真用語辞典第29回記事参照)
具体的には、歪曲収差、コマ収差、像面湾曲、非点収差
等がそれであり、中には絞りを絞り込んでも解消されない
収差も存在するし、収差以外にも、「口径食」等による
周辺減光もある為、簡便な改善方法としては、フルサイズ
対応レンズであってもフルサイズ機を使わず、APS-C機や
μ4/3機に装着して用いると良い。
他分野の簡単な事例で言えば、肉や果実等での中央部の
「美味しい部位」だけを贅沢に食べる、という感覚だ。
特に、オールドレンズ等で周辺収差が大きく、実用性能に
満たないレンズであっても、μ4/3機に装着するだけで
周辺収差が目立たず、なんとか実用範囲に収まる例もある。
まあ要は、レンズの性能や特性次第では、常にフルサイズ
機では使わない方が良い結果を得られる場合も多々ある
という事実であり、逆に言えば、フルサイズ機で欠点を
さらけだしてしまえば、そのレンズの性能的な限界点を
知る事にもなる。まあそれが「限界性能テスト」としての
今回やろうとしている事だ。
で、EF50/1.8(注:私が所有しているのは、EF50/1.8Ⅱ
型ではなく、光学系が同一の初期型=1987年である)も、
本YN50/1.8も、若干の逆光耐性の低さと、軽微なボケ質
破綻が発生する。
ただまあ、逆光耐性については、多くの銀塩時代の
レンズで同様であり、当時はビギナー層や一般層ですら
「カメラは逆光で撮ると写りが悪い」という認識を
持っていた。だから、皆に逆光を回避して撮影する習慣が
あった為、現代のスマホカメラの一般層よりも、この時代
(1990年代)の一般層の方が、逆光回避技能に優れ、
逆光時の描写力低下(フレア、ゴースト、低コントラスト
化等)については、むしろ寛容であったと思われる。
(=「逆光なので、しかたが無い」という認識)
また、当時の銀塩EOS初級中級機では、最高シャッター
速度が1/2000秒~1/4000秒止まりであった。
よって、ND(減光)フィルターを使わない限りは、
日中晴天時、ISO100の低感度フィルムを使った際でも、
絞りを最大F4(1/2000秒機)又はF2.8(1/4000秒機)
までしか開けれない(開放F1.8を使うと、シャッター
速度オーバーとなる)また当時は、ISO400等の中感度
フィルムを使う事も一般的であり(つまり、ビギナー層
では、露出の原理を知らずして、数値が大きいフィルム
の方が、単純に「良い」と思ってしまう) ISO400の
フィルムでは、さらに、F5.6~F8程度までしか、
絞りを開けて使う事が出来ない。
この環境であると、EF50/1.8(Ⅱ)を使って、日中に
背景をボカした(被写界深度が浅い)撮影は、ほぼ不可能だ。
しかし絶妙な事に、このEF50/1.8(Ⅱ)の、5群6枚
変形ダブルガウス型構成では、絞りをF4~F5.6まで
絞り込む事により解像感が向上する、という優れた特性を
持っている。
(注:EF50/1.8系に限らず、他社銀塩用AF50mm/F1.8級
レンズと、1970年代~1980年代の殆ど全ての各社の
MF50mm/F1.8級、5群6枚型構成で同様の描写特性を持つ。
別シリーズ「最強50mm選手権」、第2回AF50mm/F1.8級、
第4回MF50mm/F1.8級の対戦記事を参照。
また、近年の中国製ジェネリックレンズや、国内の
一眼レフ用エントリーレンズでは、この優秀な銀塩用
50mm/F1.8級構成をスケールダウンし、25~35mm級の
APS-C機以下用F1.8級レンズに設計変更して販売している)
すなわち、EF50/1.8(Ⅱ)の、この特性は、当時の銀塩
機材環境では、「確信犯」的に、必然的に高描写力が
得られる用法になる訳である。これを無理した利用法で
被写界深度を浅め、結果、像面湾曲や非点収差により
「ボケ質破綻」が発生してしまうケースは考え難い。
つまり、初級中級層においては、CANON EF50/1.8(Ⅱ)
や、本YN50/1.8は、多くの使用条件で、高描写力が
発揮できる事となり、結果として、EF50/1.8(Ⅱ)
が当時の銀塩機材環境において、EF50/1.8(Ⅱ)の
その特性が高く評価され、結果的にそのレンズが、
初級中級層により「神格化」されてしまったのであろう。
まあでも、別に何ら問題がある話では無い、当時の
機材環境に適切な仕様のレンズを提供した「企画上の
勝利」である。
EF50/1.8の価格が比較的安価なのも当然であり、
(1970年代より)もう、20年間近くも作り続けた、
極めて完成度の高い「5群6枚変形ダブルガウス型」
レンズ構成である。
高価な非球面レンズも異常低分散ガラスも、その光学系
には不要であるし、設計費も製造設備原価も、とっくの
昔に元が取れている状態だ、これを高価に売ろうとしたら、
むしろそれは「ぼったくり」であろう。
でも、囲い込み用途があるとは言え、安価なレンズでは、
やはり製品単独で見た場合では利益が出にくい(大きな
黒字には成り得ない)状態となってしまう。
そこで、CANONにおける初期型EF50/1.8は、国内生産で
2万円以上の定価販売となってはいたが、ここを低価格
化しようとした際、続くEF50/1.8Ⅱでは、海外(中国)
生産として、製造原価をさらに下げながらも、約1万円
の定価販売でも十分に利益が出るような原価構造にした
のだろう、と容易に想像できる。
その海外生産工場が、YONGNUO(永諾撮影器材株式有限
会社)だったか否か? そこは当然非公開であるから、
実際のところは不明である。
ただ、1990年代であれば中国での人件費は、日本の
1/10以下と言われていた。だが、2010年代前半には、
中国での人件費が高騰し(数年間で数倍となった)
海外生産がやりにくくなった、とも推察される。
(他に、勿論、2010年代からのカメラ・レンズ市場
の大幅縮退により、大量生産スタイルが効率的では
無くなってきている)

ほぼEF50/1.8Ⅱと同一である。
だから描写力も同様、長所も弱点も同様である。
あえてYN50/1.8の弱点をあげておけば
1)逆光耐性の低さ (撮影技法で回避可能。
または、下写真のように適当なフードを装着する)
2)軽微なボケ質破綻(高度な撮影技法で緩和可能)
3)若干のAF精度不足(母艦の選択で若干緩和可能)
となるのだが、これらはいずれも軽微な弱点であるから
重欠点とは言い難い。

(相場7000円前後)よりも安価に入手する機会がある
場合のみ推奨できるレンズである。
EF50/1.8Ⅱよりも高価であったら、中身はほぼ同じ物で
あるから入手する必然性は無い。
中級層以上であれば、誰にでも推奨できるレンズでは
あるが、これを「やはり安物の中華レンズだ、良く写る
筈が無い」などの、思い込み評価しかしない(できない)
ビギナー層に対しては非推奨だ。思い込み思想で満足感を
得たいならば、CANON純正品を買えば良いであろう。
----
では、次は今回ラストのYONGUNOシステム

(新古購入価格 19,000円)(以下、YN100/2)
カメラは、NIKON D300(APS-C機)
2018年頃(?)に発売された、フルサイズ対応AF中望遠
レンズ。

オリジナルとなったのは、CANON EF100mm/F2 USM
(1991年発売。現在未所有)である。
ただし、前述の状況から、本YN100/2(N)には、
USM(超音波モーター)は搭載されていない。
しかし、DCモーター内蔵であるからNIKON Fマウント
版の本レンズであっても初級機(D3000系、D5000系)
でAFが効く。
だが、NIKON Fマウント版においては、前述のEF版
(YN85/1.8)のように「強制MF」操作には対応して
おらず、本YN100/2NでAF合焦後にピントリングを
廻しても、空回りするだけでMFは効かない。
MFにしたい場合は、レンズのAF/MF切換スイッチを
MF側に倒すしか無い状態であり、面倒な操作性だ。
本レンズのオリジナル品、EF100/2USMは、銀塩時代
に使用していたのだが、事情があって銀塩時代の末期に
知人に譲渡してしまっていた。写りは気に入っていて
後年に買いなおそうとしていたのだが、中古相場が
ずっと3万円以上と高値安定であったので、コスパを
考えると、やや買い難い状況が続いていた。
そんな状況の中、近年に本YN100/2(N)の中古品を
見かけた次第だが、新古品(新品?)で、ほぼ定価販売だ。
あまり割安感を感じなかったが、NIKON Fマウント版
は、元々若干定価が高価であったし、これでもCANON
EF100/2USMの中古より安いし、あるいはあまり多くの
YONGNUOレンズを全てEF版で買うのも躊躇いがあった
ので、若干の高値相場は許容し、これを購入した。

銀塩時代のEF100/2USMが手元に残っていれば比較が
容易だったが、残念ながらそれは無い。
銀塩MF時代のNew FD100mm/F2ならば、所有しては
いるが、そのレンズは恐ろしく描写表現力が低いので
AF時代に入って、EF100/2USMに改良されたのであろう。
CANONは、そのメーカーのイメージからは意外なほどに
レンズ構成の小改良をこまめに行っている。
普通、大企業(大カメラメーカー)と言えば、
そういう手間や費用のかかる改善をあまりせず、利益を
優先する傾向があるし、ユーザー優先ではなく、メーカー
の都合で事を運ぶ傾向が極めて強い。そういう点が
目につくと、大メーカーの戦略に反発する要因となって
しまうのだ、そういう例はカメラ界ではいくらでも存在
しているし、本ブログ記事での評価では、そうした
メーカー側の姿勢を問う内容も多くなっている。
だが、CANONにおいては、他の機材での企画はともかく
として、レンズにおいては性能が低いと(自社でも)認識
されたものは、ちゃんとその改良をこまめに行っている
点は良いと思う。これはユーザー側から見た評価とも
ほぼ連動しており、「このレンズはちょっとなあ・・」
と感じるものは、短期間でそれを改善した後継機が
発売されている。
逆に言えば、CANON製レンズでロングセラーとなっている
ものは、メーカー側においても「改良の必要性が低い」
と認識されていると思われ、そういうレンズは完成度
が高く、かつ昔から販売されているから、後年において
中古相場が下落しており、購入においてコスパが抜群に
良いものが出てくる訳だ。
この製品価値判断手法は、上級マニア向けとは言えるが、
とは言え、レンズの製造年代を調べるだけで済むので
初級マニア層でも可能であろう。参考にされたし。
ただ、誰もが、そういう「えげつない」機材購入手法を
取ってしまうと新品が売れず、CANONはカメラ事業を
続ける事が難しくなり、次期新製品が、とんでも無く
高価に値上げされてしまったり、あるいは最悪では
「もう儲からないから」と、カメラ市場から撤退して
しまう危険性もある、そうなってしまうとユーザー
側でも困る(2000年代のCONTAXやKONICA MINOLTA
のカメラ事業撤退は、本当に困った状況であった)
なので、ここは申し訳ないが、「事の本質」を良く
わかっていないビギナー層等に、高価な最新鋭機材を
買ってもらい、メーカーや流通市場を潤してもらう
しか無い。ビギナーでは旗艦機や大三元レンズを
使う必要性も無いし、使いこなせない事は明白だが、
ビギナー層の、そうした無駄な出費(業界への献金)
により、カメラ市場が崩壊せずに続いているという
現状を良く鑑みれば、そういう出費は好ましい。
まあつまり、わかっている人は、無駄を無くすような
購買行動をすれば良い、そうでない人達も、好きに
購買行動を起こせば良い訳だ、それで世の中は上手く
廻っている。「自分が損をしている」(「ユーザーの
負けの状態」である)は、自身が気がついていなければ、
それはそれで、何も問題は無い。
自分でも、ずいぶんとドライな意見だとは思うが、
それが現代の世の中の真実である以上、個人的な感覚は
挟む必要も無いであろう。
余談が長くなった、本YN100/2の描写力等の詳細で
あるが、まず課題となるのは、本レンズと多くの
NIKON機との組み合わせで露出が不安定(アンダー
気味)となる事だ。
これの回避は、機種によっては、露出補正を掛けるか、
場合により、中央重点測光モードに切り替える措置も
有効な事がある。NIKON機の機種によっては安定露出
が得られる場合もあるので、レンズ側では無く、
NIKON機側の露出決定アルゴリズム上の問題点だ。
(=近代のNIKON機で、純正以外の他社製レンズの一部
でアンダー露出となる露出制御プログラム上のバグ、
または、意図的な「排他的仕様」だと思われる。
なお、このようなソフトウェア的な改変は、外部から
では認識や確認が困難だが、私の分析では、NIKON一眼
レフにおいて2007年/2013年/2016年/2020年に
行われている。注:2020年のケースは未所有で、推測
これを調べるのは難しくなく、SIGMA/TAMRON/TOKINA
等の発表で「NIKON機 xxに対する不具合の対応について」
というニュース記事を見かけたらチェックするだけだ)
後、遠距離被写体でやや解像感が落ちる印象があるが
概ね気になる程では無いと思う。これはもしかすると
解像力の問題では無く、ピント精度(DCモーターの
停止精度)かも知れず、他のYONGNUOレンズと同様の
課題であるが、本YN100/2Nは、強制MFが使えないので
他のEFマウント版レンズよりも減点対象となる。
また、組み合わせる機種(例:NIKON D500)に
よっては、AF動作が不安定になり、AFが使用できない
ケースもあった。(これもNIKON機側の問題であろう。
他にも、NIKON D5300&SIGMA製2010年代レンズ
等の組み合わせでAFが動作しない場合もある)
ボケ質破綻は起こり難い。この点、EF100/2の旧型
New FD100/2でのボケ質破綻の頻発、とは大きな
違いである。(注:NFD100/2は、さらに古い時代の
数十年前の設計を踏襲していたからだろう)

高目であったので、コスパ評価は辛目の3.5点だ。
CANON純正EF版の方が、シームレスMFが使える為
本レンズよりも優位に思えるが、いざとなれば
本レンズはミラーレス機等に装着してMFオンリーで
使ってしまえば、弱点は若干回避可能だ。
・・まあ、であっても、1万円台前半あたりまでが
適正相場であろう、2万円、となると、ちょっと
価格優位面を評価する事は厳しいと思われる。
他にも、銀塩時代から優秀な100mm/F2級レンズは
多数あるので、本レンズでなければならない理由は
さほど多くは無い。
また、組み合わせる機体によっては、露出やAF等の
問題が発生しやすい為、あくまで中上級マニア向け、
という結論にしておこう。
----
では、今回の「YONGNUOマニアックス編」は、
このあたり迄で、次回記事に続く。