本シリーズは、所有しているミラーレス機の本体の詳細を
世代別に紹介して行く記事だ。
今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は
第一回記事参照)の PENTAX K-01(2012年)を紹介しよう。
(注;この年では、PENTAXはRICOHの傘下ではあるが、
ブランドとしてのPENTAXは残っている)
![c0032138_18331799.jpg]()
(ミラーレス・マニアックス第11回,第60回記事参照)
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めて
いくが、記事後半では別のレンズに交換する。
また、掲載写真はK-01の本体機能のエフェクトを多用する。
![c0032138_18331723.jpg]()
カメラの回が来てしまった(汗)
本機K-01は発売年が2012年なので、一応、本シリーズでの
世代分類上では第二世代のミラーレス機であるのだが、
本機の性能からすると、第一世代に分類されてもおかしく無い、
なにせ、AFでもMFでもまともにピントを合わせる事ができない
と言う、致命的、あるいは落第点とも言えるカメラだからだ。
本機K-01については、過去、特集記事で紹介した事があり、
そして、デジタル一眼レフ・クラッシックス第14回(番外編)
記事でも取り上げている。
すでに3度目の登場であり、出自や仕様等は、それらの過去
記事に詳しいので、今回はまた違った内容で本機を紹介して
いく事とする。
![c0032138_18331728.jpg]()
「何をしてもピントが合わない」という重欠点である。
では、「とんでもなく低い評価なのか?」というと、それが
そうでも無いのである。
デジタル一眼記事での本機の評価点は、ちょうど平均値の
3.0点であった、本ミラーレス・クラッシックス記事では、
デジタル一眼記事よりも評価項目数が増えてはいるが、
恐らくラストの総合評価点は、平均値3点に近い位置まで
行くと思われる。
・・と言うのも、本機K-01は、性能以外の評価点が極めて
高いカメラなのである。
![c0032138_18331793.jpg]()
試験の成績は酷い点数なのに、何か飛びぬけた特技がある、
例えば、ゲームが非常に上手いとか、容姿端麗であるとか、
コメディアンのように皆を笑わす才能があるとか、まあ、
そんな類の事である。
学校の先生からすれば、ちゃんと勉強や運動が出来て、
性格が良い子供の方が扱いやすい事は確かであろう。
でも、そうした強烈な個性をも、現代の教育シーンでは、
ちゃんと認めてあげるようになってきていると思う。
さもないと、皆が皆、型にハマった画一的で優等生的な
子供達ばかりになってしまい、面白くないし、国際社会で
生き残る個性や発想を持つべき日本の将来の為にも良く無い。
本機K-01は「問題児」である。だから、一般的なカメラに
対する感覚を、使う側で変えていかなければならない。
すなわち、テストの成績が悪い子供を、先生が見放すと、
結果的に「落ちこぼれ」になってしまうようなものだ。
落ちこぼれるのは、その生徒本人に100%責任があるとは
限らない事であろう、きっと、生徒を取り巻く環境にも
様々な問題がある筈だ。
K-01を「AFが合わないからダメなカメラだ」と切り捨てて
しまったら、本当に「落ちこぼれ」だ。でもせっかく買った
カメラである、どうやったら、この問題児の個性が活かせる
のかを考えるのが、先生(ユーザー)の責務であろう。
![c0032138_18324919.jpg]()
マーク・ニューソン氏の手による、その超個性的な
スタイルが上げられる。ここは好き嫌いがあると思うが、
およそ今までのどのカメラとも異なる独特の雰囲気があり、
目立つという点では間違いない。
ただし、デザイン優先で、機械としての「作り」が犠牲に
なってしまった点も少々ある。
また、デザインの個性により、装着するレンズのバランス的
なセンスも問われてしまう、なかなかクセのあるカメラだ。
それから、マニアック度が高く、歴史的価値が高い事だ。
でもまあ、これはマニア向けの要素で、一般的ユーザーには
あまり関係が無い事であろう。
![c0032138_18324960.jpg]()
仕様および操作系により「エフェクト母艦」として使用する
際に、最大のパフォーマンスを発揮できるという点だ。
近年では、一般的なデジタル一眼レフ/ミラーレス機や、
コンパクト機、携帯電話カメラやスマホカメラのアプリでも
エフェクトは普及しているので当たり前の機能とは言えるが、
本機K-01のエフェクトは、遊びの範疇を越えて、写真表現と
しても利用可能なレベルだし、エフェクト利用時の操作系は、
一眼レフや携帯カメラの追従を許さない。
![c0032138_18324916.jpg]()
本機のエフェクト機能を用いた写真を多数掲載している、
また、これが楽しい為、評価点においては、「エンジョイ度」
が高くなり、加えて「描写力・表現力」の点数も高い。
ここが、性能や完成度が低い本機K-01でも、その他の要素が
好評価となり、どうにも気になる「問題児カメラ」という
レッテルが貼られてしまう理由だ。
![c0032138_18331713.jpg]()
でも述べたが「唯一の(孤高の)Kマウントミラーレス機」
である。
Kマウントと言うのは、ご存知、PENTAXの一眼レフ用の
マウント名称だ、その出自については例えばデジタル一眼
第5回「PENTAX K10D」の記事に詳しい。
後にも先にも、一眼レフ用と同じマウントでミラーレス機を
作ってしまった例は無い、本機K-01が、最初にして最後、
唯一無二である。本機の歴史的価値は非常に高い。
なお、APS-C型以上のミラーレス機で「初の手ブレ補正搭載」
という歴史的価値もあるが、まあ、これは他のPENTAXの
Kマウント一眼レフを使った方が遥かに便利なので、あまり
重要な意味は無いであろう。
![c0032138_18331781.jpg]()
「Q」システムが存在する。
最初の「PENTAX Q」は2011年発売、これがPENTAXでは
初のミラーレス機だ、本シリーズでの世代分類では
第二世代=普及期(各社からミラーレス機が出揃う)に
相当する時代だ。
なお「Qシリーズ」は2014年まで4機種が展開されたが、
現在では新製品の発売は止まっている。
市場の状況の変化、および親会社のHOYAからRICOHへの
変革期においての戦略転換であろう。
本機K-01は、Qシリーズの後から発売されている。
何故、2つの異なるミラーレス機のシリーズをPENTAXが
展開していたか、その理由は明らかにはされていないが
HOYA時代の戦略は、エントリー層に向けてカメラを普及する
要素が大きかったと思われるので、その一環なのかもしれない。
Qシリーズは、当初1/2.3型という、普及型コンパクト機
並みの小型センサーで展開した、しかし、2010年代では、
「センサーの大きいカメラが良いカメラ」という常識(?)が、
一般ユーザー層に広まった時代でもある。
まあ、そういう理由もあるからかQシリーズは商業的に苦しく
なってしまい、シリーズ3機種目のQ7(2013年)からは、
1/1.7型センサーに、心持ち大型化された。
しかし、これでもまだ小さい、だから、他社ミラーレス機
と同様のAPS-C型センサーのミラーレス機を、PENTAXに
おいてもラインナップする必要があったのかも知れない。
(注:Q7よりも本機の方が先に発売されている)
ただ、Qシリーズは、センサーサイズを小さくする事で
カメラ本体もレンズも小型化する事を可能とした多大な特徴
を得る事ができた、すなわち必ずしもセンサーが大きい事が
良い事ばかりでは無い、という事であり、
センサーが大きくなると、カメラ本体のみならずレンズも
含めたシステムが「大きく、重く、高価になってしまう」
という弱点(三重苦)が必然的にのしかかる。
![c0032138_18331640.jpg]()
例えば同時代のSONY NEX-7では、2400万画素であったのが
本機K-01では、1600万画素だ、これでは旧来からの
「画素数が大きい方が良い」というユーザーの思い込みに
引っかかってしまう。
で、何故「センサーが大きい方が良い」という話が広まったか
と言うと、それ以前の2000年代は、デジタルカメラの発展期
であり、一般ユーザーは、その性能基準として「画素数」に
着目していた。
つまり「画素数の大きいカメラの方が綺麗に写る」という
風に思っていたのだが、これは、ある意味、この時代特有の
「売り文句」である。つまり、そういう風に、画素数を大きく
するようにデジタル(センサー)技術が発達したから、それを
メーカーやメディアが、ユーザー層に強くアピールした結果、
ユーザー側が、そう思い込んだ、というだけの話である。
その後、2010年代になると、まずは先行したミラーレス
規格のμ4/3に対する、他社陣営の「差別化戦略」(μ4/3は
センサーが小さいから、我が社の大型センサーが優れている
という売り文句)が始まった。
そして同時に、スマホの普及による小型機(コンパクト等)
の低迷や、カメラ市場の縮退(スマホで撮れば十分だから
重たい一眼レフを持ち歩く必要が無い、というユーザー論理)
に対抗・対応する為に、大型化センサーが「高付加価値」商品
(つまり、「凄い」とユーザーに思ってもらえ、価格が高く
ても売れる=カメラの販売台数が減ってもやっていける)
であった事が、「大型センサーが良い」という話が広まった
理由であろう。
カメラに係わる業界は、こうして、ユーザー層に「ある種の
価値観」を(植えつけて)持ってもらなわないと、カメラが
売れずに市場が崩壊してしまうという危機感を感じている訳だ。
だから現在では「新しい高機能の高価なカメラが良いカメラ
である」と、業界関係者の誰もが言い、古い機種は、さっさと
市場から消し去ってしまっている。また中古店(中古市場)も
流通がだんだんと苦しくなり、「別にそれまでのカメラの性能
(仕様)でも十分」と思っても、もはやそうした古いデジタル
カメラを安価に入手する事自体が難しくなってきている。
まあ、古いカメラを安く売っても中古店は儲からないので
やっていけなくなるので、これもやむを得ない傾向であろう。
ただ、個人的には、どうも、市場に「乗せられている」
気がして、こういう傾向は好ましくないと思っている、
だから、私なりの購買(消費)行動の考え方やルールを色々と
儲けて、自分なりの価値観を構築しようとしている訳だ。
そういう考え方も、近年の「マニアックス系」のシリーズ記事
のコンセプトや執筆理由となっている事も事実だ。
![c0032138_18331649.jpg]()
まず、2000年代の「画素数神話」の件だ。
実際のところは、例えば、2004年頃の各社の600万画素級
CCDで、写真としてはもう十分に実用的なレベルにあった。
それは、デジタル一眼レフ・クラッシックスのシリーズ記事
で、第2回「PENTAX *istDs」から、第4回「NIKON D70」
あたりを読み返してもらい、掲載写真を見て貰えれば
わかる事であろう、それらのカメラは、全て600万画素機だし
実際にはさらに小さい画素数(300万画素程度)で撮って
いるが、ブログでの掲載上では何ら問題ない。
で、たとえばその600万画素で写真をプリントするならば、
具体的には、必要最小限の印刷品質である
175dpi(ドット・パー・インチ)で印刷した場合、
それが、3008x2000画素であれば、
横3008pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約43.6cm
縦2000pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約29.0cm
の用紙まで印刷する事が可能となり、これはだいたい
A3サイズ(42.0cmx29.7cm)に相当する。
2000年代、まだDPE店では旧来のフィルム用プリント機を
デジタルプリント用に流用していた。そういう店舗で
一般写真をプリントする場合、L判か、せいぜい2L判
(17.8cmx12.7cm)程度であり、600万画素は十分すぎる
画素数だ。
そして、たまに写真展などに出す(展示する)としても、
まあ、ワイド四つ切り(36.5cmx25.4cm)程度であろう。
つまり、600万画素あれば、これらのプリント用途は全て
問題なくクリアできる。
家庭用PCプリンターでも同様で、一般的にはA4までだ。
A3プリンターも勿論この時代から存在したが、大きいので
置ける家庭環境は限られていた事であろう。そして仮にA3で
印刷したとしても、前述のように600万画素で問題ない。
なお「印刷で175dpiは低すぎる」とは思うなかれ、人間の
視覚や閲覧距離、印刷用プリンターの性能(解像度)など
からすると、現実的には175~350dpiあたりが印刷品質と
しては適正な範囲だ、と様々な研究結果で述べられている。
で、印刷屋さん等に印刷を頼んで、写真を入稿する際に、
「600dpiなければ受け付けません」と言われる場合も
あるのだが、これはまあ「安全マージン」だと思えば良い
であろう、入稿画像品質が悪くて、それのせいで印刷屋さん
が文句を言われたら、かなわないからだ。
実際にはそこまでの印刷dpi数は不要である。
余談だが、印刷屋さんによっては、画素数とかdpiの計算
方法を知らない場合もあるようだ。まあ、カメラマンでも
フィルムからのデジタル化時代において、様々な誤解や
混乱が、いくらでもあったのだから、他の業界でも同様だ。
そして、時には何万画素以上とか何dpiで、とかではなく、
「2MByte以上のJPEGで下さい」と言われる場合もある。
まるで、「肉の量り売り」のようなイメージだ
画像という2次元の要素を、重さとか量とかの1次元変数に
変換しているようで、どうにも気持ちが悪い。
まあ、結局、デジタル画像に関しては実際の所では様々な
高度な知識を要求されるものだから、皆が皆、その全てを
理解しているものでは無い、という事なのであろう。
で、ファイルサイズで量るのは、これも多大な問題があり、
例えば、被写界深度の極めて浅い写真(例:マクロレンズで
近接した花を撮って背景が全てボケた画像)や、同一の色調
の画素が極めて多い写真(例:夜間の花火写真で、背景の殆ど
が漆黒の闇とか、ほとんどが青空とか)の場合、これらは、
JPEGの原理的には非常に大きい圧縮率となる、つまり目標と
する圧縮率に比べて、非常に小さいファイルサイズとなるのだ。
圧縮率の計算方法だが、まずは非圧縮の24bit形式を
基準値とする、これは、RGB(赤・緑・青)の3色に各8bitが
割り振られている訳だから、その基準ファイルサイズは
横ピクセル数x縦ピクセル数x3色でByte数が計算できる。
簡単な例として、600万画素で計算してみよう、
横約3000x縦2000x3=1800万Byte
約100万Byte(1048576Byte)で1M(メガ)Byteであるから、
上記は約17MByteとなる。
JPEGの圧縮率だが、肉眼で見た場合、上記非圧縮の容量を
1/10まで圧縮しても、標準的な空間周波数分布を持つ画像で
あれば問題は無い、だから、これをJPEG化する場合、
600万画素=1.7MByte が標準的ファイルサイズとなる。
これ以上、圧縮率を下げる(ファイルサイズを大きくする)
事をしても肉眼で見た画質は向上しない、だから、例えば
1/4圧縮などは、実は冗長なのだ(意味が無い)
そして、前記、被写界深度の浅い写真は、同じ目標圧縮率
(例えば1/10)を設定しても、ファイルサイズは、どんどん
と小さくなる、被写界深度の浅い写真では1/20程度、
さらに非常に深度の浅い、あるいは同一画素が多い写真では、
1/30~1/40程度までの比率で圧縮される。
ファイルサイズで言うと、それぞれ850KB~570KB程度である。
花火の写真も同様で、数百KBYteにしかならない。
以前、花火のイベントの電車内ポスターを作る際、その印刷
屋さんが「2MByte以上で欲しい」の類であった。けど、例えば、
5400x3500ピクセルの約1800万画素で入稿してもファイル
サイズは1MByte強にしかならない(圧縮率=1/40程度)
2MByteなんて、いくら画素数を上げても、なる訳が無いのだ。
ところが、これの説明がなかなか担当者に伝わらない、
「2メガ無いと印刷できないので困るんです」といった感じだ。
やむをえない、実例として試験的に1800万画素の真っ黒な
画像を作り、それをJPEGで保存すると、たったの300KByte
にしかならない事を実演(注:これは誰でも実験出来る)
「2MByteにしようとしたら、1億画素を越えてしまいますよ!
そんな大きな画素数のカメラは売っていないと思いますが・・」
と、「画像のパターンによってファイルサイズが違う」という
事を説明するのに苦労した事がある。
![c0032138_18331674.jpg]()
ブログや各種SNSの普及が始まった事がある。
これらは、当時は普通はパソコンの画面で見るものであった、
Windwos XP等での基本画面解像度は、XGA(1024x768)だ、
これは、約75万画素(しかない!)に相当する。
で、実際には、SNS等はブラウザで見るものであるから
PC画面いっぱいにまで写真が広がって表示される事は無い、
大きくてもVGA(640x480=30万画素)くらいである。
ちなみに、本ブログにおいては、開設当初(2005年)より、
ずっと約20万画素で写真を掲載している。
ちなみに、スマホ等では、PCより画面解像度はさらに低い。
で、これらPC閲覧環境は高々数十万画素だ、600万画素でも
巨大すぎる為、思い切り縮小しなくてはならない。
(注:縮小とは画素数(解像度)を下げる事、前記の圧縮
とは、同じ画素数でファイルサイズを小さくする事だ。
まず、この両者を混同している人が極めて多い、これは
画像処理での基本中の基本であり、間違えると格好悪い)
もし、自分自身で画像を縮小しないと、ブラウザにおいて、
HTMLコードのIMG SRCタグに書かれたサイズ・パラメーターに
より、自動的に(勝手に)縮小される。しかしながら、縮小の
方式(アルゴリズム)は、バイキュービック法やLANCZOS法
など様々な手法があり、しかも、ブラウザによって、それは
異なる(縮小精度を優先するブラウザと、表示速度を優先する
ブラウザがある為)だから、縮小の手を抜いてブラウザまかせ
にしてしまうと、それを閲覧する他の人の環境によっては、
写真の雰囲気が異なってしまう(例:輪郭線が強くなったり、
斜めの線にギザギザ=ジャギーが発生する等)
なお、大きな画素数から小さな画素数へ、画像を思い切り縮小
すると、輪郭の部分が非輪郭部に対して相対的に強くなり、
それは見かけ上「被写界深度が増した」ように見える。
だから風景写真等においては、大画素の写真を縮小する事で、
よりくっきり見える効果がある、これはPCのみならず、カメラ
の背面モニター等でも同様で、縮小率が大きいと、はっきり
見える事になる。この「縮小効果」をもって「画素数の大きい
カメラの方が良く写る」という印象をユーザーが持って
しまったのかも知れない。(注:カメラのモニターで見たら
ピントが合っていたのに、PCで見たらピンボケだった、という
現象も同様の原理からなる)
なお、大口径レンズ、近接撮影、望遠レンズ等で被写界深度が
浅くなった写真の場合は、大きく縮小効果を出してしまうと
輪郭部が強調され、目的とする写真の描写とは逆効果となって
しまう危険性がある。
私は、被写界深度が浅い写真を撮る事が多い為、
できるだけ小画素から縮小するようにしている。
この為、カメラ設定は、カメラの最小画素で撮る事が多い、
本記事でも、K-01の最低画素数である400万画素で撮影した
写真を縮小して掲載している。
なお、これは画像の理論的にはそうなのだが、ちゃんと検証
する事も可能である(例、同じ被写体を、画素数を変えて
撮って、同じ画素数まで縮小する)が、面倒なので、今回は
やっておらず、その実例掲載は見送る。
![c0032138_18340844.jpg]()
実験をやってみると良いであろう。
(なお、編集ソフトの画像縮小手法によっても結果は異なる、
また、カメラのシャープネス設定をプラスにする事で
輪郭がキツくなりすぎて逆効果となる場合もある、これは
カメラによりけりなので、各自色々試してみる必要がある)
こういう事を色々と実験や研究をしていくと、きっと、
大画素の「高画質神話」が疑問に思えてくる事であろう。
どんな事でもそうだが、自分で試して納得する必要がある、
他人の言う事を鵜呑みにしてはならない。現代の情報化社会
という物は、気をつけないと、そこに「大きな思惑」が
介在しているかも知れないのだ。が、それは市場を守る為の
「大人の事情」なのかも知れないので、必ずしも悪い事だ、
とは言い難い、だから情報の中から、真実をちゃんと見抜く
眼力が必要になり、その真実に対して、自分がどう対応して
いくかを、ユーザーは良く考える必要がある、という事だ。
![c0032138_18324915.jpg]()
事の半分だ、これ以降、「大きなセンサー」の意義について
書く予定だったのだが、際限なく文字数が増えてしまい
K-01の話が何も出来そうにない(汗)
センサーサイズの件は、またいずれ、その手のカメラの記事で
書くとして(本シリーズ第2回GXRの記事でも記載)
今回の「画素数」の話は、このあたりまでで留めておこう。
まあ、今時のカメラでは、壁一面のポスターとかを印刷して
作る必要が無い限り(それは業務用途だ)、どのカメラを
使っても画素数は十分に足りている、という事である。
(それに、これ以上画素数を上げると、レンズの性能が
追いつかなくなる)
![c0032138_18324969.jpg]()
弱点は勿論色々とある。
AFは、初期のコントラストAFのみであり、組み合わせる
レンズによっては、まったくと言って良いほどピントが
合わない(精度不足)
また、MFは、背面モニターの解像度が低く、ピーキング
機能も精度が低く、EVFがなく外付けも装着不可、
また再生系部品のバグで、ボケた画像が表示される、等で
壊滅的であり、すなわちAFでもMFでもピントが合わない。
(注:モニター再生画像がボケて見える件は、2011年~
2013年の各社ミラーレス機の数機種で同様の問題点があり
この当時に使われていた共通部品の問題だ。この時代には
本件の他にも色々と各社共通の不具合があって、もしかすると
東日本大震災(2011年)による、部品供給不足により
様々な代替部品を使用していたからであろうか?
まあ、しかしながら、こういう単純な不良が各社で見逃されて、
カメラが市場に出てきてしまうという製品品質管理体制の甘さ
や、新機種の発売により過去機種の問題点が、うやむやに
なってしまう事も、また問題だ)
で、この問題に対応する為には、できるだけピント合わせに
負担が少ないレンズを装着するしかない、具体的には、
被写界深度の深いAF広角レンズやMFならばトイレンズ系だ。
![c0032138_18340882.jpg]()
KENKO PINHOLE 02(ミラーレス第59回,第66回,補足編第5回
ハイコスパ第7回記事で紹介)を使用する。
![c0032138_18340865.jpg]()
AUTO ISOのままでISO25600まで上がる仕様は、明所での
ピンホール手持ち撮影を可能とし、背面モニターで
その映像も見れるし、エフェクトもかけ放題だ。
![c0032138_18343082.jpg]()
ピント合わせの課題が解決し、使っていて極めて楽しい
カメラに変貌する。
![c0032138_18340858.jpg]()
一眼レフ(例:KP=ISO82万等)でピンホールを使った方が
性能的にはベターだが、それらの新鋭機を、こうした目的に
使うのは高性能が生かせず、効果的では無い。
(それに、ライブビューで無いとピンホール撮影が出来ない)
むしろ性能がNGなカメラを、その欠点を相殺し、救済する
意味で適切なレンズを組み合わせる方が、テクニカルで
上級者向けであると思う。
![c0032138_18343001.jpg]()
そのあたりはネチネチと書いているので、もうばっさりと
割愛しよう。それと基本性能の数値スペック紹介も省略する、
そういうもので評価を行う類のカメラでは無いのだ。
![c0032138_18342950.jpg]()
評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★
【描写力・表現力】★★★★
【操作性・操作系】★★
【アダプター適性】☆
【マニアック度 】★★★★☆
【エンジョイ度 】★★★★
【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:17,000円)
【完成度(当時)】☆
【仕様老朽化寿命】★★★☆
【歴史的価値 】★★★★★
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.8点
総合点は予想通り平均的かやや低い程度。
ダメダメのカメラと言う状態では無い。
しかし極めて評価項目毎のデコボコが大きいカメラである、
これが「問題児」である所以であるから、ちゃんとこの
個性を見極めて、長所を活かすように使う必要がある。
![c0032138_18342994.jpg]()
あくまでマニア専用機であろう。
後継機が出る予定はまず無いと思う、入手しておくので
あればギリギリ今のうちだ。
次回記事は、第三世代のミラーレス機を紹介する。
世代別に紹介して行く記事だ。
今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は
第一回記事参照)の PENTAX K-01(2012年)を紹介しよう。
(注;この年では、PENTAXはRICOHの傘下ではあるが、
ブランドとしてのPENTAXは残っている)

(ミラーレス・マニアックス第11回,第60回記事参照)
以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めて
いくが、記事後半では別のレンズに交換する。
また、掲載写真はK-01の本体機能のエフェクトを多用する。

カメラの回が来てしまった(汗)
本機K-01は発売年が2012年なので、一応、本シリーズでの
世代分類上では第二世代のミラーレス機であるのだが、
本機の性能からすると、第一世代に分類されてもおかしく無い、
なにせ、AFでもMFでもまともにピントを合わせる事ができない
と言う、致命的、あるいは落第点とも言えるカメラだからだ。
本機K-01については、過去、特集記事で紹介した事があり、
そして、デジタル一眼レフ・クラッシックス第14回(番外編)
記事でも取り上げている。
すでに3度目の登場であり、出自や仕様等は、それらの過去
記事に詳しいので、今回はまた違った内容で本機を紹介して
いく事とする。

「何をしてもピントが合わない」という重欠点である。
では、「とんでもなく低い評価なのか?」というと、それが
そうでも無いのである。
デジタル一眼記事での本機の評価点は、ちょうど平均値の
3.0点であった、本ミラーレス・クラッシックス記事では、
デジタル一眼記事よりも評価項目数が増えてはいるが、
恐らくラストの総合評価点は、平均値3点に近い位置まで
行くと思われる。
・・と言うのも、本機K-01は、性能以外の評価点が極めて
高いカメラなのである。

試験の成績は酷い点数なのに、何か飛びぬけた特技がある、
例えば、ゲームが非常に上手いとか、容姿端麗であるとか、
コメディアンのように皆を笑わす才能があるとか、まあ、
そんな類の事である。
学校の先生からすれば、ちゃんと勉強や運動が出来て、
性格が良い子供の方が扱いやすい事は確かであろう。
でも、そうした強烈な個性をも、現代の教育シーンでは、
ちゃんと認めてあげるようになってきていると思う。
さもないと、皆が皆、型にハマった画一的で優等生的な
子供達ばかりになってしまい、面白くないし、国際社会で
生き残る個性や発想を持つべき日本の将来の為にも良く無い。
本機K-01は「問題児」である。だから、一般的なカメラに
対する感覚を、使う側で変えていかなければならない。
すなわち、テストの成績が悪い子供を、先生が見放すと、
結果的に「落ちこぼれ」になってしまうようなものだ。
落ちこぼれるのは、その生徒本人に100%責任があるとは
限らない事であろう、きっと、生徒を取り巻く環境にも
様々な問題がある筈だ。
K-01を「AFが合わないからダメなカメラだ」と切り捨てて
しまったら、本当に「落ちこぼれ」だ。でもせっかく買った
カメラである、どうやったら、この問題児の個性が活かせる
のかを考えるのが、先生(ユーザー)の責務であろう。

マーク・ニューソン氏の手による、その超個性的な
スタイルが上げられる。ここは好き嫌いがあると思うが、
およそ今までのどのカメラとも異なる独特の雰囲気があり、
目立つという点では間違いない。
ただし、デザイン優先で、機械としての「作り」が犠牲に
なってしまった点も少々ある。
また、デザインの個性により、装着するレンズのバランス的
なセンスも問われてしまう、なかなかクセのあるカメラだ。
それから、マニアック度が高く、歴史的価値が高い事だ。
でもまあ、これはマニア向けの要素で、一般的ユーザーには
あまり関係が無い事であろう。
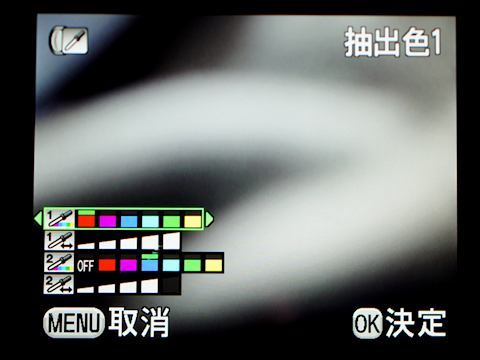
仕様および操作系により「エフェクト母艦」として使用する
際に、最大のパフォーマンスを発揮できるという点だ。
近年では、一般的なデジタル一眼レフ/ミラーレス機や、
コンパクト機、携帯電話カメラやスマホカメラのアプリでも
エフェクトは普及しているので当たり前の機能とは言えるが、
本機K-01のエフェクトは、遊びの範疇を越えて、写真表現と
しても利用可能なレベルだし、エフェクト利用時の操作系は、
一眼レフや携帯カメラの追従を許さない。

本機のエフェクト機能を用いた写真を多数掲載している、
また、これが楽しい為、評価点においては、「エンジョイ度」
が高くなり、加えて「描写力・表現力」の点数も高い。
ここが、性能や完成度が低い本機K-01でも、その他の要素が
好評価となり、どうにも気になる「問題児カメラ」という
レッテルが貼られてしまう理由だ。

でも述べたが「唯一の(孤高の)Kマウントミラーレス機」
である。
Kマウントと言うのは、ご存知、PENTAXの一眼レフ用の
マウント名称だ、その出自については例えばデジタル一眼
第5回「PENTAX K10D」の記事に詳しい。
後にも先にも、一眼レフ用と同じマウントでミラーレス機を
作ってしまった例は無い、本機K-01が、最初にして最後、
唯一無二である。本機の歴史的価値は非常に高い。
なお、APS-C型以上のミラーレス機で「初の手ブレ補正搭載」
という歴史的価値もあるが、まあ、これは他のPENTAXの
Kマウント一眼レフを使った方が遥かに便利なので、あまり
重要な意味は無いであろう。

「Q」システムが存在する。
最初の「PENTAX Q」は2011年発売、これがPENTAXでは
初のミラーレス機だ、本シリーズでの世代分類では
第二世代=普及期(各社からミラーレス機が出揃う)に
相当する時代だ。
なお「Qシリーズ」は2014年まで4機種が展開されたが、
現在では新製品の発売は止まっている。
市場の状況の変化、および親会社のHOYAからRICOHへの
変革期においての戦略転換であろう。
本機K-01は、Qシリーズの後から発売されている。
何故、2つの異なるミラーレス機のシリーズをPENTAXが
展開していたか、その理由は明らかにはされていないが
HOYA時代の戦略は、エントリー層に向けてカメラを普及する
要素が大きかったと思われるので、その一環なのかもしれない。
Qシリーズは、当初1/2.3型という、普及型コンパクト機
並みの小型センサーで展開した、しかし、2010年代では、
「センサーの大きいカメラが良いカメラ」という常識(?)が、
一般ユーザー層に広まった時代でもある。
まあ、そういう理由もあるからかQシリーズは商業的に苦しく
なってしまい、シリーズ3機種目のQ7(2013年)からは、
1/1.7型センサーに、心持ち大型化された。
しかし、これでもまだ小さい、だから、他社ミラーレス機
と同様のAPS-C型センサーのミラーレス機を、PENTAXに
おいてもラインナップする必要があったのかも知れない。
(注:Q7よりも本機の方が先に発売されている)
ただ、Qシリーズは、センサーサイズを小さくする事で
カメラ本体もレンズも小型化する事を可能とした多大な特徴
を得る事ができた、すなわち必ずしもセンサーが大きい事が
良い事ばかりでは無い、という事であり、
センサーが大きくなると、カメラ本体のみならずレンズも
含めたシステムが「大きく、重く、高価になってしまう」
という弱点(三重苦)が必然的にのしかかる。

例えば同時代のSONY NEX-7では、2400万画素であったのが
本機K-01では、1600万画素だ、これでは旧来からの
「画素数が大きい方が良い」というユーザーの思い込みに
引っかかってしまう。
で、何故「センサーが大きい方が良い」という話が広まったか
と言うと、それ以前の2000年代は、デジタルカメラの発展期
であり、一般ユーザーは、その性能基準として「画素数」に
着目していた。
つまり「画素数の大きいカメラの方が綺麗に写る」という
風に思っていたのだが、これは、ある意味、この時代特有の
「売り文句」である。つまり、そういう風に、画素数を大きく
するようにデジタル(センサー)技術が発達したから、それを
メーカーやメディアが、ユーザー層に強くアピールした結果、
ユーザー側が、そう思い込んだ、というだけの話である。
その後、2010年代になると、まずは先行したミラーレス
規格のμ4/3に対する、他社陣営の「差別化戦略」(μ4/3は
センサーが小さいから、我が社の大型センサーが優れている
という売り文句)が始まった。
そして同時に、スマホの普及による小型機(コンパクト等)
の低迷や、カメラ市場の縮退(スマホで撮れば十分だから
重たい一眼レフを持ち歩く必要が無い、というユーザー論理)
に対抗・対応する為に、大型化センサーが「高付加価値」商品
(つまり、「凄い」とユーザーに思ってもらえ、価格が高く
ても売れる=カメラの販売台数が減ってもやっていける)
であった事が、「大型センサーが良い」という話が広まった
理由であろう。
カメラに係わる業界は、こうして、ユーザー層に「ある種の
価値観」を(植えつけて)持ってもらなわないと、カメラが
売れずに市場が崩壊してしまうという危機感を感じている訳だ。
だから現在では「新しい高機能の高価なカメラが良いカメラ
である」と、業界関係者の誰もが言い、古い機種は、さっさと
市場から消し去ってしまっている。また中古店(中古市場)も
流通がだんだんと苦しくなり、「別にそれまでのカメラの性能
(仕様)でも十分」と思っても、もはやそうした古いデジタル
カメラを安価に入手する事自体が難しくなってきている。
まあ、古いカメラを安く売っても中古店は儲からないので
やっていけなくなるので、これもやむを得ない傾向であろう。
ただ、個人的には、どうも、市場に「乗せられている」
気がして、こういう傾向は好ましくないと思っている、
だから、私なりの購買(消費)行動の考え方やルールを色々と
儲けて、自分なりの価値観を構築しようとしている訳だ。
そういう考え方も、近年の「マニアックス系」のシリーズ記事
のコンセプトや執筆理由となっている事も事実だ。

まず、2000年代の「画素数神話」の件だ。
実際のところは、例えば、2004年頃の各社の600万画素級
CCDで、写真としてはもう十分に実用的なレベルにあった。
それは、デジタル一眼レフ・クラッシックスのシリーズ記事
で、第2回「PENTAX *istDs」から、第4回「NIKON D70」
あたりを読み返してもらい、掲載写真を見て貰えれば
わかる事であろう、それらのカメラは、全て600万画素機だし
実際にはさらに小さい画素数(300万画素程度)で撮って
いるが、ブログでの掲載上では何ら問題ない。
で、たとえばその600万画素で写真をプリントするならば、
具体的には、必要最小限の印刷品質である
175dpi(ドット・パー・インチ)で印刷した場合、
それが、3008x2000画素であれば、
横3008pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約43.6cm
縦2000pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約29.0cm
の用紙まで印刷する事が可能となり、これはだいたい
A3サイズ(42.0cmx29.7cm)に相当する。
2000年代、まだDPE店では旧来のフィルム用プリント機を
デジタルプリント用に流用していた。そういう店舗で
一般写真をプリントする場合、L判か、せいぜい2L判
(17.8cmx12.7cm)程度であり、600万画素は十分すぎる
画素数だ。
そして、たまに写真展などに出す(展示する)としても、
まあ、ワイド四つ切り(36.5cmx25.4cm)程度であろう。
つまり、600万画素あれば、これらのプリント用途は全て
問題なくクリアできる。
家庭用PCプリンターでも同様で、一般的にはA4までだ。
A3プリンターも勿論この時代から存在したが、大きいので
置ける家庭環境は限られていた事であろう。そして仮にA3で
印刷したとしても、前述のように600万画素で問題ない。
なお「印刷で175dpiは低すぎる」とは思うなかれ、人間の
視覚や閲覧距離、印刷用プリンターの性能(解像度)など
からすると、現実的には175~350dpiあたりが印刷品質と
しては適正な範囲だ、と様々な研究結果で述べられている。
で、印刷屋さん等に印刷を頼んで、写真を入稿する際に、
「600dpiなければ受け付けません」と言われる場合も
あるのだが、これはまあ「安全マージン」だと思えば良い
であろう、入稿画像品質が悪くて、それのせいで印刷屋さん
が文句を言われたら、かなわないからだ。
実際にはそこまでの印刷dpi数は不要である。
余談だが、印刷屋さんによっては、画素数とかdpiの計算
方法を知らない場合もあるようだ。まあ、カメラマンでも
フィルムからのデジタル化時代において、様々な誤解や
混乱が、いくらでもあったのだから、他の業界でも同様だ。
そして、時には何万画素以上とか何dpiで、とかではなく、
「2MByte以上のJPEGで下さい」と言われる場合もある。
まるで、「肉の量り売り」のようなイメージだ
画像という2次元の要素を、重さとか量とかの1次元変数に
変換しているようで、どうにも気持ちが悪い。
まあ、結局、デジタル画像に関しては実際の所では様々な
高度な知識を要求されるものだから、皆が皆、その全てを
理解しているものでは無い、という事なのであろう。
で、ファイルサイズで量るのは、これも多大な問題があり、
例えば、被写界深度の極めて浅い写真(例:マクロレンズで
近接した花を撮って背景が全てボケた画像)や、同一の色調
の画素が極めて多い写真(例:夜間の花火写真で、背景の殆ど
が漆黒の闇とか、ほとんどが青空とか)の場合、これらは、
JPEGの原理的には非常に大きい圧縮率となる、つまり目標と
する圧縮率に比べて、非常に小さいファイルサイズとなるのだ。
圧縮率の計算方法だが、まずは非圧縮の24bit形式を
基準値とする、これは、RGB(赤・緑・青)の3色に各8bitが
割り振られている訳だから、その基準ファイルサイズは
横ピクセル数x縦ピクセル数x3色でByte数が計算できる。
簡単な例として、600万画素で計算してみよう、
横約3000x縦2000x3=1800万Byte
約100万Byte(1048576Byte)で1M(メガ)Byteであるから、
上記は約17MByteとなる。
JPEGの圧縮率だが、肉眼で見た場合、上記非圧縮の容量を
1/10まで圧縮しても、標準的な空間周波数分布を持つ画像で
あれば問題は無い、だから、これをJPEG化する場合、
600万画素=1.7MByte が標準的ファイルサイズとなる。
これ以上、圧縮率を下げる(ファイルサイズを大きくする)
事をしても肉眼で見た画質は向上しない、だから、例えば
1/4圧縮などは、実は冗長なのだ(意味が無い)
そして、前記、被写界深度の浅い写真は、同じ目標圧縮率
(例えば1/10)を設定しても、ファイルサイズは、どんどん
と小さくなる、被写界深度の浅い写真では1/20程度、
さらに非常に深度の浅い、あるいは同一画素が多い写真では、
1/30~1/40程度までの比率で圧縮される。
ファイルサイズで言うと、それぞれ850KB~570KB程度である。
花火の写真も同様で、数百KBYteにしかならない。
以前、花火のイベントの電車内ポスターを作る際、その印刷
屋さんが「2MByte以上で欲しい」の類であった。けど、例えば、
5400x3500ピクセルの約1800万画素で入稿してもファイル
サイズは1MByte強にしかならない(圧縮率=1/40程度)
2MByteなんて、いくら画素数を上げても、なる訳が無いのだ。
ところが、これの説明がなかなか担当者に伝わらない、
「2メガ無いと印刷できないので困るんです」といった感じだ。
やむをえない、実例として試験的に1800万画素の真っ黒な
画像を作り、それをJPEGで保存すると、たったの300KByte
にしかならない事を実演(注:これは誰でも実験出来る)
「2MByteにしようとしたら、1億画素を越えてしまいますよ!
そんな大きな画素数のカメラは売っていないと思いますが・・」
と、「画像のパターンによってファイルサイズが違う」という
事を説明するのに苦労した事がある。

ブログや各種SNSの普及が始まった事がある。
これらは、当時は普通はパソコンの画面で見るものであった、
Windwos XP等での基本画面解像度は、XGA(1024x768)だ、
これは、約75万画素(しかない!)に相当する。
で、実際には、SNS等はブラウザで見るものであるから
PC画面いっぱいにまで写真が広がって表示される事は無い、
大きくてもVGA(640x480=30万画素)くらいである。
ちなみに、本ブログにおいては、開設当初(2005年)より、
ずっと約20万画素で写真を掲載している。
ちなみに、スマホ等では、PCより画面解像度はさらに低い。
で、これらPC閲覧環境は高々数十万画素だ、600万画素でも
巨大すぎる為、思い切り縮小しなくてはならない。
(注:縮小とは画素数(解像度)を下げる事、前記の圧縮
とは、同じ画素数でファイルサイズを小さくする事だ。
まず、この両者を混同している人が極めて多い、これは
画像処理での基本中の基本であり、間違えると格好悪い)
もし、自分自身で画像を縮小しないと、ブラウザにおいて、
HTMLコードのIMG SRCタグに書かれたサイズ・パラメーターに
より、自動的に(勝手に)縮小される。しかしながら、縮小の
方式(アルゴリズム)は、バイキュービック法やLANCZOS法
など様々な手法があり、しかも、ブラウザによって、それは
異なる(縮小精度を優先するブラウザと、表示速度を優先する
ブラウザがある為)だから、縮小の手を抜いてブラウザまかせ
にしてしまうと、それを閲覧する他の人の環境によっては、
写真の雰囲気が異なってしまう(例:輪郭線が強くなったり、
斜めの線にギザギザ=ジャギーが発生する等)
なお、大きな画素数から小さな画素数へ、画像を思い切り縮小
すると、輪郭の部分が非輪郭部に対して相対的に強くなり、
それは見かけ上「被写界深度が増した」ように見える。
だから風景写真等においては、大画素の写真を縮小する事で、
よりくっきり見える効果がある、これはPCのみならず、カメラ
の背面モニター等でも同様で、縮小率が大きいと、はっきり
見える事になる。この「縮小効果」をもって「画素数の大きい
カメラの方が良く写る」という印象をユーザーが持って
しまったのかも知れない。(注:カメラのモニターで見たら
ピントが合っていたのに、PCで見たらピンボケだった、という
現象も同様の原理からなる)
なお、大口径レンズ、近接撮影、望遠レンズ等で被写界深度が
浅くなった写真の場合は、大きく縮小効果を出してしまうと
輪郭部が強調され、目的とする写真の描写とは逆効果となって
しまう危険性がある。
私は、被写界深度が浅い写真を撮る事が多い為、
できるだけ小画素から縮小するようにしている。
この為、カメラ設定は、カメラの最小画素で撮る事が多い、
本記事でも、K-01の最低画素数である400万画素で撮影した
写真を縮小して掲載している。
なお、これは画像の理論的にはそうなのだが、ちゃんと検証
する事も可能である(例、同じ被写体を、画素数を変えて
撮って、同じ画素数まで縮小する)が、面倒なので、今回は
やっておらず、その実例掲載は見送る。

実験をやってみると良いであろう。
(なお、編集ソフトの画像縮小手法によっても結果は異なる、
また、カメラのシャープネス設定をプラスにする事で
輪郭がキツくなりすぎて逆効果となる場合もある、これは
カメラによりけりなので、各自色々試してみる必要がある)
こういう事を色々と実験や研究をしていくと、きっと、
大画素の「高画質神話」が疑問に思えてくる事であろう。
どんな事でもそうだが、自分で試して納得する必要がある、
他人の言う事を鵜呑みにしてはならない。現代の情報化社会
という物は、気をつけないと、そこに「大きな思惑」が
介在しているかも知れないのだ。が、それは市場を守る為の
「大人の事情」なのかも知れないので、必ずしも悪い事だ、
とは言い難い、だから情報の中から、真実をちゃんと見抜く
眼力が必要になり、その真実に対して、自分がどう対応して
いくかを、ユーザーは良く考える必要がある、という事だ。

事の半分だ、これ以降、「大きなセンサー」の意義について
書く予定だったのだが、際限なく文字数が増えてしまい
K-01の話が何も出来そうにない(汗)
センサーサイズの件は、またいずれ、その手のカメラの記事で
書くとして(本シリーズ第2回GXRの記事でも記載)
今回の「画素数」の話は、このあたりまでで留めておこう。
まあ、今時のカメラでは、壁一面のポスターとかを印刷して
作る必要が無い限り(それは業務用途だ)、どのカメラを
使っても画素数は十分に足りている、という事である。
(それに、これ以上画素数を上げると、レンズの性能が
追いつかなくなる)
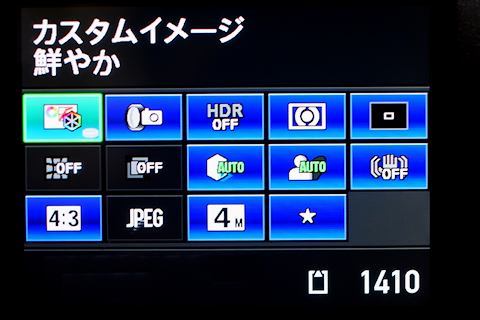
弱点は勿論色々とある。
AFは、初期のコントラストAFのみであり、組み合わせる
レンズによっては、まったくと言って良いほどピントが
合わない(精度不足)
また、MFは、背面モニターの解像度が低く、ピーキング
機能も精度が低く、EVFがなく外付けも装着不可、
また再生系部品のバグで、ボケた画像が表示される、等で
壊滅的であり、すなわちAFでもMFでもピントが合わない。
(注:モニター再生画像がボケて見える件は、2011年~
2013年の各社ミラーレス機の数機種で同様の問題点があり
この当時に使われていた共通部品の問題だ。この時代には
本件の他にも色々と各社共通の不具合があって、もしかすると
東日本大震災(2011年)による、部品供給不足により
様々な代替部品を使用していたからであろうか?
まあ、しかしながら、こういう単純な不良が各社で見逃されて、
カメラが市場に出てきてしまうという製品品質管理体制の甘さ
や、新機種の発売により過去機種の問題点が、うやむやに
なってしまう事も、また問題だ)
で、この問題に対応する為には、できるだけピント合わせに
負担が少ないレンズを装着するしかない、具体的には、
被写界深度の深いAF広角レンズやMFならばトイレンズ系だ。

KENKO PINHOLE 02(ミラーレス第59回,第66回,補足編第5回
ハイコスパ第7回記事で紹介)を使用する。

AUTO ISOのままでISO25600まで上がる仕様は、明所での
ピンホール手持ち撮影を可能とし、背面モニターで
その映像も見れるし、エフェクトもかけ放題だ。

ピント合わせの課題が解決し、使っていて極めて楽しい
カメラに変貌する。

一眼レフ(例:KP=ISO82万等)でピンホールを使った方が
性能的にはベターだが、それらの新鋭機を、こうした目的に
使うのは高性能が生かせず、効果的では無い。
(それに、ライブビューで無いとピンホール撮影が出来ない)
むしろ性能がNGなカメラを、その欠点を相殺し、救済する
意味で適切なレンズを組み合わせる方が、テクニカルで
上級者向けであると思う。

そのあたりはネチネチと書いているので、もうばっさりと
割愛しよう。それと基本性能の数値スペック紹介も省略する、
そういうもので評価を行う類のカメラでは無いのだ。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)
【基本・付加性能】★
【描写力・表現力】★★★★
【操作性・操作系】★★
【アダプター適性】☆
【マニアック度 】★★★★☆
【エンジョイ度 】★★★★
【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:17,000円)
【完成度(当時)】☆
【仕様老朽化寿命】★★★☆
【歴史的価値 】★★★★★
★は1点、☆は0.5点 5点満点
----
【総合点(平均)】2.8点
総合点は予想通り平均的かやや低い程度。
ダメダメのカメラと言う状態では無い。
しかし極めて評価項目毎のデコボコが大きいカメラである、
これが「問題児」である所以であるから、ちゃんとこの
個性を見極めて、長所を活かすように使う必要がある。

あくまでマニア専用機であろう。
後継機が出る予定はまず無いと思う、入手しておくので
あればギリギリ今のうちだ。
次回記事は、第三世代のミラーレス機を紹介する。