中古ミラーレス機にマニアックなレンズを組み合わせて
コスパの良いアダプター遊びを楽しむシリーズ、第72弾。
今回はまず、このシステムから、

カメラは、PENTAX Q7
レンズは・・・メーカー不明のCCTV用レンズ 16mm/f1.6
CCTVとは、Closed Circuit TeleVision.
すなわち監視カメラの事だ。
これは、昔のアナログTVは、カメラからの画像は無線(電波)で
飛ばすものであったのに対し、有線でカメラとTVを回路で繋ぐ物で、
つまり、これは監視カメラのような閉鎖システムを示す用語だ。
が、勿論今時の監視カメラは無線であったりインターネット回線を経由
したりして画像を遠隔地でも見れるので、CCTVという用語はあまり
適正ではないが、それでも昔からの慣習で、このように呼ばれている。
韓国製と書いてあるが、どのメーカー製かは、わからない、
そもそも韓国のメーカーを殆ど知らない。日本でも知られている
レンズメーカーはSAMYANG(サムヤン)位のものであろう。
さて、ちゃんと写るのか・・?

う~ん、ピントが合えば結構シャープには見えるのだが、
まずは解像度があまり高くない。・・というか低い。
ボケ質は、ちょっと異様だ、はっきり言えば汚い。
ボケ質をコントロールしようと、絞りを変えようとしても、
なんと、このレンズには絞りが存在していない(汗)
常に開放f1.6のままだ。
近年の監視カメラ用レンズは、電動絞りを使っているものが
多いが、本レンズのように旧世代(数十年前)のものは
手動絞りか、そもそも絞りが無かったりもする。
開放f1.6は、写真用レンズの感覚では明るい方であるが、
監視カメラ用レンズでは暗い部類であり、f1.4くらいが
普通のレベル、明るいものではf1.0やf0.95のものが
ゴロゴロしている。
ちなみに、監視カメラ用レンズでは、ズームに相当するものは
「バリフォーカル」レンズという仕様のものが多い。
バリフォーカルとは可変焦点という意味で、これはズームと
ほぼ同様なのだが、焦点距離を変えてもピント位置が変化
しないのがズームであり、変化するのがバリフォーカルだ。
すなわち焦点距離を変えるたびにピントを合わせ直さなければ
ならない。不便なようだが、こちらの方式が小型化やコストダウン
の面で有利だし、監視カメラではひんぱんに画角を変える事は
無く、普通はその使用環境に合わせて焦点距離は固定となる。
そして、もしAF機能がついていれば、ピント合わせは問題に
ならないし、そういう意味でもバリフォーカルが一般的なのだ。

解像度が低い・・というか、ピントが合わない、とも言える。
Q7(Qシステム)は、MFの精度・操作系に問題を抱えていて、
具体的には、ピーキング機能の精度が低く、画面拡大も出来ない
勿論内蔵EVFは無く背面モニターの解像度もMFには足りていない。
おまけに撮影後の再生時の画像も、何か解像度が低く感じる、
これはこのカメラだけの問題ではなく、FUJI X-E1も、PENTAX
K-01も同様であり、再生画像は、まるでプログレッシブJPEG
が途中で再生を止めた時のように、低い空間周波数の画像まで
しか表示されず、どの写真もピンボケに見える。
よって、再生画像を見てピントを確認したり再調整したりする事が
できない。
この事は大問題だと思う、上記の機種群が同じ画像再生用の
部品を使っていて、それにバグや欠陥があるのではなかろうか?
とも思えてしまう。
この問題により、Qシステムをマウントアダプター母艦として
用いる事は、実用上はほぼNGであり、私は現状、Qシステム純正
レンズの他は、CマウントでのCCTV用レンズ群しか使っていない。
Cマウントアダプターは、他のミラーレス機用のものも存在するが、
そもそも、この手のCCTV用レンズの対応センサーサイズは、
良くて1/2型か2/3型、普通は1/3型や1/4型用のイメージサークル
である事が殆どなのだ。
Q7は、1/1.7型センサーなので、これくらい小さくないと、
CCTVレンズは(他のミラーレス機では)なかなか使う事ができない。
で、Q7に装着するレンズは2/3型対応CCTVレンズが必須となるが
まあ、1/2型対応でもレンズによってはケラれずに使用できる
模様である(例:第4回、第21回、第62回記事で紹介した
TAMRONの産業用レンズ16mm/f1.4)

本レンズの最短撮影距離は25cmである。
寄れるようだが、実際の焦点距離は16mmなので、できれば
16cmまで寄れて欲しい、けど、本レンズは監視カメラ用なので
そこまでの近接性能は要求されていないのであろう。
まあ、さらに最短撮影距離を縮めようとすれば、第62回記事で
紹介したように、CマウントのCCTVレンズに、C→CSアダプター
を装着すれば、接写リングを用いたのと同じ原理で近接撮影が
可能になる(その際、無限遠撮影はできなくなる)
で、MFピント性能に問題のあるQ7では、近接撮影は絶望的な
までに困難な撮影となる。25cm程度の撮影でも勿論そうだし
CSアダプターによる数cmの近接撮影では、ピントが合う方が
奇跡的で、歩留まり(成功率)は、数%程度でしか無い。
つまり、20~30枚撮って、やっと1枚ピントが合うかどうか
というレベルであり、普通の感覚では、実用性はゼロだ。
そして解像度が低いので、ピントが合っているのかどうかも
良くわからない。絞り込んで被写界深度を深くしようにも、
そもそもこのレンズには絞りが無い(汗)
あまりに実用性が低いので、イヤになってきた、
こういう場合は、Q7の優れた特徴である、エフェクト機能で
お茶を濁してみよう。エフェクトはミラーレス機の世界では
もはや特別なものではなく、単にカメラ設定の一部という
位置付けだ、せっかく付いている機能を使わない手は無い。
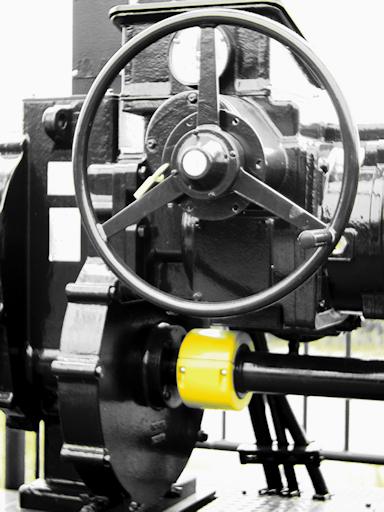
本レンズの購入価格だが、ゼロ円である。
それにはいきさつがあり、本年2016年に大阪のいきつけの
小さい中古カメラ屋で、店長と話をしていた。
店「最近、変わったレンズとか使っているの?」
匠「ええ、監視カメラ用のレンズとかも使ってますよ。」
店「それ、どんなカメラに付けられるの?」
匠「Cマウントなんで、たいていのミラーレスで付きますが、
センサーが小さい方が良いので、PENTAX Qとかが
使い易いですね」
店「監視カメラ用だったら・・こんなのもつく?」
と、店の奥から、なにやら怪しげなダンボール箱を出してくる
その中には、数台の監視カメラが・・どうやら、どこかで
仕入れてきたのか?お客さんが持ってきたけど、カメラ屋では
売り物にはならないと思っていたブツ(中古品)らしい。
最初に取り出してきた1台は・・
匠「ああ、これはちょと使えないですね、電動絞りです、
ほら、ここに絞りを制御するコードがついていますよね、
ここに信号を流さないと絞りが動かないのですよ・・」
店「なるほど、じゃあ、こちらは?」
と、それが、本レンズであった。
匠「お、手動絞りですね・・いや、絞り無しかぁ(汗)
でもまあ、これだったら使えますよ」
店「これ、どうせ売り物にはならないし、使えるのだったら
あげるから持って帰りなよ」
匠「えっ?いいんですか?! 助かります、いただきます」
という事で、ゼロ円でGETしたのだが、もっとも、さすがにタダ
で貰うのは悪いと思って、カメラ付属品等を色々買って帰った
次第であった。
----
さて、次のシステム。

カメラは、SONY NEX-3
レンズは、SONY E30mm/f3.5 Macro (SEL30M35)である。
2010年代のEマウントAPS-C機用AF等倍マクロレンズ。
30mmという焦点距離は45mm相当の画角となり、いわゆる
「標準マクロ」である。
前回第71回記事で、E18-55mm/f3.5-5.6 (SEL1855)を
NEX-3に装着して紹介したが、「面白みの無いシステム」
という結論になって、なんだか不完全燃焼であった。
もともとMF性能の悪いNEX-3だ、そしてAFレンズであっても
あまりピント合わせが厳密なレンズは使うべきでは無いだろう。
本レンズはマクロなのでピントはシビアな方だ、
はたして使えるのかどうか?限界性能テストの意味もある。

コケのような、ごく小さい被写体に思い切り近接してみた。
本レンズの最短撮影距離は、9.5cm。
ただ、この距離はセンサー面からの距離であり、レンズの
先端からの撮影距離(ワーキング・ディスタンス)は、数mm
程度しか無いであろう。
ただ、このような被写体の場合、カメラが、どこにピントを
合わせて良いかの判断はしにくいであろう、ミラーレス機の
コントラストAFは、一眼の位相差AFのように、特定の位置で
ピント合わせをする訳ではなく、画面上の任意の場所(範囲)で
ピントを合わせる事ができる。
NEX-3では、とりあえずAFは殆ど使わないので(最も安全な)
中央固定に設定してあるが、勿論任意位置に変更は可能だ。
ただ、中央固定だろうが任意位置だろうが、そんなに小さい
被写体に、果たしてピントが合うものかどうか・・??
まあ、それは「無理」と結論づけておこう。

そもそも、近接撮影時のピント精度がかなり怪しい。
FUJI XF56/1.2R APDの時(第17回、第30回記事)でも説明
したが、X-E1と組み合わせた場合では、無限遠から最短まで
このシステムでは連続的にピント合わせが出来ず、近接撮影
では近距離用のAF刻み幅(すなわちマクロモード)に手動で
切り変える必要があった。しかし、この操作系が良く無いので、
こういう状況ならば「オートマクロ」機能を搭載すれば良いでは
ないか?と仕様の不出来を不満に思っていた。
(最近の後継機ではオートマクロになっている)
で、どうやら、本システム、つまり NEX-3+SEL30M35では、
表示や説明こそないものの、オートマクロになっている様子だ。
というのも、20~30cm程度の近距離撮影ではピントがかなり
怪しくなり、ピンボケを連発するのが、20cm以下の近接撮影
になると、なにやらAFがカチリと切り替わったような雰囲気が
あるくらい、急にピントが合うようになるのだ。
で、ピントが合いにくいのは、そのあたりのグレーゾーンであり
もう少し離して撮るのであれば、ピント精度はあまり問題は無い。

レンズの描写力であるが、どうも妙な印象だ。
輪郭が異様にキツく、画像処理で輪郭強調をかけたような
雰囲気がある。カメラのシャープネスはゼロ(標準)に
設定しているが、どうもおかしい。
純正レンズというのは、ある意味恐ろしい。
例えばの話だが・・レンズの内蔵ROMから、カメラ本体に
「私は純正レンズの**ですよ」という電子情報が伝わるとしよう、
その結果、情報を受け取った同じメーカーのカメラが
「ほう、そうですか、じゃあ、輪郭をシャープに加工しましょう」
・・等という特別な処理をする事は、技術的には極めて容易だ。
そんな事をして何になるか?といえば、例えば他社のレンズとか
アダプターを使った場合は、こうした電子情報のやり取りは
行われないので、こういう特別な処理は絶対に行われない。
しかし、これをビギナーや一般ユーザーが見れば
「やはり純正のレンズは写りが用いなあ」と、あらぬ誤解をして
しまう可能性がある。悪く言えば「騙されてしまう」訳だ。
不自然な加工だ、と言っても始まらない、そういう画像を見て
「綺麗で良い写真だ」と認識する、大多数の一般ユーザー側に
問題がある事なのだと思う(スマホの撮影画像もその類か?)
まあ、本システムでそういう事をやっている確証は無いが、
不自然なまでに輪郭強調された画像はちょっと気持ち悪い。
デジタルズームをかけたような画像にも見える、まあ、まさか
マクロ光学系の補助にデジタル拡大をやっている筈は無いが・・

本レンズの中古購入価格だが、2015年に14000円台であった。
まあ高くは無い。でも本レンズの相場の推移は、一度下がった
後また上がって、そしてフルサイズα7人気の後は、また
下がった、そうして相場を追っかけていると面倒な話なのだが、
14000円程度であれば妥当な価格であろう。
画質の疑問点は、いずれまた別の機種に装着して試してみる
事にする。
----
さて、次のシステム。

カメラは、望遠アダプター母艦のLUMIX DMC-G5
レンズは、MINOLTA AF100mm/f2
1990年頃のα用AF中望遠レンズと思われる、初期のαレンズに
特有のピントリングが狭い構造も、他の同時期のレンズと同じだ。
本レンズの前身は存在せず、例えば第12回記事で紹介した
1970年代のMFレンズMC100mm/f2.5は、その後1980年代前半
に至るまで100mm/f2.5の仕様のままであったが、αシステム用で
f2にスペックアップした。レンズ構成も6群7枚となり、従来のf2.5版は、
それよりもシンプルな構成が踏襲されていたので、本レンズはα用の
新設計であろう。
思うに、1985年のα-7000や、それに続くα-9000の時代は
「αショック」と呼ばれたように、初の実用的なAF一眼レフの登場
という事で、カメラ業界に衝撃を与えたとの話だが、その際に、
カメラ本体のAF化のみならず、このように多くのレンズが新設計
されてラインナップされ、システムとしての魅力が大きかったので
あろう。開発陣は多数のαレンズを同時期に新規開発しなくては
ならず、さぞかし忙しかった事であろう。

本レンズはコントラスト再現性に弱いという弱点を持つが、
ボケ質はそれ以前のf2.5版よりも格段に良くなっている。
100mmf2級のレンズは高性能なものが多く、本シリーズでは
例えば、RTSプラナー100mm/f2(第32回,第61回記事)や
OM100mm/f2(第19回記事)を紹介している。また、FD100/2
(第69回記事)は、ちょっと個人的には好きでは無いが、
AF版のEF100/2(現在未所有)はなかなかのものだったと
記憶している。
本レンズも、それらの高性能レンズ群に肉迫するような
性能ではあるが、ほぼ完璧なP100/2等と比較すると、ちょっと
細かい欠点が目立つという感じか。

最短撮影距離は1mと標準的だが、望遠母艦のDMC-G5では、
デジタルズームを併用する事で、見かけ上の撮影倍率を上げる
事ができる。この写真もその機能を使っている。
本レンズは主要な用途として、デジタル時代でのライブ撮影や
イベント撮影によく用いていた、APS-Cのデジタル一眼での
換算画角は150mm相当と、ステージ周辺の位置からの
プレーヤーやパフォーマーの単独(1名)撮影にちょうど良い
画角となる。
カメラ好きの友人が、バンド活動もしていて、ライブ撮影用に
本レンズを私が使っているのを見て、「自分も欲しいと」
いうことで、だいぶ長期に渡って探した模様だが、結局
中古市場になかなか出て来ない模様で、諦めた様子であった。
ちょっとレアなレンズとなっているのかも知れない。
その理由は、プラナー100/2の記事でも書いたが、普通の
ユーザーは大口径中望遠は、85mm/f1.4を間違いなく購入する。
αユーザーも同様であろう、で、そのスペックと比較すると、
100mm/f2は、85/1.4にさらに追加しては買いにくい仕様だし、
最初から憧れの85/1.4をやめて100/2を買うユーザーも
極めて少ないであろう。
85/1.4程は被写界深度が浅くならないので、少し絞った状態で
ピント歩留まりを上げる事ができるし、ボケ質の破綻も、
一般的な比較では、85/1.4よりも100/2の方が起こり難い場合も
多々あるので、その点でも使いやすい。
現行のSONY製αレンズで100mmはマクロを除いてラインナップ
されておらず、この目的には、85/1.4か、あるいは135/1.8で
カバーする事になる。ZA135/1.8は、いずれは欲しいレンズとして
リストアップしてあるが、なにせ高価なレンズなので、ずっと
購入機会が無いままだ。まあ当面は本レンズで代用する事にしよう。

背の高い木のてっぺんに、ちょっと珍しい野鳥を見かけたので
デジタルテレコンおよびデジタルズームを併用して最大倍率まで
上げてみた、この時の換算焦点距離は、
100mmレンズx2倍(μ4/3)x4倍(テレコン)x2倍(デジタルズーム)
となり、都合1600mm相当の超々望遠画角だ。
「換算1500mmを超えると手持ち撮影は困難」と良く書いているが、
まさにぎりぎりの状況。
カメラ内部の画像処理による画質劣化は甚だしく、輪郭がパキパキ
に固くなる、前述のE30/3.5マクロでの輪郭強調のような雰囲気を
さらにキツくしたような状況だ。
でもまあ、これは使用用途の殆ど無い散歩記録写真なので、
遊びの撮影としては、とりあえず写っていれば良いという感じだ。
---
本レンズの中古購入価格だが、2000年頃に2万円であった、
現在では前述のようにレアなので、入手可能であるかどうかは
わからない。αマウントではこれよりはるかに高価な85/1.4や、
135/1.8を購入して代用するしか無いような気もするが、
それらよりは小型軽量という利点もあるので、運良く見つけたら、
値段次第では購入しても損は無いレンズであると思う。
----
さて、次は今回ラストのシステム。

カメラは、FUJIFILM X-E1
レンズは、ロシアKMZ製 ZENITAR 16mm/f2.8 魚眼である。
すでに第6回記事で紹介済みのM42マウント版の対角線魚眼
レンズであるが、その際は機種選定のミスで、アダプターの
構造上、絞りが動作しなかった。それを今回は回避して使う、
再登場の理由はもう1つ、ここで使っている M42→Xの
アダプターは「ティルト可能型」なのだ。
これは、前回第71回記事で冒頭に紹介したIndustar 50-2
のレンズとセットで、熊本市のカメラ通販店「ギズモショップ」
より購入したものだ。ショップ側の推奨は勿論Industar との
コンビなのだが・・
ティルトレンズと言うと、LensBaby 3Gを、第11回、第14回、
第40回記事で3回紹介している、そのレンズを使う際にいつも
思っていたのは「もう少し広角でティルト効果を出したい」
という事だった。
今回、ティルトアダプターを入手できたので、M42レンズで
あればどんなレンズでもその効果が出る。そこで、広角も広角、
魚眼レンズで試してみようと思った次第だ。
(加えて、本来のセットのIndustar 50-2と同じ、ロシアKMZ製の
ZENITAR 16mm/f2.8魚眼を使ったのも、ちょっとした拘りだ)

ティルトとは、レンズの光軸をわざと傾ける事で、
ピント面をレンズとは平行以外の角度にする事が可能となる。
つまり、画面の一部にしかピントが合わず、他はボカすという
効果が出せるのだ。
類似の機構で「シフト」があるが、こちらはレンズ光軸を
平行移動する事で、主に画像の遠近感を調整するもので、
目的がだいぶ異なる。シフト+ティルトが最強の仕様であり、
そういうレンズも多く存在するが、業務用途で概ね高価である。
写真では画面右側にピントが来て、左側は大きくボケている。
ティルトアダプターは、ティルト(傾き)量を8段階に調整
できる他、アダプター全体を概ね30度づつの角度で回転でき
任意の方向にこの効果を出す事ができるが、効果の出る方向は
レンズを傾ける方向とは感覚的には逆になる(慣れればOK)
また、カメラを横位置、縦位置で構える場合、各々の回転方向は
異なるので注意と慣れが必要だ。
なお(対角線)魚眼レンズというと、大きく直線が歪んでしまう
印象があると思うが、いつも魚眼レンズの記事で書いている通り
「フルサイズ用魚眼はAPS-C機ではあまり歪まない」
「構図の工夫(中心点に向かう直線は歪まない)」
の2点に注意すれば、
対角線魚眼レンズを使っても、「ちょっとだけ歪む広角レンズ」
のように撮る事が可能だ。

これは、いわゆる「ジオラマ効果」「ミニチュア効果」と
呼ばれる撮り方、この手法が10数年前よりアート写真分野で
流行した事で、ティルトレンズやLensBabyシリーズが、いっきに、
アマチュアカメラマンの間に普及したのであった。
まあ現代であれば、PC上での画像レタッチ(編集)作業で
同様の効果を後付けする事はできる。けど、撮影時にカメラの
画面を見ながら行った方がはるかに楽しいし、その場での
試行錯誤も色々と出来る。
で、できれば広角の方が楽しいので、今回のシステムは、
なかなか正解であった。
なお、MFでのピント合わせに多くの課題を持つX-E1であるので
厳密なピント合わせは難しい。
それに、ティルト効果を強くかけると、レンズ本来のピント位置と、
撮影に必要なピント位置は異なってしまう。
具体的には、たとえば遠距離の被写体にピントを合わせて
手前はボカしたいとする、まず、そのようにティルト機能を傾けて、
いざピントを合わせる際、無限遠だからレンズも無限遠にピント位置
を設定すれば良い訳では無いのだ。
その逆もしかりで、近距離にピントを合わせて遠距離を強くボカしたい
ようなティルト設定時も、レンズのピント位置は近距離にはならない
事がある。
このため、ピント位置は毎回ティルトの状態に合わせて
調整しなおさなければならない。ティルト角度、ティルト量、
ピント、そして勿論絞り値も影響するので、4つの操作を
毎回やらなくてはならないので、結構面倒な撮影となるし
結局、1枚撮るまでに時間はかかる。
LensBaby 3Gも撮影時に時間や手間のかかるレンズではあるが
そのレンズは蛇腹構造なので、どちらかと言えば、テキトーに
調整して撮るスタイルでも良かった。
本システムでは、アダプターがカチカチとクリックストップ
で動くので、なんだか厳密なティルト操作を要求されている
ようにも思えてしまい、さらに時間がかかるものとなる。
まあでも非常に面白い。
そもそも、X-E1のAF/MF性能が不足であり、減価償却がなかなか
進まず ちょっと困っていたところであったので、Industar
レンズセット購入時のティルトアダプーのマウントを選択できた
ものを、あえてFUJI Xマウントとし、X-E1で、こうした
トイレンズ風の遊び方を可能にする、という目的もあったのだ。

本システムの購入価格であるが、ティルトアダプターに
関しては、第71回記事で書いたとおり、新品のIndustar 50-2
とのセットで14800円(税・送料込)であった、同レンズと
アダプターの価値はほぼ同等とみて、各々7000円相当と
判断している。
レンズのKMZ製 ZENITAR 16/2.8は、1990年代に
M42マウント版を通販で新品購入、価格は2万円程であった。
通販購入は関東のロシアレンズ専門店。以前は東京都内で
店舗営業していたのだが、現在は無店舗で通販専門となって
いる模様だ。店舗時代には1~2度店に行って購入した事もあった、
銀塩時代には、ロシアンレンズは個体差があり、保有している
ボディに試験的に装着してみないと、ちゃんと付くかどうか不明で
あったし、店舗側もそれを推奨していたのだった。
だが現代ミラーレス時代では、マウントアダプターでの装着と
なり、例えば第45回記事で紹介した事件、
「OLYMPUSのM42レンズが、高価なCONTAX一眼に付けた
まま外れなくなった」等というリスクはだいぶ低減している。
最悪、マウントアダプターから外れなくなったとしても、
マウントアダプターのまま使用すれば良い訳だ。
(実は実際にそうしているレンズが1本だけある)
ティルトシステムはなかなか面白いので、オススメではある。
撮影が非常に面倒なので、途中でイヤになってくるかも知れない
が、その際には、ティルトアダプターであれば、傾き量を
ゼロにして普通のレンズとして使えば良い。
次回シリーズ記事に続く・・