毎度おなじみの、安価なミラーレス中古機に様々なマニアックな
レンズを装着して楽しむというシリーズ記事、第68回目。
まず、このシステムから。

カメラは、LUMIX DMC-G1
レンズは、CANON EF35mm/f2 である。
1990年代のAF準広角単焦点、現行製品はUSM(超音波モーター)
と内蔵手ブレ補正(IS)の仕様となっているが、本レンズは
それらの機能を持たない旧型である。
キヤノンのUSMあるいはSTMのレンズの中には、マウントアダプター
での使用時にはMFが効かないものがあるが、本レンズは大丈夫だ。
EFマウントのレンズをミラーレス機に装着する場合は、
AF等が効く電子アダプター、機械絞り内蔵アダプター、
絞り機能なし(開放のみの撮影)の3種類のアダプターが
存在するが、私が使用しているのは機械絞り内蔵型だ。
このタイプは比較的安価で、絞り効果を実現できるが、
本来のレンズ内部の絞りを制御している訳では無いので、
光学的な意味合いは変化してしまう、また、レンズによっては
あまり絞り込むとケラレが発生するので、結局のところ絞り開放
近くでの、若干の光量・被写界深度調整の目的に留めておくのが
良いであろう。

ボケ質、逆光耐性ともになかなか優秀なレンズだ。
思えば、銀塩MF版のCANON (New)FD35mm/f2 (第4回記事)
も優れたレンズであったので、その伝統を引き継いだ本レンズも
優秀なのかも知れない。
ちなみに、レンズ構成は、New FD35/2とEF35/2は大きく異る、
前者が8群10枚で、後者は5群7枚と簡略化された。
なお、最新のEF35/2 IS USMは、8群10枚なのでMF時代の
FD版とレンズ構成が似ているかも知れない。
そして、最短撮影距離は、本レンズに関しては、25cmと
35mmレンズにしては、かなり優秀な部類だ。
一般的な35mmレンズの最短撮影距離は、30~35cmとなって
いるし、New FD35/2も30cmであった。

これくらいの撮影距離なら全然余裕で、最短25cmは、まだまだ
寄れる事ができる。
ちなみに、最新のEF35/2 IS USMの最短撮影距離は、
24cmと、さらに1cm縮まっている。
このクラスになると、なかなか凄い戦いであり、マクロを
除いては、35mm級レンズにおいては、
SONY DT35mm/1.8(第60回記事)→最短23cm
ロシア製MIR24 35mm/f2(第14回、第55回記事)→最短24cm
あたりと良い勝負になってくる。
大口径と近接能力を活かしたマクロ的撮影も可能な領域だ。

レンズ性能は特に問題は無いので、後は値段だ。
本レンズは、実は韓国で購入している。
1990年代後半くらいだったか?第一次中古カメラブームの際、
カメラマニア7~8人で韓国へ「買出しツアー」に行ったのであった。
当時の日本は、中古カメラ・レンズの相場が高騰してしまっていたし、
上級マニアともなると、たいていの普通のレンズは所有しているので、
何か珍しいものがあれば、あるいは多少安く買えれば、という感じても
あったと思う。
そして、ソウルの東大門や南大門には何軒かの中古カメラ屋が
あったのだが、それらのお店は、値札がなく、いちいち店主と
交渉して値段を決める必要があった。
だが、わざわざ韓国へ買出しに行こうという上級マニアの集まり
なので、私を含め、あらゆるレンズやカメラの中古相場が頭に入って
いる連中ばかりなので、筆談で値段を書けばそれで問題ない。
店主がOKならば買うし、高ければ見送るか値切るか、
ただそれだけだ。
自由行動で、南大門の小さな中古屋で、本レンズを見つけた私は、
「これは持っていなかったなあ・・この機に買っておくか?」
と考え、本レンズの日本での中古相場を思い出す。
「確か2万円台の中~後半だったのではなかろうか?」と。
いくらなら売ってくれるだろう?2万円?いやそれではあまりに
弱気だ。
私は、17万ウォンの金額を紙に書いて提示して交渉、
店主のOKが出たのでこれを購入した。
当時のウォンと円の為替レートは、ちょうど1/10位だったと思うので、
これで約17000円相当だ。
まあ、粘ればもう少し値切れたのかも知れないが、この値段ならば
国内の相場よりだいぶ安いので、十分であった。
保証が無いのはちょっと心配であったが、まあレンズの目利きは
できるので、とりあえず問題ないだろうと判断した、
その後、20年近く経つが、現在でも問題なく使用できている。
ちなみに、2016年現在、本レンズの国内中古市場での相場は
およそ25000円前後で、今にして見ても、まだ安価であった。
韓国は全てが安いのか?というと、当時はそんな事はなく、
ESO-1NHs、NIKON F5などのフラッグシップ機は、むしろ
日本よりはるかに高価であった、ただ、エントリークラス一眼等は
日本より安価であったように思えるので、韓国のカメラ市場が
そういう傾向であったのか?あるいは税率等の差異があったのか?
(贅沢品は高い等)そのあたりは良くわからない。
現代において必要なレンズか否かは微妙なところだ、
APS-C機のEOSならば、標準レンズ相当の画角になるのは
メリットだ、小型軽量なのも良い。
USMでは無いが特にAF性能・速度に不満を感じることも小型の
レンズなので少ない事であろう。
ただ、問題は最新型との比較だ、最新型は、8群10枚構成と、
もしこれがMF時代のNew FD35/2と同等の描写力であれば、
それはなかなかのものなので、最新型に魅力を感じる。
ただ、最新型は当然現在はまだ高価で、およそ5万円前後の
中古相場となる、これだとちょっとコスパが悪いように感じてしまう。
25000円で本レンズを買って、他にもう1本、中級クラスの高性能
レンズが買える訳だから・・
まあ、EOSしか使わないユーザーでは無ければ、SONY の
高性能エントリー単焦点DT35/1.8も存在するし、どうしても
EF35/2でなくてはならない理由は少ないかも知れない。
----
さて、次のシステム

カメラは、SONY NEX-7
レンズは、MC TELE ROKKOR QF 200mm/f3.5である。
1970年ごろのMF望遠レンズ、現代で使うには、ミノルタ
MD用のマウントアダプターを用いれば何ら問題は無い。
QFというのは、Q=クワトロ(4)とF=6(番目)であるから、
4群6枚という意味である。これはまあ、望遠レンズとしては、
特に変わった構成では無い。
f3.5は中途半端であるが、確か当時の200mmでは、まだ
f2.8級は珍しかった(あるいは無い?)のではなかろうか?
200mmでは、普通f4~f4.5級が殆どであり、f3.5は口径が
大きい方だと思う。
ミノルタでは、その後MDレンズの時代(1970年代後半~
1980年代)になって、MD200mm/f2.8が誕生しているが、
そこでのレンズ構成は、5群5枚と変化している。
なお、ちなみに、前回第67回記事で紹介したミノルタα時代
(1990年代)の、HI SPEED APO AF200mm/f2.8は
レンズ構成が7群8枚と、MF時代からまたさらに変化している。
AF200/2.8は、非常に優秀なレンズではあったが、その先祖
とも言える本レンズの性能はいかに?

本レンズの詳しい情報は不明だが、当時としては高級レンズ
だったのではなかろうか?作りも良いし、描写力もなかなかの
ものである(注:上写真ではデジタルズームを数倍程度使用、
多少画質劣化があるかも知れない)
最初に弱点をあげておけば、最短撮影距離が2.5mと長い事、
そして、若干重い事である。重量は、約770g程あると思う。
内蔵フードがあるので、外付けフードは使っていないが、
見た目にもちょっと大きい感じだ。
過去紹介した同様のスペックのレンズとしては、
コニカ AR200/3.5(第21回記事)
ロシア製Телеар-Н 200/3.5(第37回記事)があるが、
特にコニカARは大きく重く感じた、それに比べれば本レンズは
さほどでも無いかも知れない。

本レンズを購入したのは、2010年代に大阪の中古カメラ屋の
ジャンクコーナーである。
2010年前後に「中古MFレンズ大放出」の時代があった事は
過去記事でも何度か述べているが、本レンズの購入はもう少し
後であり、標準レンズとかの人気のレンズがほぼ中古市場から
一掃された後であった。
本レンズには、テレコンバーター(KENKO MC6)が付属したまま
ジャンクコーナーに置いてあった。
前ユーザーは本レンズにそれをつけて、400mm/f7相当の
望遠レンズとして使っていたのであろう、銀塩時代ならば、まあ
それもありうると思う。だが、現代のミラーレス時代では、NEX-7
に装着するだけでも、300mm/f3.5相当、そこから必要に応じて
デジタルズームを2~4倍程度併用して600~1200mm
程度の超望遠として利用できる。もっと換算焦点距離を伸ばす
事も可能なのだが、1500mmを超えると手持ち撮影は非常に
困難になるので、実用的には1200mm程度までだ。

これで多分800mm相当くらい。
デジタル拡大系の仕様上は、まだ少し余裕があるが、このあたり
の換算焦点距離を越えると、レンズを向けたところにぴったりと
被写体が入らなくなってくるので、難しさが出てくる。
さて、テレコンの話だったが、ジャンクの本レンズにテレコンが
ついたまま、値札が3980円と貼ってあった。
不審に思い、店員に聞いてみると、
店「あ、それ、付属していますよ、おまけです」と言われた。
「KENKO MC6」は、「マクロテレプラスMC7」を持っているので
不要なんだけどなあ・・ と思いつつ、
匠「じゃあ貰っていきます」
と思わず購入してしまったのだ。
ジャンクといいつつも、外観、レンズともに何にも問題が無い、
ただ「古いレンズ」だ、という理由だけなのであろう。
まあ、現代の(デジタル)一眼レフに、MC/MD系レンズを
装着するのは難しい、MC/MDのフランジバックは短いからだ。
通常、この場合は、補正レンズつきの画質の劣るアダプターを
使うか、補正レンズ無しでは、無限遠の撮影が出来ず近接撮影
専用となるかのいずれかだ、いずれもあまり好ましく無い。
だが、ミラーレス機では、MC/MDでも何ら問題はなく装着できる、
補正レンズも不要だし、無限から最短までちゃんと撮影できる。

3980円のレンズ、いやテレコン代を引いて、およそ3000円の
レンズとしては、描写力はとても良好で、コスパは極めて高い。
たとえば、第67回記事のα用AF200/2.8が、現在の相場が
8万円弱程度してしまう事を考えると、本レンズが25本ほど
買えてしまう、そこまで極端な比喩では無いにしても、
他の何か7万円台の高級レンズを買ったお釣りで、本レンズが
買えてしまうのだ。そうであれば、相場って何なんだろう?
と考えさせられてしまう、値段が高すぎるレンズを購入する
意味があるのかどうか・・?
まあ勿論 AF200/2.8は非常に高性能なレンズであるが、
本レンズMC200/3.5で撮った写真と2L判プリントで並べて
「どっちが、どっちのレンズだ?」と聞いたとすれば、
その差がわかる人は、まず誰も居ないのではなかろうか?
そうした意味でも、レンズは値段が高いから良いものだ、という
訳では決してなく、「レンズはコスパが極めて重要」といった
本シリーズ記事のコンセプトの重要性を再認識する次第である。
----
さて、次はトイレンズだ。

カメラは、PENTAX Q7
Qシステム純正レンズの他、CCTV用レンズの母艦としている。
なお、Q7は、MF性能に致命的と言える程の問題を抱えるため、
一眼レフ用レンズのアダプター母艦とはしていない。
レンズは、HOLGA 10mm/f8である、Qマウント用のものだ。
HOLGAは、ミラーレス機用の25mm/f8版を第3回、第38記事で
紹介している、その際に「近年は、Qマウント版も出ているようだ」
と書いたのだが、それを見つけたので、購入した次第だ。
本レンズはトイレンズなので、「描写力」と呼ばれる類の性能は
欠片も無い、極めて酷い写りなのだ。

ダメダメな写りは、トイレンズである以上、大歓迎である。
そういう写りを期待して買う訳であり、Qシステム純正の
04広角(第31回、第55回記事)や、05望遠(第41回、第65回記事)
では、トイレンズと言っても、比較的まともに写ってしまうので
ちょっと物足りなく思っていた。
本レンズは10mm/f8なので、Q7装着時は46mm/f8相当の
標準画角だ、周辺光量落ちが僅かに出るが、一眼用60mmや
ミラーレス機用25mmのHOLGAレンズのように、BC機構
(ブラック・コーナー・エフェクト)という、絞りに蓮根状に
穴をあけた特殊な機構が入っているわけではなく、単純に
イメージサークルが小さい事で、周辺光量落ちが実現されて
いるのだと思われる。
ピントリングはあるが、ミラーレス版のように、人や山の絵が
描かれたゾーンフォーカス型ではなく、パンフォーカス位置に
線が入っているだけの単純なものだ。ピントリングをその線から
外して多少廻す事が出来るのだが、どっちに廻してもピントが
合っているようには感じられない事が大半で、しかも
Q7の貧弱なモニター解像度とピーキング精度では、ピントは
まったく不明となる。(ちなみにQ7はMFレンズでは拡大操作が
出来ない)
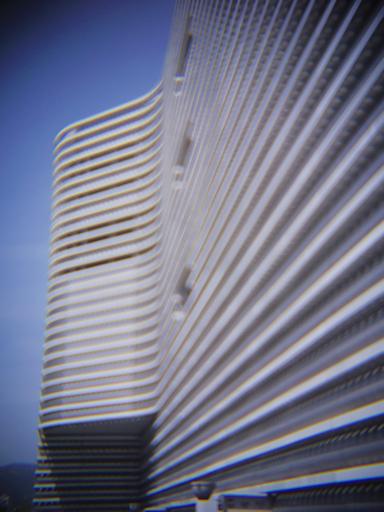
普段はパンフォーカス位置で撮るのだが、依然、ピントが
良くわからない、まあでも、そういう厳密なピント操作が
必要なレンズでは無いという事も確かだ。
ちなみに、最短撮影距離は不明だ、いずれにしてもピントが
合うようには思えないので、それが何cmであっても、あまり
意味が無い事であろう。
カメラ操作の上で、何も無いので飽きてしまうような事があれば、
その際は優秀な Q7のエフェクト機能を使えば良いと思う。
トイレンズ+わけのわからないエフェクト
(注:Q7では自作エフェクトが登録できる)
の効果はなかなか面白く、これぞ、Q7を使う上で最大の長所
なのではなかろうかと思う。

Q7の使い方だが、その小型軽量を活かそうとしても、
交換レンズには厚みのあるものが多い(例、01,02,06)ので、
カメラバッグや旅行カバン等の一角を占有する事には変わらず
あまりメリットが無い。
そうであれば、コンパクトデジカメ、GXR、小型ミラーレス機に
純正薄型単焦点(パンケーキ)レンズ、といった機材の方が
実質的に小型であるメリットが生きると思う。
また、Qシステムはセンサーサイズが小さい(1/2.3~1/1.7型)
ので、あまり高画質を期待する撮影や、被写界深度の浅い撮影と
いうのも望めない。被写界深度に関しては、カメラにBC機能
(ピント位置の異なる写真を連写合成し、背景ボケを作り出す)
もあるが、色々と制約はある(AFのみ、動体不可、合成失敗等)
それと、Q7のセンサーサイズの小ささを逆用して、どんなレンズ
でも望遠にしてしまう望遠アダプター母艦という使用方法も
考えられる。
Q7の換算焦点距離は4.6倍なので、仮に135mmレンズでも
装着すれば、600mm以上の超望遠画角に相当するのだ。
だが、これは理論上そうなる、という事だけで、Q7のMF性能を
考えれば、この使用法は実用的では無い。
とてもピントを合わせる事ができないのだ。
また、CCTV用レンズ、つまりCマウントの監視カメラ用、産業用、
シネ用などのレンズをつけるには、センサーサイズが小さい事
からなかなか相性は良い、しかしこの利用法は、Cマウント
レンズの価格が、意外に高価な割りに、写真用(一眼用)レンズ
に比べてだいぶ写りが悪い事(つまりコスパが悪い)と、
やはりこの手のレンズでもピント合わせが困難である事が課題だ。
結局、Qシステムの最適な利用法は、ピント合わせに問題の無い
レンズ(純正AFレンズ、またはトイレンズ)を装着し、その
優れたエフェクト機能・操作系をもって、エフェクト母艦として
遊び撮影に特化する事だと思っている。
Q7でのエフェクトの使い方は、ちゃんとやろうと思うと知識等
が必要となる、それだけ本格的なものが搭載されているのだ。
よってビギナーには少々ハードルが高いと思うが、Qシステムを
購入するのは、ビギナー層だけでは無いと思うので、ベテラン層
も、もっとQシステムのエフェクト機能に着目するのが良いだろう。
で、お遊びカメラとしては若干高価ではあるが、それでも
旧型の中古などは1万円前後とずいぶん安価になっている。
そして、純正トイレンズ(03.04,05,07)も新品または中古で
4000円前後と比較的安価だ。
そして本レンズ、HOLGA 10mm/f8 (Qマウント版)も、
新品価格が3000円程と、トイレンズとして妥当な相場である。
トイレンズがどういうものか、という事が十分わかっている
Qシステムのユーザーであれば、どれかを買っても悪く無いと思う。
----
さて、次は今回ラストのシステム。

カメラは、LUMIX DMC-GX7
基本性能が高く、比較的新しいμ4/3機であるが、操作系全般や
構造・仕様に若干の課題を持つ。ただそれも、色々と難しい
レンズと組み合わせて複雑な事をやろうとするから問題なので
あって、例えば、純正キットレンズとしてバンドリングて販売
されていた、G20mm/f1.7(第45回記事)との組み合わせで、
AFレンズ母艦として使うのであれば、そうした問題点は若干の
緩和に繋がるかも知れない(要検証)
結局、全てのミラーレス機に、AF,MF両者の母艦としての性能を
期待するのは無理だという事がある。アダプター使用時は
それに向いているMF操作系に優れたミラーレス機があるし、
それはAFの場合とは機種的にはイコールでは無い、ならば
GX7は将来的には、AF母艦に特化させる事として、MF母艦は
またDMC-G5/G6あたりを追加購入しようとも考えている。
レンズは、ミノルタAF 50mm/f3.5 Macroである。
1990年代のAF標準マクロ。
ミノルタαシステムには1980年代後半より超優秀な
AF50/2.8 Macroという兄貴分が存在し、何故本レンズが
併売されているのか、私は理解できなかった。
したがって、銀塩時代から長期に渡り、ミノルタαの標準マクロは、
AF50/2.8版(第38回記事)を使い続け、ついでにMF版として
MD50mm/f3.5(第7回記事)も所有していたので、
これでミノルタ標準マクロは磐石、と長らく思い続けていた。
第38回記事でf2.8版を紹介した際「f3.5版は所有していない
が、オールドマクロに近い特性なのかもしれない」と書いた。
それを書いてから、f3.5版の事が気になりだし、どうしても
試してみたくなってしまったのだ(汗)
・・という事で、f3.5版を探したところ、幸い1万円程度の価格で
中古品を発見、それ位の値段だったら良いか、と思い、本年
2016年に購入した次第であった。

α用レンズなので絞り環を持たない、しかしアダプター側に
絞りレバーを機械的に制御できる機構がついているので、
普通にレンズの内部の絞りを外からコントロールできる。
ただし絞り値は正確にはわからない、だいたいカンでアダプター
のリングを廻すしか無い。勿論露出値を見れば正確にわかる
のだろうが、「f5.6で撮らなきゃ」等と絞り値を指定する事は
テスト撮影以外では意味が殆ど無いので、まあ適当で十分で
あろう。
なお、本アダプターα→μ4/3は、リングの緩みが発生し、
第63回記事で紹介したように、アンチウェア・グリスを用いて
調整を行っている。その後、こうした小口径レンズでは、
アダプターリングが絞りの力に負けてしまう事はなく、快適に
動作しているが、大口径レンズの強大な絞り羽根の力には
やっぱり若干負けてしまう模様で、少しづつリングが廻って
しまう、ただ、その量はかなり小さいので、以前のように
指でリングを押さえながら撮影する必要は無く、実用上では
快適に使えている。そして心配していた、高温等でグリスが
溶けて流れ出てしまうといった、かなり危険な事態も、
気温30℃程度においては起こらない模様で問題無い。
さて、快調になったαアダプターで、少し絞った撮影を続けている。
これはまず、恐らく解像度重視型と、本レンズの特性を推測して
いるからだ。ボケ質は多分期待できないだろうな、という予感もあり、
おまけに本レンズは、1/2倍マクロであり、最短撮影距離は23cmと、
f2.8版(等倍)の約20cmより若干長い。なので、近接して背景を
大きくボカす等の撮影技法を行うのであれば、f2.8版の方が良い
訳であり、わざわざ本レンズにおいて、苦手な土俵で優秀な兄貴分
と戦う必要は無い訳だ。

クマ蜂を見かけると、どうも反射的に撮りたくなってしまう(笑)
なにせ、こいつらは空中にしばらく静止していたかと思うと、
急に素早く動いたりで、気まぐれだ。
その気まぐれに追従できるかどうか、というのは、MF操作の
練習にもなる、まあ普通は追いつかないのだが、頑張ってやれば
何枚に1枚かは撮れる時もある。
被写体が小さいので、デジタルテレコンを2倍にしている、
GX7では、デジタルズームの操作系は使いにくく実用的では
無いので、デジタルテレコンを使う方が良い。しかしながら、
デジタルテレコンは、あまりオススメできる機能ではなく、
まず画質が劣化する事、そして、デジタルテレコン使用時は
拡大操作系が無効となり、厳密なピント合わせが出来ない事だ。
ただ、GX7には優秀なピーキング機能が搭載されているので、
クマ蜂を追いながら、ピーキングの青色が蜂の所にかかった
瞬間にシャッターを切るなどすれば、ピント歩留まりは他の
カメラよりも若干上がる。
けど、やはりデジタルズームの操作系に優れたカメラの方が
良いであろう、GX7は、ややこしい使い方には向いていないのだ。
それと、本レンズのピントリングは、いわゆる「New」タイプ
仕様である。これは、1980年代後半~1990年代前半の
α用レンズは、ミノルタのAF化(自動化)主義のまっただ中で、
必然的に、ピントリングが極めて細く、操作性に問題があった
ものを1990年代に改良したもので、ゴム製のやや細いピント
リングとなっているものだ。しかし、この仕様でもピントのMF
操作性は、さほど良好とは言えず、おまけにデザイン的にも
あまり格好良く無い、まあ、実はそれもあって、本レンズには
過去あまり魅力を感じなかったのだが、とりあえずデザインや
操作性は目をつぶるとしておこう。

本レンズだが、f3.5と暗く、また、f2.8版より寄れないので
どちらかといえばマクロ的撮影より、中距離とかで目についた
被写体を捉えるスナップ的撮影に向いているかも知れない。
μ4/3機では100mm相当の画角となるが「スナップだから35mm」
とかいうのは銀塩時代の古いセオリーであり、現代ではそれほど
気にする必要は無い。1つは画角への慣れであり、また被写体の
求め方も、1枚撮るたびにコストがかかっていた銀塩時代と、
撮影コストがほぼゼロのデジタル時代では、全く違うものになる
事であろう。
そしてマクロレンズであるから、画角が望遠すぎるという点は
ますます緩和できる、つまり、望遠目線ではなく、マクロ目線に
する、という意味であり、これは過去の中望遠~望遠マクロの
記事で毎回のように書いてきている事でもある。

本レンズの描写力は、まだ購入後日が浅いので良くわからない(汗)
もうしばらく撮った上で、f2.8版とちゃんと比較してみようと思う。
とりあえず1万円程度の価格ならばコスパは悪いとは思えないが、
f2.8版も同様に安価なので、存在意義が依然わかりにくいレンズ
ではある。
次回記事に続く・・・